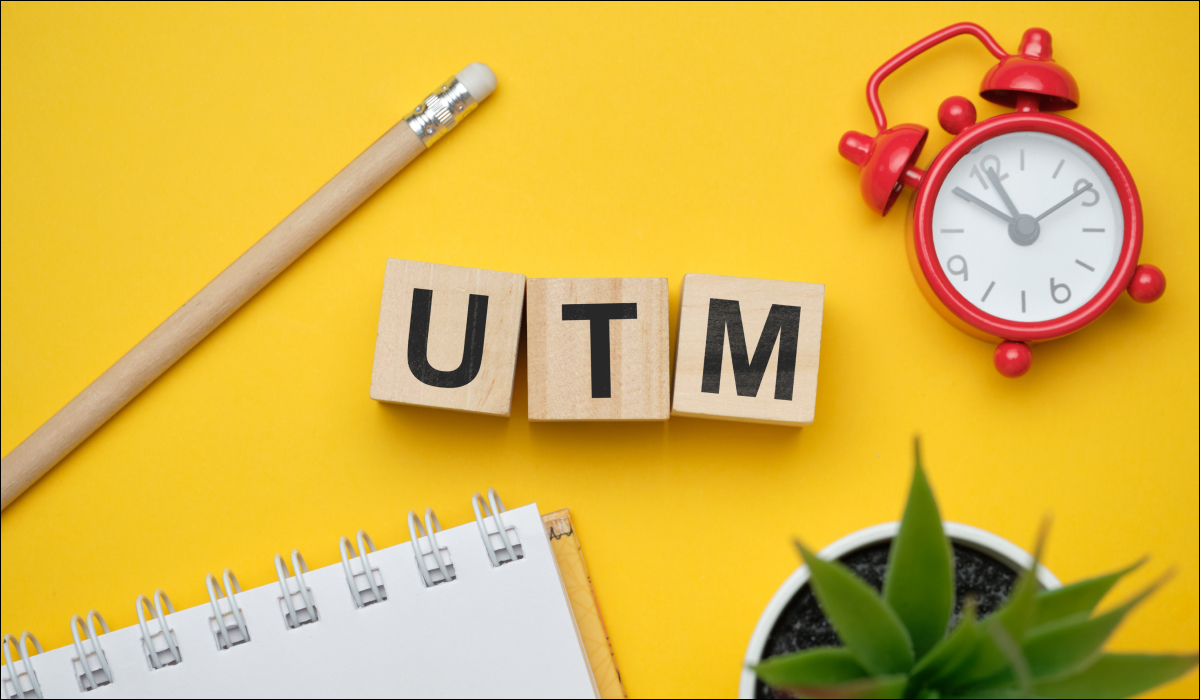UTM(統合脅威管理)とは、ファイアウォールやアンチウイルス、不正侵入防止などの機能を統合したセキュリティ対策のことです。これらの機能を一元的に管理することで、運用管理の負担を軽減できます。
とはいえ、UTMは製品によって処理能力や機能に違いがあり、適切な製品選定や設定を行わなければ、かえってセキュリティ上の脆弱性が生まれるリスクがあります。
本記事では、UTMの主な機能や導入のメリット・デメリットに加え、UTMの選び方まで詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、UTMの全体像を理解し、自社に最適なセキュリティ対策を選ぶ知識が身につきます。企業の情報セキュリティを強化したいと考えている担当者にとって、必見の内容です!
目次
UTM(統合脅威管理)とは
UTM(統合脅威管理)とは、企業ネットワークのセキュリティを統合的に管理するソリューションのことです。
従来のファイアウォールに加えて、侵入検知・防御(IDS/IPS)、ウイルス対策、Webフィルタリングなど、複数のセキュリティ機能を一元化することで、効率的な脅威対策が可能になります。
特に、中小企業や支社・拠点を持つ企業では、専門のセキュリティ担当者を配置せずに、包括的な防御を実現できる点が大きなメリットです。
具体的な活用例としては、インターネットゲートウェイでの脅威防御や、外部からの不正アクセスの監視、Webサイトのアクセス制限などが挙げられます。
UTM(統合脅威管理)が生まれた背景
UTMが生まれた背景には、サイバー攻撃の高度化と多様化があります。従来のセキュリティ対策では、マルウェア、フィッシング、DDoS攻撃などの新たな脅威への対応が困難になりました。
また、クラウドサービスの普及やリモートワークの増加に伴い、企業のセキュリティリスクが急増。特に中小企業においては、多層防御のために複数のセキュリティ製品を導入・管理する負担が大きな課題となっていました。
これらの課題に対処するため、統合的な脅威防御を可能にするUTMが登場し、企業のセキュリティ管理効率化に貢献しています。
UTM(統合脅威管理)とファイアウォールの違い
UTMとファイアウォールの違いは、提供するセキュリティ機能の範囲にあります。
ファイアウォールは、不正な通信を遮断し、ネットワークの入口を守ることに特化しています。一方で、UTMは、ファイアウォールの機能に加え、ウイルス対策、侵入検知・防御、Webフィルタリングなど、多岐にわたるセキュリティ機能を統合しています。
これにより、個別の対策を行うよりも管理の負担を軽減し、より強固なセキュリティ体制を構築できます。
UTM(統合脅威管理)の主な機能
- ファイアウォール
- アンチウイルス
- アンチスパム
- Webフィルタリング
- IDS/IPS(侵入検知・防御システム)
- その他のセキュリティ機能
ファイアウォール
ファイアウォールは、外部ネットワークと内部ネットワークの間で通信を制御するセキュリティ機能です。
ネットワークトラフィックを監視し、不正なアクセスや不審な通信を遮断することで、サイバー攻撃から企業のシステムを保護します。
例えば、特定のIPアドレスやポート番号によるアクセス制限に加え、次世代ファイアウォール(NGFW)では、アプリケーション制御や脅威インテリジェンスを活用した高度な防御も可能です。
アンチウイルス
アンチウイルス機能は、ネットワークを介して侵入するマルウェアやウイルスを検知し、駆除します。
リアルタイムスキャンにより、社内端末に脅威が到達する前に遮断することが可能です。クラウドベースのウイルス定義データベースを活用することで、最新の脅威にも対応可能です。
さらに、サンドボックス機能を搭載したUTMでは、疑わしいファイルを仮想環境で解析し、未知のマルウェアによる脅威を防御できます。
アンチスパム
アンチスパム機能は、不審なメールをフィルタリングし、フィッシング詐欺やスパムメールの侵入を防ぎます。
スパムメールは、情報漏洩やウイルス感染を引き起こす可能性があるため、適切な対策が必要です。
UTMのアンチスパム機能は、メールの送信元情報や内容解析による疑わしいメールの隔離と、ブラック/ホワイトリスト設定による必要なメールの保護を両立します。
Webフィルタリング
Webフィルタリング機能は、従業員のインターネット利用を管理し、特定のサイトへのアクセスを制限する機能です。
不正サイトへのアクセスを防ぐことで、マルウェア感染や情報漏洩のリスクを低減できます。
カテゴリ別のURLフィルタリングに加え、リアルタイムの脅威インテリジェンスを活用した動的フィルタリングが可能です。また、SNSや動画ストリーミングサイトの利用を制限することで、従業員の業務効率向上にもつながるでしょう。
IDS/IPS(侵入検知・防御システム)
IDS(侵入検知システム)とIPS(侵入防御システム)は、不正アクセスやサイバー攻撃をリアルタイムで検知し、場合によっては遮断する機能です。
ファイアウォールでは防ぎきれない高度な攻撃に対して有効な対策となります。
IDSは、攻撃の兆候を検知することに特化していますが、IPSは検知後に自動的に攻撃を遮断できます。また、機械学習やAIを活用した高度な分析機能を備えたUTMでは、未知の攻撃手法にも対応可能です。
その他のセキュリティ機能
UTMには、上記以外にもさまざまなセキュリティ機能が搭載されています。
例えば、VPN(仮想プライベートネットワーク)機能、DLP(データ漏洩防止)機能、アプリケーション制御機能などが挙げられます。VPNを活用することで、安全なリモートアクセス環境を構築し、テレワークのセキュリティを強化できます。
また、DLP機能を用いることで、機密情報が社外へ流出するのを防ぎ、企業の重要なデータを保護することが可能です。
UTM(統合脅威管理)を導入するメリット
- 複数のセキュリティ機能を一元管理できる
- 低コストで高いセキュリティを確保できる
- 新しい脅威に対しても迅速に対応できる
複数のセキュリティ機能を一元管理できる
UTMのメリットの1つ目としては「複数のセキュリティ機能を一元管理できる」というものが挙げられます。
UTMは、ファイアウォール、アンチウイルス、侵入検知・防御(IDS/IPS)などの機能を統合しており、複数のセキュリティ対策を一括で管理できます。
例えば、従来は各機能を個別のソフトウェアや機器で運用していたため、それぞれの設定や監視に手間がかかりましたが、UTMを導入することで管理負担を軽減し、セキュリティ対策の強化と一元管理が可能です。
低コストで高いセキュリティを確保できる
UTMのメリットの2つ目としては「低コストで高いセキュリティを確保できる」というものが挙げられます。
複数のセキュリティ機能を個別に導入した場合、それぞれのライセンス費用や運用コストが発生しますが、UTMは1つの機器に統合されているため、これらのコストを削減できます。
例えば、中小企業が限られた予算でセキュリティ対策を強化したい場合、UTMを導入することで必要な機能を低コストで利用でき、運用管理の負担も軽減できます。
新しい脅威に対しても迅速に対応できる
UTMのメリットの3つ目としては「新しい脅威に対しても迅速に対応できる」というものが挙げられます。
UTMは、クラウド連携やリアルタイムアップデート機能を備えており、新たなマルウェアやサイバー攻撃が発生した場合でも、自動的に最新のセキュリティ対策を適用できます。
例えば、ランサムウェアやゼロデイ攻撃など、従来のセキュリティ対策では防ぎにくい脅威に対しても、迅速に防御体制を強化し、企業の情報資産を保護できます。
UTM(統合脅威管理)導入によるデメリット
- 導入や運用の負担が増加する可能性がある
- ネットワーク速度が低下する可能性がある
- 保守運用コストが高額になる可能性がある
導入や運用の負担が増加する可能性がある
UTMのデメリットの1つ目としては「導入や運用の負担が増加する可能性がある」というものが挙げられます。
UTMは、多岐にわたるセキュリティ機能を統合しているため、設定や管理が複雑になり、IT部門の負担が増大する傾向があります。
解決策として、ベンダーのサポートが付くUTMや、クラウド型UTMの導入で管理負担を軽減し、導入時は業務内容に適した設計と運用ポリシーを策定することが重要です。
ネットワーク速度が低下する可能性がある
UTMのデメリットの2つ目としては「ネットワーク速度が低下する可能性がある」というものが挙げられます。
UTMは、多機能なセキュリティ対策が可能になる一方で、通信処理の増加がネットワーク速度に影響を及ぼす可能性があります。特に、トラフィック量の多い企業では、帯域幅の制約が顕著になります。
解決策として、企業の規模とトラフィックに合ったUTMを選び、適切な設定と最適化でパフォーマンス低下を最小限に抑えることが重要です。
保守運用コストが高額になる可能性がある
UTMのデメリットの3つ目としては「保守運用コストが高額になる可能性がある」というものが挙げられます。
UTMは、導入費用やライセンス費用が高額になるため、特に中小企業にとっては大きな負担となる場合があります。また、定期的なソフトウェア更新やハードウェアのメンテナンスにも追加コストが発生します。
解決策としては、クラウド型UTMの利用や、必要な機能を選択できる製品の導入が有効です。また、トライアルなどを活用し、自社のセキュリティ要件に合ったUTMを慎重に選定することで、不要なコストを削減できます。
UTM(統合脅威管理)の選び方と比較のポイント
- ①:セキュリティ機能の充実度で選ぶ
- ②:パフォーマンスと処理速度で選ぶ
- ③:管理や運用のしやすさで選ぶ
- ④:導入費用や運用コストで選ぶ
- ⑤:拡張性と将来のスケーラビリティで選ぶ
- ⑥:サポート体制とベンダーの信頼性で選ぶ
①:セキュリティ機能の充実度で選ぶ
UTMの選び方の1つ目としては「セキュリティ機能の充実度で選ぶ」という方法が挙げられます。
特に、ファイアウォール、IPS(侵入防御システム)、アンチウイルス、Webフィルタリング、メールセキュリティ、VPN機能などの充実度を確認することが重要です。
高度なUTMでは、AIを活用した脅威検出、サンドボックス機能、クラウド連携によるリアルタイム分析など、最新の攻撃手法に対応するための機能が搭載されています。
➁:パフォーマンスと処理速度で選ぶ
UTMの選び方の2つ目としては「パフォーマンスと処理速度で選ぶ」という方法が挙げられます。
UTMは多機能なセキュリティ機器であるため、処理能力が低いとネットワーク遅延が発生し、業務に支障をきたす可能性があります。
そのため、自社のネットワーク規模やトラフィック量に応じて、スループットや最大接続数を確認しましょう。特にクラウドサービスの利用が多い場合は、暗号化通信(SSL/TLS)の対応やVPN処理能力も重要なポイントです。
③:管理や運用のしやすさで選ぶ
UTMの選び方の3つ目としては「管理や運用のしやすさで選ぶ」という方法が挙げられます。
UTMは多機能であるがゆえに、設定や管理が複雑になりがちです。特に、IT担当者が少ない企業では、管理画面の使いやすさや設定の容易さが重要なポイントになります。
具体的には、直感的なGUIを備えたUTMを選ぶことで、設定やポリシー変更がスムーズに行えます。また、クラウド管理型のUTMなら、リモートからの監視やメンテナンスが容易になるため、外部拠点が多い企業におすすめです。
④:導入費用や運用コストで選ぶ
UTMの選び方の4つ目としては「導入費用や運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。
UTMの価格は、機能や性能によって大きく変動します。そのため、初期費用とランニングコストのバランスを考慮することが重要です。
ハードウェア型UTMは導入費用が高めですが、長期的な運用コストを抑えやすいのが特徴です。一方、クラウド型UTMは初期費用が低く柔軟に利用できるため、小規模企業やスタートアップにも適しています。
➄:拡張性と将来のスケーラビリティで選ぶ
UTMの選び方の5つ目としては「拡張性と将来のスケーラビリティで選ぶ」という方法が挙げられます。
企業の成長に伴いネットワーク環境も変化します。そのため、将来的な拡張が可能なUTMを選ぶことで、長期的に安定した運用が期待できます。
接続端末数やトラフィック増加時の対応として、ライセンス追加やハードウェア更新が容易なUTMの選定が重要です。また、SD-WAN対応のUTMを導入すると、複数拠点のネットワーク最適化にも容易に対応できます。
⑥:サポート体制とベンダーの信頼性で選ぶ
UTMの選び方の6つ目としては「サポート体制とベンダーの信頼性で選ぶ」という方法が挙げられます。
セキュリティ機器は、トラブル発生時の迅速な対応が不可欠です。したがって、サポートの質と提供元の信頼性を十分に考慮して選ぶ必要があります。
24時間365日のサポートや日本語対応の有無、およびファームウェアの定期更新やセキュリティ脅威情報提供の有無は、UTMの長期的な安全運用において重要な要素です。
まとめ
本記事では、UTM(統合脅威管理)の概要をわかりやすく解説するとともに、主な機能や導入のメリット・デメリットについて詳しくご紹介しました。
サイバー攻撃の高度化が進む中、UTM市場は世界的に拡大を続けており、AIやクラウドを活用した新たなセキュリティ対策も登場しています。今後も企業のネットワークを守るため、UTMの需要はますます高まることが予測されます。
今後もITreviewでは、UTM製品のレビュー収集に加えて、新しいUTMソリューションも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。