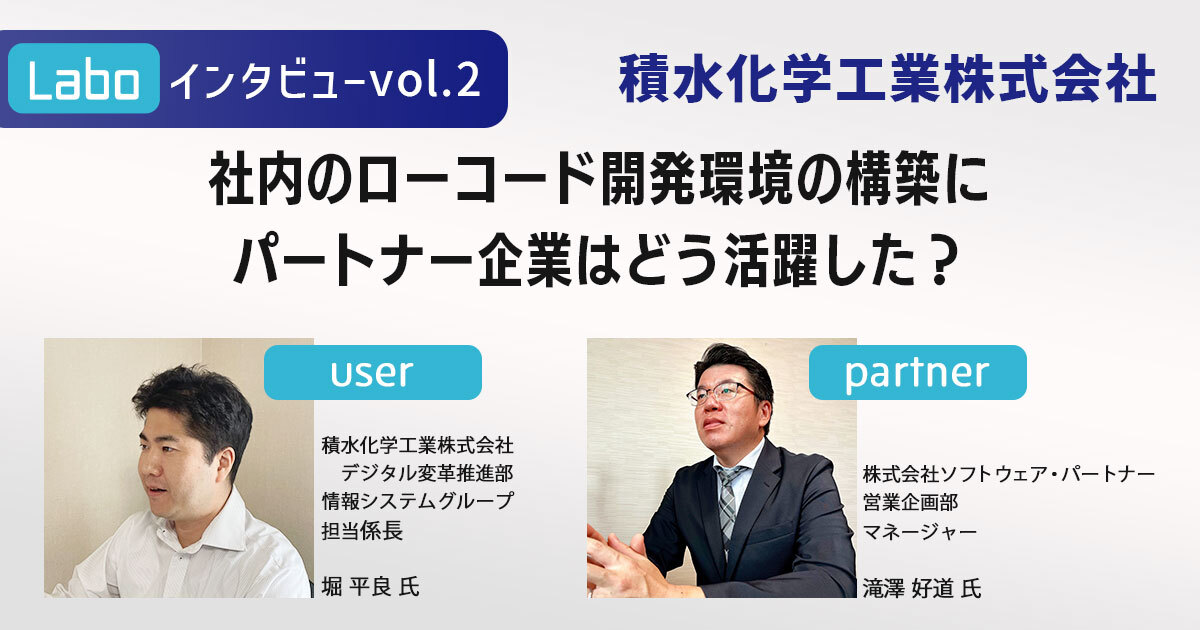今話題の「ローコード開発ツール」。誰でも容易に安く開発できるイメージが先行していますが、実際にはローコードならではの開発ノウハウが存在します。そんなローコード開発の導入を支援してくれるサービスプロバイダーの存在を知っていますか?
今回は、サービスプロバイダーの技術支援を受けながら、ローコード開発ツール「Wagby EE」でアプリケーション開発に取り組んでいる積水化学工業株式会社(以下:積水化学工業)でデジタルを活用した業務改善を推進する堀平良氏と、技術支援を提供するソフトウェア・パートナー社の滝澤好道氏にお話を伺い、サービスプロバイダーの技術支援のリアルに迫ります。
目次
Windows系アプリケーションからの脱却に向け、ローコード開発の環境づくりに挑む
ツール導入の決め手は「サポートの信頼性と、ツールの将来性」
――まずはローコード開発に至った経緯について教えてください。
堀氏:2017年に「WannaCry」というWindowsをターゲットにしたランサムウェアが横行しました。それまで.NETベースのアプリケーションをたくさん作ってきていたのですが、そういったWindows系のアプリケーションから脱却したいと考えていました。ただ、一から作り直すとなると費用も時間も相当かかります。既存のアプリケーションを置き換える手段としてちょうど「ローコード」という言葉が出てきた頃で、試験研究的にやってみようとなったのが2018年から2019年ぐらいでした。

WannaCryの収束とともにローコード開発が縮小気味になった時期もありましたが、システムを簡単に作れる点は非常に評価できると考えていました。当時、たまたま相談があった部門のアプリケーションをローコードで作ってみたところ、大好評だったことから、本格的にローコード開発に取り組むようになりました。
――ツールは最初からWagby EEを使われていたのでしょうか。
堀氏:そうですね。もちろんいろいろなツールを研究しましたが、中でもWagby EEが一番当社に合っていると判断しました。ポイントにしたのは大きく2点で、1つ目は国産へのこだわりでした。比較検討したツールには海外産のものもありましたが、海外では企業買収が多く、ユーザーの立場からすると長く使えるツールかどうかという点が評価のポイントでした。
2つ目はツールが生成する成果物についてです。Wagby EEは、一般的にはローコード開発ツールに位置付けられていますが、個人的にはJavaのソース生成ツールだと思っています。自分たちの手の届かない範囲でアプリケーションができあがってしまうことは避けたい、将来的に仮にWagby EEがなくなったとしても、自分たちで作ったアプリケーションを運用できるようにしたいという考えがありました。
――どのようなアプリケーションをローコードで開発されたのですか。
堀氏:いくつかありますが、経理業務の自動化・効率化がそのうちのひとつです。当社は海外を含めて関連会社が200社近くありますが、連結決算に向けて会計上の仕訳の情報などを毎月集める必要があります。この業務にWagby EEで作成したアプリケーションを使用しています。経理では他にも、期末の繁忙期に手作業でExcelに転記して集計していたような業務を、現在はWagby EEでシステム化しています。
ローコードに求めているのは生産性。だからこそノウハウを有するパートナーが重要
自社の考え方ややりたいことを理解してくれたことが決め手に
――積水化学工業では、自社やグループ会社で開発部門をお持ちですが、独自でローコード開発環境の構築は難しいのですね。
堀氏:ツールのライセンスを買って実際に触ってみて気づいたことですが、自分たちで一からアプリケーションを作り上げるのがやはり大変だったためです。ローコードで効率的にアプリケーションを作りたいわけですが、自分たちでツールのマニュアルを調べながら作っていくとどうしても効率が悪くなる。ローコードに求めているのは生産性ですから、そこはツールの使い方に関するノウハウ・知見のあるパートナーにお手伝いいただきたいと考えました。
――「ツールの導入にサービスプロバイダーの支援を受ける」という選択肢は以前から知っていたのでしょうか。
堀氏:既に様々なツールを利用してきていますので、導入に当たって頼れる企業がいるということは知っていました。ツールによってはメーカーに直接相談するよりも、間に入る販売代理店やサービスプロバイダーへ相談した方が親身になって対応してくれることも多いので、メーカーに直で支援を依頼するよりも親身になって相談に乗ってくれると感じています。Wagby EEの構築パートナーについては候補が数社あったと記憶していますが、ソフトウェア・パートナー社は当社の考え方を違和感なく理解いただけたことが大きかったです。実際には、まずPoCをやってみて、試験導入で問題がないことを確認して本導入という流れでしたが、最初からサポートいただいています。
代理店対応から技術支援まで顧客の課題に応じたフレキシブルな支援を提供
積水化学工業の課題に合わせた無駄のないPJ体制を構築
――支援を求めている企業によって課題や希望する支援は異なると思いますが、どのような契約形態なのでしょうか。
滝澤氏:弊社では独自のサービスとして、「技術支援サービス」を提供しています。お客様の課題に対して弊社のエンジニアが何時間動くかによる時間精算の契約で、お客様からの依頼内容に応じて対応する人員をアサインし、チームでフレキシブルに対応するサービスです。年間有効な時間数をプリペイドで購入していただき、ご依頼が発生するたびに時間見積もりをします。見積もり内容をご承諾いただけたら初めて着手するという流れです。Wagby EEというローコード開発ツールを展開している立場として、お客様を後方支援できる体制は絶対に必要だという考えで作ったサービスです。

堀氏:この契約形態は非常に助かっています。Wagby EEの設計に関する助言だけでなく、たとえば、Wagby EEのリリース作業を自動化するために、「Wagby EEのリリース作業を自動化するためのスクリプトを書いてほしい」、といったインフラレベルの相談にも対応してもらっています。時間契約の中で柔軟に対応してもらえる点がとてもありがたいです。また、Wagby EEのライセンスに関しても、メーカーではなくソフトウェア・パートナー社との契約です。ライセンスも含めて窓口が一本化できるのは、正規パートナーのメリットですね。
――通常のシステム開発プロジェクトのようにメンバーが常駐するのではなく、依頼があった場合に、都度体制を組んで対応してこられたのでしょうか。
滝澤氏:そうです。根本的な企画・設計はすべて積水化学工業でされており、あくまで技術的なご支援だけを提供しました。たとえば、Wagby EEでどのように設計すればある機能を実現できるのか、といったような課題が出た場合に、ご依頼に応じて助言するなどのご支援をしてきました。分業がはっきりしていたことは、成功したポイントだったと思います。
開発が進んで課題が立て込んできた時期は、頻繁に認識合わせの会議を開いて情報を共有していました。課題によっては双方の技術者同士で行うこともありましたし、関係者を集めて複数の課題をその場で一気にさばいていくような形式で行ったこともありました。
――開発で出た現場の課題をソフトウェア・パートナー社で取りまとめ、Wagby EEのメーカーに改善を依頼したこともあったそうですね。
滝澤氏:はい、そうです。そこが純国産のツールである利点ですし、メーカーにフィードバックしてよりよい製品にしていくことは、我々としても自信を持って製品を販売していく上で重要であると考えています。機能改善だけではなく、顧客からの要望で追加された機能も多くあります。
堀氏:ワークフロー周りで、当初はできなかったことがパラメータひとつで簡単にできるようになったこともありましたし、ユーザー権限の挙動などについても要望が取り入れられて改善しました。システムを作り上げた後、メーカーへ訪問して見てもらい、ツールの改善点をメーカーと協議したこともあります。
開発工数削減と業務改善を両立。支援を受けることで開発ノウハウも蓄積
ただの技術代行ではなく、事業を進めるパートナーとして存在感を放つ
――Wagby EEによるアプリケーション開発の結果、大きな業務改善を実現されたと伺いました。
堀氏:はい。経理の集計作業については大幅に工数を削減することができましたし、海外の関連会社からの会計情報の収集についてもこの1年で大きく進んでいます。また、開発工数についても、弊社の従来の手法で開発した場合の試算結果と比べて大幅に削減できたことがわかりました。
Wagby EEに関しても支援のおかげである程度は社内で対応できるようになってきていまして、今でもカスタマイズを続けていますが、ソフトウェア・パートナー社には引き続き相談に乗っていただいています。
――開発メンバーのスキルが上がると、Wagby EE導入当初に比べて相談内容のレベルも変わっていそうですね。
滝澤氏:ご相談の質は明らかに上がっていまして、我々としても「ちょっとお調べします」ということが最近多くなっていますね。元々、技術支援サービスは、お客様がノウハウを蓄積して自分たちでツールを使えるようになったならば、契約を打ち切っていただいてかまわないというコンセプトで始めていますので、理想的な状態だと思っています。
堀氏:ちょうど先日もWagby EEで作ったアプリケーションと他システムの連携についてご相談したところです。アプリケーションのセキュリティに関しても、我々の目線で相談に応じていただいて強固なセキュリティを実現しました。システム開発に関する一般的な常識と、それをローコードでどう実装するか、両者の間を取り持ってくれるのが、ソフトウェア・パートナー社のようなサービスプロバイダーだと思っています。
編集後記: サービスプロバイダーの支援で、情シスがない中小企業にもローコード開発が選択肢になり得る
インタビューの中で、もっとも印象に残ったのは、「ローコード開発においては成果責任は顧客の側にあると考えます。将来的にアプリケーションを運用保守していくのは自分たちなので、できあがったものについては必ず十分に説明を受けて自分たちの技術にしてきている」という堀氏の言葉でした。そのような顧客の想い・意図をソフトウェア・パートナー社が汲み取り、両社二人三脚で開発を進めたからこそ、期待した成果が得られたのだと感じました。
一方で、今回の積水化学工業のようなローコード専門の開発体制が存在しない企業も数多く存在します。滝澤氏によれば、たとえば初期開発は受託で行い、顧客が独力でアプリケーションの維持・保守ができるように指導して引き渡すといったように、顧客の要望や体制にあわせて柔軟に対応されているそうです。サービスプロバイダーの支援によるローコード開発は、情シスのない中小企業にも有力な選択肢の一つになるのではないでしょうか。
◆お話を伺った方
積水化学工業株式会社 デジタル変革推進部 情報システムグループ 担当係長 堀 平良 氏
株式会社ソフトウェア・パートナー 営業企画部 マネージャー 滝澤 好道 氏