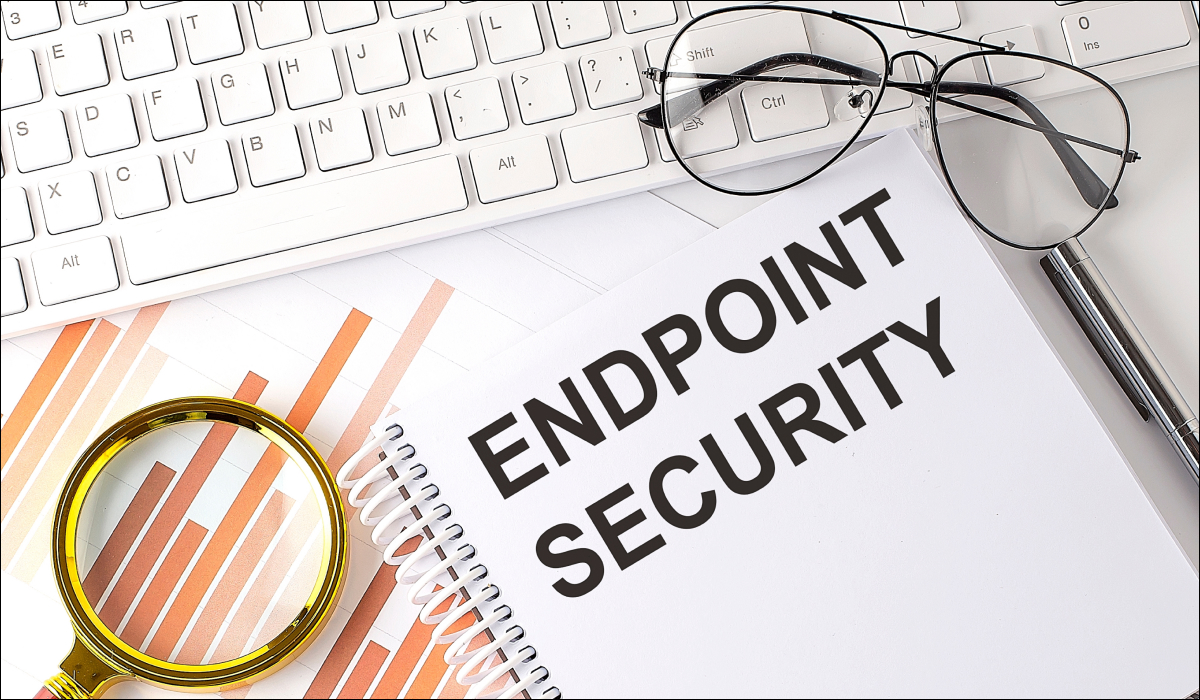EDR(Endpoint Detection and Response)とは、エンドポイント(PCやサーバー)へのサイバー攻撃を検知し、迅速に対応するためのセキュリティ対策のことです。
近年、ランサムウェア攻撃やゼロデイ攻撃の増加を背景に、EDRの重要性が高まっており、対策を怠ってしまうと、情報漏えいやデータの改ざんなど、致命的なインシデントに発展してしまいます。
しかし、一般的なEDRシステムの多くは、初期導入や運用の負担が大きく、都度適切な設定や運用体制が整っていなければ効果を発揮しにくいということも事前に理解しておかなければいけません。
本記事では、EDRの主な機能解説に加えて、従来のセキュリティ対策との違いから、導入によるメリットやデメリットまで徹底的に解説していきます。
この記事を読むだけで、EDRの全体像をまるごと理解できるため、サイバーセキュリティ対策に課題を感じている企業担当者にとっては必見の内容です!
目次
EDRとは?
EDR(Endpoint Detection and Response)とは、エンドポイント(PCやサーバー)へのサイバー攻撃を検知し、迅速に対応するためのセキュリティ対策手法のことです。
近年、サイバー攻撃の巧妙化によって従来のウイルス対策では、防御できない脅威が増加しており、このような状況に対応するのがEDRシステムと呼ばれるものです。
EDRは、リアルタイムで監視する機能や高度な解析機能を備えているため、エンドポイントにおける不審な活動を早期に発見および対応することを目的としています。
具体的な活用事例としては、未知のマルウェアを検出できることで、感染拡大を防ぐための対策や内部不正による情報漏えいの兆候を早期に発見することができます。
EDRが注目されるようになった理由
- サイバー攻撃の手段が高度化した
- ゼロトラストの考え方が普及した
- インシデントの重要性が高まった
サイバー攻撃の手段が高度化した
EDRが注目されるようになった理由の1つ目としては「サイバー攻撃の手段が高度化した」というものが挙げられます。
特に、近年のサイバー攻撃は単純なウイルス感染だけではなく、ランサムウェアの登場や標的型攻撃など、より巧妙かつ複雑な攻撃手法が増加してきています。
従来のアンチウイルスソフトでは防御できない攻撃が増加するなか、EDRはエンドポイント上の不審な挙動を検知し、迅速な対応を可能にするため、多くの企業で導入が進んでいます。
ゼロトラストの考え方が普及した
EDRが注目されるようになった理由の2つ目としては「ゼロトラストの考え方が普及した」というものが挙げられます。
ゼロトラストとは「すべてのアクセスを信用しない」という前提のもと、ネットワークの内外を問わず、常に監視・検証するセキュリティモデルのことです。
リモートワークの普及にともない、従来のセキュリティ対策では、内部端末からの脅威を防ぐことが難しくなっているため、エンドポイント単位での監視と対応が重要になっています。
インシデントの重要性が高まった
EDRが注目されるようになった理由の3つ目としては「インシデントの重要性が高まった」というものが挙げられます。
サイバー攻撃が発生した際に迅速な原因分析と対応が求められる中、EDRは攻撃の痕跡を詳細にログとして記録するため、適切なインシデント対応を支援します。
従来のセキュリティ対策では、攻撃の痕跡を見つけるのが困難でしたが、EDRを導入することで不正アクセスの経路や被害範囲を特定しやすくなるため、セキュリティレベル向上につながります。
EDRの主な機能
- リアルタイム監視
- 脅威検知アラート
- インシデント対応
- ログの収集と分析
リアルタイム監視
EDRの主な機能の1つ目としては「リアルタイム監視」が挙げられます。
EDRは、エンドポイントの動作を継続的に監視し、不審なアクティビティを検出することで、サイバー攻撃を未然に防ぎます。不正プロセスや疑わしいファイルの変更など、異常な挙動が確認されると、管理者に即時通知を行います。
脅威検知アラート
EDRの主な機能の2つ目としては「脅威検知アラート」が挙げられます。
EDRは、異常なプロセスの実行や不正アクセスの試行をリアルタイムで解析し、リスクの高い脅威を識別することができます。アラート発生時には、管理者は詳細なログを確認し、必要に応じて防御策を講じることが可能になります。
インシデント対応
EDRの主な機能の3つ目としては「インシデント対応」が挙げられます。
EDRは、マルウェア感染が確認された端末を隔離し、ネットワークから遮断することで、被害の拡大を防ぐことができます。感染の経路や影響の範囲を特定し、必要に応じてシステムの復旧や影響を受けたファイルの修復を実施します。
ログの収集と分析
EDRの主な機能の4つ目としては「ログの収集と分析」が挙げられます
EDRは、ファイルの変更履歴やプロセスの実行状況、ネットワークの接続情報などを詳細に記録します。これにより、セキュリティインシデントが発生したときには、攻撃の経路や影響の範囲を特定し、迅速な対応が可能となります。
EDRと従来のセキュリティ対策(EPPやアンチウィルスソフト)の違い
| EDR | EPPやアンチウイルスソフト | |
|---|---|---|
| 導入目的 | 検知・対応 | 予防・対策 |
| 検出手法 | リアルタイム監視 | シグネチャ検出 |
| 対応範囲 | インシデントの追跡 | ウイルス感染の防止 |
| 適用対象 | 高難度な脅威対策向け | 基本的な防御対策向け |
導入目的の違い
EDRは「検知・対応」を、EPPやアンチウイルスソフトは「予防・対策」を目的として設計されています。
EPP(Endpoint Protection Platform)やアンチウイルスソフトは、既知のマルウェアやウイルスをブロックすることを重視したセキュリティ対策です。
一方、EDRはエンドポイント上の挙動を継続的に監視し、不審な動きを検知・分析する機能を持ちます。ゼロデイ攻撃や標的型攻撃に対応するため、インシデント発生後の対応や根本原因の特定が可能となります。
検出手法の違い
EDRは「リアルタイム監視」が、EPPやアンチウィルスソフトは「シグネチャ検出」が主な検出の手法です。
EPPやアンチウイルスソフトは、既知のマルウェアをシグネチャと呼ばれる特定のパターンと照合し、検出・ブロックする仕組みで動作しています。
一方、EDRはエンドポイント上の挙動をリアルタイムで監視し、通常とは異なる異常な動作をAIや機械学習で分析します。そのため、未知の脅威やゼロデイ攻撃への対応が可能となり、攻撃の兆候を捉えることができます。
対応範囲の違い
EDRは「インシデントの追跡」が、EPPやアンチウィルスソフトは「ウイルス感染の防止」が主な役割です。
EPPやアンチウィルスソフトは、マルウェアやウイルスの侵入を防ぐことに特化しており、検出後の詳細な分析や対応には限界があります。
一方、EDRは攻撃を受けた後の調査や対応を重視し、感染経路や影響範囲を追跡できる機能を備えています。また、エンドポイントで発生した不審な挙動の記録を蓄積し、管理者が迅速に対応できるように支援します。
適用対象の違い
EDRは「高度な脅威対策」向け、EPPやアンチウィルスソフトは「基本的な防御」向けという違いがあります。
EPPやアンチウィルスソフトは、企業のセキュリティ対策の第一段階として広く導入され、ウイルスやマルウェアの侵入を防ぐことができます。
一方、EDRは標的型攻撃やゼロデイ攻撃への対応が求められる企業に向けた高度なセキュリティシステムです。導入には、リアルタイム監視やインシデント対応の体制が必要となるため、専門チームの運用が推奨されます。
EDRの導入メリット
- 高度な脅威を検知できる
- 影響の範囲を特定できる
- 詳細なログ分析ができる
高度な脅威を検知できる
EDRのメリットの1つ目としては「高度な脅威を検知できる」という点が挙げられます。
AIや機械学習を活用し、ゼロデイ攻撃や標的型攻撃をリアルタイムで検出できる点が強みです。シグネチャベースでは防げない未知の脅威にも対応し、企業のセキュリティ対策を強化できます。
影響の範囲を特定できる
EDRのメリットの2つ目としては「影響の範囲を特定できる」という点が挙げられます。
端末の動作履歴を詳細に記録し、攻撃の発生源や被害の広がりをリアルタイムで可視化できます。自動隔離機能を活用することで、被害を最小限に抑え、迅速なインシデント対応が可能です。
詳細なログ分析ができる
EDRのメリットの3つ目としては「詳細なログ分析ができる」という点が挙げられます。
攻撃の発生時に収集したログを基に、侵入経路や影響範囲を特定し、原因を分析できます。過去の攻撃データを活用し、将来的な攻撃への対策強化やセキュリティポリシーの改善に役立ちます。
EDRの導入デメリット
- 導入や運用のコストが発生する
- 誤検知が発生する可能性がある
- 監視体制を構築する必要がある
導入や運用のコストが発生する
EDRのデメリットの1つ目としては「導入や運用のコストが発生する」という点が挙げられます。
EDRは高度な監視機能を備えているため、初期導入費用やライセンス費用が比較的高額になる場合があります。解決策としては、クラウド型EDRを選択する、MDRサービスを活用するなど、コストを抑える方法があります。
誤検知が発生する可能性がある
EDRのデメリットの2つ目としては「誤検知が発生する可能性がある」という点が挙げられます。
端末の動作を詳細に監視するため、正常な業務プロセスも脅威と誤判断し、過剰なアラートが発生することがあります。解決策としては、ルールの最適化やAIによるアラート精度向上を行い、業務への影響を最小限に抑えることが重要です。
監視体制を構築する必要がある
EDRのデメリットの3つ目としては「監視体制を構築する必要がある」という点が挙げられます。
攻撃を検知しても、適切に分析し、即座に対応できる体制がなければ被害拡大を防ぐのが困難になります。解決策としては、SOCサービスの利用や社内のセキュリティチームの強化を図り、適切な運用体制を整えることが求められます。
EDRの選び方と比較のポイント
- ①:導入費用や運用コストで選ぶ
- ②:検知精度や対応範囲で選ぶ
- ③:使い勝手や運用負荷で選ぶ
➀:コストと導入費用で選ぶ
EDRの選び方の1つ目としては「導入費用や運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。
クラウド型EDRは、初期費用が安く、月額料金で利用できるため、コスト管理がしやすいのが特徴となっているため、主に中小企業への導入に適しています。
一方、オンプレミス型のEDRは、初期投資が高いものの、長期的な運用ではコスト削減が可能です。特に大企業では、独自のセキュリティポリシーを適用しやすく、安定した運用が期待できます。
➁:検知精度と対応範囲で選ぶ
EDRの選び方の2つ目としては「検知精度や対応範囲で選ぶ」という方法が挙げられます。
EDRの最大の特徴は、リアルタイムで脅威を検知し、即時に対応できるところにあります。そのため、機械学習を活用した高度な検知機能を持つ製品がおすすめです。
また、EDRにはエンドポイント単体で対応するタイプと、SIEM(Security Information and Event Management)と連携するタイプがあります。特に、ゼロデイ攻撃や標的型攻撃への対応を求める場合は、AI分析機能を備えたEDRが有効です。
③:使い勝手や運用負荷で選ぶ
EDRの選び方の3つ目としては「使い勝手や運用負荷で選ぶ」という方法が挙げられます。
EDRは、管理画面の使い勝手や管理運用のしやすさなどが導入の決め手となることも多く、インシデントを検知した後のスピーディな対応が重要となってきます。
また、SOC(Security Operations Center)との連携が容易なEDRを選ぶことで、運用負担をさらに軽減できます。セキュリティチームのリソースが限られている場合は、マネージドEDR(MDR)を活用する方法も選択肢の一つです。
まとめ
本記事では、EDRの主な機能解説に加えて、従来のセキュリティ対策との違いから、導入によるメリットやデメリットまで徹底的に解説していきました。
EDRは、ますます高度化を見せるサイバー攻撃に対しての有効な対応策として、今後はAIや自動化技術の進化により、検知精度や対応速度が向上すると期待されています。
今後も ITreview では、EDRのレビュー収集に加えて、新しいEDRサービスも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。