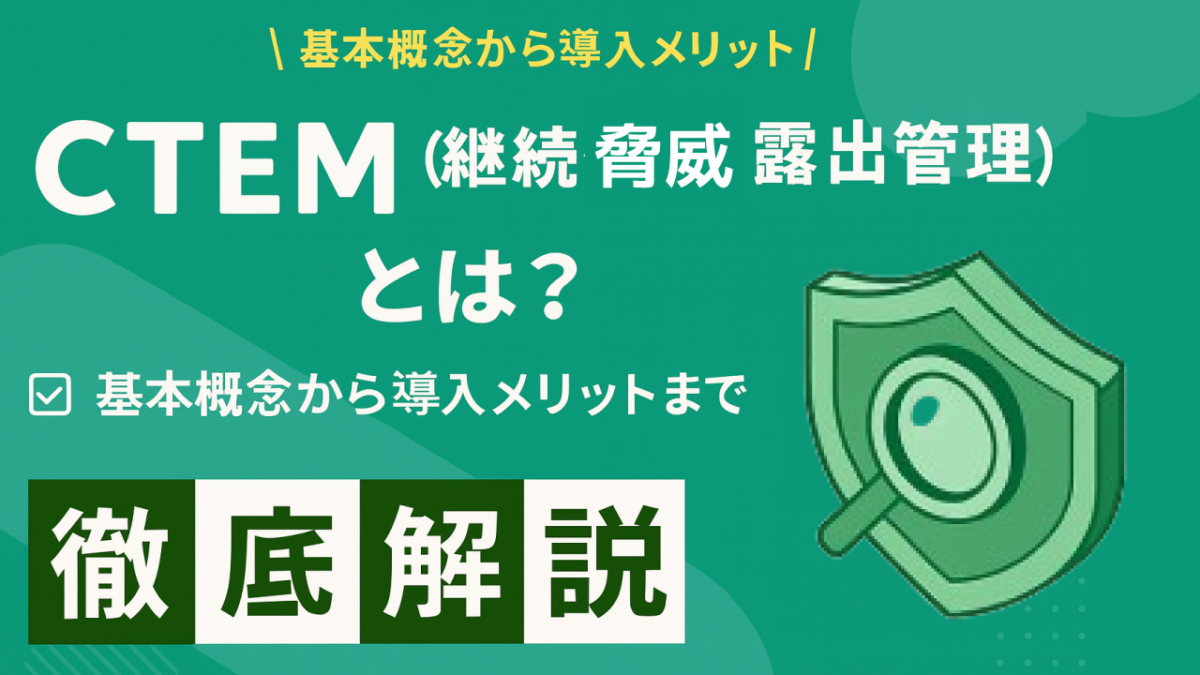CTEM(シーテム:Continuous Threat Exposure Management)とは、組織のIT環境に潜むリスクや脆弱性を継続的に可視化し、優先順位を付けて迅速な対策を行うセキュリティ管理手法のことです。
近年、ランサムウェアやサプライチェーン攻撃などのサイバー脅威が高度化するなか、多くの企業でリアルタイムかつ継続的なセキュリティ強化が求められています。
しかし、CTEMには導入のコストや人材確保といった課題があり、体制を整えずに開始してしまうと、かえって運用負荷や管理の煩雑化を引き起こすリスクもあります。
本記事では、CTEMの基本概念や注目される背景、導入によるメリット・デメリットから導入ステップまで徹底的に解説していきます。
この記事を読むだけで、CTEMの全体像をまるごと理解することができるため、サイバーセキュリティの強化や情報セキュリティ対策に悩んでいるBtoB企業の担当者には必見の内容です!
目次
CTEMとは?基本概念と定義
CTEM(シーテム)とは、英語の「Continuous Threat Exposure Management」の頭文字を取った言葉で、日本語では「継続的脅威露出管理」と訳される新しいセキュリティ概念のことです。
脅威のリスク状況を継続的に把握・管理し、実際に攻撃されるリスクにもとづいて、優先順位を付けた対策を講じるためのセキュリティ運用モデルを指します。
近年のサイバー攻撃は、理論的な脆弱性よりも実行可能な侵入口を狙う傾向にあり、例えば、パッチが適用されていない外部公開サーバーや設定ミスが残るクラウド環境など、攻撃者が容易にアクセスできる現実的な経路が狙われる傾向にあります。
CTEMは、こうした攻撃に対処するために、従来の脆弱性管理の枠組みを超えて、攻撃可能な経路(エクスポージャー)の管理に重点を置いているというのが大きな特徴となっています。
近年では、ガートナーをはじめとする調査機関によって注目されており、ゼロトラスト戦略やASM(攻撃対象領域管理)とも高い親和性を持つ新たなセキュリティ手法として注目されています。
ガートナーが提唱するCTEMの定義
米ガートナーでは、CTEMを「企業が自社のデジタル資産と物理資産のアクセス可能性、露出度、および悪用可能性を継続的かつ一貫して評価できるようにする一連のプロセスと機能」と定義しています。
同社によれば、CTEMは攻撃者視点を取り入れたリスク評価を通じて、より実践的かつ優先度の高い脅威への対応を可能にする概念とされており、従来の静的な脆弱性管理とは異なり、継続的かつ動的な評価と改善を特徴としています。
また、同社の公開した2022年のレポートでは「2026年までのCTEM導入組織のうち、少なくとも3割が重大インシデントの発生を防げる」とも発言しており、セキュリティ戦略の中心的アプローチとしての役割が強調されています。
▶ 参考:Gartner Report: Implement a Continuous Threat Exposure Management (CTEM) Program
CTEMが注目される背景
CTEMが注目される背景としては、主に以下の3つの社会的背景が挙げられます。
- サイバー攻撃の手法が高度化している
- 従来の対策では対応が困難になっている
- クラウド拡大により可視性が低下している
サイバー攻撃の手法が高度化している
CTEMが注目されるようになった理由の1つ目としては「サイバー攻撃の手法が高度化している」というものが挙げられます。
昨今の攻撃は、単純なウイルス感染にとどまらず、ゼロデイ脆弱性の悪用や多段階の侵入経路など、極めて巧妙かつ執拗な手法が主流となりつつあります。
例えば、SolarWinds事件のように、サプライチェーンを介した攻撃によって多くの大企業や政府機関が深刻な被害を受けたケースは、そのリスクの現実性を示す代表例です。日々変化する脅威に柔軟かつ継続的に対応するためのアプローチとして、CTEMの必要性が認識されているというわけです。
従来の対策では対応が困難になっている
CTEMが注目されるようになった理由の2つ目としては「従来の対策では対応が困難になっている」というものが挙げられます。
既存の脆弱性管理は、CVSSスコアを基準にして定期的な検出と修正を行う方法が一般的ですが、攻撃リスクにもとづいた評価は不十分なケースが多いのが現状です。
例えば、CVSSスコアが低くても、外部から直接アクセスできる場所であれば攻撃されやすく、数字だけでは本当の危険度を判断できないケースが多くあります。そのため、実際に攻撃されやすいポイントを起点に対策を考える必要があり、CTEMはそのギャップを埋める手段として注目されています。
クラウド拡大により可視性が低下している
CTEMが注目されるようになった理由の3つ目としては「クラウド拡大により可視性が低下している」というものが挙げられます。
企業のIT資産はオンプレミスからクラウドへと移行しており、SaaSやIaaSの利用が急増したことで、管理者が把握すべきリスクの範囲が飛躍的に拡大しています。
特に、シャドーIT”や設定ミスによるセキュリティリスクの可視化が難しくなっている現状では、従来の管理範囲だけでは脅威を把握しきれません。こうした非管理領域も含めて継続的に監視・管理できるCTEMのような新たな手法が、実践的なセキュリティ対策として注目されるようになったのです。
CTEMの5つの主要プロセス
CTEMは、単なる脆弱性検出ではなく、組織全体のセキュリティ状態を継続的に評価する一連のプロセスをともなう概念です。ここからは、その中核となる5つの主要プロセスについて、順番に解説していきます。
- ①:スコープ設定(Scoping)
- ②:発見・検出(Discovery)
- ③:優先順位付け(Prioritization)
- ④:検証・確認(Validation)
- ⑤:動員・対応(Mobilization)
①:スコープ設定(Scoping)
CTEMにおける1つ目のステップは、評価を行う対象を明確に定義する「スコープ設定(Scoping)」のフェーズです。
この段階では、自社のネットワークやクラウド、アプリケーションやサプライチェーンなど、管理対象とする「IT資産や業務プロセスの範囲」を定義します。
例えば、国内外に拠点を複数展開しているような企業では、各拠点ごとの体制の違いや管理範囲を定義することで、無駄のない調査とリソースの適切配分を実現することができます。
②:発見・検出(Discovery)
CTEMにおける2つ目のステップは、対象範囲の中に存在するリスクを洗い出す「発見・検出(Discovery)」のフェーズです。
この段階では、脆弱性スキャナーやクラウド構成管理ツール、EDRなどを活用して、攻撃対象の領域に存在する「既知または潜在的なリスク」を発見します。
特に、クラウド環境やリモートワーク環境が普及している現在では、見落とされがちなエンドポイントや構成ミスを可視化する工程として、極めて重要度の高いフェーズといえます。
③:優先順位付け(Prioritization)
CTEMにおける3つ目のステップは、発見されたリスクの対応優先度を定める「優先順位付け(Prioritization)」のフェーズです。
この段階では、CVSSスコアや脅威インテリジェンスなどを組み合わせることで、単なる数値上の危険性ではなく「実際に発生可能性の高い脅威」を特定します。
優先順位の判断精度を高めることで、修正作業の負荷軽減と迅速な対処を両立することができるため、限られたセキュリティリソースをより効果的に活用できる体制構築が可能です。
④:検証・確認(Validation)
CTEMにおける4つ目のステップは、実際に攻撃が成功するかどうかを検証する「検証・確認(Validation)」のフェーズです。
この段階では、自動化されたペネトレーションテストや攻撃シミュレーションツールを用いることで、理論上の脅威が「現実に成立するかどうか」を検証します。
実証ベースでの検証を繰り返すことで、既存のセキュリティ対策の有効性や抜け漏れの有無なども同時に明らかにすることができるため、対策の再構築や強化につなげることが可能です。
⑤:動員・対応(Mobilization)
CTEMにおける5つ目のステップは、検証結果にもとづいて実際の対策を実施する「動員・対応(Mobilization)」のフェーズです。
この段階では、これまでのプロセスを通じて、本当に対処すべき脅威に対して、現場の対応チームや関連部門が連携して「具体的な修正作業や改善策」を適用します。
また、このステップには、パッチの適用や設定変更、アクセス制御の強化や業務プロセスの見直しなども含まれており、総合的な対策を実行するCTEM全体の推進力として機能します。
CTEMと既存のセキュリティ手法との違い
CTEMは、従来のセキュリティアプローチとは異なる視点からリスクを捉え、より実践的な対応を可能にする新たなセキュリティ概念です。ここからは、CTEMと従来手法の違いについて比較していきます。
| 項目 | CTEM(継続的脅威露出管理) | VM(脆弱性管理) | ASM(攻撃対象領域管理) | CSPM(クラウド構成管理) |
|---|---|---|---|---|
| 主な目的 | 攻撃可能なリスクの発見と対応 | 既知の脆弱性の検出と修正 | 外部公開資産の可視化と管理 | クラウド構成ミスの検出と修正 |
| 評価対象 | 攻撃シナリオと実際の露出経路 | ソフトウェアやシステムの脆弱性 | ドメイン・IP・Webなどの外部資産 | IaaSやPaaSなどのクラウド環境 |
| 評価指標 | 攻撃者視点による実行可能性 | CVSSスコアが中心 | 限定的なリスク分類が中心 | ベストプラクティス違反が中心 |
| 検証機能 | 攻撃予測やBASで検証可能 | 検証機能は基本なし | 検証機能は基本なし | 限定的な検証機能あり |
| 継続性 | 継続的かつ循環的 | 定期スキャンの実施 | 継続監視が基本 | 継続監視が基本 |
| 運用難易度 | 高 (統合的な運用が必要) | 中 (単体での導入が可能) | 低 (可視化が中心) | 中 (クラウドに特化) |
CTEMとVM(脆弱性管理)との違い
CTEMとVM(脆弱性管理)との最大の違いは「優先順位の基準」という部分にあります。
従来の脆弱性管理では、CVSSスコアや公開日などの静的な情報が重視されてきましたが、CTEMでは攻撃可能性やアクセス経路といった、より現実的かつ動的なリスク指標が評価の中心となります。
例えば、CTEMのアプローチでは、パッチ未適用の脆弱性が存在していた場合でも、外部に露出していなければ即時対応は不要と判断されるケースもあり、実際に悪用される可能性をもとに判断するのが大きな特徴です。
CTEMとASM(攻撃対象領域管理)との違い
CTEMとASM(攻撃対象領域管理)は「攻撃対象となる領域の可視化」という点で重なる部分がありますが「範囲と役割」が明確に異なります。
ASMは、外部公開されているIT資産(ドメインやアプリなど)を継続的に監視しており、主に何が見えているかを検出することに特化した仕組みです。
一方でCTEMは、その検出結果に加えて、リスクの検証から優先順位付け、対応までを含めた包括的な運用サイクルを実現する部分に優位性があり、ASMはその一部を構成する要素として機能します。
CTEMとCSPM(クラウド構成管理)との違い
CTEMとCSPM(クラウド構成管理)は「クラウド環境のリスク管理」という点で重なる部分がありますが「焦点とスコープ」が明確に異なります。
CSPMは、クラウドの構成ミスやベストプラクティス違反などの検出に特化しており、主にクラウド環境の設定や権限の監査に焦点を当てた仕組みです。
一方でCTEMは、オンプレミス・クラウドを問わず攻撃経路全体を評価対象として、発見された設定ミスが実際に悪用可能かどうか検証するという部分で、CSPMを補完する立ち位置にあるといえます。
CTEM導入のメリット
CTEM導入のメリットとしては、主に以下の3つのメリットが挙げられます。
- 継続的なリスクの可視化を実現できる
- 脅威対応の迅速化と効率化を実現できる
- セキュリティ投資の最適化を実現できる
継続的なリスクの可視化を実現できる
CTEM導入の1つ目のメリットとしては「継続的なリスクの可視化を実現できる」というものが挙げられます。
多くの企業では、脆弱性や設定ミスの検出がスポット対応にとどまっており、日々変化するIT環境への継続的な対応が困難になっています。
CTEMでは、IT資産や攻撃経路を継続的に監視・分析する仕組みが整っているため、常に最新のリスク状況を把握したうえで、戦略的なセキュリティ強化を行うことができるようになります。
脅威対応の迅速化と効率化を実現できる
CTEM導入の2つ目のメリットとしては「脅威対応の迅速化と効率化を実現できる」というものが挙げられます。
従来のセキュリティ運用では、検出から修正までに時間が要することが多く、対応が後手に回ってしまうことが大きな課題となっていました。
CTEMでは、リスクの発見・優先順位付け・検証・対応を1つのサイクルとして継続的に回す運用モデルを採用しているため、現実的なリスクに絞った効率的な対処ができるようになります。
セキュリティ投資の最適化を実現できる
CTEM導入の3つ目のメリットとしては「セキュリティ投資の最適化を実現できる」というものが挙げられます。
限られたリソースや予算の中で最大限の効果を発揮するには、どの脅威に、どのタイミングで対応するかという判断が極めて重要になります。
CTEMでは、実際の攻撃可能性をもとに優先度を決定するため、無駄のないセキュリティ対策を実現しながら、効率的かつ戦略的なリスクマネジメントが実現できるようになります。
CTEM導入のデメリット
CTEM導入のデメリットとしては、主に以下の3つのデメリットが挙げられます。
- 組織体制の整備を実施する必要がある
- 既存のシステムとの連携が必要になる
- 短期的な導入効果が可視化されにくい
組織体制の整備を実施する必要がある
CTEM導入の1つ目のデメリットとしては「セキュリティ部門だけで完結しない組織体制を整備する必要がある」というものが挙げられます。
CTEMは、リスクの優先順位付けから検証、対応までを継続的に運用するフレームワークであるため、情報セキュリティ部門、業務部門、経営層との横断的な連携が不可欠となります。
特に、部門同士の情報共有や意思決定プロセスの整備を事前に行っていない場合、せっかくのCTEMが効果を発揮しない可能性も考えられるため、導入初期段階から体制構築を意識した準備が求められます。
既存のシステムとの連携が必要になる
CTEM導入の2つ目のデメリットとしては「既存のセキュリティシステムや監視ツールとの連携が必要になる」というものが挙げられます。
CTEMは、単独で完結する仕組みではなく、脆弱性管理ツール、EDR、SIEM、SOAR、アセット管理システムなどの既存のセキュリティ基盤と連携しながら機能するのが一般的です。
特に、EDRやSIEMなどのツールと連携しないまま運用を始めてしまうと、データの断絶や二重管理によって効率が損なわれるリスクがあるため、ツールの相性や拡張性を事前に見極めることが重要です。
短期的な導入効果が可視化されにくい
CTEM導入の3つ目のデメリットとしては「短期的ではシステムの導入による効果測定が難しい傾向にある」というものが挙げられます。
CTEMは、未然防止の性質が強く、実際のインシデント発生を回避できたかどうかの評価が難しいため、経営層にとっては導入による投資効果を実感しづらいという側面があります。
特に、導入後の初期段階は、コストやリソースの負担が目立ちやすくなってしまうため、検出数の推移やMTTR(平均対応時間)などのKPIを定義して、定量的に評価できる仕組みづくりを行うことが重要です。
CTEM導入を成功させる5つのステップ
CTEMを効果的に導入するには、場当たり的な導入ではなく、計画的かつ段階的なアプローチが求められます。ここからは、導入成功に向けた5つのステップについて、順番に解説していきます。
- ①:現状のセキュリティ体制を評価する
- ②:具体的なソリューションを選定する
- ③:段階的な導入計画を策定する
- ④:運用の体制とプロセスを構築する
- ⑤:継続的な改善サイクルを確立する
①:現状のセキュリティ体制を評価する
CTEM導入の1つ目のステップは「現状のセキュリティ体制を評価する」というものが挙げられます。
CTEMは、既存のセキュリティ戦略やシステム構成を土台として運用されるため、導入前には、現行体制の利点や弱点などを明確に把握しておく必要があります。
例えば、現状の脆弱性管理手法やEDRの運用状況、インシデントへの対応フローなどを棚卸しすることで「どの部分にCTEMを組み込むべきか」を具体的に計画することができます。
②:具体的なソリューションを選定する
CTEM導入の2つ目のステップは「具体的なソリューションを選定する」というものが挙げられます。
市場には様々なCTEMソリューションが存在するため、組織の規模や業界特性、予算に応じて、最適なツールやプラットフォームを選択することが必要不可欠です。
例えば、脅威インテリジェンス機能の充実度や既存システムとの連携性などを事前に比較検討しておくことで「自社の要件に最も適したソリューション」を特定することができます。
③:段階的な導入計画を策定する
CTEM導入の3つ目のステップは「段階的な導入計画を策定する」というものが挙げられます。
CTEMでは、全ての機能を一度に導入するのではなく、組織の現状や諸々の準備状況に合わせて、段階的に機能を展開していく計画を立てることが成功の鍵となります。
例えば、脅威の優先度付けから開始し、次に測定と検証機能を追加、最終的に対応を自動化させるなど「計画的かつ段階的なロードマップの策定」がスムーズな全社展開につながります。
④:運用の体制とプロセスを構築する
CTEM導入の4つ目のステップは「運用の体制とプロセスを構築する」というものが挙げられます。
CTEMの導入効果を最大限に発揮するためには、適切な人材配置や明確な役割分担をはじめとする、標準化された運用プロセスを確立させることが何よりも重要です。
例えば、脅威アナリストの育成やエスカレーション手順の明文化、定期的なレビュー会議の設定などを通じて「属人的ではない持続可能な運用体制とプロセス」を構築することができます。
⑤:継続的な改善サイクルを確立する
CTEM導入の5つ目のステップは「継続的な改善サイクルを確立する」というものが挙げられます。
CTEMは、一度導入して終わりというものではなく、脅威環境の変化や組織の成長に合わせて、継続的に改善と最適化を行っていく必要があるセキュリティ概念です。
例えば、月次のレポートや四半期ごとのプロセスの見直し、年次の戦略レビューなどの効果測定を実施することで「脅威に強い進化し続ける改善サイクル」を維持することができます。
まとめ
本記事では、CTEMの基本概念や注目される背景、導入によるメリット・デメリットから導入ステップまで徹底的に解説していきました。
サイバー攻撃の高度化やクラウド環境の普及により、IT環境はかつてない複雑さを抱えるようになり、従来の静的なセキュリティ対策では限界が見え始めています。
そのような状況において、CTEMは攻撃者視点での評価と対応を継続的に行うことで、セキュリティ運用の実効性と効率性を大幅に向上させる役割が期待されています。
今後もITreview では、日々進化を続けるSaaS市場の最新情報について、ユーザーの皆様へ真に価値あるコンテンツをお届けしていきます。ツールの選定にお悩みの方や最新トレンドに関心のある方などは、ぜひ次回の記事もご覧ください。