RPA(Robotic Process Automation)とは、ソフトウェアロボットを活用して業務プロセスを自動化する技術のことです。
近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や労働力の不足を背景に、多くの企業がRPAの導入を推進しており、業務の効率化や生産性の向上を実現しています。
しかし、RPAは決して万能のツールというわけではなく、複雑な判断を要する業務や非定型的な業務には適していないため、適用範囲を正しく理解することが重要です。
本記事では、RPAの基本概念からAIとの違い、導入によるメリット・デメリットや活用事例まで詳しく徹底的に解説していきます。
また、ツールの選定ポイントや導入ステップについても紹介しているため、RPAの導入を検討している企業担当者には必見の内容です!
▶ 関連記事:RPAの無料製品9選|ツールの特徴や選定基準を紹介
▶ 関連記事:実績豊富なRPA製品10選|市場シェアや評判の高いツールを紹介
目次
RPAとは?
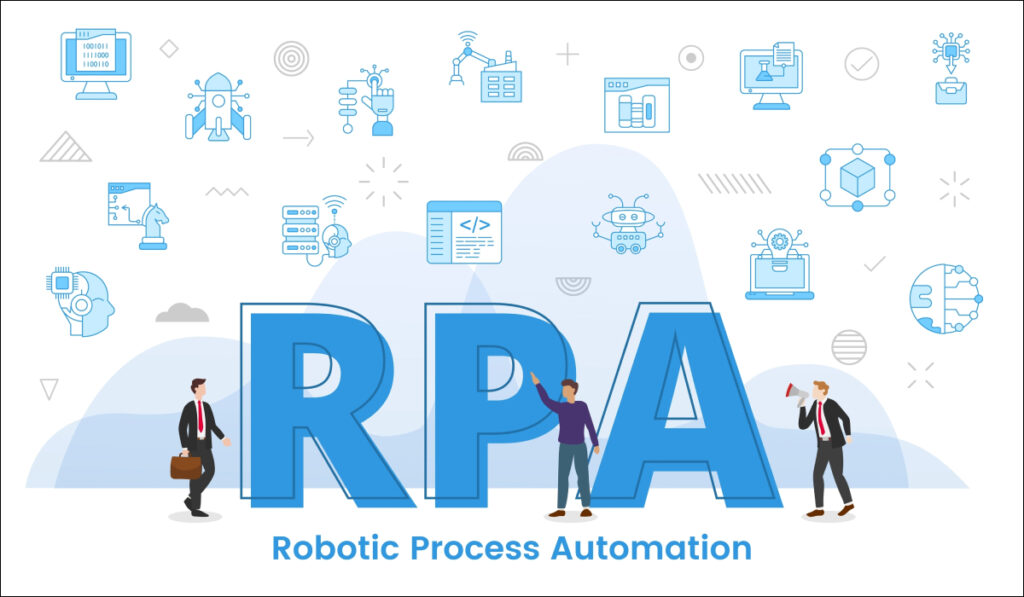
RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティックプロセスオートメーション)の略で、ロボットを活用して定型業務を自動化する技術のことです。
主に、繰り返し発生するデータの入力作業や計算の処理、管理業務などを自動化することができ、企業の業務効率や生産性の向上に大きく貢献します。
また、ルールベースのタスクを自動で実行できるため、バックオフィスやカスタマーサポートなど、分野を問わず幅広い企業や業種で活用されています。
具体的な活用事例としては、経理部門では請求書の処理、人事部門では勤怠データの集計などが挙げられ、様々な業務を自動化できるようになります。
RPAが注目されるようになった理由
- 労働人口の減少によるニーズの拡大
- 働き方改革による業務効率化の加速
- AIやクラウドなどの先端技術の進化
労働人口の減少によるニーズの拡大
RPAが注目されるようになった理由の1つ目としては「労働人口の減少によるニーズの拡大」というものが挙げられます。
特に、少子高齢化が進む日本をはじめとする多くの先進国では、企業は深刻な人手不足に直面しており、限られたリソースで効率的に業務を遂行する能力が求められています。
RPAは、定型業務を自動化することができるため、例えば、経理や人事部門では、RPAを活用したデータ入力や書類作成業務を自動化することで、社員がより価値の高い仕事に集中できるようになります。
働き方改革による業務効率化の加速
RPAが注目されるようになった理由の2つ目としては「働き方改革による業務効率化の加速」というものが挙げられます。
政府が進める働き方改革や企業が行う生産性向上が加速するなかでは、業務の効率化が重要な課題となっており、とりわけ反復的かつ単調な事務作業の効率化が求められています。
RPAは、定型業務の自動化を実現するツールとしてニーズに合致しており、例えば、経費精算や請求書の処理といった業務を自動化することで、従業員はより戦略的な業務に専念できるようになります。
AIやクラウドなどの先端技術の進化
RPAが注目されるようになった理由の3つ目としては「AIやクラウドなどの先端技術の進化」というものが挙げられます。
昨今のRPAは、AIやクラウドといった先端技術の発展により、ますます高度な自動化が可能となっており、スケーラビリティやコストカットの観点でもメリットが増しています。
AIとの組み合わせにより、RPAは単なる反復作業の自動化だけではなく、例えば、売上の予測分析や意思決定の支援などの自動化も可能となっており、より複雑な業務にも対応できるようになっています。
RPAとAIの違い
| RPA | AI | |
|---|---|---|
| 導入目的 | 反復的な定型業務の自動化 | 問題解決や意思決定の支援 |
| 動作範囲 | ルールベース | 自然言語処理 |
| 導入費用 | 安い | 高い |
| 運用費用 | 高い | 安い |
| 学習能力 | あり | なし |
| 実行速度 | 速い | 遅い |
| 柔軟性 | 低い | 高い |
| 難易度 | 低い | 高い |
RPAはあらかじめ設定されたルールに従って作業を遂行するのに対し、AIは自然言語処理を用いた問題解決や意思決定の支援を得意とするツールです。
例えば、RPAは請求書処理やデータ入力などの作業を自動化しますが、AIは文書の内容を理解してリスクを検出するなどの高度な判断を可能とします。
RPAで自動化できる業務事例
| RPAの得意分野 | AIの得意分野 | |
|---|---|---|
| データの入力 | ◯ | ✕ |
| メールの送信 | ◯ | ✕ |
| 請求書の処理 | ◯ | ✕ |
| データの予測 | ✕ | ◯ |
| クリエイティブ | ✕ | ◯ |
| 問い合わせ対応 | ✕ | ◯ |
RPAが得意な業務(できること)
RPAは、繰り返し発生する業務やルールベース処理に適しており、データの入力や請求書処理、メール送信など、人手を介さずに一定のルールに従って実行できる業務が該当します。
具体的な業務内容としては、経理業務における仕訳の作成や人事の勤怠管理業務、営業の顧客データ更新などが挙げられます。
RPAが不得意な業務(できないこと)
RPAは、非定型業務や高度な判断が求められる業務には適しておらず、クリエイティブな作業や曖昧なデータの処理が必要な業務においては、RPA単体では対応することができません。
具体的な業務内容としては、顧客対応における複雑な問い合わせ対応や戦略的な意思決定がともなう業務などが挙げられます。
RPAツールの導入メリット
- 定型的な業務を効率化できる
- コスト削減効果が期待できる
- ヒューマンエラーを削減できる
定型的な業務を効率化できる
RPAのメリットの1つ目としては「定型的な業務を効率化できる」というものが挙げられます。
これまで手作業で行っていた業務や定型作業を自動化することができるため、業務の処理速度が向上し、戦略的な業務に集中できるようになります。
例えば、経理の請求書処理や営業のデータ入力をRPAで自動化することで、人的リソースを削減しながら業務のスピードを向上できるようになります。
コスト削減効果が期待できる
RPAのメリットの2つ目としては「コスト削減効果が期待できる」というものが挙げられます。
24時間稼働が可能なRPAは、時間外労働を減らすことができるため、業務スピードが向上するのと同時に、リソースの無駄を削減できるようになります。
例えば、手作業で行っていたデータ整理やシステムへの登録を自動化することで、業務負担を軽減しながらトータルコストを削減できるようになります。
ヒューマンエラーを削減できる
RPAのメリットの3つ目としては「ヒューマンエラーを削減できる」というものが挙げられます。
RPAは決められたプロセスを確実に実行するため、入力や集計業務などのミスが発生しやすい領域においては、精度の向上を実現できるようになります。
例えば、データ管理や契約情報の処理などをRPAで自動化することによって、正確性を向上させながらミスの発生を最小限に抑えられるようになります。
RPAツールの導入デメリット
- 導入や運用にはコストが発生する
- 定型業務の自動化には限界がある
- 管理やメンテナンスが必要になる
導入や運用にはコストが発生する
RPAのデメリットの1つ目としては「導入や運用にはコストが発生する」というものが挙げられます。
RPAの導入には、ソフトの購入やインフラの整備、運用維持にかかるコストが必要となるため、短期的には相応の導入運用コストが発生することを理解しておく必要があります。
ツールを選定するときには、クラウド型のRPAツールを選択したり、無料トライアルやフリープランを活用したりなど、費用を最小限に抑えるための工夫が必要です。
定型業務の自動化には限界がある
RPAのデメリットの2つ目としては「定型業務の自動化には限界がある」というものが挙げられます。
RPAは、あらかじめ設定されたルールにもとづいて業務の自動化を遂行するツールであるため、複雑な判断や非定型業務には対応できないことを理解しておく必要があります。
ツールを選定するときには、あらかじめ対応できる業務の範囲を確認したり、AIを搭載したツールを検討したりなど、業務の種類を考慮したツールの選定が重要です。
管理やメンテナンスが必要になる
RPAのデメリットの3つ目としては「管理やメンテナンスが必要になる」というものが挙げられます。
RPAは、システムや業務フローを変更した場合、アップデートやエラー対応が求められるため、定期的な保守とメンテナンスが必要であることを理解しておく必要があります。
ツールを選定するときには、メンテナンスパックがあるサービスを検討したり、変更しやすいサービスを選んだりなど、更新の手間を考慮したツール選定が大切です。
RPAツールの選び方と比較のポイント
- ①:使いたい業務に対応しているか
- ②:必要な機能は網羅されているか
- ③:料金やコストは予算の範囲内か
- ④:外部システムとの連携は可能か
- ⑤:セキュリティ対策機能は十分か
- ⑥:サポート体制は充実しているか
①:使いたい業務に対応しているか
RPAツールの選び方の1つ目としては「使いたい業務に対応しているか」というものが挙げられます。
RPAツールは、業務内容に合わせてカスタマイズできるものが理想的です。特に、特定の業務プロセスを自動化したい場合には、そのプロセスに合った最適なツールを選ぶことを心がけましょう。
例えば、定型業務を自動化したい場合には操作を模倣できるツールを、複雑な業務を自動化したい場合には高度に操作できるツールを選びましょう。
②:必要な機能は網羅されているか
RPAツールの選び方の2つ目としては「必要な機能が網羅されているか」というものが挙げられます。
ツールを選定する場合、必要な機能がツールに含まれているかを確認することが大切です。特に、データ入力やエラーハンドリングといった基本的な機能が含まれているかは、事前にチェックしましょう。
例えば、ロギング機能や監視機能が充実したツールを選ぶことで、トラブルの発生時でも迅速に対応できるため、機能の確認は慎重に行うべきです。
③:料金やコストは予算の範囲内か
RPAツールの選び方の3つ目としては「料金やコストが予算の範囲内か」というものが挙げられます。
導入にあたっては、初期費用やライセンス料だけではなく、運用コストも考慮することが重要です。特に、ツール選定にあたっては、投資対効果(ROI)が見込めるかは事前に検証するようにしましょう。
例えば、クラウド型は初期費用が少ないため、スモールスタートには最適です。反対にオンプレミス型は運用コストが少ないため、長期運用に最適です。
④:外部システムとの連携は可能か
RPAツールの選び方の4つ目としては「外部システムとの連携は可能か」というものが挙げられます。
RPAツールは、外部の業務システムやアプリケーションと連携することが重要です。特に、ERPシステムやCRMシステム、データベースとの連携が可能なツールは、効率的な業務自動化には欠かせません。
例えば、 API連携やデータベース接続を搭載したツールを選ぶことで、異なるシステム間でもデータの転送や処理をスムーズに行うことができます。
⑤:セキュリティ対策機能は十分か
RPAツールの選び方の5つ目としては「セキュリティ対策機能が十分か」というものが挙げられます。
業務によっては機密情報を扱うこともあるため、セキュリティ対策は非常に重要です。特に、クラウド型のRPAツールを利用する場合には、通信暗号化や認証機能の有無をチェックしておきましょう。
例えば、 認証機能やデータ暗号化機能が実装されているツールを選ぶことで、不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。
⑥:サポート体制は充実しているか
RPAツールの選び方の6つ目としては「サポート体制が充実しているか」というものが挙げられます。
運用支援がしっかりしているかを確認することは、トラブル発生時の迅速な解決に繋がります。特に、RPAに慣れていない企業では、ベンダーのサポート体制を事前に確認しておくことが重要です。
例えば、24時間対応のサポートやFAQ、トラブルシューティングガイドが充実しているツールを選ぶことで、万が一の問題にも対応しやすくなります。
RPA市場の動向と今後の展望
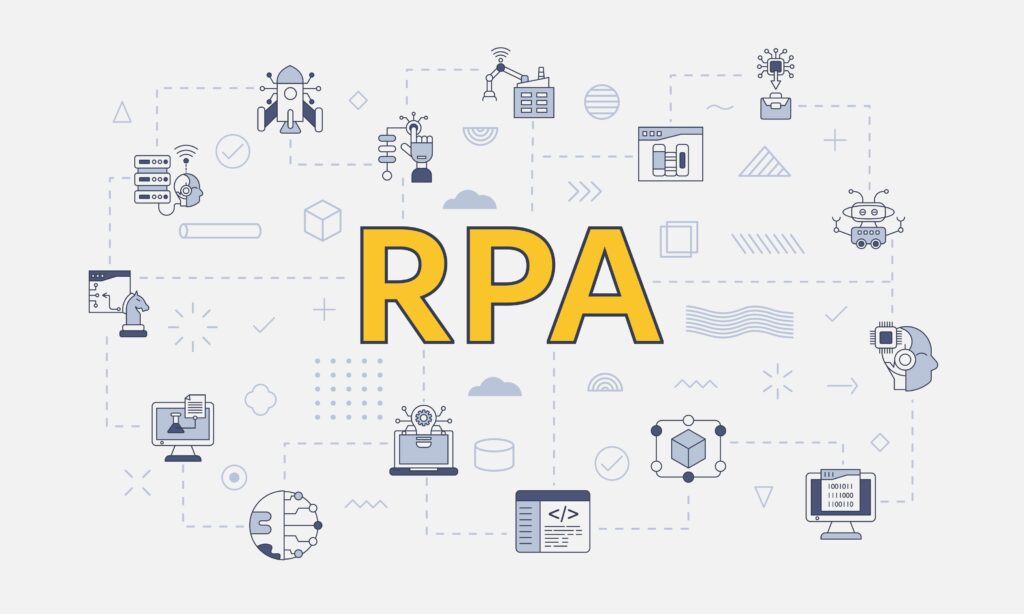
RPA市場の成長と普及の状況
RPA市場は急速に成長しており、多くの企業が業務効率化のために導入を進めています。
デロイトトーマツミック経済研究所の調査によると、2025年までに国内のRPA市場の規模は約1183億円に到達する見込みとなっており、さらなる拡大が予測されています。
出典:国内RPA市場は年10%超で堅調に推移、オンプレミス製品が9割|IT Leaders
AIとの融合による高度な自動化
近年のRPA市場では、AI技術との連携による高度かつ複雑な業務の自動化が進んでいます。
例えば、OCR技術とAIを組み合わせることで、手書き文書やPDFファイルの内容を読み取って、自動でデータ化を実行するなど、より高度な業務の自動化が実現しています。
まとめ
本記事では、RPAの概要をわかりやすく解説するのに加えて、導入のメリット・デメリット、業務分野別の活用事例、ツール選定のポイントまで、徹底的に解説しました。
世界的にも急成長を遂げているRPA市場ですが、昨今ではAIやクラウドとの連携が進み、より高度な自動化が可能になることで、今後もさらなる市場の拡大と発展が予測されています。
今後もITreviewでは、RPAツールのレビュー収集に加えて、新しいRPAサービスの情報を随時掲載する予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。



