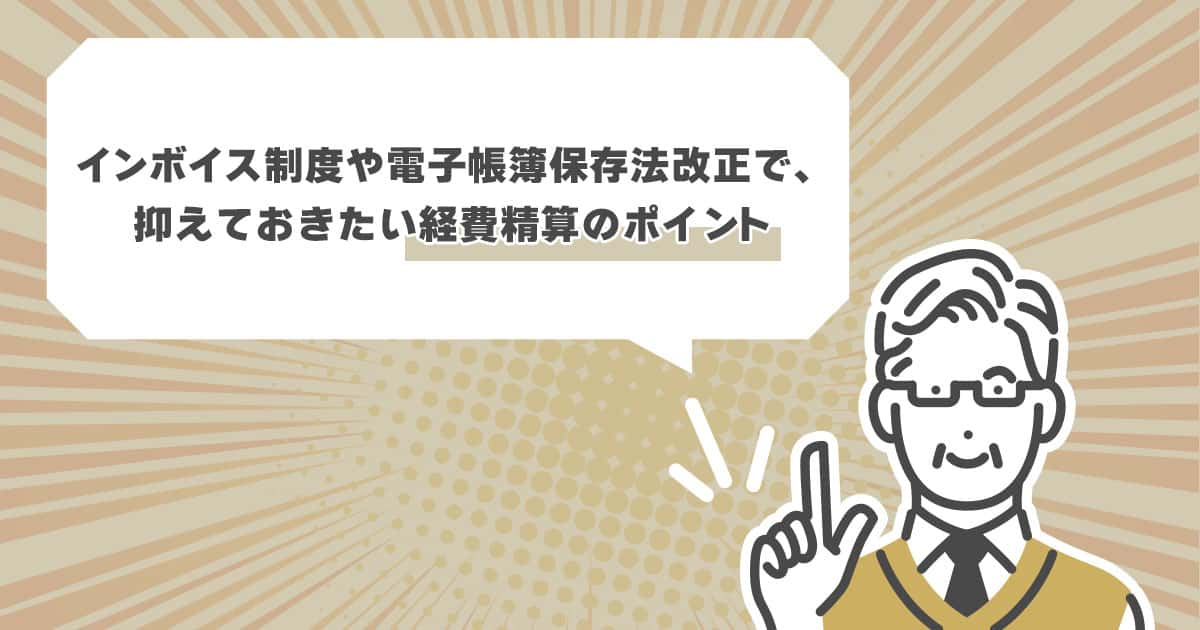2023年10月1日から開始する「インボイス制度」および2022年1月1日から施行されている「電子帳簿保存法改正」により、経費精算の方法が大きく変化します。すでに義務化が進んでいる2つの項目を知っている人もいるでしょう。しかし、内容を詳しく理解できていない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、インボイス制度の導入と電子帳簿保存法改正について、経費精算がどう変化するのか、また経費精算システムについて解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度(別名、適格請求書制度)とは、サービスの「売り手」が「買い手」に対して、正しい適正税率や消費税額などを伝える制度のことです。
この制度が作られたのは、消費税8%と10%の混在に伴い「政府が正しい消費税を把握できていない」ことが背景にあり、各事業主に正しい税金を納めてもらうため、2023年10月1日より適用される形となりました。
インボイス制度は、消費税の「仕入税額控除」を利用するために必ず登録が必要です。もし買い手が売り手にインボイスを請求したら、売り手は必ずインボイスを交付しなければなりません。
インボイス制度の導入に伴う経費精算の3つの変化
1・請求書の記載項目
インボイス制度を利用できるのは、適格請求書発行事業者として登録している事業者だけで、登録者・非登録者の違いによって請求書の記載項目が変化します。売り手が登録者である場合は、次の項目が記載された請求書を発行する必要があります。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとの消費税額
注意点として、非登録者に請求書を発行する際には、支払いの消費税が「仕入税額控除」の対象とならないようにしなければなりません。
2・仕訳
帳簿作成に欠かせない仕訳の「消費税」の項目が変化します。今までの消費税申告では、8%、10%をまとめて仕入税額に入れて問題ありませんでした。一方インボイス制度開始後は、次の2項目に分けて仕入税額を入力する必要があります。
- 仕入税額対象の課税仕入8%
- 仕入税額対象の課税仕入10%
2つの使い分けとして、取引先が適格請求書発行事業者として登録しているか否かで仕訳方法が細かく変わるので注意が必要です。
3・消費税の計算方法
売上および仕入に対する消費税の計算方法が次の2つに変化します。
- 積上げ計算(インボイスの消費税を積み上げ)
- 割戻し計算(適用税率ごとに割り戻し)
原則として売上税額は「割戻し計算」、仕入税額は「積上げ計算」を利用することとなっているので、計算方法の誤りに注意しましょう。
電子帳簿保存法改正とは?
電子帳簿保存法改正とは、国に納める税金の帳簿書類や電子データを保存することを定めた法律であり、2022年1月1日より施行されています。
この改正の背景には、コロナウイルスに伴うテレワークの普及が関係しており、場所を問わず働く際に紙資料の非効率化が顕在化したことが挙げられます。また改正では、次のような要件緩和と規制強化が新たに設けられています。
- 以下3つの要件を満たせば電子データ保存が認められる(規制緩和)
- システム関係書類などの備え付け
- 税務職員による電子データのダウンロードの求めに対応していること
- 見読可能性の確保
- 電子データとして受領した請求書・領収書は電子データのまま保存(規制強化)
- 申告漏れに生じる重加算税が10%加重(規制強化)
今までの紙資料管理をすべて電子データで管理するようになるので、事業者は納税に対する新たな動き方が必要となります。
電子帳簿保存法改正による経費精算の変化
電子帳簿保存法改正による経費精算の変化は次の通りです。
- 帳簿保存
- スキャナ保存
- 電子取引データ保存
帳簿保存
帳簿の保存方法が変化しました。
従来、紙資料として保管するのが一般的でしたが、改正後は電子データのみで管理した電子帳簿が「優良な電子帳簿」として格上げされ、過少申告加算税が5%軽減されるようになります。
また、青色申告特別控除額である65万円は「優良な電子帳簿」として認められることが適用の条件となります。
スキャナ保存
帳簿データのスキャナ保存に対する手続きが簡略化されました。
従来必要とされていたタイムスタンプや定期検査、相互保存チェックが不要となり、領収書に対しての自署も廃止されています。スキャナ保存の手間が大幅に削減されたことに伴い、電子データの管理が簡単になっています。
電子取引データ保存
2024年1月以降は電子取引データを、原則電子データのみで管理する必要があります。
従来、電子取引データを紙に印刷して保存する事業者も多くありましたが、改正に伴い電子データのみで管理しなければ税務署に認可してもらえないこととなっています。ただし、消費税関連の電子取引は事業者負担が大きいため、唯一、紙としての保管が認められています。
経費精算の変化を理解したら経費精算ツールを比較検討しよう
インボイス制度の導入および、電子帳簿保存法改正に伴い、経費精算の仕方が大きく変化します。また、納税額や控除額、それらの条件にも変化が生まれている状況であり、事業者は早急に制度・法律への対応を進める必要があります。このとき、制度・法律に則り、効率良く帳簿を作成できるのが「経費精算ツール」です。
経費精算ツールについて詳しく理解してから導入を検討したいのなら、まずはITreviewが提供するツール紹介ページを参考に、気になる製品を比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。