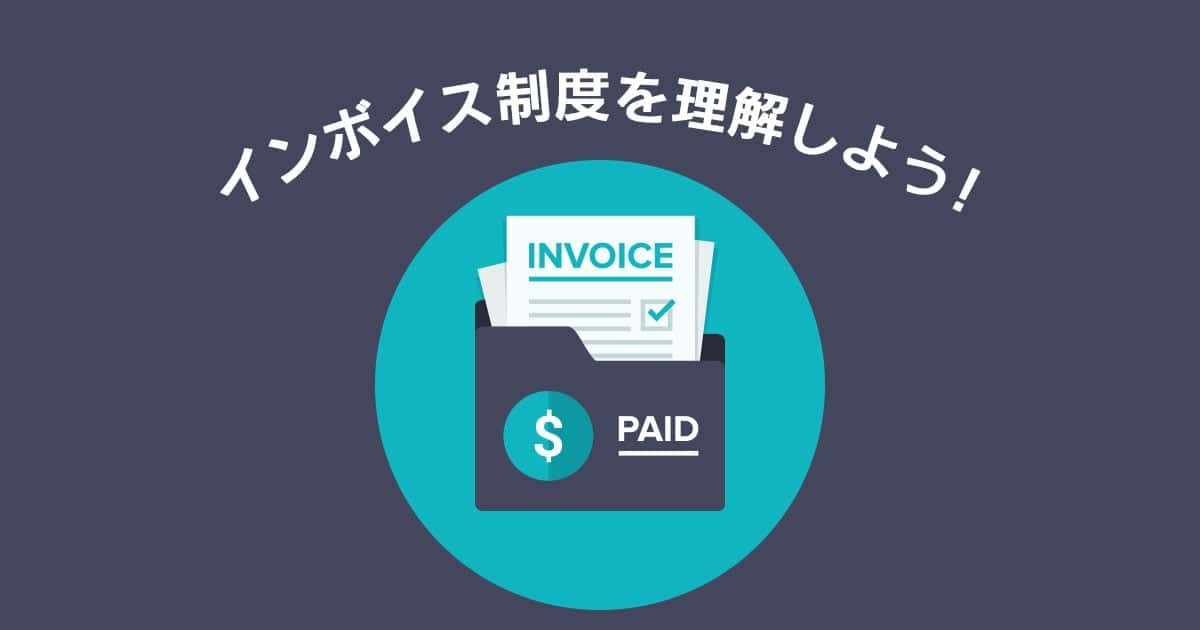2023年10月1日に開始する「インボイス制度」。しかし、詳しい概要やスケジュールを把握していない人もいるでしょう。
そこで本記事では、インボイス制度のおさらいとして、覚えておくべき用語とスケジュールをご紹介します。インボイス制度への対応に遅れないためにも、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度に関連する覚えておきたい用語
インボイス制度では、さまざまな専門用語が登場します。そこで、インボイス制度で関わってくる5つの言葉をご紹介します。用語を理解できればインボイス制度のことを理解しやすくなるので、事前知識としてチェックしてみてください。
インボイス制度(適格請求書保存方式)
インボイス制度とは、売手と買手でインボイス(適格請求書)のやり取りを行い、正しい消費税額を税務署に伝えるための制度です。正式名称を「適格請求書保存方式」といい、以下に示す請求書・納付書を発行・保存します。
- 適格請求書(インボイス)発行業者の氏名・名称・登録番号
- 取引年月日
- 取引内容・仕分
- 適用税率(8%or10%)
- 消費税額
- 買手側の事業者名・名称
インボイス制度は、発注者(買手)・受注者(売手)で異なる動きをします。まず、受注者となる「売手」は、請け負った業務の発注額に対して、正しい適用税額や消費税額を記入した請求書を保管する必要があります。この請求書がいわゆるインボイスです。また、買手からどれくらいの消費税がかかったのかを確認されたら、売手は買手にインボイスを発行しなければなりません。
次に、発注者となる「買手」は、確定申告で必要となる「仕入税額控除の適用」を受けるために、売手が発行したインボイスを保管しておく必要があります。
インボイス(適格請求書)
インボイス(適格請求書)とは、インボイス制度の中で取り交わす請求書のことです。前述した箇条書きの項目を記入する必要があることから、インボイス制度が開始する前とは請求式の様式が異なるので注意してください。
また、経理業務で利用する領収書やレシートのことは「簡易インボイス(簡易適格請求書)」と呼びます。どちらも同じような項目を書き込む必要がありますが、目的が異なるため、2つの違いを理解しておきましょう。
適格請求書発行事業者
適格請求書発行事業者とは、インボイス(適格請求書)の発行を国から認められた課税事業者のことです。インボイスは、適格請求書発行事業者に登録されていなければ発行できません。適格請求書発行事業者として認められるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。
提出した書類は一度、税務署内で審査が行われます。内容に問題がなければ提出者に「登録通知書」を発行し、適格請求書発行事業者としてインボイスを発行できるようになるのが一般的な流れです。e-Tax経由で登録申請できるため、利用しやすい提出方法を選択しましょう。
適格請求書発行事業者の対象となるのは、次に該当する事業主です。
- 法人
- フリーランス(個人事業主)
基本的には、売上1,000万円以上の事業主が対象となりますが、1,000万円以下の人でも任意登録ができます。
仕入税額控除
仕入税額控除とは、業務の中で発生する消費税のうち、「売上に関わる消費税額」から「課税仕入れに関わる消費税額」を控除できる制度のことです。主に次の項目が課税仕入れに該当します。
- 商品の購入
- 原材料の購入
- 機械や建物といった長期事業資産の購入・賃借
- 広告宣伝費、通信費、水道光熱費などの支払い
- 消耗品等の購入
- 修繕費
- 外注費
このうち、インボイス制度で大きく関わってくるのが外注費です。売上にかかる消費税から外注費にかかった消費税を控除できるため、買手(発注者)は消費税の納税額を抑えられます。
また、インボイス制度では、買手(発注者)が、仕入税額控除を適用してもらうためにインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。正しいインボイス(適格請求書)を保管していなければ、その分は控除対象とならないため確実な対応が必要です。
課税事業者・免税事業者
インボイス制度は、売上1,000万円以上の事業主が対象であるため、すべての法人・フリーランス(個人事業主)が登録する必要はありません。ただし、登録の有無によって、課税事業者・免税事業者に分類されることを覚えておきましょう。
課税事業者とは、インボイスに対応する事業者のことを指します。前述したインボイスの記入条件に基づいた請求書の作成・管理を行うのが特徴です。
一方、免税事業者は、インボイスに対応しない事業者のことを指します。仕入税額控除を行う企業にとっては控除対象にできないというデメリットがあるため、発注額や発注数の減少リスクがあることに注意してください。
課税事業者・免税事業者になるのは任意ですが、リスクなどを把握したうえでどちらを選択すべきか検討してみてください。
インボイス制度で重要となる3つのスケジュール
インボイス制度は2023年10月から開始するため、対応しようと考えている人は早めに行動することが大切です。続いて、インボイス制度対応の中でも重要な3つのスケジュールをご紹介します。
「適格請求書発行業者」の登録期間
適格請求書発行事業者になるためには、税務署に登録申請書を提出する必要があります。インボイス制度の開始日である2023年10月1日から適格請求書発行事業者になりたいのなら、原則として「2023年3月31日」までに申請を完了しましょう。
ただし、上記日付までに登録申請できない事情がある場合には、登録困難な事業を記入することによって「2023年9月30日」まで受領してもらえます。
インボイス制度の発行が始まる時期
インボイス制度の開始日は「2023年10月1日」です。この期日以降の請求書は、適格請求書(インボイス)に対応した項目を記載する必要があります。
インボイス制度の経過措置期間
インボイス制度が開始すると、消費税に関するやり取りが大きく変化します。売上に大きく影響することから、当面の間は経過措置を設けて段階的に浸透させていく流れです。経過措置の期間は、次のとおり設定されています。
- 2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額の80%を控除
- 2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額の50%を控除
ただし、経過措置の特例を受けるためには「経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿」を保存しておく必要があるので注意してください。
インボイス制度に向けて準備しておくべき3つのポイント
すでにインボイス制度の導入が急がれている時期ですが、対応する・しないを判断するのは自己責任です。最後に、インボイス制度に向けて準備しておくべき3つのポイントをご紹介します。
1.取引先の対応状況のチェック
インボイス制度は、買手・売手双方が適格請求書発行事業者でなければ機能しません。よって、取引先がインボイス制度に対応しているか否かを事前に確認することをおすすめします。
また、免税事業者になることを検討している人は、取引先と今後も継続して取引を行えるか伺っておくことも大切です。今後長期にわたって取引に影響する制度なので、きちんと確認しておきましょう。
2.インボイス制度に対応する業務ツールの導入
インボイス制度が開始すると、請求書の作成方法や保管方法が大きく変化します。また、インボイス制度の開始以前の請求書とは様式が異なってくるのが特徴です。
スムーズに対応を進めたいなら、早い段階でインボイス制度に対応する業務ツールの導入を検討してみてください。手間がかかるインボイス制度の作業を簡易化できるほか、自動化処理によってほとんど時間をかけずに対応できるでしょう。
3.従業員への連絡・周知
インボイス制度に対応する予定がある法人は、事前に従業員への連絡・周知を行いましょう。チームで活動する企業などは、担当者全員がインボイス制度を理解しておかなければ、請求書の作成などでトラブルが起きてしまいます。
インボイス制度の社内講習会を行うことはもちろん、請求書様式の検討や導入ツールの周知を行うことをおすすめします。
基礎知識を把握してインボイス制度に備えよう
インボイス制度のスタートが間近に迫っています。インボイス制度の対象者となる適格請求書発行業者になるためには、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があるので注意してください。
インボイス制度は、さまざまな専門用語とスケジュールが絡み合う難しい制度です。インボイス制度に対応する予定があるのなら、本記事の情報を参考にして早めに行動してみてはいかがでしょうか。