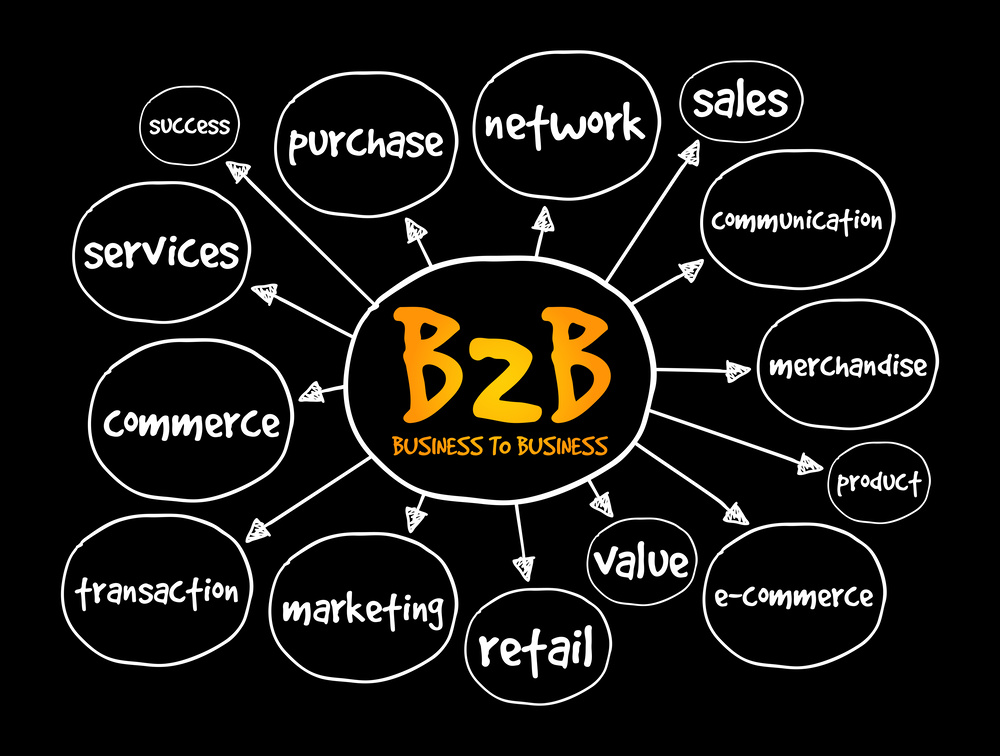新規事業を立ち上げる際は、ビジネスモデルを明確にしておく必要があります。ビジネスモデルには「BtoB」「BtoC」などさまざまな形態がありますが、特にBtoBは事業を安定させやすいといわれています。しかし、その一方で、BtoBはそのメリットがわかりにくく参入しにくい面もあります。
本記事では、BtoBとは何なのか、BtoCやCtoCとの違い、BtoBを展開している企業の事例、そしてマーケティング手法まで、BtoBに関する知識を網羅的に解説します。
目次
BtoBとは?
BtoBは「Business to Business」の略で「B2B」とも表記され、企業と企業(官公庁なども含みます)が取引を行うビジネスモデルを示します。たとえば自動車メーカーが部品メーカーから部品を購入したり、スーパーなどの小売店が食品加工メーカーから食料品を仕入れたりすることもBtoBです。あるいは企業向けのソフトウェアを開発している企業からソフトウェアを購入することもBtoBです。さらに、物質としてのモノ以外にも、経営コンサルティングやクラウドサービスの売買もBtoBに含まれます。
つまり、企業が自社だけではまかなえないモノや解決できない課題のソリューションを売買する取引がBtoBです。
BtoBとBtoCの違い
BtoBの理解を深めるために、BtoCを比較しながら、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。
BtoCとは?
BtoBと比較されやすいビジネスモデルにBtoCがあります。
BtoCは「Business to Consumer」の略で、企業が個人に対して商品やサービスを提供するビジネスモデルです。BtoCの代表的な売り手は、スーパー、百貨店、ホームセンター、家電量販店、自動車ディーラー、アパレル専門店などの小売業や、レストランやカフェ、居酒屋などの飲食店です。ほかにもホテルやリラクゼーション、遊園地、病院などもBtoCです。
BtoCは、住宅や高級車のような例外もありますが、BtoBと比較すると個々の取引金額は低いことが特徴です。
BtoBとBtoCの違い
BtoBとBtoCの違いについて、4つのポイントで解説します。
◆電子商取引での比較
| BtoB | BtoC | |
| 市場規模 | 大(334.9挑円) | 小(19.3兆円) |
| 取引金額 | 大(数百万円~数億円) | 小(数百円から数十万円程度) |
| 取引の継続性 | 安定(継続性が高い) | 不安定(変動要素が多い) |
| 決済者 | 企業・組織 | 消費者個人 |
市場規模の大きさ
BtoBとBtoCは、市場の規模が異なります。経済産業省の調査によると、2020年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模が19.3兆円だったのに対し、BtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は334.9兆円と約17倍の違いがあります。
取引金額の大きさ
BtoBは1回の取引で動く金額がBtoCに比べて大きくなります。BtoCでは、1回の取引で動く金額は数百円から数十万円程度です。もちろん、例外的に車や住宅など、数百万円から数千万円の取引もありますが、決して日常的に行われる取引ではありません。
しかし、BtoBでは数百万円から数億円の取引が日常的に行われています。たとえば1つひとつは数百円単位の部品や材料でも、一度の取引で扱われる数が膨大なため金額も大きくなります。
取引の安定さ
BtoBはBtoCに比べて取引が継続的で量の変化も少なく安定しています。BtoCの場合は、たとえば服であれば、その季節の流行や気候、競合の状況、消費者の懐具合などにより売上は大きく変化します。また、消費者は常に同じ店から定期的に服を購入する傾向は小さく、継続的な取引が行われる可能性は小さくなります。
企業間の取引であるBtoBでは、購入者があらかじめ計画した予算を確保しているため、取引金額は比較的安定しています。また、取引相手を決めるまでに時間と労力がかかる一方で、一度取引が成立すれば継続的な取引が行われることが一般的です。
決裁者の違い
BtoBとBtoCでは購買の意思決定者が異なります。BtoCでの決裁者は消費者個人ですから、意思決定のプロセスは非常にシンプルです。商品やサービスによっては家族や友人たちなどと相談することもありますが、基本的には購入者1人の意思により購入が決定されます。たとえば服を買う、食品を買う、電化製品を買うなど、購入者は自分1人の意思で購入を決定します。住宅や車などは、購入を決める際に共有する家族の合意を得る必要がある場合もありますが、それでもプロセスはシンプルです。
一方、BtoBの場合は、購入者が企業であり、一度取引を始めると継続することが多く、さらに動く金額も大きくなり、その取引内容が企業の業績に影響を与えることから、購入決定者には大きな責任が生じます。そのため、新規の取引開始の意思決定を担当者の一存で行うことができず、稟議を起案して上層部の承認を得るなど、相応の手続きと時間が必要になります。
BtoB、BtoC以外のビジネスモデル
BtoB、BtoCと類似の表記がされるビジネスモデルについて紹介します。
例として具体的な企業名も紹介します。
BtoE(企業→従業員)
BtoEは「Business to Employee」の略で、企業が自社の従業員に対して製品やサービスを提供するビジネスモデルです。もっとも身近な例としては、社員食堂や社内コンビニ、社員寮、スポーツクラブの優待などがあります。近年ではオフィスでも気軽におやつを購入できる「オフィスグリコ」や、会社が一括購入できる「オフィスでヤクルト」など、他社が提供するサービスを導入する例もあります。
元来は福利厚生の意味が強く、社員の定着率や人材確保に結びつける目的が中心でしたが、近年では従業員も消費者であるとの考えから、自社商品やサービス、企業のファンになってもらい、評判が自発的に拡散されることを期待している企業も増えてきています。
BtoG(企業→行政)
BtoGは「Business to Government」の略で、企業が国や自治体などの公的機関を相手に行うビジネスモデルです。たとえば公共事業において、入札を通じて企業が参加する取引があります。また、省庁内のインターネットインフラの構築やホームページの制作運用も増えています。
近年では、ふるさと納税へのプラットフォーム提供や返礼品の選定など寄付者への業務を代行している楽天株式会社の例や、自治体向けの広告事業を展開している株式会社ホープの例があります。ホープ社は広報誌やホームページ、公務員の給与明細の裏面を広告媒体として活用するなどの事業を展開しています。
DtoC(メーカー→消費者)
DtoCは「Direct to Consumer」の略で、メーカーが消費者に直接販売するビジネスモデルです。DtoCは以前からもカタログ販売や通信販売として行われてきたビジネスモデルですが、インターネット上で決済できるようになったことで、多くの企業が自社ECサイトを立ち上げて参入するようになりました。
また、SNSを活用したマーケティング手法を駆使することも近年のDtoCの特徴です。DtoCでは、顧客からのフィードバックが直接得られるため、顧客のニーズを製品やサービスに迅速に反映させることができることや、中間マージンを省くことで利益率を高めることができます。
DtoCの成功ブランド例としては、ビジネスウェアのカスタムオーダーサービスのFABRIC TOKYO、メンズコスメのベンチャー企業であるバルクオム、クラフトチョコレートをカカオ豆の仕入から製造・販売まで一貫して行っているミニマル、植物由来のヘアケア・スキンケア・ボディケア用品などを製造販売しているボタニストなどがあります。
GtoC(行政→消費者)
GtoCは「Government to Consumer」の略で、国や自治体が企業や個人に向けてサービスを提供することです。2019年5月に「デジタルファースト法」が国会で可決されるとGtoCの注目度が高まりました。同法は行政手続きを電子申請に統一することをめざす法律だからです。
たとえば住民票の電子申請やワクチンパスポートの発行、e-Taxによる税金のオンライン申告、道路や水道の整備、学校や図書館の運営、公共施設の電子予約などが挙げられます。少子高齢化が進み、地方創生の機運が高まっている中、GtoCの需要は高まると考えられます。
CtoC(消費者→消費者)
CtoCは「Consumer to Consumer」の略で、個人間取引を示します。インターネット上でCtoCのプラットフォームが普及したことで、不特定の消費者同士が気軽に取引を行える環境が整いました。CtoCの例として、ヤフオク!のようなネットオークションやメルカリのようなフリーマーケットがあります。個人のスキルを売買するココナラなどもCtoCの一種といえます。
BtoBマーケティングとは?
BtoBでは高額な取引が多く、提案から受注までに数年といった長い期間を必要とする場合もあります。しかし、一度契約されるとリピートされることが多く、長期的かつ継続的な取引が行われる期待ができます。また、一度取引が始まった顧客からは、オプションの購入やアップセル商品・サービスが購入される確率も高くなります。
そのため、BtoBは顧客の母数が限られていますが、長期的かつ継続的な取引が見込めるため、より多くのリード獲得と既存顧客のフォローが重要になります。
BtoBマーケティングが注目されている理由
これまでBtoBを経営の軸にしてきた企業の多くはマーケティングの専門部門をもつことは少なく、営業部門などがマーケティングに近い機能を内包していることが一般的でした。しかし、市場がグローバル化し、需要が飽和状態となった成熟市場では、商品やサービス自体での差別化が難しくなったため、従来の顧客へのアプローチ方法では顧客の囲い込みと売上の両方を伸ばすことが難しくなってきました。
しかも、インターネットによる情報収集が容易になり、顧客自身が積極的に商品やサービスを比較検討することができるようになったことからも、従来の営業手法の有効性が薄れてきています。そこでマーケティングの重要性が増してきました。
顧客の情報収集の変化
顧客がインターネットで直接情報収集できる現在、営業が訪問時に持ち込む情報によって差別化することが困難になってきました。顧客はむしろ、Webサイトやメールマガジン、ホワイトペーパーなどから情報を得ることに利便性を感じるようになってきています。そのため、Webサイトやメールマガジン、ホワイトペーパーを使って顧客にアプローチできるマーケティング部門がリード(見込み顧客)と接触する機会を増やすことが重要になってきました。
サービスモデルの変化
クラウドサービスの普及に象徴されるように、ハード製品も含めてあらゆる商品やサービスがインターネット上のサービスと連携するようになりました。このことは、顧客は常に他社の商品やサービスに乗り換えることが容易な状況をつくり出しています。したがって、一度契約した顧客に対しても、継続的に有意義な情報を提供したりサポートを行ったりすることで、良好な関係を維持する必要があります。
購買プロセスの変化
インターネットが普及したことで、顧客の購買プロセスが変わってきています。顧客は、自社の課題解決のために能動的に情報収集を行うことが容易になってきました。そのため、従来型の営業であるプッシュ型アプローチよりも、マーケティングによるプル型のアプローチが有効になってきました。
BtoBマーケティングの特徴
ここではBtoBマーケティングの特徴を、BtoCと比較しながら解説します。
BtoBマーケティングの特徴(BtoCマーケティングとの比較)
| BtoB | BtoC | |
| 取引期間 | 長期的 | 短期的 |
| 売上 | 継続的 | 単発的 |
| 対象顧客 | 限定的 | 無制限 |
| 市場開拓 | 長期 | 短期 |
| 商材単価 | 高い | 低い |
1.長期的な取引が見込める
BtoCマーケティングでは、商品がヒットすれば一時的に売上が急伸しますが、市場が変化しやすいため、売上が安定しません。一方、BtoBマーケティングでは、一度契約した顧客とは長期にわたって安定した取引が継続される傾向が強いため、トータルでは高い収益性を見込めます。
2.継続的な売上が見込める
BtoCでは、顧客が個人の消費者であるため、1つの商品・サービスに対する取引量が小さく、また短期間で商品・サービスを乗り換えられてしまうことも頻繁に起こり得ます。一方、BtoBでは基本的に企業などの法人が顧客で計画的な予算をもとに取引が行われるため、1つの商品・サービスに対する取引量が大きく長期にわたって取引が継続されやすくなります。その結果、継続的な売上が見込めます。
3.対象顧客数が有限
BtoCの顧客としては訴求すべき対象は世界中の人々となり、ターゲット数を予測することは困難です。一方、BtoBの顧客は、主に特定の業界や規模に限られるため、ターゲットは数百~数千に絞られます。
4.新規開拓までに時間がかかる
BtoBでは、新規開拓に時間がかかります。見込み顧客に対して、自社を知ってもらうプロセスがあります。1件の新規顧客を獲得するためには、見込み顧客の開拓、アポ取り、訪問、情報収集、提案のプロセスを経なければなりません。このプロセスを通じて、自社や営業担当者への信頼を得る必要があります。また、意思決定や決裁の権限をもっている担当者にたどり着き、信頼関係を構築する必要があります。
また、企業や組織の課題解決や経済的合理性を検討するため、課題の認知から製品・サービスの導入までに、念入りな情報の精査と複数の意思決定者の調整など、購入するまでに要するプロセスが多く、期間も長くなります。
一方、BtoCでは顧客である消費者は自身の一存で商品・サービスの購入を即決することができます。そのため、BtoCにおける広告では、感情を刺激するコピーやイメージが使われることも多くあります。
5.商材の単価が大きいため、リスク管理の責任が大きい
BtoCの商材は、個人の消費者の予算で購入できる価格設定であるのに対して、BtoBの商材の価格は企業の予算で購入できる価格設定になっているため、金額が大きくなります。そのため、ときには単独の決裁者が決裁できる金額を超えることもあり、その場合は複数人が承認しなければ契約できません。大きな金額が動くため、販売担当者にとっても購入担当者にとっても、リスク管理の責任が大きくなります。
BtoBマーケティングのプロセス
そこで、BtoBマーケティングが必要になってきます。ここではBtoBマーケティングのプロセスについて解説します。
BtoBマーケティングは、営業に引き渡して契約にたどり着くまで、リードジェネレーションとリードナーチャリング、リードクオリフィケーションの3つのステップを踏みます。
リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)
BtoBマーケティングは新規リードの獲得から始まります。新規リードの獲得とは、自社の製品・サービスを購入する可能性のある企業の担当者情報を獲得することです。担当者の情報には、企業名、部署、連絡先などがあります。このように、見込み顧客の情報を獲得する活動をリードジェネレーションと呼びます。
リードジェネレーションは顧客情報を獲得するマーケティングで、以下のような活動があります。
・メディア露出(PR)
・オウンドメディア
・広告
・SEO
・SNS運用
・展示会
・各種イベント
リードジェネレーションでは見込み顧客を獲得するため、その後の営業活動の効率を高めることができます。このとき、見込み度が低い顧客を獲得した場合は、次のリードナーチャリングが有効になります。
リードナーチャリング(見込み顧客の育成)
リードを獲得した後は、リードナーチャリングと呼ばれる見込み顧客の育成段階に入ります。獲得した見込み顧客の自社製品・サービスに対する購買意欲を高めるために、顧客に有意義な情報を提供し続けることで継続的な接点をもち続けるようにします。
リードナーチャリングは、獲得した顧客の購買意欲を高めるために顧客を育成するマーケティングで、以下のような活動があります。
・メールマガジン
・オウンドメディア
・テレアポ
・訪問営業
・カンファレンス
・セミナー
・イベント
・SNS運用
リードクオリフィケーション(見込み顧客の選別)
リードクオリフィケーションとは、顕在化したリード(見込み顧客)から購入可能性の高い見込み顧客を選別することです。主に下記のような活動があります。
・シナリオ設計
・スコアリング
・データマネジメント
・履歴や属性の分析
このようなリードクオリフィケーションをすることによって、商品やサービスに関心がある確度の高い見込み顧客からコンタクトを取ることで、効率よく営業にバトンタッチし、商談・契約につなげることができます。
リードクオリフィケーションで成果を出すには、まず事前に「シナリオ設計」を考えておく必要があります。シナリオ設計とは、顧客が商品やサービスと接点を持ち、商談・契約に至るまでのリードジェネレーション、リードナーチャリングも含めた一連のプロセスの設計を指します。これら3つの活動は連動しているため、シナリオ設計を明確にしておかないと、リードクオリフィケーションでよい結果を出すことができません。
購入の可能性が高い見込み顧客を絞り込む方法としては、見込み顧客のアクションや属性などに点数をつける「スコアリング」という手法を用います。スコアリングでは、高い点数がついた見込み顧客を購入可能性が高い見込み顧客として考えます。
「データマネジメント」とは、データを適切に管理してあらゆる業務に活用するための知識です。データマネジメントではデータの正確性、データが最新情報で更新されているか、データの細かさが揃っているかが求められます。
最後は結果の良し悪しを含めた蓄積された履歴や属性のデータを分析しながら、精度を上げていきます。
BtoBマーケティング施策
BtoBのマーケティング方法について、リードジェネレーションとリードナーチャリングの主な施策について紹介します。
リードジェネレーション
メディア露出(PR)
新聞やテレビ、ラジオ、Webなどのメディアに取り上げられることがメディア露出です。メディア露出による効果は以下の通りです。
メディア露出(PR)の意義
- 広く認知される:メディア露出のもっとも大きな効果は広く認知されることです。しかも、これまで接点がなかった潜在顧客に認知される可能性が大きくなります。
- 信頼度が上がる:メディアに露出すると、「メディアが取り上げたほどだから信頼できるだろう」と受け止められやすくなります。また、メディアに取り上げられたことがSNSで拡散される可能性が高まります。
- 第三者の意見を知ることができる:メディアに取り上げられると、メディアを通じて第三者による評価を知ることができます。
- 社員の意欲が高まる:メディアで紹介されることで、社員が自社の製品・サービスに誇りをもち、仕事への意欲を高める可能性があります。
- 人材を集めやすくなる:メディアに取り上げられると、求職者への認知が高まることと、就職先としての信頼感が増すため、求職者に選ばれやすくなります。
オウンドメディア
近年では、顧客は製品・サービスの購入を検討する際に、まずWeb上から情報収集を行うので、当然、製品・サービスを提供している企業の公式サイトあるいはオウンドメディアをチェックしています。そのため、自社サイトで製品・サービスの掲載情報を充実させたり、ホワイトペーパーのダウンロードを可能にしたりしておくことは、大変重要な施策となります。
また、オウンドメディアはリードジェネレーションだけでなく、リードナーチャリングにおいても非常に重要な役割を果たします。オウンドメディアは認知獲得のみならず、リードの興味・関心を維持し、ファン化するためには欠かせない施策となっています。
広告
顧客が製品・サービスの情報をキャッチするのはWebメディアである可能性が高いため、インターネット上の広告対策が重要となります。具体的には以下のような広告の種類があります。
広告の種類
- リスティング広告:検索エンジンで特定のキーワードの検索が行われた際に、検索結果の画面上に表示されるテキスト形式の広告です。コンテンツのSEOよりも即効性があり、予算に合わせた柔軟な運用が行えることがメリットです。
- ディスプレイ広告:バナー広告とも呼ばれ、Webサイトの広告枠に表示されるテキストや画像、動画を利用した広告です。凝った作り込みができるためインパクトのある広告を表示することができますが、リスティング広告に比べてコンバージョン率は低くなる傾向があります。
- ターゲティング広告:自社サイトや広告から製品・サービスのランディングページ(LP)を訪れたユーザーをcookieで認識して、その後ユーザーが閲覧するさまざまなサイトで自社製品・サービスの広告を表示させる手法です。BtoBでは製品の検討期間が長期になりやすいため、接触回数を増やすことが有効だと考えられます。
- SNS広告:SNS広告とは、FacebookやTwitter、LINE、Instagramなどで配信される広告を示します。SNSでは利用者の属性情報が登録されているため、ターゲットを絞り込んだ訴求が行えます。
SEO
SEO(Search Engine Optimization)は自社のコンテンツサイトが、検索エンジンで上位表示されるために行う対策です。オーガニックな検索結果において上位表示されたサイトは閲覧される機会が増え、信頼度もユーザーのニーズとのマッチ度も高くなります。SEOとして重要なことは、良質なコンテンツを高頻度で継続的に発信を続けることと、検索エンジンに高評価されるコンテンツやサイトの作り込みを行うことです。ただし、SEOはリスティング広告のような即効性はないので、長期的なマーケティング戦略として取り組む必要があります。
SNS運用
最近では、多くの企業がTwitterやfacebook、InstagramなどSNSを運用するのが当たり前になっています。企業の情報収集の手段がオンライン化したことによって、SNSによる情報発信が極めて重要になっています。SNSマーケティングを行うことで得られる効果としては、潜在顧客の獲得、見込み顧客への定期的な情報提供、関係性構築などがあります。SNSで効果的なマーケティングを行えば、自社の商品やサービスを提供できる潜在的な顧客との接点をつくることができます。
展示会
展示会は、顧客ごとに訪問しなくても自社製品・サービスに興味をもった見込み顧客が自ら足を運んでくれるため、営業部員を増員しなくても効率よくコンバージョン数を増やすことができます。しかも、対面営業ができるだけでなく、自社製品を体験してもらえるメリットがあります。ただし、展示会を開催するためにはコストがかかる点に注意が必要です。また、来場者が同時に問いかけてくる場合に備えて、自社製品・サービスに詳しい人員を待機させておく必要があります。
各種イベント
自社が主催するセミナーやカンファレンスをはじめ、他社が主催する外部イベントへの協賛や出展、あるいは登壇することもBtoBマーケティングに効果があります。出展や登壇をすることで、もともと自社の製品・サービスを目的としていなかった潜在顧客にアピールできますし、営業担当者が参加していればその場で商談への足がかりを得られる可能性も高まります。また、自社の認知度が低かった場合は、集客力のある外部イベントに出展や登壇することは、認知度を上げる機会となります。
リードナーチャリング
メールマガジン
BtoBマーケティングではさまざまなインターネット上の訴求方法が生まれてきましたが、メールは今も有効なマーケティングツールです。その理由は、以下の通りです。
さまざまな情報を告知できる
メールは固定されたWebサイトと異なり、都度さまざまな情報を発信することができます。新製品情報やアップデート情報、イベント情報、お役立ち情報、ニュースなどです。
定期的なフォローが行える
BtoBにおいてはリードナーチャリングの期間も購入検討期間も長くなる傾向があります。そのため、自社から定期的にフォローすることにより、関係性を維持する必要があります。このためのツールとしてメールは有効です。
確度の高いリードの絞り込みに使える
リード(見込み顧客)の中には、まだ購入意欲が低い段階のリードもいれば、購入意欲が高まっている段階のリードもいます。このとき、メールで案内したURLのクリック率などをもとにリードを購入意欲の高さで分類することで、アプローチ方法を使い分けることができます。たとえば購入意欲が高まっているリードだけを絞り込めれば、無駄な架電を省くことができます。
テレアポ
テレアポはテレフォンアポイントメントの略で、顧客に電話で営業をかける手法です。顧客からのアプローチを待つのではなく、積極的に顧客獲得を行います。オンラインマーケティングが普及したことで、テレアポに古さを感じる人は増えていますが、すべての顧客が自らICTを駆使して能動的に情報収集をできているわけではありません。このような顧客にはテレアポは有効なアプローチ方法です。
テレアポはその段階ですぐに商談につながることはありませんので、長く話すことは逆効果です。手短にポイントを押さえたトークを行うべきです。一方、テレアポは直接顧客とコミュニケーションがとれるため、顧客の課題や状況をヒアリングすることで潜在層へのアプローチを可能にします。
ただしテレアポを行う人は、相手から冷たくあしらわれたり、理由を告げられずに切られてしまったりすることも少なくありません。あらかじめ気の持ち方や対処方法を準備しておく必要があります。
訪問営業
テレアポが取れたら訪問営業を行います。訪問営業は顧客と対面で課題やニーズを聞き出すことができる貴重な機会ですから、行き当たりばったりで営業するのではなく、事前に顧客の業界動向や顧客企業の現状などについて調べておきます。顧客の業界や企業について相手と共通の知識を持つことで信頼を得やすくなり、効率よく顧客のニーズや課題を引き出すことができます。
カンファレンス
カンファレンスでは、専門家や実践者が登壇して参加者と議論したりするため、自社が提供する製品やソリューションについて、より説得力のある訴求を行えます。しかもカンファレンスは明確なテーマを掲げて開催されているので、そのテーマに興味をもっていたり、関連する課題を抱えていたりする人が集まります。さらに、カンファレンスでは一度に多くの来場者を集めることができます。これらのことから、カンファレンスは継続的に新規リードを獲得できるマーケティング施策の1つであるといえます。
BtoBマーケティングを成功させるポイント
BtoBマーケティングを成功させるためには、いくつものポイントがあります。プロセスに沿って確認しておきましょう。
ニーズを把握する
商品・サービスを販売するためには、ニーズをもったターゲットにアプローチしなければなりません。しかし、潜在顧客の中には、自らのニーズに気づいていない場合があります。そのようなニーズを掘り起こすためにもマーケティングは必要です。BtoBには意思決定者が複数であることや検討期間が長いこと、印象や衝動ではなく経済的合理性がなければ購入しないなどの特徴があります。そのため、ターゲットのニーズを的確に把握する必要があります。BtoBはBtoCに比べて母数が小さいこともあり、ターゲットを取りこぼさないことが重要です。
差別化を図る
差別化とは、競合他社や同業他社に比べて、自社の製品・サービスがどのように優れているのかを具体化することです。差別化は、価格が安いことや単に異なっているということではなく、高くても競争優位になる差異があることでなければなりません。
信頼を得る
BtoBでは購入までの検討期間が長期間になることが一般的です。その間、Webサイトやメールマガジン、展示会、セミナーなどさまざまな検討機会が訪れ、他社の情報を得る機会も増えます。そのため、販売者は購入者との間に信頼関係を構築しておかなければ、ささいなきっかけで競合他社に顧客を奪われてしまう可能性があります。また、企業は経済的合理性により購入を決定しますが、その中には販売価格が信頼できる妥当性をもっていることや、アフターフォローがしっかり行われることに対する信頼感の強さも含まれます。
タイミングを狙う
BtoBにおいては、顧客のニーズが明らかになり、自社製品・サービスがそのニーズに応えられると判明しても、タイミングが合わなければ契約に至ることは難しい場合があります。BtoBでは取引金額が大きくなるため、顧客側で予算を確保できているかどうかを見極めることが重要になります。このタイミングを見極めないままで闇雲に売り込みをかけると、敬遠されてしまう可能性があります。
ロイヤルティを高める
顧客のロイヤルティ(信頼・愛着心)を高めるために、営業であれば足繁く通う必要がありましたが、BtoBマーケティングではICTツールを利用してより効率的に働きかけることができます。ロイヤルティが高い状態で商談に入るタイミングをつかむことができれば、商談は受注までスムーズに進む可能性が高まります。また、ロイヤルティが高ければ、契約後も長期的な利益を出し続けることができます。同時に、競合他社への乗り換えを防げる可能性も高まります。
キーマンを押さえる
BtoBでは企業を相手にするため、意思決定者であるキーマンにたどり着くことが重要です。キーマン以外の人にいくらアプローチしても、無駄な労力を費やしてしまいます。また、キーマンは1人とは限りません。競合製品のリサーチをしている人もキーマンですし、製品・サービスの導入を推進する担当者もキーマンです。そして、決裁権をもち最終的な意思決定を行う人もキーマンです。これらのキーマンを押さえて各人に有益な情報を提供し、効率的なマーケティングを行う必要があります。
営業と連携する
多くの企業ではマーケティング部門とインサイドセールス、フィールドセールス、そしてカスタマーサービスなどが十分な情報共有を行えず、連携もとれないまま活動していることがあります。情報共有が十分に行われていないと、マーケティング部が獲得してナーチャリング(育成)したリードが、営業によりクローズされたのか、アップセルされたのかといったフィードバックが行われず、確度の低いリードを獲得し続けてしまう可能性があります。BtoBマーケティングを成功させるためには、各部門との情報共有と連携が欠かせません。
BtoBマーケティングの支援ツール
実際に、BtoBマーケティングの支援ツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのBtoBマーケティングの支援ツールを紹介します。
(2022年1月5日時点のレビューが多い順に紹介しています)
ABM(アカウントベースドマーケティング)
ABMは、BtoB企業におけるマーケティング戦略の1つです。自社にとって有益な顧客を選び、それぞれに合わせた戦略を立てて利益を最大化することがABMの手法です。
FORCAS
「FORCAS」は150万社以上の企業データから、自社製品・サービスと相性のよい企業をリストアップするターゲティングを行うことで、確度の高い潜在顧客へのアプローチを効率化できるBtoB向けの顧客戦略プラットフォームです。
uSonar
「uSonar(ユーソナー)」は、さまざまな顧客情報を統合管理するクラウド型のツールです。DMPやMA、CRM、SFAなどと連携することでマーケティングのDX化を実現します。
BowNow
「BowNow」は機能を厳選して使いやすくしたMAツールです。特にリストアプローチの自動化により、コストパフォーマンスの高いマーケティングを行えます。
SFA
SFAとは、「営業支援システム」です。企業の営業活動における情報収集や業務プロセスを自動化することで、情報全般をデータ化して、蓄積・分析することができるシステムを指します。
SFAについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
SFAとは?CRMとの違いや導入のメリット・おすすめツール5選
Salesforce Sales Cloud
「Salesforce Sales Cloud」は外出先でも素早く顧客にアプローチ。AIが組み込まれたCRMは、営業プロセスにあわせて柔軟にカスタマイズでき、あらゆる局面でセールスをサポートできます。営業管理、サポート状況、マーケティングデータを1カ所に集約。営業にまつわるプロセスをまとめることで、どのチャネルからでも、すべてを関連づけて観察できます。
Salesforce Sales Cloudの製品情報・レビューを観る
Senses
「Senses」は営業支援サービスで、蓄積された営業に関わるあらゆる情報を効率的に管理し、現場の営業担当者が効果的な営業活動を行えるように支援する高度なAIエンジンを搭載しています。
Knowledge Suite
「Knowledge Suite」は、統合ビジネスアプリケーションのクラウドサービスで、集計・分析ツールから問い合わせ管理、SFA、CRM、グループウェア、そして他のシステムとの連携機能などを搭載しています。
MA(マーケティングオートメーション)
MAは、収益向上を目的としてマーケティング活動を自動化するツールです。MAを導入することで、見込み顧客の興味関心に合わせたコミュニケーションが可能となります。
MAについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
MA(マーケティングオートメーション)とは?おすすめMAツール7選まで完全網羅
SHANON MARKETING PLATFORM
「SHANON MARKETING PLATFORM」はMAツールで、新規リードの獲得からナーチャリング、行動履歴の管理などマーケティング業務に必要な作業を自動化します。
SHANON MARKETING PLATFORMの製品情報・レビューを観る
Salesforce Pardot
「Salesforce Pardot」はクラウド型のMAで、マーケティング活動とセールス活動を連携し、さらにSalesforceが提供するさまざまなツールとも連携することで、営業の効率化と成果の最大化を支援します。
Salesforce Pardotの製品情報・レビューを観る
Adobe Marketo Engage
「Aobe Marketo Engage」は、世界39カ国以上の企業で採用されているMAです。BtoB、BtoCを問わずあらゆる規模と業種において、ユーザーの1人ひとりと適切なタイミングや内容、手段でコミュニケーションをとることができます。
Adobe Marketo Engageの製品情報・レビューを観る
CRM
CRMは顧客との関係性、コミュニケーションを管理し、自社の従業員と顧客との関係を一元的に把握できるようにするツールです。情報の一元化によって顧客をより深く理解することで、営業活動の向上、サービス、マーケティング、経営戦略などに生かすことができます。
CRMについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
Salesforce Sales Cloud
「Salesforce Sales Cloud」はSFAとCRMが統合されたシステムで、新規顧客の発掘からナーチャリング、そして早期受注を実現するためにあらゆる機能が備わっています。
Salesforce Sales Cloudの製品情報・レビューを観る
Senses
「Senses」は、営業管理や分析などの機能の使いやすさにこだわりがあります。蓄積された過去の営業情報から現在の営業活動に役に立つノウハウを活用できるよう、高度なAIエンジンを兼ね備え、導入企業は不動産や人材、広告代理店など多岐にわたります。
Zendesk
「Zendesk」は、メールやWebフォーム、ソーシャルメディアなどのさまざまなチャネルからの問い合わせを一元管理し、ワークフローのオートメーションやサポートのパフォーマンス測定などを行えるヘルプデスクソフトウェアです。
メールマーケティング
メールマーケティングは、メールを活用したマーケティング全般を指します。特にBtoB企業では、SNSが普及した今日もメールを中心にコミュニケーションが行われるので効果的な方法といえます。
Twilio SendGrid
「Twilio SendGrid」は、クラウド型のメール配信サービスです。開封やクリックなどの配信状況のトレースやメールが届かなかったバウンスの自動処理、配信停止管理などを効率的に行え、他システムと連携するためのAPIも豊富です。
MailChimp
「MailChimp」は、直感的な操作でメールマガジンを配信できるツールです。HTMLメールもエディターで簡単に作成でき、開封率やクリック率などのレポート機能も充実しています。
配配メール
配配メールは、メールマガジンやステップメールを配信できるメールマーケティングツールです。直感的な操作と必要最低限の機能、専任スタッフの手厚いサポートが特徴です。
Webサイト制作
Webサイト制作とは、ホームページやオウンドメディアなどのWebサイトの制作を指します。1人でも始められますが、ページのデザイン、画像の作成、サイト制作の進行管理など、分業して制作を行うことが多いです。
Adobe XD
「Adobe XD」は、Webサイトやモバイルアプリのデザインを支援するUX/UIソリューションで、共同編集が可能なためチームによる作業を効率化できます。Adobe CC・Creative Cloudと連携ができ、直感的な操作が可能です。
Dreamweaver
「Dreamweaver」は、Webサイトのデザインからコーディング、ファイル管理を視覚的に行えるソフトです。
Sketch
「Sketch」は、WebサイトやアプリのUIデザインツールです。機能の豊富さに加え、プラグインでカスタマイズすることもできます。エンジニアとの連携を効率化するコラボレーションツールやプロトタイプ作成ツールにも対応しています。
CMS
CMSは、Webサイトのコンテンツを構成するテキストや画像、デザイン・レイアウト情報などを一元的に保存・管理するシステムのことです。CMSが必要に応じて情報を取り出して、Webページを自動的に生成してくれます。
CMSについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
CMSとは?メリットや導入ポイント、活用事例、おすすめツール5選を紹介
WordPress
「WordPress」はWebサイトを構築・運営するためのオープンソースのCMSです。個人のサイトから企業のサイト、Webマガジンやニュースサイトまで幅広く利用されています。また、デザインテンプレートやプラグインも豊富です。
おりこうブログ
「おりこうブログ」は、Webサイトの作成やアクセス解析、メッセージ配信、カタログ作成などのツールが豊富なCMSです。
Movable Type
「Movable Type」は、安全で効率的なWebサイト運用を可能にするCMSプラットフォームです。豊富な機能で、大規模なコーポレートサイト、メディアサイトの構築・運用が可能です。
Web接客ツール
Web接客ツールは、Webサイトに訪れたユーザーに対して、その属性や閲覧履歴などといった情報をもとに、Webページ上で適切な対応・案内を行うツールのことをいいます。顧客データベースを参照しながら、個々人に最適なコンテンツ提供やサポートを実施するCXプラットフォームへの発展も進んでいます。
ChatPlus
「ChatPlus」は自由度が高いデザイン機能やチャットボットの挙動設定の多さが特徴です。すべてのAPIが開放されていることで、訪問者情報から行動属性まであらゆるデータを送受信できるため、柔軟なシステム連携を実現します。
Flipdesk
「Flipdesk」はチャット対応やクーポン発行、お知らせ配信など、訪問者の状況に自動的に対応することでリアル店舗のような接客をネットショップで実現します。
KARTE
「KARTE」はCX(顧客体験)プラットフォームです。Webサイトやスマートフォンアプリを利用している顧客1人ひとりの行動データを可視化し、適切なタイミングで適切なアクションを行えます。
SEOツール
SEOツールとは、特定キーワードにおける検索エンジンの表示順位を上げるための支援ツールです。SEOツールは主に適切なキーワードの選定やコンテンツの最適化、キーワードごとにおける競合サイトとの順位比較などの機能をもちます。
Google Search Console
「Google Search Console」は、Googleでの検索におけるインプレッション数やクリック数、掲載順位などを計測できるSEOツールです。
Google Search Consoleの製品情報・レビューを観る
SEARCH WRITE
「SEARCH WRITE」は誰でもSEOのPDCAを回せるように支援するツールです。CV獲得に貢献するキーワードがわかったり、キーワードごとに検索上位の記事見出しを自動で取得して上位表示される記事の書き方を示したりします。
Keywordmap
「Keywordmap」は、SEOのための競合分析や広告調査、コンテンツ作成などに活用できる日本語ビッグデータプラットフォームです。
ヒートマップ
ヒートマップは、Webサイト上でのユーザーの行動をサーモグラフィによる温度分布のように色の濃淡で可視化して表す分析手法です。Web解析では、マウスの動きを追跡し、そのマウスのログからヒートマップを作り出しています。
EmmaTools
「EmmaTools」はSEOライティングツールです。対策キーワードで上位表示させるための関連キーワードを提案したり、コンテンツ内で不足しているテーマを知らせたりなどSEO観点から改善点を明らかにします。
Ptengine
「Ptengine」はサイトに1つのタグを設置するだけで、データ収集からインサイト取得、施策実行そして効果の検証を行えるサイト運営プラットフォームです。
User Insight
「User Insight」は、Webサイトの訪問者がコンテンツのどこを見ているかやどこをクリックしているかを可視化してUI/UXの改善に役立たせるヒートマップツールです。トラフィック情報からユーザーの属性を推測することも可能です。
まとめ
本記事では、BtoBとはどのようなビジネスモデルか、BtoBマーケティングとはどのような施策かについて解説しました。BtoBは取引規模が大きくなり継続性が高くなる傾向があります。また、BtoCに比べてサイクルの短い流行の影響を受けにくいのが特徴です。
一方で取引開始までの意思決定プロセスが複雑で長期化しやすい傾向があるため、BtoBに適したマーケティングが必要になります。BtoBをすでに行っているが、より成果を出したい、あるいはこれから事業を立ち上げようとしているという方は、上記の特徴を踏まえたうえで、戦略を立てる必要があります。