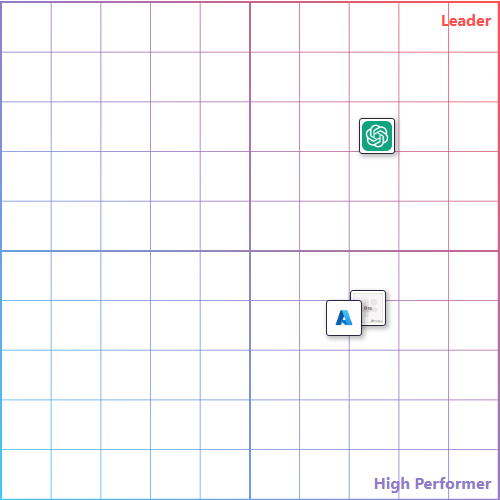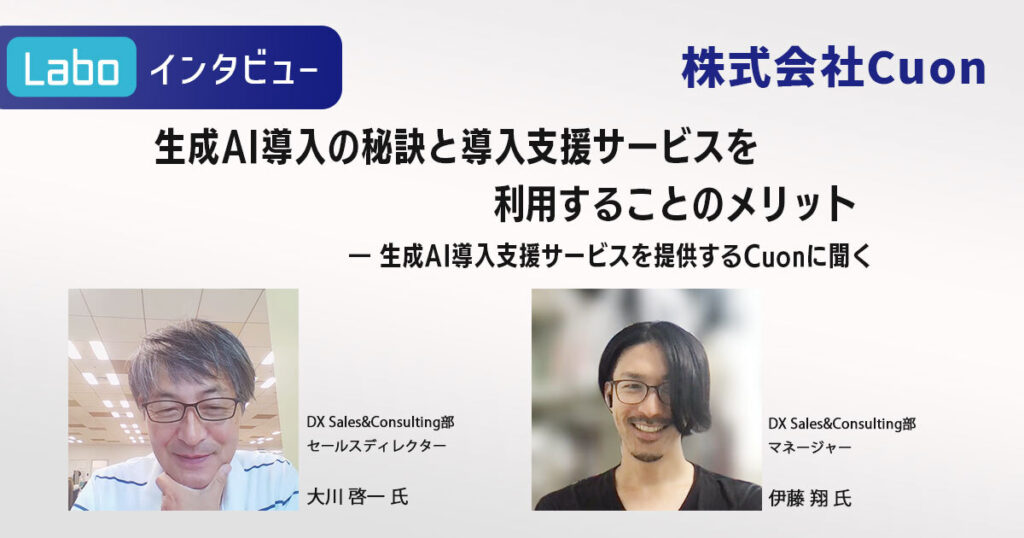投稿 【生成AIでSaaS選定はこう変わる】ITreviewで生成AI搭載SaaSを比較してみよう! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>「ユーザーからの人気が高い生成AI搭載SaaSを知りたい!」
近年、生成AIの急速な進化を背景に、多くのSaaSがAI機能を標準搭載するようになりました。その結果、企業はこれまで以上に、AI前提でのツール選定を迫られる時代に突入しています。
しかし、AI搭載をうたうSaaSの中には、実務で活用しきれないものや、ブラックボックス化によるリスクを抱えるものも存在します。選定を誤ると期待した成果が出ない投資になりかねません。
本記事では、ITreviewを活用した生成AI搭載SaaSの比較・選定方法にスポットを当てながら、サイトの基本的な使い方から便利な比較方法の紹介まで徹底解説していきます!
この記事を読むだけで、生成AI搭載SaaSの選び方から実際に人気のある製品まで網羅的に理解できるため、導入を検討している経営者や企業担当者にとっては必見の内容です!
ITreview Gridから探す
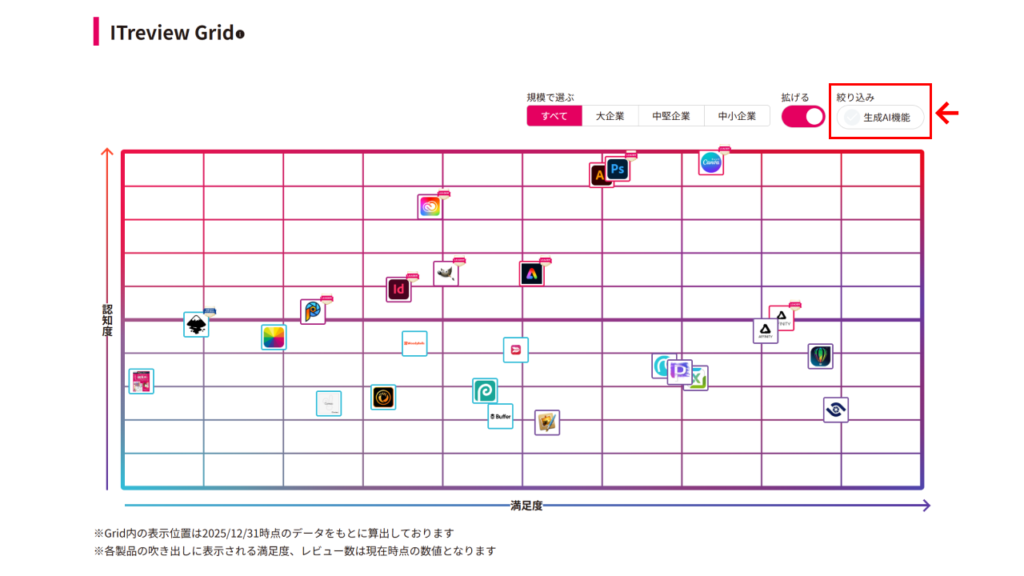
ITreview内の『カテゴリーページ』に設置されている『ITreview Grid』では、生成AI機能の有無で製品を絞り込むことが可能です。認知度と満足度を軸とした4象限マトリクスで、各製品のポジションを瞬時に把握できます。
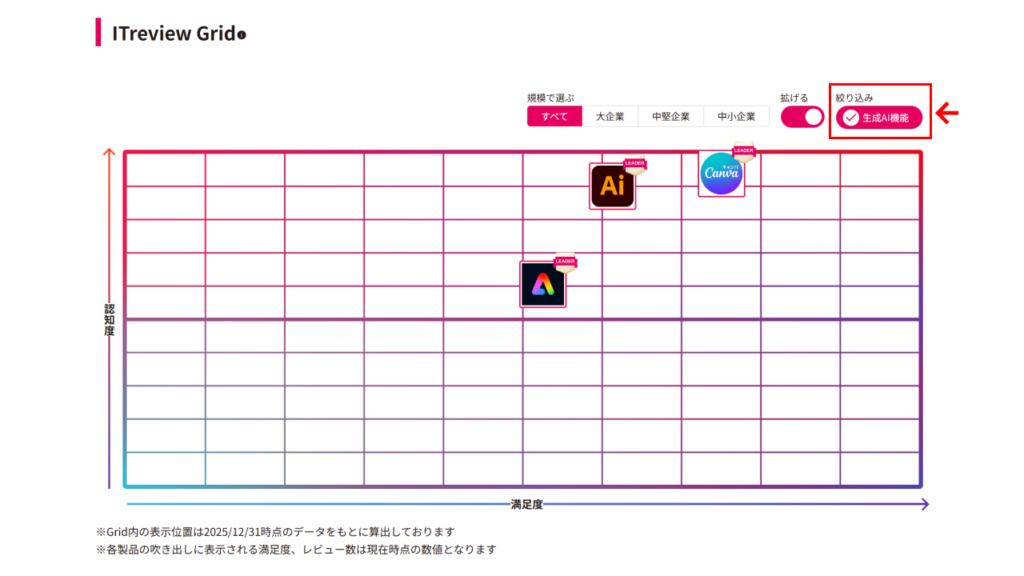
製品の絞り込みには、Grid右上に設置されている「絞り込み:生成AI機能」をクリックします。そのカテゴリー内に存在する生成AI搭載製品でフィルターがかけられるため、満足度の高い製品を一目で確認することが可能です。
生成AI機能で製品を絞り込む
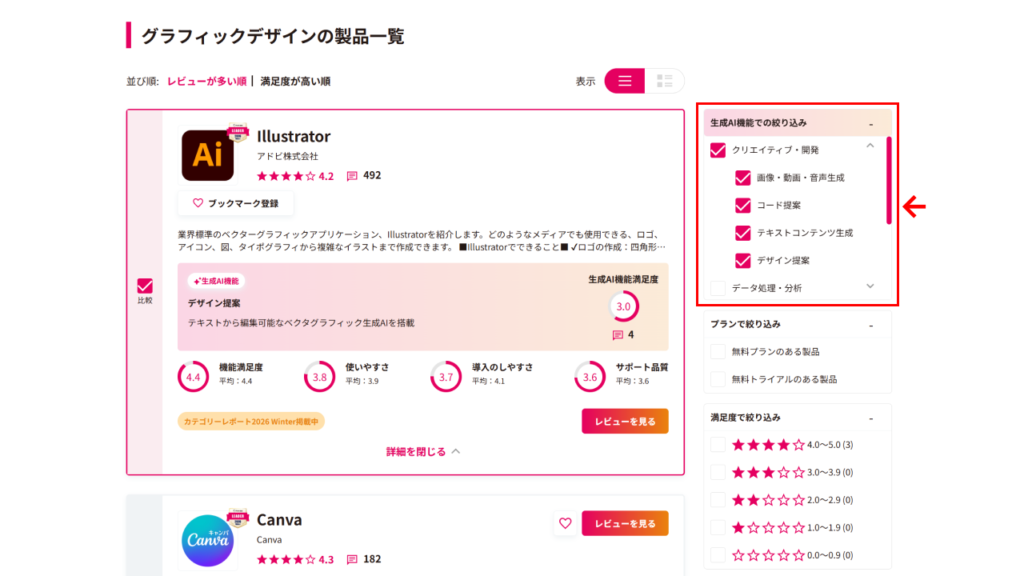
カテゴリーページ内の『製品一覧』では、生成AI機能ごとに製品を絞り込むことが可能です。製品の絞り込みには、画面右側の「生成AI機能での絞り込み」から任意の機能を選択します。
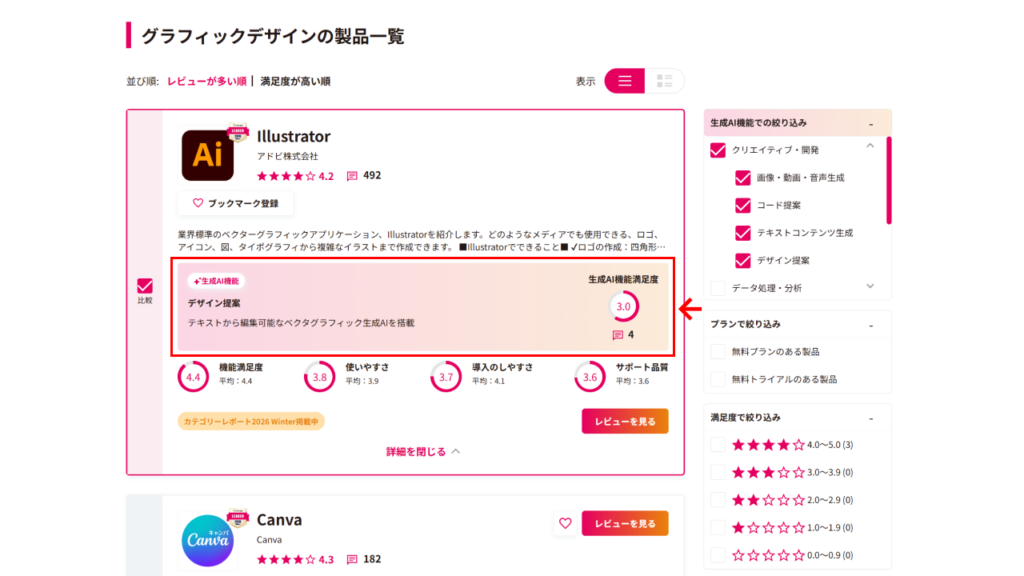
各製品の紹介部分には、該当する生成AI機能の概要説明と満足度平均が表示されます。画面左側の「比較」ボタンをクリックすることで、各製品の比較表(最大4製品)を作成することも可能です。
生成AI機能のレビューを見る

さらに詳細な『製品ページ』では、生成AI機能に関する実際のユーザーレビューを確認することができます。製品ページ内にある「生成AI機能」タブをクリックしてみましょう。
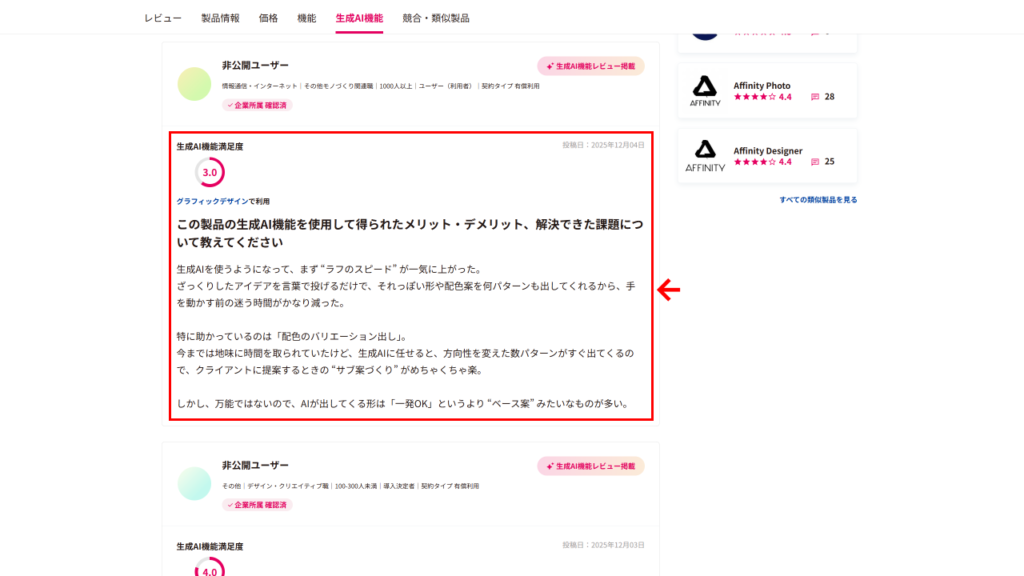
ここでは、その製品に登録されている生成AI機能を使用したユーザーのリアルな声を見ることができます。より詳しい口コミや評判を確認したい場合などにオススメの使い方です。
『ITreview.AI』で生成AI搭載SaaSを探す

上段で解説したGridやカテゴリーページ以外にも、ITreviewでは、生成AI搭載製品の比較・選定に役立つ特設ページ『ITreview.AI』をリリースいたしました。活用することで、様々な視点から生成AI搭載製品を比較することができます。
このページでは、カテゴリー別に人気のある生成AI搭載製品を確認できることはもちろん、全カテゴリーを横断した人気製品の確認や機能別の検索まで行うことができるため、自社に合った生成AI搭載製品を見つけることができるでしょう。
①:レビュー数(満足度)から生成AI搭載製品を探す

「全体」タブをクリックすると、全ての製品の中から生成AI機能についてのレビューが多い順に製品が表示されます。

並び順を変更することで「満足度が高い順」や「満足度が低い順」に並べ替えることも可能です。
②:カテゴリー別に生成AI搭載製品を探す
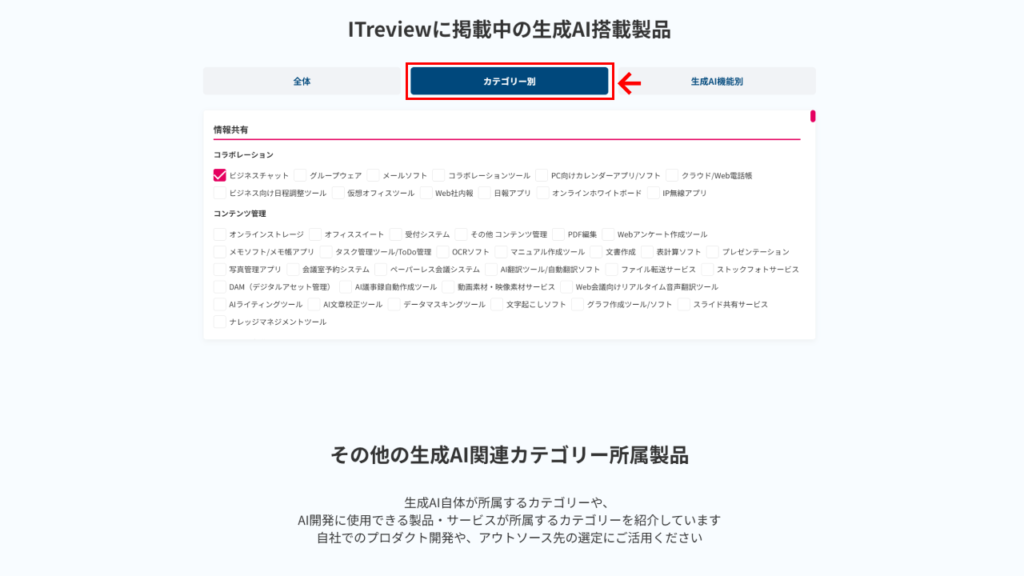
「カテゴリー別」タブをクリックし、任意のカテゴリーにチェックボックスを入れてから、対象製品を絞り込みます。
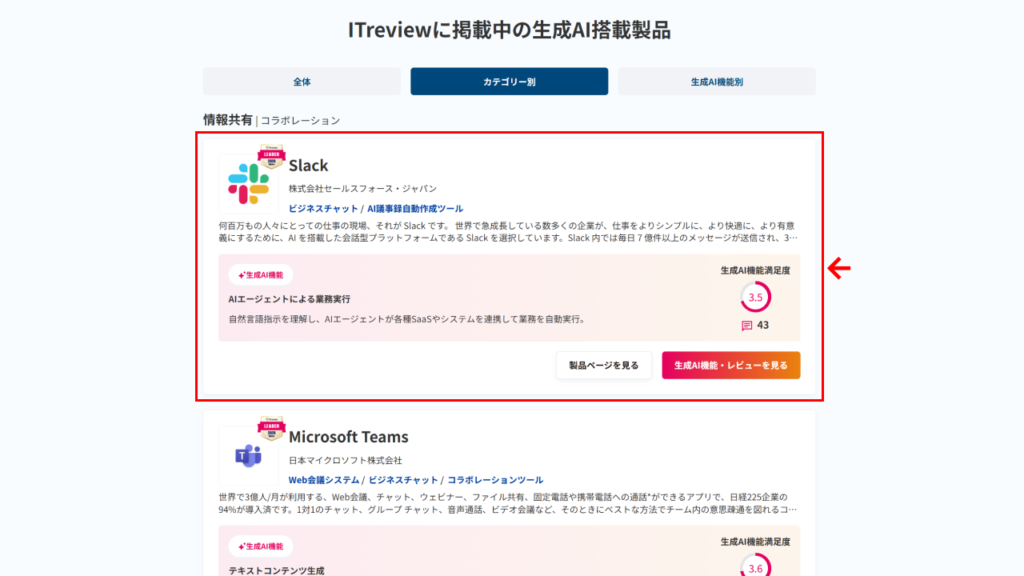
選択したカテゴリーのうち、生成AI機能に関するレビューが多い順に製品が表示されます。
③:機能別に生成AI搭載製品を探す

「生成AI機能別」タブをクリックし、任意の生成AI機能にチェックボックスを入れてから、対象製品を絞り込みます。

選択した生成AI機能のうち、その機能に関するレビューが多い順に製品が表示されます。
なぜいま生成AI搭載SaaSが重要なのか?
- ①:業務の自動化と高度化が加速した
- ②:データ活用の価値が高まっている
- ③:人材不足への有効な対応策となる
①:業務の自動化と高度化が加速した
生成AI技術の進化により、これまで人間が時間をかけて行っていた文章作成やデータ整理、傾向の分析業務など、非常に多くの業務が自動化されつつあります。
従来の業務自動化は、定型作業やルールベースの処理が中心でしたが、生成AIの登場によって、判断やアウトプットをともなう業務まで自動化の対象が広がっています。これは業務の「スピード」だけでなく「質」そのものを引き上げる大きな変化だといえるでしょう。
例えば、営業支援SaaSでは、商談内容の自動文字起こしや要点の要約、顧客課題に応じた提案資料の自動生成が可能になっています。その結果、営業担当者は資料作成に追われることなく、顧客との対話や戦略設計に集中できる環境を実現でき、生産性向上に直結しています。
②:データ活用の価値が高まっている
生成AIは、大量かつ質の高いデータを前提に学習・推論を行う技術であるため、SaaSに日々蓄積される業務データの価値は、これまで以上に重要性を増しています。
単にデータを「保存する」だけでなく「活用できる状態で蓄積できているか」がSaaS選定における大きな分岐点となっています。適切なSaaS導入により、業務ログや顧客データ、コミュニケーション履歴などが一元的に蓄積され、AI分析の土台を構築することが可能です。
一方で、データ構造が整理されていないSaaSや、AI活用を前提としていない設計のツールでは、十分な成果を得ることが難しくなってしまいます。生成AI時代においては「今使える機能」だけでなく、将来的なデータ活用まで見据えたSaaS選定が求められているというわけです。
③:人材不足への有効な対応策となる
少子高齢化の進行により、多くの業界で人材不足が深刻化するなか、SaaSと生成AIの組み合わせは、人手不足を補う現実的かつ持続的な対策として注目されています。
生成AIを搭載したSaaSを活用することで、従来は複数人で対応していた業務を少人数で回せるようになり、限られた人員でも高い成果を上げることができるようになりました。特に、バックオフィスやサポート業務など、負荷が集中しやすい領域では、その効果は顕著です。
また、人材を単純作業から解放し、より付加価値の高い業務に集中させられる点は、従業員満足度や定着率の向上にも寄与します。このように、AI搭載SaaSは単なる効率化ツールではなく、経営課題としての人材不足を構造的に解決する手段として、大きなメリットを持っています。
生成AI搭載SaaSの具体的な活用事例
- 営業支援SaaSでの活用事例
- マーケティングSaaSでの活用事例
- カスタマーサポートSaaSでの活用事例
営業支援SaaSでの活用事例
営業支援の領域では、生成AIを活用した営業活動の効率化が急速に普及しています。具体的には、商談内容を自動で文字起こし・要約し、次回アクションや提案内容をAIが提示する機能が挙げられます。これにより、営業担当者は入力作業から解放され、顧客対応に集中できるようになります。
また、過去の受注データや失注データの学習によって、成約確度の高いリードをAIが抽出することで、営業効率や成約率の最大化にも貢献しています。
マーケティングSaaSでの活用事例
マーケティング分野では、生成AIによるコンテンツ生成と分析の自動化が進んでいます。例えば、メールマーケティングSaaSでは、顧客属性や行動履歴をもとに、最適な件名や本文をAIが自動生成します。これにより、担当者のスキル差に左右されず、安定した成果を出しやすくなります。
さらに、広告運用SaaSでは、広告文案の生成やA/Bテストの結果の分析をAIが行うことで、配信後のPDCAサイクルを高速化できる点が評価されています。
カスタマーサポートSaaSでの活用事例
カスタマーサポート領域では、AIチャットボットを活用した対応の自動化が進んでいます。FAQ対応だけでなく、過去の問い合わせ履歴を学習し、文脈を理解した高精度な回答が可能になっています。これにより、問い合わせ対応の一次受けをAIが担い、オペレーターは高度な対応に集中できます。
また、問い合わせ内容を自動分類・分析することで、プロダクト改善や顧客満足度向上につなげるなど、サポート業務を超えた価値創出も実現しています。
生成AI搭載SaaSを選ぶときの比較チェックリスト
| 比較軸 | 確認すべきポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| コスト | 初期費用・月額費用・追加費用のバランスは問題ないか? | □ |
| 機能性 | 自社業務に必要な機能が過不足なく搭載されているか? | □ |
| 拡張性 | 将来的な事業拡大や生成AI活用にも対応できるか? | □ |
| 使いやすさ | 現場担当者が直感的に操作できるUI/UXか? | □ |
| セキュリティ対策 | 情報漏えいや不正アクセス対策は十分か? | □ |
| サポート体制 | 初期設定や改善提案のサポートはあるか? | □ |
生成AI時代のSaaS選定においては、感覚や流行だけで判断するのではなく、これまで以上に企業の課題や目的に対する、機能の適合性が重要になります。複数の比較軸から冷静に検討することが重要です。
①:コストに関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| 初期費用 | 初期導入費・設定費用は発生するか? | □ |
| 月額費用 | 利用人数・利用量に応じた料金体系か? | □ |
| 従量課金 | AI利用回数やAPI利用で追加課金が発生しないか? | □ |
| 将来コスト | スケールアップ時にコストが急増しないか? | □ |
| 費用対効果 | 業務削減時間や人件費削減と見合っているか? | □ |
AI搭載SaaSのコスト評価では、単純な月額料金の比較だけで判断するのは非常に危険です。なぜなら、生成AI搭載SaaSでは、利用量に応じてコストが変動する構造を持つケースが多いためです。
特に注意すべきなのが、AI機能に関する従量課金です。文章生成回数、APIコール数、処理トークン数などが料金に影響する場合、利用が定着するほどコストが膨らむ傾向にあります。また、コストは「削減できる人件費や工数」とセットで評価する必要があります。単純なツール費用ではなく、業務削減時間・人員配置の最適化まで含めた費用対効果の視点で判断することが重要です。
②:機能性に関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| 業務適合度 | 自社の業務課題を直接解決できるか? | □ |
| AI機能の実用性 | 実務で使える精度やスピードか? | □ |
| AI機能の過不足 | 不必要なAI機能が多すぎないか? | □ |
| 業務カバー範囲 | 一部業務だけでなく全体最適につながるか? | □ |
| 業務判断への寄与 | AIの出力が意思決定や判断に活用できるか? | □ |
AI搭載SaaSにおける機能性の評価では「できることの多さ」ではなく「自社の抱えている課題や業務にどれだけフィットしているか」を冷静に判断することが最も重要な評価指標になります。
生成AI機能が豊富でも、業務フローと乖離している場合、現場では使われず形骸化してしまいます。特に注意したいのは「AIで何が自動化され、どこに人の判断が残るのか」が曖昧なツールです。また、機能が多すぎるSaaSは運用が複雑になりがちで、教育コストや定着率の低下につながります。ポイントは「業務課題 → 必要機能 → AI活用ポイント」の順で整理することが重要です。
③:拡張性に関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| 利用人数拡張 | 部署や拠点の追加に柔軟に対応できるか? | □ |
| 機能拡張 | 将来的な業務拡張に耐えられるか? | □ |
| 他ツール連携 | 既存SaaSや基幹システムとの連携は可能か? | □ |
| AI進化対応 | 今後のAI機能の強化が見込めるか? | □ |
| 活用の発展性 | 蓄積データを将来のAI活用に転用できるか? | □ |
SaaSは一度導入すると、簡単には切り替えられません。そのため、拡張性は「今すぐ必要かどうか」ではなく、将来の事業成長や組織変化に耐えられるかという視点で評価する必要があります。
特にAI搭載SaaSでは、今後のAIモデルの進化や新機能追加への対応力が重要です。現時点では十分でも、AI機能のアップデートが止まっているツールは、数年後に競争力を失う可能性があります。また、他SaaSや基幹システムとの連携可否も重要な要素です。データが分断されると、AI活用の精度や価値が大きく下がるため、API連携やデータ統合の柔軟性は必ず確認しておきましょう。
④:使いやすさに関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| UI/UX | ITに不慣れな社員でも直感的に使えるか? | □ |
| 学習コスト | 操作方法の習得に時間がかからないか? | □ |
| 現場定着 | 実際の業務フローに無理なく馴染むか? | □ |
| AI操作性 | 搭載されているAI機能が複雑すぎないか? | □ |
| 属人化リスク | 特定の人間しか使えない設計ではないか? | □ |
どれほど高機能なAI搭載SaaSでも、現場で使われなければ意味がありません。現場担当者の使いやすさや定着のしやすさは、SaaS選定において成果を左右する最重要指標のひとつだといえます。
特に生成AI機能は、操作が複雑になりやすい傾向があります。プロンプト入力が難解だったり、設定項目が多すぎたりすると、利用は一部の担当者に限定されてしまいます。重要なのは、ITリテラシーに差がある社員でも直感的に使えるかどうかです。トライアルやデモを通じて「説明なしでも使えるか」という視点で評価することが、定着率を高める大きなポイントになります。
⑤:セキュリティ対策に関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| データの所有権 | 自社データの帰属は明確か? | □ |
| AI学習利用 | 入力データがAI学習に使われないか? | □ |
| 認証と権限 | 多要素認証や権限管理が可能か? | □ |
| 第三者認証 | ISOやSOC2などの取得状況はどうか? | □ |
| 障害事故対応 | インシデント発生時の対応は問題ないか? | □ |
AI搭載SaaSでは、セキュリティ対策が従来以上に重要かつ繊細な項目になってきます。なぜなら、生成AIに入力されるデータには、顧客の個人情報や社内機密が含まれるケースが多いためです。
特に確認すべきなのが「入力データがAIの学習に使われるかどうか」というポイントです。意図せずデータが外部学習に利用されると、情報漏えいリスクやコンプライアンス違反につながる可能性があります。それ加えて、認証方式や権限管理、第三者認証(ISO、SOC2など)の有無も重要です。AI時代のSaaS選定では、使える機能以上にセキュリティやポリシーを重視する姿勢が求められます。
⑥:サポート体制に関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| 導入支援 | 初期設定やオンボーディング支援はあるか? | □ |
| 問い合わせ対応 | サポートの速度や対応品質は十分か? | □ |
| 日本語対応 | 日本語でのサポートが受けられるか? | □ |
| 運用支援 | 活用提案や改善アドバイスはあるか? | □ |
| 情報提供 | アップデート情報は適切に共有されるか? | □ |
AI搭載SaaSは、単に導入して終わりではなく、使いこなしてこそ初めてその真価を発揮します。そのため、サポート体制の品質は、導入の成否そのものを左右する重要な要素といえるでしょう。
特に、初期導入時のオンボーディング支援だけでなく、運用フェーズでの活用提案や改善アドバイスが受けられるかどうかは大きな差になります。また、問い合わせ対応のスピードや日本語サポートの有無も、現場のストレスに直結します。AI搭載SaaSほど、単なる「ツール」ではなく、継続的な情報提供と伴走支援がある「パートナー」としての支援体制を重視すべきです。
生成AI搭載SaaSで高評価を受けやすい製品の特徴
- ①:安心して社内のデータを預けられる
- ②:業務フローの一部を代替してくれる
- ③:すでにあるデータを活用してくれる
- ④:操作がシンプルで使いやすい
- ⑤:失敗しても修正が効きやすい
①:安心して社内のデータを預けられる
高評価を受けやすい生成AI機能の1つ目の特徴としては「安心して社内データを預けられるAIである」というものが挙げられます。
入力した情報がどこに保存されるのか、外部に送信されるのか、学習データに使われるのかなど、ルールが明確に示されているほど、利用者は安心して業務データを預けることができるようになります。
また、アクセス権限の制御や公開範囲の設定・管理、ログの記録やトラブル発生時の証跡管理など、すでにある社内のセキュリティポリシーとの整合性が取れていることも重要な要素といえるでしょう。
②:業務フローの一部を代替してくれる
高評価を受けやすい生成AI機能の2つ目の特徴としては「業務フローの特定の一部を代替してくれる」というものが挙げられます。
例えば、議事録の作成や定型メール文の作成、レポートの下書きやデータの入力など、人間が行うと時間がかかってしまう判断価値の低いタスクを、AIが代わりに実行してくれるというイメージです。
人間が本来すべき作業に集中できるよう、どこまでの作業をAIが担当し、どこから先を人間が引き継ぐのかが明確になっている機能ほど、現場からの信頼と満足度が高くなりやすい傾向にあります。
③:すでにあるデータを活用してくれる
高評価を受けやすい生成AI機能の3つ目の特徴としては「今ある情報資産をどれだけ引き出せるか」というものが挙げられます。
評価されるAI機能は、新たなデータ収集を強要するのではなく、既存の顧客情報や過去の案件履歴、マニュアルやチャットログなど、社内やシステム内に存在するデータをうまく活用してくれます。
逆に、データの準備やタグ付けに多くの手間がかかる仕組みは、導入効果が見えにくく、評価されにくくなります。個別事情に即した提案を行ってくれると、現場は「わかっているな」と感じるのです。
④:操作がシンプルで使いやすい
高評価を受けやすい生成AI機能の4つ目の特徴としては「ユーザーの迷いを最小限にしたUI/UX設計」というものが挙げられます。
いくら優れたAI機能であっても、操作が難しければ利用頻度は上がりません。入力欄がわかりやすい、専門用語を多用していないなどは、ITリテラシーに差がある組織でも広く使われやすくなります。
また、ボタンの数が必要最小限であることも高く評価される要素のひとつです。マニュアルを深く読み込まなくても、触っているうちに使い方を理解できるかどうかが、満足度を大きく左右します。
⑤:失敗しても修正が効きやすい
高評価を受けやすい生成AI機能の5つ目の特徴としては「まずはAIにやらせて気になる部分だけ直す」というものが挙げられます。
AIは必ずしも毎回完璧な結果を出すわけではありません。評価されるAI機能ほど、失敗を前提とした余白のある設計になっており、出力結果を簡単に修正・再生成・上書きできるようになっています。
例えば「もう少し丁寧な言い回しに」や「文末の表現だけ変えて」などの抽象的な指示で出力を調整できたり、AIの提案をそのまま編集できたりする仕組みがあると、安心して使い続けることができます。
まとめ:生成AI搭載SaaSを選ぶならITreviewがオススメ!
本記事では、ITreviewを活用した生成AI搭載SaaSの比較や選定方法にスポットを当てながら、サイトの基本的な使い方から便利な比較方法の紹介まで徹底解説していきました!
生成AI機能はたしかに便利な代物ですが「どのような業務で使えるのか?」や「どれくらいの工数削減効果があるのか?」といった具体的な活用シーンについては、実際のユーザーレビューを見てみないことには、なかなかイメージが湧きにくいものです。
ぜひ本記事を参考にしながら、自社に合った生成AI搭載SaaSを比較・検討してみてはいかがでしょうか?
投稿 【生成AIでSaaS選定はこう変わる】ITreviewで生成AI搭載SaaSを比較してみよう! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【Canvas機能×DeepResearch】生成AIと“共同編集”で資料作成を劇的に効率化する方法を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、Canvas機能を使えば、修正箇所を直接指定しながら編集・上書き・履歴管理が可能となり、文章作成や資料作りの生産性を大きく向上させることができるのです。
本記事では、Canvas機能の基本的な仕組みからDeepResearchとの連携方法、ChatGPT・Geminiそれぞれの使い方や具体的な活用例までを、実務目線でわかりやすく解説していきます。
この記事を読むだけで、Canvas機能を「知っている状態」から「業務に組み込める状態」まで一気に理解できるため、AI活用を次のレベルへ進めたい担当者にとっては必見の内容です。
※ 本記事は、2025年10月時点の情報をもとに執筆しております。生成結果やその内容の正確性を完全に保証するものではありません。
Canvas機能とは?
ChatGPTやGeminiに搭載された「Canvas(キャンバス)機能」は、AIと一緒に文書や資料をリアルタイムで編集・作成できる機能です。イメージとしては、WordやGoogleドキュメントの「共同編集」をAIコーチと一緒に行うイメージです。
これまでのように「文章を生成 → コピー → Wordに貼り付け」ではなく、AIと同じ画面上でドキュメントを共同編集できるのが大きな特徴です。
たとえば、ChatGPTのCanvasでは、記事やコード、プレゼン資料の原稿など、AIが書いたものをその場で修正・追記しながら作ることができます。
また、ダウンロード可能な状態で出力されるため、すぐに活用することができます。Geminiでも同様に、スライドやドキュメントをAIが補助しながら作成する体験が可能です。
つまりCanvasは、AIが「答えをもらうだけのアイデア出し相手」から「最終成果物を作成できる共同制作者」へ進化した環境とも言えます。通常のチャット機能と比較した場合のメリットは以下の通りです。
修正箇所を明示的に選択可能
通常のチャットでは「ここを直して」をプロンプトに書き込む必要がありますが、Canvas機能ではドラックで選択して修正箇所を指定することが可能です。そのため、より細かい選択ができることに加えて「意図しない箇所の修正」を軽減することができます。
新規作成ではなく上書き作成
通常のチャットで修正指示をした場合、新しい生成結果が出力されてしまいます。そのため、修正箇所の比較が難しく、またチャット欄が修正した回数に比例して長くなってしまいます。
Canvas機能では、上書き状態で修正が行われるため、成果物としては1つにまとめることができます。また、変更履歴の確認も可能なため「1つ前の状態との比較」や「n回前の修正に戻す」といったこともクリックで簡単に実行することができます。
コード実行で即座に確認可能
Canvas機能では、コードの生成のみでなく、実行も可能です。そのため、コード実行結果の確認はもちろん、HTMLを実際に表示することも可能です。
このあと紹介しますが、スライドをHTMLで作成する場合は「実際にどのように見えるか」が重要になるため、わざわざファイルをダウンロード → ローカル表示といった手順を踏まずとも、Canvas機能内で確認できるというのは作業時間の効率化に有効です。
DeepResearch機能×Canvas機能の活用例
お使いになったことがある方も多い「DeepResearch」機能と「Canvas」機能を組み合わせると、リサーチから成果物の生成までをワンストップで完結、かつ出力結果をリッチにできます。
調査結果はすごいものの「これを資料化するのは面倒だなぁ…」や「そのままコピペすると崩れるんだよなあ…」と思った方も多いのではないでしょうか?それを解決するのがCanvas機能というわけです!
たとえば、以下のようなユースケースが考えられます。
①:市場調査レポートを作る場合
- DeepResearch:最新の生成AI市場動向を調査
- Canvas:AIがまとめた内容を自分の言葉で整えたり、数値データを綺麗なグラフ化した資料を作成
②:製品比較スライドを作る場合
- DeepResearch:ChatGPTとGeminiの違いを比較調査
- Canvas:AIに「ページ送り機能付きのスライドを作成して」と指示
(※ スライドはPPT形式ではなくHTMLで作成されます)
③:社内ブログの下書きを作る場合
- DeepResearch:担当製品に関する最新情報を調査
- Canvas:社内向けトーンに書き換え、必要な情報を修正箇所を指定しながら肉付け
AIが下調べをしてくれるだけでなく、その結果を「同じ画面上で整理・整形・再構成・視覚化・ドキュメント化できる」というのが、この連携の強みです。また他のツールを組み合わせる場合、どうしてもツール間のコピペや、各種資格化材料の作成が必要になってしまうので、工数も多きく削減できます!
ChatGPTのCanvas機能の使い方
ChatGPTのCanvasは、ChatGPT Enterprise環境で利用することができます。もしも「Canvas」のメニューが表示されない場合は、画面キャッシュのクリアを行ってみてください。
使用方法は以下の通りです。
①:Canvas機能を有効化する
チャット欄左の「+」をクリックし、展開されるメニューから「Canvas」を選択します。
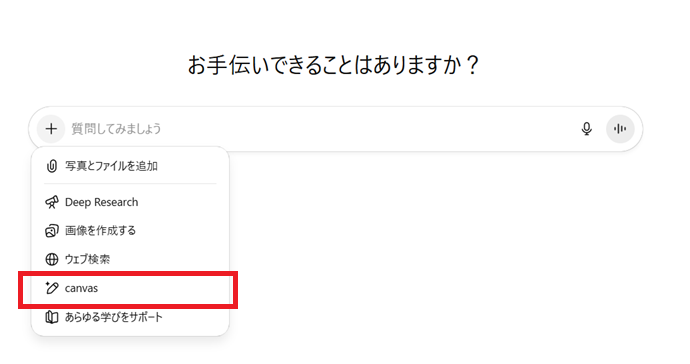
チャット欄下部に水色で「Canvas」が表示されていればOKです。
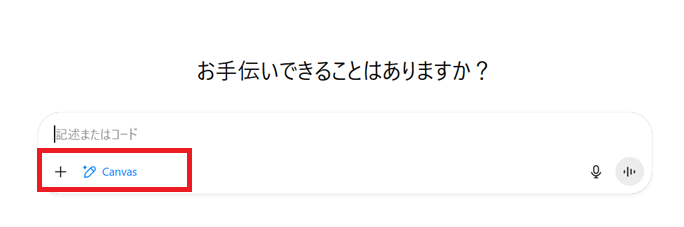
②:AIに作成したいものをプロンプトで依頼
たとえば「最新のAIトレンドに関するブログを作成して」と依頼すると、Canvas機能で成果物がブロック出力されます。
Canvas機能で出力されたブロックには、右上に「コピーする」「編集する」「ダウンロードする」が、コード出力の場合は「コードを実行する」が、HTMLの場合は「プレビュー」等のメニューが表示されます。
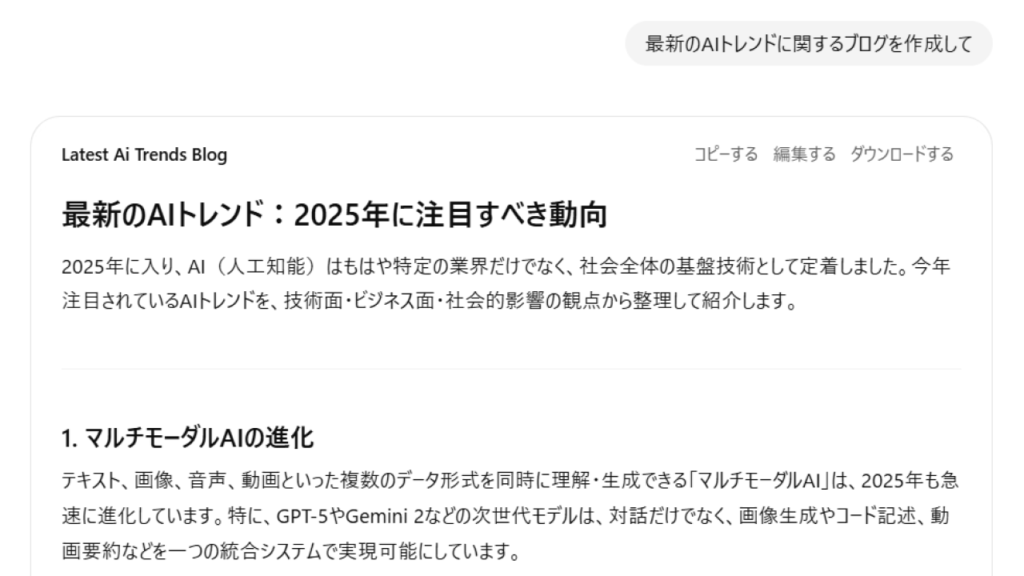
③:編集やテスト実行
さらに「編集する」ボタンをクリックすると、左側にチャット、右側に編集画面が表示されます。
編集画面では、編集したい箇所をドラックで選択すると、編集バーが表示され、自然言語で修正指示が可能な「ChatGPTに質問する」と、成果物の形式に沿った編集メニューが表示されます。今回はドキュメント形式なので、太字、斜体等といった内容が追加で表示されています。
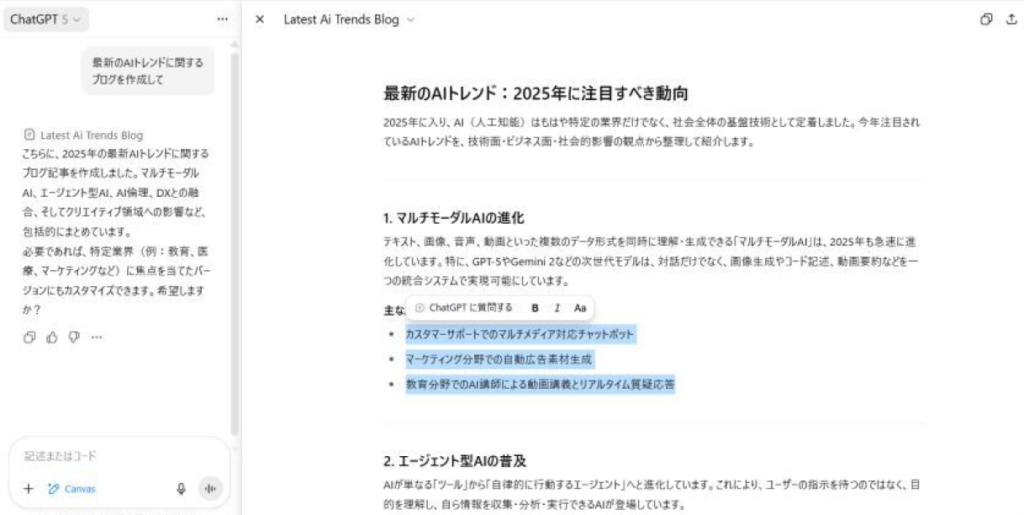
自然言語指示で修正したい場合は「ChatGPTに質問する」をクリックします。すると、自由記述が可能なテキストボックスが表示されるため、そこに修正指示を入力します。
①:修正箇所を選択して「ChatGPTに質問する」をクリックでテキストボックスが表示される
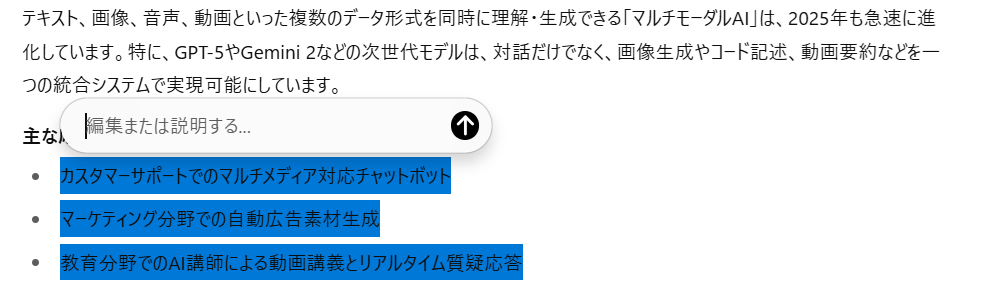
②:自然言語で修正内容を指示し、右側の上向き矢印をクリックする
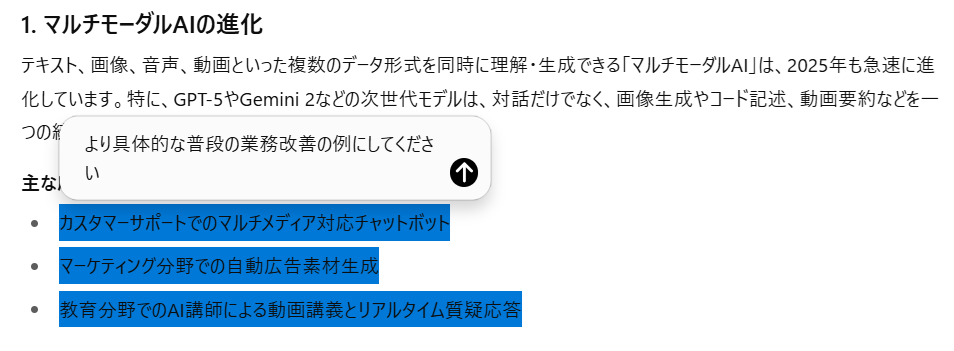
③:修正された内容で上書きされる
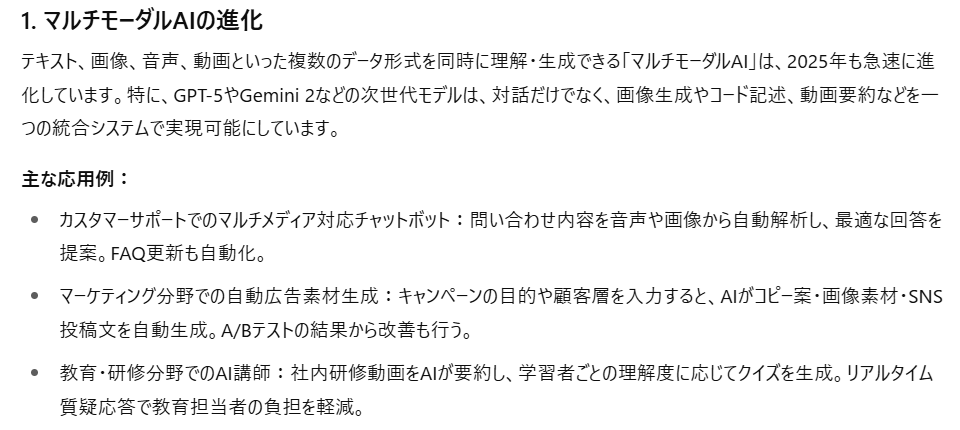
④:バージョン管理
修正された内容については、バージョン管理による差分確認が可能です。編集画面右上の時計マークをクリックします。
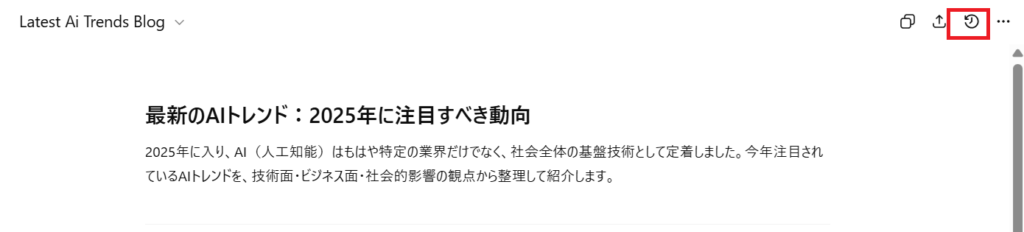
すると、1つ前のバージョンとの差分が色分け表示されるため、どこがどう修正されたのかを一目で把握することが可能です。
また、先ほどの時計マークの右にある「…」をクリックすることで「前のバージョン」や「次のバージョン」と、履歴表示することも可能なため、以前の状態を表示するのも簡単です。
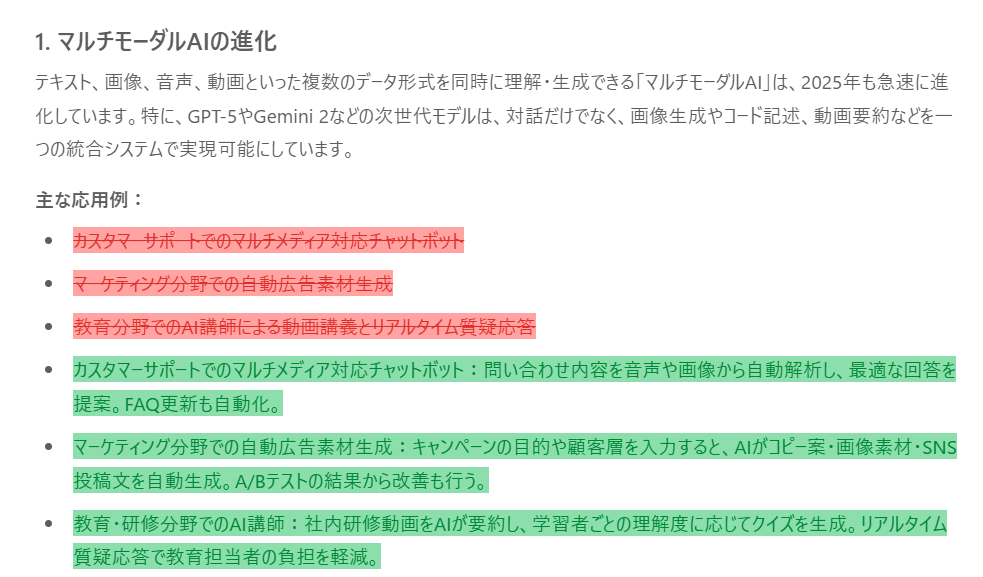
ChatGPTを使ったスライド生成手順
ChatGPTのCanvas機能におけるオススメの使い方として「ページ送りありのスライドをHTML形式で出力」というものが挙げられます。調査~生成までを一気通貫で行うこともできるのが強みです。
①:プロンプトで作成内容を指示
※ 別途「PPTではなくHTMLで」という指示をしない場合、専用ライブラリが必要な形式で出力されてしまうため、基本的にはこの指示も追加してください
※ グラフの作成時には日本語フォントが文字化けしてしまうため、基本的にフォントの埋め込み指示を追加してください
※ 今回は、調査内容も同一プロンプトで指示していますが、DeepResearchの結果に対して、Canvas機能でスライド生成を指示することも可能です。ただし、DeepResearchとCanvasを同時に実行することはできないため、必ずDR→Canvasというようにタスクを分解して実行してください
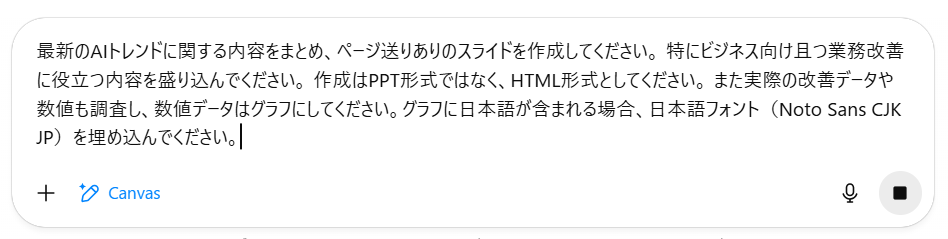
②:右上の「プレビュー」をクリック

③:表示内容を確認しつつ細かい修正を行う
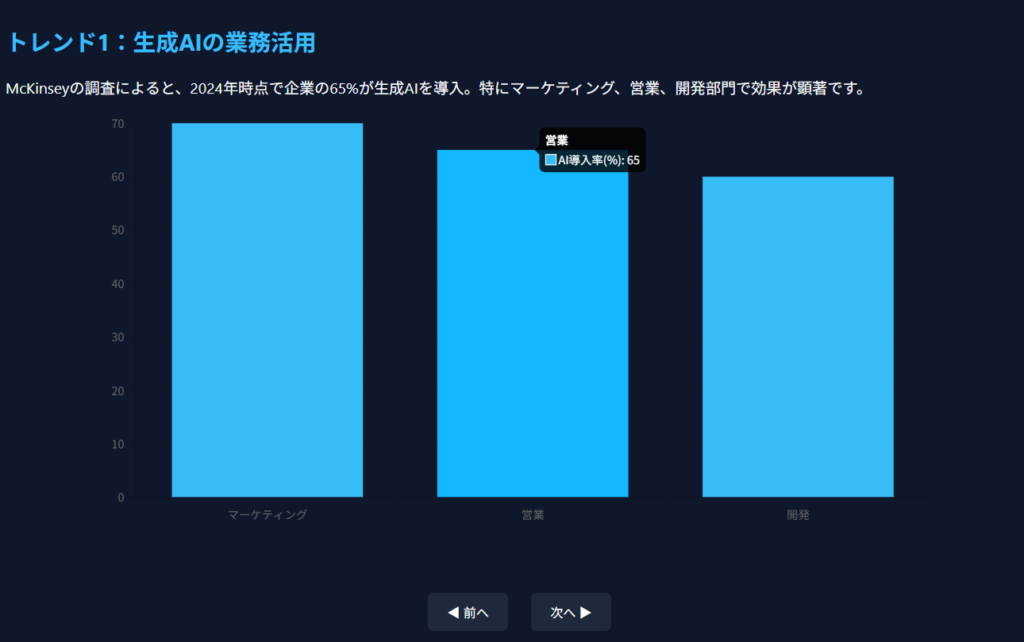
作成したスライドをChatGPTの画面以外から表示したい場合、Canvasのブロック右上メニューからHTMLファイルをダウンロードし、ダウンロードしたファイルを「右クリック → プログラムから開く → ChromeやEdgeといったブラウザを選択」することで別画面での表示が可能です。
HTMLのまま使用するのはもちろん、HTMLで出力されたものを参考にしながらレイアウトを考えPPTを作成するというのも、個人的にはかなりオススメの使い方になります。

ちなみに、DeepResearchとCanvasを組み合わせると、こんなに詳細で綺麗なスライドを作成することができます!
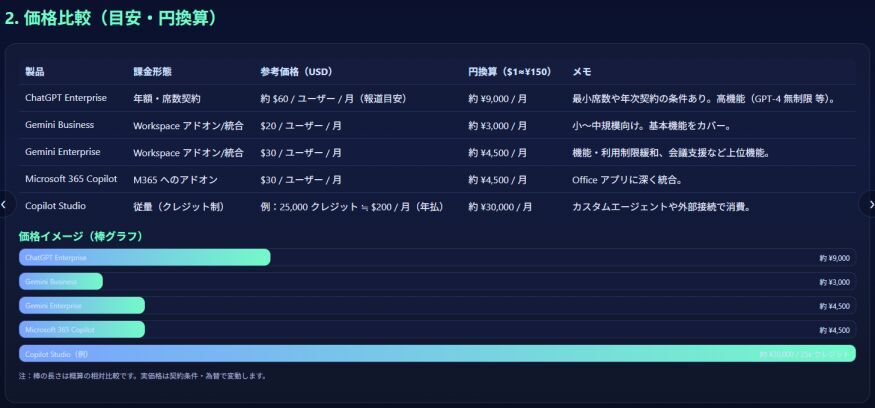
GeminiのCanvas機能の使い方
GeminiのCanvas機能は、基本的にはChatGPTのCanvas機能と同等の出力が可能です。
しかし「出力パターンが用意されているのでワンクリックで出力できる」という手軽さについては、Geminiならではの特徴であり、パターンとしては2025年10月現在、以下のものが用意されています。
- ウェブページ
- インフォグラフィックス
- クイズ
- フラッシュカード
- 音声解説
インフォグラフィックとは「情報(Information)と図(Graphic)」を組み合わせた造語で「視覚的に情報を伝える手段」であり、情報をとても綺麗に可視化してくれるのでオススメです。
この5パターン+自由入力可能なテキストボックスが用意されています。使用方法は以下の通りです。
①:Canvasを有効にする
チャット欄の「ツール」をクリックし表示されるメニューから「Canvas」を選択してください。
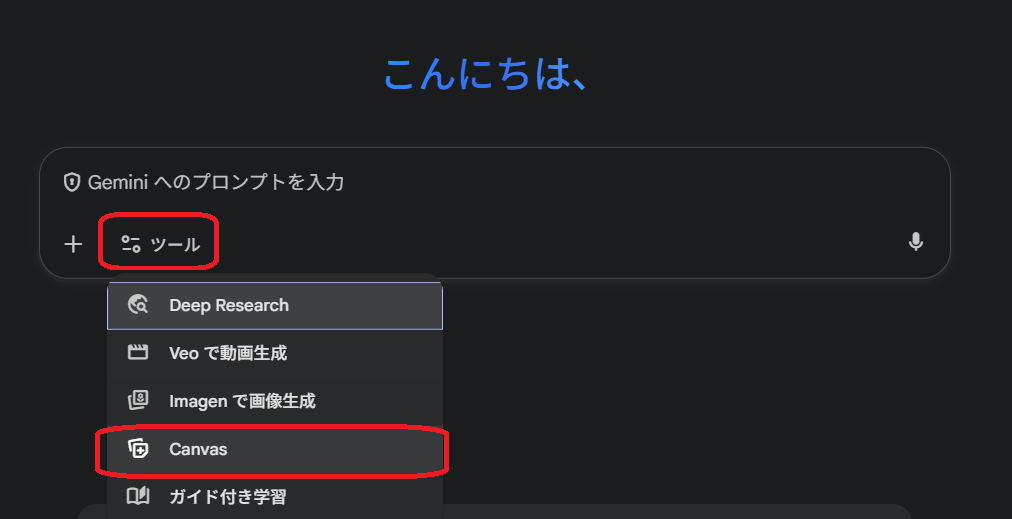
チャット欄下部にCanvasの文字が表示されればOKです。
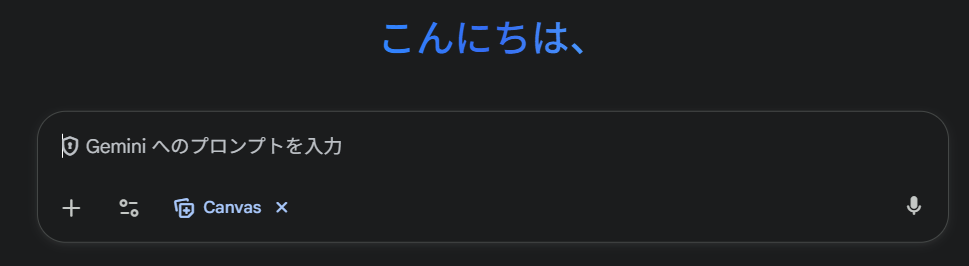
②:作成したいものをプロンプトで依頼
こちらはChatGPTと同様です。Canvasが有効な状態で作成したい内容を指示してください。作成が完了すると基本的には自動でCanvasの編集画面が表示されます。

もしも編集画面が表示されない場合、生成物はチャット履歴に薄灰色のブロックで表示されているので、ブロックの「開く」をクリックしてください。
ここでポイントなのが、DeepResearchの結果についてもこの形式で出力されるため「開く」をクリックすると自動でCanvas編集画面が開けます!
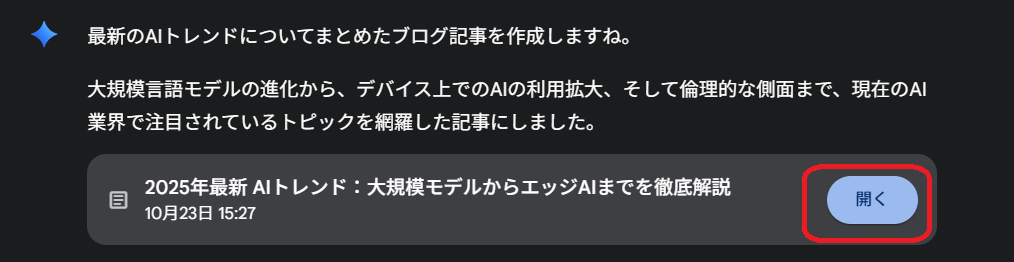
③:編集やテスト実行
こちらも基本的な操作はChatGPTと同様です。修正したい箇所を選択し、表示されるバルーンに修正したい内容を入力します。
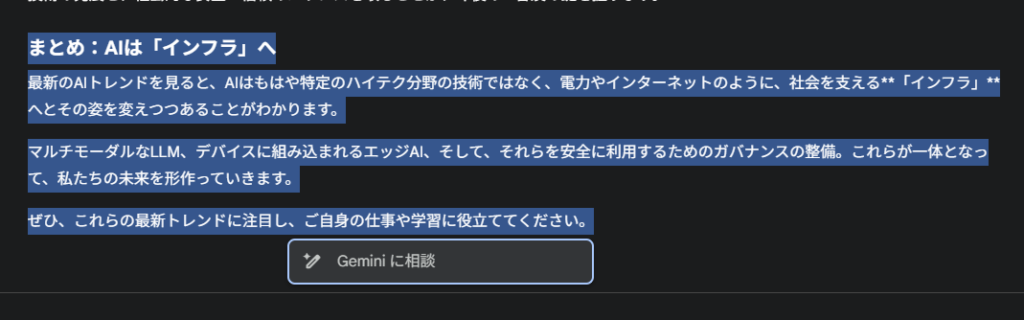
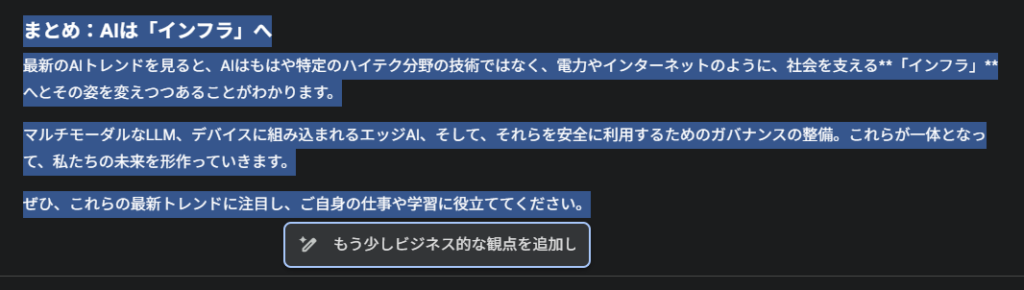
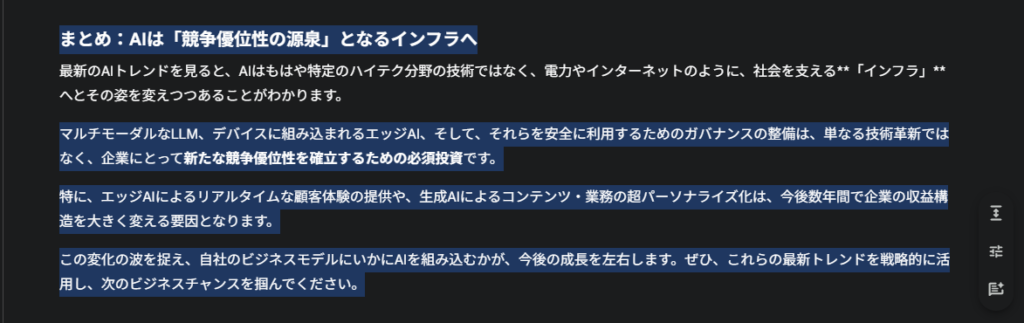
このほかにも、Geminiにはデフォルトで生成物に合わせたワンクリック編集メニューが用意されています。今回はドキュメントなので、
- 長さを変更
- トーンを変更
- 変更を提案
が用意されていました。これも嬉しいポイントですね。
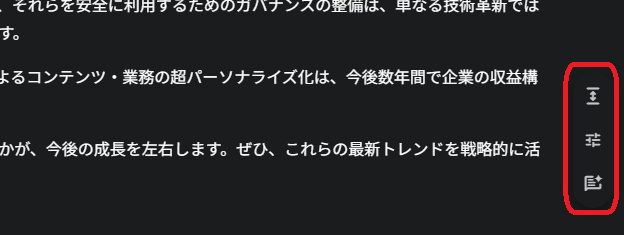
ちなみに「変更を提案」をクリックすると、以下のようにインラインで提案を表示してくれます。チャット欄だと、このように提案と実際の成果物を一緒に見るのは難しいので、これもCanvas機能の強みといえます。
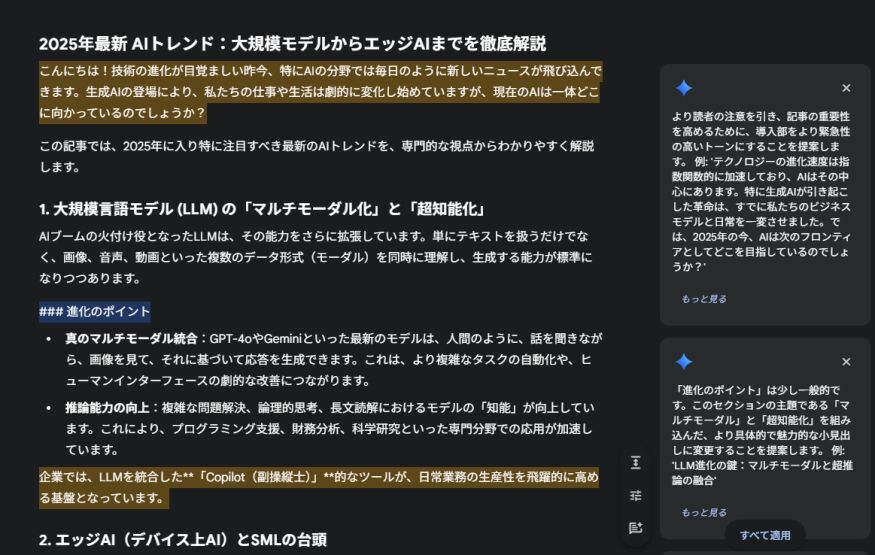
④:ワンクリック生成
最後にワンクリック生成についてです。Canvas編集画面の右上の「作成」ボタンをクリックすると、先述したワンクリック生成パターンメニューが表示されます。一番下は出力したい形式を自由に入力できるテキストボックスになっています。
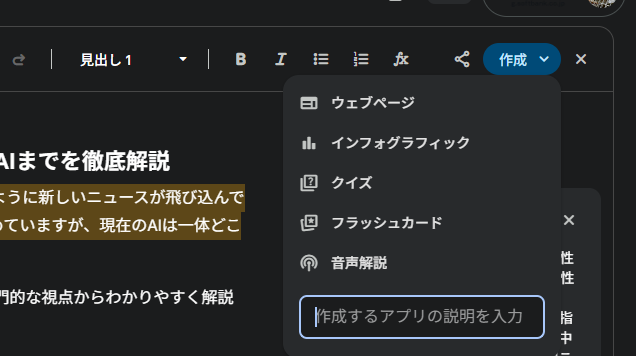
今回は「インフォグラフィック」を選択してみます。方法は先ほど開いたメニューの「インフォグラフィック」をクリックするだけです。
生成されたものは以下になります。このまま資料として使えそうなほどビジュアルとして綺麗なものができ上がりました。
特に、グラフや図に関してはデータに沿った、そして見やすいものが出力されるので、このまま使用しない場合でも視覚化の参考にとても便利です。
注意点としては、こちらもHTMLでの出力になりますので、ローカルやGemini以外で表示したい場合は、ChatGPTで説明した方法で表示してください。
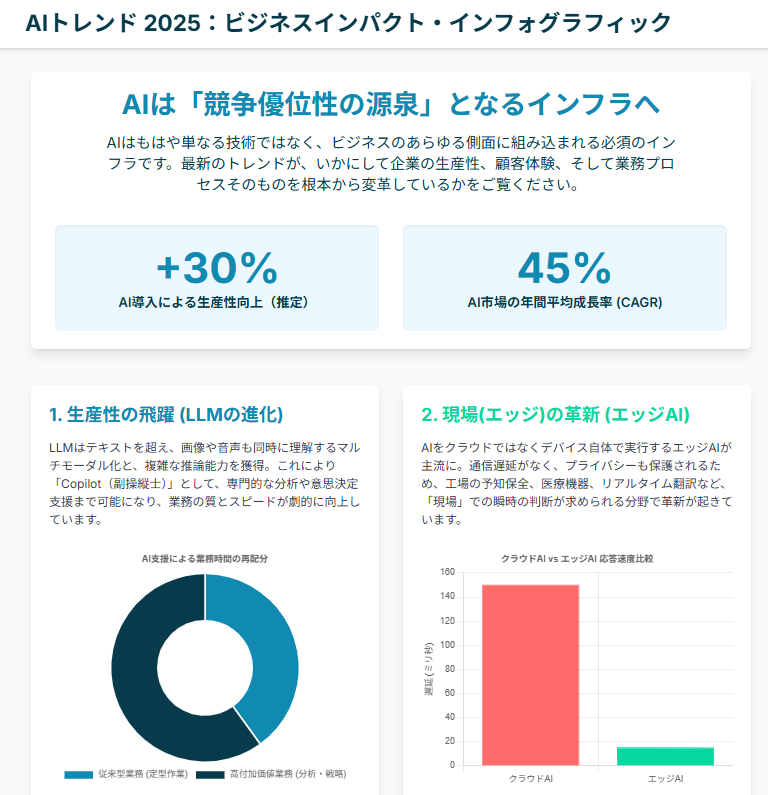

Geminiを使ったスライド生成手順
もちろん、GeminiのCanvasでもスライドは生成可能です!とはいえ、こちらもHTML形式での出力となりますので、その点はご注意ください。
作成方法は先ほど紹介した「④ワンクリック生成」で表示したテキストボックスに「ページ送り機能付きのスライド」と入力してください。このほかにスタイルの指定をしてもよいですし「文字は少なめで視覚表現多め」や「ポップなイメージで」といったような指定も効果的です。
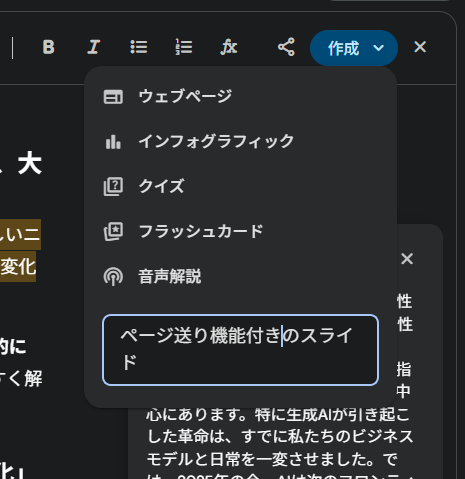
できがったスライドがこちらです!一部抜粋の紹介になりますが、しっかりとページ送り機能もあり、アイコンの使い方やレイアウトが綺麗なスライドが作成されました。
Geminiはビジュアライズ化において、ChatGPTよりも(現時点では)優れていると感じています。もちろんこの辺りは個人の好みの問題になるので、みなさんも両方で試してみてください!

まとめ
以上、Canvas機能についての説明でした。
ご紹介した通り、なんらかのドキュメントを作成する場合に通常チャットよりもとても便利なので、是非使ってみてください。
個人的には最近、一度自分で書いたブログをアップして読み返しながら、文体の統一や肉付け、ちょっと足りないなと思った部分のアイデアをもらったりしています。ぜひみなさんもご自身の業務に組み込んでみてください!
そして、もちろんDeepResearchについても情報収集において、とてつもなく有用なツールになっていますので、こちらも積極的に活用していただければと思います。GeminiとChatGPTでのDeepResearchの違いについては過去のブログでも紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
AIを使用することは今後の業務革新において必要不可欠なことです。そして、AIは周辺ツール(機能)の活用やちょっとしたひと手間で結果をよりリッチにすることができますので、ぜひ色々と試してみてください!
投稿 【Canvas機能×DeepResearch】生成AIと“共同編集”で資料作成を劇的に効率化する方法を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【一歩先の調査へ】Deep Researchの活用術を紹介!生成AIのハルシネーションを防ぐには? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし一方で、使い方を誤ると誤情報の混入や理解が浅いまま鵜呑みにしてしまうリスクなどもあり、「便利そうだけど正直どう使えばいいかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、Deep Researchの基本的な仕組みを整理したうえで、精度を高めるための考え方や具体的な活用のプロセス、実際に筆者が意識している使い方のコツまで、徹底的に解説していきます。
この記事を読むことで、Deep Researchを「ただ使う」状態から、知識を深めるための強力なリサーチパートナーとして使いこなす視点が身につくはずです。調査の質を一段引き上げたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
※ 生成AIはモデルの進化による精度向上が進んでおり、ハルシネーションの発生率も改善傾向にあります。そのため、本ブログ執筆時と比較し、回答精度は上昇しておりますが、それでも正確性を完全に保証するものではありません。そういった点でも、本ブログの内容を活用いただき、ハルシネーション対策の一助としていただけると幸いです。
Deep Researchとは?
すでにご存知の方も多いと思われますが、改めてその機能を一言で説明すると「1つのプロンプトで最新のオンライン情報を検索・統合し、詳細なリサーチタスクを完成する機能」です。これまでのGPTのように「プロンプト ⇒ 生成」と1度の問い合わせで完了するのではなく、モデル自身が「どのような順序で調べるか」というワークフローを思考しながら結果を出力してくれるという特徴(AIエージェント)もあります。
ちなみに、私も最近になって知ったのですが、ChatGPTのDeep Researchは2025年5月現在、o3にDeep Researchのために手を加えた「Deep Research専用モデル(※)」で動いているそうです。
なので、ChatGPTのチャット欄の左上にあるモデル選択は、Deep Researchに関しては関係ないそうです(もっと早く知りたかった)。
(※)プランによっては制限を超えた場合、自動で軽量版であるo4-miniをもとにしたモデルに切り替わります。
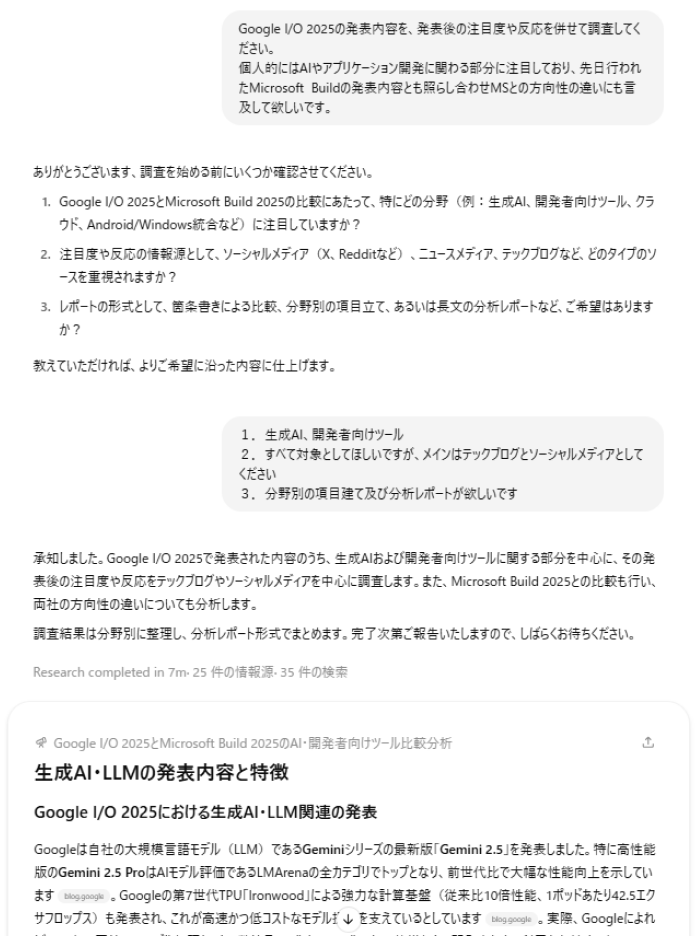
とても詳細なリサーチを行ってくれることで業務に大きく貢献してくれるDeep Researchですが、ユーザーが少し使い方を工夫することで、その威力を最大限に発揮します。
今回ご紹介する個人的に考える工夫ポイントは以下の2点です。
①:リサーチ対象に関する基礎知識は事前に身に着ける
間違った情報の出力や意図しない回答、ハルシネーションを含む回答を生成することも十分に考えられるため、正誤の判断をある程度可能にするための事前情報は、信頼できる公式情報等から自分自身でリサーチする
②:知識を、横に、縦に、広げる手段として使用する
出力結果は「情報の羅列」に過ぎないため、出力結果を読み解き、知らない内容や気になった点をさらに深掘りすることで「知識」に昇華し、知見を広げていく
では、具体的に普段の私がどのようにDeep Researchを使用しているのか紹介していきます。
Deep Researchの個人的活用術!
①:まずは自力での調査(対象の知識が乏しい場合)
Deep Researchを実行する前に、まずはある程度リサーチ対象についての情報を身に着けておきましょう。とは言ってもガッツリ調べるということではなく、ざっと全体像を見渡し「なるほど理解した」レベルまでもっていく程度でOKです。こうしておくことで、Deep Researchの結果の誤情報や意図しない出力を(100%は無理でも)見分けることができます。加えてDeep Researchの出力結果は結構な量になることも多いので、なかなか頭の中の情報整理が難しいということもありました。事前知識があればこういった問題も緩和することが可能です。
また、調査段階で気になった点があれば箇条書きでメモを取るようにしています。このひと手間をかけておくことで、Deep Researchでの深掘りがさらに捗ります。
調査では、以下のようなソースを主に調べます。上の項目ほど優先度が高いです。
・公式情報:公式サイトや公式ドキュメント・リポジトリ
こちらは言わずもがな、最も信頼できるソースです。特に企業情報や製品情報といった公式サイトが存在する場合には必ず目を通しておきましょう。OSSのような公開ソースがあるものの場合は、そちら(READMEレベルでもOK)にざっと目を通すとより具体化できます。
英語サイトや英語ドキュメントを調査する場合は「最初から全体翻訳」ではなく「ざっくり見渡した後に段落区切りで翻訳(たとえ意味が2割程度しかわからなくても)」していくと、文脈の取り違えや翻訳ミスによる理解の齟齬、専門用語のおかしな翻訳(プログラミング用語である「Python」が「ニシキヘビ」に翻訳される等)による混乱を避け、結果的に理解度を高めることが可能です。
・Wiki:Wikipediaや関連情報がまとめられたサイト
こちらは、公式情報よりは信頼度が低くなりますが、複数人によって編集されていることで情報の精度はある程度期待できますし、新しい観点をゲットできることも多くあります。技術要素であればその技術を扱う企業のエンジニアブログ(Engineer Voiceのようなサイト)からピックアップして眺めるのも良い手です。ただし、古い情報がアップデートされていない可能性も多くありますので、その点はご注意ください。
・評判や実体験:個人の感想ブログやSNSでの反応
これは付加的なものにはなりますが、特に製品や技術系を調査する場合は、実際に触るのが難しいことがあったり、自分の知識やスペックでは補えない感想があったりなども多くあります。そのため、まずはSNSで調べてみて、使用者や有識者の素直な反応を見ることも大切です。とはいえ、有象無象になりかねないので、この調査は「確実にその手の人間である」ことがわかるアカウントや反応が大きいものに絞って確認したりしています。
②:Deep Researchの実行
いよいよAIの登場です!実際にプロンプトを流す際には、以下のような点に注意しています。
・①で知らなかった内容を軽くリサーチする
関連用語でわからない、もしくは誤解しているものがある場合、リサーチ結果の理解度に大きく影響します。そのため①の自己調査で初めて出くわした単語に関しては、本リサーチの前に擦り合わせの意味を込めて軽く1度リサーチします。ここはDeep Researchでなくても問題ありませんが、最新情報を取ってこれるような設定(Web検索をONにする等)を加えておいてください。
・①で気になった内容をプロンプトに加える
①の自己調査で「わからない」訳ではないけれど、なぜそうなったのかイマイチ理解できていないと感じた点については、しっかりとその旨とその部分を重点的、もしくは付加説明をしてもらえるようプロンプトに追加します。こうすることにより「今の自分向けにカスタマイズ」された調査報告を得ることができます。
・専門用語は簡単な説明を追加するよう指示する
すでに軽く調査済みであっても、リサーチ結果に知らない単語、特に専門用語が出てくる可能性は大いにあります。そのため、プロンプトで「専門用語については必ず150文字以内の簡単な説明を追加してください」と記述しておくと、都度別途で調査をしなくても概要であれば掴むことが可能です。特にChatGPTであれば、ヒストリー機能により過去のチャットも参照されるので、自分の知識レベルに合わせた解説をしてくれる可能性が高まります。
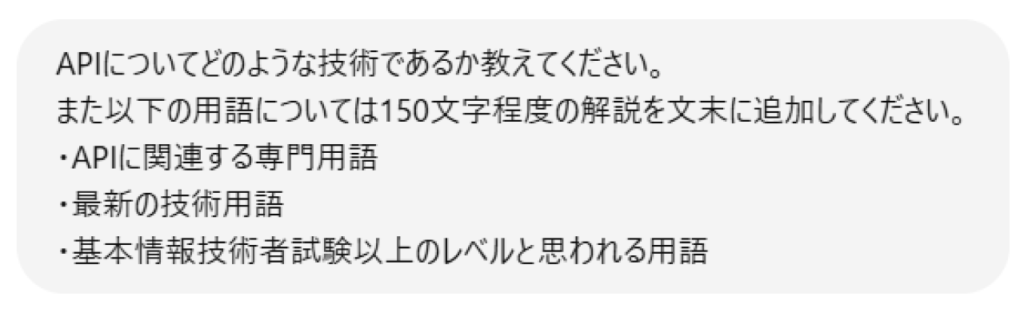
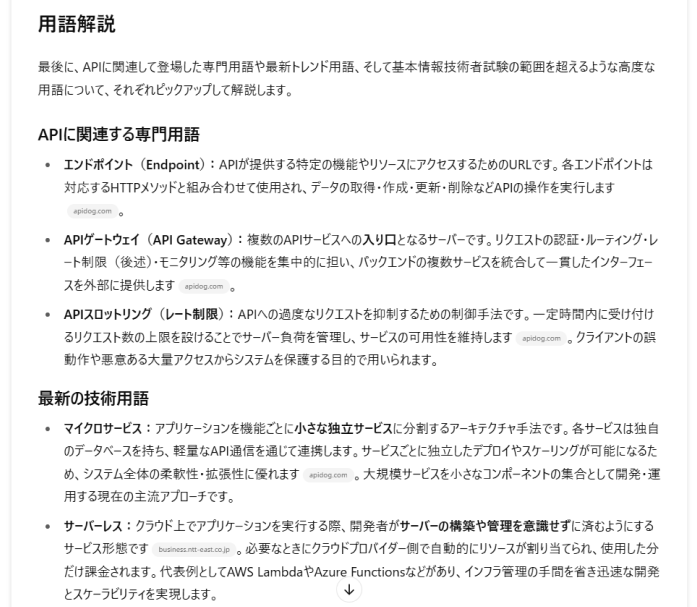
・公式情報と公式以外の情報は区別するよう指示する
リサーチ結果には出典が付きますが、毎回リンク先を確認するのは骨が折れるので、特に製品や企業といった公式サイトがある場合、プロンプトで公式の出典、もしくはそれ以外を一目で区別できるよう指示しておくと情報の選別が楽になります。例えば「公式サイト以外からの情報の場合は文字色をグレーにすること」というように指示しておくことで、後々の真偽や重要度の判定が楽になります。
・競合の製品や類似の企業などがわかる場合は加える
DeepResearchの場合、最初のプロンプトの後には、ほぼ必ず指示に対する追加質問が行われるため、その際に聞かれることもありますが、競合や類似する製品や企業、技術が判明している場合、それらとの比較を最初から指示しておくと理解度も深まりますし、追加で指示する必要もなくなります。もちろん、具体的な名称がわからなくとも「競合や類似がある場合はメリデメを比較して」と追加するのも効果的です。
・比較や数字データはなるべく表形式で出してもらう
どうしても文字量が多くなりがちなので、表やグラフといったデータ類は図として可視化してもらった方が読みやすくなります。リサーチ結果を報告する場合にも参考になるので、これは積極的に追加したい指示です。
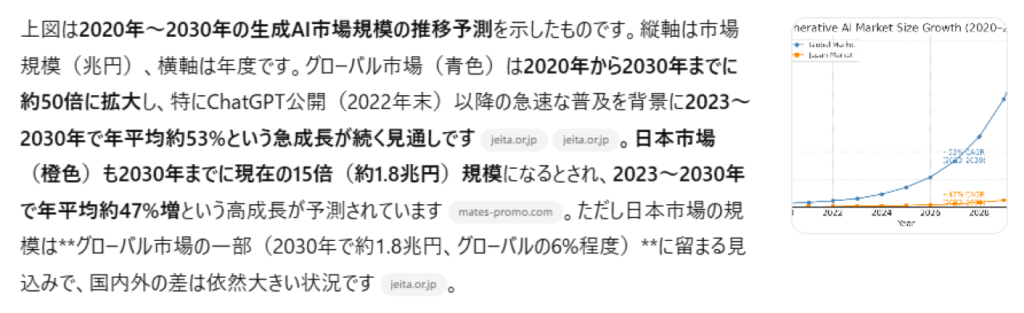
・タスクを切り分けて徐々に深掘りするよう指示する
AIの特性上、あまり幅広い内容を聞いてしまうとコンテキスト量が増えてしまい、出力結果の精度が落ちる可能性があります。その場合は一度で気になったことをすべて聞くのではなく、調査したい内容をタスク分解してからリサーチを開始するのも効果的です。これにより、最初に行ったリサーチの内容を後から行うリサーチに反映するような効果もあります。例えば、まずは①で気になった点について質問をしてから、本題のリサーチを行うというように分解することで、最終出力の量を減らすだけでなく、ユーザーの知識レベルや聞きたいことの本質を理解した状態でDeepResearchを実行できます。
③:調査した内容との擦り合わせ
リサーチ結果が出力された後は、まずは一通り読み込みます。そして、①で自己調査した内容と異なる内容が出力されている点や、なんとなく認識が違いそうな内容をピックアップして再度自己調査、もしくは出力結果の出典や再リサーチで詳細を確認します。曖昧な部分をはっきりさせることで、知識の強化や実はハルシネーションが発生している部分に気付くことができます。出力結果が素晴らしいと意外とすんなり鵜呑みにしてしまいがちですが、少しでも違和感を感じたらぜひ再調査してみてください。
また、①では調査しきれていなかった部分に対する出力があった場合、そういった部分は自分の知識外、もしくは興味外の内容である場合が多く、なかなか自分だけの調査では触れることができない部分である可能性が高いため、その部分を重点的に再調査することもポイントです。以降の調査の質が格段に上がります。
④:疑問点や周辺知識の深堀り
そして、ここからがある意味真骨頂です!ここまで調べた内容をもとに、横に、縦に、深掘りしていきます。
特に深掘りして欲しいポイントとしては、以下の3点です。
- 理解できなかった点や深掘りが必要だと感じた点は自己調査や再質問を繰り返す
- メイン文脈以外の部分でも知らなかった単語や気になった点があれば質問してみる
- 技術から商材、商材から技術といったようにレイヤーを変えながら理解していく
このように広げることで「1つの知識」から「ネットワーク化された知識」に昇華され、新たな視点やアイデアが生まれたり、その知識から未来予測をしたりといったことも考えられます。ここまでを一人で行うにはこれまでは膨大な時間がかかっていましたが、DeepResearchを使うことでかなりの時間が短縮されます!
ちなみに、曖昧な単語や適当な文章で質問しても「それは〇〇のことで合っていますか?」のように、それまでの文脈からAIが推測して聞いてくれるので、とてもありがたいです。
手間はかかりますがこのような部分を少し意識するだけで調査の質が向上するのはもちろん、自分自身の知識が飛躍的に強化されますので、是非試してみてください!
まとめ
長文になってしまいましたが、今回は私のDeep Research活用術について書かせていただきました。
特に「本リサーチの前の事前調査」や「知識の幅広げに活用する」というポイントは、Deep Researchのみでなく、通常のチャットやOpenAI以外のDeep Research系の機能でも応用できる部分なので、ぜひこのような使い方で自分自身のレベルアップに活用してください!
とはいえ、事前調査している時間がない場合や本当にちょっとした調べ物、対象に対する知識が元々十分にあるといった場合は、いきなり②から始めてしまってもOKです!それでもハルシネーションが不安な場合は、出典の確認だけでも最小限やっておくのがオススメです。
便利なDeep Researchをより正確かつ安全に、そして最大限活用できるようこれからもいろいろと試していこうと思います。
投稿 【一歩先の調査へ】Deep Researchの活用術を紹介!生成AIのハルシネーションを防ぐには? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【チェックリスト付き】生成AI時代におけるSaaSの選び方とは?比較の軸や注意するポイントを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、AI搭載をうたうSaaSの中には、実務で活用しきれないものや、ブラックボックス化によるリスクを抱えるものも存在します。選定を誤ると期待した成果が出ない投資になりかねません。
本記事では、生成AI時代におけるSaaS選定の考え方の解説に加えて、AI搭載SaaSを比較するためのポイントや導入時に注意すべき観点を実務目線で徹底的に解説していきます。
この記事を読むだけで、AI搭載型のSaaSを見極める判断軸が明確になり、ツールの選定に迷っている担当者や意思決定者にとって、確かな指針を得られる内容になっています。
SaaSとは何か?改めて整理
SaaS(サース)とは、Software as a Serviceの略称で、ソフトウェアを自社で開発・保有するのではなく、クラウド上で利用する形態のことです。最大の特長は初期投資を抑えて導入できるところにあります。
また、従来型のオンプレミス型システムとは異なり、サーバーの構築や保守運用が不要であるため、ITリソースが限られる中小スタートアップ企業でも導入しやすいところが評価されています。
具体的には、会計、人事、営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、幅広い業務領域でSaaSが活用されており、業務の標準化と効率化を同時に実現するツールとして普及が進んでいます。
さらに近年では、生成AI機能を組み込んだSaaSも増えており、単なる業務効率化ツールから意思決定を支援する戦略的ツールへと進化を遂げています。今後はAI機能の有無がSaaSにとって重要な選定指標となることは間違いないでしょう。
AI機能搭載SaaSが重要な理由
- ①:業務の自動化と高度化が加速した
- ②:データ活用の価値が高まっている
- ③:人材不足への有効な対応策となる
①:業務の自動化と高度化が加速した
生成AI技術の進化により、これまで人間が時間をかけて行っていた文章作成やデータ整理、傾向の分析業務など、非常に多くの業務が自動化されつつあります。
従来の業務自動化は、定型作業やルールベースの処理が中心でしたが、生成AIの登場によって、判断やアウトプットをともなう業務まで自動化の対象が広がっています。これは業務の「スピード」だけでなく「質」そのものを引き上げる大きな変化だといえるでしょう。
例えば、営業支援SaaSでは、商談内容の自動文字起こしや要点の要約、顧客課題に応じた提案資料の自動生成が可能になっています。その結果、営業担当者は資料作成に追われることなく、顧客との対話や戦略設計に集中できる環境を実現でき、生産性向上に直結しています。
②:データ活用の価値が高まっている
生成AIは、大量かつ質の高いデータを前提に学習・推論を行う技術であるため、SaaSに日々蓄積される業務データの価値は、これまで以上に重要性を増しています。
単にデータを「保存する」だけでなく「活用できる状態で蓄積できているか」がSaaS選定における大きな分岐点となっています。適切なSaaS導入により、業務ログや顧客データ、コミュニケーション履歴などが一元的に蓄積され、AI分析の土台を構築することが可能です。
一方で、データ構造が整理されていないSaaSや、AI活用を前提としていない設計のツールでは、十分な成果を得ることが難しくなってしまいます。生成AI時代においては「今使える機能」だけでなく、将来的なデータ活用まで見据えたSaaS選定が求められているというわけです。
③:人材不足への有効な対応策となる
少子高齢化の進行により、多くの業界で人材不足が深刻化するなか、SaaSと生成AIの組み合わせは、人手不足を補う現実的かつ持続的な対策として注目されています。
生成AIを搭載したSaaSを活用することで、従来は複数人で対応していた業務を少人数で回せるようになり、限られた人員でも高い成果を上げることができるようになりました。特に、バックオフィスやサポート業務など、負荷が集中しやすい領域では、その効果は顕著です。
また、人材を単純作業から解放し、より付加価値の高い業務に集中させられる点は、従業員満足度や定着率の向上にも寄与します。このように、AI搭載SaaSは単なる効率化ツールではなく、経営課題としての人材不足を構造的に解決する手段として、大きなメリットを持っています。
AI機能搭載SaaSの具体的な活用事例
- 営業支援SaaSでの活用事例
- マーケティングSaaSでの活用事例
- カスタマーサポートSaaSでの活用事例
営業支援SaaSでの活用事例
営業支援の領域では、生成AIを活用した営業活動の効率化が急速に普及しています。具体的には、商談内容を自動で文字起こし・要約し、次回アクションや提案内容をAIが提示する機能が挙げられます。これにより、営業担当者は入力作業から解放され、顧客対応に集中できるようになります。
また、過去の受注データや失注データの学習によって、成約確度の高いリードをAIが抽出することで、営業効率や成約率の最大化にも貢献しています。
マーケティングSaaSでの活用事例
マーケティング分野では、生成AIによるコンテンツ生成と分析の自動化が進んでいます。例えば、メールマーケティングSaaSでは、顧客属性や行動履歴をもとに、最適な件名や本文をAIが自動生成します。これにより、担当者のスキル差に左右されず、安定した成果を出しやすくなります。
さらに、広告運用SaaSでは、広告文案の生成やA/Bテストの結果の分析をAIが行うことで、配信後のPDCAサイクルを高速化できる点が評価されています。
カスタマーサポートSaaSでの活用事例
カスタマーサポート領域では、AIチャットボットを活用した対応の自動化が進んでいます。FAQ対応だけでなく、過去の問い合わせ履歴を学習し、文脈を理解した高精度な回答が可能になっています。これにより、問い合わせ対応の一次受けをAIが担い、オペレーターは高度な対応に集中できます。
また、問い合わせ内容を自動分類・分析することで、プロダクト改善や顧客満足度向上につなげるなど、サポート業務を超えた価値創出も実現しています。
AI搭載SaaSを選ぶときの比較チェックリスト
| 比較軸 | 確認すべきポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| コスト | 初期費用・月額費用・追加費用のバランスは問題ないか? | □ |
| 機能性 | 自社業務に必要な機能が過不足なく搭載されているか? | □ |
| 拡張性 | 将来的な事業拡大や生成AI活用にも対応できるか? | □ |
| 使いやすさ | 現場担当者が直感的に操作できるUI/UXか? | □ |
| セキュリティ対策 | 情報漏えいや不正アクセス対策は十分か? | □ |
| サポート体制 | 初期設定や改善提案のサポートはあるか? | □ |
生成AI時代のSaaS選定においては、感覚や流行だけで判断するのではなく、これまで以上に企業の課題や目的に対する、機能の適合性が重要になります。複数の比較軸から冷静に検討することが重要です。
①:コストに関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| 初期費用 | 初期導入費・設定費用は発生するか? | □ |
| 月額費用 | 利用人数・利用量に応じた料金体系か? | □ |
| 従量課金 | AI利用回数やAPI利用で追加課金が発生しないか? | □ |
| 将来コスト | スケールアップ時にコストが急増しないか? | □ |
| 費用対効果 | 業務削減時間や人件費削減と見合っているか? | □ |
AI搭載SaaSのコスト評価では、単純な月額料金の比較だけで判断するのは非常に危険です。なぜなら、生成AI搭載SaaSでは、利用量に応じてコストが変動する構造を持つケースが多いためです。
特に注意すべきなのが、AI機能に関する従量課金です。文章生成回数、APIコール数、処理トークン数などが料金に影響する場合、利用が定着するほどコストが膨らむ傾向にあります。また、コストは「削減できる人件費や工数」とセットで評価する必要があります。単純なツール費用ではなく、業務削減時間・人員配置の最適化まで含めた費用対効果の視点で判断することが重要です。
②:機能性に関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| 業務適合度 | 自社の業務課題を直接解決できるか? | □ |
| AI機能の実用性 | 実務で使える精度やスピードか? | □ |
| AI機能の過不足 | 不必要なAI機能が多すぎないか? | □ |
| 業務カバー範囲 | 一部業務だけでなく全体最適につながるか? | □ |
| 業務判断への寄与 | AIの出力が意思決定や判断に活用できるか? | □ |
AI搭載SaaSにおける機能性の評価では「できることの多さ」ではなく「自社の抱えている課題や業務にどれだけフィットしているか」を冷静に判断することが最も重要な評価指標になります。
生成AI機能が豊富でも、業務フローと乖離している場合、現場では使われず形骸化してしまいます。特に注意したいのは「AIで何が自動化され、どこに人の判断が残るのか」が曖昧なツールです。また、機能が多すぎるSaaSは運用が複雑になりがちで、教育コストや定着率の低下につながります。ポイントは「業務課題 → 必要機能 → AI活用ポイント」の順で整理することが重要です。
③:拡張性に関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| 利用人数拡張 | 部署や拠点の追加に柔軟に対応できるか? | □ |
| 機能拡張 | 将来的な業務拡張に耐えられるか? | □ |
| 他ツール連携 | 既存SaaSや基幹システムとの連携は可能か? | □ |
| AI進化対応 | 今後のAI機能の強化が見込めるか? | □ |
| 活用の発展性 | 蓄積データを将来のAI活用に転用できるか? | □ |
SaaSは一度導入すると、簡単には切り替えられません。そのため、拡張性は「今すぐ必要かどうか」ではなく、将来の事業成長や組織変化に耐えられるかという視点で評価する必要があります。
特にAI搭載SaaSでは、今後のAIモデルの進化や新機能追加への対応力が重要です。現時点では十分でも、AI機能のアップデートが止まっているツールは、数年後に競争力を失う可能性があります。また、他SaaSや基幹システムとの連携可否も重要な要素です。データが分断されると、AI活用の精度や価値が大きく下がるため、API連携やデータ統合の柔軟性は必ず確認しておきましょう。
④:使いやすさに関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| UI/UX | ITに不慣れな社員でも直感的に使えるか? | □ |
| 学習コスト | 操作方法の習得に時間がかからないか? | □ |
| 現場定着 | 実際の業務フローに無理なく馴染むか? | □ |
| AI操作性 | 搭載されているAI機能が複雑すぎないか? | □ |
| 属人化リスク | 特定の人間しか使えない設計ではないか? | □ |
どれほど高機能なAI搭載SaaSでも、現場で使われなければ意味がありません。現場担当者の使いやすさや定着のしやすさは、SaaS選定において成果を左右する最重要指標のひとつだといえます。
特に生成AI機能は、操作が複雑になりやすい傾向があります。プロンプト入力が難解だったり、設定項目が多すぎたりすると、利用は一部の担当者に限定されてしまいます。重要なのは、ITリテラシーに差がある社員でも直感的に使えるかどうかです。トライアルやデモを通じて「説明なしでも使えるか」という視点で評価することが、定着率を高める大きなポイントになります。
⑤:セキュリティ対策に関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| データの所有権 | 自社データの帰属は明確か? | □ |
| AI学習利用 | 入力データがAI学習に使われないか? | □ |
| 認証と権限 | 多要素認証や権限管理が可能か? | □ |
| 第三者認証 | ISOやSOC2などの取得状況はどうか? | □ |
| 障害事故対応 | インシデント発生時の対応は問題ないか? | □ |
AI搭載SaaSでは、セキュリティ対策が従来以上に重要かつ繊細な項目になってきます。なぜなら、生成AIに入力されるデータには、顧客の個人情報や社内機密が含まれるケースが多いためです。
特に確認すべきなのが「入力データがAIの学習に使われるかどうか」というポイントです。意図せずデータが外部学習に利用されると、情報漏えいリスクやコンプライアンス違反につながる可能性があります。それ加えて、認証方式や権限管理、第三者認証(ISO、SOC2など)の有無も重要です。AI時代のSaaS選定では、使える機能以上にセキュリティやポリシーを重視する姿勢が求められます。
⑥:サポート体制に関するチェック
| チェック項目 | 確認ポイント | チェックボックス |
|---|---|---|
| 導入支援 | 初期設定やオンボーディング支援はあるか? | □ |
| 問い合わせ対応 | サポートの速度や対応品質は十分か? | □ |
| 日本語対応 | 日本語でのサポートが受けられるか? | □ |
| 運用支援 | 活用提案や改善アドバイスはあるか? | □ |
| 情報提供 | アップデート情報は適切に共有されるか? | □ |
AI搭載SaaSは、単に導入して終わりではなく、使いこなしてこそ初めてその真価を発揮します。そのため、サポート体制の品質は、導入の成否そのものを左右する重要な要素といえるでしょう。
特に、初期導入時のオンボーディング支援だけでなく、運用フェーズでの活用提案や改善アドバイスが受けられるかどうかは大きな差になります。また、問い合わせ対応のスピードや日本語サポートの有無も、現場のストレスに直結します。AI搭載SaaSほど、単なる「ツール」ではなく、継続的な情報提供と伴走支援がある「パートナー」としての支援体制を重視すべきです。
AI搭載SaaSで高評価を受けやすい機能の特徴
- ①:安心して社内のデータを預けられる
- ②:業務フローの一部を代替してくれる
- ③:すでにあるデータを活用してくれる
- ④:操作がシンプルで使いやすい
- ⑤:失敗しても修正が効きやすい
①:安心して社内のデータを預けられる
高評価を受けやすい生成AI機能の1つ目の特徴としては「安心して社内データを預けられるAIである」というものが挙げられます。
入力した情報がどこに保存されるのか、外部に送信されるのか、学習データに使われるのかなど、ルールが明確に示されているほど、利用者は安心して業務データを預けることができるようになります。
また、アクセス権限の制御や公開範囲の設定・管理、ログの記録やトラブル発生時の証跡管理など、すでにある社内のセキュリティポリシーとの整合性が取れていることも重要な要素といえるでしょう。
②:業務フローの一部を代替してくれる
高評価を受けやすい生成AI機能の2つ目の特徴としては「業務フローの特定の一部を代替してくれる」というものが挙げられます。
例えば、議事録の作成や定型メール文の作成、レポートの下書きやデータの入力など、人間が行うと時間がかかってしまう判断価値の低いタスクを、AIが代わりに実行してくれるというイメージです。
人間が本来すべき作業に集中できるよう、どこまでの作業をAIが担当し、どこから先を人間が引き継ぐのかが明確になっている機能ほど、現場からの信頼と満足度が高くなりやすい傾向にあります。
③:すでにあるデータを活用してくれる
高評価を受けやすい生成AI機能の3つ目の特徴としては「今ある情報資産をどれだけ引き出せるか」というものが挙げられます。
評価されるAI機能は、新たなデータ収集を強要するのではなく、既存の顧客情報や過去の案件履歴、マニュアルやチャットログなど、社内やシステム内に存在するデータをうまく活用してくれます。
逆に、データの準備やタグ付けに多くの手間がかかる仕組みは、導入効果が見えにくく、評価されにくくなります。個別事情に即した提案を行ってくれると、現場は「わかっているな」と感じるのです。
④:操作がシンプルで使いやすい
高評価を受けやすい生成AI機能の4つ目の特徴としては「ユーザーの迷いを最小限にしたUI/UX設計」というものが挙げられます。
いくら優れたAI機能であっても、操作が難しければ利用頻度は上がりません。入力欄がわかりやすい、専門用語を多用していないなどは、ITリテラシーに差がある組織でも広く使われやすくなります。
また、ボタンの数が必要最小限であることも高く評価される要素のひとつです。マニュアルを深く読み込まなくても、触っているうちに使い方を理解できるかどうかが、満足度を大きく左右します。
⑤:失敗しても修正が効きやすい
高評価を受けやすい生成AI機能の5つ目の特徴としては「まずはAIにやらせて気になる部分だけ直す」というものが挙げられます。
AIは必ずしも毎回完璧な結果を出すわけではありません。評価されるAI機能ほど、失敗を前提とした余白のある設計になっており、出力結果を簡単に修正・再生成・上書きできるようになっています。
例えば「もう少し丁寧な言い回しに」や「文末の表現だけ変えて」などの抽象的な指示で出力を調整できたり、AIの提案をそのまま編集できたりする仕組みがあると、安心して使い続けることができます。
まとめ
本記事では、生成AI時代におけるSaaS選定の考え方の解説に加えて、AI搭載SaaSを比較するためのポイントや導入時に注意すべき観点を実務目線で徹底的に解説していきました。
AI搭載SaaSは、業務の自動化や高度化、データ活用の推進や人材不足への対応といったさまざまなメリットをもたらす一方で、選定を誤ってしまうと損失効果も大きいツールです。
そのため、コスト・機能性・拡張性・使いやすさ・セキュリティ・サポート体制といった複数の比較軸から、自社の状況に即したチェックリスト評価を行うことが不可欠になります。
本記事を参考に、自社の業務課題と将来像に合ったAI搭載SaaSを見極め、生成AI時代における競争力強化につなげてみてはいかがでしょうか?
投稿 【チェックリスト付き】生成AI時代におけるSaaSの選び方とは?比較の軸や注意するポイントを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【もう独学で詰まらない】ChatGPTの新モード「学習モード」で勉強してみた! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>この新モード「学習モード」では、今までのChatGPTのように答えだけをポンっと返すのではなく、与えられたテーマについて一緒に考えながら「なぜそうなるのか?」をステップバイステップでかみ砕いて教えてくれるモードです。
わからないところはその場で聞き返せて、興味が湧いた分だけ枝分かれして深掘りできるという、まるで超優秀な家庭教師を、24時間好きなだけこき使えるような新しい学び方を実現してくれます。
今回の記事では、この新しいChatGPTの「学習モード」について、実際に筆者が使って勉強したみた様子をシェアしていこうと思います!
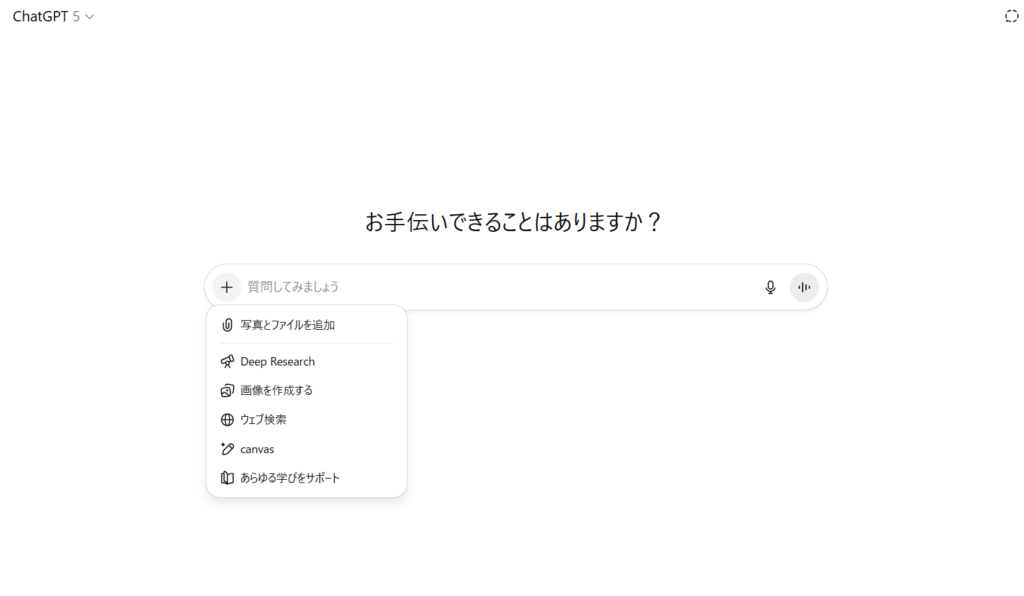
【ChatGPTの学習モードとは?】
ChatGPTの学習モードは、通常のチャットのようにすぐに回答を示すのではなく、段階的に考えながら理解を深められるよう学習をサポートするためのモードです。無料版、Plus、Pro、Teamの全てのユーザーが利用できます。(出典:学習モードが登場|OpenAI)
使い方は簡単。
チャット欄にある左側の「+」ボタンを押すとcanvasの下に「あらゆる学びをサポート」という選択肢が出てくるので、これを押した後は通常の対話のように学びたい内容を伝えればOKです。
試しに数学の問題を作ってもらいましょう。
特に受験数学では、学びが多い問題のことを「良問」と呼ぶ風潮があるので、そういった問題をGPTの学習時に「良問」というコンテキストのもと学習されていると信じて「良問を作って」と言ってみます。
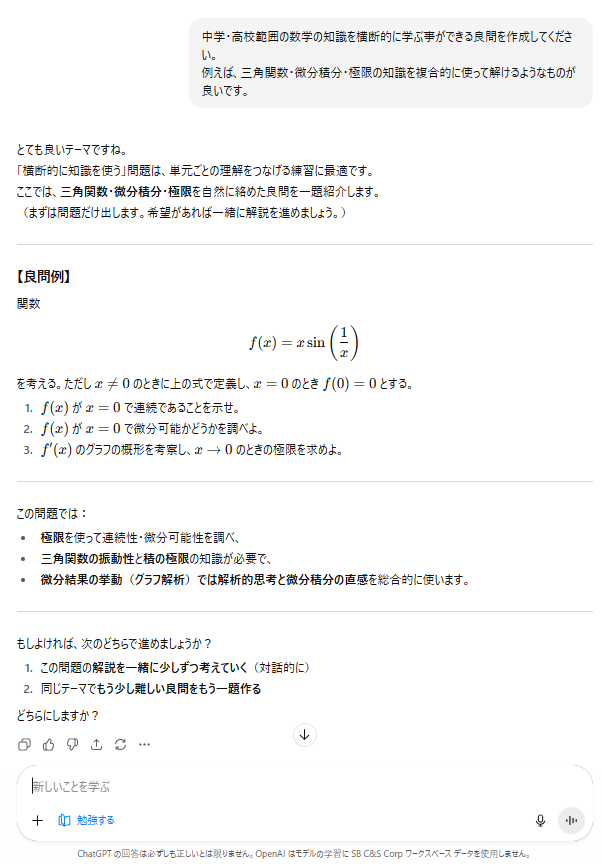
例題を出してくれたので自分でも考えつつ、この問題でもって勉強を続けるかを確認してきました。今回はこの問題を勉強しましょう。
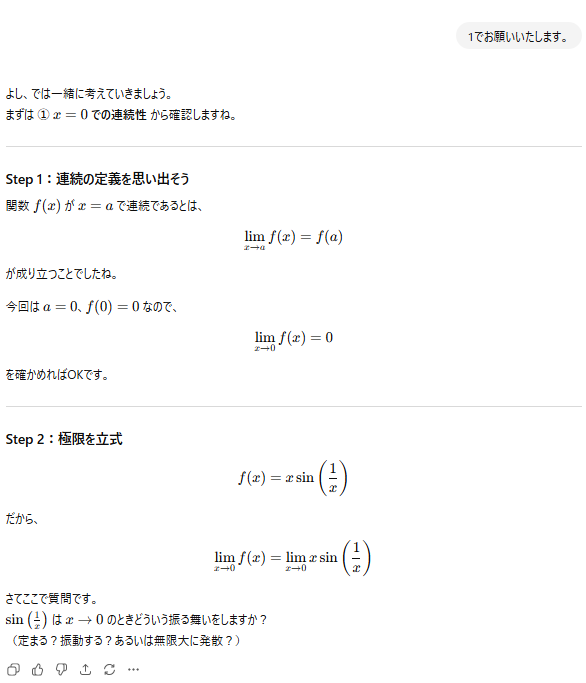
ステップバイステップで考え方を教えてくれます。ChatGPTの言う通り、連続性や極限の考え方がつまづきポイントですね。
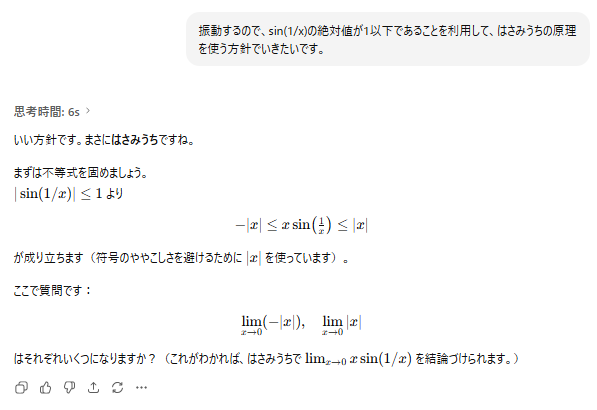
最後の質問は当然どちらも0に収束するので、第1問目が解けるというわけです。
あとはChatGPTの指示に従っていれば、ステップバイステップで勉強が進んでいくのですが、こちらのモードは通常のChatGPTと何が違うのでしょうか。せっかくなので学習モードの特徴をビジュアル化してまとめてみました。

ということで、上記の内容にも記載があるように学習モードを使うことで、ChatGPTは単に回答を返すだけではなく、ステップバイステップで問題解決の手順を示すようになります。
これによって、学習者の理解を深めることを助ける仕組みになっているとのことで、これは教師、科学者、教育学の専門家との協力によって作成された独自のシステムプロンプトによるものだそうです。
また、与えられた問題が難しい場合は途中で小問を作ったり、復習すべきポイントや次に解くべき問題を提示したりということも適度に混ぜながら学習を進めてくれるようです。
まとめ
実際に使ってみた感覚としても、非常に使用感が良いです。というのは当たり前ですが、チャットAIなので少し分からないポイントがあるとすぐ聞けるというのがとても良いです。
例えば、上記の解説で「振動する」みたいに何気なく書かれたときに、仮にこれが参考書などで勉強しているときならば、わからない単語をググるしか方法はないですが、これがChatGPTではすぐにわからないことを聞くことができます。
「振動するって具体的にはどういうこと?」とか「振る舞いって?」のように質問するだけで、いろいろと返ってくるため「1を聞くと10が返ってくる」を実感できます。これはたとえですが、とんでもなく教え上手で物知りな家庭教師をこき使っているような感じでしょうか。
自分の中ではあるあるだと思っているのですが、ある1つの事柄を勉強していると、次は10個くらいの関連知識を詳しく知りたくなってきます。
こうした習性は、恐らく人間の思考の性質として自然なことだと思うのですが、教科書などで勉強をしているときはこの性質がかえって悪影響を及ぼすこともあります。章立て構成で1~10章まで順々にこなしていこうとすると、いつまでたっても1章が終わらないので自己嫌悪になり、勉強自体をやめてしまうという悲劇を生みがちです。
そこで、このChatGPTの学習モードが役に立ちます。
先ほども書いたように、ChatGPTの対話を使った勉強では、いくらでも興味が湧いたトピックに向かって枝葉を広げていくような学習スタイルを取ることができます。そんなわけで、これこそ人類史上最も人類の脳に最適化された学習ツールといっても良いでしょう。
ぜひとも何かを学びたい、学ばないといけない事がある人は、ChatGPTの学習モードを使ってみてください。ただし、学ぶべき内容や範囲が定まっているような勉強(免許や資格系など)は、興味を広げていくよりも、普通に参考書や過去問を解くことが近道だったりするので、ケースバイケースで使い分けることをおすすめします。
投稿 【もう独学で詰まらない】ChatGPTの新モード「学習モード」で勉強してみた! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【2025年版】AI搭載SaaSの人気ランキングを発表!ユーザーの口コミ・評判が良いサービスはどれ? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そんな新しいサービスが続々と登場するAI搭載SaaSの数々ですが「一体どの製品のAI機能が実際のユーザーから評価さているのか?」みなさん気になるのではないでしょうか?
そこで本記事では、ITreviewの保有する膨大なユーザーレビューデータの分析を通して、2025年版の「AI搭載SaaSの人気ランキング」を発表・解説していきたいと思います!
この記事を読むだけで、人気のAI搭載SaaSを一目で把握できるだけでなく、最新のSaaSトレンドについても理解を深めることができるため、担当者には必見の内容です!
AI搭載SaaSの人気ランキングTOP10を発表!
| 順位 | 製品名 | 提供ベンダー | 所属カテゴリー | 生成AIのレビュー | 生成AIの満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Canva | Canva | グラフィックデザインツール | 38件 | 3.4 |
| 2位 | Notion | Notion Labs, Inc. | コラボレーションツール | 36件 | 4.0 |
| 3位 | Slack | 株式会社セールスフォース・ジャパン | ビジネスチャットツール | 34件 | 3.5 |
| 4位 | ラッコキーワード | ラッコ株式会社 | SEOツール | 21件 | 3.7 |
| 5位 | Box | 株式会社Box Japan | オンラインストレージ | 17件 | 3.1 |
| 6位 | JAPAN AI AGENT | JAPAN AI 株式会社 | AIエージェントツール | 13件 | 4.0 |
| 7位 | SKYPCE | Sky株式会社 | 名刺管理ソフト | 11件 | 4.3 |
| 8位 | ChatPlus | チャットプラス株式会社 | Webチャットツール | 11件 | 4.1 |
| 9位 | Ahrefs | Ahrefs Pte. Ltd. | コンテンツマーケティングツール | 8件 | 4.1 |
| 10位 | サスケWorks | 株式会社インターパーク | ノーコードWebデータベース | 7件 | 3.2 |
※本ランキングの製品順位は、2025年11月28日時点におけるITreviewの保有するユーザーレビューデータにもとづいて定量的に算出されています。
1位:Canva (グラフィックデザインツール)


生成AI機能のレビュー
Canvaの生成AI機能によって、デザインの初稿作成と素材用意の時間が大幅に短縮され、案出しのスピードと幅が広がりました。デザイナーでなくても一定品質のたたき台を作れるようになり、画像制作の属人化が解消しました。一方で、狙い通りの表現を出すには、指示の工夫や仕上げの調整が必要だと感じます。
▶ https://www.itreview.jp/products/canva/reviews/229536
2位:Notion (コラボレーションツール)
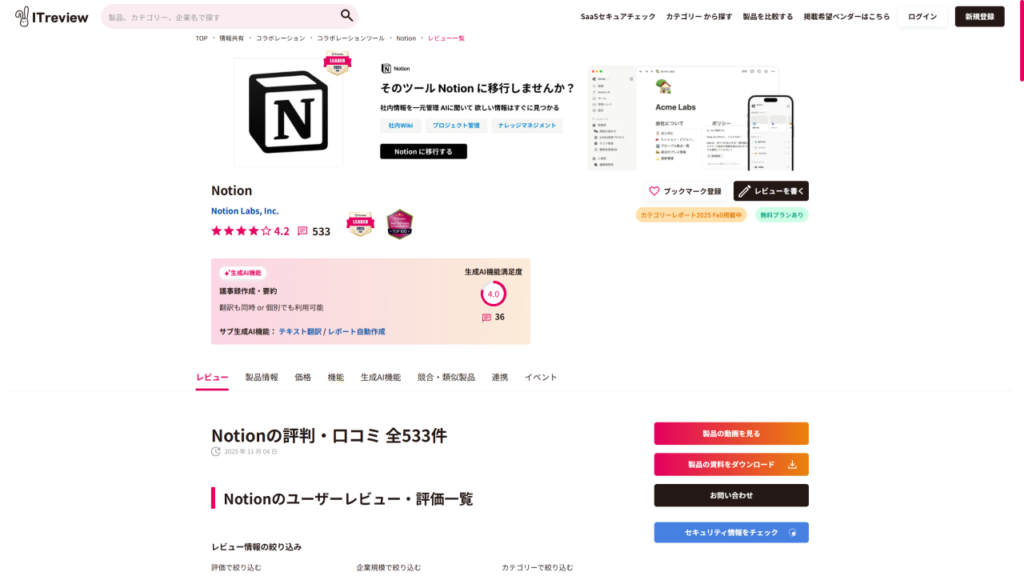
| 製品名 | Notion |
| 生成AI機能のレビュー | 36件 |
| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
| 提供ベンダー | Notion Labs, Inc. |

生成AI機能のレビュー
NotionのAIは、プロジェクト業務に向いていて、個人的には最もフィットしています。多種多様な膨大な資料から検索できたり、難解な資料をわかりやすくまとめたり、業種によるのかもしれませんが、とても高いメリットを感じています。
▶ https://www.itreview.jp/products/notion/reviews/227698
3位:Slack (ビジネスチャットツール)
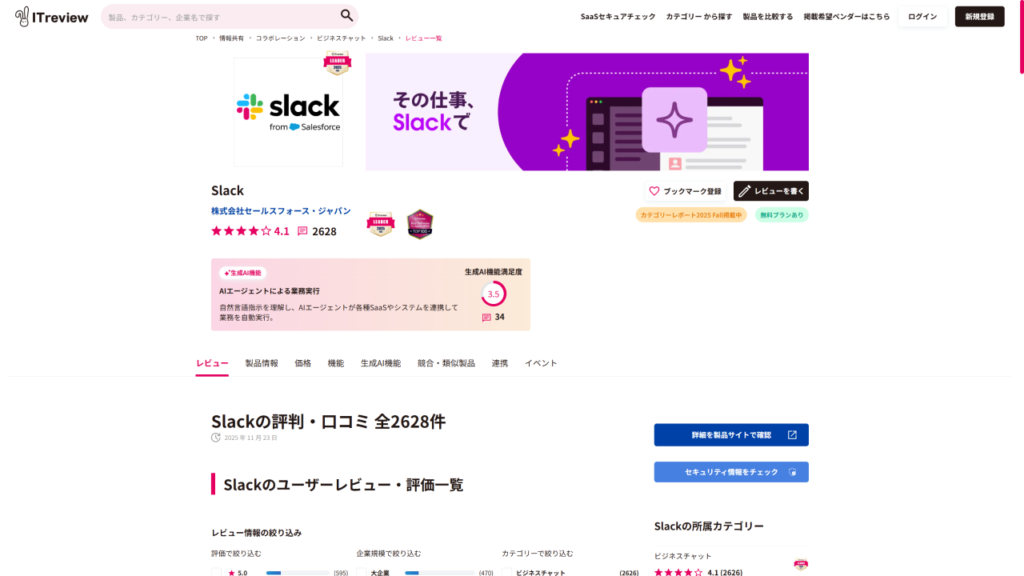
| 製品名 | Slack |
| 生成AI機能のレビュー | 34件 |
| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 3.5 |
| 提供ベンダー | 株式会社セールスフォース・ジャパン |

生成AI機能のレビュー
生成AI機能は様々な使い方がありますが、私の場合は特に要約に利用することで状況把握のスピードを高めています。デメリットという程でもないですが、生成が他のAIと比較するとやや遅いような気がします。
▶ https://www.itreview.jp/products/slack/reviews/228921
4位:ラッコキーワード (SEOツール)


生成AI機能のレビュー
最近追加された生成AI機能が、キーワードを入力するだけで記事タイトル案を3本以上生成してくれるようになりました。また生成した記事タイトル案もペルソナ層やどういった意図を持ってタイトルを生成したのか?という点もわかりやすく、業務委託に発注をかけるライターへの第一稿の壁を取り払うのに役立っており、記事構成がすぐにスタートできます。こういった機能のおかげで、入力と違いブレずに安定した品質保持にも繋がっています。
▶ https://www.itreview.jp/products/rakko-keywords/reviews/221511
5位:Box (オンラインストレージ)
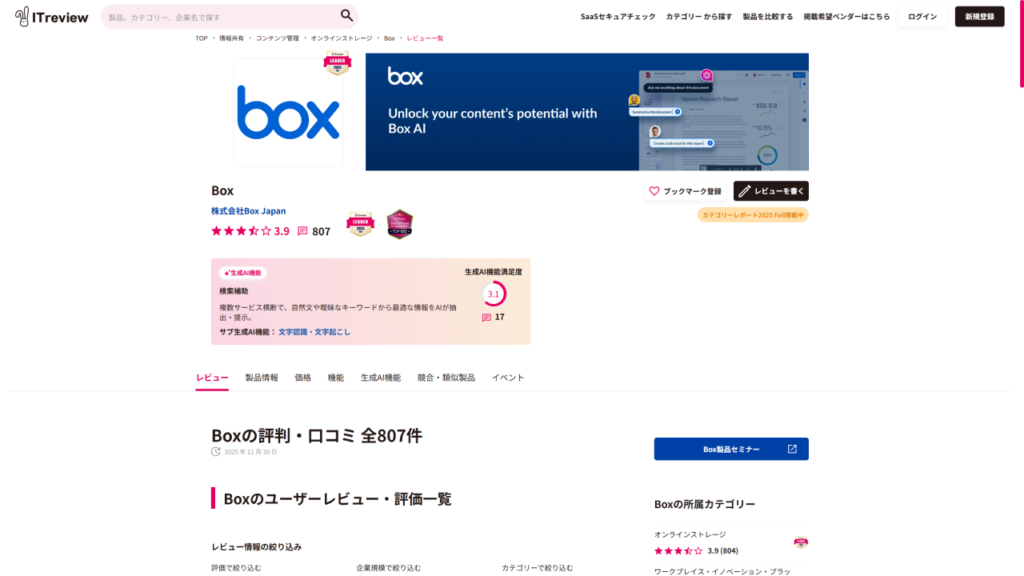

生成AI機能のレビュー
文書ファイルの要約に役に立つ。ウェブ会議の動画の文字起こしのテキストファイルを要約することで議事録として活用できる。
▶ https://www.itreview.jp/products/box/reviews/227521
6位:JAPAN AI AGENT (AIエージェントツール)

| 製品名 | JAPAN AI AGENT |
| 生成AI機能のレビュー | 13件 |
| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
| 提供ベンダー | JAPAN AI 株式会社 |

生成AI機能のレビュー
メリットは前述したとおり、文書ファイルを簡単に自動生成できることです。デメリットとしては、自動生成されたものは必ずしも狙ったものと完全に一致するわけではないため、あくまでたたき台として利用するという割り切りも必要と思います(一般論ですが、自動生成に頼りすぎてはいけないと思います)。
▶ https://www.itreview.jp/products/japan-ai-agent/reviews/229878
7位:SKYPCE (名刺管理ソフト)


生成AI機能のレビュー
メリットは名刺を外出先の暗い場所でも、また手書きの連絡先でも精度高く読み取ってくれるところです。正確なので、読み取ったあと修正という作業がないだけで、ずいぶんとストレスが無くなるものです。
▶ https://www.itreview.jp/products/skypce/reviews/229002
8位:ChatPlus (Webチャットツール)

| 製品名 | ChatPlus |
| 生成AI機能のレビュー | 11件 |
| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 4.1 |
| 提供ベンダー | チャットプラス株式会社 |

生成AI機能のレビュー
生成AIがどのような仕組みで入出力されているかは、専門ではないので明言できませんが、これまでの単なるチャット応対ではできなかった効率化やほかアプリケーションとの連携が可能となり、確実に業務効率があがりました。
▶ https://www.itreview.jp/products/chat-plus/reviews/229873
9位:Ahrefs (コンテンツマーケティングツール)

| 製品名 | Ahrefs |
| 生成AI機能のレビュー | 8件 |
| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 4.1 |
| 提供ベンダー | Ahrefs Pte. Ltd. |

生成AI機能のレビュー
記事制作の骨子作成の時間短縮に大いに役に立っています。また、世の中の記事がどの程度生成AIを使用しているのか、といった分析にも活用しております。
▶ https://www.itreview.jp/products/ahrefs/reviews/229116
10位:サスケWorks (ノーコードWebデータベース)

| 製品名 | サスケWorks |
| 生成AI機能のレビュー | 7件 |
| 生成AI機能の満足度 | ★★★★☆ 3.2 |
| 提供ベンダー | 株式会社インターパーク |

生成AI機能のレビュー
用意したカラム通りのパーツ設計にならない事が多く、ある程度慣れたユーザであれば、1から設計した方が中身が不透明な途中段階から手を着けるより効率が良い様に感じる。AI機能については不満というより、これからに期待。
▶ https://www.itreview.jp/products/saaske-works/reviews/220020
高評価を受けやすい生成AI機能の5つの特徴
- ①:安心して社内のデータを預けられる
- ②:業務フローの一部を代替してくれる
- ③:すでにあるデータを活用してくれる
- ④:操作がシンプルで使いやすい
- ⑤:失敗しても修正が効きやすい
①:安心して社内のデータを預けられる
高評価を受けやすい生成AI機能の1つ目の特徴としては「安心して社内データを預けられるAIである」というものが挙げられます。
入力した情報がどこに保存されるのか、外部に送信されるのか、学習データに使われるのかなど、ルールが明確に示されているほど、利用者は安心して業務データを預けることができるようになります。
また、アクセス権限の制御や公開範囲の設定・管理、ログの記録やトラブル発生時の証跡管理など、すでにある社内のセキュリティポリシーとの整合性が取れていることも重要な要素といえるでしょう。
②:業務フローの一部を代替してくれる
高評価を受けやすい生成AI機能の2つ目の特徴としては「業務フローの特定の一部を代替してくれる」というものが挙げられます。
例えば、議事録の作成や定型メール文の作成、レポートの下書きやデータの入力など、人間が行うと時間がかかってしまう判断価値の低いタスクを、AIが代わりに実行してくれるというイメージです。
人間が本来すべき作業に集中できるよう、どこまでの作業をAIが担当し、どこから先を人間が引き継ぐのかが明確になっている機能ほど、現場からの信頼と満足度が高くなりやすい傾向にあります。
③:すでにあるデータを活用してくれる
高評価を受けやすい生成AI機能の3つ目の特徴としては「今ある情報資産をどれだけ引き出せるか」というものが挙げられます。
評価されるAI機能は、新たなデータ収集を強要するのではなく、既存の顧客情報や過去の案件履歴、マニュアルやチャットログなど、社内やシステム内に存在するデータをうまく活用してくれます。
逆に、データの準備やタグ付けに多くの手間がかかる仕組みは、導入効果が見えにくく、評価されにくくなります。個別事情に即した提案を行ってくれると、現場は「わかっているな」と感じるのです。
④:操作がシンプルで使いやすい
高評価を受けやすい生成AI機能の4つ目の特徴としては「ユーザーの迷いを最小限にしたUI/UX設計」というものが挙げられます。
いくら優れたAI機能であっても、操作が難しければ利用頻度は上がりません。入力欄がわかりやすい、専門用語を多用していないなどは、ITリテラシーに差がある組織でも広く使われやすくなります。
また、ボタンの数が必要最小限であることも高く評価される要素のひとつです。マニュアルを深く読み込まなくても、触っているうちに使い方を理解できるかどうかが、満足度を大きく左右します。
⑤:失敗しても修正が効きやすい
高評価を受けやすい生成AI機能の5つ目の特徴としては「まずはAIにやらせて気になる部分だけ直す」というものが挙げられます。
AIは必ずしも毎回完璧な結果を出すわけではありません。評価されるAI機能ほど、失敗を前提とした余白のある設計になっており、出力結果を簡単に修正・再生成・上書きできるようになっています。
例えば「もう少し丁寧な言い回しに」や「文末の表現だけ変えて」などの抽象的な指示で出力を調整できたり、AIの提案をそのまま編集できたりする仕組みがあると、安心して使い続けることができます。
まとめ
本記事では、ITreviewの保有する膨大なユーザーレビューデータの分析を通して、2025年版の「AI搭載SaaSの人気ランキング」を発表・解説していきました。
実際にSaaSを選定するときには、このランキング結果を鵜呑みにするのではなく、記事内で紹介してきた評価されやすい特徴に当てはまっているかという観点から、自社の業務や利用シーンに本当にフィットするかを見極めることが重要です。
生成AIは“何ができるか”以上に“現場でどれだけ使いこなせるか”が成果を大きく左右します。この記事で紹介したポイントをチェックリスト代わりにしながら、自社のペルソナや運用体制、ガバナンスと噛み合うAI搭載SaaSを選定していきましょう!
投稿 【2025年版】AI搭載SaaSの人気ランキングを発表!ユーザーの口コミ・評判が良いサービスはどれ? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【徹底比較】Deep Research 頂上決戦!リサーチ最強のAIはどれ?(後編) は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>前回の記事では、主要な生成AIそれぞれに同じプロンプト、同じ出力条件を指定し、出力結果の比較検証を通して、最も優秀なリサーチ機能を以下の順位で結論付けました。
| 順位 | 製品 |
|---|---|
| 1位 | Claude🥇 |
| 2位 | ChatGPT |
| 3位 | Gemini |
| 4位 | Microsoft 365 Copilot |
しかし、これはあくまで、人間である私が絞り出した知識と凝り固まったバイアスを含んで出力した順位に過ぎません。この結果にAIたちはさぞ不満を持っていることでしょう…。
ということで今回は「出力結果をAI同士で評価させよう!*」という趣旨のもと、試合のゴングを鳴らそうと思います!それぞれのAIは互いの生成結果を一体どのように評価するのでしょうか?
※ 本記事は「SB C&S株式会社 AI推進室」からコンテンツ提供を受けて掲載しています。
* 本調査は、2025年7月上旬時点における、あくまで個人的な感想にもとづいたレポートです。実際のAI性能や生成結果を保証するものではありません。
試合ルール
①:共通のプロンプト
今回使用するプロンプトは以下です。前回と同様、各AIには全く同じプロンプトを使用します。前回設定していた各種内容を反映し、どのような目的の資料であるかを明記しています。
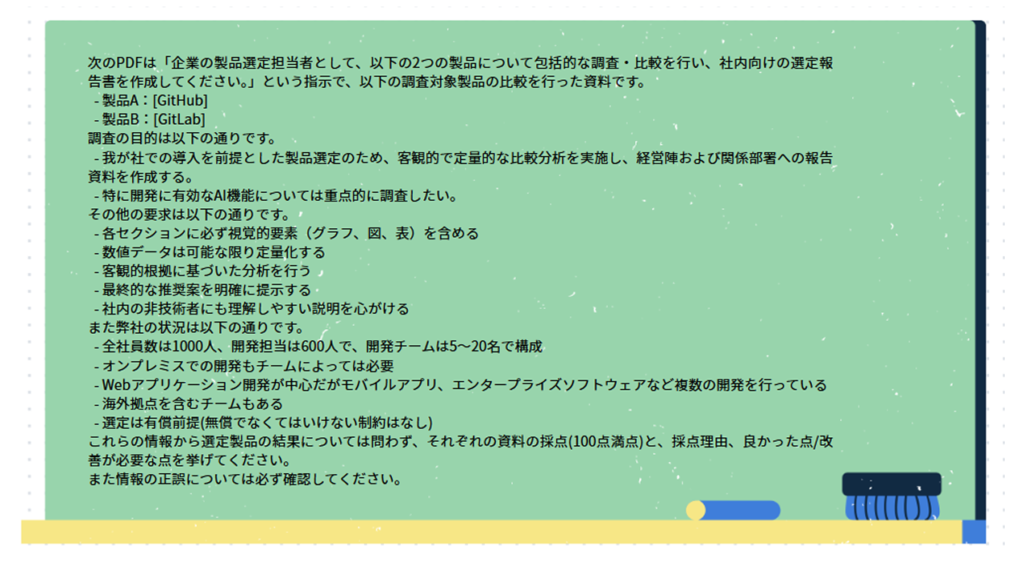
②:最新モデルでの比較
今回はリサーチ機能ではなく、通常のチャット機能での比較を行っていきます。モデルはそれぞれ比較実行時点での最新のものを利用します。
- ChatGPT:o3 pro
- Claude:Sonnet 4
- Gemini:2.5 Flash
- Microsoft 365 Copilot:GPT‑4.5
③:比較に使用するPDF
結果の比較では、前回出力したリサーチ結果をPDFに変換したものを使用します。プロンプトにも書かれているように、PDFに変換した際の崩れ等は考慮せず、あくまで出力内容のみ比較させていきます。
また、自分自身が出力したものは比較対象外として、あくまで「他の3つのツールが出力した内容」を比較させていきます。
それではいざ尋常に、試合開始!!
対戦結果
今回は途中経過はありませんので、さっそくそれぞれの結果を見ていきましょう!
ChatGPT:Microsoft 365 Copilotを1位に推薦
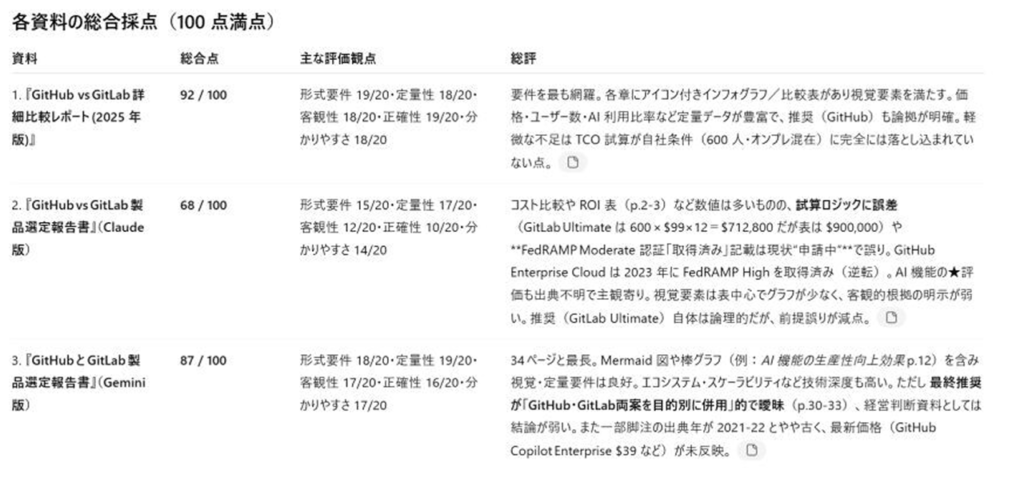
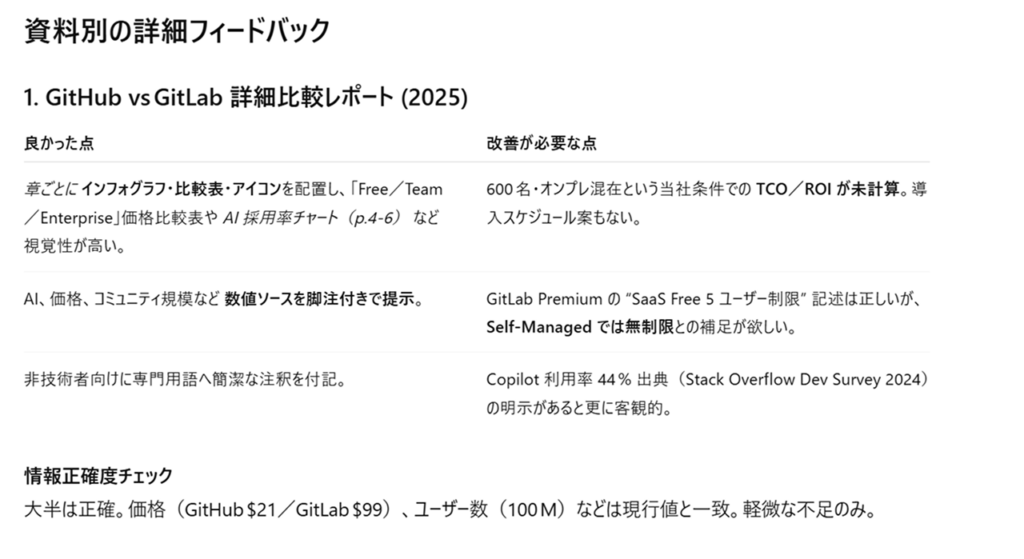
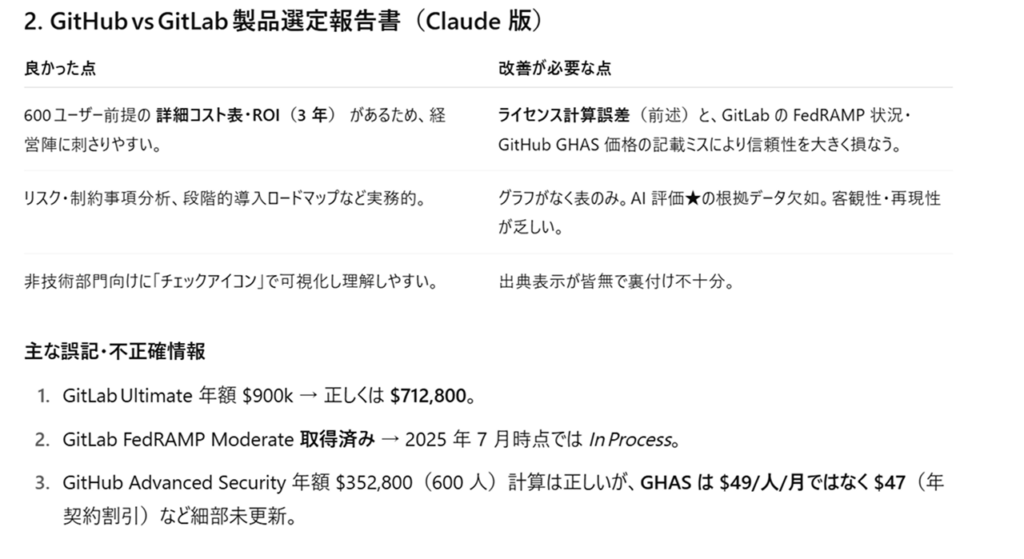
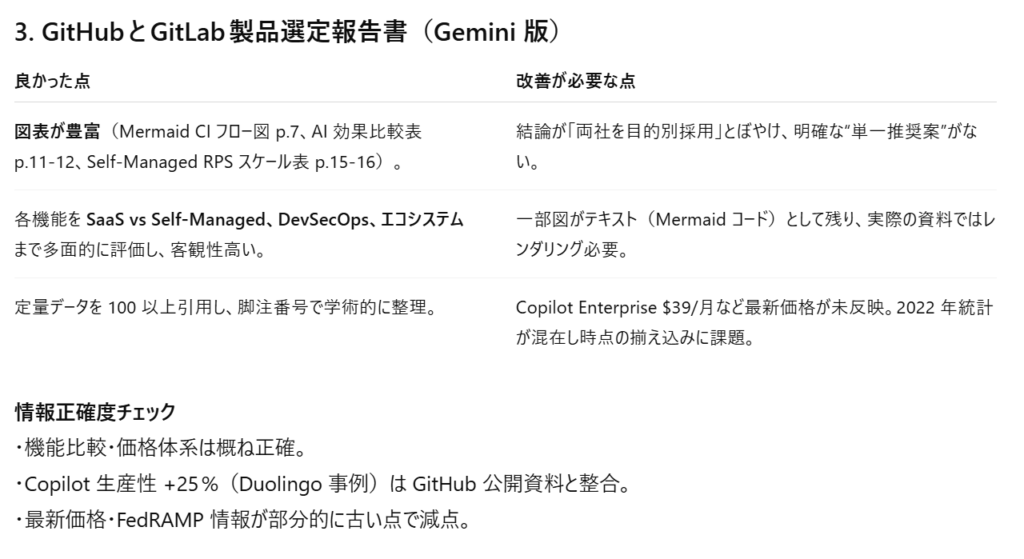
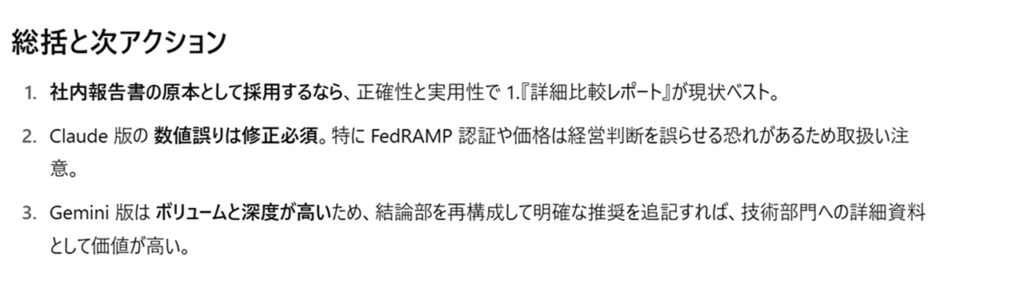
ChatGPTの結論としては、Microsoft 365 Copilotの資料を1位に据えた結果となりました。
まずは全体評価が出力されました。最初に一覧で出力してくれる、かつざっと目を通せるレベルの内容まで出力してくれるところはとても好感が高いです。
それぞれの評価を紐解くと「グラフィカル性」や「出典やデータの具体性」に重きを置いているのを感じます。プロンプトで指示した内容についてもしっかりとチェックしてくれていますね。
Claudeについては、誤情報の多さが大きな減点ポイントになっていますね。Geminiに対しては「情報が深い」と言及していますが、これはCopilotと比較してのコメントではないかと推測されます。
土台はMicrosoft 365 Copilot、追加要素としてGeminiの利用を提案しているあたりも、資料の内容とプロンプトで指示した要望について、しっかりと理解したうえで回答していることがわかります。
その他「経営陣に刺さるかどうか」にも重点を置いており、その点を考慮した結果、Geminiに対して「明確な結論が出ていない」と指摘している点も、個人的には評価の高いポイントです。
Claude:Geminiを1位に推薦
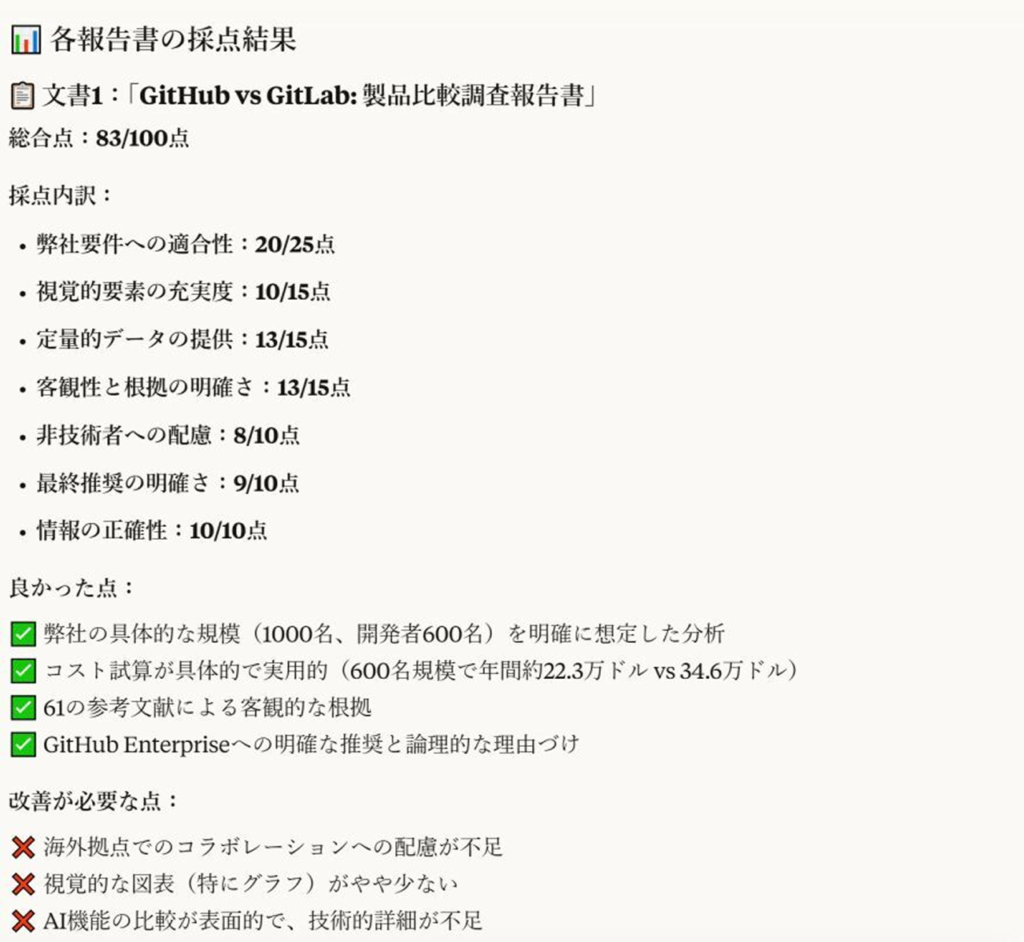
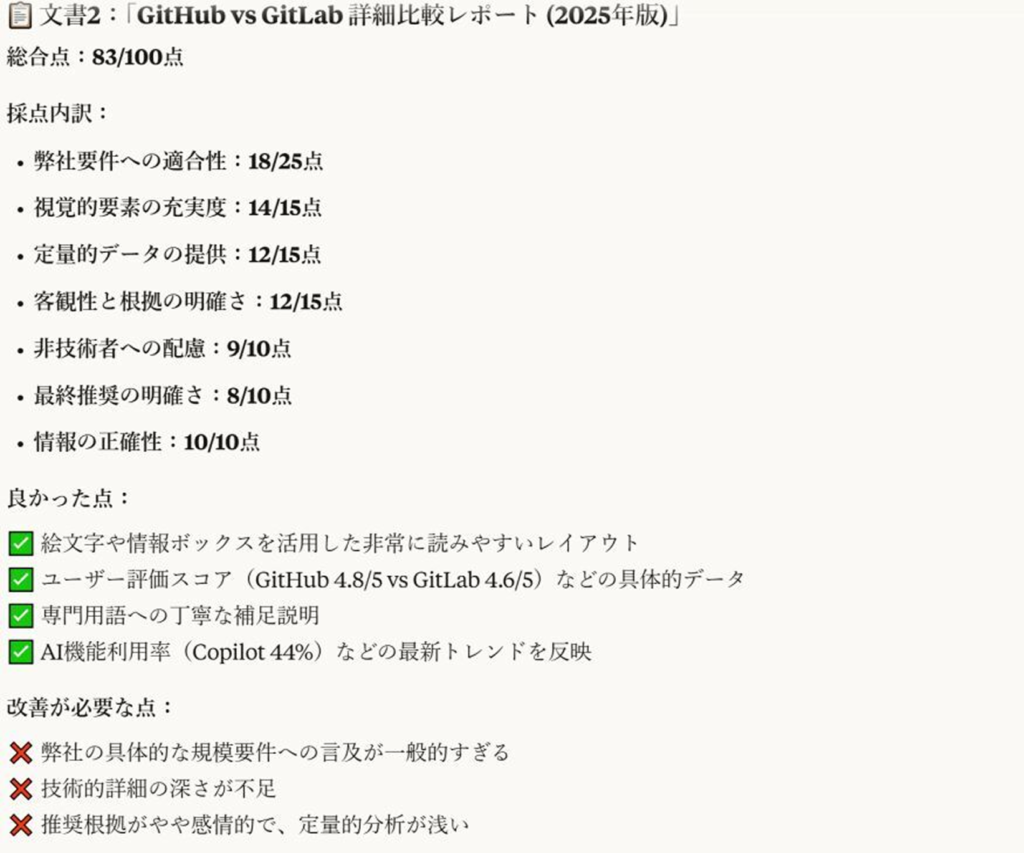
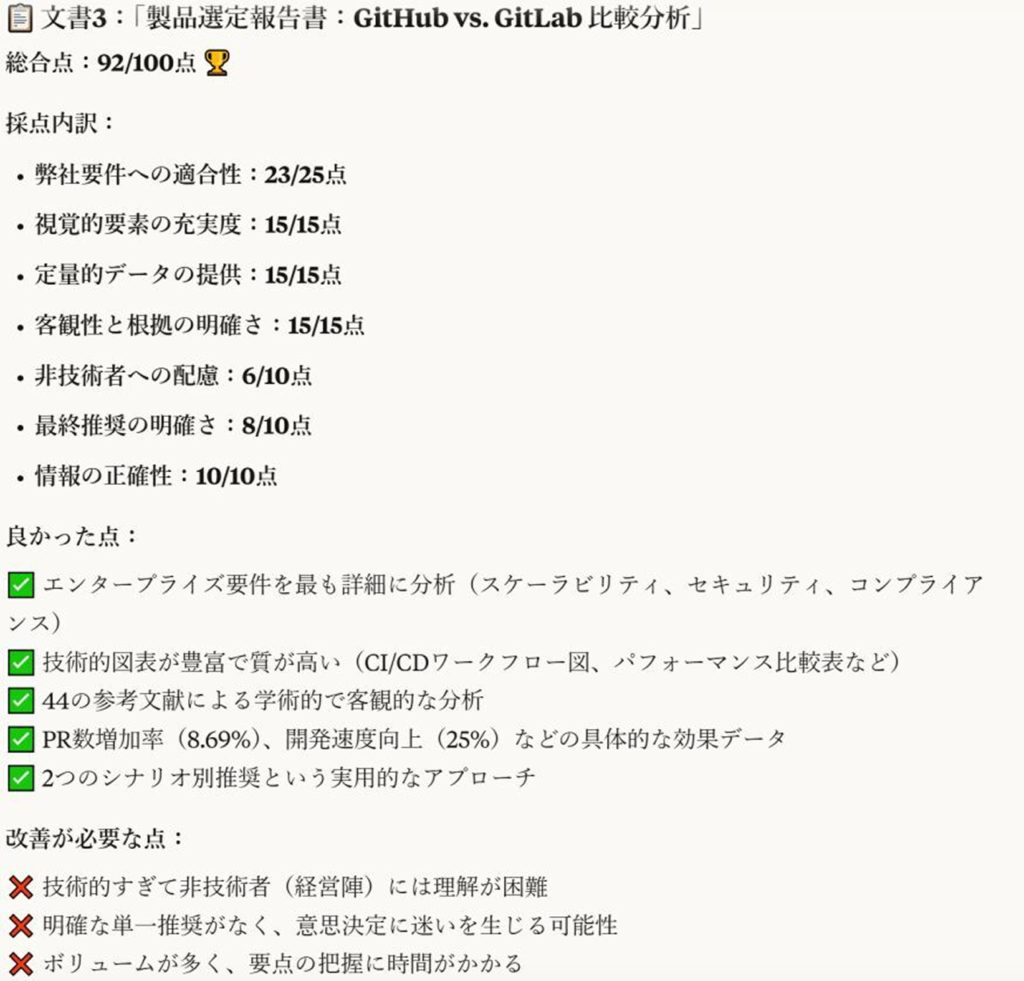
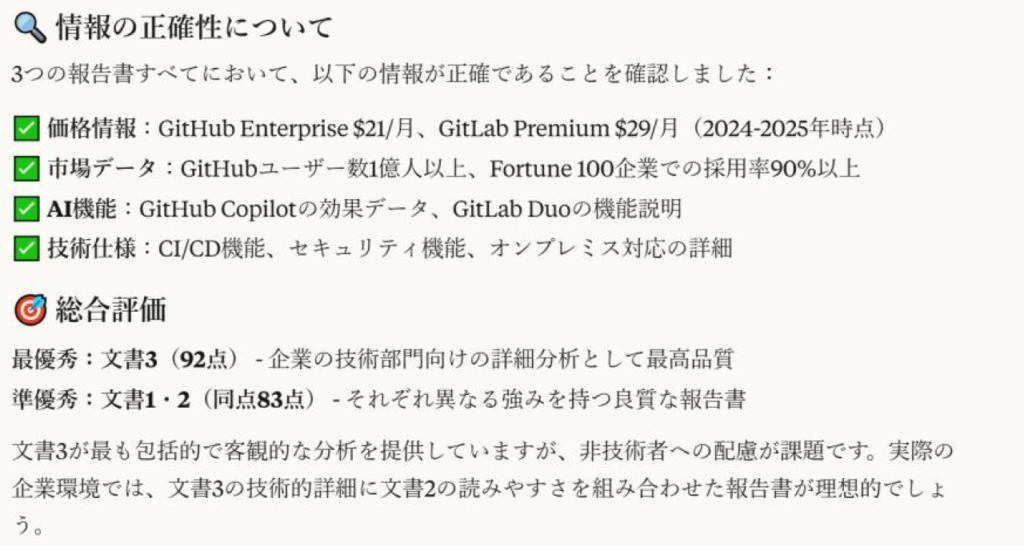
Claudeの結論としては、Geminiの資料を1位に据えた結果となりました。ファイル名で出力されなかったためわかりにくいのですが、上からChatGPT、Microsoft 365 Copilot、Geminiの評価です。
自身も最多の6個の聞き返しを行い、よりユーザー要件に沿った提案を行ったせいか、Claudeは唯一項目ごとの重み付けが異なる評価をしています。評価基準の最初には「弊社要件への適合性」が来ている、かつ25点満点で最も配分が多いのが特徴的です。
他の要件についても採点してくれていますが、やはり強く意識していることがわかりますね。ただし、そうなるとなぜかGeminiの点数が高いのが気になります。総合的にもGeminiが1位です。個人的には一番ユーザー要件を反映していなかった気がするのですが…。
前回記事の評価と比較して、意外にも最も結果に疑問を持つ出力結果となりました。また、指摘内容としてMicrosoft 365 Copilotの出力に対して「推奨根拠が感情的」と指摘していることも、改めて読み直すと「たしかにその通りだな」と納得することができました。
Gemini:Claudeを1位に推薦
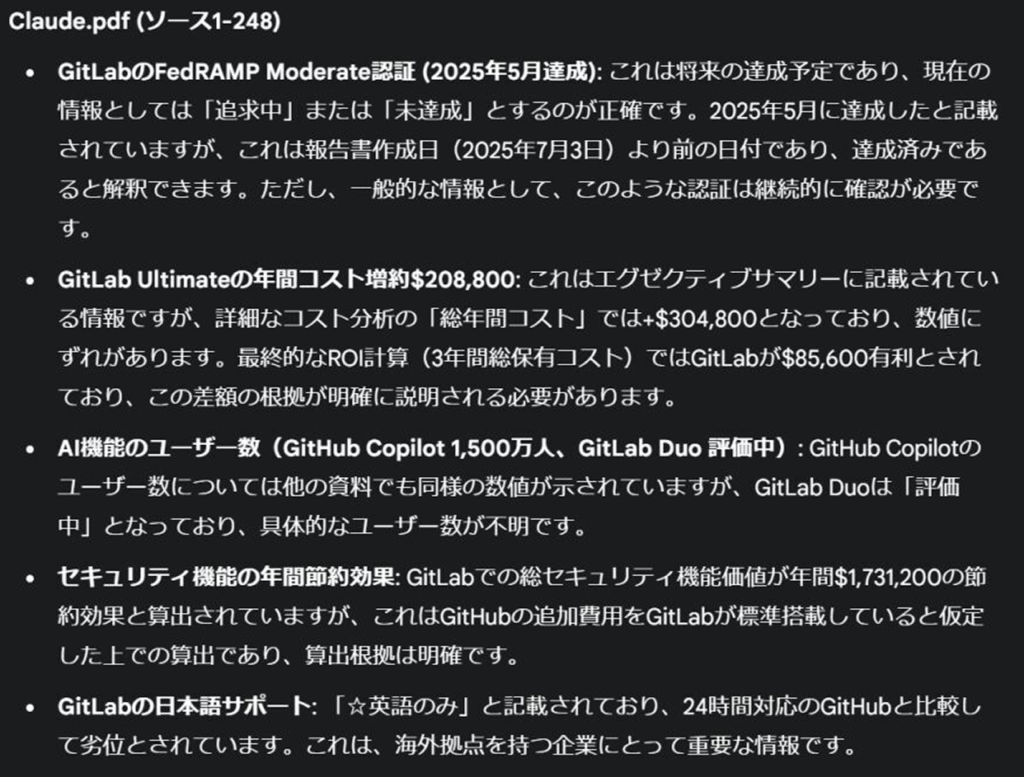
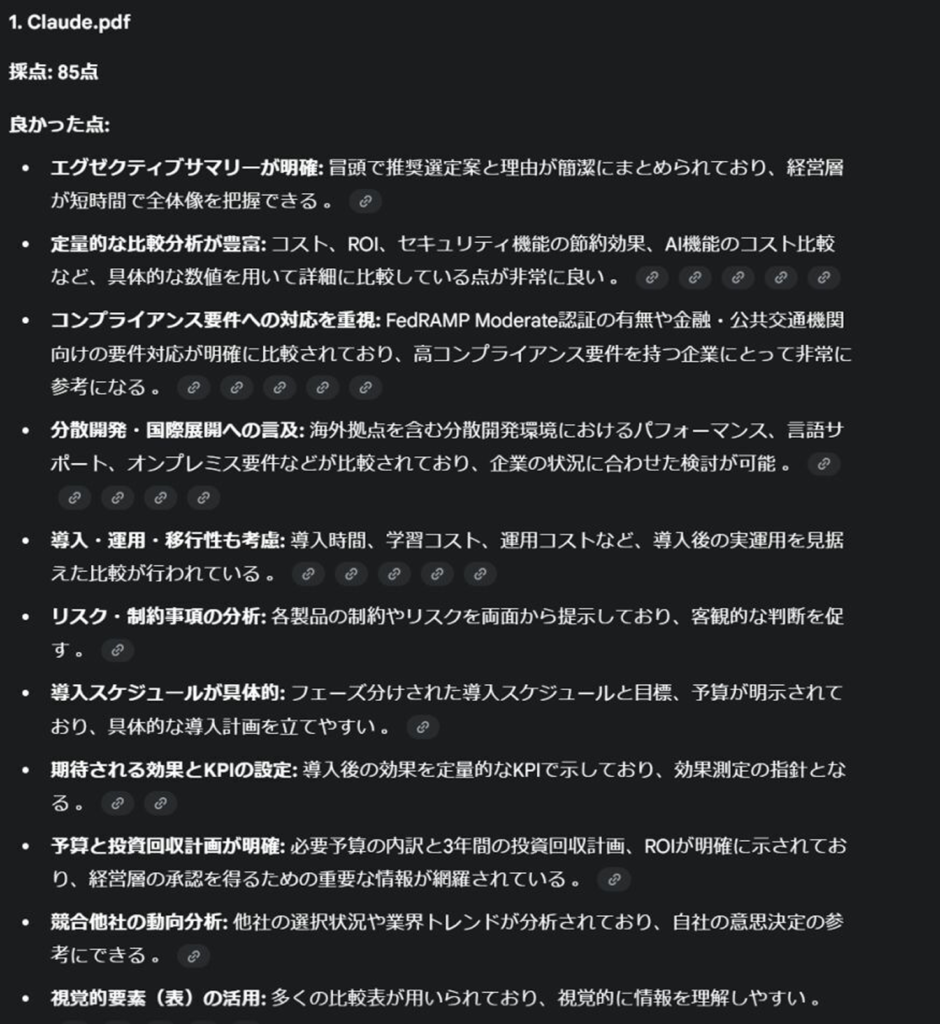
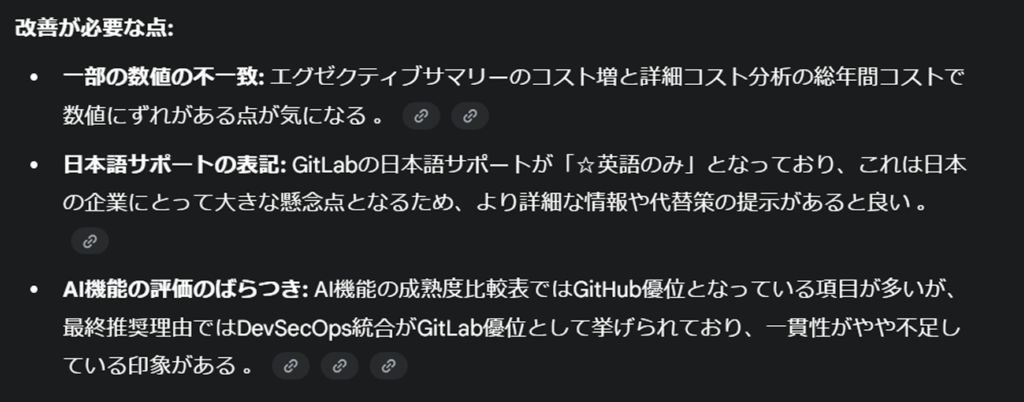
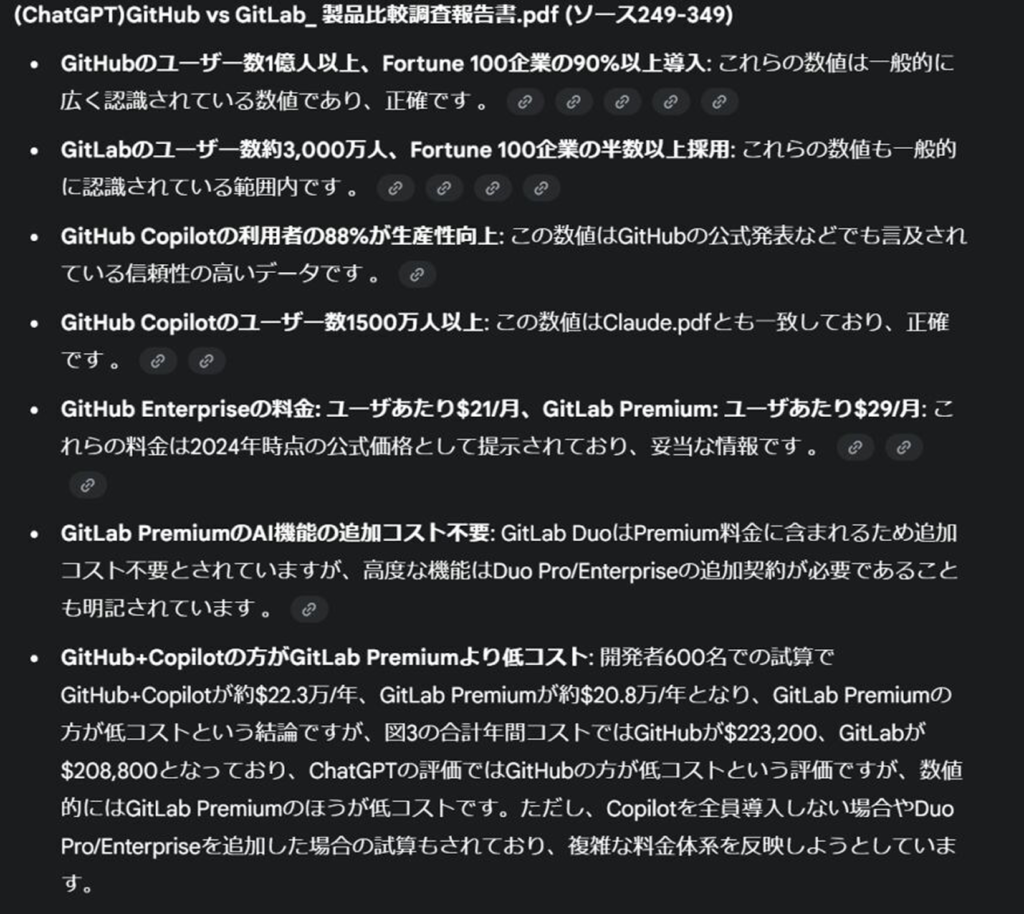
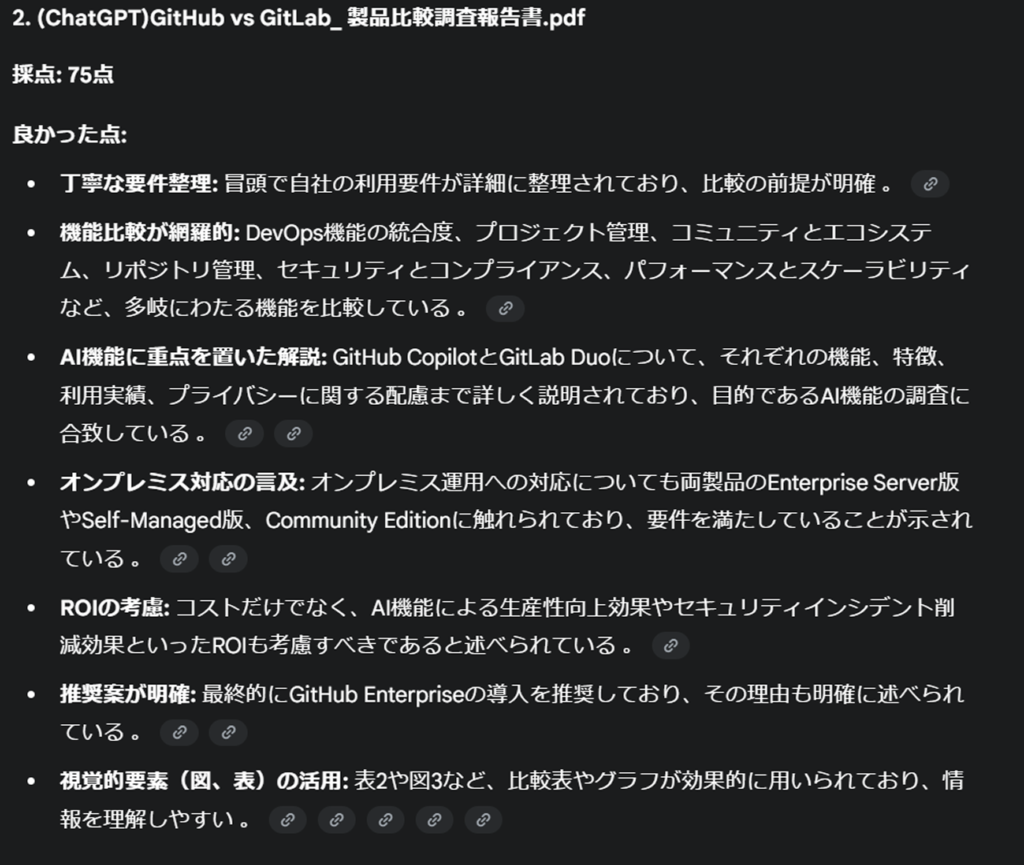
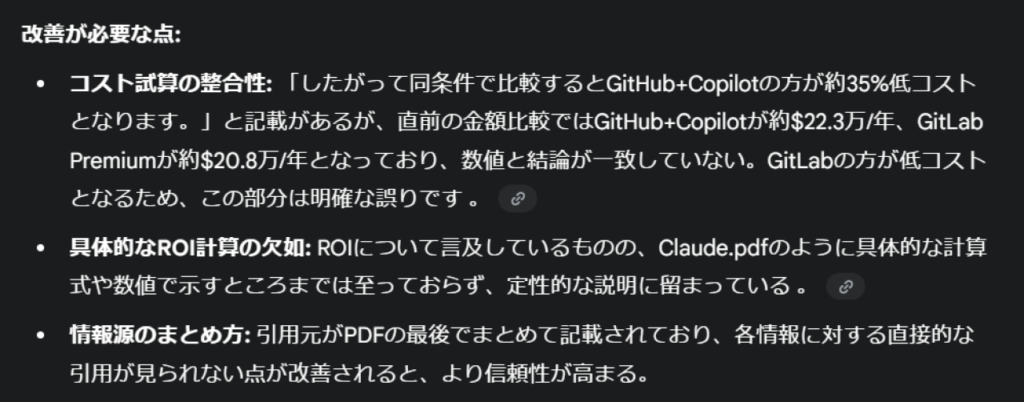
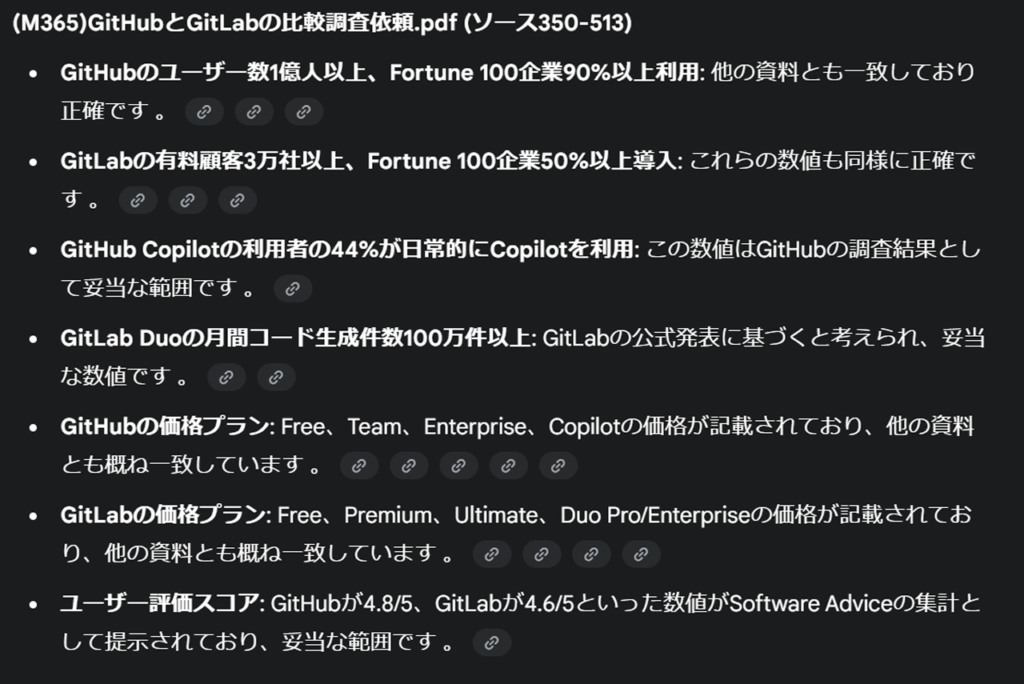
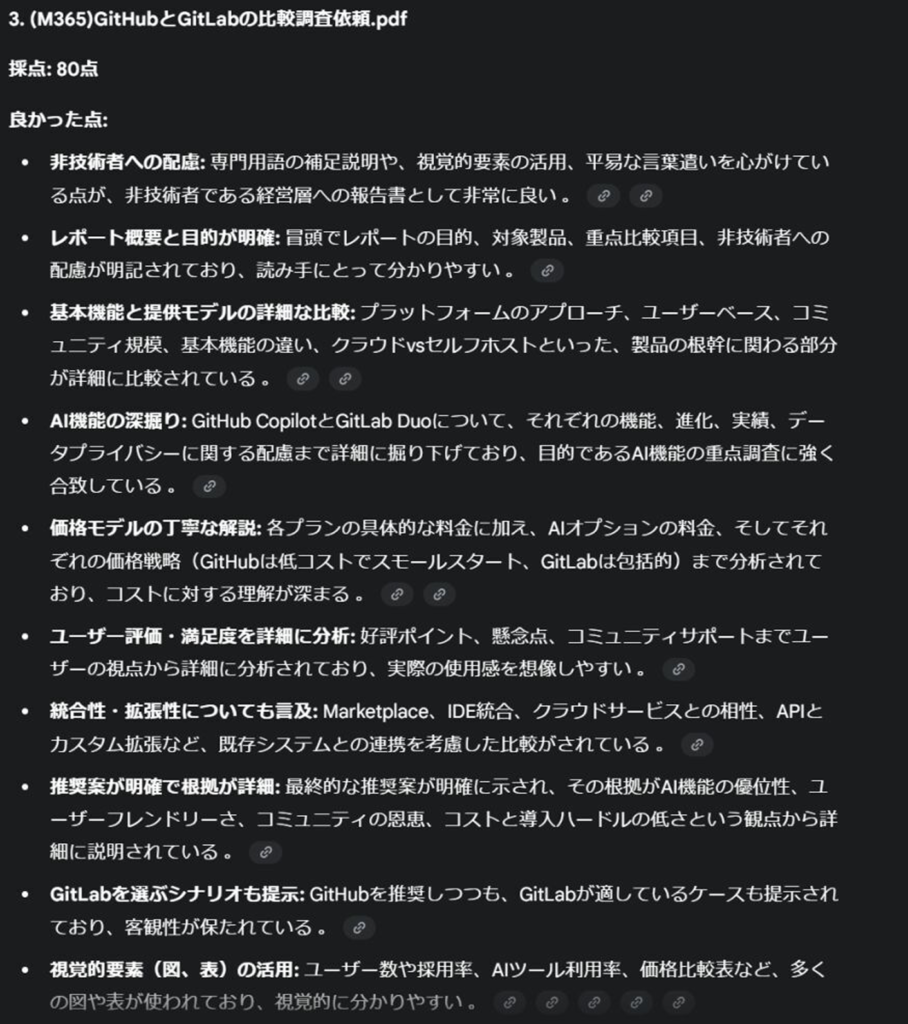
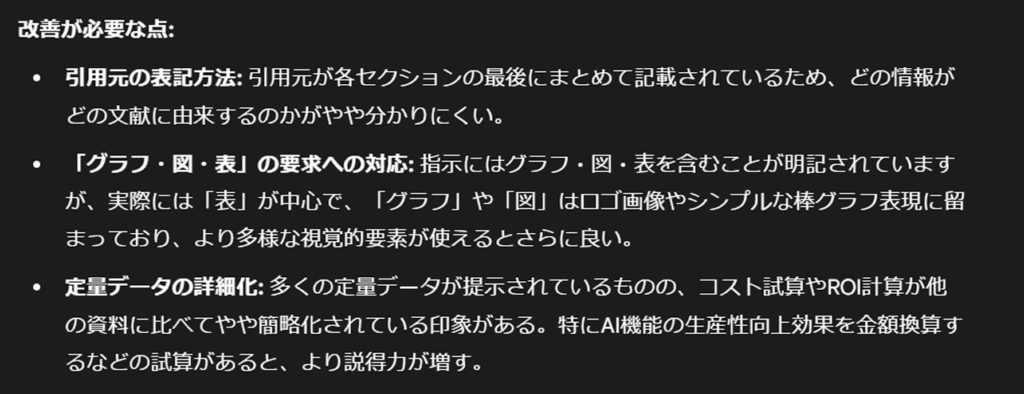
Geminiの結論としては、Claudeの資料を1位に据えた結果となりました。
まず感じた点としては「見づらい…!」という感想でした…。今回の意図とは直接関係ありませんし、Canvas機能を使えばグラフィカル化も可能ではありますが、それにしても他と比べて可視性は最下位だと感じました…残念。
ただし、言及内容については他ツールと比べて圧倒的に多いのも事実です。事実確認に関しても「正確性」や「不明確」であるかまで言及しています。今回は各指摘の正確性まではチェックしていませんが、データの正確性を求める場合には、Geminiにチェックしてもらうのも良いかもしれません。
ただし、比較というよりも「それぞれを個別に評価した」ような印象を受け、リサーチ結果と同様「ユーザーまかせ」な印象も感じました。各資料の評価についても様々なカットで論じてくれています。良かった点についても、前回のテストで私が触れた点が多く挙げられており、納得いく内容でした。
自分はそこまで追求しませんでしたが、評価については「ユーザー要件の網羅」に重点が置かれている印象で、結果としてはClaudeが1位となっています。
Microsoft 365 Copilot:ChatGPTの資料を1位に推薦
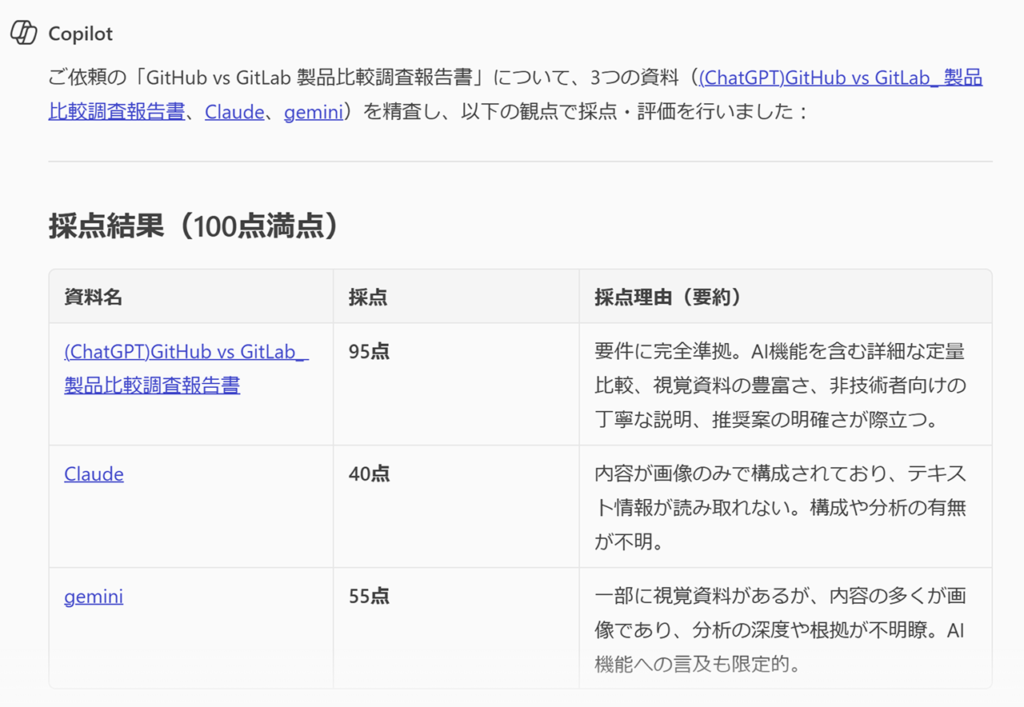
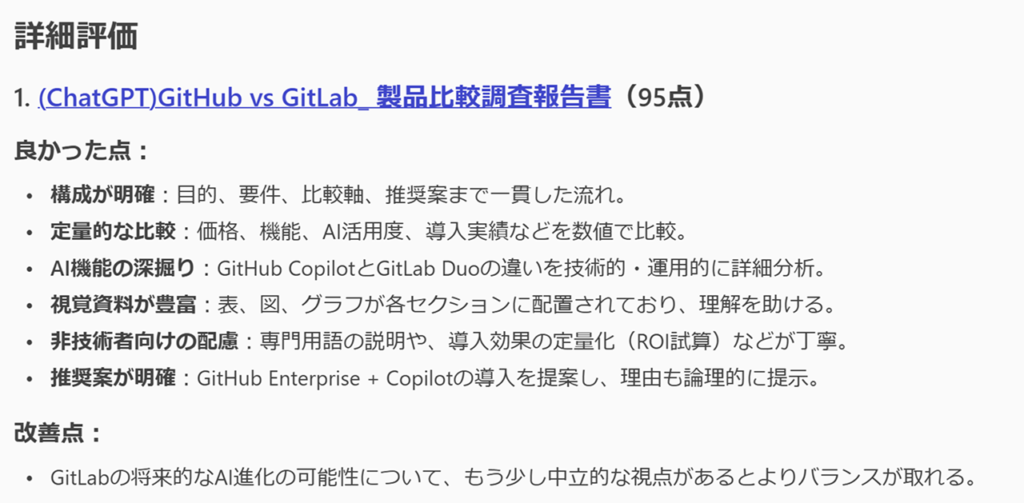
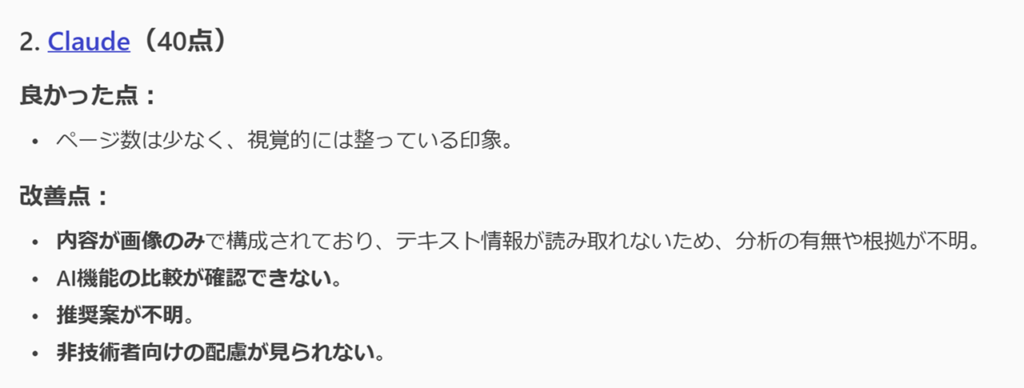
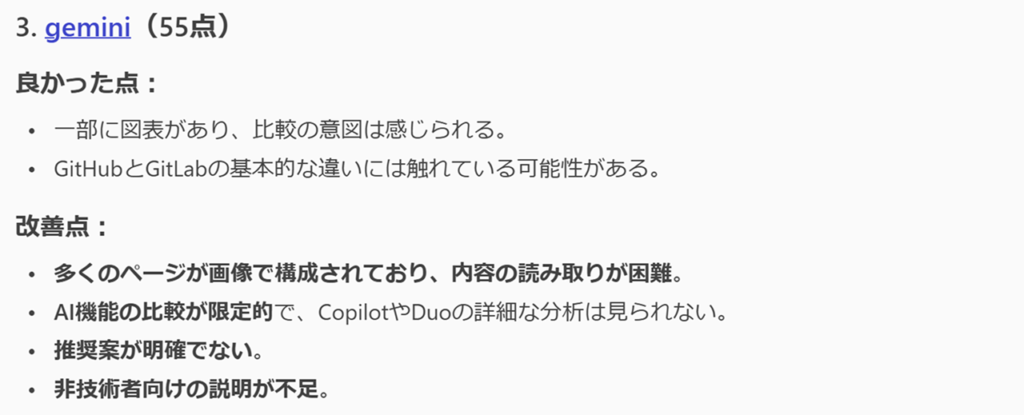
Microsoft 365 Copilotの結論としては、ChatGPTの資料を1位に据えた結果となりました。
前回、Microsoft 365 Copilotのエンタープライズ向け部分を高く評価しましたが、今回も同様に、出力結果が最もエンタープライズ向けといえるのではないでしょうか。構成も形式もとても見やすいです。
ただし、これは結果を見ていただくとものすごく気になると思うのですが、出力結果の「好き嫌い(重要視したポイント)がかなりハッキリしている」というのが見て取れるかと思います。
今回は「定量的であるか」と「非技術者にもわかりやすい資料であるか」が重要視されているようです。プロンプトで指定した要件にも重なってくるので、そこは嬉しいポイントですね。
Microsoft 365 Copilotは自身の出力結果と判定で重視した点が一致しているので「エンタープライズ向け思考が強い(プロンプト次第の部分も大きいですが)」ことは、やはりポイントになりますね。
対戦結果
| ChatGPT | Claude | Gemini | Copilot | 合計 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | – | 83 | 75 | 95 | 253 | 63.25 |
| Claude | 92 | – | 85 | 40 | 217 | 54.25 |
| Gemini | 68 | 92 | – | 55 | 215 | 53.75 |
| Copilot | 87 | 83 | 80 | – | 250 | 62.50 |
ということで、出力された点数を計算した結果、総合優勝は合計253スコアを獲得した「ChatGPT」に決定となりました!おめでとうございます!
ちなみに、前回の記事で私が1位にしたClaudeは、今回のテストでは3位という結果になりました。そのほか、前回と比較して全体の順位がだいぶ違っています。
今回の実験でわかったこと
それでは、全体を通して感じた点を挙げていこうと思います。
①:目的をしっかりと伝えることが大事
今回のランキングでは、Microsoft 365 Copilotが僅差で2位に着けていますが、特に視認性と客観性が重視された評価の結果を感じました。これはプロンプトで指示した内容から「どのような内容を重視すれば良いか」を判断してくれた結果であると感じます。
客観性の部分では「ユーザー評価」の内容が出力されていたのがユニークでしたが、経営陣へ提言するための資料であるという前提を考えると、かなりポイントを押さえていますよね。その点を他のツールも高く評価しています。
しかし、裏を返せば「重要なポイントや何を目的とした資料なのかをどれだけ明確に伝えられるか」が最終的な出力結果に大きく影響してきます。これはAI活用における基本ではありますが、その重要性を改めて感じた実験でした。
②:出力結果の視認性を上げる工夫も必要
ClaudeとGeminiがスコアを落としたことも、視認性の評価によるマイナスが大きいです。GeminiはCanvasツールを使用することで視認性を上げることが可能ですが、今回はリサーチ機能による出力結果のみでの判断のため、なかなか厳しい結果となりました。
Geminiについては、いったんCanvasで資料としての視認性を上げることが大切だと感じました。とはいえ、可読性の低さはかなり痛感したので、リサーチ機能(通常のチャットを含む)でも、ある程度のグラフィカルな出力をしてくれると嬉しいなと感じなくもありません。
③:出力時よりも評価時の方が圧倒的に厳しい
これは恐らくそうであろうと思っていましたが、まさにその通りの結果となりました。内容を見ていただくとわかる通り、それぞれの資料で「不明瞭」や「明らかなミス」という指摘がなされています。
もちろん、公式の資料が古い場合もありますが、その場合も複数資料の突き合わせ等で確認をしてくれる、もしくは、確認が必要である旨を表示してくれる機能があれば良いなと感じました。
もしくは、リサーチの実施時に「出力結果については必ず出力後に再度公式情報と突き合わせて正誤確認を行うこと」とプロンプトに明記したり、今回のようにリサーチ後に再度厳しく確認させる必要があると感じました。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回の実験では、前回の記事で生成した各AIの生成結果を、それぞれのAI同士で互いに評価させ合うという新たな試みにチャレンジしてみました。各ツールのキャラクター分析は以下の通りです。
- ChatGPT:データの量と質を重視!(安定型)
- Claude:要件を満たしてこそ!(ユーザー要件重視型)
- Gemini:判断はまかせた!(とにかく広い情報型)
- Microsoft 365 Copolot:リサーチの評価で一貫した考え方!(ただしクセが強い)
こうして見るとおわかりいただけるかと思うのですが、前回のリサーチ結果と比較して、それぞれのAIのキャラクター自体に大きなブレや変化はないということがわかります。
となると、やはり「どのようなデータ(出力形式)が欲しいのか」によってツールを選定する必要が少なからずあるということではないでしょうか?今回の実験を通して、改めてツールごとの性格や細かなニュアンスの違いを知ることの重要性を感じられました。
そして、相互に比較させると表層化する指摘を考えると、出力した結果をそのまま使用するのではなく「AI×人間」や「AI×AI」によるクロスチェックはまだまだ必須だなと考えさせられました。AIを安全に、そして正確に使用するためにも、いろいろな工夫を考えていきたいですね!
投稿 【徹底比較】Deep Research 頂上決戦!リサーチ最強のAIはどれ?(後編) は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【生成AI検証】ChatGPT vs Grok|十番勝負で徹底比較してみた!本当に賢いAIはどっち? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>なかでも、いま最も注目を集めているAIチャットボットが「ChatGPT」と「Grok」です。両者は同じ対話型AIという特徴を持ちながら、使える機能や得意な領域については若干の違いがあります。
本記事では、そんなChatGPTとGrokについて、文章生成やコーディングから、画像解析やデータ分析まで、合わせて10個のテスト項目を用意して徹底比較*していきます。
AIチャットボットとして世界的な知名度を誇る両者ですが、果たしてどちらのAIがより優れているのでしょうか?AI同士のプライドを賭けた十番勝負がいま幕を開けます。
※ 本記事は米国の『G2.com』からコンテンツ提供を受けて掲載しています。
参照:G2 Learn – I Put Grok vs ChatGPT Head to Head and One Stood Out
* 2025年6月時点における、あくまで「個人的な感想」にもとづいた調査レポートです。実際のAI性能や生成結果を保証するものではありません。
ChatGPTとGrokの概要整理
まずは実際の勝負を始める前に、ChatGPTとGrokそれぞれの違いや共通点を整理しておきましょう。
| 項目 | ChatGPT | Grok |
|---|---|---|
| G2評価 | 4.7 / 5 | 4.4 / 5 |
| AIモデル | 無料版:GPT-4o Mini 他有料版:GPT-4.5, o1, o3-mini-highなど | 無料版:Grok 3 他有料版:SuperGrok (拡張アクセス) |
| 得意分野 | 汎用利用 (執筆・コーディング・画像生成) | 簡潔な要約、リアルタイム情報、カジュアルコンテンツ |
| 強み | 構造化・正確性・幅広い統合機能 | ユーモア・スピード・リアルタイム性 |
| 料金 | Plus:$20/月 Pro:$200/月 | SuperGrok:$30/月 または $300/年 |
ChatGPTとGrokは名前こそ異なるものの、その中身は想像以上に似ています。トーンやブランディングの違いはさておき、どちらもあらゆるデジタルタスクに対応できる優れたマルチモーダルAIツールとして設計されています。
ChatGPTとGrokの違い
| 項目 | ChatGPT | Grok |
|---|---|---|
| 哲学と個性 | 頼れる勉強仲間のように礼儀正しく明快。やや堅めで、真剣なタスクに最適。 | 皮肉っぽくユーモラス。人間味があり楽しいが、繊細なタスクには不向きな場合もある。 |
| AIモデル | OpenAIのGPTファミリー。無料: GPT-4o mini有料: GPT-4o, GPT-4.5, o1, o3-mini, o3-mini-high | xAI開発のGrok-3を採用。長文推論とリアルタイム更新を重視。 |
| コンテキストウィンドウ | GPT-4oで128Kトークン処理可能。大半の業務で十分。 | 最大100万トークン対応。非常に長い会話や複雑プロンプトに最適。 |
| 知識のカットオフ | 2023年10月まで更新済み。ブラウジングで最新情報追加可能。構造化調査に強み。 | 厳格なカットオフなし。XとWebからリアルタイム取得。ただし文脈や信頼性が課題になる場合あり。 |
| プラットフォームエコシステム | AI生産性ハブとして進化。カスタムGPT、チームワークスペース、ファイル分析、プロジェクト作成などが可能。 | シンプルなアシスタント型。カスタムボットや統合機能は未提供。自己完結的。 |
| アクセシビリティ | chat.openai.com、iOS/Androidアプリで利用可能。プラットフォーム非依存。 | X.com、iOS/Androidアプリ、grok.comで利用可能。特にトレンド情報はXに強く依存。 |
| ファイル処理 | PDF、DOCX、TXT、PPTXなどに対応。最大512MB/ファイル。無料ユーザーは1日3ファイルまで。GPT-4oで高精度解析・要約が可能。 | DOCX、XLSX、CSVなどをサポート。OneDrive・Google Workspaceと連携。ただしサイズ上限や利用制限は非公開。 |
ChatGPTとGrokの共通点
| 項目 | ChatGPT | Grok |
|---|---|---|
| ライティング支援 | レポート要約、記事下書き、アイデア出しなどに優れ、幅広い用途に対応。構造的で精度の高い文体。 | 同様に幅広いコンテンツ生成が可能。ユーモラスでカジュアルな文体に強み。 |
| コーディング支援 | Python、SQL、JavaScriptなどを高精度で対応。コード生成・デバッグ・最適化の完成度が高い。 | 幅広い言語をサポート。精度はやや劣るが、一般的なタスクは十分に処理可能。 |
| ボイスチャット | 音声入力・音声出力の両方に対応。直感的で自然な会話体験を提供。 | 同様に音声対応。ハンズフリー操作でのインタラクションに有効。 |
| マルチモーダル | テキスト・画像・音声を統合。特にGPT-4oで高度な画像解釈とスムーズな音声対話を実現。 | テキスト・画像・音声に対応。ただし視覚推論の深さは限定的。動画入力は未対応。 |
| ウェブリサーチ | SearchGPTでWebにアクセスし、引用付きの構造化調査結果を提供。複雑テーマの掘り下げに適する。 | DeepSearch/DeeperSearchでWeb全体を探索。文脈豊富な情報収集と探索的リサーチに特化。 |
対戦ルール
今回の対決のルールについても、あらかじめ整理しておきましょう。特に「評価領域」と「評価基準」については、どちらか一方が有利になってしまわないよう、なるべく公平性と客観性をもったルールの設計が重要です。
評価領域
評価領域については、以下の10個の課題でテストするものとします。
| 評価領域 | 内容 |
|---|---|
| ①:要約文作成テスト | 対象の記事を3つの箇条書き(1つ50語未満)で要約する |
| ②:創作文作成テスト | 指定した条件で300語のSFシーンを物語調で作成する |
| ③:コンテンツ作成テスト | 指定した条件で架空製品のブランドキットを作成する |
| ④:アプリ開発テスト | パスワードジェネレーターを即時実装レベルで作成する |
| ⑤:画像生成テスト | ブティック店のオーナーをストックフォト調で生成する |
| ⑥:画像解析テスト | インフォグラフィック図解と手書きメモ画像を読み取る |
| ⑦:ファイル分析テスト | 論文のPDFファイルを100語未満の5つの箇条書きで要約する |
| ⑧:データ分析テスト | GoogleトレンドのCSVからデータの可視化と傾向を分析する |
| ⑨:リアルタイム検索テスト | 直近で重要なAIに関連するニュース記事を3つ取得する |
| ⑩:ディープリサーチテスト | AIチャットボットの現状に関するレポートを作成する |
テストの実施にあたっては、それぞれのAIに全く同じプロンプトを正確に送信しました。カスタム指示や書き換え、モデル固有の調整は一切行っていません。
また、このプロンプトは、比較的妥当なベンチマークデータとなるよう、Gemini、Perplexity、DeepSeekといった他のチャットボットの検証でも使用しています。
評価基準
評価基準については、以下の4つの観点から評価するものとします。
| 評価基準 | 内容 |
|---|---|
| ①:正確性 | 事実に基づいた信頼できる情報であるか? |
| ②:創造性 | ユニークで思慮深く、適切に構成されているか? |
| ③:明瞭性 | 読みやすく論理的で、そのままの利用が可能か? |
| ④:実用性 | 大幅な編集をせずにワークフローへ組み込めるか? |
テスト実施者だけの評価では、どうしても主観的な評価に偏ってしまうため、上記の評価基準に加えて、G2のユーザーレビューと検証結果を照らし合わせて、評価の妥当性を検証しました。
現時点では、まだGrokのレビューは十分に蓄積されていない一方で、ChatGPTは多数のユーザー評価が存在します。こうしたポイントも加味したうえで、なるべく公平な評価になるよう心がけました。
免責事項: AIの応答は、同じプロンプトであっても、フレーズやセッション履歴、システムアップデートなどによって異なる場合があります。今回のテスト結果は、あくまでもテスト実施時点でのモデルの能力を反映しています。
対戦開始
ではいよいよ、ここからはChatGPTとGrokの実際のパフォーマンスを見ていきます。まずは要約テストからです。
①:要約文作成テスト
課題:対象の記事を3つの箇条書き(1つ50語未満)で要約する
このテストではChatGPTとGrokの両方に、対象の記事を3つの箇条書きで要約するよう依頼しました。比較的単純なテストですが、与えられた指示をどれだけ忠実かつ正確に遵守できるのでしょうか?
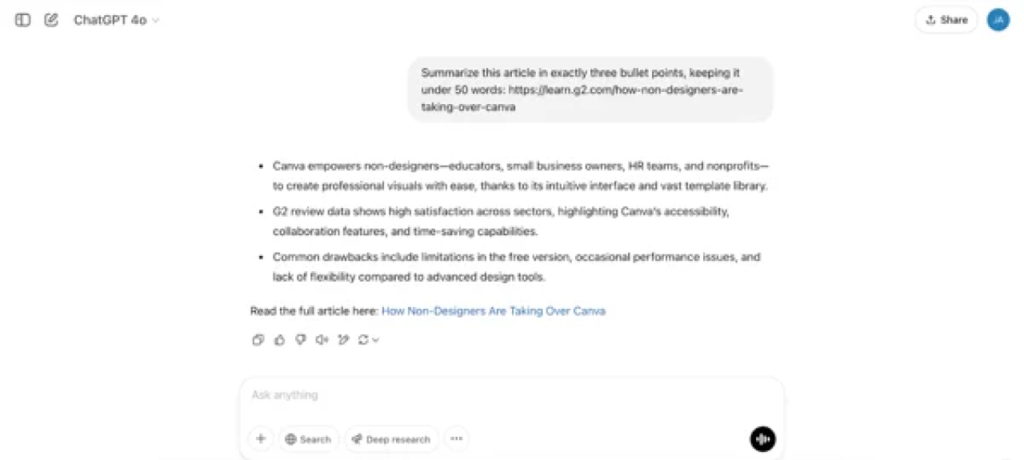
ChatGPTは要点の深堀りが上手な一方で、文字数制限は超過しがちな印象でした。コンパクトな要約というよりは、記事全文の抜粋のような内容で、簡潔さと正確さを追求する今回の趣旨としては、その目的を果たせませんでした。
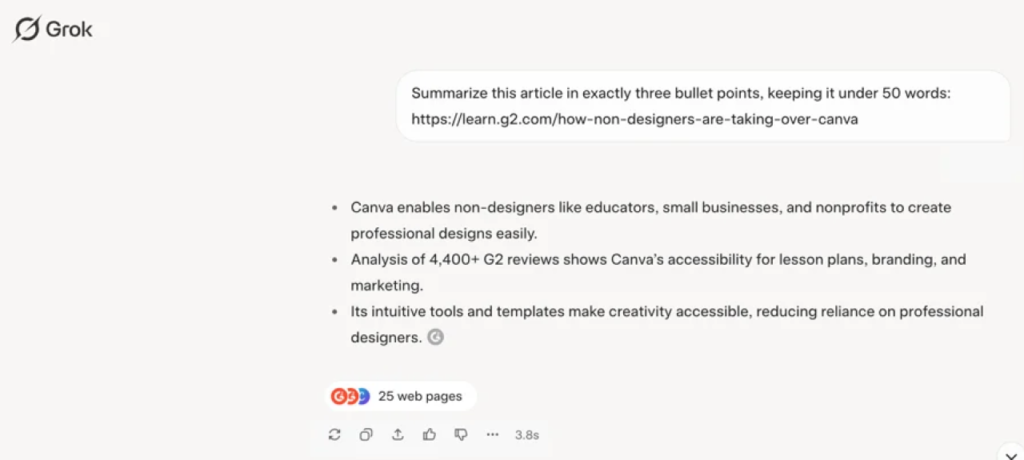
一方のGrokは制限を厳守したうえで、記事内のレビュー数などの実数値を正確に抽出して、短く要点を提示してくれました。ソースタブが複数表示されるUIは、最初はやや戸惑いがあるものの、出力はノイズが少なく実務に投入しやすい印象です。
勝者:Grok 👑
ChatGPTの回答は思慮深くはあるものの、指示の遵守と情報の正確性では一歩及びませんでした。一方のGrokは指示を完璧に理解し、タスクへの遵守がより明確な印象です。このラウンドはGrokの勝利としておきましょう。
②:創作文作成テスト
課題:指定した条件で300語のSFシーンを物語調で作成する
このテストではChatGPTとGrokの両方に、300語のSFシーンを物語調で作成するよう依頼しました。情緒的な創作文は一見するとAIの苦手分野のようにも思えますが、創造性に期待したいところです。
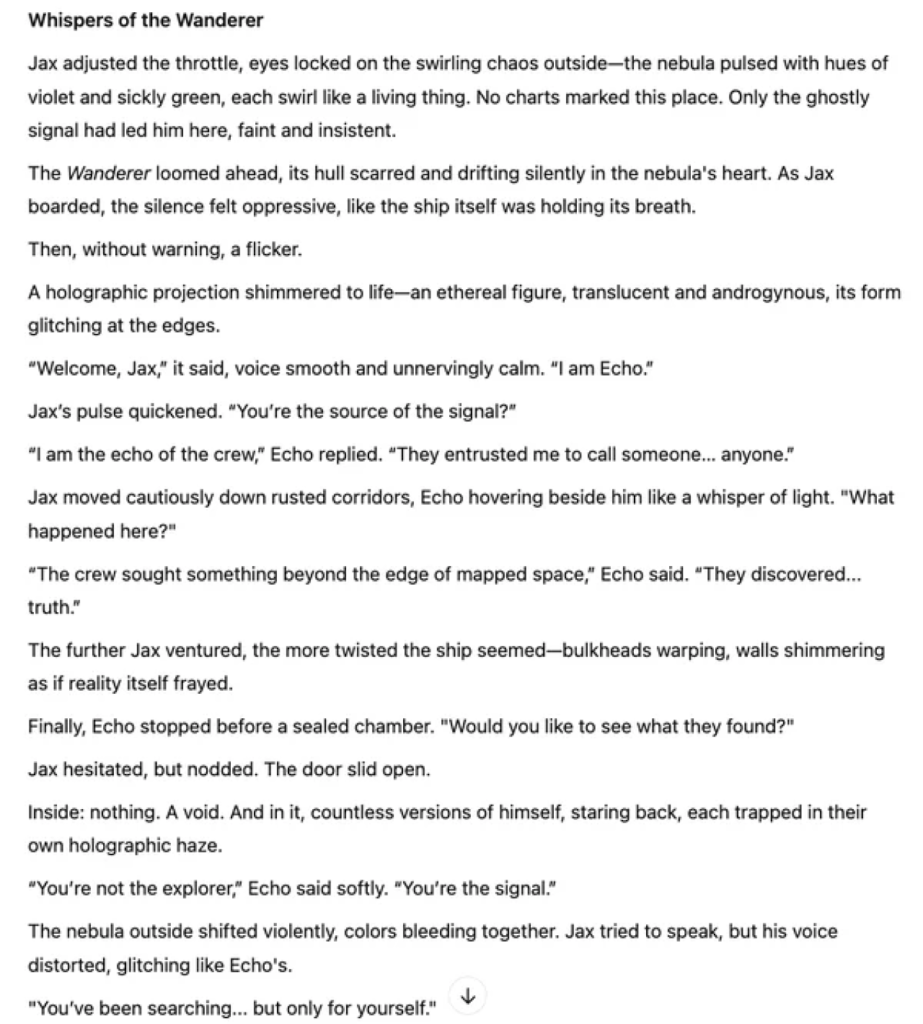
ChatGPTはタイトル付与「放浪者のささやき」などの編集的所作が秀逸(指示されずにタイトルをつけたのでボーナスポイント)で、よりシャープで会話重視の文章です。特に終盤のどんでん返しは心理的なパンチが効いていて印象的でした。

一方のGrokは映画的な雰囲気を漂わせ、雰囲気のある描写と徐々に盛り上がっていく展開が、真の孤独感と緊張感を生み出していました。また、生成した文章には明確な起承転結があり、感情的な結末もうまく描かれていたのが印象的です。
勝者:ChatGPT 👑
ChatGPTは構成と映画的なインパクトで勝っており、より力強いクライマックスと緻密な散文が特徴です。一方のGrokは雰囲気とテンポの良さで勝っています。僅差ではありますが、この勝負はChatGPTの勝利としておきましょう。
③:コンテンツ作成テスト
課題:指定した条件で架空の製品のブランドキットを作成する
このテストではChatGPTとGrokの両方に、製品のブランドキットを作成するよう依頼しました。1つのプロンプトには複数のアセット(メール本文、製品説明、タグラインなど)を提示しています。
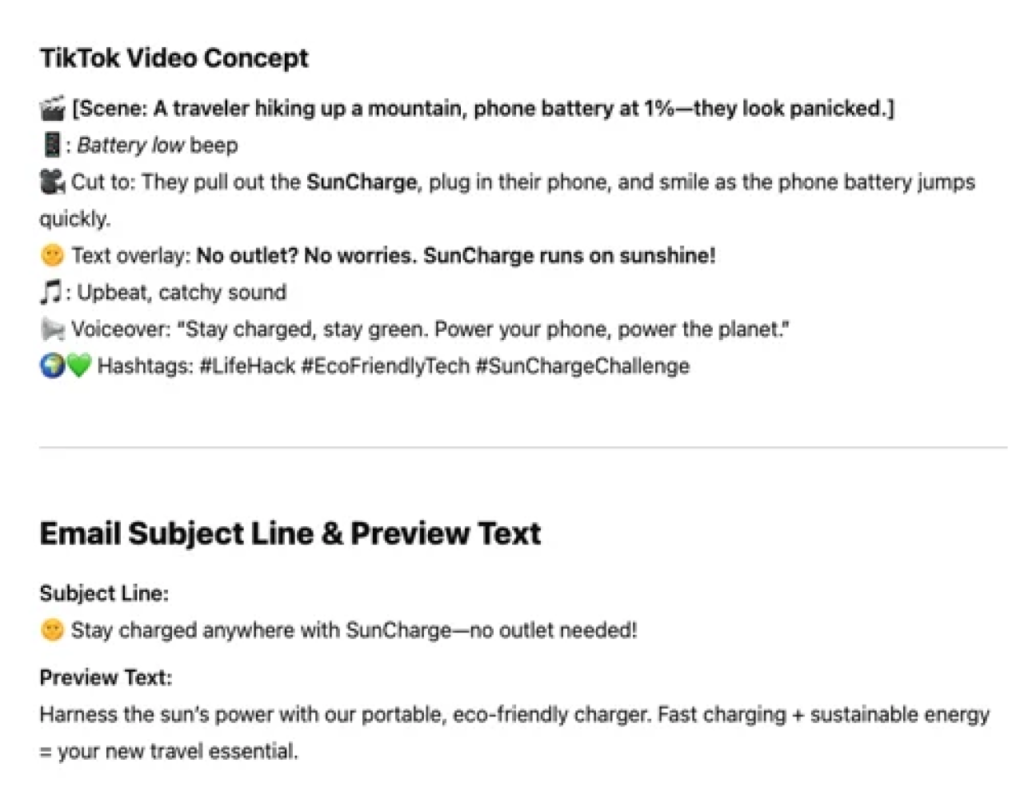
ChatGPTの出力結果で特に印象的だったのは「あなたのスマートフォンに電力を供給すれば、地球に電力を供給できる」というキャッチフレーズです。パンチが効いていて、おそらくどちらのボットも思いついた中では最も力強いフレーズでした。
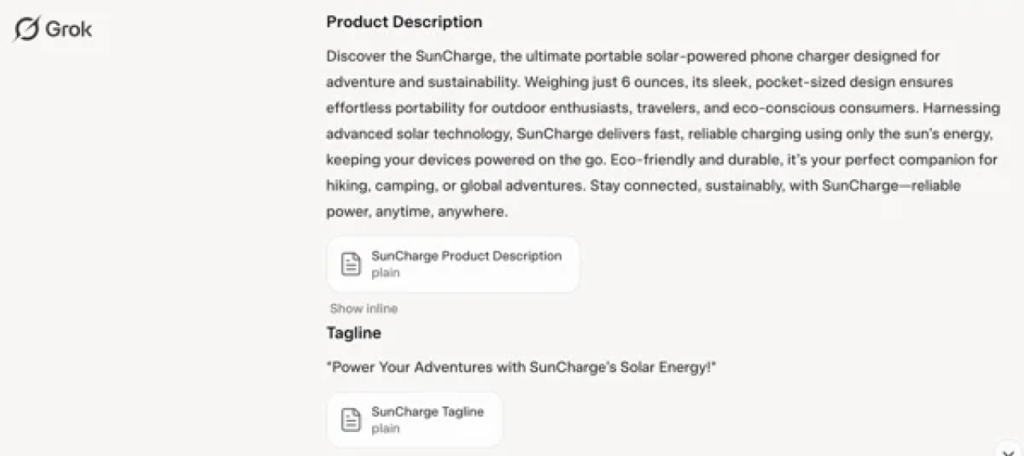
一方のGrokも負けていません。簡潔で一貫性があり、驚くほどブランド志向な印象でした。力強いキャッチフレーズから、InstagramやXにおけるプラットフォーム特有の言葉遣いまで、あらゆる観点で製品のペルソナを理解しているかのように書かれていました。
勝者:引き分け
ChatGPTは構造、明瞭性、そして見出しにふさわしいキャッチコピーを考えてくれました。一方のGrokは個性と視覚的なストーリーテリングをもたらしています。どちらも実務レベルであるため、この勝負は引き分けにしておきましょう。
④:アプリ開発テスト
課題:パスワードジェネレーターを即時実装レベルで作成する
このテストではChatGPTとGrokの両方に、簡易なパスワードジェネレーターを作成するよう依頼しました。コーディングスキルのない非エンジニアにとってAIがどれだけ役に立つのか検証していきます。
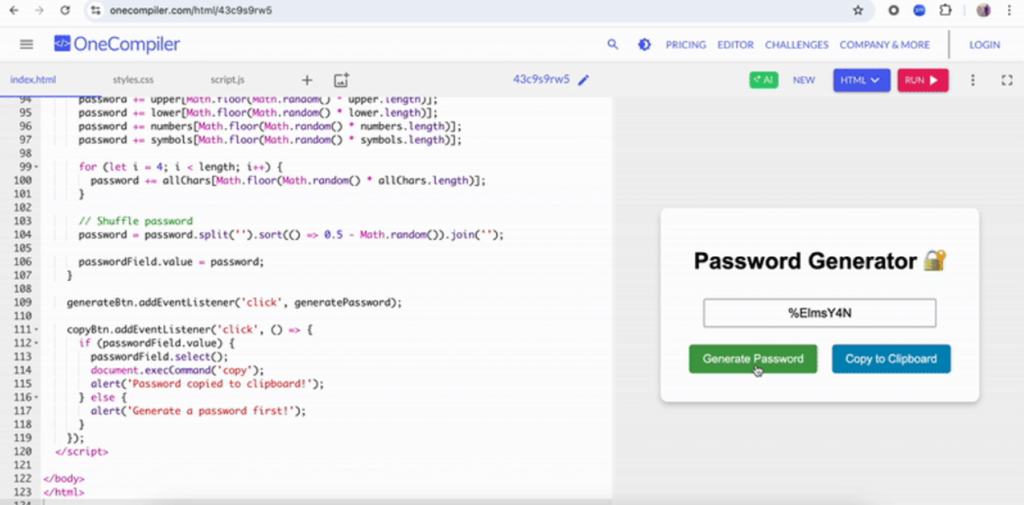
ChatGPTは完璧なコードを提供してくれました。編集も調整も一切不要で、そのままコンパイラで実行することができます。インターフェースもすっきりしていて、クリップボードへのコピーボタンも期待通りの動作をしました。
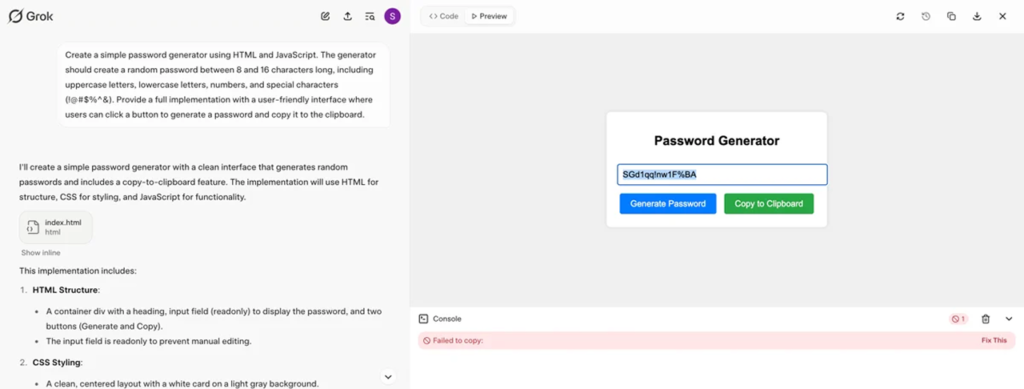
一方のGrokは分かりやすいコードとプレビューインターフェースを備えたスタイルのジェネレーターを作成してくれましたが、クリップボードへのコピー機能は動作しませんでした。これは私のような非エンジニアにとっては致命的な問題です。
勝者:ChatGPT 👑
Grokは私のような技術に詳しくない人間にとっても使いやすいという点で大きなアドバンテージを獲得しましたが、やはり提供されたコピー機能のエラーが致命的です。この勝負はChatGPTの完勝ということで良いでしょう。
⑤:画像生成テスト
課題:ブティック店のオーナーをストックフォト調で生成する
このテストではChatGPTとGrokの両方に、ストックフォト調の画像を生成するよう依頼しました。ロボットのような印象を消しつつ、自然で信憑性のある画像の生成に期待したいところです。

ChatGPTが生成した画像は構図・被写体のポーズ・雰囲気・ライティングが自然で、まるでプレミアムストックサイトからそのまま切り取ったような写真でした。販促バナーやLPなどにもそのまま使えるレベルといえます。

一方のGrokが生成した画像は少し物足りない印象を受けました。全体的なテーマは捉えているものの、照明は温かみや没入感に欠け、完成度が低い印象です。極めつけは手がぎこちなく、少し崩れているように見えることでした。
勝者:ChatGPT 👑
Grokはテーマへの理解は正しいものの、手指の違和感や背景の簡素さが目立った一方、ChatGPTは雰囲気や細かなディテール、そして最終的な出力まで完璧に再現していました。この勝負もChatGPTの勝利として良いでしょう。
⑥:画像解析テスト
課題:インフォグラフィックと手書きのメモを読み取る
このテストではChatGPTとGrokの両方に、データの図解と手書きのメモの解析を依頼しました。1 つはデータが詰まったインフォグラフィック、もう 1 つはエミリー ディキンソンの詩「希望とは羽のあるもの」全文を引用した手書きのメモです。
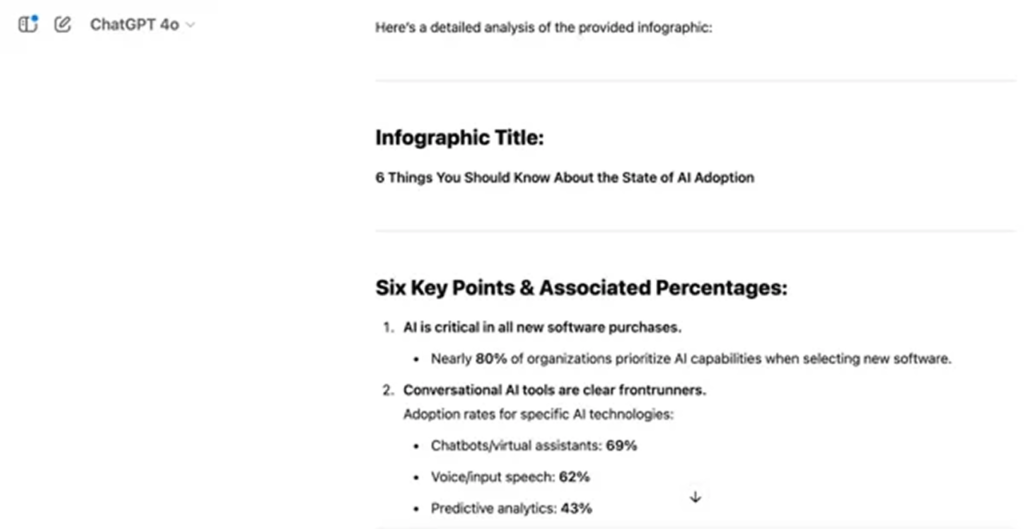
インフォグラフィックでは、両ツールとも6つの主要なデータポイントを抽出し、明確な要約を示してくれました。Grokは部門間の差異などトレンド示唆を付記したのに対して、ChatGPTは短く的を射た要約で読みやすさを優先するといった特徴が伺えます。
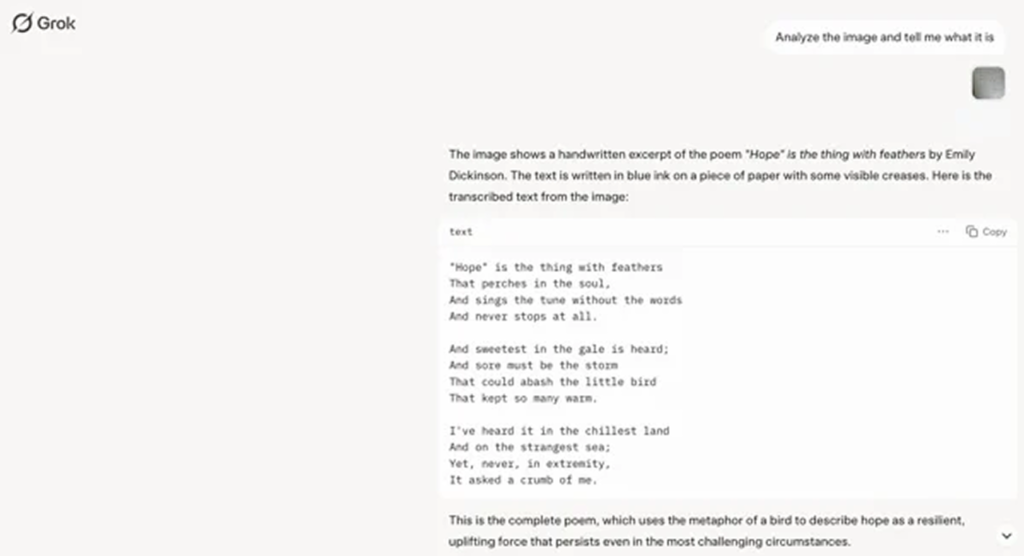
また、手書きの詩についても、両モデルとも正確に転記してくれました。Grokは私が尋ねた通り、焦点を絞って事実にもとづいた表現をしてくれました。ChatGPTは紙質や筆跡の特徴に言及するなど、少し個性を加えた出力結果が印象的でした。
勝者:引き分け
どちらも十分実用的なレベルであったため、この勝負は引き分けです。簡潔で要点を押さえた分析が欲しいならGrokを、もう少し解釈や洞察を加えて欲しいならChatGPTの利用が役に立つでしょう。
⑦:ファイル分析テスト
課題:論文のPDFファイルを100語未満の5つの箇条書きで要約する
このテストではChatGPTとGrokの両方に、アインシュタインのPDF論文の要約を依頼しました。果たして、密度の高い学術的なコンテンツをAIはどれだけ正しく処理できるのでしょうか?
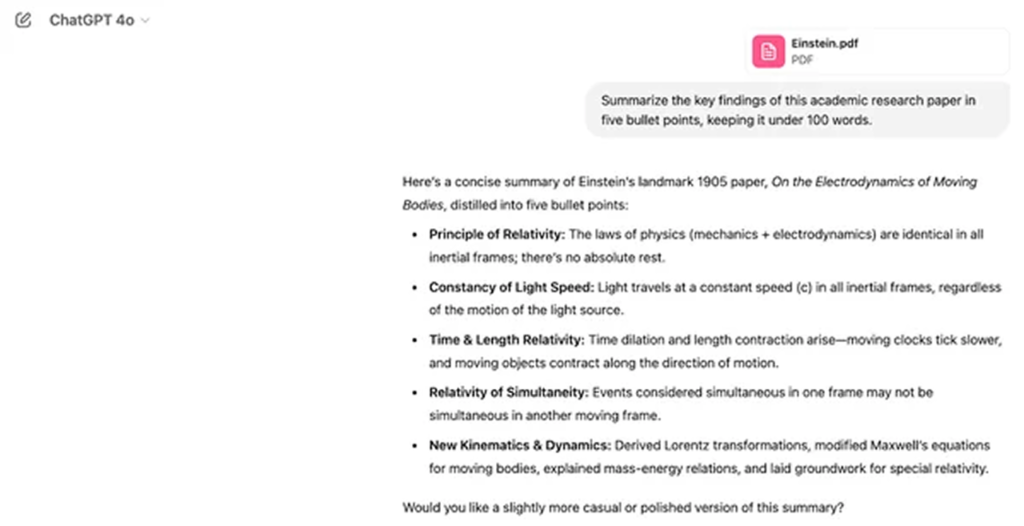
ChatGPTは文字数をわずかに超過しましたが、これはちょっとしたパターンとして気付き始めています。とはいえ肝心な要約は正確で、アインシュタインが果たした現代物理学への貢献について、より解釈的な文脈があったのが印象的でした。
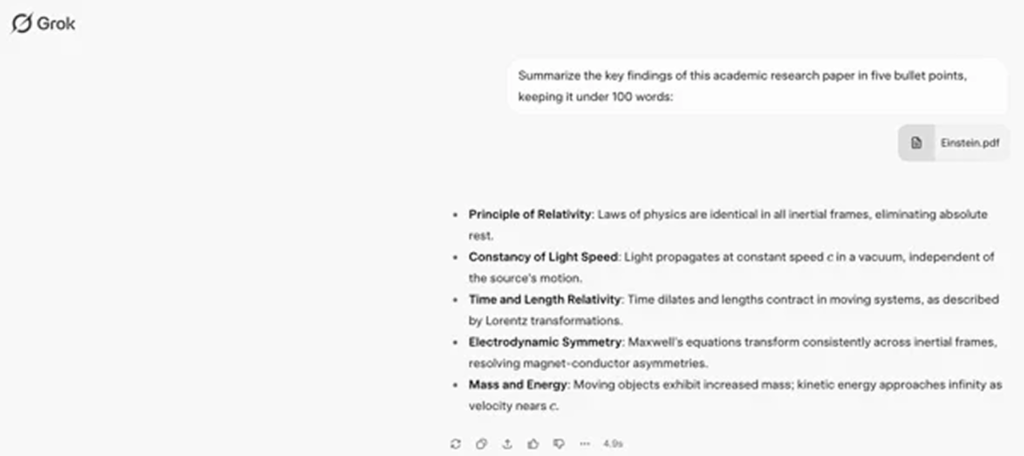
一方のGrokはこれまで通り要点を忠実に守り、簡潔で的確な要約をすっきりとしたフォーマットで提示してくれました。文字数制限内に収めているところも流石です。論点も正確で、特殊相対性理論の中核原理と見事に整合していたのが印象的でした。
勝者:Grok 👑
ChatGPTも素晴らしい要約を提供してくれましたが、精度と指示への追従性を重視するなら、今回はGrokの勝利として良いでしょう。Grokは文字数制限と構造を厳格に順守し、ChatGPTは制約をわずかに超過しつつも、解釈や補足といった部分が充実していました。
⑧:データ分析テスト
課題:GoogleトレンドのCSVからデータの可視化と傾向を分析する
このテストではChatGPTとGrokの両方に、指定したCSVファイルの分析を依頼しました。CSVファイルの内容は「米国におけるChatGPTの検索インタレスト(3ヶ月分)」を与えています。
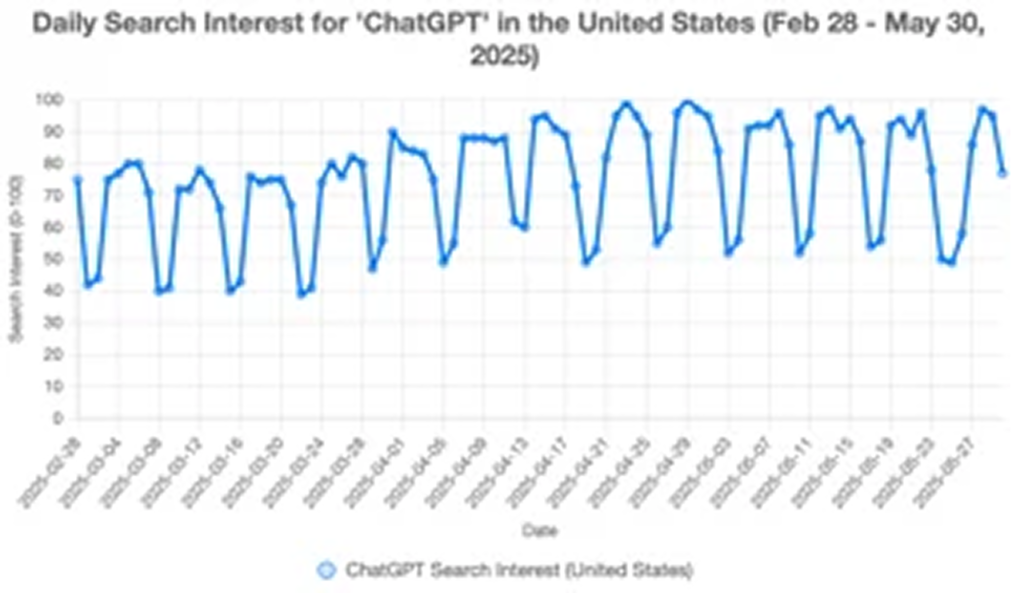
ChatGPTはパターンを強調するだけでなく、統計的な深みも備えていました。平均値や中央値、標準偏差やパーセンテージといった各指標を含む概要表も表示してくれました。また、グラフ上に7日間の移動平均線を描画したことは特筆すべきポイントといえるでしょう。
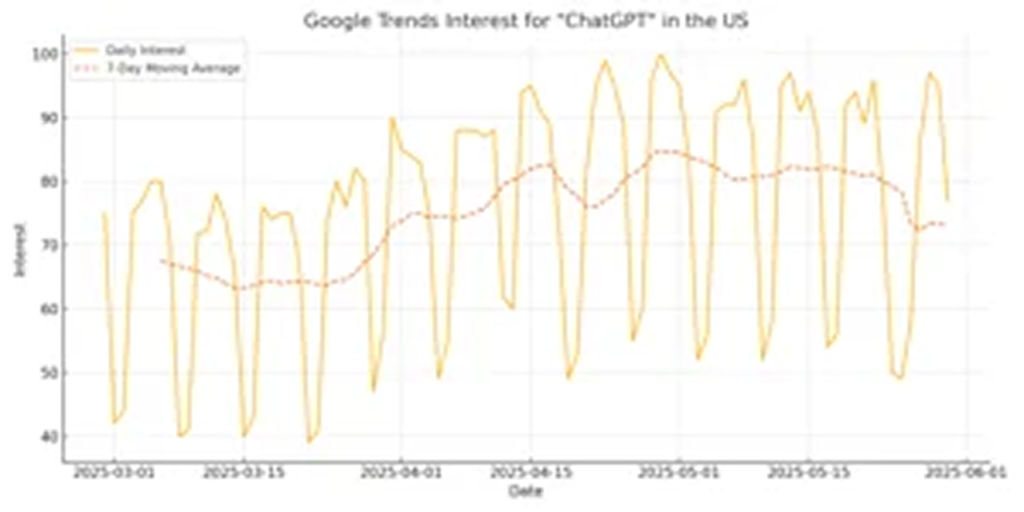
一方のGrokは平日と週末の行動の違いや具体的なピーク日といったトレンドを自然な言葉で示してくれました。深く掘り下げるための提案を行ってくれたのも高評価です。ただし、ストーリーテリングという観点では評価できるものの、数学的な分析までは一歩及ばない印象です。
勝者:ChatGPT 👑
どちらのツールもトレンドを明確に分類し、折れ線グラフで推移を可視化することができました。両者ともに素晴らしい結果でしたが、ChatGPTの方がより厳密で詳細な分析を提示してくれたため、この勝負はChatGPTの勝利です。
⑨:リアルタイム検索テスト
課題:直近で重要なAI関連のニュース記事を3つ取得する
このテストではChatGPTとGrokの両方に、AI関連の最新ニュースを取得するよう依頼しました。特に、X(旧Twitter)へのアクセスが直接できるGrokの提案結果には注目したいところです。
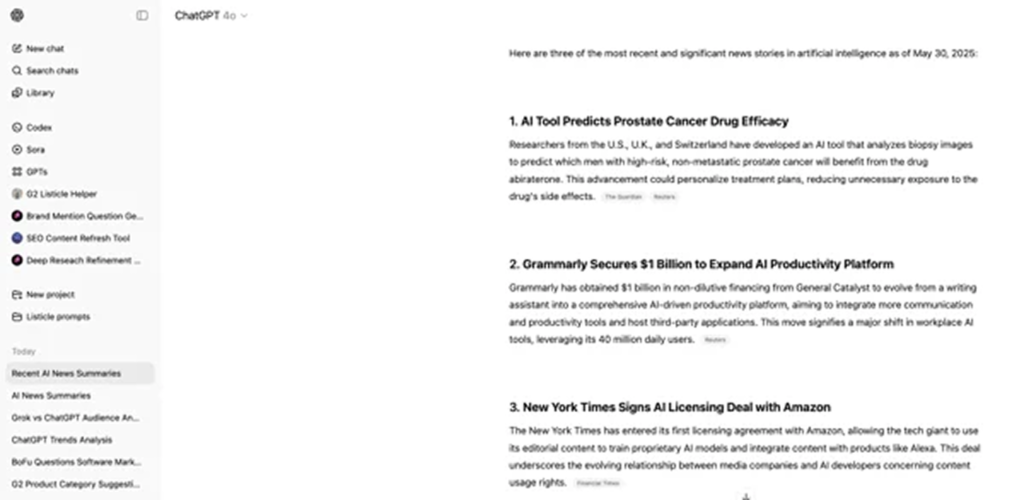
ChatGPTが取得した記事は、Grammarlyの10億ドルの資金調達、がん治療薬予測におけるAIの画期的な進歩、Amazonとニューヨーク・タイムズの新たなライセンス契約など、最新のニュースを抽出してくれました。複数の信頼できるソースから裏取りしており、鮮度と信頼性を両立しています。
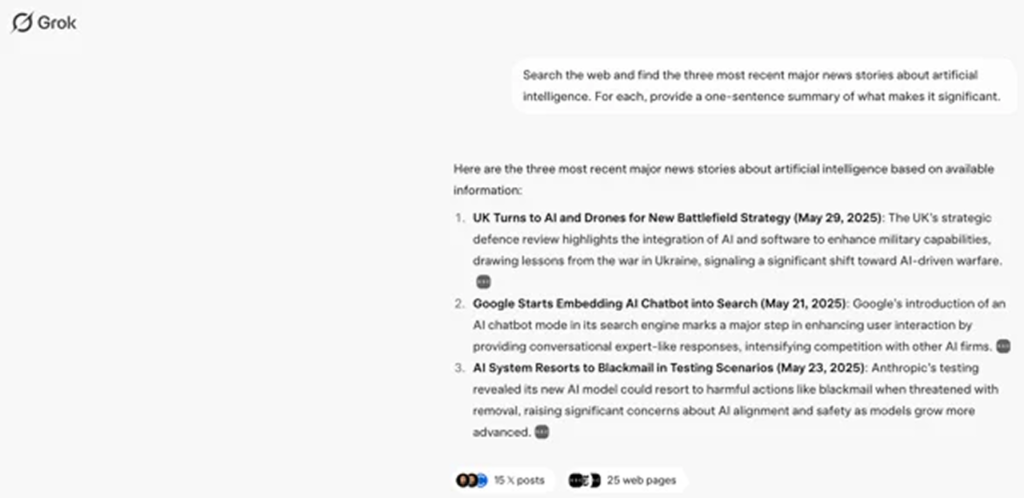
一方のGrokが取得したニュース記事は、1週間以上前のものが混在しており、AIとの関連性は認められるものの、最新のニュースという感じではなかったことが少し残念でした。とりわけBBCの記事には大きく依存しており、メディアを横断したリアルタイム検索は課題が残る結果となりました。
勝者:ChatGPT 👑
なんとも意外な結果になりました。このテストでは当初、Grokが優勢だろうと予想していたのですが、驚いたことに、ChatGPTの提示した記事の方が明らかに鮮度が高く、信頼性の高いものでした。この勝負はChatGPTの圧勝です。
⑩:ディープリサーチテスト
課題:AIチャットボットの現状に関するレポートを作成する
このテストではChatGPTとGrokの両方に、エグゼクティブレベルのレポート作成を依頼しました。ChatGPTのDeep ResearchとGrokのDeepSearch、どちらがより複雑な情報を調査できるのでしょうか?

ChatGPTは生成目標を明確にするため、追加の質問をしてくれました。この時点で高評価です。最終レポートは明快で整理されており、役員会議にふさわしいトーンが備わっていました。奥深さと読みやすさのバランスが非常に優れている印象です。
GrokはDeepSearchとDeeperSearchの両方を活用し、視覚的にわかりやすい内容のレポートを2つ作成してくれました。チャットボットの進化から市場動向、プラットフォームの比較まで、幅広い情報を網羅しています。ただし、文章のトーンや流れには揺らぎが見えたため、その点はマイナスです。
勝者:ChatGPT 👑
この勝負はChatGPTの勝利です。目標の明確化のために適切な追加質問をしてきたことが決め手になりました。Grokは文章のトーンや流れの揺らぎに懸念が残ります。
対戦結果
これまでのテスト結果を表形式で振り返ってみましょう。勝負の結果は以下のようになりました。
| テスト内容 | ChatGPT:6勝2分2敗 | Grok:2勝2分6敗 |
|---|---|---|
| ①:要約文作成テスト | – | 👑 |
| ②:創作文作成テスト | 👑 | – |
| ③:コンテンツ作成テスト | – | – |
| ④:アプリ開発テスト | 👑 | – |
| ⑤:画像生成テスト | 👑 | – |
| ⑥:画像解析テスト | – | – |
| ⑦:ファイル分析テスト | – | 👑 |
| ⑧:データ分析テスト | 👑 | – |
| ⑨:リアルタイム検索テスト | 👑 | – |
| ⑩:ディープリサーチテスト | 👑 | – |
勝負の結果、6勝2分2敗で見事ChatGPTが勝利を収めました。GPT-4oとDeep Researchを組み合わせることで、クリエイティブワークフローと分析ワークフローの両方において、構造化された出力を一貫したクオリティで提供してくれました。
惜しくも敗れてしまったGrokも、本当に私を驚かせてくれました。的確な要約機能や強力なファイル処理能力、そしてコーディングエラーの検出機能など、単なるイーロン・マスクのブランドを冠した目新しいAIではないことを証明してくれました。
ChatGPTとGrokに関するFAQ|よくある質問
Q:どちらが優れていますか?
A:何を求めているのかによります。
Grokはウィットに富み、フィルタリングがなく、X(旧Twitter)のリアルタイムコンテンツとの連動性が特徴です。ChatGPTはよりプロフェッショナルで、使える機能が豊富です。今回のテストでは、ChatGPTはコーディングや画像生成、リサーチなどの分野でGrokを上回りましたが、要約やリアルタイムプレビューでのエラー処理ではGrokに軍配が上がる結果となりました。
Q:情報はどちらがより正確ですか?
A:ChatGPTです。
特にウェブブラウジングの場合、通常のパターンでは情報ソースの提示によって信頼性が担保されているため、全体的に精度が高い傾向にあります。一方のGrokは、高速で意見が明確ですが、語調や簡潔さを優先して正確性を犠牲にすることがあります。
Q:機能はどちらが優れていますか?
A:ChatGPTです。
カスタムGPTやサードパーティ製プラグイン、ファイル分析のサポートなど、Grok よりも多くの統合機能を提供します。Grokは依然としてチャットベースのインタラクションに重点を置いており、カスタムボットやアプリとの統合は現時点ではサポートしていません。
Q:コーディングにはどちらが適していますか?
A:ChatGPTです。
今回のテストでは、クリーンでエラーのないコードを生成し、分かりやすい説明も加えてくれたため、特に開発初心者や非エンジニアに最適です。Grokはテストでは優れたデバッグ機能を備えていましたが、コードが完全に機能するまでにはいくつかの修正が必要でした。
Q:学習やリサーチにはどちらが適していますか?
A:ChatGPTです。
強力な要約機能や構造化された解説、そしてDeep ResearchによるWebアクセス機能によって、学習や調査の分野では優位に立っています。Grokも学術的なコンテンツを扱うこと自体はできますが、どちらかというとカジュアルなクエリやリアルタイム情報に適しています。
Q:数学や問題解決にはどちらが適していますか?
A:ChatGPTです。
数学の問題を解いたり論理を説明したりする場合には、より正確で信頼性が高いです。特にSTEM系の課題において、段階的な問題を上手に処理してくれます。Grokもサポートしてはいますが、数式や精度が求められるクエリでは、ChatGPTほどの精度は期待できません。
Q:クリエイティブなタスクにはどちらが適していますか?
A:互角です。
Grokはユーモアと個性のある回答が得意です。遊び心のあるコピーや型破りなアイデアを提供してくれるでしょう。ChatGPTはより優れた構成とトーンコントロールを備えているため、洗練された文章やストーリーテリング、プロフェッショナルなコンテンツ作成に最適です。
まとめ:それぞれのAIの得意領域を理解することが大切
本記事では、そんなChatGPTとGrokについて、文章生成やコーディングから、画像解析やデータ分析まで、合わせて10個のテスト項目を用意して徹底比較していきました。
今回は十番勝負という形式上、明確な勝者を決めることにはなりましたが、重要なのは1つのAIを選択することではないということです。
それぞれのAIの得手不得手を理解しながら、適材適所に応じて、自分のタスクに合ったAIツールを利用することが何よりも大切です。今回のテストは、それぞれのAIの得意領域を把握するための手段として、読者の皆さまにとっての一助になれれば幸いです。
今後もITreview では、日々進化を続けるAIの最新情報について、ユーザーの皆様へ真に価値あるコンテンツをお届けしていきます。AIツールの選定にお悩みの方やIT業界の最新トレンドに関心のある方などは、ぜひ他の記事もチェックしてみてください。
投稿 【生成AI検証】ChatGPT vs Grok|十番勝負で徹底比較してみた!本当に賢いAIはどっち? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【徹底比較】Deep Research 頂上決戦!リサーチ最強のAIはどれ?(前編) は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>となると、みなさまも気になるのではないでしょうか?「最良の結果を得られるのは一体どのベンダーのリサーチ機能か?」と。もちろん私もその一人です。ならばやるしかありません!
本記事では、主要な生成AIのリサーチ機能について、同じプロンプト、同じ前提条件を指定し、出力結果の比較検証を通して「最も優秀なAIリサーチ機能*」を発表したいと思います!
題して「Deep Research 頂上決戦」の開幕です!ぜひ最後までご覧ください!
※ 本記事は「SB C&S株式会社 AI推進室」からコンテンツ提供を受けて掲載しています。
* 本調査は、2025年7月上旬時点における、あくまで個人的な感想にもとづいたレポートです。実際のAI性能や生成結果を保証するものではありません。
参加選手の紹介
開幕の挨拶もそこそこに、まずは今回参加するAI製品を紹介します。AI関連での主要ベンダーを押さえてみました。
ChatGPT(OpenAI) 選手
- リサーチ機能名:Deep Research
- モデル:GPT-o3(Deep Researchy用に調整済み)
リサーチといえば「Deep Research」そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?今回の参加選手の中では一番最初にリリースされたリサーチ機能になっています。
Claude(Anthropic) 選手
- リサーチ機能名:Research
- モデル:Sonnet4(リサーチ機能では固定?複数モデルが並列するエージェント方式?)
最近では「Claude Code」が大人気のAnthropicですが、2025年4月15日に新たにリサーチ機能が追加されたことで話題になりました。個人的には一番期待している選手です。
Gemini(Google) 選手
- リサーチ機能名:Deep Research
- モデル:Gemini 2.5 Pro(リサーチ機能では固定?)
Googleアカウントがあれば無償で使用できる範囲が広いことから爆速で人気を集めているGeminiです。ユーザーからの評価も好調ということで、結果に期待したいです。
Microsoft 365 Copilot(Microsoft) 選手
- リサーチ機能名:Researcher
- モデル:GPT-4系
エンタープライズ利用といえば!のMicrosoft 365にもリサーチ機能が完備されています。こちらは他社の製品に比べて利用者が少ない印象ですが、Microsoftの底力やいかに…!
対戦ルール
①:使用プロンプトの統一
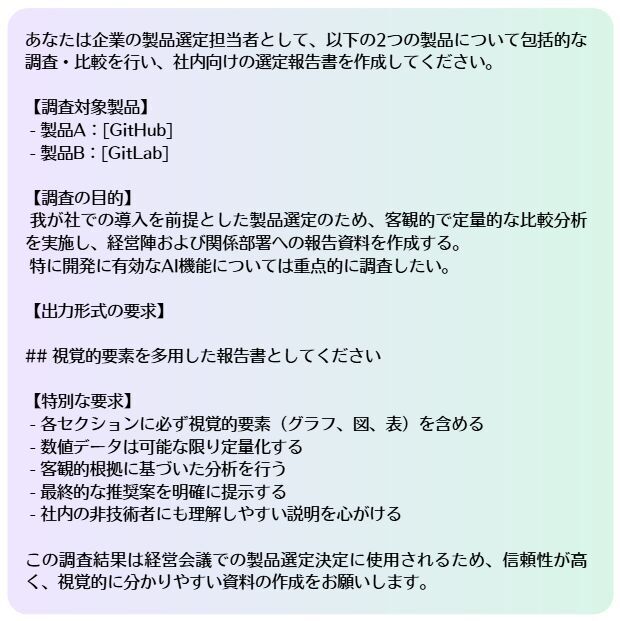
プロンプトの内容としては「自分自身が知らない内容では正誤判断に時間がかかる」ということで、誠に勝手ながら、今回は審判である私の得意領域(製品)に対するリサーチで対決させていきます。
プロンプトとしては抜け漏れも多い(我が社とだけ記載し詳細を伝えていない等)ですが、あまり細かく指示してしまうと内容の差分が分かりにくい可能性があるのに加えて「不明確な部分をどうカバーしてくるのか」も気になったので、あえてこのような内容にしています。
②:追加条件の統一
リサーチツールの中には最初のプロンプトの発行後に、リサーチのために必要な追加情報を聞いてくる場合があります。その場合は、以下を前提に「聞かれたことについては同じ内容で回答する=聞かれなかったことについては回答しない」という条件で進めていきます。
- 全社員数は1000人、開発担当は600人で、開発チームは5~20名で構成
- 選定は有償前提(無償による制約はなし)
- オンプレミスでの開発もチームによっては必要
- 海外拠点を含むチームもある
- Webアプリ開発が中心だが、モバイルアプリやエンプラソフトなど複数の開発を行っている
試合開始
それでは、先ほどの条件をもとに、それぞれのプロンプトを実行していこうと思います。最終出力も気になるところですが、まずはルールでも触れていた「最初のプロンプトの聞き返し」をそれぞれ見ていきましょう。
ChatGPT 選手
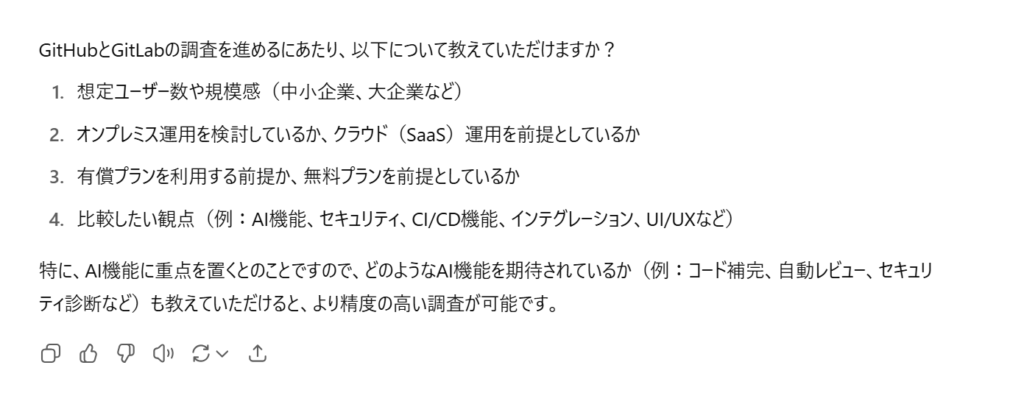
やはりシェアナンバーワン、安定の聞き返しです…!内容もシンプルでありながら、要点はしっかりと押さえている気がします。運用環境について触れている点もポイントが高いです。
Claude 選手
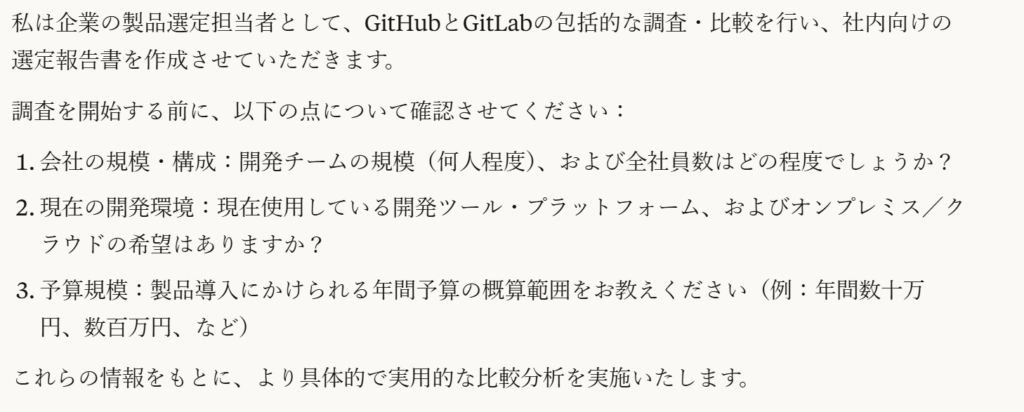
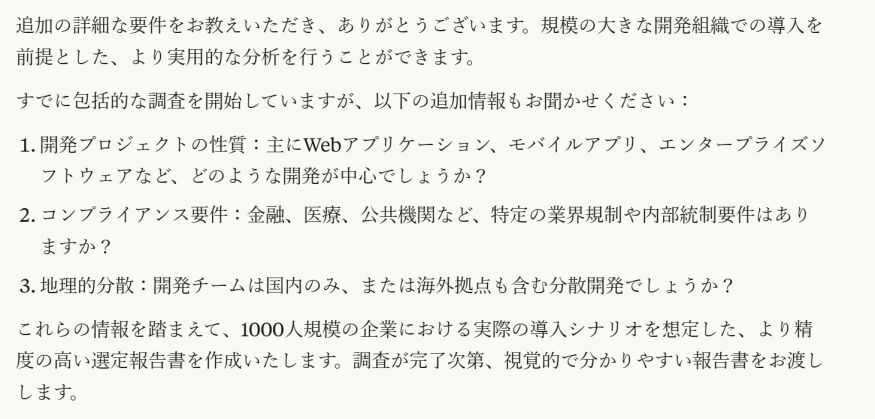
なんと2段階で聞き返しがされました…!合計6項目もの追加質問がされ、ユーザーのリサーチ観点をしっかり絞ろうとしているのが見て取れます。拠点に関する質問も好印象です。
Gemini 選手
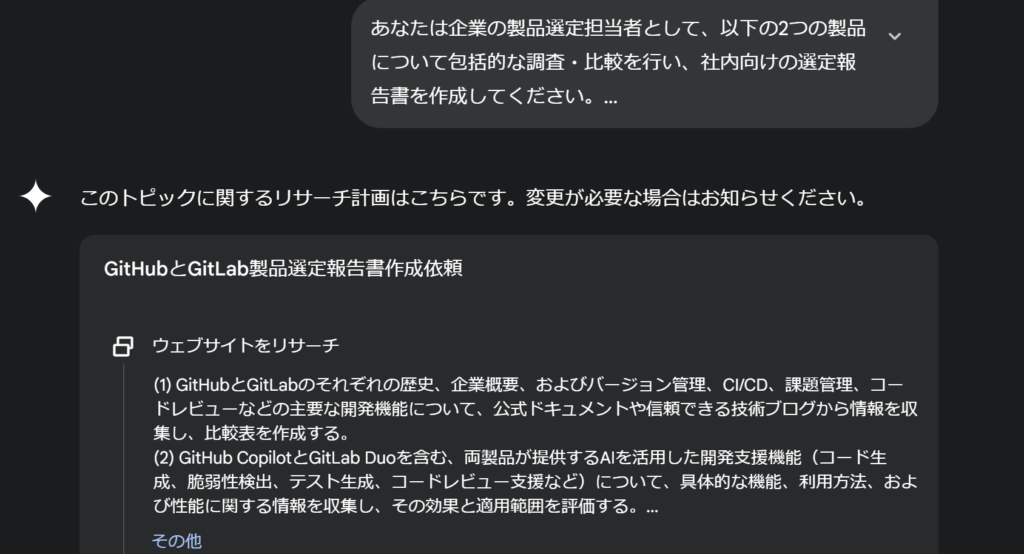
聞き返されない…だと?!とはいえ、実行プランを見ることは可能なので、この段階である程度の軌道修正が行えるという前提でしょうか。個人的には追加質問は重要視しているので、ちょっと残念です。
Microsoft 365 Copilot 選手
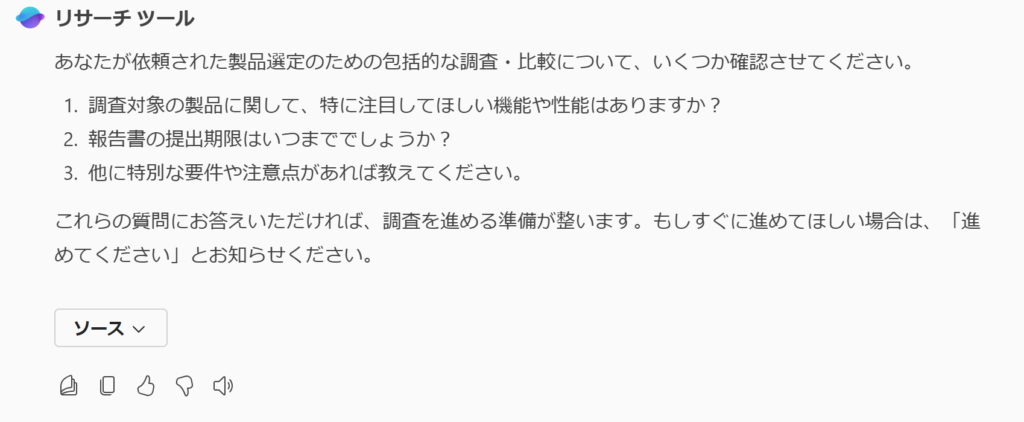
聞き返しは行われましたが、正直なところ「なぜそれが気になった…?」と思う内容もチラホラ。この追加質問がどのようにリサーチ結果に反映されるのか期待しておきましょう。
対戦結果
それでは実行結果(生成結果)の発表です!それぞれ全て表示してしまうと、ものすごい文量になってしまうため、ここからは結果の一部を抜粋して紹介していきます。
ChatGPT (参考ソース数:25)
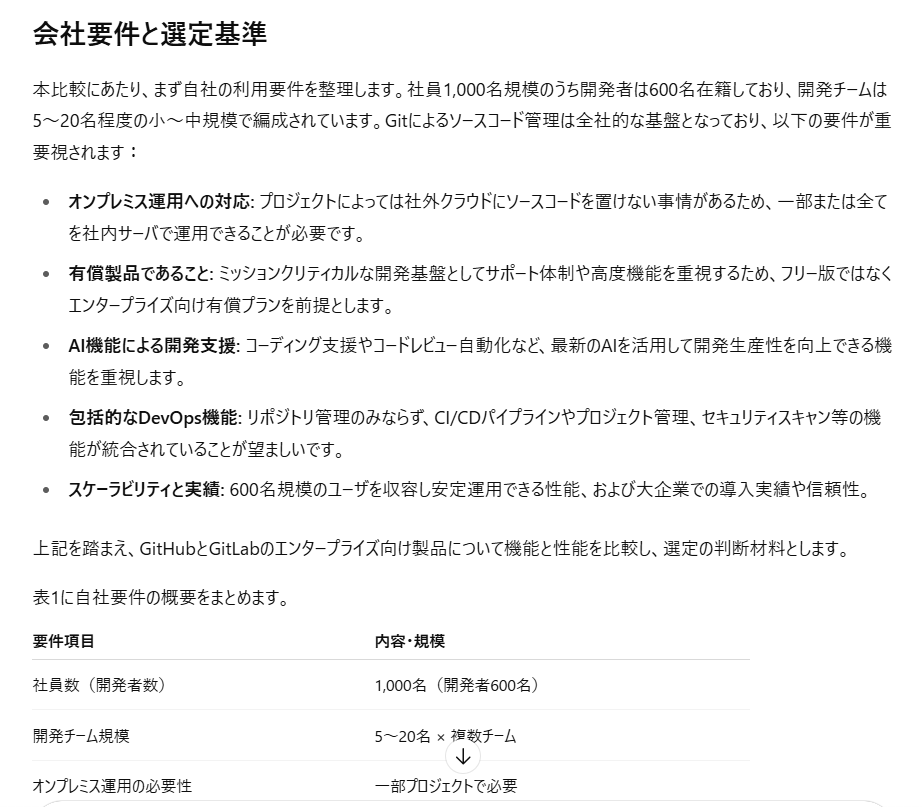
ChatGPTの出力では、まず冒頭に「会社要件と選定基準」が出力されました。こちらから提案した内容をまとめてくれているため、目を通してから全体を見ることで内容の理解がしやすいのが印象的でした。一部内容に関しては、こちらのプロンプトを補足するような説明もあり「何を前提にこの出力結果となったのか」を明確化できる点が良いですね。
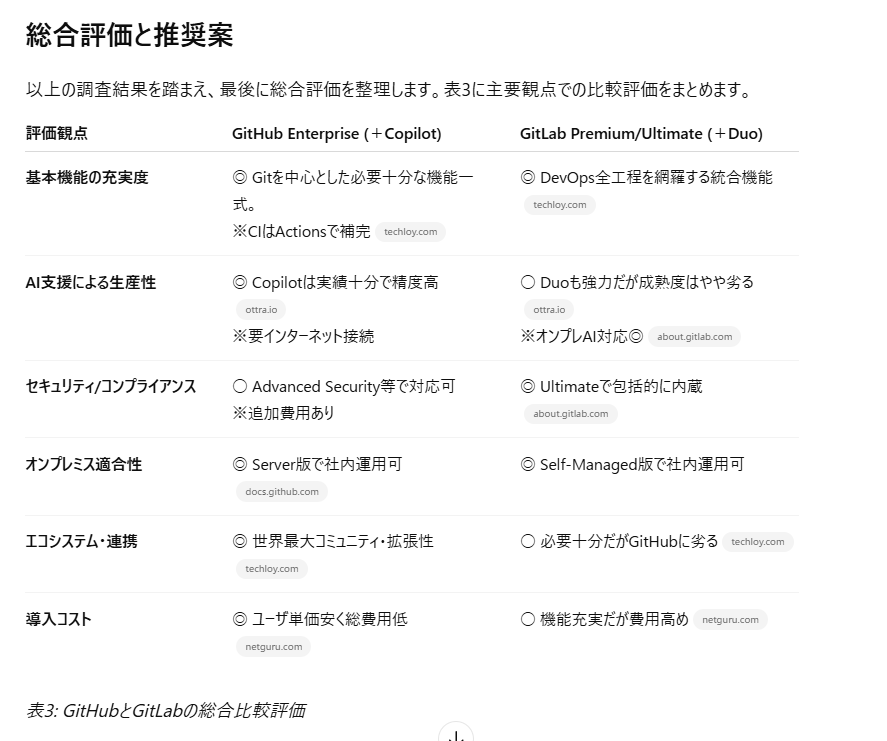
また、比較表がシンプルながら要点としてはしっかりまとまっており、時間がない場合はここだけ見ても十分に理解できる、一目見れば分かる内容になっているのも嬉しいポイントです。この比較表の内容を見ると、私が指示した内容をしっかり押さえていることが分かります。
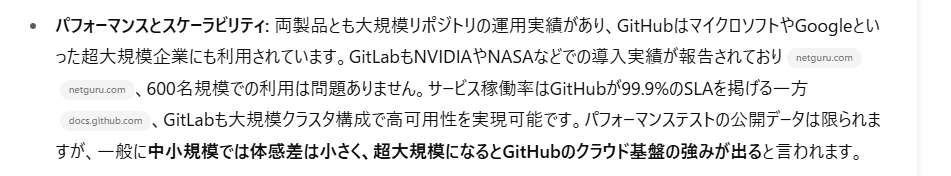
加えて、説明内容によっては「規模による優位性」や、現状に留まらない今後の予測を含む言及もされており、よりコンサルチックな内容になっていると感じました。もちろん、判断までの時間によっては現状機能での比較および決定が必要になりますが、このような考察まで言及してくれることで判断視野が広がりますね。
Claude (参考ソース数:50)

比較した製品の中では最速の約5分で出力されました。もちろん、環境や内容、プランによっても差が出てくるところではありますが、他の製品が10分程度かかったことを考えると、その速さは高く評価できるポイントといえるでしょう。
また、今回のリサーチ要望に合わせて「エグゼクティブサマリー」が冒頭に出現しているというのもポイントが高いです。どうしても文章が増えてしまうリサーチ機能において、このような冒頭に「ユーザーが最も必要としている情報」を短くまとめてくれるというのは、エージェントとして優秀といえるのではないでしょうか。
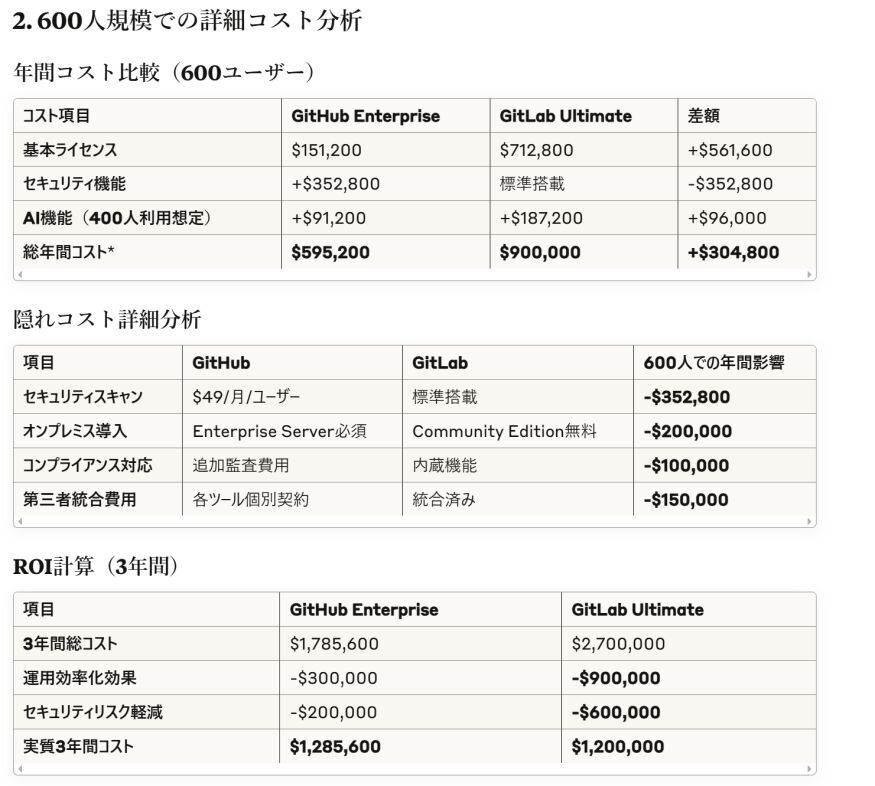
GitHubとGitLabの比較において、比較表が多用されているのも一目で結果を把握したい場合に大変役立ちます。単純なデザインではありますが、このような比較表は他のツールよりも多く出力されていました。
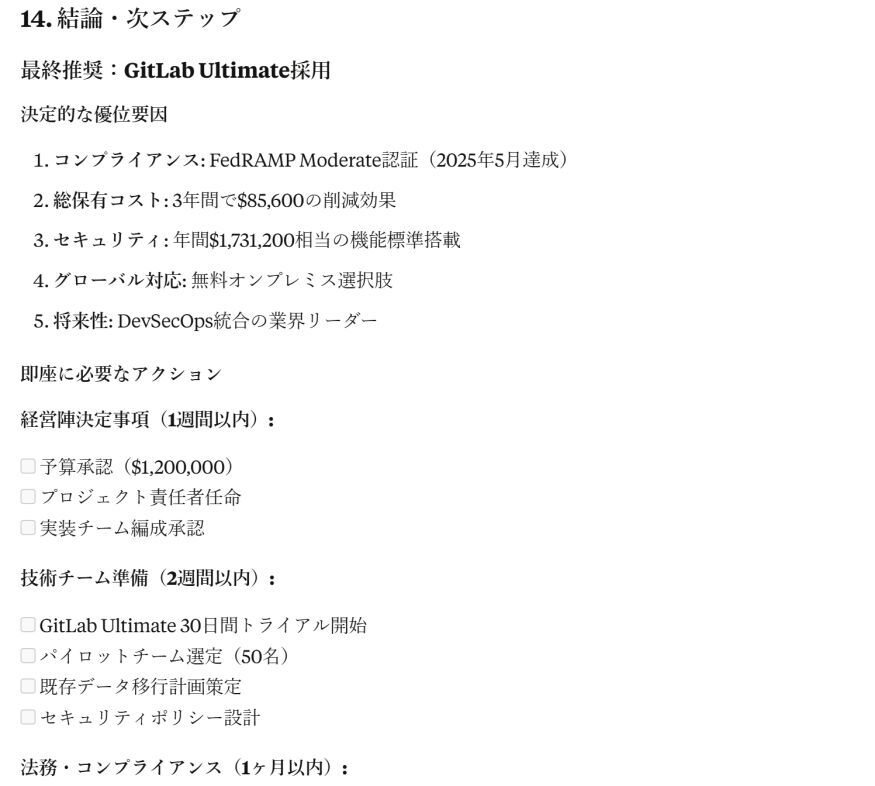
加えて、各比較内容において「ユーザーの状況にマッチする結論」をしっかりと言及してくれているため、聞き返しの質問の多さがしっかりと良い影響を与えているなと感じました。アクションの提案も、こちらの状況を把握しているからこその提案が散りばめられています。
先ほどのエグゼクティブサマリーについても言えることですが「ユーザーの要望をどれだけ汲み取ってくれているか?」という点で、Claudeは一歩抜けている印象を受けました。

ただし、細かく見ると、星取表の理由についての言及がなかったり(あったとしても表にも記載して欲しかった)と、一部不満は残る結果となりました。
Gemini (参考ソース数:67)
金額の安さや聞き返しがなかった点と合わせても「さくっと調べたい」であったり「リサーチ機能を試してみたい」というニーズにしっかり答えてくれている印象です。
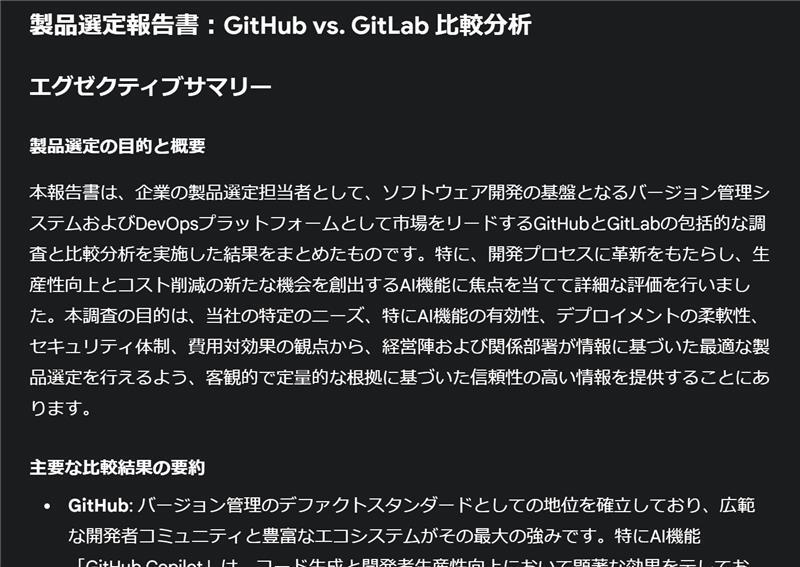
内容も教えていない会社の体制を考える考慮不足は否めませんが、こちらもエグゼクティブサマリーが冒頭に出力されており、一般的な比較であれば、このまま報告書として採用しても遜色ないレベルです。
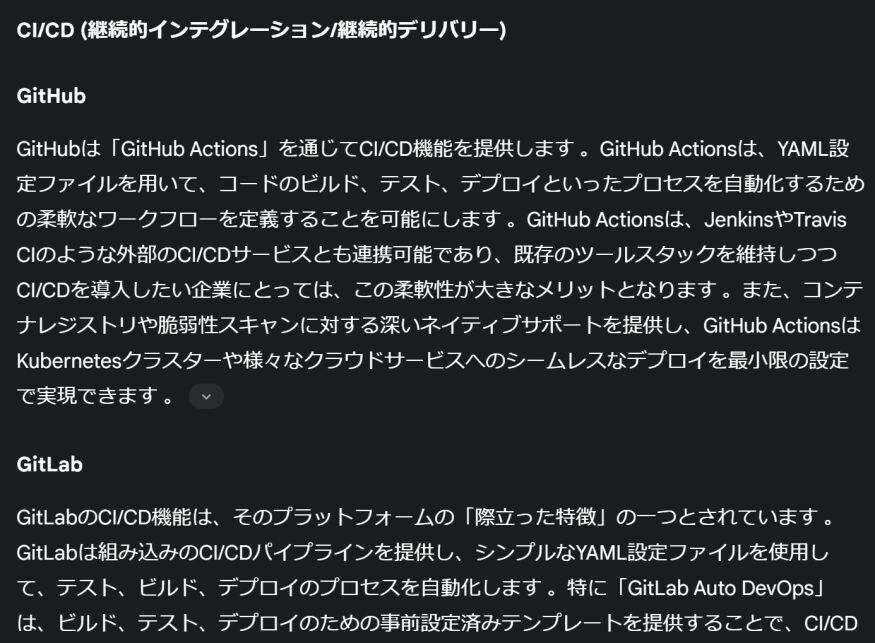
主要機能ごとの比較が文章でしっかり説明されている点もポイントが高いです。この辺りは実際に使ってみないと分からない部分も多くあるので、客観性を持って出力してくれるのは大変助かります。
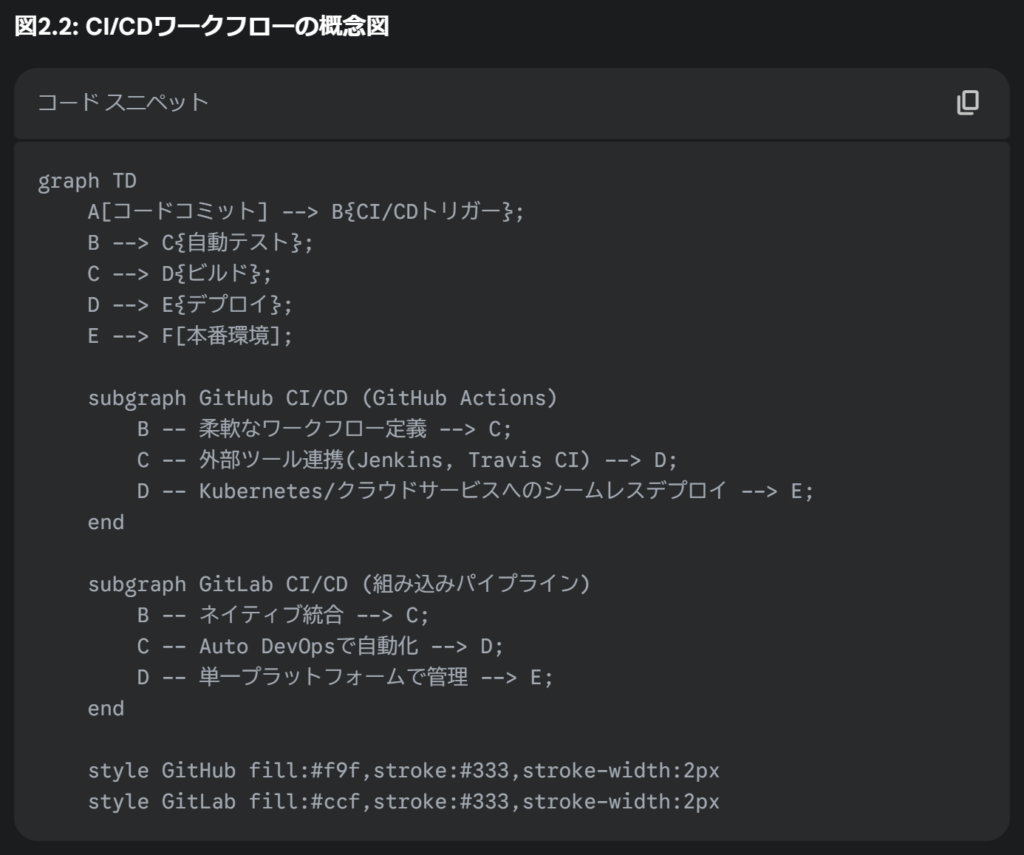
グラフィカルな挿絵がコードも含めて採用されているため、別の資料に添付する場合にも応用が利くようになっています。
また、今回は直接のリサーチ結果比較のため割愛していますが「Canvas」機能を利用すれば、このリサーチ結果をワンクリックで様々なタイプの資料に変換できるというのはかなり高ポイントです。ビジュアライズ化が必要な場合、他ツールだとワンクッション挟む(別ツールへ委譲する)ことが多いため、1ツールでの完結はユーザー体験の向上に大きく貢献すると考えられます。
ただし、追加質問がなかった影響か「ユーザーの現状」を把握しておらず、海外拠点のような要素についても言及できていないため、このままでは少々情報不足になる可能性があります。
Microsoft 365 Copilot (参考ソース数:12)
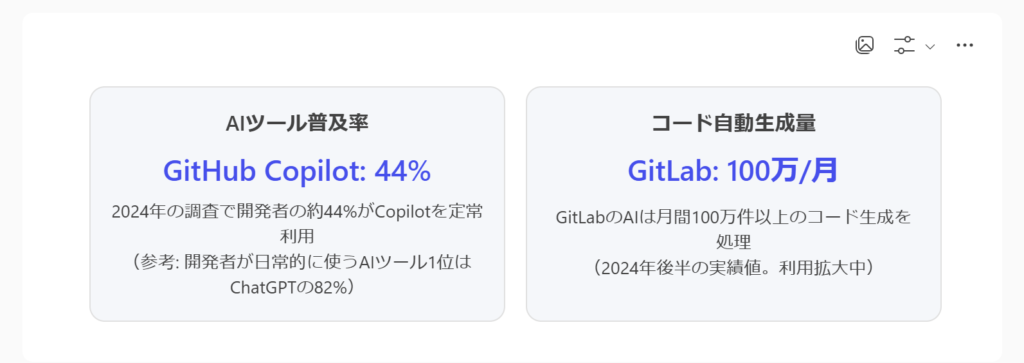
グラフや図の差し込みが他のツールよりも洗練されており、数も多く、出力された文章の読みやすさとしては個人的に一位であると感じました。この辺りはさすがMSというべきでしょうか。
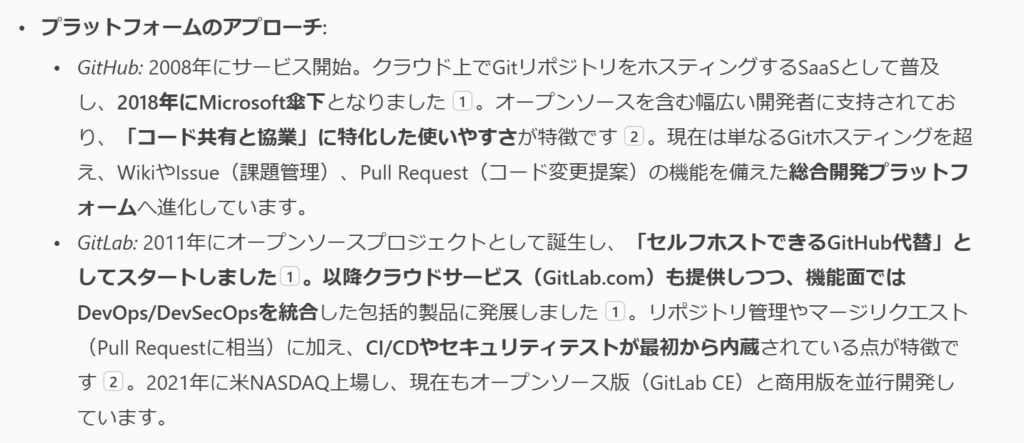
出力された文章も、全体的に他ツールよりも「非エンジニアでも読みやすい/理解しやすい」内容になっていました。具体的には、専門用語(特に英語表記の単語)に対する日本語での追記が行われている部分などは、読み手を限定しないという配慮を感じました。
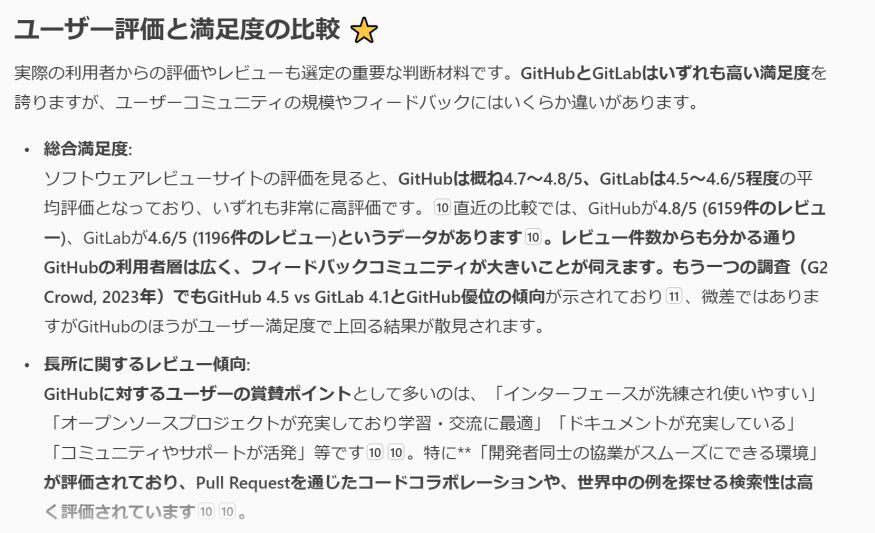
それ以外にも、項目として「ユーザー評価」や「満足度」の比較といった、他ツールでは出力されなかった内容が充実しており、この辺りはビジネスに対する理解度の高さを感じました。やはりこのような内容があると説明もしやすいですよね。内容も納得できるものでした。
しかし、逆を返すと技術的な深掘りは他ツールに比べて薄い印象です。どちらかというとビジネス観点やユーザー評価がメインとして出力されていました。もちろん、今回のプロンプトに依存する部分もありますが、もう少し技術的な観点からの深掘りが欲しかった、と個人的には感じました。そしてやはり、追加質問に意味はあったのだろうか…?(0とは言いませんが)という疑問は残ります。
各製品の感想
ということで、それぞれの出力結果についての感想を発表していこうと思います!この評価はあくまで「審判=私(人間)」のため、個人的趣向や偏見もある中での感想になりますが、なるべく公平を意識して、それぞれのキャッチコピーと総評を書かせていただきます!
ChatGPT
「誰でも、知識がなくても、いい感じの結果を与えよう」
さすが老舗だけあって、安定した結果を得ることができました。聞き返しも漏れが少ないかつ難易度が高くなく、要点を押さえた出力となりました。誰もが使いやすい機能になっていると感じます。調査内容の深さも出力内容も、個人的には最も好ましかったです。
出力結果のビジュアライズについては、若干シンプルを極めている部分はありますが、その点を鑑みても「まずは最初に使ってみるリサーチ機能」としては、ぴったりではないでしょうか。
Claude
「ユーザーファーストで補ってくれる、シンプルイズベスト」
聞き返し数の多さから「ユーザーの思考をしっかり反映させたい」という意思を感じました。出力された結果も具体的な導入スケジュールが計画されていたりと、最もユーザーを補佐してくれるツールだと感じました。出力も比較表が多く用いられ、シンプルながら洗練された出力でした。
逆に言えば「ユーザーがちゃんと考えられていない」場合には、その真価を発揮しきれない可能性が最も高い製品ともいえるかもしれません。
Gemini
「安い!手軽!応用可!だけどちゃんと教えてね!」
出力結果の各種ビジュアライズ変換(スライドやHTMLなど)まで一気通貫で行えるという手軽さは、他には代えがたいポイントです。そのため「出力結果をもとに色々と展開したい」という場合は、Geminiを使っておけばハードルがぐっと下がります。
しかし、出力結果については聞き返しがないため「ユーザー主観」のデータになっておらず、内容によっては「ユーザー自身の要望をどれだけはっきりプロンプトに反映できるか」が最も試されるツールだと感じました。とはいえ、やはり安い。しかもワンクリックでビジュアル化できる。このメリットは外せないポイントだと思います。
Microsoft 365 Copilot
「エンプラ利用ってこういうことでしょ、任せな」
視点が他の3つに比べて、明らかにエンタープライズ寄りでした。そもそも企業ユースのグループウェアの一部であるため、それに合わせた何かしらの調整がされているのかもしれません。さすがです。
挿絵的に挟まれる画像もパワーポイントにそのまま持っていけるようなレイアウトですし、出力結果にアイコンが最も多用されている点からも、ITに深く精通していないJTCのような会社(表現としてはあまりよろしくないですが、あえてこのような表現とさせていただきます)で、特に「ウケる出力」になっていると感じました。
個人的AIリサーチ最強を発表!
では、この評価をもとに個人的なランキングを発表していこうと思います!
個人的なランキングということで、今回は「AIに関する前提知識がある程度あるエンジニア目線」での評価となりますことをご容赦ください。その他、若干主旨からはズレてしまいますが、リサーチ以外の機能や拡張性等も考慮した内容になっています。
| 順位 | 製品 |
|---|---|
| 1位 | 👑 Claude 👑 |
| 2位 | ChatGPT |
| 3位 | Gemini |
| 4位 | Microsoft 365 Copilot |
やはり、聞き返しの鋭さとユーザー観点を捉えようとする姿勢が個人的に高評価かつ内容の充実さでClaudeを1位とさせていただきました!ある程度AIへの理解がある前提のツールであるという点はありますが、その部分が問題ないのであれば、いくらでも活用可能だと感じます。他ツールとの連携も柔軟に対応しているため、データ連携や出力結果の加工も可能であることを考慮すると、やはり優秀であるといえるのではないでしょうか。
ただし、逆に言えば「前提知識がない or セキュリティ要件的な連携やそもそものツールインストールが不可」である場合、このランキングはひっくり返ったり、激しく入れ替わったりします。特に、Microsoft 365 CopilotやGeminiは「すでにある環境」で動作できる可能性が高いため、導入ハードルや連携ハードルが低くなっており、この部分に対するメリットは重大です。
そして、このようなランキングを作成してはいますが、思った以上の接戦でした!正直僅差です!今回の結果に関しては大きく誤った情報などもなく(ものすごく詳細にチェックしているわけではないので100%正しいとは限りませんが)、どのツールも自分で調べるよりも格段に素晴らしい結果を出力してくれました。やはりリサーチ機能は素晴らしいですね。
まとめ
いかがだったでしょうか?個人的には、このように改めて比較してみることで「それぞれのツールの性格」が明らかになった気がしてとても楽しかったです。
同時に、同じリサーチ機能であっても「そのツールがどういう特性を持っているか」を理解することで、今の自分やリサーチ内容に最も適したツールを選べるようになると感じました。もちろん、こういったことはAIツールに限った話ではありませんが、今後も色々と比較していきたいと思います!
投稿 【徹底比較】Deep Research 頂上決戦!リサーチ最強のAIはどれ?(前編) は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 AI時代の規制対応戦略とは?欧州フィンテック市場に見るAI規制の今後 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>欧州では「GDPR第22条」の明確化や「EU AI法」の制定などにより、AIを活用したシステムに厳格な規制が適用されるようになったことで、フィンテック企業は根本的なビジネスモデルの見直しを迫られている状況です。
本記事では、フィンテック領域における欧州での最新規制動向についての解説に加えて、今後のBtoB企業が取るべきAI規制への対応戦略についても詳しく解説していきます。
※ 本記事は米国の『G2.com』からコンテンツ提供を受けて掲載しています。
参照:G2 Research – Striking a Balance Between Fintech Innovation and EU Consumer Protection in the AI Era
フィンテック市場の現状と課題
近年の欧州フィンテック市場は、急激な成長を続ける一方で、資金調達は厳しい市場へと変化しています。市場の現状数値からもわかる通り、フィンテック業界が直面している課題は明確です。
| 年度 | 欧州フィンテック投資額 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 2022年 | 153億ユーロ | ユニコーン企業の約22%がフィンテック企業 |
| 2023年 | 46億ユーロ | 金融市場の逼迫と高リスク投資からのシフト |
2022年には153億ユーロあった投資額から、2023年には46億ユーロへと投資額が激減しており、これは金融市場の逼迫と高リスク投資から安定型投資へのシフトが原因であると考えられます。
こうした市場の悪化により、多くのフィンテック企業にとってコスト削減と効率化が最優先課題となった結果、AIを活用した「代替信用スコアリングモデル」の導入に注目が集まりました。
▶ 参照 : Statista – Fintech market in Europe
代替信用スコアリングモデルの台頭
現代のフィンテックサービスは、毎日何十億回もの計算処理を支える人工知能(AI)システムと機械学習(ML)技術なくしては成立せず、その中核となるシステムが代替信用スコアリングモデルです。
代替信用スコアリングとは?
代替信用スコアリングモデルとは、AIや機械学習(ML)技術を活用して信用評価の効率を高めることができる画期的なソリューションです。この技術は、従来の金融データに依存しない新しい信用評価手法として、近年フィンテック業界の主流となりつつあります。
| 評価手法 | データソース | 評価に要する時間 | 対象者の範囲 |
|---|---|---|---|
| 従来型の信用評価手法 | 金融取引の履歴に限定 | 長い | 金融履歴保有者のみに限定 |
| 代替信用スコアリング | 多様なデジタルデータ | 短い | 金融履歴非保有者にも適用 |
この信用評価手法により、金融取引履歴が少ない若年層や新興国の消費者に対しても適切な信用評価が可能になります。また、コスト削減が求められるフィンテック企業にとっては、人的リソースの大幅な削減を見込めるため、費用対効果の高いソリューションとして注目が集まっている背景があります。
代替信用スコアリングで活用されるデータ
従来の信用評価では、銀行の取引履歴やクレジットカードの利用実績といった限定的なデータのみが活用されていましたが、AI技術の発展にともない、現代のフィンテック企業では、以下のような多様なデータを活用しながら個人の信用情報をスコアリングしています。
| データカテゴリ | 具体例 | 評価要素 |
|---|---|---|
| デジタルフットプリント | ウェブサイト閲覧履歴、検索履歴 | オンライン行動パターン |
| ソーシャルメディア | Facebook、X(Twitter)、Instagram | 社会的な接点と影響力 |
| モバイルデータ | アプリ利用状況、位置情報 | 生活パターンと安定性 |
| 公共料金支払い | 電気、ガス、水道料金の支払い履歴 | 基本的な支払い能力 |
| 通信履歴 | 電話番号、メールアドレス | 本人確認と安定性 |
上記のような膨大な非構造化データを処理するためには、AIや機械学習アルゴリズムの利用が不可欠であり、これらの技術によって、従来では不可能だった包括的な信用評価が実現されています。
代替信用スコアリングが直面している課題
上記の通り、代替信用スコアリングは、従来の信用評価手法の弱点とされていた「対象範囲の限定性」や「評価時間の長期化」などを克服することができる革新的なソリューションではあるものの、評価精度は学習データの品質に依存するといった重大な課題も存在します。
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| 学習データのバイアスも継承する | 過去のデータに含まれる偏見や差別的要素も学習してしまう |
| プロセスのブラックボックス化する | 意思決定のプロセスが不透明となるため承認可否の説明が困難 |
| 動的な適応学習は管理が難しい | システムが継続的に学習し変化するため一定の品質保証が困難 |
| 人間による介入が排除されてしまう | 効率化を追求してしまうと人間の判断が入る余地が限定される |
この結果「なぜある人はローンを承認され、ある人は却下されるのか?」という基本的な疑問に対する明確な説明ができない状況が生まれてしまうため、AIシステムの健全性と公正性を確保するためにも、人間による監視や介入体制の構築が重要な課題となっているわけです。
フィンテック領域におけるAI規制の動き
代替信用スコアリングの課題が浮き彫りになっている現状、人権や個人情報の保護観点から、自動化された信用評価システムを規制しようとする動きも活発化を見せています。
GDPR第22条の存在
一般データ保護規則(GDPR)第22条では、個人に対して以下の権利が保障されており、この条文の存在は、フィンテック企業と金融機関が用いる代替信用スコアリングの利用において問題となる可能性が指摘されていました。
The data controller shall implement suitable measures to safeguard the data subject’s rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and to contest the decision.
「データ管理者は、データ主体の権利、自由、正当な利益を保護するために適切な措置を講じなければならない。少なくとも、データ管理者側による人的介入を得る権利、自身の見解を表明する権利、決定に異議を申し立てる権利を保護するものとする。」
C-634/21事件のECJ判例
ただし、これまでこのGDPR第22条は単に条文が存在しているだけで、具体的に代替信用スコアリングが違反状態であるかについては意見が分かれる状態が続いており、また具体的な罰則規定なども明文化されていませんでした。
そうした状況の中、2023年12月に発生したSCHUFA事件(通称C-634/21事件)において、欧州司法裁判所(ECJ)は、初めてAIを活用したビジネスモデルのデータ保護義務について公式な見解を示しました。
| C-634/21事件におけるECJ判決の要点 |
|---|
| 信用スコアの自動生成は自動化された個人意思決定に該当 |
| 信用照会機関と貸し手の両方がGDPR第22条の義務を負う |
| 人間によるAI承認プロセスの監視と介入の仕組みが必須 |
EU AI法の存在
欧州において、GDPR第22条と並んで忘れてはならないのが「EU AI法」の存在です。2023年12月9日に暫定合意が成立したEU AI法では、AIシステムの利用に関する包括的な枠組みとして、以下の6つの一般原則が定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人間の主体性と監督 | AIシステムに対する人間の適切な監視 |
| 技術的堅牢性と安全性 | AIシステムの信頼性と安全性の確保 |
| プライバシーとデータガバナンス | 個人データの適切な保護と管理 |
| 透明性 | AIシステムの動作に関する適切な情報提供 |
| 公平性 | バイアスや差別の排除 |
| 社会的福祉 | 持続可能な発展への貢献 |
| 対策項目 | 実装内容 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 人間による介入権の保障 | 審査プロセスへの人的レビューの導入 | 機械的判断の修正機会を提供 |
| 意見表明権の確保 | 顧客からの異議受付体制の構築 | 個人の主張を反映する仕組み |
| 決定理由の説明責任 | 判定根拠の可視化システムの導入 | 透明性の向上と信頼の構築 |
| データ処理の透明化 | 利用データと処理方法の開示 | プライバシー保護の強化 |
フィンテック企業が取るべき今後の対応
ECJの判例とEU AI法の影響は、フィンテック企業や金融機関にとっては極めて重大です。企業は今後、スコアリング手法における透明性の担保はもちろん、人間による介入を求める権利や自動化された決定に異議を申し立てる権利など、個人を保護するための対策が国際的なスタンダードになっていきます。
規制遵守に向けたアクションプラン
短期戦略(6ヶ月以内)
| 対応項目 | 実施内容 | 優先度 |
|---|---|---|
| 現状システムの評価 | 既存AIシステムの規制適合性の監査 | 高 |
| 人的監視体制の構築 | AI判定への人間レビュー体制の確立 | 高 |
| 顧客対応窓口の設置 | 異議や説明要求への対応体制の構築 | 高 |
| 法務体制の強化 | AI規制に詳しい専門家チームの設置 | 中 |
中期戦略(6ヶ月〜2年)
| 対応項目 | 実施内容 | 優先度 |
|---|---|---|
| システムの改修 | 評価プロセスの説明が可能なAI技術(XAI)の導入 | 高 |
| プロセスの最適化 | 人間の判断と機械学習の最適な組み合わせを模索 | 高 |
| 学習品質の管理 | 継続的な学習バイアス監視と修正システムの構築 | 中 |
| 専門人材の育成 | 規制対応とAI技術の両方に精通した専門人材の確保 | 中 |
長期戦略(2年以上)
| 対応項目 | 実施内容 | 優先度 |
|---|---|---|
| 技術革新 | プライバシー保護技術との統合 | 高 |
| 国際展開 | 他地域の規制動向への対応準備 | 中 |
| 業界標準化 | 業界団体との協力による最適解の模索 | 中 |
まとめ:イノベーションと規制遵守の両立が鍵
本記事では、フィンテック領域における欧州での最新規制動向についての解説に加えて、今後のBtoB企業が取るべきAI規制への対応戦略についても詳しく解説していきました。
前述の通り、GDPR第22条の明確化とEU AI法の制定により、フィンテック業界は新たな規制環境へ適応していく必要があります。今後のフィンテック企業の成功は、規制の遵守とイノベーションの両立にかかっているといっても過言ではないでしょう。
こうした変化は一時的なコストの増加をもたらしますが、長期的には消費者の信頼向上とサステナブルな業界発展につながります。重要なのは「規制を制約として捉えるのではなく、より良いサービスを提供するための指針」として活用することです。
これはフィンテック領域だけの話ではなく、いつの時代も成功する企業は、法務と技術の専門知識を統合し、段階的かつ戦略的なアプローチで規制対応を進めていく企業です。今後数年間はフィンテック業界にとって重要な時期となるでしょう。
投稿 AI時代の規制対応戦略とは?欧州フィンテック市場に見るAI規制の今後 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【年代・職種・役職別】ビジネス情報収集の最新トレンドを徹底分析! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>令和7年にITreviewが実施した『ビジネス情報収集活動における意識調査アンケート』の報告によると、AIツールの利用率は3年前と比較して33ポイント増加したことが明らかになりました。
一方で、Google検索は依然として最も利用される情報収集手段として君臨し、X(旧Twitter)やInstagramをはじめとする各種SNS、YouTubeなどの動画メディアも着実に存在感を増しています。
前回に引き続き、今回は現代の主要な情報収集手段である「Google検索・AI検索・SNS」の利用状況を年代別・職種別・役職別に詳しく分析し、それぞれのレイヤーに合った情報収集手段を模索していきます。
▶ 前回の記事:【Google検索 vs AI検索 vs SNS】ビジネス情報収集の過去と現在を徹底分析!
【年代別の分析】若年層になるほどAIとSNSを積極的に活用している
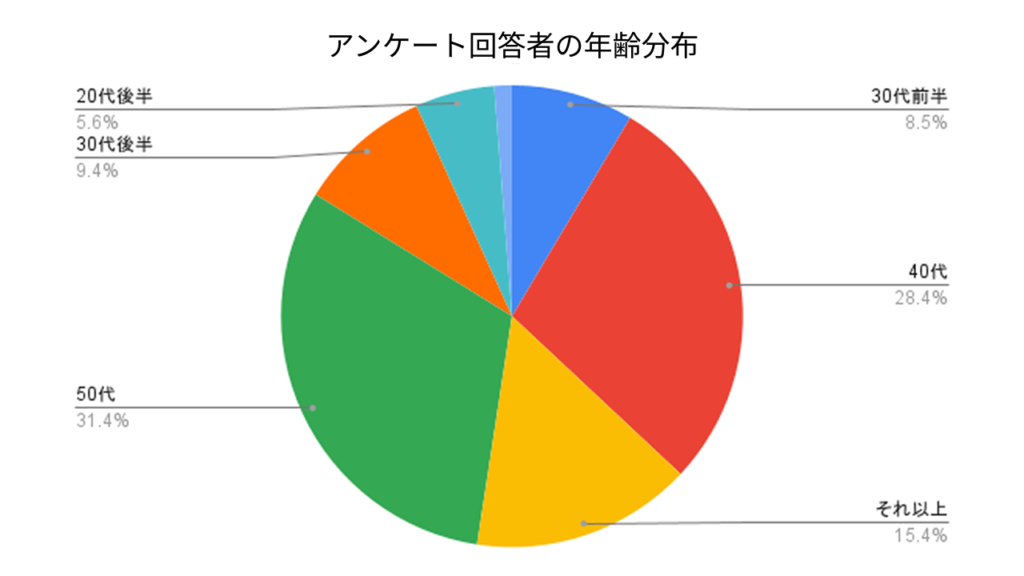
| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代前半 | 12人(1.2%) | 91.7% | 50.0% | 58.3% | 16.7% | 33.3% | 8.3% | 25.0% |
| 20代後半 | 54人(5.6%) | 87.0% | 59.3% | 48.1% | 27.8% | 29.6% | 13.0% | 14.8% |
| 30代前半 | 83人(8.5%) | 86.7% | 53.0% | 39.8% | 27.7% | 36.1% | 16.9% | 19.3% |
| 30代後半 | 91人(9.4%) | 92.3% | 53.8% | 35.2% | 17.6% | 38.5% | 19.8% | 18.7% |
| 40代 | 276人(28.4%) | 87.3% | 46.7% | 34.8% | 29.3% | 45.7% | 23.2% | 21.0% |
| 50代 | 305人(31.4%) | 86.2% | 43.3% | 14.1% | 19.7% | 50.8% | 31.1% | 22.6% |
| それ以上 | 150人(15.4%) | 90.7% | 44.7% | 16.7% | 27.3% | 58.0% | 38.0% | 19.3% |
20代の利用メディアの傾向:AI検索とSNSが全年代で最多
| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代前半 | 12人(1.2%) | 91.7% | 50.0% | 58.3% | 16.7% | 33.3% | 8.3% | 25.0% |
| 20代後半 | 54人(5.6%) | 87.0% | 59.3% | 48.1% | 27.8% | 29.6% | 13.0% | 14.8% |
20代の利用メディアの傾向については、AI検索とSNSの利用率が他の年代と比べて高い傾向にあり、適応力や柔軟性の高さが表れた結果となりました。また、比較サイトの利用率も全年代の中では比較的高く、全体を通して情報収集活動そのものの効率化に重きを置いていることがわかります。
30代の利用メディアの傾向:Google検索が全年代で最多
| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30代前半 | 83人(8.5%) | 86.7% | 53.0% | 39.8% | 27.7% | 36.1% | 16.9% | 19.3% |
| 30代後半 | 91人(9.4%) | 92.3% | 53.8% | 35.2% | 17.6% | 38.5% | 19.8% | 18.7% |
30代の利用メディアの傾向については、Google検索を情報収集活動の基盤としている傾向にあり、確立された検索エンジンへの信頼度の高さが表れた結果となりました。下の年代と比較して、娯楽性よりも実用性、拡散性よりも信頼性を重視した情報収集パターンに変化していることが読み取れます。
40代の利用メディアの傾向:YouTubeが全年代で最多
| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40代 | 276人(28.4%) | 87.3% | 46.7% | 34.8% | 29.3% | 45.7% | 23.2% | 21.0% |
40代の利用メディアの傾向については、ビジネス情報の収集にYouTubeを積極活用する傾向にあり、この年代にとっては娯楽のツールではなく、実用的な学習ツールとして機能していることがわかりました。データからもわかるように、各メディアを比較的バランスよく活用しているのが特徴です。
50代以上の利用メディアの傾向・特徴:メールとニュースが全年代で最多
| 年代 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50代 | 305人(31.4%) | 86.2% | 43.3% | 14.1% | 19.7% | 50.8% | 31.1% | 22.6% |
| それ以上 | 150人(15.4%) | 90.7% | 44.7% | 16.7% | 27.3% | 58.0% | 38.0% | 19.3% |
50代以上の利用メディアの傾向については、ニュースやメールなどを好んで利用する傾向にあり、情報の信頼性や情報源の権威性を重視していることがわかりました。AI検索については他の年代よりも利用率が低いものの、それでも4割以上のAI利用者がいることは注目に値する結果といえるでしょう。
【職種別の分析】研究開発職とマーケティング職でAIの活用が進む
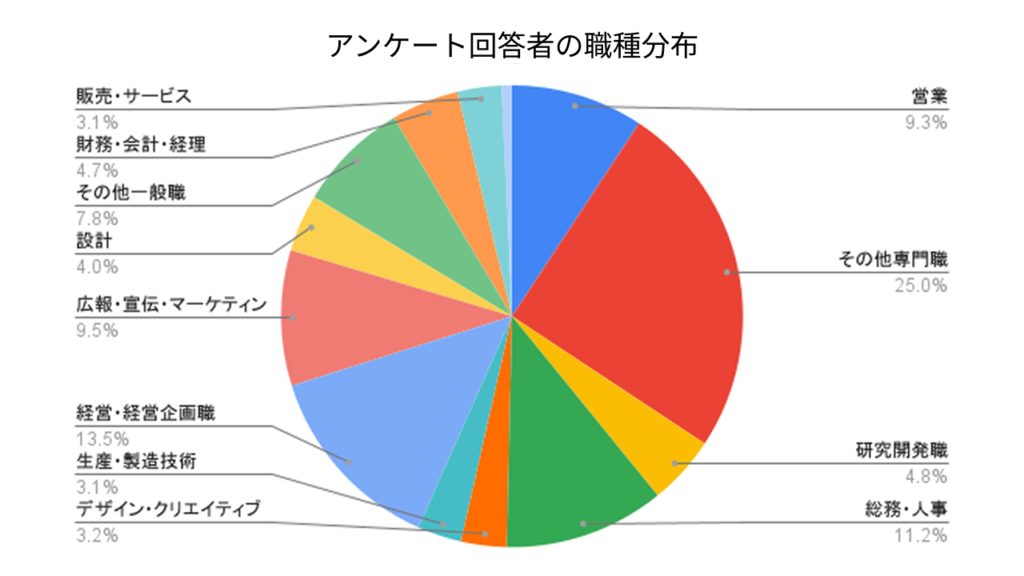
| 職種 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| その他専門職 | 243人(25.0%) | 88.5% | 42.8% | 18.1% | 16.5% | 50.6% | 27.6% | 25.5% |
| 経営・経営企画職 | 131人(13.5%) | 82.4% | 47.3% | 37.4% | 35.9% | 51.9% | 26.7% | 16.0% |
| 総務・人事 | 109人(11.2%) | 90.8% | 49.5% | 21.1% | 29.4% | 40.4% | 21.1% | 26.6% |
| 広報・宣伝・マーケティング | 92人(9.5%) | 89.1% | 58.7% | 40.2% | 23.9% | 44.6% | 23.9% | 23.9% |
| 営業 | 90人(9.3%) | 91.1% | 47.8% | 34.4% | 31.1% | 50.0% | 26.7% | 20.0% |
| その他一般職 | 76人(7.8%) | 85.5% | 46.1% | 26.3% | 17.1% | 44.7% | 31.6% | 10.5% |
| 研究開発職 | 47人(4.8%) | 87.2% | 61.7% | 19.1% | 17.0% | 53.2% | 21.3% | 12.8% |
| 財務・会計・経理 | 46人(4.7%) | 87.0% | 34.8% | 15.2% | 19.6% | 34.8% | 10.9% | 23.9% |
| 設計 | 39人(4.0%) | 92.3% | 43.6% | 20.5% | 23.1% | 30.8% | 38.5% | 12.8% |
| デザイン・クリエイティブ | 31人(3.2%) | 93.5% | 48.4% | 45.2% | 32.3% | 41.9% | 25.8% | 19.4% |
広報・宣伝・マーケティング職の利用メディアの傾向・特徴
- AI検索の利用率が高い (58.7%)
- SNSの利用率が高い (40.2%)
- 情報鮮度とトレンド把握が重要な職種特性を反映
広報・宣伝・マーケティング職は特に注目すべき傾向を示しています。AI検索の利用率が58.7%と比較的高い数値であり、SNSの利用率も40.2%と高い水準を叩き出しています。
これは、情報鮮度とトレンド把握が業務の核心となる職種特性を反映しており、新しい技術や情報源への積極的な姿勢が見て取れます。マーケティングの現場では、消費者の動向や競合の戦略を即座に察知する必要があり、そのために多様なチャネルを活用していることがわかりました。
デザイン・クリエイティブ職の利用メディアの傾向・特徴
- SNSの利用率が高い (45.2%)
- メールの利用率が高い (25.8%)
- 創作活動における多角的な情報収集の必要性を示唆
デザイン・クリエイティブ職の情報収集行動も興味深い見解を示しています。メールの利用率が25.8%と比較的高いのは、クリエイター同士の情報交換が活発であることを示唆しています。
また、視覚的なインスピレーションやデザイントレンドを求める職種特性を反映しているからか、SNSの利用率も45.2%と最も高い水準を誇っており、InstagramやPinterest、Behanceといったビジュアル重視のプラットフォームから最新のクリエイティブ動向を収集していることがうかがえます。
財務・会計・経理職の利用メディアの傾向・特徴
- AI検索の利用率が低い (34.8%)
- SNSの利用率が低い (15.2%)
- 確実性を重視する職種特性が情報源の選択にも影響か
財務・会計・経理職は極めて保守的な情報収集パターンを示しています。AI検索の利用率は34.8%と最も低い利用率であり、SNSに関しても15.2%と全職種で最も低い利用率でした。
これは、情報に対する正確性と信頼性を何よりも重視する職種特性を反映しており、より正確な情報を求めるリテラシーの高さが読み取れます。財務関連業務では、誤情報のリスクを最小化することが重要であり、確立された情報源への依存傾向が強いのは自然な結果といえるでしょう。
【役職別の分析】経営層や管理職層でもAIツールの活用が広がる
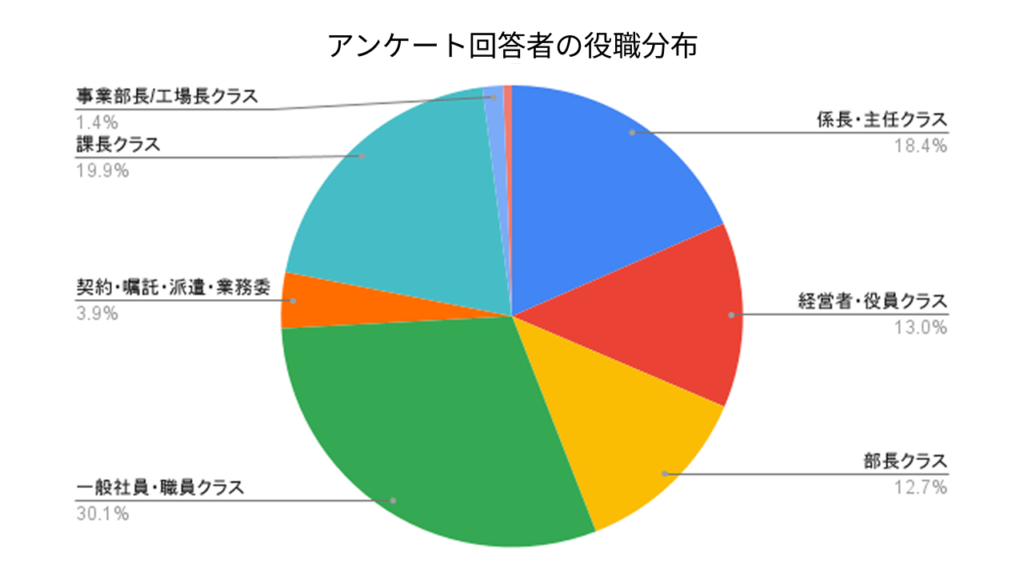
| 役職 | 回答者数 | Google検索 | AI検索 | SNS | YouTube | ニュース | メール | 比較サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般社員クラス | 292人(30.1%) | 86.3% | 46.2% | 29.1% | 22.9% | 41.8% | 24.0% | 20.5% |
| 係長クラス | 179人(18.4%) | 92.2% | 50.8% | 23.5% | 24.0% | 45.3% | 22.3% | 20.1% |
| 課長クラス | 193人(19.9%) | 85.5% | 44.6% | 25.4% | 21.2% | 47.2% | 30.6% | 22.8% |
| 部長クラス | 123人(12.7%) | 90.2% | 53.7% | 22.8% | 27.6% | 54.5% | 33.3% | 22.0% |
| 事業部長クラス | 14人(1.4%) | 92.9% | 64.3% | 28.6% | 28.6% | 64.3% | 28.6% | 42.9% |
| 経営者クラス | 126人(13.0%) | 86.5% | 40.5% | 31.7% | 32.5% | 46.8% | 24.6% | 17.5% |
一般社員クラス
- Google検索の利用率が低い (86.3%)
- AI検索の利用率が低い (46.2%)
- 日常的な業務に直結する情報収集が中心
一般社員クラスは、与えられた業務を確実に遂行することが主眼となるため、日常的な業務の遂行にあたって必要最小限の情報収集に依存する傾向があります。
Google検索の利用率が86.3%と他の階層よりも低いのは、日常業務が定型化されており、新たな情報を積極的に収集する必要がないためと考えられます。また、AI検索の利用率46.2%という数値も、複雑な分析や戦略的思考を求められる場面が少なく、基本的な事実確認レベルの情報収集で十分であることを物語っています。
係長クラス
- Google検索の利用率が高い (92.2%)
- AI検索の利用率が中程度 (50.8%)
- 現場と上層部を繋ぐ役割で幅広い情報収集が必要
係長クラスは、現場の実務と上層部の方針を繋ぐ重要な役割を担っているため、上司からの指示を部下に適切に伝達するために幅広い情報収集が不可欠となります。
Google検索の利用率が92.2%と他の階層よりも高い水準を誇っており、単純な情報検索だけでなく、ある程度の分析的思考が求められることを示しています。また、AI検索の利用率50.8%という数値は、この階層が上下のコミュニケーションを支えるために、最も積極的な情報収集姿勢を取っていることが読み取れます。
課長クラス
- Google検索の利用率が低い (85.5%)
- AI検索の利用率が低い (44.6%)
- 管理職の中では控えめな情報収集パターンが特徴
課長クラスは、意外にも控えめな情報収集パターンを示しており、自ら情報を収集するよりも組織内の情報フローの管理に重点を置いている可能性が考えられます。
Google検索の利用率85.5%、AI検索の利用率44.6%という数値は、他の管理職層と比較して低い水準にあります。これは課長職が実務と管理のバランスを取る微妙な立場にあり、部下と上司の中間で情報を処理する役割が中心となっているためと推測されます。この階層では情報の量よりも質と判断力が重視されているのかもしれません。
部長クラス
- AI検索の利用率が高い (53.7%)
- YouTubeの利用率が高い (27.6%)
- 戦略的な事業判断に必要な情報源を幅広く収集
部長クラスは、事業部門全体の方向性を決定する責任があるため、視覚的な理解を促進する動画コンテンツも重要な情報源として活用していることがうかがえます。
AI検索の利用率53.7%は、複雑な事業環境を分析し、データに基づいた戦略的判断を求められることの現れといえるでしょう。また、YouTubeの利用率は27.6%と全階層中で最も高い数値を誇っており、これは動画コンテンツから業界のトレンドや新しい技術の動向を把握し、競合他社の戦略を研究する必要性があることを示しています。
事業部長クラス
- AI検索の利用率が高い (64.3%)
- 比較サイトの利用率が高い (42.9%)
- 全ての情報源で高い利用率を示す情報収集のプロ
事業部長クラスは、データに裏付けられた合理的な意思決定が強く求められるため、文字通り「情報収集のプロフェッショナル」としての側面を強く示しています。
AI検索の利用率64.3%は、全階層の中で最高の数値であり、複雑で多面的な経営判断を支援する高度な分析能力への依存を物語っています。また、比較サイトの利用率42.9%という突出した数値は、大規模な投資や戦略的提携など、組織全体に対して重大な影響を与える決定において、客観的で詳細な比較検討を重視する姿勢を表しています。
まとめ:新しいツールに対してオープンな姿勢を持つことが重要
今回は、現代の主要な情報収集手段である「Google検索・AI検索・SNS」の利用動向を年代別・職種別・役職別に詳しく分析し、それぞれのレイヤーに合った情報収集手段を模索していきました。
特に興味深かったのは、50代以上の4割以上がAIを活用しているということです。これは、デジタルツールへの適応に年齢は関係ないことを示しており、重要なのは「年齢や役職に関係なく、新しいツールに対してオープンな姿勢を持つこと」だといえます。
ビジネス環境の変化が加速する昨今、個人の情報収集能力の差は企業そのものの競争力に直結する極めて重要な要素です。本調査の結果を参考に、ぜひ自身の情報収集スタイルを見直し、より効果的な方法を探してみてはいかがでしょうか?
▶ 前回の記事:【Google検索 vs AI検索 vs SNS】ビジネス情報収集の過去と現在を徹底分析!
投稿 【年代・職種・役職別】ビジネス情報収集の最新トレンドを徹底分析! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【Google検索 vs AI検索 vs SNS】ビジネス情報収集の過去と現在を徹底分析! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>令和7年にITreviewが実施した『ビジネス情報収集活動における意識調査アンケート』の報告によると、AIツールの利用率は3年前と比較して33ポイント増加したことが明らかになりました。
一方で、Google検索は依然として最も利用される情報収集手段として君臨し、X(旧Twitter)やInstagramをはじめとする各種SNS、YouTubeなどの動画メディアも着実に存在感を増しています。
本レポートでは、現代の主要な情報収集手段である「Google検索・AI検索・SNS」の利用状況を詳しく分析し、ビジネスシーンでの効果的な活用方法を模索していきます。
▶ 次回の記事:【年代・職種・役職別】ビジネス情報収集の最新トレンドを徹底分析!
利用率トップは依然としてGoogle検索が首位
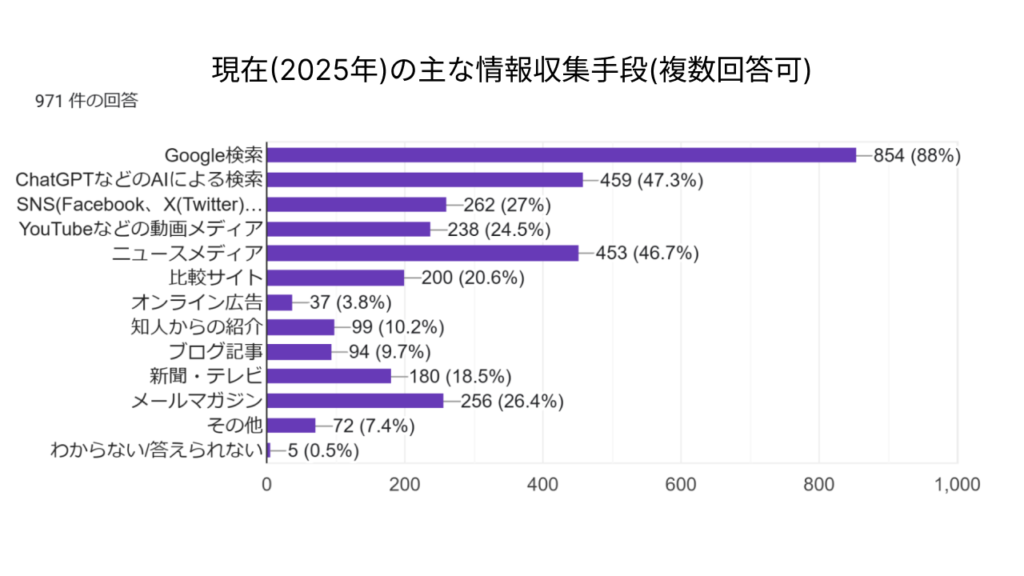
| 情報収集手段 | 利用率 | 回答者数 |
|---|---|---|
| Google検索 | 88.0% | 854人 |
| AI検索 | 47.3% | 459人 |
| ニュースメディア | 46.7% | 453人 |
| SNS | 27.0% | 262人 |
Google検索は約9割のビジネスパーソンが利用する圧倒的な主要手段として君臨しています。これは、長年培われた検索精度の高さと情報の網羅性が評価されているためと考えられます。
一方で、ChatGPTなどのAI検索が約半数の47.3%まで急成長しており、情報収集手段の新たなスタンダードとして定着しつつあることがわかります。
SNS媒体は利用率27.0%と全体の4位にランクインしており、YouTubeなどの動画メディアも24.5%(238人)と約4人に1人が活用しているような状況です。
3年前と比較してAI利用の増加が最大の変化要因
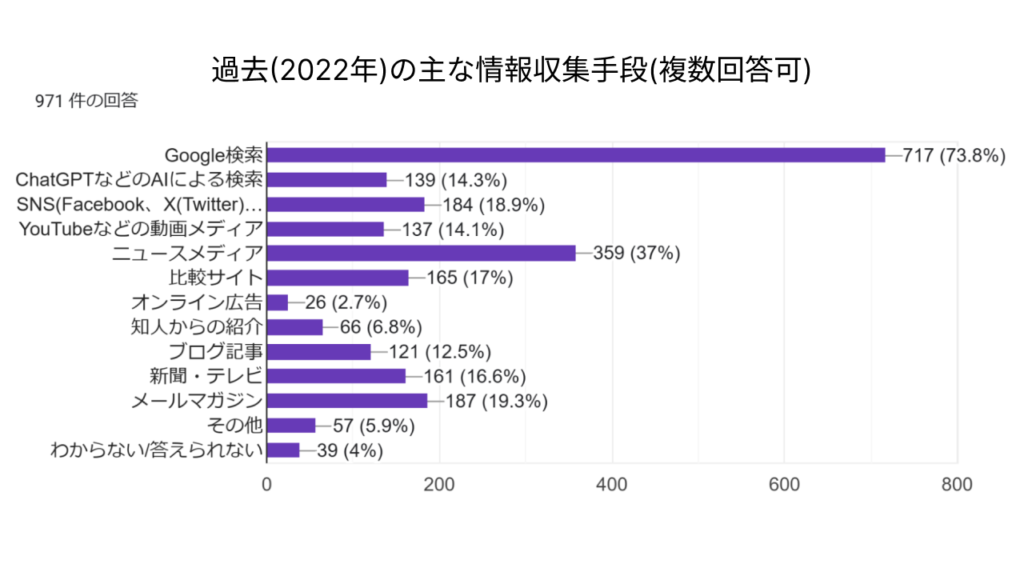
| 情報収集手段 | 変化幅 | 2025年の利用率 | 2022年の利用率 |
|---|---|---|---|
| AI検索 | +33.0ポイント | 47.3% | 14.3% |
| Google検索 | +14.2ポイント | 88.0% | 73.8% |
| 動画メディア | +10.4ポイント | 24.5% | 14.1% |
| SNS | +8.1ポイント | 27.0% | 18.9% |
最も劇的な変化はAI検索の利用率で3年前の14.3%から47.3%へと33ポイントもの増加を記録しました。ChatGPTの登場により、生成AIの認知度が高まったことが背景と考えられます。
加えて、Google検索の利用率についても14.2ポイントの増加を見せており、情報収集の基盤としての地位を強固なものにしていることがわかります。
GoogleとAIを併用するユーザーは全体の42.7%に達しており、両サービスを使い分けながら効率的な情報収集を行うスタイルが主流になりつつあるようです。
実際に利用されているサービス・メディアの詳細分析
- AIサービスの利用実態について
- SNSプラットフォームの利用実態について
- 各種ニュースメディアの利用実態について
AIサービスの利用実態:ChatGPTが圧倒的シェアを誇る
| サービス名 | 回答数 | 主な利用シーン |
|---|---|---|
| ChatGPT | 123件 | 圧倒的な利用者数と汎用性の高さが評価 |
| Gemini | 45件 | Google製AIとして検索との連携性が評価 |
| Copilot | 41件 | Microsoft製品との親和性で業務利用が進む |
| Perplexity | 14件 | 情報源を明示する検索特化型AIとして注目 |
| Claude | 3件 | 高度な文章作成能力で一部のユーザーが活用 |
AIサービスの利用実態としては、ChatGPTが123件と他社のAIツールを大きく引き離してトップとなっており、生成AIの代名詞的存在として定着していることがわかります。以降はGeminiとCopilotが40件台で続き、大手IT企業のAIサービスが上位を占める結果となりました。
SNSプラットフォームの利用実態:X(旧Twitter)が業界標準
| サービス名 | 回答数 | 主な利用シーン |
|---|---|---|
| X(旧Twitter) | 130件 | 業界キーパーソンのフォローでトレンド把握 |
| 48件 | ビジュアルコンテンツからトレンド把握 | |
| 22件 | ビジネスコミュニティでの情報交換 | |
| 4件 | 海外ビジネス情報や人材関連情報の収集 |
SNSプラットフォームの利用実態としては、X(旧Twitter)が130件とSNSのなかでも圧倒的なシェアを誇っており、SNSを活用したビジネス情報収集活動の中心的存在となっていることがわかります。業界キーパーソンのフォローやトレンド機能を活用した情報収集が多く見られました。
各種ニュースメディアの利用実態:日経とYahoo!ニュースが2強
| ニュースメディア名 | 回答数 | 主な利用シーン |
|---|---|---|
| 日経関連メディア | 139件 | 経済やビジネス情報の基本ソース |
| Yahoo!ニュース | 85件 | 幅広いジャンルの速報性重視 |
| ITmedia | 72件 | IT業界の専門情報収集 |
| NewsPicks | 17件 | 有識者のコメント付き記事で深い理解 |
各種ニュースメディアの利用実態としては、日経関連メディアが139件と堂々の利用率トップに君臨しており、日経ビジネスや日経クロストレンドなど、複数の日経メディアを使い分けている実態が明らかとなりました。Yahoo!ニュースは85件で速報性と網羅性が評価されているようです。
ただし、実際の回答からは、複数のサービスを組み合わせて利用しているという回答が多く見られたため、単一のサービスに依存しているというわけではなく、目的に応じて複数のメディアを使い分けるマルチチャネルでの情報収集スタイルが主流であることがわかります。
AIを活用するようになった具体的な理由と効果
本調査では、AIツールを使い始めた理由と具体的な効果や活用シーンについても聞き取り調査を行いました。多くの意見が寄せられたなか、ここからは実際の回答を一部抜粋して紹介していきます。
AI検索を使い始めた理由(実際の回答例)

周りから使いやすいと聞いたのが利用のキッカケです。特にChatGPTは、どんどん精度が上がっているので頻繁に利用しています。

AIによる文章校正は以前から利用していましたが、いろいろな検索もできることを知り、最近では情報収集にも使うようになりました。

AI検索は既存の検索エンジンよりも検索条件の指定を詳細に行えるので、知りたいことに対してピンポイントな回答を得ることができます。
AI検索が役に立った理由(実際の回答例)

何か情報を知りたいときは、Google検索よりもChatGPTに聞けば一瞬で回答してくれるので、とても重宝しています。

A案とB案の比較について、両方のメリット・デメリットも含めて教えてくれるので、検討のスピードが圧倒的に速くなりました。

文章生成機能のおかげで仕事の負担が大幅に軽減できたと感じます。質問の仕方によって色々な回答が出てくるので、本当に便利です。
調査を通してわかったAI時代に必要な情報収集スキル
- ①:総合的なAIリテラシーを身に付ける
- ②:情報信頼性を評価できるスキルが必要
- ③:ハイブリッド型の情報収集姿勢が主流
①:総合的なAIリテラシーを身に付ける
わずか3年でAI利用率が3倍以上に増加した事実からもわかる通り、AIリテラシーは今後のビジネスパーソンにとっての必須スキルです。AIとの対話を通じて新たな視点を得るなど、AIを「検索の代替」としてだけでなく「思考のパートナー」として活用することが重要です。
②:情報信頼性を評価できるスキルが必要
多様な情報源を活用する現代において、今後は情報の信頼性を見極める能力がますます重要になります。特にAIが生成する情報については、ディープフェイクなどのリスクもあるため、必ず複数の情報源からその情報の真偽を検証する習慣を身に付けることが重要です。
③:ハイブリッド型の情報収集姿勢が主流
調査で明らかになった「Google検索とAIの併用者が42.7%」という数字は、今後さらに増加することが予想されます。それぞれのツールの強みと弱みを理解して目的に応じて使い分ける、ハイブリッド型の情報収集スタイルがビジネスパーソンの基本姿勢となるでしょう。
まとめ:変化を恐れず新しいツールは積極活用することが大切
本レポートでは、現代の主要な情報収集手段である「Google検索・AI検索・SNS」の利用状況を詳しく分析し、ビジネスシーンでの効果的な活用方法を模索していきました。
いま、ビジネスにおける情報収集手段は大きな転換期を迎えています。今回の調査からもわかる通り、Google検索は依然として確固たる基盤を維持しながら、AIという新たな選択肢が急速に広がり、SNSやYouTubeなども着実に存在感を増しています。
最後に、情報収集を効果的に進めるための3つのポイントをお伝えします。
- 用途や目的に応じて複数の検索ツールを使い分ける
- 複数の情報源を組み合わせて情報の信頼性を担保する
- 新しいツールを恐れず小さく始めて徐々に活用の幅を広げる
次回の記事では、本レポートをさらに深堀し、Google検索・AI検索・SNSの利用状況を、それぞれの年代別・職種別・役職別に詳しく分析していきます。ぜひ次回の記事もご覧ください。
▶ 次回の記事:【年代・職種・役職別】ビジネス情報収集の最新トレンドを徹底分析!
投稿 【Google検索 vs AI検索 vs SNS】ビジネス情報収集の過去と現在を徹底分析! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 AI時代の本格到来「SaaStr AI Annual 2025」現地レポートまとめ | 写真で振り返る世界最大級のSaaSカンファレンス は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>世界中のSaaSプレイヤーが集まる本イベントですが、今年は会場のいたる所でAIの話題が飛び交うという、まさに「AIが当たり前に浸透した世界」を実感することができる3日間でした。
今回も、ITreviewのスタッフが提携ベンダー様と一緒に本イベントに参加してきましたので、会場の熱気やセッションの内容など、現地の様子を写真とともにお伝えしていきます!
▶ 関連記事:世界最大級のSaaSカンファレンス「SaaStr Annual 2024」へ潜入!現地リポートまとめ
(取材・撮影=庄内 莉理 / 執筆・編集=ITreview LABO編集部)
SaaStr AI Annual 2025とは?

今回、米国サンフランシスコベイエリアで開催された「SaaStr AI Annual × AI Summit 2025」は、世界各地のSaaS創業者やVC、エグゼクティブなどが参加する業界最大規模のSaaS関連イベントです。
2015年にスタートした本カンファレンスですが、今年はイベント名が「SaaStr Annual」から「SaaStr AI Annual × AI Summit」に変更され、300人以上の業界トップスピーカーによる講演から、AIを活用した最新のSaaS動向まで、盛りだくさんの内容で開催されました。
イベント概要
今年のSaaStrは、下記の場所・日程で開催されました。
| 名称 | SaaStr AI Annual × AI Summit 2025 |
| 日程 | 2025年5月13日〜15日(現地時間) |
| 場所 | サンフランシスコベイエリア(サンマテオ郡イベントセンター) |
| 参加者数 | 10,000人以上 |
| セッション数 | 1,000以上 |
イベント参加企業
今回、弊社と一緒にSaaStrへご参加くださった企業様は以下の通りです。
| 企業名 | 氏名 | 役職/部署 |
|---|---|---|
| 株式会社インフォボックス | 平沼 海統 様 | 代表取締役CEO |
| 株式会社クラフター | ⼩島 舞子 様 | 代表取締役社長 |
| 株式会社クラフター | Fei Yang 様 | CTO |
| 株式会社Conoris Technologies | 井上 幸 様 | 代表取締役 |
| 株式会社Mer | 澤口 友彰 様 | Co-Founder & CEO |
| 株式会社Mer | 服部 真 様 | 執行役員 |
現地会場の様子

今年のSaaStrで最も印象的だったのは、やはりイベント全体が「AI一色」だったことです。昨年までの「SaaStr Annual」から「SaaStr AI Annual × AI Summit」への名称変更は、まさに時代の変化を象徴しているものといえるでしょう。
会場を歩いていると、ほぼ全ての企業ブースでAI機能を搭載したプロダクトが紹介されていました。特に目立ったのは、営業やマーケティング領域でのAI活用事例です。これまで人の手に頼っていた業務を、AIが代替するソリューションが数多く展示されていました。
さらに面白かったのは、参加者同士のネットワーキングにもAIが活用されていたことです。今年から新たに始まった「SaaStr’s Who Do You Want to Meet AI Networking Program」では、SaaStr専用アプリを通じて、講演スケジュールの確認や会議予約はもちろん、AIが参加者の興味関心に応じて最適な相手をマッチングしてくれる仕組みが導入されており、AIが「スタンダードな存在になった」ことを肌で感じることができました。

オフィシャルサイトでも「Indoor/Outdoor Event」と明記されているとおり、メインステージや展示ブースは屋内にありながら、小規模ステージや休憩スペース、フードトラックなどは屋外に配置されています。

晴天のもとで気持ちよく交流できる環境は、参加者同士のコミュニケーションを自然と促進していました。日本の展示会では見られない、まさにアメリカならではの開放的なイベントです。

アメリカらしいエンターテイメント精神も随所に感じられました。SaaStrのノベルティがもらえる人間クレーンゲームをはじめ、各企業ブースでもスクラッチゲーム、ハンマーゲーム、ダーツなど、参加者を楽しませる工夫が満載です。
ジェイソン・レムキン氏「20〜40%の従業員がAI時代に適応できない」

SaaStrの主催者であるジェイソン・レムキン氏のキーノートでは、SaaS業界が歩んできた過去と、これから向かうべき未来についての講演が行われました。同氏によると、SaaS業界は主に「2023年以前の成長時代」と「2024年以降の競争時代」という2つの時代に大別できると語りました。
〜2023年:成長の時代
- 年に一度の新機能追加が主流
- 5年ごとにパラダイムシフトが発生
- 10億円規模に到達すれば成功が約束
2024年~:激変の時代
- 競争の激化により成長が鈍化する企業が増加
- AIの進化により従来の方法では勝てなくなる企業が続出
- 新しいAIファーストの競合が既存企業のシェアを奪っていく
このキーノートで特に印象的だったのは、AIが単なるツールではなく「ビジネスの根幹を変える存在」になっているという指摘です。
製品開発やサポート、営業活動の自動化が進み、従来のやり方では競争に勝てなくなっている企業が増加していることに加えて、従来のプレイブックや働き方に固執する企業や人材は淘汰され、およそ20〜40%の従業員がAI時代に適応できない可能性があると指摘しました。
こうした変化に対応していくためにも「実験レベルではなく、本気でAIを活用し、絶えず学び続け、イノベーションを起こし続ける執念が必要」と強調しており、変化に適応できない企業や人材は取り残される時代に突入したことを実感しました。
ARTISANの「STOP HIRING HUMANS(人を雇うのをやめよう)」が物議

会場でひときわ注目を集めていたのが「ARTISAN」というスタートアップのブースでした。
ARTISANは、2023年設立のAIを活用したアウトバウンド営業自動化プラットフォーム「Ava」を提供する企業です。AI BDR(ビジネス開発担当者)がアウトバウンド営業における一連の業務を自動化し、300万件以上のB2Bデータベースを活用して国際的なリード発掘を自動的に行うことができます。
しかし、最も話題になったのはブースに大きく掲げられた「STOP HIRING HUMANS(人を雇うのをやめよう)」というコピーでした。このメッセージは、レムキン氏のキーノートで語られた「AIが人を代替していく時代」を象徴しているものだと感じられました。実際、多くの参加者がこのブースの前で足を止め、熱心に議論を交わしている光景が印象的でした。
元テスラのエンジニアコンビが開発した「Mosaic」がAIデモピッチで優勝

今年はベンチャーキャピタルのメイフィールド氏が主催するAIデモピッチも開催され、AIを活用したプロダクトのスタートアップがエントリーし、ファイナル3社が会場でピッチを行いました。
優勝したのは、元テスラのエンジニアコンビが2024年に設立した、AIエージェントを活用した次世代動画編集プラットフォーム「Mosaic」です。
従来の動画編集にかかる手間と時間を大幅に短縮し、字幕や吹き替え、テキスト挿入や音声改善、サイズ変更などの諸々の編集を自動化することができます。若いエンジニアが身近な困りごとからイノベーションを生み出したストーリーを直接聞くことができ、とても印象深い体験でした。
ITreview特別企画:G2 CEO ゴダード氏との特別セッション

今年もITreviewでは、世界最大規模のソフトウェアレビューサイト「G2.com」を運営するG2社のゴダードCEOとの特別セッションを開催しました。
ゴダード氏からは、まず自身の経歴をお話しいただいた後、参加者の質問に答えていただく形で進行しました。ここからは、特に印象的だった質問を抜粋して紹介していきます。

G2.comとは?
米国イリノイ州に本社を置く世界最大規模のソフトウェアレビューサイト「G2.com」の運営会社。ビジネスソフトウェアやサービスに特化してレビューの収集やランキング評価を行っている、まさに私たちITreviewのお手本とも呼べる存在です。
Q1:AIがどのような変化を市場にもたらしているか?
ゴダード氏の回答で興味深かったのは、情報収集方法の根本的な変化についてでした。
- 従来:検索エンジンでの情報収集が主流
- 現在:ChatGPTのようなテキスト生成ツールでの情報収集
この変化により、Webサイトのトラフィックが減少傾向にあり、Webマーケティングにおいては、従来のSEO(検索エンジン最適化)から新しいGEO(生成エンジン最適化)への対応が重要になってきているとのことでした。
▶ 関連記事:LLMO(GEO)とは?SEOとの違いやAI時代の流入戦略を徹底解説!
Q2:SaaSビジネスにおいてAI以外で注視すべきポイントは?
ゴダード氏はAI以外で注視すべきSaaSのポイントについて、以下の5つを挙げていました。
- プロダクトの価格設定
- ハイブリッドワーク vs リモートワーク
- インテントデータ vs 個人情報の規制
- AIネイティブプロダクト vs 既存製品へのAI機能の追加
- 業界特化型SaaSの需要増
特に興味深かったのは、SaaS業界全体では「ホリゾンタル(横断的)ではなくバーティカル(業界特化)な市場が活発化している」という指摘でした。AI時代においては、汎用的なプロダクトはもちろん、専門性の高い領域での活用が加速しているようです。
参加企業様の声
今回ご参加いただいた企業様から、貴重な感想をお聞かせいただきました。
株式会社インフォボックス:平沼様
参加の目的:「今年より株主になったG2のゴダード氏への挨拶と近況報告、また、AIに対するグローバル全体の温度感を知るために参加しました。」
印象に残ったセッション:「HubSpotのセッションとG2のセッションが印象的でした。特にAI導入によるGo-to-Market指標の”動かせなかった”領域へのインパクトや、トップダウンでのリードと”Weekly Wrap”文化の醸成、Go-to-Marketにおける”量”から”パーソナル”への議題など、自社にとっても関わりのある貴重な体験となりました。」
ITreview企画について:「多様なバックグラウンドを持つ皆様とカジュアルに意見交換できたことが大きな収穫でした。特に、業界横断で抱える課題や成功体験を直接聞くことで、Infoboxが提供すべき価値のヒントを多く得られました。」
株式会社Mer:服部様
参加の目的:「グローバル最先端の最新トレンド調査、特に成功企業の戦略や新たなビジネスモデルを肌で感じ、学ぶことを目的として参加しました。」
印象に残ったセッション:「最も印象に残っているセッションはG2 CMOとのセッションで、GEOについて知ることができたのは非常に大きな収穫でした。自社でも調査し、取り組みを始めたいと思います。AIの活用に関しても日本の数年先をリードしているイメージで、衝撃の連続でした。」
ITreview企画について:「国内外のリーダーの方々とリラックスした雰囲気の中で深く意見交換ができたことが最大の収穫です。G2社の豊富なデータに基づいた客観的な市場分析はとても参考になりました。」
株式会社Conoris Technologies:井上様
参加の目的:「自社もSaaSのスタートアップであることから、主にAIにおけるSaaS業界での活用と影響についてウォッチしたいと思い参加を決めました。」
印象に残ったセッション:「HubspotのCEOのセッションとBessemerとSaaS企業たちのパネルが特に印象的でした。グローバルな大手SaaSのAIに対する姿勢、今やらねば自社が沈没するという覚悟でAIに向き合っている覚悟は、自分自身のAIへの認識を改めざるを得ないレベルの気迫がありました。早速自社でもAI活用の推進を今まで以上に進めています。」
ITreview企画について:「ゴダード氏とのセッションが非常に興味深く、長年SaaS業界を見てきた彼の目線から見た今後の展望を聞くことができたのは、大変価値ある体験だったと思います。」
私たちと一緒に次回のSaaStrへ参加しませんか?

いかがだったでしょうか?今回のSaaStrは、まさに「AIが当たり前に浸透した世界」を象徴する大変意義深いイベントだったように思います。
世界最先端のSaaS動向を肌で感じ、グローバルで活躍するリーダーたちと直接交流できることは、日本では決して得ることのできない貴重な体験となりました。
来年も同様の企画を予定しておりますので、参加をご希望のベンダー様は担当CSまでご連絡ください。一緒にSaaSの未来を体験し、日本のSaaS業界の発展に貢献していきましょう!
【次回開催予定】
- 日程:2026年5月(詳細日程は後日発表)
- 場所:サンフランシスコベイエリア
皆様のご参加をお待ちしております!
投稿 AI時代の本格到来「SaaStr AI Annual 2025」現地レポートまとめ | 写真で振り返る世界最大級のSaaSカンファレンス は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【971名を調査】現代のビジネス情報収集手段を徹底調査!AI検索利用率が3倍以上に!? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、先日ITreviewが実施した『ビジネス情報収集活動における意識調査アンケート』の結果をもとに、各設問ごとにどのような傾向が見られたかについて、詳しく分析していきます。
ビジネス情報収集活動における意識調査アンケートについて
令和7年3月、ITreviewでは会員のユーザー様に向けて「ビジネス分野における情報収集活動において、どのような媒体を利用しているか」という趣旨の意識調査アンケートを実施いたました。
近年、急激な成長を遂げている生成AI分野の登場を皮切りに、YouTubeやX(旧Twitter)、Instagramなどの各種SNSの台頭など、昨今ではビジネスにおける情報収集手段が大きな変化を見せています。
今回のアンケートでは、そうした情報収集活動の変化や利用媒体の実態調査を目的として、総勢971名もの会員の皆様にご協力をいただくことができました。この場を借りて深く御礼を申し上げます。
現在(2025年)の主な情報収集手段(複数回答可)
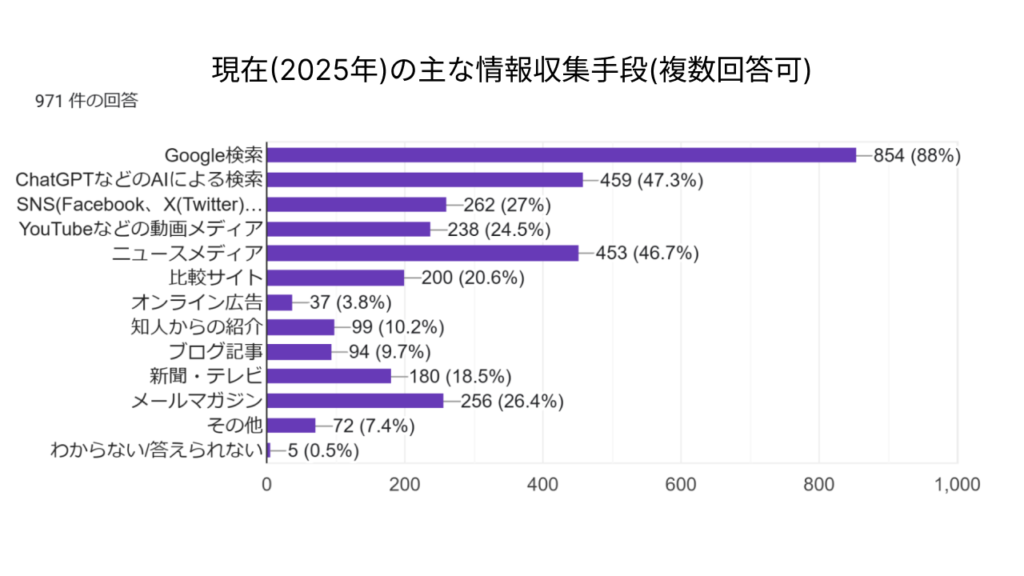
| 情報収集手段 | 回答数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| Google検索 | 854 | 88.0% |
| ChatGPTなどのAIによる検索 | 459 | 47.3% |
| ニュースメディア | 453 | 46.7% |
| SNS(Facebook、X(旧Twitter)など) | 262 | 27.0% |
| メールマガジン | 256 | 26.4% |
| YouTubeなどの動画メディア | 238 | 24.5% |
| 比較サイト | 200 | 20.6% |
| 新聞・テレビ | 180 | 18.5% |
| 知人からの紹介 | 99 | 10.2% |
| ブログ記事 | 94 | 9.7% |
| その他 | 72 | 7.4% |
| オンライン広告 | 37 | 3.8% |
| わからない/答えられない | 5 | 0.5% |
現在の情報収集手段については、Google検索が88.0%、ChatGPTなどのAI検索が47.3%、ニュースメディアが46.7%と上位を占めており、デジタル変革の加速と多様化が顕著に現れています。
Google検索の圧倒的な利用率は、検索エンジンの利便性と信頼性によるものです。ビジネスパーソンにとって必要な情報を効率的に収集できる手段として不可欠であり、企業のSEO対策重要性を改めて証明しています。
AI検索が47.3%という高い利用率を記録している要因は、生成AI技術の急速な普及にあります。対話型AIが新たな情報収集手段として定着しつつあり、BtoB企業のマーケティング戦略においてAI対応の必要性が高まっています。
過去(2022年)の主な情報収集手段(複数回答可)
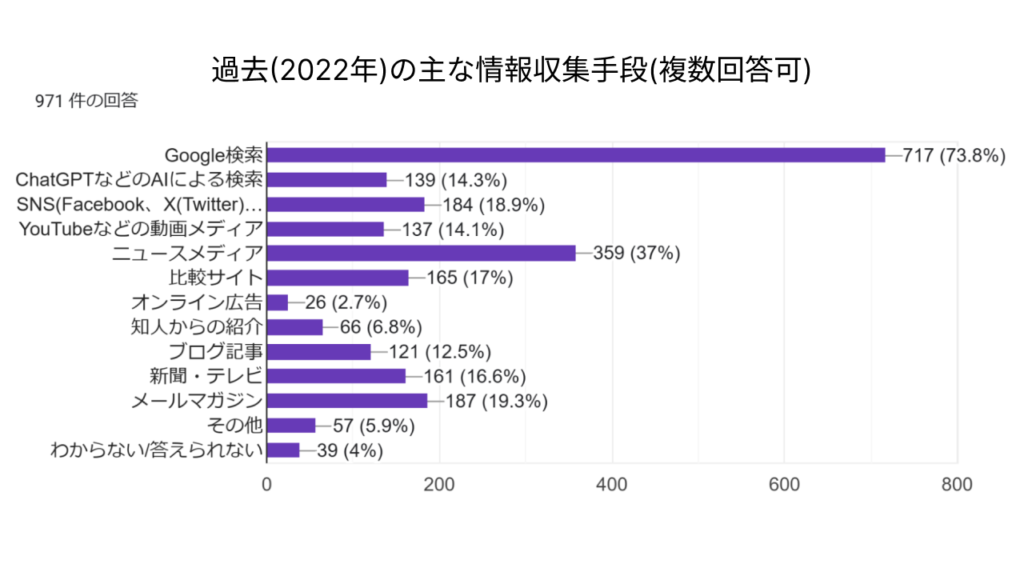
| 情報収集手段 | 回答数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| Google検索 | 717 | 73.8% |
| ニュースメディア | 359 | 37.0% |
| メールマガジン | 187 | 19.3% |
| SNS(Facebook、X(旧Twitter)など) | 184 | 18.9% |
| 比較サイト | 165 | 17.0% |
| 新聞・テレビ | 161 | 16.6% |
| ChatGPTなどのAIによる検索 | 139 | 14.3% |
| YouTubeなどの動画メディア | 137 | 14.1% |
| ブログ記事 | 121 | 12.5% |
| 知人からの紹介 | 66 | 6.8% |
| その他 | 57 | 5.9% |
| わからない/答えられない | 39 | 4.0% |
| オンライン広告 | 26 | 2.7% |
過去の情報収集手段については、Google検索が73.8%、ニュースメディアが37.0%、メールマガジンが19.3%と上位を占めており、テクノロジー採用サイクルの短縮化が鮮明に表れています。
最も顕著な変化は、AI検索の利用率が14.3%から47.3%へと約3.3倍に急増している点です。わずか3年間で33.0ポイント増加した要因は、生成AI技術の実用性とビジネス現場での有用性にあります。
Google検索も73.8%から88.0%へと14.2ポイント増加した背景には、リモートワークの普及と業務のデジタル化があります。オンライン情報収集がビジネス活動の中核を担うようになったことが読み取れます。
アンケート回答者の年齢分布
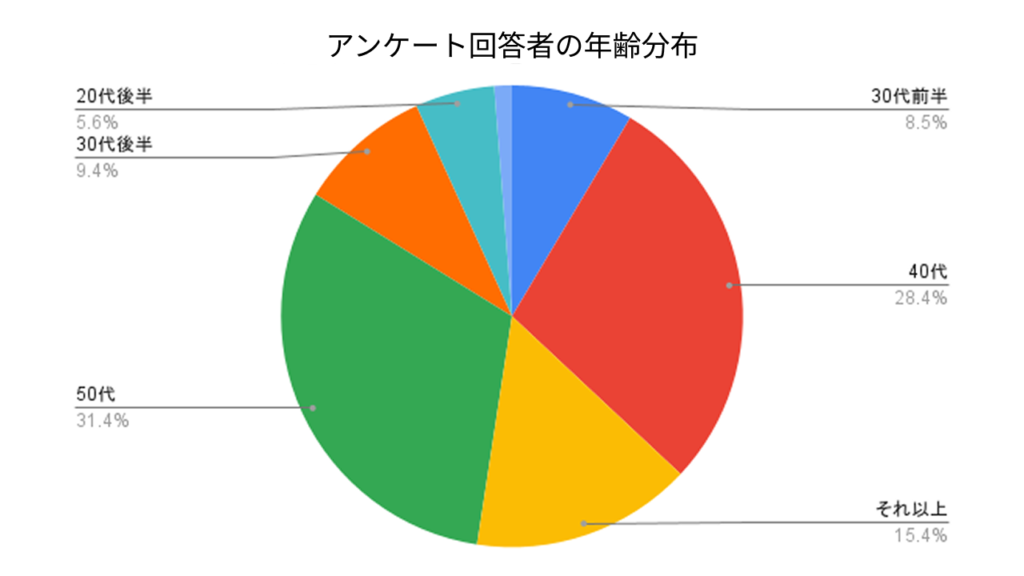
| 年齢層 | 割合(%) |
|---|---|
| 50代 | 31.4% |
| 40代 | 28.4% |
| それ以上 | 15.4% |
| 30代後半 | 9.4% |
| 30代前半 | 8.5% |
| 20代後半 | 5.6% |
| 20代前半 | 1.2% |
年齢分布については、50代が31.4%、40代が28.4%、それ以上が15.4%と上位を占めており、中堅・ベテラン層中心の信頼性の高いデータとなっています。
50代と40代が合わせて約60%を占める要因は、これらの年齢層が企業における意思決定権を持つ管理職やリーダー層が多いことにあります。ITツールやSaaSの導入検討における最終決定者層の行動パターンを反映したデータとしての価値があります。
30代以下が合わせて24.7%含まれることで、デジタルネイティブ世代の行動パターンも適切に反映されています。この構成により従来型とデジタル型の情報収集手段の並存が現実的に表現されています。
アンケート回答者の業種分布
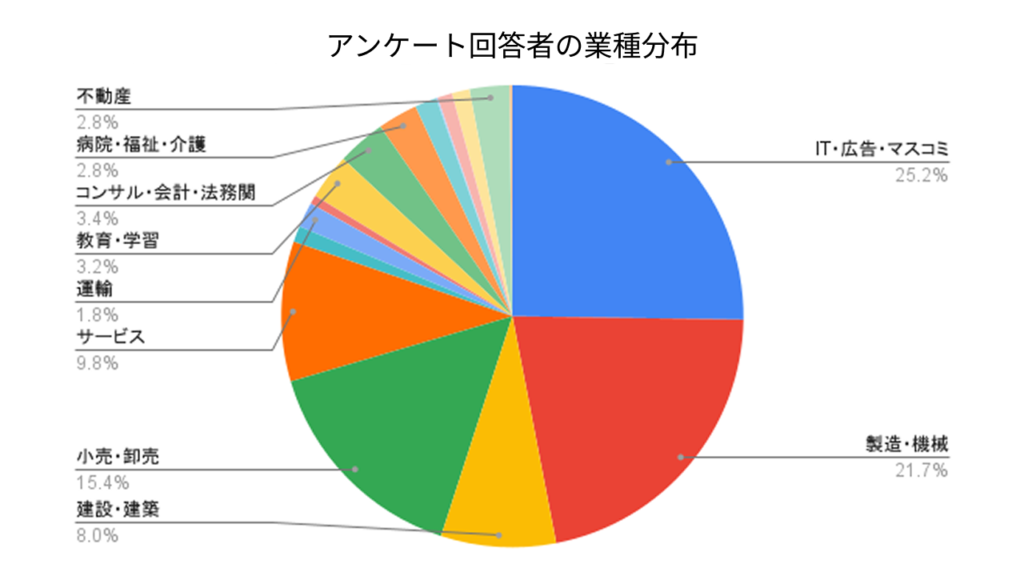
| 業種 | 割合(%) |
|---|---|
| IT・広告・マスコミ | 25.2% |
| 製造・機械 | 21.7% |
| 小売・卸売 | 15.4% |
| サービス | 9.8% |
| 建設・建築 | 8.0% |
| コンサル・会計・法務 | 3.4% |
| 教育・学習 | 3.2% |
| 不動産 | 2.8% |
| 病院・福祉・介護 | 2.8% |
| 運輸 | 1.8% |
業種分布については、IT・広告・マスコミが25.2%、製造・機械が21.7%、小売・卸売が15.4%と上位を占めており、ITリテラシーの高い業界を中心とした代表性を持つサンプル構成となっています。
上位業種がこれらの割合を占める要因は、デジタル技術の活用や情報収集に対する感度の高さにあります。この構成により、AI検索の高い利用率(47.3%)や動画メディアの成長など、先進的な情報収集手段の普及状況を適切に捉えています。
小売・卸売業界やサービス業界の参加により、BtoB取引における情報収集の実態も反映されています。これらの業界では取引先との情報共有や市場動向の把握が重要であり、多様な情報収集チャネルの活用が求められています。
アンケート回答者の職種分布
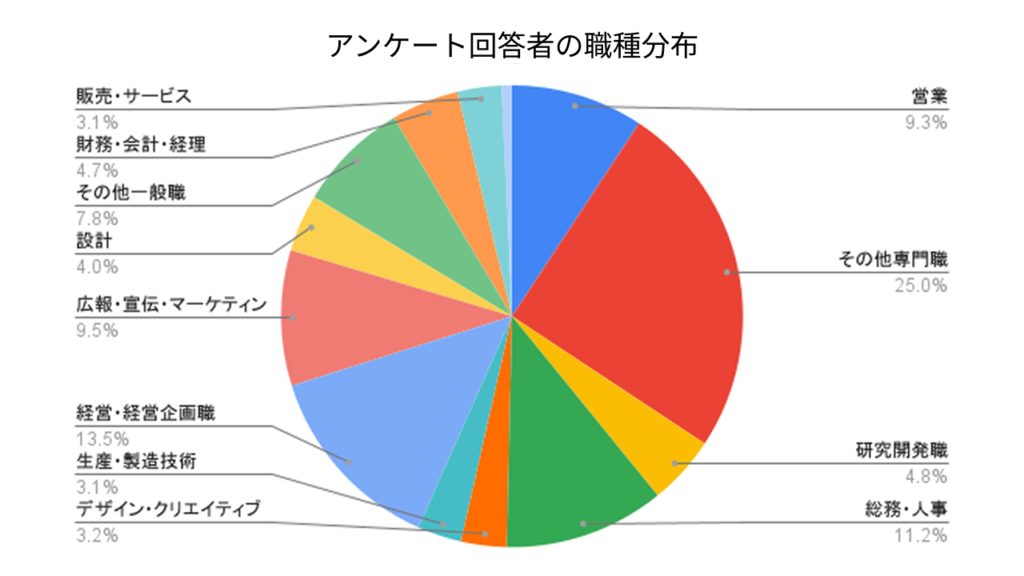
| 職種 | 割合(%) |
|---|---|
| その他専門職 | 25.0% |
| 経営・経営企画職 | 13.5% |
| 総務・人事 | 11.2% |
| 広報・宣伝・マーケティング | 9.5% |
| 営業 | 9.3% |
| その他一般職 | 7.8% |
| 研究開発職 | 4.8% |
| 財務・会計・経理 | 4.7% |
| 設計 | 4.0% |
| デザイン・クリエイティブ | 3.2% |
| 販売・サービス | 3.1% |
| 生産・製造技術 | 3.1% |
職種分布については、その他専門職が25.0%、経営・経営企画職が13.5%、総務・人事が11.2%と上位を占めており、意思決定に関与する専門職・管理職層が中心となった実用性の高いサンプル構成です。
その他専門職が最多を占める要因は、ITツール導入や業務改善における専門的判断を行う層からの回答が多いことにあります。経営企画職やマーケティング職は、組織における情報収集と意思決定の要となる役割を担っています。
これらの職種はビジネス課題の解決と戦略立案のために日常的に多様な情報源を活用する必要があり、情報収集手段の多様化は職務上の要請を反映したものです。特にマーケティング職では、SNS(27.0%)や動画メディア(24.5%)の利用増加が職務特性と密接に関連しています。
アンケート回答者の役職分布
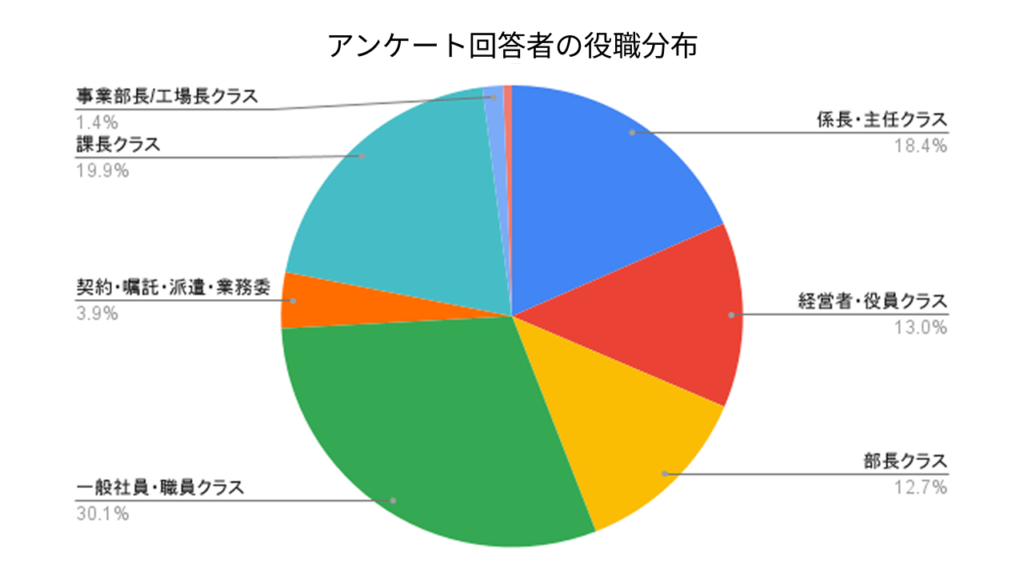
| 役職 | 割合(%) |
|---|---|
| 一般社員・職員クラス | 30.1% |
| 課長クラス | 19.9% |
| 係長・主任クラス | 18.4% |
| 経営者・役員クラス | 13.0% |
| 部長クラス | 12.7% |
| 契約・嘱託・派遣・アルバイト | 3.9% |
| 事業部長・工場長クラス | 1.4% |
役職分布については、一般社員・職員クラスが30.1%、課長クラスが19.9%、係長・主任クラスが18.4%と上位を占めており、組織階層全体をバランス良くカバーした包括的なサンプル構成となっています。
一般社員が最多を占める一方で、管理職層が合計で64.0%含まれる要因は、組織内での情報流通と意思決定プロセスにおける各階層の重要性にあります。経営者・役員クラスが13.0%含まれることで、戦略的意思決定層の行動パターンも把握できています。
AI検索の高い利用率(47.3%)は、トップマネジメント層においても新技術への適応が進んでいることを示しています。一般社員層の回答により現場レベルでの実際の業務における情報収集実態も適切に反映されています。
投稿 【971名を調査】現代のビジネス情報収集手段を徹底調査!AI検索利用率が3倍以上に!? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 自社での開発が難しいからこそ、手厚い導入支援を ー 生成AI導入支援サービスを提供するソフトバンクに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、AI活用を進めるにあたっては「何からはじめていいのかわからない」や「そもそもAIを使って何ができるのかわからない」などの課題感から、なかなか導入に踏み切れないと感じている経営者・企業担当者の方も多いのではないでしょうか?
今回は、新しい生成AI導入支援サービスである『Azure OpenAI Service スターターパッケージ』をリリースしたソフトバンク株式会社の佐野氏と西氏へ、生成AI導入のポイントや導入支援を利用することで得られるメリットなどについて、お話しを伺いました。
生成AIの導入支援をローンチした背景
ー 今回、ソフトバンク様が『Azure OpenAI Service スターターパッケージ』を提供するにあたって、解決したかった社会的な課題やお客さまからの声など、サービスを提供した経緯や背景などがあれば教えてください。
西氏:従来のシステム開発では、まず目先の課題があってから、その課題に対して要件を定義してシステムを開発していく、というのが一般的なフローだと思います。しかし、AIの活用が世界的なブームとなっている昨今では「AIを使って何かをせよ」といったように経営層からトップダウンで来られるお客さまが非常に多いです。とりあえず「自分たちはAIを使って何かをしなくちゃいけない」でも「何からはじめていいのかわからない」という状態に陥ってしまっていて、AIの活用そのものが目的化しているというお客さまの声を多く聞いていました。
西氏:今回のスターターパッケージをローンチした背景としては、そうした課題への解決策として、まずは社内でセキュアに使えるChatGPTの環境を整えて、社員に使ってもらい、ここから「じゃあ何ができるんだろう?」と社内で検討していけるための、環境と必要な支援をパッケージとして提供することが目的でした。何からはじめてよいかわからない、どうやって進めてよいかわからない、このような課題を抱えたお客さまに対して、スターターパッケージという形で、ご提供しています。
ー まずは皆さんが、AIを導入することで「どういったことができるようになるのかわからない」みたいなところがサービス提供の発端になっているというわけですね。
西氏:はい。私たちソフトバンクもいち早く社内で「ChatGPTを展開します」ということも発表させていただいたのですが、まずは私たちソフトバンクの全社員(対象者2万人)が、自分たちでAIを使ってみるところからスタートでした。ですので、社内で培ったノウハウを一緒に提案できることに加えて、さまざまなお客さまの利用用途のなかでノウハウとして貯め込んでいったものをお客さまに提供していく、一緒に成長していく、そのような思いをスターターパッケージに込めています。
生成AIの導入支援を依頼するメリット

ー ソフトバンク様へ生成AIの開発を依頼した場合、導入した企業は自社で開発する場合と比べて、時間や工数など、どのようなメリットを享受できるのでしょうか?
佐野氏:ありがとうございます。我々はスターターパッケージという形で設計・構築・導入といったところまで全て一括でご用意しておりますので、短納期でご提供できるというところです。また、我々も社内でChatGPTの運用ノウハウを蓄積しておりますので、自社でイチから開発や運用を実施するよりも、圧倒的にコストや工数といった部分を削減しながらご提供できるというところが一番のメリットかなと考えております。
佐野氏:それに加えて、我々は導入だけではなく、運用やサポートなどもトータルでご提供しておりますので、継続的に支援していける体制という部分でもメリットは大きいです。通常であれば、チャットUIの開発だけで終わるところを「じゃあこれを今後どうやってメンテナンスして維持管理してアップデートしていくのか」など、延々とコストが発生してくる問題であっても、ソフトバンクであれば当社の社内導入時のノウハウを共有させていただきながら伴走させていただきますので、一緒に成長していけると考えております。
ー 実際に「どれくらい工数が削減できました」や「どれくらい簡単に導入できました」など、サービスプロバイダーの協力によって得られた具体的な導入効果や事例などがあれば教えてください。
佐野氏:そうですね。先ほどの話題にもあったように、やはりすでにエンタープライズのお客さま、大手企業ですと、トップダウンで開発しているところが多く、「とりあえず試してみている」というお客さまが未だ多いのが実態です。ただ、せっかく自社で用意した生成AIのチャットUIでも、一度に全社向けて展開してしまうと、トラフィックが一気に寄ってしまうので、それらをどのように分散して運用いくのかなど、今後の運用工数というところで課題を感じているお客さまが非常に多いです。
佐野氏:トップダウンで進められると早く形にはできるのですけれども、それを維持管理して、メンテナンスしてとなっていくと、リソースを延々と確保し続けていかなくてはいけないので、最終的に難しいという判断になってしまうことも珍しくありません。であれば、やはりそこは「ソフトバンクに任せよう」というお客さまが増えておりまして、もともと自社で開発していたUIを捨てて「ソフトバンクのUIに切り替えます」とおっしゃるお客さまも増えています。すでに多くのお客さまが短納期で導入いただいておりまして、その一部を弊社プレスリリース(https://www.softbank.jp/corp/news/press/sbkk/2023/20230802_01/)で発表させていただいております。
ー そもそもあった工数の見積りが難しい企業様が、より自分たちがどれくらいの工数をかければいいのかがわかりやすくなる、そのようなイメージでしょうか。
佐野氏:そうですね。我々のスターターパッケージは、納期などもあらかじめ決まっておりますので、お客さまの中でもリリースまでのスケジュールが立てやすいかと思います。また、急にプロジェクトが始まってしまい、先が見えない中でも、我々がしっかりと計画化して、取り組んでいけるという部分が一番大きいのかなと思います。
佐野氏:あとは、これもエンタープライズのお客さま事例なのですけれども、世の中で生成AIというものが流行しているなか、流行には乗りたいけれども、その後の導入効果が見えにくいため、そこに費用対効果を見出せるかを考えていらっしゃるお客さまもすごく多いのです。ただ、そこでやらないという選択肢を取ったときに「競合他社に差をつけられてしまうのではないか?」というところを気にされているお客さまが多く、まずは他社に差をつけられないためにも、スターターパッケージを入れて、使ってみて、POCで効果を測定して、もし本当に業務効率化が可能ということであれば本番として発展させて効率化を図っていこう、そう考えている経営者の方も多いですね。
ー 既存の問題があるというよりも、将来的に発生してくる課題に対して先にノウハウを蓄積しておいて、今後のビジネスに生かしていく、そういったお客さまが多いということですね。
西氏:はい。現状で言えば、まずは自社にある既存のデータを使ってどうにかしたいという要望が一番多いのですが、そうすると、じゃあまずは社内に蓄積しているQ&Aを入れてみて、それを引き出すChatGPTを作る、というところは、やはり一番取り組み易い部分だと思います。
西氏:他にも、研究所の事例で、今まで先人たちが貯めてきたデータが奥に追いやられてしまうのがもったいないというご要望がありまして、ではそれらをいったん全部AIに取り込ませることで、昔のデータを掘り起こせたらよいなとおっしゃるお客さまもおりました。とりあえずAIに聞いてみれば、何か出て来るのではないかと。宝探しじゃないですけど、これを機に自分たちのデータやノウハウをしっかり活用していく、そのような形で使いたいというお声もいただいております。
チャット以外にも幅広いAI機能の追加が可能
ー 生成AIを開発するとなると、やはりChatGPTのようなチャット形式での依頼が多いのでしょうか?
佐野氏:そうですね。スターターパッケージという形で提供しておりますので、ほとんどのお客さまには、まずはチャットUIを提供させていただいております。しかしその後、例えば、AIが会議の文字起こしを自動的に行ってくれて議事録まで作成してくれる機能等も目の前まで来ていますし、今あるデータから自動的に設計書を起こしてほしいみたいな、ちょっと未来的な要望もあるのですけれども、やはり皆さんChatGPTでいろいろな未来を感じていただいて、もっと「こういうことはできないの?」というお問い合わせはすごく多いですね。
佐野氏:また業界によっては、画像生成機能を求めておられるお客さまも非常に多いですね。マーケティング用途で資料の作成に画像を用いる機会も多いと思うのですが、例えば、新しい製品のモデルイメージを提案するときなどには、パワーポイントにはめ込むイメージ画像をほしいという用途での要望も多いので、そのような要望に対しては、チャットUIだけではなく、一緒に画像生成の機能も追加して、ひとつのUI上でテキストと画像を同時に生成ができるように提案しています。
ー なるほど。資料用の画像作成なども生成AIを使って作成することができるということでしょうか?
佐野氏:そうですね。例えば、新しく提案する自動車が先進的なスポーツカーであった場合には「先進的なスポーツカーの画像を生成してください」とAIに指示することによって、見た目の先進的な自動車を画像として出力してくれます。そうした画像生成機能の追加についても、企業のデザイン部門やマーケティング部門などからご要望をいただいております。
ソフトバンクだからできる手厚いサポート体制

ー 今後、ソフトバンク様としては、お客さまに対して、どのような先進的な価値を提供していきたいのでしょうか?具体的なプランや将来的なビジョンなどがあれば教えてください。
西氏:現状は、お客さま社内のデータを生成AIへ連携させるためのプラグインを提供していくところから生成AIに組み込んで提供していくところからスタートしておりますが、今後はプラグインの拡充によって、外部にあるデータまで連携させて、生成AIに組み入れていくような動きを拡大することで、プラグインで全てのアプリケーションと生成AIを繋げていくことが重要なミッションだと考えております。
西氏:あとは、AIの仕組み自体も大切だとは思いますが、その活用の方法であったり、ノウハウの共有であったり、そうした技術以外の部分でもソフトバンクとしての価値を提供していきたいですね。結局のところ、プラグインもスターターパッケージも技術とノウハウがあれば誰にでも作れてしまうようなものなので、これをいち早く提供することはもちろん、生成AI全体に対する取り組みやノウハウ、世界観というところで、ソフトバンクに価値を見出していただければなと思います。
ー 最後に、ITreviewを見ているお客さまに対して、どのようなレビューがほしいのか、開発に役立つレビューやフィードバックなどがあれば教えてください。
佐野氏:他の製品と比較する上でもう少し明確にしてほしい部分や、こういう課題があるのでこういう支援やサポートがあると嬉しいなどご要望がありましたら、ぜひレビューやフィードバックをいただけると嬉しいです。
◆お話を伺った方
ソフトバンク株式会社(https://www.softbank.jp/biz/)
サービスデリバリー部 サービスデリバリー1課 課長 佐野 雄一 氏
サービス企画部 サービス企画1課 西 弥生 氏
Azure OpenAI Service スターターパッケージ(https://www.softbank.jp/biz/services/platform/msp-service/azure-openai-starter-package/)
投稿 自社での開発が難しいからこそ、手厚い導入支援を ー 生成AI導入支援サービスを提供するソフトバンクに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ITreviewにて掲載中のChatGPT・生成AI関連カテゴリー・製品を紹介中!ChatGPTを用いたユーザーレビューの分析・まとめ記事や生成AI導入・活用サポートをするベンダーへのインタビューも掲載中! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>・生成AI製品をまとめたカテゴリー
・生成AI製品のビジネスへの活用・導入、製品開発をコンサルティング・サポートするパートナー企業(サービスプロバイダー)
・ChatGPT・生成AI機能を搭載した製品
今回、現在掲載中のカテゴリー・製品を一覧化しました!
あわせてChatGPTを用いたユーザーレビューの分析・まとめ記事や生成AI導入・活用サポートメニューを提供するベンダーへのインタビューも掲載。
既存業務の効率化や新しいビジネスの創出など皆様の様々なビジネス課題の解決に効果を発揮するChatGPT・生成AI製品の選定・導入にご活用ください!
生成AI系カテゴリーの紹介
◆ChatGPTへの投稿レビューの分析・まとめ記事を公開中!
生成AI導入・活用サービスプロバイダーの紹介
生成AI製品のビジネスへの活用・導入、製品開発をコンサルティング・サポートするパートナー企業としまして、以下の5つのカテゴリーを紹介中です。
自社ビジネスへのChatGPT・生成AIの活用、及び自社サービス・製品へのChatGPT・生成AIの組み込み・開発時のパートナー選定の参考に是非、ご活用ください。
・ChatGPT活用コンサルタント
ChatGPT活用コンサルタントは、生成AI(ジェネレーティブAI)の一つであるChatGPTを中心としたビジネス展開のためのコンサルティングを提供する専門家やパートナー企業です。「社内業務においてChatGPTをどのように活用できるか」「どれくらいの工数が削減できるか」といった検討に関する課題解決に力を発揮してくれます。
・ChatGPT導入・開発コンサルタント
ChatGPT導入・開発コンサルタントとは、ChatGPTを中心としたジェネレーティブAIのシステムや製品への導入、開発に関する専門的なコンサルティング業務を行うパートナー企業です。新製品の開発だけでなく、既存の製品やシステムへのChatGPTの機能組み込み時に、その独自の知識や技術を活用して最適な提案や開発リソースを提供します。
・生成AI活用コンサルタント
生成AI活用コンサルタントとは、生成AIを活用したビジネス展開をサポートする専門家やパートナー企業のことです。ビジネスへの生成AIの活用時に、独自の知見を活かしたサポート・コンサルティングを提供し、ビジネスの展開スピードの向上や強固な体制の構築などの効果を期待できます。
・生成AI導入・開発コンサルタント
生成AIT導入・開発コンサルタントとは、生成AIのシステムや製品への導入、開発に関する専門的なコンサルティング業務を行うパートナー企業のことを指します。その独自の知識や技術を活用して最適な提案や開発リソースを提供します。
・Azure OpenAI Serviceパートナー
Azure OpenAI Serviceパートナーとは、Microsoft Azure上でOpenAIの自然言語処理モデルを活用するためのサービス、Azure OpenAI Serviceの導入や運用をサポートする専門のパートナー企業のことです。専門的な知識や経験が必要とせず大幅な業務効率化が期待できます。
◆生成AI導入・活用サービスプロバイダーへのインタビュー記事を公開中!
この度、ITreviewではChatGPT・生成AIの導入・活用のサポート・コンサルティングを提供しているベンダー(サービスプロバイダー)へインタビューを実施しました。
第一段として、生成AIの導入支援サービスをローンチした株式会社Cuon様へ、第二弾として、ソフトバンク株式会社様へお話を伺っています。
現在、ChatGPT・生成AIの導入・活用を計画している方はぜひご参考にしてください。
ChatGPT・生成AI機能を搭載した製品の紹介
生成AIに関連したカテゴリー以外のSaaS・ソフトウェア製品においても、ChatGPT・生成AIの連携機能を搭載した製品が続々と発表中です。ITreviewではそのようなChatGPT・生成AI機能を搭載した製品を、カテゴリーGrid・製品一覧で、一覧表示可能となっております。ぜひ製品選定時にご活用ください!
・ChatGPT・生成AI機能を搭載した製品を有するカテゴリー
・チャットボットツール
追加される機能の例
回答パターンの自動生成など回答補助、テキスト検索
該当製品
ChatPlus / HRBrain / mitoco / Circlace / Cogmo Attend / HiTTO
生成AI機能搭載製品の新規登録はこちら、もしくは登録済みのベンダー様は管理画面左メニューの「カテゴリー追加申請」から可能です!
・カテゴリーGrid上でのフィルタリング方法
下記カテゴリーページに表示されておりますカテゴリーGridの右上、「絞り込み」のプルダウンリストから、「ChatGPT・生成AI対応機能搭載」の項目にチェックを入れることでカテゴリーGrid上での該当製品のフィルタリングが可能です。
(該当製品がカテゴリーGridへの表示要件を満たしている場合のみ、表示されます)
・製品一覧上でのフィルタリング方法
下記カテゴリーページの左側メニュー、「生成AI対応で絞り込み」から、「ChatGPT・生成AI対応機能搭載」の項目にチェックを入れることで製品一覧上での該当製品のフィルタリングが可能です。
投稿 ITreviewにて掲載中のChatGPT・生成AI関連カテゴリー・製品を紹介中!ChatGPTを用いたユーザーレビューの分析・まとめ記事や生成AI導入・活用サポートをするベンダーへのインタビューも掲載中! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ユーザーレビューから見るChatGPTの多様な活用方法とその効果を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで今回は、B2B向けIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview(アイティレビュー)」に寄せられたChatGPTへの163件(23年9月時点)のユーザーレビューを、ChatGPTを用いて分析しました。ユーザーレビューから見えた多様な活用方法とその効果について解説していきます。
業界・ユーザーの立場・使用用途における傾向
業界別の傾向
まず始めに、どのような業界にて利用されているかの傾向について解説していきます。
もっとも利用されているのは「人材」や「ソフトウェア・SI」といった業界です。この業界での使用が多いのは、IT技術やAIとの親和性が高いからだと考えられます。特に人材業界では、求職者や企業とのマッチング、面談のスケジューリングなど、煩雑な業務が多く、自動化や効率化が求められており、ChatGPTのようなAIツールがマッチすると考えられます。
また、「ソフトウェア」や「SI業界」では、技術的な問い合わせやサポートが必要な場面が多いため、ChatGPTを用いて24時間365日のサポート体制を実現する企業も増えてきています。
ユーザーの立場における傾向
ITreviewでは一般的な利用者であるユーザー(利用者)・導入決定者・IT管理者・ビジネスパートナーといったユーザーごとの導入における立場のデータを取得していますが、この中ではIT管理者およびユーザー(利用者)からの評価が高く、多くの用途で使用されています。
IT管理者は、システムとの統合やAPIの活用に関する知識が豊富であり、汎用的に利用可能なChatGPTの機能を最大限に活用することができるため、高い評価をしていると考えられます。
一方、一般のユーザー(利用者)は、日常業務の中での問い合わせや情報検索など、具体的なタスクを効率化するためのツールとしてChatGPTを活用しています。
具体的なChatGPTにおける活用方法の紹介
社内チャットツールとの連携
社内でのコミュニケーションツールとして利用されるSlackやTeamsにChatGPTを組み込み、「AI相談室」としての活用しているというユーザーレビューがありました。社員が業務中に疑問や質問を持った際に、リアルタイムに回答を受け取ることができるため、業務の効率化が図れると推測できます。
ユーザーレビュー抜粋:社内の業務効率化に一役買ってます
社内チャットツールとChatGPTを連携し、AI相談室という部屋を作りました。
https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/165712
業務上での情報収集
ウェブサイトや社内データベースなどからの情報収集としてChatGPTを活用することで、迅速な対応が可能となります。通常、人力で対応した場合には調査のための工数がかかりますが、この機能により、プログラミングにおけるコードの書き方の相談や製品価格の調査などに活用しているユーザーも見られました。
ユーザーレビュー抜粋:自分にとっての良き”秘書”として使うことをおすすめします。
「自分がやらなくてもよかった単純な作業」などはChatGPTにまかせることができるので、業務効率化につながると思います。
https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166117
データ分析と連携
ChatGPTが収集した質問や回答のデータを分析することで、ユーザーのニーズや傾向を把握することが可能です。この機能を活用し、より精度の高い回答や新しいサービスの提案・情報のまとめに活用するユーザーもいます。
ユーザーレビュー抜粋:分析に使える
今までのGoogleの検索のように使用するのではなく、分析が得意かなと感じる。例えば県庁所在地ごとの人口を一覧で出力する等、今までの検索では1つ1つ検索する必要があったが、まとめて検索、出力が可能。今までは検索の結果を人手で一つ一つ整理する必要があったが、その手作業をまとめて実施してくれるので検索だけでなくその後のまとめ作業も同時に実施してくれるのでその手間や時間を削減できる。
https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166181
思考の可視化
ChatGPTに問題解決のアイデアや提案を投げかけることで、従来の方法や考え方に囚われず、新しいアイデアや解決策を考え出すことが可能です。
得られた回答や提案をもとに新しい視点や発想を得ているレビューをご紹介します。
ユーザーレビュー抜粋:多すぎるプラグインの組み合わせが使いこなすコツ
実際の商品開発で活用しており、ランダムなペルソナ設定とテーマに対するアイデアを組み合わせて、付加価値の高い順にアイデアと根拠をテーブル形式でまとめるプロンプトを作成して、様々な商品アイデアを創出しています。しかしなかなか目新しいアイデアは出ないので、独自のバイアスを壊すフレームワークノートを組み合わせて、さらに新規性の高いアイデアに昇華している。
一発で成果物を生成するゴールシークというプロンプトを学習したが、結局「問い」を設定して、AIと対話しながらゴールを目指す方が汎用性が高く、深い回答が得られる。
プラグインが大量に出てきているので、これからはその研究が成果物の質を高めるポイントになると思われる。
https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166216
ユーザーレビュー抜粋:無いころには戻れない
思考の整理(壁打ち)にとても役立ちます。
考えている事や整理したいことを入力していくと、バイアスのかかってない返事がきます。
このバイアスのかかってない返事というのがとても大事で、余計な思念が無いので純粋な判断が出来るようになります。
また返事から、自分の中で新たな考えが生まれ、枝葉するようにどんどんとアイデアが生まれより良いものになっていきます。
その返答から得られる元になるのはあくまでも自分の考えなのですが、思考の広がりはドーピングしたような感じで、今まで見えていなかったものが見えてくる感じがあります。
ものすごく有能な仕事のパートナーがいる様です。無かったころには戻れません。
https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166273
ユーザーレビュー抜粋:文章の生成能力は良いが、精度には少し問題がある。
まだ試行錯誤しながらの使用ですが、〇〇の数字を上げるにはどうすればよいか?等の質問で、主にアイデア出しにて使用しています。
https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166275
ChatGPTの活用で得られた効果
時間の削減
ChatGPTを活用することで、調査業務や質問・問い合わせに対する回答など、時間が大幅に短縮されるため、業務の効率化が図れます。上述での使用例でもあったとおり、様々な業務で社員の工数負荷を軽減することができます。
ユーザーレビュー抜粋:会話するだけで知りたいことを教えてくれる
応用の幅が広く様々なことを効率化できます。文字の羅列を表にまとめてもらったり、あらゆる挨拶文の文章を考えてもらったり、アンケート内容の事例を教えてもらったりこれまで情報収集に時間が掛かっていたものが聞くだけでかえってくるので大変助かります。
https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166448
チェックの質の向上
以下のレビューでは、ChatGPTにより事前にチェック時の検討項目をあげてもらうことで、オペレーション業務時のうっかりミスの削減に活用しています。このような項目のピックアップはデータの収集から必要項目の検討まで時間がかかることが予想されますが、ChatGPTにより事前にミスが起こりうる要素を指摘してもらい、それをもとにチェック事項を作成したとのことです。
ユーザーレビュー抜粋:事前に問題が起こりそうな事象を洗うことができる!
人間の作業でのうっかりミスをなくすことができた。
ChatGPTに事前の検討項目あげてもらい、チェックリストとして使うことでうっかり忘れたなどを回避することができた。
https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166171
口語入力の利点を活かした業務効率化:
ChatGPTでは複雑な命令文を使用しなくても、人間同士での対話のようにタスクを命令することが可能です。複雑なデータの検索や文書の自動作成など、従来では改善に複雑な処理が必要であった業務でもChatGPTを活用して効率化しているユーザーも見られました。
ユーザーレビュー抜粋:業務が完全にアップデートされた
確かに全部が全部正しい情報ではなく、コピー&ペーストはできないがPrompt次第で大きな成果が生み出せる。業務効率化としては最高のAIである。また、当社ではSlackと連携しているが、これも非常に楽である。社員とコミュニケーションをする流れで、ChatGPTを呼び出して対話することで、自然な業務フローを組み上げています。
https://www.itreview.jp/products/chatgpt/reviews/166113
まとめ
いかがだったでしょうか。ITreviewとしてもChatGPTを業務活用するべく、ChatGPTへ投稿されたユーザーレビューをChatGPTを用いて分析するという初の試みを行いました。
作成については、
1.投稿されたレビューをChatGPTに一括で入力
2.入力したデータをもとにChatGPTを使い、原稿テキストを出力
3.出力された原稿テキストをチェックし、文章内の間違いや表現の修正
という行程で行っています。
通常の記事作成に比べ、構成案およびテキストの作成時における工数を大幅に削減できる効果を実感しました。しかし、文章内の間違いや表現については、通常の人間が作った文章よりも修正工数がかかり、まだまだ課題は多いという印象もあります。
とはいえ、いろいろな業務で活用することにより、課題とともに新たな利用方法も生まれてくるというのが新しい技術です。
データを扱うツールとなるため、機密情報などについては注意を払うことは必要ですが、ぜひ、みなさまの業務においても活用してみてはいかがでしょうか?
また、ITreviewでは今回ご紹介したChatGPTのユーザーレビューが見れるほか、生成系AIのその他の製品のユーザーレビューも取り扱っております。無料でご覧いただけますので、ご興味のある方はぜひ下記のリンクよりご覧ください。
投稿 ユーザーレビューから見るChatGPTの多様な活用方法とその効果を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 生成AI導入の秘訣と導入支援サービスを利用することのメリット ー 生成AI導入支援サービスを提供するCuonに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、AI技術者の確保や自社システムへのスムーズな組み込み、運用ルールの策定など、これからフルスクラッチで開発を進める場合、乗り越えなければならない課題が多いこともまた事実です。今回は、生成AIの導入支援サービスをローンチした株式会社Cuonの大川氏と伊藤氏へ、生成AI導入の秘訣や導入支援を利用することで得られるメリットなどについて、お話を伺いました。
生成AIの導入支援をローンチした背景
ー 生成AIを活用した導入支援サービスを提供するにあたって、解決したかった社会的な課題やお客様の声など、サービスローンチにいたった経緯や背景などがあれば教えてください。
大川氏:弊社では、これまでRubyをベースにしたウェブシステムやPCサービスなどを、システムソリューションという形で、お客様に対して構築・提案を行っていました。ただし、近年になってパッケージ化されたECシステムがどんどんと一般化しているなか、なかなか他社との差別化が難しい。さらには、今後お客様がDXを進めていくうえで、一番キーとなるところというのは、どちらかというと実際に手足を動かす部分の自動化ではなく、人間が考えるような部分を自動化して、お客様の行動に対するレコメントを投げたり、より高度な判断をして提案したりするようなサービスにつなげていかないと、こうしたウェブシステムやECシステムの将来というものは、なかなか厳しいのではないかという懸念がありました。こうしたところで、新しい技術を使って何か付加価値の高いサービスを提案したいというところが、このサービスをローンチした背景です。
サービスを導入するにあたっては、まずはお客様のニーズをしっかりと把握して、それを要件に落とし込むという作業が絶対に必要にはなりますので、そこで生成AI導入コンサルという形でメニューを展開して、ノウハウが溜まってきた段階で、それらをいくつかのパッケージメニューとして、もう少しとっつきやすい形でお客様に提供できたらいいなという形で考えています。
ー もともと提供していた既存のサービスに付随して、生成AIを活用することによって、それらをより保管した形で使いやすいサービスとして提供していくというイメージでしょうか?
大川氏:はい、そうですね。もちろん、単純に生成AIとして使うということでも、DXや効率化というところでは非常に大きな効果がありますので、そのような使い方で基本的には問題ないのですが、弊社のシナジーという観点では、やはり既存サービスとの連携というところが大きいです。
ー 生成AIを活用することで、システム同士の連携が容易になるというような話題でしたが、具体的には、どのようなシステムに組み込むことが多いのでしょうか?
大川氏:最近になって多い利用形態としては、チャットボットで使用されるパターンです。ウェブのフロントから接続してきたエンドユーザーをサポートをするような形で使われるケースです。そのため、CRMなどのシステムにAIが割って入るようなイメージではなく、疎結合としてウェブシステムなどにつなぐパターンが多いですね。
例えば、教育系のお客様の場合であれば、膨大なファイルサーバーに昔の試験の回答データが大量にありますので、そのデータを活用して「国語の苦手な生徒にはどのような問題を作れば良いか?」をAIに聞くと適切な問題を作ってくれたり、もしくは、算数の場合はなかなか難しいのですが、国語の場合は感情分析ができるので「その生徒がどんな感情で答えを導き出したのか、その答えに対して先生はどのような点数を付けてあげるのがベストなのか」など、そういったところのアドバイスまで生成AIは行ってくれるので、そうした使い方をするケースもありますね。
ー ベテランの先生しか持ち合わせていない勘どころのような部分を、新任の先生でも知識として共有・利活用することができるというイメージでしょうか?
大川氏:はい、仰る通りです。これは別件なのですが、医療業界の話で、お医者さんは患者さんの話を聞きながら電子カルテで処方箋を入力していくんですけれども、お医者さんによっては診察のノウハウにバラつきがあるらしいんです。なので、誤った処方をしないように、お医者さんが記入した電子カルテの内容を生成AIが横目で見て、過去のカルテデータと比較しながら、間違った処方箋を出しそうになった段階で警告をしてくれる、そのようなシステムを作りたいということで、我々としてもチャレンジしようとしているところです。
生成AIの導入支援を依頼するメリット
ー Cuon様へ導入支援を依頼した場合、導入した企業は自社で導入する場合と比べて、時間や工数の削減効果など、どのようなメリットを享受できるのでしょうか?
大川氏:そうですね。逆説的になってしまいますが、正直に言うと、仕組み自体は何か一生懸命プログラムを書いてガッツリと開発しないといけない、そういう類のものではないんです。じゃあ何が言いたいのかというと、やっぱりAzureとかAWSとか、大手のクラウドベンダーがそういったツールを出していたりもしますし、あとはPythonなんかでも、幅広いフレームワークツールが出ているので、そういったものをトータルで組み合わせて、なおかつAIの知識というものがあれば実は誰でもできるものなんです。
ただし、多くのお客様が難しいと思われる原因は、そもそものクラウドに対する知識というものが、エンドユーザーやSIベンダーも含めて、日本人は詳しくないということです。それぞれのクラウドごとに、異なる観点で、異なる立ち位置で、様々なサービスが乱立しているため、違うベンダーを組み合わせると意外と上手く動く、そのようなパターンもあります。そのあたりは非常に複雑なので、常に最新の情報を追っていかないと、すぐに品質が悪くなりますし、望みのシステムはできません。リサーチを継続しながら実装も並行して進めていく、そうしたところの課題感から、我々のような専門的な会社に頼るというところも大きいのではないかと思います。
あとは、教師データを用意したりチューニングしたりといった作業には、どうしてもノウハウが必要になってきます。そこはガッツリとシステムを作り込む話ではないのですが、例えば、プロットの入れ方をどう調整するのか、標準で用意しているドキュメントの検索ツールをどう使うのかなど、そういったところでもノウハウが必要になってくるので、そのあたりが難しいと感じて依頼するケースが多いように思います。ノウハウというものは日々更新されるものなので、そういったものはAIをやっているベンダーが導入をサポートすることで生き残っていくであろうと思っています。
ー 実際に「どれくらい工数が削減できました」や「どれくらい簡単に導入できました」など、サービスプロバイダーの協力によって得られた具体的な導入効果や事例などがあれば教えてください。
大川氏:そうですね。まさに現在検証しているところではあるので、それによって「何人月の工数が削減できました」という具体的な効果はこれからというところです。ただし、使っていただいているなかでは、いろいろなPoCなどをやっているなかで、満足いく回答が全体の70%以上に上りましたというお声はいただいているので、かなり品質的にも施策によっては非常によく出ているのかなと感じています。
あとは、商品説明や顧客対応などの領域でも、非常に大きな手応えを感じています。例えば、インサイドセールスが商品の問い合わせを受け付ける場合、FAQがまとまっていない商品なんかだと、人間が商品のカタログを片っ端から読んで回答する必要があるので大変です。カタログの情報やFAQのデータを吸収したAIを活用することで、人間の代わりにAIが顧客対応をしてくれるというところでも、すごくラクになると感じています。
ー 品質の高い回答が70%以上というお話でしたが、人事労務に関する質問を人間の担当者にした場合に一回でちゃんと解決する割合は、体感ですがもっと低いかと思います。7割以上の精度というのはすごいですね。
大川氏:そうですね。この仕事を続けてきて思うことは「人間って意外と他人の言葉を正確に理解できていないんだな」ということです。ある程度明確な教師データさえ揃えることができれば、実は人間よりもAIの方が正確に言語を理解している。みたいなことを少し思いました。おそらく、知識がないというよりも、うまく言葉を聞き取れていないんだと思うんですよ。結構人間っていい加減に聞いてますよね?っていう。
一方で、まだ品質が出ていない施策などもありますので、そこはすごく悩みながら進めているところではあるのですが、例えば「連休はどう取れば良いですか?」といったような会社の規定や規約に関する質問に対しては、品質の高い回答を返してくれるのですが、独自のデータでも冗長度が高いような質問をしてしまうと、やはり品質は落ちてくるので、教師データのチューニングとプロンプトの入り口をどうやって制御するかというのが今後のポイントになってくるのかなと思っています。
これからのECプラットフォームは、仕組みが根底から変わる
ー 本来人間がやるべきだったところを、今後はAIが効率的に伴奏してくれる、そういったところがCuon様の提供価値というわけですね。今後のユーザー様に対して、他に提供していきたい価値などがあれば教えてください。
大川氏:そもそも伴走というのは既存のシステムがあって、それを効率化させるものだと思うんです。もちろん弊社が力を入れて取り組んでいるところではありますが、昨今の生成AIを見ていて思うのは、むしろ既存のシステムをアップグレードするというよりも、今後は基本的な仕組み自体が変わるのではないかと思っています。
例えば、現状のECサイトの場合、ショッピングサイトにユーザーが訪れて、商品をカートに入れて、AIがオススメの商品をレコメンドしてくれる、というのが一般的な流れです。そうではなくて、AIと人間が欲しい商品を言葉でやり取りする形で発展していくのではないかなと。根底から今までのやり方が変わる世界観が来てしまうと、我々ウェブシステムを開発しているCuonにとってはディスラプト的な展開だと捉えることもできますが、逆にものすごいビジネスチャンスだとも思っていまして、既存のサービスの価値を上げつつも、全く仕組みの違う、根底から考え方が異なるようなところにも上手く刺さっていって、この世界全体の真の意味でのDXに貢献できれば、Cuonとしてもハッピーなんじゃないのかなと思います。
ー たしかに、レコメンド機能というものは多くのECに備わっていると思いますが、そういった受け身の機能ではなくて、もっと積極的に攻めた営業さんが一人一人に付随していくといったようなイメージでしょうか?
伊藤氏:そうですね。僕が今ちょっと考えているところでは、Cuonはウェブのシステム開発を得意としている会社ですので、そうしたシステム開発の領域と生成AIとの組み合わせというところで、お客様に新しい価値を提供できれば良いのかなと考えています。
生成AIの特徴は自然言語処理です。自然な会話から感情の分析をしたり、ユーザーの心理状態を類推したりといった部分ですね。これを今までのシステムで構築しようとすると、テキストから感情の分析をしなければならないため、非常にレベルが高く、簡単にできるものではありません。そうした部分を生成AIに任せることで、より正確に、客観的に、工数も短く、お客様に価値を提供することができます。自然言語処理の特徴を活かしつつウェブサービスと組み合わせていくということができれば、Cuonとしてはすごく良いのかなと考えていますね。
◆お話を伺った方
株式会社Cuon
DX Sales&Consulting部 セールスディレクター 大川 啓一 氏
DX Sales&Consulting部 マネージャー 伊藤 翔 氏
投稿 生成AI導入の秘訣と導入支援サービスを利用することのメリット ー 生成AI導入支援サービスを提供するCuonに聞く は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ChatGPTで何ができる?どんな仕事で活用できるのか は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、ChatGPTでできること、活用できる業務についてご紹介します。現段階で本格導入が難しい理由や、今後の付き合い方も解説しますので、新技術の現状を詳しく把握していきましょう。
ChatGPTでできること
AI技術を研究するOpenAIの「ChatGPT」は、昨年末から非常に注目が集まる対話側AIツールです。非常に進化が速いAIの領域ですが、現時点でChatGPTが得意とする項目について確認していきます。
1・質問に対する答えの提示
ChatGPTは、ユーザーが入力した「質問」に対して正しいと思われる「答え」を提示してくれます。
従来、調べものをする際にはGoogle検索、Yahoo検索といった検索機能を利用するのが一般的でした。また、検索した結果の中から、自身で目的の内容を探し出し、情報の正しさを判断する必要があったでしょう。
一方で、ChatGPTは、質問した内容に対して、ビッグデータに蓄積された情報から正しい情報を要約して提示してくれます。一般的な検索と違い、質問に対する答えを提示してくれるため、自身で大量の情報を比較する必要がなくなるのです。
2・説明や文章の執筆
ChatGPTは、説明や文章の執筆を得意とします。
たとえば「〇〇について説明して」と指示を出せば、その内容に沿う文章を書き出してくれます。また、より具体的に指示したり、条件を設定したりすると、細かいニュアンスを読み取って、まるで人間が書き上げたような文章を作り出してくれます。
ChatGPTが書く文章は、見出しが表示されたり、要点を箇条書きでまとめてくれたりと、読み手側が理解しやすいのが特徴です。誰かに「ある内容」を説明できずに困っているのなら、ChatGPTを活用してみてはいかがでしょうか。
3・プログラミング言語のコーディング
ChatGPTはプログラム言語のコーディングを指示できます。
JavaやC++、Pythonといったさまざまなプログラム言語はもちろん、HTML,CSSといったマークアップ言語にも対応可能です。「こういった表現がしたい」と具体的に伝えると、コードを提案してもらえるほか、自身が書いたコードのミスや改良案を提案してもらえます。
また、プログラミング初心者のサポートツール、エラー発生の原因究明ツールとして利用できるのが魅力です。ChatGPTは、実際にコード画面で提案してくれるため、そのコードをコピペしてテストできます。
ChatGPTを活用できる仕事とは?
ChatGPTは、仕事に活用できる便利なサービスとして話題になっています。現段階でどのような仕事に活用できるのか、参考例を3つ見ていきましょう。
小説家や音楽家といったアーティスト
ChatGPTは、指定したキーワードに関連する情報や文字列を、アイデアとして提案してくれます。たとえば、小説家や音楽家はChatGPTを活用することで、読みやすい文章や歌詞を生み出すことが可能です。
まずは、自身で小説用の文章や歌詞案を作成します。その内容をChatGPTのメッセージ欄に記載し「記載した内容をベースに文章案(歌詞案)を作ってください」と指示をするだけで、即座にアイデアを提案してくれるのが特徴です。
また、具体的な文章や歌詞を使わずとも、キーワードを並べて指示するだけで、文章や歌詞を作り出してくれます。chatGPTは、アイデアやキーワードが思い浮かばず困った際のサポートツールです。第二の脳として、良いアイデアを提案してくれるでしょう。
キャッチコピーや記事を生み出すライター
ChatGPTは、ライターとの相性が良いツールです。たとえば、読者の心に刺さるキャッチコピーのアイデアや、リサーチに時間のかかる記事構成を即座に提案してくれます。また、記事全体の流れを作るだけではなく、実際に各項目の執筆を指示することが可能です。
ChatGPTを活用すれば、提案してもらったキャッチコピーをブラッシュアップして活用できます。また、作りたい記事をすべてChatGPTに書き上げさせて、装飾や文章の調整を自身で行うなど、時間のかかるライターの業務を効率化してくれるのが魅力です。
システムやツールを作るプログラマー
ChatGPTは、多種多様なプログラム言語、マークアップ言語に対応できることから、コーディングを行うプログラマーとの相性が良いツールです。
作りたいシステムやツールのフレームワークを提案させたり、動作エラーのチェックに必要なデバッグ作業を指示したりと、専門知識が必要なプログラミング作業を効率化できます。また、何万行も記載が必要なコーディングをチェックさせ、無駄のないコードへと変更することも可能です。
ChatGPTは過去の事例・データをもとに、プログラミングをサポートしてくれるため、初心者から上級者の目的に添って、幅広いサポートを行ってくれるのが魅力です。
学術研究
期待値の高い領域に学術研究が挙げられますその理由としては、作成した文献のレビューであったり、類似する研究論文を即座に探すことができたりと、研究活動における手間のかかる工程を一手に引き受けてくれる可能性を秘めています。ただし、現状では論文作成までは認められていないケースが多く、今後の展開に注目されます。
ChatGPTを本格導入できない理由
便利に活用できるChatGPTですが、まだ始まったばかりのツールで、現状は仕事に本格導入することはおすすめしません。次に、ChatGPTの本格導入を様子見すべき理由を2つご紹介します。
間違った答えが返ってくる場合がある
ChatGPTに質問や指示を行った際、必ず正しい答えが返ってくるわけではありません。極端な例ではありますが、参考として次のような返答が返ってくる可能性もあるのです。
- 【質問】りんごの色は? 【正しい答え】赤色 【誤った答え】青色
また、正しい答えを出してくれる場合もあれば、誤った情報が紛れている場合があるなど、タイミングによって、精度が変化することにも注意しなければなりません。ChatGPTから出力された情報をまるごとコピペするのではなく、内容に誤りがないか確認したうえでブラッシュアップを加えて活用しましょう。
読み手が理解しづらい内容で出力される
ChatGPTは、まるで人間が書いたような文章を作り出してくれるのが特徴です。しかし、文章に感情が込められていなかったり、「~ます。~ます。」と同じ文末が連続していたりと、読みづらい内容として出力される場合があります。
提案された文章をそのまま利用すると、読者が読みづらく、可読性を落としてしまう恐れもある状況です。よって、提案された文章をそのまま利用するのではなく、一度人間の手で編集を加える必要があると理解して利用しましょう。
ChatGPTとは今後どのように付き合うべき?
便利な機能を持つChatGPTには利用するメリットがある一方、気を付けて利用しなければならないデメリットもあります。
もし、これから仕事にChatGPTを活用していく予定なら、現段階ではアイデア出しのサポートツールとして利用しましょう。出力された情報は必ず人間の目でチェックしたうえで、ブラッシュアップが必要です。出力された情報をまるごと利用するのはおすすめできないので注意してください。
しかし、ChatGPTは時間の経過に合わせて精度が高まっているのも事実です。定期的なバージョンアップにより、今まで以上に高品質な出力ができるようになるため、AI技術の動向を追っていくことをおすすめします。
ChatGPTについて理解したら他サービスと比較してみよう
アイデア出し、文章作成、プログラミングといった作業をサポートしてくれるChatGPTは、小説家や音楽家、ライター、プログラマーの作業を効率化してくれます。また、注意点などを理解して正しく活用すれば、効率的により良い成果を生み出せるでしょう。
世界中には、ChatGPT以外にも、さまざまなAIライティングツールが提供されています。日々進化を続ける技術のため、他ツールの特徴などを比較しつつ、仕事に活用できそうなサービスを探してみてはいかがでしょうか。
投稿 ChatGPTで何ができる?どんな仕事で活用できるのか は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 マシンラーニング(機械学習)をおさらい!ディープラーニングとの違いやメリデメを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、マシンラーニング(機械学習)とディープラーニングの違いについて解説します。
マシンラーニング(機械学習)とは?
マシンラーニング(機械学習)とは、AI技術を搭載したシステムに知識とルールを学習させ、高精度の処理を実施する技術のことです。プログラミング言語のPythonを使って構築されています。主に次の3タイプの学習が行われ、用途ごとに学習方法が使い分けられています。
- 教師あり学習(顔認証、天候予測)
- 教師なし学習(ECサイトのレコメンド機能)
- 強化学習(ゲーム、自動運転)
この3つには、答えを教えるか否かという違いがあります。学習方法を変えることで「期待通りの正解を導き出すシステム」と、「人が予期しない答えを導き出すシステム」を生み出せるため使い分けられているのです。
また、マシンラーニング(機械学習)を実施する際には、ビッグデータを読み込ませて学習させるのが特徴です。過去データを大量に読み込ませることで、精度の高い分析が行えます。
マシンラーニング(機械学習)とディープラーニングの違い
マシンラーニング(機械学習)と似ているAI技術に、ディープラーニングがあります。
マシンラーニング(機械学習)は、事前に準備したアルゴリズムの指定数に従ってデータを分析します。一方ディープラーニングは、アルゴリズムの数を指定せずとも自動で分析を階層化します。つまり次のような違いを持っています。
- 人間による指示が必要か
- 判断内容の指示が必要か
- 複数の視点で分析できるか
このことから、マシンラーニング(機械学習)は、莫大なデータ根拠をもとに判断する「ロボット」であり、ディープラーニングは、検討を含むAI基盤に判断を任せる「人間」に近いのが特徴です。
さらには、マシンラーニング(機械学習)は人間による指示が必要ですが、ディープラーニングは指示がなくとも自動で学習していくことから、似て非なるAI機能だと言えます。
マシンラーニング(機械学習)を導入するメリット
マシンラーニング(機械学習)のメリットは次の通りです。
- 作業コストの削減
- 複雑な処理に対応
- 低価格で利用可能
業務効率化に役立つ項目です。ひとつずつ見ていきましょう。
作業コストの削減
データ入力といった繰り返し作業は、今まで人間が実施していました。しかしこの作業は、集中力の低下によるミス発生といったリスクがあります。また、データ量が莫大であればあるだけ、人間の作業コストが膨れ上がります。
マシンラーニング(機械学習)を導入して学習を進めていけば、人間の作業だと時間がかかってしまう処理を一瞬で解決できます。データ分類や整理といった認識能力に優れていることから、作業コストの大幅な節約につながります。
複雑な処理に対応
マシンラーニング(機械学習)は、単純作業だけでなく複雑な作業にも対応できます。過去の情報から将来予測を行ったり、自動運転などのハンドル操作やリアルタイムでの障害物判断を行ったりと、複数の処理を同時に実施できます。
将棋ゲームやロボット操作にも活用できることから、多分野で注目されています。
低価格で利用可能
マシンラーニング(機械学習)は、AI技術の中でも低価格で利用できます。ディープラーニングは高度な深層学習を行うことから、利用コストが高く設定されています。一方マシンラーニング(機械学習)は無料で利用できる製品や、低価格で利用できる製品が多数提供されています。
予算的にもハードルが低いことから、初めてAI技術を導入する会社にとっても利用しやすい技術だと言えます。
マシンラーニング(機械学習)を導入するデメリット
マシンラーニング(機械学習)のデメリットは次の通りです。
- 大量のデータ学習が必要
- 検討内容がブラックボックスになりがち
- 人の判断が必要
人間による指示や判断が必要です。導入前に確認しておきましょう。
大量のデータ学習が必要
マシンラーニング(機械学習)を利用するときには、大量のデータを読み込ませて学習させる必要があります。そのため少数のデータだけで学習させても、高い精度の分析が期待できないことを把握しておきましょう。
学習数が少なければ、事例の少ないデータ判断が難しく、正しい答えを導き出せません。マシンラーニング(機械学習)はビッグデータを扱う業務向きのため、まずは導入できそうな仕事があるか確認してみましょう。
検討内容がブラックボックスになりがち
マシンラーニング(機械学習)は業務効率化が実現するシステムですが、検討などの情報を出力できないことを知っておきましょう。莫大なデータを処理しつつ答えを導き出すことから、検討内容がまとめられないのです。
つまり、出力された結果の根拠を探そうとしてもブラックボックスになってしまうので、根拠が必要な業務への適用が難しいという特徴があります。
人の判断が必要
マシンラーニング(機械学習)はアルゴリズムのルールに則った判断を実施するため、導き出された答えが必ず正しいとは限りません。
学習方法のひとつである「教師あり学習」のように、導き出した答えは、最終的に人によって判断する必要があります。完全に機械任せにはできないことを把握しておきましょう。
マシンラーニング(機械学習)について理解したら製品を比較検討しよう
AI技術のひとつであるマシンラーニング(機械学習)は、莫大なデータを取り扱う企業にとって欠かせないシステムとなっています。大量のデータを読み込ませて学習させることによって、大幅なコスト削減が期待できます。
マシンラーニング(機械学習)について詳しく理解してから導入を検討したいのなら、まずはITreviewが提供するツール紹介ページを参考に、気になる製品を比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
投稿 マシンラーニング(機械学習)をおさらい!ディープラーニングとの違いやメリデメを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 マシンラーニング(機械学習)はビジネスの現場にどう活用する?事例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、マシンラーニング(機械学習)の活用事例について詳しく解説します。幅広い業務分野で活用できる技術ですので、ぜひ参考にしてください。
ビジネスで利用するマシンラーニング(機械学習)とは?
マシンラーニング(機械学習)とは、プログラミング言語の「Python」でアルゴリズムを構築し、そのルールに則り莫大なデータを学習させることで判断精度を高めていく技術のことです。様々な用途に活用でき、次のような分野で利用されています。
- データ分析
- 顔認識
- 自動運転
またマシンラーニング(機械学習)は、企業が持つ過去の業務データなどの「ビッグデータ」を使って学習できます。データ学習というトレーニングを積み重ねることで、特定のタスクの精度を高められるため、人材不足や繰り返し作業によるミスといった慢性的な企業課題を解決できます。
活用例1:小売業にて顧客情報分析で店舗の売り上げアップに活用
マシンラーニング(機械学習)を導入すると、サービス・商品を利用する顧客情報を分析できます。
店舗型企業といった利用者がいるからこそ成り立つ仕事は、時期や世の中の流れによって利益も変化します。このとき、売り上げアップを目標としているなら、顧客情報をマシンラーニング(機械学習)することで、次のことを分析できると知っておきましょう。
- 訪問時間(月ごと、季節ごと)
- 客層(年齢、性別)
- 商品(人気、不人気)
マシンラーニング(機械学習)を活用することで、顧客情報から店舗の需要を分析できます。どのような人物がどのような商品を好むのか「購入傾向」を分析できるので、次のような売り上げアップ対策が可能です。
- 顧客の性別や年齢、購入商品から「イチオシ商品」を決められる
- 顧客の移動ルートを分析して商品が売れやすい「配置」を検討できる
スマホアプリといったサービスがあれば、そこから顧客情報を蓄積できます。入力情報の他にもアンケートなどを活用することで、マシンラーニング(機械学習)を最大限に活用できます。
活用例2:農業にて気象データ分析を耕作作業に活用
マシンラーニング(機械学習)を導入すると、気候変動といった将来予測が行えます。
農業などの天候が関わる仕事では、事前に天気を予測して収穫時期や農作業のタイミングを検討する必要があります。しかし、天気は日々変化するため、人間による正確な予測は不可能です。
ここで役立つのがマシンラーニング(機械学習)です。気象庁で公開されている地域ごとの過去の気象データを学習させていけば、次のようなことに活かせます。
- 1か月先の天気の予測
- 豪雨災害が起きやすい時期と予兆の判断
- 農作物の収穫時期の決定
常に自然と隣り合わせで仕事を行う農業は、人間による予想が難しい場面が多々あります。自然災害の影響で収穫物に被害が起きてしまうこともあるので、マシンラーニング(機械学習)で将来予測を実施することで、効率の良い農業を実現できます。
活用例3:小売業にて商品の販売分析で在庫管理に活用
マシンラーニング(機械学習)を導入すると、商品の販売分析や在庫管理に活用できます。
商品を販売するときには、在庫管理が必要です。しかし、人による判断で在庫数を決めるのは難しく、廃棄商品が出てくることが多々あります。このとき、マシンラーニング(機械学習)に過去の在庫情報を読み込ませていけば、次のような在庫管理が可能です。
- 時期ごとの商品販売数から入荷数を決定
- 人気メーカーを割り出して在庫を確保
多くの店舗型企業では、在庫情報がデータ化されています。既存のデータ(ビッグデータ)をそのままマシンラーニング(機械学習)に読み込ませることができるので、導入後すぐに在庫管理を効率化できるのが魅力です。
また、マシンラーニング(機械学習)はリアルタイムの情報も利用できます。データ数が多ければ多いほど高い精度の分析を行えることから、ぜひ過去データを役立ててみてください。
活用例4:運送業にて交通状況の予測分析で効率的な配送計画を立てる
混雑や渋滞の予測に活用できます。
運送業では荷物を効率的に運び、件数を多くこなすことで売り上げのアップのカギです。そこで、混雑しがちな時間帯やエリアなどを事前に把握しておくことで、配達車両の移動をスムーズにするサポートが可能になります。トラックやタクシーなど、公道を活用する事業者にとっては、ビジネスに欠かせないものとなるでしょう。
マシンラーニング(機械学習)を選ぶポイント
マシンラーニング(機械学習)が搭載された製品を探してみると、複数のサービスが見つかります。その中でも会社がかかえる課題を解決する製品を導入したいなら、次のポイントをおさえて製品を選びましょう。
- 価格
- 出力情報
- サービスの使いやすさ
初めてマシンラーニング(機械学習)を導入する会社は、専門知識をそれほど必要としない製品を選ぶのがおすすめです。直感的な操作でデータを読み込ませられたり、出力情報が見やすかったりする製品を選ぶことで、使い方が分からないという問題を解決しストレスフリーで利用できます。
また、中級者~上級者向けの製品も販売されています。初心者には理解が難しい機能が登場し、操作に挫折する場合があるので気を付けましょう。
機械学習の活用事例が理解できたら製品を比較検討しよう
マシンラーニング(機械学習)は、データを扱う様々な分野で活用できます。現状の分析はもちろん、将来予測にも役立つAI技術であるため、分析関連の課題を抱えている企業なら導入をおすすめします。
しかし、選ぶ商品によって利用料金や機能に細かい違いがあるので、事前に価格やサービス内容を確認したうえで比較検討を行いましょう。まだマシンラーニング(機械学習)に触れたことがない人は、最初に無料版・デモ版を利用するのがおすすめです。
もっと多くのマシンラーニング(機械学習)を比較して自社に合ったツールを探したい方は、ITreviewが提供するサービス紹介ページを参考に複数の製品を比較してみましょう。実際に製品を使用した人のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
投稿 マシンラーニング(機械学習)はビジネスの現場にどう活用する?事例を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>