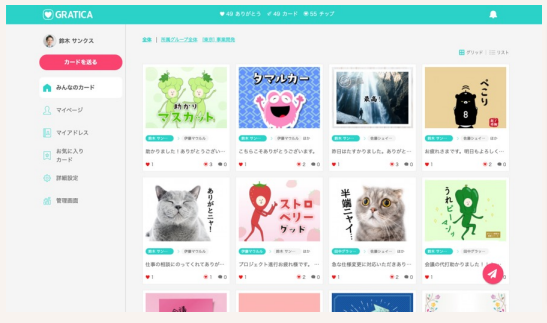投稿 ITreview会員へ「安否確認システム」の導入実態を調査しました は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>能登半島地震の発生後、ITreviewの「安否確認システム」を集約したカテゴリーページでは、1月期におけるページ表示回数が前月に比べ6倍、閲覧ユーザー数は7倍に増加しました。
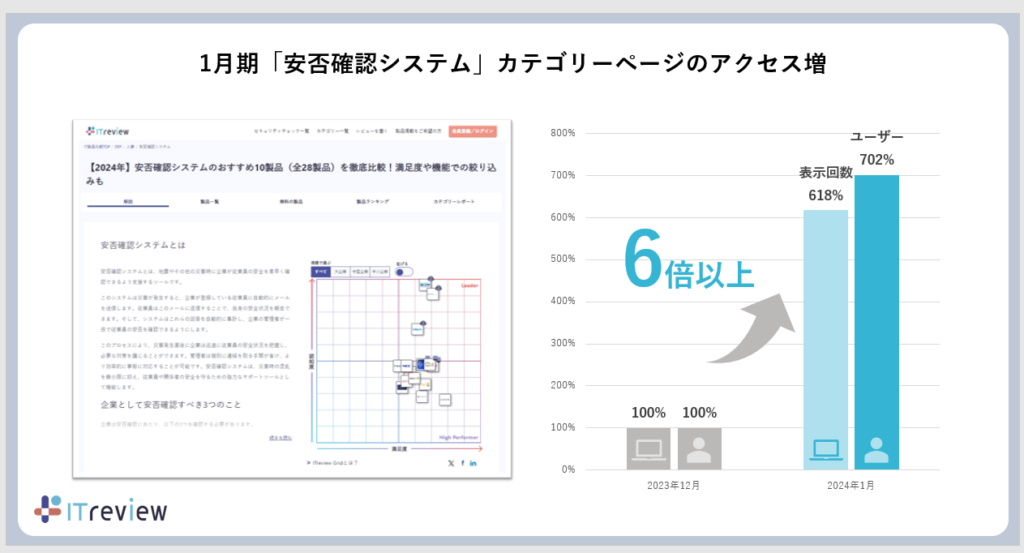
このような状況を踏まえ、私たちは国内企業における安否確認システムの導入状況を明らかにし、企業が今後、安否確認システムの選定や導入に役立つ情報を提供したいと考え、本調査を実施しました。
「安否確認システム」とは?
安否確認システムとは、災害や緊急事態などの際に、自社の社員もしくは社員の家族も含めた安否情報を迅速に確認するためのシステムを言います。
安否確認システムの導入によって、被災者や影響を受けた人々の安否情報を素早く収集することができるため、適切な支援を行うことができます。ITreviewでは、安否確認システム28製品を紹介しています。
約55%が勤務先で安否確認システムを導入中と回答
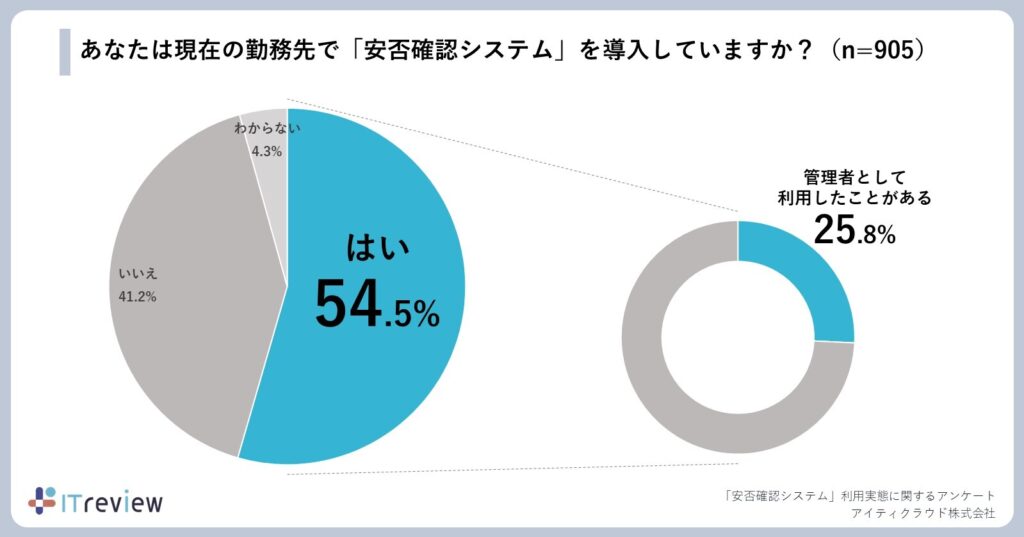
法人向けIT製品のレビューサイトである「ITreview」の会員を対象に、勤務先における安否確認システムの導入状況を調査しました。
結果、導入中であると回答したユーザーは54.5%という結果になりました。また、導入中と回答したユーザーのうち四人に一人が管理者※としてシステムを活用していることがわかりました。
※管理者とは、安否確認メッセージの配信設定や回答結果の収集・閲覧ができる立場を指します。
ここからは実際に、安否確認システムをIT管理者として活用しているユーザーレビューを紹介します。
安否確認システムのユーザーレビュー

安否確認だけでなく社内事故速報ツールとしても利用
利用開始から10年以上経過しており、社内に浸透しています。新入社員へは、入社時の手続き案内を行う際にシステム利用趣旨説明と併せて登録をお願いしています。
製品名:Biz安否確認/一斉通報
企業名:非公開(企業所属確認済)
従業員規模:100-300人未満
業種:総合(建設・建築)

シンプルな安否確認サービスとして
各社員(正・定時・嘱託・派遣・ポスティング業務)で使用している機器が会社貸与から個人物まで様々だが、ガラホからスマホまでシンプルにインターネット(メール)が使用できれば対応できるところが良い。
製品名:セコム安否確認サービス
企業名:非公開(企業所属確認済)
従業員規模:100-300人未満
業種:保険

電話とメールの同時配信が出来、応答も簡単です。
この製品の特長は、電話とメールの同時配信が出来ること。受け取った側の対応が簡単に出来ること。が特徴です。また、配信側は受け取るユーザーの規模を自由に設定することが出来るので、地域やグループを設定することが出来ます。
製品名:エマージェンシーコール
企業名:非公開(企業所属確認済)
従業員規模:300-1000人未満
業種:総合(建設・建築)

実際に使用してみた感想
まず登録のしやすさがこれまで使用した安否システムとは違いスムーズに行えた。使用の実感としても返信のしやすさ、手軽さはスマホ操作が苦手な方でも苦手意識を持たずにできると思いました。
製品名:安否コール
企業名:非公開(企業所属確認済)
従業員規模:300-1000人未満
業種:その他製造業
国内最大級のレビュー掲載数を誇るITreviewでは、すべてのレビューを自由に閲覧いただけます。
レビューは、実際に製品を利用しているユーザーからのみ投稿いただいており、独自のガイドラインに則ってすべての内容を人の目で確認・公開しています。
IT管理者に限らず、導入決定者やユーザーの立場で書かれたレビューも多数掲載しているので、製品利用者が直面する様々な課題や利点に関する洞察を得ることができます。
システム導入を検討中との回答は12%
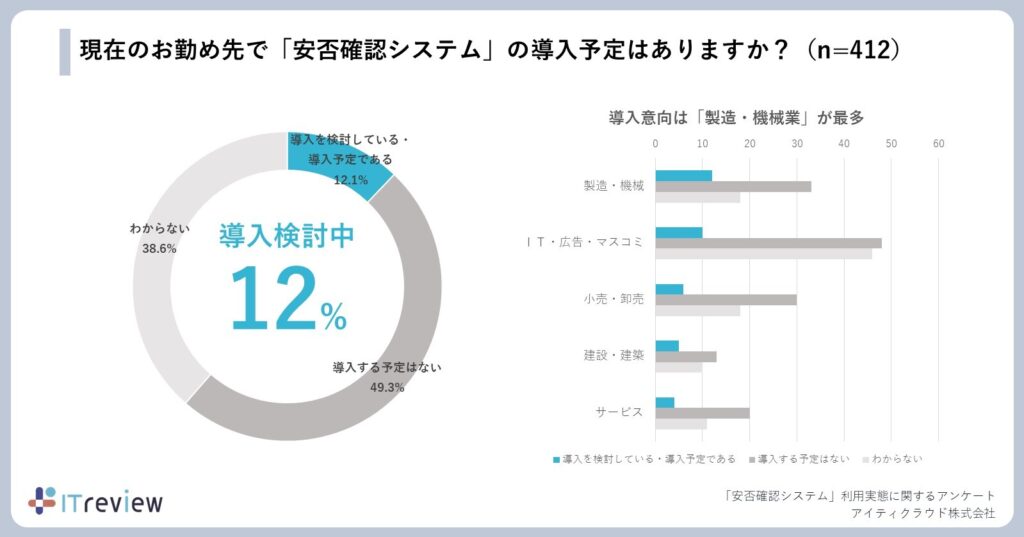
安否確認システムについて、未導入または導入状況がわからないと回答したユーザーへ、安否確認システムの導入予定を伺いました。
結果、導入を検討中との回答は12.1%に留まりました。業種別の集計では、導入検討中との回答が最も多かったのは「製造・機械業」となりました。
調査について
- 実施期間:2024年2月14日~2月20日
- 調査対象:法人向けIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」登録会員
- 調査方法:インターネット調査
- 調査期間:自社調査
- 有効回答数:905
あなたの勤務先では「安否確認システム」を導入中でしょうか?
ITreviewでは、安否確認システムを含む、法人向けIT製品のユーザーレビューを募集しています。
投稿されたレビューは、製品導入を考えているユーザーが参考にするだけでなく、すでに製品を利用しているユーザーにとっては活用のヒントになり、製品を提供するベンダーにとっては、サービスを改良する際の重要な情報源として役立っています。あなたの声が必要です。
【3月1日開始】レビューキャンペーンのお知らせ
ITreviewに掲載中の全製品を対象としたレビューキャンペーンを期間限定で開催しています。
キャンペーンでレビューを投稿いただくと、レビューが1件掲載されるたびにPayPayポイント最大1,000円分をプレゼントします。詳細は以下のバナーをクリックしてキャンペーンページでご確認ください。
社内の業務連絡で使用しているツールや勤怠を記録するためのシステム、社内資料作成のために使っているソフトウェアなど、9,000超の登録製品からあなたが利用中の製品を検索してレビューを投稿してみてください。
投稿 ITreview会員へ「安否確認システム」の導入実態を調査しました は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 企業が安否確認システムを入れるべき3つの理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、安否確認システムの必要性についてご紹介します。また、利用できる主な機能や導入手順も解説しますので、システム導入の参考にしてみてください。
企業が安否確認ツールを入れるべき3つの理由
大地震や津波といった緊急事態は、日本に住んでいる限り避けては通れない課題です。また、緊急事態が発生すると、企業経営に大きな影響が発生する恐れもあるでしょう。そこで役立つのが、従業員の安否を確認できる安否確認ツールです。
まずは、企業が安否確認ツールを導入すべき理由を3つご紹介します。
1.緊急事態の際に事業を立て直しやすくなる
災害による緊急事態が発生すると、従業員にもしものことが起こるかもしれません。なかには災害で動けない人や、ケガをしてしまう人もいるでしょう。このとき、安否確認ツールがあれば、誰が被害に遭ったのか、誰が問題なく動けるのかを把握できます。
安否確認ツールでは、クラウドを通じて従業員の状況が分かるため、緊急時の「事業の立て直し計画」を再構築しやすいのが特徴です。また、緊急事態の影響で、そのまま経営難に陥る企業もあります。早い段階で従業員の状況を把握し、事業の立て直しを検討できれば、企業経営を立て直す可能性を高められるでしょう。
2.従業員の安否状況を自動でリスト化できる
企業は、災害といった緊急事態が発生した際、従業員の安否確認を行わなければなりません。これは、中小企業庁の「中小企業BCP策定運用指針」にも記載されており、緊急連絡網を回して、従業員一人ひとりの状況を把握する必要があります。このとき、効率的に安否確認を実施できるのが安否確認ツールです。
クラウドを通じて従業員が自主的に安否状況を入力するため、管理ミスや確認漏れを防止できます。報告がない従業員だけに集中して安否状況を確認できるため、ハイスピードな対応が可能です。
3.従業員の家族も含めて安否確認できる
もしかすると、就業時間中に緊急事態が発生するかもしれません。家族のことを心配して、自ら危険に飛び込む従業員もいるでしょう。このとき、安否確認ツールを導入しておけば、その危険性を回避しやすくなります。
安否確認ツールは、従業員の連絡先と一緒に家族の連絡先も管理可能です。従業員のみならず、その家族にも安否確認ツールの利用ルールを整えておけば、電話回線がつながりにくい状況でも素早く安否を確認できます。
安否確認ツールの代表的な機能
安否確認ツールは、企業と従業員、そしてその家族をつなぐ便利な機能を搭載しています。その中でもメインで利用するのが、こちらで紹介する2つの機能です。各機能の特徴を見ていきましょう。
メール送信機能
メール送信機能とは、従業員やその家族宛てに自動でメールを送信する機能です。ワンクリックで登録された人たちにメールが届くので、従業員がメールに返信するだけで、即座に安否状況を把握できます。
また、送信するメールの文章は、自社の目的に合わせて調整可能です。メール内に緊急事態時に役立つ情報のリンクを掲載しておけば、安否確認できるだけでなく、従業員が緊急事態時でも安全に過ごすための情報を提供できます。
データ集計・管理機能
データ集計・管理機能とは、前述したメール送信にリアクションを出してくれた人たちのデータを集計し、一覧表として管理できる機能のことです。管理者が個別の情報を人力で管理する必要がないことはもちろん、従業員の家族の情報も管理できます。
クラウドを通じて情報を管理するツールも豊富にあることから、管理データの紛失やバックアップといったサポートが充実しているのが特徴です。データ集計・管理機能を用いることで、安否確認を行う担当者の負担を削減できます。
安否管理ツールの導入手順
安否確認ツールは簡単に導入できる便利なツールです。しかし、いざ導入したとしても、うまく運用できずに途中で利用を止めてしまう人もいます。これは、導入手順を理解せずに利用していることが原因です。
そこで最後に、スムーズな導入・運用を実現するために、3ステップで導入手順をご紹介します。ツールの準備に必要なポイントや、従業員との連携に必要なポイントを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
利用者・関係者を登録する
安否確認ツールを導入したら、まずは以下に示す利用者・関係者の情報を登録しましょう。
【登録すべき対象者】
- 経営者
- 従業員
- 経営者や従業員と関係する家族
- 取引先
【登録する内容】
- 名前
- 連絡先(メール・電話番号)
- 住所
もともと従業員の情報を管理している企業も多いので、登録準備は簡単です。また、従業員やその家族だけでなく、企業経営を左右する取引先などの情報も登録しておきましょう。経営に影響を及ぼす関係者すべてを登録することで、ハイスピードな事業の立て直しが可能です。
社内教育を実施する
安否確認ツールを導入して、関係者の情報を登録できたら、次に従業員への告知・社内教育を実施しましょう。従業員の中には、安否確認ツールの存在を把握しておらず、緊急事態の際にうまく活用してくれない人もいます。社内に安否確認ツールの導入を告知したり、家族用の資料を準備したりしておくとよいでしょう。
また、ただツールがあることを伝えるのではなく、社内教育を実施して実際に利用してみることが大切です。どのように利用するツールなのか、従業員やその家族がイメージできることが最終的なゴールとなります。
動作テスト・本格運用
前述したすべての準備が整ったら、実際に運用を開始して動作テストを行いましょう。登録した従業員やその家族の抜け・漏れがないか確認しながらテストを実施してください。たとえば、緊急事態になったことを想定し、実際に緊急連絡メールを送信してみるとよいでしょう。
従業員やその家族に、メールを送信するタイミングを伝えておけば、テストの精度を実証できます。定期的に緊急時テストと称して訓練することによって、本格運用が可能です。
安否確認ツールの必要性を理解したら製品を比較してみよう
緊急事態が発生した際には、従業員の安否確認を確認し、企業の経営を安定化させる必要があります。しかし、担当者の人力による安否確認では、確認に抜け・漏れがあることはもちろん、管理の負担が大きくなってしまうでしょう。そこで、安否確認の効率化に役立つのが安否確認ツールです。
しかし、安否確認ツールといっても、さまざまなサービスが提供されています。安否確認ツールの機能などを比較検討して、自社に合ったより良いツールを見つけてください。
投稿 企業が安否確認システムを入れるべき3つの理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 人事評価にOKRを取り入れるメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、人事評価にOKRが必要とされる理由や導入するメリット・デメリットをご紹介します。目標設定や管理手法の検討に貢献する考え方なので、ぜひ参考にしてください。
OKRが人事評価に必要とされる2つの理由
米国のインテル社で誕生したOKRは、高頻度で設定・追跡・再評価を行う目標管理の手法です。GoogleやFacebookなどの有名企業が取り入れていることもあり、世界中で注目されています。
OKRは、中小企業といった一般企業の人事評価業務でも広く活用されています。まずは、OKRが人事評価に必要とされる理由を2つご紹介します。
急速な市場・消費者ニーズの変化
近年、急速な社会の変化に伴い、数多くの便利なサービスやシステムが登場しています。続々と新たな商品・製品が登場することも関係し、市場はめまぐるしく変化している状況です。
その影響を受けて、顧客となる消費者のニーズも変化しています。毎年のようにブームが発生したり、少し前まで「新しい」といわれていたものが、いつの間にか忘れ去られたりしていることもよくあるでしょう。
そういった急速な市場・消費者ニーズに企業が対応するためには、高頻度で目標設定・管理を行うOKRの考え方が欠かせません。人事評価を効率よく回し、企業全体で新たな取り組みにチャレンジすることが、現代において必要不可欠となっています。
従業員の働き方の変化
世の中の変化は、企業で働く従業員の働き方を変化させます。なかでも、新型コロナウイルスのまん延を皮切りに浸透していった「テレワーク」は、従業員の働き方を大きく変化させました。
働く場所を自由に選択できることはもちろん、顔を合わせずに仕事ができる状況は、一見働きやすいように感じます。しかし、企業の考え方を共有しづらかったり、チームを統率するのが難しかったりと、新たな課題が生まれている状況です。
激動する世の中に対応するためには、OKRを積極的に活用し、従業員全員の考え方や方向性を揃えていくことが必要だといえます。
人事評価にOKRを導入する3つのメリット
人事評価は、OKRを導入しなくても運用できます。しかし、OKRを導入することで得られるメリットが多いことをご存じでしょうか。続いて、OKRを導入する3つのメリットをご紹介します。
従業員のやりがいが生まれる
OKRでは、頻繁に設定・追跡・再評価を実施することから、次の項目を可視化できます。
- 従業員ごとの進捗状況
- 業務ごとの進捗状況
OKRを続けていけば、設定したゴールに向かって少しずつ評価値が高まっていくのが特徴です。またOKRを設定することにより、従業員全員のコミュニケーションが活性化します。目標に向かって一丸となり業務に励むことから、チームの団結力を作りやすいのがメリットです。
一定間隔で目標設定を行えば、状況の変化に対応するため、社内に協力関係が生まれていくでしょう。今まで関わりが薄かった社員間のコミュニケーションが活性化するのも、OKRの魅力だといえます。
人事評価の属人化を防止できる
人事評価は、人事担当者が中心となって実施するのが一般的です。そのため、従来の手法は担当者のバイアスによって、評価が属人化しやすい傾向にあります。
一方、OKRで目標設定や評価のルール決めを行っておけば、属人化の問題を解消できます。OKRを導入して目標設定と管理、ゴールを明確にしておけば、無駄のない効率的な人事評価を通して、正しい采配のもとで業務を実施できるでしょう。
会社で取り組む優先順位を「見える化」できる
OKRを導入すれば、人事評価の実施結果をグラフや表にまとめられます。会社全体の取り組みはもちろん、従業員の動き方まで詳しく分析できるため、世の中の動向に対して会社の「今」を知ることができるでしょう。
また、集計した情報を細かく分析していけば、目標に対して現状で「満足していること」「不足していること」を明確にできます。企業活動の中で改善の余地がある項目をあぶり出すことで、業務に優先順位をつけられます。改善を重ねつつ、品質を高めていけるのもOKRのメリットです。
人事評価にOKRを導入する3つのデメリット
OKRの使い方や導入の考え方を間違えてしまうと、デメリットを生み出してしまうため注意が必要です。最後に、人事評価OKRを導入する3つのデメリットをご紹介します。
導入に時間やコストがかかる
OKRの導入は、人事評価の手法を大きく変更することから、導入に時間やコストがかかってしまいます。しかし、計画・周知・教育などの段階を経ずに導入してしまうと、失敗しやすいため注意しましょう。
人事評価は、従業員と協力して実施することから、事前に導入の周知を行うことが大切です。人事評価のルール決めなどを行い、社内研修などで告知・教育することも必要でしょう。また、OKRの考え方に基づき効率よく運用するために、専用ツールの活用を検討する必要があります。
評価ミスが従業員の信頼に関わってくる
OKRでは、評価の指標を綿密にルール決めしておくことが大切です。もしOKRを導入して評価をミスした場合、従業員全員の評価にもミスが影響します。
その結果、従業員の業績に見合った評価が出ず、モチベーションが低下する要因になるかもしれません。また、従業員によって評価にばらつきがあり、軋轢を生み出してしまう可能性もあるでしょう。
綿密な準備を行わなければ、OKRの信用がなくなり人事評価に参加する従業員が減ってしまう点もデメリットです。
ボトムアップや主体性を育成したい企業には向いていない
OKRは、人事担当者を中心に経営者層と話し合いを行いながら、人事評価の目標設定やルール決めを行います。よって、現場からのボトムアップ(底上げ)や主体性を育成したいと考えている企業に不向きな管理手法です。
OKRは、企業全体が同じ考えを持って同じ方法性の中で動くことを主体とします。内勤と現場というように、働き方に大きな差のある企業だと、OKRの人事評価がうまく機能しません。
もし、ボトムアップや主体性の育成を行いたいのなら、社内全体で実施するOKRではなく、従業員と直属の上司で人事評価を行う「MBO」の導入が望ましいといえます。
メリット・デメリットを理解して効率よく人事評価を行おう
世界的大企業も利用している人事評価の手法であるOKRは、従業員のモチベーション向上やルールの属人化防止に役立つ考え方です。しかし、段階的に導入していかなければ、マイナスの要素を生み出す可能性があります。
今やOKRの考え方は、市場・消費者ニーズが激動する現代において、欠かせない人事評価の手法です。社内全体で一丸となり生産性を高めたいと考えているのなら、メリット・デメリットを理解したうえで導入を検討してみてください。
また上記を実践できる人事評価システム(OKRツール)をお探しの方は下記のページからツールの比較が可能です。ご興味のある方はぜひ参考にしてみてください。
投稿 人事評価にOKRを取り入れるメリット・デメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 クラウド型人事評価システムを選ぶ時に押さえておきたい5つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、導入前に押さえておきたいクラウド型人事評価システム(OKR)の魅力や、準備ポイントについてご紹介します。提供されている複数のシステムから1つを選ぶ比較ポイントも解説しますので、人事評価業務を効率化するヒントにしてみてください。
クラウド型人事評価システムを導入する3つの魅力
クラウド型人事評価システムは、人事評価業務の中で発生する目標設定や従業員・入社希望者の情報管理、業務状況評価といった作業をすべて電子化して管理効率を上げるサービスのことです。まず初めに、導入前に理解しておきたいシステムの魅力を3つご紹介します。
人事評価業務を効率化できる
クラウド型人事評価システムを導入すれば、従業員の働きを評価する「人事評価業務」を効率化できます。従来用いられてきた紙による評価手法からクラウドを通じて評価できるほか、登録した従業員のステータスを一元管理できるのが魅力です。
一元管理されている表では、フィルター検索を使うことによって特定の従業員を効率良く検索できます。業務状況や作業状況などをカテゴライズして対象者を抽出できるため、目的に合った検索を行えるのがメリットです。
また、クラウド型人事評価システムは自動集計機能も搭載しています。情報をグラフや表として可視化して、報告資料の作成をスピードアップできるのも魅力です。
最適な人材配置を検討できる
従業員の情報を一元管理すれば、次の項目を「ステータス」として1つのページに集計できます。
- スキル(資格)
- 経歴・実績
- 得意分野
例えば、業務状況とステータスを比較していけば、スキルに合った働きができているのかを確認できます。もしマイナスの働きをしている従業員がいる場合、集計されたデータを人材配置の検討に役立てられるでしょう。
適材適所を見抜くことで、従業員が働きやすい環境を整えられるのがメリットです。モチベーションを向上することによって、企業活動の活発化も期待できるでしょう。
人事評価をルール化できる
従来の人事評価では、人事担当者の経験と知識によって従業員の評価が決まっていました。なかには、バイアスのかかった評価が行われていたのも事実です。
一方、クラウド型人事評価システムを導入すれば、属人化しやすい人事評価にルールを設定できます。システム内で作成した評価シートを用いれば、誰が担当者になっても同じように評価を行えるのが魅力です。
クラウド型人事評価システムを導入する前に準備すべき3つのポイント
クラウド型人事評価システムの導入を検討しているなら、スムーズな移行のために事前準備が欠かせません。続いて、導入前に準備すべきポイントを3つご紹介します。
導入する目的を明確にする
システムを導入する前に、目的を明確にしておきましょう。例えば、次のように人事評価業務の中で発生する課題を抽出してください。自然と目的が見えてきます。
- 【課題】紙での管理に手間がかかっている
- 【目的】作業効率化のためにペーパーレス化を目指す
- 【課題】担当者によってルールがバラバラで困っている
- 【目的】一元管理やルール設定を行う
目的が定まっていれば、複数の中から自社の目的にぴったりのシステムを見つけやすくなります。また、使わない機能が多いのにも関わらず費用が高いシステムを避けるきっかけを生み出せるでしょう。
システムを適用する業務範囲を決める
人事担当者は、莫大な作業に忙殺されやすいため、事前にシステムを適用する業務範囲を決めておきましょう。なかでも人事評価は、作業量が多いのが特徴です。主に次に示す作業を実施します。
- 設定(ルール設定・目標設定)
- 面談(初回・中間・期末・フィードバック)
- 評価(自己評価・一次評価・二次評価)
- 評価結果の反映
- 実際の業務(雑務)
従業員を1人評価するだけでも、長い期間が必要です。また従業員数が増えるほど、人事担当者の負担も増大するでしょう。
システムによっては、対応業務数で利用料金が変化する製品もあります。人事担当者の負担を減らすことはもちろん、予算を考慮しながら適用業務範囲を検討してみてください。
既存システムで対応できないか確認する
なるべく予算をかけずにシステムを利用したいのなら、新規でシステムを導入する前に既存システムで対応できないかチェックしてみてください。企業によっては、データを一元管理したり、評価として利用したりできるシステムを運用している場合があります。
また、利用しているサービスの中に追加で人事評価のシステムを組み込める場合もあるでしょう。連携性のあるシステムなら、企業内の作業をより効率化できます。新しいシステムよりも慣れ親しんだシステムの方がユーザビリティに優れていることから、社内の浸透率を大幅にスピードアップできます。
クラウド型人事評価システムの導入時に抑えるべき5つのポイント
クラウド型人事評価システムは複数のサービスが提供されているため、比較検討を行いながら選びましょう。最後に、比較検討の中でチェックすべきポイントを5つご紹介します。
自社の課題を解決できるか
人事評価業務に課題を感じているのなら、課題解決に役立つシステムを探してみましょう。比較検討の条件に設定するため、抽出する課題は複数用意しておくことをおすすめします。
1つの条件では導入するシステムを絞り切れませんが、複数の条件があれば、システムごとにいくつ当てはまるのかが変わってきます。機能、料金、使いやすさなどいろんな視点から課題を抽出し、自社のニーズにぴったりのシステムを見つけてください。
自社の規模に対応できるシステムか
システムによっては、同時作業人数が決まっているものもあります。人事担当者の人数が多い場合には、システムを操作できない従業員が出てくるため、自社の規模に合ったシステムを探しましょう。
業務時間中に作業できない人員が出た場合、作業効率が下がってしまいます。まずは同時作業が必要な人事担当者数を抽出し、各サービスのプランに記載されている同時作業人数を比較してください。
費用対効果を期待できるか
クラウド型人事評価システムの比較では、費用対効果の検討が大切です。現状からどれくらいの効果を生み出せるのかを分析してみましょう。
費用対効果をチェックするときに役立つのが「作業時間」と「人件費」です。例えば、従来の1か月分の作業を表としてまとめ、トータル作業時間と対応担当者の人件費を集計します。これにより1か月分のランニングコストを抽出できます。次に、導入するシステムで削減・時間短縮できる作業を整理することによって、導入後のランニングコストを抽出可能です。
2つのランニングコストを比較し、システム導入後のコストが安くなっていれば費用対効果を期待できると判断できます。候補に挙げたシステムごとにチェックすれば、自然と導入すべきシステムを選定できるでしょう。
サポート・セキュリティが充実しているか
新規でシステムを導入するのなら、サポート・セキュリティが充実している製品を選びましょう。サポートが充実していれば、導入時に相談したり、ちょっとしたトラブルをすぐに質問したりできます。また、セキュリティが充実していれば、従業員の個人情報を安全に管理可能です。
導入後のトラブルを防止するためにも、自社で対応が難しいサポート・セキュリティはチェックしておくべき条件だといえるでしょう。
既存ツールなどと連携できるか
導入するシステムが、自社で利用している他のツールと連携できるかチェックしてみましょう。連携機能を持つ場合、入力したデータを自動反映できるため、横のつながりを持つシステムすべての効率化に役立ちます。連携機能を駆使することによって、人事評価業務をより楽にできる場合もあるため、サービスサイトの連携機能をチェックしてみてください。
自社のニーズや製品機能をチェックしつつより良いシステムを見つけよう
クラウド型人事評価システムを導入すると、人事評価業務の課題を解決して人事担当者の負担を軽減できます。また、従業員の情報を一元管理し、ルールに則った無駄のない評価を実施できるのがメリットです。
自社の目的や業務範囲、既存システムの状況をチェックすれば、効率良く目的のシステムを見つけられるでしょう。また比較検討のポイントを理解することで、より効果的なシステムを導入できます。クラウド型人事評価システムを探している方は、自社のニーズや製品情報を把握したうえで、より良いシステムを見つけていきましょう。
投稿 クラウド型人事評価システムを選ぶ時に押さえておきたい5つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 大企業でも行われるリファラル採用とは?メリットやデメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、リファラル採用の概要や導入するメリット、注意点を解説します。リファラル採用を効率化するおすすめのツールもご紹介しますので、人事採用の参考にしてください。
リファラル採用とは?
リファラル採用とは、企業に従事している社員の交友関係を活用して、友人や知人を紹介してもらう採用手法です。現場のことを理解している社員が人材を探すことから、より現場向きの人材を紹介してもらえる魅力があります。
社員に対して紹介報酬といったインセンティブを設ける企業も多く、社員の参加意欲を高めながら実施するのが一般的です。企業への思い入れを強められるなど、企業・社員にとってWin-Winの関係を作り出せます。
似た採用手法として縁故採用や親族採用がありますが、身内を対象とした人材確保は社内に不公平感を生み出す原因になるでしょう。一方、リファラル採用はスキル等を重視して外部から人材を確保するため、企業へのエンゲージメントを下げることなく活用できます。
リファラル採用を導入するメリット
採用活動の一環としてリファラル採用を導入すると、企業に3つのメリットがあります。まずは、導入を検討するために、各種メリットを参考にしてみてください。
採用コストを削減できる
リファラル採用では、採用活動に必要なコストを抑えられます。一般的な採用活動では、求人サイトを利用することが多いでしょう。しかし、次のようなコストがかかってしまいます。
- 求人サイトへの登録料
- 人材採用時の手数料
- 求人ページ作成の手間
- ミスマッチ人材のフィルタリング
一方、リファラル採用は求人サイトを介さず社員の交友関係から人材を探し出すため、上記コストを削減できます。もちろん、安定した人材確保のためには求人サイトの利用も必要です。また、社内のカルチャーをよく知る人材が事前にチェックしているため、面接コストの削減も期待できます。
人材のマッチング・エンゲージが向上する
一般的な採用方針だけで動いた場合、相手の知識やスキル、現場への適応力を判断するのに時間がかかってしまうでしょう。リファラル採用を導入すると、現場のことを理解した社員に、より実働的な人材を見つけてもらえます。
また、リファラル採用で確保した人材は、あらかじめ社員から企業の風土や勤務状況などを聞いているため、採用後のギャップが起きにくいのが特徴です。確保した人材のエンゲージメントを高められることも含め、企業・社員の双方にメリットがあるといえます。
転職潜在層にアプローチできる
リファラル採用を導入することによって、転職顕在層だけでなく転職潜在層の人材にアプローチできます。転職顕在層であれば求人サイトを通じてリーチできますが、優秀な人材なのか判断するのに時間がかかってしまいます。一方、リファラル採用なら、転職潜在層にアタックできることはもちろん、実働性のある優秀な人材にリーチしてくれる可能性を高められるのが特徴です。
また、優秀な社員であるほど周囲にいる優秀な人材にアプローチしてくれる傾向にあり、転職潜在層の中から優秀な人材を見つけ出してくれます。
リファラル採用を実施する注意点
複数の魅力を持つリファラル採用ですが、実施する際に注意すべき項目があります。次に、リファラル採用で検討すべき注意点を3つご紹介しますので、導入時の参考にしてください。
制度・ルールの設計を行う
リファラル採用では、社員の動きに対するインセンティブやフォロー体制、KPI設計など、事前に制度やルールを決めておくことが大切です。なかには、ルール決めを行わず、社員に採用活動を投げてしまう企業もあります。しかし、動き方が統一されなかったり、業務とのすみわけができなかったりと、採用活動が効率よく進みません。
よって、リファラル採用はPDCAサイクルを用いて、制度やルールを設計することをおすすめします。目標や現状把握ができなければ、リファラル採用が形骸化する場合もあるので注意してください。
事前に社内告知を行う
リファラル採用のメリットを理解し、採用活動に導入を検討している企業も多いでしょう。しかし、事前に社内告知を行わなければ、リファラル採用がうまく進みません。
それは、企業に従事する社員に人材確保を任せることに関係しています。通常業務を行いつつ採用活動も引き受ける必要があるため、リソースの問題で対応が難しい人もいるでしょう。つまり、急に導入しようとしても思ったような成果を上げられない状況を作り出してしまうのです。
業務利益を生み出しつつ人材確保も行う必要があるため、あらかじめ余裕を持ってリファラル採用の社内告知を行ってください。
不採用時の対応を考える
社員の紹介とはいえ、応募者を不採用にすることもあるでしょう。その際に、社員の交友関係に悪影響が出ないようにフォローする必要があります。
社員が紹介する人材だからといってすべての対象者がマッチしているわけではないので、アフターフォローについても検討しておくとよいでしょう。
リファラル採用において意識すべきポイント
今後、リファラル採用を本格始動させていくなら、次に示す採用活動で意識すべきポイントをチェックしておきましょう。
- 既存従業員の協力数を把握する
- 各従業員の紹介数の目標と結果分析を行う
- 採用率の分析を行う
採用活動は運ではなく、計画的に進めていくことが大切です。例えば、協力者が何人いて、各社員で何人の紹介をしてもらうというような現状把握や目標設定を行ってください。
また実施後においてもリファラル採用の精度を高めるために、結果分析や採用率分析が必要です。ツールなどを活用しつつ採用活動を可視化することが重要なので、活動前に注意しておきましょう。
リファラル採用を効率化するツール
リファラル採用の効率を高めつつ管理・検討を行いたいなら、採用ツールの利用がおすすめです。最後に、おすすめのツールをご紹介しますので、導入の参考にしてください。
MyRefer
MyReferは、株式会社MyReferが提供する国内初のリファラル採用活性化プラットフォームです。各社員のプロフィールを登録することによって、リファラル採用の進行度をチェックできるほか、活動者を評価してランキングを作成できます。ダッシュボード上で採用分析を簡単に確認できるなど、人材採用の効率化が期待できるツールです。
Refcome
Refcomeは、株式会社リフカムが提供するリファラル採用活性化ツールです。友人や知人に紹介する資料を簡単に共有できるほか、社員に対してアプリ通知で紹介依頼を行えるため、採用活動を効率化できるのが特徴です。
また、当ツールでは人事経験者や人材業界出身のアドバイザーによるサポートを受けつつリファラル採用の課題解決に取り組めるサービスを提供しています。プロの支援を受けつつ優秀な人材確保をスタートしてみてはいかがでしょうか。
リファラル採用とコネや縁故採用の違い
「従業員が知人・友人を紹介する」と聞くと、コネ採用や縁故採用に近しいと感じられるかもしれません。大きな違いは、採用する人材に対する位置づけです。コネ採用や縁故採用は、空いているポジションに対して戦力として期待される採用ではなく、能力に関係なく政治的な意味合いやプライベートな人間関係を重視して採用するという側面が強い傾向にあります。
リファラル採用は、自社のビジネスの増強のために採用する意味合いが強いのです。成長期にあったGoogleが「優秀な人材の周りには優秀な人が揃う」という考えからリファラル採用を強化したということもあります。ただ仲のいい人材を迎え入れるわけではないので注意しましょう。
リファラル採用を採用活動の武器のひとつに
社員の交友関係を頼りに優秀な人材へリーチするリファラル採用は、採用活動のコスト縮減やより良い人材とのマッチングで効果を発揮します。現場のことを理解している社員が人材を探し出すため、実働性の高い人材を見つけられるなど、即戦力を見つけやすい採用手法ではないでしょうか。
採用活動全体を見直していくなかで、これまでと違ったアプローチをしたいとお考えであればリファラル採用は打ち手の一つとなってくれるでしょう。協力してくれる社員を見ることで、会社に対する評価もわかってきます。
採用に関する以下の記事もご一読ください。
求職者に魅力が伝わるページでよい人材を獲得!採用サイト専門ツールのメリット
中途採用に広がるリファレンスチェックとは?目的やサポートツールを紹介
投稿 大企業でも行われるリファラル採用とは?メリットやデメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 中途採用に広がるリファレンスチェックとは?目的やサポートツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、企業が実施するリファレンスチェックの概要と、実施する目的、質問内容や注意すべきポイントを解説します。リファレンスチェックを効率化するサポートツールもご紹介しますので、中途採用の対策として参考にしてください。
リファレンスチェックとは?
リファレンスチェックとは、転職希望者が以前まで働いていた職場の関係者(上司・同僚)にヒアリングを行い、書類や面接の内容が正しいか確認することを指します。あまりなじみのない事柄ですが、近年では外資系企業を中心に、リファレンスチェックの必要性が広がっている状況です。
前職関係者のヒアリングは、電話で行うこともあれば、オンライン会議ツールを利用する場合もあります。また、リファレンスチェックは個人情報保護法にかかわる対応です。ヒアリングを行う前に、必ず転職希望者の許可を取りましょう。
リファレンスチェックを行う目的
リファレンスチェックは、転職希望者本人が面接を通して提示した内容と、前職関係者にヒアリングした内容の整合性を確認するために実施する企業活動です。では、具体的にどのようなチェックを行うのでしょうか。まずは、リファレンスチェックを行う3つの目的をご紹介します。
目的1.採用した人材のスキル・経験のギャップを防止する
転職希望者と面接するとき、スキルや経験などをヒアリングします。このとき、所持する資格を提示することで理解できる内容なら問題ありませんが、経験や業務中の活躍は証明することができません。
よって、転職希望者本人の話を信じて採用したところ、実際には求めるスキル・経験が不足していたという事態が発生する可能性もあるでしょう。そういったギャップを防止し、企業が求めるスキル・経験を持つ人材を確保するためにリファレンスチェックを行います。
目的2.人材の細かな人柄や働き方をチェックする
近年では、オンライン面接を実施する企業が増えており、短時間で転職希望者の人となりを判断する必要が生じています。しかし、短い面接では抽象的な情報しか集められず、採用の判断に迷う場合もあるでしょう。
そこで役立つのがリファレンスチェックです。実際に働いていた前職の関係者に、応募者本人の人柄や働き方を聞き出せば、第三者視点での評価をチェックできます。
目的3.応募者に対する現職企業の評価を確認できる
応募者との面接で得られる情報は、当然のことながら応募者の主観によって話されています。もしこれまで関わってきたプロジェクトや実績に対して話を膨らませて語っていたとしても、アサインした上司にヒアリングをすれば、会社内での重要性やポジションに対しての理解を深めることができます。
これにより、面接ではスタープレイヤーのような印象を持ったが、実際はそんなことがなかった。反対に小さなプロジェクトでオーナーだったのかと思ったら会社として重要なポジションにいた。などという自己評価とのギャップや理解度を埋めることができるでしょう。
リファレンスチェックで用いられる質問内容
リファレンスチェックを行う際には、あらかじめ質問内容を準備しておくことが大切です。次に、3つのシーンに分けて質問内容を紹介します。チェックする内容を網羅するための参考にしてください。
勤務状況に関する質問
転職希望者の働く姿勢や仕事に対する熱意を知るために、勤務状況について質問しましょう。
- 転職希望者の勤務期間はどのくらいか
- 役職や職務内容はどのようなものか
- 遅刻や欠席等があったか
- 以前に別の会社で働いていたという話を聞いていないか
大切なのは、転職希望者が適切に勤務できていたのかを確認することです。勤務時間中の動きをしっかりイメージできるように、複数の質問を準備してください。
コミュニケーション・人間性に関する質問
転職後に円滑なコミュニケーションが取れるかを確認するため、前職でのコミュニケーションや人間性について質問しましょう。
- 周囲と円滑にコミュニケーションを取れていたか
- 反発や折り合いが悪い状況がなかったか
- 行動が把握できないシーンが多くなかったか
- 転職者はどんな人物だったか
どの企業においても、上司や同僚との連携が欠かせません。できる限り、上司・同僚・部下など複数の前職関係者に質問する準備をしておきましょう。
スキル・職務能力に関する質問
採用後、即戦力で働いてもらう必要があるため、前職で培ってきたスキルや職務能力について質問しましょう。
- 業務実績にはどのようなものがあるか
- どういった役職が向いていると感じたか
- 効率よく仕事を行っていたか
- 連携が必要な仕事を卒なくこなしていたか
- 所持する資格に間違いはないか
新卒採用と違い、中途採用はすぐに即戦力として動いてもらう必要があります。基準を満たす能力があるかを確認するために、働き方やスキルについて詳しく質問してください。
リファレンスチェックで注意すべきポイント
リファレンスチェックは、転職希望者を正しく判断するために効果的な取り組みです。しかし、企業の好き勝手に動いてよいものではありません。なかでも、次の項目については細心の注意を払いながらチェックを行いましょう。
- 個人情報保護法に抵触しない
- 内定取り消しに注意する
リファレンスチェックは転職希望者本人ではなく、前職関係者という第三者に対して実施します。ヒアリングでは、転職希望者の情報を事細かに聞き出したいと思いがちですが、個人情報保護法に抵触するような際どい質問は大きな問題に発展します。したがって、踏み込みすぎた質問には注意してください。
また、リファレンスチェックを行ったからといって、転職希望者を必ず採用するとは限りません。内定取り消しなどが発生する場合もあるため、事前に採用に関する要件を転職希望者に伝えておくことが大切です。
リファレンスチェックを効率化するサポートツールをピックアップ
リファレンスチェックは、企業と転職希望者のミスマッチを防止するために実施します。しかし、企業担当者が独断で動いてしまうとチェック内容が属人化したり、ポイントがズレたりする可能性もあるでしょう。
そこで、リファレンスチェックを効率化するサポートツールを紹介します。ルールに則って正しくリファレンスチェックを行うため、導入の参考にしてください。
ASHIATO
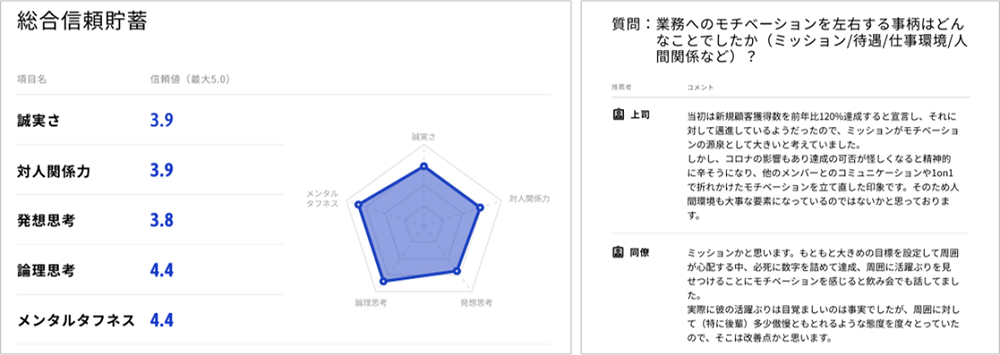
ASHIATOは、エン・ジャパン株式会社が提供するリファレンスチェックのサポートツールです。リファレンスチェックに利用できる質問テンプレート、チェック結果の分析内容を可視化できる機能などを搭載しています。
また、専任担当者によるフォロー体制が整っており、面接のアドバイスをもらったり、定期ミーティングで面接の品質を高めたりと、充実したサポートを受けられるのが魅力です。
ASHIATOの参考価格
チケットプラン:30,000 円 / 人
ASHIATOの参考レビュー
面接者の合否判定がバラバラになってしまった場合の最終判断材料として非常に効果的でした。
ASHIATOへのレビュー「ASIATO使用感レビュー」より
ASIATOを使用し採用した人で問題行動があったり、期待していた人物と違ったという事は今のところなく、導入前よりも質の高い人物を採用できていると感じています。
back check
back checkは、株式会社ROXXが提供しているリファレンスチェックのサポートツールです。リファレンスチェック結果を基に、転職希望者のスキル・実績の確認や性格診断、活躍条件の確認などを数値化して分析できます。
また、面接前のコンプライアンスチェックをお願いしたり、チャットサポートで素早いコミュニケーションを取れたりと、企業が「気になる」と感じるポイントに丁寧な対応を実施してくれるのが魅力です。
back checkの参考価格
お問い合わせ
back checkの参考レビュー
採用をする上で、実際に候補者がどのような働き方をしていたかどうかなどは把握出来ない状況だったが、リファレンスチェックを実施することにより候補者の同僚や上司から直接生の声を聞くことが出来て、採用に大きく影響した。
back checkへのレビュー「ハードルが高そうなリファレンスチェックがとても楽。」より
良さそうな人だと思っていたら、実は勤怠が乱れ気味だったなど、面接では見えないところまで把握出来るようになったのが良いポイント。
Parame Recruit

Parame Recruitは、株式会社Parameが提供するリファレンスチェックのサポートツールです。独自アルゴリズムを使った転職希望者の性格診断を行えるほか、コンサルタントによる面接内容のフィードバックをもらえます。
スマホデバイスを利用し、チャット形式で担当者と内容確認・質問できることも含め、気軽に利用できるサポートツールとして活用できるサービスです。
・Parame Recruitの参考価格
チケットプラン(従量課金):10,000 円 / 回
・Parame Recruitの参考レビュー
業務委託や採用の際のオンボーディングに利用できました。特に候補者(エンジニア)の得意業務や、営業職の方はについては得意業界など、本音でご記入頂けたことが良かったです。実際にリファレンスを書いた方と個別にコミュニケーションをとれることもいい点でした。※Parame以外のサービスでは、誰が書いた推薦か判別できなかったため、追加質問ができて参考になりました。
Parame Recruitへのレビュー「候補者を効率的にアサインできるオンラインリファレンスチェック」より
リファレンスチェックで中途採用を効率化したいならITreviewで製品を比較しよう
優秀な人材を確保するために、中途採用の面接と一緒にリファレンスチェックを実施したいと考える企業も多いでしょう。であれば、まずは注意点や質問内容を理解して導入の準備を始めてみましょう。
また、リファレンスチェックを効率化するサポートツールの導入を検討しているなら、本記事で紹介したツールとあわせてITreviewで製品を比較してください。各ツールに利用者のレビューが掲載されているため、どのツールが自社にマッチしているのか簡単に確認できます。
投稿 中途採用に広がるリファレンスチェックとは?目的やサポートツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 「組織サーベイ」とは?導入する目的や会社へのメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、組織サーベイの目的や調査の種類、期待できるメリットなどについて解説します。組織のコンディションに悩みを抱えている場合には、ぜひ参考にしてください。
組織サーベイとは
組織サーベイは、現在自社組織がどのような状況であるかを調べるための調査全般を指す言葉です。従業員の仕事へのモチベーションやエンゲージメントの程度、その他どんな課題を従業員が感じているかといったことを調べます。
また、組織サーベイと混同してよく紹介されるのが、社内アンケートです。組織サーベイはより大きな調査活動全般を指す言葉であり、社内アンケートはサーベイを実施する上での手段の1つに過ぎません。
そのため、組織サーベイは社内アンケートも施策の1つとして扱いますが、それだけではない点に注意しましょう。
組織サーベイの目的
組織サーベイを実施する目的は、まず従業員の課題意識を丁寧に探ることが挙げられます。自社で働く従業員は、そもそもどのような組織の姿を理想としているのか、理想の組織と現在の姿には、どんな隔たりがあるのかを深堀りする上で役に立つ取り組みです。
また、組織サーベイによって、組織全体の課題の把握にも貢献できます。従業員個人の意見を複数求めることにより、組織として目指すべき姿や解消すべき問題に対して、優先順位をつけられるようになるでしょう。
組織サーベイの種類
組織サーベイは大きく分けて、以下2つの手法に分けることができます。
- パルスサーベイ
- センサス
パルスサーベイは、従業員のエンゲージメントを把握するための調査方法を指す言葉です。「パルス」という言葉の通り、脈拍のようにテンポが良く短いスパンで簡単な質問を従業員へ投げかける方法です。
毎週、毎月といった期間で調査を行うことで、企業と従業員の関係を正確に測定できることから、有用な手法として取り入れられています。
一方のセンサスは、パルスサーベイとは異なり年に1回のような長いスパンで行われる、重みのある調査手法を指す言葉です。設問の数は100を超えることも珍しくなく、従業員がじっくりと質問に向き合って回答できるため、多角的な課題発見が期待できる手法として採用されてきました。
ただし近年、センサス調査による課題発見と分析は、リアルタイムで現場のニーズに応えづらい調査方法であるとして、短期間で実施するパルスサーベイへの移行が進みつつあります。
パルスサーベイは頻度が高いとはいえ、数分で調査が終わるため従業員への負担を軽減できるのがメリットです。組織サーベイをこれから実施する場合は、パルスサーベイに優先して取り組むと良いでしょう。
組織サーベイのメリット
組織サーベイの第一のメリットは、組織が抱える課題を具体的に数値化できる点にあります。組織が抱えている問題が複数ある場合、まずどの課題から手をつけていくべきなのか、ということは現場の声をなんとなく聞いているだけでは見えづらいものです。
組織サーベイを実施することで、従業員がアンケートを通じて、どの問題を最も重く捉えているかということを5段階評価で表したりできるため、優先的に取り組むべき課題が明らかになります。
また、組織サーベイの実施によって現場課題の発見と改善のスパンを促せるので、迅速に就業環境の改善が実現します。従業員の課題がすぐに解消される環境は居心地が良く、人材の流動性が高まっている今日においても高い定着率を維持する上で役に立ちます。
組織サーベイで見える化できる項目
組織サーベイを通じて見える化できる項目としては、主に以下が挙げられます。
- 企業の経営方針に関する項目
- 職場の人間関係に関する項目
- マネジメントに関する項目
- 待遇に関する項目
企業の経営方針においてどんな課題や不明点を感じているか、人間関係はうまくいっているか、プロジェクト管理において不満はないか、満足のいく待遇が得られているかといった、組織課題に直結する調査を積極的に展開できるのが強みです。
特に待遇に関しては、時代に応じた給与水準をすぐに察知する上でも役に立ち、待遇を理由とした離職の予防には欠かせない取り組みです。
何度も組織サーベイを実行することで、それぞれの項目における課題の具体性も高まってくることが期待できます。
組織サーベイをうまく活用して課題解決につなげよう
事業を軌道に乗せるためには、顧客への理解やビジネスそのものへの理解を深めることも大切ですが、企業活動を支える組織内部の問題にも眼を向ける必要があります。
従業員が不満を抱えている現場のままでは、1人ひとりのポテンシャルが活かせず、生産性の改善や売上の向上は見込めなくなってしまいます。
組織サーベイを定期的に実行することは、組織課題を数値化していち早く察知し改善するきっかけを掴む上で重要です。優先して取り組むべき組織課題を常に把握し、従業員が生き生きと活躍できる職場づくりを目指しましょう。
投稿 「組織サーベイ」とは?導入する目的や会社へのメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 タレントマネジメントの効果とは?評価に役立つツールもピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>この記事では、タレントマネジメントシステムの概要や導入の目的と効果について解説します。また、業務に利用できるおすすめツールを5つご紹介しますので、人材管理や人材開発の参考にしてください。
タレントマネジメントの目的と効果
タレントマネジメントは、次のような目的で導入されています。
- 人材管理の効率化
- 人材のスキルを活かした評価
- 人材の成長戦略
- 離職防止
タレントマネジメントのフレームを利用すれば、従業員の管理が効率化します。従来、不明確であった従業員のスキル・経験の分析ができることはもちろん、収集・分析した情報から根拠のある業務割り振りが可能です。
また、企業に従事する人材を育成することも大切でしょう。業務知識や実戦経験を学ばせることに加えて、取得してほしい資格もあるはずです。タレントマネジメントツールを活用していけば、人材の成長戦略を計画できます。継続的に分析しつつ従業員の成長動向を探っていくことで、求める人材を生み出しやすいのが特徴です。
さらに、従業員が働きやすい環境を構築できれば、社内満足度を高めることにつながり離職防止効果を得られるでしょう。少子高齢化の影響を受け、多くの企業が人材不足に悩んでいます。その課題を事前に解消できる魅力があるため、今タレントマネジメントツールは多くの企業から注目を集めているのです。
タレントマネジメントシステムとは
タレントマネジメントシステムは、従業員の情報を総合的に管理する便利なツールであり、主に次のようなことを実施できます。
- 人材管理
- 人材育成
- 人材開発
- マネジメント
従来の企業では、各個人の抽象的な情報しか把握しておらず、スキルや経験とは関係なく業務が割り振られる場合もありました。その状況を背景として、現在タレントマネジメントツールの導入が進んでいます。このツールを導入して人材と業務の相性を分析していけば、効率的な業務采配を指示できるほか、従業員が働きやすい環境の構築を実現できます。
また、このツールで従業員のスキルや経験・実績を可視化・数値化することによって、適切な業務に人材を配置し、業務効率化と社員満足度を高める2重の効果を得られます。従業員が持つ能力を数値化していくことで、業務の向き不向きを簡単に把握でき、現在の働き方の割り振りが正しいのか分析できます。
タレントマネジメントシステムの選び方
タレントマネジメントツールの導入を検討しているなら、次のポイントを参考にツールを選びましょう。
- 課題を解決できるツールを見つける
- ライフサイクルコストを比較する
- デモ版で使いやすさを比較する
まずは企業が抱える課題を抽出することが大切です。人材不足や人材の能力が把握できていないなど、企業によって課題が異なるでしょう。これに対し、タレントマネジメントツールは利用するツールで機能が異なるため、課題解決できるツール選びが欠かせません。
またタレントマネジメントツールは、メーカーや人気度によって価格が異なります。最近ではサブスクリプション形式の契約が主流となっており、継続的な支払いを必要とするのが一般的です。そのためライフサイクルコストを把握し、機能と料金を比較していくことが長期利用において重要だと言えます。
タレントマネジメントツールの多くは、あらかじめ使いやすさを把握できる「デモ版」を利用できます。デモ版は無料で使うことができ、操作性や機能の確認に役立ちます。比較候補として挙がったツールはそれぞれデモ版を試し、どれが自社ニーズに合うツールなのか検討することをおすすめします。
業務で使えるタレントマネジメントシステム5選
人材管理に役立つタレントマネジメントツールですが、どのようなツールを選択すべきか悩んでいる人もいるでしょう。そこでここではITreviewの評価を参考に、おすすめのツールを5つご紹介します。
人材管理以外でも利用できる多機能なツールも提供されています。ぜひツール選びの参考にしてください。
HRBrain
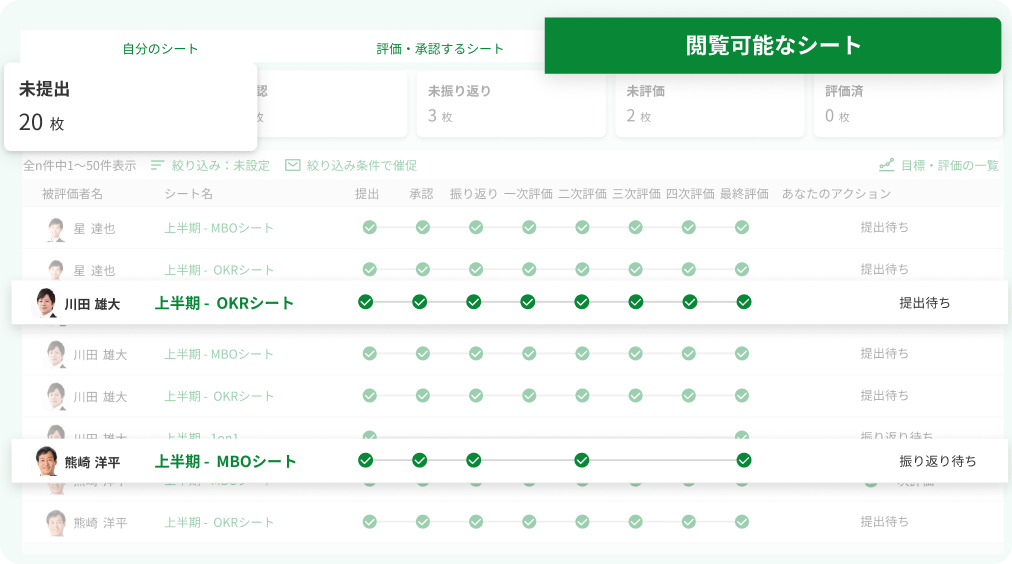
HRBrainは、組織全体を可視化して、各従業員のデータを事細かに管理できるプラットフォームです。入力項目を埋めることで簡単に人材データを収集・分析し、グラフや表として自動抽出できます。
リアルタイムで人材の動向を探れることから、サポートや今後の対策といった成長戦略を立てやすいのが魅力です。
・利用者レビュー
これまではエクセルファイルでの書類で提出していたが、このHRbrainでの管理となり、提出に関する業務は時間短縮になった。
引用:https://www.itreview.jp/products/hrbrain/reviews/131535
テーマ事の入力もしやすく、操作もそれほど難しく無いため、部署内で評価表の運用変更による大きな混乱も無かったように思う。
タレントパレット

タレントパレットは、人材データを集約することによりマーケティング思考を取り入れた人材管理を行えるツールです。ただ人材管理を行うのではなく、従業員アンケートによる業務采配やヘルスケア対策にも効果を発揮します。
利用者向けのコンサルティング、オンライン相談会なども実施されているため、利用を続けることで人材管理のノウハウを学べるのもメリットです。
・利用者レビュー
人財の見える化をベースとしてたくさんの項目があるのはどのタレントマネジメントシステムでも同様だが、それを駆使して、マーケティングをするように分析が出来る点。具体的にはダッシュボードは重宝している。今後は、OKR機能は発展途上ではあるものの、バージョンアップも期待できるので、それを駆使してタレントマネジメントに反映していく。
引用:https://www.itreview.jp/products/talentpalette/reviews/72411
カオナビ

カオナビは、社員の活躍をリアルタイムでトレースして評価運用を行うことで、戦略的な人事活動を実現できるツールです。
人材情報の閲覧者設定などセキュリティ面にも優れており、経営者および人事だけが詳細情報を閲覧できる環境を構築できます。またユーザー同士のコミュニケーションプラットフォームも用意しており、業務ノウハウを学べる環境構築にも効果を発揮するのがメリットです。
・これまではExcelで各自の目標設定を記載し、ファイルサーバへ格納していたものが、
引用:https://www.itreview.jp/products/kaonavi/reviews/140519
システムで一元管理できるようになり、記載・提出が容易になり時間削減につながった。
スマカン
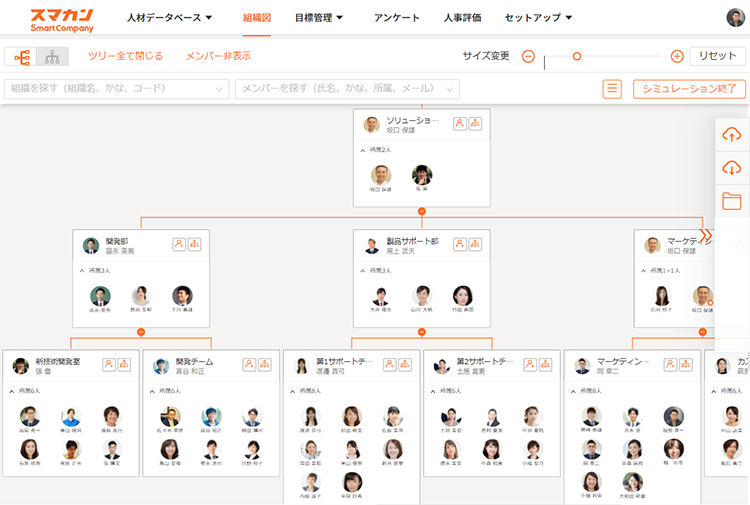
スマカンは、人材管理に加えて、人材の目標管理や管理シミュレーションを実施できる分析向けのツールです。
人事業務を大幅に自動化できることはもちろん、煩雑な人材評価シートの入力を簡易化し、数値化されたデータから適任な人材を探し出す機能を搭載しています。企業規模に合わせた機能設定を行えるため、企業ニーズにマッチするサービス利用が可能です。
jinjer人事
jinjer人事は、人材管理のほかにも労務手続きや雇用契約、社内のペーパーレス化にも力を発揮する一元管理型のタレントマネジメントツールです。
jinjer人事を提供する「jinjer」シリーズでは、経理、コミュニケーションなど複数のツールを提供しています。ツール同士の連携性に優れており、効率的に人事業務を遂行できるのが魅力です。
もっとタレントマネジメントツールを見たいならITreviewで比較しよう
タレントマネジメントツールは、人事業務を効率化できる便利なツールです。多くの企業で抽象的に管理されている人材スキル・経験を可視化できることから、戦略的な業務采配や社内満足度の向上による離職防止効果を期待できます。
なかには、もっと詳しく理解したうえでタレントマネジメントツールの導入を検討したい人もいるでしょう。ITreviewではランキング形式でツールを紹介しています。利用者コメントや評価など、自社の目的に合うツールを見つけやすい情報を掲載しているので参考にしてください。
投稿 タレントマネジメントの効果とは?評価に役立つツールもピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 バイリンガルじゃなくても海外の人とビジネスMTGができる?使えるツール6選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>自動翻訳に使えるビジネスツールはAI議事録やAI通訳ツール
海外の担当者とMTGを開くためにリアルタイムで自動翻訳を利用するには、AI議事録または自動翻訳ツールが利用できます。それぞれの特徴について解説します。
AI議事録とは
AI議事録とは、会議や商談の音声を記録して自動でテキストデータへと変換するツールです。本来は議事録を作成するためのツールなので、すべてのツールが自動翻訳に対応しているわけではありませんが、Zoom連携の機能と併用することで対談者の音声を翻訳してテキストデータとして表示できます。
リアルタイム翻訳・AI通訳ツールとは
AI通訳ツールとは、会議や商談の音声を識別して自動で翻訳・通訳するツールです。AI議事録のように記録したテキストデータをまとめる機能は基本的にありませんが、安価で自動翻訳を実現できます。なかには、自動議事録の作成に対応しているツールもあります。
自動翻訳に使えるAI議事録3選
AI議事録に搭載されている機能は、自動翻訳にも使えます。AI議事録のなかでも、自動翻訳に適したツール3選をご紹介します。必要な機能はZoom連携と自動翻訳機能であるため、どちらの機能も有したツールをご紹介します。
知名度で選ぶなら「Webex」
「Webex」は、アメリカに本社を置くCisco Systemsが提供するコミュニケーションツールです。オンライン会議やクラウド電話の機能を有しており、企業向けのツール「Webex Suite」を用いることで自動議事録や自動翻訳ツールとしても利用できます。
日本でも1,000社以上とのパートナーシップを結ぶ同社の知名度は国内でも高く、有名企業のツールを選びたいなら「Webex」がおすすめです。
国内企業の製品で選ぶなら「AIGIJIROKU」
「AIGIJIROKU」は、株式会社オルツが提供する自動議事録ツールです。5,000社以上の導入実績を持ち、30ヶ国語に対応したリアルタイム翻訳機能を有しています。音声認識精度99.8%の高性能なAI機能を有しており、話者を特定して自動的に議事録を作成可能です。
AIに翻訳テキストを発話させることもできるため、自動翻訳ツールとしても利用できます。国内企業の自動翻訳ツールを選びたいなら「AIGIJIROKU」がおすすめです。
公的機関発のツールで選ぶなら「ZMEETING」
「ZMEETING」は、Hmcommが提供するAI議事録自動化システムです。Hmcommは経済産業省所管の公的研究機関「国立研究開発法人産業技術総合研究所」発のベンチャー企業であり、「AI×音声認識」のスペシャリストとして活動しています。
英語・中国語(簡体)・中国語(繁体)・韓国語・ベトナム語・タイ語・ドイツ語に対応したツールで、会議の出席者ごとに言語を設定可能です。議事録データ・通信の暗号化、IPアドレスのアクセス制限などの機能を搭載しており、重要な会議でも安心して利用できます。公的機関発の自動翻訳ツールを選びたいなら「AIGIJIROKU」がおすすめです。
自動翻訳に使えるリアルタイム翻訳・AI通訳ツール3選
AI通訳ツールは、自動翻訳による多言語対応に適したツールです。ここでは、ITreviewの口コミでも評価が高いAI通訳ツールを3つご紹介します。
知名度で選ぶなら「Wordly」
「Wordly」は、米国に本社を置くWordlyが提供するSaaSプラットフォームです。20以上の言語をライブ翻訳することができ、対面でもオンライン会議でも通訳者を介さずにAIによるリアルタイムの同時翻訳を実現します。
ORACLEやsalesforceなどの大企業を含む600社以上の導入実績を持ち、100万ユーザー以上を獲得するほど世界的に有名なツールです。知名度で自動翻訳ツールを選ぶなら「Wordly」をおすすめします。
価格で選ぶなら「Secure Meet」
「Secure Meet」は、チャットプラス株式会社が提供するWeb会議ツールです。96%以上の人口をカバーできるほどの翻訳機能を持ち、95%以上の文字起こし精度を誇ります。
契約プランも、最大10ライセンスまでなら月額1,500円〜と安価に利用できるのも魅力です。40分までの会議であれば、無料で利用できます。価格で自動翻訳ツールを選びたいなら「Secure Meet」がおすすめです。
アプリで導入するなら「ドコツーAI」
「ドコツーAI」は、東京都港区北青山に本社を置く株式会社スマートボックスが提供するAI翻訳アプリです。NICT(情報通信研究機構/総務省所管の国立研究開発法人)の多言語翻訳エンジンを搭載しており、日本語との相性では世界最高峰の性能を誇ります。
ゲスト側は専用機不要でインストールすることなく、QRコードやURLからペアリングして使用できる利便性の高さも魅力です。ゲスト側の言語は、英語・中国語など異なっていても同時に多言語翻訳できます。スマホで手軽に導入できる自動翻訳ツールを選ぶなら「ドコツーAI」がおすすめです。
ZoomやMicrosoft Teamsの翻訳機能を利用する
Web会議システムには、自動翻訳の機能を備えるものが増えてきました。ZoomやMicrosoft Teamsなどは、リアルタイムで音声を識別して、外国語を日本語の字幕として表示する機能を搭載しています。
Zoomは日本語を含む11言語、Microsoft Teamsは日本語を含む25以上の言語に対応可能です。すでにZoomやMicrosoft TeamsをWeb会議に導入している企業なら、これらの翻訳機能を利用することもできます。
自動翻訳ツールで海外の人とのビジネスMTGをスマートにしよう
自動翻訳ツールを用いることで、海外の担当者ともスムーズにコミュニケーションを図れます。すでに利用しているWeb会議システムの中にも、日本語字幕に対応しているツールも存在します。AI議事録などのビジネスツールを用いれば、海外の担当者とのWeb会議も自動で議事録を作成してスムーズに取引を進められるでしょう。
自然言語処理も発展が目まぐるしいため、まるで相手が日本語で話しているかのようにリアルな会話につなげられるほど技術は進歩しています。グローバル展開を目指す企業にとっても有益な自動翻訳ツールを探している方は、本記事を参考にして自社に最適な製品を見つけてください。
投稿 バイリンガルじゃなくても海外の人とビジネスMTGができる?使えるツール6選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 組織サーベイツールの機能とは?導入目的別ピックアップ5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>従業員の満足度調査や自社の課題を見つけるために有効なのが、「組織サーベイツール」です。本記事では、おすすめの組織サーベイツールを5つご紹介します。
組織サーベイツールの代表的な機能
組織サーベイツールとは、人材データや従業員へのアンケート調査をもとに、組織の課題を洗い出し、組織改革や人材育成を支援してくれるツールです。
組織サーベイツールの機能例
- 従業員へのアンケート作成機能
- 調査結果の自動集計・データ化
- データをもとにした改善アクションプランの提案
- 他社とのデータ比較
従業員のエンゲージメントや満足度が数値で見える化され、離職につながる兆候を発見することも可能です。解決すべき課題の優先順位が分かり、データにもとづいた効果的なアクションプランを立てられます。他社とのデータ比較を通して、自社に不足している点を発見できるのもメリットです。
機能はツールによって違うため、「組織課題の発見」「離職防止」など自社の課題に合わせて最適なツールを選びましょう。
組織サーベイツールのピックアップ5選
1.データ分析や活用までトータルサポート:HRBrain
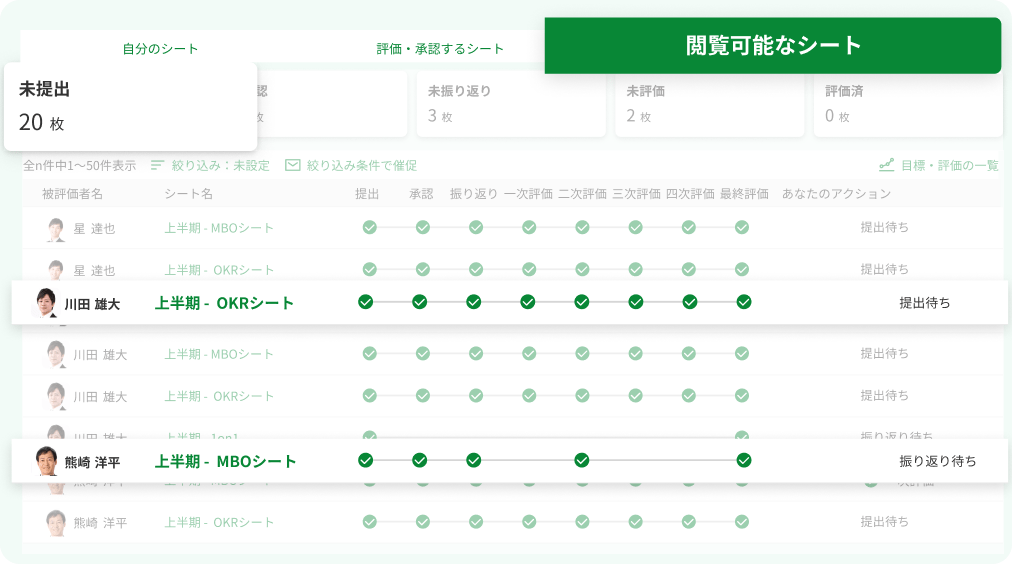
HRBrainは、豊富な機能で組織サーベイをトータルサポートしてくれるツールです。アンケート調査の項目や配信対象、調査頻度などを細かくカスタマイズできるのが特徴です。部署・年齢・役職・性別・評価データなど多角的な視点で分析でき、人事や経営、現場などレイヤーごとの施策を立てられます。
課題に対しての改善施策を示唆するアクションレポートを発行し、分析だけでなく課題解決までサポートします。データアナリストや人事コンサルタントなど、専門的な知識を持ったスタッフによるサポート体制も充実しており、組織サーベイを初めて導入する企業や、データの活用方法が分からない企業におすすめです。
2.人材データを一元管理:Talent palette(タレントパレット)

タレントパレットは、組織サーベイ機能を搭載したタレントマネジメントシステムです。従業員の人材データを一元化し分析することで、科学的根拠にもとづいた人事戦略の立案・実行を可能にします。
サーベイ機能では、目的に合わせて自由に設問を設定可能。未入力者への自動催促メールや、定期アンケート機能で効率的に運用できます。アンケート結果を人事評価やスキルなどの人材データと連携できるため、マネジメントサポートや組織体制の変革まで幅広く活用可能です。組織サーベイを「人材マネジメントに活かしたい」という企業に選ばれているツールです。
3.人材の定着をサポート:ハタラクカルテ
ハタラクカルテは、「人材が定着する組織づくり」を支援する組織サーベイツールです。専門家と共同開発した人材定着に影響する15の項目ごとに、従業員の満足度をスコア化できます。従業員が重視する課題が具体的に分かるため、課題の優先度を洗い出して適切なフォローやマネジメント立案に役立てることが可能です。
PC・スマホどちらからでも回答可能なフォームを提供し、組織サーベイで課題になりがちな調査回答の負担が低いのも魅力です。「使いやすさ」「機能」「リーズナブル」などバランスの取れたシステムなので、初めてツールを使用する企業でも導入しやすいでしょう。
4.低コスト・少人数で導入可能:wevox
wevoxは、チーム単位の少人数利用や、「コストを抑えて組織サーベイツールを導入したい」という企業におすすめです。最低利用人数の制限はなく、1人300円/月から利用できます。一部の部署で利用し、結果が出たら全社で活用するなど導入しやすいため、社内稟議も通りやすいでしょう。
自社に合わせたアンケートを作成したり、部署や役職ごとにデータを分析したりと柔軟に使用できるのも魅力です。課題解決に役立つ他社事例やオンライン学習も提供しており、組織の課題発見に加えて改善までサポートしてもらえます。
5.従業員のエンゲージメント向上に特化:THANKS GIFT
THANKS GIFTは、組織のコミュニケーションを活性化させるための機能が充実したツールです。従業員同士で日々の感謝を伝え合う「サンクスカード」、企業理念や行動指針を浸透させる「オリジナル理念コイン」の発行機能により、従業員エンゲージメント向上を促します。
組織サーベイ機能で効果測定ができるため、ツールの活用モチベーションも保ちやすく、組織文化の定着に役立ちます。また、組織サーベイの調査レポートと合わせて施策立案のアドバイスを提供してもらえるのもメリットです。コミュニケーションを中心に組織課題を解決したい企業におすすめのツールだと言えるでしょう。
組織サーベイツールを活用して、組織の課題を解決しよう
組織サーベイツールを活用することで、組織の課題が可視化されます。ツールを選ぶ際には、離職率や生産性の低下など、顕在化している課題に適した製品を比較検討しましょう。従業員規模や組織体制に合うかどうかは、レビューや満足度調査が参考になります。各ツールレビューやの機能比較は以下からご覧ください。
投稿 組織サーベイツールの機能とは?導入目的別ピックアップ5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Googleやメルカリでも採用された「ピアボーナス」とは?言葉の意味や仕組みを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、ピアボーナスが必要とされる理由や導入するメリット・デメリットについて詳しく解説します。従業員エンゲージメントの向上に役立つ取り組みですので、ぜひ参考にしてください。
ピアボーナスとは?
ピアボーナスとは、従業員同士で評価を行い、その評価値に応じて報酬(ボーナス)や特別手当を決定する仕組みのことです。従来の「会社が従業員を評価して報酬を決定する仕組み」とは異なる制度であり、従業員自らが報酬決定に関与できることから、働く側のモチベーションを高められると話題を呼んでいます。
ピアボーナスは、すでにGoogleやメルカリといった大企業で導入されています。たとえば、Googleは1回の評価で175ドルのボーナスを与えるという風に、従業員の評価次第で高額報酬が手に入る仕組みを整えています。
目の前で仲間の活躍を見ている従業員が実施する評価だからこそ、正しい業務評価を通して報酬を決定できます。この取り組みによって従業員エンゲージメントや離職防止につながることから、現在多く企業で導入が進んでいます。
ピアボーナスが求められる理由
今、ピアボーナスが注目される理由として、AIやIoTといった技術発展が関係しています。
従業員は、技術発展に伴う社会環境の変化に対して柔軟な対応が求められています。会社に新たな技術が導入されると、従業員の負担が増加します。しかし多くの会社では評価の見直しが行われることは少なく、給料が低いままであることがほとんどです。
評価が変わらなければ従業員のモチベーションが高まらず、次のようなトラブルが発生する可能性があります。
- 作業量が報酬に見合わず離職者が出る
- 従業員の負担に差がついて社内コミュニケーションが悪化する
これに対してピアボーナスは、従業員の頑張りに応じた評価を付けやすい制度です。社会環境の変化に対応するべく努力している人間を評価することによって、従業員のモチベーション維持を期待できることからピアボーナスが求められているのです。
ピアボーナスを導入するメリット
会社にピアボーナスを導入するメリットは次の通りです。
- 社内コミュニケーションの向上
- 従業員モチベーションの向上
- 離職防止
社会環境の変化が著しい現代において、ピアボーナスの導入が企業を長生きさせるポイントです。ひとつずつ見ていきましょう。
社内コミュニケーションの向上
ピアボーナスで評価を受けるためには、効率よく働くことが重要です。情報伝達や周囲へのアドバイスなど、多くの従業員が評価につながる行動を取ろうと活動します。その結果、チームで働く会社では必然的に社内コミュニケーションが向上します。
社内コミュニケーションが向上すると、会社全体の活気が高まるだけでなく、お互いが感謝を伝え合う「風通しのよい職場」が生まれるきっかけとなります。
従業員モチベーションの向上
ピアボーナスは会社全体だけでなく、各個人のモチベーション向上に役立ちます。「周囲の人間よりも評価されたい」という気持ちを生み出せるだけでなく、年齢や経験を問わず報酬に変化が現れるため、会社に所属する全員のモチベーションを高められます。
離職防止
ピアボーナス導入は、優秀な人材の離職防止につながります。
ピアボーナスを導入していない会社の場合、優秀な人材であっても報酬が少ないことが多く、外部から引き抜かれたり、今の報酬に満足できずに離職したりしてしまう人が発生してしまいます。
ピアボーナスを導入すれば、頑張りに応じた報酬を得られるため、優秀な人材の離職防止につながり、会社で長期的に活躍してくれるでしょう。
ピアボーナスを導入するデメリット
会社にピアボーナスを導入するデメリットは次の通りです。
- システム導入にコストがかかる
- 従業員にプレッシャーを与えてしまう
- 従業員の関係性が崩れやすい
ピアボーナスは、従来の評価基準を大きく変化させるため、デメリットが生まれる場合もあります。重要な項目ですので、デメリットについても確認しておきましょう。
システム導入にコストがかかる
ピアボーナスを導入するためには次のアクションが必要です。
- システム導入
- 従業員への教育・告知
今までの動き方を大きく変える「新たな報酬制度」なので、評価内容を正しく管理するシステムが必要です。また、従業員に詳しく説明しなければ上手く制度を運用できないため、十分な教育も必要です。
管理システムの導入や従業員への教育・告知には、導入費用や人件費が必要となります。初期導入で大きなコストがかかることを把握しておきましょう。
従業員にプレッシャーを与えてしまう
従業員同士が評価を行うため、なかには評価されない従業員が出てきます。評価されないことが従業員のプレッシャーとなり、それがストレスにつながる場合もあります。
ピアボーナスを導入する場合には、0か100かのように極端な報酬体系を採用するのではなく、特別手当というような形でピアボーナスの制度を組み込んでいくと従業員のプレッシャー緩和につながるでしょう。
従業員のトラブルの要因にもなる
評価される従業員と評価されない従業員が出てしまうと、同年齢でも報酬に大きな差が生まれます。その結果、授業員同士の関係性が崩れやすく、トラブル発生の要因にもなるため、評価ルールの整備が重要です。
ピアボーナス管理のためにシステムを導入して、評価値を管理者だけが閲覧できるようにするなど、他人に見えない対策を取るのがおすすめです。
ピアボーナスについて理解したら製品を比較検討しよう
ピアボーナスの導入によって、従業員エンゲージメントの向上や離職防止につながります。また従業員は頑張った結果が報酬に反映されるようになるため、長生きする会社づくりの基盤を整備したり、社内コミュニケーションの向上に役立てたりできます。
ピアボーナスについて詳しく理解してから導入を検討したいのなら、まずはITreviewが提供するシステム紹介ページを参考に、気になる製品を比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
投稿 Googleやメルカリでも採用された「ピアボーナス」とは?言葉の意味や仕組みを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 コミュニケーションの活性化に寄与する「ピアボーナス」ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、ピアボーナスの導入効果や製品の比較ポイント、おすすめのピアボーナスツールについて詳しくご紹介します。離職防止や従業員エンゲージメント向上にも効果的な制度ですので、ぜひ導入の参考にしてください。
社内コミュニケーションを活性化するピアボーナスとは?
ピアボーナスとは、従業員間で評価し合った結果が報酬に反映される制度のことです。同じ職場で働く従業員の生の仕事を見ている社員が評価するので、企業が評価を行う従来の報酬制度と比べて、年齢や経験を問わず平等に評価しやすいのが特徴です。
また、ピアボーナスには社内コミュニケーションを活性化する効果があります。従業員による評価は相手への感謝を伝えるきっかけとなります。また評価された側は、自分の貢献を数値で把握できるため、仕事のやりがいにもつながります。
ピアボーナスは、Googleやメルカリを筆頭に多くの企業で導入が進んでいます。管理する製品も多数登場していることから、現在では制度導入の敷居が低くなっています。
ピアボーナスの導入効果
ピアボーナスを導入することによって、次の効果を得られます。
- 従業員のモチベーション向上
- 優秀な人材の離職防止
- テレワークでのコミュニケーション向上
ピアボーナスの効果は、コミュニケーションの面で力を発揮します。従来の「会社が評価する働き方」の場合、従業員同士で「感謝を伝える」「褒める」ということが少なく、従業員のモチベーションが高まりません。一方で、ピアボーナスを導入すると感謝の気持ちを従業員に届けられることはもちろん、それが報酬に反映されるため、各社員のモチベーション向上や離職防止につながります。
また近年では、リモートワークの導入によってひとりで仕事をする機会が増えました。そのため、自分がどれくらい会社に貢献できているか分からず、勤続する不安を感じている従業員もいます。ピアボーナスは顔が見えない従業員に対しても評価できるので、テレワーク時のモチベーション維持にも効果的です。
ピアボーナス導入で比較すべきポイント
ピアボーナスツールの導入を検討しているなら、次に示すポイントで比較検討を行いましょう。
- 導入コスト
- 社員目線での使いやすさ
- デモ版の有無
ピアボーナスの導入は、報酬制度に関わる大きなターニングポイントとなります。きちんと理解するためにひとつずつ見ていきましょう。
導入コスト
ピアボーナスの導入には次のようなコストがかかります。
- ツールの導入コスト
- 報酬制度変更の告知
お金というコストがかかるだけではなく、制度を浸透させる手間といったコストがかかります。選ぶツールによって価格が変化するので、費用対効果が生まれるのか入念に検討するのがおすすめです。
社員目線での使いやすさ
ピアボーナスを導入しても、社員に浸透しなければ意味がありません。このとき、ツール選びで注意したいのが「社員目線」から考える使いやすさです。
ツールの中には多機能である反面、初心者にとって操作が難しいものもあります。ピアボーナスツールを操作する従業員は、年齢や知識量が異なるので、事前に操作性を確認しておきましょう。
デモ版の有無
ツールを選ぶ際には、デモ版が利用できるのか確認しましょう。なかにはデモ版が利用できなかったり、使えたとしても制限が設けられていたりする製品もあります。しかし、デモ版を使えなければ具体的な導入結果をイメージできません。
ピアボーナス導入を成功させるためには、実際にツールに触れてから導入を検討することが重要です。導入候補にデモ版があるか確認し、実際にテスト導入してみてはいかがでしょうか。
ピアボーナスのおすすめツール3選
Googleやメルカリといった大手企業によるピアボーナスの導入を筆頭に、役立つツールが多数登場しています。しかし、種類が多すぎてどれを選べばよいか悩んでいる人もいるでしょう。
ここでは、数あるピアボーナスツールの中でも、ユーザー評価が高いおすすめツールを3つご紹介します。ユーザビリティに優れているツールばかりですので、参考にしてみてください。
THANKS GIFT
株式会社Take Actionが提供する「THANKS GIFT」は、「ITreview Best Software In Japan 2022」においてSaas・ソフトウェアTOP50に選出された実績を持つ人気のピアボーナスツールです。
ピアボーナスに欠かせない評価機能はもちろん、コラムや掲示板、チャット機能が利用できることから、従業員のコミュニケーション向上に役立ちます。
また、クラウドで利用できるため、PCやスマホを通じて従業員同士で評価を行えます。評価されて貯まったポイントは景品と交換できるので、従業員にとっても魅力的なツールだと言えるでしょう。
RECOG
株式会社シンクスマイルが提供する「RECOG」は、充実したプランが特徴のピアボーナスツールです。
一般利用の基本プランに加え、ホメ研修や活用コンサルティング、称賛給プログラム導入を含む追加オプションが充実しているので、プロの意見を取り入れつつピアボーナスを運用できます。
またRECOGは、従業員同士の評価である「レター」をひとりあたり月10通送ると、発展途上国へ食料供給ができるなど、SDGsにも効果を発揮します。従業員だけでなく企業活動の一環としても役立つツールです。
Unipos
Unipos株式会社が提供する「Unipos」は、TOYOTA・JT・ZOZOなど幅広い業種で導入実績のあるピアボーナスツールです。
ピアボーナスツールに必要な機能がすべて揃っていることはもちろん、評価者に対してコメントしたり、チャットツールと連携したりできる機能を備えています。とくに、ビジネスチャットツールを利用している会社にとって導入メリットが大きいでしょう。
Unipos株式会社はピアボーナスというワードを商標登録しています。制度登場当時からサービス展開を行っている老舗ツールなので、安心して導入できるでしょう。
もっと詳しくピアボーナスツールを知りたいならITreviewで比較しよう
ピアボーナスツールは、従業員同士が評価し合う環境をつくれるため、従業員のモチベーション向上につながります。優秀な人材の離職防止やテレワークのコミュニケーション課題の改善を図れることから、多くの企業で導入が進んでいます。しかし、ツールによって操作性や機能に違いがあるので、まずは無料体験版をダウンロードして使いやすさを確認するのがおすすめです。
ご紹介したツール以外にも製品を比較したい人は、「ITreview」を利用して自社にぴったりのピアボーナスツールを見つけてください。
投稿 コミュニケーションの活性化に寄与する「ピアボーナス」ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 語学を活かした業務をサポート!おすすめAI翻訳ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、和訳、英訳はもちろん、多言語に対応したおすすめのAI翻訳ツールを3つ紹介します。多機能かつクオリティの高い翻訳を行うツールを厳選しましたので、ぜひ導入時の参考にしてください。
AI翻訳ツールとは
AI翻訳ツールとは、ディープラーニングと呼ばれる学習機能を用いて、正しい翻訳結果を導きだす翻訳ツールのことです。従来の文字列を直訳していた機械翻訳に対し、より人間らしい言葉で翻訳できることから、多くの企業が導入を進めています。
またAI翻訳ツールは、継続して学習を続けるのも特徴です。読み込ませる文書が多ければ多いほど間違いの少ない翻訳ができるため、翻訳作業が必要な業務の効率化を図れます。
外国語を使う企業ならAI翻訳ツールの導入がおすすめな理由
グローバルな働き方をしている企業の中には、外国語文書のやり取りが多い会社もあるでしょう。そのような企業には、AI翻訳ツールの導入がおすすめです。ここでは導入をおすすめする理由を3つ紹介します。
- 実績やスキルを問わず翻訳できる
- 翻訳コストの削減
- リアルタイムでのメール翻訳
実績やスキルを問わず翻訳できる
AI翻訳ツールは、誰が利用しても安定した翻訳品質を期待できます。企業に属する社員には語学力に差があり、翻訳にかかる時間が大きく異なります。また翻訳スキルを持たない人材の場合、外国語を理解できないという課題があります。
これに対して、AI翻訳ツールは実績やスキルの差による課題を解決します。AI翻訳ツールは、プロの翻訳者と同等の翻訳能力を有していることから、語学力に差がある企業におすすめです。
翻訳コストの削減
AI翻訳ツールは、翻訳作業のコストを削減できます。従来、人が実施していた翻訳作業には莫大な人件費がかかります。また、文書の量が多いほど翻訳に長い時間を要したり、場合によっては多言語に対応したりする必要があります。
このコストの課題を解決してくれるのがAI翻訳ツールです。大量の文書を一瞬で翻訳できることはもちろん、多言語に対応しているため、ツール導入のコスト以外は必要ありません。翻訳に対するコスト負担が問題となっている企業におすすめです。
リアルタイムでのメール・チャット翻訳
AI翻訳ツールは、外国企業とのメール・チャットの翻訳にも役立ちます。企業によっては直接外国企業とコミュニケーションが必要な会社もあるでしょう。しかし、多言語への対応やスムーズなやり取りを行うためには、語学スキルが必要です。
AI翻訳ツールは、外国語を瞬時に翻訳できることから、メールやチャットといったリアルタイムでのやり取りにも導入できます。外国企業との直接対応を求められる企業におすすめです。
ITreviewで評価の高い翻訳ツール3選
翻訳ツールは昨今の技術の進化により、翻訳精度が飛躍的に高まっています。そこで、ITreviewに掲載の製品より評価の高いツールを3つピックアップ。ぜひ参考にしてみてください。
おすすめ翻訳ツール1:shutto翻訳
株式会社イー・エージェンシーが提供する「shutto翻訳」は、多言語を最短3分で高品質に翻訳するAI翻訳ツールです。世界100言語以上に対応しており、グローバル企業のコミュニケーションをサポートしてくれます。文書以外にWebサイトの翻訳も可能です。
画像に含まれる文字を翻訳する「画像置換機能」など充実したサービスを利用できます。30日間の無料トライアルを利用できるので、まずは翻訳の精度を確認してみましょう。
・shutto翻訳の参考価格
無料トライアルあり
エントリープラン:6,600 円 / 月(税込)~
・shutto翻訳の参考レビュー
自社サイトを多言語対応する場合、従来はプロの翻訳業者に依頼することになるが、shutto翻訳を使えばかなりの精度で自社サイトを瞬時に翻訳できるので大変便利。より詳細に翻訳したい場合には、プロ翻訳を依頼することもできる。
shutto翻訳へのレビュー「AI翻訳とプロの翻訳のいいところ取り」より
おすすめ翻訳ツール2:DeepL
DeepL SEが提供する「DeepL」は、世界最高レベルの高精度なAI翻訳ツールです。言葉の中に隠れた細かいニュアンスまで翻訳できることから、世界各地20万以上のプロフェッショナルが導入しています。
有料プランにはセキュリティ対策が施されており、テキスト量無制限で翻訳できるため、企業利用に最適なツールだと言えるでしょう。
・DeepLの参考価格
無料版あり
STARTERプラン:1,200 円 / 1ユーザー(月払い)
・DeepLの参考レビュー
今まで使った翻訳ソフトの中でも一番翻訳の精度が良く、自然な日本語の文章に訳してくれるので、とても役に立つ。
DeepLへのレビュー「翻訳の精度が素晴らしい」より
無料のアカウントであってもある程度の長さの文章までは入力、もしくはコピペでき、すぐに翻訳してくれるので便利。
PDFやワードなどの形式でもデータごとアップロードすることができ、文字部分の翻訳をしてくれるので、素晴らしいシステムだと思う。
おすすめ翻訳ツール3:ヤラクゼン
八楽株式会社が提供する「ヤラクゼン」は、Word・Excel・Powerpoint・PDFなどさまざまな形式のファイルに対応したAI翻訳ツールです。全28言語に対応しており、エレクトロニクス・インバウンド・IT企業など業界を問わずさまざまな企業で導入されています。
ユーザー数に応じて月額9,000円から150,000円までのプランを提供しており、自社の利用人数に応じて選択できるのも魅力です。ファイルのドロップもしくはテキストを入力するだけで簡単に翻訳を開始できるため、初心者でもすぐに利用できるのもメリットです。
・ヤラクゼンの参考価格
スターター3:9,000 円 / 月(税別)
・ヤラクゼンの参考レビュー
とにかく翻訳の精度が高いことが一番のメリットだと思います。外資系企業の弊社でも、そのままコピペで問題なくコミュニケーションがとれるため、メールやチャットのやり取り、資料作成など多方面で利用することができます。
ヤラクゼンへのレビュー「精度が高すぎる翻訳ツール」より
特に日本語の資料を全て英訳しなければならないシチュエーションによく遭遇しますが、極端な話ですがそのまま英訳をした資料でも相手はほぼ理解できる資料のクオリティにまで持っていくことが可能です。
翻訳のエンジンとしてDeepLが活用できることが精度を担保できている理由かと思いますが、非常に便利で年間で契約する価値があります。
有料であれば上限などもなく自由に使うことができるため、いざ困った時にブックマークを1クリックするだけでこの機能がいつでも利用できることはシンプルに大幅な業務改善に繋がっている。
もっと詳しくAI翻訳ツールを知りたいならITreviewでツールを比較しよう
AI翻訳ツールは、どのサービスも高性能な翻訳が期待できます。しかし、利用料金やサービス範囲に細かい違いがあるので、事前に料金表やサービス内容を確認して利用しましょう。まだAI翻訳ツールに触れたことがない人は、無料プランや体験期間が設けられたサービスを利用するのがおすすめです。
もっと多くのAI翻訳ツールを比較して自社に合ったツールを探したい方は、ITreviewが提供するサービス紹介ページを参考に気になるサービスを比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
投稿 語学を活かした業務をサポート!おすすめAI翻訳ツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 AIの自動翻訳のレベルは?無料版と有料版はどう違う は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、急速に進歩を遂げているAI自動翻訳の特徴や仕組み、そして有料版と無料版の違いといった導入検討に役立つ情報を解説します。
AI自動翻訳とは
AI自動翻訳とは、クラウドを通じて利用できるAI学習機能を持つ翻訳のことです。翻訳したい文章をワンクリックで簡単に翻訳できる便利なツールであり、グローバルコミュニケーションが一般化した現代で、次のような人たちから利用されています。
- 外国人とコミュニケーションを取りたい人
- 外国語の文書翻訳をしたい人
- 外国企業と取引を行う人
以前までのロークオリティな機械翻訳に比べて、自然な文章に翻訳できることはもちろん、専門用語にも対応しているため、現在多くの個人・企業が注目しています。
AI自動翻訳の仕組み
AI自動翻訳は「ディープラーニング(深層学習)」という仕組みによってハイクオリティな翻訳を行います。ディープラーニングには、人間の脳の神経回路に似せた数式をプログラミングし「何重にも考える」という仕組みが採用されています。データベースに蓄積されたビッグデータから正しい答えを導きだして翻訳するため、データの量が多いほど正確な翻訳が可能です。
以前までの翻訳は、ただ文字列を認識して機械翻訳していたシンプルなツールでした。一方、AI自動翻訳は世界中から集めた翻訳結果をデータベースに読み込ませてAIに何度も学習させています。正誤情報を振り分けつつ正しい翻訳を導きだしていくことから、プロの翻訳者と同レベルの翻訳が可能です。
また日々学習を続けるのもディープラーニングの仕組みです。翻訳した情報をもとに、さらなる学習を進めていくことから、今後はより精度が高い翻訳を実現できるでしょう。
AI自動翻訳の無償と有償の違い
ハイクオリティな翻訳を実現するAI自動翻訳ですが、インターネットで検索すると無料版と有料版のサービスが見つかります。このとき、どちらのサービスを利用すべきか悩んでいる人もいるでしょう。そこで、無料版と有料版の違いを3つのポイントに分けてご紹介します。サービス導入を検討中なら、ぜひ参考にしてください。
翻訳ファイル数
価格の違いには、翻訳ファイル数が関係しています。読み込める文字数の違いはありませんが、複数ファイルの同時翻訳の数が無料版と有料版で異なります。個人利用といった少数のファイル翻訳であれば無料版で問題ありませんが、大量の翻訳が必要な企業は有償版の導入がおすすめです。
サポート
価格の違いには、サポートの充実度も関係しています。無料版の場合はメール問い合わせ等を利用できますが、回答までに時間がかかる場合が多いです。一方で、有料版ならメール問い合わせはもちろん、電話サポート、AI翻訳ツール運用者向けのコンサルなど、充実したサポートを受けられます。利用するAI翻訳ツールによりサービス内容が異なるため、事前に確認してみましょう。
セキュリティ
価格の違いには、セキュリティも関係しています。無料版の場合は、オンライン上のクラウドサービスを通じて翻訳を行うため、インターネット経由で情報が流出する恐れがあります。一方、有料版の場合は、ローカル環境にインストールできる「オンプレミス」タイプのAI翻訳ツールを利用できるため、ウイルス感染や情報流出を防止できます。
AI自動翻訳の必要性
AI自動翻訳が必要とされる理由は、世の中のグローバル化が関係しています。以前までの日本は、国内だけで仕事が完結する国内完結型の企業ばかりでした。しかし、現代の日本企業のほとんどは、海外企業と関わりを持つことが増えています。
たとえば、取引先の言語でメール文書や書類を受け取ることがあります。特に世界共通言語となっている英語の文書をよく見るようになりました。これに対し、日本人の多くは英語学習が苦手であり、自身で英文を読んだり、ライティングしたりできない人が大勢います。つまり、英文を読もうとしても、かなりの時間を消費してしまうのです。
AI自動翻訳は、それらの課題を簡単に解決する便利なサービスです。英語が苦手な日本人にとって役立つサービスなので、今後益々需要が高まるでしょう。
AI自動翻訳を利用したいならITreviewでツールを比較しよう
ディープラーニングを使ったAI自動翻訳は、すでにプロの翻訳者と同等レベルの翻訳ができます。また、ディープラーニングは今後さらなる発展を遂げていくことが期待されていることから、海外と取引を行っている企業や翻訳関係の仕事をしている人にとって大きな利益を生み出してくれるでしょう。AI自動翻訳は無料版と有料版で機能やサポートに違いがあるため、自社の活動に当てはまるツールを選ぶのがおすすめです。
投稿 AIの自動翻訳のレベルは?無料版と有料版はどう違う は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 採用管理もできる?採用に強いサイト作りに役立つツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、手間と費用を抑えつつ採用ページ作成をしたい人向けに、おすすめの「採用サイト作成ツール」を3つご紹介します。初心者でも簡単にハイクオリティなページを作れるだけでなく、充実した採用管理機能を利用できるので、ぜひチェックしてみてください。
採用サイト作成ツールを活用して求職者にリーチする
優秀な人材を確保するためには、求人情報の公開が必要です。求人活動において自社採用ページをインターネット上に準備して管理したい人も多いでしょう。
しかし、採用ページを準備するためには多くの手間と費用が必要であり、ページ制作のノウハウがなければ難しいのが実情です。そこで役立つのが「採用サイト作成ツール」です。このツールを利用すれば、ページ制作のノウハウがない初心者でも、簡単に高品質な採用ページを作れます。採用に役立つ機能を整えており、低価格で利用できることから、現在多くの企業がツールを活用しています。
自社にぴったりのツールを探すポイント
採用サイト作成ツールを探してみると、さまざまなサービスが検索にヒットします。どのツールも同じように見えてしまい、どれを利用すればよいか分からない人も多いでしょう。そこで、まずは自社にぴったりなツールを探すために押さえるべき3つのポイントをご紹介します。
予算
採用サイト作成ツールを選ぶときは、まず「予算」をチェックしましょう。提供されているツールはそれぞれ金額が異なります。なかには高額だったり追加オプションに費用がかかったりするツールもあるので、費用を見誤ってしまうと継続利用が難しくなる可能性があります。長期的に利用することを前提としているなら、必ず押さえておくべきポイントです。
使いやすさ
採用サイト作成ツールごとに「使いやすさ」が異なります。たとえば機能の多さやデザインなど、ユーザーが使いやすいと感じるポイントは複数あります。購入後に使いづらいと感じてしまっても後戻りできません。そのため、まずは無料体験期間を利用して試験的に利用するのがおすすめです。
目的
ツール選びは会社の「目的」を意識して選びましょう。会社によって、ただ採用ページとメールフォームがあればよいと考える人もいれば、採用管理や応募者の情報分析まで行いたい人もいます。採用サイト作成ツールは搭載されている機能が異なるので、会社の目的に合わないツールを選ばないように注意しましょう。
おすすめツール1:engage(エンゲージ)
エン・ジャパン株式会社が提供する「engage(エンゲージ)」は、無料で求人掲載できる採用サイト作成ツールです。基本機能が充実しているため、無料プランの利用でハイクオリティな採用ページを準備できます。また、応募者の性格特性が分かる「オンライン適正テスト」、早期離職を回避できる「フォロー機能」といった機能を利用できる有料オプションプランも準備されています。
採用ページは、事前に用意されたフォーマットを埋め込んでいくシンプルなつくりであり、リンクやバナー作成もボタン1つで準備できます。PC版・スマホ版に対応した採用ページを準備できることから、多くの求職者に閲覧してもらえるページを公開できるでしょう。
おすすめツール2:toroo(トルー)
株式会社ダトラが提供している「toroo(トルー)」は、ツール1つでサイト制作から応募管理まで一連の採用マーケティングを実施できます。月額1.65万円(税込)から利用でき、採用ページのほかにも次のようなページを準備できます。
- イベントページ
- ブログページ
また、有料オプションも充実しており、リッチなデザインのページに変更できる機能や、月次レポートに基づいて改善点を提案してもらえる機能など、企業の目的にあったオプションを追加できます。有料での利用が必須のツールなので、まずは無料デモを利用してみるのがおすすめです。
おすすめツール3:採用係長
株式会社ネットオンが提供する「採用係長」は、連携機能に優れた採用サイト作成ツールです。indeed(インディード)や求人ボックスなど、最大6つの求人検索エンジンに作成した採用ページを連携できます。また、初めて利用する方でも安心して採用ページを準備できる電話・メールサポートが充実しているのがメリットです。
採用ノウハウセミナー等が毎月開催されているため、採用に関する情報を集めながら、ハイクオリティな採用ページを準備できるでしょう。「ベーシック」「プロ」「エンタープライズ」など細かく分類された有料プランも用意されていますが、無料で利用できるトライアルプランも提供しています。まずは、無料プランから利用してみてはいかがでしょうか。
もっと詳しくツールを比較したいならITreviewをチェック
多くの企業が人材不足に悩んでいるなか、優秀な人材を集めるためには魅力的な採用ページが必要です。しかし、インターネットを利用した求人募集は、求人サイトや検索エンジン等と連携が必要であり、採用ページ自体も専門知識がなければ作れません。
そこで活躍するのが、採用サイト作成ツールです。基本機能が利用できる無料版はもちろん、高機能な有料版が提供されているため、簡単に採用ページを準備できます。
もっと多くの採用サイト作成ツールを比較して自社に合ったツールを探したい方は、ITreviewが提供するサービス紹介ページを参考にして気になる製品を比較してみてはいかがでしょうか。利用者のレビューや評価も掲載しているので、ぜひ参考にしてください。
投稿 採用管理もできる?採用に強いサイト作りに役立つツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 採用サイトは必要?専門ツールを活かしてよい人材を獲得しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>新卒採用や転職者採用を希望する人材に向けて企業の魅力が伝わりやすい採用サイトを効率よく作成できるので、ぜひ採用サイト専門ツールの利用を検討してみてください。
この記事では、採用活動の準備をしている採用担当者向けに、採用サイト専門ツールの特徴、このツールが必要とされる理由、利用する3つのメリットについて詳しく解説します。
採用サイト専門ツールとは
採用サイト専門ツールとは、採用専門のWebサイトをオンライン上で簡単に制作できるツールのことです。あらかじめ用意されたデザインテンプレートや要素ブロックを用いて、自由にサイトページをカスタマイズできます。
また、サービスによっては、次のような採用活動に役立つ機能を利用できます。
- サイト作成機能
- スケジュール管理機能
- サービス連携機能
- 応募者情報管理機能
- CMS機能
ただ採用サイトを作成できるだけではなく、データの見える化ができるのも特徴です。採用活動に役立つ機能が充実しているので、効率よく人材獲得したいときに活用してみてはいかがでしょうか。
採用サイト専門ツールが必要とされる理由
近年、採用サイト専門ツールを用いて採用ページを作る企業が増えています。その理由は次の通りです。
- 1からWeb制作の知識を覚える必要がない
- 機能を準備する手間や費用がかからない
- Web制作の知識がない初心者が始めやすい
1から採用サイトを作る場合には、Web制作の知識が必要です。自社で採用ページを制作するためには、HTMLやCSSといったマークアップ言語を覚えるのに何か月もの勉強期間を要します。ほかにも複数のプログラミング言語を学ぶ必要があり、非効率的です。
そこで役立つのが採用サイト専門ツールです。あらかじめ用意されたデザインテンプレートに必要項目を埋め込んでいくだけで、おしゃれな採用サイトを簡単に作り出せます。公開までに時間がないときや、Web制作の知識がない初心者におすすめのツールだと言えます。
採用サイトの専門ツールを導入することによるメリット3つ
1.UI・UX・SEOに特化した採用サイトを制作できる
採用サイト専用ツールを利用することで、次の要素を意識した採用サイトを制作できます。
- UI
- UX
- SEO
UIとはUser Interface(ユーザーインターフェース)の略称で、Webサイトで言えば見た目や操作性を指します。UXとはUser Experience(ユーザーエクスペリエンス)の略称で、ユーザーがサービスを通して得られる体験のことです。SEOとはSearch Engine Optimization(サーチ エンジン オプティマイゼーション)の略称で、検索エンジン最適化という意味があります。
これらの要素は、ユーザーの使いやすさや検索ツールのサイト評価に大きく関わる項目であり、全く知識がない初心者が準備するのは困難です。一方、採用サイト専門ツールには、経験豊富なツールベンダーのノウハウが蓄積されています。上記3項目を考慮したデザインテンプレートを利用できるので、初心者であっても品質が高いサイトを作り出せるというメリットがあります。
2.簡単におしゃれな採用ページを制作できる
採用サイト専門ツールには、おしゃれなデザインテンプレートが充実しています。企業イメージやカラーを表現したデザインテンプレートを簡単に見つけられるため、求職者に企業のことが伝わりやすいサイトを作り出せます。
また、企業情報や業務紹介といった情報を求職者に知ってほしいときには、すでに完成したページへブロックのように情報を埋め込んで追加することも可能です。カスタマイズ性に優れているのも採用サイト専門ツールのメリットだと言えます。
3.ノーコードで制作できるから開発費用を抑えられる
従来のWeb制作では、マークアップ言語やプログラミング言語を用いた「コーディング」が必要です。一方、採用サイト専門ツールは、コーディングが不要な「ノーコード」で制作できます。
コーディングを行う場合には莫大な費用と制作期間が必要ですが、ノーコードの場合は、費用と期間を抑えることができます。ノーコードには、採用担当者が直感的に採用サイトを作れるというメリットがあるため、Web制作の知識がない企業から重宝されています。
自社に合うツールと出会うためにも、まずは製品を比較しよう
人手不足が叫ばれる昨今の企業は、より多くの求職者に企業のことを知ってもらい、よい人材に就職・転職してほしいと考えています。しかし、ありきたりな採用サイトを作るだけでは見向きもされない可能性があります。
そこで活躍するのが採用サイト専門ツールです。ツールを利用すれば、低予算、短期間でおしゃれかつ求職者に魅力が伝わる採用サイトを準備できます。新卒や転職希望者の多くはオンラインを通じて求人情報を集めるので、多く閲覧してもらうためにも、ぜひ採用サイト専門ツールを導入してみましょう。
投稿 採用サイトは必要?専門ツールを活かしてよい人材を獲得しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 目的別「適性検査」をピックアップ!採用計画やほしい人物像に合わせて導入しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>この記事では、採用計画や求める人物像に合わせて導入できる適性検査サービス5選をご紹介します。まずはサービスごとの特性を知り、導入効果についてイメージを膨らませてみましょう。
1.営業職の採用に特化/SALES SCORE(セールススコア)
SALES SCOREは、営業人材の採用に特化した適性検査サービスです。営業成績に影響する人材特性を分析し、応募者が入社した後のパフォーマンスまで予測できます。離職リスクの分析まで行えるため、採用活動を無駄にしないためのサービスとしても有効です。既存人材の離職リスクを分析すれば、離職率の高い営業職においても優秀な人材を継続的にキープする環境を整えられるでしょう。
さらに、営業組織全体のスキルアップにも活用できます。成績優秀層の分析を行うことで、トップセールスマンの共通特性を可視化し、これを基準とした営業組織を組み立てることが可能です。
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 費用 | 要お問い合わせ |
2.じっくり精度の高い検査/V-CAT(ブイ・キャット)
V-CATは日本能率マネジメントセンターが提供する、人材の「持ち味」と「メンタルヘルス」を把握するための適性検査サービスです。多様なシーンにおいて自分の強みを発揮できる人材かどうか、ストレス耐性の高い人材かどうかを測定でき、採用面接だけでは分かりにくい特性や本質を知ることができます。
実施時間は50分と、じっくり適性検査を行うタイプなので人材の性格的要素などを細かく分析できます。60年以上にわたる累計1,500万人を超える臨床データをもとに開発されているため信憑性が高く、経験豊富な専門家が測定用紙を1枚ずつ確認して解析してくれます。
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 費用 | 要お問い合わせ |
公式:https://www.jmam.co.jp/hrm/course/assess/item_v-cat.html
3.新卒採用でお馴染み/SPI3
SPI3はリクルートが提供する適性検査サービスであり、新卒採用でもお馴染みの検査となっています。利用企業数、受験者数が非常に多いため検査結果に信頼性があります。2021年12月期の実績では14,400社が利用し、215万人が受験しました。
長年の実績だけでなく、分かりやすく実践的な報告書を入手できるのもSPI3のメリットです。また、受験後すぐに結果が分かるため採用面接の直前に実施すれば、採用活動の効率化にもつながります。
SPI3-UEなら性格検査と能力検査に合わせて、英語能力検査まで実施できるため、グローバル人材の積極採用を行っている企業にもおすすめです。
| 初期費用 | 無料 |
| 費用 | 1,500円~/受験者1名 |
公式:https://www.spi.recruit.co.jp/
4.社内活用もできる/CUBIC適性検査
CUBIC適性検査は、e-人事株式会社が提供する適性検査サービスです。SPI3と同じく新卒採用でよく利用されているサービスでもあります。受験者1名からの利用も可能であり、トライアルも実施しているので、気軽に導入できます。
気分性・慎重性などの性格面、協調性・責任感などの社会性などを数値で把握できるため、応募者の性格を客観的データから分析することが可能です。採用面接では知れない深層部分の参考情報を提供してくれるため、新卒採用はもちろん中途採用にも利用できます。
また、適性検査は採用活動での利用イメージが強いものの、CUBIC適性検査は既存社員に対する人材の適材適所やモチベーション管理にも活用できます。
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | 通常バージョン:~1,700円/受験者1名ストレス耐性バージョン:~2,200円/受験者1名※受験者数が多いほどお得 |
5.5分でビッグファイブ分析/Jobgram(ジョブグラム)
Jobgramはたった5分の診断により、2,040パターンの中から応募者の性格特性を分析できます。データの根拠となっている「ビッグファイブ」とは、心理学者でありアメリカ・オレゴン大学の名誉教授でもあるルイス・ゴールドバーグが提唱した理論です。
ビッグファイブでは、開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症傾向の5因子によって人の性格を判断します。サービスによってその呼称はさまざまですが、基本的にこの5因子をベースにしています。
Jobgramなら5分程度の診断によって応募者の深層的な性格を把握し、自社環境への適合性や入社後のパフォーマンスなどを判断できます。トライアルプランを提供しているので、10人までなら無料で受験可能です。
| 初期費用 | 無料 |
| 月額 | 半年プラン:30,000円~/月年間プラン:25,000円~/月 |
採用活動効率を上げるために適性検査を活用しよう
適性検査サービスには、それぞれ異なる特徴があります。検査精度を重視するのか、コストパフォーマンスを重視するのか、適性検査サービスを利用する目的をあらかじめ明確にするのがポイントです。
加えて、適性検査サービスを導入するメリットについても理解しておきましょう。『新卒や中途採用のマッチングに使える?適性検査を導入するメリット』ではサービス導入のメリットについて詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
投稿 目的別「適性検査」をピックアップ!採用計画やほしい人物像に合わせて導入しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 適性検査にはどんな種類がある?適性検査を導入するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>一方で、通年採用には一括採用以上のコストがかかるため、採用のミスマッチを防ぐことが何より重要です。中途採用においても、新卒者よりも採用コストが高いことが基本なので、やはり採用ミスマッチは限りなくゼロにしたいものです。
そこでこの記事では、採用活動に適性検査を導入するメリットについてご紹介します。採用ミスマッチの防止や採用活動効率化など、この機会に適性検査導入の魅力を知りましょう。
2種類の適性検査
適性検査は一般的に「能力検査」と「性格検査」の2種類があります。それぞれの特徴を整理してみましょう。
能力検査
社会的常識、知識、技術を測る検査です。論理的思考能力や判断力などを知ることができ、応募者の「地頭」を判断するのにも利用されます。
性格検査
協調性、思考性、柔軟性、情緒安定性、ストレス耐性など応募者の性格に深く関わる部分の検査です。適性検査サービスによって根拠とする理論が異なるため、サービスごとに違う結果が出ることもあります。
採用活動においては、一次審査において能力検査を用いて応募者をふるいにかけ、審査が終盤に差し掛かると性格検査を用いて採用候補者の性格的要素を判断するというのがベターなやり方です。
適性検査を導入する5つのメリット
それでは、採用活動に適性検査を導入するメリットを紹介していきます。
メリット1.大量募集において採用活動の手間を省ける
大量募集においては1人ひとりにかけられる時間は限られているため、一次審査などで適性検査を行うと採用活動を効率良く進められます。能力検査を実施し、企業が求める水準に達している応募者のみを残すことで、採用活動初期の審査通過判断をスピーディに行えるようになります。
メリット2.事前検査により採用ミスマッチを防げる
採用活動において一番避けたいのは「人材と企業のミスマッチ」です。双方にとって良い結果にはならないため、採用ミスマッチを防げる仕組みづくりが欠かせません。
そのためのツールとして活用できるのが適性検査であり、とりわけ性格検査が有効です。データを用いて応募者の性格を客観的に分析することにより、本人すら知らない深い部分の性格を把握できます。
分析結果をもとに業務や職場環境の適合性を判断すれば、高い精度で採用ミスマッチを防げるようになるでしょう。
メリット3.入社後の配置や人材育成の参考情報になる
組織全体の能力を底上げするには、人材1人ひとりに合った配置や育成方法を考える必要があります。
ある環境で能力をうまく伸ばせていない人材が、別の環境では見違えるほどに能力を伸ばし、ビジネスに大貢献するのはよくある話です。つまり、環境によって人材の成長性は大きく左右されます。そのため、入社後の配置や人材育成を効率よく進めるために適性検査が有効です。
また、新卒者・中途採用者だけでなく既存人材に対しても適性検査を実施することにより、人材の適材適所をかなえることができます。
人材1人ひとりが生き生きと成長できる環境をつくれば、組織全体の能力底上げだけでなく、離職率低下などにもつながるでしょう。
メリット4.社内人材の客観的評価にも活用できる
人事評価において、今まで以上に公正・公平な評価が求められている時代です。完全成果主義の偏った人事評価では不満が生まれ、人材の流動性を高めるリスクがあります。
ビジネスというのは、一部の人材が生み出す成果だけで成り立っているものではありません。数字には表れなくとも、裏方的に努力をしてチームの精神的支柱になる人材などもしっかりとビジネスに貢献しています。問題は、そうした人材の評価基準をつくるのが難しいことです。数値では表れない人事評価については適性検査でカバーできる部分があります。
性格検査を用いて協調性、情緒安定性、ストレス耐性などを把握すれば、ビジネスにおける精神的な貢献度を把握できるようになります。
メリット5.定期的な検査で従業員のコンディションを把握できる
リモートワークの推進、新型コロナウイルスの猛威などにより、多くのビジネスパーソンがかつてないストレスを受けています。この激動の時代において、従業員のコンディションを整えることは身体的・精神的な健康を維持するために欠かせない業務です。
そのためにも、まずは各従業員のコンディションを把握する必要があります。性格検査を定期的に実施すれば、過去との比較によりコンディションの変化を分析できます。従業員の心に何が起きているのかを把握することで、コンディションの悪化やモチベーションの低下などを事前に察知できるのです。
その上でコンディションを改善する取り組みを行えば、従業員の心理的安定性が保たれ仕事にもプライベートにも意欲的に行動できるようになり、最終的には自社ビジネスに貢献する人材として成長していくでしょう。
適性検査は採用活動のためだけにあらず!幅広い活用を
適性検査を導入するメリットは採用活動にとどまりません。既存人材に実施することでさまざまなメリットを得られるため、適性検査は現代社会を生きる企業に欠かせないツールとなっています。
ただし、適性検査はサービスによって根拠となる理論や尺度が異なるため、サービスごとの特徴を知った上での導入検討が大切です。
投稿 適性検査にはどんな種類がある?適性検査を導入するメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 安否確認システムを導入するべき3つの理由|緊急事態にも対応できるワークフローをつくろう は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>一方で、緊急時の安否確認手段として手動メールを採用している企業は少なくありません。メールはコミュニケーションを図る上で便利なツールではあるものの、緊急時には適さない理由がいくつかあります。
この記事では、緊急時に手動メールではなく安否確認システムを使った方がいい理由についてご紹介するので、この機会に安否確認プロセスについて再考してみてください。
安否確認ツールとは?
安否確認ツールとは、メールやその他の手段によって緊急時の安否確認を行うためのツールです。ツールには主に次のような機能が備わっています。
「安否確認」ツールの代表的な機能
- 緊急事態通知の一斉配信(気象庁連動)
- 安否未回答者への自動再配信
- 特定のグループへの限定配信
- 回答時の位置情報取得
- 回答状況の自動集計
- 回答結果の検索
- デジタル掲示板による情報共有
- 平常時のアンケート
- コロナ禍における健康確認
- スマホアプリによる通知
これだけの機能が揃っている安否確認ツールには、緊急時の安否確認において手動メールよりも優れた点がいくつもあります。また、ツールによっては従業員の家族情報も登録でき、家族の安否確認まで行えます。
安否確認ツールを導入するべき理由とは?
理由1.緊急時でもスムーズかつ確実に安否確認が行える
緊急時の安否確認に手動メールを採用すると、プロセスが計画通りに運ばないケースが想定できます。震度6以上の大地震が発生した場合で考えてみましょう。
激しい横揺れにより家具が倒れ、モノがあちこちに散乱するとメール送信に必要なスマートフォンが紛失する可能性があります。その上パソコンやネットワーク機器まで故障してしまうと、メール送信が完全に行えなくなる可能性があるのです。
一方、安否確認ツールでは気象庁の情報と連動し、大地震などが発生した際は安否確認メッセージが自動的に送信されるため、安否確認の初動を高速化できます。また、ツールが運営されているデータセンターの多くは堅牢性が高められているため、システム障害なども発生しにくいと考えられます。
理由2.メール・電話とは異なる通信手段を確保できる
東日本大震災発生時は、関東一円には「メールが届かない」「電話がつながらない」という問題が発生しました。安否確認を行おうにも、そもそもメールが送信できなければせっかく策定した安否確認プロセスも意味がありません。
安否確認ツールならメールによる安否確認の他に、SMS(ショートメッセージ)やスマホアプリ通知によって通知を自動配信できます。メールや電話が使用できなくなる万が一に備えて、他の通信手段を確保しておくことは重要です。
理由3.BCP(事業継続計画)を策定し、緊急時に事業をどう継続するか意思決定ができる
緊急時において、企業は従業員の安否確認を徹底するのはもちろんのこと、自社ビジネスの継続性についても検討する必要があります。いわゆるBCPの策定です。
東日本大震災では「停電によりパソコンや通信サービスが使えず社内外のやり取りに苦労した」「仕入れ情報がわからなくなった」など、BCP不足によってさまざまな問題が浮上しました。
大地震や台風による水害など、大規模な自然災害が発生した場合でも自社ビジネスの継続性を高めるにはBCPが欠かせません。そして、ビジネスを継続するには人材最優先ということを忘れてはいけません。
安否確認ツール導入の注意点
緊急時に欠かせない安否確認ツールですが、導入の際には以下の3点に注意してください。
- 従業員やその家族の個人情報取り扱い
- 安否確認ツール以外の通信手段を確保
- 定期的な訓練実施により緊急時に備える
特に大切な点は、「定期的な訓練実施により緊急時に備える」ことです。東日本大震災では、安否確認ツールを導入していたものの、実際の緊急時にはツール利用が後回しになってしまったという事例があります。
安否確認ツールを導入するだけでは、いざという時にツールを利用できないケースが想定されます。緊急時に備えて定期的な訓練を実施し、実際に自然災害などが発生した際にスムーズに利用できるようツールを定着させる必要があるのです。
備えあれば憂いなし!安否確認ツールで緊急時対策を
日本は世界の0.25%という少ない国土面積に対して、地震の発生回数の割合は全世界の18.5%となっています。今後は首都直下型地震や南海トラフ地震など、マグニチュード7以上の地震が30年以内に70%程度の確率で発生すると考えられています。企業運営における備えは、常に検討しておくべきです。
『リモートワークでも従業員の安全確認ができる安否確認システム7選』ではおすすめの安否確認ツールをご紹介しています。こちらも合わせて参考にしてみましょう。自社に合ったツールを選定・比較してみてください。
投稿 安否確認システムを導入するべき3つの理由|緊急事態にも対応できるワークフローをつくろう は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 リモートワークでも従業員の安全確認ができる安否確認システム7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>大切な従業員とビジネスを緊急時から守るためにも、この機会に安否確認システムについて検討しておきましょう。そこで今回は、リモートワークでも安全確認ができる安否確認システム7選をご紹介します。
安否確認システムの必要性
地震や台風など、自然災害は予知することができません。仮に起こった際に、会社は従業員の安否を確認する必要があります。安否確認システムが重要とされるのは、「安否確認の漏れがない」「従業員の家族まで安否確認の対象にできる」といった点があげられます。
従業員側の中には会社にプライベートな連絡先を預けることを嫌がる方がいるかと思いますが、緊急時だけの利用であることやシステムからの自動連絡のみが通知されることを説明すればそこまで怪訝にされることもないでしょう。
以下では安否確認システムをピックアップしたので比較検討時にご活用ください。
ITreviewからピックアップ!安否確認システム7選
1.セキュリティ会社大手運営 セコム安否確認サービス
総合セキュリティ会社のセコムが運営する安否確認システムです。災害発生時はセコムが安否確認メールの送信を代行するため、緊急時でも少ない手間で安全確認が行えます。また、安全確認以外の緊急連絡網としても使用できるので、会社の急な予定変更やアクシデント対応なども素早く行えるようになります。
・セコム安否確認サービスの参考価格
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | 要お問い合わせ |
・セコム安否確認サービスの参考レビュー
当社では、台風の接近している地域の支店長が早期退社を促したり、警報の出ている地域への外出を禁止したりすることにも使っています。各支店は、ほとんどが営業職で外出していることが多いので、非常に役立っています。
セコム安否確認サービスへのレビュー「台風接近時の連絡にもつかってます」より
2.安全対策指示までサポート トヨクモ安否確認サービス2
トヨクモ安否確認サービス2は、1ユーザー当たり月額がわずか136円で利用できる安否確認システムです(50ユーザー/ライトプランの場合)。年額払いなら5%OFFなので、コストメリットを追求したい企業におすすめです。もちろん、安否確認システムとしての基本機能を網羅しています。
また、登録メールアドレスが存在しているか否か毎月チェックする機能も備わっているため、緊急時の通知漏れも防げます。
・トヨクモ安否確認サービス2の参考価格
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | 6,800円~/50ユーザー |
・トヨクモ安否確認サービス2の参考レビュー
トライアル期間が十分に設けられ、じっくりと評価できました。
トヨクモ安否確認サービス2へのレビュー「安価に手軽に始めることができ、UIもマニュアルなしで対応」より
価格が安いので、万が一運用上問題があったとしても、途中で終了することも視野にしていましたが、特に問題は発生していません。
また、UIがとても分かりやすく、マニュアルを参照しないで使うことができています。
3.大規模災害での運用実績あり エマージェンシーコール
エマージェンシーコールはインフォコムが運営する安否確認システムです。東日本大震災、熊本地震が発生した際の稼働実績もあり、災害発生時でも安心して利用できるシステムとなっています。また、アプリ・メール・電話など複数の連絡先を登録できるため、災害発生時に確実な安全確認が行えます。グループトーク機能も提供されているため、緊急時のコミュニケーションツールとしても活躍します。
・エマージェンシーコールの参考価格
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | 要お問い合わせ |
・エマージェンシーコールの参考レビュー
普段は安否確認訓練で使用しています!万一を想定して本社より通知が届き、迅速に回答・集計・報告をすることを年に数回行っています。その結果、実際の通知が届いた際に多くの従業員がすぐ回答でき、安否確認をすることができました。
エマージェンシーコールへのレビュー「万一の際に備える!使える!」より
4.多機能システムが月額100円以下 安否確認システム 安否コール
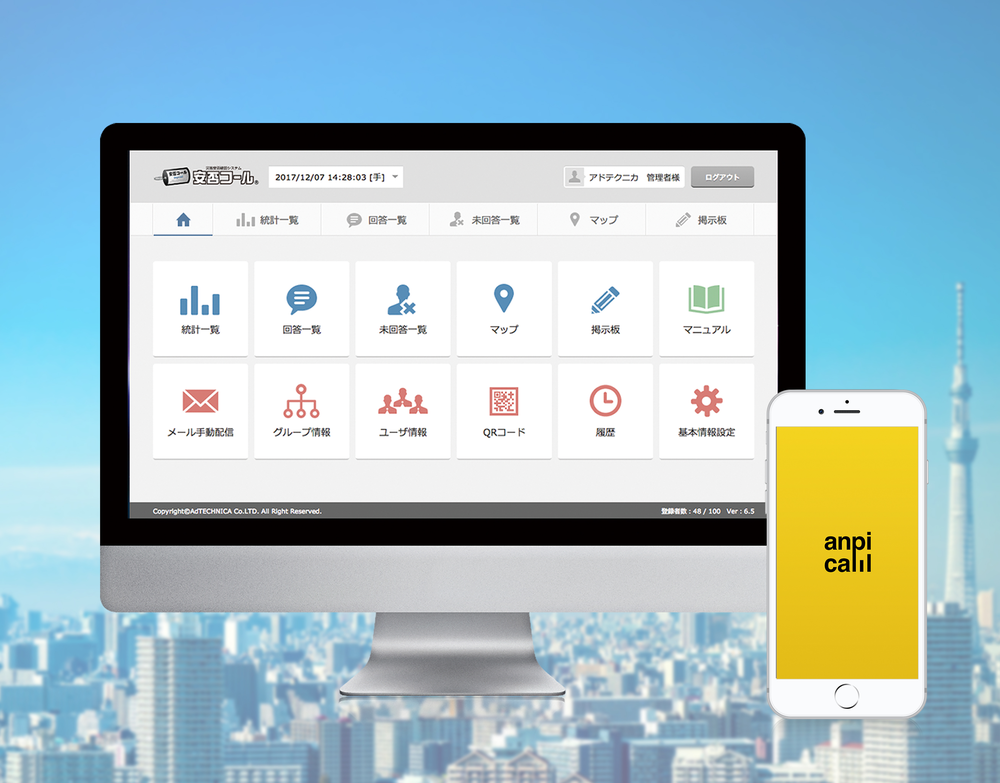
安否確認システム 安否コールは最低価格が1ユーザー当たり月額100円と、中小企業にもおすすめの安否確認システムです。震度やエリアごとに設定できる自動メール配信や、アプリによるプッシュ通知で確実な安全確認を実施できます。オプションでGPSマップ機能を追加し、外出先でも誰がどこにいるのかを瞬時に把握できます。
従業員の家族からコメントや位置情報も届くため、社員も安心して緊急時に備えられます。
・安否確認システム 安否コールの参考価格
| 初期費用 | 80,000円または105,000円 |
| 月額費用 | 5,000円~/50ユーザー |
・安否確認システム 安否コールの参考レビュー
今までは全て手動確認だったものが、コール発信から集計までが全自動となったことで大幅な工数削減、また万が一被災し会社が機能しなくなったとしても、このソフトは別システムなのでそういう心配もないことは大きなメリットです。
安否確認システム 安否コールの参考レビュー「緊急連絡網が不要となった」より
5.強力なバックボーンで安定運営 Yahoo!安否確認サービス
Yahoo!JAPANが運営する安否確認システムです。Yahoo!のプラットフォームを利用することにより、1ユーザー当たり月額44円以下という破格のサービスを提供しています(プランAの場合)。他の安否確認システムに比べて機能面はシンプルであり、インターフェースは少し古めですがコストメリットを追求する企業におすすめです。
導入後の各種設定はユーザー企業で行う必要があるため、サポート体制を重視する場合は注意してください。
・Yahoo!安否確認サービスの参考価格
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | 4,400円/100ユーザーユーザー数に応じてディスカウント |
・Yahoo!安否確認サービスの参考レビュー
本番の安否確認メールのほか、訓練メール(表題に【訓練】などの文字列が付与される)が送れるのが便利です。
また、グループ管理やユーザ管理もシンプルで使いやすい作りだと思います。受け取るユーザ側はログインなどを特に必要としない、というのも利用時の状況を想定した良い作りだと感じました。
Yahoo!安否確認サービスへのレビュー「シンプルながら必要機能が揃ったサービス」より
6.通信大手NTTの安心感 Biz安否確認/一斉通報
さらに破格のサービスを提供しているのがBiz安否確認/一斉通報です。お手軽導入プランなら月額10,400円で100,000ユーザーまで利用できるため、10,000ユーザーで利用したと仮定して1ユーザー当たり月額1.04円となります。通信大手のNTTコミュニケーションズが提供しているため、震度7にも耐える堅牢性もメリットの1つです。
組織階層ごとの権限管理が可能であり、個人情報の表示/非表示も設定できるためセキュリティを重視したい企業におすすめです。
・Biz安否確認/一斉通報の参考価格
| 初期費用 | 0円~200,000円 |
| 月額費用 | 10,400円~/100,000ユーザーまで |
・Biz安否確認/一斉通報の参考レビュー
勤務地付近で大地震が起こると、勝手に安否確認が発動してくれるので事務局が楽です。集計結果を確認するだけで良いので。また安否確認訓練をしても、特に追加課金されるわけではないので安心です。本来の使い方とは違うのかもしれませんが、台風や雪で交通機関が乱れる際の連絡にも活用できます(今日は電車が止まっているので、無理に出勤しなくてOK等)。
Biz安否確認/一斉通報へのレビュー「慣れると便利で使いやすい」より
7. 緊急時のネットワーク混雑回避 NEC緊急連絡・安否確認システム
NECが運営する安否確認システムです。シンプルな機能を提供し、1ユーザー当たりの月額120円以下という低価格で利用できます。スマートフォン・/携帯電話の空メール返信により安全確認を行うため、災害時のネットワーク混雑に関係なく安全確認ができます。また、システムはNECの堅牢なデータセンターによって運営されています。
事業体制の変更に伴う異動が発生した場合は、システム連携で情報を反映できるのでデータ更新作業の手間がありません。
・NEC緊急連絡・安否確認システムの参考価格
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | 12,000円/100ユーザーユーザー数に応じてディスカウント |
・NEC緊急連絡・安否確認システムの参考レビュー
入退場システムや、これまで利用していた在宅時の安否システム等、他システムとの連携が柔軟に行えます。連携方法も、決まったフォーマットのexcelファイルをサーバーに置いておくだけなので、開発もそれほど難易度は高くありませんでした。
NEC緊急連絡・安否確認システムへのレビュー「必要な機能は一通りそろいます」より
社員の安全確保、BPOに安否確認システムは必須!
安否確認システムの導入により、大規模災害時に欠かせない社員の状況把握いち早く行えます。企業にとって人材は宝です。人材を守ることは、ビジネスを守ることにもつながります。まだこうした仕組みを導入していなければ、この機会に自社にピッタリのシステムを探してみてください。
投稿 リモートワークでも従業員の安全確認ができる安否確認システム7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 人事評価システムとは?利用者に人気のツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そんな人事評価の悩みを解決し、HR領域のDX化を加速するのが人事評価システム(OKR)です。
この記事では、人事評価システムの概要や特に人気の高い5つのツールの特徴について紹介します。
人事評価システムとは
人事評価システムとは、従業員の評価制度をサポートするツールです。目標達成の評価といった体系的なシステムを提供すると同時に、社員の顔写真や性格などのパーソナルな情報も一元的に管理できます。
かつては管理者の趣向が反映されていた人事評価に対して、客観的なデータ分析を基に評価することで公正な人事評価を実現します。例えば、人材データベースや組織ツリー図、レイアウトされた評価ワークフローなどの機能です。
人事評価システムは、社員数の多い大企業や公的機関、公正な評価を実現したいベンチャー企業などに導入されており、人事評価の工数削減、従業員満足度の向上を実現できます。
このように、正解のないタレントマネジメントに柔軟な課題解決を支援するのが人事評価システムです。今回はITreviewに掲載されている「人事評価・OKR」のカテゴリから、レビュー数の多い5製品をご紹介します。
代表的な人事評価システム5選
ITreviewに掲載されている製品の中からレビューを多く集めている製品TOP5をご紹介。製品選定の参考にしていただけたら幸いです。
社員の顔を一覧表示する人事評価システム『kaonavi(カオナビ)』

カオナビは、社員1人ひとりと向き合うために作られた人事評価システムです。TOYOTAやみずほフィナンシャルグループなど、大手企業を含む2,500社が導入しています。
カオナビの特徴は、まるでタレント図鑑のように社員の顔写真を一覧表示した社員データベース。顔写真と名前がパッと並ぶシンプルなインターフェースです。OKRやMBO、360度評価などの評価用テンプレートを用意しており、特別な知識がなくてもすぐに評価システムを導入できます。
・利用者レビュー
期首、期中、期末と年3回使用しますが、
引用:https://www.itreview.jp/products/kaonavi/reviews/141546
今までEXCELにて提出をしていたため、どの内容が最新かわからない時がありましたが、
非常にわかりやすくなりました。
過去の内容を参照したいときも便利になり、費やす時間が半分ぐらいになりました。
科学的人事戦略を実現する人事評価システム『Talent Palette(タレントパレット)』

タレントパレットは、科学的な根拠を武器にサポートする人事評価システムです。NISSINやSoft Bankなど大手企業の導入実績を持ち、継続率99.6%を誇ります。
タレントパレットの特徴は、マーケティング思想を人事に取り入れ、人事決定を高度化する科学的人事を実現できる点です。人材の最適配置、データ分析、見える化など、経営の意思決定をサポートする機能が揃っています。MBOやコンピテンシー評価など人事業務に必要な評価フローをワンストップで実現し、被評価者にも使いやすいインターフェ-スを搭載しています。
社員情報の見える化、ダッシュボードを利用して、タレントマネジメント視点で経営幹部と議論。つねにタレントパレット画面を横に置きながら、社員情報、分析などを議論する。その後、実際の人事組織異動案を議論する中でも、タレントパレット画面を開きながら、具体的な社員名とその人の個性や思いを軸に議論が進み、約2ヶ月の異動議論を完結。
引用:https://www.itreview.jp/products/talentpalette/reviews/72411
シンプルで洗練されたUI/UXの人事評価システム『HRBrain』
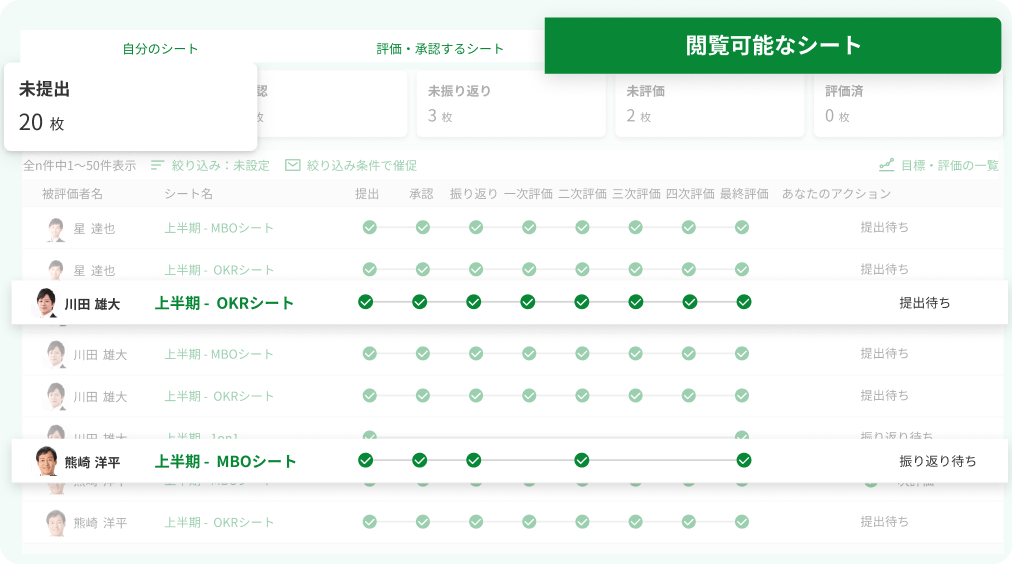
HRBrainは、OKR・MBO・1on1など、豊富なテンプレートを取り揃えており、スマートで利用者がストレスなく操作できる人事評価システムです。Yahoo! JAPANなどの大手企業が導入しています。
HRBrainの特徴は、人材・組織のあらゆる課題をシンプルに解決して人事評価の効率化や人事配置の最適化をサポートする点です。洗練されたシンプルなデザインとスマートな設計で、人材データを可視化することで手軽な分析を実現します。
・利用者レビュー
コロナ禍にあって当社内でもDX化を推し進めているところに良いタイミングで評価システムを導入した為、色々な面で効果を期待しています。現在導入して初めての評価運用をしていますが、リモート体制でも全く問題なく運用できて助かっています。これがエクセルを使ってやっていたかと思うと本当に導入して良かったと思います。
引用:https://www.itreview.jp/products/hrbrain/reviews/57515
課題解決をサポートする人事評価システム『あしたのクラウドHR』
あしたのクラウドHRは、人事評価の課題解決に強みのある人事評価システムです。KIRINやDeNAなどの大手企業を含む4,000社が導入しています。
あしたのクラウドHRの特徴は、「給与シミュレーション機能」「目標添削機能」「評価者モニタリング機能」などのAI機能を搭載し、人事評価における課題解決をサポートする点です。1on1や360度評価など評価業務フローを改善するさまざまな機能を提供します。利用時には専任のカスタマーサクセスチームが徹底サポートし、相談や質問を無制限に受け付けています。
ビズリーチの人事評価システム『HRMOSタレントマネジメント』
HRMOSタレントマネジメントは、東証マザーズ上場企業が提供する安定した人事評価システムです。NTTドコモやauなど大手企業の導入実績があるハイクラス転職サイト「ビズリーチ」が提供しています。
HRMOSタレントマネジメントの特徴は、ユーザーにとって使いやすいタレントマネジメントシステムを実現する点です。従業員情報の「見える化」や管理・活用により、評価業務を効率化して従業員体験を高められます。採用管理クラウド「HRMOS採用」と連携することで、採用から人事評価まで包括的にサポートします。
自社に最適な人事評価システムを選ぼう
人事評価システムには同じような機能が標準装備されているケースが多いものの、選ぶ製品によってシンプルな構造であったり、科学的根拠を重要視していたり、企業文化を反映したりとさまざまな工夫が加えられています。
導入したシステムを再構築するのも、データ移行や運用手順の見直しなどの多大な工数がかかるものです。基本機能はどのツールも確かな技術がありますので、この記事でまとめた各ツールの特徴を把握して、自社の理念に共通するシステムを見つけてください。
投稿 人事評価システムとは?利用者に人気のツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 HRテックとは?人事評価システムを導入する6つのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そんな企業の抱える人事マネジメントを改善し、業務の効率化に活用できるサービスや技術が、HRテックです。
この記事では、HRテックの概要とHRテックを導入するメリットについて紹介します。企業の意思決定スピードを早め、社員満足度向上につながるHRテックについて確認してみましょう。
HRテックとは?期待される6つのメリット
HRテックとは、人材資源を意味する「Human Resources」の略語と「technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語です。ビックデータやAIなどのITテクノロジーを利用して、タレントマネジメントや従業員サーベイなどの人事戦略に関わる課題点を洗い出します。
さらには、マイナンバー管理や給与計算などの事務処理作業を効率化することによって、組織改革とスピード感を持った組織経営をサポートします。テクノロジーを活用してヒューマンリソースを最適化する考え方や技術がHRテックです。
HRテックのメリット1:給与計算の時間を圧縮できる
HRテックの考えは1990年代に誕生したと言われており、主に従業員の勤怠管理や給与計算で使われていました。DX化により技術が進化したこともあり、給与計算に加えて、源泉徴収票や離職証明書の発行手続きなどの事務手続きもスマートに対応できるようになりました。
さらには、マイナンバーカードと連携することによって、税務処理の工数カットを実現するシステムもあります。SmartHRの試算によると、HRテックを導入したWeb給与明細なら作業時間の99%をカットできると算出しています。
HRテックのメリット2:タレントマネジメントとして使える
タレントマネジメントシステムとは、企業のイデオロギーやミッションを達成するために、タレント(人材)の能力やスキルを経営資源としてコントロールする人事戦略です。社員のキャリア希望や業務経験、性格特性、目標設定などの情報を収集し、システムへ一元管理で蓄積します。
社員の入社から退職までのプロセスを振り返り集約することによって、データの分散化を防ぎ、適切な人員配置を実現することで企業の生産性向上にもつながります。HRテックは、社員1人ひとりを会社の財産として、社員のモチベーション管理と正しい評価を行うタレントマネジメントシステムを実現します。
HRテックのメリット3:パフォーマンスを最適化できる人事評価
社員とマネジメント側が相互に納得できる人事評価システムを実現できるのもHRテックのメリットです。従業員ひとりひとりの業務内容と実績を入社から蓄積し、自社の評価軸に合わせた包括的な人事評価を実現します。
キャリア設計をHRテックで共有し、現在のポジションで身につけるべきスキルと将来的なポジションの見通しを立てることもできます。社員のパフォーマンスを最適化できるのもHRテックのメリットです。
HRテックのメリット4:従業員サーベイを活用できる
従業員サーベイとは、社員の満足度を把握するための調査です。職場環境や福利厚生の不満、ハラスメントの発見など、組織として解決すべき課題を従業員の視点から見なおすことができます。子育て世代のための特別なアンケート、ある部署に限定したアンケートなど、対象者を絞りながら調査をすることも可能です。
組織の抱える課題点を洗い出して、社員の意見が反映される風通しの良い職場の実現には従業員サーベイは欠かせません。
HRテックのメリット5:マイナンバーと紐付けられる
税金や社会保障などに利用できる社員のマイナンバーを管理する企業も増えてきました。HRテックの導入により、セキュリティの確保された安全なシステムで、マイナンバーを管理することができます。個人情報を社員が直接入力することもできるため、上司が部下のマイナンバーを把握する必要もなく、安全に管理することができます。
また、HRテック内のデータは暗号化されているため、仮に情報流出の事故が起きたとしても、データの中身までは第三者に解読されません。事務処理の負担を減らすだけでなく、安全なデータ保護にも利用できるのがHRテックのメリットです。
HRテックのメリット6:社員教育の管理に使える
入社後のオリエンテーションや研修などにもHRテックの管理機能が使えます。HRテックへ社員1人ひとりのキャリア希望を登録し、現在所持している資格やスキルから、今後のキャリアに向けて必要となる資格やスキルの助言にも利用できます。
HR領域のDX化を促進する人事評価システムを導入しよう
タレントマネジメントや人事評価にはHRテックを取り入れたツールが活用できます。「SmartHR」や「あしたのクラウドHR」など、HRテックの思考を取り入れた人事評価システム(OKR)も販売されています。
事業拡大に伴い社員数が増えたとしても、HRテックの思考を取り入れた人事評価システムなら、事務処理を効率化しながら確実なタレントマネジメントを実現できます。企業のミッション・ビジョン・バリューを社内へ浸透させながら、社員にとっても満足度の高い組織経営にはHRテックを取り入れた人事評価システムの導入がオススメです。
人事評価システムに興味をもたれたら、こちらの記事も合わせてチェックしてみてください。
投稿 HRテックとは?人事評価システムを導入する6つのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 モチベーション管理ツール7選|社員のやる気をデータ化して離職を予防 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、社員のデータ活用などマネジメントに使えるサービスを7つご紹介します。人材マネジメントのPDCAを回し、強い組織になるためのツール選びの参考としてぜひ活用してください。
1.HRBrain
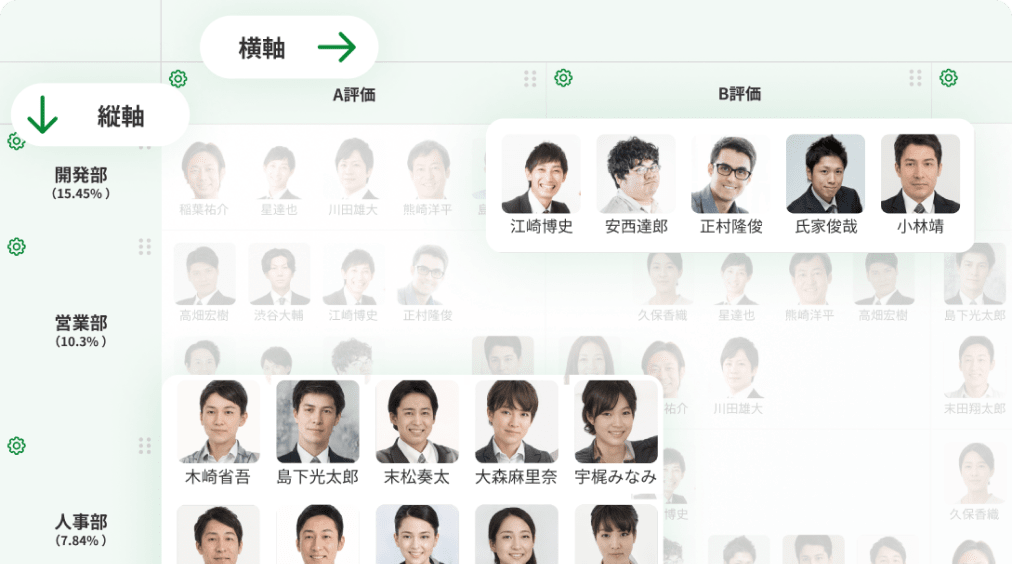
HRBrainは人材マネジメントに加えて、人事評価や労務管理などの機能も備えた総合的なサービスです。2019年にはグッドデザイン賞を受賞しており、人事や現場が使いやすいシンプルなUI(ユーザーインターフェース)も人気を呼んでいます。
専任のカスタマーサクセスがツールの初期設定から運用までサポートしてくれるので、初めて人材マネジメントツールを導入する企業にもおすすめです。
・HRBrainの参考価格
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | 要問い合わせ |
・HRBrainのユーザーレビュー
「アンケート」の結果を社員名簿に登録することで、「アンケート」のコンディションチェックでコンディションが下がってしまっている社員を一覧で確認し、面談の設定や社員のメンタルケアやフォローを行うことができております。
HRBrainへのレビュー「(現在導入中)慣れれば使いやすく、自由度が高いです!」より
まだ使い始めたばかりですが、定期的に行うことで離職率低下を目指して利用・運用しています。
2.CBASE 360(旧名:スマレビfor360°)
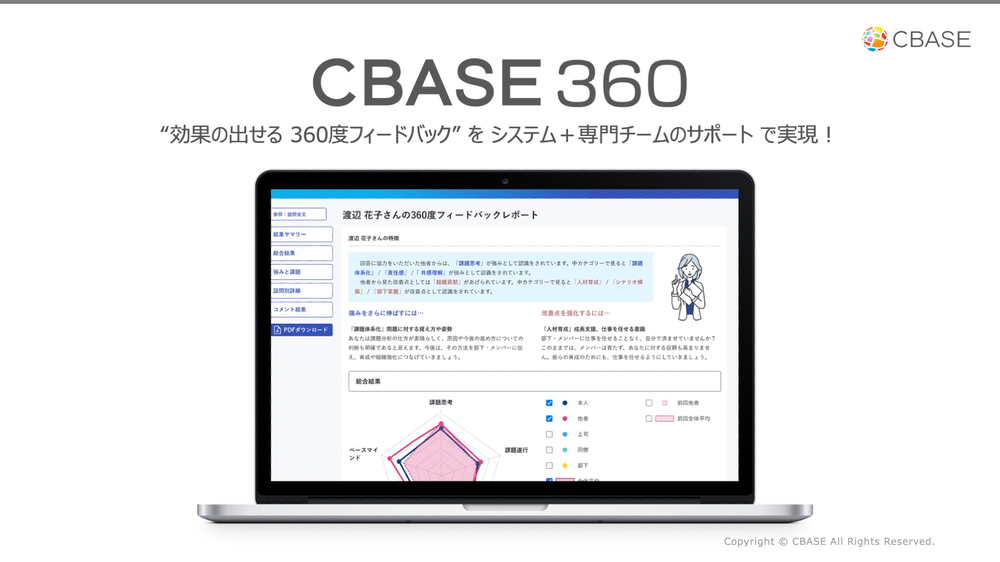
CBASE 360は社員の自己評価と、上司・同僚・部下といった周囲の人の評価を収集・分析することで、社員1人ひとりの評価を多角的に実施する360度フィードバックシステムです。
500社以上の導入実績から得たノウハウに基づき、360度フィードバックをすぐに始められる標準設問が備わっています。社員と組織全体の状況を把握し、人材マネジメントのPDCAを正確に回せるようになるシステムです。
・CBASE 360の参考価格
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | ライトプラン3,200〜4,000円/1ユーザースタンダードプラン4,000〜5,000円プレミアムプラン3,800円/1ユーザー |
※プランごとに別途年間基本料金がかかります
・CBASE 360のユーザーレビュー
働き方が大きく変わってきている中で、メンバーのモチベーションをいかに高め、チームで成果を出すかはとても重要なテーマだと認識しています。その肝となるのが、管理職のマネジメント。しかし、管理職は日々業務に追われ、なかなか自分のマネジメントについて振り返りをする時間が持つことができておらず、人事担当として支援の在り方に悩んでいました。
CBASE 360へのレビュー「毎年継続して実施したい管理職支援施策」より
このスマレビを使うことで、節目のタイミングで他者からフィードバックをもらい、管理職が日々のマネジメントにおける自分の強みや課題を認識して次の取り組みを考えるきっかけが作れるようになりました。1回だけでこの取り組みを終えるのではなく、毎年の健康診断のように全社でこの施策を取り入れ、今では全社の課題の傾向や個別の状況を把握し、管理職に対してどんな支援をしていくかを社内で議論する材料にもなっています。特にスマレビは結果の帳票がわかりやすく、その後の改善行動につなげやすいので、社員からも好評です。
3.ハタラクカルテ
ハタラクカルテは組織課題の見える化を促し、人材定着を支援するサービスです。主にアンケート機能と結果の集計・分析機能によって、社員個人と組織全体の課題を把握・分析できます。
社員個人のメールアドレスがなくても、パソコン・スマホ両方からアンケートに回答可能。アンケート回答における負担を軽減するよう設計されているので、社員もストレスなく回答できます。
・ハタラクカルテの参考価格
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | 167円/1ユーザー(年間契約の場合) |
・ハタラクカルテのユーザーレビュー
人材定着・離職防止に特化しており、専門の先生の監修が入っていることや統計的な分析を元に設問が設計されているので、信頼して利用できる。
そして、無料から利用できるのですが、無料プランでも充分すぎるほどの機能を利用できます。
ハタラクカルテへのレビュー「人材定着・離職防止を実現するならこのツール」より
4.GRATICA
GRATICAは社員同士でサンクスカードを送り合えるサービスで、感謝の気持ちを伝え合う組織文化の醸成に貢献します。同僚や上司などを積極的に助けている社員にはサンクスカードが贈られ、ポイントが溜まります。溜まったポイントをギフトと交換することもできるため、福利厚生の一環としても活用できるサービスです。
普段は目に見えない「ありがとう」の気持ちが届くことにより、仕事に対するモチベーションがアップする可能性があります。人材マネジメントを管理するというよりは「やる気をマネジメントする」イメージのサービスです。
・GRATICAの参考価格
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 30,000円~/100ユーザーまで |
※ユーザー数が増えるほど1ユーザー当たりの料金が安くなります
・GRATICAのユーザーレビュー
感謝のメッセージが見えるようになることで自分の知らないところでの社員の動きを見ることができるようになり、関係性の理解が進むようになったり、このツールをきっかけに会話が行われることがあるため社内活性化のメリットを感じています。
GRATICAへのレビュー「他部署の方と交流できるコミュニケーションツール」より
5.wevox
wevoxは、回答・分析・改善というサイクルを回すことに重点を置いたサービスです。社員にとって負荷の少ない3分間アンケートを行い、結果を自動で集計・分析することで組織課題を把握できます。
他社の成功事例に基づいた最適な改善策が提案されるので、モチベーションアップに向けて今何をやるべきなのかをすぐに判断できます。人材マネジメントに向けた支援サービスも行っているので、初めて導入する企業も安心して利用可能です。
・wevoxの参考価格
| 初期費用 | 0円 |
| 月額費用 | 300円~/1ユーザー |
・wevoxのユーザーレビュー
隠れた離職リスクの発見や、チームの問題を客観的に炙り出すことができた。
wevoxへのレビュー「メンバーのエンゲージメント サーベイサービス」より
総数100名ほど、チーム数10の組織に使用し、まずはチームの特色や問題点のリストアップが出来た。
具体的な結果数値は未だ測れないが、10のチームのうち2チームについて固有の問題点を見出し対策にあたっている。
6.Geppo
Geppoは、2018年にグッドデザイン賞を受賞したサービスです。個人の課題と組織の課題を見える化し、働き方改善を個人・組織の両方から支えてくれます。テレワークにおけるストレスマネジメントにも対応しており、社員のコンディションを常に把握できます。
ストレスやメンタル面での不安を解消することで、テレワーク環境下においても従業員の仕事に対するモチベーションをアップさせられるでしょう。
・Geppoの参考価格
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | 20,000円/25ユーザーまで39,800円/50ユーザーまで68,000円/100ユーザーまで |
※ユーザー数が増えるほど1ユーザー当たりの料金が安くなります
・Geppoのユーザーレビュー
モチベーションチェックをする上で、社員が入力をしてくれない
Geppoへのレビュー「超簡単なモチベーションチェックサービス」より
結局ワークしない ということがあるが、このサービスは入力がめちゃくちゃ簡易的だからこそ回答率を非常に高められる。
また、管理画面などでも社員の毎月の状態を可視化出来るので、
月次でのモチベーションの変化を元に1on1などに活かすことができた
7.いっと

「いっと」は在職者だけでなく、退職者の本音を交えて現在の社内にどのような問題があるかを探すことができるツールです。離職者に対して専門インタビュアーがヒアリングを実施し、解決案を作成してくれるため、第三者的な視点で組織課題の発見に貢献します。また、出戻りの採用にも貢献してくれるなど、会社関係者との深いつながりを構築するのにも役立ちます。
・いっとの参考価格
| 初期費用 | 問い合わせ |
| 月額費用 | 20,000円(ミニマムプラン) |
・いっとのユーザーレビュー
●適性テストを用いて行った在籍者インタビュー
「ハイパフォーマー」「ミドルパフォーマー」「ローパフォーマー」の分析の中で、
ミドルパフォーマーのボリュームが多くハイパフォーマーの育成が急務の状態でした。
適性テストを用いて選定頂きながら、合計96名の社員インタビューを実施したところ、
ハイパフォーマーの素質のある社員や、そもそも環境に問題があること、
配置転換が必要そうな社員や、離職の可能性など、有意義なデータを取ることが出来ました。●新入社員のメンターのヒアリング能力の向上
いっとへのレビュー「社員の”本音”を引き出し解決まで伴走してくれる強い味方です!」より
こちらは「いっと」のサービスとは逸れてしまうかもしれませんが、
メンター制度において個々のヒアリング能力に課題があり効果に差が生まれていました。
そこで、ご相談して研修の一環としてメンタリングの同席をお願いしております。
今まで新入社員とメンターの会話の場に人事が介入したことはなく、
報告書については今後活用していきたいと思います。
モチベーション管理ツールでPDCAを高速回転&データ活用促進!
モチベーション管理ツールは、それぞれに機能面やサポート面で違いがあるので、まずはどのような人材マネジメントを行いたいかを考えることが大切です。その上で機能・サポート・コストを比較して、自社にとって最適なサービスを選びましょう。
投稿 モチベーション管理ツール7選|社員のやる気をデータ化して離職を予防 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 モチベーション管理ツールが解決する課題とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>また、モチベーションの把握などだけでなく、社員の評価面談や1on1にも使えるモチベーション管理ツールもあります。そうしたツールの有効性は知りつつも、具体的な利用シーンが思い浮かばない方もいるでしょう。
モチベーション管理ツールが解決する課題6つ
モチベーション管理の主な利用シーンを6つご紹介します。参考にしながら、自社でのツール活用をイメージしてみてください。
1. 業務効率化は進めているが思うように成果が出ない
ほぼ全ての企業が業務効率化に取り組んでいるにもかかわらず、思うように成果が上がらないケースは少なくありません。その原因は業務効率化の取り組み方自体ではなく、「社員のモチベーションに関係があるのでは」と考えたことがあるのではないでしょうか。
組織全体で仕事に対するモチベーションが下がっていると、いくら業務効率化を推進しても成果は上がりません。一方で、モチベーション管理ツールにより組織全体のモチベーションが上がれば、業務効率化が促進され、明確な成果が現れる可能性があります。
2. コロナ禍以降、離職率が急速に高まってしまった
コロナ禍の影響により急ピッチでテレワーク化を進めた企業は多いものの、待遇面の整備が伴わなかったことにより、社員に転職を考えるきっかけを与えることになった企業もまた多いようです。
type転職エージェントが実施した調査によれば、2018年の転職理由ランキングでは「業務内容」が約半数票を獲得して第1位となっていましたが、コロナ禍の2020年1月〜8月に集計した結果では「年収・待遇」が「業務内容」を上回る結果となりました。
出典:【2020年転職理由ランキング】コロナ禍による転職理由の変化と面接での伝え方|type転職エージェント
コロナ禍の影響で転職理由が大きく変化したことにより、今まで安泰と考えられてきた企業で離職率が急速に高まった、というケースも少なくないでしょう。
離職率が高まると、企業の評判が悪くなることで優秀な人材を確保しづらくなり、人材採用コストも多くかかります。悪循環に陥りかねないため、一刻も早くその状況から脱さなければいけません。モチベーション管理ツールを活用し、社員のモチベーションアップを促して「この会社で働き続けたい」と思わせることで、離職率低減にアプローチできます。
3. 社員1人ひとりのキャリア・ライフプランを大切にしたい
人材とは企業にとって最も大切にすべき資源であり、その人材を尊重しながら一緒に成長していきたい企業も多いでしょう。
「社員1人ひとりのキャリア・ライフプランを大切にする」ことは、そこで働く人材にとって大きな幸福の1つです。また「会社に大切にされている」という意識が根付くことにより、仕事に対するモチベーションは当然アップします。
モチベーション管理ツールの中には総合的な人材管理機能を備えたものも多いため、社員1人ひとりのキャリア・ライフプランを管理することも可能です。「社員を大切にする」「仕事に対するモチベーションがアップする」「利益として還元される」という好循環をつくるためにも欠かせないツールと言えるでしょう。
4. 1on1ミーティングでストレスチェックをこまめに行いたい
コロナ禍による環境変化やストレスが多い状況下などにおいて「1on1ミーティングでストレスチェックをこまめに行いたい」という場合にも、モチベーション管理ツールはおすすめです。
1on1ミーティングを頻繁に実施するためには、スケジュール調整や回答管理など細かい作業が多いので決して簡単ではありません。一方、1on1ミーティングに対応した機能を備えているモチベーション管理ツールなら、細かい作業を効率化しながら社員との対話に専念できます。
5. 社員が相互に行う福利厚生環境を整えたい
社員の仕事に対するモチベーションを上げる方法として、「社員同士の奨励制度」も有効な施策です。例えば、自分の仕事をサポートしてくれた同僚に「ありがとう」を送り、送られた社員はそれを確認できる上にポイントが貯まります。
貯まったポイントはギフトカードなどに変換でき、ありがとうの数だけメリットがあるといった福利厚生です。仕事に対するモチベーションがアップするだけでなく、助け合う企業文化が自然と生まれます。
こうした奨励制度を実現できる機能を備えたモチベーション管理ツールもあるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
6. 仕事に対するモチベーション課題を発見・改善したい
「人材マネジメントを成功させたい」と願っている企業がまず取り組むべきは、人材マネジメントのスタートラインにしっかりと立つことです。そのスタートラインとは「社員・組織が抱えている問題を発見し、原因を究明すること」となります。
モチベーション管理ツールがあれば、今まで感覚で行っていた社員・組織の問題発見や原因究明を、定量的なデータを用いて把握できます。正確な問題・原因を知ることこそ、人材マネジメントのスタートラインです。
仕事に対するモチベーション課題を発見・改善するためにも、モチベーション管理ツールの活用をおすすめします。
モチベーション管理ツールで人材マネジメントを始めましょう
人材マネジメントの重要性が叫ばれる中、アナログでの管理に限界を感じている企業は多いでしょう。独自にアンケートを実施して結果をExcelなどで管理しても、実施や情報更新の手間が非常に多いことから、挫折する確率はかなり高くなってしまいます。
そこで、モチベーション管理ツールを活用して徹底した人材マネジメントを検討してみましょう。ツール導入にコストはかかりますが、それ以上に効率的な人材マネジメントを実感できるはずです。
投稿 モチベーション管理ツールが解決する課題とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 なぜ退職者が増えるのか|モチベーション管理ツールで組織の状況をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>仕事へのやりがいや評価されているなどの実感がなければ、モチベーションを維持するのが難しく「この会社でもっと働きたい」という意志が湧きません。逆を言えば、仕事に対するモチベーションが上がれば、今後も同じ会社で働く意欲へとつながります。
本記事では、モチベーションを管理するためのツールについてご紹介します。離職率の高さで悩まれている方は、ぜひ参考にしてみてください。
離職率の平均はどれくらい?
自社の離職率は「退職者数を1月1日の常用労働者数で割る」という単純な計算で知ることができます。多くの企業は、自社の離職率について把握していることでしょう。では、業界の離職率平均についてはご存知でしょうか。厚生労働省が2021年12月に発表した資料によると、産業別の離職率は次のグラフの通りです。
離職率が最も高いのは宿泊業・飲食サービス業で15.6%でした。宿泊業・飲食サービス業に関しては離職率が毎年高い産業なので、退職者数の多さに悩んでいる企業は多いでしょう。そのほかでは、教育・学習支援業、生活関連サービス業・娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)の離職率が10%前後と高めになっています。
自社が属する産業の離職率はいかがでしょうか。自社の離職率が産業ごとの離職率を超えている場合は、改善が必要と考え、行動を起こす必要があるでしょう。
離職率が高いと何がいけないのか?
「退職したらまた雇用すればいい」という考え方の方もいるかもしれませんが、離職率が高いと企業にとっていろいろとデメリットが生じます。
1つ目のデメリットは、「優秀な人材を確保することが難しくなる」点です。厚生労働省は2015年より、大学生・大学院生向けのハローワークの求人票に、離職率を記載するよう求めています。強制ではないものの「離職率の記載がない求人はブラック企業」という考え方が優勢です。また、離職率の高さは業界内で情報が漏れやすいので、引く手の多い優秀な人材が集まりにくくなります。
2つ目のデメリットは、「離職率が高いことで人材コストが上がる」点です。人材にかかるコストは給与を除くと、採用と育成の2点に多くかかります。中途採用の場合、採用コストは平均103.3万円かかるというデータもあります。
中途採用するたびにこれだけ多くのコストがかかれば、企業財政を圧迫しかねません。「OJTだから育成コストはかかってない」と考える方もいるでしょうが、新卒社員・中途社員が一通り仕事を覚えるまで、先輩や上司が指導に掛ける時間や労力は多大なものです。目には見えないコストが必ずかかっているので注意してください。
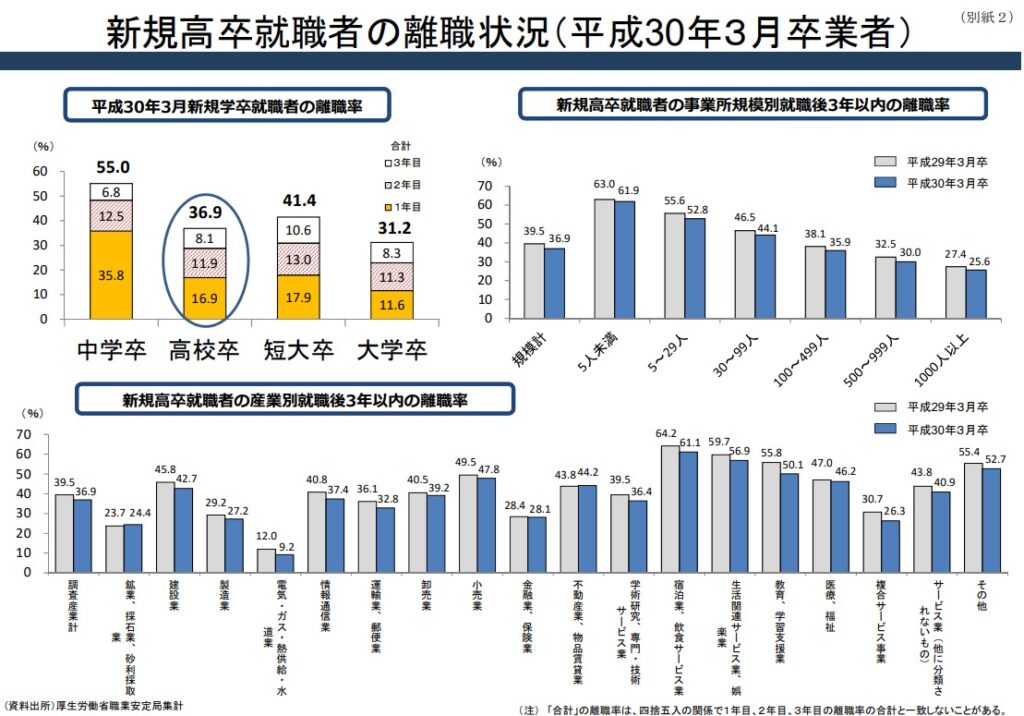
なお、新規大卒就職者の3年後離職率が平均を超えるとブラック企業というレッテルを貼られる可能性があります。参考までに、2021年10月に発表された離職率は31.2%でした。
ぜひ3年後離職率を算出し、照らし合わせてみてください。
退職が続く組織に欠かせないモチベーション管理ツールとは?
モチベーション管理ツールとは、アンケート機能などを活用して社員の仕事に対するモチベーションや業務状況などを把握し、フォロー施策や環境整備支援などを個別に行うためのツールです。
モチベーション管理ツールが提供している質問テンプレートを使用すれば、社員が抱えている本音を知ることができ、個別のモチベーションチェックが行えます。さらに、集計結果から組織の課題診断や分析などを行い、離職率低下のための具体的な施策を考えることも可能です。
退職者数が多く離職率に悩んでいる企業にとってはもちろん、離職率は平均より低いが先手を打ちたい企業、社員のモチベーションをアップさせて更なる業績向上を目指したい企業にもおすすめのツールです。
モチベーション管理ツールに期待する効果
離職率の高い企業には、必ず何かしらの問題が潜んでいます。それは業務プロセスであったり福利厚生であったり、人間関係であったりと原因はさまざまです。
社員のモチベーションをアップさせるにはまず、企業が抱えている問題とその原因を深く究明しなければいけません。ただし、経営者や役員の感覚と経験で仮説を立てる、あるいは社員を呼び出して直接ヒアリングするなどの方法で行うのは危険です。定性的な情報だけでは物事の本質を捉えるのは難しいため、問題と原因を誤り、より悪い状況へと突き進んでしまう可能性があります。
モチベーション管理ツールに最も期待できる効果は、離職率が高い原因を定量的なデータとして把握できることです。ツールを使ってアンケート結果を集計・分析すれば、感覚やヒアリングだけでは気づけなかった問題や原因まで把握できるようになります。
つまり、「離職率低減に向けた施策のスタートラインに立てる」のが、モチベーション管理ツールに期待できる大きな効果なのです。
モチベーション管理ツールで離職率を低下させましょう
現在、離職率の高さや人材コストの増加に悩んでいる企業は、ぜひともモチベーション管理ツールの導入を検討してみてください。
離職率低減が難しいのは、いまだ当事者意識を持っていない企業が多いからです。そうした課題をモチベーション管理ツールで乗り越えた上で、離職率低減に向けて歩み始めてみましょう。
投稿 なぜ退職者が増えるのか|モチベーション管理ツールで組織の状況をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 採用管理とは?採用業務の課題を解消する採用管理システムのメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>今さら聞けない採用管理の基本
まずは採用管理の概要について押さえておきましょう。定義や目的など、採用管理に関する基本的な情報について説明します。
採用管理とは?
採用管理とは、企業が外部から人材を雇用するための施策および計画のことです。また、内定後の人員配置や部署間の異動など、バランス調整も採用管理に含まれます。新しい人材を積極的に採り入れ、企業の力を維持していくためには重要な取り組みです。
採用活動を行う目的
採用活動の代表的な目的として「不足している人材の確保」と「新しい人材の追加による企業の活性化・ステップアップ」の2点が挙げられるでしょう。
事業規模の拡大や新事業の開拓などにより、企業の人材が不足してくるケースがあります。近年は労働人口の減少により、新しい人材の獲得が難しくなってきているのが現状です。ITなど特定の業界ではすでに深刻な人材不足が起きており、人材の確保を急いでいる企業は少なくありません。
加えて、国内外の市場で生き残っていくために、企業の活性化・ステップアップを余儀なくされています。これらを実現するための優秀な人材の獲得は、企業にとって急務になっており、多くの業界で人材獲得の競争が激化しています。
採用管理はこれらの目的を踏まえ、効率的で安定した採用活動を行うための取り組みといえます。
採用活動の具体的なステップ
採用活動を無計画に進めると無駄な時間やコストがかかってしまいます。事業計画から逆算して、順序立てて計画していくことが大切です。以下では、採用活動の具体的なステップをご紹介します。
1.採用計画の立案
まず、採用計画を明確にする必要があります。採用計画において決めるべきポイントは、大きく分けて「採用人数」「雇用形態」「採用のタイミング」の3つです。
採用人数については、予算や業務量から算出するのが一般的です。予定している事業の戦略から、概算で必要な人数を割り出すこともあります。
雇用形態として選ばれることが多いのは自社雇用です。ほかに、派遣社員の雇用やアウトソーシングなどを選択肢として加えておくと、計画の幅が広がります。
採用のタイミングについては特に慎重な判断が必要です。新しい人材は企業に参加した直後から力を発揮できるわけではありません。その人材に活躍してほしい時期から逆算して採用のタイミングを決める必要があります。
2.採用戦略の策定
続いて、自社に必要な人材を獲得するための採用戦略を検討します。
まずは必要な人材をイメージし、その人材に対して自社をどのようにアピールできるのか検討しましょう。単に新しい人材に望む知識やスキルをイメージするだけでは十分でありません。悩みやキャリアプランを仮定するなど、具体的な「ペルソナ」まで定義することが大切です。緻密な採用戦略を策定しておくことで、その後の施策に一貫性が生まれます。
3.採用手法の選定
採用戦略で定義したペルソナに対し、どの媒体でどのようにアプローチしていくのか検討します。以下のような手法が代表的です。
- 求人サイト
- エージェント
- スカウト
- リファラル採用
- SNS採用
それぞれに強みがあり、かかるコストも異なります。ペルソナがどんな媒体を利用しているのか検討したうえで、リーチしやすい手法を選びましょう。また、複数の施策を組み合わせることも一般的です。
4.募集活動の開始
採用手法を決めたあとは、募集活動に着手します。各媒体の利用手続きのほか、掲載する募集要項・スカウトのテキスト作成を行います。
募集要項は、「必要事項」と「歓迎事項」を分けて記載するのが一般的です。「求めている人材」の解像度が高いほど、求職者にとっては自分に合った求人案件なのか判断しやすくなります。企業の理念についても、あらかじめ求職者と共有しておくことが重要です。
企業側から能動的に転職を検討している人にアプローチする「スカウト」は、近年ではスタンダードな採用手法になりつつあります。テンプレートを使うと多くの人材にアプローチできるため効率的ですが、本当に欲しい人材に対しては個別に書いたテキストのほうが効果的でしょう。
5.選考
一定の応募が集まった段階で選考・面接を開始します。面接時は、必要条件・歓迎条件を踏まえて、評価基準を明確に設定しておきましょう。担当する面接官によって採用基準が異なるケースが生じるためです。
また、スカウトや紹介の場合は選考をスキップして面談に進んでもらうなど、柔軟に対応することも大切です。
6.内定・入社フォローの実施
内定を出したからといって、その人材を獲得できるとは限りません。入社までは、内定者の不安や疑問の解消に努める必要があります。こうしたフォローが不十分だったために辞退されるケースは少なくありません。入社後のミスマッチを防ぐためにも、内定者が求めている情報は隠さず正確に伝えましょう。
採用管理には、入社した人材がスムーズに活躍できる仕組みづくりも含まれます。社内SNSへの参加案内、マネージャーとの1on1ミーティングの実施といった取り組みで、新入社員が組織になじめるように誘導しましょう。
企業が直面している採用業務の課題
採用は企業にとって欠かせないタスクです。しかし、多くの企業が以下のような採用業務の課題に直面しています。
採用状況の把握が難しい
一度に大人数を採用する新卒採用は、複数人の人事スタッフで取り組むのが一般的です。業務的にも非常に忙しいため、情報共有が困難になります。内定者の数が把握できない、それぞれの応募者がどの採用ステップまで進んでいるのかわからない、といった問題が起こりやすくなります。
対応ミスで信用を落としてしまう
多くの応募者に対応していると、連絡の遅れや情報の取り違いといった対応ミスが頻発します。契約までは、応募者も企業を吟味している段階です。対応ミスによって信用を落とせば、優秀な人材を逃してしまうことがあります。
セミナー・面接の調整に手間がかかる
セミナーや面接のスケジュール調整は採用業務の中でも特に煩雑です。人事スタッフのリソースの多くが消費されてしまいます。
求める人材と採用する人材のミスマッチが起こる
採用戦略が十分に検討されていない場合、求める人材と採用する人材のミスマッチが起こりがちです。採用した人材も企業に不安や違和感を抱くため、離職者が増えてしまいます。
求人ページの情報が不足し求職者に訴求できない
募集要項のテキスト作成スキルや作成経験がないことから、十分な情報を提供できないケースがあります。「お気軽にお問い合わせください」という記載だけでは、企業や仕事のアピールにはなりません
採用管理システムの導入で採用の課題解決
上述した課題を解決するため、多くの企業では「採用管理システム」が導入されています。以下では、採用管理システムの概要や代表的な機能を紹介します。
採用管理システムとは?
採用管理システムとは、採用業務を効率的に処理するためのシステムのことです。求職者への情報発信、採用スケジュールの管理、応募者情報の管理などをシステム上で処理できます。特に大規模求人を出している場合や複数の媒体を利用している場合に力を発揮するツールです。
採用管理システムの機能
採用管理システムの主な機能を紹介します。
応募者情報管理
各媒体から送られる応募者の情報を一元管理できる機能です。履歴書に記載される基本情報のほか、採用の進捗などを管理できます。
採用タスク管理
採用活動において処理すべきタスクを管理する機能です。書類選考、面接、最終選考といったタスクを配置することで、それらの抜け落ちを防ぐことができます。
採用スケジュール管理
面接、セミナー開催などのスケジュールを管理する機能です。空いている日時が可視化されるため、応募者を交えたスケジュール調整が容易になります。
採用状況分析
媒体や施策ごとの採用状況を分析する機能です。採用しやすい媒体やかかるコストに対する予想応募数・採用数などがわかるため、媒体の選定などに役立ちます。
採用ページ作成
自社の採用ページを作成する機能です。多くの採用管理システムではテンプレートが用意されており、簡単に自社のイメージに合ったデザインの採用ページを作成できます。
採用管理システム導入のメリット・デメリット
採用管理システムの導入には以下のようなメリット・デメリットがあります。双方を理解したうえで導入することが肝要です。
採用管理システム導入のメリット
1.採用業務の効率化につながる
情報が1つのシステムにまとめられることにより、採用業務が効率化します。限られた採用担当者のみが情報を管理している場合、フローを進めるたびにその担当者に確認をとらねばならず、非効率です。採用管理システムを使えば、複数人がアクセスできるため情報共有が容易になります。
2.より効果的な採用戦略を策定できる
採用管理システム上で過去に実施した採用活動の内容や結果を記録しておくことができます。施策による応募数の増減、面接以降の辞退率といったデータを分析することが可能です。こうしたデータは、次回の採用戦略の策定に役立ちます。
3.対応ミスを減らせる
多くの採用管理システムに搭載されているタスク管理機能は、細かな業務の抜け落ち防止に役立ちます。応募者への連絡漏れ、連絡ミスなどは自社の信用を大きく落とすことにつながるため、可能な限り防止しなければなりません。採用管理システムによっては、こうしたミスを防止するためのアラート機能が搭載されたものもあります。
4.求人サイトと連携できる
採用管理システムは一般的に求人サイトとの連携が可能です。特に複数の求人サイトを利用している場合は、各サイトからの応募情報管理が煩雑を極めます。採用管理システムには求人サイトからの応募情報が自動で反映されるため、情報把握が大幅に効率化されるでしょう。
採用管理システム導入のデメリット
1.コストがかかる
採用管理システムを導入する場合、初期費用のほかにランニングコストが発生します。月々5万~10万円程度が目安です。Excelなどの管理と比較すると大幅にコストアップしてしまう点がデメリットです。採用の規模が小さい企業では、コストに対して十分な恩恵を感じられないかもしれません。
2.自社と相性のよいシステムを探す必要がある
採用管理システムの操作感や搭載機能は製品によって異なります。自社と相性の悪いシステムを導入すると無駄にコストがかかってしまうため、導入する製品は慎重に選ばなければなりません。
3.社内で定着するまで時間がかかる
採用管理システムは人事スタッフ、面接担当者など多くの社員が利用することになります。導入によって各社員の業務が変わることになるため、事前の準備は不可欠です。情報共有やマニュアルの整備、研修、権限付与といった準備が必要になります。実際に導入したあとも、明確な効果を感じるまでは時間がかかるでしょう。
採用管理システムの活用事例
採用管理システムを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
年間で数百時間の工数削減に繋がっています
「弊社は中途採用が中心の為、導入に際してはかなり迷いがあったのですが、自動化機能による業務工数削減を最優先にてSONARを導入しました。以前はHRMOSを利用していましたが、面接日程の調整メール、確認メール、SPIの受検登録~依頼などが完全自動化し、年間で数百時間の工数削減に繋がっています。工数削減だけではなく、面接官が判定した瞬間から日程調整に進められるため、リードタイムも若干ではありますが縮めることに繋がっています。
https://www.itreview.jp/products/sonar/reviews/70880
▼sonar ATS
▼企業名:BCホールディングス株式会社 ▼従業員規模:300-1000人未満▼業種:経営コンサルティング
管理業務の時間削減に役立っている
「応募者や採用関係者が何年増えていく中で管理業務に時間を割く時間が増えてきていましたが、SONAR ATSでは候補者への連絡・面接予約などの設定や一括連絡が容易になっており、管理業務の時間削減に役立っていると感じています。結果的に、本来時間を割くべき候補者とのコミュニケーションに時間を取ることができていると感じています。
https://www.itreview.jp/products/sonar/reviews/65528
また、近年様々な採用媒体ができていますが、それらとのAPI連携を非常に積極的に実施いただいている(=SONAR ATSで一元管理できる)のも大変助かっています。今後更に連携先が増えることを期待しています」
▼利用サービス:sonar ATS
▼企業名:三井化学株式会社 ▼従業員規模:1,000人以上 ▼業種:その他の化学工業
採用業務が迅速にすすめられました
「人事部から事業部門への求人情報の共有、連絡、進捗把握が明瞭になる素晴らしいツールです。旧来はExcel、メール、チャットを組み合わせて状況把握していたものが一か所に集約され選考過程の状況が明確です。大勢の面接を同時に並行していく際に状況がよく分かるため採用業務が迅速にすすめられました」
https://www.itreview.jp/products/hrmossaiyoukanri/reviews/87212
▼利用サービス:HRMOS採用
▼企業名:株式会社ハンモック ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
採用管理システムの業界マップ
採用管理システムのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
採用管理システムの選び方のポイント
自社に合った採用管理システムを見つけるためには、以下のようなポイントを意識しましょう。
操作性
実際にシステムを操作する社員がスムーズに使えるように、直観的な操作ができる製品を選ぶのがおすすめです。また、画面の遷移スピードなどの細かなレスポンスも業務効率に影響します。ストレスなく利用できるか判断するため、無料のトライアルを活用しましょう。
導入・運用コスト
各システムのコストについても注目してください。大規模で多機能なシステムほどコストが高くなります。無駄にコストを増大させないためにも、自社の規模に合ったシステムを選ぶことが大切です。
分析機能
頻繁に採用活動を行っている場合は、分析機能が充実した採用管理システムがおすすめです。分析機能を利用して採用活動の実施と改善を繰り返すことで、優秀な人材を効率よく獲得できるようになっていきます。
外部システムとの連携
人事関連システムをすでに導入している場合は、外部システムとの連携可否について確認が必要です。連携できない場合は担当者が手作業でデータを入力する必要があり、工数が増えてしまいます。
採用管理システムおすすめ比較5選
実際に、採用管理システムを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの採用管理システムを紹介します。
(2021年12月23日時点のレビューが多い順に紹介しています)
i-web
「i-web」は、充実した機能とシンプルな操作性で、多くの企業に評価されている採用管理システムです。基本機能のほか、進行している採用活動の状況を可視化する統計機能が搭載されています。効果検証機能も優秀なため、採用活動を着実に改善していけるシステムです。
sonar ATS
「sonar ATS」は、選考状況を見える化する機能や、連絡の自動化機能が高く評価されている採用管理システムです。対応している採用手法が豊富なため、年度によって手法を変える場合もシステムを切り替える必要はありません。使った分だけ費用が発生するクラウド型のため、コスト削減効果も期待できます。
RPM
「RPM」は、年間100人以上の大規模採用を行う企業に向けて開発された採用管理システムです。350以上の求人サイトから、応募者情報を自動取得できます。オンライン面談、LINEによる応募者とのコミュニケーション、応募者自身による面接予約など、大規模採用の負担軽減につながる機能が豊富です。
HRMOS採用
「HRMOS採用」は応募者情報管理、採用業務の進捗管理、採用活動のデータ分析など基本的な機能を網羅した採用管理システムです。クラウド型のため、複数人での情報共有が容易になります。転職支援サービスを運営している株式会社ビズリーチが提供しており、人材採用関連のサポートを受けられる点も特徴です。
HERP Hire
「HERP Hire」は、Slack、Chatworkとの連携により、スピーディーな情報共有を実現するツールです。応募の通知や応募者との連絡は各コミュニケーションツール上に表示されます。「Find Job!」「SCOUTER」「YOUTRUST」など、IT企業に広く利用されている求人サービスとの連携が可能な点も強みです。
ITreviewではその他の採用管理ツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
採用管理システム(ATS)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧はこちら
まとめ
採用業務による負担を問題視している企業は少なくありません。将来的には多くの業界が人材不足に陥ることが予想されているため、採用業務を効率化し、競合よりも先に人材を獲得することは重要です。
採用管理システムの導入によって、業務負荷の改善、人材不足問題への対応の双方を実現できます。ぜひ、自社に合った採用管理システムを探してみてください。
投稿 採用管理とは?採用業務の課題を解消する採用管理システムのメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 クラウドソーシングとは?活用するメリットや注意点を受注・発注側から解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>クラウドソーシングとは?
クラウドソーシングとは、Crowd(群衆)とSourcing(調達)を合わせた造語で、企業や個人がインターネット上で不特定多数の人に業務を依頼するビジネス形態を指します。
・関連記事
BPOとは?アウトソーシングとの違いは?注目される背景と導入時のポイント
クラウドソーシングという言葉が使われはじめたのは、2000年代に入ってから。クラウドソーシングの名づけ親は、米国の雑誌「WIRED」の編集者ジェフ・ハウ氏とされています。2006年6月に同誌の記事で、科学課題解決コミュニティサイトや写真素材提供サイトなどが、ビジネスや研究開発に多大な影響を与えていることを紹介し、この現象をクラウドソーシングという言葉で表現しました。
クラウドソーシングで受発注されている業務の種類は非常に幅広く、代表的なものは以下です。
・IT系…Webサイトデザイン、アプリ開発、システム開発、サーバ構築
・デザイン系…イラスト作成、ポスターデザイン、映像編集、写真撮影
・オフィス系…経理代行、翻訳・通訳、データ入力
・アイデア系…ネーミング、商品企画
・その他…記事作成、テープ起こし
クラウドソーシングに注目が集まる理由
クラウドソーシングは、従来の雇用や外注方法の課題を解消する手段として注目されています。企業は専門性をもった人材を雇用することによって、ビジネスや研究開発における優位性を担保してきました。一方で人材の確保が困難であることやコストがかかることがデメリットでした。
しかし、インターネットの発展とともにネットワークを活用して業務委託者を幅広く募ることが可能となり、クラウドソーシングで業務内容に見合ったコストで最適な労力・スキルを確保できるようになったのです。専門性の高い人材を雇用せずとも自社業務に活用できます。社外の人材の力を借りることで、効率的な経営課題の解決につながり、採用や雇用継続にかかる費用を抑えて組織をスリムに保つことも可能です。
フリーランス人口の増加も、クラウドソーシングが普及した理由の1つでしょう。インターネットやテクノロジーの進化で、より多くの人が在宅勤務できるようになりました。これまでさまざまな事情でオフィスで働けなかった人たちが、フリーランスとして活躍しやすくなりました。クラウドソーシングは、地方在住者が都市部の仕事を受注したり、日本にいながら世界中の案件を獲得したり、ライフスタイルに合わせた働き方を実現できる新しい業務形態として注目を集めています。
クラウドソーシングの仕事の特徴
業務内容はさまざま
クラウドソーシングで受発注する業務には主に3つの形式があります。1回完結の「タスク形式」、長期間のやりとりが必要な「プロジェクト形式」、複数の提案からより高品質なものを採用する「コンペ形式」です。いずれの業務もインターネットを介して作業、納品するものがほとんどです。システムやアプリ開発のようなIT系はもちろん、動画編集、デザインや翻訳、データ入力なども募集されています。多くの分野で業務の受発注が可能です。
1億総クラウドワーカーの時代
副業・兼業奨励やジョブ型雇用が注目される中、企業に所属するしないにかかわらず、すべての人がフリーランス感覚をもつことが求められています。今後は、自分のスキルや経験を証明し、それを武器にビジネスチャンスを獲得していくことが必要となります。クラウドソーシングが普及したことで、インターネットとパソコン、場合によってはスマートフォン1台あれば仕事ができる時代になりました。これまでさまざまな事情で通勤や定時勤務が難しかった人たちも、時間や場所を問わず、自分の専門性やスキルをもとに活躍できる時代になりつつあります。
「クラウドソーシングは単価が安い」のは本当か?
クラウドソーシングには業務ごとの相場がほとんどなく、同じ業務レベルでも報酬には差があります。クライアント側から見れば、スキルや人となりが見えない状態で依頼するため、なるべくリスクを回避したいという事情もあり、比較的安価な依頼に偏ってしまうという面もあります。
また、一見して単価が高くても工数が多かったり、不慣れなために時間がかかったりして、時給換算では安くなってしまうことも。しかし継続依頼を受けたり、地道に信頼関係を構築したりしていくことで、より重要で高額の案件を紹介してくれるケースも少なくありません。最初は収入面で厳しいかもしれませんが、着実に案件を完了していくことが大切です。自分がもつスキルや実績をプロフィールやポートフォリオにまとめておくなど、自ら発信する姿勢も必要です。
どのぐらい稼げるのか?
請け負う業務内容や受注量、必要なスキルによっても異なるため、収入金額には個人差があります。スキルがあり成果物の品質が高い場合、同じクライアントから継続依頼が見込めるほか、高評価が集まれば次の案件につながり、収入が増える傾向にあります。クラウドソーシングサイト内で実績を重ねるまでは単価や時給が低い可能性も。しかし、着実に高評価を獲得し、ポートフォリオを作成する、過去の実績をプロフィールに盛り込むなど、さまざまな工夫を続けていけば、収入アップも期待できます。
クラウドソーシングの3つの形式
クラウドソーシングにおける業務の遂行形式は主に「プロジェクト形式」「コンペ形式」「タスク形式」の3つがあります。報酬についてはサイトの信頼度を保つために、業務着手前の仮入金となる場合がほとんどです。マッチングしたワーカー(受注者)が滞りなく業務を完了した際には支払われ、何らかの事情で未完了に終わった場合にはクライアント(発注者)に返金される仕組みです。
プロジェクト形式
長期の依頼、事前の説明や作業中のやりとりが必要な依頼、修正対応が発生する依頼はプロジェクト形式がおすすめです。限られた人数と契約して、段階的に業務を進めていきます。サイトやバナー制作、アプリ開発、システム構築などが代表例です。
タスク形式
修正の必要がなかったり、フォームだけで作業が完結できたりする依頼はタスク形式を利用します。スキルや経験不問の単純作業で、多数の作業が必要な場合に向いています。データ入力、アンケート回答、記事作成などがタスク形式の主な業務です。
コンペ形式
クライアントが多くの人に依頼して「なるべくたくさんのアイデアから気に入ったものを選びたい」という場合に使われます。あらかじめ要件が決まっているため、ワーカーはクライアントの要望に沿ったものを提案します。たとえば、ロゴデザインやチラシ・ポスター作成、キャッチコピーなどが該当します。
クラウドソーシングの仕事概要
クラウドソーシングを具体的に始める際に知っておきたい仕事の概要を、発注者側と受注者側の立場から説明します。
発注者側にとってのクラウドソーシングとは?
・仕事を依頼する方法
依頼したい業務のカテゴリ内に、新規案件のタイトルと詳細内容を記載します。業務を任せたい、相談したいワーカーが決まっている場合には、ワーカーに直接働きかけることも可能です。
・仕事の依頼形式
依頼したい業務によって「プロジェクト形式」「コンペ形式」「タスク形式」の中から適切な依頼方法を選びます。
・依頼オプション料金
依頼の応募率を上げたり、応募ワーカーの質を担保したりするため、案件の上位掲載や特定のワーカーに対してのみ募集するなど、さまざまな有料オプションがあります。
・仕事の発注相場一覧表
発注相場を一覧にして公開しているサイトがほとんどです。あくまで一例ですが、値付けの参考になるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
・支援サービス
依頼内容に合わせて、スキルがあり評価の高いクラウドワーカーを紹介してくれるマッチング支援サービスもあります。自社に合うワーカーの探し方がわからない、該当者が多く迷ってしまうなど、人選に困ったときに利用すると便利です。
受注者側にとってのクラウドソーシングとは?
・仕事を受注する方法
サイトへのプロフィール登録を済ませたら、興味のあるカテゴリから仕事を探します。受注形式や報酬額、報酬形式など、細かく条件を付加しての検索も可能です。気になる案件が見つかったら応募します。
・仕事の受注形式
長期間にわたる「プロジェクト形式」、テーマに沿って提案を提出して採用を待つ「コンペ形式」、単純作業に多い「タスク形式」の3つが一般的です。
・ワーカーシステム利用料
多くのサイトが登録から受注まで無料で利用でき、ワーカーの確定報酬から天引きする形でシステム利用料を支払います。
・安心・安全への取り組み
各サイトで、悪質なクライアントの取り締まりを強化し、ワーカーの労働力搾取の防止措置を講じています。たとえばマルチ商法やネットワークビジネスなどの悪質案件に関する対策や、優良クライアントの可視化、適正報酬での取引推進など、さまざまな対応がなされています。
クラウドソーシングの仕事の流れ
クラウドソーシングは、サービスごとにシステムや使い方に多少の違いはありますが、進行上の基本ルールは共通です。クライアント(発注者)側とワーカー(受注者)側の立場で、登録から掲載・応募、業務遂行、報酬の支払いと受け取りまでを説明します。
クライアント(発注者)側の発注の流れ
・クラウドソーシングサイトを選び、利用登録をする
・発注したい業務の詳細を掲載する
・ワーカーから送られてきた提案内容、見積もりを検討する
・業務を依頼するワーカーを選び、発注する
・業務途中のチェックをし、修正を依頼する
・納品物を受領、検収する
・報酬を支払う
・ワーカーを評価する
ワーカー(受注者)側の受注の流れ
・クラウドソーシングサイトを選び、利用登録をする
・職歴や実績などのプロフィール、受注したい業務の詳細を掲載する
・クライアントが掲載している募集内容、予算を検討する
・業務を選び、契約する
・業務途中の修正依頼、修正作業を行う
・クライアントへ納品、検収してもらう
・納品が完了したら報酬を支払ってもらう
・クライアントを評価する
クライアント(発注者)側のメリットとデメリット
クライアント(発注者)が、クラウドソーシングを通じて業務を委託するメリットとデメリットを紹介します。コスト削減や幅広い人材活用ができる一方で、余分な手間がかかる可能性やトラブルの危険性も秘めています。
※図表入る
発注者側が利用するメリット
1.必要なときのみ利用できる
2.従業員を抱える費用や人材育成コストが抑制、削減できる
3.自社にない専門スキルを利用できる
4.柔軟かつスリムな組織運営が実現できる
5.海外人材や地方人材も活用できる
6.ワーカーの評価制度により客観的な採用が可能
発注者側が利用するデメリット
1.社内人材の成長機会が損なわれる
2.細かな仕様設定や進捗管理が必要となり、余計な工数がかかる可能性がある
3.情報漏えいのリスクがある
4.知的財産権トラブルの危険性がある
5.スキルやコミュニケーション面における、ワーカーのミスマッチが起こる可能性がある
ワーカー(受注者)側のメリットとデメリット
ワーカー(受注者)にとって、クラウドソーシングを利用して仕事を得るメリット・デメリットは以下のとおりです。時間や場所にとらわれず、自分のスキルを生かして報酬を得られる点は大きなメリットですが、クライアントとの信頼関係構築、収入の安定には時間がかかります。信用できるクライアントかどうかを見極める目も重要です。
受注者側が利用するメリット
1.ライフスタイルに合わせた仕事ができる
2.副業がしやすくなる
3.本業以外でのスキルアップ、経験値の蓄積が可能になる
4.家事や育児、障害などで自宅から出られなくてもできる
5.隙間時間を有効に使える
6.仕事量や時間を選べる
受注者側が利用するデメリット
1.収入が安定しづらい
2.外部の信頼を得にくい
3.知的財産権トラブルの危険性がある
4.クライアントの信頼性における担保がない
5.安価な仕事が多い
6.スキルや要望とマッチした仕事があるとは限らない
クラウドソーシング導入のポイント
企業がクライアントとしてクラウドソーシングを導入する場合のポイントを解説します。特筆すべきは、2023年10月1日からスタートするインボイス制度です。取引先がインボイス(適格請求書)を発行しない場合、企業は消費税の仕入額控除を受けられなくなります。クラウドワーカーには課税売上1000万円以下の個人の免税事業者が多いため、適格請求書発行事業者になる予定があるか確かめておくとよいでしょう。継続的に取引したい免税事業者がいる場合は、課税事業者と分けて管理する必要も出てきます。
適切な発注方法を選ぶ
依頼したい業務が「プロジェクト形式」「コンペ形式」「タスク形式」のうち、どの形式での発注が適しているか検討します。それぞれの発注形式でメリット・デメリットが異なるため、適切な発注方法の選択はワーカーや成果物の品質に直結します。
ワーカーと機密保持契約を結ぶ
ワーカーが個人であることも多いクラウドソーシング。情報漏えいリスクについては念入りに注意したいものです。紙媒体のコピーや記録デバイスの持ち出し、紛失をはじめ、依頼内容に関する機密情報を口外してしまう、SNSの個人アカウントからの情報漏えいなど、情報管理トラブルの例は枚挙にいとまがありません。機密保持契約(NDA)を結び、情報の取り扱いについて確認と同意を得たうえで業務の依頼を進めるようにしましょう。
成果物に対するチェック体制を構築する
クラウドソーシングの最大の特徴は、不特定多数の人と気軽に広くつながれる点です。専門性の高い仕事を適任者に任せたり、質の高いアイデアを効率的に収集できたりとメリットが大きい反面、ワーカーのスキルや経験値には大きく差があり、一般的な採用フローのようにじっくり調べられないことも事実です。
成果物や納品物の品質がまちまちだったり、盗作や著作権侵害の危険性があったり、さまざまなトラブルも予想されます。品質に関する評価基準を明確にする、著作権に関する取り決め、チェックルールを構築するなど、クラウドソーシング導入前に社内でのチェック体制や項目をつくっておきましょう。
適格請求書発行事業者登録の有無を確認
2023年10月に始まるインボイス制度は、インボイス(適格請求書)がないと仕入税額控除が受けられなくなる制度です。これまでは確定申告の際に無条件で仕入税額控除を受けることができましたが、インボイス制度導入後に今までどおり確定申告をした場合、本来の税率より消費税を多く納める必要があります。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみなので、免税事業者がワーカーの多数を占めるクラウドソーシングでは注意しなければなりません。契約前に適格請求書発行事業者登録がされているか、または今後対応する予定があるかを確認しておくことが大切です。
クラウドシーシングの発注で失敗しないポイント
クライアントがクラウドソーシングの発注で押さえるべきポイントを解説します。気軽に受発注できる分、ワーカーのスキルや人柄のチェック、仕事内容の確認は基本的に自己責任と捉えて臨むことが大切です。トラブルの可能性は前もって摘み取る工夫も必要になります。
※図表入る
1.クラウドワーカーのスキルを確かめる
ワーカーのスキルチェックは基本中の基本です。プロフィールを読み込み、ポートフォリオや個人サイト、ブログなどがあれば確認しましょう。近年はSNSで情報発信しているワーカーも多いので、アカウントの記載があれば、どのような発信がされているのかを見るのもおすすめです。多少なりとも人となりが垣間見られる貴重な資料となります。
2.金額で決めない
安価な見積もりは魅力的ですが、その裏には実績や経験が乏しいケースも多いので注意が必要です。ワーカーの提示金額はあくまで見積もりで、契約締結前であれば交渉余地があるため、掲載された提示金額だけで決めずに、ヒアリングや相談を重ねることがワーカーや成果物とのマッチング精度を上げるコツです。
3.サポートを重視する
個人商店の集まりともいえるクラウドソーシングでは、サポートの手厚さに関しても千差万別です。納品後の相談やサポートが皆無だと、何かトラブルがあったときに困ります。特にアプリ開発やサイト制作、システム構築などは、納品後の運用が重要です。運用保守サポートの有無や費用なども確認しておきましょう。
4.スケジュールを確認する
希望納期に合わせて対応可能なワーカーを選ぶことも重要です。特に急ぎの業務に関しては事前のやりとりで合意をとることが大切です。また、ワーカーが提示してきた納期が守られるかどうかに保証はありません。過去の評価を参考にするほか、こまめな進捗確認、バッファをもった期限設定、要件定義を念入りにして手戻りを防ぐなど、できる限りの工夫を凝らすべきです。
5.契約内容を確認する
クラウドソーシングでは正式に契約書を交わす機会が少ないため、業務内容や注意事項、責任範囲など、あらゆるリスクを想定して契約しましょう。機密保持契約(NDA)や独自の契約書など、必要に応じて追加対応をすることが重要です。ワーカーと個別に契約書を交わす際にはクラウドソーシングサイトの規約を守って行いましょう。
クラウドソーシングの受注で失敗しないポイント
ワーカーがクラウドソーシングで仕事を受注する際に確認すべきポイントを解説します。目の前の案件を獲得したいがために見過ごしてしまう点も、トラブル回避、将来につながる可能性を考えて判断したいものです。
1.単価と仕事内容を見極める
業務にかかる時間と報酬が適正かどうかは非常に重要な判断基準です。クラウドソーシングの報酬体系は、稼働時間分だけ報酬が得られる時間単価制と、成果物に対して一定報酬が支払われる固定報酬制に分かれます。固定報酬制の場合、一見すると高単価の案件も、詳細をよく読んで実際の作業をシミュレーションしてみると割に合わないことが多々あります。未経験だったり、経験が浅かったりして判断に迷う場合には、まず少量から始めて、だいたいの工数を測ってみるとよいでしょう。
2.「よいクライアント」を選ぶ目を養う
クラウドワーカーにさまざまなレベルの人がいるように、クライアントの発注者としてのスキルや経験もまちまちです。中には良識の欠けたクライアントも、残念ながら存在します。
・クラウドソーシングサイトを通さず、直接取引を持ちかける
・仮入金前なのに作業を要求してくる
・外部サイトへの登録、有料資料や情報商材購入を促す
・契約内容とは異なる作業を過剰に追加してくる
・ワーカーからの評価が低い
など、ワーカーの労働力を搾取しようとしたり、規約違反をして一方的に取引をもちかけたりする傾向があります。発注者としての経験が乏しく配慮が行き届かない場合や、サービスに不慣れなために誤解しているケースもありますが、契約締結は慎重に行い、少しでも不安があればサイトのサポート窓口に相談しましょう。
3.自分にとって都合の悪いことも誠実に伝える
自分のペースを守りながらの仕事が、質の高い成果物を継続して提供できることにつながります。育児や介護、障害、病気といった事情は前もってクライアントに伝えておきましょう。良識のあるクライアントであれば、無理強いはしてこないはず。長く良好なつき合いができる関係を築くためにも、特別な配慮が必要と思われる事情は共有すべきです。
4.報酬額より「スキル」を生かせる仕事を選ぶ
報酬にばかり目がいってしまうと、自分のスキルと案件にミスマッチが生まれる可能性があります。スキルが生かせる仕事であれば、スピーディーに質が高い成果物を提供でき、スキルアップにもつながります。
しかしスキルと見合わない場合、時間がかかるだけでなく、品質にも不安が残るかもしれません。いくら報酬が高額でも時間単価は低かったり、よい評価が得られなかったりしては本末転倒です。今後スキルを伸ばしたい、経験を積みたいなど、将来に向けた投資にあたる仕事を選ぶことが大切です。
5.契約前に疑問点は残さない
仕事の条件や内容に関して疑問や不明点がある場合、契約前に必ず確認することが重要です。どんな作業をどの手順で行うのか、評価基準はどうなっているのか、修正作業はあるのかなど、仕事内容を十分に理解してから契約に進みましょう。
まとめ
これまでビジネスチャンスが都心部に集まっていたことから、地方在住者は仕事の獲得面で不利とされてきました。また、企業に雇用され、決まった時間と場所に縛られるワークスタイルや、介護や育児、自身の病気など、さまざまな事情により難しい人も多数います。
しかしクラウドソーシングを活用すれば、場所や時間の制約を取り払って働くことが可能です。自分の専門性を生かして仕事ができるため、受注することでさらなるスキルアップや市場価値の向上につなげられます。デメリットや注意すべきポイントを踏まえつつ、クラウドソーシングを上手に活用して、自分に合った働き方を探してみてはいかがでしょうか。
投稿 クラウドソーシングとは?活用するメリットや注意点を受注・発注側から解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 エンゲージメントとは?従業員の能力を最大化するために知っておきたいポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>従来は、労働環境や条件といった明確なメリットを提示することで従業員を動かすのが一般的でしたが、それだけは精神的な満足が得られず、貢献が長続きしないケースがあります。そんな中、近年になり重視されはじめたのが、「従業員のエンゲージメントを高める」という考え方です。この記事では、エンゲージメントの定義や、場面によって異なる使われ方について説明します。
エンゲージメントとは?
エンゲージメントの定義
エンゲージメント(engagement)は、「契約」「約束」「婚約」などを意味します。企業の人事分野では「従業員が企業に対して抱くつながりの気持ち」として定義されています。また、マーケティング分野においては、「顧客が企業に対して抱いている愛着・つながり」という意味もあります。単に「エンゲージメント」といった場合はどちらを指しているのかわからないため、前者を「従業員エンゲージメント」、後者を「顧客エンゲージメント」と区別するのが一般的です。
従業員エンゲージメントとは?
従業員エンゲージメントは、企業と従業員の間で構築される信頼関係といった意味で使われる言葉です。従業員エンゲージメントが高いほど、企業への貢献が期待できます。
混同されやすいのが「従業員満足度」という言葉です。どちらも従業員が企業に対してどれだけポジティブな感情を抱いているかを示しています。異なるのは、フォーカスしている対象です。従業員満足度は環境・人間関係にフォーカスしているに対し、従業員エンゲージメントは理念・ビジョンにフォーカスしています。
顧客エンゲージメントとは?
顧客エンゲージメントとは、企業と顧客との親密な関係性を指す言葉です。顧客エンゲージメントが高まった状態においては、顧客によるサービス・商材の継続的な利用・購入が期待できます。顧客が事業に協力してくれる状態となるため、前向きなフィードバックなど企業が成長していくために必要な情報が得られることも少なくありません。
従業員エンゲージメントの重要性
従業員エンゲージメントと顧客エンゲージメントのうち、特に近年になり注目されているのが従業員エンゲージメントです。以下では、多くの企業が従業員エンゲージメントを重要視するようになった理由を解説します。
利益の増加が期待できる
従業員エンゲージメントを高めると、利益の増加が期待できます。これは、従業員1人ひとりが貢献意識をもち、営業利益や労働生産性を高めようとするためです。企業に愛着を抱き、能動的にモチベーションを高めている状態では、従業員が「企業に貢献しよう」という明確な意志をもちます。そのため、企業が利益を獲得するうえでは、従業員エンゲージメントを高めることが重要だと考えられています。
離職を抑制できる
企業にとって大きな問題となる離職を防止できる点も、従業員エンゲージメントが重要視される理由の1つです。企業と従業員の間に信頼関係が築かれると、その企業から離れたいと思う従業員は少なくなります。労働力を維持できるだけではなく、人材の流出や採用コストの削減にもつながるでしょう。環境や条件を整えて従業員をつなぎとめるだけではなく、従業員エンゲージメントを高めて離職を防ぐ方向に多くの企業がシフトしています。
従業員の主体性が向上する
従業員エンゲージメントの高まりによって、従業員が高い主体性をもった状態で仕事に取り組むようになります。これは、従業員が仕事を「自分ゴト化」し、それぞれが自分の考えや決断をもとに仕事をするようになるためです。企業が従業員の主体性を認めるようになると、個々人の思いや個性を重視する、多様性を受け入れる企業風土が形成されるでしょう。
顧客満足度の向上が期待できる
従業員エンゲージメントは、顧客の満足度にも間接的に好影響を与えます。これは、企業への貢献の1つとして、従業員が「お客さまを喜ばせたい・満足させたい」と思うようになるためです。顧客満足度の向上が従業員のモチベーションアップにつながれば、理想的なサイクルが生まれます。そのため、従業員エンゲージメントの向上は、同時に顧客エンゲージメントを高める取り組みであるといえるでしょう。
企業の従業員エンゲージメントを高めるためには?
従業員エンゲージメントは、自然と高まっていくものではありません。以下のような、向上のための取り組みが必要です。
「エンゲージメントが高い状態」を具体的に設定する
まずは「従業員エンゲージメントが高い状態」を曖昧にせず、具体的に設定する必要があります。その状態は、他社と比較したり同じにしたりする必要はありません。自社にとっての「エンゲージメントが高い状態」をイメージし、評価の基準として設定することが大切です。
その後の施策は、目的として設定した状態をめざして打ち出していきます。重要なのは、環境や条件だけではなく、「仕事そのもの」に満足感を覚えている状態を目標として設定することです。
エンゲージメント向上につながる取り組み
続いて、設定した状態を実現するために具体的な取り組みを開始します。必要な取り組みは企業によって異なりますが、以下のようなものが代表例です。
明確なビジョンの共有
「会社と同じビジョンをもっている」という認識は、従業員にとって貢献する理由になります。会社のビジョンが実現されることにより、自分の理想の働き方や人生に近づくためです。単にキーワードやスローガンを覚えさせるだけではなく明確な経営ビジョンを共有し、その実現のためどのように働いてほしいのか伝えると、積極的な貢献が期待できます。
ワーク・ライフ・バランスの良好な環境構築
ワークライフバランスの良好なバランスを保てる環境構築も重要です。どちらかといえば、従業員満足向上のための取り組みですが、従業員エンゲージメント向上をめざすうえでも無関係ではありません。リモートワークやフレックス制の導入などが代表的な取り組みです。私生活を楽しみ、不安がない状態で仕事に打ち込めるようになるほか、「この会社は自分たちのことを考えてくれている」という印象を与えられます。
・関連記事
コミュニケーションの活性化
活発なコミュニケーションを促進することも、従業員エンゲージメントの向上につながります。十分なコミュニケーションがとれている組織内では、従業員のストレスが軽減されます。従業員間のつながりが強化されるため、離職率の低下につながる点もメリットです。テレワークが普及している現在では、従業員同士が対面する機会が以前よりも少なくなっています。そのため、チャットなどのツールを柔軟に活用することが大切です。
成長できる機会の提供
従業員には、ビジネスパーソンとして成長できる機会を積極的に与えましょう。成長を実感することで従業員はモチベーションを高め、社内でのキャリアプランを見出せるようになります。従業員のスキルに対して難しい仕事や、専門外の仕事を積極的に与えるのもよいでしょう。その仕事を経て成長した従業員の中には、スキルや知識だけではなく、喜びやさらなる成長への意欲が芽生えているはずです。
現状のエンゲージメントを把握するためには?
従業員エンゲージメントを高い状態にするために、闇雲に取り組みを行うことはおすすめできません。課題を明確にするためには、まず現状のエンゲージメントを把握することが重要です。エンゲージメントは可視化できない部分もありますが、以下のような手法を用いるとその後の取り組みを考えるうえで役立つデータが得られます。
eNPSでエンゲージメントを数値化
eNPS(Employee Net Promoter Score)とは、「自社を友人や知人にどの程度おすすめしたいか?」という調査の結果から、従業員エンゲージメントを数値化する手法です。もともとは顧客に対して行われていた調査が従業員を対象として行われるようになったといわれています。
調査では、対象となる従業員に「自社や現在の職場をどの程度おすすめしたいか?」という質問をして、0~10までの推奨度を回答してもらいます。0~6は「批判者」、7~8は「中立者」、9~10は「推奨者」として回答者を分類します。その後、全体に対する推奨者の割合から批判者の割合を引き、eNPSのスコアを算出します。スコアが高いほど、従業員エンゲージメントが高いことを意味します。
一般的な従業員満足度の調査では「自社に対して満足しているか?」という質問をします。一方、eNPSの場合は自分ではなく、身近な人を想定しているのが特徴です。より慎重に考えて回答するようになるため、信頼できる結果が期待できます。
エンゲージメントサーベイ
エンゲージメントサーベイは、現状の従業員エンゲージメントを把握するための社内調査です。多くの場合は、アンケート形式で実施されます。
質問の内容は企業によって異なりますが、以下のような項目が一般的です。
・会社から何を期待されているか理解していますか?
・直近の1週間で仕事を褒められたことがありますか?
・業務における成長を応援・サポートしてくれる人が社内にいますか?
・組織内で、周りから必要とされている実感がありますか?
組織サーベイツール
組織サーベイツールとは、従業員への質問や回答の収集のために利用されるツールです。従業員エンゲージメントのほか、従業員満足度、ストレスレベルなどさまざまな調査に活用できます。
システム上に回答が集約されるため、結果の集計・確認作業が効率的になります。スマホからの調査も可能なため、従業員にとっても気軽に参加しやすいツールです。
組織サーベイツールの活用事例
組織サーベイツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
公平に納得感のいく評価が行われるようになりました
「目標管理や評価などのデータはすべてクラウドで管理されているので働く場所を選ばないです。そして、蓄積されたデータは自動分析されるので人事担当者の工数がかなり削減することができるとともに、社長や上長の主観での評価が決まることなく公平に納得感のいく評価が行われるようになりました」
https://www.itreview.jp/products/hrbrain/reviews/64946
▼利用サービス:HRBrain
▼企業名:山崎石材工業株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:その他製造業
会社により大きな利益やメリットになるかを考えることができる。
「個人の目標や想いを、定量的にも定性的にも書くことができ、保存・上長などと共有が出来ること。また、会社が何を求めているかなども、記入出来るのも良いポイントである。上司や会社が何を求めているかを知ることで、どのようなことをすれば会社により大きな利益やメリットになるかを考えることができる。また、個人が自分の目標を記録できるのは、振り返りの際に、個人と会社どちらにとっても、メリットがある」
https://www.itreview.jp/products/hrbrain/reviews/24741
▼利用サービス:HRBrain
▼企業名:株式会社ネクストビート ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
信頼関係構築のために役立っています
「チームとしてセグメントした際に、そのチームの課題を検討する為に必要なチーム状態を抽出できます。ハイジーンファクターが数値として顕在化されるので、結果を用いて課題や解決策をブレストするなどの使い方をしています。ただ、今は課題を解決するフェーズではなく、回答率を90%以上にする為に行動を起こしています。この行動も、信頼関係構築の為に役立っています」
https://www.itreview.jp/products/hygi/reviews/58640
▼利用サービス:ハタラクカルテ
▼企業名:株式会社グッド・クルー ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:人材
感謝を伝え合う文化が育まれ、仕事が円滑に
「出社が前提だった当社が急遽リモートワーク比率8割となり、コミュニケーション不足を口にする社員がたくさん居ました。THANKS GIFTを導入したことで、ちょっとしたことでも感謝を伝え合う文化が育まれ、仕事が円滑に回るようになりました。感謝すると気持ちイイ、感謝されると嬉しい。ありがとうを伝える基準が下がり、感謝が身近になりました。副次効果として相手の良いところに目が行くようになり、コミュニケーションの質が格段に高まったと感じています。獲得ランキング、贈呈ランキングがリアルタイムで可視化されるため、コインを贈り合う後押し効果として機能しています」
https://www.itreview.jp/products/thanks-gift/reviews/88102
▼利用サービス:THANKS GIFT
▼企業名:株式会社セミナーインフォ ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:その他サービス
組織サーベイツールの業界マップ
組織サーベイツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
組織サーベイツールのおすすめ5選
実際に組織サーベイツールを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのツールを紹介します。
(2021年12月12日時点のレビューが多い順に紹介しています)
HRBrain
「HRBrain」は、シンプルなUI設計でシステムの操作に慣れていないユーザーでも簡単に使える人材管理ツールです。集計機能が自動化されており、効率的に従業員エンゲージメントの調査結果を集計できます。余分なオプション費用やサポート費用が発生しないシンプルな料金体系も高く評価されています。
ハタラクカルテ
「ハタラクカルテ」は、組織が抱えている課題の見える化に重きを置いて設計されたサービスです。離職率の低い組織づくりをサポートします。アンケートは従業員にとって負担が少ないように配慮されているため、積極的な参加が期待できます。組織全体と個人の回答結果をどちらも詳細に分析できるため、組織全体としての課題だけでなく、従業員1人ひとりが抱えている問題にもアプローチ可能です。
wevox
「wevox」は、エンゲージメントの可視化に特化したツールです。質問作成の自動化、多角的な分析、注目すべき調査結果の検出など、現場での使いやすさに主眼を置いて開発されています。現状を把握できるだけではなく、オンライン学習などベンダー側でエンゲージメント向上のためのサポートを実施している点も特徴です。充実して内容ながら、月額300円(税抜)/1名とコストが低い点も評価されています。
Geppo
「Geppo」は、個人サーベイと組織サーベイの両方をカバーし、企業が抱える本質的な働き方の課題を見える化するツールです。「仕事満足度」「人間関係」「健康」という3ジャンルの質問から、従業員が抱えている顕在化していない本音を吸い上げます。従業員エンゲージメントの測定用にeNPSをベースといた設問が用意されています。
Attuned
「Attuned」は、社内のモチベーションを速やかに可視化することに特化したサービスです。55の質問の結果からモチベーションを測定し、AIが見やすくまとめられたエンゲージのデータを出力します。調査結果から個人レポートが即時発行されるほか、必要に応じて1on1ミーティングのアドバイスも得られます。
ITreviewではその他の組織サーベイツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
まとめ
従業員は会社にとってもっとも重要な資産です。個々のエンゲージメントを高めることは、企業としての大きな成長につながるでしょう。従業員の性格や企業との相性によって左右されるため、闇雲な取り組みでは従業員エンゲージメントを高めることは困難です。
現在は、多くの手法が確立されているほか、従業員エンゲージメントの見える化、従業員のモチベーション向上に役立つツールも数多くあります。それらをうまく活用して、企業として掲げるビジョンの実現のため、従業員が積極的に協力してくれる組織づくりをめざしましょう。
投稿 エンゲージメントとは?従業員の能力を最大化するために知っておきたいポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 KPIはなぜ必要?|KGIとの関係やOKRとの違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>KPIとは?
KPIとは「Key Performance Indicator」の略語で、「重要業績評価指標」を表します。読み方は「ケーピーアイ」です。KPIは、企業の目標や組織の目標が達成されるために、各業務においてどの程度のパフォーマンスを出せばよいのかを示す指標です。
たとえば営業部が掲げた目標を達成するために、訪問件数や受注件数などを数値で評価できるように、指標として設定するのがKPIです。目標達成にどの程度近づいているのかを客観的に把握することができるようになります。もしKPIが設定値に達していなければ、パフォーマンスが落ちているプロセスを見つけやすくなります。
あらゆる業務に使えるKPI
KPIというと、営業の訪問件数や目標受注件数、企業全体であれば財務指標などが思い出されるかもしれませんが、実際にはあらゆる業務やプロセスに利用できます。たとえば営業担当者の顧客訪問回数や受注件数などのほかに、研修の回数やクレーム件数などにも設定できます。あるいは製造現場であれば、在庫率や不良品の発生率などに設定できます。
組織や個人が行うあらゆる業務プロセスでKPIが設定されることで、会社や組織の目標に対する状況把握ができます。なんとなく進んでいるといった曖昧な状態ではなく、どのプロセスがどの程度達成できているのか、達成度が低いプロセスがどの工程なのかが明らかになります。
わかりやすくして形骸化を防ぐ
KPIはあらゆる業務プロセスに設定できます。しかし、複雑に設定したり目標との因果関係が希薄なままに数値設定したりすると、KPIはとりあえず設定しただけの指標になってしまい形骸化してしまいます。このような形骸化を防ぐためには、目標との因果関係が明白なプロセスに絞ってKPIを設定し、実行者が理解できる範囲に抑えます。
また、KPIは一度だけ設定すればよいというわけではありません。組織の目標の変化や戦略の変化に応じて、柔軟に変更していく必要があります。さらにKPIを変えるたびに、従業員の理解を深めるための教育プログラムが必要になります。
KPIを設定するメリット
KPIを設定することには多くのメリットがあります。
KGI達成までのプロセスが明確になる
KGIは「Key Goal Indicator」の略で、「重要目標達成指標」を表します。たとえば「自社の今期の売上を10億円にする」などがKGIです。このKGIの達成に必要な業務プロセスのパフォーマンスを可視化するのがKPIです。KPIの設定により、各業務プロセスの達成度がKGIの達成にどの程度貢献できているのかを確認することができます。
1.各人の目標が定まる
KGIだけでは大まかすぎて各人の行動の指針は明確にできません。そこで各業務のプロセスでどのような成果を出すべきかを示すKPIの設定が必要になります。何をどれだけ行うべきかが明らかになるので、組織全体のパフォーマンスが高まります。同時に、組織の成果が出なかった場合に何を改善すべきかが明確になり、PDCAサイクルを効率よく回すことができるようになります。
2.必要なアクションが明らかになる
組織が目標を成し遂げる際に各人が何をすべきかを明らかにするためにKPIを設定します。その結果、各人は努力の方向性で迷わなくなります。たとえば営業部の売上目標を成し遂げるために、1人当たりがめざす訪問数や成約率が明確になります。
3.評価基準が明確になる
評価基準を明確に統一するためにKPIを設定します。たとえば営業部員1人の月の売上が500万円と設定された場合、それが達成できたかできなかったかは金額という数値で明かになります。KPIとして月の訪問数や成約率を数値で設定していれば、目標が達成されなかった場合も、理由が訪問件数不足だったのか、あるいは訪問件数は達成していたが、成約率が低すぎたのかが明らかになります。このように、各人を評価する際の曖昧さが減り、客観性が高まり公平性が担保されます。
4.組織のモチベーションが高まる
KPIが定められると各人の目標を共有できるため、組織全体のモチベーションが高まります。たとえば業務プロセスにおいて課題が発生した場合でも、組織内の共通の課題として共有し、メンバー全員が自分ゴトとして解決に向かいます。このことで結束力が強まりモチベーションも高まります。
5.PDCAを回しやすくなる
目標達成のための業務が細分化され、行動した結果がKPIにより評価できるようになれば、改善点が明確になるためPDCAを回しやすくなります。その結果、各人のパフォーマンスが高まり、組織全体としてもより大きな成果を出すことができます。
KPIに関連する指標
KPIと混同されやすいKGIとKFSという指標について説明します。
KGIとは?
KGIは「Key Goal Indicator」の略で、「重要目標達成指標」を表します。特定の期間で達成すべき目標を数値化することを示します。たとえばある企業が、「今期は売上を大きく伸ばすぞ!」と目標を立てたとします。しかし、このような大まかな目標では、販売部門の目標が定まりません。
そこで具体的な指標として、「売上1兆円を達成するぞ!」と設定します。このようにKGIが設定されれば、販売部門は売上1兆円を実現するためには月間何件を受注すればよいのかがわかり、そのために何件訪問すればよいのかも決まってきます。これがKPIです。ほかにも、「利益率を○○%に改善する」というKGIが設定されれば、商品の販売数や仕入れの値引きを目標としたKPIが設定できます。
KFSとは?
KFSは「Key Factor for Success」の略語で、「重要成功要因」を表します。ビジネスが成功するためのカギとなる要因がKFSです。たとえば、あるサービスの売上目標を達成したい場合に、必要となる要因は集客数や価格設定だとすれば、それぞれがKFSとなります。そして、これらのKFSを指標化したものがKPIだといえます。
KPIとKGI、KFSはどのような関係にあるのか?
KPI(重要業績評価指標)、KGI(重要目標達成指標)、KFS(重要成功要因)がどのような関係にあるのか解説します。
KGIとKPIは何が違うのか
KGIは最終目標です。これに対してKPIは、KGIを実現するための中間目標です。たとえばKGIとして自社のECサイトの今月の売上を2000万円にした場合、月間のECサイトへのセッション数の目標値を決めたり、新たに販売を開始する新規商品の点数を決めたりすることがKPIです。
KGIとKFSは何が違うのか
目標を示すKGIを実現するための要因がKFSです。逆にいえば、KFSに取り組むことによってKGIが達成されます。KFSが不明確なままKGIをめざしても闇雲に努力することになり、組織や個々人のモチベーションが低下します。たとえば自社ECサイトで○月の売上を○○万円にするというKGIが設定された場合は、アクセスを伸ばすことがKFSの1つとなります。
KFSとKPIは何が違うのか
前項のように、ECサイトの売上目標額をKGIとしたときのKFSの1つが、ECサイトへのアクセス数だと分析できた場合、KPIは具体的に必要なアクセス数を示します。このKFSはさらに細分化できます。つまりアクセス数を延ばすために必要な月当たりのサイト更新回数や新商品の取り扱い頻度、広告の露出頻度などの見直しを行い、それぞれをKPIとして数値化します。
OKRとの違いとは?
OKRとは?
OKRは「Objectives and Key Results」の略で、「目標と成果指標」を示します。会社が定める目標と社員の目標を関連づける目標管理方法です。OKRではまず、会社の目標と、その目標を達成した際の成果を明確にします。そして、この目標を達成して成果を得るためには、チームや個人はどのような目標をめざして成果を出すべきか紐づけていきます。
たとえば、以下のようなOKRが考えられます。
| 企業の目標(Objectives) | 3年後に業界シェア○○%を獲得 |
| 企業の成果指標(Key Results) | 利益率○○%獲得リピート率○○%獲得 |
| チームの目標(Objectives) | 新規顧客○○%獲得リピート率○○%獲得 |
| チームの成果指標(Key Results) | 上半期に集客イベントを行う今月中にWeb広告のキーワード見直し |
| 個人の目標(Objectives) | 自社サイトのリニューアル |
| 個人の成果指標(Key Results) | SEO実施広告キーワード見直し |
OKRとKPIの違いとは
KPIが目標に対する現在の行動の状況を客観的に測定する指標であることに対し、OKRは目標を達成するプロセスを見える化して共有する仕組みだといえます。また、KPIでは実現可能な数値を設定するので100%達成することをめざしますが、OKRではプロセスを重視しますので、可能な限り近づくことをめざします。
たとえばダイエットにたとえるなら、半年後までに6キロ痩せることを目標にした場合、毎日ウォーキングと食事制限する方法を選ぶことがOKRで、「ウォーキングは1日に○○キロ歩き、食事は○○キロカロリー以内に」と定めるのがKPIです。
KPIを設定する手順
KPIをいきなり設定することはできません。まず、KGIを設定する必要があります。
以下、手順を紹介します。
1.KGIを設定する
KPIを設定するためには、先に企業や組織の最終目標であるKGIを定めます。KGIはただ高ければよいのではなく、現実的に達成できる数値で示します。たとえば売上であれば金額を明確にします。また、KGIはできるだけ社員やチームメンバーからの意見を募り、全員で納得できる数値を決めることで、各人が合理的に納得できるKPIを設定できるようになります。
2.KGIを分解してKFSを引き出す
KGIが定まったら、次にKGIをKFS(重要成功要因)に細分化します。たとえば自社のECサイトからの売上を上げることがKGIであれば、KFSは「サイトの見やすさ」や「SEO対策」「コンテンツの品質の高さ」「SNSとの連携」「効果的な広告出稿」などが考えられます。
3.KFSを選ぶ
プロセスを細分化してKFSを洗い出すことができたら、KFSを特定します。KFSを決める基準は、まずそのプロセスがコントロール可能かどうかです。次に、目標達成に対する影響の大きさです。この2つの基準によりKFSを特定します。
4.KFSからKPIを設定
KFSを選定したら、KPIを設定します。前述の「サイトの見やすさ」や「SEO対策」「コンテンツの品質の高さ」「SNSとの連携」「効果的な広告出稿」であれば、それぞれ「検索流入数」や「サイト内滞在時間」「SNSからの流入数」「広告からの流入数」となります。つまり、KFSの達成度を客観的に評価できる指標を数値で示すことになります。
KPIの設定例
KPIは各社ごとの業務プロセスを定量的に評価する指標です。そのため、業種ごとのKPIとしての数値が規格として用意されているわけではありません。しかし、業種ごとによく使われるKPIの例はありますので、以下に紹介します。
セールスのKPI例
セールス部門でもっとも困るのは、「今月の売上○○円の達成のためにがんばれ!」という激励です。これでは何をどのように「がんばれ」がよいのかわかりません。そこで、各部署でどういった役割でどこに力を入れるかを明確になるKPIを設定します。
たとえば、インサイドセールス部署であれば、リード創出のために「アポ数」や「商談化数」をKPIに設定すると有効でしょう。またフィールドセールスであれば、受注数を上げるために「案件化数」や「受注率」といったものがKPIに設定されます。
よく使われる例は以下のとおりです。
| 架電数 | アポ数 | 訪問数 | 新規リード獲得数 |
| 平均顧客単価 | 案件化数 | 受注数 | 受注率 |
システム開発のKPI例
システム開発において、品質保証のための「エラー件数」や「標準化率」や納期厳守を実現するために「進捗率」や「稼働率」がKPIの設定として有効です。
よく使われる例は以下のとおりです。
| エラー件数 | 標準化率 | 進捗率 |
| 稼働率 | 生産性 | テスト終了件数 |
製造業のKPI例
製造業では利益、生産性向上の基本をQuality(品質)、Cost(費用)、Delivery(納期)のQCDとしています。KPIは、原料費の管理や稼働効率、品質の維持、あるいは現場の安全性を確保するために有効です。
たとえば、費用を抑え、生産効率を高めるために「総合設備効率」や「時間稼働率」「稼働率」「不良率」をKPIとして設定することが有効です。
その他よく使われる例は以下のとおりです。
| 原材料歩留差異 | 収率差異 | 工数差異 | 設備稼働差異 | 設備稼働率 |
| 時間稼働率 | 総合設備効率 | ライン編成効率 | 稼働率 | 不良率 |
| 事故発生件数 | 度数率 | 製造リードタイム |
人材採用のKPI例
人材採用のKPIは、選考フローの効率化やミスマッチの防止などに有効です。
たとえば、採用者数を増やすために「母集団形成」から「応募人数」「面接突破率」「内定率」などをKPIとして設定します。
よく使われる例は以下のとおりです。
| 母集団形成 | 応募人数 | 面接設定率 | 一次面接人数 |
| 最終面接人数 | 説明会・インターンへの参加人数 | 書類選考数の通過率 | 内定率 |
| 内定承諾率 | 採用達成度 | 1人あたりの採用コスト | 職場定着率 |
購買のKPI例
購買におけるKPIは、品質の維持と原価低減、納期厳守に有効です。
たとえば、購入した資材の品質を高めるために「受入不良率」や「VOS(Voice of Supplier:取引先評価)」がKPIとして設定されます。
よく使われる例は以下のとおりです。
| 受入不良率 | 原価低減率 | CR(コストダウン)率 |
| 納期遵守率 | VOS(Voice of Supplier:取引先評価) |
KPIを設定するポイントとなるSMARTとは?
KPIを設定するコツとして、「SMART」を意識する方法があります。SMARTとは、以下の頭文字です。
それぞれを見ていきましょう。
Specific(明確な)
「Specific」は「明確な」を意味します。KPIは誰が見てもわかる指標になっていなければなりません。人により解釈が変わってしまうような曖昧な設定はKPIとはいえません。明確にすることで、KPIを見れば各業務における目標を達成できたかどうかが客観的に判断できます。
Measurable(測定可能な)
「Measurable」は「測定が可能なこと」を意味します。KPIは数値化できる業務プロセスに設定しなければ、達成度を客観的に判断できません。数値化できれば課題も発見しやすくPDCAを回しやすくなります。
Achievable(達成可能な)
「Achievable」は「達成可能なこと」を意味します。KPIを設定する際、「目標は高いほどよいだろう」と現実的ではない数値を設定してしまうと、従業員は「どうせ無理」と諦めてしまい、「あくまで理想だろう」と実際に達成する意欲が削がれてしまい、モチベーションが下がってしまいます。そのため、KPIを設定する際には、達成の可能性が高い数値を設定します。
Related(関連性)
「Related」は「関連性」を意味します。KGIと関連しないKPIを設定して達成しても、企業の目標達成に貢献することができません。場合によってはKPIの達成のための労力やコストが企業にとってマイナスに作用する可能性もあります。したがって、KPIは必ずKGIと関連させます。
Time-bound(期限を定めた)
「Time-bound」は「期限を定めた」を意味します。KPIを設定する際には、期限を設定しなければなりません。期限が決められていないと、業務は漫然と進められてしまいます。期限が決められることで、行動に具体性が生じます。
KPIを運営するコツ
KPIは一度設定してそれきりというものではありません。企業や組織の目標が達成されるためには、継続的なKPIの運営が必要です。
ここでは、KPIを運営するコツについて紹介します。
KPIはシンプルに
KPIを継続的に運営するためには、KPIの設定をシンプルにする必要があります。項目が多すぎたり測定方法が複雑すぎたりすると、KPIの運営に多くのリソースとコストを投入することになってしまいます。結果的に、いつのまにかKPIは単なるスローガンになってしまいます。KPIは重要な項目に絞り、シンプルな測定が可能な内容にしておきます。
評価を明確に
KPIを設定して測定できていたとしても、評価基準が定まっていなければ次の行動への指針となりません。KPIを企業の目標達成のための加速器として活用するためには、評価基準を明確にしておく必要があります。
定期的に見直す
KPIは固定されるべき指標ではありません。定期的に軌道修正を行う必要があります。日々の進捗度合いを評価し、KPIの設定を見直します。適切なKPIを設定することで、業務改善への効果を発揮できます。
KPI管理に役立つツール
各業種でKPI管理に役立つツールを紹介します。
SFA
営業向けにはSFAツールがKPI管理におすすめです。SFAは営業プロセスの自動化や、効率的に業務を遂行するための営業支援です。見込み顧客の獲得から訪問や商談・クロージングまでのフローを可視化することにより、アポイント獲得数や受注率などの営業プロセスを把握できます。これにより、課題の解決に役立てられます。
SFAの詳しい解説はこちらをご覧ください。
SFAとは?CRMとの違いや導入のメリット・おすすめツール5選
プロジェクト管理
プロジェクト管理ツールは、システム開発やWeb制作の現場で用いられているKPI管理ツールです。作業量・作業負荷の可視化、生産性の監視、リソースの最適化などの各種ツール群によって構成されています。
「プロジェクト管理」記事へのリンク追加(URL未定)
採用管理(ATS)ツール
採用の現場では、採用管理ツールがKPI管理で用いられています。採用管理システム(ATS)とは、企業が行う人材採用活動において、応募者の情報管理や採用スケジュールの進行管理など、人材採用に関する業務を一元管理できるシステムになります。
BIツール
さまざまな業種でKPI管理として活用できるのがBIツールです。BI(ビジネスインテリジェンス)とは、企業における各種業務データや市場データなどを収集し、分析・可視化を行うことでビジネスの現状や過去の傾向を把握する手法です。
BIツールの詳しい解説はこちらをご覧ください。
BI(ビジネス・インテリジェンス)とは? 導入のポイントからおすすめのBIツール5選
BI(ビジネスインテリジェンス)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧
まとめ
ビジネスに限らず、目標が達成されるためにはKPIは必須となる指標です。KPIは行動指針となるだけでなく、組織全体のモチベーションを高めることも期待できます。
本記事ではKPIの意味からほかの指標との違いと関連性、設定手順や運営上のコツまでを解説しました。自社のビジネスに合ったKPIを設定・運営することで、目標達成を実現してください。
投稿 KPIはなぜ必要?|KGIとの関係やOKRとの違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 クラウドサービスとは何か?定義から活用ポイントまでを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>クラウドサービスとは?定義や由来を解説
「クラウドサービス」の起源
「クラウド」という略語で知られるクラウドコンピューティングは、インターネット経由でサーバやデータベース、ストレージなどのコンピューティングサービスを利用できる仕組みのこと。大規模なインフラ構築やソフトウェア導入が不要な点が特徴です。この仕組みで提供されるサービスをクラウドサービス、クラウド上にデータを保存して利用することをクラウド化と呼びます。
クラウドコンピューティングの概念は、1997年に南カリフォルニア大学教授のラムナト・チェラッパにより提唱されました。しかし世界的に認知されるようになったのは、それから約10年後の2006年。当時GoogleのCEOだったエリック・シュミットがクラウドコンピューティングについて発言したことがきっかけで、一躍話題となったのです。
クラウドサービスでは、ソフトウェアの場所やデータ保管先はインターネット上の見えないところにあります。IT業界のエンジニアたちが、その状態をシステム構成図に表す際、雲(=クラウド)のマークを使う慣習があったため、「クラウド」と呼ぶようになったといわれています。
日常に浸透しているクラウドサービス
身近なクラウドサービスの例として、メールサービス、SNS、オンラインゲームなどが挙げられます。Googleが提供するGmailやヤフー株式会社が提供するYahoo!メールが、メールサービスの代表的なクラウドサービスです。アカウントとインターネットがあれば利用でき、パソコンやスマートフォンなどの端末にメールソフトをインストールする必要はありません。同じようにInstagramやTwitterなどのSNSも、インターネット経由で利用できるクラウドサービスの一種です。
ゲームの世界でもクラウドサービスが活用されています。オンラインゲームは、インターネット上のクラウドサーバにゲームソフトがあり、ゲームデータやメモリはクラウドサーバに保存されています。従来のような物理的なゲームソフトの購入や、端末へのゲームデータのダウンロードは不要です。
企業におけるクラウドサービス利用状況
多くの企業でクラウドサービスの活用が進んでおり、今後もビジネスの現場でさらに広く利用されると予測されます。
企業のクラウドサービス導入は増加傾向
総務省の令和2年版「情報通信白書」によると、2019年時点でクラウドサービスを全社導入している企業は36.1%、一部導入している企業は28.6%で、64.7%の企業がクラウドサービスを活用しています。割合は年々増加し、前年2018年の58.7%から6.0%増、調査を開始した2015年の44.6%からは20.1%増えています。ビジネスの現場でクラウドサービスの活用が進んでいることがわかるでしょう。今後も利用率の上昇傾向は続くと予測されます。
業種によるクラウドサービス利用格差
「クラウドファースト」「クラウドバイデフォルト」の考え方が広まっていることから、今後はより多くの業種でクラウドサービスの活用が期待されています。「クラウドファースト」は、組織がITシステムを導入・更新する際に、クラウドサービスの利用を基本とすべきという考え方です。政府の方針としても採用されており、組織体質がレガシーと呼ばれるような、新規システムの導入に慎重な傾向がある官公庁や金融業界でも、クラウド化の動きが見られます。
総務省の令和2年版「情報通信白書」の調査結果を産業別に見ると、クラウドサービスを利用していると答えた割合は、情報通信業(90.5%)で9割を超えています。金融・保険業(80.8%)、不動産業(80.6%)が8割程度で高い数値を示していますが、運輸業・郵便業(55.2%)、サービス業・その他(59.5%)、製造業(62.0%)は導入が進みきっていません。
一方で「クラウドサービスについてよくわからない」と答えた業種は、多い順に運輸業・郵便業(8.2%)、サービス業・その他(8.7%)、製造業(7.1%)で、クラウドサービス利用が進んでいない業種とリンクする形となりました。クラウドサービスの活用促進をするにあたり、知識やメリット・デメリットの理解は必須といえます。
※「比重調整後合計企業数」に対する「利用している」「クラウドサービスについてよくわからない」の割合を筆者が計算。小数点第2位を四捨五入
クラウドサービスの進化に伴う利用の増加
複数のクラウドサービスを組み合わせて使うマルチクラウドや、オンプレミス型とクラウドサービスを併用するハイブリッドクラウドなど、新しい導入方法や利用方法が生み出されています。それぞれの事情に応じた選択肢が増えているため、これまで導入をためらっていた企業がクラウドサービスを利用する可能性は高くなっています。さまざまなニーズに応えるサービスも続々と提供され、今後も企業規模や業種を問わず、企業のクラウドサービス利用は進んでいくでしょう。
クラウドサービスが普及した理由
クラウドサービスが普及した背景には、ITが発展して世界中の人がインターネットやデジタルツールに親しむようになったことや、ビジネスを取り巻く環境の変化があります。災害対策や、コロナ禍による社会変化も色濃く影響しています。
インターネット利用の世界的な広がり
クラウドサービスは、インターネット技術の発展、インターネット利用者の増加とともに普及。またスマートフォンなどにより、誰でも場所や時間に関係なくネットワークにつながることができるようになりました。近年ではIoT(Internet of Things)が急速に発達し、これまでインターネットとは無関係だった物理的なモノも、インターネットにつないでより便利に活用しようという動きがあります。ますます多様化するITサービスの中で、さまざまな種類のデジタル端末管理、大量のデータ収集や分析が必要とされています。ネットワーク経由で集約管理ができるクラウドサービスが普及した背景には、インターネットの普及とその活用があるのです。
利用者のITリテラシー向上
インターネットやデジタルデバイスの普及で、過去に比べるとパソコンやソフトウェアの操作に抵抗がある人が減ってきています。インターネットの恩恵を受けて育ってきた「デジタルネイティブ」と呼ばれる世代も増えており、当たり前にITツールを活用する時代になってきました。かつてないほど多くの情報を日常的に処理する必要性が、利用者がクラウドサービスを便利な仕組みとして受け入れ、普及を後押しする背景となったこともあるでしょう。
使い勝手のよさ・従量課金モデル
使い勝手のよさもクラウドサービスが普及した大きな理由の1つです。導入準備がほとんど要らず、複数人での同時作業や共有が実現。パソコンやスマートフォンなどの端末とインターネット環境があれば、誰でもどこからでも利用できる手軽さ、いつでも使える柔軟性が魅力です。メンテナンスや運用をクラウドサービス提供事業者が行うため手間がかからない点も、使い勝手のよさを高めています。
従量課金モデルを採用している点も特筆すべきでしょう。クラウドサービス特有の料金体系で、利用状況に応じて料金が変動するのが特徴です。必要なときに、必要な分だけの機能や容量を選ぶことが可能なので、高いコストパフォーマンスで利用できます。
ビジネス環境の変化
近年はビジネス環境の変化が激しくなっています。商品やサービスのコモディティ化のサイクルが加速し、企業は常に新しい価値提供を求められています。ビジネスのライフサイクルが短いため、ITシステムにもその速度に順応するスピードと柔軟性が必要とされているのです。クラウドサービスは導入スピードと拡張性に優れているだけでなく、状況に応じて機能や規模を一時的に縮小することも自在なので、ビジネス環境に合ったITシステムの採用を実現できます。
DX推進
DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の観点からもクラウドサービスの活用が注目されています。DX実現には、ビジネスの実務に詳しい業務部門と、最新技術に精通した情報システム部門の連携が重要です。クラウドサービスは両者のニーズを満たせることから、DX推進とともに普及してきた背景があります。
・導入スピード:競争優位性を保つ
・初期費用の低さ:低リスクで開始できる
・カスタマイズの柔軟性:必要なときに必要なだけ利用可能
・サポート体制:事業者によるメンテナンスなど、情報システム部門の運用負荷軽減
→DXの詳しい解説はこちらをご覧ください。
https://www.itreview.jp/blog/archives/8713
多様な働き方の広がり
クラウドサービスは、テレワークや在宅勤務など、多様な働き方を実現できます。インターネット環境が整っていれば、いつでもどこでも社内ネットワークにアクセス可能です。育児や介護など、さまざまな事情で出社が難しい人材、地方や国外在住の人材を活用することもできるようになります。
BCP対策
BCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)対策とは、企業のリスクマネジメントの一環です。企業が自然災害や人的災害などの緊急事態に見舞われた際、事業に関わる被害を最小限にとどめつつ、スムーズな復旧と事業存続ができる体制を、あらかじめ整えておくことを指します。クラウドサービスのデータサーバが保管されるデータセンターは、自然災害に強い立地や構造になっています。自社オフィスが損害を受けたとしてもデータセンターが災害を受けている可能性は低いため、スムーズな事業再開ができるのです。クラウドサービス提供事業者による定期的なバックアップも、自社の重要なデータを守る仕組みの1つです。
代表的なクラウドサービス
クラウドサービスには代表的なものに3種類の形態があります。
SaaS(サース:Software as a Service)
SaaSは、アプリケーションソフトをインターネット経由で提供するサービスです。ソフトウェアをクラウド化することで、より安全な場所にデータを保存できる、多様な端末からデータにアクセスできる、複数人でデータ編集や共有ができるなどの特徴があり、従来のパッケージ製品では難しかった点が解消されています。SaaSの代表例には、オンラインストレージ、インターネットブラウザで利用するメールサービスやオフィスソフトなどがあります。
PaaS(パース:Platform as a Service)
アプリケーションソフトを稼働するためのデータベースやプログラム実行環境をプラットフォームと呼びます。プラットフォームにはOSやハードウェアなどが含まれ、PaaSは、それらのプラットフォーム一式をインターネット経由で提供。エンジニアはプログラムだけを用意するだけでよく、スピーディかつ低コストでシステム開発できる点が特徴です。Google Apps EngineやMicrosoft Azureなどが代表的なサービスです。企業の開発環境として利用されるケースが目立ちます。
→PaaSの詳しい解説はこちらをご覧ください。
IaaS(イアース/アイアース:Infrastructure as a Service)
IaaSはシステム稼働に必要となるインフラ、つまり仮想サーバやハードディスク、ファイアウォールなどを、インターネット上のサービスとして提供します。自由度が増したPaaSの発展形として見られることが多く、OSの種類やハードウェアのスペックは開発者側で採用判断や自力の運用が必要です。自由な開発が可能になる一方で、求められる知識や技術のレベルは高くなります。代表例はGoogle Compute EngineやAmazon Elastic Compute Cloudなどです。
クラウドサービス2つの基本形態
クラウドサービスの提供形態には主に2種類があり、パブリッククラウドとプライベートクラウドに分かれます。
パブリッククラウド
パブリッククラウドは、クラウドサービスを不特定多数に向けてオープンに提供している形態です。利用者に関して、組織、個人を問わず、また業界や業種、所属なども不問です。利用したい人が利用申し込みと利用料の支払いをすれば、必要なときに必要な分だけ自由にクラウドサービスが利用できます。大がかりな設備や特別な準備が必要なく、容易に導入できる一方でカスタマイズ性は低く、機能や利用環境に制限があります。
プライベートクラウド
プライベートクラウドは、企業や組織が専用のクラウドサービスを構築して専有する形態。従来の社内システム同様に、利用目的や自社の状況に応じて独自のカスタマイズが可能です。パブリッククラウドと比べると自由度が高い反面、コストが高額になりがちで、開発に高度な知識や技術が必要となる点がネックでしょう。自社内に回線やサーバを用意してクラウド環境の開発をするオンプレミス型と、クラウドサービス提供事業者からパブリッククラウドの一部を自社専用に提供を受けて開発を進めるホステッド型に分かれます。
マルチクラウドとハイブリッドクラウド
クラウドサービスが普及するにつれ、使い方も多様化しています。複数のパブリッククラウドを利用するマルチクラウド、パブリッククラウドをオンプレミスのプライベートクラウドと組み合わせて使用するハイブリッドクラウドについて解説します。
マルチクラウド
マルチクラウドは、複数のクラウドサービスを組み合わせて最適な環境を実現する使い方です。それぞれのクラウドサービスの優れた点に着目して使い分けるため、作業効率や利便性の面でメリットが大きい使い方といえます。アクセスの分散ができるためデータ通信量の負荷を減らさせられるほか、データ保管先が複数あることで消失リスクも軽減。一方で、複数のクラウドサービスを契約することでコストがかさんだり、利用者が操作方法を覚える手間が増えたり、管理負担が増えたりといったデメリットが考えられます。
ハイブリッドクラウド
ハイブリッドクラウドは、パブリッククラウドとオンプレミス型のプライベートクラウドを組み合わせる使い方です。それぞれを独立して利用するのではなく、お互いのデータに接点をもたせて一元的に活用します。マルチクラウドのように複数のサービス特長を生かしながら、デメリットを補完し合える点がハイブリッドクラウドの最大の特徴です。たとえば、プライベートクラウドのセキュリティ面・カスタマイズ性の高さと、パブリッククラウドのコストパフォーマンス・利用の手軽さなど、両方のいいところ取りができます。
クラウドサービスのメリット・デメリット
クラウドサービスを利用することで、以下のようなメリットとデメリットが考えられます。
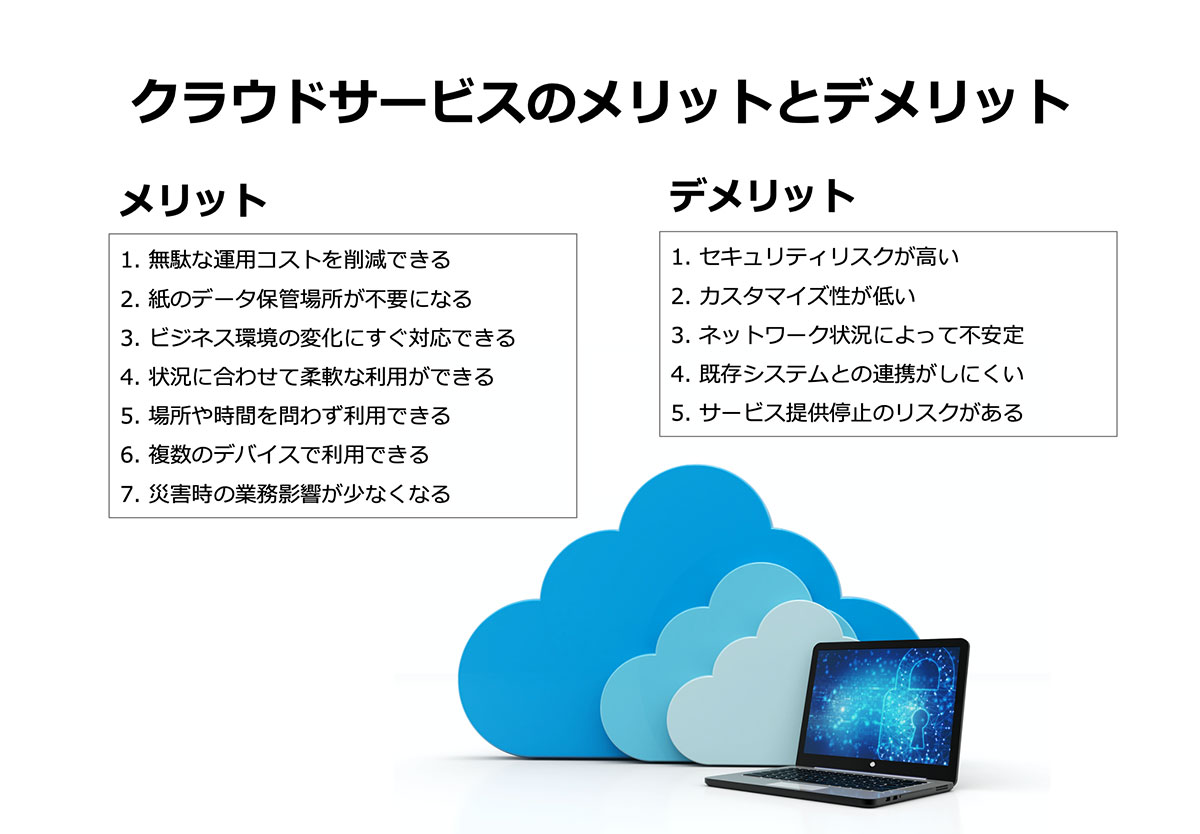
クラウドサービスのメリット
1.無駄な運用コストを削減できる
2.紙のデータ保管場所が不要になる
3.ビジネス環境の変化にすぐ対応できる
4.状況に合わせて柔軟な利用ができる
5.場所や時間を問わず利用できる
6.複数のデバイスで利用できる
7.災害時の業務影響が少なくなる
クラウドサービスのデメリット
1.セキュリティリスクが高い
2.カスタマイズ性が低い
3.ネットワーク状況によって不安定
4.既存システムとの連携がしにくい
5.サービス提供停止のリスクがある
分野別クラウドサービス
あらゆる分野でクラウドサービスが提供されており、種類も豊富です。自社の状況に適したサービスを導入するために、課題の現状把握や導入目的、サービスごとの特徴をしっかり比較検討しましょう。
コミュニケーション
・ビジネスチャット
→ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。
ビジネスチャットツールを徹底比較! ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選
・メールシステム
・オンライン会議
グループウェア
・グループウェア
→グループウェアの詳しい解説はこちらをご覧ください。
グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア比較、活用事例も紹介
・タスク管理・工数管理
→タスク管理の詳しい解説はこちらをご覧ください。
タスク管理で押さえるべき3つのポイント!おすすめのタスク管理ツール5選を紹介
・オンラインストレージ
セールス
・名刺管理ソフト
→名刺管理ソフトの詳しい解説はこちらをご覧ください。
名刺管理ソフトとは? 法人・個人でおすすめの名刺管理ソフトを紹介
・CRM(顧客管理システム)
→CRMの詳しい解説はこちらをご覧ください。
・SFA(営業管理システム)
→SFAの詳しい解説はこちらをご覧ください。
SFAとは?CRMとの違いや導入のメリット・おすすめツール5選
マーケティング
・MA(マーケティングオートメーション)
→MAの詳しい解説はこちらをご覧ください。
MA(マーケティングオートメーション)とは?おすすめMAツール7選まで完全網羅
・CMS(コンテンツマネジメントシステム)
→CMSの詳しい解説はこちらをご覧ください。
CMSとは?メリットや導入ポイント、活用事例、おすすめツール5選を紹介
・メール配信システム
バックオフィス
・労務管理
→労務管理の詳しい解説はこちらをご覧ください。
労務管理とは?これだけは知っておくべき基本機能とおすすめツール5選
・マイナンバー管理
・勤怠管理
→勤怠管理の詳しい解説はこちらをご覧ください。
勤怠管理システムのメリットや種類を詳しく解説&おすすめシステム5選を紹介
・会計ソフト
→会計ソフトの詳しい解説はこちらをご覧ください。
会計ソフトとは?初心者でも利用できる基本機能からおすすめ会計ソフト7選
ネットワークセキュリティ
・仮想デスクトップ(DaaS)
VDI・DaaS(仮想デスクトップ)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧
・WAF(Webアプリケーションファイアウォール)
人材活用
・人材管理
・採用管理
クラウドサービスの選び方
クラウドサービスを導入する場合、どのようにして自社に合うサービスを選べばよいか、検討ポイントを解説します。
ストレージのデータ容量
クラウドサービスの比較検討で欠かせないのが、ストレージのデータ容量です。テキストデータが多いのか、画像や動画を利用したいのか、業務によって扱うデータの種類が異なるため、事前に必要な容量を確認しておきましょう。1回あたりのアップロード最大容量に制限がある場合もあるので、業務で頻繁に使用するデータが十分に扱えるサービスを選ぶ必要があります。途中で容量を増やせるかも確認したい点です。
サポート体制
サポート体制が充実しているかも重要なポイントです。自社の従業員のITリテラシーのレベルに合わせたサポート体制を整える必要があります。特に海外サービスではマニュアルや問い合わせが英語対応のみのケースも。予期せぬエラーが起こったときの対応は24時間体制だとより安心でしょう。長期的な視点で自社に適した運用ができる環境を選ぶことが大切です。
・検討段階で事前ヒアリング、相談できるか
・導入やシステム構築について依頼できるか
・障害対応に関するレスポンス
・問い合わせ窓口の営業時間、対応方法、対応言語
機能性・拡張性
クラウドサービスによって機能性や拡張性も異なります。まずは対象業務に必要な機能が揃ったサービスであることが重要です。今後クラウド化する領域が広がったときに備えて、機能を追加できたり、アクセス権限設定や他社サービスとの連携ができたり、拡張性が高いことにも着目して比較しましょう。
利用可能なデバイス・操作性
パソコン(主Webブラウザ)とスマートフォンやタブレット(主にアプリ)両方に対応していると、業務効率がより高まります。テレワークや在宅勤務をはじめ、出張や外勤など社外からアクセスする際には、場所や端末の制限が少ないサービスが適しています。また、マニュアルを詳細に読まなくても基本操作がわかる、どこに何の機能があるかひと目でわかる、などの操作性にも注目してみましょう。操作が難しかったり画面がわかりにくかったりすると、社内で定着しにくいうえに、ミスやトラブルが起こりやすくなるかもしれません。
ランニングコスト
料金の安さだけにこだわってサービスを選ぶと、必要な機能が足りなかったり、サポート体制や拡張性に不安があったり、大事な点を見落とす可能性があります。場合によっては追加料金が高額で、トータルで高くなってしまう可能性も否めません。コストとパフォーマンスのバランスをしっかり見極めて、多面的・長期的に比較検討する必要があります。
セキュリティ
セキュリティ対策に関しては念入りに確認しましょう。クラウドサービスはインターネット上で重要情報を保管・送受信する仕組みです。個人情報や機密情報の漏えいを防ぐため、情報の暗号化、IPアドレス制限、アクセス認証など、強固なセキュリティが備わったサービスを選ぶことが重要でしょう。不正アクセスや疑わしいアクセスに対する監視体制がとれているか、国際基準に準じたセキュリティ内容かなどもチェックしたい項目です。
まとめ
急速なビジネス環境の変化に適応するため、クラウドサービスを活用する企業は今後も増えることは間違いありません。一方でクラウドサービスの具体的な活用イメージがわかない、導入メリットがわからないなど、活用に至っていないケースも散見されます。クラウドサービスの仕組みや身近な例に対する理解を深めることで、業務活用のイメージも明確になるでしょう。
投稿 クラウドサービスとは何か?定義から活用ポイントまでを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 コワーキングスペースとは? メリットやシェアオフィスとの違い、おすすめサービス5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>働く場所の選択肢を増やすことは、企業にとってはオフィスにかかる費用や通勤費が抑えられたり、従業員にとっては通勤にかける時間や労力を節約してプライベートな時間を確保できたり、仕事の生産性を高められたりと、多くのメリットが考えられます。ここでは、働く場所の選択肢として注目されるコワーキングスペースについて解説します。
コワーキングスペースとは?
コワーキングスペースとは、独立して働く個人が、会議室や作業スペース、デスク、ネットワーク設備といったオフィスの実務環境を共有して仕事できる空間のことです。起業家やフリーランサー、テレワークで働く人、ノマドワーカーなど、働く場所の制約がない人たちが利用しています。
一般的に6カ月未満の短期契約で借りることが多く、単なる作業空間の提供にとどまらず、異なる属性の利用者同士の交流、コミュニティ形成を通じた相乗効果やイノベーションをめざす傾向が強い点が特徴です。
コワーキングスペースの概念は、1995年ドイツのベルリンで誕生したハッカースペースの「C-base」が原型といわれています。「コワーキング」という用語は1999年にアメリカのゲームデザイナー、Bernard De Koven 氏が使い始めた造語。彼はニューヨークで自宅やカフェ以外の仕事場を求める個人などに向けて、コワーキングスペースを提供しました。当時は利用者同士の交流を目的としたイベント開催や仕組みなどはなく、コミュニティ形成に重点は置かれていませんでした。
2005年にソフトウェアエンジニアの Brad Neuberg 氏が、サンフランシスコに、現在の形のコワーキングスペースを開設。在宅勤務で生産性を上げられない人たちを対象に、仕事環境とコミュニティをセットで提供したのが、今のコワーキングスペースの始まりとされています。
2006年以降、コワーキングスペースはアメリカを中心に急拡大しており、日本でも、2010年以降のコワーキングスペース開設数は増加傾向にあります。
なぜ今、コワーキングスペースなのか?
コワーキングスペースが注目されている背景には、働き方の多様化や、大都市一極集中の回避、地方創生などが挙げられます。
インターネットの普及と働き方改革が進むにつれ、従業員の生産性や利便性向上の観点から、働く場所や時間の自由を認める企業が増えてきました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、半強制的にテレワーク導入が進んだり、オンラインで仕事の受発注ができるサービスが発達したりと、オフィスに出社しない働き方が広がりつつあります。
近年は大都市一極集中で生産性を高めてきた日本の構造が、大きな転換期を迎えています。東京や大阪のような大都市に人口や産業が集中しているため、天災などで被害を受けた場合に日本全体に与える影響が甚大な点、生活コストの高さが享受できるメリットを超えている点などが課題となっていました。このような現状のもと、改めて重要視されているのが地方活性化です。
日本では全国的なテレワーク推進のため、政府と自治体主導で「テレワーク・デイズ」と銘打ったキャンペーンを実施してきました。テレワークによる企業進出、滞在、移住推進などを通じて、地方在住の人材を最大限に活用した地方創生を進めています。テレワークを支えるコワーキングスペースに、特に期待が寄せられています。オフィス拠点のある大都市でなくても、効率を落とさずに働ける仕事場としてコワーキングスペースが求められています。
フレキシブルオフィス化するコワーキング、シェアオフィスなどとの違い
フレキシブルオフィスとは、従来の長期契約で1社ごとの占有スペースがあるオフィスとは異なり、コワーキングスペースやシェアオフィスのような、柔軟な利用形態で使用できるオフィスのことです。
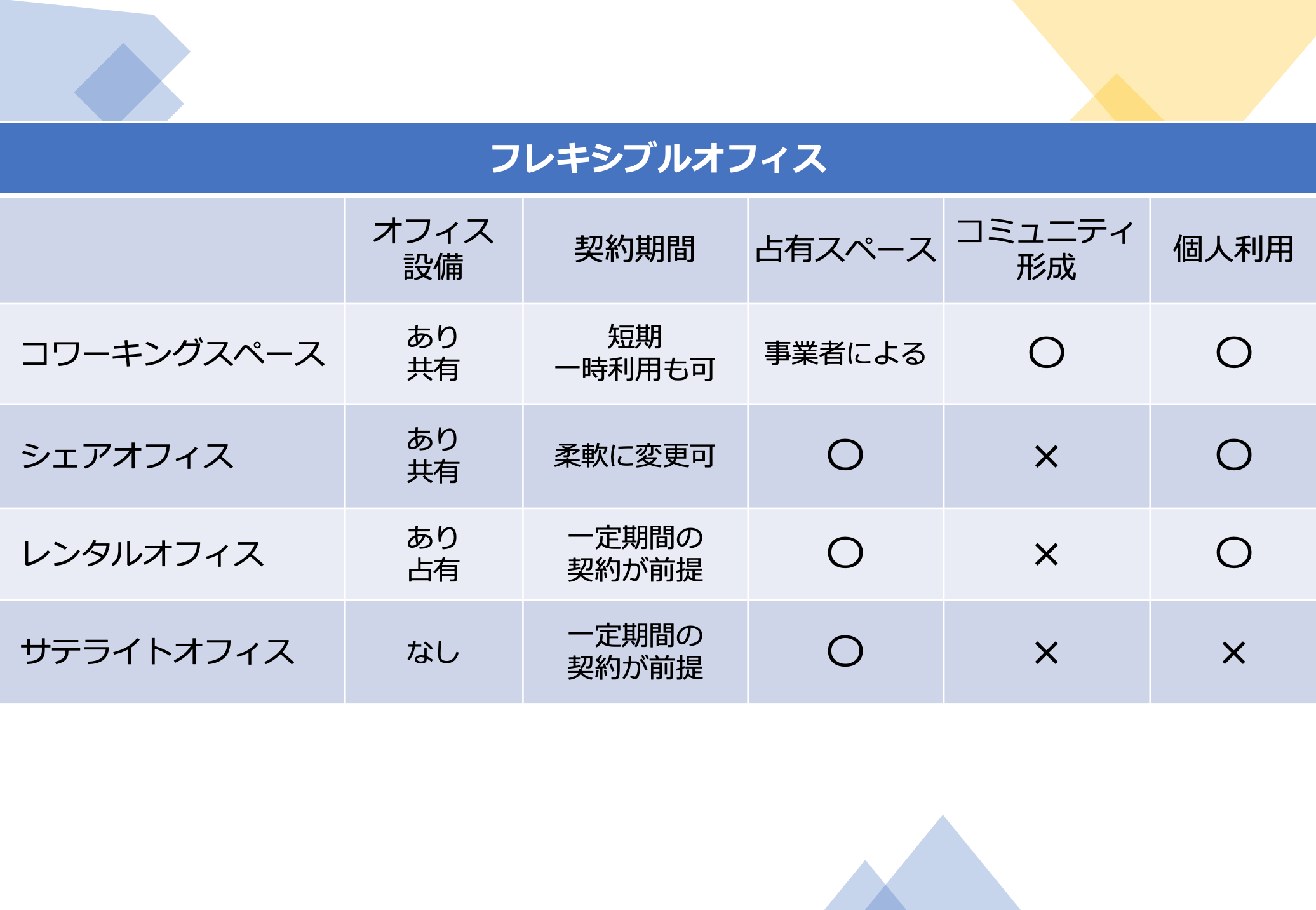
コワーキングスペース
複数の個人や企業などが共用する、仕事に必要な設備がそろったオープンなワークスペースです。一般的にはフリーアドレス式で、個々に固定の席をもたずに働きます。シェアオフィスやレンタルオフィスとの大きな違いは、よりコミュニティ色が強い点。イベントやワークショップを開催し、異業種の利用者同士の出会いや、新しいアイデアとインスピレーションが生まれる機会を提供するコワーキングスペースもあります。
シェアオフィス
コワーキングスペースと同様、複数の個人や企業で共有するオフィス機能をもつスペースです。コワーキングスペースの違いは、占有スペースがある点。企業の成長度合いに応じて柔軟に契約変更ができるのが特徴です。
レンタルオフィス
レンタルオフィスは個人や企業が賃借するオフィスです。一般的には占有スペースがあり、仕事をするために必要な設備も整っています。1つのフロアを複数社が間借りしてオフィスを構えるイメージです。
サテライトオフィス
サテライトオフィスは、企業が本社とは離れた場所に設置するオフィスのことです。支店ほど規模は大きくないのが特徴で、数人が働けるだけのスペースと通信環境が用意された小規模なものが一般的。企業に属さないフリーランスや個人は利用できません。
コワーキングスペースのメリットとデメリット
さまざまな社会背景から、コワーキングスペースの需要はますます増えていくと考えられます。コワーキングスペースの特性を理解して上手に活用しましょう。
| コワーキングスペース | シェアオフィス | レンタルオフィス | サテライトオフィス | |
| 主な特徴 | ●フリーランスやテレワーカー、ノマドワーカーなどの個人の利用が多い。 ●別の会社や異業種の人たちとの交流が盛ん。 |
●都市型が中心 ●フリーランスの方や副業で、自宅に仕事をする場所がないテレワーカーの利用が多い。 |
●都市型が中心 ●ベンチャーや中小企業でも都心の一等地にオフィスを構えることができる。 |
●地方・郊外型が中心。 ●大企業の支店や事業所として利用されることが多い。 |
| メリット | ●初期費用が安い ●新たなコミュニティができる ●設備が整っている ●イベントやセミナーに参加できる |
●すぐに導入できる ●基本的に保守が不要●初期費用・月額料金を抑えながら、作業場所を確保できる ●移動時間の短縮できる |
●すぐに導入できる ●基本的に保守が不要 ●個室がある ●一般の貸事務所より低費用で、専有スペースを確保できる ●仕事に必要な設備が揃っている |
●低コストで各所に支社や事業所を展開しやすい ●すぐに導入できる ●基本的に保守が不要 |
| デメリット | ●機密性が低い ●作業スペースが狭い場合がある ●情報漏洩のリスクがある |
●機密性が低い ●作業スペースが狭い場合がある ●情報漏洩のリスクがある |
●シェアオフィスやサテライトオフィスと比べると高価格 ●内装変更ができない |
●コミュニケーションの機会が減る |
コワーキングスペースのメリット
・初期費用やオフィスにかかる費用を抑えられる
賃貸オフィスに比べて、オフィス費用を大幅に削減できます。賃貸オフィスにかかる費用は、オフィス賃料、コピー機などのリース料、通信費、光熱費、備品費や維持管理費などが含まれます。契約期間は長期契約が前提になることが多い傾向です。コワーキングスペースは必要に応じて契約期間を選べるため、固定費が減らせます。
・新たなビジネスチャンスが生まれる可能性がある
異業種や他社の利用者がいるため、所属の枠を超えた人との交流で、新しい情報が得られたり、インスピレーションにつながったりする可能性があるでしょう。コワーキングスペースによっては、事業者が積極的に利用者同士を紹介してくれたり、交流イベントを企画していたりします。
・仕事に必要な設備が揃っている
電源やWi-Fiなどの基本的な設備や機能が揃っているので、契約すればすぐにオフィスと変わらない環境で仕事ができます。
・仕事に集中して長時間の作業ができる
作業スペースとして設計されているため、デスクや椅子のつくりや、隣席との仕切りなど、集中しやすい環境が整っています。何より、周囲の人が集中している空気感が集中力も高めてくれるでしょう。共有エリアでの会話を禁止しているところもあるので、自分に合った環境を選ぶことが大切です。
・打ち合わせや会議の場所を確保できる
多くのコワーキングスペースには、簡単な打ち合わせ用スペース、個室の会議室が設置されています。スムーズに全員分のスペースを確保したり、機密を守りながら話し合ったりが可能です。
・周りの目を気にせずに作業できる
必要な時間だけ好きに作業できるのがコワーキングスペースのメリット。カフェやファミリーレストランなどのように、店の人やほかの客からの視線を気にするストレスがありません。集中力と作業効率が上がる可能性も高いでしょう。
コワーキングスペースのデメリット
・周囲の音や会話が聞こえる
基本的にオープンスペースなので、周囲の会話や環境音が気になってしまう人は仕事に集中できないかもしれません。耳栓やイヤホンの利用など、自分が集中しやすい環境をつくる工夫が必要です。
・コワーキングスペースによって設備に差がある
大抵のコワーキングスペースは、パソコンでの作業を行うための最低限の設備はそろっています。デスク、椅子、Wi-Fi、給水機などが代表的。会議室、ホワイトボード、プリンターのほか、受付や郵便受けなど実際のオフィスと同じようなサービスを提供していたりすることもあります。飲食スペースやドリンク、休憩用ソファ、仮眠室など長時間滞在をサポートするサービスに力を入れている事業者もあるので、自分の使い方に合ったコワーキングスペースを選びましょう。
・作業スペースの確保が難しいこともある
コワーキングスペースはいつでも必要なスペースが確保できるとは限りません。予約が取れても混雑していたり、会議室や個別スペースが埋まっていたりすることもあります。
・作業スペースが狭いコワーキングスペースもある
コワーキングスペースによっては作業スペースが狭く、作業効率が落ちてしまう場合があります。広い作業スペースを確保したい方は、個々の割り当てスペースが広いコワーキングスペースを探すようにしましょう。定額や追加料金で固定席を選べるサービスもあります。
・情報漏えいのリスクがある
不特定多数の利用者がいるため、仕事に関する重要項目や機密情報を聞かれたり、見られたりする可能性があります。個室を確保する、資料やデバイスの管理を入念にするなど、細心の注意が必要です。
・必ずしもビジネスが生まれるわけではない
異業種の利用者との出会いや交流があることと、新しいビジネスが生まれることは別の問題です。人脈やチャンスが得られる可能性があるという認識にとどめ、あくまでサードプレイスの仕事場として利用しましょう。
・ある程度の積極性やコミュニケーション力が必要になる
空間や設備を共有している以上、ある程度の社交性は必要です。また、異業種交流やビジネスの種を見つけるチャンスが比較的多い環境ではあるものの、期待していたほどチャンスや交流がない場合もあります。チャンスを自分から作っていく積極性、チャンスを次につなげる努力も必要になるでしょう。
都市型と郊外型に集約されるコワーキングスペース
コワーキングスペースの多くは都市部に集中。起業数の多さ、多数あるビルの空きフロア対策、リモートワークの必要性など、さまざまな社会背景でニーズが年々高まっています。
地方都市でもコワーキングスペースは増加傾向にあるものの、事業として採算がとれない、都市ほど賃貸料が問題にならないなど、課題も多いのが現状です。ここではジャパンメジャーレポート – コワーキングオフィスと大都市政策研究機構が調査したレポートを元に 特にニーズが高い東京各地区の市場動向を紹介します。
大都市政策研究機構によると、コワーキングスペースの施設数が最も多いのは港区、千代田区、渋谷区、中央区の順です。国内大手から外資系、スタートアップまで多様な規模の企業、ITやFintechのようなビジネスの成長分野を扱う企業を抱える地域にコワーキングスペースの浸透が進んでいるといえます。区単体では都心3区に及ばないものの、新宿区や豊島区、世田谷区などの城西地区も多くの施設が見られます。
一方、ジャパンメジャーレポートの報告では地域ごとの坪数で見ており、全体坪数が多い順に、千代田区、港区、渋谷区と順位が入れ替わります。地域特性として、千代田区は高水準のサービスが付加された大型コワーキングスペースが目立ち、渋谷区は幅広い規模のコワーキングスペースが集まっているとしています。特徴的なのは城西地区で、保育施設を併設する事業者が多く、子育て世代が多い地域性が反映されています。ほとんどが50坪未満の小規模なコワーキングスペースで、地域密着型の小さな企業や個人が利用しているケースが多いようです。
コワーキングスペースの賢い利用方法
コワーキングスペースを企業が活用する場合の賢い利用方法や、メリットについて紹介します。社員の仕事環境に選択肢を増やすことは、生産性や効率性を高めるだけでなく、企業ブランドの向上にも貢献する可能性があります。

隙間時間を有効活用
外勤の営業など、移動が多い社員はデスクワークの効率が落ちやすく、その都度で拠点のオフィスに戻るのは時間の無駄になりかねません。カフェやファミリーレストランの利用も、探す手間はもちろんのこと、必ずしも座席が確保できない点、セキュリティ面で仕事に向かない環境である点など、さまざまな問題があります。ドロップイン利用ができる訪問先最寄りのコワーキングスペースを利用すれば、隙間時間を有効に使えるでしょう。1つのコワーキングスペースを拠点に、そのエリアを重点的に回っていくという効率的な使い方も可能です。
在宅勤務時の生産性を維持
コワーキングスペースのほとんどが、Wi-Fiや電源、プリンターなど、パソコン作業に必要な基本設備が整っています。それぞれの事業者が作業に集中できる空間づくりをめざしているので、自宅やカフェなどでは集中できない人におすすめの使い方です。
たとえば家族やペットの存在、作業スペースの狭さや通信環境など、自宅が仕事環境として整っていない場合の在宅勤務は大きなストレスになります。なにより、仕事の成果が出にくい状況は看過できません。自宅近くのコワーキングスペースを利用すれば、オフィスにいなくても充実した仕事環境を確保でき、生産性や効率性を維持しながらテレワークが可能です。自宅から離れることで、オン・オフの切り替えもスムーズにできるメリットもあります。
会議室として使う
コワーキングスペースは会議室として使うこともできます。カフェやファミリーレストランなどの手軽な場所で会議や打ち合わせを行うデメリットは、話に集中しづらい点と機密情報の取り扱いができない点です。
デメリット解消のためにレンタル会議室を借りる場合、手間やコストがかかるという難点があります。コワーキングスペースであればフリースペースを利用して打ち合わせができ、個室や会議室を設けている場合は機密性の高い内容を話すことも可能です。クライアントからの信用も増すでしょう。
イベント会場として使う
コワーキングスペースにイベントスペースやレンタルスペースがある場合、セミナーや展示会、交流会などのイベント会場として使うことができます。デザインやレイアウトによって、フォーマルな雰囲気からカジュアルな雰囲気まで、いろいろなイメージでイベント開催が可能です。
ビジネスマッチングの場として使う
コワーキングスペースは異なる経歴の持ち主が集まります。利用者同士の交流から価値ある情報を得られたり、新しいビジネスのアイデアが生まれたりするかもしれません。ビジネスの人脈を広げる目的で利用する場合は、イベントや交流会の開催、利用者同士のマッチングサービスなどに注目してコワーキングスペースを選びましょう。
災害時に通勤できない社員がテレワーク場所として利用
コワーキングスペースを活用すれば、自然災害などの場合にオフィス出社を切り替えて、自宅近くの安全な場所で仕事をしてもらうことが可能です。地震や災害、疫病の流行などによる混乱は予期せず起こります。緊急事態を想定し、リスク管理の一環としてコワーキングスペースを活用することで、企業活動への影響を最小限に抑えられるでしょう。
企業イメージ向上、ブランド力強化
2021年7月にパーソル総合研究所が2万人を対象にテレワークに関する調査を行い、テレワークを実施している人の78.6%が「今後も継続希望」という結果が出ました。1週間に1日以上のテレワーク実施を希望する人は、テレワーク経験者が78.8%、テレワーク未実施の人が33.0%と、テレワーク需要が非常に高いことが読みとれます。より自由な働き方を求める人が増えており、企業のコワーキングスペース利用は、採用競争率を向上させる可能性も大きいです。
「五輪開催中のテレワークの実態について、2万人規模の調査結果を発表」
コワーキングスペースを選ぶポイント
コワーキングスペースは、予算や利用目的に応じて選ぶことが重要です。気分や雰囲気だけで選んでしまうと、作業に必要な設備がない、居心地が悪いなど、ミスマッチが起きてしまう可能性があります。コワーキングスペースの特徴や設備を事前によく調べたり、見学に行ったりして、未然に選択ミスを防ぎましょう。
料金
予算との兼ね合いは非常に重要なポイントです。どんなに設備や立地が良くても、安定して使い続けられなければ意味がありません。また、コワーキングスペースの料金体系は、月額制とドロップインが一般的。月額制は1カ月定額で利用でき、営業時間内であれば何日でも利用できます。利用回数が少ないと割高になるため、コワーキングスペースを頻繁に使わない人には向いていません。
一方のドロップインは時間単位で利用するプランです。いろいろなコワーキングスペースを気軽に試すことができるほか、必要なときだけ使えるメリットがあります。月額制に比べると時間当たりの単価は高くなるので、お気に入りのコワーキングスペースを利用する機会が多い人にはあまりおすすめできません。
利用できる設備
オープンスペースに電源つきの座席があり、最低限の設備だけを揃えているコワーキングスペースもあれば、モニターやキーボード付きの座席、個室や会議室を備えているところもあります。飲食や休憩時の設備もさまざまで、自販機やコーヒーマシンのほか、仮眠室やマッサージチェアなどユニークな設備があるコワーキングスペースも。有人受付や郵便受けなど、賃貸オフィスと変わらないサービスを行っている事業者も見られます。自分が利用するシチュエーションや滞在時間などを踏まえて選ぶとよいでしょう。
立地
コワーキングスペースの使い方に合わせた立地も重要なポイント。多くのフリーランサーや自営業者、在宅勤務者は、交通費削減を目的として、自宅の最寄り駅にあるコワーキングスペースを利用するケースが一般的です。
しかし、クライアント先に出向いての打ち合わせや移動が多い人は、活動拠点やアクセスの利便性を考慮した立地を選ぶことが大切になります。クライアントを招いて打ち合わせをすることが多いなら、クライアント目線でわかりやすい立地かどうかチェックが必要です。
雰囲気・快適さ
利用者ごとに快適な環境は異なります。ある程度、周囲の会話が聞こえてきたほうがいい人もいれば、静かな環境でないと集中しづらい人もいます。内装についても、ポップでカジュアルな雰囲気で気分が乗る人、シンプルでモダンなデザインが落ち着く人、重厚で高級感があるほうがやる気が出る人などさまざま。実際にコワーキングスペースを利用してみないとわからない部分もあるので、まずはドロップインでの一時利用で試してみるとよいでしょう。
おすすめのコワーキングスペース5選
世界中に広がるコワーキングスペースですが、ここでは日本で利用できるおすすめのコワーキングスペースを5つ紹介します。多くの事業者が1つの空間の中に複数の形態を採用しており、従来の画一的なオフィスでは実現できなかった、さまざまな働き方がかないます。ぜひ自分のワークスタイルや価値観に合ったコワーキングスペースを見つけて、生産性高く働きましょう。
STATION DESK〜駅を拠点にした半個室型スペース〜
JR東日本が運営するコワーキングスペースです。駅の改札内や連絡通路に設置されており、多くが半個室型。普通の椅子以外に、ソファ席やスタンディング席などを導入している場所もあり、さまざまなスタイルで働けます。電話をする場合には専用のフォンブースで行い、共有スペースでの会話は基本的いできません。静かな環境で集中したい人、移動の合間や電車待ちの時間を有効活用したい人におすすめです。
WeWork〜コワーキングスペースを世界に広げた先駆け〜
WeWork(ウィワーク)は、アメリカ発のコワーキングスペースです。基本のオフィス共有機能以外に、自分だけの固定デスクや、鍵付きの部屋を借りられるサービスもあります。駅前や一等地の有名ビルを拠点にできるので、起業家やフリーランスが社会的信用度を高めたい場合におすすめ。利用者同士の交流会やイベントも積極的に開催しているほか、利用者から人材を探したり、マッチングを手助けするサービスも行っています。作業のモチベーションを上げてくれるおしゃれな内装も、人気の理由の1つです。
パセラのコワーク〜カラオケで培った防音やサービスが売り〜
バリのリゾートをテーマにしたカラオケ運営で有名なパセラグループの新業態です。コワーキングスペースの内装もバリを意識しており、リゾート地で仕事をしている気分になれるでしょう。カラオケ業態で培った防音設備、きめ細かいサービスなど、居心地の良さを追求しながら生産性を高める工夫が行き届いています。一部の会員は追加費用なしで住所登記できる点も魅力。自宅の住所を公開するリスクがなく、ビル名が記載できることで信用も担保できます。
AOKI WORK SPACE〜ビジネスパーソンのニーズを知り尽くす使い勝手〜
衣料品や服飾品を手がけるAOKIが2021年2月末にスタートしたコワーキングスペースです。シンプルモダンがコンセプトの内装で、落ち着いて作業ができる空間に仕上がっています。オープンブースは机を広めにとったり、隣席との仕切りがあったり、入り口付近に商談コーナーを設け非会員との打ち合わせができるようにされていたりと、働く人の使い勝手を十分に配慮したつくりが特徴です。24時間オープンしており、時差のある海外とのビジネスにも対応できます。
Regus〜都市型コワーキングスペースの雄〜
Regus(リージャス)は外資系大手のコワーキングスペース事業者です。拠点は世界120カ国、3300拠点以上という圧倒的な数を誇っています。出張や営業移動が多い人は特に重宝するでしょう。数多くの事例から得られたノウハウを反映し、機能的なレイアウト、おしゃれな内装や家具など、生産性を高めるための工夫が凝らされています。
ITreviewではその他のコワーキングスペースも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
まとめ
今後も働き方の多様化はどんどん広がることが予想されます。働き方を変え、新たなビジネスチャンスを生み出す、自由な形態のコワーキングスペースが増えています。移動時間や通勤コストの削減、作業の効率化、幅広い人材活用など、利用目的を明確にして選ぶことで、メリットを最大限に生かすことができるでしょう。
見学やドロップイン利用できるコワーキングスペースも多いので、目的に応じて比較検討し、まずは体験するところから始めてみてください。
投稿 コワーキングスペースとは? メリットやシェアオフィスとの違い、おすすめサービス5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>