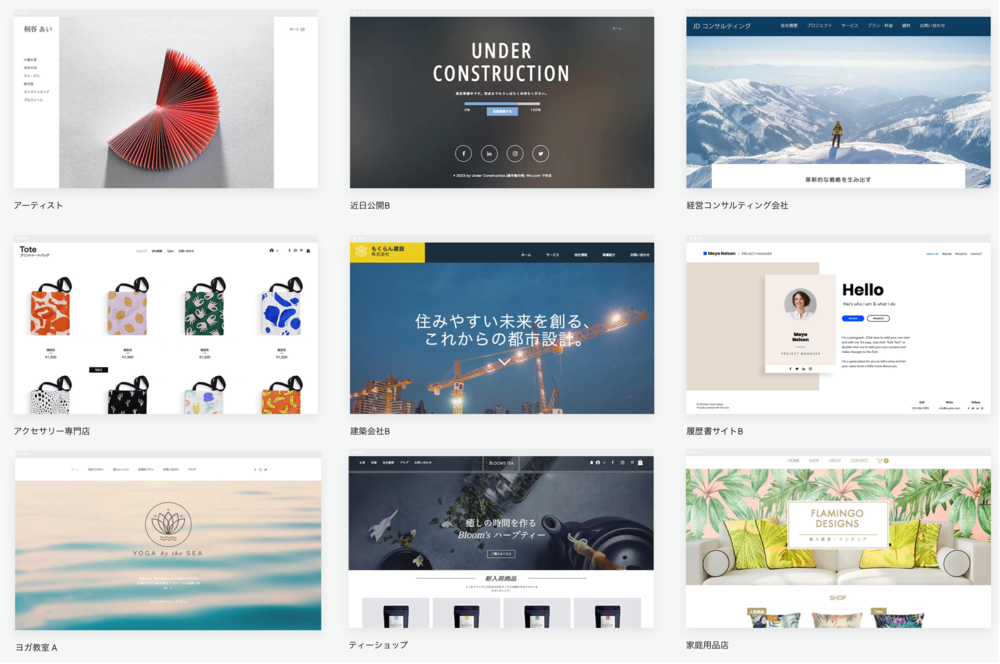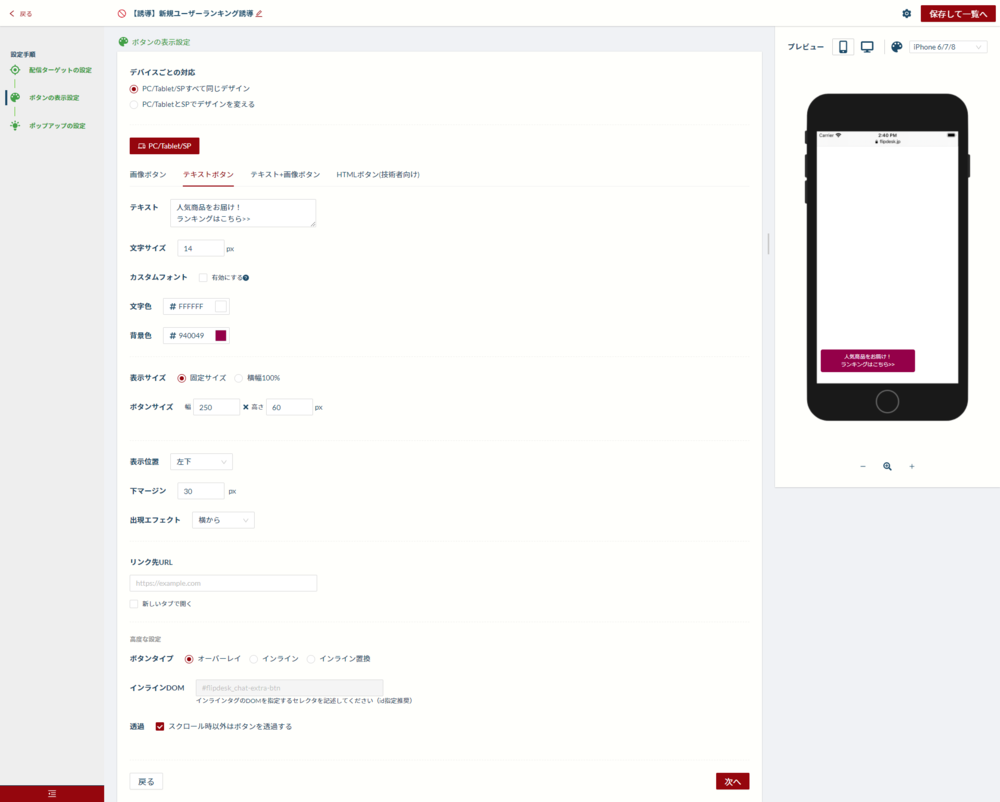投稿 LPOとは?SEOやEFOとの違いから効果的な改善方法までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、LPOにはデザインの最適化やCTA(コール・トゥ・アクション)の調整、A/Bテストの実施など、多岐にわたる項目が存在しているため、適切に運用しなければ効果が表れにくく、広告費の無駄使いにつながってしまう可能性もあります。
本記事では、LPOの概要をわかりやすく解説することに加えて、導入によるメリット・デメリット、具体的な改善方法まで詳しく解説します。
この記事を読むことで、LPOの全体像を理解しながら成果につながる施策を実行できる知識が身につくため、Webマーケティング担当者や広告運用担当者には必見の内容です!
LPO(ランディングページ最適化)とは?
LPO(ランディングページ最適化)とは、Webサイトのランディングページ(LP)を改善し、コンバージョン率を高める施策のことです。広告効果を向上させ、ユーザーの意思決定を促すため、多くの企業が導入しています。
主に、A/Bテストやヒートマップ分析、UI/UX改善を活用し、訪問者の行動を可視化しながら最適化を進めます。例えば、CTAボタンの色や配置を変更したり、フォームの入力項目を減らすことで、コンバージョン率を向上させます。
具体的な施策としては、CTAボタンの配置変更やコピーの最適化、フォームの簡素化などが挙げられます。さらに、スマートフォン対応を強化し、ユーザーの離脱を防ぐことで、問い合わせ数や売上の増加につなげることが可能です。
LPOが注目されるようになった理由
- デジタルマーケティングの競争の激化
- デジタル広告費の高騰とROI向上の必要性
- ユーザー行動の活用とパーソナライズの進化
デジタルマーケティングの競争の激化
デジタルマーケティングが急速に広まり、さまざまな企業がオンラインでの顧客獲得に乗り出しています。
その結果、検索エンジンやSNS広告などでユーザーをランディングページへ誘導する施策が一般化し、競争が激化しました。
競争が激しい中で成果をあげるには、単に広告を出すだけでなく、訪問後のユーザーを確実にコンバージョンさせるため、ランディングページを効果的に改善・最適化する必要が生まれています。
デジタル広告費の高騰とROI向上の必要性
オンライン広告市場の拡大に伴い、広告出稿費用が大幅に上昇しています。企業は限られた予算内で最大限の成果(ROI:投資対効果)を上げることが求められています。
こうした状況で、広告費を無駄にせず、訪問ユーザーを効率よくコンバージョンに結びつける手法としてLPOが注目されるようになりました。
広告効果の最大化と費用対効果の改善を実現する手法として、LPOの重要性は今後も高まっていくでしょう。
ユーザー行動の活用とパーソナライズの進化
近年のマーケティングでは、ユーザー行動データの収集・分析技術が飛躍的に進化しました。
これにより、ユーザーの属性や興味関心に合わせてランディングページをパーソナライズする手法が可能になっています。
ユーザーごとのニーズに適した情報を提供することで、離脱率を下げ、コンバージョン率を高めるLPOが現実的な選択肢となったことも、LPOが注目を集める背景となっています。
LPOとSEO・EFOの違いとは?
| LPO | SEO | EFO | |
|---|---|---|---|
| 最適化対象 | ランディングページ(LP) | サーチエンジン(SE) | エントリーフォーム(EF) |
| 実施の目的 | コンバージョン率の改善 | 検索表示順位の改善 | 入力完了率の改善 |
| 施策の具体例 | ・クリエイティブを変更する ・CTAの色やテキストを変更する ・コピーの文言や配置を変更する |
・コンテンツの質を高める ・被リンク施策を展開する ・サイトマップ構造を見直す |
・入力項目を簡素にする ・エラー表示の視認性を高める ・フォーム入力の負担を軽減する |
LPOとSEOの違い
LPOとSEOの違いは、対象とするページの目的です。SEO(検索エンジン最適化)は、検索結果での上位表示を狙い、集客を増やすことを目的としています。
具体的には、適切なキーワードの選定やコンテンツの質の向上を行い、検索エンジンからの流入を増やします。一方で、LPOは、訪問者が成約(コンバージョン)しやすいページ設計を行うことが目的です。
例えば、SEOでは「特定のキーワードで検索結果の上位を狙い、流入数を増やす施策」を行います。一方、LPOでは「流入したユーザーの問い合わせ率や購入率を高める施策」を重視します。
LPOとEFOの違い
LPOとEFOの違いは、最適化する対象の範囲にあります。EFO(エントリーフォーム最適化)は、ユーザーが入力フォームで離脱しないように改善する施策です。
具体的には、「入力項目の簡素化」「エラー表示のわかりやすさ」「スマートフォンでの入力のしやすさ」などを最適化し、フォームの送信率向上を目指します。一方、LPOでは「ランディングページのデザインを改善し、ユーザーの関心を引き、行動を促す施策」に重点を置きます。
例えば、EFOでは「入力ミスの修正をしやすくする」「フォーム入力の負担を軽減する」などの施策を行います。一方、LPOでは「CTAボタンの色や配置を変更する」「ページのファーストビューを改善する」などの改善が主な施策です。
LPOのメリット
- コンバージョン率(CVR)を向上できる
- 広告の費用対効果(ROI)を改善できる
- ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる
- ページの離脱率や直帰率を低減できる
- 顧客のインサイトを把握しやすくなる
コンバージョン率(CVR)を向上できる
LPOのメリットの1つ目としては「コンバージョン率(CVR)を向上できる」というものが挙げられます。
LPOを実施することで、訪問者が必要とする情報を適切に提示し、行動を促しやすくなります。特に、CTA(Call To Action)の最適化やフォームの簡略化は効果的です。
例えば、A/Bテストを用いて、よりクリックされやすいボタンのデザインや文言を検証することで、エントリー率の向上が期待できます。
広告の費用対効果(ROI)を改善できる
LPOのメリットの2つ目としては「広告の費用対効果(ROI)を改善できる」というものが挙げられます。
適切にLPOを実施することで、広告から流入したユーザーのコンバージョン率を高め、無駄な広告費を削減できます。特に、ターゲットユーザーに最適化されたページを用意することで、広告の成果を最大限に引き出すことが可能です。
例えば、リスティング広告のキーワードごとに専用のランディングページを作成することで、クリック後のユーザー体験が向上し、広告費の投資対効果を高められます。
ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる
LPOのメリットの3つ目としては「ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる」というものが挙げられます。
訪問者が求める情報を分かりやすく提供し、目的をスムーズに達成できるページ設計を行うことで、ユーザーの満足度が向上します。特に、直感的なデザインや読みやすいコンテンツは重要です。
例えば、ページの読み込み速度を改善したり、モバイル端末向けにレスポンシブデザインを導入することで、ストレスのない閲覧環境を提供できます。
ページの離脱率や直帰率を低減できる
LPOのメリットの4つ目としては「ページの離脱率や直帰率を低減できる」というものが挙げられます。
ランディングページの構成を最適化することで、訪問者が途中でサイトから離れてしまうリスクを減らせます。特に、視線誘導を意識したデザインや適切な情報配置が重要です。
例えば、ファーストビューに魅力的なキャッチコピーを配置したり、画面をスクロールせずに重要な情報を伝えたりすることで、ユーザーの興味を引きつけやすくなるでしょう。
顧客のインサイトを把握しやすくなる
LPOのメリットの5つ目としては「顧客のインサイトを把握しやすくなる」というものが挙げられます。
ランディングページの改善プロセスを通じて、ユーザーの行動データを蓄積し、ニーズを深く理解できます。特に、ヒートマップ分析やA/Bテストの活用は効果的です。
例えば、どのボタンがクリックされやすいのか、ページのどの部分でユーザーが離脱しやすいのかを分析することで、より成果につながるページ設計が可能になります。
LPOのデメリット
- 継続的な分析と改善が必要になる
- 専門的な知識やツールが必要になる
- 短期間では成果が出ない可能性がある
継続的な分析と改善が必要になる
LPOのデメリットの1つ目としては「継続的な分析と改善が必要になる」というものが挙げられます。
LPOは一度実施すれば終わりではなく、常にデータを分析しながら改善を続ける必要があります。特に、ユーザーの行動パターンや市場の変化に合わせて最適化していくことが求められます。
解決策としては、ヒートマップやA/Bテストを定期的に実施し、効果的な施策を自動化できるツールを導入することが有効です。継続的な運用体制を整えることで、最小限の工数で最大の成果を得ることが可能になります。
専門的な知識やツールが必要になる
LPOのデメリットの2つ目としては「専門的な知識やツールが必要になる」というものが挙げられます。
効果的なLPOを実施するためには、ユーザー行動の分析やページ設計に関する専門知識が求められます。また、A/Bテストやヒートマップ解析などを行うためには、専用のツールを活用する必要があります。
解決策としては、使いやすいLPOツールを導入し、マーケティング担当者が基礎的なデータ分析スキルを習得することが有効です。また、専門のLPOコンサルティングサービスを活用することで、より効率的に最適化を進めることも可能になります。
短期間では成果が出ない可能性がある
LPOのデメリットの3つ目としては「短期間では成果が出ない可能性がある」というものが挙げられます。
LPOはデータをもとに改善を重ねる手法であるため、即効性のある施策とは限りません。特に、最適なデザインやコンテンツを見つけるまでに一定の時間がかかることが課題となります。
解決策としては、短期間で効果を検証できるA/Bテストを積極的に活用し、小さな改善を積み重ねることが重要です。また、既存の成功事例を参考にすることで、効果的な施策をスムーズに実施しやすくなります。
LPOの効果的な実施手順
- ①:目的設定とKPIを決定する
- ②:現状分析と課題を特定する
- ③:改善方針を決定する
- ④:A/Bテストを実施する
- ⑤:効果検証と継続的な改善を行う
①:目的設定とKPIを決定する
LPOを成功させるためには、明確な目的設定とKPIの決定が不可欠です。LPOの目的は、主にコンバージョン率の向上ですが、具体的なゴールを明確にすることで、最適な施策を実施できます。
例えば、ECサイトなら「購入完了数」、リード獲得型なら「問い合わせ数」など、目的に応じたKPIを設定することが重要です。KPIは「クリック率」「直帰率」「フォーム入力完了率」など、測定可能な数値を設定し、改善の指標とします。
明確なKPIを設定することで、LPO施策の効果を適切に評価し、継続的な最適化を進められます。まずは自社のビジネスモデルに応じたKPIを定め、改善の方向性を明確にしましょう。
②:現状分析と課題を特定する
LPOを成功させるには、現状のデータを分析し、課題を特定することが重要です。どの要素がコンバージョンを妨げているのかを特定し、具体的な改善策を検討する必要があります。
Google Analyticsやヒートマップツールを活用し、直帰率・離脱率・クリック率などを確認しましょう。例えば、CTAボタンのクリック率が低い場合は、配置やデザインの変更が有効です。
また、ユーザーのフィードバックや行動データを活用し、定性的な分析を行うことも重要です。これらの情報をもとに、課題を明確化し、効果的な改善策を導き出しましょう。
③:改善方針を決定する
課題が明確になったら、具体的な改善方針を決定します。優先度の高い問題から取り組み、ユーザーの利便性やコンバージョン率向上につながる施策を検討しましょう。
例えば、CTAボタンのデザイン変更やフォームの入力項目削減など、ユーザーの負担を減らす施策が考えられます。また、ページの読み込み速度を改善することで、離脱率を下げることも可能です。
改善策は、仮説を立てて実施し、データをもとに効果を検証することが重要です。最適な手法を見極めながら、継続的にブラッシュアップしていきましょう。
④:A/Bテストを実施する
改善策の効果を正しく検証するには、A/Bテストの実施が必要です。異なるデザインやコンテンツを比較し、どの要素がコンバージョン率向上につながるのかをデータで検証します。
例えば、CTAボタンの色や文言、フォームの入力項目数、画像の配置などを変更し、ユーザーの反応を比較します。A/Bテストの実施には、専用のツールを活用することで、簡単かつ効率的にデータを収集できます。
テスト結果は、十分なサンプル数を確保したうえで統計的に分析し、確実な改善につなげることが重要です。データに基づいた意思決定を行い、効果的なLPへと最適化していきましょう。
⑤:効果検証と継続的な改善を行う
A/Bテストの結果をもとに、LPOの効果を検証し、継続的に改善を進めましょう。一度の施策で最適な状態になるとは限らないため、データを分析しながらPDCAサイクルを回していく必要があります。
具体的には、コンバージョン率や直帰率の推移を確認し、改善の成果を数値で把握します。仮説通りの効果が得られなかった場合は、別の要素を見直し、再度テストを行うことが有効です。
LPOは一度実施して終わりではなく、ユーザーニーズや市場の変化に合わせて継続的に最適化することが重要です。データに基づいた効果的な改善を積み重ね、成果を最大化していきましょう。
LPOの具体的な改善ポイント
- ファーストビューの最適化
- CTAやリンクボタンの最適化
- 問い合わせフォームの最適化
- 説得力のあるコンテンツの追加
- スマートフォンへの対応の強化
ファーストビューの最適化
「ファーストビューの最適化」は、LPOにおいて最も重要な要素のひとつです。訪問者がアクセスした瞬間に興味を引き、目的の行動へと誘導する必要があります。
最適化されていないとユーザーはすぐに離脱し、コンバージョン率が低下します。視線の動線を考慮したレイアウト、直感的なメッセージ、適切なビジュアルの活用が欠かせません。
例えば、「魅力的なキャッチコピー+目立つCTAボタン+信頼を高める要素(実績・ロゴ)」を組み合わせると効果的です。
CTAやリンクボタンの最適化
「CTAやリンクボタンの最適化」は、LPOの成果を大きく左右する重要なポイントです。CTAとは、購入・問い合わせ・資料請求などの行動を促すボタンやリンクを指します。
CTAが分かりにくい、目立たない、魅力がない場合、ユーザーのアクション率は低下します。そのため、「視認性の向上」「訴求力のあるテキスト」「配置の最適化」が必要です。
例えば、「目立つ色に変更」「アクションを具体化(例:無料で試す)」「視認しやすい位置に配置」することで、コンバージョン率が向上します。
問い合わせフォームの最適化
「問い合わせフォームの最適化」は、LPOにおいてコンバージョン率を向上させる重要な施策です。入力項目が多すぎる、分かりにくい、動作が遅いといった問題があると、ユーザーは離脱してしまいます。
コンバージョン率を上げるには、「入力負担の軽減」「直感的なUI」「信頼感の向上」がポイントとなります。具体的には、入力項目を最小限にする、リアルタイムでエラーを表示する、オートコンプリート機能の活用が効果的です。
例えば、「名前・メールアドレス・電話番号」のみに絞ったシンプルなフォームにすると、離脱率が低減し、コンバージョン率が向上します。また、プライバシーポリシーの明記やSSL対応を行い、ユーザーに安心感を与えることも重要です。
説得力のあるコンテンツの追加
「説得力のあるコンテンツの追加」も、コンバージョン率を向上させるには不可欠です。ユーザーは購入や問い合わせ前に「信頼できるのか?」と疑問を持つため、不安を解消する情報を提供する必要があります。
具体的には、「実績の紹介」「顧客の声」「データや数値による根拠」を活用することが効果的です。例えば、「導入企業数〇〇社」「満足度95%」「具体的な成功事例」を掲載すると、信頼を獲得しやすくなります。
さらに、ビフォーアフターの事例やFAQ(よくある質問)を掲載し、ユーザーの疑問を事前に解決することで、安心してCTAをクリックできる環境を整えることが重要です。
スマートフォンへの対応の強化
「スマートフォンへの対応の強化」も、LPOにおいて欠かせない要素の一つです。多くのユーザーがスマートフォンからWebサイトを閲覧するため、最適化されていないと直帰率が増加し、コンバージョン率が低下します。
最適化のポイントは、「レスポンシブデザインの採用」「読み込み速度の向上」「タップしやすいUI設計」です。例えば、「テキストやボタンのサイズ調整」「画像・動画の軽量化」「縦スクロールで快適に閲覧できる構成」といった施策が効果的です。
例えば、CTAボタンを親指で押しやすい画面下部に配置し、フォーム入力を簡単にすることで、スマートフォンユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョン率を向上できます。
LPOを社内でスムーズに進めるためのコツ
LPOの必要性を社内で理解してもらうには?
LPOの導入を社内で進めるには、データを根拠に説得することが重要です。特に経営層はROIを重視するため、数値で示すと効果的です。LPの直帰率やCVRを提示し、課題の明確化が必要になります。
「広告費を増やさずに売上を伸ばせる」点を強調すると、LPOの価値が理解されやすくなります。例えば、コンバージョン率が1%向上すれば、売上が大幅に増加する可能性があることを示します。また、他社の成功事例を示すことで、導入の決断を促せます。
経営層を説得する際は、改善のロードマップを示すことも有効です。施策のスケジュールや想定ROIを具体的に提示しましょう。
クライアントにLPOを提案する際のポイントは?
クライアントがLPOに投資するかは、ROIの明確さにかかっています。LP改善がCVR向上を通じて売上にどう直結するかを示し、データや事例を活用して説得力を高めることが重要です。
また、業種ごとにLPOのメリットを強調すると納得感が増します。例えば、ECサイトなら購入率向上、不動産なら問い合わせ増加など、具体的な成果を提示すると理解が深まります。
クライアントの不安を解消するには、低リスクな導入方法を提案すると効果的です。A/Bテストを一部のページで実施し、データに基づいた判断が可能であることを示すと、LPOの導入をスムーズに進められます。
LPO実施の社内リソースが不足している場合は?
LPOの実施には時間と労力がかかるため、社内リソースの確保が課題となります。まずは、スモールスタートで始め、ファーストビューやCTAの改善など、短期間で実施できる施策から取り組みましょう。
また、内製と外注の判断も必要になります。社内にリソースがあれば、データ分析やテストを自社で進められますが、不足している場合は外部支援を活用するのもおすすめです。
外注を検討する場合は、LPOコンサルやツールを活用すると効率的です。A/Bテストツールを利用すれば、負担を最小限に抑えつつ効果的に改善を進められます。
LPOツールの選び方と比較のポイント
- できることや機能面の充実度で選ぶ
- 導入や操作画面の使いやすさで選ぶ
- 価格やコストパフォーマンスで選ぶ
できることや機能面の充実度で選ぶ
LPOツールの選び方の1つ目としては「できることや機能面の充実度で選ぶ」という方法が挙げられます。
高度なLPOツールには、AIを活用した自動最適化機能や詳細な分析レポートが備わっているものもあります。これにより、ユーザー行動をリアルタイムで分析し、コンバージョン率を向上させる施策がスムーズに実施できます。
特に、マーケティングチームが頻繁にテストを行う場合、簡単に仮説検証できるA/Bテスト機能や視覚的なヒートマップがあると便利です。
導入や操作画面の使いやすさで選ぶ
LPOツールの選び方の2つ目としては「導入や操作画面の使いやすさで選ぶ」という方法が挙げられます。
特に、ドラッグ&ドロップでページ編集ができるビジュアルエディタや、コード不要でテスト設定ができる機能があると便利です。ノーコード・ローコード対応のツールであれば、マーケティング担当者がエンジニアに頼らずに改善施策を実施できます。
また、導入のしやすさを考慮するなら、既存のCMSや広告プラットフォームと連携しやすいツールを選ぶのもポイントです。
価格やコストパフォーマンスで選ぶ
LPOツールの選び方の3つ目としては「価格やコストパフォーマンスで選ぶ」という方法が挙げられます。
コストを抑えつつ運用するなら、必要な機能が揃ったシンプルなプランや従量課金制のツールを選ぶのがおすすめです。特に、小規模なサイト運営なら、基本的なA/Bテストやヒートマップ分析が使える無料プランでも十分な効果を得られる場合があります。
一方で、大規模なサイトや本格的にLPOを実施する企業なら、高度な分析機能やAIによる最適化機能が搭載された有料プランがおすすめです。
LPOのよくある質問
LPOの施策は、どのくらいの期間で成果が出ますか?
成果が出るまでの期間は施策内容やテスト頻度によりますが、一般的に効果が明確になるまで1〜3ヶ月ほどかかります。早期に小さな改善を繰り返すことが重要です。
LPOツールを使用せず、自社だけで実施できますか?
基本的な改善は自社でも可能ですが、効果検証やA/Bテストには専門ツールが必要です。データ分析や精度の高い改善を目指すならツールの活用をおすすめします。
LPOの施策で、特に効果が高いポイントはどこですか?
特に効果が高いのは、ファーストビューとCTAの改善です。ユーザーが最初に目にする部分を最適化すると、離脱率低下やCVR改善に直結します。
まとめ
本記事では、LPOの概要をわかりやすく解説するのに加えて、導入のメリット・デメリットや実施手順、改善ポイントまで、まとめて徹底的に解説しました。
近年、デジタルマーケティングの重要性が高まる中で、LPOは企業の成長に欠かせない施策となっています。特に、AIやパーソナライズ技術の進化により、今後もLPOの手法はさらに多様化し、効果的な最適化が求められるでしょう。
今後もITreviewでは、LPOツールのレビュー収集に加えて、新しいLPOツールも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 LPOとは?SEOやEFOとの違いから効果的な改善方法までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 CDPとは?主な機能やマーケティングの活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>ECサイトやPOS、SNSなど、複数のチャネルから取得したデータを統合し、顧客の行動を詳細に分析することができるようになります。
しかし、CDPの導入にはコストやデータ統合の複雑さといった課題があり、適切な運用ができなければ期待する成果を得られないリスクもあります。
本記事では、CDPの概要をわかりやすく解説することに加えて、基本機能や導入のメリット・デメリット、選定のポイントまで徹底解説します。
この記事を読むことで、CDPの全体像を把握し、自社に最適な活用方法を理解できるため、マーケティング担当者やデータ活用を検討している企業の意思決定者にとって必見の内容です!
CDP(Customer Data Platform)とは?
CDP(Customer Data Platform)とは、企業が保有するオンライン・オフラインの顧客データを一元管理し、マーケティングや営業活動に活用するプラットフォームのことです。
様々なチャネルから取得した顧客データを統合し、顧客一人ひとりの詳細なプロファイルを作成することで、よりパーソナライズされた顧客体験の提供が可能になります。
具体的には、購買履歴やWeb行動、SNSの反応、CRMデータなどを統合し、顧客の属性や興味関心、行動履歴などを把握できます。
主な活用例としては、ECサイトでのレコメンド強化、広告配信の最適化、カスタマーサポートのパーソナライズなどがあり、企業のマーケティング戦略を大きく向上できます。
CDPとCRM・MAとの違いは?
CDPと、CRM(顧客関係管理)、MA(マーケティングオートメーション)は、それぞれ異なる役割を持つツールです。
CRMは、既存顧客の情報を管理し、営業やカスタマーサポートを支援するために活用されます。一方、MAは見込み顧客の育成を自動化し、メール配信やスコアリングを通じて購買につなげることを目的としています。
CDPをCRMやMAと連携させることで、それぞれのツールが持つ機能をさらに強化し、より高度なマーケティング戦略を展開できます。
CDPの主な機能と活用事例
- データの収集と統合
- 顧客プロファイルの作成
- データ分析とセグメンテーション
- マーケティング施策への活用
➀:データの収集と統合
CDPの主な機能の1つ目は「データの収集と統合」です。
CDPは、Webサイトやアプリ、CRM、POS、SNSなど、複数のデータソースから顧客データを一元的に収集し、統合します。これにより、バラバラに管理されていたデータを統一し、企業全体で一貫性のある顧客データを活用できるようになります。
例えば、ECサイトの購買履歴や閲覧履歴、カスタマーサポートの問い合わせ履歴など、異なるデータを統合することで、顧客の全体像を把握することが可能です。
➁:顧客プロファイルの作成
CDPの主な機能の2つ目は「顧客プロファイルの作成」です。
収集したデータをもとに、顧客ごとに詳細な統合プロファイルを作成し、購買履歴や行動パターン、興味・関心などを明確にします。これにより、個別の顧客ごとに最適なマーケティング施策の立案が可能です。
例えば、CDPを活用することで、ECサイトの利用履歴やメール開封履歴、SNSでの反応をもとに、ユーザーが好む商品やコンテンツを特定できます。
③:データ分析とセグメンテーション
CDPの主な機能の3つ目は「データ分析とセグメンテーション」です。
CDPは、統合した顧客データをもとに、AIや機械学習を活用した高度なデータ分析を行い、顧客を細かく分類(セグメント化)します。これにより、企業は特定のターゲットに向けた精度の高いマーケティング施策を実施できるようになります。
例えば、購買頻度の高いリピーター層や、一度だけ購入したが再訪していない顧客など、行動パターンごとに異なるマーケティング戦略を立案できます。
④:マーケティング施策への活用
CDPの主な機能の4つ目は「マーケティング施策への活用」です。
CDPは、統合データや顧客プロファイル、セグメントデータをもとに、各種マーケティングチャネルへ自動連携し、最適な施策を実行します。これにより、広告配信、メールマーケティング、SNSマーケティング、パーソナライズ施策などの効果を最大化できます。
例えば、過去の購買履歴をもとにリピーター向けのクーポンを発行したり、Webサイトの行動データを分析して離脱防止のポップアップを表示したりすることが可能です。
CDPの導入メリット
- データの一貫性を維持できる
- リアルタイム対応が可能になる
- データセキュリティを強化できる
データの一貫性を維持できる
CDPのメリットの1つ目は「データの一貫性を維持できる」というものが挙げられます。
CDPは統合されたデータ基盤を提供するため、異なる部署やシステム間でデータの不整合が発生するリスクを軽減できます。これにより、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、部門ごとに異なるデータを参照することなく、共通のデータを活用できます。
例えば、マーケティング部門が配信したキャンペーンに対する顧客の反応を、営業部門がリアルタイムで確認し、最適な営業アプローチを実施することが可能です。
リアルタイム対応が可能になる
CDPのメリットの2つ目としては「リアルタイム対応が可能になる」というものが挙げられます。
従来のデータ管理システムでは、データの更新に時間がかかり、迅速な顧客対応が難しい場合がありました。CDPを導入することで、顧客の行動データを即座に取得し、それに基づいた施策をリアルタイムで実行できます。
例えば、ECサイトで特定の商品をカートに入れたまま離脱した顧客に対して、すぐにリマインドメールや限定クーポンを自動配信し、購入率を向上させる施策が可能です。
データセキュリティを強化できる
CDPのメリットの3つ目としては「データセキュリティを強化できる」というものが挙げられます。
顧客データの取り扱いに関する法規制が厳しくなる中、企業はデータの管理と保護を徹底する必要があります。CDPは、データのアクセス制御や匿名化、暗号化といった機能を提供し、企業が法規制を遵守しながら安全にデータを活用できる環境を構築します。
例えば、GDPRやCCPAなどの規制に対応するため、顧客の同意管理やデータの保存期間を適切に設定し、コンプライアンスを維持することが可能です。
CDPの導入デメリット
- 導入や運用にコストが発生する
- データ統合に時間と労力がかかる
- 活用には専門的な知識が必要になる
導入や運用にコストが発生する
CDPのデメリットの1つ目としては「導入や運用にコストが発生する」というものが挙げられます。
CDPの導入には初期費用や月額料金に加えて、データの統合・運用に関する人的リソースも必要です。特に大規模なCDPを導入する場合、データ管理やシステム統合にかかるコストが増大します。
解決策としては、自社のビジネス規模に適したプランを選択することや、無料トライアルやデモ環境を活用して費用対効果を事前に検証しましょう。
データ統合に時間と労力がかかる
CDPのデメリットの2つ目としては「データ統合に時間と労力がかかる」というものが挙げられます。
CDPは顧客データを統合して活用するため、各種データソースとの接続設定やフォーマット変換が必要です。データクレンジングやタグ設計の見直しが必要になることもあり、短期間での導入が難しい場合があります。
解決策としては、既存システムとの連携が容易なCDPを選定することや、導入支援サービスを活用してデータ統合をスムーズに進めることが有効です。
活用には専門的な知識が必要になる
CDPのデメリットの3つ目としては「活用には専門的な知識が必要になる」というものが挙げられます。
CDPを効果的に活用するには、データ分析のスキルやマーケティングオートメーション(MA)との連携に関する知識が必要です。データを収集・統合するだけではなく、それを活用して顧客インサイトを導き出すことが求められます。
解決策としては、CDPのトレーニングを実施することや、専門家を採用・育成することが重要です。
CDPの選び方と比較ポイント
- ①:データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ
- ②:セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ
- ③:他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ
- ④:リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ
- ⑤:セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ
①:データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ
CDPを選ぶポイントの1つ目としては「データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ」というものが挙げられます。
CDPはさまざまなデータを統合するためのプラットフォームですが、対応するデータソースが限定されている場合、運用に制約が生じます。幅広いデータソースと連携できるCDPを選択することで、より包括的なデータ管理が可能です。
例えば、SalesforceやGoogle Analytics、広告プラットフォーム、POSデータ、IoTデータなどの多様なソースに対応するCDPを選ぶことで、マーケティング施策の幅が広がります。
②:セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ
CDPを選ぶポイントの2つ目としては「セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ」というものが挙げられます。
CDPは顧客データを統合するだけでなく、適切なセグメントを作成し、データを活用できる分析機能を備えているかが重要です。高度なセグメンテーションやAIを活用した予測分析が可能なCDPを選ぶことで、マーケティング施策の最適化が期待できます。
例えば、リアルタイムでセグメントを作成し、広告配信やメールマーケティングと連携できるCDPは、顧客の行動変化に素早く対応できます。
③:他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ
CDPを選ぶポイントの3つ目としては「他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ」というものが挙げられます。
CDP単体ではなく、CRM、MA、広告管理ツールなどとスムーズに連携できるかが、実用性に大きく影響します。APIやノーコードでの連携機能が充実しているCDPを選ぶと、マーケティング施策の自動化が容易になります。
例えば、HubSpotやMarketo、Google広告、Facebook広告、LINEなどの複数チャネルとシームレスに接続できるCDPを選ぶと、データの一貫性を保ちながら施策を実行できます。
④:リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ
CDPを選ぶポイントの4つ目としては「リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ」というものが挙げられます。
顧客の行動データを即座に分析し、リアルタイムで施策に反映できるかがCDPの性能を大きく左右します。リアルタイム処理が可能なCDPを選ぶことで、ECサイトやアプリ上でのパーソナライズ施策がスムーズに実行できます。
例えば、顧客がサイトに訪問した瞬間に、最適なクーポンや広告を表示できるCDPは、購買意欲を高めるのに効果的です。
⑤:セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ
CDPを選ぶポイントの5つ目としては「セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ」というものが挙げられます。
個人情報や機密データを扱うCDPでは、セキュリティ対策やデータガバナンスの仕組みがしっかりしているかが重要です。特に、GDPRやCCPAといったプライバシー規制への対応が求められます。
例えば、アクセス権限の細かい管理、暗号化機能、データの匿名化が可能なCDPを選ぶことで、データ漏洩のリスクを軽減できます。
まとめ
本記事では、CDPの概要をわかりやすく解説するのに加えて、活用事例や導入によるメリット・デメリット、選定ポイントまで、まとめて徹底的に解説していきました。
CDPは、AIや機械学習の進化により、高度な予測分析やリアルタイムマーケティングの活用がさらに進むと予想されます。
今後もITreviewでは、CDPのレビュー収集に加えて、新しいCDPについても続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 CDPとは?主な機能やマーケティングの活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MAツールのMarketo(マルケト)とは?できることからメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>マーケティング施策を実施するうえで強力な味方となり得るマルケトですが、では一体、その特徴やメリット・デメリットなどは、どのようなところにあるのでしょうか?
本記事では、マルケトの特徴から利用できる基本的な機能、料金プラン、口コミや評判からわかったメリット・デメリットなどについて、まとめて徹底解説していきます!
Adobe Marketo Engage(マルケト)とは?

マルケト(Adobe Marketo Engage)とは、世界6,000社を超える企業で導入されている、世界的なMA(マーケティングオートメーション)ツールのことです。
現在では「Adobe Marketo Engage」の名称で展開されていますが、もともとは米Marketo社が開発を行っており、2018年10月にはAdobe(アドビ)社が大型買収を行ったことでも話題になりました。
既存の顧客から見込み顧客、匿名のサイト訪問者まで、幅広いユーザーのインテントデータを収集することができるため、より効果的かつ戦略的なマーケティング施策に活用することができます。
MAツールとは?
MAツール(Marketing Automation)とは、営業などの現場において、リード顧客から成約までのマーケティング業務を自動化し、マーケティング活動そのものを効率化するツールのことを指します。
▶ 関連記事:【MAとは?】マーケティングオートメーションの機能・特徴・選び方を徹底解説!
Adobe Marketo Engage(マルケト)の特徴
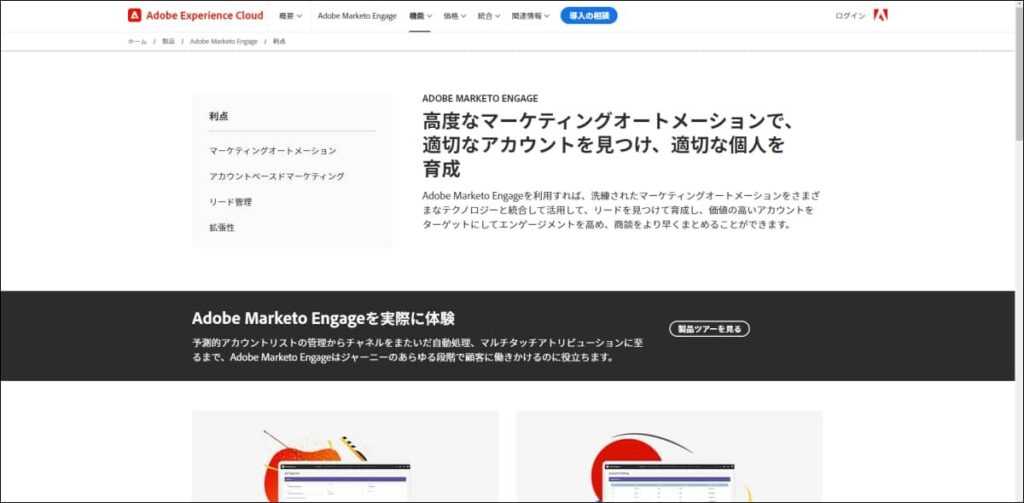
リード獲得を支援できる
マルケトは、マーケティングツールにおける、多様な機能を統合したプラットフォームです。ランディングページやフォームの作成、リードスコアリング、自動化されたキャンペーンなど、豊富な機能を活用することで、効果的なリード獲得活動を支援することができます。
見込み顧客を育成できる
マルケトは、リード獲得だけではなく、見込み顧客を育成するための機能も充実しています。顧客の行動や興味にもとづいたパーソナライズされたコンテンツの配信、ターゲティングされた電子メールキャンペーンなど、見込み顧客との良好な関係構築に役立ちます。
ワークフローを改善できる
マルケトは、顧客の獲得以外にも、ワークフローを改善するための機能も提供しています。ワークフローエディタを使用したマーケティングプロセスの自動化やA/Bテスト、リアルタイムのアナリティクスなど、ワークフローの効果を評価し、最適化することが可能です。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の機能
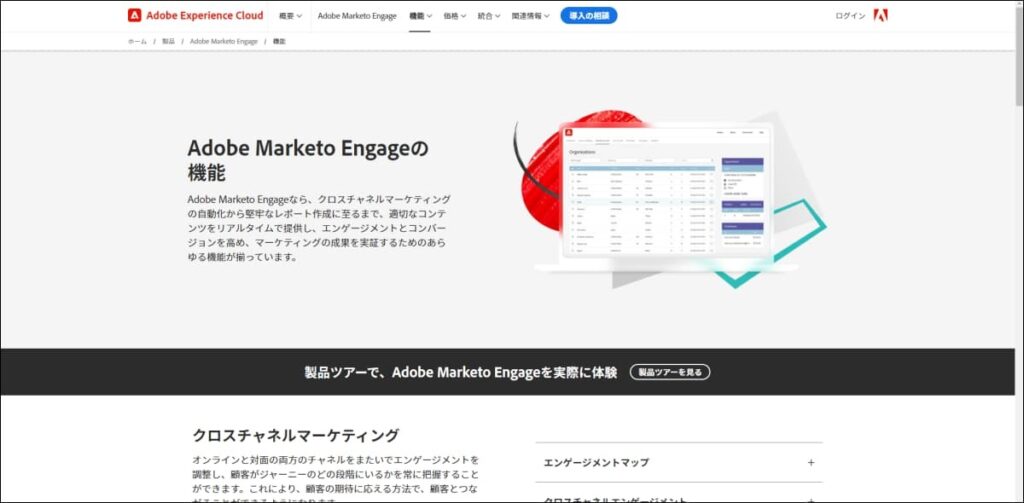
マルケトの大きな特徴の一つとして「10個の機能(アプリケーション)」の存在が挙げられます。活用することにより、効果的なリードの獲得と顧客のエンゲージメントを実現することができます。
マーケティングオートメーション
マーケティングオートメーション(MA)に役立つ機能です。リードの生成から顧客のナーチャリング、顧客関係管理(CRM)まで、マーケティング活動におけるプロセス全体を自動化することができます。
メールマーケティング
ユーザーごとにパーソナライズされたメールキャンペーンを作成する機能です。リアルタイムな追跡と詳細な分析を行うことによって、メールマーケティングの成果を最大化することができます。
モバイルマーケティング
モバイルデバイスへのターゲティングやパーソナライゼーションを実施する機能です。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に向けて、リーチとエンゲージメントを最適化することができます。
ソーシャルマーケティング
ソーシャルメディアプラットフォームでのマーケティング活動を支援する機能です。ソーシャルリスニングやターゲティングを行うことによって、サービスやブランドの知名度を高めることができます。
デジタル広告
自社の獲得したいターゲットオーディエンスに対して効果的な広告を配信する機能です。デジタル広告の管理と最適化を実施することにより、企業のROI(投資利益率)の最大化に貢献することができます。
Webパーソナライゼーション
ウェブサイトの訪問者に対して個別にカスタマイズされたアプローチを提供する機能です。匿名の訪問者に対して適切なアプローチを行うことにより、コンバージョンの増加に貢献することができます。
アカウントベースドマーケティング
アカウントベースでエンゲージメント率が高いユーザーをリストアップする機能です。重要なアカウントに対してパーソナライズされたアプローチを実現し、ビジネスチャンスを追求することができます。
マーケティングアナリティクス
実施したマーケティングキャンペーンの効果を迅速に評価する機能です。リアルタイムなデータ分析と可視化によって、どのキャンペーンが効果的なのか、戦略的な意思決定を支援することができます。
プレディクティブコンテンツ
ユーザーの行動と関心にもとづいて次に表示するコンテンツを予測する機能です。それぞれのユーザーごとにレコメンドするコンテンツを選択し、パーソナライズされた体験を提供することができます。
プレディクティブオーディエンス
ユーザーの行動履歴と属性にもとづいて将来の消費行動を予測する機能です。AIによる顧客セグメンテーションによって、ターゲティングとマーケティングメッセージの最適化を行うことができます。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の料金
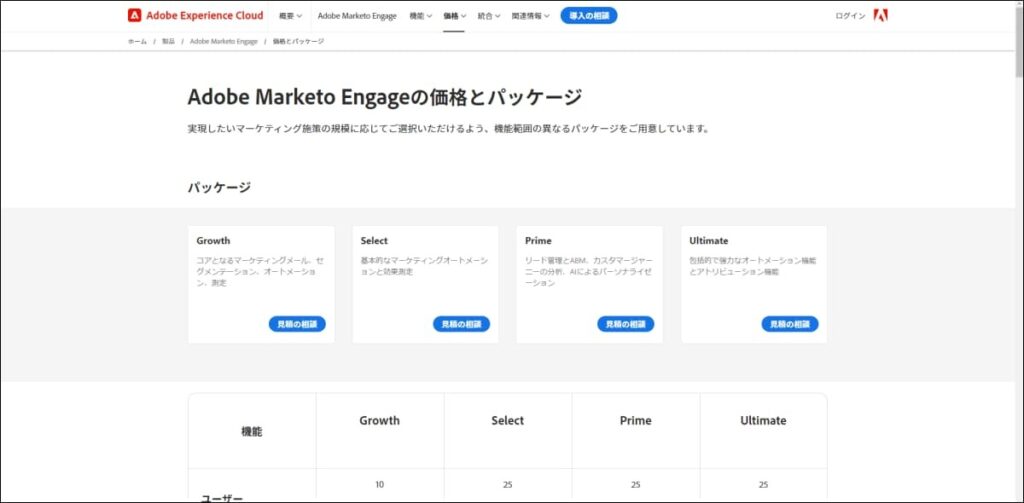
マルケトには、主に下記の4つの料金プランが存在します。各プランの詳細な価格は公式HPには明記されていないため、詳細な料金情報についてはAdobeの担当者への見積もり相談が必須になります。
- Growthプラン
- Selectプラン
- Primeプラン
- Ultimateプラン
また、それぞれのプランごとで、対象となる法人ユーザーや利用できる機能などは異なるため、導入するときには、自社の従業員規模やニーズにマッチしたプランを選択するようにしましょう。
Growthプラン
Growthプランは「小規模なビジネス向けのエントリープラン」です。主な機能には、基本的なマーケティングオートメーション機能やリード管理機能、アナリティクスでの分析機能などが含まれています。
Selectプラン
Selectプランは「中規模の企業向けのミドルプラン」です。マーケティングオートメーション機能やリード管理機能はもちろん、ソーシャルメディア管理などの高度なマーケティング機能が含まれています。
Primeプラン
Primeプランは「大規模な企業向けのハイエンドプラン」です。ABM(アカウントベースドマーケティング)や高度なアナリティクス、カスタマイズ機能など、さらに高度な機能とサポートが提供されます。
Ultimateプラン
Ultimateプランは「複雑なマーケティングニーズを持つ企業向けのカスタムプラン」です。このプランでは、包括的なマーケティング機能や専任のアカウントマネージャーサポートなどが提供されます。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の導入事例
導入企業①:コクヨ株式会社

コクヨ株式会社は、マルケトを導入し、マーケティングプロセスの効率化と顧客エンゲージメントの向上に成功しました。
マルケトを活用することで、コクヨは顧客の行動や興味にもとづいた、パーソナライズされたコンテンツを提供し、リード獲得から顧客育成までのプロセスを自動化することができました。
導入企業②:LINE Pay株式会社

LINE Pay株式会社は、マルケトを導入し、ユーザーエンゲージメントの向上とマーケティング効果の最大化を実現しました。
マルケトを活用することで、LINE Payはユーザーの行動データを分析し、ターゲットに合わせたパーソナライズされたマーケティングキャンペーンを展開することができました。
導入企業③:株式会社日立製作所
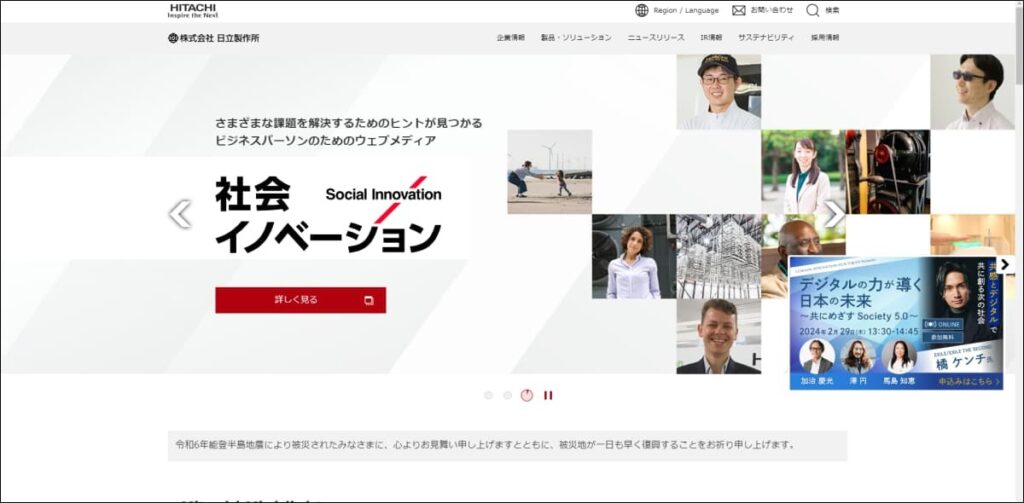
株式会社日立製作所は、マルケトを導入し、グローバルなマーケティングプロセスの統合と効率化を実現しました。
マルケトを活用することで、日立は世界中の顧客とのコミュニケーションを統一し、一貫したブランドメッセージの発信と有益なコンテンツを提供することができました。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の口コミ・評判
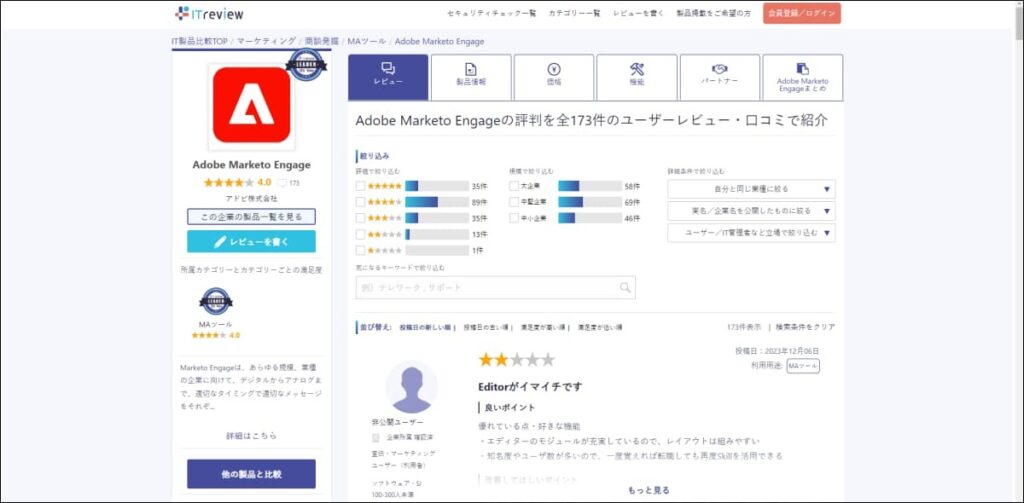
Marketo(マルケト)の良い口コミ・評判

あらゆるマーケティング業務をこれ1つでできる
今まではメール配信用、リード管理用、LP作成など業務によってツールを使い分けており連携性もなくログインも面倒で業務が煩雑でしたが、Marketoはそれらをつでできるので業務負荷をかなり削減できました。
企業名:コムテック株式会社
従業員規模:1000人以上
業種:ソフトウェア・SI

いまのマーケティング活動には不可欠
メール、Web、広告など、複数のチャネルに分かれつつ、利用する画像やPDFなどのアセットは共通で管理できるなど、効率的にマーケティング活動が可能となっている。マーケターが”作業”する時間を少なくできるので、本来考えるべきことに集中できる。
企業名:ソフトバンク株式会社
従業員規模:1000人以上
業種:情報通信・インターネット

マーケティング分析に役立つ
なかなか人力では難しい実用的なマーケティング分析を自動的にしてくれるので、ビジネスマーケティングの世界において実用的です。顧客がどこから流入し、何に興味を持っているのかジャーニーを把握できるので、質の高い情報が得られます。
企業名:Horaanna
従業員規模:20人未満
業種:日用雑貨
Marketo(マルケト)の悪い口コミ・評判

便利な点もなるが、とてつもなく不便な点もある
モバイル対応したメールテンプレートやランディングページテンプレートはあるが、細かな修正が全くできない。きちんとしたものを作ろうとすると、HTMLやCSSでゴリゴリに編集しないといけないので、全く使い物にならない。この点は、本当にAdobeがベンダーなのかと疑うレベルで質が低く、自由度の高いHubspotと比べるとその差は天と地ほどある。
企業名:非公開(企業確認済)
従業員規模:20-50人未満
業種:ソフトウェア・SI

必要な機能がほぼ揃っているが使い勝手とコストは悩ましい
コストの上がり方は使い続ける中でいずれぶつかる壁。機能網羅性の弊害ともいえるが、ユーザビリティも直感的とは言えない。
企業名:コムテック株式会社
従業員規模:1000人以上
業種:ソフトウェア・SI

Editorがイマイチです
とにかく、日本向けにフォントなど改行位置なども仕様が整っていないため、汚く見えてしまい、フォントは明朝ゴシック一択なので、イケてない見た目になってしまう。ここを何とかまずしてほしい。
企業名:非公開(企業確認済)
従業員規模:100-300人未満
業種:ソフトウェア・SI
Adobe Marketo Engage(マルケト)のメリット

利用できる機能が豊富
マルケトのメリットの1つ目としては「利用できる機能が豊富」というものが挙げられます。
マルケトは、マーケティングオートメーションからメールマーケティング、ソーシャルメディア管理、デジタル広告まで、多岐に渡る豊富な機能を利用することができます。
本来であれば複数のSaaSを導入して並列に使用なければならない部分まで、さまざまな機能が網羅されているため、マルケト単体で包括的なマーケティング戦略を展開することができます。
外部ツールとの連携が簡単
マルケトのメリットの2つ目としては「外部ツールとの連携が容易」というものが挙げられます。
マルケトは、同じAdobe製品との機能連携はもちろんのこと、SalesforceやZoom、Slackなど、他社の外部ツールやプラットフォームとのシームレスな連携をサポートしています。
ビジネスには必須のCRMシステムやデータ分析ツール、顧客データプラットフォームなど、さまざまなツールとの統合が容易になることで、マーケティング活動の効率化を実現することができます。
ユーザーコミュニティが活発
マルケトのメリットの3つ目としては「ユーザーコミュニティが活発」というものが挙げられます。
マルケトは、ユーザーコミュニティが非常に活発なことでも有名であり、ユーザー同士の知識共有や情報交換など、業界や業種を問わずグローバルな交流が盛んに行われています。
公式コミュニティフォーラムやイベント、ウェビナーなどを通じて、最新のトレンドやベストプラクティスを学ぶことができるため、マーケティング戦略の改善や効率化に役立てることができます。
Adobe Marketo Engage(マルケト)のデメリット

競合の製品と比較してランニングコストが高い
マルケトのデメリットの1つ目としては「競合の製品と比較してランニングコストが高い」というものが挙げられます。
マルケトは、豊富な機能が特徴となっている反面、導入費用やライセンス料、カスタマイズやサポートにかかる費用は、競合の類似製品と比較して、高額になりやすい傾向にあります。
とくに、中小企業や予算が限られている企業にとっては、導入コストが障害となることも多いため、全体的な価値やROI(投資利益率)を事前に評価し、費用と期待される効果を試算することが重要です。
扱える機能が多く初心者には操作が難しく感じる
マルケトのデメリットの2つ目としては「扱える機能が多く初心者には操作が難しく感じる」というものが挙げられます。
マルケトは、マーケティングオートメーションから分析、コンテンツ管理まで幅広い機能を提供している反面、なんでもできることが、かえってストレスとなってしまう可能性があります。
これらの多様な機能を理解し、適切に操作することは初心者にとっては難しい場合があるため、操作方法や機能の使い方については、公式のトレーニングやサポートを受ける必要があるでしょう。
英語表記が多く日本語の対応が不十分な場面がある
マルケトのデメリットの3つ目としては「英語表記が多く日本語の対応が不十分な場面がある」というものが挙げられます。
マルケトは、グローバルなマーケティングプラットフォームであり、英語表記が主流となっているため、日本語のドキュメンテーションやサポート体制が不十分な場合があります。
わからない機能や単語に遭遇したときには、公式のサポートに問い合わせるか、外部の翻訳サービスなどを利用して自力で解決する必要があるため、使い勝手が悪いと感じるユーザーも多いようです。
MAツールを選定するときのポイント

①:利用の目的はBtoB向けかBtoC向けか
MAツールを選定するときのポイントの1つ目としては「利用の目的はBtoB向けかBtoC向けか」というものが挙げられます。
BtoB向けのツールは、企業のビジネスプロセスや顧客関係管理をサポートする機能が重視されますが、BtoC向けのツールは、大量の消費者データを処理し、個々の顧客との関係を構築する機能が重要です。
②:現場の従業員が使いやすい操作性であるか
MAツールを選定するときのポイントの2つ目としては「現場の従業員が使いやすい操作性であるか」というものが挙げられます。
MAツールは、現場のマーケティング担当者や営業担当者が使いやすいことが重要です。直感的なインターフェースやカスタマイズ可能なダッシュボードなど、使い勝手の良さは生産性の向上に直結します。
③:自社の導入目的と機能がマッチしているか
MAツールを選定するときのポイントの3つ目としては「自社の導入目的と機能がマッチしているか」というものが挙げられます。
例えば、リードの獲得や顧客エンゲージメントの向上を目指す場合には、それらをサポートする機能が必要です。自社のニーズと選定候補の機能がマッチしているかは、あらかじめ確認しておきましょう。
④:自社と同規模の会社への導入実績はあるか
MAツールを選定するときのポイントの4つ目としては「自社と同規模の会社への導入実績はあるか」というものが挙げられます。
自社と同規模の会社への導入実績がない場合、導入前後での運用や効果予測が難しくなってしまうため、同程度の会社への実績がないサービスについては、なるべく導入を控えておくのが無難でしょう。
⑤:セキュリティやサポートは充実しているか
MAツールを選定するときのポイントの5つ目としては「セキュリティやサポートは充実しているか」というものが挙げられます。
データのトラブルや障害発生時における迅速な対応は、安定した運用を実現するうえでは不可欠です。MAツールのセキュリティやサポート体制が充実しているかどうかは、事前に確認しておきましょう。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の導入なら運用・導入支援パートナーがおすすめ!

本記事では、マルケトの特徴から利用できる基本的な機能、料金プラン、口コミや評判からわかったメリット・デメリットなどについて、まとめて徹底解説していきました。
もはやデファクトスタンダードともいえるMAツールのマルケトですが、利用できる機能が多い一方で、初心者には扱いが難しいというデメリットも見えてきました。
自社だけでの構築や運用が難しいという場合には、ぜひこの機会に「運用・導入支援パートナー(コンサル)」の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
投稿 MAツールのMarketo(マルケト)とは?できることからメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MEO対策とは?メリデメや実施の方法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そのなかで注目を集めているのが「MEO対策」です。MEO対策は比較的難易度が低く、成果を上げやすい手法として多くの店舗ビジネスで取り入れられています。そこで今回は、MEO対策のメリットとデメリット、および実施する方法、MEOツールについてご紹介していきます。
MEO対策とは?
MEOとは、Map Engine Optimization(マップエンジン最適化)を略した言葉で、Googleマップ検索の結果で上位表示を目指すことです。ローカル検索(ローカルSEO)とも呼ばれており、「地域名+サービス名/業種」のような地域性をともなうキーワードが結果に反映されます。
たとえば「鎌倉_カフェ」で検索した場合は以下のような結果となり、上位3店舗が目立つ位置に表示されます。
MEOとSEOの違い
MEOとSEOはよく混同されがちですが、区別して考える必要があります。
MEOがマップ検索であるのに対し、SEOは「検索エンジン最適化」という意味で、検索エンジンで上位を目指すものです。つまりSEO対策はWebサイト全体に対するもので、自社のWebサイトを通常の検索エンジンで上位表示するために行います。
またSEO対策では製品のブランディング強化や自社のWebサイトへの流入数を増やすことを目的としていますが、MEO対策は特定の地域で店舗ビジネスをアピールして集客につなげることが目的です。
MEO対策によるメリット4つ
メリット1:SEOより検索結果が目立つ
以下を見てわかるように、MEOはSEOよりも上に表示され目に留まりやすいのが特徴です。その理由は、Googleが検索ワードからユーザーの意図を分析し、必要だと判断された結果を表示しているためです。上位3位に入れば、このように店舗情報や地図情報などの詳細まで表示することができます。
メリット2:見込み客に訴求できる
「地域名+サービス名/業種」による検索では、ユーザーがその地域で店舗やサービスを探していることが想定できます。とくにスマホユーザーの場合、リアルタイムで店舗とルートを探している可能性は非常に高いと言えるでしょう。つまりマップ検索で上位表示されることが見込み客に対する訴求となり、新たな顧客獲得へとつながります。
メリット3:広告よりもリーズナブルに集客できる
MEO対策は、Googleが提供するGoogle ビジネス プロフィールを用いて行います。無料のため、リスティング広告やSEO対策に比べてリーズナブルに利用することができます。通常、リスティング広告は1カ月30万円~、SEO対策だと月額10~30万円程度の費用が発生してしまいますが、MEO対策は自分で実施するなら0円です。
メリット4:SEOに比べて競合が少ない
MEO対策は、SEOと比べて競合が少ないのもメリットの1つです。SEOはすでに対策されている場合が多く、Google検索での上位表示は大手企業サイトが占めています。これから参戦するとなると多大なコストと労力を要することが想定されます。
一方、MEOはまだ対策している企業は少ないため、比較的成果が出やすいのが現状です。とくにローカルビジネスにおいてはWeb施策自体に力をいれている店舗が少ないため、見込み客に対して効果的にリーチすることができます。
MEO対策によるデメリット4つ
デメリット1:誹謗中傷を受ける可能性がある
Googleマップで店舗情報が掲載された際、避けて通れないのが口コミへの誹謗中傷です。口コミはユーザーが自由に投稿できるため、良い評価だけでなく悪い内容を書かれることがあります。仮に悪い口コミが多くなると、他のユーザーが来客を敬遠し始める可能性があります。したがってMEO対策を始める場合は、常にお客様に満足してもらえるサービスを心掛ける必要があります。
デメリット2:自力での対策は手間と時間がかかる
MEO対策はコストを抑えられる反面、自力で対策するにはそれなりの手間と時間がかかります。上位表示を目指すには、表示する店舗情報を充実させ定期的な情報発信などの施策を続けていく必要があります。始める際は、運用する担当者を決めてスケジュールの確保も行いましょう。
デメリット3:ビジネスによっては効果が得られない
MEOは地域密着型の施策であるため、飲食店や美容室、医院、小売店など実店舗のあるビジネスに効果のあるマーケティング手法です。逆に言えば、実店舗のない通販やインターネットサービスなどのビジネスには向いていません。効果が得られるビジネスが限られているという点でデメリットだと言えます。
MEO対策を実施する方法
ここからはMEO対策の実施方法について解説します。具体的には以下の5つの手順で行います。
- Googleビジネスプロフィールを登録する
- Googleビジネスプロフィールを充実させる
- 投稿を活用して積極的に最新情報を発信する
- 口コミに返信してコミュニケーションを取る
- SNSなど他のメディアでも施策を行う
Googleビジネスプロフィールを登録する
Googleマップに表示させるには、Googleビジネスプロフィールへの登録が必要です。Googleによって提供されており、無料で利用することができます。
出典:Google ビジネス プロフィール|Google にビジネスを掲載
ここで注意すべき点は、NAP情報と呼ばれるName(会社名・店舗名)、Address(住所)、Phone(電話番号)を、他のメディアと統一させることです。Googleの評価基準の1つとして「知名度」がありますが、WebやSNSでの話題性は上位表示に影響を及ぼします。NAP情報が統一されていないと同じ店舗であると判断されず、知名度が評価されない可能性があります。
Googleビジネスプロフィールを充実させる
続いてGoogleビジネスプロフィールの情報を充実させていきましょう。店舗の名称や住所といった基本情報だけでなく、営業時間やサービスの内容、公式WebサイトのURLなど、情報量が多いほど表示順位に良い影響を与えます。またロゴの設定や、店舗の雰囲気や商品が分かる写真の投稿も効果的です。情報が充実することで検索ワードとの関連性が高まり、上位に表示されやすくなります。
投稿を活用して積極的に最新情報を発信する
顧客に向けて店舗の情報を発信できるのが投稿機能です。たとえば旬な情報を発信できる「最新情報」やセールの告知に使える「イベント」などの機能があり、定期的に投稿することで既存顧客および潜在顧客にアピールすることができます。
口コミに返信してコミュニケーションを取る
MEO対策では、口コミ機能によるユーザーとのコミュニケーションも重要です。とくに悪い口コミがあった場合は、ユーザーと真摯に向き合い、サービス改善に向けた方法を丁寧に説明しなければいけません。オーナー側の誠意が伝われば相手も納得し、他のユーザーにも良い印象を与える可能性があります。店舗のイメージが向上すれば集客につながり、さらに口コミや評価を増やすことができます。
SNSなど他のメディアでも施策を行う
MEO対策とセットで行うと効果的なのが、TwitterやFacebookなどのSNSを使った情報発信です。Googleの評価基準には「知名度」があるため、他のメディアで言及される機会が多いほど上位表示しやすくなります。自社サイトにおけるSEO対策も同様で、掲載順位が上がれば上位表示の可能性が高くなります。
MEO対策を効率的かつ効果的に行うには?
MEO対策は、非常に多くの手間と時間を要します。しかし以下の方法を行えば、効率的かつ効果的にMEO対策を進めることができます。
専門の業者に依頼する
専門業者に全ての管理を任せる方法です。具体的には、Googleビジネスプロフィールの情報更新や情報発信、口コミへの返信などを依頼することができます。費用面はSEO対策に比べると低コストですが、初期費用+(成果報酬または月額)が必要となり、1年間でおよそ30万円〜の費用が発生します。とはいえ、MEO対策における知識や経験も豊富なため、短期間で軌道に乗せられる可能性があります。
MEO対策ツールを導入する
MEO対策ツールは、上位表示を目指すためのさまざまな機能を搭載しています。たとえば、複数店舗のGoogleビジネスプロフィールを一括更新したり、基本情報を最適化するためのアドバイスをもらえたりする機能です。そのほか競合を含めた順位の計測や口コミ促進機能なども搭載しており、業者に依頼するのとほぼ変わらないレベルのMEO対策を行えます。
さらにMEO対策ツールの場合、専門業者に依頼するよりも低価格で利用することができます。ツールやプランによって異なりますが、ひと通りの機能が備わった製品でも月額1500円程度から始めることが可能です。長いビジネスとして捉えた場合、コストパフォーマンス面から見てツールの活用がおすすめだと言えます。
MEO対策ツールを活用してビジネスを拡大させよう!
MEO対策は、店舗ビジネスにおいて効果的な集客施策です。Googleマップ検索において上位表示されることでユーザーの目に留まりやすくなり、新たな顧客を獲得できる可能性があります。しかしMEO対策は手間と時間がかかるうえ、継続して行わなければいけません。
そこでおすすめしたいのがMEO対策ツールです。MEO対策ツールは上位表示を目指すためのさまざまな機能を搭載しており、効率的かつ効果的に施策を進めることができます。気になる方はぜひ試してみてください。
投稿 MEO対策とは?メリデメや実施の方法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 マーケティングと広告の違いとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、マーケティングと広告の違いについて解説します。自社のプロモーション活動を最適化する方法もご紹介しますので、マーケティングを活用して広告効果を高めたい方は参考にしてください。
マーケティングと広告の違い
まずは、マーケティングと広告それぞれの特徴と違いをご紹介します。
マーケティングとはなにか?
マーケティングは、製品やサービスを顧客に提供する際に企業が取り組むべき戦略的活動です。製品やサービスの開発・販売促進・価格設定・販売戦略・サービス提供など、さまざま要素が含まれます。マーケティングでは、消費者とのコミュニケーションや顧客関係の構築を重視する、双方向コミュニケーションが基本です。
広告とはなにか?
広告は、メディアを利用して製品やサービスを消費者に伝える手段のことです。テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット・看板などのメディアを使って、消費者に製品やサービスの情報や魅力を広く伝えることが目的になります。ただし広告は、しばしば企業のメッセージを一方的に伝える手段になることがあるので注意しなければなりません。
広告はマーケティングの一部である
広告は、製品やサービスを売り出すための手段であり、テレビやネットなどのメディアを利用して、消費者へ製品やサービスの価値を一方向にアピールすることを目的とします。
一方で、マーケティングとは、顧客層を正確に理解し、双方向コミュニケーションを通じて顧客のニーズや要望に応えるプロモーション戦略を策定することを目的とします。たとえば、顧客のフィードバックを収集し、製品やサービスの改善に役立てるなどの取り組みがあります。
つまり、マーケティング戦略の一部として広告が組み込まれます。広告が一方向的なコミュニケーションになりがちなのに対し、マーケティング戦略を用いることで双方向のコミュニケーションが可能になる点が大きな違いです。
さらに、広告だけでなくマーケティング全体を活用することで、製品開発や企業戦略の策定プロセスにも影響を与えられる点が大きな違いであると言えます。
なぜ広告にマーケティングが必要なのか?
一方向的な広告に対して、なぜ双方向的なマーケティングが有効であるかについて解説します。
広告効果を最大限に発揮できる
マーケティングを行うことによって、ターゲット顧客層を正確に特定し、価値のある製品やサービスを消費者に届けることができます。マーケティングを活用して訴求対象を明確にすることで、効果の薄い広告を削減してROIを向上させることが可能です。
プロモーション活動を最適化できる
広告を活用したプロモーション戦略はマーケティングにおいて不可欠です。しかし広告だけでは、消費者に対して直接的な促進ができず、最終的な製品やサービスの購入まで至らない可能性があります。広告の効果は消費者への認知度向上やブランドイメージ構築の訴求に充分な効果を発揮しますが、そこで止まってしまうのが一般的だからです。そのため、プレゼント配布や割引キャンペーンなどのセールスプロモーション戦略を用いることで、マーケティング活動が消費者の購入意欲を刺激し、販売促進につながります。
自社と競合他社を差別化できる
同じような製品やサービスを提供する企業が複数ある場合、製品の魅力をそのまま広告を用いて伝えても競合他社の製品を選択されるリスクは避けられません。そのため、広告を打つ際には他社との差別化が必要です。
魅力的なキャンペーンの提示やユーザー目線に立ったメッセージ性のある広告など、ターゲットを理解していなければ広告は成功しないことが多くなるからです。
マーケティング戦略を活用することで、顧客の視点から自社の製品やサービスの魅力を最大限に引き出し、競合他社との差別化を実現し、効果的な広告戦略を展開することができます。
販促課題と製品課題の改善につながる
マーケティング活動を通じて、現行の広告キャンペーンや製品開発における問題点を明らかにし、改善することができます。たとえば、マーケティング分析を通じて、潜在顧客に対してはTVコマーシャルよりも専門性の高い雑誌広告が最適であると発見することがあります。
また、製品が市場のニーズに応えられていないことが明らかになれば、製品開発のプロセスにおいても役立つでしょう。たとえば、安さと高品質を売りにした製品であっても、消費者の求める機能性やデザイン性が不足しているようでは「売れる製品」にはなりません。消費者が求める機能性やデザイン性についても改善していく必要性が生じるでしょう。
マーケティング活動を通じて、製品開発・広告・販売といった全プロセスで改善が見込めます。これにより、市場での競争力を向上させ、より効果的なプロモーション戦略を展開して、新たなビジネスチャンスを切り開くことができます。
マーケティング戦略を活用して広告効果を高めるポイント
実際に広告を打つ際に、効果的なマーケティング戦略を用いて広告効果を高める方法について解説します。
マーケティングと広告の目的を明らかにする
広告の目的は、自社の製品やサービスを世間に広く知らせることにあります。一方で、マーケティングの目的は、消費者について理解し、消費者のニーズに対応する製品やサービスを提供することです。
そのため、広告を単に打ち出すことだけを目的にせず、マーケティング目標を達成するための手段として広告を活用することが重要です。
ターゲットや潜在顧客の趣向を把握する
広告は企業の伝えたいメッセージを一方的に発信するだけでなく、ターゲット層や潜在顧客に向けて発信する必要があります。顧客に共感を得られる広告は、使用するメディアやデザインが異なります。
顧客のアンケート調査、ご意見やご要望、SNSやブログなどを活用した顧客との対話など、顧客との双方向コミュニケーションが重要になるからです。
広告を展開する際は、ターゲット層の好みを把握し、適切なメディアやデザインを選定しなければなりません。さらに、ソーシャルメディアやAIなどを用いたインタラクティブ広告もマーケティングの機能の一部として活用することもできます。
自社と他社の強みや弱みを理解する
マーケティング活動により、自社と競合他社のポジションを把握できます。それにより、自社製品やサービスの強みと弱みを理解し、顧客に正しい情報を伝えることにつながります。
たとえば、SWOT分析を用いて自社と競合他社の強みと弱みを詳細に分析すると、市場のニーズに対応した戦略を立案できます。
マーケティングを活用して広告効果を高めよう
マーケティングと広告は、自社の製品やサービスを成功させるために重要な要素であり、どちらも欠かせないものです。マーケティング戦略を活用し、ターゲット層のニーズを把握して適切な訴求を行うことで、プロモーション活動を最適化できます。
広告を出して売上アップを狙っても効果を感じられない場合は、マーケティング戦略を取り入れて広告の効果を高めましょう。
投稿 マーケティングと広告の違いとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MAツールの導入で失敗する理由と事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、MAツールの導入に失敗する理由とその解決法についてご紹介します。なぜMAツールの導入で失敗してしまうのかを参考にして、ぜひ運用の改善につなげてください。
MAツールの導入に失敗する理由と失敗事例
まずは、失敗事例を交えながらMAツールの導入に失敗する理由を解説します。よくある失敗体験から、MAツールを効果的に導入する方法を把握しましょう。
MAツールの導入目的が不明瞭である
MAツールの失敗事例のなかには、なんとなくMAツールを導入してしまったケースが少なくありません。したがって、MAツールをどのような目的で導入するのか明確にすることが重要です。たとえば、リード獲得の強化、顧客満足度の向上、営業プロセスの改善などに応じてツールの選択やカスタマイズが必要です。
また、MAツールを導入した後のKPIやKGIを設定していなかった事例が多く、MAツールの導入前と導入後の効果測定が不明瞭であることもあります。MAツールの導入と運用には具体的な数値目標を掲げ、PDCAやDCAPなどの改善も含めて検討する必要があります。MAツールをなんとなく導入すると、正しい効果を得ることはできないので注意しましょう。
コンテンツやリード数が少ない
MAツールを導入したことによって作業時間の短縮には成功したものの、売上拡大やコスト削減に効果を発揮しないケースもあります。
MAツールは、膨大なコンテンツやリードを管理するために用いるツールですが、これらのリソースが不十分な状態でツールを導入しても、MAツール本来の目的を果たせるとは言えません。MAツールを導入する前に、まずはコンテンツ戦略やリード獲得を改善することが重要です。
スキルや人的リソースが不足している
マーケティングの仕事をサポートするMAツールでは、専門的なスキルや経験が必要になることが少なくありません。したがって、スキルや人的リソースが不足している場合には、思ったような効果が出ない事例が多くあります。
大企業であれば、マーケティングには担当の専任部署を設けて、リードジェネレーションやセールスファンネル管理などを専門的に実践するのが一般的です。しかし、日本の多くの企業では、マーケティングを担当するのは、営業部やシステム部との兼任の場合が多いです。そのため、スキルやリソースが不足したままマーケティングを実践してしまい、思ったような効果が出ない事例が多くあります。
最近では、日本政府観光局もデジタルマーケティングの専門部署を立ち上げており、マーケティングには専門性が必要であることが示されています。マーケティング担当部署を設置することは難しくとも、最低限でも広報担当者は専任の部署を持っておくのが望ましいでしょう。
ツール導入前にプロセス設計をしていない
MAツールを導入するには、ペルソナやカスタマージャーニーマップなどの設計が欠かせません。よくある失敗例が、MAツールを導入したものの、メール配信やレポート作成などの一部機能しか活用できないケースです。その背景には、ツール利用者のスキル不足もあるでしょう。MAツールを効果的に活用するためには、プロセス設計を含めた包括的な利用が必要です。
MAツールを正しく活用するには?
では、実際にMAツールをうまく活用するにはどのような方法があるでしょうか?その答えはいくつもありますが、特に押さえておくべき項目について解説します。
MAツールの導入目的を整理する
はじめに、MAツールの導入目的を明確にする必要があります。会社ごとにMAツールを導入する理由は異なるため、まずは市場調査、戦略の策定、そして実行評価の3つのステップから自社にとってのMAツールの目的を整理しましょう。
たとえば、顧客との関係強化を目的とする場合はメール自動配信機能、リードの分析を目的とする場合はリード・スコアリング機能を利用することができます。マーケティングに必要なスキルについては、こちらの記事も参考になるでしょう。
コンテンツ制作やリード獲得を強化する
MAツールを導入しても、コンテンツやリード数が不足している場合は、効果が期待できません。そのため、MAツールの導入に加えて、コンテンツ制作やリード獲得の強化にも取り組む必要があります。
たとえば、自社製品やサービスに関連する記事や動画をWebサイトに公開したり、メール会員の登録ユーザーを増やしたりすることで、処理するデータ量を増やす必要があります。SEO対策やコンテンツマーケティングに力を入れることで、MAツールの効果を最大限に引き出すことが可能です。
MAツールに専任の担当者をつける
MAツールを効果的に活用するには、専任担当者の存在は不可欠です。マーケティングの専任担当者がいることで、市場や顧客のニーズを正確に把握し、それに基づいたマーケティング施策を計画・実行することができるからです。また、データ分析や市場動向の把握、コンテンツの企画・制作など、多岐にわたる業務を担当することができます。
オートメーション化することで労力を削減することはできますが、競合他社との差別化や市場動向の把握といった複雑なマーケティングを極める担当者をきちんと育成しましょう。
ベンダーのサポートや外部委託に頼る
専任の担当者の確保や育成が難しい場合、外部委託に頼ることも1つの選択肢となります。マーケティングに関する相談やアドバイスを受ける場合、マーケティングに特化した専門家やコンサルタントのサポートを受けるのが一般的です。
また、MAツールのサポートを利用することで、一般的なマーケティングの知識やトレンドについての情報提供、ツールを活用したマーケティング戦略の提案などを受けられる場合もあります。そのため、ツール提供元のサポートサイトやマニュアル、または利用者コミュニティなどで情報収集を行い、必要に応じてマーケティングの専門家やコンサルタントに相談するのがおすすめです。
MAツールを正しく運用してマーケティング活動をサポートしよう
MAツールを導入することで、マーケティング活動をより効果的にサポートすることができます。ただし、失敗しないためには、まず自社のマーケティングについて整理し、ツールを利用する担当者を育成する必要があります。
また、必要に応じてベンダーやコンサルタントに相談することで、MAツールを正しく運用し、マーケティング活動の成功につなげましょう。
投稿 MAツールの導入で失敗する理由と事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 デジタルマーケティングの業務や必要なスキル は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>デジタルマーケティングの業務内容
デジタルマーケティングの業務内容には、「企画立案」「企画実行」「効果測定」の3つがあります。順番に解説していきます。
1.企画立案
企画立案では、商品やサービス、顧客などの情報を詳しく理解し、デジタルマーケティング実施後の目標を設定していきます。また、一言にデジタルマーケティングと言ってもSEO対策やWeb広告、SNSなどさまざまな施策があります。どの施策で、目標達成を目指すのかも企画立案の段階で決めていきます。
2.企画実行
企画実行では、企画立案で決めたデジタルマーケティングの施行案を社内やクライアントにプレゼンしていきます。その後、決定したデジタルマーケティングの施策を実行します。デジタルマーケティングは、エンジニアやライター、デザイナーなどと協力して進めていくことも多いです。
3.効果測定
効果測定では、企画実行から一定期間が経過したところで、効果の測定を行います。効果測定の結果をもとに施策の改善や修正を行い、目標達成を目指します。
デジタルマーケティングに必要なスキル
デジタルマーケティングには、さまざまなスキルが必要です。そこで、デジタルマーケティングに必要なスキルを7つご紹介します。
1.マーケティング知識
デジタルマーケティングには、さまざまな種類の施策があり、企業が扱っている商品やサービス、ユーザーの年齢層や性別によって、施策を変えていく必要があります。そのため、どの施策を選べばどのような結果が得られるのか把握し、適切に選択するマーケティングの知識と経験が求められます。
2.コミュニケーション能力
デジタルマーケティングを行う際は、エンジニアやライター、デザイナーなどさまざまな人と協力して進めていくことが多いです。そのため、他部署や外部の方々と上手く付き合えるコミュニケーション能力が求められます。
3.情報収集能力
デジタルマーケティングは、数か月や1年単位でトレンドが大きく変化します。そのため、今実施している施策よりも優れた施策が数か月後には出てくる可能性が十分にあります。トレンドの情報をいち早くキャッチし、自分のものにするためには、常に情報収集をしておく必要があります。
4.企画促進力
デジタルマーケティングにおいて最も重要なのは、決めた企画を行動に移すことです。反対に、どんなに優れた企画を思いついたとしても行動に移すことができないのであれば意味がありません。デジタルマーケティングの手法には、明確な正解はありませんが、答えがない中でも何かしらの仮説を立て、進めていく企画促進力が必要となります。
5.好奇心
デジタルマーケティングは分野が非常に広いため、さまざまなことに興味を持ち、常に新しい技術や価値観を取り入れようとする好奇心が必要です。また、現在トレンドの手法や他者が実施している施策を見て、「なぜこの手法は上手くいっているのか」「この点をもっと工夫したらより良い成果が生まれるのではないか」「あの企業が成功した手法を改良して自社に取り入れたら、自社でも成果が出るのではないか」と多角的な目線で物事を考える力も重要となります。
さらに、デジタルマーケティングはインターネットやIT技術を駆使して行うマーケティングですが、ユーザーのニーズ把握のために、ときには店舗で直接ユーザーにインタビューして情報を集めるなど行動力が求められます。好奇心を絶やさず、行動につなげていける人がデジタルマーケティングには必要です。
6.AIやビッグデータに関する知識
近年、AIやビッグデータなど最新のIT技術を使用してデジタルマーケティングに取り組む企業が増えています。AIやビッグデータを活用すると、市場の未来予測やデータ分析が簡単に行えるようになります。また、人手不足の解消にもつながります。このように、少子高齢化により労働人口が減少している日本において、AIやビッグデータを活用したデジタルマーケティングは今後必須となるでしょう。
7.マーケティングツール活用力
マーケティングツールを使用して、デジタルマーケティングを行うのが一般的です。そのため、マーケティングツールを上手く活用する力が求められます。
マーケティングツールは多くの企業からリリースされており、初心者でも操作しやすい製品も数多く存在します。使いこなせるか心配な場合は、サポートが手厚いマーケティングツールを選ぶと良いでしょう。
デジタルマーケティングに役立つ資格
デジタルマーケティングは、専門知識を必要とします。そして、その知識は資格の取得によって証明できます。本項では、デジタルマーケティングに役立つ資格を3つご紹介します。
SEO検定
SEO検定とは、一般社団法人全日本SEO協会が主催するSEOに対する検定です。4級〜1級まで4つのレベルがあります。SEO検定を取得することで、Webサイト検索で記事を上位表示させるために必須となるSEOに関する知識が身に付きます。合格率の平均も約70〜80%と比較的高いため、初心者にもおすすめです。
Google広告の認定資格
Google広告の認定資格とは、Google広告に関する知識を問うGoogle公式の認定資格です。試験は「検索」「ディスプレイ」「ショッピング」「動画」「アプリ」「測定」の6つの科目から問題が出題されます。Google広告認定資格を取得することで、Google広告に対する専門知識があることを明示できます。
Webアナリスト検定
Webアナリスト検定とは、ホームページやブログなどのアクセス解析やデータ分析を行い改善へとつなげていくための基礎知識を学べる資格です。主にGoogle Analyticsを使用してアクセス解析やキーワード分析を行うための知識を取得できます。ホームページやブログを用いてデジタルマーケティングを行う予定の方に、取得をおすすめします。なお、より深く学びたい方は、Webアナリスト検定のワンランク上の資格である「ウェブ解析士」を取得するのもおすすめです。
デジタルマーケティングに必要なスキルを磨こう
デジタルマーケティングは非常に専門的な領域のため、マーケティング知識や情報収集力、AIやビッグデータに関する知識など専門的な知識を多く求められます。自社にデジタルマーケティングの知識保有者が少ないと感じている企業は、資格を取得したり、セミナーに参加したりして、デジタルマーケティングに必要なスキルを磨いていきましょう。
投稿 デジタルマーケティングの業務や必要なスキル は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 デジタルマーケティングに失敗する5つの理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、デジタルマーケティングが失敗する理由と事例を解説します。これからデジタルマーケティングに取り組む企業や、過去にデジタルマーケティングに失敗して再挑戦を考えている企業の方は、ぜひ参考にしてください。
失敗理由1:ターゲットが明確でない
デジタルマーケティングを実施するとなると、サイトのPV数の増加やSNSのフォロワーの増加などデジタルマーケティングを行うこと自体が目的となってしまっている場合があります。しかし、あくまでもデジタルマーケティングは手段であり、目的は顧客に質の高い価値を提供し、自社の売上を向上させることです。そのためには、自社の商品やコンテンツを提供するターゲットを明確に設定し、ターゲットのニーズの理解に努める必要があります。
しかし、デジタルマーケティングに失敗する企業の多くは、ターゲットが明確に定まっていない場合が多いです。ターゲットが不明確ということは、ゴールが定まっていないことを意味するため、デジタルマーケティングに失敗する可能性は必然的に高まります。
失敗理由2:施行期間が短すぎる
デジタルマーケティングにはSEO強化やSNS運用、WEB広告の活用などさまざまな取り組みがあります。しかし、どの手法を選択したとしても、一定期間は選定した手法に継続して取り組む必要があります。
デジタルマーケティングが上手く行かない企業の多くは、施行期間が短すぎる傾向にあります。そのため、デジタルマーケティングに失敗した企業は、施行期間が適切であるかを今一度確認するのがおすすめです。また、結果が出ないからといって、施策を頻繁に変更するのも失敗の原因となります。
失敗理由3:スキルが不足している
デジタルマーケティングで成果を上げるためには、マーケティングに対するスキルとマーケティングツールに対するスキルが必要です。しかし、デジタルマーケティングで失敗する企業の多くが、この2つのスキルのうちどちらかあるいは両方が大きく不足しています。そのため、社内でスキルが不足していると感じる企業は、スキル保有者を補いましょう。
最近は、サポートの手厚いマーケティングツールを提供している企業も多く存在します。また、プロの専門家によるマーケティングセミナーを開催し、マーケティングツールの使い方だけでなくマーケティングに対する知識を教えてくれる企業もあります。このような企業のマーケティングツールを活用すれば、マーケティング初心者の企業でもスキルを身に付けられます。また、マーケティングツールを使いこなせないといった失敗もなくなります。
失敗理由4:誤った手法を選択している
誤ったマーケティング手法を実行していては、望んだ成果は得られません。また、企業によって適切なマーケティング手法は異なります。たとえば、10代、20代の女性をターゲットとしている企業ではSEOを強化するよりもInstagramやYouTubeなどのSNSを強化したほうが上手く集客できる可能性が高いです。一方で、企業向けの会計サービスを提供している企業は、SNSよりもSEOを強化して検索流入でサイトへ集客したほうが効果的です。
一定期間施策を実行してみて、成果が得られないようであれば、現在実施している施策が自社にとって適しているかを検討しなおすのが良いでしょう。
失敗理由5:運用するための資産が不足している
デジタルマーケティングを運用するためには、運用資金が必要になります。しかし、サイトの開発に費用をかけすぎて運用費用が足りなくなってしまう失敗事例も少なくありません。そのため、これからサイト開発を行う企業は、あらかじめ運用に回す資金を考えたうえで、開発費用を決めましょう。
失敗事例:ZOZOSUIT
デジタルマーケティングの失敗事例としてZOZOSUITの事例を紹介します。
大手アパレルECサイトのZOZOは、2017年にZOZOSUITを発表しました。ZOZOSUITは、専用のスーツを着て、スマートフォンで撮影を行うことで、自分の詳細な体型を正確に計測できるといったサービスでした。
ZOZOは、ZOZOSUITの導入によって、ECサイトで商品を購入する際に一番のデメリットである商品の試着ができない点を解決しようと考えました。自分の体型を計測するためには、水玉のマーカーをデザインした全身タイツを着用して回転する必要がありました。しかし、着用するのが面倒、マーカーを読み取れないなどの使い勝手の悪さもあって、2022年6月にZOZOSUITはサービスが終了となりました。
このように、企業と顧客のニーズがズレていたりサービスの品質が不十分だったりすると、ZOZOSUITのように失敗する可能性が高くなります。
デジタルマーケティングの成功に必要な3つのポイント
では、デジタルマーケティングで成功するためにはどうすれば良いのでしょうか。本項では、デジタルマーケティングの成功に必要な3つのポイントを解説します。
1.目的とターゲットの明確化
デジタルマーケティングを行う目的と、デジタルマーケティングによって影響を与えたいターゲットが明確になっていない企業は高確率で失敗します。デジタルマーケティングを導入して「売上を3倍にする」「10代〜20代の女性をターゲットに施策を行う」など、デジタルマーケティングに取り組む前に一度自社内で目的とターゲットをできる限り明確にしましょう。
2.ターゲットの理解を深める
ターゲットのニーズをいかに理解しているかが、デジタルマーケティングでは重要となります。そのため、商品購入者やサービス利用者へ定期的にアンケートを実施したり、店舗を構えている企業であれば顧客に直接インタビューを行ったりするなどしてターゲットとなる顧客の理解を深めましょう。その結果をもとに、デジタルマーケティングで施策を実行していきます。
3.正しい手法を選択し、ツールに費用をかけすぎない
デジタルマーケティングツールには数多くの種類が存在し、機能や価格帯もさまざまです。しかし、高額すぎるツールは、運用コストがかさむため注意が必要です。
最近は、安価な月額で利用できるマーケティングツールが非常に充実しています。また、無料お試し期間がついているツールもあるため、無料期間で自社に向いているツールか見極めるのも良いでしょう。デジタルマーケティングの手法の選択に困ったときは、一度プロの専門家にアドバイスをもらうのもおすすめです。
焦らず着実にデジタルマーケティングに取り組もう
デジタルマーケティングで成功するためには、一定期間時間がかかります。本記事で紹介した失敗理由の多くが、デジタルマーケティングで成果が出るまでの時間を少なく見積もってしまったことによる失敗です。そのため、デジタルマーケティングを実施する際は、焦らず着実に取り組みましょう。
投稿 デジタルマーケティングに失敗する5つの理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 BtoBにおけるデジタルマーケティングの手法とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、BtoB事業者向けにデジタルマーケティングの手法をご紹介します。複数ある手法の用い方や、デジタルマーケティングの動き方も解説しますので、本格運用の参考にしてみてください。
BtoBデジタルマーケティングで用いられる主な手法
BtoBデジタルマーケティングでは主に、以下の目的で手法を活用します。
- リードジェネレーション:見込み顧客を獲得するための活動
- リードナーチャリング:見込み顧客の購入意欲を高めて受注につなげる活動
それぞれ、複数の手法を利用します。まずは、一般的に利用されている手法を見ていきましょう。
リードジェネレーションの3つの手法
見込み顧客をダイレクトに獲得するリードジェネレーションでは、3つの手法を用います。情報提供をもとに、商品やサービスに興味を持ってもらう手法です。オンライン上で一般的に利用されているマーケティング方法なので、まずは3つの手法を確認してみてください。
SEO対策
SEO対策は、Web検索の上位表示を目指して見込み顧客を獲得するデジタルマーケティング手法です。主にGoogleが定めている「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」というルールに従ってコンテンツを作成することにより、上位表示を目指せます。また、読者ニーズを考慮し、興味を引くコンテンツを生み出すことも、評価に大きく影響するのが特徴です。
SEO対策を実施して検索上位に表示できれば、検索した企業担当者の目に留まり、コンテンツを閲覧してもらいやすくなります。その結果、コンテンツを通じてBtoB商品・サービスの問い合わせや購入の申し込みが発生する可能性を高められるのです。
コンテンツ作成において重要な手法のため、デジタルマーケティングを行う際には必ず実施しましょう。
Web広告
Web広告は、検索ページやブログ、サービスサイトといったコンテンツに広告を掲載して、見込み顧客を獲得するデジタルマーケティング手法です。自社サイトだけでなく、外部のサイトにもWeb広告を掲載します。広告掲載料金を支払うことによって、設定した頻度でユーザーに広告が公開されるのが特徴です。
近年では、ユーザーのコンテンツ利用の傾向をもとに、適切なWeb広告を公開できるようになっています。BtoB向け商品・サービスに興味があるユーザーにのみアプローチできるため、生産性の高いデジタルマーケティングが可能です。
ダウンロード資料
ダウンロード資料は、Webコンテンツの中だけでは説明できない商品・サービスを、別資料として提供するデジタルマーケティング手法です。SEO対策といった枠にとらわれず、デザイン性にあふれる表現方法を利用できます。たとえば、次のような資料がダウンロード資料として用いられているのが特徴です。
- 商品カタログ
- パンフレット
- 自社独自の調査・分析資料
ダウンロード資料を取得する際に、個人情報の入力申請画面を準備すれば、顧客情報を取得して、次項で紹介する「リードナーチャリング」の手法として活用できます。
リードナーチャリングの4つの手法
見込み顧客に寄り添い、将来的な購買を狙うリードナーチャリングでは、4つの手法を用います。継続的な情報発信や情報提供がメインとなる手法です。見込み顧客からの信頼性と購買意欲を高められる手法なので、ぜひ参考にしてください。
メルマガ
メルマガは、自社サービスに登録してくれた見込み顧客に対して、一定間隔でメールを送信するデジタルマーケティング手法です。
たとえば、商品・サービスの事例や、新商品の紹介、見込み顧客が興味を持ちそうな内容をメールにまとめて配信します。継続的に情報提供を行うため、見込み顧客に対して、さらなるアプローチが可能です。
アンケート
アンケートは、自社商品・サービスを利用・購入してくれた顧客にアンケートを行い、収集したデータから、傾向やニーズを見出していくデジタルマーケティング手法です。
アンケートを実施すれば、商品・サービスに満足しているポイントや不満を感じるポイント、興味を持ったきっかけなどを把握できます。どのようなマーケティング手法が効果的なのかを推定できるため、今後の動き方や改善点などを検討可能です。
ステップメール
ステップメールは、自社サービスに登録するといったアクションを起こした見込み顧客に対して、事前に設定したメールを配信していくデジタルマーケティング手法です。
特定のアクションごとにステップメールを用意し、ニーズに合う情報を提供することで、見込み顧客の購買意欲を向上できます。顧客の起こしたアクションに合うステップメールを複数用意しておくことで、さらに購買意欲を高めることも可能です。
オンライン商談
オンライン商談は、Web会議ツールなどを活用して、非対面で商談を行うデジタルマーケティング手法です。
移動や商談スペースの準備が不要であることから、スムーズに商談に移ることができます。PC・スマホといったデバイスで簡単に実施できるのが魅力です。オンライン商談を通じて見込み顧客に有益な情報を提供すれば、低コストで商談を成立できるでしょう。
BtoBデジタルマーケティングにおける3つの動き方
BtoBデジタルマーケティングは、活用する手法だけ決めて動き出すのではなく、動き方を決めることが大切です。続いて、BtoBデジタルマーケティングの動き方を3つご紹介します。準備〜運用までに必要な要素を把握していきましょう。
KPIを設定し優先順位を決める
デジタルマーケティングを行う場合には、スタートからゴールまでの道筋にKPI(評価指標)を設定しましょう。運用の段階ごとに評価指標を準備し、実際の評価値と照らし合わせていけば、マーケティングの状況を判断できます。
すべての項目を同等の評価とするのではなく、事前に優先順位を決めておけば、マーケティングの微調整や軌道修正が可能です。
能動・受動のどちらで実施するか決める
デジタルマーケティングは、手当たり次第に実施するのではなく、能動的な「リードジェネレーション」、受動的な「リードナーチャリング」の手法に優先順位を設け、どのような順番で実施するのかを検討しましょう。
一度に両方の手法を取り入れて動き出すと、社内がパンクしてしまう恐れがあります。まずはどのような動き方をするのか決めて、社内の状況を把握したうえで、少しずつデジタルマーケティングの幅を広げていきましょう。
作業コストから動き方を決める
デジタルマーケティングを継続するためには、次のような作業コストがかかります。
- 準備期間
- 作業時間
- 人件費
- システム運用費
デジタルマーケティングには複数の手法があります。ただし予算内で動く必要があるので、一度にすべてを実施するのではなく、最初のうちは無理なく続けられる手法だけにチャレンジしてください。
BtoBデジタルマーケティングの必要性が高まる理由
IT化や働き方改革の影響を受けて、BtoBの事業においてもデジタルマーケティングの必要性が高まっています。最後に、必要性が高まる理由を2つご紹介します。顧客ニーズを把握する重要なポイントなので、デジタルマーケティングを実施する際の参考にしてください。
デジタルテクノロジーの発展
IT化による技術の発展に伴い、現代ではさまざまなデジタルテクノロジーが登場しています。すでに多くの企業でクラウドサービスが利用されており、デジタルを活用した商品・サービスの提供が必要不可欠となっているのです。また、そこに人を呼び込むためには、同じくデジタルを活用したマーケティングが欠かせません。
その一方で、オフラインでテクノロジーを提供する機会は、少しずつ減少しています。オンラインによる事業が普及している現代では、デジタルマーケティングを活用しない手はないのです。
Web検索の一般化
以前まで、Web検索を利用して商品・サービスを購入していた人は少ない状況でした。しかし、近年発生した新型コロナウイルスのまん延やスマホの一般化により、誰もがWeb検索で商品を探すニーズが生まれています。
もちろん企業担当者の多くも、Web検索を利用します。BtoBの商品・サービスをWeb検索で見つけだすユーザーも多いことから、デジタルマーケティングを活用して、見込み顧客にアプローチをかける必要があるのです。
BtoBデジタルマーケティングを実施するために製品を比較検討しよう
BtoB向けの事業で活用できるデジタルマーケティングには複数の手法があり、見込み顧客へのアプローチ方法がそれぞれ異なります。また、マーケティングの手法と一緒に、動き方を理解しておくことも重要です。
ただし、デジタルマーケティングを実施するためには、莫大な労力、時間が必要となります。限られた予算の中で動く必要があるため、マーケティングの効率化が必要不可欠です。
マーケティングの負担を減らして生産性を向上させたいのなら、デジタルマーケティングのシステム・サービスを導入してみてはいかがでしょうか。複数の製品を比較検討して、自社の目的に合うサービスを見つけてください。
投稿 BtoBにおけるデジタルマーケティングの手法とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 デジタルマーケティングとは?目的とビジネスへのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、デジタルマーケティングの基礎知識を詳しくご紹介します。デジタルマーケティングの目的やWebマーケティングとの違い、ビジネスに利用するメリットも解説しますので、今後の業務手法のひとつとしてご検討ください。
デジタルマーケティングとは?
デジタルマーケティングとは、デジタル技術を駆使して、オンラインで取得できるデータを活用するマーケティング手法のことです。たとえば、次のような情報媒体から、マーケティングに利用するデータを取得します。
- ポータルサイト
- Webメディア
- 検索エンジン
- メール
- アプリ
- SNS
- 動画サイト
対象のデジタルコンテンツは多岐にわたり、インターネットでつながる媒体であれば、そのほとんどをデジタルマーケティングに活用できます。では、取得したデータをどうやって活用するのでしょうか。
まずは、デジタルマーケティングの目的とWebマーケティングとの違いについてご紹介します。
デジタルマーケティングの目的
デジタルマーケティングは、以下のデジタル施策の効率化を図るために実施します。
- データ収集・分析(ビッグデータの蓄積・ニーズの分析)
- 広報(Web広告・メルマガ・コンテンツ作成)
計画的にサービスを提供するためには、収集したデータにもとづく計画の立案が欠かせません。この際に利用できるのが、オンラインから取得できるユーザー情報や世の中のニーズです。蓄積した情報を分析して方向性を検討、また検討した内容から広報などの施策を実施することで売上効果を期待できます。
現在、世の中のデジタル化に伴い、デジタルコンテンツを活用して売上を向上させる企業が増えている状況です。同業他社より突出したサービスを提供するため、マーケティング手法のひとつとしてデジタルマーケティングの必要性が増しています。
デジタルマーケティングとWebマーケティングの違い
デジタルマーケティングと似たマーケティング手法として「Webマーケティング」があります。Webマーケティングとは、Web上で取得できるデータを活用する手法です。主に、自社で提供するコンテンツ(ホームページやサービスページ)の「訪問者の動き」などを分析して、効果的な施策を検討します。
ここからも分かるように、WebマーケティングはWebに特化したマーケティング手法なので、デジタルマーケティングの一部として位置づけられているのが特徴です。オンライン全体のマーケティングは「デジタルマーケティング」、その内のWebに特化したマーケティングは「Webマーケティング」という違いがあります。
デジタルマーケティングをビジネスに利用する5つのメリット
デジタルマーケティングをビジネスで活用することには、合計5つのメリットがあります。業務効率化、生産性向上、売上の上昇など、幅広いメリットがあるので、自社で抱える課題と見比べつつチェックしてみてください。
メリット1:マーケティングのコストを削減できる
デジタルマーケティングを活用すれば、マーケティングのコストを大幅に削減可能です。例として、従来のマーケティング手法では、次のようなコストがかかります。
- 情報収集・整理・分析を手動で行う人件費
- 経験にもとづく施策実施による調整作業
- マーケティングの外注費
マーケティングを外注している場合には、委託費が継続して発生します。また、自社でマーケティングを行う場合には、データを取り扱う人件費や調整作業が欠かせません。
一方、デジタルマーケティングのシステムを導入すれば、情報収集の自動化が可能です。委託費用や人件費を削減できるため、自然とマーケティングコストを削減できます。
メリット2:ノウハウの属人化を防止できる
デジタルマーケティングを導入すれば、従業員の経験に頼らず計画的なマーケティング施策を用意できます。
従来のマーケティングでは、担当者の経験による判断で施策が決定されていました。しかし、効果にブレがあるだけでなく、ノウハウが属人化してしまうため、他の担当者では対応できなくなってしまいます。
一方、デジタルマーケティングを活用すれば、システムのルールに合わせてノウハウを準備可能です。初心者でもすぐに内容を理解できるデジタルマーケティングを実施できるため、成功率の低い自己判断に比べて施策の成功率を向上できます。
メリット3:生産性の高いマーケティングを実施できる
デジタルマーケティングのシステムを導入すれば、データ収集・分析をほぼ自動化してマーケティングの生産性を向上できます。データ収集のルールを決めてしまえば、継続してデータを自動収集してくれるのが特徴です。人力での作業を削減できるほか、リアルタイムで最新の情報を取得できます。
また、データ分析においても最新のデータを活用して表やグラフにまとめてくれるため、時間をかけず高品質な根拠データを準備できるのが魅力です。
メリット4:営業部門の人件費を削減できる
デジタルマーケティングを活用して集客性・売上を向上すれば、営業の負担を削減できます。足で稼ぐ営業から、オンラインを駆使した集客方法に移行できれば、人件費を抑えられるでしょう。また、デジタルマーケティングによって取得したデータを利用して見込み顧客にアプローチをかけるなど、効率的な営業活動が可能となります。
メリット5:見込み顧客を漏れなくカバーできる
デジタルマーケティングは、顧客情報などを収集・分析できることから、提供しているサービスの見込み顧客を漏れなくカバーできます。
従来のマーケティングでは、おおよその見込み顧客を想定できるものの、精度に大きなブレがありました。効率的に動けないと、営業アプローチに漏れが生じるケースもあるでしょう。一方、デジタルマーケティングを活用すれば、アプローチをかける優先順位を決定できるため、手広いアプローチが可能となります。
デジタルマーケティングの必要性
情報化社会が進む日本においては、デジタルマーケティングの必要性が高まっています。特に近年では、これまで以上に必要性が増している状況です。
最後に、企業活動においてデジタルマーケティングが欠かせなくなっている理由を2つの視点からご紹介します。
非対面コミュニケーションの増加
新型コロナウイルスのまん延をきっかけに、日本中の企業でテレワークが浸透しました。人々の働く時間が変化したり、Web会議などの非対面コミュニケーションが増加したりしている状況です。
非対面コミュニケーションが増えると、その分だけデジタルを利用するユーザーが増加します。世の中の需要がデジタル寄りになるにともない、見込み顧客を探し出す手法として、デジタルマーケティングの有用性、そして必要性が高まっているのです。
働き方改革の導入
国が提示した働き方改革の影響を受けて、日本中の企業が「業務効率化」「生産性向上」に力を入れるようになりました。マーケティング手法の検討も例に漏れず、働き方改革への対応として必要不可欠となっています。
より効率的なマーケティングを実施するためにも、現代のニーズをくみ取れるデジタルマーケティングの必要性が高まっているのです。
デジタルマーケティングの基礎知識を理解したら製品を比較しよう
デジタルマーケティングは、現代日本の情報収集・分析に必要不可欠なマーケティング手法です。従来のマーケティングを効率化できるだけでなく、コストを大幅に改善できます。
デジタルマーケティングを活用するためには、システムを導入するのが効率的です。各製品の特徴を比較検討して、自社に合うサービスを探してみてください。
投稿 デジタルマーケティングとは?目的とビジネスへのメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客はどんなサイトに必要なのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>コンバージョンにつながりにくい理由としては、商品そのものに課題があることもありますが、多くはサイトに問題があります。
たとえば商品が原因とならないコンバージョン率の低さの要因には以下のようなものがあります。
・直帰率や離脱率が高い
・サイトの使い勝手が悪く、訪問者が見たいページに行きつけていない
・サイト側がアピールしている商品・コンテンツが見られていない
・入力フォームが使いづらい
・商品検索がしづらい
Web接客は、サイトになんらかの課題があり、それだけでは売上やコンバージョン率が芳しくない場合に特に必要になります。
Webサイトの使い勝手や、視認性を向上するための行動はもちろん必要です。しかし、並行してWeb接客を行うことで、サイトの欠点をフォローしつつコンバージョン率の向上が可能になります。
接客の本質はユーザーの満足度を高めることにあり、売上やコンバージョン率の向上はその結果です。実店舗では、とても対応のよいスタッフがいたことが理由となってリピートにつながったり、訪問回数が増えたりといったことが珍しくありません。
そのような好循環をWebサイト上でも起こすのが理想です。Web接客はそのための手段です。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客はどんなサイトに必要なのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客の代表的なシナリオとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>代表的なものを紹介します。
・ポップアップ型のシナリオ
ポップアップ型におけるシナリオとは、Webサイト上でのユーザーの特定の動きに合わせてポップアップウインドウを表示させるというものです。
たとえばサイト上で購入を一定時間悩んでいるユーザーに対し「30分以内に購入すれば今回から使用できるクーポンを配布」といった購入の後押しをするものや、商品詳細ページで一定時間が経過した場合に「ご不明な点はございますか?」と相手の不安を取り除くための声かけの役割をするものなどがあります。
・チャット型のシナリオ
チャット型のWeb接客ツールでは、人間のオペレーターが直接対応するものと、チャットボットが半自動的に対応するものがあります。そしてチャットボット型には、自由な質問に対してAIが回答をするものと「お悩みのことは以下の中でどれですか」というような選択肢を提示して、選択されたものに対して自動的に答えを出すというものがあります。後者のものをシナリオ型といいます。
ユーザーが選ぶ選択肢とそれに対する回答メッセージをあらかじめシナリオ(道筋)として設定しておくので、シナリオ型と呼ばれています。
例えば携帯電話キャリアのWebサイトであれば、
・新規契約番号でのご契約
・他社からのお乗り換え
・機種変更のご希望
といった選択肢を提示し、その回答に合わせた次の選択肢がフローチャートのように続きます。これはすべてシナリオとしてあらかじめ設定されています。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客の代表的なシナリオとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールを採用する企業が増えている理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>自社で販売サイトを運営するとなると、そこで販売しているのは自社商品のみです。さまざまな商品が比較できるモール型サイトではなく、自社の販売サイトで購買をしてもらうためには、単に広告配信を強化するだけでは不十分です。自社販売サイトならではの強みを生かし、ユーザーの満足度を上げるために、柔軟な個別対応がリアルタイムに可能なWeb接客ツールに注目が集まっています。
また、Web接客ツール自体の機能の発達も採用が増えている要因となっています。情報を蓄積することで、サイトの訪問回数や滞在時間など、相手に合わせた情報の提示が可能になり、接客を行うツール以上の役割を担えるようになってきています。
さらには、業務効率化につながる点も評価されています。チャット型のWeb接客ツールなら1人の担当者が複数の問い合わせに同時に対応できます。近年では、コミュニケーションツールとして電話やメールよりもチャットタイプのアプリの使用頻度が高まっています。サイトを訪問するユーザーが気軽に使用できるという点も導入を後押ししているといえます。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客ツールを採用する企業が増えている理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールを導入して失敗する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>Web接客ツールは、あくまで「接客」や「お客様対応」を行うツールです。実店舗の場合、過剰な売り込みや不必要な声かけを行うと、かえって売上につながらないものです。つまり、どのような場合であっても「接客すればするほどよい」とは限らないわけです。
このことを理解せずにWeb接客ツールを導入すると、過剰なポップアップウインドウの表示や、執拗なチャット誘導をしてしまい、結果としてコンバージョン率の低下や離脱率の上昇といった悪影響につながりかねません。
ポップアップ型のWeb接客ツールなら営業とマーケティングが、チャット型のWeb接客ツールならカスタマーサポートがその役割です。Webサイトへの訪問客であっても、場所が実店舗からWebに移っただけで、画面の向こうには実際に人がいることには変わりません。Web接客ツールの導入時には、営業担当やカスタマーサポートを配置するのと同様に、適材適所を心がけることが重要になります。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客ツールを導入して失敗する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールを選定するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そのため、せっかくWeb接客ツールを導入しても、きちんと成果が上がっているのかの可視化が難しいことが多くなります。
Web接客ツールにはポップアップ型とチャット型の2つのタイプがありますが、どちらのタイプのWeb接客ツールを導入するにしても、効果検証ができるもの選ぶことがポイントになります。
実店舗と同様に、Webサイト上であっても接客の仕方次第で購入にも離脱にもつながります。接客の有無による効果検証はもちろんのこと、接客の仕方によっても結果にどのような違いが発生したかを検証できるものがよいでしょう。
施策の実行は、あくまで課題解決のためのスタートに過ぎません。施策のやりっぱなしにならず、的確にPDCAを回すためにもWeb接客ツールを選定する際には「効果検証ができるものを選ぶこと」がポイントになります。
効果検証ができることと同様に重視したいのが、運用する側にとって使いやすいツールであるかどうかです。実際に現場でWeb接客ツールの活用を担当する部署の意見を取り入れて、使い勝手のよいものを選ぶことも重要になります。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客ツールを選定するポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールを導入する際の注意点 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>・ツールを導入する目的を明確にする
当然のことではありますが、ツールは導入しさせすればよいわけではありません。ツールを導入する目的は何か、ツールを導入することでどのような効果を期待するのをあらかじめ具体的にしておきましょう。この際に重要なのは「業務を効率化する」「売上を上げる」のような抽象的な目的にしないことです。
現在自社のWebサイトにどのような課題があり、それをどのように解決するためにWeb接客ツールを導入するのかを徹底的に考え抜くことが重要です。
・導入後の運用方法も具体的に決定しておく
また、導入目的と同様に、運用方法も明確にしておく必要があります。たとえばチャット型のWeb接客ツールを実際にスタッフがリアルタイムにやり取りをするのか、するのであればどの部署のどの人物が担当するのか、その間の他の業務はどうするかといった導入後の運用までも検討しておきましょう。
導入したはいいものの、手が空いている人物がいないから使われずに終わってしまったということがないように注意すべきです。
営業・マーケティング目的でポップアップ型のWeb接客ツールを導入する際は、特に注意が必要です。その理由は、ポップアップウインドウはときにユーザーに不快感を与えてしまうからです。
ポップアップウインドウを出すタイミングや頻度によっては、かえってユーザーの離脱を招く可能性も秘めています。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客ツールを導入する際の注意点 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールにはどんな種類があるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>・ポップアップ型は営業やマーケティング向け
ポップアップ型のWeb接客ツールでは、Webサイトにポップアップウインドウでクーポンや案内を表示します。ポップアップウインドウを表示させるタイミングも「特定のページで何秒以上滞在した場合」「特定の画面をスクロールした場合」「戻るボタンで離脱しようとした場合」など、任意で設定できます。また、ユーザーの属性に合わせての表示も可能で、初めてサイトを訪問した場合に初回限定のクーポンを発行するといったことも可能です。
表示させるウインドウのデザインもテンプレートが用意されていることが多く、デザインソフトを使用せずとも簡単に作成できます。
・チャット型はカスタマーサポート向け
チャット型のWeb接客ツールでは、Webサイト上にチャットウインドウを表示させて訪問者とリアルタイムでメッセージのやりとりを行います。
訪問者の質問に対して適切な情報を直接提示したり、疑問を選択肢で表示し、選ばれたものについて回答を表示したりすることができます。
チャットでのやり取り時に、ユーザーは個人情報を入力する必要がありません。気軽に質問できる点でメリットがあります。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客ツールにはどんな種類があるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールによってどんな業務が効率化されるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>チャット型のWeb接客ツールの導入では、オペレーターが行うサポート業務の効率化が期待できます。
オペレーターが行う電話対応や、カスタマーサポートチームが行う問い合わせメールへの返信対応などは、チャットによって効率化が可能です。
すべての電話対応やメール返信対応をなくすことは難しいですが、チャット上のチャットボットによる自動返信で対応できないものに限り、スタッフがチャット対応をするまたはオペレーターが電話対応をするといった仕組みを設ければ、大きく業務効率化が可能になります。
また、チャット型のWeb接客ツールの導入によって、営業時間外でもあってもチャットボットによる自動返信を行うことで24時間対応が可能になります。
チャット型のWeb接客ツールは、運営者側の業務効率化だけでなく、サイト訪問者側にもメリットがあります。電話や問い合わせのメールをおっくうに感じるユーザーは少なくありません。簡単な質問なのですぐに返信がほしいが、電話がつながるまで待たされたり、通話料金がかかったりすることにマイナスイメージがあるユーザーは多いでしょう。
しかし、すぐにその場で返信がもらえるチャットであれば気軽に質問できます。
これにより、聞きたいことが質問できないことによるサイト離脱が防げ、ユーザー満足度の向上につながります。さらには、そもそもの電話問い合わせやと問い合わせメールへの回数の減少も期待できます。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客ツールによってどんな業務が効率化されるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールの基本的な機能とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>・ポップアップによるサイト訪問者へのアクション(クーポン、セール、おすすめ商品情報などの表示)
・チャットを利用した訪問者対応(問い合わせ、質問対応)
・訪問者の属性やサイト上の閲覧ページ履歴、購買履歴などのデータ収集
・収集したデータをもとにした、類似属性へのアプローチ
Web接客ツールには、サイト訪問者の動きに合わせてポップアップウインドウを表示させるものと、チャットでの問い合わせ対応を行うものの2種類があります。
さらに、ツール導入によって得られるメリットとして、データの蓄積や分析ができるようになる点が挙げられます。
サイト訪問者の属性や購入履歴のデータを蓄積することで「この商品を買った人は、あの商品も同時に購入することが多い」「このページを見たあとはあのページを見ている」「この質問が多い」といったデータが収集できます。
それらのデータをもとにして、似た属性の訪問者に対して効果的なアプローチを行ったり、よくある質問に対する返答を自動化したりといったことが可能になります。
ポップアップ型とチャット型で搭載されている機能は大きく異なります。そのため、自社サイトの課題に合わせてツール選択が重要です。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客ツールの基本的な機能とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客ツールでどんな課題が解決できるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>チャット型のツールには実際にスタッフが文字入力を行うものやチャットボットやAIが自動返信するもの、時間帯や状況によってスタッフとチャットボットやAIが切りかわるものがあります。
Web接客ツールを導入することで解決できる課題として代表的なものが、高い直帰率・離脱率と低いコンバージョン率です。
直帰率や離脱率、コンバージョン率は、Webサイトの使い勝手に依存するところが多いです。しかしWeb接客ツールを導入することで、実際の店舗のように、訪問者に合わせた適切な対応が可能になります。いわば訪問者にとって「かゆいところに手が届く」状態にできるといえるでしょう。
また、運営者側がサイト訪問者に届けたい情報を、確実に届けるという点でもWeb接客ツールは活躍します。特にポップアップ型のWeb接客ツールなら、クーポンや、セール情報、新商品の紹介などが容易になります。
Web接客ツールは、課題を抱えるWebサイトの使い勝手をサポートし、ユーザーの満足度を向上させつつ、運営者側の情報発信力も高めるものだといえます。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客ツールでどんな課題が解決できるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【1分解説】Web接客の意味とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>Web接客という言葉からは、ZOOMのようなWeb会議システムを使った、オンラインでの物件内見や、店舗のようすを撮影しながらの接客をイメージするかもしれません。
しかし、Web接客はオンラインシステムを使った対面での接客ではなく、Webサイト上でのチャットツールを使った文字でのやりとりや、サイト訪問者に対して広告やクーポンを画面上にポップアップウインドウで表示させることを指します。
Web接客を行う意味は、実店舗と同じく、訪問者の質問に答えたり、商品購入の後押しをしたりすることです。
Webサイトではアクセス数を増やすためのSEO対策や広告施策が行われますが、これは実店舗でいうところの集客にあたります。しかし、いくら多くの人が集まっても、購入に至らなければ店舗の売上が上がらないのと同様に、Webサイトであっても集客に続く段階である「接客」に力を入れる必要があります。
Web接客を実施することで、商品購入というコンバージョン率の上昇や直帰率・離脱率の改善が見込めます。また、実店舗と同じように、訪問者の属性に合わせた商品をすすめるといった行動によるユーザーの満足度向上にもつながります。
次回以降でWeb接客ツールについても解説していきます。
・Web接客に関する1分解説シリーズはこちら
投稿 【1分解説】Web接客の意味とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Web接客(オンライン接客)で何ができる?ツールの基本機能から利用シーンを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで、従業員の時間を奪わずにセールスの機会を生かしたいなら、Web接客ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。本記事では、Web接客ツールで実現できること、利用シーンについて解説します。
Web接客ではなにができる?
Web接客を導入すると、Webサイトを訪れたユーザーへ自動的にアクションできます。たとえば、おすすめの製品やサービスを紹介したり、キャンペーンの告知をしたりできます。
なお、Web接客とオンライン接客はよく似た言葉ではありますが、オンライン接客がビデオ通話やチャットなどを用いて人が接客するのに対して、Web接客はAIやシナリオ設計が自動で接客するといった違いがあります。
どちらも明確な定義があるわけではありませんが、2つの違いを区別しておくと目的のサービスが見つけやすくなるでしょう。ここでは人を介さないサービスという定義で、Web接客ツールについて解説します。
AIを活用してユーザーの質問や要望に答えられる
AI会話機能を搭載したWeb接客ツールもあり、ユーザーの質問や要望に対してチャットを用いて自動応答で返信できるようになります。ユーザーが投げかけた質問にAIが回答することで、人的コストをかけずにユーザーの求める製品やサービスに誘導することが可能です。
ポップアップ表示でキャンペーンをお知らせできる
プロモーション活動の一環として広告表示を目立たせたい場合、Web接客ツールはユーザーの端末画面にポップアップを表示できます。せっかく企画したプロモーションでも、ターゲットの目にとまらなければ効果を期待できないでしょう。
ポップアップであれば、ユーザーが情報確認する確率が高まり、広告効果が向上してコンバージョンアップも期待できます。
Web行動分析を用いてユーザーデータを収集できる
Web行動分析機能を利用すると、ユーザーが閲覧したWebサイトやチャットボットへの質問内容から行動履歴を分析できます。行動履歴からユーザーの好みや趣向を確認できるため、リアルタイムマーケティングとして活用している企業も少なくありません。
例えば、AmazonやYouTubeなどに表示される「あなたへのおすすめ」のように、ターゲットの行動から分析した最適なアプローチにつながります。
Webサイトからの離脱を防げる
Webサイトにアクセスしたユーザーは、目的の製品・情報が見つからない場合、検索サイトに戻ったり他の検索方法に切り替えたりして離脱する可能性が高くなります。
したがって、情報を見つけやすいユーザーファーストのサイトを作り込むことが重要ですが、サイトマップやワイヤーフレームの改善だけでは優れたUXとは言えません。ユーザーがWebサイトに求めているのはデザイン性ではなく、使いやすい機能性やシンプルな操作性だからです。
チャット機能を備えたWeb接客なら、ユーザーは欲しかった製品や情報に最短距離でアクセスできます。
CVRの改善が見込める
Web接客の導入により、ユーザーへの最適なレコメンドやサイトの離脱率改善が期待できるため、CVRの改善にも効果を発揮します。購入者のモチベーションが高いうちに探していた答えを提供できれば、実際の数値としてWeb接客ツールの導入効果を感じられるでしょう。
実際にWeb接客ツールを導入して、顧客接点を増やすことによって、売り上げが30〜200%増加した実績もあるほどです。WebサイトのCVRの改善に悩むマーケティング担当者にとって必要な機能を提供してくれるでしょう。
Web接客の種類と利用シーン
Web接客は、大きく分けて3種類あります。次に、それぞれの特徴と利用シーンを解説します。
AIと会話する「チャットボット型」
AIチャットボットは、リアルタイムで短文の会話(チャット)のコミュニケーションを自動で返信するプログラムです。ユーザーが投げかけた質問にチャットボットが答えるため、問い合わせが多い質問に対して人が応答する頻度が少なくなります。
ビジネスシーンでは、Webサイトの相談窓口や社内ヘルプデスクの相談窓口として活用できます。Webサイトならチャットを通して顧客が欲しい商品を検索表示したり、社内ヘルプデスクでは属人的に確認をとっていた社内手続きをチャットボットが自動で案内したりできます。
重要な情報を表示する「ポップアップ型」
ポップアップは、スマホやパソコンの操作画面の最前面へ飛び出すように情報表示する機能です。ユーザーは必ずポップアップを見ることになるため、重要な案内や強調したい告知などの表示に用いられます。
ビジネスシーンでは、Webサイトの広告表示や注意書きを強調したいときに利用できます。売り上げアップを狙いたい特別な値引きキャンペーンをユーザーの端末画面に表示したり、チュートリアルとしてユーザーに操作方法を教えたりすることができます。
ポップアップは、ユーザーアテンションを向ける効果が高いことから、さまざまなシーンで利用されています。一方で、その特性からユーザーに敬遠される可能性がある点に注意が必要です。ポップアップについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。
記事:Web接客におけるポップアップとは?どんな効果があるのかを解説
どちらの機能もあわせた「ハイブリッド型」
ハイブリッド型は、チャットボットとポップアップの両機能を持ち合わせたWeb接客ツールです。汎用性が高く、利用シーンに合わせて必要な機能を選択できます。
ただし、ハイブリッド型のWeb接客ツールは、他のツールに比べて高コストなのがデメリットです。予算の無駄遣いにならないように、自社に必要な機能を調べたうえで、最適なツールを選ぶようにしましょう。
ビジネスシーンでは、チャットボット型とポップアップ型どちらでも対応可能です。また、チャットボットの案内をポップアップ表示することで、ユーザーをAI会話へ誘導するといった使い方もできるようになります。
Web接客の事例も確かめてみよう
大切な顧客と従業員のどちらにとってもプラスの効果を得るには、Web接客ツールの導入がおすすめです。
同じ問い合わせを何度も受けた経験のある従業員にとっては、タイムパフォーマンスの向上に驚くほど効果を発揮してくれることでしょう。ある企業では、Web接客ツールの導入により電話問い合わせを30〜50%も削減できた例もあるほどです。
なお、Web接客についてもっと知りたい方には、以下の「Web接客の事例紹介」の記事もおすすめです。
記事:Web接客ツールの事例紹介|利用者のレビューから製品をピックアップ
投稿 Web接客(オンライン接客)で何ができる?ツールの基本機能から利用シーンを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Web接客ツールの事例紹介|利用者のレビューから製品をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、Web接客ツールの事例を紹介するとともに、利用者のレビューや製品の特徴を解説します。Web接客ツールを導入して業務効率化を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。
株式会社インゲージ(ユーザー:20人未満)|ツール:ChatPlus
株式会社インゲージは、クラウドサービスの開発・提供などの事業を展開している企業です。ChatPlusを導入したことにより、メール対応とチャット対応を同一画面で行えるようになり、チャット対応の効率化が進みました。
その結果、対応できる問い合わせ件数が増加し、見込み客とのタッチポイントが増えて、チャットからの問い合わせでのCVが向上しました。
参考レビュー:設定も簡単で導入が楽、API連携もできて便利
ChatPlusはリーズナブルなチャットロボットツールを探している企業におすすめ!
ChatPulsは、チャットサポートツール、AIチャットボットツールです。ChatPulsの特徴は、初期費用0円、月額1,500円〜というリーズナブルな価格で利用できる点です。さらに、トライアル期間として10日間無料でChatPlusをお試しすることが可能です。リーズナブルなチャットロボットツールを探している方や、初めてチャットロボットを導入する企業におすすめだと言えるでしょう。
株式会社シーオーメディカル(ユーザー:100~300人未満)|ツール:FLIPDESK
株式会社シーオーメディカルは、化粧品・サプリメントなどの通信販売を行っている企業です。宣伝・マーケティング部門でFLIPDESKを導入したところ、LINE友だちリストを250%ほど増加させることができました。
FLIPDESKを導入する以前は、Webサイトにバナーを表示させるために、GTMを逐一埋め込んだり、WordPress内で実装したりと手間のかかる方法で作業を行っていました。しかし、FLIPDESK導入後は作業の手間が減り、スピード感を持って施策を進めていくことが可能となりました。具体的には、サイトの適切な場所にLINE友だち登録に誘導するバナー表示させたことによって、登録者の増加がイマイチだったLINE友だちが250%ほど増加しました。
参考レビュー:細かい条件設定など、痒い所に手が届く理想のツール
FLIPDESKは初心者でも使いやすいWeb接客ツールを探している企業におすすめ!
FLIPDESKは、キャンペーン告知や製品の提案、チャットサポートなど、サイトに訪れたユーザー1人ひとりに合わせて最適なWeb接客を提供するツールです。FLIPDESKの特徴は、直感的に操作可能な管理画面です。目的別に効果的なシナリオ例を公開しているため、専門知識を持ち合わせていない初心者でもワンクリックで簡単に操作できます。専門のコンサルタントがつくプランもあるため、導入や運用でつまずいてしまった場合でも安心です。
株式会社JTB(ユーザー:1000人以上)|ツール:KARTE
株式会社JTBは、旅行業を中心に事業を展開している企業です。システム分析・設計分野でKARTEを導入したところ、社内のPDCAサイクルの効率化に成功しました。
導入以前は、会社の規模の大きさから小さな施策を1つ実行するのにもかなりの時間を要していました。しかし、KARTEを導入してからは、ツールの手軽さや自由度の高さ、分析のしやすさのおかげで、施策の実行サイクルが格段に早くなりました。
参考レビュー:CXという言葉を体現したツール
KARTEは幅広いユーザーが使いやすいWeb接客ツールを探している企業におすすめ!
KARTEは、Webサイトやスマートフォンの顧客情報を一元管理・可視化することで、サイトに訪れたユーザー1人ひとりに対して最適なCX(顧客体験)を提供するツールです。
KARTEの特徴は、シンプルで使用しやすいデザインと充実した機能です。「Web接客」「マーケティングオートメイション」「広告配信最適化」「チャットサポート」などWeb接客に必要な機能が充実しています。初心者は直感的に操作でき、上級者は自由度高くカスタマイズできるなど、幅広いユーザーに使いやすいツールです。
株式会社メディカルサポートジャパン(ユーザー:20人未満)|ツール:Ptengine
株式会社メディカルサポートジャパンは、医療系のマーケティングを行っている企業です。Ptengineの導入以前は、担当者や部内の主観的な判断でサイト改善を行っていました。しかし、Ptengineの導入後はユーザー視点でサイト改善を行えるようになりました。
また、社内の人材がマーケティング未経験のため、Google Analyticsだと敷居が高く上手く機能を上手く活かせない状態でした。しかし、Ptengineはヒートマップで分析が行えるため、マーケティング未経験の社員でもツールを使いこなせました。
参考レビュー:GA+Ptengineでのサイト改善
Ptengineは直感的にサイト最適化を行いたい企業におすすめ!
Ptengineは、世界184ヶ国、20万人以上の利用者数を誇るサイト運営プラットフォームです。国内では、Google Anlyticsに次いで利用者数が多いツールであり、顧客満足度は93.4%と高い値を記録していることから、多くのユーザーに信頼されているツールであると言えます。
タグを1つサイトに設置するだけで、直感的な分析とサイト最適化が行えるようになるのが特徴です。ノーコードでさまざまな機能を利用できるため、初心者でも簡単に操作できます。
株式会社イタミアート(ユーザー:100~300人未満)|ツール:Rtoaster
株式会社イタミアートは、印刷業を営む会社です。Rtoasterの導入によって、自社に存在する1万点以上の商品の中から買い合わせの良い商品を自動で選定し、表示させることに成功しました。その結果、客単価の向上につながりました。
また、Webサイト内のポップアップを期間や条件を絞って出し分けることが可能なため、キャンペーンなどの案内が行いやすい点も客単価の向上につながった1つの要因です。さらに、動画のポップアップや期間限定で表示するバナーをコーディングなしで制作可能になったため、作業工数の削減にも成功しました。
参考レビュー:商品を登録するだけで自動で買い合わせの提案ができる
Rtoasterはサポート体制が充実しているWeb接客ツールを探している企業におすすめ!
Rtoaserは、高精度のパーソナライズによって、ビジネス上の課題解決や成果向上を達成するパーソナライゼーション基盤です。解決したい課題に合わせて、以下3つの製品を提供しています。
・Rtoaster action+
ユーザー1人ひとりにパーソナライズされた最適な商品やコンテンツを提供するためのWeb・アプリコンテンツ最適化プラットフォーム
・Rtoaster reach+
ユーザー1人ひとりをパーソナライズした情報により、メールやLINEを送信できるマルチチャンネルメッセージサービス
・Rtoaster insight+
ユーザー1人ひとりにパーソナライズした情報を届けるために必要となるデータを統合し、実行へとつなげるカスタマーデータプラットフォーム
Rtoasterを導入した企業が製品を使いこなせないことがないように、コンサルタントが導入から運用、定着までサポートしてくれます。その結果、2017年〜2020年までの3年間の対応満足度が98.6%を記録しました。Rtoasterは、サポート体制が充実したWeb接客ツールを探している会社におすすめだと言えるでしょう。
自社に適したWeb接客ツールを導入しよう
業種・業界問わず多くの企業が、Web接客ツールの導入により工数の削減や売上向上に成功しています。自社で抱えている課題を洗い出し、自社に適したWeb接客ツールを導入しましょう。
投稿 Web接客ツールの事例紹介|利用者のレビューから製品をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Web接客におけるポップアップとは?どんな効果があるのかを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>ポップアップを上手く活用すると、CVRを改善したりサイトの離脱を防止したりする効果が期待できます。本記事では、Web接客におけるポップアップ型の機能や効果、注意点について解説します。
Web接客のポップアップとは?
Web接客ツールは、Webサイトを訪れたユーザーへ自動的にアクションできる双方向コミュニケーションツールです。チャット型とポップアップ型、またどちらの機能も持ち合わせたハイブリッド型の3種類があります。
このうちポップアップ型とは、適切なタイミングで操作端末にウィンドウを表示することによって、確実にユーザーへメッセージを届けるための仕組みです。
ポップアップはウィンドウからお知らせを表示する機能
ポップアップは、ユーザーの操作端末の最前面にメッセージを浮き上がらせるように表示します。したがって、ポップアップを見たユーザーはボタンをクリックしたり閉じるボタンをクリックしたり、なんらかのアクションをしなければなりません。
視認率はほぼ100%を記録できるため、ユーザーへ絶対に伝えたいキャンペーンの表示やCookieの使用を承認するボタンとして多くの企業が活用しています。
Web接客のチャット型とはなにが違う?
Web接客のチャット型とポップアップ型は、どちらもユーザーのアクションに反応する双方向コミュニケーションである点は同じですが、利用目的が異なります。チャット型がユーザーからのメッセージによって自動応答を返すのに対して、ポップアップ型はユーザーのWeb行動に合わせて自動アクションします。
チャット型はユーザーのメッセージを待つ受動型になる特性がありますが、ポップアップはサイト構築者のシナリオ設計によって設定が可能であるため、能動的なアプローチとなります。
ポップアップ型の仕組み
自ら積極的に表示するポップアップでは、シナリオ設計によって動作を作り込むことができます。たとえば、ユーザーがある製品のWebページへアクセスした際に、30%オフで買えるキャンペーンを表示したり、購入フォームに必要となるデータの入力を求めたりすることができます。
これによってユーザーの作業工数を減らして、必要な情報をユーザーへ伝え、ユーザーに必要な動作を促すことが可能になります。
ポップアップ型にはどんな効果がある?
WebサイトやLP上にメッセージをポップアップ表示することによって、どのような効果を期待できるのか解説します。
キャンペーンを表示してCVRを改善
ポップアップの効果の1つに、CVRの改善が挙げられます。たとえば、キャンペーン情報の表示には顧客の購買意欲を刺激する効果があり、実際の購買行動につながる可能性もあります。また、ユーザーのWeb行動から分析したパーソナライズ化された訴求によって、顧客が求めている最適な製品の紹介にもつながるでしょう。
ボタンクリックを促してサイト離脱を防止
ポップアップ機能は、ユーザーの離脱するタイミングに興味深いオファーを提示することを可能にします。たとえば、ユーザーがサイトにアクセスしてカートに商品を入れたまま離脱するカゴ落ちに悩んでいる場合、ユーザーが離脱する前にポップアップで「送料無料」「お得なセット」などの訴求を打ち出すことでユーザーの離脱を防ぐ効果が期待できます。
ターゲティング機能によりアップセルを実現
アップセルとは、既存顧客に自社のよりハイランクな商品・サービスを利用してもらう営業手法です。ユーザーがすでに自社のサービスを利用しているなら、より快適で高性能なサービスを提案することに成功したら、ユーザーにとっても自社にとっても有益な取引となります。
たとえば、すでにブロンズ会員に登録しているなら、シルバーランクの会員にアップセルといったことが考えられます。また、より高単価な製品・サービスをポップアップ表示して購買につながれば、客単価の上昇にもつながります。
リピーターに特典を表示してLTVを向上
マーケティングを考えるうえでは、既存顧客の定着を図ることも重要です。さまざまな製品・サービスがあふれている現代においては、新規顧客を獲得することは容易ではありません。加えて、新規顧客の開拓には膨大なコストと手間がかかります。
一方で、一度は自社製品を購入したことがある既存顧客は、少なくとも自社製品に興味がある層です。ポップアップで特典を表示して特別感を演出すれば、顧客満足度がアップして自社のより強いファンになってくれる可能性があります。
ポップアップ型の注意点
ポップアップ型はユーザーに強い注意を向けられる点で、能動的なアプローチができる反面、ユーザーに不快感を与える危険性がある点には注意しましょう。ポップアップが出現するたびに、ユーザーはなんらかのリアクションをしなければならないからです。
ユーザーが本当に求めている情報を表示する
たとえば、一度は閉じたはずのポップアップが何度も出現すると、ユーザーはもう2度とWebサイトにアクセスしない可能性も出てきます。そのため、ポップアップの表示では、本当にユーザーが求める情報を提供する必要があります。
Web接客ツールのなかには、ターゲティング機能を持ち合わせた製品もあるため、ユーザー属性、購買履歴などから最適なポップアップが表示されるように工夫する必要があるでしょう。
ポップアップの表示位置とサイズに注意する
ついつい行ってしまいがちなのが、ユーザーのクリック率を高めようと、画面中央に大きなポップアップを表示してしまうことです。しかし、端末操作の邪魔になりすぎて、ユーザーからすぐにポップアップを閉じられてしまう可能性があります。
ユーザーは「左上→右→左下→右」の順で視線を動かすと言われています。この法則にしたがうと、画面中央ではなく、「左上」「右上」「左下」「右下」にポップアップを表示するのが効果的だと言えるでしょう。
ポップアップ機能を用いて顧客満足度を向上しよう
ポップアップを用いることで、CVRの改善やサイト離脱防止の効果が期待できます。しかし、ポップアップは必ずしもユーザーが求める機能ではなく、なかには煩わしさを感じるユーザーがいる点も注意しなければなりません。そのためには、ユーザーに適したポップアップを表示することに留意して、ターゲティング機能やシナリオ設計を充実させて顧客満足度を向上させましょう。
投稿 Web接客におけるポップアップとは?どんな効果があるのかを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 無料で使えるWeb接客ツールをご紹介。使える機能や有料プランの価格も は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで今回は無料で使えるWeb接客ツールをご紹介します。実際にITreviewに寄せられたユーザーのレビューも合わせてご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてみてください。
無料のWeb接客ツール
Web接客ツールには大きく分けて、下記の3つのタイプが存在します。
| チャット型 | WEB上にチャットを設置し、ユーザーからの質問に有人対応で行う |
| ポップアップ型 | 画面上にポップアップを表示し、ユーザーの離脱を防ぐ |
| ハイブリッド型 | チャット型とポップアップ型の両方兼ねそろえたもの |
それぞれ特徴が異なるため、目的に応じたツールを選定することが重要となります。
ちなみにチャット型は、チャットボットとよく混同されることが多いですが、以下のように異なります。
| Web接客のチャット型 | 人による対応 |
| チャットボット | AIなどによる自動対応 |
主に人による対応か、AIなどを活用し自動での対応かになります。
Webでのおもてなしを強化したい場合は、「Web接客ツールのチャット型」を、業務効率化を強化したい場合は「チャットボット」をお勧めします。
チャットボットの無料製品をお探しの方は下記ページをご覧ください。
チャット型
Chat Plus

Chat Plusはあらゆる業界のチャットに対応するテンプレートが用意されており、初めての方でも安心して利用することができます。またGoogleAnalyticsやLINE、Slackなどの他社製品との連携も可能であるため、幅広いシーンで利用が可能です。
全プランで、サポートがつきますので、初めての方でも安心して始めることができるのも特徴の1つです。
また、Chat Plusでは、無料プランの提供はありませんが、10日間無料トライアルがあり、全機能が使用できます。そのため、期間中に使用感などを把握し、必要な機能が利用できるプランを選んで導入しましょう。
| 無料プラン | × |
| 無料期間 | トライアルでの10日間 |
| 無料版の機能制限 | なし。トライアル期間中は全機能利用可能 |
| 有料プランの金額 | ¥1,500~¥170,000 |
| 外部連携 | Google Analytics, LINE, Slack, Salesforceなど |
| 利用実績 | 導入企業10,000社以上 |
ポップアップ型
PtEngine

PtEngineには3つの大きな機能があり、そのうちの1つであるPtEngine ExperienceでWeb接客機能を利用することができます。またPtEngine Insightという別プラン(無料プランあり)に申し込むことで、ヒートマップが利用でき、ヒートマップデータと連携して、コンバージョン改善に結びつけることも可能です。
無料プランでは、PV数の上限や、作成できる体験数に制限があるため、Insightと合わせて範囲内でまずお試ししてみることをおすすめします。
| 無料プラン | 〇 |
| 無料期間 | 永年無料(2023/02時点) |
| 無料版の機能制限 | あり |
| 無料プランで使える機能 | 計測可能PV数/月:3,000、作成できる体験数:2、ユーザーセグメント:2、ポップアップ、ノーコードサイト編集、体験ごとのレポート、CSVダウンロード、表示ページ指定、表示ユーザー条件指定、配信スケジュール管理、キャンペーンゴール、A/Bテスト、パーソナライゼーション |
| 有料プランの金額 | ¥9,878~ |
| 外部連携 | 不明 |
| 利用実績 | 世界20万人以上の利用者数 |
ecコンシェル

ecコンシェルはNTTが提供しているツールになります。
「だれに」「どこで」「いつ」「なにを」のキャンペーンを設定するだけで、狙ったセグメントに最適なタイミングで訴求することができます。また、NTTドコモと PKSHA Technology が共同開発した人工知能(AI)技術を搭載しており、自動で複数のA/Bテストを回すことが可能です。
無料プランは永年無料であるため、決まった期間内に使って判断する必要がないため安心です。登録サイト数や、キャンペーン数が1つのみで、配信数も100までとなっておりますので、注意して使いましょう。
| 無料プラン | 〇 |
| 無料期間 | 永年無料(2023/02時点) |
| 無料版の機能制限 | あり |
| 無料プランで使える機能 | サイト数:1、キャンペーン数:1、接客配信数100回/月、想定配信数ユーザー予測、複数リンクウィジェット |
| 有料プランの金額 | ¥9.800~ |
| 外部連携 | Google Analytics, LINE, Slack, Salesforceなど |
| 利用実績 | 導入企業6,500社以上 |
無料プランを利用するうえでの注意点
無料で製品が使えることは魅力的である一方で、その分できないことも増えます。
事業において、成果を出したり、業務効率を上げることが重要であるため、有料プランを利用するほうがコストパフォーマンスが良くなるケースがあります。主に以下のに注意して利用しましょう。
自分が必要な機能が使えるか確認する
先ほども挙げましたが、無料プランであるが故、機能に制限がある場合があります。
例えば、接客配信数の制限や、登録サイト数の制限などが一般的です。
そのため訪問ユーザー数が多い場合や、サイト保持数が多い場合は有料プランを利用することをお勧めします。
有料プラン含め様々な製品をご希望の方へ
ITreviewでは、有料プランを含めた数多くの製品のレビューや製品情報をご確認いただけます。
ぜひ合わせてチェックしてみてください。
投稿 無料で使えるWeb接客ツールをご紹介。使える機能や有料プランの価格も は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 サイト運用のSEO対策とは?お役立ちツールもピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、サイト運用のSEO対策とSEOツールをご紹介します。自社のサイト運用に携わっている方は、ぜひ参考にしてください。
サイト運用のSEO対策とは?
サイト運用のSEO対策とは、サイトの検索順位を上げてユーザーを獲得するために行います。具体的には以下のような対策になります。
対策1:WordPressでサイトを作成する
WordPressを使用してサイトを制作すると、Web制作の知識がない初心者でも簡単にデザインの変更や記事の更新を行えます。また、最近はパソコンよりもスマートフォンからの検索が増加しています。そのため、検索順位を上げるためには、パソコン・スマートフォン両方のデバイスからのアクセスに対応したホームページが必要です。WordPressの場合、拡張機能(プラグイン)が充実しており、スマートフォン対応も簡単に行えます。
以上のような理由から、ホームページを含む多くのサイトがWordPressを使用して作成されています。インターネット上にあるサイトの約半数はWordPressで作成されているのが現状です。
対策2:競合サービスとなるサイトを分析する
せっかく自社サイトのページを充実させても、自社よりも優れたページがある状態では、ユーザーが競合サイトに流れてしまいます。そのため、自社の競合となるサイトは定期的にチェックしましょう。そこで得た分析結果をもとに、サイト内のコンテンツの質と量を高めていきましょう。
具体的には獲得したい検索キーワードにおける、自社ならではの独自性です。競合他社にはない切り口や、新しい解釈をページ内に取り入れることで、ユーザーにとって価値あるページが生まれます。それにより検索エンジンからの評価が高まり、表示順位が上がるといわれています。ただし、即座に効果が表れるものではないので、じっくりとPDCAサイクルを回していくことが重要です。
対策3:ユーザーの使いやすさを第に一優先する
たとえば、Googleの検索順位は、Googleの検索エンジンシステムによって決定します。検索順位を決定するために200以上の評価項目が準備されていますが、その評価項目についてGoogle側は何も明らかにしていません。
しかし、Google側は一貫して「ユーザーファースト」を求めています。そのため、ユーザーにとっての使いやすさを第一優先にしてホームページ運用を行いましょう。具体的には「スマホでも見やすい文字サイズにする」「ホームページの表示速度を早める」「ホームページ内の内容の質を上げる」などが効果的です。
対策4:実績を掲載する
実績を掲載していると、ユーザーからの信頼が高まります。また、実績の掲載はGoogleにも評価されやすく、検索順位の向上につながる可能性があります。自社で運営しているサービスの導入実績やメディア掲載実績は、積極的にホームページへ掲載しましょう。
対策5:Googleアナリティクスなどの計測ツールを導入する
Webサイトは一度制作して終了ではなく、定期的にメンテナンスする必要があります。その際に役立つのが、Google Analytics(グーグルアナリティクス)などの計測ツールです。
Googleアナリティクスは、Google社が運営する無料の計測ツールです。サイトへのアクセス数やユーザー属性を確認できるため、SEO対策を行う上で最低限導入しておきましょう。
対策6:ブログやコラムを併設する
サイト内にブログやコラムを併設すると、ブログやコラム記事からのアクセスが増加します。また、ブログやコラム内に自社商品やサービスの紹介を入れると売上が増加する可能性があります。このようなメリットから、ホームページ内にブログやコラムを併設する企業が近年増えています。
自社サイト運用のSEO対策を行うメリット
サイト運用のSEO対策を行うことにより、以下3点のメリットを得られます。
メリット1:低コストでホームページに集客できる
SEO対策の一番のメリットは、低コストで集客できる点です。SEO対策を行うために必要な費用はサーバー代、ホームページ制作費、コンテンツ制作費のみです。このうち、ホームページ・コンテンツ制作は、WordPressを使用して自社で行えば、月数千円のサーバー代のみでSEO対策できます。結果が表れるまでは時間がかかりますが、コスパの良さでいえばSEOに勝る対策はないでしょう。
メリット2:企業や自社商品・サービスの認知拡大につながる
サイトの検索順位が上がれば自然とアクセス数が増加し、企業や自社商品・サービスの認知拡大につながります。よく目にする商品やサービスほど顧客は安心して利用できるため、認知拡大は重要です。
メリット3:マーケティングにつながる
Googleアナリティクスなどの計測ツールを使用すると、アクセス数が高い記事を洗い出し、ユーザーの年齢や性別を調べられます。その結果、自社の商品・サービスがどの年代に需要があるのかを一目で確認できます。
この結果をもとに自社商品やサービスの向上に努めることで、より顧客に求められる商品・サービスを作り出せます。
SEO対策お役立ちツール
本項目ではサイト運用のSEO対策に役立つツールを3つご紹介します。
ツール1:Google Search Console
Google Search Consoleは、Google社が運営するSEO対策ツールです。無料で利用できるツールでありながら、インプレッション数・クリック数・掲載順位などさまざまな分析ができます。また、サイト上に問題が発生するとメールで通知が届くため、サイトの修正にも役立ちます。Googleアナリティクスと同様に、SEO対策に必須のツールです。
・Google Search Consoleの参考価格
無料
・Google Search Consoleの参考レビュー
Googleでどんなワードで検索されて自分のサイトのどのページに訪問されたのか、その際には検索結果で何番目に表示されたのかということが分かる。
Google Search Consoleへのレビュー「GAとあわせてウェブマスター必須のツール」より
広告費用が掛からない自然検索経由の流入は、誰でも喉から手が出るほど欲しいが、そのために必要な情報が自社サイトに関わる部分ではほぼsearchconsoleだけで入手でき、しかも無料なのはすごい。
ツール2:SEARCH WRITE
SEARCH WRITEは、株式会社PLAN-Bが運営するSEO対策ツールです。SEOの知見がない人でも、簡単に使いこなせるのが特徴です。新規訪問者数・平均滞在時間などの重要指標を抽出したり、対策すべきキーワードを確認したりできるので、知見がなくともコンテンツの最適化を実現できます。チーム運用に特化した設計で、タスクの進行状況や成果を誰でも見られるため、チームでホームページを運用している企業のSEO対策にピッタリです。
・SEARCH WRITEの参考価格
ツール+カスタマーサクセス:50,000 円 / 月額
・SEARCH WRITEの参考レビュー
「競合から見つける」を利用すればベンチマークしているサイトのキーワードを、検索順位や検索数順に表示することができるので、自社のブログキーワード選定の参考にしています。
また、選定したキーワードから「コンテンツ立案」を作成すれば、検索上位のブログ構成がひと目でわかるので、網羅性を担保することができます。
そして公開したブログキーワードを登録すると「検索順位チェック」から日々の検索順位が表示されるので、どの記事が注目されているのか、リライトが必要なのかなど指標にすることができます。キーワード選定→ブログ構成作成→公開ブログキーワードの順位チェック→リライトなど一連の流れをわかりやすく誘導してくれるので初めてでも使いやすく、PDCAも回しやすいです。
SEO課題チェックというツールもあり、現在のサイトで改善したほうがいい箇所(改善すればサイトの評価につながる)をピックアップしてくれるので、こちらも役立っています。
また、なによりカスタマーサポートが充実しているので、初歩的な説明から現状の分析、KGI・KPIなどのアドバイス、将来的な目標設定など親身に相談に乗ってくれるのでとても助かっています。
SEARCH WRITEへのレビュー「初めてのSEOでも使いやすく分かりやすい」より
ツール3:ミエルカSEO
ミエルカSEOは、株式会社Faber Companyが運営するSEO対策ツールです。「ツール」「学習コンテンツ」「運用支援コンサル」の3つが一体となっているのが、ミエルカSEOの特徴です。17年で1,700社以上の導入実績があり、多くの企業におすすめのSEO対策ツールだといえるでしょう。
・ミエルカSEOの参考価格
MIERUCAスタンダードプラン:150,000 円(月額)
・ミエルカSEOの参考レビュー
他のSEOツールも検討したが、サジェストインテンションでの競合流入数調査や、サジェストネットワークでのワード取得等、コンテンツを作るにおいて必須な機能がたくさんある。また競合流入キーワード調査では自社の弱みと他社の強みが一気に可視化されるため、対策が立てやすくその後のコンテンツ制作に活用することができた。
ミエルカSEOへのレビュー「コンテンツ作りやSEOを考える際に利用したいツール」より
SEO対策を行い、ホームページの検索順位を上げよう
ホームページのSEO対策を行うことで、認知拡大や売上向上などさまざまなメリットを得られます。効率的に実施するには、SEO対策ツールが必須です。社内のホームページ運営者数や知見者数から自社に適したSEO対策ツールを見つけて、ホームページの検索順位向上に努めましょう。
投稿 サイト運用のSEO対策とは?お役立ちツールもピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MEO対策を自分たちで完結させるためのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>MEO対策は「SEOのように専門業者に依頼すべきでは?」と思われがちですが、実はMEOツールを活用すれば自社でも対策可能です。そこで今回は、MEO対策の具体的な手順と押さえるべきポイントについて解説します。
Googleマップの検索結果で上位表示される仕組み
MEO対策とは、Googleマップ検索の結果で上位表示させることです。初めにこの仕組みを理解しておきましょう。
鍵となるのがローカル検索
MEOでは、特定の地域や場所に関連するキーワードの検索結果が反映されます。これはローカル検索(ローカルSEO)と呼ばれ、スマートフォンの場合、搭載されたGPSの位置情報が考慮されます。特定の地域でユーザーを集客したい場合、ローカル検索で上位表示されれば目につきやすくなり、新たな顧客獲得のきっかけとなります。
ローカル検索での上位表示の決定要因
Googleの公式サイトには以下の内容が記載されており、ローカル検索における決定要因は「関連性」「距離」「知名度」の3つとなります。具体的な内容を見ていきましょう。
「ローカル検索結果では、主に関連性、距離、知名度などの要素を組み合わせて最適な検索結果が表示されます。たとえば、遠い場所にあるビジネスでも、Google のアルゴリズムに基づいて、近くのビジネスより検索内容に合致していると判断された場合は、上位に表示される場合があります。」
引用:Google のローカル検索結果のランキングを改善する方法|Google ビジネス プロフィール ヘルプ
・関連性
関連性は、ユーザーが検索したキーワードがGoogleビジネスプロフィールの内容や投稿、口コミなどに一致するかどうかです。例えば「鎌倉_カフェ」で検索したときに、一致率が高ければ高いほど上位表示される可能性があります。ユーザーがどのようなキーワードで検索するのかを推測し、コーヒー、喫茶、焙煎など関連性のある言葉をGoogleビジネスプロフィールや投稿に記載する必要があります。
・距離
距離は、検索キーワードで指定された場所から店舗までの距離を指します。場所の指定がない場合は、検索ユーザーの現在地情報をGPSから取得して距離が計算される仕組みです。ユーザーの取りこぼしを防ぐためにも、Googleビジネスプロフィールは正確性が求められます。
・知名度
知名度は、そのビジネスがどれだけ一般に認知されているかを指します。例えば多くの人に知られているホテル、ショッピングセンター、観光地などはローカル検索で上位表示されやすくなります。MEO対策としては、積極的な投稿や評価の良い口コミの収集、SNSでシェアされる仕掛けを作るなどWeb上での露出を増やす施策が有効です。
MEO対策の具体的な方法
MEO対策の具体的な手順を見ていきましょう。
1.Googleビジネスプロフィールへ登録
初めに、以下のGoogleビジネスプロフィールにビジネスの情報を登録します。Googleビジネスプロフィールは無料のサービスで、Googleマップ上に店舗の情報を表示させることができます。
出典:Google ビジネス プロフィール|Google にビジネスを掲載
2.NAP情報の統一
NAP情報とは、「Name(店舗名)」「Address(住所)」「Phone(電話番号)」の3つを指します。NAP情報を統一する理由は、MEOの要素である「知名度」「関連性」に関係するためです。公式サイトやSNS等、情報発信の際はすべてNAP情報を統一するよう心掛けましょう。
3.カテゴリの設定
ビジネスカテゴリは、検索順位に大きな影響を与える重要な要素です。メインカテゴリと追加カテゴリの2種類があり、この両者を使い分ける必要があります。
メインカテゴリには、店舗の主軸となるビジネスを設定します。選択できるのは1つだけで、登録するとGoogleマップ上に業種別のアイコンとして表示されます。
追加カテゴリには、メインビジネスと並行して運営する事業を設定します。最大9つまで選択可能で、登録すればGoogleに認識されるようになります。ただし、追加カテゴリは組み合わせと数に注意が必要です。異業種を組み合わせたり多すぎたりする場合、ビジネス領域が曖昧になり評価を下げる原因になります。
4.キーワードの設定
MEO対策としては、基本的に「地域名+業種名」の複合キーワードを使います。これは検索ユーザーがGoogleマップ検索する際に、最も多い組み合わせとなるからです。
しかし「新宿_美容室」「渋谷_美容室」のようなキーワードの場合、検索ボリュームと競合店が多くなります。メジャーすぎるキーワードでは大手のチェーン店など有名店が上位に表示されやすいため、検索順位を上げるのは難しくなります。
おすすめは、検索ニーズが一定数ある競合の少ないキーワードの設定です。例えば「渋谷_美容室_芸能人」のように、複合ワードを追加すれば上位表示を狙いやすくなります。
MEO対策で押さえるべきポイント
MEO対策では以下のポイントを押さえておきましょう。
Googleビジネスプロフィールの情報量を充実させる
Googleビジネスプロフィールは、テキストの情報だけでは十分とは言えません。基本情報を充実させ、写真の掲載も行いましょう。実存する店舗の写真は、検索ユーザーへ安心感や信頼を与え、クリック数や電話による問合せを増やす効果が期待できます。同様に、建物や室内を360°パノラマで表現できるインドアビューの活用も効果的です。視覚効果によってGoogleビジネスプロフィールがより魅力的に見え、ユーザーのアクションにも大きく影響します。
また、投稿機能の活用も情報量を充実させる方法の1つです。イベントやキャンペーン情報の告知、最新モデルの紹介、来店者への特典などでキーワードを活用し、常に最新の情報を発信するのがポイントです。
口コミ数を増やし、管理する
ローカル検索では、口コミの件数や内容も大きく順位に影響します。
一般的に口コミが多く、評価が高いほど上位に表示されやすくなります。そのため、ユーザーに口コミを投稿してもらえるような工夫が必要です。口コミ促進用のQRコード発行やSMSなどを利用すると良いでしょう。
また、書き込まれた口コミを日々管理することも大切です。良い口コミには感謝の言葉を伝え、ネガティブな口コミは今後の改善策を提案するなど、1人ひとりのお客様を大切にする姿勢を保つことが評価につながります。
MEO対策ツールを活用する
検索順位を上げるには、MEO対策ツールを使うのも1つの方法です。MEO対策ツールはGoogleビジネスプロフィールの管理だけでなく、順位変動の確認や競合調査、口コミ管理、予約投稿、SNS連携など多くの機能を搭載しています。すべて手作業で行うよりも、効率的かつ効果的にMEO対策を進められるので便利です。
MEO対策ツールの選定ポイントは3つ
MEO対策ツールを選定する際のポイントは3つです。
1.必要な機能を備えているかどうか
まず初めに、自社のMEO対策で行うべき内容を整理してみましょう。多くの店舗を抱えているチェーン店であれば、多店舗管理に長けたツールがおすすめです。また口コミを多く収集したいなら、口コミ促進のQRコードを発行できるツールや、自動返信機能、一元管理機能を搭載した製品を使うと日々の運用が楽になります。
さらにデータ分析や調査、レポート機能などを活用して上位表示を目指すなら、競合調査に重点を置いたツールを選択すると良いでしょう。
2.サポート体制が整っているかどうか
MEO対策に初めて取り掛かる場合、ツールに慣れるまである程度の時間を要します。不明点や課題に直面した際、スピード感を持って手厚いサポートを受けられるかどうかは重要です。
「充実のサポート体制」と謳われていても、実際はAIチャットボットによる機械的なサポートやメールなどのやり取りがメインになる可能性があります。電話サポートを受けられるかどうか、初心者でも安心してツールを使えるかなど、総合的に見て利用しやすいと思えるツールを選びましょう。
3.費用対効果が高いかどうか
MEO対策ツールはさまざまな機能を搭載していますが、おおむね多機能・高機能になるほど月額料金は高くなります。イメージだけで高額なツールを選んでも、利用しない機能が多ければ無駄なコストだと言えるでしょう。
どの程度の機能・月額料金が自社に合っているか確認するには、無料トライアル期間のあるツールを試してみるのがおすすめです。実際にいくつかのツールを利用して、必要な機能や費用対効果を確認しておきましょう。
MEO対策ツールを上手く活用してGoogleマップの上位表示を目指そう
これまでのSEO(検索エンジン最適化)やリスティング広告とは異なり、MEO対策は低コストで手軽に始められる集客施策です。ツールを利用することで、専門業者に頼ることなく自分でMEO対策を完結させることができます。気になる方はぜひMEO対策ツールを上手く活用して、Googleマップの上位表示を目指しましょう。
投稿 MEO対策を自分たちで完結させるためのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 クリニック・病院のMEO対策。MEOのメリットや活用事例をご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>クリニック・病院におけるMEO対策の必要性
MEO対策とは、Googleマップ検索の際に自分の店舗やクリニック・病院などを上位表示させるための施策です。MEO対策が必要な理由は以下のようになります。
スマートフォン利用者が増加している
総務省の「令和4年(2022年)版 情報通信白書」によると、デジタルを活用する際のインターネット端末について、2021年の世帯保有率は、スマートフォン88.6%、パソコン69.8%となっています。5年前と比較するとスマートフォンの保有数は増え続け、16.8%の上昇です。
スマートフォンの場合、場所を特定するため地域性の高い「鎌倉_内科」等のキーワードで検索されるのがほとんどです。このことから、スマートフォン利用者をターゲットにしたGoogleマップ検索の上位表示が集患に有効であるとわかります。
SEOによる検索結果より上に表示される
MEOがGoogleマップ検索の施策であるのに対し、SEO(検索エンジン最適化)は地域性を伴わない一般検索の上位表示です。Google検索ではこれらは別々に表示されています。
下記のイメージからわかるように、MEOはSEOよりも結果が上位に表示されます。つまり、SEOよりも目につきやすくなるということです。
SEO対策による検索結果で上位表示の難易度が上がっている
SEOでは内容の薄い低品質な記事を除外し、読み込みの速いページやユーザーに有益なサイトを表示させるよう年々アップデートを繰り返しています。そのため、サイト運営者は時間を掛けて有益なコンテンツを作らなければ検索エンジンに評価されない状況です。さらに、内部構造の整備やコンテンツ追加などあらゆる施策を講じても、上位表示まで6ヶ月以上かかるのが一般的です。
一方MEOでは、地域に信頼される企業や病院に関する情報は上位に表示される傾向にあります。期間も施策後1ヶ月程度で上位になることがあり、SEOに比べて効率的だと言えるでしょう。
クリニック・病院はMEO対策の効果が出やすい
MEOの効果が出やすい業種は、実店舗を持っているビジネスです。理由は、「鎌倉 内科」のようにGoogleマップで検索され、なおかつGoogleマップ上で比較されることが多いためです。地域密着型で、商圏の幅が非常に狭いのも理由の1つだと言えるでしょう。
具体的にはクリニック・病院、飲食店、美容室、不動産、カーディーラー、鍵交換、買取業など、場所を明確に特定できるビジネスに有効です。
クリニック・病院のMEO対策で得られるメリットとは?
クリニック・病院がMEO対策によって得られるメリットを見ていきましょう。
ユーザーの目に留まりやすい
MEO対策によって上位3位以内に入れば、SEOより上に表示されるようになります。加えて以下のイメージのように地図や住所、連絡先などが掲載されるため、ユーザーのクリック率も高まります。またスマートフォンの場合、ファーストビュー(Webページを表示した際に最初に目に入るエリア)として表示されるため、より効果的にユーザーのアクションを促すことができます。
MEO対策によって毎回上位表示が続けば、長期的にユーザーから認知されやすくなります。さらに詳細情報を写真などで充実させれば、まだ獲得できていない見込み患者に対してアピールできるため、宣伝材料として効果的です。
広告費のコストを削減できる
MEOは、SEOやリスティング広告に比べて費用対効果が高いのが特徴です。
SEO対策では、上位表示させるため専門の業者に依頼することが多く、月額数十万円になることも珍しくありません。リスティング広告も同様で、広告掲載費は月額10〜50万円、プラス専門業者への委託費が2〜10万円になります。
一方、MEO対策の場合、無料で使えるGoogleビジネスプロフィールに登録するだけで始められます。もちろんGoogleマップの上位を狙うにはクリニック・病院の情報を詳しく登録して内容を充実させる必要がありますが、SEOほどの難しさはありません。専門業者に依頼しても月額2〜3万程度となり低コストに抑えられます。
口コミによる集客の相乗効果を期待できる
Googleマップ検索では、以下のイメージのように詳細情報とともにユーザーの口コミも掲載されています。口コミはユーザーが検索結果を比較するときに利用されるため、集患に関わる重要なポイントです。
口コミの数が多いほど、近隣地域で人気があることが伺えます。そして良い口コミが増えれば、満足度の高いサービスが提供されるイメージへとつながります。口コミによる信頼感・安心感が新たな患者獲得となり、さらに口コミを増やす相乗効果を生み出してくれます。
競合が絞られる
MEO対策は、SEOに比べて競合が少なく成果も出やすい施策です。SEOは全国のユーザーをターゲットとしていますが、MEOでは特定の地域に存在するクリニック・病院のみが競合となります。近隣の医院がMEO対策をしていなければ、より上位に表示される確率が高くなると言えるでしょう。
MEO対策の活用事例
実際のMEO対策でどのような成果が出ているのか、利用ツールも合わせて見ていきましょう。
利用ツール:MEO Dashboard byGMO
機能:Googleビジネスプロフィールの運用・管理、キーワード別の日々の自店舗・競合店舗の順位測定、ユーザーの検索後の行動分析、アンケートを使った口コミ促進機能など。
活用事例:歯科クリニックでアクション数228%UP、婦人科クリニックで表示回数が500%UPなどの実績。全国に100店舗を展開する美容クリニックでは、検索上位3位以内に表示される割合が50%から80%に上昇。
利用ツール:MEOチェキ
機能:Googleビジネスプロフィールの運用・管理、順位取得、予約投稿、過去のインサイトや口コミなどデータの可視化・分析、内部分析・競合分析など。
活用事例:首都圏に44店舗を構える音楽スクールで、週2時間を要した投稿作業が20分に軽減。ツール利用後、4ヶ月でGoogleマップ経由の問い合わせが1.5倍。
利用ツール:Gyro-n MEO
機能:Googleビジネスプロフィールの運用・管理、順位計測、多店舗一括管理、競合のベンチマーク、インバウンド対応など。
活用事例:仙台市拠点の不動産会社で、3ヶ月目から表示回数が伸び9ヶ月目には当初の3倍近くまで増加。間接検索数は4ヶ月目から増え続け、9ヶ月目の時点で2倍を達成。
利用ツール:ローカルミエルカ
機能:店舗情報の一括管理、情報発信の自動化 + 一斉配信、マップ順位計測(自社・競合)、お客様アンケート+クチコミ獲得など。
活用事例:質屋などを全国約210店舗展開する企業において、2ヶ月でGoogleマップ経由の問い合わせ数が390件から470件に増加。平均単価は前月比で5000円UPし、Googleマイビジネス内のアクション増加により、Webサイトへ流入したコンバージョンも増加。
ツールの活用で効果的なMEO対策を!
MEO対策はSEOに比べて比較的取り組みやすく、成果が出やすい集患方法です。とくに近隣地域の競合医院でMEO対策が進んでいないのであれば、いち早く取り組むことで新たな患者獲得につながります。
MEO対策ツールを活用すれば一連の作業がスムーズになり、効率的にMEO対策を進められます。気になる方はぜひツールの活用を検討してください。
投稿 クリニック・病院のMEO対策。MEOのメリットや活用事例をご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 大事なのは工数削減の「先」を見据えること――Googleマップの店舗情報を管理するMEOツールの選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そうした課題を解決するためのMEOツールも続々と登場しています。複数店舗の情報一括更新や、MEO対策に向けた分析・改善を可能にする株式会社トライハッチの「MEOチェキ」もその1つ。MEOツールによって何が可能になり、どのように活用していけばいいのか、同社の藤井智氏に話を伺いました。
どんな企業、店舗がMEO対策をすべきなのか
――そもそもMEOとはどういうものなのでしょうか、SEOとの違いも含め教えてください。
これまで多くの企業が行ってきたSEO対策は、Googleなどサーチエンジンの検索結果におけるホームページの表示順を改善していくという活動です。一方でMEOはローカルSEOとも呼ばれ、Google マップでの検索の結果として現れる店舗情報などを管理し、その表示順を改善していく、というのがMEO対策の主な活動となります。
――MEO対策が有効とされるビジネス分野や業態はどういったものが考えられますか。
主に飲食店、クリニック、トレーニングジム、塾、中古買取などリアルの施設・店舗を運営しているのであれば、MEO対策は有効な施策となります。ユーザーがGoogle マップで検索したとき、キーワードや場所に応じて付近エリアの施設・店舗の情報が一覧表示されますが、その表示順位を高めることで、より多くの顧客を誘導しやすくなります。
工数削減から表示順位の改善まで目指せるMEOツール
――MEO対策をしていくうえで、店舗などはどのような課題を抱えているのでしょうか。
Google マップで表示する情報は、店舗の運営者が「Google ビジネス プロフィール」というサービスを通じて登録することができます。ただ、このサービスの仕様上、とりわけ複数の店舗を運営している場合は、全店舗で共通の情報にしたくても、各店舗の情報管理・更新を個別に行わなければならないため非常に大きな手間になっています。
また、店舗情報を登録した後は、顧客の来店につなげるための具体的な施策を考えていく必要もあります。ユーザーの目に留まりやすい順位でGoogle マップに表示されることを目指すわけですが、そのためにどんな情報をどのように登録・更新していけばいいのかわからない、という方も少なくありません。管理工数の削減だけでなく、運用していく部分で課題感をもっているところも多いのではないかと感じています。
――そこでMEOツールはどのような役割を果たすのでしょうか。
大きく分けて2つあります。1つは、情報登録などの管理工数の削減です。MEOツールは現在主だったところで20ほどありますが、その大半が工数削減のためのツールという位置付けです。たとえば複数の店舗をグルーピングして同じ情報で一括更新する、といったことが可能になっているものが多いかと思います。
もう1つが、Google マップでの表示順位を上げていくための分析や施策の実践です。たとえば競合の店舗と比較して自分の店舗に足りていないところを理解し、効果的な施策を打っていく。MEOツールではそういったことが可能になっています。店舗運営者が自らツールを活用してMEO対策していける、というものですね。
また、企業によってはツール外のところまでサポートしてくれる場合もあります。より効果的な施策をアドバイスするコンサルティングや、ツールの実運用を代行するサービスなどです。管理工数を削減したうえで、その削減した分の時間で何ができるのか、ということもMEO対策では大事なことだと考えています。
工数削減の「先」も考えたMEOツールを選ぶべき
――Google マップで上位に表示されるためにはどういった活動が必要になってきますか。
ご存じの通りGoogle マップでは、店舗の基本的な情報が表示されるだけでなく、ユーザーのクチコミが投稿され、店舗側からは写真を掲載したり、ブログのような形で情報を投稿できたり、クーポンを発行したりもできます。
こうしたクチコミへの返信や情報の登録は、先ほどお話ししたようにGoogle ビジネス プロフィールの管理画面から行うわけですが、登録している情報の「充実性」や「クチコミ」、「外部Webサイトからの評価」などが表示順位に影響すると言われています。たとえば設定しているカテゴリー、写真の掲載枚数、ブログの更新頻度、クチコミへの返信の割合、クチコミに含まれるキーワードなどが関係するようです。
さらに店舗名でGoogle検索したときに、自社以外のWebサイトでその店舗名が言及されている数が多ければ、外部からも支持・評価されていると判断され、順位に反映されることがあります。つまり、SEOも若干関係してくることが想定されます。
――MEOツールを選ぶときに気を付けておきたいポイントはありますか。
運用工数の削減だけでなく、その先まで対応できるかが重要です。工数削減の目的は、あくまでも運用改善によって集客につなげることのはずです。単に工数を削減するだけであれば、だいたいどんなツールでも実現できますが、手間が減って業務が楽になった後、必ず「集客にはどうつながったのか」という話になってくるでしょう。
そのとき、工数削減しかできないツールだと先に進めません。結局、集客を目指せる別のツールを探して乗り換えざるを得ず、ツールを見直すことになります。工数削減のツールだけを提供しているのか、その先のビジネス改善に向けた分析・運用までカバーしているのか、導入前に確認することが大事です。そのうえで使用料はいくらか、といったコストの部分を考えたいですね。
競合と比較することが表示順位の改善に
――成果を出しやすい導入・運用のコツがあれば教えてください。
シンプルに競合と比較することだと思います。表示順位が上がっている店舗は、Googleに評価されているということです。評価されている店舗と自分の店舗を比較することで、どんな施策を行っていくべきかの判断基準を作ることができると考えます。
ユーザーに見てもらえる順位まで上げようとしたときには、情報の見せ方や更新頻度が重要になってきます。新しいお客様に店舗を見つけてもらえるようにする、そして、すでに見つけてもらっているお客様にはより有益な情報を与えられるようにする、この2つの観点を大事にして取り組むと良いのではないでしょうか。
――最後に、MEOツールの導入を検討している方に向けてメッセージをいただければ。
当社では「MEOチェキ for HP」というサービスをリリースしました。店舗のホームページを簡単に作成し、Google ビジネス プロフィールと連携できるというものです。このサービスを利用すれば、Google マップ上の複数店舗の情報を一括更新できるとともに、ホームページの更新も同時に行えます。当社のサービスがその解決の一助になれば幸いです。
投稿 大事なのは工数削減の「先」を見据えること――Googleマップの店舗情報を管理するMEOツールの選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 LPOの基礎知識|SEOとの違いや導入目的を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、LPOの基礎知識からSEOとの違いや導入目的を解説します。LPOの導入手順や注意点についても解説しますので、Web運営に携わっている方は参考にしてください。
LPOの導入目的
LPOの導入目的は、サイトに訪れたユーザーを商品購入や会員登録などのコンバージョンまで導くことです。そのために、サイトに訪れるユーザーのニーズを把握し、ライティングページの最適化を進めていきます。
LPOとSEOの違い
LPOとSEOの違いは、それぞれの目指す目的にあります。LPOの目的は、サイトに訪れたユーザーを商品購入や会員登録などのコンバージョンまで導くことです。一方、SEOの目的はサイトの訪問者を増加させることです。
このように、LPOとSEOは目指す目的が違いますが、サイト運営においてどちらも重要であるため、どちらか一方に注力するのはおすすめしません。LPO対策とSEO対策、両方とも並行して進めていきましょう。
LPOの施策
LPOの施策には以下のようなものがあります。
施策1:現状の課題を分析する
初めに現状のランディングページの課題を分析し、把握する必要があります。課題を把握することにより、修正点が明確になります。課題の分析には、GoogleアナリティクスやLPOツールを使用するのがおすすめです。
施策2:サイトのデザインを最適化する
ランディングページのコンバージョン率を向上させるためには、ターゲットとなるユーザーに適したサイトデザインである必要があります。例えば、若い女性がターゲットであれば、サイト内のカラーや色彩を明るくしたり、高齢者がターゲットのサイトであれば、文字のサイズを大きめにしたりすると良いでしょう。
また、サイト内のボタンの配置は特に重要です。購入ボタンをどこに配置するかでコンバージョン率は大きく変化します。サイトに訪れたユーザーが迷わずクリックできるようにボタン配置も見直しましょう。
施策3:表示速度を改善する
サイトのURLをクリックしてもなかなか画面が表示されないランディングページは、サイトの読み込みが完了する前にユーザーが離脱してしまいます。そのため、表示速度をなるべく高速にする対策が必要です。
表示速度の改善には、画像サイズの縮小化や不要なソースコードの削除、WordPressでサイト構築している場合は、不要なプラグインを削除すると良いでしょう。
施策4:ファーストビューを変更する
読者はランディングページのファーストビューによって、記事を読む価値があるかを判断しています。そのため、ファーストビューの変更はLPO改善に非常に効果的です。何のサービスや製品を紹介しているのかを具体的にファーストビューに明記すると良いでしょう。また、読者の心をつかむキャッチコピーを追加するのもおすすめです。
LPOのメリット
LPOを実施することによって、様々なメリットを得られます。本項では、LPOのメリットについて解説します。
メリット1:離脱率の低下とコンバージョン率の向上
サイトに訪れたユーザーのニーズを分析し、ランディングページの最適化を図ることにより、離脱率の低下が期待できます。また、ユーザーのニーズをしっかりと把握し、最適化を図ったランディングページのコンバージョン率は向上していきます。
メリット2:顧客満足度の向上
LPOの実施により、顧客満足度の向上が期待できます。ユーザーのニーズにしっかりと応えられるコンテンツや操作性の良いサイトは、サイトに訪れたユーザーに満足感を与えます。それにより、サイト自体の価値も向上します。
LPOの実施手順
LPOは、現状を正しく理解し、仮説を立て、改善を行い、結果を評価するといったPDCAサイクルを回すことが重要です。正しい手順を踏まないと、LPOの効果は得られません。本項では、LPOの実施手順について解説します。
手順1:LPOツールを導入する
LPOを実施するには、初めにLPOツールを導入するのがおすすめです。LPOツールを導入することにより、以下のメリットを得られます。
- 現状のランディングページが抱えている問題が分かる
LPOツールには、サイトのUI/UXを改善するための「ABテスト機能」、アクセス状況やコンバージョン率を調査してレポートとして出力する「アクセス分析レポート機能」など様々な機能があります。これにより、ランディングページが抱えている現状の課題点を簡単に把握できます。
- スピーディーに課題を解決できる
LPOツールの導入により、サイトのアクセス数やURLクリック数が即座に分かるようになります。これにより、データ集計や分析に使用する時間を大幅に短縮できます。その結果、LPOツールを導入しなかった場合と比較して課題解決までの時間を圧倒的に短縮可能です。工数の削減や従業員コストの削減にもつながります。
手順2:サイト内の現状を把握し、課題点を把握する
LPOツールを導入したら、サイト内を解析します。LPOツールやGoogleアナリティクスを使用すると素早く解析が完了します。また、サイトの解析をする際は、以下の項目に目を向けると良いでしょう。
- アクセス数
- コンバージョン率
- ページごとの離脱率
- 滞在時間
これらの項目をチェックすることが、手順3の仮説と改善策の立案に役立ちます。
手順3:仮説と改善策の立案
課題を解決するための改善策を立てていきます。改善策を考える際は、何が原因で問題が発生しているのか論理的に考える必要があります。例えば、コンバージョン率は高いが、期待したほどサイトの売上が伸びていない場合、サイトのアクセス数に問題があるのかもしれません。
サイトのアクセス数を確認し、低い場合は、SEOを強化するための施策を実行する必要があります。このように、複数のデータを結びつけて改善策を立案しましょう。
手順4:改善策を実行する
手順3で作成した改善策を実行しましょう。
手順5:結果を分析する
実行結果を分析していきます。結果が期待通りに出なかった場合、もう一度手順2から再度実行していきます。
LPOの注意点
LPOを実行する場合は、課題に優先順位を振り分け、優先度の高い課題から順番に解決していきましょう。同時に複数の課題を解決しようとすると、どの項目を改善したことがどの課題解決につながったのか不透明になってしまいます。
LPOツールを導入してみよう
自社に適したLPOツールを導入できるかが、LPOを成功させる大きな鍵となります。自社で運営しているサイトやランディングページの特徴をしっかり把握した上で、自社に適したLPOツールを導入しましょう。
投稿 LPOの基礎知識|SEOとの違いや導入目的を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 インフルエンサーマーケティングはどう進める?ワークフローから業務効率化をするコツをご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、インフルエンサーマーケティングの概要やコツ、利用するメリット・デメリットについて解説します。マーケティングを成功に導く方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
インフルエンサーマーケティングとは?
インフルエンサーマーケティングとは、次のようなSNS等で活躍するインフルエンサーと協力して行うマーケティングのことです。主に企業が提供するサービス・商品の認知度を高めて、利益につなげていくために用いられています。
- TikTok
- Youtube
企業が提供するサービス・商品に興味を持つ顕在層に対するアプローチは、広告やCMといった宣伝で問題ありません。しかし、企業のサービス・商品自体を認知していない潜在層も大勢います。
インフルエンサーマーケティングを実施すれば、インフルエンサーを通して潜在層にサービス・商品を認知してもらえる可能性が高まります。そのため、変化し続けるニーズに対応するべく、影響力が大きいインフルエンサーの協力を得てマーケティングを実施する企業が増えているのです。
インフルエンサーマーケティングを効率化する3つのコツ
インフルエンサーマーケティングは、インフルエンサーの影響力を借りて、サービス・商品の認知度を高めるマーケティング手法です。しかし、ただ依頼するだけでは効率的に結果を生み出せません。
まずは、インフルエンサーマーケティングを進めるために必要な3つのコツを解説します。インフルエンサーへ依頼するにあたり、何を行うべきか検討する際の参考にしてください。
目的・目標設定に力を入れる
インフルエンサーマーケティングを実施するなら、あらかじめ目的・目標設定に力を入れましょう。なかでも重要なのが、KPIの設定です。
KPIとは、目標達成に必要なプロセスのフェーズごとに設定する評価指標を指します。例えば、「認知度UP」「購買」「共有」といった目的があれば、次のようなKPIを設定可能です。
| 目的 | KPI(目標設定) |
| 認知度UP | 閲覧数・再生数リーチ数UGC数 |
| 購買 | 登録者数購買者数SNSのサイト経由率 |
| 共有 | コメント比率(ポジティブ/ネガティブ)UGC数SOV |
目的・目標があれば、それを実現するために必要な施策を検討できます。また、実際に動き出してから数値を分析していけば、どのアクションが最も効果的なのかを判断できるようになります。
インフルエンサーマーケティングを成功に導くためには、目的設定が欠かせません。目的を実現するために、目標値を決めて動き出すことも重要です。2つの要素がマーケティング実施において欠かせない要素のため、まずは何から動き出すべきか整理しましょう。
自社と親和性の高いインフルエンサーを選ぶ
SNS等を見ていくと、さまざまな特徴を持つインフルエンサーが見つかります。マーケティングを依頼するインフルエンサーによって、次のようなことに影響することを覚えておきましょう。
- フォロワー数・認知度:依頼費用に影響する
- 発信ジャンル:ユーザーニーズに影響する
フォロワー数や認知度は、インフルエンサーの発信力に直結します。発信力が高ければ高いほど、利益を生み出せる代わりに依頼費用が高額になりがちです。
また、インフルエンサーによって発信ジャンルが異なるため、自社と親和性の高いインフルエンサーに依頼する必要があります。美容系のインフルエンサーにITツールやガジェットの告知を依頼しても、購買率を高められないので注意してください。
自社サービス・商品のイメージを崩さないSNS運用を行う
インフルエンサーマーケティングを実施することによって、インフルエンサーに興味を持つ客層からのアクセス・購買が増えていきます。インフルエンサーが投稿する内容についても、しっかりと企業内でチェックしましょう。
なかには自社サービス・商品のイメージを崩す投稿の場合があります。インフルエンサーに宣伝をお任せにするのではなく、どのような情報を発信してもらいたいのか、事前に計画してきちんと連携する必要があります。
インフルエンサーマーケティングのメリット
インフルエンサーマーケティングを実施するメリットは、次のとおりです。
- SEOの強化につながる
- ユーザーに受け入れてもらいやすい
- ネット・SNSを通じて拡散されやすい
インフルエンサーの協力を得られれば、SNSの投稿からHPやサービスページにユーザーが流入していきます。その結果、閲覧数や購買率が高まり、サイト自体のSEOの強化につながるでしょう。SEOで評価されれば検索上位に表示されて、さらなる利益UPにつながります。
また、インフルエンサーを仲介してサービス・商品を宣伝することによって「この人がおすすめする商品だから大丈夫だ」と、ユーザーに受け入れてもらいやすいのがメリットです。インフルエンサーの発信はファン等が多くの人に共有していくので、より多くの人たちに拡散されやすいことも利点だと言えます。
インフルエンサーマーケティングのデメリット
インフルエンサーマーケティングには複数の魅力がある一方、次のようなデメリットもあります。
- インフルエンサーの選定次第で結果が変わる
- ユーザーからステマを疑われる可能性がある
- 炎上でイメージダウンになる危険性がある
インフルエンサーごとにキャラクターや影響力が異なるため、広い視点で依頼する人物を決めていかなければ、上手く利益を生み出せない可能性があります。サービス・商品宣伝を頻繁に行うと、ステマ疑惑をかけられる場合もあるので注意しましょう。
また、インフルエンサーの投稿で炎上してしまうと、それが飛び火して企業のイメージダウンにつながることもあります。まずはデメリットを理解したうえで、インフルエンサーマーケティングの導入を検討するのがおすすめです。
インフルエンサーマーケティングを成功させる方法
インフルエンサーマーケティングを成功させたいなら、押さえるべきポイントが2つあります。それぞれの方法は、マーケティングを可視化できるほか、計画的な管理を実施するために欠かせません。具体的な方法をご紹介するので参考にしてください。
すべてのマーケティングを仲介業者に任せない
インフルエンサーマーケティングでは、企業とインフルエンサーの間に仲介業者が入る場合があります。仲介業者はマーケティングのプロなので、企業のサポートやアドバイスをもらえるでしょう。
しかし、すべてを仲介業者に任せることはおすすめしません。特に次のポイントは、必ず自社独自にチェックすることをおすすめします。
- マーケティングの動き方
- インフルエンサーの投稿内容
自社が思いもしない方向にマーケティングが進む可能性があります。また、自社のサービス・商品が理解されないまま投稿される危険性もあるので、マーケティングチェックを欠かさないように気を付けてください。
プラットフォームツールを活用する
複数のインフルエンサーを通じてサービス・商品を宣伝する企業もあるでしょう。しかし、人数が増えてくると、各インフルエンサーを上手く管理できずに統制が取れなくなってしまいます。
複数のインフルエンサーの動きや今後のスケジュールを可視化して、最小限の人員で対応したいなら、プラットフォームツールを活用してみてください。
専用の管理ツールを使えば、インフルエンサーの情報をデータとして管理できます。また、SNSの情報を連携して、KPI分析を実施できるのも魅力です。クラウドを通じて社内共有できることも含めて管理効率化を期待できるので、ぜひ導入を検討してみてください。
インフルエンサーマーケティングを活用したいならITreviewでツールを探そう
インフルエンサーマーケティングを実施すれば、自社のことを知らない潜在層にアプローチできるほか、SEOの評価や利益率の向上が期待できます。複数人のインフルエンサーに宣伝協力をお願いしたいなら、インフルエンサーの動きや宣伝効果を管理・分析できるプラットフォームツールの導入がおすすめです。
ITreviewでは、インフルエンサープラットフォームツールの比較検討やレビューチェックを行えます。導入を検討している方は、どのツールを利用するのがよいのかチェックしてみてください。
・合わせて読みたい
投稿 インフルエンサーマーケティングはどう進める?ワークフローから業務効率化をするコツをご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 インフルエンサーマーケティングにおけるKPIの考え方とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、インフルエンサーマーケティングでKPIを意識すべき理由、KPI設定に役立つ指標、測定方法について解説します。KPIと相性のよいSNSも紹介しますのでマーケティング戦略の参考にしてください。
インフルエンサーマーケティングでKPIを意識すべき理由
インフルエンサーマーケティングとは、SNS等で影響力を持つインフルエンサーにサービス・商品の宣伝を協力してもらうマーケティング手法です。インフルエンサーマーケティングを実施すれば、インフルエンサーが抱えるフォロワー、そしてフォロワーが情報共有したユーザーに自社サービス・商品を宣伝できます。
ただ宣伝をお願いするのも効果的ですが、同時にKPIを意識すれば、さらなる効果を期待できます。KPIを意識すべき理由は次のとおりです。
- コスト縮減
- 顧客の動きを測定する
- 施策の改善・改良
マーケティングを実施する際には、限られた予算の中で動く必要があります。事前にKPIによる目標値を設定したうえで動き始めれば、効率よく結果を生み出せるでしょう。
また、数値として分析することによって、結果の改善・改良が行えるのも魅力です。KPIを意識するとインフルエンサーマーケティングの効果を何倍にも高められるので、ぜひ導入に合わせて設定してみてください。
インフルエンサーマーケティングのKPI設定に役立つ3つの指標
インフルエンサーマーケティングのKPIを設定するためには、指標を活用していくことが大切です。まずは、KPI設定に役立つ3つの指標について解説します。どのような設定が必要なのか参考にしてください。
オーディエンス
「オーディエンス」とはインフルエンサーが投稿するコンテンツを閲覧する集団のことで、リンクのクリック数や購買に直結する重要な指標です。
ユーザーがコンテンツを見ないことには、次のアクションに進みません。そこで、まずはSNSのアナリティクス機能を活用して数値を分析してみましょう。
投稿したコンテンツごとに数値を分析していけば、各インフルエンサーの影響力を可視化できます。また、閲覧数はフォロワー数の15〜30%が一般的だといわれています。1万人のフォロワーがいる場合、1,500〜3,000のインプレッションを獲得できるため、インフルエンサーの選定時に活用してみてください。
エンゲージメント
インフルエンサーマーケティングの有効性を測定したいなら「エンゲージメント」の指標設定がおすすめです。エンゲージメントとは、次のようなリアクションを指します。
- いいね
- コメント
- シェア
- リンク移動
これらは、オーディエンスの次のアクションとして生み出される要素です。エンゲージメントが多いほど、マーケティングの有効性が高いことを示します。投稿するコンテンツや、依頼したインフルエンサーと自社との相性を分析することに役立つので、並行してチェックしてみてください。
リード・販売コンバージョン
インフルエンサーマーケティングは、最終的に自社のサービス・商品にユーザーを誘導することが大切です。そこで「リード」「販売コンバージョン」の指標を設定してみましょう。
リードは、どのコンテンツから誘導されたのか確認できるなど、何の影響を受けて興味を持ってくれたのか把握できます。販売コンバージョンは、サービス・商品の購入や利用に直結したユーザー分析として利用可能です。
リード・販売コンバージョンは、企業が求める最終的な到着点となります。どのコンテンツから利益を生み出せたのか分析できれば、今後の施策を検討する根拠として利用できるため確実に設定しておきましょう。
インフルエンサーマーケティングで設定したKPIの測定方法
インフルエンサーマーケティングでは、ただKPIを設定するのではなく、測定を行い分析することが大切です。次に、測定におすすめの方法を3つ解説します。活用しやすいツールの導入をしてみてください。
SNS分析ツールを活用する
SNSには、サービス独自の分析ツールが搭載されています。例えば、SNSによって次のようなツールを利用可能です。
- Instagram:Instagramインサイト
- Twitter:Twitterアナリティクス
- YouTube:YouTubeアナリティクス
それぞれ、オーディエンスやインプレッションの数値を測定できます。また、プラットフォームツールを利用すれば、上記測定ツールを一括でまとめて簡易的に管理・分析できるので便利です。
ソーシャルリスニングツールを活用する
インフルエンサーが投稿するコンテンツの施策を決めたいなら、ソーシャルリスニングツールで次の条件を測定してみるのがおすすめです。
- 既存の投稿においてよく使われるキーワード
- 投稿されやすい写真や動画
- コメントの比率はポジティブ/ネガティブどちらが多いか
- SNS利用者の年齢・性別・生活地域
ソーシャルリスニングツールは、企業向けのサービスとしても提供されています。ITreviewではソーシャルリスニングツールの比較検討を行えるほか、利用者レビューがチェックできるので参考にしてください。
パラメータ付きURLを活用する
複数人のインフルエンサーに宣伝を依頼する予定があるなら、パラメータ付きURLを活用してみてください。
パラメータ付きURLとは、URLにインフルエンサーの情報を持たせて情報測定を行う特殊なURLのことです。あらかじめ各インフルエンサーに設定したURLを渡しておけば、投稿したコンテンツからの流入を数値として分析できます。
投稿コンテンツからHP訪問する人数、サービス・商品の成約数などを自動で測定できるため、ぜひ準備してみましょう。パラメータ付きURLは無料ツール等を利用して準備できるので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
KPIの設定に役立つSNSとは
インフルエンサーマーケティングでは、主に次のようなSNSを利用してコンテンツを作成します。
- TikTok
- Youtube
この中でKPIを設定したいなら、各サービスでチェックできる次の項目に設定してみましょう。
- 閲覧数
- いいね数
- シェア数
- フォロワー増加数
- プロフィールへの移動数
- URL移動数
- Google検索ボリューム
設定したい指標は、企業が目的とするコンバージョンの内容によって異なります。まずは、どのような導線でユーザーをコンバージョンさせたいのか決めることが重要です。インフルエンサーを含め、マーケティングの流れを検討してみてください。
投稿 インフルエンサーマーケティングにおけるKPIの考え方とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ダイレクトメールは時代遅れ?効果を最大化するためのメールマーケティングの考え方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかしメールマーケティングの観点から言えば、多様な手段を併用するメリットは大きく、ダイレクトメールも使い方次第で依然として効果が期待できます。本記事ではダイレクトメールの活用方法や、メールマーケティングを実践する上でのポイントについて解説します。
ダイレクトメール(DM)とは
ダイレクトメールは、見込み客に対して手紙や封筒を送付し、商品の案内や新サービスの紹介を行うための手法です。メールなどとは異なり紙を使って情報を発信するため、メールアドレスではなく送り先の住所を知っておく必要があります。
ダイレクトメールは特定の個人に対して手紙を送る施策のため、不特定多数に配るチラシとは少し扱いが異なります。
ダイレクトメールは時代遅れなのか?
紙媒体を使ったマーケティング手法は以前であれば頻繁に行われてきましたが、インターネットが普及した現在は下火になりつつあります。紙媒体は発行コストや郵送コストがかかる上に、そもそもポストを見る習慣がない人にとっては読まれもしないためです。
また、SNSや電子メールでも同じような役割を果たせるため、わざわざDMを紙で送る必要はないと考える企業は増えています。しかし、ダイレクトメールはデジタルが普及した今だからこそ新しい価値を生み出している媒体でもあり、一概に「ダイレクトメールは時代遅れ」と言い切ってしまうのも早計です。
メールマーケティングのメリット
ダイレクトメールを含めた、メールを使用したマーケティング手法をメールマーケティングと呼んでいます。メールマーケティングの良いところは、見込み客のメールアドレスや住所が分かれば案内を送付できるため、営業担当者が直接訪問する必要がなく、コストパフォーマンスに優れている点です。
電子メールであればメールの開封率やリンクのクリック率を測定できるため、どれくらい効果が出ているのか、何を改善すればよいのか分かりやすいのもメリットです。チラシやWeb広告とは異なり、アドレスや住所と他の個人情報を紐づけておけば、誰にどんな案内を送るべきかというパーソナライズされた情報を提供できます。
メールマーケティングの主な方法
メールマーケティングの主な手法としては、以下4つの方法が挙げられます。それぞれの特徴について確認しましょう。
メルマガ
メルマガは、メールマーケティングのスタンダードな施策の1つです。定期的に商品紹介やサービスの紹介情報をまとめ、あらかじめ把握している見込み客のメールアドレスに向けて発信します。キャンペーンや新商品の展開など、大きなイベントがあった際に一斉送信して注目度を高めることもできます。
ステップメール
ステップメールは、以前に資料請求をしてくれた見込み客や、商品を購入してくれた顧客に対して送信するメールです。商品に関する追加情報を提供したり、前回購入した商品の新しいバージョンが新たに登場したことを伝えたりすることで、新規契約やリピーターの確保を促します。
商品購入者に対しての商品レビューの依頼や、サンキューメールの送信もステップメールの一種で、顧客との関係を強化するきっかけづくりに役立ちます。
リターゲティングメール
リターゲティングメールは、特定の条件に当てはまる見込み客に対して、条件ごとに用意したシナリオに基づくメールを送り、新規顧客の獲得や興味関心を集めるための施策です。
例えばオンラインショップに訪問したが、商品をカゴに入れたまま決済していないユーザーに対して「お買い忘れの商品はありませんか?」と購入を促したり「新たにクーポンが付与されました」と来店を促したりする施策が挙げられます。
購入の意図が初めはあったが途中でなくなってしまったユーザーに再度興味を持ってもらう、あるいは購入をうっかり忘れていたユーザーの買い忘れを防止する効果が期待できます。
ダイレクトメール(DM)
DMは上でも紹介した通り、ダイレクトメール施策全般を指します。ダイレクトメールを見込み客個人に送付することで、詳細なサービス情報を提供するのに役立ちます。
通常のチラシとは異なり、立派な封筒に手紙が入っていたり、質の高い紙を使って案内を提供したりすることで、特別な招待状を手渡されたような感覚を与えられる点もDMならではのメリットだと言えます。
成果につながるメールマーケティングのポイント
メールマーケティングを成功に導く上では、その使い方を工夫することも大切です。ここでは、メールマーケティングのポイントを3つ解説します。
効果測定と改善のサイクルを確立する
メールマーケティングはただメールを送って終わりではなく、メールを送ったことでどんな効果が得られたかということを正しく把握する必要があります。
メールの開封率や商品の購入率を測定し、目標の数値は達成できたか、どうすれば更なる改善効果が得られるかということを丁寧に検証しましょう。
デジタルとアナログ手法を併用する
メールマーケティングはデジタル手法が主流ですが、ダイレクトメールのようなアナログ手法も依然として有効です。デジタルだけ、アナログだけではなく、どちらも必要に応じて使い分けることで、高いマーケティング効果を発揮できます。
デジタルを使えていない場合にはデジタル施策に、アナログを使えていない場合はアナログ施策の可能性に注目し、適切な運用方法を検討してみましょう。
中長期的な運用を前提とする
メールマーケティングはいずれも短期で効果が出る施策ではないため、中長期的な運用効果を見込むのが妥当です。短期での成果を求める場合、Web広告などを使って改善効果を期待しましょう。
ツール活用でメールマーケティングの効果を高めよう
メールマーケティングは近年活躍している代表的な施策ですが、ダイレクトメールのようなアナログ手法も併用することで、より高い効果を期待できます。メールマーケティングの効果を最大限高めるためにも、各施策の違いや強みを理解し、適切なタイミングで施策を展開することが大切です。
また、メールマーケティングの効果を高めるためには、各社が提供しているツールを利用するのも1つの方法です。ITreviewでは、各メールマーケティングツールの特徴や口コミを多数掲載しています。メールマーケティングの成果が上がらずに悩んでいる方は、ツールを比較した上で導入を検討してみてください。
投稿 ダイレクトメールは時代遅れ?効果を最大化するためのメールマーケティングの考え方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 SNS管理ツールとは?法人アカウントの管理に使える機能とメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、マーケティング担当者向けに会社のSNSアカウント管理に役立つツールと導入するメリットについて解説します。
SNS管理ツールとは
SNS管理ツールとは、TwitterやFacebookなどのSNSアカウントを管理して、運用をサポートするツールです。複数のSNSアカウントでの一括投稿や投稿日時を指定した予約投稿などの機能を搭載しています。
例えばSNS管理ツールがあれば、キャンペーン開催を知らせる投稿を同じ時間に複数のSNSにまとめて予約できます。また、投稿後の反響について分析したり、複数の担当者が1つのツールで一元管理したりできるなど、SNSの運用と管理をサポートします。
SNS管理ツールの機能とメリット
SNS管理ツールに備わっている機能とメリットについて解説します。
SNSアカウントを一括管理できる
SNSは1つのアカウントだけでなく、TwitterやFacebookなど複数のアカウントを運用することでターゲットの目に届きやすくなります。Twitterの利用者数はおよそ4,500万人、Facebookにはおよそ2,500万人のユーザーがいます。1つのSNSでは届かないメッセージでも、TwitterとFacebookのどちらにも公開することで投稿の露出度が高まるでしょう。
また、SNS管理ツールを使うことで、複数のアカウント運用と管理の両方がスムーズになるのもメリットです。
予約投稿できる
キャンペーンの開催通知や創業フェアの通知など、情報解禁時間ぴったりに投稿したい告知もあるでしょう。SNS管理ツールの予約投稿機能を使うと、あらかじめ決めておいた時間に投稿できるようになります。
マーケティング担当者が1人だけでも、予約投稿なら複数のSNSアカウントで同時に投稿可能です。SNS管理ツールの予約投稿機能によって、スムーズにSNS運用できるのもメリットだと言えるでしょう。
SNSアカウントを複数人で管理できる
1人のマーケティング担当者だけでなく、複数でSNSアカウントを管理したい企業も少なくありません。しかし通常のアカウントでは、複数の担当者で管理するとログインが重複したり、パスワード管理が煩雑になったりする可能性があります。
SNS管理ツールを導入すると、SNSアカウントを一元管理して、アカウントの利用状況をひと目で把握できます。また、SNS管理ツールのパスワードを共有できれば、別々のSNSアカウントのパスワードを全員で把握する必要がなくなります。
投稿のPV数やリーチ数を分析できる
TwitterやFacebookなどで投稿したら、マーケティング担当者はユーザーの反響も把握する必要があります。SNS管理ツールには、フォロワーの獲得状況や投稿のインプレッション数(表示された回数)などを分析できるソーシャルリスニング機能が備わっています。
SNSアカウントに投稿しただけで終わるのではなく、重要なのは投稿の閲覧数や拡散数、口コミ内容などの反響の分析です。分析結果のエビデンスとして、PV数やリーチ数をミーティングの議題として提出できる点もSNS管理ツールを導入するメリットだと言えます。
SNS管理ツールを選ぶポイント
実際にSNS運用を始めるにあたっては、アカウント管理するツールの選び方を把握しておきましょう。
目的のSNSに対応しているか
SNS管理ツールには、TwitterやLINEに特化したものもあります。自社で運用したいSNSに対応していないツールを選んでしまうと、SNS管理ツールをいくつも保有しなければならなくなります。
運用予定のSNSはあらかじめ決めておき、対応しているSNS管理ツールを選ぶようにしましょう。「comnico Marketing Suite」「Semrush」などの有料ツールのなかには、複数のSNSと連携して管理できる製品もあります。
日本語に対応しているか
SNS管理ツールのなかには、海外で人気を高めているものもあります。社内公用語を外国語にしているグローバル企業であれば問題ありませんが、ほとんどの企業では日本語に対応しているツールの方が運用効率は高まります。
また、日本語に対応していないツールは、そもそも日本語で予約投稿できるかどうかも分かりません。最悪の場合は、日本国内に向けて発信できない可能性もあります。日本国内のユーザーをターゲットにしている企業は、基本的に日本語に対応しているツールを選ぶようにしましょう。
予算内で利用できるか
予算はSNS導入前に決めておく必要があります。SNS管理ツールの支払いは月額制である場合が多く、SNS運用を辞めたり別のツールに乗り換えたりして解約するまでは支払いを続けなければいけません。
予算を大きく超えたツールを導入してしまうと、SNSアカウントの運用途中でツールの利用を諦めなくてはならなくなる可能性があります。予算を超えたくない場合は、連携できるSNSが少なくても価格の安いツールを初めから導入するのも1つの方法です。また予算に合わせて、運用を予定していたSNSの変更も検討してみましょう。
必要な管理機能は備わっているか
SNS管理ツールは、基本的にフォロワー管理や投稿管理などの機能を搭載しています。しかし、1つのSNSに特化していたり、複数のSNSに連携していたりするツールなど様々です。さらには、SEO管理や広告管理などの機能を備えたツールもあるため、管理機能はSNSに限定するのか広告管理まで付け加えるかなども検討しなければなりません。
例えば、Twitterの運用だけなら月額980円〜で導入できる「SocialDog」で構いませんが、広告管理まで含めるなら月額119.95ドル〜で導入できる「Semrush」などが良いでしょう。必要な管理機能から、自社に適したSNS管理ツールを選ぶのも1つの方法です。
SNSマーケティングを戦略的に運用しよう
SNSマーケティングは、ツールを用いることで管理を効率化して戦略的に運用できます。しかし、TwitterやFacebookに特化したツールもあり、複数のSNSと連携しているツールとどちらが必要なのかでも選択肢は変わります。
また、予算や管理機能によって選ぶツールも異なるので、気になる人はITreviewの口コミを参考にしてみてください。きっと自社のSNS運用にぴったりなツールが見つかるはずです。
投稿 SNS管理ツールとは?法人アカウントの管理に使える機能とメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Webサイトの開設に必要なものは?CMSで簡単に自社サイトを作る方法 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事ではWebサイトを自作する際に必要なものをまとめていますのでぜひご一読ください。
Webサイトに必要なもの
Webサイトの立ち上げに必要なものは「サーバー」「ドメイン」「CMS」の3つだけです。専門知識のない人でも、仕組みを理解するだけで容易にWebページを立ち上げられます。
・24時間アクセスできる「サーバー」
自社で立ち上げたWebサイトは24時間アクセスできるようにする必要があります。そのために必要となるのが「サーバー」です。サーバーとは、利用者がアクセスする専用のコンピュータであり、自分たちで機器を導入する「自社サーバー」、クラウドでサーバーをレンタルする「レンタルサーバー」の2種類があります。
自社サーバーは、24時間ずっと電源を付けられるコンピュータであれば何を使っても構いません。しかし、サーバーに不具合が起きるとWebページにアクセスできなくなるため、迅速に保守対応のできる人材や保守サービスなどが必要です。
そのため、最近は予備のサーバーも含めて24時間監視体制が整っている「レンタルサーバー」が人気を集めています。「自社サーバー」「レンタルサーバー」いずれが適しているかを自社の体制から検討して、まずは、24時間アクセスできる「サーバー」を用意しましょう。
・Webページの住所となるドメイン
「ドメイン」とは、「.jp」「.com」などで知られるWebページの住所となる情報です。ネットの住所には、本来MACアドレスやIPアドレスなどのアクセス情報が必要になりますが、利用者や管理者の目で見ても分かりやすい言語に変換することでアクセスしやすくなります。
ドメインは、サイトから購入して準備することができます。しかし、「.info」「.biz」などの1円〜利用できるものもあれば、人気が高すぎて高額で取引されているドメインもあります。
・Webページを管理する「CMS」
HTMLやSQLなどの開発スキルがない方や企業がWebページを作るには、CMSを導入するのが一般的です。「CMS」とは、前述したとおりWebページを容易に作成できるツールです。CMSを導入することで、サイトデザインの構築を簡略化してサイト運用の工数も減らせます。
自社のホームページやブランドサイトの制作も、CMSを用いると日本語を入力するだけでほとんど完結できます。初期設定やデザインのアレンジにはWebページ制作の知見が求められますが、必要な手順はインターネットで調べられるため、そこまで苦労することはないでしょう。
CMSとはWebページを簡単に作るツール
CMSとは「Contents Management System(コンテンツ・マネジメント・システム)」を略した言葉であり、手軽にWebサイトを構築して管理するためのツールです。PC・スマホなどのデバイスを問わず見やすく表示できる「レスポンシブデザイン」に対応しているため、サイト構築の専門知識がなくても、使いやすいホームページやブランドサイトを自分たちで立ち上げることができます。
今までのWebページ作成では、HTMLやSGMLなどのマークアップ言語を習得しなければなりませんでした。しかし、CMSが誕生したことによって専門性は薄れ、既に出来上がったテンプレートのデザインを選択するだけで容易にWebページを立ち上げられるようになったのです。
個人でもWebページを立ち上げる人が増えているのも、CMSの誕生で参入障壁が低くなったことに起因するでしょう。
CMS(WordPress)でWebページを作る方法
Webページは、「サーバー」「ドメイン」「CMS」の3つがあれば構築可能です。ここでは、CMSの中でも特に人気の高いWordPressを用いたWebページの作成手順について、重要なポイントを簡潔にご紹介します。
Webページのレンタルサーバーとドメインを用意
まずは、Webページの筐体(箱)となるサーバーとドメインを用意しましょう。自社サーバーの導入にはエンジニアのスキルが必要となるため、「Xserver」「ロリポップ!レンタルサーバー」などのレンタルサーバーを導入するのが手軽です。
また、ドメインもレンタルサーバーから取得できます。レンタルサーバーの手順に従って、ドメインを取得しましょう。人気のドメインはSEO(検索エンジン最適化)でも高い効果を期待できるので、高額なドメインを購入する企業も少なくありません。
レンタルサーバーにCMSをインストール
CMSは、レンタルサーバーにインストールすることで利用できます。なかでも高い人気を誇るのが、無料で使える「WordPress」というCMSです。インストール手順については、レンタルサーバーの公式ページに公開されているため、詳細はそちらを確認してください。
WordPressは世界でも利用者が多く、拡張機能であるプラグインの開発や更新も頻繁に進められています。また、Webページのデザインとなる「テーマ」も開発が進んでおり、有料のテーマの中にはSEOの効果が高いと言われているものもあります。
テンプレートからデザインを決める
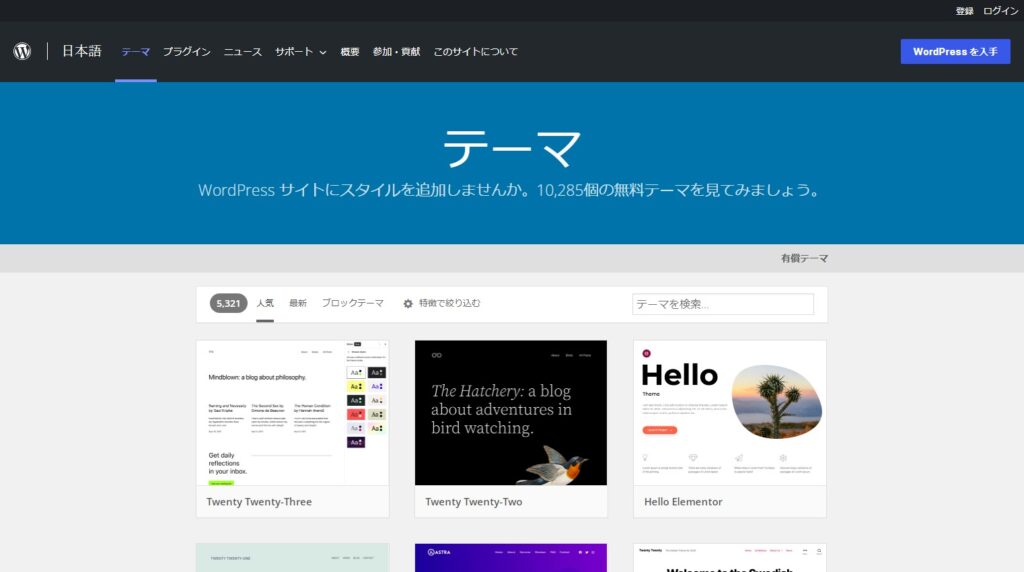
CMSを導入すると、Webページのデザインを一から作り上げる必要はありません。すでにテンプレートとしてWordPressに公開しているもの、または有料でテーマを購入してテンプレートを選ぶだけで洗練されたデザインを容易に利用できます。
スマホに対応したレスポンシブデザインもあるため、CMSを導入することでPCやスマホによって異なるデザインを意識する必要もありません。
記事の作成・更新
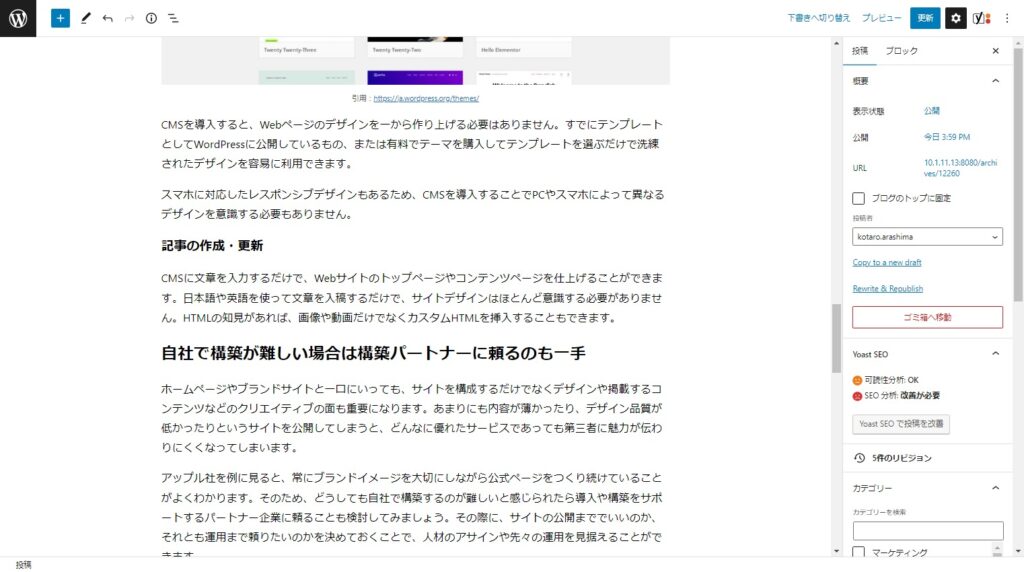
CMSに文章を入力するだけで、Webサイトのトップページやコンテンツページを仕上げることができます。日本語や英語を使って文章を入稿するだけで、サイトデザインはほとんど意識する必要がありません。HTMLの知見があれば、画像や動画だけでなくカスタムHTMLを挿入することもできます。
自社で構築が難しい場合は構築パートナーに頼るのも一手
ホームページやブランドサイトと一口にいっても、サイトを構成するだけでなくデザインや掲載するコンテンツなどのクリエイティブの面も重要になります。あまりにも内容が薄かったり、デザイン品質が低かったりというサイトを公開してしまうと、どんなに優れたサービスであっても第三者に魅力が伝わりにくくなってしまいます。
アップル社を例に見ると、常にブランドイメージを大切にしながら公式ページをつくり続けていることがよくわかります。そのため、どうしても自社で構築するのが難しいと感じられたら導入や構築をサポートするパートナー企業に頼ることも検討してみましょう。その際に、サイトの公開まででいいのか、それとも運用まで頼りたいのかを決めておくことで、人材のアサインや先々の運用を見据えることができます。
ホームページやブランドサイトは簡単に作ることができる
ホームページやブランドサイトの構築は、「サーバー」「ドメイン」「CMS」の3つがあれば難しいものではありません。昔のようにWeb制作会社へ数百万円をかけてサイト構築を依頼する必要もなくなりました。
予算を組むことが難しい個人経営の店舗であっても、月々1万円程度で作り上げることもできるでしょう。憧れの自社サイトやブランドサイトを構築するために、CMSの導入を検討してみてください。
投稿 Webサイトの開設に必要なものは?CMSで簡単に自社サイトを作る方法 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 イベント管理ツールとは?ウェビナーや展示会の運営を効率化しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、イベントの準備からアフターフォローまで、イベントの管理を楽にするツールと機能についてご紹介します。イベント管理ツールの選び方もあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
多様化するイベント
今まで展示会やイベントは、対面式のリアルイベントが主流でした。しかし、2020年の緊急事態宣言以後、オンラインでのイベント開催が急激に増えています。
出典:2021年 Peatixイベント調査レポート|Peatix Japan株式会社
オンラインイベントは場所を選ばずに開催できるため、多くの参加者を集めやすく、会場費などの経費を抑えられるのが魅力です。また、オフラインイベントをオンラインで中継する「ハイブリッドイベント」も注目を集めています。
イベント方法が多様化・デジタル化している現代では、イベント管理の負担が増えています。イベントの管理を効率化させるデジタルツールの導入が必須だと言えるでしょう。
イベント管理ツールの機能
次に、イベント管理ツールの代表的な機能を5つ紹介します。
顧客情報の管理
イベント参加者の会社名・氏名・連絡先などの情報を一元管理し、データベース化して集計できる機能です。参加率や来場者属性を分析でき、次回のイベント企画や自社のターゲット理解に活かせます。
イベント管理システム上で権限があれば誰でも情報を確認でき、情報を共有しやすいのもメリットです。サービスによっては、CRMと連動してオンラインイベントの参加申込登録から顧客管理できるツールもあります。
商談管理
商談管理機能では、顧客情報から成約の可能性が高いリード顧客の抽出・分析をでき、マーケティングオートメーションやCRMシステムと連携させて営業に活かせます。集客プラットフォーム機能を備えたツールもあり、告知ページを作成したりプラットフォームの登録顧客へイベントメールを送信したりして集客をサポートします。
スケジュール管理
イベントのスケジュールを管理できる機能です。イベントの告知や出店者の管理、書類管理や機材のレンタルまで展示会の準備は多岐にわたります。それぞれのタスクと進行状況をまとめて管理できるため、スムーズにイベントの準備を進められます。システム上で情報を共有できるため、社員同士で協力しやすくなるのもメリットです。
予約・決済管理
イベント管理システム上で、予約受付や決済を完結できる機能です。事前登録フォームを作成して、アンケートなど必要な項目を設定できます。予約が完了するとともに顧客情報がシステムに登録され、当日の来場受付や顧客管理機能とシームレスにつながるため効率的です。
予約と支払いがすべてシステムで完結するので、参加者の利便性も高まります。有料・無料、イベントの目的が違う複数の展示会を開催する場合、予約・決済管理機能が充実しているツールを選ぶとよいでしょう。
来場受付
QRコードやアプリ内でチケットを発行し、当日受付できる機能です。電子発行できるため、来場者の手間もかからず当日の来場状況もリアルタイムで確認できます。イベントや会場に合わせた複数の受付方法を併用することも可能です。
担当者と来場者を紐づけておくと顧客の来場を担当者に通知できるので、日常業務とイベント対応の両立もしやすくなります。
オンライン配信
ウェビナーやイベントの中継などができる、オンライン配信プラットフォーム機能です。オンライン配信のためのサイト構築や技術を必要とせず、プラットフォーム上で簡単にオンラインイベントを開催できるため、さまざまな業界で活用されています。
BtoB向けでは、Web上のバーチャル空間に展示会スペースを構築できるバーチャルショールームや、過去の配信をオンデマンドコンテンツとして残せる機能などを提供しており、顧客のエンゲージメントを向上させます。
BtoC向けでは、入場者数制限などの管理機能を提供しており、高画質・高音質な配信で大人数の集客イベントもスムーズに開催可能です。
サービスによって、集客機能があるもの、顧客管理に強みのあるもの、オンラインに特化したものなどさまざまです。自社に合ったシステムを選ぶのが重要です。
イベント管理システムを選ぶポイント
次に、イベント管理システムを選ぶポイントを3つご紹介します。
展示会の目的に合った機能を搭載しているか
1つ目のポイントは、展示会の目的に合った機能を備えているかどうかです。オンライン・オフラインなどの開催方法に加えて、集客力を上げたいのか、準備や受付業務を効率化させたいのかなど、イベントの目的によって必要な機能が変わります。
また、展示会後の顧客情報をどう活用するかも重要です。たとえばBtoBイベントの場合、商談管理機能やCRMとの連携など、成約につなげやすい機能があると展示会の効果が高まります。一般から広く人を集めたい場合は、集客プラットフォーム機能のあるツールが役立ちます。
料金が適正であるか
2つ目のポイントは料金です。イベント管理システムは、サービスによって機能や強みが異なることから料金の差が大きく、月額制や従量課金制など料金形態もさまざまです。
そのため、必要な機能をベースに、イベントの規模や予算を踏まえて料金が適正なのか検討する必要があります。そのためにも、自社に必要な機能の洗い出しを事前に行っておくことが大切です。
オプション機能を追加したり、自社に合わせてカスタマイズしてくれたりするサービスもあるため、見積もりを取って比較検討してみましょう。
システムの使いやすさ
3つ目のポイントは、入力のしやすさや管理画面の見やすさなど、担当者が扱いやすいシステムであるかどうかです。効率化のために導入したシステムが扱いにくければ、かえって業務負担が増えてしまいかねません。
参加者にとって使いやすいかどうかも、必ず確認したいポイントです。入力画面の負担が多ければ、参加者は途中で離脱してしまう可能性があります。参加率を高めるためにも、使いやすさは重要です。トライアル期間などで実際の画面を確認することをおすすめします。
イベントを管理できるシステムをまとめて比較
イベント管理システムは幅広い機能を搭載しており、目的を明確にしてツールを選ぶことが大切です。とはいえ、どのようなツールがあるか分からない人も多いのではないでしょうか。
投稿 イベント管理ツールとは?ウェビナーや展示会の運営を効率化しよう は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MEOは効果がない?コストやメリットなど活用法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、MEO対策の概要やメリット、ランニングコストについて解説します。また検索エンジン最適化であるSEOとの違いやMEOに効果がないとされる理由、評価の高いMEOツールについても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
MEO対策に効果がないとされる理由
マップの検索最適化として注目されているMEO対策ですが、一部で「効果がない」と言われていることをご存じでしょうか。その理由には次のことが関係しています。
- MEO最適化のための知識・技術が必要である
- 費用対効果が小さい可能性がある
- 長期的に計画が必要だが、短期で辞める人が多い
MEO対策は、一度行ったからすぐに上手くいくというものではなく、長期的な投資や分析が欠かせません。しかし最適化のための知識・技術を学ぶ必要があったり、投資した金額に対して売り上げが出なかったりと、必ずしも劇的な効果が期待できるわけではないのです。
また、MEO対策は長期的に動く必要があるため、本業が忙しくなって短期で辞める人もいます。とくに初期段階は結果が伸び悩む場合も多いため、早い段階でやる気をなくしてしまう人もいるのです。その結果、MEO対策を行っても、効果を生み出せずに終わってしまう人が出てきます。
MEO対策が有効なのは店舗型の業態
MEO対策は、消費者サービスを提供している業種向けの対策です。MEO対策が活かせる業種には飲食店、販売店などがあります。例えば、マップ検索でお店を調べた人に商品・メニューの写真を表示させることにより、消費者の購買意欲を高めて訪問率・利益率を向上させること可能です。
少し似た対策としてSEOがあります。MEOとSEOの違いは、検索の目的が違うユーザーを対象にしているということです。SEOはネット上の情報・商品・店舗等を網羅的に検索しますが、店舗情報・商品情報といった具体的な検索に弱い特徴があります。一方MEOはマップを使って店舗・商品を検索できるため、ユーザーの購買ニーズを意識した検索最適化が行えるのです。
MEO対策のメリット
店舗や販売店のなかには、MEO対策自体を行っていない人もいるでしょう。このときMEO対策を始めることで、次のようなメリットを得られます。
- 潜在層の集客力をUPできる
- 上位表示させやすい
- 広告費よりも費用を抑えられる
店舗を訪問して商品・メニューを購入してくれるのは、そのお店のことを知っている顕在層だけです。しかし、世の中には店舗のことを知らない人もいます。そういった潜在層にお店のことを知ってもらい、集客力を高めることにMEO対策が効果を発揮するのです。
とくにSEOは、店舗を総まとめしている「大手サイト」が上位を牛耳っています。一方MEOでは、大手サイトの参入ができず、店舗単体での競争が可能です。よってSEOよりもMEOのほうが、競合が少なく上位表示させやすいという特徴があります。
またSEO対策を行う場合、公式サイトの運営や広告に費用を要するのが一般的です。これに対しMEO対策は無料登録できる場所も多く、広告費用をかけずに対策しやすいため、出費を抑えることにも効果を発揮します。
MEO対策で考えるべきランニングコスト
MEOは、自店舗で対策を実施していけば、ランニングコストをかけずに集客対策を行えます。しかしMEO対策の知識がない場合には、有料サービスの利用や業者への外部委託がおすすめです。このとき、次のような費用が必要になります。
- 初期費用
- キーワード選定
- 順位測定
- 対策実施
- オプション料金
MEO対策を行う場合の費用相場は、約3~5万円です。利用する内容が濃いほど金額がUPするので、予算決めと対応してくれるサービスや業者を探していく必要があります。自店舗で対策するか外部委託するかを決定する前に、一度自身でMEO対策についてリサーチすることも大切です。
自店舗で対応できる範囲を把握すれば、外部委託に要する費用を抑えられるほか、外部委託でMEO対策が進行する際の状況判断が可能となります。
MEO対策業者を探すポイント
MEO対策の外部委託を考えているなら、自店舗に利益のある対策を行ってくれる業者を見つける必要があります。業者探しでは、次の3つのポイントを意識してください。
- 順当な価格で利用できるか(相場に収まるか)
- ノウハウを提供してくれる業者か
- 業者の得意分野であるか
まずは、相場内の料金で利用できる業者を見つけるのがよいでしょう。高額なサービスを提供している業者もありますが、価格が効果に直結することは少なく、同じようなサービス内容を提供しているなら相場内に収まる業者のほうが出費を減らして利益率をUPできます。
また、独断で動き出す業者も多く、結果を出せずに費用だけ取られてしまうパターンもあります。よって、外部委託を検討するなら、あらかじめ綿密な打ち合わせをして、次のような業者を選ぶのがおすすめです。
- MEO対策のノウハウを提供してくれる
- どのような動きを取るか事前説明してくれる
- MEO対策の計画検討に参加させてくれる
MEO対策を実施する業者の中にも得意分野があります。自店舗が求める内容を不得意とする業者もいるので、過去の実績などを参考にしてどの分野が得意なのか確認しておきましょう。もし自店舗が求める内容を得意とする業者を見つけることができれば、効率よくMEO対策の効果を生み出し、店舗の認知度を上昇させてくれるでしょう。
利用者から評価の高いMEOツール
ここで参考までに実際の利用者から評価されているMEOツールを4つ紹介します。
リンクからツールに寄せられたすべてのレビューが見られるため、ぜひチェックしてみてください。
上記で紹介したMEOチェキを提供しているトライハッチさんからMEOに関するヒントをお聞きしたので、ぜひ以下の記事も合わせてご一読ください。
記事:大事なのは工数削減の「先」を見据えること――Googleマップの店舗情報を管理するMEOツールの選び方
MEO対策には専用ツールで対策しよう
MEO対策は店舗の集客力・利益率・認知力を高め、SEOでは難しい上位表示を達成しやすいのがメリットです。また、自店舗でMEO対策をしていけば外部委託した場合のランニングコストを抑え、低予算でMEO対策を実施できます。
自店舗でMEO対策に力を入れたいなら、MEO対策を効率化するツールの導入が役立つのをご存じでしょうか。MEO対策に必要なキーワード選定・管理、検索状況の分析など、MEO対策を網羅的に実施できる機能が低価格で提供されています。
そこでもっとMEO対策について詳しく理解したいなら、まずはITreviewで紹介しているMEO対策ツールをチェックしてみてください。ツールの人気度はもちろん、利用者の口コミなど使いやすさも具体的に把握できます。
投稿 MEOは効果がない?コストやメリットなど活用法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 SNSマーケティングの重要性と効果|各SNSの特徴をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、SNSマーケティングの重要性と具体的な活用方法をご紹介します。SNSならではの注意点もあわせて解説するので、ぜひ参考にしてください。
SNSマーケティングの重要性と効果
総務省が実施した「令和2年通信利用動向調査」によると、日本では73.8%の人がSNSを利用しています。そのうち62.1%が情報収集を目的に利用しており、SNSが情報源として活用されていることが分かります。さらに、アライドアーキテクツ株式会社が令和2年に実施した「SNSをきっかけとした購買行動・口コミ行動調査」によると、SNSがきっかけで商品購入・来店した経験がある人は50%を超え、売上にも影響することが分かりました。
また、SNSをマーケティングに活用する企業も増加しています。SNSマーケティングは、企業や商品の認知拡大、ブランディングなどの効果を生み出し、拡散力があることから莫大な広告費をかけずに多くの人へ情報を届けられるのがメリットです。
近年では急激な拡散で話題になることを指す「バズる」という言葉も生まれ、バズを狙ったマーケティングも増えています。SNSユーザーは全年代で増加傾向にあり、SNSマーケティングの重要性は今後ますます高まると考えられるでしょう。
代表的なSNSの特徴をおさらい
次に、代表的な6つのSNSを紹介します。
| ・実名登録のため、実生活の人間関係に近い人とつながれる ・公式性が高く、ビジネス利用するユーザーも多い ・月間アクティブ利用者数2,600万人(2019年時点) ・30〜40代の利用率が高く、男女比はほぼ同じ |
|
| Instaglam | ・画像や動画などの視覚的な訴求が得意なため、ブランディングに向いている ・国内の月間アクティブアカウント数3,300万人(2019年時点) ・10〜30代の利用率が高い ・女性が多いと言われているが、男性の利用率も増えている |
| ・「リツイート」や「いいね」のリアクション機能を搭載しており、拡散力が高い ・匿名ユーザーが多いこともあり、炎上リスクが比較的高い ・国内の月間利用者数4,500万人(2017年時点) ・20代の約80%が利用し、男女比はほぼ同じ |
|
| LINE | ・利用率NO.1のSNS ・企業公式アカウントでユーザーと「友だち」になり、直接情報を届けられる ・国内の月間利用者数8,800万人(2021年時点) ・全年代で利用率が高く、平均90%の人が利用している |
| TikTok | ・キャッチーなショートムービーがバズりやすく、流行の起点となることもある ・世界では10億人が利用し、今後も成長が期待されている ・10代の利用率が圧倒的に高い |
| YouTube | ・世界最大級の動画共有プラットフォーム ・視覚的な訴求に加え、字幕をつけられる ・世界中の人に見てもらえる可能性がある ・全世界のログインユーザー数は20億人 ・日本では全年代で利用率が高く、約85%の人が利用している |
SNSは、それぞれユーザーの属性が異なるため、自社のターゲットにあわせたプラットフォームを選ぶことが重要です。また、SNSごとにユーザーとの距離の近さや文化が異なるため、SNSの特色にあわせた施策を心がけましょう。
SNSマーケティングの活用法5つ
次に、企業がSNSを活用する具体的な方法を紹介します。
SNSアカウント運用
SNSマーケティングで真っ先にできることは、企業アカウントの運用です。アカウントのフォロワーが増えれば、多くの人に情報を届けられ、認知度向上や顧客ロイヤリティの向上が期待できます。
アカウントが成長するまで時間がかかるため、広告やSNSキャンペーンなどの施策もあわせて活用するとよいでしょう。
SNS広告
SNS広告は、登録情報と「いいね」などの行動をもとに配信できるため、ターゲティングの精度が高く、投稿画面へ自然に表示されるのが魅力です。そのため、ほかの広告に比べてユーザーに避けられにくく、クリックされやすいと言われています。
一方で、ほかの投稿に埋もれて流されやすいため、印象的なクリエイティブを作ることが重要です。低コストで始めやすく、上手に運用すればコストパフォーマンスの高い広告になるでしょう。
インフルエンサーマーケティング
インフルエンサーマーケティングは、SNSで影響力の高いインフルエンサーに商品を紹介・拡散してもらう手法です。口コミサイトの普及の影響もあり、消費者は信頼のおけるインフルエンサーのレビューを参考に購買する傾向が強まっています。
爆発的な拡散や売上向上が期待できる一方、意図しない見せ方になってしまい、ブランドイメージが低下する可能性に注意が必要です。
SNSキャンペーン
SNSキャンペーンは、認知拡大や商品購入のきっかけ作りに有効な施策です。アライドアーキテクツ株式会社が実施した「SNSをきっかけとした購買行動・口コミ行動調査」によると、企業アカウントをフォローする目的として80%以上の人が「お得なクーポンやキャンペーン・セール情報を取得するため」と答えています。
プレゼント企画や抽選企画など、思わず参加したくなるキャンペーンを実施し、シェアやアカウントのフォローを促しましょう。
ソーシャルリスニング
ソーシャルリスニングとは、SNS上の会話やキーワードを分析し、商品開発やブランディングに活かす方法です。実際の声を収集できるため、顧客のリアルなニーズや新しい視点を得られるのがメリットです。キャンペーンやSNS広告の反応から、施策の効果改善にも活かせます。
SNSマーケティングの注意点
SNSは、拡散性の高さが魅力です。しかし多くの人に届くからこそ、炎上リスクが高い点に注意が必要です。炎上してしまうと、ブランドイメージを傷つけたり顧客離れを引き起こしたりします。コンプライアンスを意識したガイドラインや、運用ルールを決めておくとよいでしょう。
SNSマーケティングを活用しよう
SNSマーケティングは、低コストで始められ、さまざまな効果を生み出します。しかし、中長期的な運用が前提であり、リアルタイムでの対応が必要になるため、担当者の負担が大きくなりがちです。
そこで、SNSマーケティングでは、運用を効率化させる仕組みやツールの導入をあわせて検討しましょう。SNSの運用に役立つツールは以下からまとめて比較可能です。
投稿 SNSマーケティングの重要性と効果|各SNSの特徴をチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 LINEマーケティングとは?ビジネスの活かし方からお役立ちツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>いまや多くの企業で行われているLINEマーケティングですが、まだよく知らない方も少なくないでしょう。そこで本記事では、LINEマーケティングの概要やメリット、お役立ちツールを紹介します。LINEマーケティングを始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
LINEマーケティングとは
LINEマーケティングとは、LINEを使用して集客することです。NTTドコモモバイル社会研究所が実施したSNS利用率の調査結果によると、15〜79歳のスマホ・ケータイ保有者の81.6%がLINEを利用していることが明らかになりました。
出典:【サービス】LINE利用率8割超え:10~50代まで8~9割が利用(2022年5月16日)|レポート|NTTドコモ モバイル社会研究所
LINEは利用率が高く幅広い世代が活用しているため、商品の販促や会社の認知度を高めるために有効なSNSです。
LINEマーケティングを行うメリット
LINEマーケティングには、以下のようなメリットがあります。
- 顧客と親密な関係を築きやすい
- メッセージ開封率が高い
- 導入のハードルが低い
通常のメルマガ開封率が約10~30%なのに対して、LINEは約60%と開封率が非常に高いです。それほどまでに、LINEが身近なサービスであるということなのでしょう。
LINEマーケティングの販促機能
LINEマーケティングには、以下のような販促機能があります。
LINE公式アカウント
LINE公式アカウントは、企業の公式アカウントを作成し、友だち追加したユーザーにメッセージを届けられる機能です。友だち追加したユーザーと1対1のコミュニケーションを取れるのが特徴で、あいさつメッセージやLINEチャット、クーポンなどの豊富な機能を搭載しています。
「フリープラン」「ライトプラン」「スタンダードプラン」の3プランを提供しており、プランによって月に送信できるメッセージ数が異なります。フリープランは、無料で利用可能なので気軽に導入可能です。
LINEチラシ
LINEチラシは、LINEアプリで配信可能なデジタルチラシサービスです。友だち追加してくれているユーザーに直接チラシを配布でき、配布したチラシの閲覧数などを基にデータを分析可能です。
LINE広告
LINE広告は、LINEに広告を出稿できる広告配信プラットフォームです。通常、LINEはユーザーと1対1でのコミュニケーションがメインですが、LINE広告を活用すれば、タイムラインやLINEニュースなどより多くのユーザーの目に留まる場所に広告を掲載できます。
LINEアカウントの友だち獲得から顧客管理に強い「LIBERO」
株式会社ギブリーが運営するLIBEROは、LINEマーケティングの効果を最大化できるツールです。ラベル機能や友だち登録経路分析、チャットボットなどの豊富な機能を搭載しています。2022年4月現在でLINE運用支援数は1,500を超えており、プロのコンサルタントが企画、実行、運営までサポートしてくれます。
実際にLIBEROを利用しているユーザーからは、「UIが分かりやすく、直感的な操作が可能なため、プログラミングの知識がなくても綿密な作りこみができる」「LIBEROの導入で細かいデータを収集できるようになったことにより、新しい施策やアンケートを実施できた」といった口コミが寄せられています。
・LIBEROの参考価格
お問い合わせ
・LIBEROの利用者レビュー
スマホを持つユーザーが当たり前のように使用しているLINE。企業が公式LINE運用をする上で、LIBEROの活用が顧客とのコミュニケーションを円滑でリッチなものにしてくれていると感じています。
下記、特に気に入っている点です。●ステータスに応じた個別配信
LIBERO内でユーザーにラベルを付与することが可能です。ユーザーが商品を購入する確度というのは、アンケートの回答内容や、友だち登録同線などアクション一つ一つにヒントがあります。これらのアクションに対し、LIBERO内でラベルを付与し、それぞれの層に対して適切なLINEメッセージを送ることが可能です。LINE公式の管理画面だと一括でしか行えないコミュニケーションが、LIBEROによってより綿密になりました。●ビジュアライズ化された管理画面
LIBEROへのレビュー「LINEを効率よく運用でき、社内での活用もしやすいツール」より
LINE公式ではセグメント配信やリッチメニュー(画面下部のメニュー)の設計は通常APIを使用したものしか用意されていません。LIBEROはプログラミングの工程が一切不要で、非プログラマーでも直感的に操作できるUIが用意されています。
シンプルなUIなので、社内での運用も非常に楽に行えています。
自社サービスにソーシャルログイン機能を考えるなら「Loghy」
インキュデータ株式会社が運営するLoghyは、最小限の工数で効果を最大化できるソーシャルログイン機能導入ツールです。Loghyの導入によって、「会員獲得・サイトCV向上」「再ログイン率アップ」「SNSデータのマーケティング活用」などを実現できます。月額費用は32,500円で、LINEに加えてYahoo!JAPAN・Facebook・Twitter・Google・Apple・TikTokの全7つのソーシャルログインに対応しています。
実際にLoghyを利用しているユーザーからは、「運用している会員サイトとLINE公式アカウントの連携がスムーズにできるようになった」「簡単にデータを可視化できるのが魅力」といった口コミが寄せられています。
・Loghyの参考価格
お問い合わせ
・Loghyの利用者レビュー
新規会員数を伸ばすと同時に離脱ユーザを減らすという命題を抱えるサービスなこともあり、新規会員登録/ログインにおけるUXの最適化は必須であった。その点ユーザーのSNSアカウントを用いて1クリックでログインを可能にできたことは特に離脱ユーザーの防止につながっていると感じる。
Loghyへのレビュー「ユーザーエクスペリエンスの改善に」より
公式LINEに友達追加いただくことで様々なOne to One施策が行えるため、今まではポイント付与を行うなどしてQRコードを別途読み込んでいただき友達追加してもらっていたが、Loghy導入後はWebでの新規会員登録と同時にLINEに友達追加を行えているため友達追加数向上にも非常に役に立っている。
また追加の月額費用なくLINEの友達追加機能やProfile+の機能が利用できる点も含め価格メリットは非常に感じた。
LINEを使ったコミュニケーションを考えるなら「C-mo」
株式会社CS-Cが運営するC-moは、SaaS型統合マーケティングツールです。ローカルビジネスに特化しており、集客や作業効率化に関する課題を解決できます。C-moの導入数は3,700を超えており、マーケティング初心者の方にもおすすめのツールです。自社にWebマーケティングやSNSに詳しい人がいなくても、簡単に成果を出せる機能が集約されています。
実際にC-moを利用しているユーザーからは、「LINEメッセージを配信する際に絞り込み機能を使用できるため、送りたい人にしっかりと送信できる」「絞り込みカテゴリーが豊富なため、活用しやすい」といった口コミが多数寄せられています。
メッセージの自動配信やレポート機能が充実した「LOYCUS」
エキステム株式会社が運営するLOYCUSは、LINE公式アカウントを拡張利用できるクラウド型のCRMです。LINE公式アカウント運用の自動化・効果可視化を実現できます。「スタンダード」「プロフェッショナル」「エンタープライズ」の3プランを提供しており、全プラン14日間無料でお試しが可能です。
LOYCUSを実際に利用しているユーザーからは、「LINEに登録したユーザーを個別に識別可能なため、それぞれのユーザーがとった行動からユーザー情報を蓄積し、蓄積した情報を活用して配信やメニューをカスタマイズできる」「友だち追加経路別に、友だち追加時のメッセージやシナリオ配信を分けられるのが良い」といった口コミが寄せられています。
顧客対応をLINEに集約できる「CScloud」
スタークス株式会社が運営するCScloudは、LINEの1対1トークを楽にするツールです。1対1トークの対応コストの高さ、すぐに返信できず顧客を逃してしまう問題などを解決できます。
実際にCScloudを利用するユーザーからは、「自動応答メッセージの編集ができ、自動応答メッセージを表示するタイミングや対象者を詳細に設定できる」「LINE公式アカウントを既に持っていれば、CS cloudをすぐに利用できる」といった口コミが寄せられています。
LINEマーケティングを理解できた方は、複数のツールを比較してみよう
本記事を通してLINEマーケティングを理解できた方は、複数のLINEマーケティングツールを比較してみましょう。比較には、ITreviewのサイトがおすすめです。グラフを用いて製品を視覚的に比較でき、実際に製品を利用しているユーザーの口コミも閲覧可能です。自社の状況をしっかりと考えたうえで、最適なLINEマーケティングツールを導入しましょう。
投稿 LINEマーケティングとは?ビジネスの活かし方からお役立ちツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 デジタルマーケティングとは?Webマーケティングとの違いや7つの施策をご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで本記事では、デジタルマーケティングの基本とWebマーケティングとの違い、具体的な手法について解説します。自社商品・サービスの効率的な売上アップを実現するためにも、ぜひ参考にしてください。
デジタルマーケティングとは
デジタルマーケティングとは、インターネットやITなどのデジタル技術を活用したマーケティング手法のことです。市場・顧客分析からマーケティング戦略の実行、効果改善まで、すべての工程においてデジタル技術を活用します。
インターネットが浸透するまでは、対面営業、新聞・雑誌・テレビなどを利用したアナログマーケティングが主流でした。インターネットが登場してからは、Webサイト・SNS・Eメール・アプリ・loTなどで得られるデータを活用したデジタルマーケティングが台頭するようになりました。
デジタルテクノロジーが発展した現代では、ビッグデータやAIなどを活用した実店舗での購買行動も分析・検証されています。このようにチャネルを越えて、顧客へ購買行動を促すのがデジタルマーケティングの特徴です。
デジタルマーケティングとWebマーケティングの違い
デジタルマーケティングに近い言葉として「Webマーケティング」があり、同じ意味で利用されているケースもあります。しかし、Webマーケティングはデジタルマーケティングに包括されており、より狭義の部分的なマーケティング手法です。
Webマーケティングの具体的な手法は、Webサイトの閲覧履歴にもとづいた広告配信、Web上で優位に表示されるための対策など、すべてWeb上で行われます。一方で、デジタルマーケティングは、店頭での行動、AIやビックデータ活用なども範囲に入ります。
とはいえ、Webマーケティングは、デジタルマーケティングの中でも中心的な手法であり、商品の認知拡大や購買促進には欠かせません。双方を理解した上で、自社に最適な手法を取り入れていくと良いでしょう。
デジタルマーケティングの手法7選
次に、デジタルマーケティングの具体的な手法を7つ紹介します。
1.ホームページ運用
ホームページは、デジタルマーケティングの基盤です。後述するSEOやデジタル広告もホームページへの流入を目的としているため、まずはホームページを充実させましょう。「商品の販売」「資料請求」「ブランディング」など、マーケティングの目的にあわせて設計し、常に情報を更新することが大切です。アクセスを解析することで、ターゲットのニーズ分析や広告の効果改善にも活かせます。
2.SEO対策/MEO対策
SEO対策は、ユーザーがインターネットで自社に関連するキーワードを調べた際、検索結果の上位にサイトを表示させるための施策です。検索上位のサイトほどユーザーの目につきやすくアクセスしてもらいやすいため、集客効果を高められます。
MEO施策は、Google マップ上で自社が上位に表示されるために行う施策です。たとえば「ラーメン」と検索すると、スマホの位置情報をもとに近隣のラーメン店が検索結果に表示されます。来店につながりやすいため、店舗型ビジネスにとって特に重要な施策です。
SEOツールや、MEOツールを用いた細かい手法がありますが、まずはコンテンツや情報の充実を図りましょう。
3.デジタル広告
デジタル広告とは、オンラインで配信される広告です。大きく分けて、リスティング広告・ディスプレイ広告の2種類があり、配信先が異なります。
- リスティング広告:検索結果の上部/下部に表示される広告。商品やサービスに興味のある、購買意欲の高いユーザーをサイトに誘導する。
- ディスプレイ広告:WebサイトやSNS、アプリで表示される広告。画像や動画など表現方法が多岐にわたる。
デジタル広告は、認知拡大や購買意欲の熟成など、目的にあわせて広告の種類を選ぶことが大切です。
4.メールマーケティング
メールマーケティングとは、メールを通して顧客に商品情報やキャンペーン情報を届けたり、コミュニケーションを取ったりする施策です。すでに一度商品を購入した顧客や、自社を知っている顧客にアプローチするため、新商品にも興味を持ってもらいやすくリピーター獲得が期待できます。
ユーザーの購入意欲を引き上げて成約につなげる「ステップメール」や、定期的に情報を発信する「メールマガジン」などの方法があります。
5.アプリマーケティング
アプリマーケティングとは、スマートフォンやタブレットのアプリを通して、情報収集や顧客との関係性強化を行う施策です。アプリにユーザーを集めることで、ダイレクトに情報を発信でき、ユーザーの囲い込みにもつながります。
アプリの登録情報や行動を分析することで、精度の高いターゲティングができ、広告施策やキャンペーンの精度を高める効果もあります。クーポンやスタンプカード機能など、リアル店舗運営との組みあわせも有効です。
6.マーケティングオートメーション
マーケティングオートメーションとは、マーケティング活動を自動化・効率化させる仕組みです。システム上で管理した顧客情報をもとに、最適なマーケティング施策を導き出します。アクセス分析や広告への反応から見込み客の状況が可視化され、アプローチのタイミングを逃しません。
また、メールマガジンやキャンペーン周知などの業務を効率化できる機能もあります。MAとも呼ばれ、多機能なツールの活用が効果的です。
▼「マーケティングオートメーション」に関連する記事も合わせてチェック
MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方
7.SNSマーケティング
SNSアカウントを運用し、認知拡大やユーザーとのコミュニケーションを取る施策です。
消費者庁委託調査事業「インターネット消費者トラブルに関する総合的な調査研究報告書」によると、企業アカウントの投稿をきっかけに商品・サービスを購入した経験がある人は4割を超えており、売上拡大にも効果的だと分かります。炎上リスクに注意しながらも、共感を集める発信を続けることが大切です。
▼「SNSマーケティング」に関連する記事も合わせてチェック
SNSマーケティングは活用できていますか?押さえておきたいSNSと活用法
デジタルマーケティングを活用しよう
インターネットが普及した現代において、デジタルマーケティングは、どの業界にも欠かせない戦略だと言えます。さまざま手法があるため、自社の目的にあった方法を選び、優先順位をつけて取り組むことが重要です。
また、デジタルマーケティングにはデジタル技術を活用したツールの導入も欠かせません。デジタルマーケティングの最適なPDCAサイクルを追求し、ビジネスの成功に役立ててください。
投稿 デジタルマーケティングとは?Webマーケティングとの違いや7つの施策をご紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 「DMP」とは?マーケティングへの活かし方や導入のメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>近年、Webマーケティングのトレンドとして広がりを見せるDMPですが、DMPについて詳しく理解している方はまだ少ないのではないでしょうか。そこで、本記事では、DMPの概要やマーケティングへの活用法、導入するメリットなどを解説します。Webマーケティングに携わっている方は、ぜひ参考にしてください。
DMPとは
DMPとは「Data Management Platform」の略称で、インターネット上にあるユーザーの行動履歴や購入履歴など、様々なデータを管理・分析してマーケティングに活かすための環境です。DMPを活用すると、自社で取得したユーザーデータと外部で取得したユーザーデータを分析して、マーケティング施策ができます。その結果、各ユーザーに適した広告やおすすめ商品の表示ができ、PV数の増加や離脱率の減少につながります。
DMPの種類
DMPは、「オープンDMP」「プライベートDMP」の2種類に分けられます。以下、それぞれの特徴を説明します。
オープンDMP
オープンDMPは、外部のデータを扱います。外部サイトから取得したユーザーの行動履歴や年齢、性別などの属性情報は全て匿名データとして扱うのが特徴で、自社だけでは把握できない情報を取得できるといったメリットがあります。
プライベートDMP
プライベートDMPは、オープンDMPのデータと自社独自で取得したユーザーの行動履歴や属性情報を組み合わせて保有・管理するプラットフォームを表します。自社の顧客情報をもとに自社に最適なマーケティングを行えるといったメリットがあります。
以上のように、オープンDMPとプライベートDMPは、それぞれ特徴やメリットに違いがあります。どちらを導入するのが良いのか、自社で扱うデータの範囲をもとに決めましょう。
DMPを導入するメリット
DMPを導入するメリットには、以下のようなものがあります。
マーケティングを効率化できる
DMPを導入すると、自社だけでは入手が難しいユーザーデータを使用することでユーザーのターゲティングが可能です。ユーザーをより細かい属性単位でターゲティングでき、マーケティングの効率化につながります。また、素早くデータ取得・分析できることにより、工数の削減にもつながります。
様々なデータを一元管理できる
DMPを導入することで、ユーザーの購入履歴や行動履歴、個人情報などの自社サイトで取得したデータとSNSなどから取得した外部データを一元管理できます。これにより、データ管理の手間が減り、総合的にデータ分析を行うことが可能です。
ユーザーの正確な情報を手にできる
DMPを導入することで、Googleアナリティクスでは入手できない「ユーザーが自社サイトに訪れる直前に滞在していたサイト」「どのような経路をたどって自社サイトにたどり着いたのか」といったデータを取得できます。これにより、より正確なユーザーデータが取得可能となります。
以上のように、DMPには様々なメリットがあり、いずれもマーケティングの効率化につながります。
DMPを活用する方法
ではDMPをどのように活用すればよいのでしょうか。本項目では、DMPの基本機能と活用方法を解説します。
データを収集する
初めにDMPにデータを収集します。外部データはオープンDMPを活用してデータ取得し、社内データはWebサイト内にDMPのタグを埋め込むことにより取得します。
データを分析する
データの収集が完了したら、データを分析していきます。
データ分析では、「正規化」と「セグメント」が行われます。データの正規化とは、データを扱いやすい形に整えることです。あらゆるWebサイトの情報を利用して同一ユーザーを特定します。
データのセグメントとは、行動履歴にもとづいてユーザーを分類分けすることです。購入履歴やアクセス数など、あらゆるデータを用いてユーザーに点数を割り当て、分類します。
データを活用する
データ分析が完了したら、分析したデータを活用していきます。具体的には、セグメント化したユーザーごとにメルマガやリスティング広告を配信していきます。
セグメント化されたユーザーごとに行動を変化させられるため、よりユーザーが興味を引く行動が取れます。
DMPを導入する際の注意点
DMPを導入する際は、下記のような点に注意しましょう。
DMPの導入目的が明確か
DMPによる効果を最大限引き出すためには、DMPの導入目的を明確にする必要があります。「何となく効率化したいから」「何となくPV数を増やしたい」といった理由ではなく、自社サイトの状況をしっかりと把握し、分析した上で、導入目的を決めましょう。
コストに値する結果が得られそうか
DMPツールを導入する場合、初期費用や運用コストがかかります。せっかくツールを導入しても使いこなすことができないなど、払ったコスト分の結果が得られないのでは、意味がありません。コストに値する結果が得られそうか、DMPツールを導入する前にしっかりと検討しましょう。
DMPを理解した方は、DMPツールを調べてみよう
DMPのメリットが理解できた方は、DMPツールを調べてみましょう。DMPツールを調べる際は、「ITreview」がおすすめです。ツールの詳細な情報が取得できるだけでなく、利用者の口コミも確認できます。
DMPツールは、Webマーケティングの効率化を考えている企業には、ピッタリのツールです。自社の状況を考えたうえで、最適なDMPツールを導入してください。
投稿 「DMP」とは?マーケティングへの活かし方や導入のメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ASO対策(アプリストア最適化)の重要性とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>いまや多くの企業で取り入れられているASOですが、ASOを詳細に理解できている方は少ないのではないでしょうか。そこで、本記事では、ASOの概要やメリット、アプリストア内で表示順位を上げるために重要なことを解説します。自社でアプリを提供している企業の方は、ぜひ参考にしてください。
ASO対策はアプリストア内での戦略に欠かせない対策
ASOとは「App Store Optimization」の略称で、日本語では「アプリストアの最適化」と呼ばれています。アプリストア内で自社アプリを上位表示させ、ユーザーに見つけてもらいやすくするための手法です。SEOのアプリ版と考えるとすんなりと理解できるでしょう。
ASO対策の重要性
GooglePlayストアやAPPstoreなどのアプリストア内で「電卓アプリ」と検索すると、いくつものアプリが順番に並んで表示されます。多くのユーザーは、上位に表示された電卓アプリの中から自分に使いやすそうなモノをインストールするでしょう。
その結果、下位に表示されたアプリはユーザーの目に留まることはなく、当然インストールもされません。このように、アプリストア内での表示順位はダウンロード数を伸ばすために非常に重要であり、表示順位を上げるためにASOは存在します。
では、アプリストア内で表示順位を上げるためには、具体的にどんな施策を行えばよいのでしょうか。これについては、記事の後半で解説します。
ASO対策を行うメリット
ASO対策を行うことで、下記のようなメリットが得られます。
メリット1:広告費の削減につながる
ASO対策を行う以外にアプリのダウンロード数を伸ばす方法として、バナー広告・SNS広告・動画広告などがあります。さまざまな広告を打ち出すことによって、認知度を高めてダウンロード数を伸ばす方法です。しかし、広告を出稿するためには費用がかかる上に、長期間広告を出稿し続けるには巨額の費用が必要です。そのため、中小企業などの広告にかけられる予算が限られている企業は、長期間に渡って広告を出し続けるのが難しいでしょう。
しかし、ASO対策であれば、アプリストア内から自然とダウンロード数が増加する効果を狙えるため、コストが抑えられます。その結果、広告費の削減へとつながります。
メリット2:自社アプリの露出度が高くなる
通常、アプリストア内でのアクセス数とダウンロード数には相関関係があり、アプリストア内でのアクセス数が増加すればするほど、ダウンロード数も伸びていきます。ASO対策を行えば、アプリストア内で自社アプリの露出度が高くなるため、自然とダウンロード数も伸びていくでしょう。
このように、ASO対策には、さまざまなメリットがあります。メリットをしっかりと理解したうえで、ASO対策に取り組みましょう。
アプリストア内で表示順位を上げるために重要なこと
アプリストア内で表示順位を上げるためには、以下の点が重要です。
・アプリ名
アプリ名は、簡潔で分かりやすいのがよいですが、ユーザーに覚えてもらいやすいように、他のアプリと被らない独創性も重要です。Appstoreでは30字以内、GooglePlayストアでは、50字以内でアプリ名を入力する必要があります。
・サブタイトル
サブタイトルでは、アプリの魅力をユーザーに伝えます。Appstoreのサブタイトルの文字数上限は30文字で、簡潔で分かりやすいアプリの説明が求められます。
・アイコン
アイコンは、ユーザーがアプリストア内で最初に目にする部分であり、アプリのインストール後も頻繁に目にするため非常に重要です。ユーザーの目に留まりやすい独創的なデザインが求められます。また、ユーザーにアプリを覚えてもらうといった観点から一度決定したアイコンを頻繁に変更することはおすすめできません。そのため、じっくりと時間をかけて制作しましょう。
・スクリーンショット
アプリのスクリーンショットを掲載することで、アプリの雰囲気やイメージを視覚的にユーザーに伝えられます。Appstoreでは、最大スクリーンショットを10枚掲載できます。特に最初の1〜3枚目のスクリーンショットはユーザーに見られやすいため、アプリの魅力が伝わるようなスクリーンショットを選びましょう。
以上のように、アプリストア内での表示順位には、さまざまな要素が関わっています。
ASO対策について理解できた方は、ASOツールを調べてみよう
ASO対策は、アプリのダウンロードを伸ばすうえで非常に重要です。ASOについて理解できた方は、ASOツールを調べてみましょう。調べる際は、ITreviewのサイトがおすすめです。製品の詳細や特徴が分かりやすく掲載されています。数あるASOツールを比較して、自社に最適なツールを導入してください。
投稿 ASO対策(アプリストア最適化)の重要性とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ユーザーデータをビジネスに役立てる!4つの目的別「DMP」ツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>近年、Webマーケティングのトレンドとして人気を集めるDMPツールですが、種類が多く、どれを選べば良いか迷っている人も少なくないでしょう。そこで本記事では、目的別におすすめのDMPツールを4つご紹介します。サイト運営に携わっている方は、ぜひ参考にしてください。
世界中で利用される「Salesforce Marketing Cloud」
株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する「Salesforce Marketing Cloud」は、リアルタイムのユーザーデータを利用して最適なコミュニケーションを実現するツールです。Webメディアだけでなく、メールやSNSなどあらゆるメディアやデバイスのコミュニケーションを最適化できるのが特徴です。また、Slackとのデータ連携をスムーズに行えるといったメリットもあります。このような汎用性の高さから、世界中のユーザーに利用されています。
実際に、Salesforce Marketing Cloudを利用するユーザーからは、「他社製品と比較してデータコネクトが柔軟的で、利用可能チャネル数の豊富さ、ツール内でSQLを記載できる点からローデータを取り込むだけで、高度なシナリオ作成が可能」「メールやシナリオ作成のGUIが優れているため、直感的に操作できる」「メール作成もテンプレートが多く、必要に応じてコードを記述して対応可能なため、制作と管理工数をかなり削減できた」といった口コミが寄せられています。
無料で利用できるDMPツール「Juicer」
ログリー株式会社が提供する「Juicer」は、無料で利用可能なDMPツールです。0円で利用できる基本プランには、「ペルソナ分析」「A/Bテスト」「ユーザー分析」などサイトの分析・改善に必要な基本機能が揃っています。コストを抑えてDMPに取り組みたい方におすすめのツールです。
実際に、Juicerを利用するユーザーからは、「基本機能は全て無料のため、導入しやすい」「万能でありながら、シンプルに使用できる高機能分析ツール」といった口コミが寄せられています。
直感的な操作が魅力の「b→dash」
株式会社データXが提供する「b→dash」は、ノーコードで利用可能なSaaS型マーケティングプラットフォームです。SQLやプログラミングなどの技術がなくても直感的に操作可能なため、エンジニアではない方でも簡単にデータを分析できます。また、BI機能やWeb接客機能など16種類もの機能がオールインワンで搭載されており、導入後別のツールを導入する必要はありません。
実際に、b→dashを利用するユーザーからは、「直感的な操作で日に日に使いこなすことができ、MAとBI両方で重宝している」「b→dashは、UI/UXが優れており、操作方法が分かりやすく、操作のガイドラインもあるため、セグメントデータの作成やシナリオの設定といった作業を誰でも簡単に行うことができる」「色々な機能が網羅されており、複数のツールを使い分ける必要がない点が良いと思う」と言った口コミが寄せられています。
b→dashは、業界業態に合わせたテンプレートがあることもあり、業界・業種問わず500社を超える企業に導入されています。テンプレートを選択するだけで誰でも簡単にデータマーケティングができるため、幅広い業界におすすめのツールだと言えるでしょう。
サポートが充実している「activecore marketing cloud(アクティブコアマーケティングクラウド)」
株式会社アクティブコアが提供する「アクティブコアマーケティングクラウド」は、200を超える企業に導入されている独自開発型のマーケティングプラットフォームです。導入・運用のサポート体制が充実しており、自社開発という強みを活かして「導入プランのご提案」「導入設定」「メールサポート」「定期メンテナンス」「トレーニングセミナー」の5つのサポートを準備しています。
株式会社アクティブコアが提供する「アクティブコアマーケティングクラウド」は、200を超える企業に導入されている独自開発型のマーケティングプラットフォームです。導入・運用のサポート体制が充実しており、自社開発という強みを活かして「導入プランのご提案」「導入設定」「メールサポート」「定期メンテナンス」「トレーニングセミナー」の5つのサポートを準備しています。
実際に、アクティブコアマーケティングクラウドを利用しているユーザーからは、「システム系に詳しくないマーケット担当者でも簡単に操作でき、心配な際はサポートしてくれるため、安心して利用できる」「アクセス解析、レコメンド表示、MAが全て1つのプラットフォームで管理できるため、ユーザーの行動履歴を可視化できる」「使い勝手がよく、スキルがない人でも簡単に操作可能な点が良いと思う」といった口コミが寄せられています。
まずはDMPツールを比較しよう
各ツールの特徴が理解できた方は、複数の製品をITreviewのサイトで比較しましょう。比較することで、より製品の特徴が分かり自社に最適なDMPツールを選定できます。自社の現状を把握した上でしっかりと比較・検討して、最適なDMPツールを導入してください。
投稿 ユーザーデータをビジネスに役立てる!4つの目的別「DMP」ツールをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ECサイトにレコメンド機能を導入するメリットとは?機能や仕組みを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>いまや多くのECショップやWebサイトで、レコメンドエンジンが活用されていますが、詳細に理解している方は少ないでしょう。そこで本記事では、レコメンドエンジンの概要から仕組みと種類、メリット・デメリットまで解説します。ECショップやWebサイトを運営している方は、ぜひ参考にしてください。
レコメンド機能とは
レコメンド機能とは、ECサイトやWebサイトで、ユーザーの好みに合わせて「おすすめの商品」や「おすすめの記事」を提案するシステムです。レコメンドエンジンによっておすすめされる商品は、ユーザーの購入履歴や閲覧履歴に基づいて決定します。
ユーザーは効率的に欲しい商品を見つけられ、企業側は販売促進できるため、買い手と売り手両方に利点があるのがレコメンドエンジンの特徴です。
レコメンドエンジンの仕組みの種類
レコメンドエンジンの仕組みは、下記の5種類です。
協調フィルタリング
協調フィルタリングは、レコメンドエンジンで一番活用されている仕組みです。ユーザーの購入履歴やWebサイトの閲覧履歴をもとに、おすすめする商品・コンテンツが選定されます。さらに、協調フィルタリングは、「アイテムベース」と「ユーザーベース」の2つに分類されます。
ルールベースレコメンド
ユーザーが、ある商品Aを購入した場合、それに関連する商品Bをおすすめする仕組みです。例えば、パソコンを購入したユーザーに対して、マウスをおすすめしたり、一眼カメラを購入したユーザーに対しては、レンズをおすすめしたりするのがルールベースレコメンドです。
ユーザーの行動を予測しておすすめ商品を表示させるのが、ルールベースレコメンドの特徴だと言えるでしょう。
コンテンツベースレコメンド
コンテンツベースレコメンドは、事前にグルーピングしておいた商品をおすすめとして表示させる仕組みです。例えば、あるイヤホンAを閲覧したユーザーに対して、別商品のイヤホンBやイヤホンCをおすすめ商品として表示させるのが、コンテンツベースレコメンドです。
グルーピングする商品は自由に決められるため、閲覧履歴や購入履歴などのデータが十分にたまっていないユーザーに対してもおすすめ商品を表示できます。
パーソナライズレコメンド
ユーザーの行動履歴を分析することで、そのユーザーの関心が高いと思われる商品をおすすめする仕組みです。パーソナライズレコメンドでは、協調フィルタリングのように他人の行動履歴は見ないため、よりユーザーに適した商品をおすすめできます。
ハイブリッド・レコメンデーション・システム
ハイブリッド・レコメンデーション・システムは、ここまでに紹介した4つのレコメンドシステムの仕組みを組み合わせる手法です。複数の仕組みを組み合わせることで、それぞれのレコメンドシステムのメリットを掛け合わせて自社独自のレコメンドシステムを構築できます。
最近では、アメリカに本社を構えるNetflix社をはじめ、多くの企業でハイブリッド・レコメンデーション・システムが活用されています。
以上のように、レコメンドエンジンの仕組みには様々な種類があります。そのため、それぞれの仕組みをしっかり理解したうえで、自社に適した仕組みを導入しましょう。
レコメンドエンジンのメリット
レコメンドエンジンを導入するメリットは、以下の通りです。
購買率の向上
サイトを訪れたユーザーに興味を引く商品をおすすめできるため、闇雲に商品をおすすめするよりも購買率が向上します。また、ECサイトだけでなく、Webメディアでもユーザーの興味関心が強いコンテンツをおすすめできるため、PV率や滞在時間も向上します。
リピーターの増加
ユーザーに適した商品をおすすめできるサイトは買い物が楽しめるため、またこのサイトで買い物がしたいとユーザーに思わせることができます。その結果、リピーターの増加につながります。また、ユーザーの潜在意識を引き出し、商品を購入してもらえる点もレコメンドエンジンのメリットでしょう。
レコメンドエンジンのデメリット
レコメンドエンジンを導入するデメリットは、以下の通りです。
商品やコンテンツが少ないサイトでは、効果が薄い
出品数が少ないECサイトや記事数の少ないWebメディアでは、ユーザーにおすすめできる商品やコンテンツが少ないため、レコメンドエンジンの効果をあまり発揮できません。出品数やコンテンツ数が少ないサイトは、出品数の増加やコンテンツの充実から取り組みましょう。
コールドスタートである
まだ商品を一度も購入していないユーザーや初めてサイトに訪れるユーザーに対しては情報がないため、おすすめする商品の精度が低くなってしまいがちです。
レコメンドエンジンは、購入履歴や閲覧履歴などユーザーに対する情報が溜まるほど、効果を発揮するため、複数のレコメンドエンジンの仕組みを取り入れるなど、コールドスタートを補う必要があるでしょう。
代表的なレコメンドエンジン3つ
ここで代表的なレコメンドエンジンをご紹介します。ECサイトはもちろん、サイト上でなんらかのコンテンツを取り扱っているなら、ECサイトでなくとも使えるものもあるのでぜひチェックしてみてください。
幅広いサイトで利用できるKARTE
株式会社プレイドが提供する KARTE は、心地よい顧客体験を通してLTVの向上や事業の成長を実現するツールです。KARTEの特徴は、顧客の現在・過去のデータをつなぎ、顧客1人ひとりの体験を鮮明に可視化できる点です。お客様1人ひとりの状況を深く理解し、それぞれの状況に相応しいコミュニケーションを通じて、ECサイトやWebサイトのサービス向上を実現します。
また、「ユーザー行動分析」「セッションリプレイ」「ウェブ・アプリ内接客」「データ連携」などの機能を搭載した高機能ツールであるにも関わらず、初心者でも使いやすいのが魅力です。直感的に使用できるシステムなので、プログラミングなどの専門知識を持ち合わせていない初心者でも、シンプルにサイトを運営できます。上級者、初心者問わず幅広い方が利用しやすいレコメンドエンジンだと言えるでしょう。
実際に、KARTEを利用するユーザーからは、「初心者は直感的に使え、上級者は自由度高くカスタマイズが可能なため、幅広い層が使いやすいようにできている」「テンプレートが豊富なため、ポップアップ施策を制作したことがない初心者の方でも、画像とテキストさえ準備すれば簡単に設定できる」「ユーザーセグメントがかなり細かくできるため、Webサイトに訪れたユーザーをタイプ別に、適切な案内ができるおかげで、ユーザビリティの高いサイトにすることができた」といったプラスの口コミが多数寄せられています。
さらに、KARTEは、ECサイトやWebメディアに限らず様々な業界に導入されています。導入実績のある業界は以下の通りです。
- 金融・保険
- 人材
- ECサイト
- アパレル・スポーツ・アウトドア
- 化粧品
- BtoB SaaS
- メディア・コンテンツ
- 旅行・運輸
- 不動産
- アプリビジネス
豊富な機能が魅力のCustomerRings(カスタマーリングス)
株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する カスタマーリングス は、CRM/MAツールが進化した顧客実感型マーケティングプラットフォームです。顧客管理から、分析・施行までを1つのツールで完結できる機能の豊富さが魅力です。「データ統合(CDP)」「セグメント(顧客抽出)」「分析(BI)」「アクション(MA)」以外にも、以下の顧客実感機能を搭載しています。
- カスタマージャーニーマップ
- 分析ドリルダウン
- 実感モニタリング
- テキストマイニング
- シナリオマップ
実際にカスタマーリングスを利用しているユーザーからは、「多機能で操作画面が分かりやすい」「分析の柔軟性とスピード感が優れている」といった口コミが多数寄せられています。
カスタマーリングスは、多機能がゆえに初心者が完全に使いこなすのは少し難しいかもしれません。しかし、FQAサイトを準備していたり、Webフォーム・メール・電話で問い合わせできたりと、サポート体制が充実しているため疑問点をすぐに解決できます。
サポートが充実しているRtoaster(アールトースター)
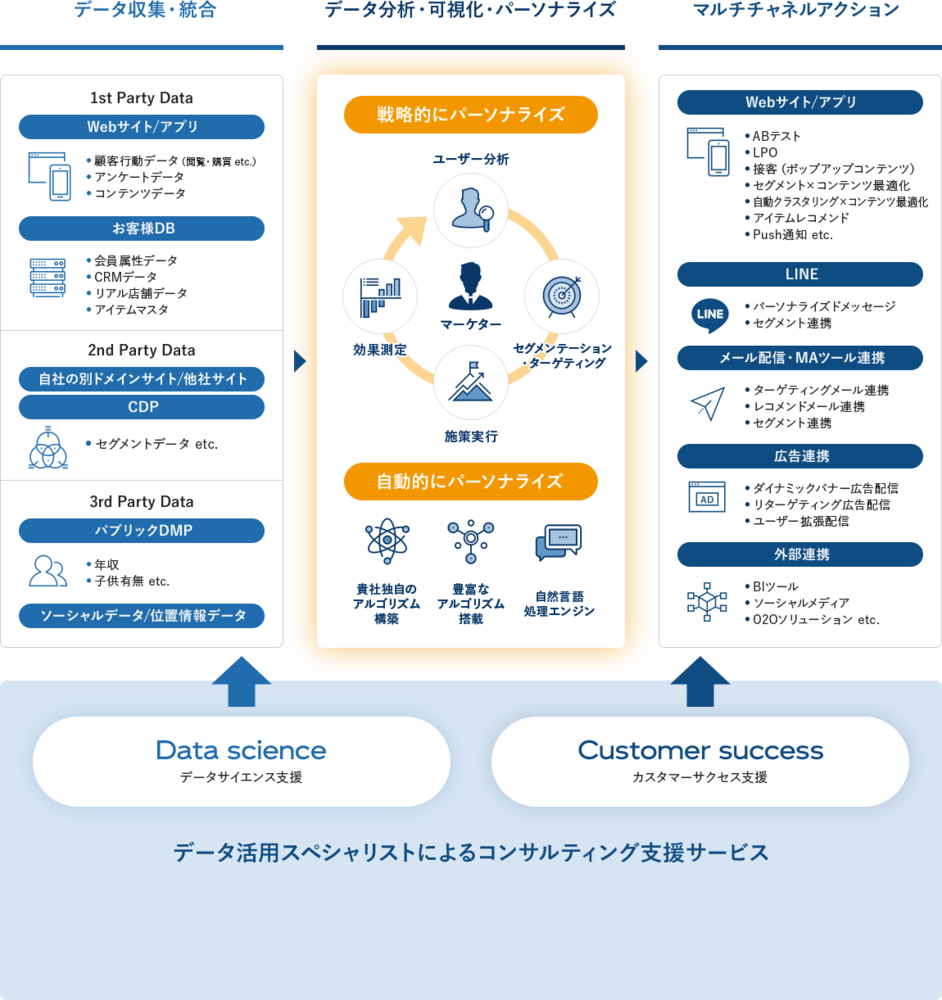
株式会社ブレインパッドが提供している Rtoaster は、高精度なパーソナライズでビジネスの成果を高めるパーソナライゼーション基盤です。「Rtoaster insight+(インサイトプラス)」「Rtoaster action+(アクションプラス)」「Rtoaster reach+(リーチプラス)」の3機能群で構成されており、顧客データを統合して1人ひとりに適した自然なアクションを促すことで個別接客を実現します。LINE・プッシュ通知(アプリ)などの外部チャネルに、パーソナライズされた情報を発信できるのも魅力です。
また、サポート体制が充実しており、対応満足度は98.6%を記録しています。初めてレコメンドエンジンを使用する方にとっても、使いやすい製品であると言えるでしょう。
実際に、Rtoasterを利用しているユーザーからは、「使い方に迷っても担当者とコミュニケーションを取れる時間を契約から時間が立った後でも取れるのが良い」「高機能ツールのため、使いこなせるか心配だったが、サポート体制が充実しているため安心である」といった口コミが寄せられています。
Rtoasterの導入社数は350社を超えており、幅広い業界で使用されています。多くの方におすすめできるレコメンドエンジンだと言えるでしょう。
レコメンドエンジンを調べてみよう
レコメンドエンジンについて理解が深まった方は、レコメンドエンジンツールを調べてみましょう。レコメンドエンジンツールを使用することで、初心者でも簡単に自社サイトの商品やコンテンツをユーザーにレコメンド可能です。
ツールを調べる際は、ITreviewのサイトがおすすめです。ツールの詳細な情報が分かるだけでなく、実際にツールを利用しているユーザーの口コミも確認できます。自社サイトの売上やPV数を伸ばしたい方は、ぜひチェックしてみてください。
投稿 ECサイトにレコメンド機能を導入するメリットとは?機能や仕組みを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 エントリーフォームを見直してサイトを改善!押さえておきたいEFOツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>今や多くの企業で導入されているEFOツールですが、様々な製品がリリースされているため、どれを選べば良いか迷っている方もいるでしょう。そこで本記事では、押さえておきたいEFOツールを5つご紹介します。EFOツールの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
EFOツール1:Sprocket
株式会社Sprocketが運営するSprocketは、ユーザーの行動をもとにコンバージョンを最適化するツールです。「行動データの計測」「シナリオ作成」「ユーザー数分析」などサイトを利用しやすくするために必要な機能が揃っているのが特徴です。これにより、ユーザーの行動を分析し、サイト内で使いにくい点や離脱しやすい点(フリクションポイント)を探し出し改善へとつなげていきます。
実際にSorocketを利用するユーザーからは、「LPや商品ページでユーザーの動向に合わせたポップアップ表示やシナリオ設定が可能」「フォロー体制がしっかりしっかりしており、分からない点は丁寧に教えてくれる」といった良い口コミが多数寄せられています。
平均CVR改善率は145.4%、これまでに300社以上のサイトを改善した実績を残しているため、安心して利用可能です。
EFOツール2:SiTest
株式会社グラッドキューブが運営するSiTestは、サイトの解析から改善までを一元化可能な国産のツールです。「A/Bテスト機能」「パーソナライズ機能」「ポップアップ機能」などWebサイトを使いやすくするために必要な機能が全て備わっているため、余計な追加ツールを導入することなくシンプルな運用が可能です。
実際にSiTestを利用するユーザーからは、「ABテストする素材やテキストを用意しておくだけで即時開始できるため、スピード感を持ってPDCAを回せる」「テスト結果が視覚的に分かるため、他部署への共有も簡単に行える」といった口コミが寄せられています。
無料トライアル期間が設けられており機能の制限なく利用できるため、導入前に自社に適したツールか見極めることも可能です。
EFOツール3:エフトラEFO
株式会社エフ・コードが運営するエフトラEFOは、ガイドナビゲーションやリアル・タイムアラート、離脱ブロックなどの機能により、ユーザーの離脱率を改善するツールです。導入時間がわずか15分で、スピード感を持って改善サイクルを回せる点が魅力です。
実際にエフトラEFOを利用するユーザーからは、「タグマネージャー経由で導入が素早く簡単だった」「導入のハードルが比較的低く、一度導入した後は、ほぼ手放しで運用可能」といった口コミが寄せられています。
2013年からサービスを開始し、2022年9月現在では約7,000件も導入されている確かな実績があるため、安心して利用できます。
EFOツール4:GORILLA EFO
株式会社エフ・コードが運営するGORILLA EFOは、1タグ設置で簡単に導入できるEFOツールです。タグを設置するだけで導入できるため、今使っている入力フォームを変更することなく最適化できるのが特徴です。また、入力サポート機能の種類も非常に豊富で、他社平均が11機能であるのに対して、20種類もの入力サポート機能を利用できます。
実際にGORILLA EFOを利用するユーザーからは、「導入はタグを埋め込むだけという、エラーの起こりようがないシンプルな機能」「機能や性能が全て揃っていてとても使い勝手が良い」といった口コミが寄せられています。
月額利用料が9,800円と安価なため、初めてEFOツールを導入する方にとっても非常におすすめのツールです。
EFOツール5:EFO CUBE
株式会社エフ・コードが運営するEFO CUBEは、「入力支援機能」と「分析レポート機能」の2つを兼ね備えたEFOツールです。初期費用0円、サポート費用0円、月額利用料50,000円といったシンプルな料金体系が魅力のひとつです。
実際にEFO CUBEを利用するユーザーからは、「EFOの機能が多彩で、それをスクラッチで実装していくことを考えると、開発費用が膨らむため、このツールを導入するだけで、EFO対策できるのはメリットが大きい」「一般的なEFOの料金算出手法は、追加機能などの課金によって複雑化されがちである。しかし、EFO CUBEの料金算出手法は、1ドメインに対して5フォームまで利用可能といった縛りのみであるため分かりやすい」といった口コミが寄せられています。
サポートも充実しており、ツールの導入サポートはもちろん、導入後のフォーム改善のサポートまでも対応してくれます。そのため、EFOツール初心者でも安心して利用可能です。
複数のEFOツールを比較しよう
それぞれのツールに関して理解できた方は、複数のEFOツールを比較しましょう。製品の比較には、視覚的に複数製品を比較でき、利用者の口コミもチェック可能な「ITreview」がおすすめです。
自社の現状を踏まえて、しっかりと比較・検討することで、自社に最適なEFOツールを導入してください。
投稿 エントリーフォームを見直してサイトを改善!押さえておきたいEFOツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 サイト改善に欠かせないEFOって知ってる?解説から取り入れ方を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>今や多くの企業で使用されているEFOですが、よく知らない方もまだまだ多いでしょう。そこで本記事では、EFOの用語説明から、重要性、取り入れ方までご紹介します。EFOに興味がある方やサイト運営を行っている方は、ぜひ参考にしてください。
EFOとは
EFOとは「Entry Form Optimization」の略称で、日本語では「入力フォーム最適化」と呼ばれています。EFOを行うことによって、ユーザーの動作を遮ることなく、スムーズに申し込みや購入を完了させられます。
EFOの重要性
EFOを導入する目的は、Webサイトの入力フォームをユーザーが利用しやすいように最適化し、サイトからの離脱率を低減することです。
冒頭でも紹介した通り、使いづらい入力フォームはユーザー離脱率が高くなり、大きな機会損失を生みます。しかし、EFOを行うことにより入力フォームが使いやすくなり、ユーザーはストレスなく注文を完了できるため、結果的に離脱率が下がり機会損失も減少します。
では、具体的にどのような理由でユーザーは入力フォームから離脱してしまうのでしょうか。次の項目では、ユーザーが入力フォームから離脱する原因について見ていきます。
ユーザーが入力フォームから離脱する原因
ユーザーが入力フォームから離脱する原因は、主に以下のようなことが考えられます。
入力フォームのデザインに問題がある
1つ目の離脱原因は、入力フォームのデザインに問題が見られるケースです。
具体的には、「文字が小さすぎて読みづらい」「入力項目の感覚が狭すぎてスマートフォンだと操作が困難」などのような入力フォームのデザインは好ましくありません。特に、目が悪く機械操作が苦手な高齢者は、入力の途中で挫折してしまう可能性が高いです。
さらに、やっとの思いで入力を完了したとしても、頻繁に入力エラーが発生するフォームや入力エラーのたびに前の情報が削除されてしまい再度1から入力を求められる入力フォームも改善の必要があります。
入力フォームが長すぎる
長すぎる入力フォームは、ユーザーに大きな負担を与えます。ユーザーの中には、入力フォームの長さを見ただけで、サイトから離脱してしまう人もいます。
また、入力項目が多いと入力ミスも増えやすいため、ユーザーにストレスを与えてしまう可能性があるため注意が必要です。
セキュリティ面で負担を与えてしまう
入力フォームは、住所や電話番号など個人情報を入力する場所です。そのため、セキュリティ面でユーザーに不安を与えてしまうと「個人情報が流出したら嫌だから購入は諦めよう」といったように、離脱するユーザーが増えてしまいます。
このように、ユーザーが入力フォームから離脱するのには様々な理由が存在します。
では、ユーザーの離脱率を低下させるためには、どのようなEFOを実施すれば良いのでしょうか。次の項目からは、離脱率を低減させるためのEFOを紹介していきます。
EFO対策の代表例
・入力項目の削減
入力項目の削減は、ユーザーの負担低減につながります。入力項目削減のために、まずは本当に必要な項目はどれなのか現状の入力項目の見直しから行いましょう。
しかし、サイトによっては、どうしても入力項目数を減らせない場合もあるでしょう。そのような場合は、表示や文章を分かりやすくすることで対策しましょう。
・入力例の表示
ユーザーの入力ミスを削減するためには、入力例の表示が得策です。住所や郵便番号、電話番号などあらかじめサイトに入力例が表示されているだけで、何を入力する場所なのか一目で理解できるようになります。
また、半角文字などで入力を求める場合は、赤などの目立つ色で注釈を記載すると親切でしょう。
・エラーや入力漏れの指摘
エラーや入力漏れを分かりやすく指摘することも大切です。具体的には、入力ミス項目は入力枠を赤色で表示したり、警告文を出したりしてユーザーに指摘を求めるのが良いでしょう。
また、入力の進捗を表示する進捗率を表示したり、入力開始画面に入力完了までの目安時間を記載したりしておくと、ゴールまでの時間が明確になり離脱率が低減します。
・EFO専用ツールの導入
EFOツールの導入によって、離脱率を低減させるのもおすすめです。
EFOツールには、入力支援機能、レポート機能、運用サポート機能など入力フォームを使いやすくするために様々な機能が準備されています。これにより、どの項目でユーザーが離脱しやすいのか分析でき、改善へとつなげられます。
対策の一環として、EFOツールを調べてみよう
EFOの概要が理解できた方は、EFOツールを調べてみましょう。EFOツールは様々な企業から数多くのツールがリリースされているため、複数のツールを比較するのも良いでしょう。EFOに対する理解を深めて、自社の入力フォームを最適化してください。
投稿 サイト改善に欠かせないEFOって知ってる?解説から取り入れ方を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 メールトラッキングツールとは?メールマーケティングを効率化するツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、メールトラッキングツールを導入したい人に向けて、おすすめのツールを3つご紹介します。ツールごとの特徴や魅力を解説しますので、ひとつずつ確認して使いやすいツールを見つけてみてください。
メールトラッキングツールとは
メールトラッキングツールとは、メルマガや営業メール等を追跡(トラッキング)するツールのことです。このツールを利用することで、メールを受信したユーザーが行う次のアクションを可視化でき、メールマーケティングの分析に利用できます。
- メール開封・既読のタイミング
- メール内URLのクリック
- 添付ファイルのダウンロード
メールに対するユーザー行動を事細かに分析できれば、どのタイミングでメールを配信するのが最適なのか判断できます。またユーザーがどのようなメールの内容に興味を持つのかを数字で分析できるため、高品質なメールマーケティングを行えます。
ほかにもメールトラッキングツールには、顧客情報の管理、メール配信のスケジュール管理、メールプラットフォームの統合といった、マーケティングを効率化する機能があります。メールマーケティングをツール内で完結できることから、現在多くの企業がメールトラッキングツールを導入しています。
メールトラッキングツールが求められる理由
近年、メールトラッキングツールを含むITツールを求める企業が増加しています。その理由は、大きく分けて2つあります。
- IT導入補助金の利用
- 顧客情報の見える化
IT導入補助金の利用
※2022年9月時点の情報です。
日本では様々な補助金制度が設けられており、そのなかにはIT関連の補助金もあります。メールトラッキングツールを含む「IT導入補助金」は、業務効率化のために新たに導入されたソフトウェアやクラウドサービスを対象として補助を適用できます。主に次のような補助項目が設けられています。
- 通常型:補助率1/2以内
- 低感染リスク型ビジネス枠:2/3以内
この補助金は、企業のデジタル化や業務効率化をサポートするために登場した制度であり、補助を利用することによって、通常価格よりも安くツールを導入できます。多くの企業がデジタル化や業務効率化をリーズナブルに推進するため、メールトラッキングツールに注目しているのです。
※IT導入補助金の詳細はこちら。条件・申し込み期限等が決められているのでご注意ください https://www.it-hojo.jp/
メールマーケティングで収集した顧客情報の見える化
従来のメールマーケティングでは、メールを配信した後に顧客の動きが見えず、ただ待つだけでした。一方、メールトラッキングツールを活用すれば、見ることができない顧客の動きを「見える化」でき、今後の営業戦略に役立つデータを蓄積できます。
顧客がメールに対して行うアクションを細かく分析できれば、今後の方針を立てやすくなるだけでなく、ユーザーニーズを分析する手段として役立てることができます。また今まで見ることができなかった顧客の動きが分かれば、売上につながる営業戦略を練ることが可能なため、今多くの企業で求められています。
押さえておきたいトラッキングツール3選
1:Mailtrack
「Mailtrack」は、The Mail Track Companyが提供するメールトラッキングツールです。Chrome・Firefox・Edge・Operaの拡張機能として利用でき、Gmailに特化したトラッキングを実施できます。送信した相手の情報をリアルタイムで確認できることはもちろん、ポップアップ機能を使うことによって、ユーザーアクションの見落としを減らせます。
言語自体が英語ではありますが、シンプルで使いやすいのが特徴です。無料で利用できるため、気軽に導入できるでしょう。
2:Mailcastr
「Mailcastr」はPyten Labs Pvt. Ltd.が提供するメールトラッキングツールです。GmailやGsuiteから送信したメールを追跡することが可能で、メール開封と同時にデバイスやIP情報などを細かく情報収集できます。また、このツールも英語版で利用する必要があります。
無料版ではメール追跡やツールブランディング機能を使用できますが、有料版を利用すればリンク追跡やメールテンプレート設定も利用できます。本格的なメールマーケティングを実施したいなら有料版の導入がおすすめです。
3:Mixmax
「Mixmax」はMixmax Inc.が提供するメールトラッキングツールです。Gmail用のトラッキングツールで、ユーザーがアクションを起こしたデータを蓄積し、時間、名前、場所、デバイスといった情報を事細かに分析できます。
ユーザーアクションはアラートで通知が届くため、リアルタイムの情報を収集できるのが特徴です。
もっと詳しくメールトラッキングツールを比較したいならITreviewをチェック
メールトラッキングツールは、メールを受信したユーザーのアクションを「見える化」して分析できることから、営業戦略の効率化を図れます。ただし、基本的に英語版として利用するツールなので、まずは無料体験版をダウンロードして使いやすさを確認するのがおすすめです。
ご紹介したツール以外にも製品を比較したい人は、「ITreview」を利用して自分にぴったりのメールトラッキングツールを見つけてください。
投稿 メールトラッキングツールとは?メールマーケティングを効率化するツール3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 無料で使えるツールも紹介!ホームページ作成ツール7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>いまや多くの企業がホームページ作成ツールを使用して、自社サイトやネットショップを作成しています。しかし、多くの企業から様々な製品がリリースされているため、どれを選べばよいか迷っている人もいるでしょう。そこで、本記事では目的別に7つのホームページ作成ツールをご紹介します。ホームページ作成ツールの利用を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
無料で利用できるホームページ作成ツール
無料で利用できるホームページ制作ツールを探している方には、下記の5製品がおすすめです。
Wix
Wix.inc,Incが運営するWixは、世界中で1億人以上が利用するホームページ制作ツールです。直感的な操作でホームページを制作できるのが特徴で、800以上のテンプレートから最適なスタイルを選択し、ドラッグ&ドロップで自由に機能をデザインできます。
Wixを利用するユーザーからは、「直感的にWebページを作成できる最高のサービス」「テンプレートが豊富にあるため、ベースを選び、文章を加えるだけでそれっぽいホームページが作成できる」といった口コミが多数寄せられています。
Wixには無料版と有料版があり、有料版では独自ドメインの設定、広告の非表示設定が可能です。
・Wixの参考価格
無料(ホームページプラン:900円/月)
・Wixの参考レビュー
コーディングの知識も予算もない場合こういったサービスしか選択肢がないので、取っ掛かりにはよいと思います。こういったサービスを利用してしばらく運用し、必要なコンテンツを洗い出すのもよい。
Wixへのレビュー「60点くらいのウェブサイトなら簡単に作れる」より
Googleサイト
Google社が提供するGoogleサイトは、完全無料で利用できるWebサイト作成ツールです。無料で利用できるツールでありながら、スマホやPCからアクセスしてリアルタイムで協同作業できる機能、サクセス権限の制限機能を有するなど機能が充実しています。
しかし、あまり高度なホームページは作成が難しいため、デザイン性や機能性の高いサイトを制作したい方は注意が必要です。自社内だけで使用するポータルサイトなど利用範囲が狭いサイトの作成を検討している方におすすめです。
・Googleサイトの参考価格
無料
・Googleサイトの参考レビュー
完全無料で社内ポータルを作成することが可能で、専門的な知識がなくても簡単に社内ポータルを作ることができる。スマホ対応になっていることも強み。また、社内ポータルを作る際に、複数人での編集が可能で、部署内のメンバーで分担してページの作成を進めれば、スピーディーに作成することができるのも良いポイントと感じる。
Googleサイトへのレビュー「社内ポータルの作成に」より
クローバ PAGE

クローバ株式会社が展開するクローバPAGEは、コーディングの必要が一切なく、スマートフォンに完全対応したホームページをすぐに作成できるのが特徴です。クローバPAGEの利用者からは、「テンプレートの作成や既存のプロジェクトの再利用もでき、サイトを立ち上げるスピードが非常に早い」「UI/UXが利用者に寄り添ったサービス」といった口コミが多数寄せられています。
クローバPAGEには、無料版と有料版があり、有料版ではメッセージの一斉配信や決済機能を利用できます。
・クローバ PAGEの参考価格
ベーシック:0円(プレミアム:2,000円/月)
・クローバ PAGEの参考レビュー
ブログ機能(記事)があるので、他のブログサービスと併用せず、ひとつにまとめることができるのはクローバの良さ。
クローバ PAGEへのレビュー「小さな事業にぴったりのホームページ作成サービス」よえい
あと、オンラインサロンをやりたい人は、定期決済とクローズのコミュニティ、投稿記事の限定公開ができるのでとても便利です。(別のプロジェクトで使ってます)
ペライチ
株式会社ペライチが展開するペライチは、素早くホームページを作成・公開できるホームページ作成ツールです。「デザインを選ぶ」「内容を作る」「公開する」のたった3ステップでホームページを公開できます。
ペライチの利用者からは、「難しいことを考えずに、文字通りペライチのサイトを瞬時に作成・公開できる」「作成開始から公開まで1時間程度でできるため、急ぎで立ち上げる必要がある場合などに便利」といった口コミが寄せられています。
30日間無料でお試し利用も可能なため、一度使用感を試してみてはいかがでしょうか。
・ペライチの参考価格
スタートプラン:0円(1ページのみ)
・ペライチの参考レビュー
ペライチの名の通り、1P内で全てのアナウンスが可能。
ペライチへのレビュー「優良な無料HP作成サイト」より
簡潔かつ必要充分という、無料サイト作成の企業では一番容易に使い勝手が良い。
ジンドゥー
JindoJapanが展開するジンドゥーは、世界中の3,200万以上のサイトで使用されているホームページ制作ツールです。「デザインを選ぶ」「内容を作る」「公開して分析する」の3ステップでホームページを公開できます。
ジンドゥーの利用者からは、「iPhoneのみでホームページを制作できる」「PC操作さえできれば、小学校低学年の子でも利用可能な優れたツール」といった口コミが寄せられています。
SNS連携・SEO・アクセス解析など豊富な機能を備えているため、幅広いユーザーが利用可能です。
・ジンドゥーの参考価格
無料
・ジンドゥーの参考レビュー
ノーコードで直感的な操作でホームページが簡単に作成できます。
テンプレートをベースにカスタマイズして作成できるので、デザインができなくても「ぽい」ものができます。
UIもシンプルで動作も重くなく操作できるのも良いです。
私はランディングページを作成するのに重宝しています。Google Search Console、Analyticsとの連携ができるのも便利です。
ジンドゥーへのレビュー「ノーコードで簡単にホームページができる」より
サポート体制が手厚いホームページ作成ツール
おりこうブログ
株式会社ディーエスブランドが展開するおりこうブログは、手厚いサポート体制が特徴です。FAXやメールを使用した文章での問い合わせはもちろん、電話で専門のスタッフに直接問い合わせできます。
実際におりこうブログを利用しているユーザーからは、「担当者の方が、いつも丁寧なサポートをしてくれるおかげで、ホームページからのお問い合わせやご入会といった成果につながっている」「分からない操作方法があれば、カスタマーセンターが丁寧にメールで操作方法を送信してくれる」といった口コミが多数寄せられています。
2006年のリリース以来18,000社以上で利用されており、「ITreview Grid Award 2022 Winter」のホームページ作成部門でお客様満足度No.1を獲得している製品であるため、初心者でも安心して導入できるでしょう。
・おりこうブログの参考価格
お問い合わせ
・おりこうブログの参考レビュー
主に求人を掲載する用途で使用していますが、過去に構築したホームページと比べて、「(デザイン的な意味で)見やすくなった」「求人の検索がしやくすくなった」というお声をいただきました。
おりこうブログへのレビュー「直感的に操作できる★」より
また、操作手順も少なくて済むので、時間の短縮にもつながっています。
機能が充実したホームページ作成ツール
DG1
株式会社ディージーワンが運営するDG1は、機能が充実したホームページ制作ツールです。Eコマース、マーケティング、Webサイト構築、オンライン予約、モバイルアプリといった機能を備えているため、後から機能を追加する必要がない点が特徴です。
ホームページの作成だけでなく、ネットショップを運営したい方にもおすすめの製品です。
・DG1の参考価格
T1:27,000 円 / 月
・DG1の参考レビュー
ホームページ制作に踏み出した時、WEB制作会社に依頼しようという案も出たのですが、制作費用が想定していたよりも高いことが分かりました。ですが、DG1は毎月の維持費が3万円程と比較的安価なため、コスト面で非常に助かっています。
DG1へのレビュー「初めてでもECサイトを作ることが出来ました!」
また、ホームページ作成後も不明点等をスタッフさんに相談でき、対応方法など丁寧に教えてくださる点もありがたいです。
ホームページ作成ツールは無料・有料を使い分けよう
ホームページ作成ツールは、コンテンツの更新を自社で行うことを目的としたものが多いため、無料お試し期間だったり、ミニマムプランを無料で提供しているツールも数多くあります。どのツールを選定するのもじっくりと使用感を試したうえで本導入をすると失敗の少ない選択ができるでしょう。また、中には無料プランの場合はサイトのPVに対して上限を設けているものがあります。自社のサービスの規模に合わせて活用しないと、ユーザーにとって不便となる可能性もあるので十分注意してください。
複数のホームページ制作ツールを比較してみよう
ホームページ制作ツールは多くの製品がリリースされているため、導入前に複数の製品を比較するのがおすすめです。ITreviewのサイトを使用すれば、簡単に複数の製品を比較できます。自社の状況を考えたうえでしっかりと検討をして、最適の製品を選んでください。
投稿 無料で使えるツールも紹介!ホームページ作成ツール7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ダイレクトメールの効果測定に使える!トラッキングツールの機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>メールの開封やリンクのクリック、添付データのダウンロードといった細かい顧客の動きを「見える化」できるため、メールマーケティングを効率化してくれます。この記事では、メールトラッキングの特徴や主な機能をご紹介します。
メールトラッキングツールとは
メールトラッキングツールとは、メールを追跡(トラッキング)して顧客の動きをデータとして蓄積できるツールのことです。
配信したメールに対して、ユーザーが実施した次のアクションを通知してくれる便利なツールであり、近年ではマーケティングツールとして多くの企業が導入しています。
収集できるユーザー行動の例
- メール開封・既読のタイミング
- メール内URLのクリック
- 添付ファイルのダウンロード
顧客が取ったアクションは、専用の分析ツールに数値が蓄積されていき、顧客情報と紐づけたり、アクション状況の分析からユーザーニーズやメール配信のタイミングを検討したりできます。また、次のような基本機能が備わっており、メールトラッキングツールを利用する企業に大きな利益をもたらしてくれます。
代表的な機能
- 顧客情報管理
- アクション状況の通知・分析
- メールマーケティングのスケジュール調整
- バラバラに利用していたメールプラットフォームの統合
メールマーケティングに特化した便利なツールであることから、メール営業やメルマガ配信を実施する企業におすすめです。
機能1:メール追跡により顧客のアクションを分析
メールトラッキングツールを利用することで、メール営業やメルマガ配信を受け取った顧客の動きを「見える化」できます。このツールでは、顧客のメールに対するアクションを細かく分析でき、分析した情報から次の項目を営業戦略に組み込めます。
メールを開封
メールタイトルの良し悪しを分析できる。また、メールを受信したユーザーの中でもインプレッションにつながる顧客候補を割り出せる。
URLのタップ・クリック
ユーザーへの訴求に対応したURL配置ができているか確認できる。また複数のURLからどのURLに興味が集まるのかを分析できる。
添付ファイルダウンロード
データダウンロードは興味のあるユーザーのみのアクションであるため、サービスに興味を持っているユーザーを分析できる。
従来のメールマーケティングでは、顧客が受け取ったメールをどう扱っているのか見えません。そのため、上記のようなアクション分析が行えず、手探りで顧客候補を見つけていくしかなかったのです。
これに対して、メールトラッキングツールを活用すれば、リアルタイムでユーザーの行動を分析できます。メールマーケティングの効率化を図れることから、使い方次第で少ない手間で売上アップが期待できます。
機能2:メールプラットフォームの統合管理
メールマーケティング用にGmailやyahooメールといった別々のメールプラットフォームを利用している会社も多いでしょう。また、専用の分析ツールを複数利用している会社も多いはずです。しかし、複数のメールプラットフォームを個別管理するのは手間であり、プラットフォームごとに顧客情報の管理が必要です。
そんな2度手間、3度手間が発生する方法に対し、メールトラッキングツールは1つのメーラーを利用しつつ分析まで実施できます。つまり、複数のメールプラットフォームのメール文や顧客情報をすべてメールトラッキングツールで管理・配信できるのです。管理の手間が減るだけでなく、従来の環境を崩すことなく利用できるので、導入ハードルが低いというのも魅力的なポイントです。
機能3:見込み客への計画的なメールスケジューリング
メールトラッキングツールを活用することによって、配信したユーザーのアクションをデータや数値として確認できます。その中には、ユーザーが「メールを開いた時間」について分析する項目があり、どの時間帯にメールが開かれやすいのかを分析できます。これにより、メール配信が効果的な時間帯を探り、メールトラッキングツールのスケジューリング機能で、毎日同じ時間にメールを自動配信できます。
時間帯を考えず、手あたり次第にメール配信を行っていないでしょうか。しかし、メールを送付しても開封されないのであれば顧客獲得につながりません。メールトラッキングツールを活用すれば、企業が提供しているサービスに興味を持つ人たちがメールを見てくれる時間帯を簡単に把握できます。
つまり今後ベストなタイミングでメール配信が行えるようになるのです。顧客から集めたデータをもとに効率的な営業戦略を立てていけば、今後の売り上げにつなげていくことができるしょう。
メールトラッキングを活用してビジネスを加速させよう
メールトラッキングツールは、メールを確認したユーザーのアクションを細かく分析できるなど、企業のメールマーケティングを効率化できるのが魅力です。分析した情報を活用して顧客ニーズに合ったメールマーケティングを実施すれば、高品質なメール配信ができるほか、売上アップにもつながるでしょう。
投稿 ダイレクトメールの効果測定に使える!トラッキングツールの機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ホームページ作成ツールは使える?非エンジニアなら覚えておきたいメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>いまや多くの企業で利用されているホームページ作成ツールですが、様々なツールがあってどのようなメリットがあるのか分からない方もいるでしょう。そこで本記事では、ホームページ作成ツールのメリットを詳細に解説します。
ホームページ作成ツールとは
プログラミングやデザインの専門知識がない方でも、ホームページを簡単に作成できるツールです。フォントサイズの調節や装飾、画像や動画の配置、レイアウトの調節といったことがプログラミング不要で操作できます。
ホームページ作成ツールには、無料ツールと有料ツールの2種類があります。やはり無料ツールでは使用できる機能は少ないものの、コストを抑えたい方にはおすすめです。一方、有料ツールでは、様々な機能が使えるため、よりデザイン性が高かったり、特殊な機能を持たせたホームページを作成したい方におすすめです。
ホームページ作成ツールを導入するメリット5つ
エンジニアでなくとサイトを作成できるホームページ作成ツールを利用するメリットを紹介します。
メリット1:プログラミングやデザインの専門知識を必要としない
冒頭でも解説した通り、自分でホームページを1から作成する場合、HTMLやCSSといった言語を使用し、自らコーディングしていく必要があります。すでにプログラミングに知見がある方であればよいですが、全くの初心者の場合、プログラミングの習得までに時間がかかる、ホームページの完成までにはさらに時間を要するといったデメリットがあります。
ホームページ作成ツールは、コーディングの知識が必要なく、制作から公開までにかかる期間も短いといったメリットがあります。
メリット2:初期費用・月額利用料が安い
ホームページを作成するスキルを持ち合わせていない方が、ホームページを作成する方法の1つには、制作会社にホームページの作成を依頼するといったやり方があります。社員の時間を割かずにクオリティの高いホームページを制作できるといったメリットがある反面、費用が高いといったデメリットがあります。
ホームページ作成ツールでは、自由度は多少落ちるもののコストを抑えることが可能です。また、WordPressのように初期費用、月額利用料が無料のツールもあるため、幅広い方が利用できます。
メリット3:プラグイン機能が優れている
プラグイン機能とは、WordPressなどのCMSに機能を追加し、使いやすくすることです。「差し込む」「つなぐ」などの意味を持つ英語の「plug in」から名前がきており、日本語では「拡張機能」と呼ばれることもあります。プラグイン機能を使用することで、プログラミングをせずとも簡単に便利機能が使えるようになります。
プラグイン機能は非常に充実しており、世界最大のCMSシェアを誇るWordPressでは、約6万もの無料のプラグインが準備されています。以下にWordPressのプラグインの一例を記載します。
例1.XML Sitemaps
XMLサイトマップを自動で作成してくれるプラグイン機能です。これは、Webサイトの情報(更新日時、更新頻度)などを検索エンジンに知らせるために記載したファイルです。XMLサイトマップを上手く活用すれば、SEOの向上につながります。
例2.Contact Form7
WordPress上で、お問い合わせフォームを簡単に作成できるプラグイン機能です。無料のプラグインでありながら、FQAが準備されていたり、公式サポートフォーラムで質問できたりとサポート体制が整っているのが特徴です。
例3.BackWPup
WordPressのデータのバックアップをしてくれるプラグイン機能です。バックアップだけでなく、データベースの最適化や検証、修復なども行えます。
メリット4:スピーディーにホームページ制作・運営が可能
自分でコードを書く、もしくは制作会社に依頼する方法でホームページを制作する場合、制作を開始してから運用するまでに数か月ほどの時間がかかります。しかし、ホームページ制作ツールを使用すれば、ホームページの制作と運営をよりスピーディーに開始できます。すぐにでもホームページ制作し、公開したいという方はホームページ制作ツールを使用しましょう。
メリット5:サポート体制の手厚さ
有料のホームページ作成ツールは、サポート体制が手厚いのが特徴です。メールやチャットなど文章でのお問い合わせ以外に、電話で直接サポートを受けられるツールもあります。そのため、初心者の方でも安心してホームページ制作に取り組めます。
導入を検討するなら製品を比較しよう
ホームページ制作ツールを使用することで、誰でも簡単にホームページを作成できます。しかし、様々な製品があり、自社に適した製品を選ばないと思い描いたホームページが制作できないといった結果に終わることもあります。そのため、ホームページ制作ツールのメリットが理解できた方は、複数の製品を比較しましょう。
投稿 ホームページ作成ツールは使える?非エンジニアなら覚えておきたいメリット は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 フォーム作成ツールとは?サイト運営者が覚えておきたいメリット3つ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、お問い合わせフォームの開発は、手間がかかるものだと考える人も多いでしょう。そこで今回は、フォーム作成ツールを利用すればお問い合わせフォームを簡単に作れること、加えてフォーム作成ツールを利用するメリットについて解説します。
フォーム作成ツールとは
フォーム作成ツールとは、Webサイト経由でのお問い合わせ、申し込みや資料請求、アンケートなどに利用するフォームを作成できるツールです。従来、こうしたフォームを作成するときには、自社開発するのが一般的でした。最近ではフォーム作成ツールの登場により、既存テンプレートのカスタマイズだけで自社用のお問い合わせフォームの作成が可能になりました。
直感的な操作で必要な項目を準備できるため、簡単にお問い合わせページを作れます。そんなフォーム作成ツールのメリットを紹介していきます。
メリット1:フォーム作成費用をカットできる
フォーム作成ツールは、有料ツールと無料ツールが提供されています。なかでも無料ツールを利用すれば、フォーム作成にかかる費用を大幅にカットできます。たとえば、従来のサイトページ開発では、次のポイントで費用が発生していました。
- 自社開発による人件費と制作時間のロスによる費用
- 開発を外部委託する費用
- お問い合わせページの修正作業に関する費用
このような費用発生に対し、無料ツールを導入すれば最低予算でお問い合わせページを作成できます。サイト運営を行う必要があるけれど準備に多くの費用をかけられない運用担当の悩みを解決できるだけでなく、大手企業が作るようなクオリティの高いお問い合わせフォームを作成できるため、高品質なCS対応が期待できます。有料ツールと比較し、問題ないようであれば無料ツールの導入を検討してみましょう。
メリット2:専門知識不要でフォームを作れる
フォーム作成ツールの一番の魅力は、誰でも簡単にお問い合わせフォームを準備できる点です。プログラミングの知識やデザインスキルがない運用担当でも、手早くおしゃれなデザインのお問い合わせフォームを準備できます。また、フォーム作成ツールを導入すれば、次のような機能を簡単に利用できます。
- 基本入力項目(名前・メールアドレス・質問カテゴリ等)の設定
- フォームデザインの変更
- 自動返信メールの内容作成
- データ集計
フォーム作成の基本機能のほかにも、問い合わせするユーザーに安心感を提供する自動返信メールを作成したり、データ集計によってサービスの改善に役立てられたりするなど、さまざまなメリットがあります。
とくにイベントやキャンペーンといったユーザーが疑問を持ちやすい活動を行っている企業の場合、日常的に多数のお問い合わせが届くでしょう。対応作業を大幅に削減できるため、ぜひ活用してみましょう。
メリット3:集計・管理の手間を削減できる
お問い合わせを受けた項目は、次のように情報の集計・管理を行う必要があります。
- サービスページの不明点や改善点の集計・管理
- ユーザーからのクレーム集計・管理
- スパム・迷惑メール管理
お問い合わせメールをフィルタリングせずに受け取ると、問い合わせのカテゴリが分からず管理が煩雑になります。フォーム作成ツールでは、「質問カテゴリ」といった項目を指定して入力するフォームを準備できます。カテゴリ分けをすることで、対応の優先順位を決めることができます。さらに、カテゴリごとに集計できる機能がついているものもあり、問い合わせ内容の傾向を分析することでサービスの改善に役立てられるでしょう。
サービス品質向上のため、フォーム作成ツールの導入を検討してみよう
サービス改善には、サイト運営の中でユーザーの意見を聞ける「お問い合わせページ」が欠かせません。専用ツールを利用することで、開発工数の削減と効率アップにつなげられるでしょう。まさに、運営のコストを抑えて、CS対応の体制を整えたいなら導入しておきたいツールです。ぜひ以下のボタンから、ビジネスに役立つフォーム作成ツールを探してみてください。
投稿 フォーム作成ツールとは?サイト運営者が覚えておきたいメリット3つ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 お問い合わせフォームを作るなら、押さえておきたいツール7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、押さえておきたいフォーム作成ツールを7つご紹介します。各ツールのレビューなども含めて確認し、自社に合ったフォーム作成ツールを選んでみてください。
1.チャットツールとの連携可能/formrun
formrunは無料プランも提供されているため、初めてフォーム作成を利用する方にもおすすめのツールです。住所保管機能やフリガナ自動入力など、お問い合わせフォームでユーザーストレス軽減に欠かせない機能も瞬時に実装できます。Slackなどのチャットツールとの連携も可能なので、問い合わせ対応を効率化できるのもformrunのメリットです。
・formrunの参考価格
| 初期費用 | 要問い合わせ |
| 月額費用 | フリープラン:無料ビギナープラン:3,880円スタータープラン:12,980円プロフェッショナルプラン:25,800円 |
・formrunの参考レビュー
「お客様フォームを工数かけずに作成したい、かつ低コストで抑えたい」と言う状態だったので、フォームランはうってつけでした。当社ではお問合せ、資料請求、イベントセミナー受付など全てをフォームランで管理することができています。
formrunへのレビュー「とにかくカンタン!」より
2. Kintoneユーザーにおすすめ/フォームブリッジ
フォームブリッジは、業務アプリ作成ツールのKintoneへお問い合わせデータが自動保存されていくフォーム作成ツールです。そのためKintoneで顧客管理アプリなどを構築している場合はフォームブリッジの導入がおすすめです。条件分岐が必要な複雑なフォーム作成にも対応しているため、さまざまな業務に適しています。
・フォームブリッジの参考価格
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | ライトプラン:6,600円スタンダードプラン:9,900円プレミアムプラン:15,400円プロフェッショナルプラン:26,400円 |
・フォームブリッジの参考レビュー
kintoneを利用できる環境であれば、フォームブリッジを使うことで、簡単にwebフォームを実現できます。
フォームブリッジへのレビュー「kintoneが便利になるwebフォーム拡張」より
フォームからの入力データをkintoneに溜めて、kintone上で分析等の二次加工ができるので、kintoneを業務で活用している利用者であれば重宝します。
また、webフォーム自体の機能についても、ルート分岐や期限設定、アクセス制限など、充実していると思います。
3.アクセス解析の連携まで可能/フォームメーラー
フォームメーラーはランディングページ作成などの機能も備えたフォーム作成ツールです。フォーム作成からランディングページ作成、アクセス解析との連携までこれ1つで完結します。独自ドメイン設定(オプション)により1つのランディングページとして仕上げることができるため、集客したい個人事業主にもおすすめです。
・フォームメーラーの参考価格
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | フリープラン:無料プロプラン:1,375円ビジネスプラン:6,875円 |
・フォームメーラーの参考レビュー
今までメールやFAX、申込用紙などで
イベント参加を受付していた時は、管理も大変で、いちいちエクセルのリストにまとめるのも手間がかかっていたが、今は参加希望の方へフォームのURLを送りさえすれば、イベント受付の手間も省け、また参加者一覧がリアルタイムで一目瞭然となった為、現状の把握や、管理の手間が格段に減った。
フォームメーラーへのレビュー「簡単に瞬時にフォーム作成可能」より
4.総合カスタマーサポート/Tayori
Tayoriはフォーム作成に加えてFAQ(よくある質問とその回答)作成、アンケート実施、さらにチャットにも対応しているツールです。単にお問い合わせフォームを作るのではなく、カスタマー業務全般をサポートする機能が備わっています。カスタマーサポートを充実させたいEC事業者にもおすすめです。
・Tayoriの参考価格
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | フリープラン:無料スタータープラン:3,400円プロフェッショナルプラン:7,400円 |
・Tayoriの参考レビュー
弊社は店舗運営を事業の主軸としているため、知見が全くありませんでしたが、Tayoriは初めてでも簡単にでき、文字通り「誰でもできる」ツールだと感じています。
Tayoriへのレビュー「社内各所でTayoriの導入が広がっています」より
簡単に即時登録、反映ができることも有難いですが、何より困ったときのマニュアルが非常にわかりやすくマニュアル一つで大体の疑問は解消できます。
また、アフターフォローも充実しており、お問い合わせでも対面でも使い方の質問をできる場があるのが安心して使える要素となっています。
5.本格カスタマイズ可能/Synergy! LEAD
クラウドCRMを提供するシナジーマーケティングが運営するフォーム作成ツールです。HTML/CSS/JavaScriptを使ったカスタマイズが可能なので、Webサイトのデザインに合ったお問い合わせフォームを作成・設置できます。また、Salesforceとの連携で登録されたリード情報を一元的に管理できるようになります。
・Synergy! LEAD参考価格
| 初期費用 | 無料 |
| 月額費用 | 10,000円~ |
・Synergy! LEADの参考レビュー
Salesforceを導入し案件の管理はできるようになっていたのですが
数万件保有しているリードの管理ができておらず、一度失注してしまった顧客を放置している状況でした。そのような状況の中、Synergy!LEADでまず取り組んだのは
Synergy! LEADへのレビュー「Webマーケ初心者でも使いやすいMAツール」より
「メールマーケティング」と「フォーム作成」でした。
顧客が問い合わせした内容がSynergy!LEADのフォームを経由してSalesforceに取り込まれ営業マンが対応。
そこで失注となってしまった顧客や、過去の名刺をリスト化しマーケチームがメルマガでフォロー。
問い合わせや営業タイミングだけでなく、メルマガを通して常に顧客と接点を持ち続けることで
再度、弊社サービスが必要となったタイミングで、メルマガへの返信などで顧客から新たに問い合わせをもらえるようになりました。
6.オンプレミスにも対応/WEBCAS formulator
WEBCAS formulatorはクラウドで使えるフォーム作成ツールの他に、オンプレミスでの導入にも対応しています。ユーザーから送信された個人情報を厳格に管理し、セキュリティ対策をさらに強化したいという企業にはオンプレミスがおすすめです。レスポンシブデザインに対応したテンプレートが用意されているため、素早くお問い合わせフォームを作成できます。
・WEBCAS formulatorの参考価格
| 初期費用 | ASP型:50,000円~SaaS型:500,000円~ |
| 月額費用 | ASP型:30,000円~SaaS型:100,000円~ |
・WEBCAS formulatorの参考レビュー
カタログ通りの機能であるアンケートはもちろんのこと、セミナー申し込みのように次々に日付や場所を変えながら受け付けるものも、タイマーで受付の開始・終了をすることができ、連休などにも対応しやすくなりました。
WEBCAS formulatorへのレビュー「複数の部署でも利用しやすい」より
7.Salesfoeceとシームレスに連携/formstack
formstackは自由にフォームを作成でき、Salesforsと簡単に連携できるツールです。日本語未対応なので使いにくさを感じるかもしれませんが、海外では高い評価を得ています。ユーザーは週に18時間の作業時間を短縮できるとされており、業務効率化にも貢献するツールです。
・formstackの参考価格
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | スタータープラン:150ドルチームプラン:500ドルプロプラン:2,000ドルエンタープライズプラン:要お問い合わせ |
・formstackの参考レビュー
使える機能や作れるフォームの数の制限などによりますが、月額19ドルから使えるなど、ほかのサービスと比べても比較的柔軟なプラン設定になっていると思い、良心的だと感じます。
formstackへのレビュー「使用頻度などに合わせて様々なプランを選べる」より
フォーム作成の機能も充実していて、使いやすいです。テンプレートも多いので、いろいろなフォームを作ってみたくなります。
ビジネスに欠かせないお問い合わせフォームだからこそツール活用を
ビジネスの種類に関わらず、お問い合わせフォームは必要です。また、どのようなフォームを作るかにより、ビジネスへの貢献度は大きく変わります。
元アメリカ大統領のバラク・オバマ氏が大統領選で勝利した際は、フォームのABテストを実施してよりコンバージョン率の高いデザインを採用し、6,000万ドルもの寄付金増加に貢献したそうです。このようにフォーム作成はビジネスに想像以上の価値をもたらすので、積極的に良いフォーム作成を目指しましょう。
フォームはゼロから作るよりも、または外注するよりもツールを活用する方が作業時間短縮・コスト削減になるため、この機会にフォーム作成ツールの利用をご検討ください。
投稿 お問い合わせフォームを作るなら、押さえておきたいツール7選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 CMSを選ぶポイント5つ|コストよりも大切なものとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>いまや多くの企業やプロジェクトでも使われるCMSですが、コストやサポート体制はブランドによって様々。安直にコストを優先してしまうと、導入に想定以上の時間やコストがかかったり、難易度によっては新規で担当してくれる人材を採用するなんてことも。スムーズに導入を進めるためにも、CMS選定の初期検討時に押さえておきたい5つのポイントをご紹介します。
ポイント1:自社サイトの運用課題の確認
自社サイトを運用していく上で、CMSを導入したい理由を明確にすることが大切です。CMSと一言でいっても、サイトの規模やサイトが取り扱う情報の質によってクリアできる要件が異なります。
自社でシステム担当がいて「誰でも簡単にコンテンツをサイトにアップできるようにしたい」「スマホ最適化をしたい」ということであれば「Wordpress」。システムに詳しい人材はいないが、自社のホームページをつくっておきたいなら「おりこうブログ」といった選択肢も考えられます。
また数十ページ程度の小規模サイトか、それとも数百ページにも及ぶような大規模サイトなのかによっても適したサービスが異なります。
仮に、現在のサイトから切り出して投資家向けのIRページの運用するという場合は「Share With」、BtoBマーケティングに特化したサイトづくりがしたいなら「ferret one」など、各社で施策に特化したCMSが展開されているのでチェックしてみましょう。
ポイント2:CMSの導入や運用の経験がある人材の有無
CMSの導入でまず候補にあがるのが、「Wordpress」ではないでしょうか。安価で使える上に、プラグインによる拡張性が魅力で多くの企業で採用されています。自由度の高いカスタマイズが可能ですが、基本的には自社での運用・改善が必要です。また、オープンソースがゆえにセキュリティ対策が必須です。情報漏洩のリスクを減らしたければ「Movable Type」の選択もあるでしょう。
また、既存のHTMLサイトを乗せ換えるという場合には相応のスキルが必要です。情報システム担当者が在籍していても、移行期間の見積りをしておかないと事業計画で予期してなかったリソース不足が発生する可能性があるため注意が必要です。
スキルを持った人がいない場合は構築代行サービスの利用や、導入支援サービスもパッケージに含まれている製品を検討しましょう。
ポイント3:カスタマイズの必要性
デザイン性に優れたページデザインであったり、機能を追加したいといった場合は拡張性の高いツールが候補になります。「Wordpress」はプラグインによるカスタマイズが魅力ですが、拡張機能の説明が英語の場合が多々あるので対応できる体制が必要になります。
ポイント4:有償CMSを選ぶ場合は初期コストと運用コストを把握しよう
有償CMSを導入するなら、予算をどの程度押さえられるかが課題となるでしょう。「Wordpress」と比較検討されることの多い「Movable Type」の場合は、初期費用のみで済む場合もありますが、月額払いで利用契約を更新しながらの利用がほとんどです。初期費用のほか、月額利用料金、オプション料金と加算されます。導入前の検討は入念に行いましょう。
ポイント5:サポートページの充実や窓口の有無
無料のCMSもありますが、その場合、導入や運用のサポートはほぼ無く、自社の情報システム担当者のスキル次第で構築を進めていくことになります。属人的な運用を回避するなら、有償のものが安心です。海外の製品であっても、日本のパートナー企業がサポートしてくれたり、日本語のFAQが充実していたりするものもあります。
エンジニア中心の会社で誰でもCMSの保守・メンテナンスができるといった場合や、ITリテラシーが高い企業でない限りは有償のものを選ぶほうがベターでしょう。
導入要件が定まったらCMS製品を比較してみよう
CMSは導入して終わりではなく、運用のフェーズまで見据えて選定することが大切です。コストだけに注目してCMSを選定すると、専門知識を持つ人材の確保、さらには属人的な運用までもが重なり「当初解決したかった課題が解消されなかった」なんてことになりかねません。
自社の状況に合わせて、間違いのないCMSの選択をするためにも、しっかりと比較検討をして導入する製品を決められたらいいですね。
投稿 CMSを選ぶポイント5つ|コストよりも大切なものとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ソーシャルリスニングとは?SNS運用をサポートする製品をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そんなSNSマーケティングの悩みを解決してくれるのがソーシャルリスニングです。SNS運用の導入をスムーズに進めるためにも、ソーシャルリスニングのメリットとデメリット、使いやすい3つの製品を確かめましょう。
ソーシャルリスニングとは
ソーシャルリスニングとは、SNS上で交わされるユーザーの自然な会話を収集・分析し、ビジネスプロセスに活用することです。商品を手にした顧客のリアルな声や競合他社の製品を利用した潜在顧客の声など、リアルタイムに発信される情報の獲得へつながります。ソーシャルリスニングに特化したツールでは、主に「データの収集」「収集したデータの分析」2つの機能を提供しています。
データ収集では、TwitterやFacebook、知恵袋などから指定したキーワードなどのビッグデータを収集します。データ分析では、収集したデータの口コミ件数や性別や年齢、話題性などを分析可能です。ソーシャルリスニングは、マーケティングにおける市場調査やトレンド調査、認知度調査として活用できます。
ソーシャルリスニングのメリット
メリットとしてあげられる点は、担当者ひとりでは把握しきれないビッグデータを収集して分析できる点にあります。消費者目線のマーケティングは以前から重要視されていましたが、アンケート調査やモニター調査などのごく限られた情報のみ利用され、対象となるデータの母数はあまり多くありませんでした。ソーシャルリスニングの対象は、国内のSNS利用者7,000万人以上となり、ビッグデータを活用したより確度の高い分析が期待できます。
さらに、消費者の生の声を反映するSNSでは、企業や製品に対して好感を持ったプラス要素の意見だけでなく、改善すべきマイナス要素の意見の収集にもつながり、自社の抱える課題の発見にもつながります。
ソーシャルリスニングのデメリット
一方で、ソーシャルリスニングのデメリットは、各投稿の質が見えづらくなる点です。SNSをマーケティングへ活かすには、データを収集するキーワードの選定が重要です。しかし、キーワードによっては必要なデータが集まらないこともあれば、熱烈なファンの声が大量の投稿に埋もれてしまい見落とすことも考えられます。
実際に製品を使ったわけではなく、イメージで製品について口コミするユーザーの声も、何年もその製品を利用し続けたロイヤルカスタマーの声も同列に扱ってしまうのです。情報の精査についてはソーシャルリスニングのデメリットと言えるでしょう。
ソーシャルリスニングに特化したツール5選
Twitterに特化したツールやキャンペーンの展開に強いツール、顧客満足度調査に優れたツールなどソーシャルリスニングの種類によって選べる機能は様々です。それぞれの機能を把握して自社に必要なソーシャルリスニングを把握しましょう。
ツール1:Twitterマーケティングのための『SocialDog』

SocialDogは、Twitterマーケティングに特化したソーシャルリスニングツールです。Twitterのフォロー管理、口コミツイートの自動収集など、Twitterマーケティングに必要な機能を揃えています。80万人を超える利用アカウントは、SNSツールユーザー数で国内最大規模を誇ります。
ツイートの予約投稿やアカウント分析など、Twitterを円滑に運用するために用意された豊富な機能でサポートします。Twitterマーケティングの利用には、SocialDogがオススメです。
・Social Dogの参考価格
Business:12,800円/月(無料トライアル7日間・無料で使えるLiteプランあり)
・socialdogのユーザーレビュー
ツイッターの公式アナリティクスでは過去28日間しか遡れないのですが、socialdogなら、それ以前の過去にまで遡れてチェックすることができ、フォロワー推移のチェックなど「そういえばあの時どうだったかな?」と知りたくなったときに、すぐに確認・振り返りができます。SNSのPDCAに非常に役立っております。
socialdogへのレビュー「使いやすい管理画面。フォロワー推移など過去を遡れて便利。」より
ツール2:キャンペーンの実施なら『Social Insight』

Social Insightは、複数のソーシャルメディアの情報収集に利用できるソーシャルリスニングツールです。対応しているメディアは、Twitter、Instagram、Facebook、LINE、YouTube、Pinterest、ブログ、TikTokなど、日本最大級のアカウトデータを蓄積しています。
Social Insightの特徴は、フォローやリツイートなどを条件に抽選してユーザーにプレゼントを贈るキャンペーンを実施できる点です。他にも、アカウント管理や競合アカウントの分析などさまざまな機能を提供しています。プレゼント企画をスムーズに進めるには、Social Insightがオススメです。
・Social Insightの参考価格
お問い合わせ
・Social Insightのユーザーレビュー
Twitterはもちろん、facebook、LINE、Yutube、Instagramのインサイト(アナリティクス)分析。
上記+TikTokやnoteなどのアカウント分析を行えるため、自社で運用するSNSはもちろん競合他社の分析結果も一覧で見ることができるので他社の運用方法を丸裸にできる。また、各SNSへの投稿の管理もこちらでできるので運用側としては各SNSの投稿画面を開く必要がなくなり、かなり運用しやすくなった。
Social Insightへのレビュー「SNSの分析に役立つ」とは
ツール3:顧客満足度調査なら『見える化エンジン』

見える化エンジンは、顧客の感情分析に特化したソーシャルリスニングツールです。Twitter、Instagram、Blogの情報収集に利用できます。
見える化エンジンの特徴は、感情マップによりユーザーのリアルな声を可視化できる点です。心理学に基づいたマップでは、期待や驚き、怒りなど、ユーザーの感情に基づいたキーワードを図式化してひと目で把握できます。
製品やサービスを利用したユーザーの満足度を図るには、見える化エンジンが適しているでしょう。
・見える化エンジンの参考価格
お問い合わせ
・見える化エンジンのレビュー
業務活用でよかったポイントは下記になります。
見える化エンジンへのレビュー「潜在顧客ニーズの仮設検証に役立つツール」より
・消費者の潜在ニーズを簡単に調査・確認でき、資料化が容易であること。
・テキストをデータ化し、自社で運用している他ツールと連携ができていること。
・共起語や関連ワードを把握し、マーケティング戦略の立案の説得力に厚みがもてた
ツール4:ビッグデータを活かしたTwitterの感情分析『Keywordmap for SNS』
Keywordmap for SNSは、日本語によるSEOキーワードを分析し、ビッグデータとして活用するサービスを手掛けるCINC社が展開するサービスです。Twitter運用におけるサポートに特化しており、キーワードやハッシュタグなどからツイートを一括抽出し、感情分析を行うことができます。従来の投稿数によるトレンド理解ではなく『興味関心数』による本質的なソーシャルリスニングを実現し、消費者の本音を知るために役立ってくれるでしょう。
・Keywordmap for SNSの参考価格
お問い合わせ(1週間無料トライアルあり)
・Keywordmap for SNSのユーザーレビュー
特定のアカウントを分析するにあたり、データが定量的に見れるので非常に使いやすく感じています。
Keywordmap for SNSへのレビュー「使いやすさと高精度分析」より
例えば、投稿に関する曜日や時間帯による反応が定量的に分かる機能があります。最小限の工数で最大限の効果を、適切なターゲットに対して生み出す事が理想的ですが、このKeywordmap for SNSがあれば具体的な数値を見ながら投稿に活用できる為、非常に役に立っています。
また、ビッグデータを扱う企業としての強みや精度の高い日本語分析機能によって、取得したいデータを確実に、また、文字では区別の難しい日本語特有の区切りも綺麗にデータとして拾い上げる事ができる為、ストレスなく、最短でデータの活用ができる為、重宝しています。
ツール5:インスタに特化した機能を持つ『Reposta』
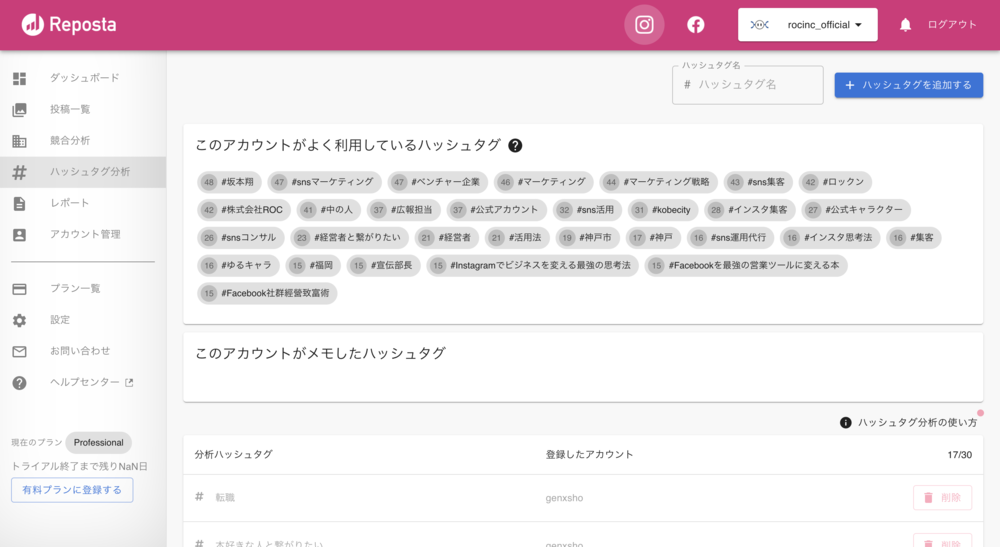
Repostaは、instagramやFacebookの運用に役立つツールです。アカウント運用におけるダッシュボードはもちろん、競合アカウントとの比較やハッシュタグ分析(instagramのみ)といった機能を展開しています。毎日の運用成果を毎日メールでレポート送信してくれるため、担当者のKPIに対するコミットメントを強化してくれるでしょう。
・Repostaの参考価格
Basic:11,000円/月(お試しフリープランあり)
・Repostaのユーザーレビュー
インスタグラムに対する知見がなくとも、ロジカルな投稿解析を通じて改善を試みることができました。我々のような小規模で大きな予算をさけない会社にとってこの点は魅力的です。
Repostaへのレビュー「ロジカルな分析機能と明快なレポート」より
ソーシャルリスニングでSNS運用の品質をアップしよう
ソーシャルリスニングを利用することで、マーケティングにSNSを活用できるようになります。SNSの情報の収集、プレゼントキャンペーンの効率化、収集したデータの分析など、さまざまな機能が提供されています。
ソーシャルリスニングを活用すれば、担当者ひとりでは把握しきれないビッグデータをスマートに把握できるでしょう。SNSの膨大なデータを分析して、マーケティングやブランディングに活かしましょう。
投稿 ソーシャルリスニングとは?SNS運用をサポートする製品をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 炎上リスクを早期発見!SNS担当者をサポートするソーシャルリスニングとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで利用したいのが、ソーシャルリスニングです。ソーシャルリスニングには、クロスチャネルモニタリングやソーシャルメディアレポートなど、SNS運用を円滑にする機能が備わっています。SNS運用における課題点とソーシャルリスニングの機能について知ることでスムーズなSNS運用を実現しましょう。
SNS運用における課題点
マーケティング施策にSNSを利用する企業も増えていますが、炎上案件やリサーチ能力の不足といった課題を抱えている企業も多くあります。SNS運用を始めたもののデータの収集が追いつかなければ、インフルエンサーの発信した情報を見落としてトレンドに遅れたり、炎上案件に気づかないまま初期鎮火が遅れたりすることもありえます。
SNS運用に必要なのは、発信スキルだけでなく、情報を集め、解析し、正しく活用するシステムです。ソーシャルリスニングは、これらの課題を解決するためのさまざまな機能を提供します。
ソーシャルリスニングを利用すると、好意を持ったユーザーの声を拾い集めるだけでなく、嫌悪感を持ったユーザーのマイナスな声まで集めることができます。実際に、ソーシャルリスニングでどのような機能を利用できるのか確認しましょう。
ソーシャルリスニングの機能1:SNSを一括管理できるクロスチャネルモニタリング
クロスチャネルとは、ひとつのSNSで顧客とつながるシングルチャネルや複数のSNSで顧客とつながるマルチチャネルから進化した、複数のSNSのチャネルを一元管理する機能です。複数のSNSアカウントの一括管理やさまざまなSNSの口コミを一括収集できるようになります。
ひとつのプラットフォームで機能を提供するので、ユーザーにプレゼントを贈るキャンペーン企画の抽選や効果測定なども一括して行えます。複数のSNSをひとつのプラットフォームで管理できるのがクロスチャネルモニタリングです。
ソーシャルリスニングの機能2:数値で可視化できるSNS運用分析
SNS運用分析とは、SNSのフォロワー数の増減やコンバージョン率などを分析する機能です。例えば、フォロワー数が1年前からどれだけ増えたか、ツイートのインプレッション数、プロフィールへのアクセス数などを可視化できます。
ユーザーの反応を数値として集め、SNS投稿の反応率や効果の検証などの分析に使えます。ユーザーのリアルな反応を数値として可視化できるのが、SNS運用分析機能です。
ソーシャルリスニングの機能3:文章としてまとめるソーシャルメディアレポート
ソーシャルメディアレポートとは、TwitterやYouTubeなどの情報を収集して、レポートとしてデータやグラフをエクスポートする機能です。利用者の性別や年齢、地域などペルソナに合わせて個別のデータを把握することもできます。
ネガティブなキーワードを登録しておくことで、炎上モニタリングや風評被害の対策にも使えます。火種が小さいうちに消化活動に努めることで、早期沈静化にもつながるでしょう。文書としてまとめることで情報を把握しやすくなるのが、ソーシャルメディアレポートです。
ソーシャルリスニングの機能4:顧客心理を分析できるセンチメントスコアリング
センチメントスコアリングとは、顧客がSNSに書き込んでいる商品や会社に対しての投稿を分析してスコアリングする機能です。好き、嫌い、楽しい、すごいなどの顧客の感情をSNSから読み取り、投稿数に比例して声の大小を図式で表します。
顧客の声を可視化することによって、自社の製品やブランドイメージをひと目で把握できるようになります。
ソーシャルリスニングの機能5:反応率を高めるインフルエンサーの識別
インフルエンサーの識別とは、SNSで自社の製品やブランドについて投稿、発信している人物を特定する機能です。例えば、チャンネル登録者数100万人のYouTuberに製品を紹介されたり、フォロワー10万人のインフルエンサーに自社のイメージを損ねる書き込みされたりすると、その投稿元を即座に把握することができます。
関連性の高いインフルエンサーを把握することは、コンバージョンの高い宣伝にもつなげられ、無駄なく広告費を捻出することが可能です。ビジネスチャンスや炎上案件に迅速な初期対応をすることにもつながります。
炎上のリスク分析をしてSNS運用のサポート
正しくSNS運用するには、情報の収集と分析は欠かせません。ソーシャルリスニングの導入によって、炎上のリスクやビジネスチャンスを逃さずスピード感を持った対応ができるでしょう。
SNS運用を利用していなくても、顧客のリアルな声を集められる機能の利用は、消費者心理を反映したマーケティングにもつながります。ソーシャルリスニングの導入によりスピード感のある経営につながるでしょう。
投稿 炎上リスクを早期発見!SNS担当者をサポートするソーシャルリスニングとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 アプリのプッシュ通知を許諾している人は8割?効果的な使い方とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>出典:アプリユーザーをアクティブにする!専門家が教える「プッシュ通知」5つの真実と間違い。D2CRアプリセミナー|AppMarketingLabo.
さらに、NTTコムオンラインが行ったアンケート調査では、アプリのプッシュ通知を「全てON」にしている人と「アプリによって使い分けている」人は、全体の77%に達していることがわかっています。
出典:プッシュ通知の許諾率とその理由とは|NTTコムオンライン
調査データからもわかる通り、今やユーザーに直接コンタクトのとれるプッシュ通知は非常に有効なマーケティング手法です。
プッシュ通知の有効的な使い方4つ
これから自社のアプリにプッシュ通知を導入したい方、もしくは導入済みだが反応率が思うように上がらない方は、ぜひ参考にしてみてください。
使い方1. 反応率の高い時間帯に配信する
まず初めに、「ターゲットの反応率が高い時間帯を知ること」が大切です。株式会社日本マーケティングリサーチ機構が行った調査によると、「スマホを見るのはどの時間帯が一番多いですか。」という質問に対する回答は、次のような割合になりました。
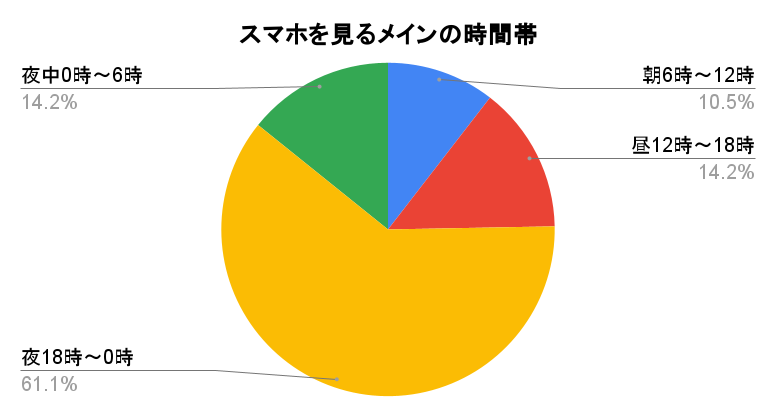
このように、18:00〜0:00にスマホをチェックする人が圧倒的に多くなっています。ただし、あまり遅くにプッシュ通知を配信すると反応率は高くともユーザーに嫌がられる可能性があります。遅くとも21:00までにはプッシュ通知を配信し、一般的な生活リズムに配慮することが大切です。例えば社会人をターゲットにしたサービスであれば、朝の通勤時間やランチタイムに送付するのも一手でしょう。
また、キプロス共和国のゲーム会社であるNekki社が行った調査によれば、プッシュ通知の開封率が最も高かった曜日は「月曜日」であり、週末にかけて開封率は徐々に低下し、日曜日には最低を記録しています。
出典:7 Surprising Facts About The Open Rates Of Push Notifications|Tapjoy
プッシュ通知の開封率が高い時間帯はジャンルによっても若干異なるため、こうしたデータを参考にしながら、自社ビジネスにとって最適な配信時間帯を模索しましょう。
使い方2. 適切な回数で配信する
ターゲットの反応率が最も高まる時間帯を把握したとして、次に大切なのが「適切な回数で配信すること」です。プッシュ通知はメルマガとは異なり、お得情報やイベント情報の発信、クーポン配布などに利用されています。
つまり、ビジネスに直接つながるような内容が多いのです。そうした中で毎日のようにプッシュ通知が届くと、ユーザーはアプリやサービスに対して「うっとうしい」と感じるようになります。情報化社会と呼ばれ、いたるところで広告や営業に触れる時代だからこそ、プッシュ通知を適切な回数で配信し、「セールス感、押し売り感を感じさせないプッシュ通知」を心がけましょう。
使い方3. ユーザーにメリットのある内容を発信する
お得情報やクーポン配布は、基本的にユーザーにとってメリットのある内容です。しかし、「どのユーザーに配信するか?」によっても変わります。
例えば商品Aに対するニーズを抱えているユーザーに対して、商品Bのお得情報の発信やクーポン配布を行っても、反応率が上がることはありません。適切なターゲットやセグメントの設定が行えていないため、そのユーザーにとってはメリットのある内容になっていないのです。
反応率を上げたいなら、ターゲット設定を普遍的に行うのではなく、細かなターゲット・セグメント設定を行った上で、ターゲット・セグメントごとにパーソナライズされたプッシュ通知を送信していきましょう。
使い方4. PDCAサイクルを繰り返す
最後に大切なことは、「ひたすらPDCAサイクルを繰り返す」ことです。PDCAサイクルの繰り返しに終わりはありません。常に改善し続けることで、プッシュ通知の反応率を上昇できます。
とはいえ、数ヶ月や1年もPDCAサイクルを繰り返さなければ成果が上がらないわけではありません。企業によっては1ヶ月、あるいはもっと短期間でプッシュ通知の反応率が上がることは珍しくないのです。
ポイントは「細かいサイクルをつくること」です。大掛かりなPDCAサイクルでは結果が出るまでに時間がかかります。改善→実行→検証→改善のサイクルが大きくなってしまうと、その分成果が上がるまで時間がかかってしまうのです。
可能なら、アプリの開発・運用・マーケティングチームが一丸となって細かいPDCAサイクルを回せるような環境を整えましょう。そうすれば、「プッシュ通知の反応率が日ごとに上がる」状況は夢ではありません。
正しい使い方でプッシュ通知の効果を高めましょう
スマートフォンの普及率が80%を超えている現代において、プッシュ通知は当たり前に活用されているマーケティングツールです。企業と顧客の距離が近くなった分、しっかりと顧客視点に立ち、顧客と良好な関係を築けるようなマーケティングが重視されるようになりました。
アプリのプッシュ通知をこれから利用する、あるいは反応率をアップさせるための施策を実施する際は、この記事でご紹介した使い方をぜひ実践してみてください。
投稿 アプリのプッシュ通知を許諾している人は8割?効果的な使い方とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 プッシュ通知をどう活かす?代表的な機能や効果を高める方法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>この記事では、プッシュ通知の代表的な機能について紹介します。マーケティングツール選びに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
プッシュ通知で行うABテストとは?
ABテストとは、2つの異なるコンテンツを同時に配信し、どちらが高い反応率を示すかを確かめるための分析手法です。
Webサイト媒体などでは「ボタンのテキストを少し変えただけで反応率がアップした」という事例がよくあります。プッシュ通知においても同様であり、タイトルやメッセージ内容を少し変更するだけで反応率が上がったり下がったりすることは、よくあるのです。
できる限り反応率の高いプッシュ通知を配信するほうがビジネスへの貢献度は高いため、ABテストを繰り返してより反応率の高いコンテンツを見極めていくのです。
例えば、「リプロはツールにプロがつく」で知られるReproを導入した事例では、プッシュ通知のABテストを繰り返すことによって1ヶ月で顧客維持率を10%改善することに成功しています。
出典:徹底的にA/Bテストで検証!プッシュ通知により継続率が10%改善|Repro
プッシュ通知に備わっている機能
一口にプッシュ通知といっても、ツールによってさまざまな機能が整っています。ここでは一般的な機能についてご紹介するので、プッシュ通知導入を検討する際の参考にしてみてください。
パーソナライズ通知
顧客1人ひとりに応じたプッシュ通知を配信する機能です。数千・数万単位の顧客に対しては、事前に定義したセグメント(集団)に応じて作成したプッシュ通知を配信することもできます。
予約配信通知
予約した日時にプッシュ通知を配信できる機能です。サービスやLINEなどに登録してくれた顧客に対し、段階的にプッシュ通知を配信して「シナリオメール」のようなマーケティングを実施することもできます。
ABテスト
ABテストを実施できる機能です。実施したABテストはデータが自動的に集計され、どちらのコンテンツが優れているかを瞬時に判断できます。
レコメンド
商品購入やサービス利用を悩んでいるユーザーに対して、レコメンド(おすすめ)のプッシュ通知を配信できる機能です。購買意欲を高める効果があり、既存顧客を維持する効果も期待できます。
パフォーマンス分析
プッシュ通知がどれくらい開封されたか、メッセージ内のリンクがどれくらいタップされたかなどを計測できる機能です。さまざまなデータが収集され、自動的にレポートとして出力されるためマーケティングの分析と改善に集中できます。
プッシュ通知の導入効果を高める方法
プッシュ通知は、導入するだけでマーケティング効果が高まるものではありません。大切なのはプッシュ通知の効果を高める方法を知り、正しく運用することです。
まず大切なポイントは、「適切な時間に配信する」ことです。開封率の高いプッシュ通知といえども、時間帯によって開封率は増減します。より多くのユーザーにメッセージを届けるには、開封率の高い時間帯を知らなければいけません。
次に、「有益な情報を配信する」ことが大切です。プッシュ通知に限らずどの媒体でも同じことが言えますが、ユーザーは「自分にとって有益な情報」でなければ反応しません。プッシュ通知を配信しても反応率が悪い場合、その情報はターゲットにとって有益でない可能性が高いでしょう。あるいは、ターゲット設定がそもそも間違っているケースもあります。
このように、プッシュ通知の導入効果を高めるにはいくつかのポイントを押さえなければいけません。詳しいポイントについては『アプリのプッシュ通知を許諾している人は8割?効果的な使い方とは』で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
プッシュ通知導入時の注意点
プッシュ通知の導入により顧客と直接的なコミュニケーションを取る基盤を整えられますが、1つ注意点があります。それは、「セールス感を出しすぎないこと」です。
情報化社会と呼ばれ始めて久しい昨今、顧客は常にさまざまな広告・営業に触れながら生きています。日常的に触れる広告・営業だけで十分と感じているなかで、セールス感満載のプッシュ通知が届いても決して良い反応は示しません。
では、セールス感を出さないために何が必要かというと、前述のように「有益な情報を発信する」に徹することです。常にユーザーの目線に立って、どのような情報を欲しているのかを考えてテキストを考えましょう。
プッシュ通知で効果測定を繰り返しましょう
プッシュ通知のABテストとは、1日にして成るものではありません。何度もABテストを繰り返すことで、顧客の反応率を高められます。
PDCAサイクルをしっかりと回しながらABテストを実施すれば、Reproの事例のように1ヶ月で高い成果を上げることも可能です。まずは、プッシュ通知のABテストを実施することで自社が得られるメリットについて考えてみましょう。
投稿 プッシュ通知をどう活かす?代表的な機能や効果を高める方法を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 プッシュ通知の重要性とは?おすすめツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>この記事では、プッシュ通知の概要とおすすめのツールを5つご紹介します。企業と顧客の直接的な関わりが重視されている時代です。ぜひ、今後のマーケティングに取り入れてみてください。
「プッシュ通知」とは?
プッシュ通知とは、スマートフォン上に表示される通知のことであり、主にアプリやSMS(ショートメッセージサービス)を経由して配信されるお知らせのことです。
ユーザーがアプリを起動していなくても通知が届くため、アクティブ率を高めることができます。仮にロック画面していても通知されるため「この情報を確実に届けたい」という際に最適な通知手段です。
ダイレクトマーケティングにおけるプッシュ通知の重要性
スマートフォンの所有率は80%を超える一方で、パソコンの所有率は減り続けています。「マーケティングにおいてどちらの端末が重要か?」と考えたとき、スマートフォンだと考えてよいでしょう。
また、SNSが普及したことで「企業と顧客の距離」は以前にも増して近くなり、顧客と対話しながら購買意欲を高めるダイレクトマーケティングが重視されるようになりました。プッシュ通知を活用すると、ターゲットユーザーにメッセージを確実に届けられるため、顧客とより多くの接点を持てるようになるのです。
利点だらけに見えますが、ユーザー離れの要因になることも忘れてはいけません。やりがちなのが、送付時間や送付内容のミスマッチです。ユーザーにストレスを与えてしまい、自社アプリからの「通知しない」設定をオンにされてしまっては挽回するのは難しくなります。
ダイレクトマーケティングに欠かせないプッシュ通知5選
次に、プッシュ通知機能を搭載したツールを5つご紹介します。
1.Flipdesk
Flipdeskは導入社数1,000社以上、導入サイト1,300以上を誇るツールです。Webサイト上で実店舗のような顧客体験を提供しながら、プッシュ通知機能※を使ってメッセージの開封率を高めることができます。プランに応じた明瞭会計なので、予算を組みやすいのもポイントです。
・Flipdeskの参考価格
| 初期費用 | ライトプラン0円スタンダードプラン50,000円 |
| 月額費用 | ライトプラン8,000円スタンスタンダードプラン50,000円 |
・Flipdeskの参考レビュー
・導入しやすい費用感
→同機能の他社ツールと比較しても安い。
・細かな分析指標がある
・ポップアップのみならず、様々なアウトプット機能がある
→プッシュ通知(有料だが安い)、サイトの置き換えなど
・カスタムデータ連携も可能あと、個人的に良いと思うのは、
Flipdeskへのレビュー「費用対効果が高い」より
サポートの方のリアクションが早く、かず改善要望に対しての動きも早いのが素晴らしいと思います。
2.KARATE
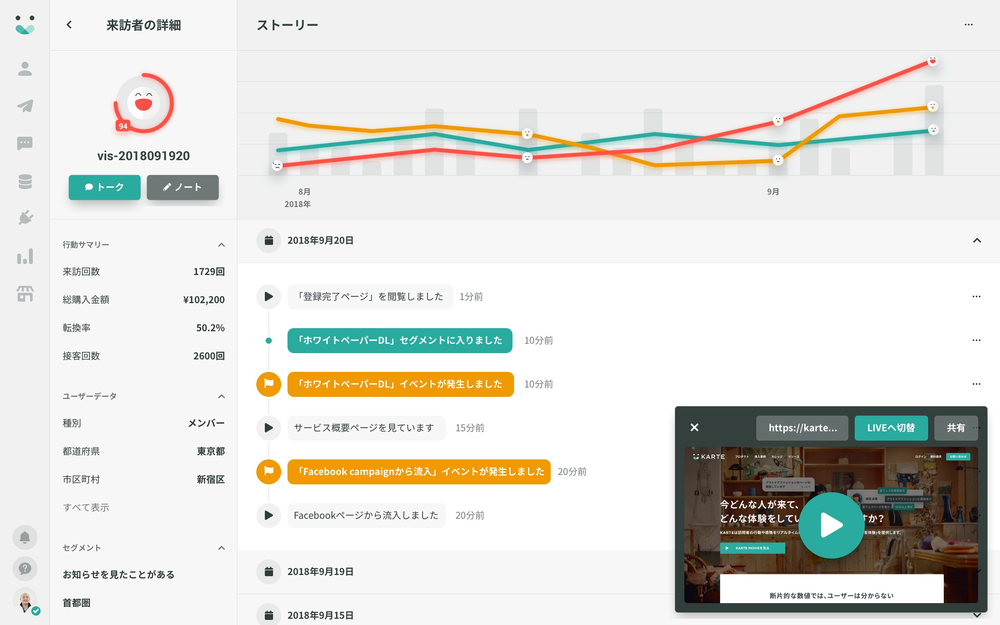
KARTEはWebサイトやアプリの訪問者の行動・感情をリアルタイムに解析できる、CX(顧客体験)ツールです。Webサイト訪問者にはSMSで、アプリユーザーにはアプリ経由でプッシュ通知を配信できるため、メッセージ開封率の更なるアップが期待できます。メールを開封しなかった人だけにSMSを配信するなど、細かい設計ができるのも魅力です。
・KARATEへの参考価格
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | 要お問い合わせ |
・KARATEへの参考レビュー
Datahubに連携した属性情報・課金情報をもとに、プッシュ通知やバナー表示をセグメントごとに出し分けることができ、ユーザーごとに適切なコミュニケーションが行えるようになりました。
KARATEへのレビュー「データドリブンな接客ツール」より
結果的に、チャーンレートの改善に成功しました。
3.カスタマーリングス
カスタマーリングスは、顧客1人ひとりの情報を深掘りして分析できるCXツールです。分析情報はさまざまな切り口で出力され、顧客の行動だけでなく感情の変化まで把握できます。メールやLINEに加えてSMSのプッシュ通知によって横断的なマーケティングが可能になり、顧客満足度向上にも貢献します。
・カスタマーリングスの参考価格
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | 98,000円~ |
・カスタマーリングスの参考レビュー
ステップメール配信やプッシュ通知などのオンライン施策は当然ですが、きめ細かくで行うことが難しいオフライン施策も、リストの自動抽出とメール配信機能を使うことで、デイリーで顧客の最適なタイミングにDMなど郵送物を発送することができるようになったため、CRMの精度が大きく向上しました。
カスタマーリングスへのレビュー「充実の機能と手厚いサポート体制」より
4.Rtoaster
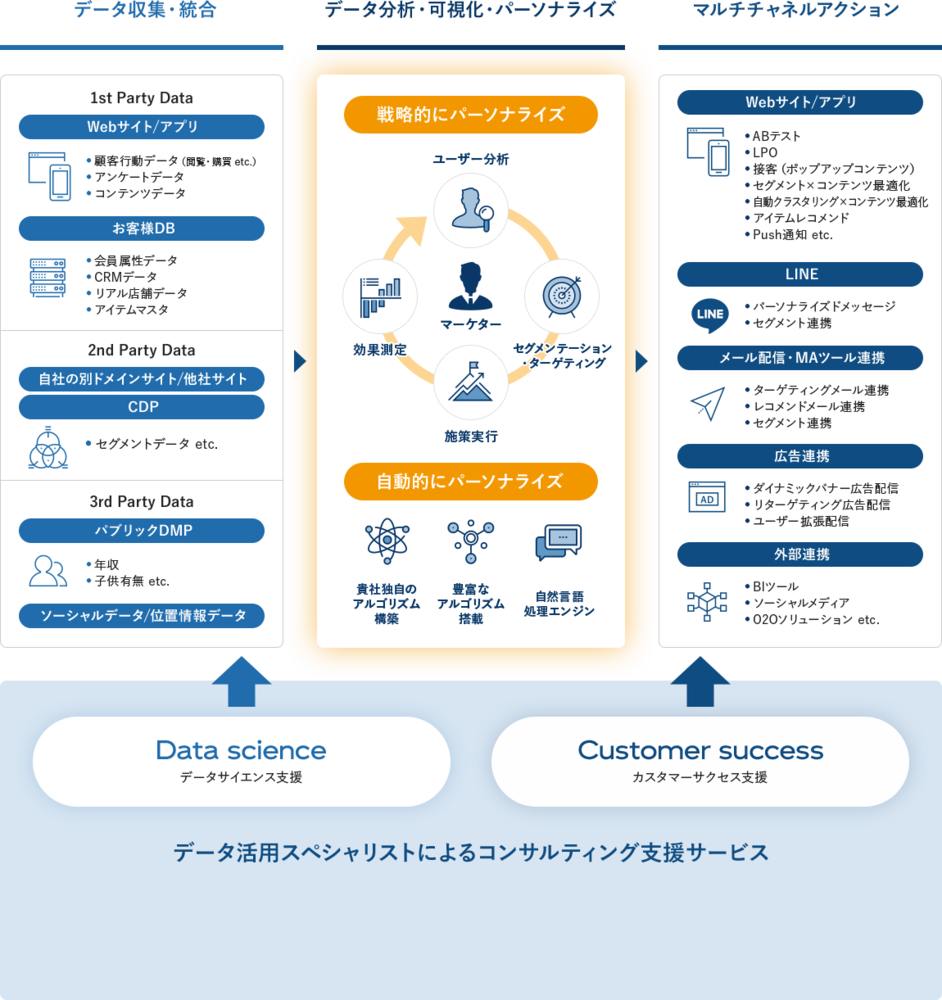
Rtoasterはユーザーの行動に合わせて接客をカスタマイズできるCXツールです。万全のサポート体制により対応満足度は98%以上、IT技術が不足している企業にもおすすめできます。自動レコメンドで顧客に応じた対応が行えるため、売上やコンバージョン率アップが期待できます。
・Rtoasterの参考価格
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | 要お問い合わせ |
・Rtoasterの参考レビュー
プライベートDMPを利用した顧客別へ効果的なWEB接客を行う機能が年々進化をしている素晴らしいツールだと思っています。レコメンドを出すのはもちろんのこと、メール送信との連携、プッシュ通知などよりWEB上での体験だけではなくWEBに再訪してもらうマーケティング施策もうてるツールは少ない。その分析精度の高さは流石データサイエンティスト集団のブレインパッドの商品だと感じさせられます。
Rtoasterへのレビュー「本製品により当社でもデジタルマーケティングを始められました」より
5.Repro

Reproは「ツールにプロがつく」をコンセプトに、日本に限らず世界で提供されているマーケティングツールです。アプリにプッシュ通知やアプリ内接客ポップアップなどの機能を搭載しており、アプリ利用者の満足度を高められます。何より、専門のサポート部隊が1社ごとにつくのはIT人材が不足している企業にとって心強いサービスです。
Reproの参考価格
| 初期費用 | 要お問い合わせ |
| 月額費用 | 要お問い合わせ |
Reproの参考レビュー
アプリ利用者へのプッシュ通知やアプリ内メッセージが簡単なUIで作成、送信ができるため、突発的な対応もすぐに行えます。
Reproへのレビュー「一通りの機能がそろっている」より
また、送信先をフィルタリングする際も同じ画面内からAnd Or Notで条件を追加していくだけなのでわかりやすいてす。
予約送信も行えるので、中長期的な施策も可能です。
プッシュ通知を選ぶ際のポイント
プッシュ通知を導入する際に大切なポイントは、まず「必要な機能を整理すること」です。
一口にプッシュ通知といってもアプリ経由かSMS経由か、プッシュ通知のみを扱ったサービスか総合的なツールかなど、いくつかの分類があります。
上記ではプッシュ通知機能を搭載したWeb接客ツールなどを紹介しましたが、「SMS送信に限定したサービス」も存在します(例:空電プッシュ)。つまり、プッシュ通知機能を手に入れたいからといって、必ずしもWeb接客ツールやCXツールを導入する必要はないというわけです。
ただし、プッシュ通知機能を求めている企業の多くはマーケティングツールやIT人材が不足していることもあり、「プッシュ通知機能を搭載しているITツール」を選ぶケースは多いでしょう。知名度やシェアといった観点ではなく、自社に必要な機能しっかり見定めるべきです。
最終的にはコスト面で比較をしながら、性能とコストのバランスの取れたツールやサービスを選ぶのが一般的な方法です。単純なコスト比較ではなく、導入後の費用対効果まで考慮しながら比較することをおすすめします。
プッシュ通知でマーケティングの反応率を高めましょう
アプリやSMSでプッシュ通知が届き、メッセージを開封した経験は誰にもあるでしょう。プッシュ通知は他の連絡ツールを圧倒するほど高い開封率を有しています。最大限に活かすためにも自社に合ったプッシュ通知機能搭載ツール、またはプッシュ通知サービスを選びましょう。
投稿 プッシュ通知の重要性とは?おすすめツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 広告運用の目的をおさらい!目的別に使える運用ツールの機能をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>広告運用の目的1.売上を伸ばしたい
広告運用ツールを導入することで、売上を伸ばしたいと考えている企業は多いでしょう。売上を伸ばすために役立つ機能には以下の3つが挙げられます。
広告別効果測定
広告別効果測定機能は、出稿広告がどの程度成果を挙げたのか測定する機能です。広告効果測定の指標には、「CV数」「クリック率」「訪問者数」などの数値が使用されます。売上を伸ばすためには、広告運用ツールの効果測定機能を使用して、数値を上げていく必要があります。
SEO効果測定
SEO効果測定とは、SEO対策をした前後で数値がどのように変化したか測定する機能です。SEO効果測定に使用される指標には、「キーワード順位(検索順位)」「離脱率」「滞在時間」「直帰率」などがあります。Webサイトでは、検索順位の高いサイトの方がクリックされる確率が大きい傾向にあります。seoClarityが2021年に公開した調査によると、日本では検索順位1位だとクリック率は13.94%、2位の場合7.52%、3位だと4.68%という結果が出ています。
出典:2021 CTR Research Study: The Largest Ever for SEO
当然、クリック数が大きい方が広告の成果も大きいため、売上を伸ばすためには、SEO効果測定の値は非常に重要です。
メルマガ・SNS効果測定
近年メルマガやSNSを利用して、広告を出稿する企業が増えています。特にInstagramやTwitter、YouTubeなど様々なSNSが発達している現代では、SNSで如何に上手く広告運用できるかで売上が大きく変わります。そんなときに重要になってくるのが、メルマガ・SNS効果測定です。メルマガ・SNS効果測定とは、メルマガ・SNSに対してユーザーがどのように反応したかを数値化して、メルマガ・SNSに対する効果を測定するものです。メルマガ・SNS効果測定では、「開封率」「CVR(コンバージョン率)」「登録者数」などの値を見ます。
以上のように、売上を伸ばすためには、様々な効果測定機能を使用して、数値を上げていく努力が必要です。
広告運用の目的2.進捗率や集客率をまとめたい
広告運用の担当者は、費用対効果の報告のために進捗率や成果をレポートにまとめて決済者に提示する必要があります。しかし、Excelやスプレッドシートで資料を作成するのは時間がかかり大変です。
そんなときに役立つのが、レポート機能です。レポート機能では、初心者でも簡単に分かりやすい資料作成が可能です。また最近では、自動でレポートを作成してくれる機能もあり、担当者の負担を減らすことができるでしょう。
広告運用の目的3.ユーザーの行動を分析したい
ユーザーの行動が分析できれば、Webサイトの集客率や広告のクリック率を増加させることが可能です。ユーザーの行動を分析するために役立つ機能は以下の3つです。
時間帯・エリア分析
時間帯・エリア分析では、何時にどこで広告を視聴または、広告をユーザーがクリックしたのかを数値で表します。また、男女比や年齢を確認できるツールもあります。ユーザーの反応を適切に把握することで、広告の視聴数が最も多い時間を狙って広告を出稿可能です。
ユーザー行動分析
ユーザー行動分析とは、Webサイトにアクセスしたユーザーの行動を分析する機能です。サイトに訪れたユーザーがどのページにどれくらいの時間滞在し、どのページへと遷移したのか分かります。ユーザー行動分析を行うことで、ユーザーのニーズを知ることができ、よりユーザーが求めている広告を出稿可能です。
デバイス効果測定
デバイス効果測定とは、ユーザーがスマホやPCなどどのデバイスから広告にアクセスしているか、またCV数やクリック数が良いのはどのデバイスかを測定する機能です。自分が運用している広告がどのデバイスからクリックされやすいのかを知っておくことで、そのデバイスに適した形で広告を出稿できます。
このようにユーザーの行動を分析することで、よりユーザーが求めているモノが把握でき、広告の質を高められます。
広告運用の目的4.影響力の強いコンテンツを把握したい
Webサイト内で影響力が強いのはどのコンテンツなのかを把握したい場合は、以下の2機能が有効的です。
アトリビューション分析
アトリビューション分析とは、ユーザーがコンバージョンに至るまでのプロセスを評価し数値化する分析方法です。アトリビューション分析を行うことで、どの要素が広告の成果につながったのか分かります。反対に、アトリビューション分析を行わなかった場合、顧客のニーズや成果に繋がる重要な点を見逃してしまう恐れがあります。
コンテンツ分析
コンテンツ分析とは、WebサイトまたはSNS上のコンテンツを分析することです。コンテンツ分析をすることで、コンテンツの効果比較ができたり、数字が伸びているようであれば要因の分析ができます。
広告運用の目的5.分析したデータを出力したい
分析したデータを外部ツールに読み込ませるために、CSVファイルなどで出力したいと考えている方もいるでしょう。その際には、エクスポート機能が便利です。エクスポート機能を使用すれば、一瞬でCSVファイルが作成できるため、外部ツールに読み込ませるために新たにデータを用意する必要はありません。
広告運用ツールを比較してみよう
広告運用ツールには、目的別に様々な機能が搭載されています。自社に合った広告運用ツールを選ぶためには、まずは、自社で広告運用ツールを利用する目的を明確にしましょう。目的が明確になったら、複数の広告運用ツールを比較してみてください。
比較には、「ITreview Grid」がオススメです。気になる広告運用ツールを複数個選定するだけで、すぐに比較表が作成できます。また、ITreviewのサイトに集まった広告運用ツールに対するレビューも役立つでしょう。
投稿 広告運用の目的をおさらい!目的別に使える運用ツールの機能をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 広告運用ツールの使える6つの機能でPDCAを回す は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>機能1:SNSやWebサイトの情報を一元管理することで、管理の手間を省く
従来のメディアに加えて、SNSマーケティングという言葉が生まれたように、数年ごとに巨大プラットフォームが誕生する昨今、複数の広告媒体を手動で管理するのは非効率です。管理する媒体が増加するほど、手間や時間を取られ、ミスや間違いが増加する傾向にあります。
多くの広告運用ツールには、データの一元管理機能があり、複数のメディアをまとめて1つの画面で管理できます。これにより、担当者はアカウントを切り替えてログインする手間が省けるため業務効率化につながります。
機能2:作業の進捗率を分かりやすく管理する
進捗率の管理は、作業が滞りなく進められているか確認するために必須です。また、上司やクライアントへの報告のためにも進捗管理は大切です。
Excelやスプレッドシートを利用して進捗率を管理している企業も少なくありませんが、広告運用ツールを利用して進捗を管理することも可能です。また、複数媒体の進捗率を管理する場合、媒体ごとに進捗率を一人で管理してまとめるのには手間がかかります。
一方で、広告運用ツールであれば、媒体ごとの進捗管理機能が搭載されているため、進捗管理が乱雑になる心配がありません。
機能3:進捗や成果を分かりやすくまとめて、クライアントに提出する
多くの企業では、出稿している広告の進捗に問題はないか、運用成果を順調に出せているかレポートにまとめています。しかし、進捗率や成果等をまとめる作業は予想以上に時間を取られるものです。
そんなときに役に立つのが、レポート機能です。レポート機能では、具体的に以下の点などを確認できます。
- 前月と比較して、成果は上がっているか、下がっているか
- 何日進捗が遅れているか、または進んでいるか
- CVやクリック率の増加率
広告運用ツールを使用すれば、グラフや表などでデータを視覚化することが容易なため、管理画面を眺めているだけでは気づくことのできなかった問題点も発見できます。また、どのような運用をすれば結果に結びつきやすいのか、過去のデータを分かりやすくデータにまとめておくことも可能です。
機能4:運用担当者によって、運用結果に差が生まれないようにする
広告運用において、初心者と経験者では、作業のスピードだけでなく、広告運用結果にも大きな差が生じてしまいます。その問題は、広告運用自動化機能を使用することで解消できます。
広告運用ツールの中には、広告運用自動化できる製品があり、「広告運用作業」と「運用レポート作成」の2種類を自動化可能です。「広告運用作業」の自動化では、リスティング広告やSNS広告の作業、広告出稿予約やキーワード設定などの業務を自動化することが可能です。「運用レポート作成」の自動化に関しては、進捗や運用結果をレポートにまとめる作業を自動で行ってくれます。
広告運用ツールの使用方法さえ理解できれば、これら2つの自動化機能を利用することで広告運用経験者でも未経験者でも結果に差が生じることはありません。
機能5:広告の影響力や集客力を分析する
広告運用時には、「成果が伸びているか」「集客できているか」のデータを分析する必要があります。そんなときに役立つ機能が、「SEO効果測定」「広告別効果測定」機能です。
「SEO効果測定」とは、SEO対策を行った前後で、検索順位やCV数に変化が現れたか測定する機能です。一方、「広告別効果測定」とは、SNSやWebサイトに出稿した広告がどの程度成果を出したか、広告別に効果を測定できる機能です。2機能とも広告運用には、欠かせません。
機能6:ユーザー分析をする
ユーザー分析機能を使用することで、どの時間帯にユーザーの広告クリック率が高いのか、どこのエリアから広告がクリックされる可能性が高いのか確認できます。
また、PCやスマホなどどのようなデバイスから広告にアクセスされる可能性が高いのか確認できるため、ユーザーの行動に合わせた広告運用が可能です。
機能が把握できたら広告運用ツールを比較してみよう
広告運用ツールの使える機能について理解できた方は、複数の広告運用ツールを比較してみましょう。比較には、「ITreview Grid」を使用するのが良いでしょう。人気の広告運用ツールを視覚的に比較できるだけでなく、レビューコメントも参考になります。
広告運用ツールと一言でいっても、様々な種類や特徴があります。必要な機能を分析したのち、自社に合った広告運用ツールを選定しましょう。
投稿 広告運用ツールの使える6つの機能でPDCAを回す は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 広告運用ツールのメリット6つ|ポータルサイトやSNSの広告運用を効率化 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>いまや多数の企業で導入されている広告運用ツールですが、メリットを正確に把握できているのでしょうか。そこで本記事では、運用ツールを導入する6つのメリットをご紹介します。
データ分析や工数削減など、広告運用ツールのメリットを考察
メリット1:データ収集と分析がしやすい
広告運用では、コンバージョン率やクリック率を定期的に集計し、より成果を出すために運用を改善していく必要があります。そのために欠かせないのが、Web広告を客観的に評価できるようにすることです。施策の内容と数字を並べることで、次回の広告施策に対しての改善点が見えてきます。
もし、他社の広告運用を代行している企業であれば、コンバージョン率やクリック率によって「クライアントの売上増加」にどの程度貢献できたか、正確なデータを提示する必要があります。
このように、データ収集と分析は広告運用に必要不可欠です。広告運用ツールを導入すれば、素早く正確なデータの収集と分析が可能になります。
メリット2:業務の効率化と工数削減
広告運用には膨大な業務があります。前述のデータ分析のほかに、運用結果の報告、競合他社の広告分析、次回の広告戦略の立案・企画、クリエイティブチェックなどがあります。これらの業務を担当する社員の負担は相当なものです。これらの問題を解決するためには、1つひとつの作業を効率化し、工数削減を図る必要があります。
広告運用ツールの導入により、広告の管理やデータ収集などの業務を効率化が可能に。より生産性の高い作業に注力できるようになるでしょう。
メリット3:複数の広告を一元管理できる
広告戦略では、複数の広告を同時に運用するケースがほとんどです。最近では、InstagramやYouTube、TwitterなどさまざまなSNSがあり、複数のメディアを活用しているケースがほとんどです。その場合、担当者は手動でアカウントを切り替えてログインを繰り返す必要があります。アカウントの切り替えが面倒なだけでなく、レポートも別々になってしまい、無駄が多い管理方法です。さらに、管理する媒体が増えれば増えるほど余計に時間がかかります。
多くの広告運用ツールにはデータの一元管理機能があり、アカウントを手動で切り替えなくてもチェックが可能です。広告の運用媒体数が多いとなれば、こうした機能は意外と助けになるはずです。
メリット4:引継ぎがしやすい
Excel等で独自のマクロを組んでデータを管理する場合、担当者によってはデータ管理方法に少なからず相違点が生まれるため、引継ぎがしにくい傾向にあります。広告運用に関しても、初心者と経験者で運用成績に大きな差が生まれてしまいます。
広告運用ツールなら、データ管理の仕方が統一されるため引継ぎが容易に。経験値に左右される部分が少なくなり、「アイデアはいいんだけど実務が苦手」という人材でもアサインしやすくなるでしょう。
メリット5:一人が受け持てるキャパ数の増加
広告運用ツールを導入することで、以下の業務の工数を削減できます。
- 進捗率管理業務
- データ分析業務(複数のアカウントに手動で切り替える必要がなくなるため)
- 振り返りレポート作成業務
工数を削減できると、広告運用ツールを導入する前と比較して、1人が受け持てるキャパ数が増加します。
メリット6:PDCAサイクルの高速化
PDCAサイクルとは、PLAN(計画)、DO(実行)、CHECK(確認)、ACT(改善)の頭文字を取った言葉です。これら4つの要因を1サイクルとして複数サイクル回し、より良い結果につなげていくという手法です。PDCAサイクルは多くの企業で導入されており、効果についても証明されています。
広告運用ツールを導入すれば、PDCA1つひとつの要素を効率的に行えるため、PDCAサイクルの高速化につながります。その結果、より短期間で効率的に成果を出せます。
メリットが理解できたら運用ツールを比較してみよう
広告運用ツールのメリットを理解できたら、複数のツールを比較してみましょう。比較することで、それぞれの広告運用ツールの特徴がより明確になります。
広告運用ツールの比較には「ITreview Grid」がおすすめです。「ITreview Grid」とは、ITreviewサイトに集まったレビューから、製品の認知度と満足度を四象限マップに表示する機能です。四象限マップで比較できるため、視覚的に違いを把握できます。「ITreview Grid」でさまざまな製品を比較して、自社に合った広告運用ツールを見つけてみてください。
投稿 広告運用ツールのメリット6つ|ポータルサイトやSNSの広告運用を効率化 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 アプリ解析ツールとは?基本機能や導入のメリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>出典:スマートフォンの実利用データに見る人々のインターネット利用の実態|三菱UFJリサーチ&コンサルティング
ビジネスへの貢献度が高いアプリですが、インストール数が増えたからといって喜ぶのは早計です。自社アプリがどのように使われているかをしっかりと把握しながら、アプリの改善等に努めなければ高いビジネス効果は見込めないでしょう。
この記事では、自社アプリの解析に加えて業界や他社の動向まで探れる、アプリ解析ツールのについてご紹介します。
アプリ解析ツールとは?
アプリ解析ツールとは、アプリ内でユーザーがどのような行動をしているか、ユーザーはどのような属性情報を持っているかなどを把握できるツールです。次の3点が主な役割となります。
- 属性情報、アプリの利用状況などのユーザーデータを分析する
- アプリの顧客満足度と問題点を把握して改善活動に役立てる
- アプリ解析のレポートを自動的に作成してPDCAサイクルを高速化する
インストール数を把握するだけでは、アプリ解析として不十分です。コンテンツが想定していた通りに使われているか、ユーザーごとにどのような属性情報を持っているかなどを把握して初めて、PDCAサイクルを増すことができるです。
アプリ解析ツールは、アプリの改善サイクルを効率よく回すために必要な、さまざまな情報を提供してくれます。インストール数やアクティブユーザー数に限らず、さまざまなKPIを用いた改善活動が可能になります。
アプリ解析ツールの基本的な機能
基本的には分析機能が中心です。ユーザーの属性情報からアプリ内での行動データを軸にしながら、さまざまな分析機能によって自社アプリの実態を明らかにします。
ユーザー実態を分類ごとに把握するセグメント分析、アプリのビジネス貢献度を把握するコンバージョン分析、アプリがどれくらいの収益を生んでいるかを知るLTV(顧客生涯価値)分析などが主な分析機能です。
アプリ解析ツールによっては、ヒートマップ分析を備えていることもあります。ヒートマップとは、アプリ内のどこが最もタップされているか、何が注目されているかなどをサーモグラフィーのように表す分析機能です。アプリのUIを少し変更するだけでビジネス貢献度が変化することは珍しくないので、ヒートマップ分析を用いると効率よくアプリを改善できます。
また、アプリのクラッシュ分析も可能です。アプリに不具合が発生した際に、なぜ・どこで不具合が発生したのかなどを自動的に分析できます。
このようにアプリ解析ツールには、アプリでビジネスを促進するために欠かせない機能が整っています。
アプリ解析ツールなら業界のトレンドや他社の動向も探れる
アプリ解析ツールによっては、他社アプリの分析を通して業界のトレンドまで把握できます。たとえば、App Ape(アップ・エイプ)、SimilarWeb(シミラー・ウェブ)などが該当します。
アプリ解析ツールを利用すると、他社アプリのインストール数、アクティブユーザー数、リテンション率(顧客維持率)などを分析可能です。これらの分析により、業界のトレンドを把握し、業界全体や他社に比べて自社アプリがどういった立ち位置にあるかを正確に知ることができます。
正確な3C分析(顧客、競合、自社の3者分析)が行えるようになり、戦略的なアプリ運用を目指せるようになります。
アプリ解析ツールを導入するメリット
アプリ解析ツールを導入する何よりのメリットは、「今まで知り得なかった自社・他社アプリの現状を把握できるようになること」です。
ビジネス貢献のためにアプリを運用している企業は多いものの、KPI(重要業績指標)としてインストール数やアクティブユーザー数しか追っていないケースが珍しくありません。この2つのKPIで把握できるのは、「アプリがインストールされている数」と「そのうち実際に使われている数」のみです。
これでは正確なアプリ解析ができず、ユーザーの視点に立ったアプリ改善が行えません。「アプリがどのように使われているか?」「使用頻度の低い機能はどれか?」など、アプリの現状を幅広く把握し、ユーザーの視点に立ったアプリ改善を行うためにはさまざまなデータを収集し、インストール数・アクティブユーザー数以外のKPIも追う必要があります。
アプリ解析ツールを利用すれば、利用データをツールが自動的に取得し、さらに分析レポートとして出力してくれるためユーザーの視点に立ったアプリ改善を進めることができます。
ツールを活用して戦略的なアプリ運用を目指そう
この機会に、アプリ解析ツールを使って戦略的なアプリ運用を目指してみましょう。複数のKPIを設定してアプリの利用状況を正確に把握し、ユーザーの視点に立った適切な改善施策を効率よく実施していきましょう。そのためにも、まずは業界のトレンドや他社アプリの現状を把握できるアプリ解析ツールを検討してみてください。
投稿 アプリ解析ツールとは?基本機能や導入のメリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 アプリ解析ツールできる3つのこと|代表的な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>ビジネスと密接な関係を持つアプリを運用する場合、「ユーザーがアプリをどのように使っているか?」というデータを解析することで、さまざまなメリットがあります。この記事では、アプリ解析ツールの役立つ機能について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
アプリ解析ツールでできる3つのこと
アプリ解析ツールを使ってできることは、主に3つあります。ユーザーデータの分析、顧客満足度の把握、そしてレポートを自動でつくることです。
ユーザーデータを分析する
アプリ解析ツールを使えば、ユーザーデータをさまざまな角度から分析できます。一般的に分析できるのは、ユーザーが使用している端末やOS、現在位置情報などの属性情報、ユーザーがアプリをどのように操作しているかなどの行動情報です。ユーザーデータを分析すれば、アプリの改善点を見つけ、より良いアプリ開発に情報を役立てられます。
顧客満足度を把握する
アプリ解析ツールが収集する情報により、顧客満足度を把握することもできます。ユーザーがアプリ利用に満足しているかどうかは、ビジネスの結果を大きく左右する要素です。顧客満足度の向上を目指すには、アプリ解析ツールが欠かせません。
レポートを自動でつくる
アプリ解析ツールで収集した情報はレポートとして出力できます。Excelを使って担当者自身がグラフ等をつくる必要はなく、アプリ解析ツールが自動で作成してくれるのでレポート出力の手間がなくなります。
アプリ解析ツールの役立つ機能とは
それでは、アプリ解析ツールに備わっている一般的な機能についてご紹介します。
アクセス分析
ユーザーごとに使っている端末、OSの種類やバージョンなどを分類し、ユーザーがアプリをどのように使っているかを把握できます。アクティブユーザーの数、イベントごとの実行回数など、アプリ運営に欠かせない指標ばかりです。
セグメント分析
ユーザーの属性情報からセグメンテーション(分類)を行い、セグメントごとにユーザーを分析できます。
ヒートマップ分析
アプリ内のどこがよくタップされているのか、ユーザーはどこに着目しているのかなどをサーモグラフィーのように表せます。
コンバージョン分析
アプリが目標としているコンバージョン(成果)を設定し、ユーザーの数や利用回数などに対するコンバージョン率をチェックできます。
LTV分析
アプリに対する課金頻度や期間などを集計し、アプリのLTV(顧客生涯価値)を把握できます。
クラッシュ分析
アプリに発生したクラッシュ(不具合)を発見し、クラッシュ発生の日時やバージョンなどを分析できます。
ABテストの実施
AとB、2つの要素を同時に公開し、どちらのほうがコンバージョン率が高いかをテストできます。
レポート作成
アプリ解析ツールで集計したさまざまなデータを、好きな切り口からレポートとして出力できます。
アプリ解析ツールで確認できるKPI(指標)
アプリ解析ツールを利用すれば、さまざまなKPIを確認しながらアプリ運用を最適化できるようになります。アプリ運用においてビジネスに関連のあるKPIといえば下記の4点です。
- アプリのインストール数
- アプリのアンインストール数
- アクティブユーザー数
- プッシュ通知の開封率
適切なアプリ運用によりPDCAサイクルを継続的に回すためには、これらのKPIを常に追い続けなければいけません。アプリ解析ツールがない環境ではKPIを追うことが難しいため、アプリ運用の適正化のためにもアプリ解析ツールの導入を検討しましょう。
アプリにおけるKPIに関しては『アプリを成長させたい!KPIを設定するために覚えておきたいポイントを紹介』にて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
アプリ解析ツール選びのポイント
最後に、アプリ解析ツールの選び方についてご紹介します。
1つ目に大切なポイントは「導入目的の明確化」です。アプリ解析ツールを導入する主な目的は「アプリ運用の最適化」ですが、企業によって細かい目的は異なります。
広告収入のアップなのか、顧客満足度の向上なのか、あるいはユーザーの行動分析により利用状況を把握したいのか。こうした細かい目的を明確にしていないと、自社に合ったアプリ解析ツールを選ぶのが難しくなってしまいます。
アプリ解析ツールの導入目的を感覚的に決めるのではなく、改めて議論し、細かい目的まで明確にしてから製品選びを始めましょう。
2つ目に大切なポイントは「コストの比較」です。多くのアプリ解析ツールは月額性のクラウドサービスで提供されるため、アプリ解析ツールを利用する人数や、解析する範囲などによってコストが異なります。
また、アプリ解析ツールには無料で提供されているものもあるため、そうした製品も含めてコスト比較を行いましょう。
「無料で使えるならそれが良いに決まっている」と思われるかもしれませんが、有料製品に比べると機能面で不足する部分が多いため、必ずしも安ければ良いわけではありません。
したがって、1つ目のポイントで導入目的の明確化をしっかりと行い、自社が導入するアプリ解析ツールに必要な機能を整理した上でコストを比較することが大切です。
アプリ解析ツールでユーザー行動を解析しましょう
アプリ解析ツールを導入すれば、ユーザーがアプリをどのように利用しているかなどの情報を隅々まで把握できるようになります。
ただし、アプリ解析ツールを導入すればアプリがすぐに改善されるわけではありません。あくまで情報提供ツールであり、最終的には人の判断によってアプリを改善していかなければならない、ということを忘れないでください。その上で、自社に合ったアプリ解析ツールを選んでみましょう。
投稿 アプリ解析ツールできる3つのこと|代表的な機能を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 アプリのKPIは設定できてる?グロースに欠かせないポイントを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、アプリは提供して終わりというものではありません。利用者が増えなければ、アプリ制作を行った本来の目的が達成できないことになってしまいます。アプリを成長させることが、企業の成長へとつながります。
その成長を図るための手法として用いられるのがKPIです。KPIとは、目標達成に向け達成度合いを計測・監視するための定量的な指標です。顧客満足度向上のため、ユーザーからの反響を分析するにはKPIが重要な役割を果たします。そこで今回はアプリで用いられるKPIと、計測するためのアプリ解析ツールについて解説します。
アプリでKPIを設定する目的
アプリでKPIを設定する目的は、プロセスを評価し改善につなげることです。そのポイントとなるのが「各プロセス」で行うことです。つまりダウンロード数だけをゴールとするのではなく、複数の指標を用いて評価しなければいけません。
しかしなぜプロセスが重要となるのでしょうか。その理由は、アプリを運用する目的に合わせて考える必要があります。
ダウンロードされても、アプリが利用されない、もしくはアンインストールされれば意味がありません。一方で頻繁にアクセスしたり課金・売上単価が高かったりするユーザーは、目標達成に向けて確実に貢献してくれます。このことから、アプリにおいてはダウンロード数だけでなくその後の過程を見る必要があり、それらを継続して評価することで目標達成に近づくことになります。
アプリにおける主要KPI
企業アプリの目的はECストアの開設やブランド広告などさまざまですが、その用途によって必要なKPIは異なります。ここでは共通してよく使われるKPIをご紹介します。
1.インストール数
アプリをインストールした数を表します。ここで注意すべき点は、あくまでインストールの数でありダウンロードの数ではないことです。ダウンロードはアプリのデータを保存したもので、まだ利用できる状態になっていません。利用できる状態になっているものがインストールとしてカウントされます。
2.継続率
ユーザーがどれだけ継続利用しているのかを示す指標です。具体的な見方としては、翌日・7日・30日という単位で、インストール後に再度起動したユーザーの割合を算出します。
3.ARPU
一定期間における1ユーザーあたりの平均売上額です。アプリのマネタイズ方法によって違いがあり、課金モデルであれば平均購入単価、無料アプリは広告単価、クリック広告モデルはクリック単価を用いて計算されます。
KPIの設定で注意すべきポイント
KPIの設定で注意すべき点はいくつかありますが、「SMARTの法則」を用いることでより効果的な指標の設定が可能です。
SMARTの法則は次の5つの要素で構成されています。
- S(Specific/具体的に)
- M(Measurable/数値で計測できること)
- A(Achievable/実現可能な)
- R(Relevant/目標と関連すること)
- T(Time-bounded/期限が明確であること)
つまり指標が抽象的で分かりにくいものや実現の可能性が低いもの、最終的な大きな目標に関連性のないものは指標として適切ではありません。メンバー全員が共通認識を持てる数値を用いて、細かくプロセスや期限を区切り目標の進捗度を可視化することが重要です。
KPIを達成するためにはPDCAを回すことが不可欠
KPIを達成するためにはPDCAを回すことが不可欠です。指標設定は、単なる評価でしかありません。評価した結果を活用し目標到達に向けて施策を繰り返すことがアプリの成長につながります。
具体的には以下のステップを繰り返します。
1.Plan(計画)
アプリの目的に合わせたKPIを設定します。
2.Do(実行)
日々のデータの推移を観察します。1回の計測だけではなく、2回、3回と繰り返し変化を見ながらその原因を探るのがポイントです。
3.Check(確認)
計測結果を用いて分析を行います。とくに前回の施策によって大きな変化がある場合は、徹底的な分析が必要です。
4.Action(改善)
分析結果から次の戦略を立て、改善を行います。ここでのポイントは、改善効果を明確にするために、ターゲットをある程度絞ることです。例えばある年代や性別を対象としたり、特定のクーポンだけ改善したりすることなどです。
これら4つのステップを繰り返すことで、リリース直後よりもアプリは飛躍的に成長します。またPDCAサイクルを回すことでそれぞれの精度が増し、業務効率の向上とともに大きな目標達成に近づけるのです。
運用をサポートしてくれるアプリ解析ツールを探そう
KPIの指標には、集計だけで済むものもあれば手間のかかる計算もあります。それら全てを自社で行う場合多大な時間とコストが必要となり、かえって業務の支障になる可能性があります。そのようなときに便利なのが、アプリ解析ツールです。アプリ解析ツールに寄せられたレビューをご紹介します。
・KARATE
Webサイトやアプリを利用するユーザーの行動をリアルタイムに解析・可視化できる「KARATE」には以下のようなレビューが投稿されました。
・KARATEの参考レビュー
KPIの改善(主に新規ユーザーの会員登録率及び継続率の向上に貢献)
KARTEでは事前に定義しておいた条件でユーザーをグルーピングできます。(新規ユーザー・ライトユーザー・ヘビーユーザー ✕ サービス利用開始からの経過日数 のかけ合わせ等)
これによって、ユーザーの状態にあわせて最適なコミュニケーションを取る事ができ、冒頭に記載したような効果が出ています。
KARATEへのレビュー「CRM領域・コンテンツ企画領域での良いパートナーです。」より
Rtoaster(アールトースター)
高精度のレコメンデーションによるWeb・アプリのコンテンツ最適化機能を持つ「Rtoaster」には実用性のあるレビューが届きました。
・Rtoaster(アールトースター)の参考レビュー
ABテストとポップアップ広告を主に使っている。ユーザー単位のターゲティングを手軽に実行に移せることに加えて、セグメントとの掛け合わせによってユーザー層に合わせたクリエイティブを届けるという高度なデジタルマーケティングができている。他のABテストツールやDMPツールでは手の届かないような細やかなターゲティングを設定できることで、経験豊富なマーケターの方の満足度も高い。
Rtoasterへのレビュー「多彩な施策展開が可能なプライベートDMP」より
Repro
「Repro」はユーザー行動・属性データをもとに⾼速PDCAを実現できるWebとアプリの接客ツールです。アプリ運営に必要な機能がワンセットになった頼れるツールです。
・Reproの参考レビュー
アプリ利用者へのプッシュ通知やアプリ内メッセージが簡単なUIで作成、送信ができるため、突発的な対応もすぐに行えます。
また、送信先をフィルタリングする際も同じ画面内からAnd Or Notで条件を追加していくだけなのでわかりやすいてす。
予約送信も行えるので、中長期的な施策も可能です。
Reproへのレビュー「一通りの機能がそろっている」より
アプリ解析ツールは利用者の起動状況や活用状況など、アプリの目的に沿ってさまざまな角度からデータを集計して可視化できるものです。なかには操作の様子を録画し、そのアプリの改善点を発見できるツールもあります。気になる人は、ぜひ比較検討してみてください。
投稿 アプリのKPIは設定できてる?グロースに欠かせないポイントを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 CPA(顧客獲得単価)とは?計算方法から改善のアイデアまで解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、CPAの意味から計算方法や改善方法、類似の指標について解説します。
CPAとは?
CPAは「Cost Per Acquisition」もしくは「Cost Per Action」の略で、「顧客獲得単価」や「コンバージョン単価」と呼ばれ、新規顧客を獲得するために費やしたコストを示します。一般的には1人の顧客や1件の成約を獲得するためにかかった広告費を指します。
CPAは広告の費用対効果を把握できる指標なので、たとえば広告の出稿量が増えたとしても、CPAが低ければ費用対効果が高く広告費以上のリターンを得ていると判断できます。
このときのリターンとは、商品・サービスの購入や入会、サンプルや資料の申し込みを示します。
なぜ、CPAが必要か?
広告の費用対効果を数値で確認できなければ、その広告の運用を継続すべきかどうか、あるいは強化すべきかどうかの判断ができません。
そのため、CPAを使用して、広告でコンバージョンが獲得できているかどうかを確認する必要があります。
コンバージョン(Conversion)とは「変換」や「転換」「交換」を表す英語ですが、マーケティングでは広告によって商品・サービスの購入や、入会や資料取り寄せなど、広告主にとって価値のある行動に至ることを意味します。
CPAの値が小さければ、少ない広告費で多くのコンバージョンを獲得できたことを意味します。逆にCPAの値が大きくなることは、コンバージョンを獲得するための広告費がかさんでおり、費用対効果が低いことを意味します。
したがって、CPAの値が大きい場合は、広告の運営に関して改善すべき点があること判断して見直しを行う必要があります。
CPAの計算方法
CPAはコンバージョン1件当たりの広告費を求める次の式で算出できます。
CPA = 広告費 ÷ コンバージョン件数
たとえば、ある月に広告費を50万円投入した結果として新規顧客を5人獲得できていれば、
CPA = 50万円 ÷ 5人 = 10万円
とCPAが10万円になります。そして次の月に70万円の広告費を投入した結果、新規顧客を10人獲得できていれば、
CPA = 70万円 ÷ 10人 = 7万円
とCPAが7万円になります。
この結果から、前の月のほうが広告費は安く済んでいますが、費用対効果はあとの月のほうが高かったことになり、効果的な広告運用ができたことがわかります。
目標CPAの決め方
費用対効果の高い広告運用を行うために、目標CPAを算出しておく必要があります。
目標CPAを設定するためには、商品原価や人件費、広告費などを算出しておきます。
広告は利益を上げるために行う施策ですから、目標CPAは利益が出ることを前提に設定します。そのために、採算が合わなくなる限界CPAをあらかじめ算出しておく必要があります。
しかし、コンバージョンに直接利益が出ない資料請求や無料トライアルの申し込みなどを設定している場合は、必ずしも直接的な利益が出る設定をする必要はありません。
以下、限界CPAと目標CPAについて解説します。
限界CPAとは?
限界CPAは、コンバージョン1件にかけられる広告費の上限です。式は次のとおりです。
限界CPA = 売上単価 - 原価 - 経費
たとえば、売上単価が2万円で原価が7,000円、経費が3,000円だとすると、限界CPAは1万円になります。1万円はあくまで上限値ですから、この上限まで広告費をかけては利益がなくなってしまうことに注意が必要です。
また、限界CPAは損益分岐点ですから次の式でも算出できます。
限界CPA = 顧客単価 × 利益率
前出の例をこの計算方法に当てはめると、顧客単価は2万円で利益率は50%でしたから、やはり限界CPAは1万円になります。
ただし、会員登録や資料請求、無料トライアルなど、直接利益が出ないコンバージョンを設定している場合は、成約率を加味した計算式になります。
限界CPA = 顧客単価 × 利益率 × 成約率
目標CPAとは?
目標CPAはコンバージョン1件あたりにかけられる費用の目標額なので、計算式は次のとおりです。
目標CPA = 限界CPA - 確保したい利益
たとえば、限界CPAが1万円で7,000円の利益を確保した場合の目標CPAは3,000円となります。
つまり、利益の何%を広告費に当てるのかによって目標CPAを設定するので、次の計算式にもなります。
目標CPA = 限界CPA × 広告費の割合
たとえば、2万円の商品で利益率50%の限界CPAは1万円です。この中から確保したい利益が70%だとすると、広告費には30%を当てられるので、目標CPAは3,000円となります。
売上が成果となる場合の目標CPA
コンバージョンが売上になる場合の目標CPAは比較的シンプルに算出できます。
たとえば、商材の価格が3万円、製造原価が9,000円、人件費が6,000円の場合、
限界CPA = 売上単価 - 原価 - 経費 = 3万円 - 9,000円 - 6,000円
なので、限界CPAは1万5,000円となります。
確保したい利益が8,000円だった場合、
目標CPA = 限界CPA - 確保したい利益 = 1万5,000円 - 8,000円
なので、目標CPAは7,000円となります。
直接売上にならない場合の目標CPA
コンバージョンが直接売上にならない場合の目標CPAは次のように算出できます。
たとえば、コンバージョンが資料請求で、成約率が資料請求者の50%とします。商材は8万円で製造原価が3万円、人件費などの経費に1万円かかっている場合、限界CPAは次の式で求められます。
限界CPA =(売上単価 - 原価 - 経費)× 成約率 =(8万円 - 3万円 - 1万円)× 50%
したがって限界CPAは2万円となります。
目標とする利益を1万円とした場合、
目標CPA =(限界CPA - 確保したい利益)× 成約率=(2万円 - 1万円)× 50%
ですので、5,000円となります。
CPAの改善方法
広告の費用対効果を高めるためにはCPA改善する必要があります。つまり、CPAを低く抑えるのです。
以下、CPAを改善する方法を解説します。
1.クリック当たりの広告費を下げる
CPCは「Cost Per Click」の略で、クリック当たりの広告費を表し「広告費用 ÷ クリック数」で算出できます。つまり、CPCの値が小さいほど、低い広告費で多くの反応を得られたことになり、費用対効果が高いことを示します。
広告の費用対効果を高めてCPCを下げるためには、ユーザーの注意や興味を引くクリエイティブ(広告用に作成した成果物)になっているかどうか、あるいはターゲットに届いているのかどうかを見直す必要があります。
また、一度効果があったからといって同じクリエイティブを使用し続けると新鮮さが失われてくるため、CPCが高まってしまう可能性もあります。クリエイティブは定期的に新しくすることが望ましいでしょう。
特にリスティング広告では「品質スコア」を上げることでGoogle広告における評価が上がり、表示順位によい効果があります。品質スコアを上げるためには、キーワードと広告の関連性を見直したり、移動先のランディングページの利便性(見やすさや読み込み速度など)を見直したりする必要があります。
さらに、広告の掲載順位を決める要素である入札単価の上限を低く設定することでも広告コストが下がり、CPCを下げる可能性があります。ただし、この方法では同時に掲載順位と露出度が下がってしまうリスクもあるので、慎重さが必要です。
2.広告の文章を改善する
長期間広告文を変更せずに使用していると、広告文がターゲットやキーワードに合わなくなってしまい、コンバージョンを減らしてしまうことがあります。ターゲットを取り巻く環境などが変化することで、ターゲットが興味をもつ対象も変化し、競合の増加と競合の戦略の変化によりキーワードの重要性が変化するためです。それを防ぐためにも、広告文は定期的に見直す必要があります。
3.キーワードを変更する
広告がクリックされても成約につながっていない場合は、商材を購入する動機をもつユーザーが求めているキーワードと関連性が薄いキーワードを設定している可能性がありますので、見直しが必要です。
その場合は、関連性の薄いキーワードを除外設定することも検討してみます。無駄にクリックされることを防ぐことで、広告費の無駄を削減できる可能性があります。
一方、クリック自体が少ない場合は、適切なキーワードが設定されていない可能性があります。キーワードを新たに選定し直すことも検討すべきです。
4.ターゲットを再確認する
広告文やキーワードを見直した結果、クリックはされるようになったが成約には至らない、という場合は、そもそものターゲットの選定に問題がなかったかを見直します。
つまり、実際にクリックしているユーザーが想定していたターゲットと異なっていたり、あるいは想定していたターゲットのニーズと商材が応えられるニーズが適合していなかったりする可能性もあります。その場合は、たとえクリックされるような広告文やキーワードが選定されていても、肝心の商材の特性がターゲットに響いていない可能性があります。
5.移動先の再確認
広告がクリックされているにもかかわらず成約率が上がらない場合は、クリックした移動先が適切かどうかを見直す必要もあります。
たとえば、ダイエットサプリの広告に興味をもってクリックしたのに、健康食品全般を扱うECサイトのトップページに誘導されても、ユーザーは困惑したり面倒に思ったりして離脱してしまう可能性があります。
6.LPの改善
LP(Landing Page:ランディングページ)とは、広告をクリックした直後にユーザーが閲覧するWebページを示します。つまり、ユーザーが着地する(landing)ページを示します。
LPには通常、広告で紹介した商品の説明ページや会員登録を促すページ、あるいは資料を請求するページなどが作成されます。
このとき、LPが広告に興味をもったユーザーにとって違和感がなく、コンバージョンに結びつく内容になっているかを見直す必要があります。
広告運用ツールでCPA改善
インターネットでの広告には、Web検索サイトやSNSなどさまざまな媒体があり、これらの媒体への広告出稿や分析などの運用を手作業で行っていたのでは効率が悪くなります。
そこで、これらの運用管理や分析を自動化することで、広告担当者の労力を削減し、運用コストを抑えるために、広告運用ツールを活用することが考えられます。
広告運用ツールの比較検討を行うためにも、ITreviewの「広告運用の比較・ランキング・おすすめ製品一覧」をぜひ、参考にしてください。
CPAに類似の指標の比較
広告を運営するに当たって、CPA以外にも覚えておきたい類似の指標がありますので紹介します。
| CPO | 広告費 ÷ 受注件数 |
| CPR | 広告費 ÷ 登録や申し込み件数 |
| CPC | 広告費 ÷ 獲得したクリック数 |
| ROAS | 売上 ÷ 広告費 × 100 |
| CTR | クリック数 ÷ インプレッション数 × 100 |
| CVR | コンバージョン数 ÷ サイトへのアクセス数(訪問数) × 100 |
CPO
CPOは「Cost Per Order」の略でOrderは注文の意味ですから、1件の受注を得るためにかかるコストを表します。計算式は次のとおりです。
CPO = 広告費 ÷ 受注件数
たとえば、20万円の広告費をかけて5件の受注をすればCPOは4万円です。
CPAがコンバージョンあたりの広告費であったのに対し、CPOは受注当たりの広告費となります。コンバージョンには問い合わせや資料請求などを設定することもできますが、受注を設定した場合はCPAとCPOは同じになります。
CPR
CPRは「Cost Per Response」の略で、Responseとは無料の登録や申し込みなどの反応を示します。つまり1件の登録や申し込みを得るためにかかるコストを表します。計算式は次のとおりです。
CPR = 広告費 ÷ 登録や申し込み件数
たとえば、10万円の広告費をかけて4件の無料サンプルの申し込みを獲得できた場合のCPRは2万5,000円となります。コンバージョンに無料登録や無料サンプル申し込み数を設定した場合は、CPAとCPRは等しくなります。
CPC
CPCは「Cost Per Click」の略で、ユーザーからのクリックを1回得るためにかかる費用を表します。計算式は次のとおりです。
CPC = 広告費 ÷ 獲得したクリック数
たとえば、30万円の広告費を費やして獲得したクリックが2,000回だったとき、CPCは150となります。これは、1回のクリックを獲得するために150円の広告費を費やしたことを表します。
注意しなければならないのは、クリックしたユーザーが必ずしも商品やサービスを購入したり無料サンプルの申し込みをしたりするわけではないため、CPCが下がったからといって、広告の効果が高かったとは評価できないことです。
ROAS
ROASは「Return On Advertising Spend」の略で、広告費の回収率を表します。計算式は次のとおりです。
ROAS = 売上 ÷ 広告費 × 100
たとえば、60万円の広告費をかけて120万円の売上があったとき、ROASは200%となります。つまり、広告費に費やした金額の2倍の売上があったことを示します。
ROASは、総合的な広告の効果を示す指標といえます。
CTR
CTRは「Click Through Rate」の略で、インプレッション数(ユーザーに広告が表示された回数)に対して、クリックされた回数の割合を表します。CTRの計算式は次のとおりです。
CTR = クリック数 ÷ インプレッション数 × 100
たとえば、広告が1万回表示された内、クリックされた回数が200回の場合は、CTRは2%となります。また、商品の購入ページやイベントの申し込みページのURLを記載したメールを2万件配信したときに、URLをクリックしたユーザーが500人いた場合、CTRは2.5%となります。
CVR
CVRは「Conversion Rate」の略で、顧客転換率と呼ばれます。Webサイトへのアクセスの内、登録や申し込みなどのコンバージョンが発生した割合を示します。計算式は次のとおりです。
CVR = コンバージョン数 ÷ サイトへのアクセス数(訪問数)× 100
たとえば、無料サンプルの申し込みサイトへのアクセス数が2万だったときに、実際に申し込まれた数が500件の場合、CVRは2.5%となります。
CPAを下げる際の注意点
CPAの低さだけに注目してしまうと、広告効果を正しく把握できない場合があります。
近年、カスタマージャーニーが複雑になってきています。カスタマージャーニーとは、ユーザーが商品やサービスを認知することから検討、そして購入へ至るまでの顧客体験を示します。
たとえば、自社の製品を購入した顧客は、検索で見つけたリスティング広告をクリックしたことで自社オウンドメディアを閲覧することになり、その結果表示されるようになったリターゲティング広告をクリックしてたどり着いたLPから商品を購入したかもしれません。
しかし、ここでCPAを算出すると、LPに対するコスト評価しかできません。実際には、リスティング広告が決め手だったのかもしれませんし、オウンドメディアで醸成された信頼感が購入に踏み切らせたかもしれないのです。
このようにCPAというのは、直前の広告の効果しか測れないことを理解しておく必要があります。
まとめ
CPAは広告を運営するうえで費用対効果を把握するためには重要な指標です。しかしCPAを下げることだけに固執すると、コンバージョンと売上を下げてしまう可能性もあります。
広告を評価する際には、CPOやCPR 、CPC、ROAS、CTR、CVRなどの指標にも注意を払いつつ、さらにカスタマージャーニーも考慮したうえで、複合的な検証を行う必要があります。
投稿 CPA(顧客獲得単価)とは?計算方法から改善のアイデアまで解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MEOとSEOの違いとは?対策のポイントからMEOツール4選を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>MEOとは?
MEOは「Map Engine Optimization」の略で、「地図エンジン最適化」と訳されています。自社や店舗の情報をGoogleマップの検索結果(ローカル検索)で、より優位に露出させるための対策を示します。また、MEOはGoogleマップ上の表示だけでなく、Google検索の結果の表示のされ方にも影響を与えます。
そのため、特にローカルなビジネスにおいては、必須の対策と考えられるようになっています。近年は外出先でスマートフォンを使って会社や店舗を検索する需要が増加しているため、MEOを重視する事業者が増加しています。
ちなみにMEOは日本独自の呼び方で、海外では同じ施策に対してLocal SEOという呼称が使われています。そのため、海外のクライアントとMEOの話をする際には、用語の使い方に注意が必要です。
MEOとSEOは何が違うのか?
| SEO | MEO | |
| 立地 | 検索場所に応じて最適な検索結果を表示するアルゴリズムが組み込まれている | Googleビジネスプロフィールに登録された位置情報が軸となり、検索結果に表示 |
| 口コミ(レビュー) | 口コミそのものが存在しない | Googleビジネスプロフィール上に投稿された口コミの件数や評価。投稿された文章の内容などが検索順位に影響を与える |
| 評価されるページ | 対象のページやホームページ全体が評価の対象 | Googleビジネスプロフィール上の情報が評価対象 |
SEOは、基本的には世界中のどの端末で検索しても同じになることを前提に対策が行われます。しかし、実際に日常的な検索では地域により異なる結果が表示されることが多くあります。
たとえば「ラーメン店」と検索すれば、検索した人の所在地が神奈川県と千葉県では異なる検索結果が表示されます。それぞれ検索者の所在地周辺で営業しているラーメン店が検索結果として表示され、各店舗の所在地を示す地図も表示されます。
これは「ローカル検索」と呼ばれる機能です。Googleが検索者にとってより実益がある検索結果を返しているのです。実際、神奈川県でラーメン店を探している人に、北海道や九州の名店を表示しても、役に立たないことが多いでしょう。
このようなローカル検索でより上位に表示されることをめざして行う施策がMEOです。そのため、MEOではSEOでは行わない、地域性に関わる対策が必要になります。
なぜ、MEOを重視するのか?
実店舗や地域に根ざした事業を行っている事業者にとっては、商圏外の検索者に知られることよりも商圏内の検索者に知られることのほうがビジネスに有利です。そのため、商圏内の検索者が検索した結果としてGoogleマップと共に店や事業所の情報が表示されることは、マーケティング上有益です。
場合によっては、ローカル検索で初めてその店舗や事業所の存在に気づく検索者も多いと考えられます。このことは、潜在顧客へアプローチできることを示します。また、ローカル検索は、SEOと比較して地域性が加味される分、検索結果の競合が少ないことも有利に働きます。
特に近年では、パソコンよりもスマートフォンで検索する利用者が増加しているため、MEOの重要性はさらに増してきています。また、SEOはGoogle側のアップデートにより検索順位が変動する可能性が大きいですが、MEOではSEOほどの大きな変動が起きる可能性は今のところ低いと考えられます。
MEO対策のポイント
MEO対策の大きな方針は、Googleビジネスプロフィール内「Google のローカル検索結果のランキングを改善する方法」で紹介されていますが、ビジネスプロフィール情報の拡充と更新性になります。ここでは、MEO対策のポイントを紹介します。
未登録であることを確認する
まず、登録したい店舗名や法人名をGoogleマップで検索します。下図のように店舗名や法人名で表示されていれば、すでに登録されていることになります。Googleマップでまだ確認できない場合は、Googleビジネスプロフィールの登録を行います。
Googleビジネスプロフィールを登録する
MEOはGoogleビジネスプロフィールを登録することから始まります。Googleビジネスプロフィールは無料のツールで、Googleでの検索やGoogleマップでの検索時に、自店舗や自社の情報を表示させるために必要です。
情報は正確に登録してください。特に名称、住所、電話番号は正確に登録します。名称や住所の表記が自社のWebサイト上の表記やポータルサイト上の表記などとブレがないように統一します。
GoogleビジネスプロフィールはGoogleマップの検索フィールドに店舗の住所を入力し、左側のメニューをクリックして表示されるメニューから「自身のビジネス情報を追加」をクリックし、質問に答えていくことで登録されます。
MEO用のキーワードを決める
MEO用のキーワードを決めます。キーワードは、近くのユーザーがどのようなキーワードを使ったときに店舗や事業所が表示されてほしいかを考えます。
Googleビジネスプロフィールを充実させる
Googleビジネスプロフィールを登録したら、情報を充実させます。情報を充実させることでキーワードとの関連性も高めます。また、情報が充実しているほど、Googleの評価も高くなります。
業種のポータルサイトに登録する
MEOはGoogleビジネスプロフィールへの登録で終わりではありません。外部のポータルサイトに掲載することもMEOとして効果があります。その際、店舗名や住所などは、Googleビジネスプロフィールと統一するようにします。
自社のサイトを立ち上げる
MEOとして、自店舗や自社のWebサイトも立ち上げます。Googleビジネスプロフィール以外のサイトに同じ情報が掲載されていることで、MEOの評価が高くなります。また、自店舗や自社サイトが立ち上げてあれば、より詳しい情報を求めているユーザーからの信頼性が高まります。
投稿する
Googleビジネスプロフィールの投稿機能を使って、テキストや写真を積極的に投稿することがMEOとして評価されます。
口コミの投稿を増やす
口コミの投稿を増やすことは、Googleからユーザーの支持を得ていると評価され、表示順位に影響を与えます。また、ほかのユーザーにとっても重要な情報となります。それを見たユーザーの行動を促すことになります。
よい口コミを増やすためには、ユーザーに評価される質の高い商品・サービスを提供することがもっとも基本的なことです。この基本を押さえたうえで口コミを促さなければ、かえって悪い評価を書き込まれてしまうリスクが高くなります。なお、ユーザーの好意による口コミをお願いすることは問題ありませんが、なんらかのインセンティブを付与して口コミを集めることは禁止されていますので注意してください。
順位をチェックする
MEOを実施したあとは、定期的に表示順位を確認します。順位を上げるための施策を行ったあとで順位が下がっていれば、その施策は効果がなかったことになるので中止すべきですし、順位が上昇していれば、その施策は有効だったことになるので継続的に実施する必要があるとわかります。
MEO対策を行うメリットとデメリット
MEOを実施する際のメリットとデメリットを紹介します。
MEO対策を行うメリット
1.店舗に来られる距離にいるユーザーに訴求できる
店舗の近くにいるユーザーの検索結果に自店舗が表示されることは、今すぐ来店する顧客の獲得につながりやすくなります。この効果をSEOでめざすことは非常に難易度が高くなります。また、リスティング広告で同じ効果を得ようとすると、高い費用がかかります。
2.ローカル検索の結果で上位に表示されやすくなる
MEOを行うと、Googleマップに登録されている店舗や事業所の検索順位を上げるだけでなく、「地域+業種」などのローカル検索が行われた際にも順位が上がりやすくなります。
3.SEOより短期間で上位表示される可能性がある
SEOで検索結果の上位表示を狙った場合、サイトの内部構造に手を入れたりコンテンツを充実させたりするなどのコストや手間がかかり、表示順位に反映されるまでに半年から1年ほどかかります。しかし、MEOの場合は低コストで手間もかからず、早い場合は1週間ほどで表示順位に反映されます。
4.外出中のユーザーに訴求できる可能性がある
日本では情報を検索する際、デスクトップパソコンよりもスマートフォンなどのモバイル端末による割合が圧倒的に多くなっています。ドイツのSISTRIX社が2021年3月に公開した調査結果(※)によると、日本で検索が行われているデバイスはデスクトップパソコンが24.9%でモバイル端末が75.1%です。米国やフランス、ドイツ、スペイン、イギリスでのモバイル端末の割合はそれぞれ64.9%、62.1%、64.1%、65.1%、66.4%といずれも6割台でした。つまり、日本においては外出先での検索のニーズが大きいため、MEOの重要性がより大きいといえます。
出典:『The proportion of mobile searches is more than you think – What you need to know – SISTRIX』
出典(※):『The proportion of mobile searches is more than you think – What you need to know – SISTRIX』
5.検索意図とマッチしやすい
たとえば「新宿+フランス料理」と検索するユーザーは、検索結果を参考にして実際に行動する可能性が高いといえます。そのため、ローカル検索としてのMEOの実施は、「地域+業界」という検索ニーズにマッチしやすいと考えられます。
6.無料で始められる
MEOは専門的なスキルがなくても始められます。また、Googleビジネスプロフィールへの登録は無料で、テキストや画像の投稿、口コミへの返信も無料です。
7.SEOよりまだ競合が少ない
今や多くの企業がSEOに取り組んでいます。そのため多くの競合と検索順位を争うことになります。一方、MEOはまだ取り組んでいる店舗や企業が少ないため、実施した分だけ効果を出しやすいといえます。また、全国規模で検索順位を競うのではなく、ローカル検索で優位になることをめざすので、手続もシンプルです。さらに、MEOは自力で実施することができるので、SEOに比べて費用負担が少なく済みます。
MEO対策を行うデメリット
MEOはぜひ実施したい施策ですが、デメリットについても確認しておきましょう。
1.口コミへの対応が必要
Googleビジネスプロフィールを登録したあとは、投稿された口コミの管理を行う必要があります。評価が高い口コミへの迅速なお礼も重要ですが、それ以上に低評価の口コミへの対応は迅速かつ慎重に行う必要があります。過度に悪質な口コミに対しては、削除できることもあるので、こまめなチェックを心がけましょう。
2.風評被害のリスクもある
Googleビジネスプロフィールに口コミ投稿が可能なことは、反面、ネガティブな投稿が行われるリスクがあることを意味しています。中には悪意ある第三者により事実ではないクレームが書き込まれるなどして風評被害に遭う可能性もあります。たくさんの口コミが書かれているにもかかわらず、すべてが高評価の場合もユーザーから怪しまれるので、必ずしもネガティブな口コミが業績に悪影響を及ぼすとは限りませんが、このような口コミにも真摯に対応することで、接客の丁寧さをアピールすることが大切です。
MEOツールとは?
MEOツールとは、Googleマップから店舗情報や事業所情報へのアクセス状況を解析するツールです。たとえばアクセス数やキーワードの順位、どのようなキーワードで検索してきたのかなどを分析します。これらの分析結果は、グラフや表に表されて可視化され、視覚的にアクセス状況を把握することができます。
MEOツールの基本機能
MEOツールにはさまざまな機能が備わっていますが、ここでは主な基本機能について紹介します。
自動順位計測
MEOツールには、登録したキーワードごとに自店舗や他店舗の検索順位を計測して一覧表示する機能があります。順位で明らかになった競合店の商品・サービス内容を確認することで、自店舗の商品・サービス内容の見直しに生かすことなどができます。
レポーティング
MEOツールには、MEOの効果を集計・分析し、レポートとして出力する機能があります。このレポートで、チェーン店の状況を本部に報告する業務を効率化したり、MEOの効果を関係者間で共有したりすることができます。
分析/比較機能
MEOツールは、Googleビジネスプロフィールの内部分析や競合分析を行い、上位表示のための最適化の手がかりを得ることを支援します。
インサイトデータ
MEOツールは、過去のインサイトデータを確認し、MEOの効果や季節要因による変動、前年比などを定量的に確認することができます。
複数店舗のビジネスプロフィール管理・一括編集
MEOツールには複数店舗のビジネスプロフィールを一括で管理できる機能が備わっているものがあります。複数店舗のメニューや投稿、営業時間などを一括で編集することができます。
MEOツールの活用事例
MEOツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
結果がすぐに出はじめました
「結果がすぐに出始めた。そしてそれを確認できました。GMOに依頼してから、検索して来ました。というお客様が来店されました。普段利用されない客層のお客様が急に必要になった場合、検索して上位表示されている当店舗にご依頼頂き高額案件でした。幅広いお客様層に有効です」
https://www.itreview.jp/products/meo-dashboard/reviews/69050
▼利用サービス:MEO Dashboard byGMO
▼企業名:買取専門 大吉 シーマークスクエア店 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:その他サービス
ポータルサイトに登録するよりMEO対策の方が効果が高い
「WEBでの検索において、MEOは常に1ページ目の上段に表示される。また、地図も表示されるので、どのあたりにあるのかが分かりやすい。口コミも掲載されるので、初めて利用しようとする際の参考になる。検索ページの1ページ目の上段に名称が口コミ込みで記載されるというのは、非常に大きな宣伝効果となる。例えば、ポータルサイトに登録したとしても、検索ページに自社の名称が乗るわけではなく、ポータルサイトを開いてその中で何番目・・・といったような感じ。効果がないわけではないが、自社名が表示されるまでに2アクション以上必要となるので効果としてはMEO対策の方が高いと感じられる。
▼利用サービス:MEO Dashboard byGMO
▼企業名:K’sデンタルクリニック ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:歯医者
https://www.itreview.jp/products/meo-dashboard/reviews/75097
MEO対策の改善に繋がり役にたった
「順位表示の際にGoogeビジネスプロフィール内の何が影響して上位表示になっているのかが、簡単にわかって、MEO対策の改善に繋がり役にたった。Googleビジネスプロフィールの「運用代行」を行う上で、毎月の作業内容と順位レポートが簡単に提出できるのでとても便利です。しかも一度設定してしまうと毎月クライアント様に自動送信してくれるのもありがたいです」
▼利用サービス:Gyro-n MEO
▼企業名:株式会社FotoReise ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ITコンサルタント
https://www.itreview.jp/products/gyro-n-meo/reviews/88942
MEOツールの業界マップ
MEOのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
おすすめのMEOツール4選
実際に、MEOツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのMEOツールを紹介します。
(2021年12月23日時点のレビューが多い順に紹介しています)
MEO Dashboard byGMO
「MEO Dashboard」は、MEOの順位計測管理ツールです。キーワード別に毎日の自店舗や競合店舗の順位測定を行います。また、Googleビジネスプロフィールのインサイト情報を閲覧・分析できます。さらに、基本情報や投稿情報の更新管理なども行えます。
MEO Dashboard byGMOの製品情報・レビューを見る
MEOチェキ
「MEOチェキ」は、ローカルビジネスを行っている事業主様のMEOおけるGoogleビジネスプロフィールやYahoo!プレイスの順位計測・効果測定・運用効率化・分析などができます。
Knowledge Graph
「Knowledge Graph」は、店舗の位置や営業時間、キャンペーン、商品、メニュー、駐車場、専門家の資格情報など、検索される可能性のある企業やブランドに関するあらゆる公開情報を一元管理することで、公式情報の更新や配信を容易にします。
Canly
「Canly」は、Googleビジネスプロフィールや各SNSで使用している店舗アカウントを一括管理するクラウドシステムです。そのことで管理・運用コストを軽減し、データ分析により店舗運営上の課題を明らかにします。
ITreviewではその他のMEOツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。
まとめ
MEOはSEOに比べて取り組みやすいうえに効果が出やすいという特徴があります。適切なMEO対策を行えば、地域での知名度を高められ、継続的なビジネス成長にも期待がもてるでしょう。
BtoBビジネスを行う企業にとって、Googleビジネスプロフィールへの登録・活用はメリットの大きい施策です。特に増加しているモバイル端末ユーザーを取り込むためには、ぜひGoogleマップにおける自店舗や事業所の検索上位をめざしたいところです。
投稿 MEOとSEOの違いとは?対策のポイントからMEOツール4選を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 BtoBとは?BtoCとの違いやマーケティングのポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、BtoBとは何なのか、BtoCやCtoCとの違い、BtoBを展開している企業の事例、そしてマーケティング手法まで、BtoBに関する知識を網羅的に解説します。
BtoBとは?
BtoBは「Business to Business」の略で「B2B」とも表記され、企業と企業(官公庁なども含みます)が取引を行うビジネスモデルを示します。たとえば自動車メーカーが部品メーカーから部品を購入したり、スーパーなどの小売店が食品加工メーカーから食料品を仕入れたりすることもBtoBです。あるいは企業向けのソフトウェアを開発している企業からソフトウェアを購入することもBtoBです。さらに、物質としてのモノ以外にも、経営コンサルティングやクラウドサービスの売買もBtoBに含まれます。
つまり、企業が自社だけではまかなえないモノや解決できない課題のソリューションを売買する取引がBtoBです。
BtoBとBtoCの違い
BtoBの理解を深めるために、BtoCを比較しながら、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。
BtoCとは?
BtoBと比較されやすいビジネスモデルにBtoCがあります。
BtoCは「Business to Consumer」の略で、企業が個人に対して商品やサービスを提供するビジネスモデルです。BtoCの代表的な売り手は、スーパー、百貨店、ホームセンター、家電量販店、自動車ディーラー、アパレル専門店などの小売業や、レストランやカフェ、居酒屋などの飲食店です。ほかにもホテルやリラクゼーション、遊園地、病院などもBtoCです。
BtoCは、住宅や高級車のような例外もありますが、BtoBと比較すると個々の取引金額は低いことが特徴です。
BtoBとBtoCの違い
BtoBとBtoCの違いについて、4つのポイントで解説します。
◆電子商取引での比較
| BtoB | BtoC | |
| 市場規模 | 大(334.9挑円) | 小(19.3兆円) |
| 取引金額 | 大(数百万円~数億円) | 小(数百円から数十万円程度) |
| 取引の継続性 | 安定(継続性が高い) | 不安定(変動要素が多い) |
| 決済者 | 企業・組織 | 消費者個人 |
市場規模の大きさ
BtoBとBtoCは、市場の規模が異なります。経済産業省の調査によると、2020年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模が19.3兆円だったのに対し、BtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は334.9兆円と約17倍の違いがあります。
取引金額の大きさ
BtoBは1回の取引で動く金額がBtoCに比べて大きくなります。BtoCでは、1回の取引で動く金額は数百円から数十万円程度です。もちろん、例外的に車や住宅など、数百万円から数千万円の取引もありますが、決して日常的に行われる取引ではありません。
しかし、BtoBでは数百万円から数億円の取引が日常的に行われています。たとえば1つひとつは数百円単位の部品や材料でも、一度の取引で扱われる数が膨大なため金額も大きくなります。
取引の安定さ
BtoBはBtoCに比べて取引が継続的で量の変化も少なく安定しています。BtoCの場合は、たとえば服であれば、その季節の流行や気候、競合の状況、消費者の懐具合などにより売上は大きく変化します。また、消費者は常に同じ店から定期的に服を購入する傾向は小さく、継続的な取引が行われる可能性は小さくなります。
企業間の取引であるBtoBでは、購入者があらかじめ計画した予算を確保しているため、取引金額は比較的安定しています。また、取引相手を決めるまでに時間と労力がかかる一方で、一度取引が成立すれば継続的な取引が行われることが一般的です。
決裁者の違い
BtoBとBtoCでは購買の意思決定者が異なります。BtoCでの決裁者は消費者個人ですから、意思決定のプロセスは非常にシンプルです。商品やサービスによっては家族や友人たちなどと相談することもありますが、基本的には購入者1人の意思により購入が決定されます。たとえば服を買う、食品を買う、電化製品を買うなど、購入者は自分1人の意思で購入を決定します。住宅や車などは、購入を決める際に共有する家族の合意を得る必要がある場合もありますが、それでもプロセスはシンプルです。
一方、BtoBの場合は、購入者が企業であり、一度取引を始めると継続することが多く、さらに動く金額も大きくなり、その取引内容が企業の業績に影響を与えることから、購入決定者には大きな責任が生じます。そのため、新規の取引開始の意思決定を担当者の一存で行うことができず、稟議を起案して上層部の承認を得るなど、相応の手続きと時間が必要になります。
BtoB、BtoC以外のビジネスモデル
BtoB、BtoCと類似の表記がされるビジネスモデルについて紹介します。
例として具体的な企業名も紹介します。
BtoE(企業→従業員)
BtoEは「Business to Employee」の略で、企業が自社の従業員に対して製品やサービスを提供するビジネスモデルです。もっとも身近な例としては、社員食堂や社内コンビニ、社員寮、スポーツクラブの優待などがあります。近年ではオフィスでも気軽におやつを購入できる「オフィスグリコ」や、会社が一括購入できる「オフィスでヤクルト」など、他社が提供するサービスを導入する例もあります。
元来は福利厚生の意味が強く、社員の定着率や人材確保に結びつける目的が中心でしたが、近年では従業員も消費者であるとの考えから、自社商品やサービス、企業のファンになってもらい、評判が自発的に拡散されることを期待している企業も増えてきています。
BtoG(企業→行政)
BtoGは「Business to Government」の略で、企業が国や自治体などの公的機関を相手に行うビジネスモデルです。たとえば公共事業において、入札を通じて企業が参加する取引があります。また、省庁内のインターネットインフラの構築やホームページの制作運用も増えています。
近年では、ふるさと納税へのプラットフォーム提供や返礼品の選定など寄付者への業務を代行している楽天株式会社の例や、自治体向けの広告事業を展開している株式会社ホープの例があります。ホープ社は広報誌やホームページ、公務員の給与明細の裏面を広告媒体として活用するなどの事業を展開しています。
DtoC(メーカー→消費者)
DtoCは「Direct to Consumer」の略で、メーカーが消費者に直接販売するビジネスモデルです。DtoCは以前からもカタログ販売や通信販売として行われてきたビジネスモデルですが、インターネット上で決済できるようになったことで、多くの企業が自社ECサイトを立ち上げて参入するようになりました。
また、SNSを活用したマーケティング手法を駆使することも近年のDtoCの特徴です。DtoCでは、顧客からのフィードバックが直接得られるため、顧客のニーズを製品やサービスに迅速に反映させることができることや、中間マージンを省くことで利益率を高めることができます。
DtoCの成功ブランド例としては、ビジネスウェアのカスタムオーダーサービスのFABRIC TOKYO、メンズコスメのベンチャー企業であるバルクオム、クラフトチョコレートをカカオ豆の仕入から製造・販売まで一貫して行っているミニマル、植物由来のヘアケア・スキンケア・ボディケア用品などを製造販売しているボタニストなどがあります。
GtoC(行政→消費者)
GtoCは「Government to Consumer」の略で、国や自治体が企業や個人に向けてサービスを提供することです。2019年5月に「デジタルファースト法」が国会で可決されるとGtoCの注目度が高まりました。同法は行政手続きを電子申請に統一することをめざす法律だからです。
たとえば住民票の電子申請やワクチンパスポートの発行、e-Taxによる税金のオンライン申告、道路や水道の整備、学校や図書館の運営、公共施設の電子予約などが挙げられます。少子高齢化が進み、地方創生の機運が高まっている中、GtoCの需要は高まると考えられます。
CtoC(消費者→消費者)
CtoCは「Consumer to Consumer」の略で、個人間取引を示します。インターネット上でCtoCのプラットフォームが普及したことで、不特定の消費者同士が気軽に取引を行える環境が整いました。CtoCの例として、ヤフオク!のようなネットオークションやメルカリのようなフリーマーケットがあります。個人のスキルを売買するココナラなどもCtoCの一種といえます。
BtoBマーケティングとは?
BtoBでは高額な取引が多く、提案から受注までに数年といった長い期間を必要とする場合もあります。しかし、一度契約されるとリピートされることが多く、長期的かつ継続的な取引が行われる期待ができます。また、一度取引が始まった顧客からは、オプションの購入やアップセル商品・サービスが購入される確率も高くなります。
そのため、BtoBは顧客の母数が限られていますが、長期的かつ継続的な取引が見込めるため、より多くのリード獲得と既存顧客のフォローが重要になります。
BtoBマーケティングが注目されている理由
これまでBtoBを経営の軸にしてきた企業の多くはマーケティングの専門部門をもつことは少なく、営業部門などがマーケティングに近い機能を内包していることが一般的でした。しかし、市場がグローバル化し、需要が飽和状態となった成熟市場では、商品やサービス自体での差別化が難しくなったため、従来の顧客へのアプローチ方法では顧客の囲い込みと売上の両方を伸ばすことが難しくなってきました。
しかも、インターネットによる情報収集が容易になり、顧客自身が積極的に商品やサービスを比較検討することができるようになったことからも、従来の営業手法の有効性が薄れてきています。そこでマーケティングの重要性が増してきました。
顧客の情報収集の変化
顧客がインターネットで直接情報収集できる現在、営業が訪問時に持ち込む情報によって差別化することが困難になってきました。顧客はむしろ、Webサイトやメールマガジン、ホワイトペーパーなどから情報を得ることに利便性を感じるようになってきています。そのため、Webサイトやメールマガジン、ホワイトペーパーを使って顧客にアプローチできるマーケティング部門がリード(見込み顧客)と接触する機会を増やすことが重要になってきました。
サービスモデルの変化
クラウドサービスの普及に象徴されるように、ハード製品も含めてあらゆる商品やサービスがインターネット上のサービスと連携するようになりました。このことは、顧客は常に他社の商品やサービスに乗り換えることが容易な状況をつくり出しています。したがって、一度契約した顧客に対しても、継続的に有意義な情報を提供したりサポートを行ったりすることで、良好な関係を維持する必要があります。
購買プロセスの変化
インターネットが普及したことで、顧客の購買プロセスが変わってきています。顧客は、自社の課題解決のために能動的に情報収集を行うことが容易になってきました。そのため、従来型の営業であるプッシュ型アプローチよりも、マーケティングによるプル型のアプローチが有効になってきました。
BtoBマーケティングの特徴
ここではBtoBマーケティングの特徴を、BtoCと比較しながら解説します。
BtoBマーケティングの特徴(BtoCマーケティングとの比較)
| BtoB | BtoC | |
| 取引期間 | 長期的 | 短期的 |
| 売上 | 継続的 | 単発的 |
| 対象顧客 | 限定的 | 無制限 |
| 市場開拓 | 長期 | 短期 |
| 商材単価 | 高い | 低い |
1.長期的な取引が見込める
BtoCマーケティングでは、商品がヒットすれば一時的に売上が急伸しますが、市場が変化しやすいため、売上が安定しません。一方、BtoBマーケティングでは、一度契約した顧客とは長期にわたって安定した取引が継続される傾向が強いため、トータルでは高い収益性を見込めます。
2.継続的な売上が見込める
BtoCでは、顧客が個人の消費者であるため、1つの商品・サービスに対する取引量が小さく、また短期間で商品・サービスを乗り換えられてしまうことも頻繁に起こり得ます。一方、BtoBでは基本的に企業などの法人が顧客で計画的な予算をもとに取引が行われるため、1つの商品・サービスに対する取引量が大きく長期にわたって取引が継続されやすくなります。その結果、継続的な売上が見込めます。
3.対象顧客数が有限
BtoCの顧客としては訴求すべき対象は世界中の人々となり、ターゲット数を予測することは困難です。一方、BtoBの顧客は、主に特定の業界や規模に限られるため、ターゲットは数百~数千に絞られます。
4.新規開拓までに時間がかかる
BtoBでは、新規開拓に時間がかかります。見込み顧客に対して、自社を知ってもらうプロセスがあります。1件の新規顧客を獲得するためには、見込み顧客の開拓、アポ取り、訪問、情報収集、提案のプロセスを経なければなりません。このプロセスを通じて、自社や営業担当者への信頼を得る必要があります。また、意思決定や決裁の権限をもっている担当者にたどり着き、信頼関係を構築する必要があります。
また、企業や組織の課題解決や経済的合理性を検討するため、課題の認知から製品・サービスの導入までに、念入りな情報の精査と複数の意思決定者の調整など、購入するまでに要するプロセスが多く、期間も長くなります。
一方、BtoCでは顧客である消費者は自身の一存で商品・サービスの購入を即決することができます。そのため、BtoCにおける広告では、感情を刺激するコピーやイメージが使われることも多くあります。
5.商材の単価が大きいため、リスク管理の責任が大きい
BtoCの商材は、個人の消費者の予算で購入できる価格設定であるのに対して、BtoBの商材の価格は企業の予算で購入できる価格設定になっているため、金額が大きくなります。そのため、ときには単独の決裁者が決裁できる金額を超えることもあり、その場合は複数人が承認しなければ契約できません。大きな金額が動くため、販売担当者にとっても購入担当者にとっても、リスク管理の責任が大きくなります。
BtoBマーケティングのプロセス
そこで、BtoBマーケティングが必要になってきます。ここではBtoBマーケティングのプロセスについて解説します。
BtoBマーケティングは、営業に引き渡して契約にたどり着くまで、リードジェネレーションとリードナーチャリング、リードクオリフィケーションの3つのステップを踏みます。
リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)
BtoBマーケティングは新規リードの獲得から始まります。新規リードの獲得とは、自社の製品・サービスを購入する可能性のある企業の担当者情報を獲得することです。担当者の情報には、企業名、部署、連絡先などがあります。このように、見込み顧客の情報を獲得する活動をリードジェネレーションと呼びます。
リードジェネレーションは顧客情報を獲得するマーケティングで、以下のような活動があります。
・メディア露出(PR)
・オウンドメディア
・広告
・SEO
・SNS運用
・展示会
・各種イベント
リードジェネレーションでは見込み顧客を獲得するため、その後の営業活動の効率を高めることができます。このとき、見込み度が低い顧客を獲得した場合は、次のリードナーチャリングが有効になります。
リードナーチャリング(見込み顧客の育成)
リードを獲得した後は、リードナーチャリングと呼ばれる見込み顧客の育成段階に入ります。獲得した見込み顧客の自社製品・サービスに対する購買意欲を高めるために、顧客に有意義な情報を提供し続けることで継続的な接点をもち続けるようにします。
リードナーチャリングは、獲得した顧客の購買意欲を高めるために顧客を育成するマーケティングで、以下のような活動があります。
・メールマガジン
・オウンドメディア
・テレアポ
・訪問営業
・カンファレンス
・セミナー
・イベント
・SNS運用
リードクオリフィケーション(見込み顧客の選別)
リードクオリフィケーションとは、顕在化したリード(見込み顧客)から購入可能性の高い見込み顧客を選別することです。主に下記のような活動があります。
・シナリオ設計
・スコアリング
・データマネジメント
・履歴や属性の分析
このようなリードクオリフィケーションをすることによって、商品やサービスに関心がある確度の高い見込み顧客からコンタクトを取ることで、効率よく営業にバトンタッチし、商談・契約につなげることができます。
リードクオリフィケーションで成果を出すには、まず事前に「シナリオ設計」を考えておく必要があります。シナリオ設計とは、顧客が商品やサービスと接点を持ち、商談・契約に至るまでのリードジェネレーション、リードナーチャリングも含めた一連のプロセスの設計を指します。これら3つの活動は連動しているため、シナリオ設計を明確にしておかないと、リードクオリフィケーションでよい結果を出すことができません。
購入の可能性が高い見込み顧客を絞り込む方法としては、見込み顧客のアクションや属性などに点数をつける「スコアリング」という手法を用います。スコアリングでは、高い点数がついた見込み顧客を購入可能性が高い見込み顧客として考えます。
「データマネジメント」とは、データを適切に管理してあらゆる業務に活用するための知識です。データマネジメントではデータの正確性、データが最新情報で更新されているか、データの細かさが揃っているかが求められます。
最後は結果の良し悪しを含めた蓄積された履歴や属性のデータを分析しながら、精度を上げていきます。
BtoBマーケティング施策
BtoBのマーケティング方法について、リードジェネレーションとリードナーチャリングの主な施策について紹介します。
リードジェネレーション
メディア露出(PR)
新聞やテレビ、ラジオ、Webなどのメディアに取り上げられることがメディア露出です。メディア露出による効果は以下の通りです。
メディア露出(PR)の意義
- 広く認知される:メディア露出のもっとも大きな効果は広く認知されることです。しかも、これまで接点がなかった潜在顧客に認知される可能性が大きくなります。
- 信頼度が上がる:メディアに露出すると、「メディアが取り上げたほどだから信頼できるだろう」と受け止められやすくなります。また、メディアに取り上げられたことがSNSで拡散される可能性が高まります。
- 第三者の意見を知ることができる:メディアに取り上げられると、メディアを通じて第三者による評価を知ることができます。
- 社員の意欲が高まる:メディアで紹介されることで、社員が自社の製品・サービスに誇りをもち、仕事への意欲を高める可能性があります。
- 人材を集めやすくなる:メディアに取り上げられると、求職者への認知が高まることと、就職先としての信頼感が増すため、求職者に選ばれやすくなります。
オウンドメディア
近年では、顧客は製品・サービスの購入を検討する際に、まずWeb上から情報収集を行うので、当然、製品・サービスを提供している企業の公式サイトあるいはオウンドメディアをチェックしています。そのため、自社サイトで製品・サービスの掲載情報を充実させたり、ホワイトペーパーのダウンロードを可能にしたりしておくことは、大変重要な施策となります。
また、オウンドメディアはリードジェネレーションだけでなく、リードナーチャリングにおいても非常に重要な役割を果たします。オウンドメディアは認知獲得のみならず、リードの興味・関心を維持し、ファン化するためには欠かせない施策となっています。
広告
顧客が製品・サービスの情報をキャッチするのはWebメディアである可能性が高いため、インターネット上の広告対策が重要となります。具体的には以下のような広告の種類があります。
広告の種類
- リスティング広告:検索エンジンで特定のキーワードの検索が行われた際に、検索結果の画面上に表示されるテキスト形式の広告です。コンテンツのSEOよりも即効性があり、予算に合わせた柔軟な運用が行えることがメリットです。
- ディスプレイ広告:バナー広告とも呼ばれ、Webサイトの広告枠に表示されるテキストや画像、動画を利用した広告です。凝った作り込みができるためインパクトのある広告を表示することができますが、リスティング広告に比べてコンバージョン率は低くなる傾向があります。
- ターゲティング広告:自社サイトや広告から製品・サービスのランディングページ(LP)を訪れたユーザーをcookieで認識して、その後ユーザーが閲覧するさまざまなサイトで自社製品・サービスの広告を表示させる手法です。BtoBでは製品の検討期間が長期になりやすいため、接触回数を増やすことが有効だと考えられます。
- SNS広告:SNS広告とは、FacebookやTwitter、LINE、Instagramなどで配信される広告を示します。SNSでは利用者の属性情報が登録されているため、ターゲットを絞り込んだ訴求が行えます。
SEO
SEO(Search Engine Optimization)は自社のコンテンツサイトが、検索エンジンで上位表示されるために行う対策です。オーガニックな検索結果において上位表示されたサイトは閲覧される機会が増え、信頼度もユーザーのニーズとのマッチ度も高くなります。SEOとして重要なことは、良質なコンテンツを高頻度で継続的に発信を続けることと、検索エンジンに高評価されるコンテンツやサイトの作り込みを行うことです。ただし、SEOはリスティング広告のような即効性はないので、長期的なマーケティング戦略として取り組む必要があります。
SNS運用
最近では、多くの企業がTwitterやfacebook、InstagramなどSNSを運用するのが当たり前になっています。企業の情報収集の手段がオンライン化したことによって、SNSによる情報発信が極めて重要になっています。SNSマーケティングを行うことで得られる効果としては、潜在顧客の獲得、見込み顧客への定期的な情報提供、関係性構築などがあります。SNSで効果的なマーケティングを行えば、自社の商品やサービスを提供できる潜在的な顧客との接点をつくることができます。
展示会
展示会は、顧客ごとに訪問しなくても自社製品・サービスに興味をもった見込み顧客が自ら足を運んでくれるため、営業部員を増員しなくても効率よくコンバージョン数を増やすことができます。しかも、対面営業ができるだけでなく、自社製品を体験してもらえるメリットがあります。ただし、展示会を開催するためにはコストがかかる点に注意が必要です。また、来場者が同時に問いかけてくる場合に備えて、自社製品・サービスに詳しい人員を待機させておく必要があります。
各種イベント
自社が主催するセミナーやカンファレンスをはじめ、他社が主催する外部イベントへの協賛や出展、あるいは登壇することもBtoBマーケティングに効果があります。出展や登壇をすることで、もともと自社の製品・サービスを目的としていなかった潜在顧客にアピールできますし、営業担当者が参加していればその場で商談への足がかりを得られる可能性も高まります。また、自社の認知度が低かった場合は、集客力のある外部イベントに出展や登壇することは、認知度を上げる機会となります。
リードナーチャリング
メールマガジン
BtoBマーケティングではさまざまなインターネット上の訴求方法が生まれてきましたが、メールは今も有効なマーケティングツールです。その理由は、以下の通りです。
さまざまな情報を告知できる
メールは固定されたWebサイトと異なり、都度さまざまな情報を発信することができます。新製品情報やアップデート情報、イベント情報、お役立ち情報、ニュースなどです。
定期的なフォローが行える
BtoBにおいてはリードナーチャリングの期間も購入検討期間も長くなる傾向があります。そのため、自社から定期的にフォローすることにより、関係性を維持する必要があります。このためのツールとしてメールは有効です。
確度の高いリードの絞り込みに使える
リード(見込み顧客)の中には、まだ購入意欲が低い段階のリードもいれば、購入意欲が高まっている段階のリードもいます。このとき、メールで案内したURLのクリック率などをもとにリードを購入意欲の高さで分類することで、アプローチ方法を使い分けることができます。たとえば購入意欲が高まっているリードだけを絞り込めれば、無駄な架電を省くことができます。
テレアポ
テレアポはテレフォンアポイントメントの略で、顧客に電話で営業をかける手法です。顧客からのアプローチを待つのではなく、積極的に顧客獲得を行います。オンラインマーケティングが普及したことで、テレアポに古さを感じる人は増えていますが、すべての顧客が自らICTを駆使して能動的に情報収集をできているわけではありません。このような顧客にはテレアポは有効なアプローチ方法です。
テレアポはその段階ですぐに商談につながることはありませんので、長く話すことは逆効果です。手短にポイントを押さえたトークを行うべきです。一方、テレアポは直接顧客とコミュニケーションがとれるため、顧客の課題や状況をヒアリングすることで潜在層へのアプローチを可能にします。
ただしテレアポを行う人は、相手から冷たくあしらわれたり、理由を告げられずに切られてしまったりすることも少なくありません。あらかじめ気の持ち方や対処方法を準備しておく必要があります。
訪問営業
テレアポが取れたら訪問営業を行います。訪問営業は顧客と対面で課題やニーズを聞き出すことができる貴重な機会ですから、行き当たりばったりで営業するのではなく、事前に顧客の業界動向や顧客企業の現状などについて調べておきます。顧客の業界や企業について相手と共通の知識を持つことで信頼を得やすくなり、効率よく顧客のニーズや課題を引き出すことができます。
カンファレンス
カンファレンスでは、専門家や実践者が登壇して参加者と議論したりするため、自社が提供する製品やソリューションについて、より説得力のある訴求を行えます。しかもカンファレンスは明確なテーマを掲げて開催されているので、そのテーマに興味をもっていたり、関連する課題を抱えていたりする人が集まります。さらに、カンファレンスでは一度に多くの来場者を集めることができます。これらのことから、カンファレンスは継続的に新規リードを獲得できるマーケティング施策の1つであるといえます。
BtoBマーケティングを成功させるポイント
BtoBマーケティングを成功させるためには、いくつものポイントがあります。プロセスに沿って確認しておきましょう。
ニーズを把握する
商品・サービスを販売するためには、ニーズをもったターゲットにアプローチしなければなりません。しかし、潜在顧客の中には、自らのニーズに気づいていない場合があります。そのようなニーズを掘り起こすためにもマーケティングは必要です。BtoBには意思決定者が複数であることや検討期間が長いこと、印象や衝動ではなく経済的合理性がなければ購入しないなどの特徴があります。そのため、ターゲットのニーズを的確に把握する必要があります。BtoBはBtoCに比べて母数が小さいこともあり、ターゲットを取りこぼさないことが重要です。
差別化を図る
差別化とは、競合他社や同業他社に比べて、自社の製品・サービスがどのように優れているのかを具体化することです。差別化は、価格が安いことや単に異なっているということではなく、高くても競争優位になる差異があることでなければなりません。
信頼を得る
BtoBでは購入までの検討期間が長期間になることが一般的です。その間、Webサイトやメールマガジン、展示会、セミナーなどさまざまな検討機会が訪れ、他社の情報を得る機会も増えます。そのため、販売者は購入者との間に信頼関係を構築しておかなければ、ささいなきっかけで競合他社に顧客を奪われてしまう可能性があります。また、企業は経済的合理性により購入を決定しますが、その中には販売価格が信頼できる妥当性をもっていることや、アフターフォローがしっかり行われることに対する信頼感の強さも含まれます。
タイミングを狙う
BtoBにおいては、顧客のニーズが明らかになり、自社製品・サービスがそのニーズに応えられると判明しても、タイミングが合わなければ契約に至ることは難しい場合があります。BtoBでは取引金額が大きくなるため、顧客側で予算を確保できているかどうかを見極めることが重要になります。このタイミングを見極めないままで闇雲に売り込みをかけると、敬遠されてしまう可能性があります。
ロイヤルティを高める
顧客のロイヤルティ(信頼・愛着心)を高めるために、営業であれば足繁く通う必要がありましたが、BtoBマーケティングではICTツールを利用してより効率的に働きかけることができます。ロイヤルティが高い状態で商談に入るタイミングをつかむことができれば、商談は受注までスムーズに進む可能性が高まります。また、ロイヤルティが高ければ、契約後も長期的な利益を出し続けることができます。同時に、競合他社への乗り換えを防げる可能性も高まります。
キーマンを押さえる
BtoBでは企業を相手にするため、意思決定者であるキーマンにたどり着くことが重要です。キーマン以外の人にいくらアプローチしても、無駄な労力を費やしてしまいます。また、キーマンは1人とは限りません。競合製品のリサーチをしている人もキーマンですし、製品・サービスの導入を推進する担当者もキーマンです。そして、決裁権をもち最終的な意思決定を行う人もキーマンです。これらのキーマンを押さえて各人に有益な情報を提供し、効率的なマーケティングを行う必要があります。
営業と連携する
多くの企業ではマーケティング部門とインサイドセールス、フィールドセールス、そしてカスタマーサービスなどが十分な情報共有を行えず、連携もとれないまま活動していることがあります。情報共有が十分に行われていないと、マーケティング部が獲得してナーチャリング(育成)したリードが、営業によりクローズされたのか、アップセルされたのかといったフィードバックが行われず、確度の低いリードを獲得し続けてしまう可能性があります。BtoBマーケティングを成功させるためには、各部門との情報共有と連携が欠かせません。
BtoBマーケティングの支援ツール
実際に、BtoBマーケティングの支援ツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのBtoBマーケティングの支援ツールを紹介します。
(2022年1月5日時点のレビューが多い順に紹介しています)
ABM(アカウントベースドマーケティング)
ABMは、BtoB企業におけるマーケティング戦略の1つです。自社にとって有益な顧客を選び、それぞれに合わせた戦略を立てて利益を最大化することがABMの手法です。
FORCAS
「FORCAS」は150万社以上の企業データから、自社製品・サービスと相性のよい企業をリストアップするターゲティングを行うことで、確度の高い潜在顧客へのアプローチを効率化できるBtoB向けの顧客戦略プラットフォームです。
uSonar
「uSonar(ユーソナー)」は、さまざまな顧客情報を統合管理するクラウド型のツールです。DMPやMA、CRM、SFAなどと連携することでマーケティングのDX化を実現します。
BowNow
「BowNow」は機能を厳選して使いやすくしたMAツールです。特にリストアプローチの自動化により、コストパフォーマンスの高いマーケティングを行えます。
SFA
SFAとは、「営業支援システム」です。企業の営業活動における情報収集や業務プロセスを自動化することで、情報全般をデータ化して、蓄積・分析することができるシステムを指します。
SFAについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
SFAとは?CRMとの違いや導入のメリット・おすすめツール5選
Salesforce Sales Cloud
「Salesforce Sales Cloud」は外出先でも素早く顧客にアプローチ。AIが組み込まれたCRMは、営業プロセスにあわせて柔軟にカスタマイズでき、あらゆる局面でセールスをサポートできます。営業管理、サポート状況、マーケティングデータを1カ所に集約。営業にまつわるプロセスをまとめることで、どのチャネルからでも、すべてを関連づけて観察できます。
Salesforce Sales Cloudの製品情報・レビューを観る
Senses
「Senses」は営業支援サービスで、蓄積された営業に関わるあらゆる情報を効率的に管理し、現場の営業担当者が効果的な営業活動を行えるように支援する高度なAIエンジンを搭載しています。
Knowledge Suite
「Knowledge Suite」は、統合ビジネスアプリケーションのクラウドサービスで、集計・分析ツールから問い合わせ管理、SFA、CRM、グループウェア、そして他のシステムとの連携機能などを搭載しています。
MA(マーケティングオートメーション)
MAは、収益向上を目的としてマーケティング活動を自動化するツールです。MAを導入することで、見込み顧客の興味関心に合わせたコミュニケーションが可能となります。
MAについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
MA(マーケティングオートメーション)とは?おすすめMAツール7選まで完全網羅
SHANON MARKETING PLATFORM
「SHANON MARKETING PLATFORM」はMAツールで、新規リードの獲得からナーチャリング、行動履歴の管理などマーケティング業務に必要な作業を自動化します。
SHANON MARKETING PLATFORMの製品情報・レビューを観る
Salesforce Pardot
「Salesforce Pardot」はクラウド型のMAで、マーケティング活動とセールス活動を連携し、さらにSalesforceが提供するさまざまなツールとも連携することで、営業の効率化と成果の最大化を支援します。
Salesforce Pardotの製品情報・レビューを観る
Adobe Marketo Engage
「Aobe Marketo Engage」は、世界39カ国以上の企業で採用されているMAです。BtoB、BtoCを問わずあらゆる規模と業種において、ユーザーの1人ひとりと適切なタイミングや内容、手段でコミュニケーションをとることができます。
Adobe Marketo Engageの製品情報・レビューを観る
CRM
CRMは顧客との関係性、コミュニケーションを管理し、自社の従業員と顧客との関係を一元的に把握できるようにするツールです。情報の一元化によって顧客をより深く理解することで、営業活動の向上、サービス、マーケティング、経営戦略などに生かすことができます。
CRMについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
Salesforce Sales Cloud
「Salesforce Sales Cloud」はSFAとCRMが統合されたシステムで、新規顧客の発掘からナーチャリング、そして早期受注を実現するためにあらゆる機能が備わっています。
Salesforce Sales Cloudの製品情報・レビューを観る
Senses
「Senses」は、営業管理や分析などの機能の使いやすさにこだわりがあります。蓄積された過去の営業情報から現在の営業活動に役に立つノウハウを活用できるよう、高度なAIエンジンを兼ね備え、導入企業は不動産や人材、広告代理店など多岐にわたります。
Zendesk
「Zendesk」は、メールやWebフォーム、ソーシャルメディアなどのさまざまなチャネルからの問い合わせを一元管理し、ワークフローのオートメーションやサポートのパフォーマンス測定などを行えるヘルプデスクソフトウェアです。
メールマーケティング
メールマーケティングは、メールを活用したマーケティング全般を指します。特にBtoB企業では、SNSが普及した今日もメールを中心にコミュニケーションが行われるので効果的な方法といえます。
Twilio SendGrid
「Twilio SendGrid」は、クラウド型のメール配信サービスです。開封やクリックなどの配信状況のトレースやメールが届かなかったバウンスの自動処理、配信停止管理などを効率的に行え、他システムと連携するためのAPIも豊富です。
MailChimp
「MailChimp」は、直感的な操作でメールマガジンを配信できるツールです。HTMLメールもエディターで簡単に作成でき、開封率やクリック率などのレポート機能も充実しています。
配配メール
配配メールは、メールマガジンやステップメールを配信できるメールマーケティングツールです。直感的な操作と必要最低限の機能、専任スタッフの手厚いサポートが特徴です。
Webサイト制作
Webサイト制作とは、ホームページやオウンドメディアなどのWebサイトの制作を指します。1人でも始められますが、ページのデザイン、画像の作成、サイト制作の進行管理など、分業して制作を行うことが多いです。
Adobe XD
「Adobe XD」は、Webサイトやモバイルアプリのデザインを支援するUX/UIソリューションで、共同編集が可能なためチームによる作業を効率化できます。Adobe CC・Creative Cloudと連携ができ、直感的な操作が可能です。
Dreamweaver
「Dreamweaver」は、Webサイトのデザインからコーディング、ファイル管理を視覚的に行えるソフトです。
Sketch
「Sketch」は、WebサイトやアプリのUIデザインツールです。機能の豊富さに加え、プラグインでカスタマイズすることもできます。エンジニアとの連携を効率化するコラボレーションツールやプロトタイプ作成ツールにも対応しています。
CMS
CMSは、Webサイトのコンテンツを構成するテキストや画像、デザイン・レイアウト情報などを一元的に保存・管理するシステムのことです。CMSが必要に応じて情報を取り出して、Webページを自動的に生成してくれます。
CMSについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
CMSとは?メリットや導入ポイント、活用事例、おすすめツール5選を紹介
WordPress
「WordPress」はWebサイトを構築・運営するためのオープンソースのCMSです。個人のサイトから企業のサイト、Webマガジンやニュースサイトまで幅広く利用されています。また、デザインテンプレートやプラグインも豊富です。
おりこうブログ
「おりこうブログ」は、Webサイトの作成やアクセス解析、メッセージ配信、カタログ作成などのツールが豊富なCMSです。
Movable Type
「Movable Type」は、安全で効率的なWebサイト運用を可能にするCMSプラットフォームです。豊富な機能で、大規模なコーポレートサイト、メディアサイトの構築・運用が可能です。
Web接客ツール
Web接客ツールは、Webサイトに訪れたユーザーに対して、その属性や閲覧履歴などといった情報をもとに、Webページ上で適切な対応・案内を行うツールのことをいいます。顧客データベースを参照しながら、個々人に最適なコンテンツ提供やサポートを実施するCXプラットフォームへの発展も進んでいます。
ChatPlus
「ChatPlus」は自由度が高いデザイン機能やチャットボットの挙動設定の多さが特徴です。すべてのAPIが開放されていることで、訪問者情報から行動属性まであらゆるデータを送受信できるため、柔軟なシステム連携を実現します。
Flipdesk
「Flipdesk」はチャット対応やクーポン発行、お知らせ配信など、訪問者の状況に自動的に対応することでリアル店舗のような接客をネットショップで実現します。
KARTE
「KARTE」はCX(顧客体験)プラットフォームです。Webサイトやスマートフォンアプリを利用している顧客1人ひとりの行動データを可視化し、適切なタイミングで適切なアクションを行えます。
SEOツール
SEOツールとは、特定キーワードにおける検索エンジンの表示順位を上げるための支援ツールです。SEOツールは主に適切なキーワードの選定やコンテンツの最適化、キーワードごとにおける競合サイトとの順位比較などの機能をもちます。
Google Search Console
「Google Search Console」は、Googleでの検索におけるインプレッション数やクリック数、掲載順位などを計測できるSEOツールです。
Google Search Consoleの製品情報・レビューを観る
SEARCH WRITE
「SEARCH WRITE」は誰でもSEOのPDCAを回せるように支援するツールです。CV獲得に貢献するキーワードがわかったり、キーワードごとに検索上位の記事見出しを自動で取得して上位表示される記事の書き方を示したりします。
Keywordmap
「Keywordmap」は、SEOのための競合分析や広告調査、コンテンツ作成などに活用できる日本語ビッグデータプラットフォームです。
ヒートマップ
ヒートマップは、Webサイト上でのユーザーの行動をサーモグラフィによる温度分布のように色の濃淡で可視化して表す分析手法です。Web解析では、マウスの動きを追跡し、そのマウスのログからヒートマップを作り出しています。
EmmaTools
「EmmaTools」はSEOライティングツールです。対策キーワードで上位表示させるための関連キーワードを提案したり、コンテンツ内で不足しているテーマを知らせたりなどSEO観点から改善点を明らかにします。
Ptengine
「Ptengine」はサイトに1つのタグを設置するだけで、データ収集からインサイト取得、施策実行そして効果の検証を行えるサイト運営プラットフォームです。
User Insight
「User Insight」は、Webサイトの訪問者がコンテンツのどこを見ているかやどこをクリックしているかを可視化してUI/UXの改善に役立たせるヒートマップツールです。トラフィック情報からユーザーの属性を推測することも可能です。
まとめ
本記事では、BtoBとはどのようなビジネスモデルか、BtoBマーケティングとはどのような施策かについて解説しました。BtoBは取引規模が大きくなり継続性が高くなる傾向があります。また、BtoCに比べてサイクルの短い流行の影響を受けにくいのが特徴です。
一方で取引開始までの意思決定プロセスが複雑で長期化しやすい傾向があるため、BtoBに適したマーケティングが必要になります。BtoBをすでに行っているが、より成果を出したい、あるいはこれから事業を立ち上げようとしているという方は、上記の特徴を踏まえたうえで、戦略を立てる必要があります。
投稿 BtoBとは?BtoCとの違いやマーケティングのポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 マーケティングオートメーション(MA)とは?おすすめツール7選をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、今後MAの導入を考えている方にもわかりやすく、MAの基礎からメリット・デメリット、導入ポイントやおすすめのMAツールまで、MAについて詳しく解説します。
MA(マーケティングオートメーション)とは?
MA(マーケティングオートメーション)とは、マーケティング活動を自動化することにより、見込み顧客を育成するツールやソフトのことをいいます。株式会社矢野経済研究所による「DMP/MA市場に関する調査」によると、MAのマーケット規模は年々拡大を続け、2021年のDMP/MA市場規模は600億円となることが見込まれています。
インターネットの普及により、さまざまな情報に溢れた現在は、顧客の興味はより複雑化し、ニーズの抽出が困難な時代となっています。そんな中、MAは最良のコンテンツの提供や営業による最適なアプローチを行うために導入・活用されています。MAが果たす役割には、主に以下の4つが挙げられます。
- 情報の収集
マーケティング戦略はユーザー情報の収集からスタートします。メールやWebサイト・動画やSNSなどバリエーションに富んだ情報の中、顧客のライフスタイルの多様化に合わせ、マーケティング戦略も細部まで丁寧な対応が求められます。
- 情報の蓄積
顧客から収集した情報は、それに相応しい方法で蓄積を行います。
- 見込み顧客の育成
ユーザー情報の収集・蓄積後、見込み顧客の育成を行います。近年注目されているOne to Oneコミュニケーションを実現するためには、見込み顧客のリスト登録や招待メールの配信・テレアポなどの業務が欠かせません。見込み顧客の求める情報を最適なタイミングで提供できれば、購買意欲を育てることにもつながります。
- マーケティング戦略の分析
メールの開封や未開封・自社サイトへの訪問など、個々の顧客のオンラインアクションを追跡することで、顧客行動などの情報を一元化することができます。一元化した情報は、マーケティング戦略や収益過程などの効果測定にも利用できます。そのため、PDCAサイクルもスピーディーに回すことが可能になります。
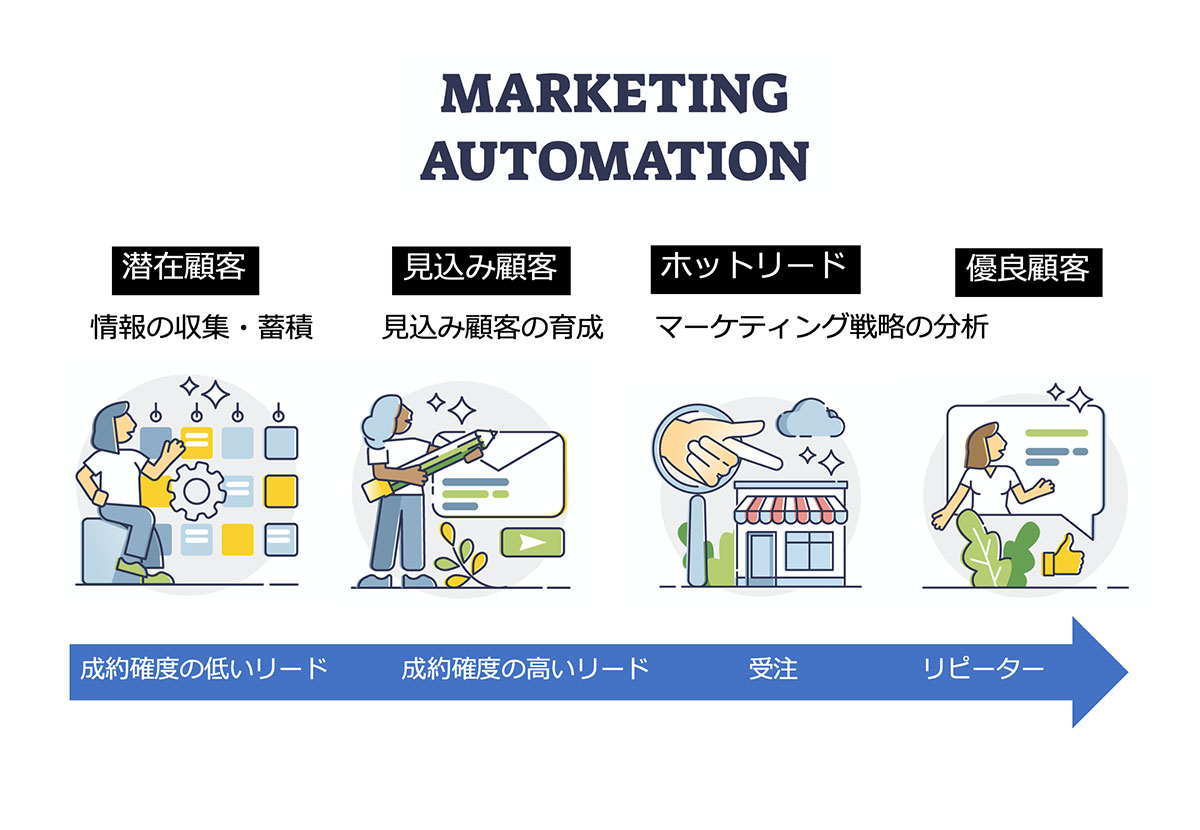
また、MAツールはBtoBだけでなく、BtoCでも利用できるように設計されています。BtoBのツールでは、名刺管理やセミナー・イベントなどの受付管理と連携できるものが増加しています。BtoCルールは、見込み顧客の一元化が可能であり、顧客優先のマーケティングを支援します。
MAツールの基本機能
MAを導入・活用により得られるメリットは数多くあります。BtoB・BtoC問わず、MAを導入する企業は増加傾向にありますが、システムを十分に扱えていないと感じるケースも出てくるでしょう。見込み顧客のアクションログに対し、最適なタイミングでマーケティング戦略を行うために必要な機能について紹介します。
リード(見込み顧客)管理機能
名刺やデータの履歴・資料請求や取引履歴などを一元管理できる機能のことをいいます。情報を得たルートがまったく異なることから、個々に管理されやすい情報も、MAを導入・活用することでリード(見込み顧客)の特性を生かしながらアプローチすることが可能となります。
スコアリング機能
見込み顧客が受注までに至る確度を計算することをスコアリングといい、割り出されたスコアは高い見込み顧客であるかどうかの可能性を知る指標になります。これを自動計算する仕組みを、スコアリング機能といいます。ツールであらかじめ定められた規定に基づき点数が割り出されます。
メール作成機能
メールを作成する機能のことをいいます。テンプレートも豊富に用意されているツールが多くメールの作成が苦手な社員であっても、シンプルでわかりやすく扱いやすい機能となっています。
メール配信機能
メールを配信する機能のことをいいます。メール配信機能は、リード管理機能やシナリオ作成機能などと結びつけて活用することができます。そのため、顧客の特徴や状態に応じた配信が可能です。
シナリオ作成機能
リードの行動を予測したうえでそのアクションに対し、実行する行動作成機能のことをいいます。顧客と自社とをつなぐ信頼関係構築のために必要な機能です。あらかじめシナリオを作成しておくと、メールの配信や電子クーポンの配布というような誘導の一部分をMAが自動で行います。
LP作成機能
広告をクリックしたユーザーが見るページのことを、LP(ランディングページ)といいます。自社の商品やサービスを紹介することにより、ユーザーのアクションを促すために必要な機能です。LP作成を通して得たユーザー情報はリード情報として記録され、見込み顧客の育成に活用されます。
フォーム作成機能
自社のWebサイトへの問い合わせや、資料請求をする場合に名前や電話番号・メールアドレスなどの個人情報を入力する欄のことをいいます。自社とユーザーが出会う契機となることから、重要な機能であるといえます。フォーム作成で得たユーザー情報もリード情報として記録され、その後の育成に活用されます。
レポート・分析機能
正確な誘導を行い、受注につなげて顧客を増加させるために必要となる機能のことをいいます。レポート・分析機能でアクセス解析を活用ことにより、顧客の企業規模や業界まで幅広い情報を把握することができます。問題なく戦略を実行するためにも、顧客情報を詳細まで知ることはとても大切です。
メディア連携機能
TwitterやInstagramなどのSNSと連携を行う機能のことをいいます。目的とするユーザーにアプローチする場合にも、この機能を活用することが効果的です。さまざまなメディアを一元管理し、どのような顧客がどれほどクリックしているなどの分析を行うことができます。
システム連携(SFA・CRMなど)機能
SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)などのシステムと連携可能な機能のことをいいます。マーケティング部門の育成した顧客を、SFAを通して営業部門がチェックするような活用法になります。顧客情報や案件情報から結果としてのマーケティング活動評価に結びつけられる仕組みも導入されています。
MAツールを導入するメリットとデメリット
MAの導入・活用により、営業活動の最適化や小規模でも効果を生むマーケティング戦略が可能となります。MAのメリットや効果を最大限に引き出すためには、オペレーションや明確な目的をもとにした設計を行うことが大変重要になります。
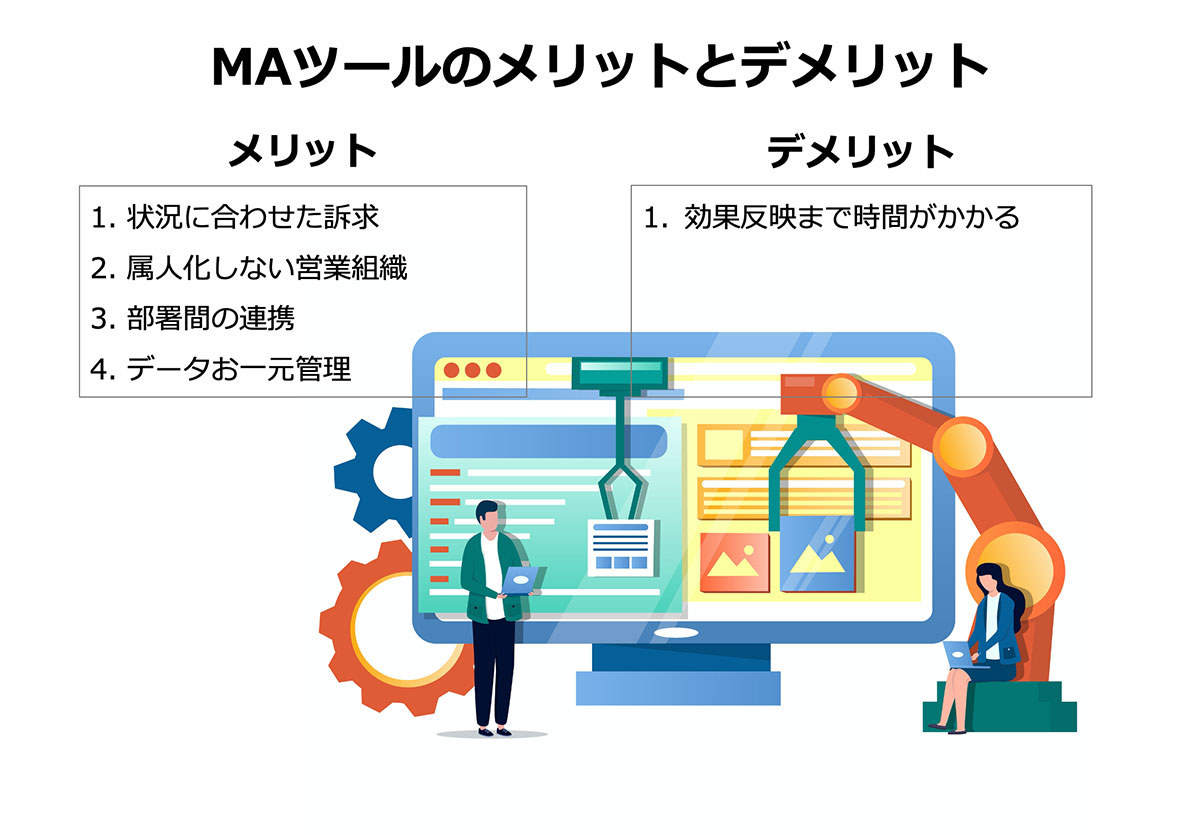
MAを導入するメリット
・見込み顧客の状況に合わせた訴求ができる
MAでは見込み顧客の行動履歴をもとに、自動で状況に応じたアプローチができます。シナリオ設定をして見込み顧客の状況に合わせた訴求をすることで、属人的な手間を省くことが可能です。
すべての問い合わせ客やメルマガ購読者が必ずしも自社製品に興味をもっているとは限りません。見込み顧客は毎日膨大な量の情報を受け取っているため、適切なタイミングで適切な情報を届ける必要性があります。しかし、マーケターや営業が個別に状況を把握し、その状況に合ったアプローチをし、コミュニケーションをとるのは困難です。
見込み顧客のケアを人的作業で行うことには限界がありますが、放置すれば他社の顧客となる可能性もあります。MAを導入・活用すると、見込み顧客の情報を一元化してメール配信やコンテンツ提供などから連絡をとり続けることができます。このような方法により、見込み顧客の流出を防ぐことができます。
MAで見込み顧客の行動変容が把握できれば、製品・サービスに興味があることや、どういった情報を求めているのかまでがわかります。見込み顧客の状況に合わせた訴求により、取りこぼしのないようにアプローチするためにも、MAはとても有効な手段だといえます。
・属人化しない営業組織をつくれる
アウトバウンドが前提だった時代の営業は、属人的な側面がとても強かったといえます。営業の受注率の高さは、各々の性格や能力、経験によって左右されていました。しかし、欲しい情報や商品がオンライン上で簡単に購入できる現代では、営業が直接売り込むアウトバウンドの機会が減少しています。MAはオンライン上で接点のある見込み顧客に持続的コミュニケーションをとることができるため、インバウンドでスムーズなコミュニケーションを具現化できます。
MAを導入してマーケティング部隊が見込み顧客のフィルタリング(選別)とナーチャリング(育成)を終えたところで営業部に見込み顧客をパスすれば、営業の能力に依存せずに営業組織全体の生産性を上げることができます。
また、MAでは経験や勘に頼らずに客観的な判断軸でアプローチをすることができます。“オートメーション”の名の通り“自動化”を推進することで、情報共有が容易になり、属人化した営業活動に頼ることなく効率的なアプローチが可能になります。
・営業とマーケティングで連携しやすくなる
営業は顕在化した確度が高い見込み顧客へのアプローチに注力しがちなので、潜在ニーズ層へのアプローチはどうしても後回しになってしまいます。しかし、それでは潜在的な顧客を逃してしまうリスクもあります。
MAを導入するとマーケティング施策の履歴やWebサイトの閲覧状況などがまとまって管理されるため、マーケティングと営業の間で、状況の共有がよりスムーズにできるようになります。
見込み顧客の検討段階がわからないと、的外れなタイミングや内容でアプローチをしてしまう可能性が高いですが、MAを使って見込み顧客の行動ログに合わせた情報を提供することで、“かゆいところに手が届く”アプローチが可能になります。つまり、マーケティングと営業が連携することで、ニーズが顕在化していない見込み顧客へのアプローチも放置せずに効率よく行うことができるようになるのです。
・見込み顧客のデータを一元管理できる
多くの施策を実施し、管理する情報が増えると、見込み顧客の情報の管理がバラバラになりがちです。MAを使うことで、見込み顧客のデータを一元管理することができます。MAにはデータ分析機能があり、見込み顧客ごとに、資料のダウンロード履歴やセミナーの参加状況、Webサイトの閲覧状況などのデータから戦略の効果を測定することもできます。受注確度の高い見込み顧客を抽出することで、より生産的なアプローチも可能となります。
MAツールを導入するデメリット
・効果反映まである程度の時間が必要
MA導入後は繰り返しPDCAを実行し、戦略を練り続けることが必要となります。またMAを活用するにはコンテンツの制作費やメール配信のための設計により出費が増える可能性があります。そのため、短期的な視野に捉われることなく、時間をかけて効果を上げていくことが重要です。
MAとSFA・CRMの違い
MAのほかに注目を集めるツールとして、SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)があります。MAがマーケティング活動を自動化するツールであるのに対し、SFAは営業担当者を支援するツールです。またCRMは、顧客との信頼関係構築のためのツールとなっています。これら3つのツールにそれぞれ異なる点があるように、得意とする分野にも以下のプロセスにおいて明確な違いがあります。
MA・・・リードの育成や選定
SFA・・・商談から契約に至る過程
CRM・・・優良顧客との関係維持・改善
一連のフローを通じて、プロセスごとに必要となる取り組みを支援するのが、これら3つのツールの特徴です。自社の求めるツールの選別には、以下の課題解決法を知る必要があります。
| MAツール | 集客への迷いがあるケースには、リードの育成や選定を行いたい場合に最適 |
| SFAツール | 営業知識の蓄積不足のケースでは、商談情報の共有と業務効率化に有益 |
| CRMツール | 優良顧客の維持・改善不足のケースには、優良顧客の育成に効果的 |
MAツールの活用事例
MAツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
円滑なコミュニケーションと生産性の向上を実現
「現状の弊社の管理項目との突き合わせや提案など親身になって調整や提案をしていただきスムーズな導入に結び付いた。資料請求を処理する業務部署と、その後のアプローチをかける営業部とのやりとりがシームレスに行えています」
https://www.itreview.jp/products/saaske-lead/reviews/54121
▼利用サービス:サスケLead
▼企業名:株日本ビスカ株式会社 ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:デザイン・製作
セミナーの参加率が増加、顧客の好みも可視化
「当社の強さであった営業マン主導の顧客関係維持は、移動制限、実の営業が制限されるコロナ下では、属人化されたものであると問題視されました。シャノンマーケティングプラットフォームを使い、属人化した顧客情報をSMPを使い組織的に共有し、顧客主導の顧客関係維持に変革しました。これまで、製品紹介セミナーの案内も営業マンが主導でしたが、SMPを活用して行いました。結果として、セミナーの参加率が増加、顧客の好みも可視化されました。より顧客が求めるニーズの把握にもつながり、増収増益にもつながる事になりました」
https://www.itreview.jp/products/shanon-marketing-platform/reviews/71780
▼利用サービス:HANON MARKETING PLATFORM
▼企業名:イスクラ産業株式会社 ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:医薬品
マーケティングに必要な全てを達成可能
「2020年のMarketo Masterです。レベニューモデルを構築し実施できるツールはMarketo Engageだけです。顧客の獲得から、育成、インサイドセールスにパスをして、商談化、営業がクローズした受注情報までも取り込むことで、一気通貫でマーケティングに必要な情報を管理、運営、可視化まですることができるツール。メールの送信、イベントの管理をする”だけ”のマーケティングオートメーションではなく、SalesforceなどのCRMともシームレスに連携をすることができるので、全ての情報をMarketoの中で管理し、マーケティング活動を行うことができるのがMarketo Engageの最大の価値だと考えています。売上を最大化するために必要なマーケティングを実施することができるのは、Marketo Engageがあってこそです」
https://www.itreview.jp/products/marketo/reviews/50335
▼利用サービス:Adobe Marketo Engage
▼企業名:株式会社エイトレッド ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
MA初心者にもおすすめ!
「ステップメールやシナリオメール機能を使って、営業がフォローしきれない顧客のフォローを実施しています。また、シナリオメール配信の途中でHOTになった顧客は営業にパスできるように自動通知メールを送っています。結果的に、放置してしまう顧客がいなくなったことで機会損失が減り、逆に確度の高い顧客だけを営業にパスできるようになったので営業の無駄アポも減りました。副次的な効果かもしれませんが、営業担当と企画担当の関係性も良くなったように感じます」
https://www.itreview.jp/products/kairos3/reviews/49936
▼利用サービス:Kairos3
▼企業名:株式会社リクルート ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:人材
業務効率化や効果の数値化に寄与「カスタマーリングス」
「メルマガの到達率が上がりました。今まで何らかのエラーで配信ができなかったお客様も自動で届くまでアプローチしてくれるので、エラーで配信できなかった人の数が減りました。分析データは、条件の掛け合わせがたくさんできるので、複雑なデータ分析が効率よく簡単に抽出できるようになり、楽になりました」
https://www.itreview.jp/products/customer-rings/reviews/30112
▼利用サービス:カスタマーリングス
▼企業名:関西鉄工株式会社 ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:50-100人未満
MAツール導入のポイント
近年、多くのMAツールが登場していますが、機能や操作性・費用面は個々のツールによってまったく異なります。ツールを導入する際に大切なことは、他社製品との比較を行ったうえで自社に合う最良のMAツールを選ぶことです。導入後問題なく活用していくためには、以下の8つのポイントを押さえておきましょう。
導入目的を明確に
MAツール導入前のプロセスとして、どういう機能のある製品でどういったマーケティング戦略を実現したいのか明確にしておきましょう。MAツールは機能が多岐にわたるものから限定的なものまで幅広くあります。自社の導入目的を定め、必要な機能と不必要な機能とに分類を行い、選定を進めていきます。
自社のリード情報をチェック
ナーチャリングの対象であるリード(見込み顧客)を自社でどれほど保有しているかということも、導入前に把握しておくべき情報です。また自社と顧客との関係の確認も、顧客ごとに適切な戦略実行のために必要です。関係の確認をすることによって、導入後の誘導設計を行いやすくなります。
マーケティング戦略の構築
導入前のプロセスとして顧客にどういう課題があり、解決のためにどういったコンテンツが必要であるのかなどの戦略を組み立てるための指標を出します。しかし、目的を設定して戦略を実行しても、必ずしもすぐに効果が反映されるとは限りません。そのため、常に先の状況を想定しながら次なる戦略を立てる必要があります。
確実に自社に合う製品を選定
自社に最適なMAツールを選ぶことは、導入前にさまざまな対策を講じるうえでも大切なことです。自社の目的から逸れることなく、他社ツールとの比較を上手に行いながら選定をすることを心がけましょう。
課題解決に必要な機能の確認
自社の抱える課題を解消してくれるツールを導入することは必然ですが、導入前に想定していた施策があとで変更される可能性も否定できません。そうしたこともあらかじめ想定して、必要になりそうな機能をしっかり考えたうえでツールを導入することも視野に入れておきましょう。
運用プロセスの調整
導入後も順調にMAツールを運用してくためにも専任の担当者を定めておきましょう。効果は顧客の求めるニーズによっても変化するので、動向を常に把握し確認や変更を繰り返すことが大切です。戦略の促進とより円滑なコミュニケーションには、PDCAサイクルを上手に活用する担当者の存在が必要不可欠です。
他部門との緊密な連携
MAツールを導入・活用した結果として、受注率の増加に成功していることが求められます。そのため、営業部門との強固な連携が欠かせません。また具体的な連携内容を、マーケティング部門で確認可能な仕組みを整えることも重要です。社内で積極的に情報共有ができれば、課題の解決や改善にも寄与します。
SFA・CRMといった他ツールとの連携
SFAやCRMなどのほかのツールと連携を行うことにより、企業のデータ管理をより最適なものにできます。また高い精度の効果測定や検証も可能となるだけでなく、部門ごとの社員のスキルを高めることにもつながります。マーケティング部門と営業部門の連携不足と思われる企業は、SFA・CRMなどとの連携をすることを検討しましょう。
MAツールの業界マップ
MAツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
おすすめのMAツール7選
実際にMAツールを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのMAツールを紹介します。
(2021年12月4日時点のレビューが多い順に紹介しています)
SHANON MARKETING PLATFORM
あらゆる業務の効率化・自動化・データ管理から、スムーズな情報伝達を可能にするクラウドアプリケーションです。目的や工程を明確にしたマーケティング活動のサポートや、セミナー・イベント運営の拡張によりリードの獲得に向けるバーチャルイベント等、幅広い業務をサポートしています。
SHANON MARKETING PLATFORMの製品情報・レビューを見る
Adobe Marketo Engage
デジタルからアナログまで最適な瞬間にメッセージを届けるマーケティングエンゲージメントプラットフォームです。BtoBやBtoC・業種問わず、国内外に5000社以上の導入実績をもつマーケタ―に向けたプラットフォームを提供しています。
Adobe Marketo Engageの製品情報・レビューを見る
Kairo3
扱いやすさに焦点を置いたクラウド型MAサービスです。営業とマーケティングを1つに結びつけることでニーズを把握し、高品質な営業活動を支援します。豊富なサポート体制と、リーズナブルな費用で利用できます。
ホットプロファイル
名刺管理と見込み顧客発掘・SFAを融合させることで生産性や売上の向上を目的としたクラウド型の営業サポートツールです。データベースを中心として営業戦略と顧客のリアクションを一元化し、リアルタイムで情報を可視化できることでスムーズな営業戦略を具現化します。
カスタマーリングス
顧客データを分析し、メール配信や郵送DMなどの方法での接客を実現するツールです。ECサイトの在庫情報と連携を行うと、在庫の少なくなったタイミングで通知できます。ある程度検討期間の長い業界を中心にさまざまな国内企業で活用されています。
BowNow
シンプルで使いやすくローコスト、リストアプローチ業務の自動化が可能なツールです。高いコストパフォーマンスを発揮できるマーケティング戦略を立てられます。マーケターと営業の両者が共通認識を持ち、最適なタイミングでピンポイントに見込み客にアプローチをすることで、効率的にマーケティング施策の成果を出すことができます。
サスケLead
見込み客を管理・育成するためのクラウドサービスです。リードデータを一元管理できるだけでなく、名刺や書面資料のデータ化やパソコンからの電話受発信可能なCTI機能などのほか、クリック率やアクセス解析といったシステムも備えています。多くの企業に導入・活用されています。
ITreviewではその他のMAツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
MA(マーケティングオートメーション)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧
まとめ
MAツールを導入・活用するときには、当然のことながらコンプライアンスを遵守しながら活用する必要があります。システムを適切に扱うことさえできれば、会社の利益にもつながっていきます。またスムーズな運用を実現するためには、導入前から慎重に施策を練ることが重要です。
MAツールを運用する際には、運用コストに対し結果が伴っていることも重要です。そのためには人的リソースや将来的なビジョンまで見通したうえで、現実的な運用計画を構築しましょう。他社製品との十分な比較も行いながら、自社に最適なツールを選ぶことが必要となります。
投稿 マーケティングオートメーション(MA)とは?おすすめツール7選をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 CMSとは?メリットや導入ポイント、活用事例、おすすめツール5選を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>かつてWebサイトを作成・管理・運用するためには専門知識が必要で、コストも時間もかかりうまくいかないケースがよく見られました。しかし、効率よく運用できるCMSツールの導入により、Webサイトをとりまく環境に大きな変化が起きました。予算の少ない中小企業や個人でも気軽に情報を発信できるようになったのです。
CMSとは?
「CMSとはいったい何なのか?」「CMSを活用するとどんなことができるのか?」
そのような疑問をもたれている方は多いと思います。ここではそんなCMSに関する疑問を解決します。
CMSは「Contents Management System」の略称で、Webサイトの作成、管理および運用を行うために開発された管理システムのことをいいます。書類作成を行うWordやプレゼンテーションツールのPowerPointのように、CMSを導入することで、専門的な知識がなくても簡単にWebサイトの運用ができます。

CMS導入のWebサイトとそれ以外との違い
従来のWebサイト作成では、プログラム言語(HTMLやCSS、JavaScriptなど)を理解して、その言語でサイトの構築を行う必要がありました。それぞれのプログラム言語の規則に合わせて入力する必要があり、1つのWebページごとに1から作り直す必要があるため時間や手間がかかっていました。またWebサイトを更新する際にも、プログラム内で編集を行うため確認作業が大変でした。このような理由から、Webサイトの作成・管理を“外注”している企業が多数存在していたのです。
CMSを使ったWebサイト作成では、必要な画像やテンプレート・画像・テキストを、個別にデータベースで保管できます。そのデータとCMS内のデータを組み合わせることにより、Webページが自動作成されます。データベース上に保管しているデータを編集するだけで更新できるため、プログラム言語の知識も不要です。
CMSの基本機能
CMSにはさまざまな機能がありますが、主な機能として「作成・編集・管理機能」「Webマーケティング機能」「ユーザー管理機能」の3つに分類することができます。
作成・編集・管理機能
CMSの最大の機能は、コンテンツの作成・編集・管理機能です。プログラム言語の知識が必要ないため、簡単にWebサイトを作成・編集できます。また、多くのCMSは「更新履歴を保存・復元することが可能」「視覚的に更新できる」「承認フローの管理が可能」といった機能も備えています。通常のプログラミングでは更新履歴を残せませんが、CMSでは過去の内容を消さずにデータを保存できます。更新や更新前の内容に戻すことも簡単で、記事の公開日時の指定も可能です。
通常のプログラミングではデータ入力後に、Webサイトが想定通りに完成しているか確認する必要があります。そのため、「入力→サイト確認」の繰り返しで、時間と手間がかかっていました。しかし、CMSでは視覚的に確認しながらWebサイトの作成・編集・更新が簡単に行えます。また承認フローに関する履歴も残すことが可能なので、承認フロー機能が付与されているCMSで管理をすれば見落としも防げます。
Webマーケティング機能
CMSにはWebマーケティング分析に必要な機能も多く搭載されています。Webサイトのアクセス分析ができ、Google Analyticsとの自動連動も可能です。また、CMS上で立ち上げたLPサイトの改善方法を分析して、コンバージョン率を高めるLPO(ランディングページの最適化)機能も備えています。また、「アンケート・メルマガ配信機能」を使えば、メルマガ配信やアンケートの回答結果も簡単にダウンロードでき、Webマーケティングに有用なデータ収集も可能です。さらに、「問い合わせ・FAQ作成機能」を使えば、製品に関する問い合わせや過去の問い合わせをFAQとして記載することもできます。
ユーザー管理機能
CMSはサイトを作成・管理するだけでなく、作成に関わるメンバーの権限をユーザーごとに設定することができます。CMSにログインして操作した履歴の確認ができるため、責任の所在を明確にできます。また、作成・変更・削除の操作に関する権限をユーザーごとに設定可能なので、重要データに関しては特定のユーザーのみに操作権限を与えることで間違った変更・削除を防げます。ユーザーをグループ分けして管理することも可能で、グループごとに権限条件を変えたり承認フローの設定ができたりします。
CMSの主な分類
CMSには、Web制作会社などが独自に開発を行う「独自開発型」と、比較的自由度が高くソースコードが無料で提供されている「オープンソース型」の2種類あります。
独自開発型
システム開発を行うベンダーが制作し、販売するCMSです。導入には初期費用がかかりますが、ベンダーのサポートが受けられるので、不具合や脆弱性に対し保証してもらえます。企業の商業利用が前提となっているため、大量のページ数にも十分対応できます。
オープンソース型
プログラムが一般公開されているCMSのことで、ライセンス料が必要なく安価に導入できます。汎用性が高く、デザインやテンプレートのカスタマイズも簡単です。しかし、多くのオープンソース型CMSは商業利用の前提で設計されていないため、ページ量が多い場合には不向きでしょう。またサポート体制も万全ではないため、不具合が起きた場合はすべて自己責任となります。
また自社システムとの緊密な連携や独自機能で複雑なカスタマイズを行いたい場合に導入するためのCMSツールもあります。ただし一からの設計・開発となるため、導入費用が高く導入までの時間も長くなる傾向にあります。
CMS導入のメリットとデメリット
CMSを導入することにはさまざまなメリットがありますが、もはやデジタルマーケティングに必要不可欠なマストアイテムになっているといえるでしょう。

CMS導入のメリット
1.一元管理
CMSには複数のテンプレートが用意されており、操作方法やデザインが共通化されています。そのため担当者が変わったとしても、デザイン性のばらつきや配置ミスが起こらないため、一貫性のないWebサイトになるのを防げます。
2.検索エンジンの最適化
タイトルやディスクリプションにSEO効果の期待できる設定を施すことで、検索エンジンで高評価されやすいサイトを作成できます。また、制作したコンテンツは随時増やすことも簡単です。
3.Webマーケティングに効果的
Webサイトはすべてリアルタイムで情報更新できるので、アクセス数やコンバージョン計測などのWebマーケティングに生かせます。また、反響次第でコンテンツ追加も可能なことから、PDCAサイクルを回しながらの運営にも非常に適しています。
4.複数人での同時作業が可能
CMSの保管データを編集するだけなので、データ編集を複数人で同時に行うこともできます。
5.レスポンシブ対応の自動化
レスポンシブ対応とは、画面サイズに応じて最適に表示されるようデザインを変えることをいいます。CMSを用いるとその設定も簡単にでき、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットでも見やすいWebサイトを作成できます。
6.SNSとのスムーズな連携
FacebookやTwitter、Instagram、そのほかのSNSと自由に連動させられます。そこからサイトへの流入・集客が見込めるでしょう。
7.コストの削減
従来のプログラミング言語による作成では専門的な知識が必要で、外注している企業も多くありました。CMSを使うことで、外注せず自社で作成・更新ができるため、コストと時間の削減に大きく寄与します。
CMS導入のデメリット
1.コンテンツ移行作業の手間
コンテンツを別の場所に移行するためには、テンプレートごとの変更が必要となるため、ある程度時間がかかります。
2.最低限のCMS操作知識が必要
従来のような専門知識は必要ありませんが、最低限のCMS操作を覚える必要はあります。
CMSの活用事例
CMSを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
負荷分散がうまくできるようになった
「これまで、サイト作成や編集作業においては、特定の修正要件があった際、HTMLタグやCSSを、一人の担当者のみで編集して、対応していました。WordPressは、複数人のアカウントをWordPress上に直接作成でき、共同編集もできるため、特定の修正案件を担当者一人に依存することなく、分業(共同作業)することができます。それまでは一人の担当者のみに負荷が集中していましたが、負荷分散がうまくできるようになり、サイト作成や編集作業の運用が効率的にできるようになりました」
https://www.itreview.jp/products/wordpress/reviews/81304
▼利用サービス:WordPress
▼企業名:世界真光文明教団 ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:IT管理者
WEB営業という面にまで貢献
「会社のコーポレートサイトとECサイトのブログで運用しているのですが、SEO的にも強く、上位のランディングページをつくりこめているので、WEB営業という面にまで食指を伸ばすことができたのが非常に貢献していると思います」
https://www.itreview.jp/products/wordpress/reviews/77100
▼利用サービス:Wordpress
▼企業名:タイヘイ化成株式会社 ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:製造業
短期間で高機能な自社サイトを立ち上げるのに便利です。
「プラグインを追加するだけで必要な機能を無料で導入できる点、ビジネスブログから店舗案内、会社案内とサイトデザインのバリエーションは多く、無料、有料に関わらず世界中のデザインを選択できる。小規模事業者にとっては、導入しやすいシステム。各種テンプレートもそろっていて、会社案内などで必要な項目を入れ替えるだけで良い」
https://www.itreview.jp/products/movable-type/reviews/5688
▼利用サービス:Wordpress
▼企業名:オフィスHANEDA ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:デザイン・製作
イニシャルコストを大幅に削減
「営業担当者もサポートの方にも良くしていただき満足しています。ホームページ製作にかかるイニシャルコストがリース扱いの為、大幅に削減でき、ランニングコストも安く費用対効果がかなり高いと思います。イメージを伝えるとイメージ通りの案を提案いただき、その場で修正した物を見れるのでスムーズに製作が進みました。また、公開後は自分で手を加えることが出来るところが良いです」
https://www.itreview.jp/products/orikoublog/reviews/78606
▼利用サービス:おりこうブログ
▼企業名:株式会社サーモテクノス ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:経営企画
テンプレートがいくつもあるので、作業効率がものすごく上がった
「HPを手軽にそして割と自由に作成することができます。使用できるテンプレートが豊富にあります。以前はGoogleサイトを使っていましたがWixの方が自分たちの思い通りのページを作ることができました。テンプレートがいくつもあるので、自分のイメージに合ったものがあるとそれをそのまま使うことができるので作業効率がものすごく上がりました。ある程度機能を理解することができれば、それなりに凝ったページを作り込むことができるので、様々なイメージに合わせたページ制作ができることがとても気に入っています」
https://www.itreview.jp/products/wix/reviews/59112
▼利用サービス:Wix
▼企業名:山崎石材工業株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:その他製造業
CMS導入のポイント
ツールによって機能や性能が異なるCMS。自社のWebブサイトを運用する上で、目的を達成できて継続的に効果を上げやすいCMSの見極めが必要です。CMS導入にあたって押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
1.目的の明確化
Webサイトを作成する目的をしっかりと明らかにしましょう。どのようなサイトにしたいのか、どれくらいのボリュームにまとめるのか、どういった機能を活用するかなどを検討し、サイト全体のイメージや達成目標などを明確にすることが重要です。
2.自社に合うツールであるか
種類によって使い勝手がまったく異なるのがCMSツールです。操作性の良し悪しで導入効果も変わってくるため、まずは使いやすさを確認しましょう。また、検討しているツールが自社の求めるツールであるのかどうかも重要です。しっかり製品の情報収集をしたうえで決断しましょう。
3.セキュリティの確認
導入前に、セキュリティを自社でどこまで重視するかを定め、目的に合わせたセキュリティの度合いを判断します。セキュリティを強化する必要がある場合には、きちんとセキュリティ対策が施されている製品を選びましょう。セキュリティに関する保証と初期費用のどちらを優先させるかが判断基準の1つです。
4.コストの確認
CMSの導入にはある程度のコストがかかります。そのため、希望のツールと自社のコストとが見合っているかどうかを確認する必要があります。
5.サポート体制の有無
サポート体制の有無も、CMSツールによって異なります。オープンソース型CMSはサポート体制がないに等しいといえます。商用パッケージ型CMSの場合であれば、適宜サポートを受けることができますが、自社の求めるサポート体制があるかどうかを必ず確認しましょう。
CMSの業界マップ
CMSのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
おすすめのCMSツール5選
実際に、CMSツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのCMSツールを紹介します。
(2021年11月29日時点のレビューが多い順に紹介しています)
WordPress
「WordPress」は、一般のブログ作成者から大手企業まで多くのユーザーが使用するCMSツールです。2021年11月現在で、全世界のWebの42%がWordPressで構築されています。簡単な操作で文章の投稿や写真の追加、編集などさまざまな作業ができ、デザインテンプレートも豊富。手軽に美しいデザインに仕上げられます。自社でサーバ構築を行う方法が一般的ですが、レンタルサーバサービスを使う多くの企業でも利用可能なので、手軽に導入することができます。
おりこうブログ

累計導入実績1万8000件以上、ホームページ作成機能を中心にアクセス解析やメッセージ配信・カタログ作成など、多彩な機能をそろえています。1つの管理画面で作業でき、手間とコストを抑えたオールインワン導入も可能です。また生体認証によるログインなど、セキュリティ対策も万全。主なプランとその費用については、公式Webサイトからの問い合わせが必要です。
Movable Type
安全性や信頼性が評価され、国内5万サイト以上で導入されています。ブログ形式で簡単にサイト作成でき、機能が充実しています。官公庁や教育機関などのWebサイトでも活用されています。日本語での問い合わせができ、表示速度が速いのも魅力です。
a-blog cms
導入実績は4000件を超え、サポート体制が充実しています。運営会社自ら導入サポートを行い、トラブルシューティングにはビデオ通話を使ったサービスを展開。またWebサイトの作成初心者にも優しい仕組みで、ブログ感覚でスムーズな作成できます。さらに、セキュリティ面での脆弱性を排除しているのも魅力です。
ferret One

600社を超える企業に導入され、BtoBマーケティングに必要なコンテンツを網羅しているツールです。専門的な知識がなくてもサイトの作成が可能です。Webマーケティング専門メディアが運営しているため、蓄積したノウハウで快適・効率のよい運用ができます。PDCAを回せる設計にもなっており、プレゼン資料を作成するような感覚でWebサイトを運用できます。
ITreviewではその他のCMSも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。
まとめ
デジタルマーケティングを成功させるためには、自社のWebサイトを充実させることが重要です。効果的で充実したWebサイトをめざすCMSの導入は、デジタルマーケティングの効果を上げる起爆剤となるでしょう。CMS導入の際には、導入目的を明確化し自社に合うツールを選定すること。万全のサポートを約束するシステムベンダーと出会うことも大切です。
投稿 CMSとは?メリットや導入ポイント、活用事例、おすすめツール5選を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 人気のMAツール11選|マーケティングオートメーションツールの特徴や機能を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>リードの情報管理や、営業プロセスの支援が必要となる現場において活用されていますが、ツールによって注力している点が異なるため、競合の有無や商品の特長をつかんだ上で適切に選びたいところです。
本記事では、企業への導入実績の多い代表的なMAツールを厳選しました。実際に使用している担当者のレビューを交えながら、ツールの特徴や強み、機能解説を行います。自社の課題と照らし合わせ、最適なMAツールを見つけてください。
マーケティングオートメーション(MA)は業務を自動化し、見込み客への適切なアプローチを可能にする

マーケティングオートメーション(MA)とは、従来は手作業で行なっていたリード獲得〜育成〜分類のプロセスを自動化し、適切なタイミングで適切なアプローチを可能にすることで、見込み顧客の自社製品への関心や購入意欲を効率よく高めることです。
マーケターの業務の効率化が図れると共に、受注確度の高いリードを抽出できるので、営業部門のリソースを無駄なく、適切に配分を可能にします。「リードをうまく可視化できていない」「営業活動が成約に結びつかない」といった課題を抱えている企業は、MAツール導入を検討すると良いでしょう。
しかしMAツールは、何を導入しても良いという訳ではありません。それぞれのツールで、搭載している機能が異なるので、自社の取り扱う製品やサービスによって適切なものを選ぶ必要があります。
MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方
MAツールの選び方

MAツールと一言でいっても、ベンダーの提供しているツールごとに特色があります。
自社に適したMAツールを選ぶためにも、以下の点を確認するようにしましょう。
- BtoB向けとBtoC向けどちらに向いているか
- CRMなどのシステムと連携できるか
- 幅広いチャネルに対応しているか
- サポート体制が充実しているか
BtoB向けとBtoC向けどちらに向いているか
自社のサービスや製品が「BtoB向け」「BtoC向け」なのかで選ぶべきMAツールが異なってきます。
BtoB向けのMAツールは、一元管理できるリードの数が1万件程度なのに対して、BtoC向けのMAツールは、10万件程度を管理できます。一般的に取り扱うリード数の多いBtoC向けのサービスや製品を展開している企業は、管理ができるリード数に着目すると良いでしょう。
また、BtoB向けのMAツールには、セミナー・イベント等への集客機能や名刺管理機能が実装されているツールもあります。オンラインのみならず、オフラインでのリード獲得を実施・検討している企業は、これらの機能が備わっているMAツールを選定しましょう。
CRMなどのシステムと連携できるか
現代のマーケティングでは、自社製品を利用・購入した顧客に対して、いかにリピートやファン化を促進できるかが重要になってきます。そのため、CRM(顧客関係管理)ツールと相互に連携できるかを確認する必要があります。
MAツールの中には、自社のCRMツールと連携できるものや、サードパーティのCRMツールと連携できるものが展開されています。
幅広いチャネルに対応しているか
メール配信に限らず幅広いチャネルでのアプローチに対応しているかを確認しておく必要があります。
最近では、LINEやFacebookといったSNSとの連携が可能なMAツールも増えています。従来のメルマガやWebコンテンツではアプローチできなかった層にも、サービスや製品を訴求ができます。
サポート体制が充実しているか
MAツールを初めて導入する場合は、サポート体制が充実しているかを確認しましょう。導入初期には、正確にデータを計測するために設計や各種設定を行う必要があります。
ベンダーによっては、24時間365日対応のオンラインサポートや導入・運用支援のサポートを実施しています。有償になる場合もあるので、事前に確認が必要です。
代表的なMAツール11選
1. Marketo Engage(マルケト エンゲージ)

(参照元:https://jp.marketo.com/)
「BtoB」「BtoC」問わずに、全世界で5,000社以上の導入実績があるアメリカ発のMAツール「Marketo Engage(マルケト エンゲージ)」。日本国内でも大企業から中小企業・スタートアップまで業界や業種を問わずに導入されており、MAツール導入の第一候補とも言えるツールです。
ユーザーへのメール配信以外にも社内のオペレーション改善やメール以外のアクションを簡単に設定できるので、組織のオペーレーション改善にも有効です。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | FUJIFILM(製造・化学/電子) ロート製薬(製薬) LINE(IT・サービス) PASONA(人材サービス) Panasonic(製造・電気機器)など |
| 他システムとの連携 | ◯(CRMとの連携) |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | 無料と有料のサポート体制が充実 |
| 月額料金 | 個別に見積もり |
| 主な機能 | マーケティングオートメーション、メール、モバイルマーケティング、ソーシャル、デジタル広告、ウェブ、アカウントベースドマーケティング、マーケティングアナリティクス、プレディレクティブコンテンツ、Marketo Sales Connect |
長期的な顧客との関係性を気づく統合型プラットフォーム

(参照元:https://jp.marketo.com/company/)
顧客とのエンゲージメント向上を目的に設計されており、見込み客の認知から自社製品の購入、実際に製品を購入した顧客がファン化や再購入に至るまでの長期的な関係構築が可能な統合型のプラットフォームになっています。
機能の網羅性が高いことや外部システムとの連携がしやすいことから、一貫性を持ったマーケティング施策を打ち出すことができるのが特長です。
2. SATORI

(参照元:https://satori.marketing/ )
「あなたのマーケティング活動を一歩先へ」をミッションとしている、株式会社SATORIが提供している国産のMAツールです。900社以上の導入実績があり、国産ならではの迅速なサポート体制が整っています。
また、匿名リードのデータ管理や蓄積も可能な「アンノウンマーケティング機能」を搭載し、実名リード獲得への施策を打てるという特長があります。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | USEN(情報・通信) ユニ・チャーム(化学) アデランス(ビューティ・ヘルス) ログミー(IT・サービス) オノヤ(リフォーム・不動産)など |
| 他システムとの連携 | kintone、Salesforce Sales Cloudなど |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・広告) |
| サポート体制 | オンラインサポートデスクや無料の利活用セミナーを用意 |
| 月額料金 | 初期費用:30万円~ 月額費用:14.8万円~ |
| 主な機能 | リード管理機能、リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーション、オートメーション、レポート、データ提供(オプション)、独自ドメイン(オプション) |
初心者マーケターにおすすめのシンプルで直感的な操作性

(参照元:https://satori.marketing/features/)
ウェブサイトに計測タグを埋め込むだけで即日からの運用が可能。日本語のインターフェースで視認性の高いグラフが表示させるので、初めてMAツールを運用するマーケターでも操作や効果測定がしやすいのが魅力です。
また、セミナーや個別説明会の実施や導入ユーザーのコミュニティを形成するなど円滑な運用へのサポート体制も充実しています。
3. b→dash(ビーダッシュ)

(参照元:https://bdash-marketing.com/)
業界シェアNo.1を誇り、業種業界を問わずに大企業からベンチャー企業まで多数の導入実績を持つ統合型のMAツールです。非常に多くの機能を搭載しているのが特徴で、データ統合やメール配信だけでなくWeb接客やアプリPUSHといった機能も含まれています。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | 阪急百貨店(百貨店) KIRIN(飲料) 楽天イーグルス(スポーツ) クレディセゾン(金融) UNDER ARMOUR(衣料品)など |
| 他システムとの連携 | ― |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | 運用サポートあり |
| 月額料金 | ライトプラン:5万円/月 スタンダードプラン:要相談 |
| 主な機能 | データパレット、データ統合(CDP)、メール/MA、Web接客、BI、LINE連携、広告連携、SMS配信、レコメンド、CMS(フォーム)、CRM、Push通知 |
マーケティングに必要な機能を全て網羅したAll in Oneツール

(参照元:https://bdash-marketing.com/)
LINE連携やSMS、アプリPUSHといった多様なチャネルで見込み客へのアプローチが可能。アプリやWebサイトに訪れたユーザーに対して、デモグラフィックデータや行動情報に基づいたクーポン配布や告知などWeb接客機能も備えています。
また、自社製品やサービスの利用購入後の顧客との関係性を管理するCRM機能も搭載。長期的な視点で顧客ロイヤリティを高める施策を実行することもできます。
4. SHANON MARKETING PLATFORM

(参照元:https://www.shanon.co.jp/products/)
デジタルとアナログの顧客データを統合管理できる国産MAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」。国内の導入実績は900社以上、キャンペーン実績は22万件以上を誇ります。オンラインのリード管理だけでなく、オフラインが開催されるイベントやセミナーの管理に関する機能も充実しているのが特長です。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | SB C&S NTTソフトウェア NTTコミュニケーションズ 野村総合研究所 時事通信社など |
| タイプ | 統合型 |
| 他システムとの連携 | ◯ |
| サポート体制 | 提案から設定、コンサルティングまでトータルサポートが可能 |
| 月額料金 | ― |
| 主な機能 | リード管理、ランディングページ/WEBフォーム、セミナー管理、イベント管理、ソーシャルマーケティング、キャンペーンマネジメント、Webトラッキング、シャノンコネクト |
イベント・セミナー運営に関する煩雑な作業を効率化

(参照元:https://www.shanon.co.jp/products/event/)
実名でのリード獲得に効果的なオフラインでのイベント開催やセミナー運営の効率化をはかることによって、作業時間を約50%削減できます。また未申込者に対してフォローやリマインドを行うことで、集客力のアップも期待できます。
5. Synergy!

(参照元:https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/)
「伝えたいメッセージを、顧客にきちんと届けるために」をコンセプトとした、最適な顧客管理を行うCRMシステムです。正確にはMAツールではありませんが、メール配信やLINE連携・フォーム作成などの機能と組み合わせて使用すれば、マーケティング活動の効率化につながります。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | 阪急阪神不動産(不動産) ブラザー(電機メーカー) 仙台銀行(金融) ヤクルトスワローズ(スポーツ)など |
| 他システムとの連携 | - |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | 活用支援サービスあり |
| 月額料金 | 利用機能によって異なる |
| 主な機能 | データベース、フォーム、アンケート、メール配信、LINEへの配信、広告連携、Web |
安全・安心の最新セキュリティー

(参照元:https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/)
IDとパスワードを入力するだけでアクセス可能な一般的なMAツールと異なり、クライアント証明書(デジタル証明書)をインストールしたPCからのみログインができる設計になっています。第3者のなりすましなど不正アクセスを防げます。
6. Probance

(参照元:https://www.probance.jp/ )
株式会社ブレインパッドが提供するBtoC事業向けのMAツール「Probance(プロバンス)」。強みは、AI(機械学習)を活用し、顧客のニーズを予測した的確なコミュニケーションを実行できることです。
| 向いている形態 | B to C |
|---|---|
| 導入実績 | OZ mall(ITサービス) マイナビ転職(IT・人材) クラウドワークス(ITサービス) WOWWOW(放送)など |
| 他システムとの連携 | ― |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | 活用支援サービスあり |
| 月額料金 | スタートプラン:180,000円〜 プロ:375,000円〜 |
| 主な機能 | データベース、フォーム、アンケート、メール配信、LINEへの配信、広告連携、Web |
AIが膨大なデータを分析し、顧客行動を予測
AIによる顧客データの分析を基に行動を予想することにより、顧客にとって心地良いアプローチが可能となり、新規顧客の獲得やリピーターの育成、休眠顧客の掘り起こしなどをサポートします。
顧客と持続的に良好な関係を築きたい企業や、エンゲージメントの構築によるリピーター獲得を目指す企業に適しています。
7. Salesforce Pardot

(参照元:https://www.salesforce.com/jp/products/pardot/overview/)
「SFA(営業支援システム)」や「CRM(顧客関係管理)」において世界トップシェアを誇る米国のセールスフォースが提供するクラウド型MAツール。同社のSFAシステムである「Sales Cloud」とシームレスに連携できることにより、見込み客の創出ら育成、営業活動に至るまで包括的に管理できます。
Webサイトやフォームを活用したリードジェネレーションをはじめ、CRMへの接続、ROIレポート作成などを活用することにより、確度の高い見込み客に対して効果的に販売を促進します。マーケティングチームと営業チームのワークフローを同期し、効果的なBtoBマーケティングを支援します。
| 向いている形態 | B to B |
|---|---|
| 導入実績 | パーソルキャリア(人材) RIZAPグループ(ヘルスケア) セブン&アイ・ホールディングス(小売)など |
| 他システムとの連携 | ◯(CRM、SFAシステムとの連携) |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯ |
| サポート体制 | 電話、メール、訪問によるサポート |
| 月額料金 | 月額費用:150,000円〜 |
| 主な機能 | ― |
Sales Cloudとの連携が可能
営業の効率化のために非常に多くの企業で導入されている「Sales Cloud」。このツールとの連携によって、リード獲得からナーチャリング、営業への引き渡しをスムーズに行うことが可能になります。
8.Hubspot Marketing hub

(参照元:https://www.hubspot.jp/products/marketing)
コンテンツの作成やリードへの転換、ROIの測定までできる統合型のマーケティングプラットフォームです。営業効率化を図る「Sales hub」とカスタマーサポートの支援をする「Service hub」との連携を行うことができます。
ツール内で、誰でも簡単にコンテンツ作成が可能。書式やフォーマットを手軽に変更できるので、ユーザーの読みやすい魅力あるコンテンツを作り出せます。
またリアルタイムでSEOに関するアドバイスを確認できるので、専門的な知識がなくても検索エンジンでの上位表示に結びつけることが可能。自社製品やサービスへの関心を集めることができます。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 |
YAHOO! JAPAN(IT) |
| 他システムとの連携 | ◯(CRM、SFAシステムとの連携) |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | ◯ |
| 月額料金 | 月額費用:6,000円〜(Starterプラン) |
| 主な機能 | ブログ、ランディングページ、Eメール、マーケティングオートメーション、リード管理、アナリティクス、パーティション化、SNS、SEO、広告、 Call-to-Action、Salesforceとの連携 |
9.Kairos3

(参照元:https://www.kairosmarketing.net/marketing-automation)
マーケティングと営業に必要な機能を備えた、MAツール兼SFA(営業支援)ツールです。「始めやすさ・使いやすさ」に定評があり、難しいマニュアルがなくても簡単に扱うことができます。
名刺管理アプリとの連携やセミナー管理にも対応しており、オフラインでのマーケティング活動のサポートが可能です。関連セミナーへの誘導やセミナー後のフォローアップを通じて、見込み顧客の育成に貢献します。
加えて営業活動の状況を管理できるので、マーケティング・営業の部門間連携による売上アップにも期待できます。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 |
リクルートライフスタイル(サービス業) |
| 他システムとの連携 | ◯(SFAシステムとの連携) |
| 幅広いチャネルへの対応 | ― |
| サポート体制 | ◯ |
| 月額料金 | 初期費用:10,000円 月額費用:15,000円〜 |
| 主な機能 | リード管理、メール配信、フォーム作成、スコアリング、ホットリード、リードナーチャリング、セグメンテーション、オフライン接点管理、マーケティング分析、名刺管理アプリ連携、セミナー管理、シナリオ、独自ドメイン、SFA(営業支援)、Kairos3 API |
10. List Finder

(参照元:https://promote.list-finder.jp/)
株式会社イノベーションが提供するMAツール。月額3.98万円~と比較的安価から始められ、利用の面でも専任のコンサルタントが支援してくれることから、MA初心者でも安心のサービスです。
基本的なMA機能を包含しシンプルな操作性が特徴です。また、コンテンツとしてPDFを活用でき、ユーザーによ閲覧の分析が可能です。導入アカウント数も国内で1,600アカウントを超えているツールです。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | 三菱電機システムサービス株式会社 東洋インキ株式会社 など |
| 他システムとの連携 | Salesforce(CRM・SFA)、Sansan(名刺管理)など |
| 幅広いチャネルへの対応 | メールのみ |
| サポート体制 | ○ |
| 月額料金 | 3.98 万円~ |
| 主な機能 | 名刺データ化代行、企業属性付与、フォーム作成、メール配信、アクセス解析、PDF閲覧解析、セミナーページ作成、スコアリング、優先リード通知、アプローチ管理 など |
11. Oracle Marketing Cloud

(参照元:https://www.oracle.com/jp/cx/marketing/)
日本オラクル株式会社が提供する米国のMAツール。リードの属性や行動などのデータを生かしたパーソナライズを強みとしており、可能性が高いリードに対して最適なアプローチを実行します。BtoBとBtoCの双方の現場において、ブランドのロイヤリティ向上や新規顧客の創出につなげます。
営業活動に活用できる自動スコアリング機能や、セキュリティを高める厳しい権限設定も可能なため、幅広い商材を持つ企業や、膨大なデータを迅速に処理・分析して生かしたい企業に適しています。
| 向いている形態 | B to B/B to C |
|---|---|
| 導入実績 | ― |
| 他システムとの連携 | ◯ |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯ |
| サポート体制 | ― |
| 月額料金 | ― |
| 主な機能 | リード管理、セグメンテーション、スコアリング、ナーチャリング |

まとめ|自社に最適なMAツールを導入して、質の高いマーケティングを実現
MAツールにはいくつかの種類がありますが、企業によって必要となる機能は異なります。BtoBあるいはBtoC事業向けであるかどうかをはじめ、集客や誘導、分析の有無、顧客育成などさまざまな特徴があるため、機能の必要性を見極めることが重要です。また、MAツールの効果を最大限に生かすためには、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)とシームレスな連携も欠かせません。
海外メーカーは圧倒的なシェアを誇りますが、国内メーカーはある分野に特化したMAツールも多いため、自社の用途やニーズに応じて比較検討しましょう。
※各製品の価格や特徴は掲載時点のものとなります

投稿 人気のMAツール11選|マーケティングオートメーションツールの特徴や機能を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ヘッドレスCMSとは?定義やメリットを徹底解説!ツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]> しかし、開発チームに聞いてみれば、従来のコンテンツマネージメントシステム(CMS)の首(ヘッド)を切り落とすことに賛成するかもしれません。それは、コンテンツの管理と配信に潜在的に無限の可能性をもたらすからです。
この記事の要点
1.ヘッドレスCMSとは?デカップルドCMSとヘッドレスCMSの違い
2.ヘッドレスCMSの機能とメリット
3.おすすめのヘッドレスCMS3選
~この記事はおよそ10分で読めます~
ヘッドレスCMSとは?
従来のコンテンツマネジメントシステム(CMS)の「頭」(ヘッド)は、フロントエンドフレームワークやテンプレートシステムなどのフロントエンドコンポーネントのことを指します。
ヘッドレスCMSは、これらのフロントエンドコンポーネントを取り除くことにより、生の未公開コンテンツを開発チームが自由に使えるようになります。開発者らはコンテンツを配信するためのデフォルトのフロントエンドシステムひとつに縛られないので、コンテンツを表示するためのヘッドをいくつでも好きなだけ作ることができます。APIの力を少しでも利用すれば、Webサイト、アプリ、スマートウォッチなど、さまざまなプラットフォームにコンテンツを配信することができます。
一方、従来のCMSには、すでにフロントエンドの配信レイヤーが組み込まれています。つまり、コンテンツは1つのプラットフォームにしか表示されないのです。
デカップルドCMSとヘッドレスCMSの違いは何ですか?
この2つのCMSタイプの主な違いは、アーキテクチャタイプにあります。デカップルドCMSではアクティブなアーキテクチャを採用しており、コンテンツが公開されると即座にページに表示されます。ヘッドレスCMSはリアクティブなアーキテクチャで、つまり、ユーザーからの問い合わせがあった時にのみコンテンツがページに表示されます。
ヘッドレスCMSの機能
ヘッドレスCMSの機能は以下の通りです。
API機能
ヘッドレスCMSを従来のCMSから分けるのはAPIです。APIは様々な言語やフレームワークとの連携が可能です。様々なフロントエンド配信システムをAPI上に構築することで、ヘッドレスCMSはあらゆるプラットフォームにコンテンツを配信することができます。
コンテンツモデルの作成
CMSは、あらかじめ定義されたコンテンツモデルに制限されている。ヘッドレスCMSはそうではなく、コンテンツを配信するための独自のプラットフォームを柔軟に作成することができます。
アセットマネジメント
アセットマネジメントでは、ファイルをクラウド上に保存し、1つのシステムで管理することができます。ローカルに保存したコンテンツも、クラウドに保存したコンテンツも、同じプラットフォームで管理することができます。ヘッドレスCMSでは、自分でコンテンツを作成、閲覧、更新、削除することができます。
多言語でのコンテンツ公開
ヘッドレスCMSの最大のメリットのひとつは、複数のプラットフォームでコンテンツを公開できることです。そのため、時には、異なるプラットフォーム上のコンテンツを異なる言語で表示しなければならないこともあります。ヘッドレスCMSのコンテンツは、どのようなフロントエンドフレームワークにも配信できるため、APIの助けを少し借りれば、必要であればどのような言語でも公開することができます。
ヘッドレスCMSのメリット
すでに述べたように、ヘッドレスCMSの最大のメリットは、開発者らがコンテンツを配信するヘッドを複数も構築できることです。これこそが、この種のコンテンツ管理ソリューションを従来のCMSと異なるものにする主な要素です。しかし、このソフトウェアに検討する価値を与える特徴はそれだけではありません。
実装が簡単
従来のCMSでは、コンテンツを別のプラットフォームにアップロードしたいと思うたびに、ツールを再実装する必要がありました。ヘッドレスCMSには、フロントエンドの配信システムが含まれていないため、このような再実装の必要がありません。
ユーザーフレンドリー
従来のCMSはウェブサイトの上に構築されており、そのためには多くのコードやコンテンツが必要となります。ヘッドレスCMSは少しのコードで立ち上げることができるため、従来のCMSよりもはるかに使いやすくなっています。Forbes誌によると、「ビジネスチームが新しい機能を作るのにも、より迅速に対応できます。例えば、マーケティング部門が新シリーズの製品ミニサイトを作成したい場合、CMSに直接アクセスしてすぐにコンテンツの作成を開始することができます」
迅速な導入
前述したように、ヘッドレスCMSの有益な特徴は、さまざまな作業を無駄のない迅速なものにできることです。その一つが、コンテンツ制作者と開発者がヘッドレスCMSを使って二人三脚で作業できることです。従来のCMSではコンテンツを作成する前にシステムを完全に開発する必要があリましたが、この機能があれば従来のCMSよりも早くコンテンツを立ち上げることができます。
オムニチャネル対応
オムニチャネルマーケティングは、あらゆる形態の小売業に変革をもたらしています。ヘッドレスCMSのコンテンツは反応性が高いため、数多くのチャネルでコンテンツを再利用することができます。それは、ソーシャルメディア、モバイル、VR、そして、顧客やユーザーがいるあらゆる場所を含みます。
ヘッドレスCMSの事例
ヘッドレスCMSの領域はまだ発展途上であり、それはいくつかのビッグネームがまだ姿を現していないことを意味しています。ここでは、米国G2 Crowdで波紋を広げ始めている領域で、最高のヘッドレスCMSプラットフォームと考えられる製品をいくつか紹介します。
1. 最高のヘッドレスCMS「Contentstack」
Contentstackは、Web、モバイル、IoTなどの複数のデジタルチャネルにおけるコンテンツ管理を迅速化・簡素化するヘッドレスCMSです。ワークフローや承認、デジタルアセット管理、多言語展開などの機能を備えています。
Contentstackには3種類のプランがあり、1つ目はContentstackが提供するすべての機能を評価できる無料トライアル。2つ目の選択肢はビジネスプランで、規模の拡大を計画しているような企業に最適です。月額3,500ドルで提供されています。最後は、カスタム価格で提供されるエンタープライズプランです。詳細については、Contentstack社にお問い合わせください。
2. オープンソースのヘッドレスCMS「Contentful」
Contentfulは、ヘッドレスCMS機能を備えたWebコンテンツ管理システムです。このツールにより、編集者はコンテンツを管理し、開発者はコンテンツをモバイルやウェブアプリケーションに配信することができます。Contentfulは、作成したコンテンツをプログラム可能にすることで、開発者の生産性を高め、新しいプラットフォームでのイノベーションを可能にすることを誇りとしています。
ユーザーレビュー:
APIで柔軟にコンテンツ配信ができるモダンなCMS
WordPressよりは開発者向けのサービスのような気がしますが、自由度の高いCMSです。APIを利用してJSON形式でコンテンツのデータをリクエストすることができるので、フロントエンドが開発できるのであれば、柔軟にサイトを構築することができると思います。
https://www.itreview.jp/products/contentful/reviews/15113
Contentfulの評判はこちら!https://www.itreview.jp/products/contentful/reviews
3. 日本製ヘッドレスCMS「microCMS」
microCMSはAPIベースの日本製のヘッドレスCMSです。
もう社内向け編集/管理画面を自作する必要はありません。
開発・運用コストを大きく下げることでビジネスを加速させます。
コンテンツ管理のためのサーバ管理は一切不要で、サインアップするだけですぐにサービスを利用開始できます。
また、APIを作成するとデータ入稿用の管理画面が自動生成され、誰でも簡単にコンテンツを作成・管理できます。
さらに、コンテンツはAPI経由で取得可能なためエンジニアやデザイナーはさまざまなプラットフォームでコンテンツを利用できます。
ユーザーレビュー:
サイト運営にかかる時間・コストともに半分以下になった
機能ごと・メンバー毎で権限管理できるので、運用がとにかく楽。テスト環境での社内のステークホルダーへの確認だったり、機能ごとの使い分けが簡単にできるのが便利。
また、予約投稿機能があるので、ページの開始・終了時間を自由に設定できるのも結構助かっている。
https://www.itreview.jp/products/microcms/reviews/49328
microCMSの評判はこちら!https://www.itreview.jp/products/microcms/reviews
※この記事は、https://learn.g2.com/headless-cmsを翻訳し、国内向けに再編集しています。
投稿 ヘッドレスCMSとは?定義やメリットを徹底解説!ツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ダウンロード率が2倍に!投稿されたレビューの活用が、新たなマーケティング施策として効果を発揮 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>≪背景・課題≫
● 顧客の声は主にプロダクト改善に反映しており、マーケティングには生かせていなかった
● 担当者による顧客ヒアリングでは得ることが難しい「顧客の本音」を捉えたかった
≪ITreview利用の効果・メリット ≫
●レビューを二次利用した“口コミ集”資料を作成、見込み客の資料ダウンロード率が約2倍に向上した
●“口コミ集”をお客さまの検討度合いに応じた活用方法に落とし込むことで、アポ率、商談化などのスピードも早まった
●“口コミ集”が新規営業の場面でも説得力のある資料になり、営業プロセスを前に進めるのに有効なものになった
● ITreviewというオープンな場所に顧客の声があることで、新規顧客にもサービスの良さをフラットに知っていただくきっかけになった
ITreviewのPremiumプランには、四半期ごとに表彰されるITreview Grid Awardの「Leader」「High Performer」 の称号(バッジ)をWebサイトや展示会で掲示できるほか、投稿されたレビューそのものをパンフレットやLPなどへ転載できるというメリットがある。。
そのメリットをいち早く日々の営業やマーケティング活動に結び付けているのが、SEOツール・コンテンツマーケティングツール「MIERUCA(以下、ミエルカ)」を提供するFaber Companyだ。今回同社は、レビューを活用したホワイトペーパーを作成し、見込み客へのアプローチに成功したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leadersを受賞。「いただいたレビューを“口コミ集“としてまとめたホワイトペーパーをメルマガで配信しています。通常の製品資料などと比べると、ダウンロード率は約2倍です」と語るIMC部 エグゼクティブ・マーケティング・ディレクター 月岡克博氏へ、同社が実践するレビューの二次利用について詳しくお伺いした 。
ITreviewは第三者機関なので、バイアスのかからない、顧客のリアルな声を広く集められる
――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?
月岡氏: 大きくは2つあります。1つは、日々既存のお客さまをフォローしているカスタマーサクセスチームが活動の中で伺った声を収集して、それをテキストベースで社内共有しています。もう1つは、定期的に開催しているユーザー会や既存顧客向けのセミナーでヒアリングしたり、アンケートにご回答いただいた内容をお客さまからの声として収集していました。

月岡 克博 氏
株式会社Faber Company
エグゼクティブ・マーケティング・ディレクター
――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?
月岡氏:人によってお客さま理解にバラつきがあるということが課題でした。ヒアリングベースになってしまうので、「こうあるべきだ」というような個人のバイアスがかかってしまうことがありますよね。社内共有されたヒアリングの記録を見ても「これは本当にお客さまが言っていること?」と感じることがあり、そういう意味ではリアルな声を十分に集められていなかったのかもしれません。また、ミエルカはリリースしてから5年ほど経ち、おかげさまで多くのお客さまにご利用いただいておりますが、全てのお客さまの声を伺うことが難しいということも課題でした。
――ITreviewは、人を介さず、フラットなお客さまの声が聞けるプラットフォーム。お客さまのリアルな声を広く集めたいということがITreviewをご利用するきっかけに?
月岡氏: そうですね。第三者の立場で、ミエルカの評価やレビューを集めていただけるのは、とても意味のあることだと思っています。例えば、悪いことは面と向かって言いにくいものですから、私たちのヒアリングではお客さまは良いことしか言ってくださらなかったりします。直接のヒアリングでは知ることができなかった声を、レビュー投稿を通して知ることができる点は有益ですね。
“口コミ集”によって、見込み客へのアプローチを加速。新規営業のプロセスを前に進めるのにも有効
――そのようにして集めた声を、どのように活用していらっしゃいますか?
月岡氏: カスタマーサクセスチームが、ヒアリングした内容からお客さまの要望を読み取って持ち寄るニーズ会議を定期的に開催していました。その場でそれらの要望をプロダクトにどう反映していくのかを議論します。ITreviewを利用する以前は、マーケティング活用というよりも、プロダクトをどう良くしていくかという観点でお客さまの声を集めているという傾向が強かったと思います。
――ITreviewを利用することで、マーケティング活動にも顧客の声を活用することができるようになったということでしょうか?
月岡氏: そうですね。これまでもお客さまの声をマーケティングに全く活用していないわけではなかったのですが、ITreviewへレビューが投稿されるようになってからマーケティング施策の幅は広がりました。
ITreviewに投稿されたレビューから、お客さまがミエルカで出来ることのうちで「何を」評価しているのかを整理し、「SEOの順位改善」「コンテンツの競合差別化」など評価しているポイントごとにまとめた“口コミ集”をホワイトペーパーとして作成しました。新規のお客さまには、実際にミエルカで課題解決をしている口コミや評価を見ていただく。その上で業務や課題をヒアリングするほうが、お客さまの課題把握もしやすく、商談プロセスも早く進めることができます
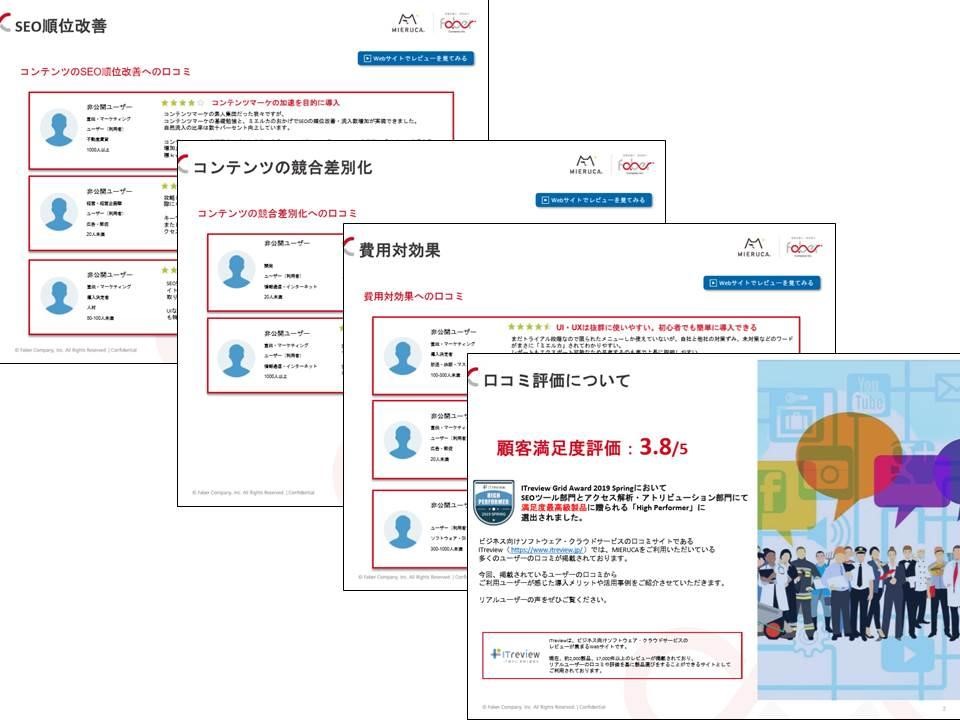
――なるほど。商談を効率的、かつ効果的に行うために、投稿レビューをホワイトペーパーにまとめる形で二次利用されているということですね。そのホワイトペーパーの具体的な成果は実感されていますか?
月岡氏: はい。リードに対するメールコミュニケーションの中で、この“口コミ集”をダウンロードコンテンツにしています。口コミ集はミエルカ製品資料よりもダウンロード率が高く、約2倍のダウンロード率です。口コミがまとまった資料が珍しいというのもあるかもしれませんが、リードの見込み度合いの判定スピードは早くなっていますね。
また、このホワイトペーパーは営業担当の「打ち手」の1つにもなっています。新規営業を行っていると、どこかのタイミングで必ず競合サービスと比較される時が来ます。そういった時に、手前みその比較ではなく、実際のユーザーからの評価としてこういうものがありますと提示できるのは強い。“口コミ集”が、新規営業の場面でも説得力のある資料になり、営業プロセスを前に進めるのに非常に有効なものになっています。
自社で集めた声をオープンにするには、事前に許諾をとるなどの手続きが必要になるため、クローズドな活用に限られがちです。ITrevewの顧客の声は最初からオープンな場所にあるので、私たちの製品を知らない人にも、製品の良さを知っていただくきっかけにもなっています。

――レビューを増やすために工夫されていることはございますか?
月岡氏: オフラインのイベントが一番投稿をお願いしやすいですね。定期的に開催されるミエルカユーザー会や、月1~2回開催されるユーザー向けのセミナーなどの場で、チラシを配布してお願いしています。あとは、ユーザー向けのメルマガの中の常設コンテンツとして、レビュー投稿をお願いしています。ITreviewでキャンペーンが走っていれば、優先順位を上げてメルマガの上のほうに表示することもあります。ただあまり強くプッシュすると、フラットな声が集まらなくなると思うので、告知する程度にとどめていますかね 。
今後は“口コミ集”のバリエーションを増やし新規のリード獲得のために、“口コミ集”を活用することも計画
――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください
月岡氏: まずは、“口コミ集”のバリエーションをさらに増やしていきたいですね。“口コミ集”は、事例作成ほど手間も工数もかからず手軽に作成できるので、評価ポイントや課題ごとに編集するだけではなく、例えば業種、お客さまの規模ごとなどでも編集できそうです。今後は、この“口コミ集”を新規のお客さまに出会うための手段とすることも検討しています。Web広告からのランディングページとして“口コミ集”のダウンロードページがある。そういうような使い方もできるのではないかと考えています。
また、カスタマーサクセスがいただいたレビューによって、臨機応変な対応を行う、サポートを改善する。そんなふうに、既存ユーザーさまの利用頻度向上やサポートなどにもITreviewを活用できると良いかなと思っています。
――最後に、ITreviewに対してのご要望やご期待などをお聞かせください
月岡氏: 今回のこの“口コミ集”も、ITreviewの担当の方とレビューの活用法をいろいろお話しさせていただく中で生まれたものです。集まったレビューをどう活用していくのか、マーケティングでどのように活用できるのか、これからもひきつづきご提案していただけるとありがたいです。
また、どうやって多くのレビューを集めるのかということが重要だと思っています。ホワイトペーパーの取り組みもレビュー数を増やすことがベースになっていますので、そこにも期待しています。
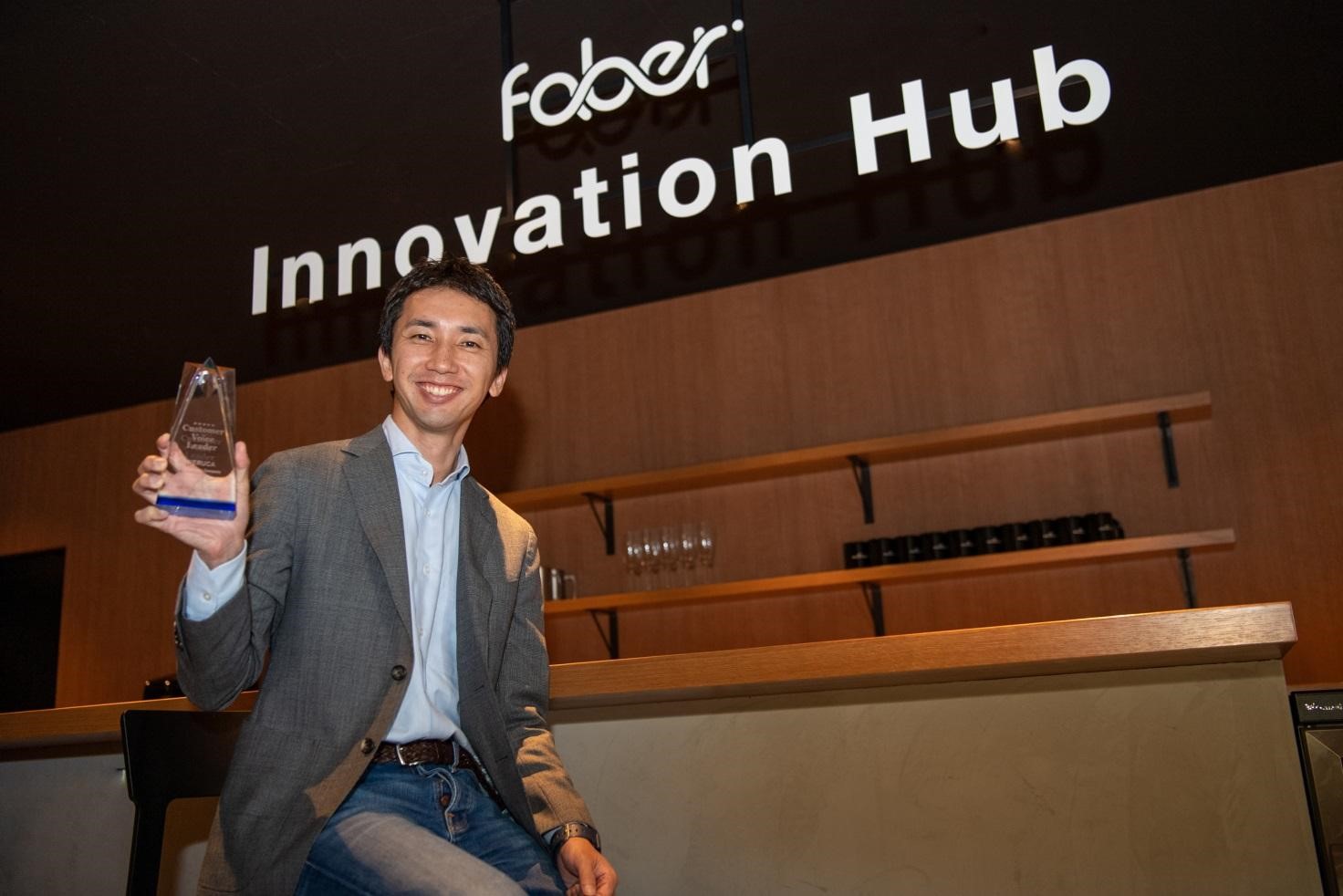
投稿 ダウンロード率が2倍に!投稿されたレビューの活用が、新たなマーケティング施策として効果を発揮 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、MAツールの基礎知識をはじめ、代表的なツールの機能を比較していきます。
MAツールとは
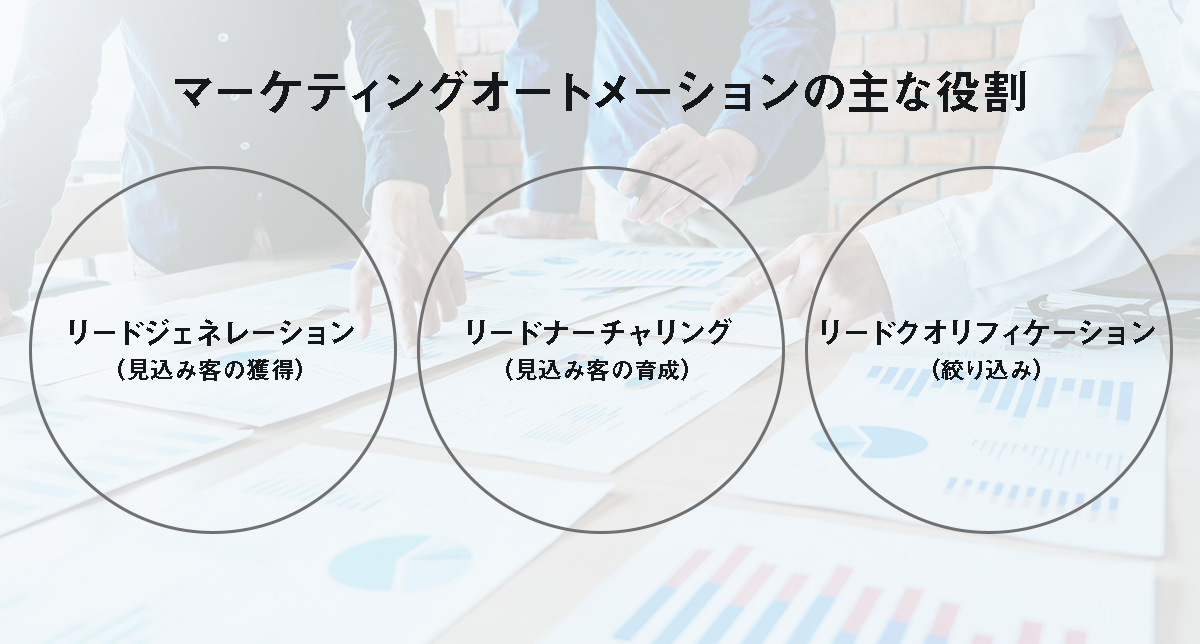
MAツールとは、マーケティングオートメーション(Marketing Automation)の略で、マーケティング全体のプロセスを自動化し、見込み客の獲得・育成に向けた適切なアプローチを可能にするツールのことを指します。
MAツールの主な役割は、下記の3つです。
- リードジェネレーション(見込み客の獲得)
- リードナーチャリング(見込み客の育成)
- リードクオリフィケーション(絞り込み)
| 役割 | 主な機能 |
|---|---|
| リードジェネレーション (見込み客の獲得) |
・リード管理 ・Webページの作成 ・ランディングページの作成 ・お問い合わせページの作成 ・フォームの作成 |
| リードナーチャリング (見込み客の育成) |
・シナリオ設計 ・アクセス分析 ・Webコンテンツ配信 ・メルマガの配信 ・Push通知 |
| リードクオリフィケーション (絞り込み) |
・スコアリング ・ホットリード抽出 |
このように、見込み客の獲得〜育成〜絞り込みに必要な業務を自動で行えるのがMAツールです。
さまざまな情報が行き交う現代において、企業が顧客に対して効果的にアプローチするには、見込み客一人ひとりのニーズに合わせた情報を最適なタイミングで提供し、コミュニケーションを構築する「One to Oneマーケティング 」が重要です。
MAツールでは、見込み客の行動を一元で管理することで、適切なタイミングで適切なターゲットにメールやコンテンツが配信できます。結果的に、製品への関心や購入意欲を高めることができ、企業の収益向上へと貢献します。
また手作業では限界があったメール配信やスコアリングといった膨大な作業を自動化することで、マーケターの作業効率の向上も期待できます。
MAについての更なる詳細はこちら
マーケティングオートメーションが必要とされる背景

2020年現在、企業にマーケティングオートメーションの導入が急速に進んでいます。ベンダーから提供されるMAツールの種類もより豊富に、そして高機能な製品が増えています。
では、企業においてなぜマーケティングオートメーションが求められるようになったのでしょうか。その背景について解説していきます。
顧客の購買プロセスの変化
まず第一にあげられるのが、顧客の製品やサービス購買に至るまでのプロセスが大きく変化したことがあります。
インターネットの普及により、顧客は製品やサービスに関するさまざまな情報を簡単に手に入れることができるようになりました。
そのため顧客は、他社製品やサービスと比較検討をした上で、オンライン上で購買、もしくは購買直前になってはじめて営業担当者と接触するといったケースが増えています。
従来のテレアポや直接訪問といった営業手法は効果を失い、いかにして顧客とオンラインを接点として購入意欲を高めていくかというインバウンド型の手法が重要になってきています。
顧客のオンライン上の行動を分析することで、最適なコミュニケーションを図ることができるMAツールの需要が高まっているのも、当然のことと言えるでしょう。
営業効率の最大化よるコスト削減
MAツールには、スコアリングやホットリードの抽出といった機能が備わっています。これらの機能を活用することで営業効率を高め、今までかかっていた無駄なコストの削減ができます。
従来は獲得した見込み顧客の興味や関心そして購買意欲の可視化ができずに、営業担当者が受注確度の低い見込み客に対して、繰り返しアプローチをするといった非効率な営業がなされることが多くありました。
MAツールを導入することにより、精度の高いナーチャリング(見込み客の育成)が可能になると共に、受注確度の高い見込み客を絞り出すスコアリング・ホットリードの抽出機能で、効率的な営業を展開できます。
労働人口の減少による慢性的な人手不足という課題に直面している日本企業において、限られたリソースを有効に使うMAツールの活用が求められています。
MA導入によるメリット

マーケティングオートメーションの導入によって得られるメリットには、次のものが挙げられます。
- リード獲得作業の効率化
- 精度の高いナーチャリング
- 受注数や受注確度のアップ
リードジェネレーション(見込み客の獲得)の段階では、顧客の情報収集を目的としたWebサイトの作成やフォーム作成、SNSとの連携などが求められます。MAツールを利用することで、これらの作業を効率化できます。
見込み客を獲得した後は、リードナーチャリング(見込み客の育成)によって購買意欲を高める必要があります。MAツールでは、顧客のニーズに合ったメール配信や広告配信、Webサイトでのリアルタイムなコミュニケーションが可能となるため、効率的なプロセスでゴールに導きます。
さらに大きな利点といえるのは、ナーチャリングによって可能性が高まった顧客をスコアリングによって選別できる点です。確度の高い顧客を優先的に営業につなげられるため、成約に至る可能性も高まるでしょう。
MAツールの機能を比較する上でのチェックポイント
導入実績が多い代表的なMAツールをご紹介します。機能の比較で特に注目すべきポイントとしては、下記が挙げられます。
1. 幅広いチャネルに対応しているか
顧客との接点が多様化した現代において、幅広いチャネルで顧客にアプローチする必要があります。
特にBtoC向けのサービスを提供している場合、メールチャネルの他にも、LINEやFacebookといったSNSの活用やスマホアプリ、ブラウザのプッシュ通知など顧客の行動に適したクロスチャネルの活用が考えられます。
そのために、MAツールの機能を比較するときには、幅広いチャネルに対応しているかの確認を怠らないようにしましょう。
2. CRMなどのシステムと連携できるか
マーケティング活動は、自社製品の利用や購入が必ずしもゴールではありません。利用・購入を行ってくれた顧客にリピーターやファンになってもらうために、CRM(顧客関係管理)の視点が必要です。
MAツールは、業務の自動化やリードの獲得、受注確度を上げていくナーチャリングに重きをおいて設計がされています。顧客の購入履歴やコンタクト管理を得意とするCRMツールとは得意領域が異なるので、MAツールとCRMツールの相互の連携を図ることが欠かせません。あわせてCRMツールもチェックしておきましょう。
3. 総合的な機能 or ひとつの機能に特化しているもの
MAツールは、「統合型」と「特化型」に区分できます。
統合型のMAツールは、リードの獲得からナーチャリング、リード管理まで幅広く利用でき、多機能なのが特徴です。一方の特化型のMAツールは、リードの獲得やエンゲージメントの向上など特定の領域に強みを持ちます。
どちらの方が優れているということはありませんが、自社がどの領域に課題を抱えているのかという点に照らし合わせながら、ツール選びを行いましょう。
4. BtoBとBtoCのどちらが向いているか
MAツールは、「BtoB向け」と「BtoC向け」に設計されたものに分かれています。BtoB向けのツールは、展示会やイベントの受付管理など名刺管理ツールなどとの連携が可能なものが多くなっています。
一方の、BtoC向けのツールは、非常に多くの見込み客の一元管理ができ、消費者の興味関心に合わせたOne to Oneマーケティングをサポートしてくれます。自社の扱っている製品やサービス、ビジネスモデルを加味しながら、最適なものを選ぶ必要があります。
また最近では、toCとtoBの双方に対応しているサービスも多く展開されているので、複数のサービスや製品を扱う場合などはそちらも検討すると良いでしょう。
5. サポートの内容
MAツールは効果的に運用すると、売上アップや工数の削減など非常に大きな恩恵を受けることができる反面、運用には高度な知識が必要なケースも多いため、ベンダーの適切なサポートを受ける必要があります。
特に自社に初めてMAツールの導入を行う場合には、手厚いサポートが期待できるツールを選定することが大切です。ツールの中には海外ベンダーが提供するものもあり、日本語でのサポート対応が受けられない場合があります。
各MAツールの機能を比較していく上で、サポート体制に関しても必ず確認をするようにしましょう。
代表的なMAツール
導入実績の多い代表的なMAツールの機能についてみていきましょう。製品の特徴や実績と共に、自社課題にマッチしたツールなのかをしっかりと見極める必要があります。
Marketo Engage(マルケト エンゲージ)

世界の6,000社が が採用しているというMAツール「Marketo Engage(マルケト エンゲージ)」。MAツールに必要な機能が十分に備わっているとともに、顧客とのエンゲージメントの向上に力を入れた一貫性のあるプラットフォームが特徴です。
- 向いている取引形態:BtoBとBtoCに限らない、顧客とのエンゲージメントの実践が目的
- 多様なチャネルに対応:〇
- 統合型 or 特化型:統合型
- 他システムとの連携:〇
- サポート体制:無料と有料のサポートが充実
- 費用:要問合せ
SHANON MARKETING PLATFORM

デジタルとアナログの顧客データを統合管理できるMAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」。国内の導入実績は900社以上、キャンペーン実績は22万件以上を誇ります。
リードジェネレーションやリードナーチャリングに特化した機能が含まれており、継続的な顧客抽出を可能にするスコアリング機能、キャンペーン機能も充実しています。
- 向いている取引形態:BtoBとBtoCの双方に対応
- 多様なチャネルに対応:〇
- 統合型 or 特化型:統合型
- 他システムとの連携:〇
- サポート体制:提案から設定、コンサルティングまでトータルサポートが可能
- 費用:要問合せ
SATORI

国内で900社以上が導入している国産のMAツール「SATORI」。通常のMA機能に加え、匿名の顧客にもアプローチできる「アンノウンマーケティング」機能を搭載しており、Webメディアの集客に強いことが特徴です。シンプル設計で直感的に操作しやすいため、MA運用経験がない担当者でも安心して利用できます。
- 向いている取引形態:BtoBとBtoCの双方に対応
- 多様なチャネルに対応:メールが中心
- 統合型 or 特化型:特化型(リードジェネレーション)
- 他システムとの連携:一部のみ
- サポート体制:オンラインサポートデスクや無料の利活用セミナーを用意
- 費用:148,000円~/月 (別途初期費用が必要)
人気のMAツール11選|マーケティングオートメーションツールの特徴や機能を紹介
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
投稿 MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 顧客からの評価を包み隠さず伝えることで、顧客ロイヤリティーの向上に寄与 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>《背景・課題》
・顧客の声は対面でお伺いすることが中心だったが、なかなか本音を聞き出せていなかった
・社内で顧客の声を報告する際にも、営業からは定性的な情報が多く、「本当のお客さまの声」が把握しにくかった
《ITreview利用の効果・メリット》
・フィルターのかからないお客さまの生の声が把握できるようになった
・レビューによって、自社で強く認識していなかった自社製品の良さに気付かされた
・ヘルススコアにレビューの有無を追加し、顧客の健康状態を細かく把握できるように
・レビューを顧客からの評価として新規営業の際に活用
自社製品に対するレビューをプロダクトの改善に生かすだけでなく、マーケティングやセールス、カスタマーサクセスの活動にどう生かしていくかは、ITreviewをフル活用する上で重要なテーマ。確かにITreviewでは「これまで聞けなかったようなお客さまの声が聞ける」「プロダクトの改善点が明確になった」という、声そのものにメリットを感じられているユーザーは多いが、一方で、レビューとしていただいた声を自社の活動にどう生かしていけばいいのか、レビューの活用法を思案されているケースは少なくない。
そんな時に参考になるのが、国産MA(マーケティングオートメーション)の「SHANON MARKETING PLATFORM」(以下SMP)を提供するシャノンのレビュー活用事例だ。
同社は、顧客とのエンゲージメント指標としてヘルススコアに「レビューの有無」を追加、顧客の声の広範囲なカバレッジに成功したとして、ITreview 2019 Customer Voice Leaderを受賞。
「ヘルススコアの項目の1つに加えるだけでなく、顧客に対する次の打ち手を的確なものにするために、レビューを役立てています」と語るマーケティングソリューションセールス部 兼 アカウントセールス部 部長 角田雄司氏へ、同社が率先して行っているレビューの活用法を詳しくお伺いした。
対面だけでは拾いきれない声が聞きたい。ITreviewでは、営業では拾いきれないお客さまの生の声が聞ける
――ITreview導入以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?
角田氏: 今までは、既存のお客さまへの活用支援を担当しているアカウントセールス部のカスタマーエンゲージメントマネージャーが中心となってお客さまの声を対面でお伺いしていました。それ以外に、東京と宮崎にあるカスタマーサポートセンターで、日々お客さまのサポートをしながら、お声をいただくことをしています。
3カ月に一度のペースで、いただいた声を社内の各部署へ上げていき、機能面や使い勝手に関するご要望は、プロダクト側の製品企画部に渡したり、お客さまへの対応のことであればカスタマーサポートへリレーしたりしています。

株式会社シャノン バイスプレジデント マーケティングソリューションセールス部 兼 アカウントセールス部 部長
――その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?
角田氏:対面では声をお伺いする営業が目の前にいますから、気を使ってなかなか言いにくいこともあるかなと。使い勝手や、UIをこうしてほしいなど、そういった声は拾えるのですが、本当に全部拾えているのか、対面ではなかなか難しいなとは感じていました。社内で報告をする際にも、定性的な情報が多く、本当のお客さまの声というのが把握しにくくなってしまうという課題もありました。
――より多くの声を集めるためにITreviewをご利用いただいているということですね。それまで対面で集めていた声と、ITreviewに書かれた声の違いは何か感じますか?
角田氏:営業が拾いきれないお客さまの生の声が把握できるようになりました。直接伺っていた時は、営業担当が帰社してからヒアリング内容を入力するので、文章が短く端的になりがちでしたが、ITreviewの場合、お客さまが私たちの製品のことを思いながら書いてくださっているので、文章も長く、内容が把握しやすい。その違いはあると思います。
また、1つ1つレビューを見ていると、製品の良さとして自分たちの認識があまりなかったこと、例えば営業から導入サポート、そしてカスタマーエンゲージメントマネージャーへの引き継ぎがとてもスムーズだという声をいただき、私たちとしては当たり前のこととして実践していることでも「こんなところも評価していただいているのか」と、気付かされることもありますね。
ヘルススコアにレビューを活用。また、新規営業でもレビューを活用し、ユーザーからの評価を包み隠さず伝えることが、さらなる顧客ロイヤリティーを生む
――貴社は、どんなメリットを感じてITreviewのPremiumプランを選択されたのでしょうか?
角田氏: ITreview Grid Awardの「High Performer」 の称号やレビューそのものを二次活用できるのは、もちろん有償プランのメリットだと思います。それ以上に私たちがメリットだと感じているのは、レビューの投稿者が、どちらの企業に所属されているかが分かること。投稿企業が分かれば、こちらにストックしているご支援履歴とひもづけて、この企業はこういう使い方をしている、だからこういうご意見が出る、ということがすぐに把握できる。その後のフォローも素早くできる。どなたかが分かることが、有償プランの一番のメリットだと感じています。

――貴社は、ヘルススコアにレビューの有無を追加されていますよね?
角田氏: お客さまとのエンゲージメント指標として、ヘルススコアにレビューの有無を追加しました。レビュー内容は関係なく、書かれているかどうか。手厳しいご意見でも、レビューを書かれているということは私たちのMA製品に期待していることの表れだという判断で、ヘルススコアの項目の1つに加えています。
ヘルススコアとは、このお客さまのここが悪いということを見つけるものではなくて、健康か、健康でないかを把握するものだと捉えています。ヘルススコアによって、このお客さまは健康的に使っていらっしゃるのか、ちょっと注意が必要なのか、不健康なのかを把握する。その観点でお客さまを分けて、活動内容や次の打ち手を変えています。また、レビューの内容によっては、それが健康なお客さまでも、注意が必要なお客さまでも、局所的に対処しなければいけないこともあります。
――ヘルススコアやプロダクト改善に生かすこと以外に、レビューをどのように活用されていますか?
角田氏: 新規のお客さまへの提案資料の中に、ITreviewのURLやレビュー内容を盛り込んで、お客さまの声が今こうなっていますということをお伝えしています。「実は、High Performerをいただいています」「今シャノンはこのぐらいのご評価をいただいています、一度ITreviewをご覧になってください」とお伝えしています。
当然そこには、ご要望や手厳しいご意見なども包み隠さず入っていますから、シャノンのMA製品の良さを、部分的には少しもの足りないといった内容も含めてご理解いただくためにレビューを活用しています。
ITreviewを見ていただいて、もの足りなさを分かっていただいた上で買っていただくことも、ある意味大事なことだと私は思っています。包み隠さずお伝えすることで会社の姿勢を分かっていただき、それが長いお付き合いにもつながります。完璧な製品があるとは思っていないので、もの足りないところも分かって買っていただくというのは、さらなる顧客ロイヤリティーなのかなと思います。
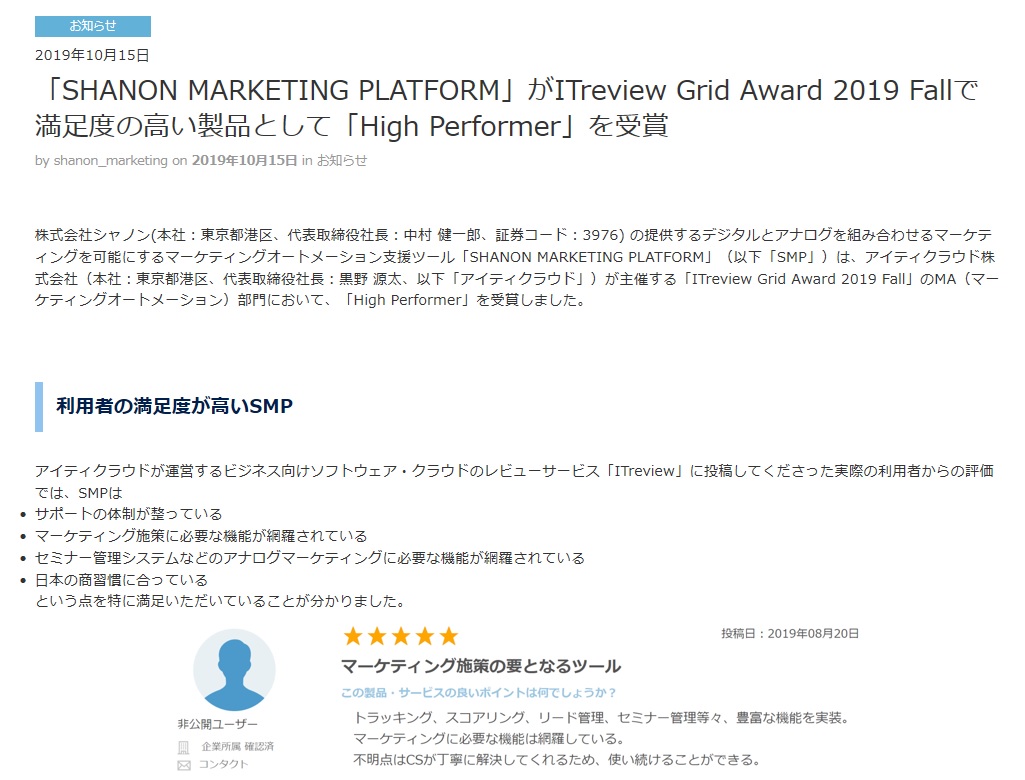
――これまで投稿された中で、印象に残っているレビューは?
角田氏: サポートが良いとご評価いただいているレビューが多いです。ほとんどのお客さまが書いてくださっているという印象がありますね。
あと、同じUIでも、「すごく分かりやすい」とおっしゃるお客さまもいれば、ちょっと分かりづらい、使いづらいとおっしゃるお客さまもいる。やっぱり人それぞれだなと改めて思いますね。
どちらかに振れるというのは難しいのですが、UI改善のウェビナーをやる、オンラインでUI・UXの賢い使い方サポートを提供するといった施策も考えられます。ITreviewのレビューが、施策を考えるための材料になっているのです。
――レビューを増やすために工夫されていることはございますか?
角田氏:営業担当やカスタマーエンゲージメントマネージャーが直接お客さまへ働きかけています。ただし、お客さまの書きたい気持ちを喚起させる程度に止めています。あまり強くプッシュしすぎると、「シャノンが良い評価を書いてと言っている」と受け止められてしまう懸念があるからです。あくまでも、良いも悪いも評価して頂き、今後に生かしていきたいと。と伝えています。
レビューによる受注率の変化などをデータ化、テキストマイニングを活用したデータ化構想も
――ITreviewの活用方法について、今後さらに構想されていることがございましたら、お聞かせください。
角田氏: まず、ITreview単体の効果が数値として取り切れていないので、2~3カ月後に一度データを取りたいと思っています。ITreviewでの取り組みによって、例えば受注率がどう変わったか、お客さまのロイヤリティーがどう変わったか、そういったものをデータとして取りたいと考えています。そのデータを分析することで次の一手が生まれてくると思うのです。
データ化は本格的にやると、テキストマイニングツールなどを使って……ということになるのかもしれません。AIや機械学習を使って、レビューに書かれたいろいろなワードでデータ化するのも面白い。こんなワードがあるレビューを書いてくださったお客さまは平均3年使っていますなど、そんなデータが取れれば、マーケティングや営業の施策を立てやすいですよね。ただ、今私たちの自力で行うには、人手がかなり必要です。それをどうするかが、大きな問題ですね。
――最後に、ITreviewに対してのご要望やご期待などをお聞かせください
角田氏: 先ほどお話したテキストマイニングのサービスを提供していただければ、人手の問題も解決しますし、とてもありがたいです(笑)。また、レビューをトランザクションとして私たちのMAに取り込んで、新規顧客へのマーケティングに生かせるようになれば、さらに良いですね。SFAやCRMに連携して、顧客情報を一元管理できるとなおうれしい。近い将来、ITreviewに連携機能が加わることを大いに期待しています。

投稿 顧客からの評価を包み隠さず伝えることで、顧客ロイヤリティーの向上に寄与 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 満足度の定量把握から”顧客支持が高い”というブランドの形成、競合製品の分析まで―― は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>《背景・課題》
・営業やカスタマーサクセスのメンバーがヒアリングしたお客さまからの声や満足度は人づてに集まってくるが、定量的に把握できていなかった
・直接、声を寄せていただけないお客さまの意見は聞けていなかった
《ITreview利用の効果・メリット》
・顧客満足度の定量データが取得できるようになり、お客さまの満足度がより細かく具体的に把握できるようになった
・競合製品のレビューから各社の強みを再確認できた。満足度の競合比較では、評価点が低い項目もあり、改善すべきポイントが明確になった
・ITreview Grid Award の称号をWebサイトに掲載、展示会でもボード掲示するなど顧客支持が高いというブランドを形成、リード獲得につながった
カスタマーサクセスの展開において、ユーザーコミュニティーの立ち上げに取り組むSaaSベンダーは少なくない。そんな時、多くのベンダーがモデルの1つとするのが、ユーザー同士が盛んに意見交換し合う「Marketo」が運営するユーザーコミュニティーだ。
関連記事:Marketoのユーザーコミュニティーは、なぜ盛り上がるのか?コミュニティーを牽引する“マルケトチャンピオン”に、その理由と本音を聞いた
「このユーザーコミュニティーの熱量を、ITreviewへも展開できれば……」と構想を語るのは、アドビ システムズ 株式会社 マルケト事業担当 マーケティング本部 シニアカスタマーエクスペリエンスマネージャーの森山裕之氏だ。ITreview Grid Award MAカテゴリーにおいて、4期連続で「Leader」の称号を持つMAツールのMarketo Engageは、レビュープラットフォーム「ITreview」をどのように活用して成果を創出しているのか。また今後の活用法は? ITreview 2019 Customer Voice Leader を受賞した森山氏に詳しくお伺いした。
顧客満足度を定量データとして把握。ITreviewの活用で、顧客からの評価がより具体的で、客観的に
――ITreview活用以前、貴社は、顧客の声をどのように収集していらっしゃいましたか?また、その中で、どのような課題感をお持ちだったのでしょうか?
森山氏: 営業やコンサルティング、カスタマーサクセスのメンバーがお客さまと接する場面は多かったので、それぞれが活動する中で、直接ご意見やご要望はいただいていました。非常に満足いただいているという手応えはありましたが、人づてに集まってくるので、定量的に、かつ、客観的に満足度を把握することが大きな課題ではありました。
また、あまり声を寄せていただけないユーザーの意見は聞けていなかったというのも課題として認識していました。
――顧客満足度を定量的に把握したいというのが、ITreviewを活用するきっかけになったというわけですね
森山氏: はい。一般的なアンケートによる顧客満足度調査も2019年から始め、それにあわせて、ITreviewを使わせていただくことにしました。ITreviewを活用することで、より客観的な顧客満足度の定量データが取得できるようになり、さらにお客さまの満足のポイントがより細かく具体的に把握できるようになりました。
例えば、総合評価では他のMA製品より高い満足度をいただいている場合でも、使いやすさなど1つ1つの評価項目で他社と比べて高いのか低いのかを把握できるため、まだまだ改善の余地はあると感じています。それに関連したレビューも書かれているので、改善すべきポイントがより明確になったのは、ITreview活用の大きなメリットだと思っています。
私たちの製品は、ファンになってくださる方、好んで使ってくださる方がとても多いので、日頃からうれしいコメントはたくさん寄せられます。でも、Marketo Engageではなく他のプロダクトを選んだお客さまは、なぜそちらを選んだのかということがこれまで十分には分からなかった。それがITreviewに掲載されている競合製品のレビューを見ていくと、競合製品を選んだ方はこんなポイントを評価している、そのポイントを私たちはなぜ評価してもらえなかったのか、ということが非常に客観的に見えるようになった。それはとてもありがたいと感じています。

アドビ システムズ 株式会社 マルケト事業担当 マーケティング本部
シニアカスタマーエクスペリエンスマネージャー
――競合他社のレビューをご覧になって、どんなことが印象的だったでしょうか?
森山氏: 改めて、各社の強みが違うなと気付かされたというはあります。匿名顧客のフォローアップに便利だというレビューが多い製品もあれば、展示会などイベントのフォローアップに役立つとレビューされている製品もある。それであれば、私たちのMarketo Engageではこういう機能を提供していますということをちゃんとお伝えすれば、競争力のある価値を提供できると感じました。
私たちがお客さまに対し伝え切れていないことが分かってきて、ツールを使いこなしていただくための支援を強化しなければいけないことに気付かされました。
Grid Awardの称号をバナーとして二次活用――新たなリード獲得につなげ、顧客支持が高いという製品ブランドを形成
――貴社はPremiumプランにてITreviewを活用されています。どんなメリットを感じてこのプランを選ばれたのでしょうか?
森山氏: ありがたいことに、Marketo Engageは、ITreview Grid Award MAカテゴリーにおいて、4期連続で「Leader」 の称号をいただいておりますが、Premiumプランの中に、Grid Awardなどの称号をバナーとして二次活用できるというのがあります。それをお客さまへのアピールに使うことで、新たなリード獲得につなげていく。そこが有償プランのメリットだと思います。
私たちはマーケターから高い評価を得ている証としてGrid Awardの称号をWebサイトにバナー掲示するほか、展示会などのイベントでもボードとして作り、デモPCのすぐそばに掲示しています。その場で対応しているメンバーからは、短い時間での説明では、口頭でさまざま説明するよりも、レビュープラットフォームにおいて「Leader」のポジションをいただいていますというのが、端的にMarketo Engageのポジションを伝えやすいという声をよく聞きます。
有償プランのメリットは、リード獲得につなげられる、私たちのアピールに使えるというところだと思います。
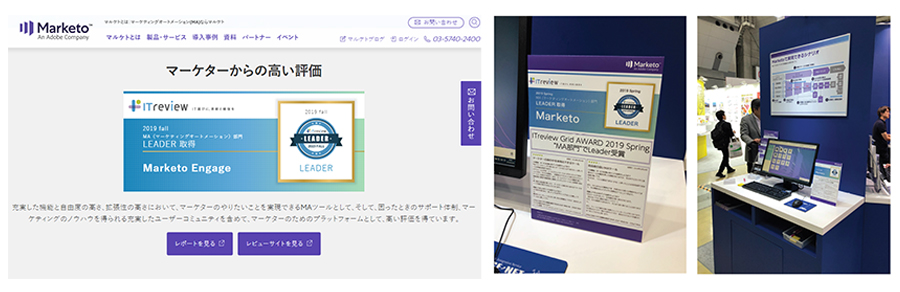
――Grid Awardなどの称号をバナーとして二次活用することでリード獲得につなげ、顧客支持が高いという製品ブランドを形成されているということですね
森山氏: そうです。主には新規顧客向けのアピールに活用していますが、既存のお客さまにも、私たちの事例記事とあわせてレビューをご紹介するケースもあります。ITreviewのレビューはみなさん、本当に正直に書いていただいているので、お客さまにも正直に伝わりやすいというのはあると思います。Marketo Engageを使いこなして満足している人はどのような成果を出しているのか、どのような点を評価しているのか、その点をお客さまに感じていただける材料の1つになっていますね。
――ITreviewに寄せられたレビューそのものを二次活用していく予定はありますか?
森山氏: それも考えています。各業界のユーザーがこのように使っているというレビューがもう少し集まればレビュー集のようなものを作りたいなと思っています。
例えば、もっと金融業界のお客さまを増やしたい場合、金融業界の他のユーザーがこのように活用してこう評価していますというレビューを事例と一緒に提供できるとより強いかなと思っています。レビューをピックアップしてLPを作れる「リファレンスLP」機能も使ってみたいと思っています。

ユーザーのレビューに、先輩ユーザーが答える。ユーザーコミュニティーの熱い対話をITreviewでも実現したい
――レビューとして寄せられた顧客の声に対して、返信されていますか?
森山氏: やりたい、やるべきだと思っているのですが、まだできていないのが実情です。きちんと体制を作って対応していきたいと考えています。
今、構想としてあるのは、私たちのオンラインのユーザーコミュニティーで盛んに行われているお客さま同士の熱い対話が、ITreviewのレビュー上でも実現できないかということです。ユーザーのレビューに対して、先輩ユーザーが答えるような、そんな世界。
ありがたいことに、Marketo Engageのユーザーコミュニティーでは、あるユーザーが「こういう場合はどうすればいい?」と投稿すれば、他のユーザーがすぐに「うちではこのようにしている。」と実体験をもとにした解決策を示してくれる。そんなユーザー同士の活発な対話が日々繰り広げられており、「熱量のあるユーザーコミュニティーがあるから」とMarketo Engageを選んでくださるお客さまも少なくありません。
ただ、それはユーザーに閉じたもので、まだユーザーでない方は見ることができません。ITreviewという誰からも見えるオープンな場所で、ユーザー同士が対話しこういうやりとりがされている、ユーザーがユーザーにアドバイスをしている、ユーザーでない方もそこに質問できる、そしてまたユーザーが答える。そういう世界が構築できると、ユーザーコミュニティーの外にいる見込みのお客さまにとって、Marketo Engageはこういう使い方ができる、こういうユーザーがいる、使える人はこのくらいのレベルで使いこなしているといった全体像が広く見える。ITreviewをそういうプラットフォームに持っていけたら、私たちが直接伝えるより、Marketo Engageの強みを実感していただけるのかなと思います。
――それは、熱量のあるユーザーコミュニティーを持つ貴社ならではの、とてもいいアイデアだと思います。ITreviewの新しい活用法として、ぜひ実現してください。
森山氏: はい。ITreviewを見れば、Marketoユーザーの熱量が分かるというのが理想かなと思います。MAというツールは、自社の目的に合った使い方ができるのかということが他のITツールと比べてもかなり重要で、それがなかなかWebサイト上の情報だけでは分かりにくいという悩みもありました。
よく飲食店の口コミなどでも「結婚記念日で使えますか?」という質問に、私が使った時にはこういうふうにアレンジしてもらえました、すごくいいレストランですよとか利用者が答えている。そういうのを見ると安心して使えますよね。そういったことがITreviewで見える、ユーザー以外の人たちにも見えるというのは、私たちが出せない価値の提供かなと思います。

投稿 満足度の定量把握から”顧客支持が高い”というブランドの形成、競合製品の分析まで―― は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 マーケティングオートメーションが失敗する理由とは?原因や成功ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、MAツールはベンダーによって使える機能や特徴が異なるほか、マーケターによるシナリオ設計や検証などの作業が必要となるため、うまく活用できず導入に失敗するケースも少なくありません。
本記事では、MAツールを導入するメリットや、導入する上で失敗を防ぐために事前にチェックしておきたいポイントを解説していきます。導入コストや労力を無駄にしないためにも、自社で活用できるMAツールを見極めましょう。
MAを導入するメリットとは?
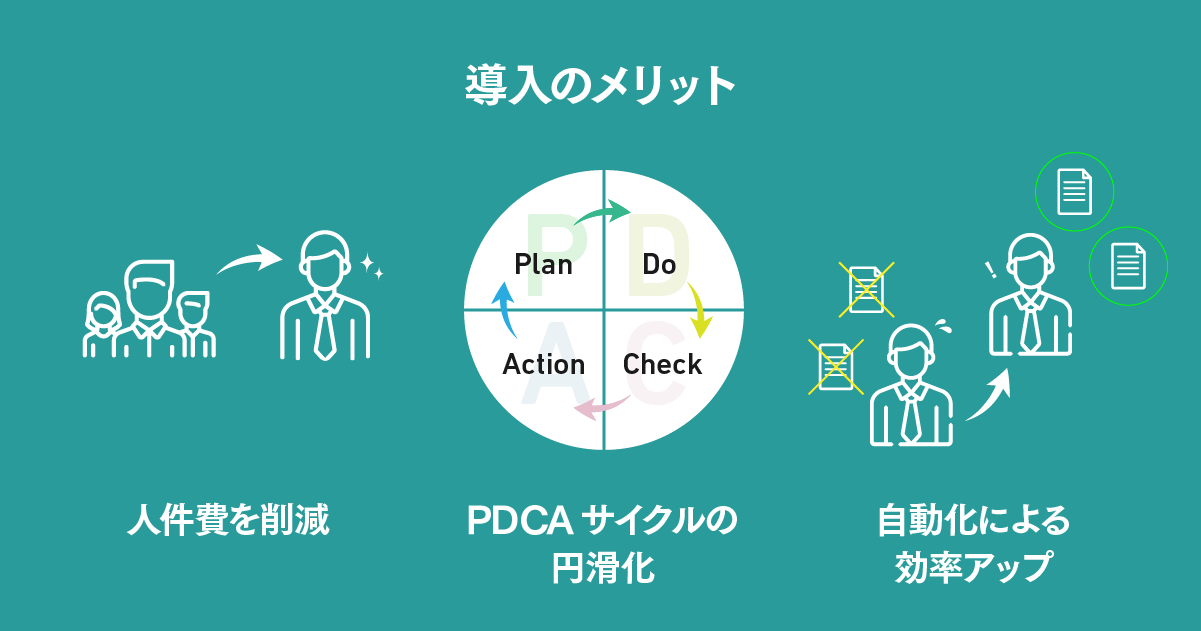
MAツールの導入を始める前に、まずは導入後に得られるメリットをしっかりと理解しておく必要があります。MAツールは正しく運用することによって、以下のようなメリットを受けることができます。
1. 見込み客の集客や育成の作業プロセスを自動化
MAツールを導入する最大のメリットは、Webサイトの作成やフォーム作成、SNSとの連携といった見込み客(リード)の情報を収集するためのプロセスから、メール配信やキャンペーンの実施といった見込み顧客を育成するまでのプロセスまでを自動で行える点です。
これまで手作業で行っていたプロセスの自動化を図ることによって、より効率的なマーケティング活動を行うことができます。
2. 顧客情報の一元管理
従来は、リードジェネレーション(見込み客の獲得)〜リードナーチャリング(見込み客の育成)〜リードクオリフィケーション(見込み客の選別)といった各プロセスごとにツールが分かれており、データの管理や効果測定にコストがかかっていました。
こういった課題を解決するために、MAツールを導入し顧客情報の一元管理を行うことによって、情報の管理にかかるコストや工数を削減できます。データの「入力」や「更新」といった作業を短縮し、分析業務や新たなマーケティング施策に時間を割くことも可能にします。
3. 見込み客の興味関心に合わせたアプローチ
獲得した見込み客を育成する「リードナーチャリング」は、現在のマーケティングには欠かせません。MAツールを導入することで見込み客の自社製品への関心度や適合度を分析し、セグメントを行うことができます。
MAツールの導入により、それぞれの見込み客に対して、適切なタイミングでメール配信や広告配信といった適切なアプローチができ、結果、購入意欲を高め「商談の成立」や「売上の向上」に繋げることができます。
4. 営業部門との情報共有がスムーズになる
MAツールに蓄積された顧客リストを営業部門と共有することによって、効果的に営業活動を進めていくことができます。MAツールには、「メール開封率」や「サイト閲覧履歴」といった見込み客の行動データに基づき、受注確度を得点化するスコアリング機能を搭載したものがあります。
このようなスコアリング機能をうまく活用することによって、「どの見込み顧客にアプローチするべきか」といった情報をセールス部門と共有することができます。社内の営業リソースを最大限活かす為にも、MAツールの導入は欠かせません。
MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方
MAツールの導入が失敗してしまう理由
MAツールは、導入すれば必ずしも十分な効果を得られる訳ではありません。実際にMAツールを導入したけれども、うまく活用することができずに「費用対効果に見合わない」「機能が多くて使いこなせない」といった声もマーケターの方から多く聞かれます。
こうした失敗事例の多くには、2つの共通する点が見られます。
理由その1. MAツールを導入する目的が明確でない
MAツールはマーケティング活動を全て自動化してくれる万能なツールというイメージがあるため、事前準備を行わずにとりあえず導入をしてしまったといったケースが多々あります。
しかし、MAツールの導入で効果的に成果を出すためには、まずは自社の課題をしっかりと理解し、その課題解決のためにMAツールを最適に利用する必要があります。
業種や業態、また各企業によって直面する課題は異なりますので、「どの課題を解決したいのか」を十分に検討してから、MAツールを導入しましょう。
理由その2. MAツールを効果的に運用できる人材がいない
MAツールは近年急速に導入が進められているツールです。また、製品によって搭載している機能が異なります。そのため、ある程度の専門性を有している人材でなければ効果的に運用することができません。
MAツールの導入と同時に、しっかりと運用できるスキルを持った人材の確保や組織作りを進めていくことも大切です。
MAの導入に失敗しないための4つのチェックポイント
MAツールは、単に導入するだけで効果が得られるものではありません。目標となる成果を出すためには、導入の目的を明確にすることや、事前準備が必要となります。
以下の項目をチェックしながら、導入前に必要な作業を再確認しましょう。
1. 具体的な目標を設定する
業種や業態などによってMAを導入する目的は異なります。自社に合ったMAツールを選定するためには、まずは目的を明確化し、具体的な目標設定が重要です。
BtoB企業では、リードの育成やCRMとの連携が重視される傾向があるのに対し、BtoC企業ではリード獲得や顧客との継続的なコミュニケーションが求められるなど、業態によって必要な機能が異なるため、それぞれ目的に合ったMAツールを選びましょう。
そして、最終的な「商談の成立」「売り上げ向上」「顧客エンゲージメントの獲得」といった目標を設定するとともに、「受注率を30%上げる」などの具体的な数値目標を立てることも忘れてはいけません。
2. カスタマージャーニーマップを作成する
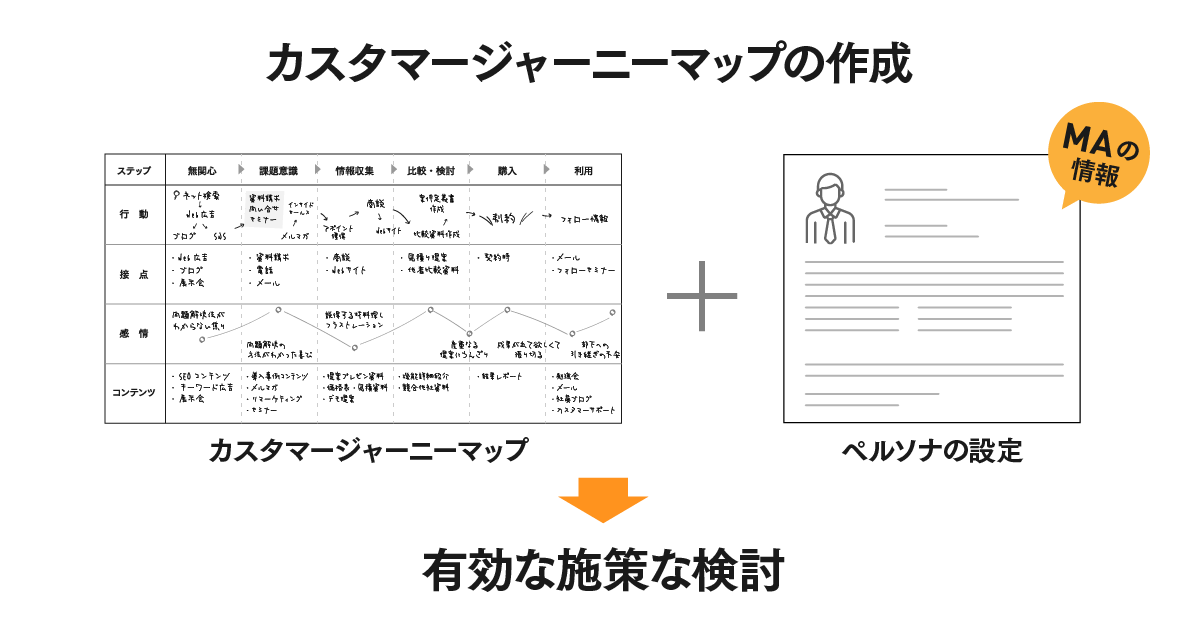
顧客が最終的なゴールに至るまでの購買プロセスを把握できるカスタマージャーニーは、MA導入において重要なポイントの1つです。
どのようなルートで接点を持ち、体験によってどのような行動や心理に至るのかを可視化することで、求められるコンテンツやアプローチするタイミングを想定できます。これにより、顧客に伝わりやすい精度の高いシナリオ設計が可能となります。
なお、カスタマージャーニーマップ作成時には、MAなどで収集したデータを基にしたペルソナ設定も重要です。マーケティング部門と営業部門と認識を共有しながら、有効な施策を検討しましょう。
MA活用に欠かせない!カスタマージャーニーの作成方法・効果・注意点とは
3. コンテンツを作成する
MAで利用するコンテンツが十分でない企業は、カスタマージャーニーを参考に必要なコンテンツを制作しましょう。認知からゴールに至るまでの段階によって適切なアプローチは異なるため、各フェーズで適切なコンテンツを提供する必要があります。
業種や業態によって必要なコンテンツは異なりますが、リード獲得段階では、オウンドメディアやメルマガ配信などが挙げられます。リード育成段階では、ソーシャルメディアなども有効です。デジタルメディアのみならず、企業パンフレットや製品資料などのオフラインのコンテンツも検討しましょう。
4. 運用体制を整える
MA導入後の運用体制が整備されているか確認しましょう。
MAによる継続的な効果を得るためには、PDCAを繰り返して実績を重ねることが重要です。MAツールを操作できるスキルを持った人材を用意できるか、営業部門とのスムーズな連携ができるかなど、組織的な体制を整えてフローを改善することも大切です。
社内で対応できない場合には、一部を外注するというのも方法の1つです。
継続的な成果を生むMA活用を
MAツールを生かしたマーケティング活動には、目標設定やコンテンツ制作などのさまざまな事前準備が必要です。アプローチするべきターゲットを把握し、効果的なコンテンツを提供できるよう、まずは自社のリソースを十分に確保しておきましょう。
そして、実践したものの効果が得られない場合には、分析によるボトルネックの発見も欠かせません。分析データを基に改善を重ね、より精度の高いシナリオを設計することで、成果を生み出すMA活用の実現につながります。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
投稿 マーケティングオートメーションが失敗する理由とは?原因や成功ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MAのシナリオ設計の4ステップ|マーケティングの精度を上げるコツとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>MAツールを効果的に活用していくためには、「誰に」「いつ」「何を」「どのように」アプローチするのかといった、シナリオの設計が大切です。
本記事では、マーケティングにおけるシナリオとはそもそも何か、シナリオはどのように作るべきかについて解説します。
MAについての解説はこちら
シナリオとは?
シナリオとは映画やドラマなどの「脚本・台本」を意味する言葉ですが、マーケティングにおいては見込み客の獲得から製品の利用・購入に至るまでの「筋書き」のことを指します。
適切なシナリオを設計できれば、「誰に(Who)」「いつ(When)」「何を(What)」「どのように(How)」アプローチすべきかという最適なコミュニケーション方法を導き出せるようになります。また、設計したシナリオをベースにすれば、MAツールを最大限活用できます。
MAツールにおけるシナリオの作り方
STEP1:ターゲットを決める
まずは、企業のマーケティング活動の基礎となる「誰にアプローチすべきか」を決めましょう。誰とコミュニケーションを取るのかを明確に決めないと、MAツールを活用する・しないに関わらず、適切な施策を打つことができません。
ターゲットを決める工程では、顧客をいくつかの軸に分類して考えるのが一般的です。
ライフサイクル軸
企業と顧客の関係性を軸に分類する方法です。「見込み客」「新規顧客」「一般顧客」「優良顧客」「休眠顧客」などに区分されます。
顧客行動軸
「メールをクリックした」「セミナーに参加した」「商品を購入した」など顧客の実際の行動をもとに分類する方法です。MAツールのWebトラッキング機能を活用することによって、管理することできます。
顧客属性軸
年齢や性別、職業や年収といった顧客の属性によってカテゴライズする方法です。
STEP2:アプローチするタイミングを決める
ターゲットが決定したら、続いてアプローチをするタイミングを決めましょう。例えばメルマガの配信であれば、「何時に送るべきか」「顧客がどの行動をとった後に送るべきか」「どれくらいの頻度で送るべきか」といった視点で考えることが大切です。
適切なタイミングで有益な情報を届ければ、顧客の自社製品への関心度や購入意欲を高められます。しかしその反面でアプローチのタイミングや頻度を誤ると、顧客の嫌悪感に繋がり、メール配信の停止・アプリの削除といった受信拒否を招いてしまいます。
MAツールを用いて効果検証を繰り返しながら、最適なタイミングを見極めることを意識しましょう。
STEP3:提供するコンテンツを決める
顧客のライフサイクルやアプローチのタイミングによって、提供するべきコンテンツの内容は異なります。
例えば、かつては製品の購入や利用をしていた「休眠顧客」に対しては、明確なベネフィットを提示するインセンティブコンテンツを配信することによって、再び自社製品への関心度を高めることができます。
新しく自社製品の購入や利用を始めた「新規顧客」に対しては、ブランドの紹介や自社製品の詳しい使用方法といったコンテンツを配信することによって、企業への信頼度やリピート率を高めることができます。
このように、全ての見込み客に対して同じコンテンツを配信するのではなく、ターゲットやタイミングを見極めて、適切な内容にチューニングすることが大切です。
STEP4:チャネルを決める
顧客とのコミュニケーション方法(チャネル)は、オンライン・オフライン含めて、多数あります。「メール配信」「Webサイト」などが代表的ですが、その他にも「DM(ダイレクトメッセージ)」や「店頭・営業」「セミナー」と多岐に渡ります。
自社のリソースやコストなども加味して、効果的なアプローチを行いましょう。
実名リードの獲得がシナリオ設計の鍵になる
質の高いシナリオ設計を行い、効果的MAツールを活用するためには、実名でのリード獲得が重要になってきます。氏名や年齢、所属や年収といった詳細なリード情報を獲得することによって、適切なリードナーチャリング(育成)が可能になり、最終的に大きな効果をあげることができます。
オフラインでの獲得
オフラインでの代表的なリードジェネレーションには、展示会やセミナーが挙げられます。主にB to B企業におけるリード獲得に活用されています。
展示会では、自社のブースに立ち寄った顧客と名刺交換ができるほか、ある程度興味関心を持った顧客と接点を持つことができるため、リード獲得につながりやすいといえます。
セミナーでは、参加申込書やアンケートにて企業名や担当者名などの詳細な情報を入手できるほか、共催セミナーでは自社だけでは集客できない顧客情報を得られるため、獲得した個人情報をMAツールに登録することにより、幅広いパターンのシナリオ設計に役立てられます。
効果的なシナリオには、下記のようなものが挙げられます。
- 展示会の自社ブースで名刺交換をする
- ノベルティと引き換えにアンケートを実施する
- セミナーの最後にアンケートを実施する
オンラインでの獲得
顧客接点の多様化・複雑化により、オフラインだけでなくWebサイトなどのオンライン上のリード獲得にも注力する必要があります。Webサイト上の問合せフォームや資料のダウンロードなどで顧客の情報を入手し、見込み客の実名化につなげるというものです。
Webサイトでは、サイトの訪問者にとって興味関心のありそうな情報や、役立つ技術などを資料として無料でダウンロードできるように設計することで、ダウンロード時の無料会員登録などを経由して、リアライゼーションします。
また、入力後すぐに情報が表示される「見積もりフォーム」などのコンテンツを設置することで、見込み客の個人情報を自然に入手しやすくなります。
効果的なシナリオには、下記のようなものが挙げられます。
- 自社サイトでホワイトペーパーや有益な情報を無料で提供し、個人情報の入力を促す
- お得な情報やキャンペーンを受けられるよう無料会員登録を促す
- 無料相談や診断コンテンツを利用する際に個人情報の入力を促す
- 無料プレゼントの応募により個人情報の入力を促す
実名リード獲得で重要なポイント
WebサイトやSNSなどを利用して獲得した見込み客をリアライゼーションにつなげるには、上述したシナリオでの個人情報の収集が必要となります。しかし、より多くの個人情報を収集するためには、顧客ニーズの高い有益な情報を提供しなければなりません。
そのためには、入念なペルソナ設定によって顧客ニーズを具体化することも重要です。サイトに訪れた人が「どのような悩みを持っているのか」「どのような情報を得たいのか」を把握することにより、その課題を解決するためのコンテンツを用意できるようになります。
コンテンツの作成時には、入力フォームの設計やサイト内の導線、提供するコンテンツの内容などを考慮し、自然なステップで個人情報の入力を促しましょう。そうすることで、より多くの実名リード獲得につながるでしょう。
匿名顧客へのアプローチを可能にする「アンノウンマーケティング」とは
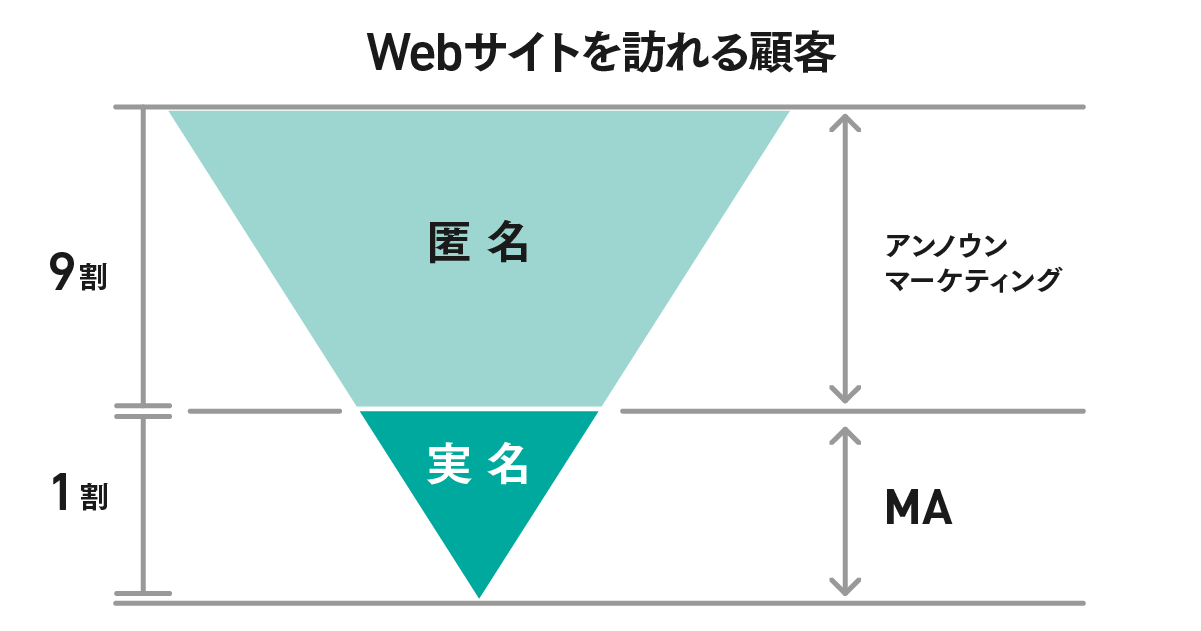
これまでのMAツールでは、実名化された顧客に対してのリードジェネレーションが一般的でした。しかし、実際に展示会に参加するなどのアクションを起こす顧客はごくわずかであるとともに、Webサイトを訪れる顧客のうち約9割が匿名状態であることから、従来のMAではアプローチしきれない匿名顧客が多いことが課題とされていました。
こうした課題を解消できるマーケティング手法として新たに注目されているのが、アンノウンマーケティングです。実名顧客に加えて匿名の見込み客に対しても情報管理・分析することで、リードジェネレーションを効率化し、多くの見込み客へリードナーチャリングが可能となります。
MAツールの活用にあたり、リードジェネレーションを強化するアンノウンマーケティングについても検討してみると良いでしょう。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
投稿 MAのシナリオ設計の4ステップ|マーケティングの精度を上げるコツとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MA活用に欠かせない!カスタマージャーニーの作成方法・効果・注意点とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、企業目線で作成するなどの適切なシナリオ設計ができていない場合、顧客ニーズに沿ったマーケティング施策が打てず、十分な効果が得られないかもしれません。 MAツールを効果的に活用するためにも、シナリオ設計の精度を高める「カスタマージャーニー」の設定が有効です。
本記事では、MAツールと関係性の深いカスタマージャーニーの重要性やカスタマージャーニーマップの作成方法、注意すべきポイントについて解説します。
MAについての解説はこちら
カスタマージャーニーとは
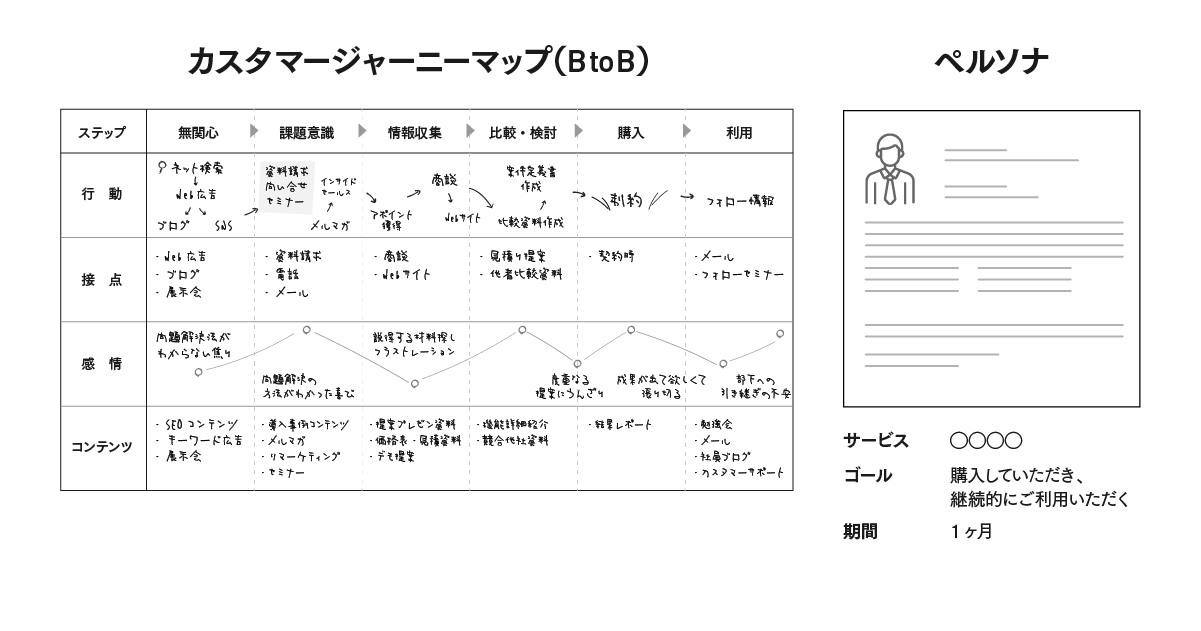
近年、マーケティングの手法として新たに役立てられるようになった「カスタマージャーニー」。直訳すると「顧客の旅」を意味しますが、マーケティング業界では“顧客が購買に至るまでの行き来のプロセス”を示します。
そして、購入までの行動や心理をストーリーに見立てて可視化したものを「カスタマージャーニーマップ」と呼びます。 業界や商材によって適切なフレームは異なりますが、認知から最終的なゴールまでをフェーズ化し、設定したペルソナの行動や思考の変化を時系列で図式化することで、適切なマーケティング施策を検討できます。
MAの効果を引き出すカスタマージャーニー
Webサイトに加え、SNSやブログなど、顧客接点が多様化するデジタル環境において、企業が顧客の行動を把握することは難しくなっています。最適な情報をタイミング良く顧客まで届けるには、各タッチポイントに効果的なマーケティング施策を講じなければなりません。
同時に、MAツールを用いる場合でも、どのタッチポイントでどのようなマーケティング施策を実行するのか、精度の高いシナリオ設計がオートメーション(自動化)の基盤となります。 カスタマージャーニーが重要といえるのは、こうした顧客ニーズが複雑化・多様化している環境において、顧客の行動や心理を理解するためです。
マーケターが「どのような行動や意識で購買に至ったのか」を把握することで、タッチポイントの洗い出しが可能となり、顧客に寄り添った情報提供ができます。
カスタマージャーニーの活用により得られる効果
MAツールのパフォーマンスを高めるカスタマージャーニー。常に変化する顧客の行動や心理を把握することで、継続的かつ有効なアプローチが可能となります。
カスタマージャーニーを活用することで、以下のような効果を得られます。
One to Oneマーケティングの実現
顧客の行動範囲が多様化・複雑化している現代では、顧客一人一人に沿ったマーケティングを実施する「One to Oneマーケティング」の重要度が高まっています。
MAツールの活用により顧客ニーズに合わせた個別のアプローチができますが、それらを活用するためには“顧客の行動を把握した精度の高いシナリオ設計”が不可欠です。
カスタマージャーニーを活用すれば、ゴールに至るまでの顧客の行動を意識できるため、必要な情報を最適なタイミングでアプローチできるシナリオ設計が可能となり、One to Oneマーケティングの実現につながります。
顧客ニーズの高いサービスを提供できる
カスタマージャーニーの注意点として、企業目線ではなく顧客目線で作成することが挙げられます。
マップ作成時には、つい自社が理想とする購買プロセスで作成してしまいがちですが、自社のファネルを意識した時系列を設定することや、各タッチポイントの行動や心情を顧客目線で考えることが重要です。
こうした顧客目線のカスタマージャーニーを作成することにより、「各タッチポイントでどのような行動をするのか」「体験によってどのような心理状態にあるのか」など、顧客全体の行動傾向を把握できます。 同時に、「どのプログラムに効果が出ないのか」「強化すべき点はどこか」などの課題発見につながります。
その課題に沿った新たなマーケティング施策を講じることで、顧客ニーズに寄り添った商品やサービスを提供できます。
カスタマージャーニーマップの作り方
MAツールを効果的に運用していくためにはもちろん、マーケティング部署内や社内全体で共通の認識を持つためにも、カスタマージャーニーマップを作成する必要があります。
ここからはマップの作り方についてステップごとに解説していきます。
STEP1:ペルソナを設定する
カスタマージャーニーマップを作る準備段階として、ペルソナ(理想の顧客像)の設定を行う必要があります。
想定したペルソナが、製品を認知するフェーズから製品の利用や購入に至るまでのフェーズを図式したものがカスタマージャーニーマップです。ペルソナがどのような行動をとるのか詳細まで想定できるように、できるだけ具体的に設定しましょう。
なお、ペルソナは必ずしも1人である必要はありません。複数のペルソナが想定される場合は、それぞれの顧客ニーズに沿ったカスタマージャーニーマップを作成しましょう。
ペルソナ設定に必要な項目
チーム内や部署内で共通の認識を持つためにも、ペルソナは具体的に設定しましょう。
以下にペルソナ設定に必要な項目例をまとめていますが、必ずしもこの項目に従う必要はありません。自社製品と顧客の関係性を加味して、項目を取捨選択してください。
| 属性 | 氏名・性別・年齢・職業・家族構成・居住地・年収・雇用形態 |
| パーソナリティ | 性格・価値観・こだわり・不安・コンプレックス・送ってきた人生 |
| ライフスタイル | 生活リズム・家族や周囲との関わり方・仕事への意識 |
| 興味や関心 | SNSの利用頻度・主要な情報源・コミュニティー |
STEP2:カスタマージャーニーマップの項目を設定する
ペルソナの設定ができたら、続いてカスタマージャーニーマップの項目を決めていきましょう。
項目とは、「ステップ」「行動」「接点」「感情」「コンテンツ」といったマップの縦軸に当たる部分を指します。
ペルソナや扱っている製品によって設定すべき項目は変わってきますが、一般的には以下のような要素が盛り込まれます。
- ステップ(タイムライン):購入や利用に至るまでの段階
- 行動:想定されるペルソナの具体的行動
- 接点:ペルソナとのタッチポイントやチャネル
- 感情:ペルソナのインサイト(思考)
- コンテンツ:フェーズごとにユーザーが求めるコンテンツ
カスタマージャーニーマップ作成の注意点
1. 企業側の願望をマップに反映しすぎない
カスタマージャーニーマップは、顧客の行動やインサイトをベースとして作成していくものです。企業側の「こう動いて欲しい」「必ずこう動くはずだ」といった願望を色濃く反映しすぎてしまうと、実態とはかけ離れたものになってしまいます。
MAツールの顧客データベースといったファクトに基づき、客観的な視点から作成していく必要があります。 また、マーケティング担当者のみではなく営業やカスタマーサポートといった、他の視点から顧客を観察することのできる人材と一緒に取り組むこともおすすめです。
2. マップのブラッシュアップを繰り返す
カスタマージャーニーマップは、一度作って終わりにしないことが大切です。
市場環境や消費者の興味・関心の移り変わりが早い現代において、古いカスタマージャーニーマップでは十分な効果を得られません。定期的にマップを更新する機会を設けて、バージョンアップを行う必要があります。
マーケティング活動をする上で気づいたことやデータベースに十分な顧客データのサンプルが集まった時点で、ブラッシュアップを行い、精度を高めていきましょう。
マーケティング施策を強化するカスタマージャーニー
MAツールと切っても切れない関係といえるカスタマージャーニーマップ。精度の高いアプローチを継続的に実施できるとともに、企業間で顧客に対する認識を共有できるという利点があります。
マーケティング部門では、企業内で「Web担当」「SNS担当」などのようにチームが細分化されているケースもあるため、全体的な顧客傾向を認識できていないこともあるでしょう。カスタマージャーニーマップを活用することで、「どの段階でどのようなアプローチが必要か」といった各チームの役割を認識・共有できるため、マーケティング部門が一丸となって効果的な施策を打てるようになります。
MAツールの精度向上に向けて、カスタマージャーニーを意識したマーケティング施策を検討しましょう。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
投稿 MA活用に欠かせない!カスタマージャーニーの作成方法・効果・注意点とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MA・SFA・CRMの違いとは?定義や導入目的を分かりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>消費者の購買プロセスがインターネットで完結する現代において、より効果的かつ的確にアプローチするには、ユーザーの心理を把握したインターネット上のコミュニケーションを構築しなければなりません。
こうしたデジタル環境下において活躍するのがMAツール、SFAツール、CRMツールです。混同される場合もありますが、基本的な定義は異なるため、それぞれの特徴を理解したうえで導入を検討しましょう。
本記事では、企業のマーケティング活動を支えるMAツールとCRMツール、そして営業活動を効率化するSFAツールについて、その定義の違いや機能について解説します。
MA・SFA・CRM、それぞれの違いとは

MA(マーケティングオートメーション)
MAとは、「Marketing Automation(マーケティングオートメーション)」の略で、マーケティング活動の自動化を意味します。リードの獲得から育成、管理を目的としており、見込み客に対して有益な情報を最適なタイミングで提供することで、購買意欲を高めることを目的としています。
一般的なマーケティング活動では、あらゆるチャネルからアクセスされるユーザーに対して、一人ひとりに最適な対応をすることは難しく、マーケターの作業が煩雑化してしまいます。そのため、可能性の高いリードを見逃す、ニーズに合ったアプローチができないといおった課題がありました。
MAツールの活用によって、見込み客のアクセス頻度や行動履歴、属性情報などを管理し、スコアリングによって可能性の高いリードを判別できます。これにより、顧客のニーズに合わせたOne to Oneマーケティングが実現します。
また、シナリオ設計によりメール配信などの業務を自動化できるため、リード獲得と育成に向けたプロセスを効率化できるのが特徴です。
MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方
SFA(セールスフォースオートメーション)
SFAとは、「Sales Force Automation(セールスフォースオートメーション)」の略で、営業活動を効率化するためのシステムを指します。MAツールで獲得・育成されたリード情報をもとに、商談状況を管理し、効果的に成約につなげることを目的としています。
従来は、営業担当者が個別に顧客情報や案件の管理をしていました。そのため、管理コストが発生してしまう、担当者間の情報共有ができないといった課題がありました。
SFAツールを活用することによって、案件のスケジュール管理や工数管理、売り上げレポートの作成を迅速に実行できます。また、営業部門内で情報を共有することによって、チームの機会損失を防ぎ、今まで取りきれなった商談の獲得や成約率の向上が期待できます。
SFAについての更なる解説はこちら
CRM(カスタマーリレーションシップマネジメント)
CRMとは、「Customer Relationship Management(カスタマーリレーションシップマネジメント)」の略で、日本語では顧客関係管理といいます。顧客との良好な関係を構築して管理することにより、顧客満足度や顧客ロイヤルティーの向上を図るためとして開発されました。
見込み客の獲得や育成に向けた継続的なアプローチを自動化するツールがMAなのに対し、CRMは既存顧客との有効な関係を築くための継続的なフォローに特化しています。
顧客の性別や年齢などの基本的な情報に加え、購買頻度や注文履歴などを細かく記録し、それらの情報をセグメント化することにより、セグメントごとの最適なフォローが可能となります。また、コミュニケーション履歴や購入履歴を管理できるため、営業活動にも役立てられます。
CRMについての更なる解説はこちら
各ツールの使い分け、導入目的や活用方法の違い
見込み客を獲得・育成するMAツール
MAツールが得意とするのは、見込み客に対するアプローチです。活用できる機能は、次の3つが挙げられます。
- リードジェネレーション(見込み客の獲得)
- リードナーチャリング(見込み客の育成)
- リードクオリフィケーション(ホットリードを営業部門へ引き渡す)
多くのリードを獲得するためには、一人ひとりのニーズに合わせたアプローチが理想です。見込み客の属性や行動によって求められるアプローチが異なりますが、MAツールの機能を活用したリードジェネレーションやリードナーチャリングによって効果的に見込み顧客の受注確度を高められます。
また、受注確度の高い顧客(ホットリード)に絞って営業部門に引き渡せるため、営業活動を効率化できます。
MAツールの主な機能
- 見込み客の行動をチャネル別に可視化
- 見込み客の属性情報をセグメント化し、最適なシナリオ設計が可能
- シナリオ設定によりアプローチを自動化
- 興味の高い顧客をスコアリング機能によって判別
- ホットリードを抽出し、営業部署まで連携
マーケティングオートメーション(MA)ツールの製品・ユーザー評価を比較する
商談情報を管理し、受注率を高めるSFAツール
SFAツールは、「顧客管理」だけでなく「営業履歴」「営業日報」「受注予測」といった情報を一元で管理し、営業の効率化を図ることができます。また、設定した営業目標と照らし合わせて現状の営業活動を分析することによって、企業の売り上げ向上に大きく貢献します。
Webサイトやランディングページなどオンラインでの見込み客の獲得が可能になり、営業一人あたりが対応する案件は増加する傾向にあります。そのため、かつては属人的に行うことができた商談状況の管理も今では難しくなっています。あわせて顧客の検討期間の長期化に伴い、以前の商談で得られた情報をもとに複数回のアプローチも必要です。
SFAツールの主な機能
- 製品やサービスごとに案件を管理
- 受注までのシナリオ作成
- 商談の日付や内容を管理
- 営業チーム内のスケジュール管理
- 受注予測による適切な予算管理
- 営業活動における分析や集計機能
顧客を育成し、リピーターを高めるCRMツール
一度商談に至った顧客と継続的な関係を築くためには、顧客満足度の向上が不可欠です。顧客がすぐに解約してしまう場合や、リピーターにつながりにくいという場合には導入を検討しましょう。
さまざまな物やサービスであふれている現代において、新規顧客を獲得することは困難であることはもちろんですが、継続的な顧客の確保や一度離れてしまった顧客を取り戻すことはさらに難しいといえます。
CRMツールは、ゴールに至った顧客情報を複数のセグメントに分けて管理できるため、クロスセル・アップセルなどのアプローチが可能です。例えば、顧客の誕生日に合わせて割引クーポンを配布する、期間限定のサービスを提供するなどのさまざまなキャンペーンも実施できます。
CRMツールの主な機能
- 会社名や電話番号などの顧客情報を管理
- 顧客情報をセグメント化し、それぞれに適切なフォローが可能
- 既存、新規顧客へのキャンペーン管理
- 顧客とのコミュニケーション履歴の管理
「MA」「SFA」「CRM」の相互連携でさらなる効果を得る
MAツール、SFAツール、CRMツールは、それぞれマーケティング活動における役割が異なります。MAツールは案件化前の見込顧客へのアプローチを得意とし、SFAツールは案件の効率化や受注、CRMツールは既存顧客の育成やリピート化を得意としています。
マーケティングや営業活動をより効率的かつ適切に進めるには、いずれか一つに絞るのではなく、相互のシームレスな連携が求められます。組織の体制や企業の課題によっても導入するべきツールは異なりますが、マーケティング部門と営業部門のつながりが重要視される現場においては、3つのツールが連携可能なものを導入することも検討しましょう。
また、自社のニーズを分析せず、目標を立てないままツールのみを先に導入してしまうのは危険です。それぞれのツールは、リード獲得や満足度向上などの利益向上を期待できますが、それらを最大限に活用するためには、各部門にとどまらない企業全体での取り組み(全体最適)が不可欠です。
マーケティング部門や営業部門、企画部門におけるニーズを把握し、どのような施策を打つべきか、アプローチ方法はどうするかなど、実際の分析データを考慮しながら戦略的に導入しましょう。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
投稿 MA・SFA・CRMの違いとは?定義や導入目的を分かりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MAが営業のムダを解決!マーケティングオートメーションが質の高い営業を創出する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そういった課題を解決する手段のひとつとして近年注目されているのが、マーケティングオートメーション(MA)です。マーケティング施策におけるさまざまな作業を自動化し、業務効率化を支援するツールとして多くの業界が導入を進めています。
本記事では、MAツールの活用と営業活動の関係について解説します。MAツールを効果的に活用してマーケティング施策の効率化を図り、営業活動のムダを解決しましょう。
MAツールと営業活動の関係
マーケティングと営業活動は同じフロー上にあります。そのため、マーケティングプロセスに弊害が出ると、その後の営業活動が非効率になることが懸念されます。
例えば、獲得した見込み客の情報や興味・関心を追求できず、不明瞭なリストを作成した場合、営業担当は確率の低い見込み客に対して営業を繰り返すこととなります。そうなると成約率が低下するだけでなく、成約につながる顧客の特徴をつかめないまま、また新たに可能性の低い顧客リストが作成されるといった非効率なサイクルが繰り返されてしまいます。
MAツールを導入すると、見込み客の獲得から精度の高いナーチャリングが実行できるため、可能性の高い見込み客のデータをピックアップし、営業部門へと引き継ぐことができます。これにより、マーケティング業務を効率化するだけでなく、ホットリードに絞った効率的な営業活動ができるため、商談アポ獲得や成約率向上につなげやすくなります。
マーケティングと営業活動の互いの質を高めるテクノロジーとして、MAツールは重要な役割を担っているといえるでしょう。
今、MAツールが注目されている理由
MAツールが注目されている理由として、まずはインターネット技術の発達が挙げられます。クラウドやプラットフォームの多様化といったインターネットの広がりから、インターネットで可能となるアクティビティが増加し、マーケティング施策において活用できる技術が多く開発されました。それにより近年は国内外のベンダーからさまざまなMAツールがリリースされ、需要も年々拡大を見せています。
また、これまで営業担当が顧客の入口となっていたBtoB企業も、Webサイトなどのオンラインが入口となることが一般的になりました。顧客はWeb上で製品の比較検討をし、選定後に初めて営業担当者にコンタクトを取るため、Web上でのマーケティングがこれまで以上に重視されるでしょう。
一人一台スマートフォンを持つ時代背景に伴い、デジタルテクノロジーを生かしたマーケティングがカギとなりつつある現代。MAツールを活用した強力なオンラインマーケティングは企業にとって不可欠となってきています。
MAツールの導入がムダな営業を解決
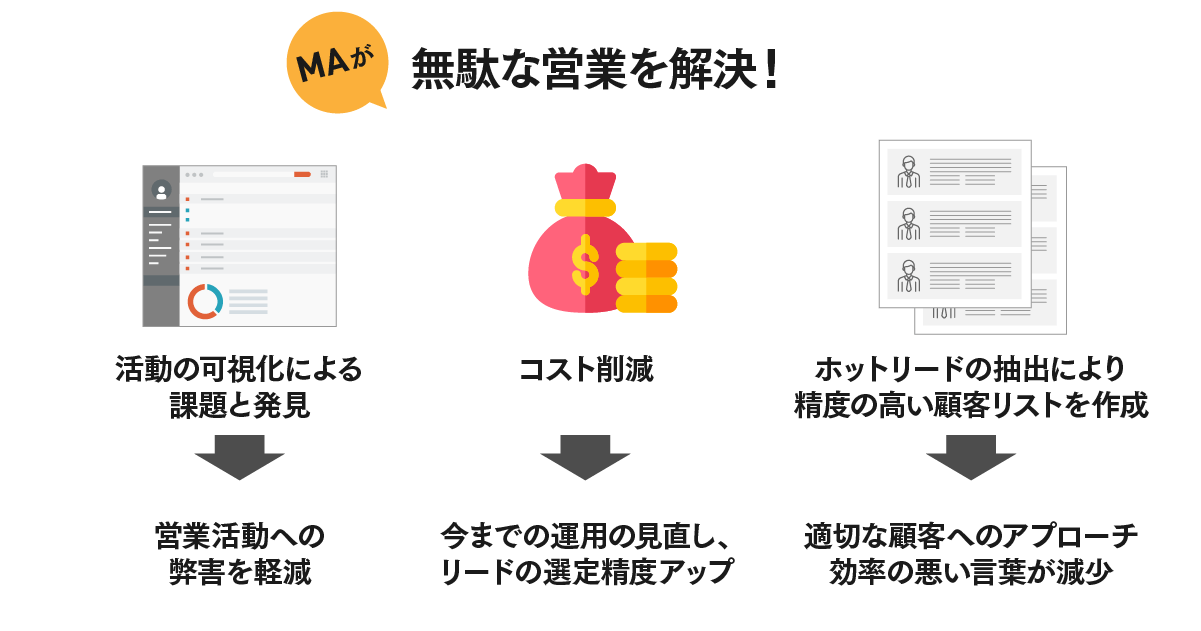
活動の可視化により課題を発見
さまざまな業務を自動化することにより、マーケティング活動における全体像を可視化できます。これにより、従来のマーケティングにどのような課題があるのか問題点を洗い出し、より精度の高いシナリオ設計が可能になります。リード獲得から育成までのマーケティング課題を改善できるため、質の高いリードを優先した的確な営業活動につなげられます。
コスト削減
メール配信やキャンペーン実施などの搭載された多様な機能を活用することで、大幅なコスト削減も期待できます。
例えば、アウトソーシングしていたセミナー参加後のフォローアップ作業もカバーできるなど、これまでの運用を見直しコストパフォーマンスを向上させることができます。フォローアップの頻度や内容を自社内で把握できるため、リードの選定精度もアップします。
精度の高い顧客リストを作成
ホットリード抽出機能により、より成約に結びつけやすい顧客リストの作成が可能です。スコアリングやWeb解析などの情報を基にホットリードを数値化し、今アポイントを取るべき顧客の洗い出しができます。これにより、やみくもに顧客を選ぶといった効率の悪い営業を改善できます。
営業活動を効率化する代表的なMAツール
Marketo Engage(マルケト エンゲージ)

(参照元:https://jp.marketo.com/)
全世界で5,000社以上の導入実績がある、アメリカ発のMAツールです。匿名の見込み客の獲得から顧客のファン化やリピートまでのマーケティング施策を一貫して実行できる統合型のプラットフォームです。
「アカウントベースドマーケティング(ABM)」という機能では自社にとって有望な見込み客を抽出し重要顧客にターゲットを絞ることが可能で、成約までのスピードが早まります。
こういった機能を効果的に活用することで、限られた営業リソースでも、多くの顧客をカバーできます。今までアプローチしきれなかった顧客にもフォローが行き渡るので、売上への貢献も期待できます。
Marketo Engageのユーザーレビュー・口コミを見る
Salesforce Pardot(セールスフォース パードット)

(参照元:https://www.pardot.com/)
世界的シェアを誇るセールスフォース・ドットコム社の提供するMAツール「Salesforce Pardot」。SFA(営業支援ツール)とのシームレスな連携が可能で、販売促進に大きく貢献します。
各営業担当者の顧客へのメール履歴や商談情報とリンクして管理できるなど、マーケティング活動と営業活動を一貫して実行できます。
今まで担当者が属人的に管理をしていた顧客とのやりとりを可視化することによって、営業の優先順位が付けやすくなります。
Salesforce Pardotのユーザーレビュー・口コミを見る
SATORI(サトリ)
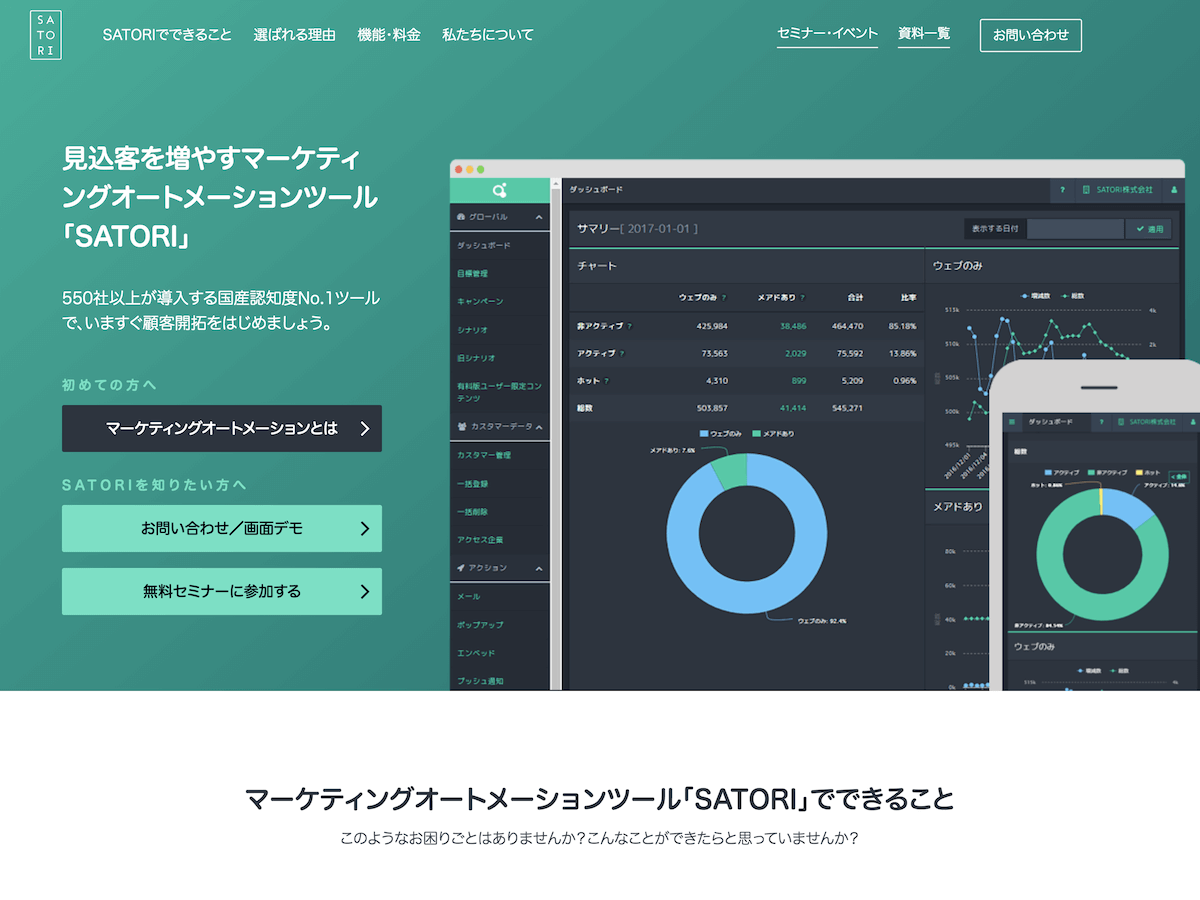
(参照元:https://satori.marketing/)
株式会社SATORIが提供する純国産のMAツールです。国産ならでは、サポート体制の充実と日本のビジネス環境にマッチした設計が行われているのが特徴です。
ランディングページの閲覧履歴やメルマガのクリック率などから見込み客をスコアリングする機能と、購入意欲の高い見込み客を抽出するホットリード抽出機能を搭載。適切なタイミングで適切なターゲットにアプローチすることができます。
リードを適切に管理することで、今までアプローチしきれなかった休眠顧客への接触も可能になります。スコアリング機能を利用し、優先順位を付けることで効率よく商談創出に結びつけることができるでしょう。
マーケティングの効率化は営業活動の効率化
人手だけでは賄いきれない集客やナーチャリング、分析などの施策は、MAの導入によって業務を大幅に効率化できます。マーケティング部門において育成した可能性の高いリードを営業部門に引き渡すことにより、営業担当の顧客リスト作成までの作業が効率化され、結果的に営業活動の質を高めることができます。
MAツールを導入する際は、マーケティング活動から営業活動までの長い流れを考慮し、相互に効率化を図れるツールを選ぶことがポイントです。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
投稿 MAが営業のムダを解決!マーケティングオートメーションが質の高い営業を創出する理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MAでマーケティング業務を自動化!マーケティングオートメーションの活用事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>メールの自動配信やスコアリングなどの多種多様な機能がありますが、企業の課題や目的によって必要な機能は異なるため、導入前に活用方法を理解しておく必要があります。
本記事ではMAツールを活用することによって自動化できる業務について解説します。
MAツールで自動化できる業務
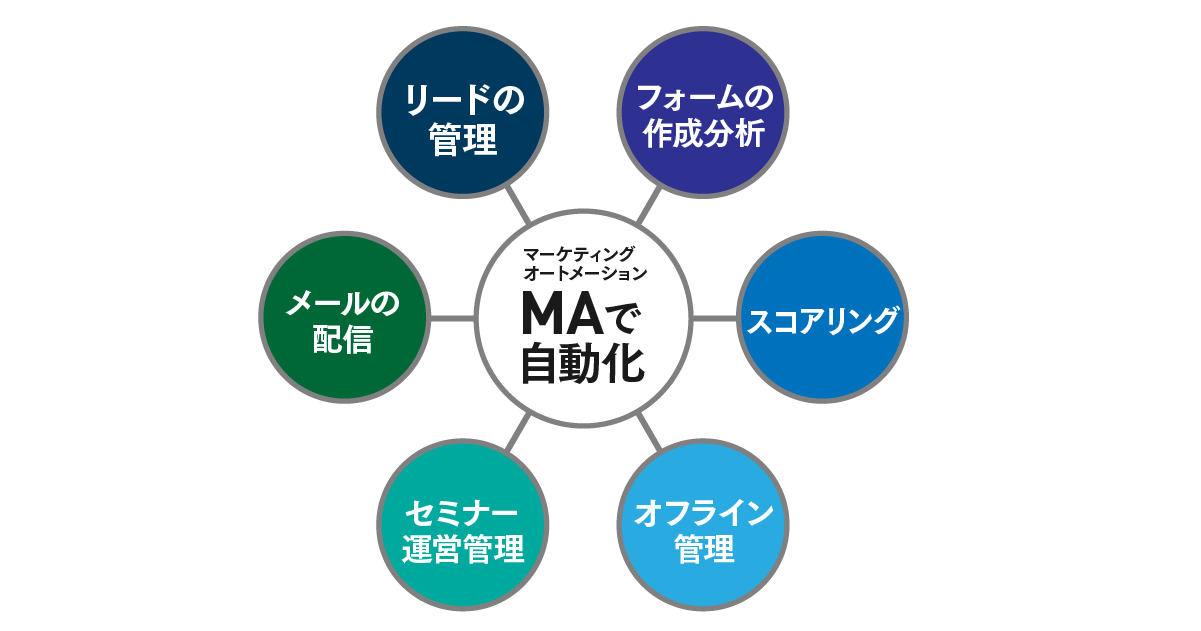
見込み客管理
メールの開封率やWebサイトの訪問履歴などから、見込み客(リード)の情報を自動的に収集できます。各見込み客のステータス状況や行動パターンが把握できるため、その後のナーチャリングやスコアリングに役立てられます。また、これらの情報を見込み客の情報として一元管理することも可能です。
これまではExcelや台帳といったアナログな方法で見込み客の管理をしている企業も多くありましたが、顧客の数が増えるほど管理が複雑になります。データ上で自動的に管理にできることで、可能性の高い見込み客を逃さず、管理漏れや記入ミスといったヒューマンエラーを減らすことにもつながります。
また、従来担当者レベルで管理していた見込み客情報を社内で一元管理することで、チーム全体が顧客の興味・関心やニーズを把握できます。購買行動につながる最適なアプローチを効果的に打ち出せるため、成約に至る可能性も高くなります。
フォーム作成・分析
MAツールは、お問い合わせフォームや申し込みフォームの作成、それらから集まった情報の集計や分析といった業務を効率化できます。
手動でフォームに入力された情報を管理することも可能ですが、その情報を他のマーケティング業務と連携させ、活用できるという点がMAツールを利用する大きなメリットといえます。
例えば、フォームに入力された情報をそのまま見込み客情報として保存し、保存が完了した時点から顧客のWeb行動解析を実行します。見込み客が何に興味・関心があるかを可視化させることで、より効果的なアプローチが可能になります。
他にも、流入分析による広告効果の確認や、メール配信機能との連携も可能なため、フォーム作成・分析の自動化でさらに精度の高い集客効果を期待できます。
メール配信
獲得した見込み客に対するアプローチ方法として有効なメールマーケティング。従来では、顧客の行動を予想して配信内容やスケジュールを組んでいたため、期待値がまだ低い段階でもメールを配信してしまうケースが見られました。
配信済みのメールが未開封である場合は、購入意思が低い顧客と考えられるため、続けてステップメールを配信しても十分な効果を発揮できないことがあります。
MAツールを活用すればメールの開封率やWeb行動履歴を可視化できるため、顧客の属性や特徴などをカテゴライズし、顧客ニーズに応じた適切なメールを個別に自動配信できます。顧客が望むタイミングかつ、顧客にとって有益となる内容のメールを配信することにより、購買意欲を高められます。
さらには、フォーム作成機能で作成したフォームから申し込みがあった場合に、完了メールなどの配信業務を自動化できます。これまで手動で行っていたメール配信をはじめ、獲得したリードへの自動ステップアップメールなど、メールマーケティングによる効率的なナーチャリングが実施可能です。
スコアリング
スコアリングとは、Webページへのアクセス状況などから見込み客の期待値を点数化し、顧客の優先順位を明確にするための機能です。点数によって成約の可能性が高い見込み客を選別することにより、点数のステージに応じた適切な広告やコンテンツを打ち出しやすくなります。また、精度の高いスコアリングは、より成約に結び付きやすいホットリードを抽出できます。その情報を営業部門へとスムーズに引き継ぐことで、営業効率を高められるという効果もあります。
手動で顧客一人一人の行動を把握してスコアリングすることは非常に難しく、リード数が多い場合には個別の人的アプローチが困難になります。そこでMAツールを活用すれば、膨大な顧客の行動をスコアリングによって可視化できるほか、メール配信やキャンペーンなどを自動で実施できます。手動での作業工数をカットできるだけでなく、有望な顧客の取りこぼし防止にも有効といえるでしょう。
セミナー運営管理
セミナーの運営・実施には、フォームの作成やメールの返信、ドキュメントの送付など、工数のかかる業務が多いですが、これらの業務もMAツールによって自動化できます。
申込フォームから入力された情報を自動で分析し、それに対して最適なステップメールを配信します。出欠状況やセミナーに参加する顧客のデータも一元化管理できるほか、開催前のリマインドメールや、参加のお礼とその後のアプローチメールなどの自動配信が可能です。
セミナーの企画から運営に関する業務プロセスの多くを自動化することで、運営中に手の回らなかった作業に注力できるようになり、業務全体の効率とクオリティの向上が期待できます。
MAツールの導入事例
事例1:メール配信の業務効率化(株式会社Faber Company)
株式会社Faber Companyは、検索エンジン最適化のためのサポートやサイト制作、リスティング広告代行業などを行う会社です。以前から、自社セミナーの参加者などにメルマガの配信をしていましたが、営業活動をより円滑に行うためにも仕組みとして管理する必要性を感じ、MAツール「SATORI」を導入しました。
MAツールを導入したことによって、社内に「リードを管理して、しっかりと顧客を育成していく」という認識が浸透し始め、成果が出るようになりました。初期はMAツールを利用し、メールの配信を実施。リード情報からセグメントに分け、それぞれのターゲットに対して最適な内容にすることによって、クリック率が向上しました。
事例2:セミナー運営管理の業務効率化(SB C&S株式会社)
SB C&S株式会社は、IT関連のサービスやソリューションを提供しています。部門によっては、年間で100回以上のセミナーやキャンペーンの実施があり、告知サイトの制作や申し込みフォームの作成などを2週間ほど工数をかけて毎回ゼロベースから行っていました。
またセミナーの開催そのものは外部業者に委託していたため、部門に管理運営のノウハウが蓄積されず、コストもかかってしまうという悪循環が発生していました。
2009年よりイベントやセミナー管理に強みを持つMAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」を導入。Webページ自動作成やフォーム作成の機能を活用することにより、2週間の工数を要していたセミナー告知サイト制作を、わずか10分程度に短縮することに成功しました。
また、MAツールで一元管理されたセミナー参加者の情報に基づき、営業部門も集客の最適化を実現。年間数百万円のコスト削減にも成功しています。
自動化できる業務をうまく活用し売り上げアップへ
MAツールによってさまざまな業務を自動化できるため、マーケティング担当者の作業効率を高め、顧客へ質の高いアプローチを実現できます。しかし、必ず業務を自動化しなければならないというわけではありません。
効果的にMAツールを活用するには、まずは自社の現状を把握したうえで、必要性の高い機能を活用することが重要です。リード数が多い場合には、スコアリングやナーチャリングに注力する必要がありますが、リードが十分に獲得できていない場合には、WebサイトやSNSなどを視野に入れた集客に力を入れるべきでしょう。
自社のニーズや目的に応じて自動化するべき機能にはMAツールを活用し、人手が必要な作業にはマーケターを配置するなど、バランスをうまく図りましょう。
投稿 MAでマーケティング業務を自動化!マーケティングオートメーションの活用事例 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 マーケティングオートメーションの仕組みとは?効率化の重要ポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、ここ数年で急速に普及したツールであるため、どういった仕組みであるかをしっかり理解できていないという方も少なくないはずです。
本記事では、MAツールの仕組みと効率化できる業務について解説します。MAツールをよく理解することで、円滑な導入とより良い運用を目指しましょう。
企業への導入が進むMAツール
MAは「Marketing Automation」の略で、直訳すると「マーケティング自動化」を意味します。見込み客の集客〜管理〜育成の各フェーズの業務を自動化できます。
ツールによってさまざまな活用方法がありますが、メール配信をはじめ、見込み客の情報を基にカテゴライズするなど、リードの獲得やナーチャリングに役立てられます。
マーケティング担当者の業務効率向上だけでなく、顧客のニーズに応じて個別のアプローチができるため、売り上げ向上や成約率向上といった効果が期待できます。
顧客との接点がデジタル化している現代において、MAツールは企業マーケティングでの必要性が高まっており、市場は年々拡大しています。クラウドなどのインターネット技術の発達に伴い、今後も伸び続けることが予想されています。
MAツールの仕組みは「マーケティングファネル」によるもの
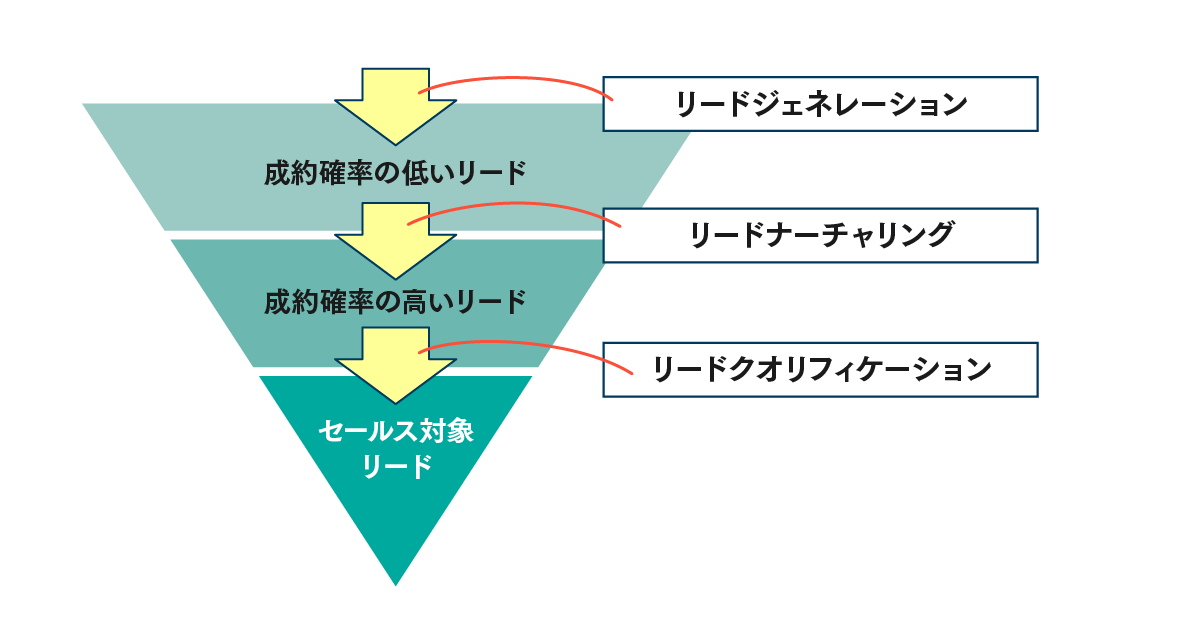
MAツールの仕組みは「マーケティングファネル」という考え方に基づきます。ファネルは日本語で「漏斗(じょうご)」を意味します。見込み客を集める時点から営業の成約までの一連の流れを図式化すると、漏斗のような形になるからです。
リードジェネレーション(見込み客の情報獲得)
マーケティングファネルの第1ステップとなるのが、見込み客の集客です。見込み客の獲得にかかる名刺交換や資料請求など、多様な接点から顧客を獲得することを「リードジェネレーション」といいます。MAツールでは、リードジェネレーションで獲得した顧客を細かな属性に分けて管理することが可能です。
リード管理機能今まで手作業で行っていた顧客情報の管理をCSVファイルなどをMAツールにインポートすれば、一括管理できます。また、属性や特定のアクションを行ったユーザーにタグ付けをすることによって、効果的な広告運用やメール配信を可能にします。
ランディングページ・フォームの自動作成機能見込み客の獲得に効果的なランディングページやお問い合わせページを、自動作成できます。情報の更新や変更、画像アップロードも一括で行えます。
リードナーチャリング(見込み客の育成)
獲得した見込み客に対してメールなどでコミュニケーションを図り、見込み客にとって有用な情報を提供することによって、顧客の購買意欲を高めます。これを「リードナーチャリング」といいます。
リードナーチャリングは中長期的なアプローチが必要な場合に有効的とされており、各アプローチに対する顧客の反応やWeb行動履歴などから顧客の興味関心を知ることもできます。
メール配信ユーザーの属性ごとに、One to OneのHTML/テキストメールを配信できます。また、メールの内容をあらかじめ設定しておけば、ユーザーのアクションごとに自動配信も可能です。結果として円滑なユーザーフォローが実現し、担当者の負担を減らすことができます。
リードクオリフィケーション(絞り込み)
育成した顧客からさらに成約に結びつきそうな顧客を絞り込む作業が「リードクオリフィケーション」です。
リードクオリフィケーションの手法としては、「スコアリング」と呼ばれるアプローチすべき顧客に優先順位を付ける機能を活用します。優先順位を設定することにより、受注確度の高いリード情報や効果的なアプローチのタイミングが明らかになります。
このようなリード管理工程を経て、最終的に営業成約までつなげる一連の流れがマーケティングファネルの考え方です。
スコアリング機能ランディングページの閲覧やメールのクリック、セミナーの参加など見込み客のアクションに点数を付けることによって、自社製品の購入意欲を可視化することができます。
ホットリード抽出機能スコアリング機能で点数化した見込み客の中で、特に購買意欲の高い層のみを抽出することができます。営業部門へのスムーズなリードの受け渡しや営業リソースの見直しができます。
MAツールで効率化できる業務
MAツールは、煩雑な作業を自動化し業務の効率化を図ることができます。マーケティングファネルの流れのうち、ほとんどの業務がMAツールによって自動化できるため、顧客管理やメール配信といった作業を効率化できます。また、成約につながる可能性の高いホットリードを抽出できるため、営業部門に引き渡す顧客リストの精度が向上し、営業効率を高められます。
活用できる機能としては、リードジェネレーションで獲得した顧客データの一元管理や細かな属性の分配、メルマガの自動配信、トラッキングによるリードナーチャリング活動の自動化が挙げられます。さらに、リードクオリフィケーションにおけるスコアリング作業も、機械操作によりミスなくスピーディーに完了するため、これまで人員を使い計算・表作成を行っていた工数を省くことができます。
作業の自動化により担当者が本来の業務に集中できるようになるため、より質の高いマーケティング効果が期待できるようになります。
アイデア次第で活用方法が広がる
MAツールはアイデア次第でさまざまなビジネスシーンにて活用でき、BtoBだけでなくBtoCのマーケティングにも有効です。
しかし、MAツールの機能は多様なため、その仕組みや効率化させる方法を理解しておかなければ、上手く活用できないことがあります。自社の課題に応じて、必要性の高い機能を検討してから導入しましょう。
投稿 マーケティングオートメーションの仕組みとは?効率化の重要ポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 マーケティング効率化に欠かせない!MA導入に欠かせない3つの機能とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、MAツールを導入するメリットや、導入にあたり押さえておきたい3つの機能について解説します。
MAとは?
MAとは「マーケティングオートメーション(Marketing Automation)」の略で、直訳すると「マーケティングの自動化」を意味します。
これまで手動で行っていたマーケティング業務の一部を自動化することで、業務効率やコンバージョン率の向上を図るためのツールです。
インターネットの普及により、顧客との接点はオンラインへと移行しています。そのため、顧客へ効率的にアプローチするには、顧客一人一人のニーズに応じたマーケティング施策が重要といえます。しかし、インターネット上で収集される顧客データを全て把握することは難しく、手動かつ個別にメールやコンテンツを打ち出すことは困難といえるでしょう。
そこで活躍するのがMAツールです。見込み客の情報を管理できるほか、顧客の行動履歴や属性に応じてメール配信などのアプローチを自動化できるため、作業担当者の負担を大きく削減します。可能性の高い見込み客を逃すことなくアプローチできるため、マーケティング運用効率の改善が期待できます。
代表的な機能には、Webサイトを用いた見込み客の集客をはじめ、獲得した見込み客に対するメール配信やスコアリング、収集した顧客情報の一元管理などが挙げられます。
MAツールを導入するメリット
MAツールを自社に導入する最大のメリットは、売り上げの拡大を図ることができることにあります。ただ、売り上げの拡大といっても、具体的に自社のマーケティング環境にどのように作用するのかイメージできない場合もあると思います。
ここではMAツールの導入前に、いま一度、導入するメリットについて理解していきましょう。
- 見込み客の集客や育成の作業を自動化
- 顧客情報の一元管理
- 見込み客の興味関心に合わせたアプローチ
- 営業部門との情報共有がスムーズになる
MAツール導入のメリットは、上記の4つに分けることができます。
まずは、新規顧客の獲得から、スコアリングやナーチャリングといった一連のマーケティングプロセスを自動化ができる点です。
従来は、一連のマーケティングプロセスをそれぞれ手作業で行っていました。それをMAツールを導入して全て自動化すれば、今までかかっていた工数やコストの削減につながります。また、MAツールでは見込み客の情報を一元管理するため、シートの管理や更新といった作業を減らし、業務の効率化を図ることもできます。
そして売上の拡大に大きく作用するのが、見込み客の興味関心に合わせたアプローチが可能になる点です。Webサイトの閲覧頻度やメルマガの開封率によって、自社製品への関心度や適合度を分析することができます。これにより見込み顧客に対して、最適なタイミングで最適なアプローチが可能になり、CVへの確率を高めることができます。
そして最後に、自社製品の受注確度を計測できるスコアリング機能によって、限られた営業のリソースを効果的に使えるようになります。その結果、相談の獲得や成約といったコンバージョンが得られる可能性が広がるでしょう。
MAツール導入の目的を明確化しよう
MAツールは、見込み客の認知から自社製品の利用や購買までに至るプロセスを自動化できる便利なツールであることは間違いありません。しかしながら、何のために導入するのかといった明確な目的がなければ、効果的な運用を行うことはできません。MAツールの導入に失敗しないためにも、まずは導入前に自社のマーケティングにおける課題をできるだけ詳細に洗い出すことが大切です。
例えば、ランディングページの制作やお問い合わせフォームの作成などに時間や工数がかかってしまう場合は、これらの機能を実装したMAツールの選定が必要です。
また、見込み客の購買意欲を高めたい場合は、メルマガ配信などリードナーチャリングの機能が充実しているツール選びが大事です。
何となく効果が出そうだからとMAツールを導入するのではなく、自社課題から逆算した導入や運用が必要不可欠です。
MAツールの導入にあたり必要最低限な3つの機能
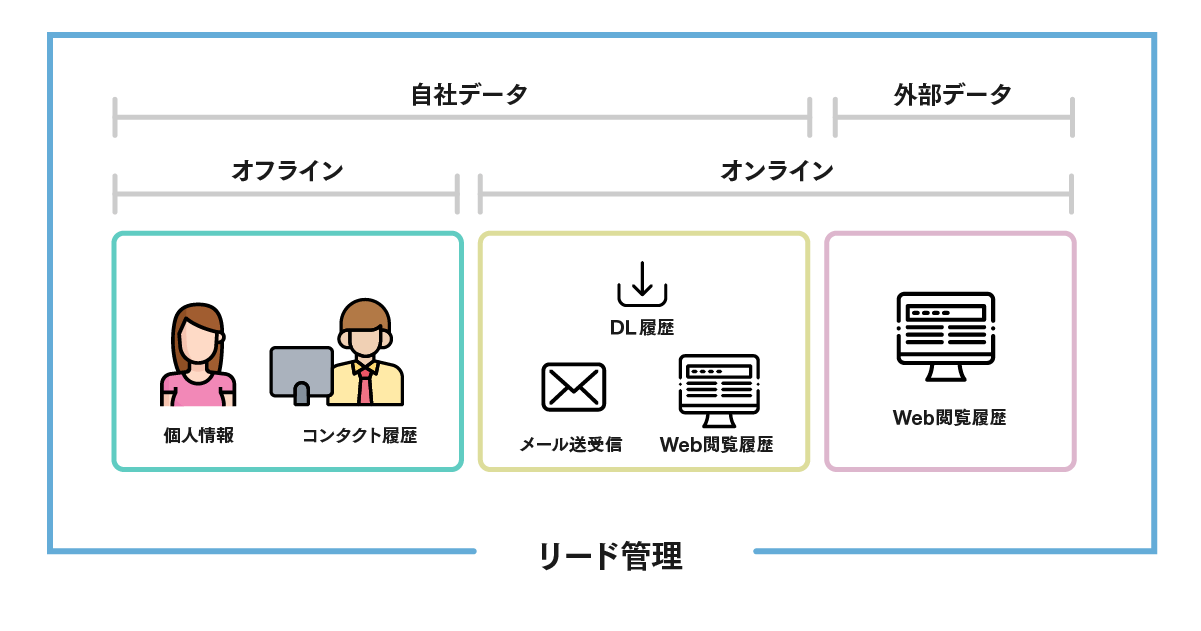
1. リード管理機能
営業や展示会、セミナーなどオフライン・オンラインを問わず獲得した見込み客を一元で管理する「リード管理機能」は、MAツールの運用において必須といっても過言ではありません。
これまでリード管理は、顧客を獲得した営業担当者やマーケティング担当者がそれぞれで対応していましたが、社内で一元管理することにより、リード対応の取りこぼしやアプローチの重複を防ぐことができます。
2. リードナーチャリング機能
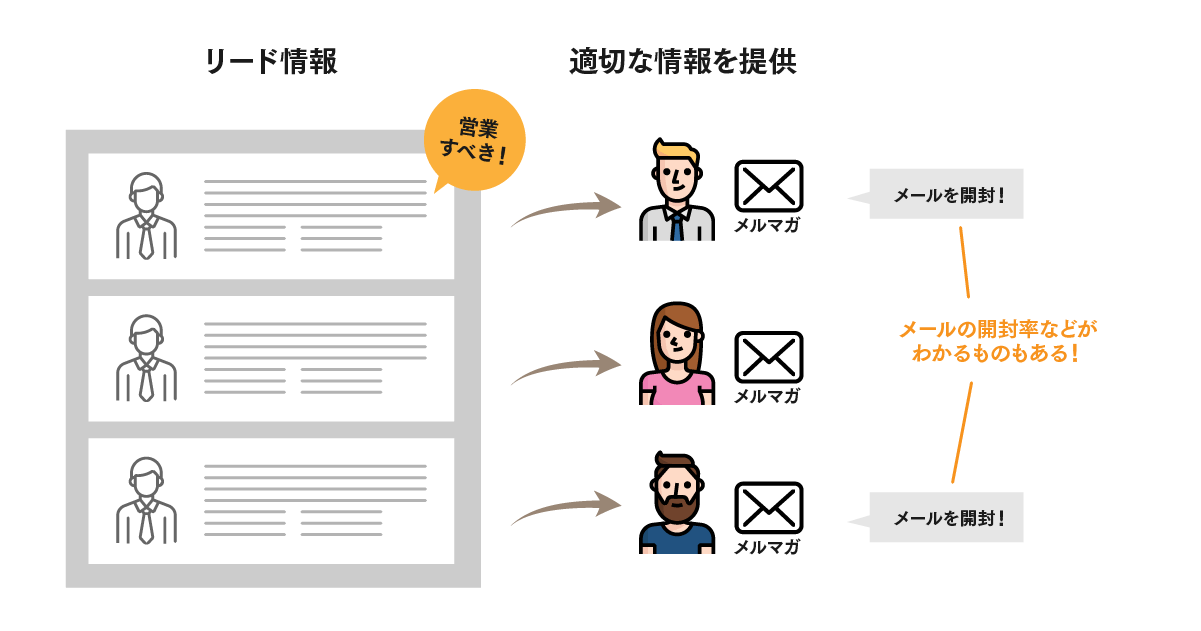
獲得したリードの反応から、すぐに営業をかけるべきホットリードを探し出し、有効なアプローチをする「リードナーチャリング機能」も欠かせません。
獲得したリードにメルマガなどで定期的なコミュニケーションを図り、中長期かつ適切なタイミングで情報を提供できます。また、メールの開封率や「誰がいつWebサイトに訪問したか」といったオンラインでの行動履歴を記録し、そのデータを基に最適なコンテンツや広告を打ち出せるものもあります。
見込み客一人一人の興味関心に応じた最適なアプローチは、成果へつながる有望なリード育成に効果的です。
3. スコアリング機能
育成したリードの反応に対して得点をつけ、アプローチするべきリードの優先順位をつけるスコアリング機能も、MAツールに外せない機能といえます。
Excelなどに手動でスコアリングする場合、膨大な作業時間を費やす上に、計算漏れなどが発生する可能性があるため、結果的に作業の効率を下げてしまうことがあります。
MAツールによってスコアリングを自動化することにより、煩雑なスコアリング作業が削減できるほか、設定した基準で正確に算出・解析ができるため、より的確なアプローチができるようになります。
また、リードの購買意欲の数値化・可視化をすることで、マーケティング活動自体に評価をつけることも可能です。施策に対する効果測定、改善といった組織強化に欠かせない「PDCAサイクル」の効率化にも役立てられます。
リードに関する3つの機能で業務の効率化を
MA導入の際には、まずは上記3つの機能について注目しましょう。特にマーケティングの領域を絞っている中小企業にとっては、さまざまな機能が含まれるMAツールよりも、3つの希望に注力したシンプル設計のものが運用しやすい場合があります。
自社に必要な機能を見極めるとともに、操作性や運用コストも踏まえて導入することが重要です。最適なMAツールの導入で、マーケティング業務の効率化や売り上げ向上を目指しましょう。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
MAについての更なる解説とおすすめ製品紹介はこちら
投稿 マーケティング効率化に欠かせない!MA導入に欠かせない3つの機能とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 チャットプラスのカスタマーサクセス事例―毎日5件の製品改善で顧客の声をスピード反映 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。
2019年6月現在、契約数は約4,400アカウント。今もなお1カ月に100~150アカウント増のペースで利用ユーザーが増え続けている。そんな快進撃を見せているWeb接客(Webチャット)ツールが「ChatPlus(チャットプラス)」だ。月額1,500円からと低価格、また申込み後わずか1分でID発行、JavaScriptのタグを配置するだけですぐにチャットを始められる利便性の高さが世の中に支持されるゆえんとなっているのだが、「低価格なのに、機能の充実ぶりがスゴイ」という理由から、ChatPlusを選ぶユーザーも少なくない。
Founder and CEOの西田 省人氏は言う。「ChatPlusにもともとあった機能というのは、現在の10分の1ぐらい。9割はお客さまから寄せられた要望で開発し、どんどん追加していった機能です。つまり現在のChatPlusの90%は、お客さまの声でできています」そんな新機能開発の源となるお客さまの声は、カスタマーサクセスチームの3人が中心となって集めているという。同社のカスタマーサクセスチームはどのようにして顧客の声を集めているのか。西田 CEOと、取締役 COOの大江 繭子氏へ「顧客の声の生かし方」について詳しくお伺いした。
自社Webサイトに設置したチャットが、顧客の声の入口。1日50件の声に、カスタマーサクセスチームが対応
――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?
西田氏: 2016年8月に創業し、ChatPlusをリリースした当初から、カスタマーサクセスに取り組んでいると言っていいと思います。お客さまに提供するチャットツールをやはり自社のWebサイトにも設置していますので、お客さまがChatPlusを使ってみてどんな反応なのかをチャットを通して確認し、使い方が分からないなど、お客さまが抱えた課題に対して丁寧に対応していくということは、リリース直後から始めています。
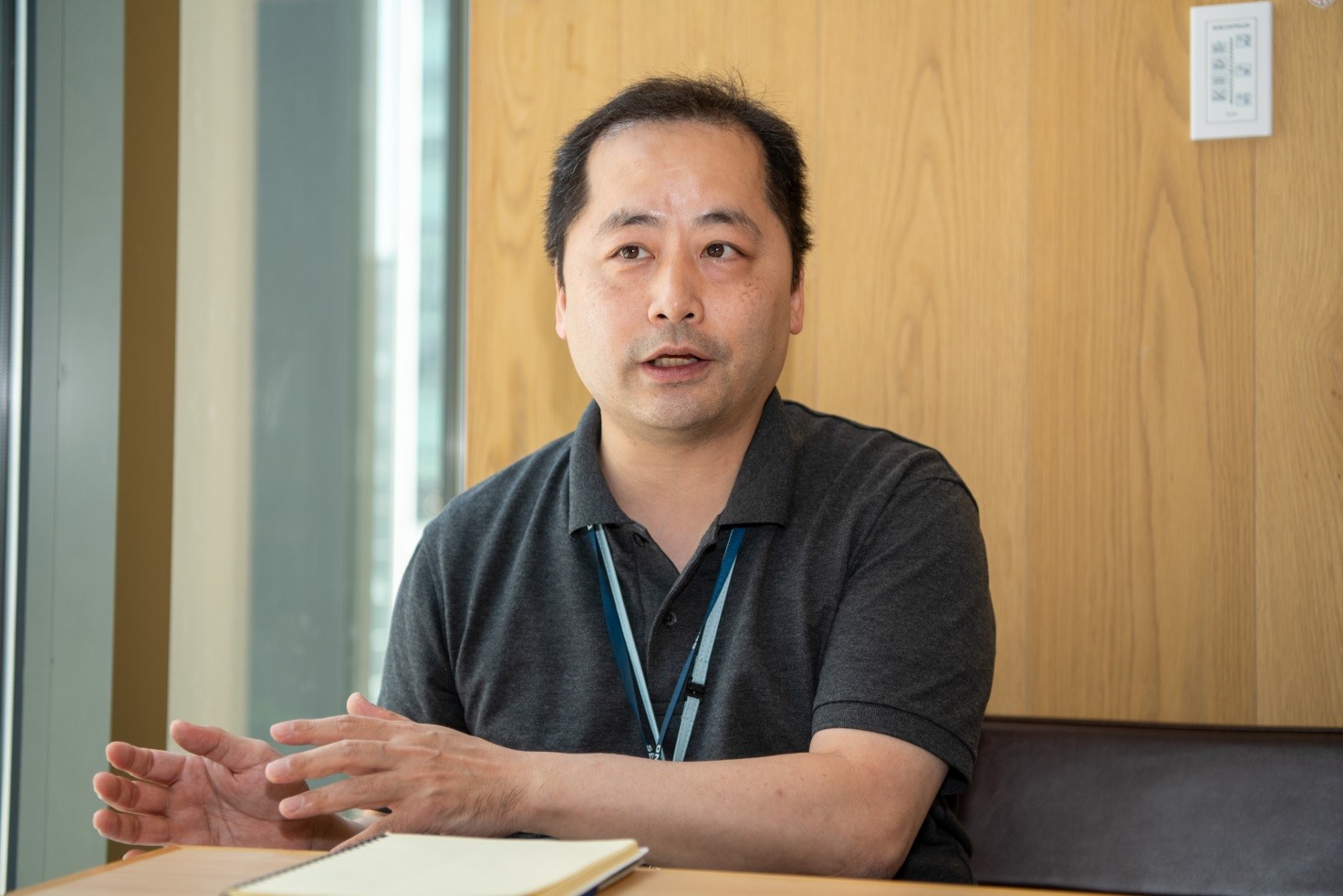
――カスタマーサクセス担当の方々は、どのようにしてお客さまの声を集めていらっしゃいますか?
西田氏:自社Webサイトに置いているチャットがお客さまの声の入口になっています。もちろん、そこは新規のお客さまがお問い合わせされる窓口なのですが、既存のお客さまもこのWebサイト上のチャットからお問い合わせされるケースが最も多いのです。Chatbot(定形の質問に対しボタン形式で自動回答する機能)で自動回答することも少なくないのですが、チャットには1日50件ぐらい、お客さまからフリーワードでのお問い合わせやご要望が寄せられます。カスタマーサクセス担当は、新規、既存を問わず、そのお問い合わせやご要望へ対応していく役割を担います。

――新規、既存を問わず顧客対応されるということは、カスタマーサクセス担当の方が新規営業のような活動をされることもあるということでしょうか?
大江氏:チャットへのお問い合わせはいったん、カスタマーサクセスチームで受けて、「この機能の使い方は?」「この機能の設定方法は?」といった内容であれば、そのままカスタマーサクセスチームのほうで対応します。新規のお客さまから導入にあたっての相談事があった場合も、担当営業の訪問セッティングは、カスタマーサクセスが行います。カスタマーサクセス担当がお客さまへ訪問することはあまりないですが、顧客と担当営業のWebミーティングにカスタマーサクセス担当が同席することもあります。
西田氏: 営業が商談を行った後のフォローは、カスタマーサクセスチームで担当します。そのフォローがとても重要です。しっかり顧客フォローしているとやはり成約率が高いので、カスタマーサクセス担当のフォローが新規営業のカギを握るといっても過言ではないですね。
毎日、5~6件は新機能などの開発を実施。ChatPlusの機能のほとんどは、顧客の声が源
――顧客の声の中には、「もっとこういう機能がほしい」といったプロダクトへの要望はございますか?
西田氏: ChatPlusは従来のチャットツールと比べても、かなり機能が充実しているツールだと自負していますので、明確に「こういう機能がほしい」というご要望は少ないのですが、「こういうことをやりたいのだが、どの機能を使えばいい?」といったお問い合わせは少なくないですね。既に実装している機能で解決できる件であれば、その方法をカスタマーサクセス担当はお客さまへお伝えしますし、今機能として備わっておらずお客さまの「こうしたい」にお応えできない時は、「仕様外です」とは決して返答せずに、「実装しておらずご不便をかけて申し訳ございません。承ったご意見は開発担当に伝え、機能開発を検討させていただきます」とお返しするようにしています。
そういった機能に関するご要望は、課題管理ツールに蓄積して、私がチェックし開発担当へリクエスト。順次追加機能として実装していきます。実装されたら、意見を寄せてくださったお客さまへ「以前いただいたご意見を参考に追加機能として開発/リリースしましたので、よかったらぜひご利用ください」とフィードバックするようにしています。
――そのように機能拡張されていく際に、開発の優先順位をつけていらっしゃいますか?
大江氏: お客さまから同じ意見が多数挙がっている、汎用性の高いものの優先順位が高いです。LINE連携機能などがそうですね。
西田氏: 分析機能の中で、日付指定だけだったものを時間指定までできるようにしたというのも、複数のお客さまからご意見が寄せられていたためです。すぐに実装できるものであれば、1~2日で追加機能を実装します。大体、1日5~6件は新機能開発やバグ対応などを行っていますね。そのようなスピード感でプロダクト改善を行っていますので、ChatPlusにもともとあった機能というのは、現在の10分の1ぐらい。9割はお客さまから寄せられた要望で開発し追加していった機能です。つまり現在のChatPlusの90%は、お客さまの声でできています。
――なるほど。機能が充実していると評判のChatPlusですが、機能開発の源となっていたのは、顧客の声だったわけですね。チャット以外で、顧客の声を集めるために何か取り組まれていることはございますか?
西田氏: 定期的に開催している運用相談会が、それにあたるかもしれません。
大江氏: 運用相談会は、リアルの場でもWeb上でも開催しており、新規のお客さまも既存のお客さまも、どなたでも参加できます。今、設定をしているけどやり方が分からないというお客さまもいれば、導入を検討していて、こんなこと考えているけど実現できますか?というお客さまもいらっしゃいます。また、導入してしばらくたつけど、いまひとつ効果が上がらないという相談だったり、これまでチャットは単純な対話だけだったけど他のツールと連携したいだったり。さまざまな相談を個別にお伺いするのが、運用相談会です。その場で、直接伺ったお客さまの生の声は、やはりプロダクト改善に生かされていきます。
西田氏: 私たちよりお客さまのほうがチャットツールに対して柔軟な考え方だというケースもよくあり、Chatbotの使い方にしても、よくこんなことを考えつくなというようなアイデアをお持ちです。それをユーザー会などで横展開するだけでも世の中に有益だと思っています。これは、今後取り組んでいきたいテーマですね。

顧客は何を目的としてチャットツールを利用しているかを確認し、目的の達成に伴走する
――カスタマーサクセスチームのKPIは、どこに設定していらっしゃいますか?
西田氏: 1つあるのは、お客さまの満足度です。セットアップが終わった後に、お客さまの評価をお伺いしていますので、そこの満足度は見ています。現状は、90%以上の満足度をキープしていますので、それを維持していくことが、カスタマーサクセスの目標になります。
おかげさまで1カ月に100~150件の契約が増えていっている伸び盛りのプロダクトなので、今はチャーン(解約)を減らしていくというよりは、どんどん増えていくアカウントに対してどうレスポンスよく対応していくか、お客さまからの要望に対してどう速やかにプロダクトへ反映していくか、カスタマーサクセスの活動も現在はそこに注力しています。
――カスタマーサクセス担当の主務は、顧客の成功にどう貢献していくかということだと思います。ChatPlusというツールを使う顧客の成功とは、どんなことでしょうか?
大江氏: それは、お客さまによってさまざまですね。問い合わせ対応を自動化して工数を削減したいという目的でChatbotがあるChatPlusをご利用されることもあれば、Webサイトに訪問してくれた方をお目当ての情報までガイドするためにチャットをご利用されることもあります。また、Webページから離脱させないために対話形式で簡潔に伝えたいことを伝えられるからとご利用されることもあれば、社内連絡をスムーズに行うためにChatPlusを利用してくださることもあります。
利用する目的がさまざまなので、一概に顧客の成功とはこうだと言うことは難しいですが、あえて言うなら、お客さまの目的が達成されること、イコール、お客さまの成功でしょうか。目的が達成されるように伴走していくのが、カスタマーサクセスチームや営業の重要な役割だと思います。
ChatPlusの場合、Webでお申込みされるお客さまがほとんどなので、契約された時は、どんな目的で導入されたか分からないケースが多くあります。設置したけどあまりチャットが来ないといったお問い合わせや、もうちょっとコンバージョン率を上げたいという相談があった場合、私たちはまず何を目的にしているのかを確認して、もっとチャットを活用できる方法をサポートします。例えば、個人情報を入手するタイミングではないにもかかわらず、わざわざ名前を入力いただいてからチャットを開始していたのを止めていただいたというケースもあります。そういうところを少しずつ改善していって、目的を達成できるように伴走する。実際、問い合わせ数が増えたとか、コンバージョンが4倍になったとか、そういう事例もあります。
――今後、カスタマーサクセスチームで取り組んでいきたいことがあれば教えてください。
西田氏: 今のところ、たくさん来る問い合わせを丁寧に返すことに注力していますが、もう少しマーケットが落ち着いてくれば、お客さまの利用状況をスコアリングして、チャーンを減らしていく活動をやっていきたいですね。チャーンされてしまうお客さまは、あまり使わずにチャーンされていく傾向があるので、しばらくログインしていないユーザーなどに対するPUSH型のアプローチを強化していきたいと考えています。こちらから設定をし直しに行くといった先回りの活動が、今後必要になってくるかなと思っています。
あと、これは願望に近いのですが、メーカーなど世の中のいろいろな企業に、カスタマーサクセスの概念がもっと広まっていけばいいなと思います。私たちが、ChatPlusで集めたお客さまの声をプロダクト改善に生かしているのと同じように、さまざまなメーカーがカスタマーサクセスの実践によって、集めた顧客の声を商品開発や改良に生かすような潮流が巻き起これば、私たちのビジネスにとっても好影響をもたらすと思います。なぜなら、ChatPlusは、「顧客の声を集める」カスタマーサクセスの実践には、かなり強力なツールになり得ると思うからです。
取材にご対応いただいた チャットプラス株式会社 の製品レビューはこちら
・ChatPlus
ITreviewとは
ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。
ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?
投稿 チャットプラスのカスタマーサクセス事例―毎日5件の製品改善で顧客の声をスピード反映 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 マーケティングオートメーション(MA)の設計に効果的なファネル分析とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そして、ファネルの適切な設計や分析において効果的なのが、マーケティングオートメーション(MA)ツールの活用です。MAツールで一元管理しているリード情報や見込み客の行動履歴をファネルの各フェーズごとに当てはめることによって、自主のマーケティングにおいて「何を見直し」「どこに重点を置くのか」を把握できます。
今回は、「パーチェスファネル」「インフルエンスファネル」「ダブルファネル」の3つの代表的なファネルと、ファネル分析におけるMAツールの活用について解説します。
ファネルとは
ファネルとは、日本語で「漏斗(じょうご)」という意味を持ち、逆三角形上の「ろ過」するための器具のことを言います。
見込み客の認知から購入までの遷移をフェーズ化すると、ユーザーの人数が漏斗のように逆三角形型に図式化されることから、ファネルと呼ばれるようになりました。
実際に、ユーザーがさまざまなチャネルから商品やサービスの購入に至る際、フェーズごとに購入に至らなかった離脱者が存在しています。商材について全く知らなかったユーザーが最終的な購入に至る人数は、漏斗のように窄まった形になるのです。
MAツールでは、ファネル全体でどのフェーズを改善するべきかを把握できる「ファネル分析」が可能になるため、フェーズ段階のターゲティングやタッチポイントの設計に役立てられます。オンラインでの顧客アプローチが多様化している現代において、このファネル設計はマーケティングプランを立てるうえで重要な施策といえます。
代表的なファネルの種類
ファネルには、3つの代表的な定義が存在します。
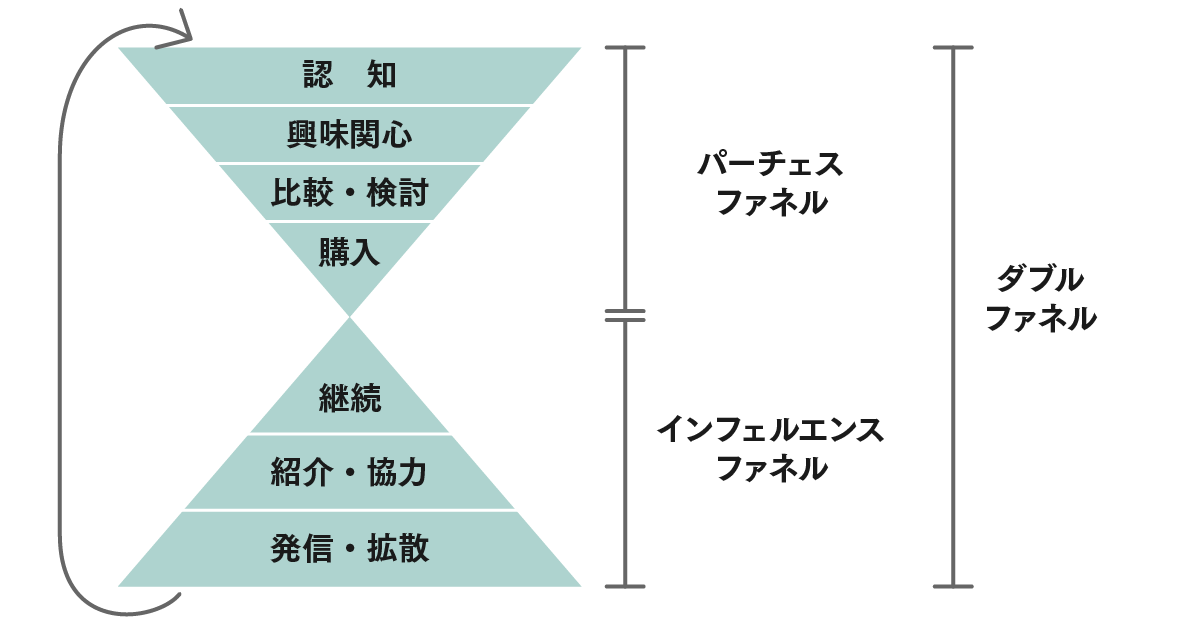
1.パーチェスファネル
「パーチェスファネル」は、見込み客が自社製品を認知する段階から実際に購入に至るプロセスの中で、なるべく離脱者を少なくしようという考えを元にしたファネルです。
消費者の行動を「認知」「興味関心」「比較・検討」「購入」といったフェーズに分解し、マーケティングによって獲得した消費者数を当てはめます。
これにより、どのフェーズで見込み客が離脱しているのかを可視化することができるようになります。
例えば最初のフェーズである「認知」の獲得数が少ない場合は、広告やプロモーションなどを用いて、多くのユーザーに認知を拡大するといったアプローチが有効です。
2.インフルエンスファネル
見込み客の認知から購入までのプロセスを図式化した「パーチェスファネル」に対し、「インフルエンスファネル」は購入した後の行動をフェーズ化したものです。
自社製品を購入した顧客と良好な関係を築くことによって、ファン化やリピート化を促すと共に、さらなる新規顧客の獲得へと繋げるためのファネルです。
特に最近はSNSやレビューサイトの普及に伴い、口コミが消費者に与える影響が大きくなりました。この第三者による口コミが、新たな見込み客に認知に大きく貢献します。
企業は消費者の製品購入をゴールとするのではなく、購入後に「紹介・共有」「発信・拡散」をしてもらうといった点もファネル設計時に検討する必要があります。
3.ダブルファネル
上記で挙げた「パーチェスファネル」「インフルエンスファネル」の2つのファネルを組み合わせたものを、ダブルファネルといいます。
見込み客の獲得から購入までのフェーズごとの効果を高めるとともに、購入後の口コミなどで新たな顧客獲得を目指すという概念です。企業からのアプローチだけでなく、購入に至った消費者からの発信によって新たな開拓が期待できることから、それぞれの相乗効果を期待できます。
MAツールがファネル分析に有効な理由
ファネル分析を的確に行うためには、具体的な数値を当てはめるなどの膨大な工数がかかります。しかしデータの抽出や入力・更新といった作業は、手作業で行うと時間や労力がかかる上に、入力ミスを招いてしまいます。
そこで導入を検討したいのがMAツールです。ファネル分析に必要なデータ収集をはじめ、顧客行動に合わせた最適なアプローチを自動化できるため、マーケターの作業効率化や見込み客の購入確度を高められるという利点があります。
参考記事:【3分で理解】企業がMAツール導入に失敗しないための4つのポイント
タッチポイントを考慮したファネル設計が必要
ファネルを活用する目的は、各フェーズにおける見込み客のステータス状況を可視化するためだけではありません。
より有効にファネルを機能させるためには、設定したファネルより導き出されたレスポンスデータを基に、どのようなタッチポイントやチャネルが効果的なのか、課題を発見することが重要といえます。
例えば、潜在顧客から見込み客へと段階を進めたい場合、ターゲットの年齢や属性から求めるものをアプローチし、集客に注力しなければなりません。10~20代の若い世代では、メールよりもLINEやSNSの方が高い訴求が期待でき、タッチポイントとして有効です。
Webサイトの集客や、営業現場における商談獲得を目標とする場合においても、ゴールに至るまでの工数を複数パターンでファネル分析することで、各フェーズのウィークポイントを発見できます。そうすることで、問合せやアポ獲得といった成果につなげるアプローチを効果的に打ち出せるようになります。
BtoBやBtoCによってもファネル設計の定義は異なりますが、いずれもファネル設計だけにとどまらず、その後のファネル分析やタッチポイントなどの改善を図り、段階ごとの課題に向けてアプローチしていくことが重要です。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
投稿 マーケティングオートメーション(MA)の設計に効果的なファネル分析とは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 もう失敗しない!マーケティングオートメーション(MA)ツール導入で確認すべき5つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>MAツールはここ数年で急速に普及したツールです。そのため、あまり詳しく理解できないまま導入し、結果的に使いこなすことができず、ツールの乗り換えに至るというケースは少なくありません。
本記事では、新しいMAツールに乗り換えるにあたり、必ず確認しておきたい5つのチェックポイントについて解説します。
MAツール選びに失敗してしまう原因とは?
新しいツールに乗り換える前に、まずはなぜ前のツールでは失敗してしまったかを明確にしておく必要があります。
MAツール選びに失敗してしまう多くの原因は、事前にMAツール導入の目的が定まっていなかったことにあります。MAツールは本来、自社のマーケティング課題もしくは全社での課題を解決するために導入するものです。しかし自社課題の洗い出しの作業が疎かなまま早急にツールの導入を決定してしまうと、MAツールの設定に失敗してしまった、ということが起きます。
例えば、営業のリソースが少なく十分な営業活動ができていないといった課題を抱えている場合は、受注確度を可視化するスコアリング機能が充実しているツールを選ぶと、少ないリソースでも優先順位を決定して効果的に営業活動を展開できます。
このように、まずは自社課題を明確にして、その課題解決に合ったMAツールを選定することが重要です。
新しいMAツールに乗り換える際のチェックポイント
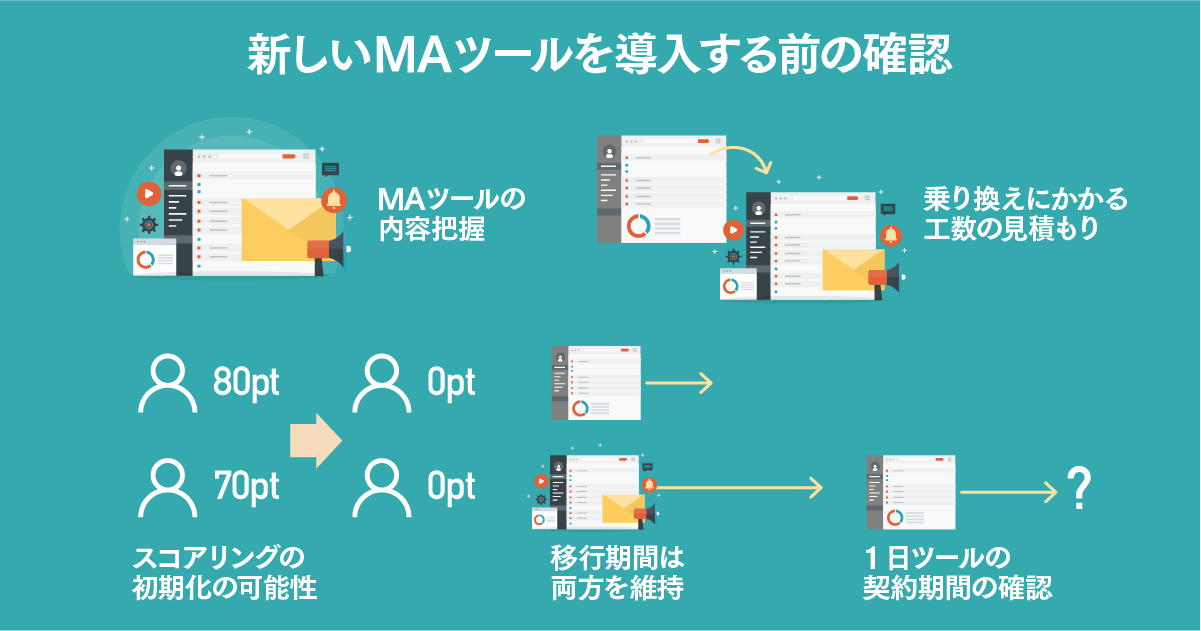
1. MAツールに含まれる機能を把握する
MAツールには、マーケターの業務を手助けする便利な機能が備わっていますが、含まれる機能や特徴は各社製品によって異なります。
ECサイト運営における集客を目的としたBtoC向けMAツールもあれば、高度なナーチャリングやCRMツールとの連携を強化したBtoB向けMAツールなど、ニーズによって必要性が異なります。そのため、導入前には自社の運用方法や課題に応じて慎重に選定することが重要です。
もし初めて導入したMAの機能が自社ニーズと合っていなかった場合は、強化するべき、あるいは不要な機能を明確化し、他の製品と比較したうえでツールの変更を検討しましょう。
MAツールの主な機能
| 機能 | 概要 |
| リード管理 | 営業や展示会などオンライン・オフライン問わずに獲得した見込み客の情報を一元で管理する機能。この情報に基づいて、マーケティング施策を実行する。 |
| スコアリング | 獲得したリードに基づき、受注確度を可視化する機能。見込み客に優先順位をつけることによって、的確なアプローチを行うことが可能になる。 |
| メルマガ配信 | テキストメール、HTMLメールの作成・配信を行う機能。リード情報に基づき、見込み客の興味関心によって、配信内容を適切なものにチューニングすることができる。 |
| ランディングページ作成 | ランディングページやお問い合わせフォームを簡単に作成することができる機能。リードの獲得にも繋がる。 |
| SNS連携 | TwitterやFacebookといったSNSでのマーケティング活動を支援する機能。 |
2. 乗り換えにかかる工数の見積もり
MAツールを導入する際は、マーケティング戦略やシナリオに伴う各機能の設定が必要になるため、運用開始までに時間がかかる可能性があります。特に他のMAツールを乗り換える場合には、データ移行などに時間がかかることがあるため、時間の余裕を持った導入が必要です。
ツールによって機能やデータ移行の概念が大きく異なる場合もあるため、事前にデータ移行にかかる工数を見積っておくことで、導入後の作業がスムーズに進むでしょう。
また、MAを活用するマーケティング部門の業務フローの変更が必要となるため、誰が何を担当するのかを事前に決めておかなければなりません。MA導入によって従来の業務が大幅に効率化できるため、人手でしか対応できないシナリオ設計などの業務にマーケターを増員するのも1つの方法といえます。
3. スコアリングが初期化される可能性がある
MAツールを乗り換える際、利用していたスコアリングの記録が初期化されることがあります。これは各社のロジックの違い上起こりうる現象であるため、それまで蓄積したスコアリング情報は新たなMAツールに移行できないことが一般的です。
乗り換えの際はスコアリング情報が初期化されるということを事前に認識しておきましょう。
4. 移行期間は両方を維持させてMAツールの運用を止めない
乗り換え時のデータ移行期間については、初期に導入したものの契約は止めず、運用し続けることをおすすめします。乗り換え先のMA運用が不安定なまま従来のツールを止めてしまうと、マーケティング運用に影響を及ぼすことがあります。
一概にはいえませんが、新旧両方の契約を維持したまま移行し、新しいMAツールが本運用し始めてから2カ月ほどの猶予を持って旧ツールを解約するのが安心でしょう。万が一のトラブルを想定し、可能な範囲内で余裕を持って移行手続きをしましょう。
5. 旧ツールの契約期間の確認
初期に導入したMAツールの契約期間を確認しておくことが大切です。
最低契約期間よりも短く契約を終わらせてしまう場合は違約金が発生するため、余分なコストがかかってしまいます。また、最低契約期間内は解約できない場合もあるため、乗り換え前には必ず旧ツールの契約期間について確認しておきましょう。
最適なMAツール選びと円滑な乗り換えのために
MAの導入は決して安い投資ではないからこそ、乗り換えには慎重にMAツールを選定することと、事前準備を怠らないことが大切です。
より最適なMAツールを選定してスムーズに移行するには、まずは現在のMAツールの課題点を見出し、その課題を解消できる機能を見極めることが重要です。そして、移行にかかる工数やコスト、データ移行についても見積もりをしておきましょう。
ノウハウに自信がない場合には、ベンダーのサポート体制やユーザー向け学習ツールが充実しているかもチェックしておくことをおすすめします。
マーケティングオートメーション製品を比較する
投稿 もう失敗しない!マーケティングオートメーション(MA)ツール導入で確認すべき5つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【5分でチェック】マーケティングオートメーション(MA)導入の3つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>インターネットの普及拡大によるWebマーケティング施策の台頭により、その市場規模は年々増加傾向にあります。
しかし、MAツールは活用方法を誤ると効果を期待できないどころか、無駄なコストを掛けてしまう要因となることがあります。
本記事では、MAツールの導入や運営に失敗しないための3つの注意ポイントについて解説します。
MA(マーケティングオートメーション)とは
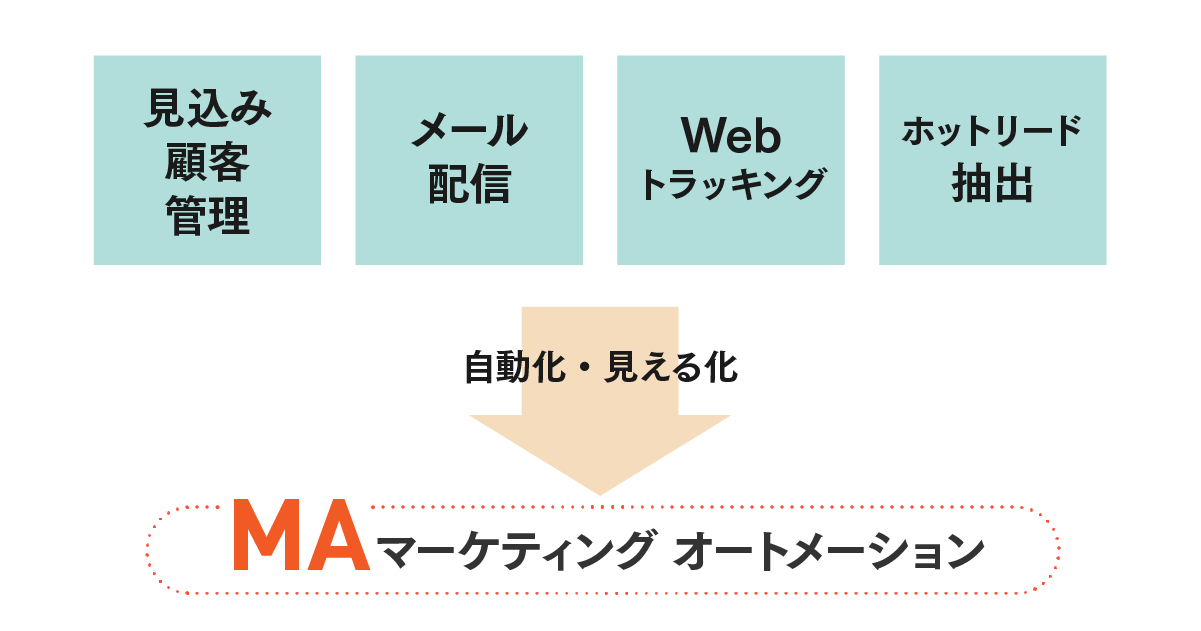
MAは、Marketing Automationの略で、「マーケティングの自動化」を意味します。
その名の通り、マーケティング業務の一部を自動化できるツールのことで、見込み客の集客から情報の一元管理、シナリオに基づいた見込み客の育成(ナーチャリング)を実施するために役立てられています。
主な機能には、見込み客との接点となるメール配信などのアプローチを自動化したり、顧客の属性や特徴に基づいたキャンペーン管理、行動履歴や閲覧したページのスコアリングなどが挙げられます。見込み客の収集から育成までのプロセスを自動化できることで、成約数や売り上げの向上が期待できます。
導入の大きなメリットといえるのは、これまでマーケターが手動で作業していたメール配信や見込み客の管理などを自動化することで、作業効率を向上できることです。また、成約につながりやすいホットリードを把握することにより、営業効率を高められるという利点もあります。
MAツール単体での導入でも十分なメリットが得られますが、CRMツール(顧客管理システム)との連携によって営業部門とのスムーズな運営が可能となるため、業務効率化などのMAの効果を高められるでしょう。
MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方
MAツールを社内に導入する前に確認しておきたい3つのポイント
1. 導入目的・求める役割を明確にする
MAツールを導入する際は、導入の目的や課題を明確にしておく必要があります。
近年では多種多様なMAツールが展開されているため、製品によって強みとする機能や特徴はさまざまです。導入するべき機能は企業のニーズによって異なるため、まずはMAによってどのような課題を解消したいのか、注力したい施策は何なのかを明確にしましょう。闇雲にツールを導入してしまうと、機能が見合わずコストを無駄にしてしまうかもしれません。
また、MAツール導入の目的を明確にする際、企業目線の施策に偏らないよう注意が必要です。KPIを利用するなどして、目標設定におけるパフォーマンスの動向を数値化することで、顧客目線とバランスの取れた的確なマーケティング施策が講じられるでしょう。
効果的にMAツールを活用するためには、強化したい施策や自動化したい業務、改善すべきプログラムを的確に把握することが重要です。
MAでマーケティング業務を自動化!マーケティングオートメーションの活用事例
2. 顧客・ペルソナの把握
一貫性のあるマーケティング施策を打つためには、MAツール活用時のシナリオ設計が鍵となります。MAツールはシナリオに沿ってアプローチを自動化してくれるため、シナリオが適切に作られていなければ、効果的なマーケティングを実行することはできません。
このシナリオ設計に重要となるのが、ペルソナ(架空の顧客像)の設定です。自社の製品やサービスを検討したいと思う人物が「どのような課題を持っているのか」「どのような手段でアプローチすれば購買意欲を高められるか」などを想定し、最終的なゴールに至るまでのプロセスを定めましょう。
この時、企業目線で考えるのではなく、実際のWeb上での行動履歴やフォーム問合せ情報などのデータを考慮することで、精度の高いシナリオ設計が可能になります。
また、施策に対する効果が十分に得られない場合には、MAツールのスコアリング機能などを利用し、PDCAサイクル繰り返すことも重要です。顧客の分析を通して、いかに適切なペルソナを設定できるかがMA活用に不可欠といえるでしょう。
MAのシナリオ設計の4ステップ|マーケティングの精度を上げるコツとは
3. 社内の連携が必須
MAツールの実践には、マーケティング部門だけでなく、営業部門とのスムーズな情報共有が必要です。
マーケティング部門において可能性の高い顧客をピックアップしたとしても、営業部門との連携ができていなければ、顧客の取りこぼしなどの問題が起きやすくなります。また、顧客管理に関する認識が共有できていない場合は、成約に至るまでの効果的なプロセスをMA設定に生かせなかったり、案件に至らなかったアプローチ方法を改善するといった、PDCAが効果的に回らなくなるでしょう。
例えば、「マーケティング部門が確度の高い見込み客を絞り込んでいる段階であるのに、営業部門が個人の認識だけで先に見込み客リストを作成してしまった」などのように、業務に支障が出ることも考えられます。
特にマーケティング部門と営業部門には相互連動性が高いため、互いの活動状況や顧客情報をシームレスに共有することは、マーケティング活動において重要です。MAツールを導入する際は、営業部門との連携がスムーズにできる基盤づくりも行いましょう。
MAツールを社内に導入するまでの流れ
STEP1:カスタマージャーニーマップの作成
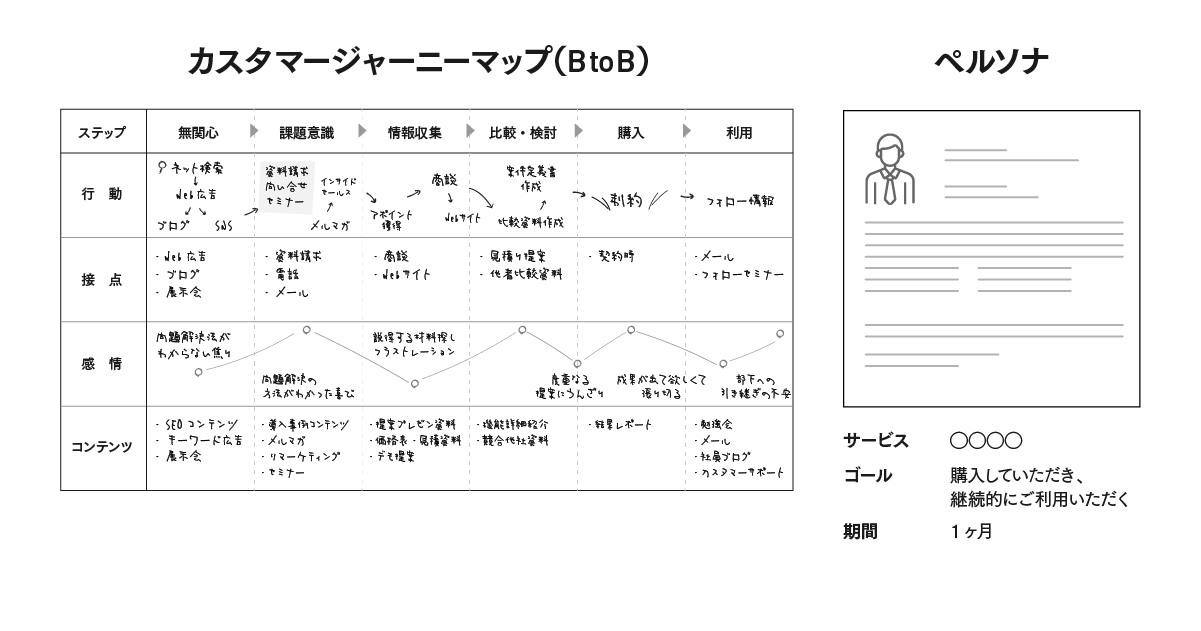
MAツールを効果的に運用するためには、どのタッチポイントでどのようなマーケティング施策を実行するのかといったシナリオの設計が欠かせません。そこで有効なのが、カスタマージャーニーマップを作成する方法です。カスタマージャーニーマップとは、見込み客が自社製品を認知するフェーズから実際に製品の利用や購入に至るまでのフェーズを、図によって可視化したものです。
マーケティングに関わる部門は「マーケティング部門」だけでなく「営業部門」「カスタマーサポート」などもあります。また、マーケティング部門でも、「Web担当」「SNS担当」などチームが複数に分かれていることもあります。このように関係する部門やチームが多くなると、関係者の間で顧客傾向に対する認識のずれが発生しているケースがあります。
そこでMAツールを導入する前にカスタマージャーニーマップを作成し、社内やチーム間で共通の認識を持つことによって、効果的なマーケティング施策を打つことができるようになります。
MA活用に欠かせない!カスタマージャーニーの作成方法・効果・注意点とは
STEP2:自社のニーズに最適なMAツールを選定
MAツールの導入が一般的になってきたこともあり、国内のベンダーからさまざまなツールが提供されています。ツールによって搭載している機能も異なるので、自社の課題や目的に沿って導入するツールを選定しましょう。
特にMAツール選びの際に多い失敗例が、自社のニーズにそぐわない多機能なツールを選定してしまうケースです。多機能ゆえにうまく使いこなすことができずに、費用対効果に見合わない結果に陥ってしまう可能性があります。
詳しい選び方に関しては後述しますが、あくまでも自社の課題やMAツールを導入する目的を念頭に選んでいくことを頭に入れておきましょう。
マーケティングオートメーション(MA)ツールの製品・ユーザー評価を比較する
STEP3:ベンダーと契約し、インストール
MAツールの選定が終わったら、実際にベンダーとの契約を行い、自社の環境にインストールを行いましょう。ツールには、オンプレミス環境に導入するソフトウェアパッケージとアカウントが発行され次第すぐに利用ができるクラウド型のものがあります。
前者のソフトウェアパッケージのMAツールの場合、自社のサーバーやネットワーク環境を整える必要があるので、技術システム部門との連携を図りながら進めていく必要があります。
STEP4:初期設定
MAツールのインストールが終わり次第、自社のマーケティング施策に最適なカスタマイズを行います。
例えば、資料請求を受けた際の自動返信メールのテンプレート作成や自社のWEBサイトの各ページにスコアリング用のタグを設置する作業などが必要です。
サーバーやネットワーク環境の構築も含めて、自社での初期設定が難しい場合は、ベンダーや外部のMA導入支援サービスを活用することを検討しても良いでしょう。
STEP5:運用の開始
MAツールは、導入してからの効果検証が重要です。見込み客のスコアリングの数値も、運用後に少しずつ改善を重ねることにより、精度の高いアプローチが可能になります。
短期的な結果ではなく、中〜長期的な視点で運用を行うことが大切です。また、それに伴いMAツールを正しく運用することのできる人材の確保や育成、組織の構築も進めていきましょう。
自社に最適なMAツールを選ぶポイント
1.ツールごとの違い
MAツールは、「BtoB向け製品」と「BtoC向け製品」に分けることができます。自社製品やサービスの環境に合わせて、適切な製品を選びましょう。
| BtoB向け製品 | 法人顧客をターゲットとした企業向けのMA。キャンペーン、セミナーやイベントを管理したり、実施した結果を分析・評価する機能が充実している。 |
| BtoC向け製品 | ECサイト運営やオウンドメディアなどオンライン経由で集客したリードの獲得、育成に重点が置かれていることが多く、昨今ではLINEやFacebook、TwitterなどのSNS連携の強化が図られているものも多い。また、BtoC製品と比べ、見込み客として扱うデータの数が豊富に扱えるものも多い。 |
2.導入形態
MAツールの導入形態には、「ソフトウェアパッケージ」と「クラウドサービス」の2パターンあります。
ソフトウェアパッケージのタイプは、自社のサーバーやネットワークといったオンプレミス環境に導入を行います。そのため、サーバー構築など初期段階で時間を要することやインフラ環境の整備や運用が必要になります。その反面、クローズドなネットワークでの運用が可能なため、セキュリティー面が強固で自由にカスタマイズできます。
一方のクラウドサービスのタイプは、自社でインフラ環境を整える必要がなく、迅速に導入できます。最近はクラウドコンピューティングのセキュリティ向上に伴い、多くのMAツールがクラウドで提供されるようになっています。
3.価格形態・契約形態
クラウドサービスの場合は相場が月額10〜20万円程度、ソフトウェアパッケージの場合は相場50万円〜100万円程度で提供されています。
また、クラウドサービスのMAツールでは、利用できる機能によって「ベーシック」「プロ」「アルティメイト」といったプランごとに価格形態が異なるケースが多々あります。メルマガの配信数や登録するデータベースなど自社の条件と照らし合わせながら選びましょう。
加えて、効果的に運用を行うためのコンサルティング費用や保守サポート費用が別途でかかってくるケースもあります。
4.オプション
フォームの作成やトラッキング機能・セミナー管理・SNS連携などが基本機能に含まれず、オプションで契約が必要な場合があります。
「何が基本機能として備わっているか」を契約前にしっかりと見極め、自社のマーケティングに必要なサービスが過不足なくある製品であることを確認しましょう。
ツール選びは慎重に
自社ニーズに応じたツール選定に気を付けるだけでなく、導入後のシナリオ設計や他部署との連携なども重要となります。安い投資ではないからこそ、事前準備を怠らず、綿密な顧客分析を忘れないようにしましょう。
自社に最適なツールを導入し、入念なペルソナ設定やシナリオ設計をすることで、MAの可能性を最大限に生かすことができます。また、CRMツール等を利用した他部署との連携によってさらなる相乗効果が期待できるため、社内の情報共有・管理体制づくりの見直しも検討しましょう。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
投稿 【5分でチェック】マーケティングオートメーション(MA)導入の3つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 シンプルな機能で操作しやすい、低価格なMAツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>なかでもシンプルな機能に特化したMAツールは、操作性が高く比較的低価格であることが特徴です。試験的に導入したり、マーケティング知識が無くとも操作できる点が魅力といえます。
本記事では、多くの企業が導入しているMAツールの中で、低価格かつシンプルな機能に絞ったおすすめMAツールをご紹介します。
1、SATORI

SATORI株式会社が提供する国産のMAツールで、集客に特化した機能が特徴です。匿名顧客へのアプローチする「アンノウンマーケティング」により、個人が特定できていない潜在顧客に対しても、セグメントを設定して有効な施策を出し分けることができます。そして、閲覧履歴から分析した有効なタッチポイントにより個人情報の入力を促し、より効果的なナーチャリングにつなげます。
また、プライベートDMPであるため、自社のWebサイトでの行動履歴や購買履歴などをオンライン・オフライン問わず一元管理が可能です。顧客の趣味嗜好に対して最適なアプローチを実現します。リード数を増やしたい企業に有効といえるでしょう。
特長
・集客に強い
・匿名顧客へのアンノウンマーケティングが可能
・匿名、実名問わず顧客との接触履歴を一元管理
・プライベートDMPできめ細かな顧客セグメントが設定可能
・GoogleやYahoo、Facebookなどと広告連携が可能
月額費用
148,000円~
2、カスタマーリングス
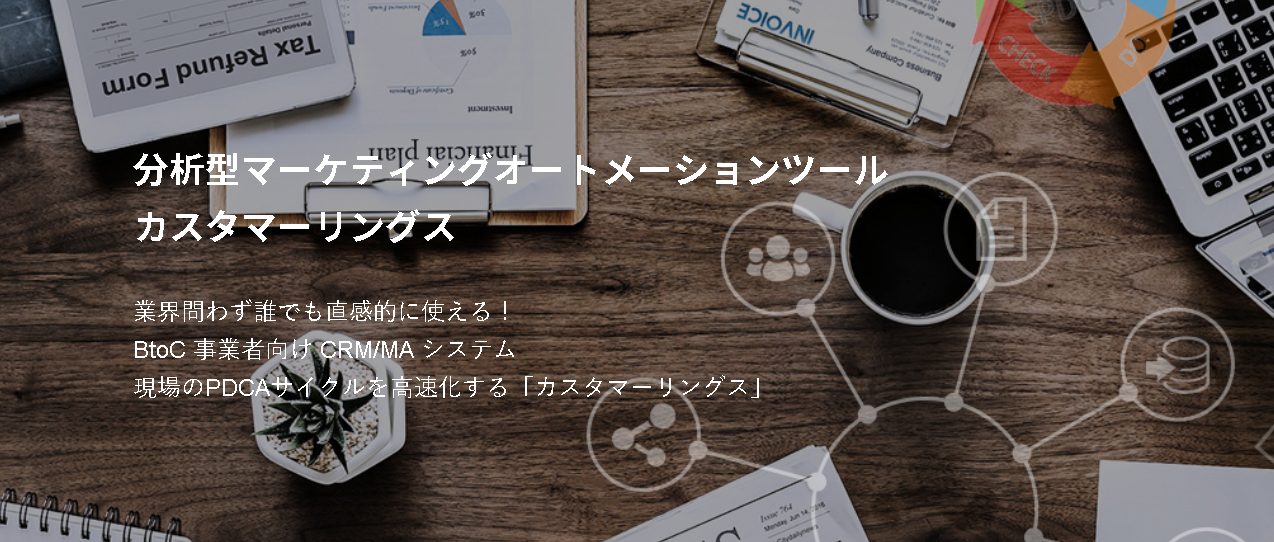
プラスアルファコンサルティングが運営するMAツール。
マーケターの作業効率化や顧客管理・育成などに加えて、顧客情報の収集や分析による”見える化”を提案し、現場のPDCAサイクルの効率化を実現します。
特にECサイトなどのBtoC事業者向けのMAやCRM機能に注力しており、顧客の反動をいち早く収集・改善ができる点が特徴です。ECサイト上のデータ抽出やドリルダウン分析、自動シナリオ化により、シームレスなサイト運営が可能となります。
また、企業アプリをインストールした顧客に対するアプリプッシュ連携や、セグメント化した顧客への個別のSNS配信など、現代のサイト運営に欠かせない機能も充実しています。
特長
・ECサイトなどのBtoCに特化したシステム
・サイト運営のPDCAサイクルを効率化
・顧客データ収集や分析を自動化
・アプリプッシュ連携やSMS配信に対応
・操作しやすいインタフェース
・充実したサポート体制
月額費用
98,000円~
3、MAJIN

株式会社ジーニーが提供する、AIテクノロジーを活用したMAツール。BtoB、BtoC企業向けのそれぞれのプランが選定できます。
顧客接点が多様化していることへの対応策として、AI技術を活用した「AIスコアリング」機能を搭載。コンバージョンに至りやすい顧客の傾向を予測し、膨大かつ複雑な顧客の行動データを分析することにより、購買促進、成約数向上につなげます。
一般的なMA機能に加えて、「MAJIN DMP(媒体評価分析)」やコンバージョンに至るまでの接触履歴の解析「アトリビューション分析機能」など、MAJINならではの広告集客機能も充実しています。
小規模かつ低価格で始められるアプリ事業者向け・Webサイト運営者向けプランもあるため、目的やコストに合わせて選定できます。
特長
・BtoB、BtoCの両方に適切なプラン
・One to One マーケティングに特化した機能
・オンライン、オフラインで取得した顧客情報を管理・分析
・MAJINならではの広告集客機能(MAJIN DMP等)が充実
・AIスコアリングによって顧客の関心度合を可視化
・Webプッシュ配信やアプリプッシュ通知にも対応
月額費用
BtoB MAJIN:100,000円~
BtoC MAJIN:100,000円~
App MAJIN(アプリ事業者向け):50,000円
Push MAJIN(Webサイト運営者向け):50,000円
4、Kairos3
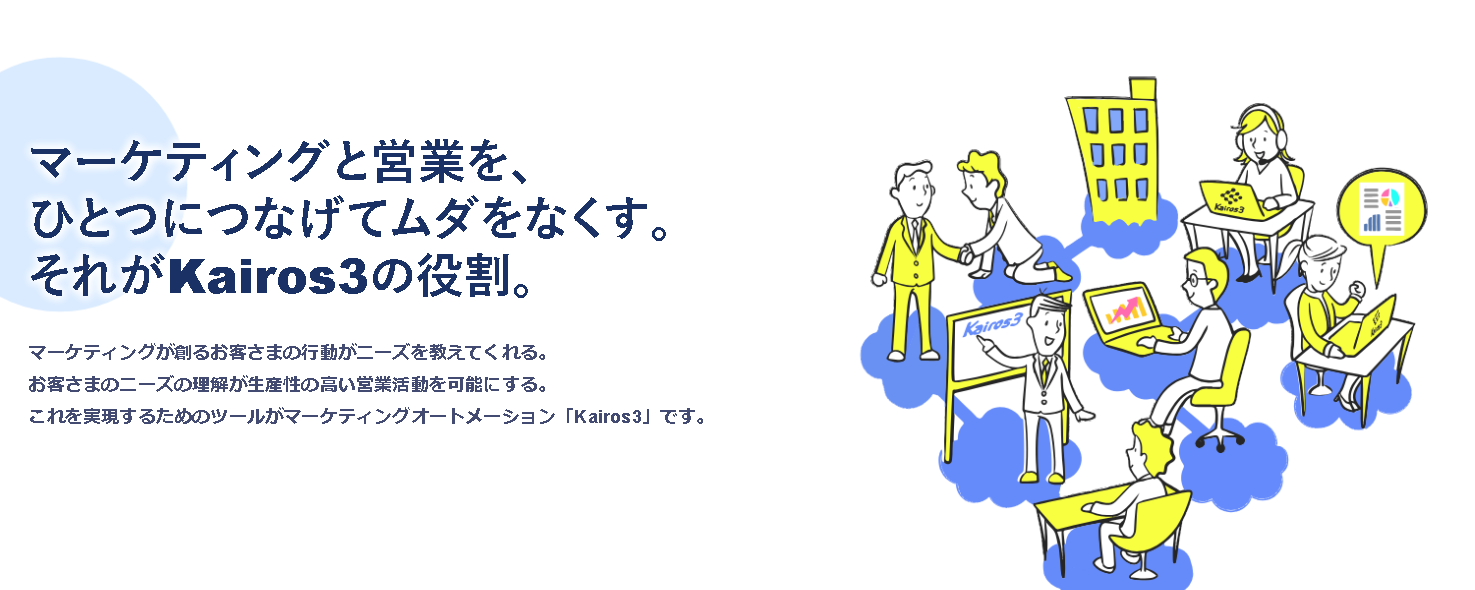
カイロスマーケティング株式会社が提供するMAツール。
メール配信やリード管理、ROI分析などのマーケティング機能を搭載しており、低価格で導入しやすいため、スタートアップや個人事業主にも利用者が多いのが特徴です。
なかでも注力しているのは、リードに対する育成や誘導です。スコアリングによってホットリードを逃すことなくアプローチできるほか、リードナーチャリングによって休眠顧客を探り、投資効果の高い施策を分析するなどのあらゆる活用が可能です。
業務の手間を削減したい場合や、シンプルな機能のみを効率よく活用したいBtoC事業に適しています。
特長
・MA機能に特化
・Excel上の顧客情報管理データを移行がスムーズ
・セミナーやアンケート管理にも対応
・申込後すぐに利用可能
・シンプルなインタフェース
月額料金
5,000円~
5、Hubspot Marketing Hub
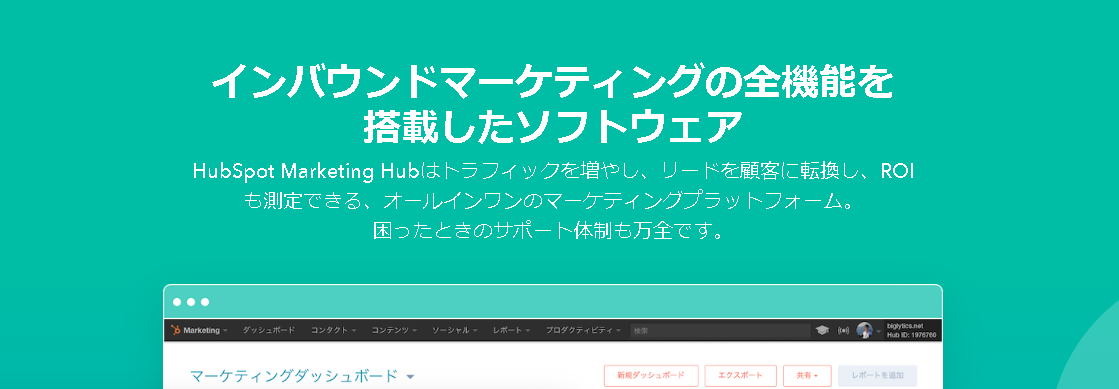
HubSpot Japan株式会社が提供する総合マーケティングツール。
主にインバウンドマーケティングに特化した機能が備わっており、オウンドメディアからのリード獲得やナーチャリング、SNSを活用したリーチなどを実現します。Webサイトの構築やROI測定も可能なため、Web広告の改善やWebサイトへのアクセス数向上が期待できます。
複雑なプログラミングは不要で、簡単な操作のみで最適なコンテンツ作成ができるほか、リードから顧客へ自動フォローアップが実行されるなど、操作しやすい点も魅力といえます。Webサイトを活用したインバウンド施策を低価格で実践したい企業に適しています。
特長
・インバウンドマーケティングに特化
・簡単にコンテンツ制作が可能
・ROI測定に対応
・豊富なリードナーチャリング機能
・無料版あり
・SNSマーケティングに対応可能
・同社のCRMツールと組み合わせ可能
月額料金
Starter:6,000円~
Professional:96,000円~
Enterprise:384,000円~
CRMやSFAツールとの連携性について
MAツールを選定する上で、機能の種類やコストを重視することは欠かせません。より細かな設定ができる多様な機能を持つツールは高コストになりやすいですが、各フェーズに特化したシンプルな機能のものは低コストで始められるものもあります。自社の課題と予算などを考慮して比較検討しましょう。
また、MAによる効果を生かして持続的な運営をするためには、CRMやSFAによって顧客の維持や営業プロセスの強化が欠かせません。それぞれのデータ連携がスムーズになるほか、業務効率化や各チームの連携による生産性向上につながります。
MAツールを選定する際は、自社ニーズやコストだけでなく、CRMやSFAとの連携性についても考慮すると良いでしょう。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAを選ぼう!
投稿 シンプルな機能で操作しやすい、低価格なMAツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MIERUCAのカスタマーサクセス――ファン化につながるユーザー会の作り方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。
カスタマーサクセスの実践において、オンラインでのユーザーコミュニティー運営やオフラインでの定期的なユーザー会開催など、ユーザー同士が交流できる場の提供を重要な施策の1つに挙げる企業が少なくない。本連載の「カスタマーサクセスの夜明け」でも、これまでユーザー間で活発に意見交換を行っているユーザーコミュニティー運営企業をいくつか取り上げさせていただいた。
人工知能も活用しつつ検索ユーザーのニーズを分析し、より有効なSEOやコンテンツマーケティングにつなげるための話題SEOツール・コンテンツマーケティングツール「MIERUCA(以下、ミエルカ)」。この話題のプラットフォームを提供するFaber Companyも、導入企業1,000社を対象としたユーザー会を2カ月に1回程度のペースで開催している、ユーザー会実践企業だ。「セミナーの開催も案内していますが、ユーザー会のほうの参加予約がとても早く埋まっていきますね」と言うカスタマーサクセスチームの渡邊 雅俊氏、大江 奈々子氏へ、ユーザーが我先に参加したくなるユーザー会はどのようにして生み出されているのか、同社のユーザー会運営術を中心にお話を伺った。
顧客のライフサイクルに合わせ、役割を3つに分担した体制に
――貴社は、いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?
渡邊氏: 私が入社したのが2年前の2017年。その時、既にカスタマーサクセスのチームがありました。「ツール+学習コンテンツ+コンサルティング」この3つの領域に力を入れていくというのが、私たちの会社のスタンス。この3つの中の「ツール」に関して私なりに理解しているのは、今世の中にあるどのツールも、機能だけで見ると負けず劣らず素晴らしいものかなと思いますが、実際それを活用できないと何も役に立たない。お客さまはツールを導入して終わりではなくて、活用してそこから何かしらのアクションを起こさないと、成果にはつながりません。
当社もはじめはツールを導入いただく際に、提案から導入後の支援までフロント担当者が実施していたのですが、導入企業数が増えて専任チームが必要となったため、カスタマーサクセスチームが創設されました。チームの立ち上げ当初は2人でしたが、今では約20人のカスタマーサクセス担当でお客さまのツール活用をはじめとしたSEO・コンテンツ施策を支援しています。

――お二人はカスタマーサクセス担当として、どのような役割を担っていらっしゃいますか?
渡邊氏: 私は担当するお客さまに1対1で向き合いながら、ミエルカというツールをどう活用するのが有効なのかを支援、フォローする役割です。それと合わせて、導入いただいたお客さまがミエルカのファンになっていただけるよう、ユーザーイベントや勉強会などを企画、運営しています。
大江氏: 私も同じくお客さまであるWebマーケターの方々へミエルカの活用支援を行っています。これまでは、導入時の立ち上げ対応から、導入後のお問い合わせ対応などお客さまが自走してくださるまで、1人のカスタマーサクセス担当がお客さまに伴走していました。2019年6月より、グロースチーム、アカウントチーム、サポートチームに大きくチームを分割しました。導入時から運用立ち上げを中心に支援する、いわゆるオンボーディングを担当するのがグロースチームです。立ち上げ後の運用フェーズでミエルカをどのように活用すべきかなどを伴走支援するのがアカウントチーム、お客さまからの機能や契約に関する問合せ対応を行うサポートチーム、この3つのチームに役割が分担された体制になりました。私はグロースチームで、日々お客さまがミエルカを活用しながら施策をどう進めていくかをやりとりしています。

顧客のKPI達成に伴走することが、カスタマーサクセスチームのKPI達成に結び付く
――貴社では顧客の声をどのように集めていらっしゃるのでしょうか?
渡邊氏: お客さまと1対1の対面でご要望をお伺いすることが多いですね。また2カ月に1回程度、ユーザー会を行っています。そこでのアンケートなども非常に参考になります。今後ユーザー会は、少人数の分科会の開催も実施するなどバリエーションと頻度を増やしていく想定です。そうなれば、ユーザーともっと密な情報交換ができるのではと期待しています。
大江氏: 立ち上げの段階では、お客さまとの打ち合わせの機会が多数あり、コミュニケーションを密に取りながら進めます。そのときのお客さまのご意見は非常に参考になりますね。あとは、ミエルカ管理画面で定期的に、サービスやツールの満足度について聞かせていただくためのNPS(Net Promoter Score)調査を実施しており、そこで入力いただいたフリーアンサー内容も貴重なお客さまからの声になります。

――そのようにして集めた声をどのように活用していらっしゃいますか?
渡邊氏: イベントに参加してくれたお客さまにも同じようなNPS調査を実施しており、その変動を見て、お客さまがどういう状況なのか、施策に対してどれくらいモチベーション高く取り組めているのか変化を読み取り、こちらからの適時アプローチを行うようにしています。
大江氏:これらのNPS調査のスコアや普段のやりとりから把握している施策状況をもとに、お客さまの活用ステータスごとにラベルをつけ、ネクストアクションはどうしていくのかを管理しています。カスタマーサクセス担当のアクション後にお客さまがどう変わっていったのかもデータで残せるようになっていて、分析できるくらいにデータが蓄積されています。
渡邊氏: また、お客さまからいただいた声をツールの改善にも生かしています。最近の改善例でいうと、「ミエルカヒートマップ」の表示画面の刷新です。機能には3種類のヒートマップデータがあって、それらを1つ1つ別の画面で見せていたのですが、「3つ同時に閲覧できるようにしてほしい」というお客さまからの声がありまして。その数日後には3画面同時表示を新機能としてリリースしました。
他にも多くのご要望をいただいておりますが、優先順位やその他ユーザーへの影響なども加味しながら、順次対応できるようエンジニアチームと連係しているところです。やはり普段活用いただいているユーザーの声が一番参考になると感じています。

――カスタマーサクセスチームのKPIやKGIは、どこに設定していらっしゃいますか?
渡邊氏: KPIはLTVの最大化。ツールの運用を定着させ、いかに長くご活用いただくか。もちろん解約率もみています。KGIというか、カスタマーサクセス担当が目指すのは、最終的にはお客さまのビジネスを成長させることですね。
大江氏: 私たちにKPIがあるように、お客さまにもKPIがあります。今、新体制の立ち上げの段階でカスタマーサクセス担当は、改めて何をしていくべきなのか整理しているところです。お客さまとKPIを一緒に設定して、それを達成していくために、どういうタスクとスケジュールを引けばいいのかを一緒に決めていく。施策効果を計測するために、どんな指標を見ていけばよいかポイントを抽出して、どういうフォーマットで効果計測を行うのか、というところまでお客さまと決めていければよいね、などをチームで議論しています。
直近では、お客さまのKPI達成に伴走する取り組みを複数社でテストさせていただき、「いいね、これだと(施策が)うまくいきそうだね」という声をいくつかいただいています。お客さまによっては「検索流入アップ」をKPIにするケースもあれば、「コンバージョン数アップ」をKPIにするケースもあります。課題もさまざまなので達成までのロードマップは個別に作成していかなければなりません。
私たちの持っているノウハウをもっと集約し、「検索流入アップの場合は……」「コンバージョン数アップの場合は……」と、お客さまの達成したい目標に応じた成功パターンをフォーマットにした上で、展開していく予定です。
課題解決型のユーザー会を企画・運営し、製品のファンを生み出す
――貴社のユーザー会は、とても盛況だとお伺いしています。どのようにユーザー会を運営されているのでしょうか?
渡邊氏:まず、「ツール+学習コンテンツ+コンサルティング」のうち、学習コンテンツとしての「動画マニュアル」や、集合研修の「ミエルカ大学」など、コンテンツ施策やSEOの学びの場を多く提供しています。これに加え、主にユーザー同士の交流と活用状況の共有の場として、2018年から始めたのがユーザー会です。
企業内でWebマーケティングやSEOなどを担当している人数は少ないことが多いんですよ。各種施策の方向性、自分のやっていることは正しいのか、相談する人がいないというお悩みは、お客さまからよく伺っていました。ミエルカユーザーさん同士は、日々同じような課題に向き合っています。そこでユーザーさん同士で交流してもらって、新しい発見や施策の相談ができたら、モチベーションを高めあっていただける。そういう場を私たちが提供しよう、というコンセプトです。その中でミエルカの新しい活用を発見したり、新たな施策を思いついたりする。ひいてはミエルカをより好きになってもらえたらうれしいなと。
ユーザー会のテーマは毎回お客さまの声からヒントを得ています。普段の業務の中で「どんな点が気になりますか?」「どんなことが課題になっていますか?」などを聞いてきていますので、それらを整理して、ユーザーの役立つのではないかという企画のストックを作っています。それぞれのテーマに対し、実際取り組んでいるユーザーさんや知見をもっているユーザーの方に登壇を依頼、施策内容を共有してもらったり、どんなふうに解決してきたのかなどをライトニングトーク形式で発表してもらうのが評価の高いコンテンツです。登壇ユーザーのみなさまが惜しげもなく技を披露してくださる(笑)おかげでもあるのですが、ユーザー会の満足度はいつも高いですね。

https://mieru-ca.com/blog/users-conference3/
――ユーザー会は、ある意味、競合関係にある者同士の集まりという側面があると思います。そのあたりは、交流の場を持つ上で、懸念されませんでしたか?
渡邊氏: そうですね。最初、実は社内からも集まる人の競合性や関係性をとても心配されました。しかし実際参加されたユーザーの生の声を聞いてみると、全然そのようなことはなくて。さきほどもお伝えしたとおり、ユーザーであるWebマーケターは会社の中で孤独なことが多い。そういう状況の中で、同じような役割を担っている方と横のつながりを持ちたいという思いを抱いている方が多いんです。そこには競合がうんぬんという話はそもそも存在していませんでした。
ユーザー会に参加することによって、まだ知り得ていないWebマーケティングのノウハウを手に入れることができ、同じコンテンツマーケティングやSEO担当者ともつながりができる。もちろんミエルカを好きになってくれるとさらに良いのですが、ミエルカというサービスを通じて、多くのWebマーケッターのみなさんのスキルアップやキャリアアップにつながる。そういう世界観を作りたいですね。結果、「ミエルカいいじゃん!」って感じてもらえたらいいかなと。またユーザー会の場では、私たちが考えもしなかったミエルカ活用方法がシェアされたりもしていて、私たち自身も学ばせてもらっています。私たちとユーザーとが一緒になって、業界を盛り上げていきたいなというのがありますね。

https://mieru-ca.com/blog/industry_conference1/
担当者個人の成功支援もファン化に必要――ファン獲得からアップセルを生み出す効果も
――ユーザー会を通して、ユーザーをファン化していくためのコツや秘訣は何かございますか?
渡邊氏: 「ファンになってもらう」は結果だと考えています。私たちが相対するお客さま個人がどう成功するかがカスタマーサクセスに必要な視点です。どうしたらその方が成果を上げられるか。社内外問わず評価され、マーケターとしてキャリアアップやスキルの研さんにつながるのか。私たちカスタマーサクセス担当がサポートできるところは少なからずあるのではないかと思っています。
ライトニングトークに登壇いただくユーザーさんには、プレゼン資料作成をお願いしています。資料を作ると、自分のやってきた施策や成果を再認識される。その資料を自社内で共有し、社内成果報告してもらうのと同時に、「ミエルカを使ってこういう成果が出ました」と自主的に宣伝してくださるユーザーさんまでいます。実際、その会社の他部門の方から「〇〇さんに聞いて…」と問い合わせをいただくことも多いので、既存ユーザーさんからのアップセルも「社内紹介」から増えています。
大江氏: まずはミエルカを使いこなしていただけることが大前提です。その上で渡邊がお話ししたように、「ミエルカを使っていると自分も成長できるし、悩んでいる人がいたら紹介しよう」とお客さま自身に自然に思っていただけるレベルまで徹底的にサポートすることでしょうか。
また、ユーザー会の企画やコンテンツを増やしていって継続することも重要だと思います。ご好評いただいた業種別勉強会は今後、ユーザー会後の分科会として開催する案や、その他ECやメディアだけを集めて開催する案も出ています。さまざまなユーザーニーズをカタチにしていって、「コツをつかんだ」「成果が出た」「仲間ができた」、さらには「ユーザー同士で新しいサービスやコンテンツを始めた」というケースも、今後増えていくことを期待しています。
2019年9月には今までで最大規模のユーザー会を開催する予定があります。コンテンツは徐々に決まってきていますが、たくさんのユーザーさんにお会いできるのが楽しみです。

https://mieru-ca.com/blog/users-conference4/
取材にご対応いただいたFaber Companyの製品レビューはこちら
・ミエルカ
ITreviewとは
ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。
ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?
投稿 MIERUCAのカスタマーサクセス――ファン化につながるユーザー会の作り方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 イー・エージェンシーの日本流カスタマーサクセス、「おもてなし」の心を込める顧客対応とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>製品・サービス提供後も、顧客企業の成功を第一として積極的に伴走を続ける「カスタマーサクセス」を取り入れようとする動きが日本でも活発化し始めている。本連載ではカスタマーサクセスに取り組む企業とその立役者を連載形式で取り上げ、具体的な施策やうまく推進するための秘訣などを紹介する。
Webサイトの構築やデータ分析・活用にまつわるさまざまな製品を展開するイー・エージェンシー。データドリブンによるWebサイト制作を得意とする同社は、レコメンドエンジンや低価格メール配信システム、多言語変換サービス、カゴ落ち対策ツールなど、マーケティング支援ツールの分野でも国内有数の販売実績を持つ。
そのマーケティング支援ツールを利用する数多くの顧客に対し、カスタマーサクセスを実践しているのが、カスタマーコミュニケーション部CS課の女性7人だ。彼女たちは、自らの活動を「おもてなし」の観点からスコアリングし、それを日々の顧客対応に生かしているという。「おもてなしを科学する」をビジョンに掲げる同社ならではの、「おもてなし」の心を込めたカスタマーサクセスとは? CS課を率いる長沼 彩花 課長と金子 美穂 リーダーにお話を伺った。
「CS」には、カスタマーサポート、カスタマーサクセス、カスタマーサティスファクションの3つの意味がある
――貴社は、どのような体制で、カスタマーサクセスを実践されているのですか?
長沼氏: メンバーは組織長の私を含めて7人です。私たちがサポートする商品は、レコメンドエンジンの「さぶみっと!レコメンド/コンテンツレコメンド」を始め、「さぶみっと!メール配信 / API Mail」、カゴ落ち対策ツールの「カートリカバリー」、PCサイトをそのままスマホに変換する「shutto(シュット)」、自動翻訳サービスの「shutto翻訳」、LINEメッセージ配信「KANANETO」と6商品あり、2商品をメンバー2人で担当する体制で顧客対応を行っています。
CS課の「CS」には、カスタマーサポート、カスタマーサクセス、そしてカスタマーサティスファクションと3つの意味があります。あるメンバーはカスタマーサポートだけを行うというような業務分担はしておらず、6人のメンバー全員が、カスタマーサポートもカスタマーサクセスの活動も、カスタマーサティスファクション(顧客満足)を向上させる活動も、全て行います。

――いつからカスタマーサクセスに取り組まれていますか?
長沼氏: 課の名称にカスタマーサクセスを据えたのは2018年ですが、2015年ぐらいからカスタマーサクセスといえる活動は行っていました。初めはカスタマーサポートといった業務がメインで、お客さまから問い合わせに対して答えていくのが私たちの役割。でもやっぱりその業務だけでは、1年、2年と使っていただいた後に、突然解約されてしまったり、その解約の理由がよく分からなかったり。そういうことが目立つようになってきました。導入前にトライアルをやってみたけど、本契約には至らないケースもあり、こちらがお客さまを十分に把握していないために離脱してしまう。やっぱりお客さまのことをもっと理解しないといけないということに気付きました。お客さまと同じ方向を向く、同じゴールを目指すということがないと、いい関係が作れない。そういうスタンスでやっていこうとしたのが、3年ぐらい前ですね。
――カスタマーサクセスとしての活動には、どのようなものがありますか?
金子氏: トライアルをしてくださっているお客さまへ状況を伺ったり、何か困ったことがないかなどを確認したり。あとは既存のお客さまへ電話や訪問で要望をお伺いして、それを社内に持ち帰って、開発を検討したりしています。また、残念ながら解約になってしまったお客さまへその理由をお伺いし、深く議論することもあります。それらがカスタマーサクセスとして活動していることになります。

長沼氏: 新規でのお問い合わせももちろんあるので、直販だけでなく、代理店の営業担当の方と一緒にお客さまのもとへお伺いしてご説明し、トライアルをしていただいて、そこから本契約まで進めていく。これも私たちの活動の1つです。導入時の設定フォローや、導入後のフォローも私たちが行います。トライアルのお客さまを本契約まで引き上げるのは、私たちの役割です。あとは、1年後、3年後、5年後、解約されずにさらに取引を大きくしていくために、どういうことをしていくべきか、どう改善していくべきかをチームの中で考えて実行していくことも現在行っています。
――既存顧客のフォローだけでなく、新規営業のような活動も行っていらっしゃるのですね。
長沼氏: はい。私たちの商品には基本的に、トライアルの期間が設けられています。ですので、実際にお客さまが導入し、それらのフォローを私たちが行うのは、受注前ということになります。トライアルをしてくださった見込み客のお客さまが、本契約していただけるよう適切なフォロー、つまり新規営業のような活動を私たちが行うのは、ごく自然なことのように思っています。
仕組み化よりも、できるだけ多くのお客さまと触れ合う、手触り感のあるカスタマーサクセスを展開
――貴社では顧客の声をどのように集めて、それをどのように活用していらっしゃるのでしょうか?
金子氏: 電話で対応させていただくことが多いのですが、そこでご要望やお客さまの課題をお伺いします。あとは、お申込みの時にアンケートでご意見を伺ったりしています。どういうところに期待してお申込みされましたか? 何にお悩みですか? などをお聞きし、お客さまの課題を把握できるようにしています。また、お客さまには、弊社の導入事例として取り上げさせていただくお願いもしているので、そこで詳しくお客さまの声をお伺いしたりもします。
長沼氏: お客さまからいただいたご要望は、ツール改善の中に落とし込んでいくことも当然あります。自社開発ツールなので社内にはエンジニアのチームがあり、プロダクトごとにエンジニアと定例ミーティングをしています。そこにお客さまの声を持ち込んで、改善を検討することは毎週行います。あとは、使い方が分かりづらいところは資料に落とし込んだり、FAQにしたり、マニュアルに反映させたり。より使いやすいツールにしていくことに、お客さまからの声を活用させていただいています。
また、販売チャネルを拡大、強化するために各パートナーさんと連携しキャンペーンなどを企画していますが、そこでヒアリングできる内容も大切にしています。弊社のツールは、サイトを構築するためのメイン基盤にオプションでつけていただくことが多いので、代理店になっていただける制作会社さまや広告代理店さま、サイト構築パッケージのベンダーさまなどと密に連携させていただいています。その中で、お客さまが自社サイト構築にあたって、どのような課題感を抱いていらっしゃるのかといった声を把握し、ツール提案に生かしています。
――問い合わせ対応というカスタマーサポートから、既存顧客の継続率を上げるための活動、トライアルから本契約へ引き上げる新規営業、また代理店フォローまで、CS課の方々の活動はかなり幅広いですね。仕組み化して業務を効率的に行っていく方法もあるかと思いますが、そのお考えはございますか?
長沼氏: そうですね。もちろん仕組みやシステム化などは行っております。顧客数は、レコメンドエンジンで1300社ぐらい。カートリカバリーは500サイトにご利用いただいていますが、現在よりも顧客数がかなり増えたり、チームメンバーの数が減ってしまったり、というような状況になれば、よりシステマチックな仕組みで品質を保ち、お客さまに対応していくことも重要なことだと考えています。ただ、システム化することだけでなく、少しでも多くのお客さまと触れ合うことがもっとも重要だと考えています。商品のことはもちろん、営業のこともサポートのことも理解した私たちが、より多くのお客さまと対峙することで、仕組み化するよりもスピード感や一貫性のある顧客貢献ができているのではないかと思っています。
日々の活動に「おもてなし」の心を込めていこうという取り組みを開始
――そんな幅広い活動を行うメンバーの方々が顧客に相対していく中で、貴社なりに工夫されていることは、何かございますか?
長沼氏: より事業貢献できるCS(カスタマーサポート+カスタマーサクセス+カスタマーサティスファクション)を実践するために、日々の私たちの活動に「おもてなし」の心を込めていこうという取り組みを始めています。
東京工業大学の教授がまとめられた「おもてなしを構成する要因の体系化」という論文に、例えば「おもてなしは、相手に『安心感』を与えなくてはいけない」「おもてなしには、相手の状況、ニーズを読み取る観察力/洞察力といった『感受性』が必要である」などの「おもてなし55項目」というのがあるのを見つけまして。その中から、「おもてなしに必須なもの」22項目をピックアップし、私たちが行っている業務の中で大切にしていることは、どの項目に当てはまるだろうか? 逆にできていないことはどれだろうか? 次にこのおもてなしができるようになるためには、具体的にどんなことを行っていけばいいのだろうか? などをチームミーティングで話し合っています。
22項目の中で特に重要だと話していたのは、先ほどの「安心感」「感受性」に加えて、「心(おもてなしには、相手を敬う「心」がなくてはならない)」「立場に立つ(おもてなしを行う上で、相手の立場に立って考えるということは最も重要な考えである)」「目的(おもてなしは、相手の目的を把握しそれに沿って行われなければならない)」です。この5項目について、どういったアクションを起こしていけるか、チームの中で話を進めているところです。チームとメンバー個々で、この項目はできている、これはできていないなどスコアリングして、今後のお客さまへの対応に生かせるようにしています。
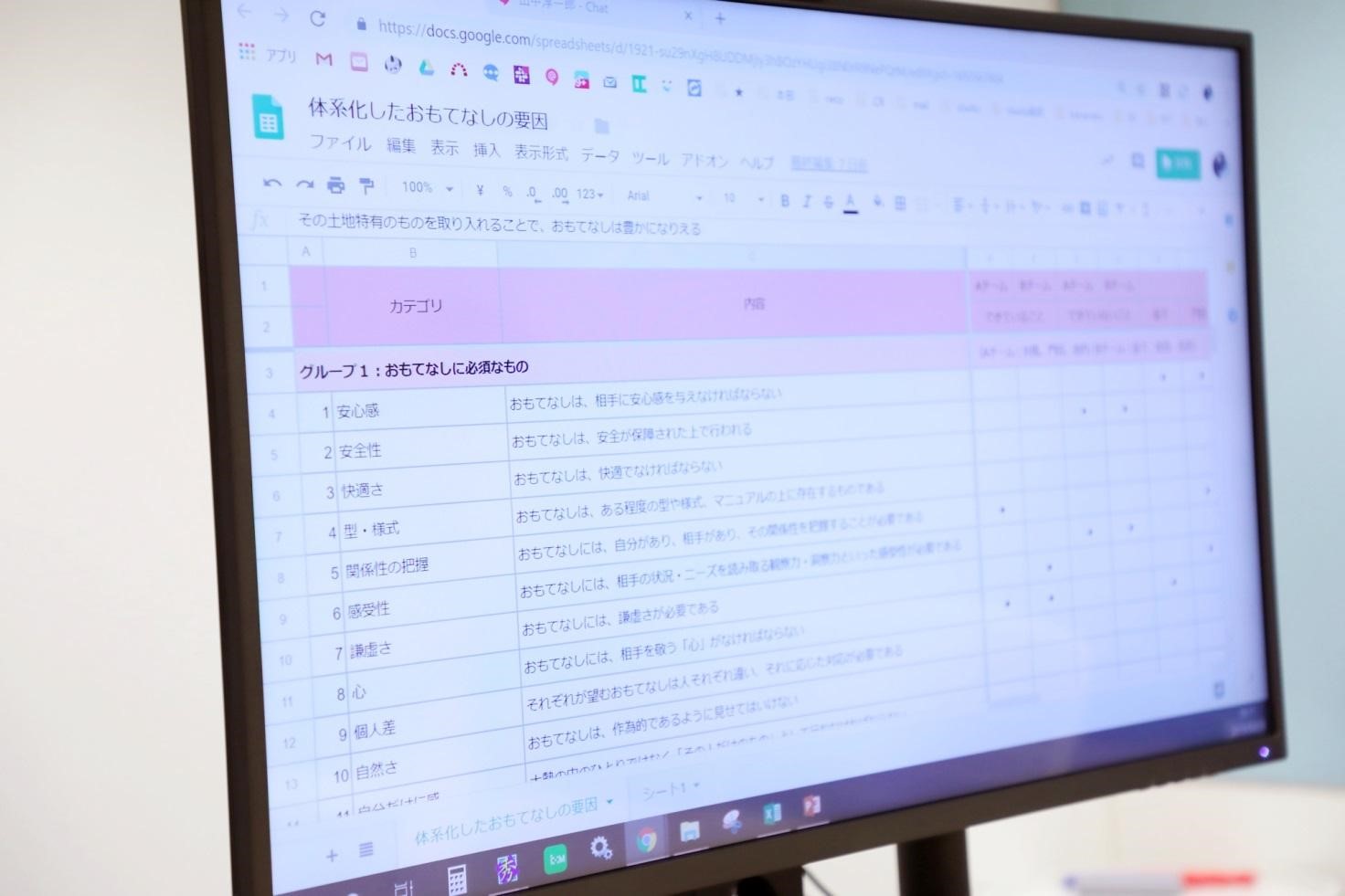
――顧客のスコアリングはカスタマーサクセス実践企業でよく行われることですが、自分たちのヘルススコアを「おもてなし」の観点からつけていく取り組みは、とてもユニークですね。
長沼氏: そうですね。そもそも私たちの会社のビジョンが「おもてなしを科学する」というもので、私たちCS課の活動が「おもてなし」なのか、どうすれば「おもてなし」の心が込められた活動ができるのかは、以前からずっと考えていました。
カスタマーサクセスというと、お客さまの利用状況を可視化し、スコアリングをして、それに対するアクションというのが明確にあって、システマチックにお客さまへ対応していくというのがイメージされるのですが、そこで取りこぼしてしまうものや、スコアだけではくみ取れないお客さまの声というものも一方であるだろうと思っています。そういったものをどこまで丁寧に、ちゃんと見つけられるかを考えた時に、私たちの活動に「おもてなし」の心があれば、お客さまの声も拾いやすくなるのではないかと思いました。
スコアリングというのはとても参考になる指標だと思いますが、現時点で私たちは必ずトライアル(受注前)の段階からお客さまに伴走していますので、スコアだけに頼らない、お客さまそれぞれに合った対応ができると思います。その上で、お客さまは本当は何をご要望されているのか、それをちゃんと把握するために始めた活動が、この「おもてなし」なのです。
プロダクトごとに目標シートを作成し、エンジニアとも同じ方向を向く
――CS課のKPIはどこに設定されていますか?
長沼氏: アカウントの件数だったり、継続率だったり、ツールを利用しているサイトのセッション数であったり、担当するプロダクトによって、KPIは変わってきます。例えば、リリースしたばかりの「shutto翻訳」というプロダクトだと、新規の顧客を獲得していこうという活動がメインになるので、新規問い合わせ数やトライアルの申込み数がKPIとして設定されています。一方で、「さぶみっと!レコメンド」というレコメンドエンジンは成熟期に入っているプロダクトなので、解約をどれだけ防止できるかといった継続率がKPIになります。先ほどお話した「おもてなし」の取り組みが成果を上げるようになれば、「おもてなし」のスコアがKPIになることも十分にありえるかと思います。
金子氏: 私が担当する「カートリカバリー」は、これから伸びるか、成熟してしまうか微妙なライン上にあるプロダクトなので、新規獲得と継続率の両方をKPIとして追っている状況です。
長沼氏: 私たちは、期の始まりに、プロダクトごとに目標シートを作っています。大項目として、チャレンジ目標(売り上げ)のクリア/顧客満足度(LTV)のアップなどの方針があり、財務的業績の向上のために、どのように行動すべきか、例えば代理店/子アカウント件数の増、直販アカウント件数の増、単価アップ、生産性の向上などがあります。そしてそのために、私たちはどんな施策を行うべきかまで具体的に落とし込んでいます。この目標シートによって、私たちの活動も明確になり、エンジニアなどほかのチームとも同じ方向を向くことができます。極力マーケットインの、お客さまの声を反映したプロダクトを作っていきたいと思っているのですが、エンジニアのリソースも限りがありますから、優先順位をつけて開発していくことがすごく大事。今なぜその機能を優先して作らなければならないのか、話ができる土台をこうしてきっちり作っておくことがとても大事かなと思っています。
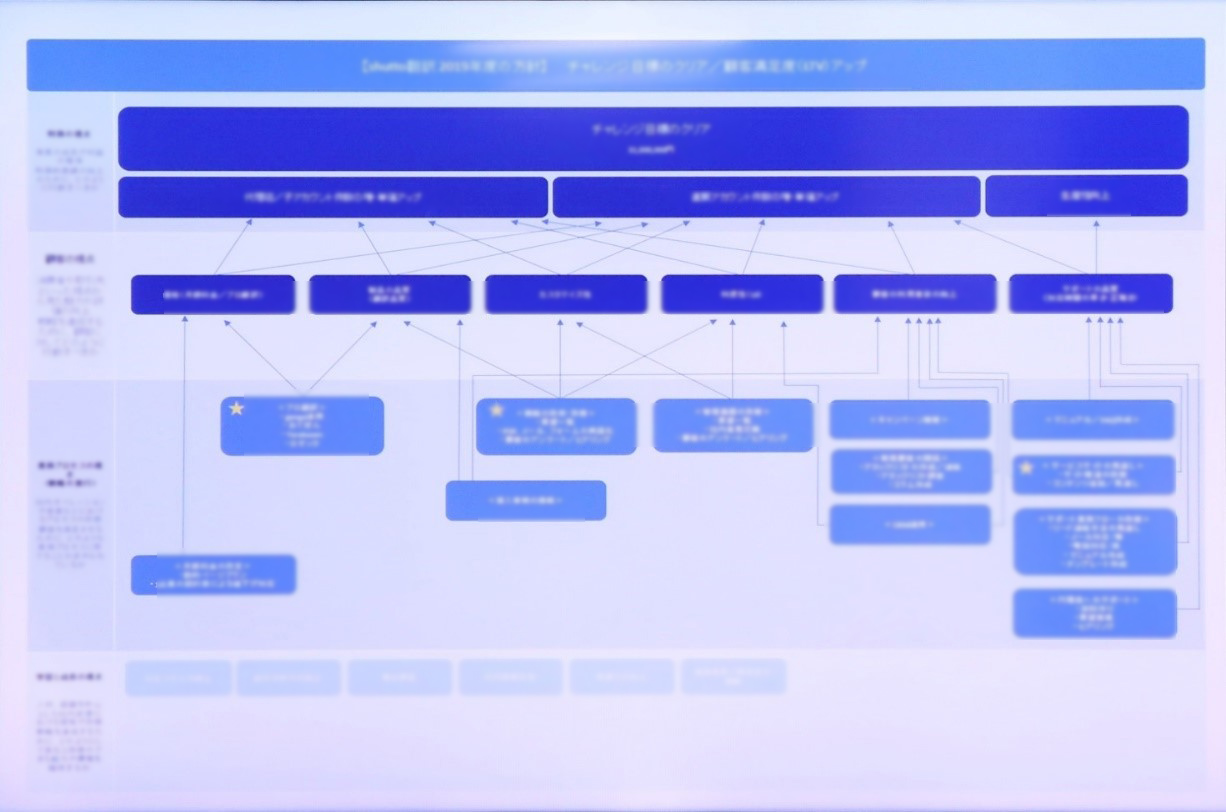
――最後に、顧客の声を集めるのに苦労していることなどはありますか?
長沼氏: 弊社のサービスは導入が簡単で一度導入すると、その後、特に設定を弄っていただかなくても使えてしまうサービスがほとんどです。そのため、導入後に定期的にお客さまとコミュニケーションをとることが難しくなります。現在は、お客さまに役立つ情報を記事やホワイトペーパーにまとめて配信したり、定期的に機能のアップデートのご連絡をしながら、反応していただいたお客さまとコミュニケーションを取り、悩んでいることや要望などの吸い上げを行っています。
また、お客さまの中にはWebの知識があまりないお客さまも多く、何がしたいのか、何を解決したいのかなどをお客さま自身がよく分かっていなかいことも少なくありません。そういった場合でも、「おもてなし」の心で、とにかく話を聞いてあげて、一緒に設定したりしていますね。

金子氏: 以前、お客さまから「ステップメールはできますか?」とお問い合わせいただいたことがあって。「ステップメールは対応していないのですが、予約配信をうまく使ってステップメールに近い配信を行うことならできます」とお答えした時に、そのお客さまから「ちなみにステップメールって何ですか?」とご質問されたことがあって(笑)。お客さまは「まわりでステップメールがいいって言っているから、どんなメールなのかよく分からないけど聞いてみた」とおっしゃっていて、どんなことをしたいのかよくよく聞いてみたら、予約配信で十分だったので、「さぶみっと!メール配信システム」のトライアルをお試しいただいたということがありました。
細かいことかもしれませんが、「ステップメールは対応していません」で終わらずに「予約配信を使ってならできます」とご案内できたのは、「おもてなし」に必須な「相手の状況、ニーズを読み取る観察力/洞察力といった感受性」について日々考える機会があったからかもしれません。たまたまかもしれませんが(笑)これからも意識して「おもてなし」の心を込めて対応していきたいなと思います。
取材にご対応いただいたイー・エージェンシーの製品レビューはこちら
・さぶみっと!レコメンド (レコメンドエンジン)
・コンテンツ レコメンド (レコメンドエンジン)
・さぶみっと!メール配信 (メールマーケティング)
・API Mail (メール配信)
・CART RECOVERY (カゴ落ち対策)
・shutto (スマホ最適化)
・shutto翻訳 (Webサイト翻訳)
ITreviewとは
ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。
ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?
投稿 イー・エージェンシーの日本流カスタマーサクセス、「おもてなし」の心を込める顧客対応とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Marketoのユーザーコミュニティは、なぜ盛り上がるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>ユーザーコミュニティーを立ち上げるIT製品が増加する中、ユーザーが主体的にコミュニティーに参加しているMarketoのような例は少ない。「なぜMarketoのユーザーコミュニティーはここまで盛り上がっているのか? その魅力は何なのか?」今回は、Marketo活用による実績を評価されたMarketoチャンピオン5人にリアルトークを繰り広げていただき、ユーザーコミュニティーの魅力に迫る(取材日:2019年2月1日)。
今回お話を聞いた5人のMarketoユーザーとレビュー(写真左から)
HENNGE株式会社 水谷博明氏 : レビューを読む
株式会社UNCOVER TRUTH 河原里香氏 :レビューを読む
株式会社FORCAS 嶋田真弓氏 :
トレンドマイクロ株式会社 山田泰志氏
Sunity株式会社 CTO 西田正洋氏 :レビューを読む
「マーケティングを日本でもっと広めたい。でも、1人ではできることに限界が」
――ITreviewに投稿されたMarketoのレビューに「コミュニティーに助けられた」というコメントがあるように、Marketoのユーザーコミュニティーはユーザーの困り事を他のユーザーが助けてあげるというサイクルができ上がっているように思います。山田さんは、オンラインコミュニティーの管理者を担当されていますよね?
トレンドマイクロ 山田泰志氏(以下、山田氏): はい。他のユーザーの方々からの投稿を、仕事が終わった後や休日などに見て、困っている方がいれば、自分で答えられる範囲で、できるだけ返信するようにしています。
FORCAS 嶋田真弓氏(以下、嶋田氏): Marketoの使い方で何か困った時にコミュニティーに投稿すると、サポートより早く、山田さんが答えてくれます(笑)。
――それはすごい。どうして、そこまで積極的にコミュニティーへ参加していらっしゃるのですか?
山田氏: 日本のマーケティングは遅れているという危機感からでしょうか。私はずっとマーケティングに従事し、海外の情報に接しやすい立場にあることからそのことを痛感していました。今ようやく、Marketoを始めとするMAツールが定着し始め、日本でもマーケティングが職種として確立しつつあります。しかし、マーケティングを日本でも広めたいと思っていても、1人ではできることに限界があります。だからこういうコミュニティーの場で盛り上がる人を増やしていければ、マーケターの輪も広がっていくのではないかと、そう思いました。あと、海外で得たMAのノウハウをせっかくだから同じユーザーの方々にも提供できたらとも思っています。でも、そんなに難しいことはやりません。「私は分からないので、誰か分かる方いませんか?」と返信することもあります。

――そのような返信でも、反応があるのは、投稿者にしてみればうれしいですよね。
嶋田氏: 私がコミュニティーに投稿し始めたのは、他のユーザーがコミュニティーで投稿して、山田さんが返信をしているのを見て、「あっ、誰かが返信してくれるんだ」と思ったからです。自ら返信するようになった今、山田さんには私の投稿に返信してもらいたので、その分、他の人たちの投稿に答えられるものは返すようにしています(笑)。

山田氏: 嶋田さん、たくさん投稿して、たくさん返信していますよね。やっぱり投稿する人と返信する人が増えていくと、みんなノってきますよね。
UNCOVER TRUTH 河原里香氏(以下、河原氏): 私がオンラインコミュニティーを見始めた時は、嶋田さんがたくさん返信している時で、それで自分も投稿してみたら、すごく早い段階で嶋田さんが返信してくれました。山田さんの恩恵が嶋田さんへ行って、嶋田さんの恩恵を私が受けているみたいです(笑)。また、水谷さんの講演動画を見て、「これ、ウチの会社でもやったら絶対いい」と取り入れているように、いろいろな方の知識をコミュニティーから分けていただいているなと感謝しています。Marketoユーザーは、いい人が多く(笑)単純に、集まりなどへ行くのが楽しみになります。

山田氏:ユーザーの方々は皆さん、マーケティングに対して前向きですよね。
Sunity 西田正洋氏(以下、西田氏): そんな中、私のコミュニティーへの参加理由は、結構ヨコシマでして。コミュニティーで活躍すると、どうやらラスベガスにタダで行けるかもしれないという話を聞きつけて(笑)。でも、投稿しているうちに、Marketoはこんなに面白いことができるというのをみなさんに知ってもらいたくなっていきました。そして、いろいろな人の質問を見ていると、「これ、結構簡単に解決できるのに」と思うこともあり、僕からのコメントでみなさんが助かるのであれば、こちらとしてもうれしいことですから、積極的に返信するようになりました。

山田氏: 私は管理者なので、オンラインコミュニティーへのアクセス数が分かるのですが、見ていらっしゃる方は想像以上にたくさんいます。投稿はしないまでも、みなさん、参考にしていただいているのであれば、ありがたいと思います。
「Marketoはいい意味で放任主義。変に空気を読む必要もない」
――オンラインコミュニティーの投稿の内容は、Marketoの使い方などが多いと思いますが、ユーザー間でマーケティング活動そのものについてディスカッションされるようなことはあるのでしょうか?
HENNGE 水谷博明氏(以下、水谷氏): マーケティング活動そのものの部分は、オンラインでというよりリアルなFace to Faceのユーザー分科会で行っています。僕はどちらかというと、リアルな場のほうが好きです。リアルの場は、それこそ「どうすれば成果が上げられるのか」といったことがテーマ。マーケティング論の話ばかりでMarketoの話を一切しないということもあります。加えて、マーケターは周りに誰も聞く人がいないという環境に置かれがちなもの。切実な悩みを聞く場としても、リアルな分科会が機能していると思います。

山田氏: 今、オンラインとリアル、ちょうどいいバランスだと思います。オンラインのほうは気軽に参加できる分、そこまで濃い話はなかなかできないですから、そのような投稿があった場合は、リアルのユーザー分科会へ誘導するようなこともあります。オンラインとリアルを使い分けられるということを喜んでくださる方も多いです。
河原氏: 正直、私も最初は、リアルのユーザー会に行くのはハードルが高かったです。
嶋田氏: そうですよね。そのような時に、オンラインで相談できる場があるのはとても助かる。慣れてきて、たまにオフラインのユーザー会に行ってみると、「あっ、オンラインで投稿している嶋田さんですよね?」と声をかけてもらえる。そこで、「女性のマーケターだけのFEMIKETO(フェミケト)という分科会があるのですが、今度来てみませんか?」って言われて、「はい、行きます。行きます」みたいな……(笑)。
水谷氏: 僕はSalesforceとの連携をテーマとしたSFKETO(セフケト)という分科会を運営しているのですが、Marketoのユーザー分科会は、いい意味で、放任主義。ベンダー主導の宣伝色強いユーザー会もあったりしますが、Marketoは、「みなさんで盛り上がってください」という感じ。そのほうが、ユーザー間は盛り上がりやすいし、変に空気を読む必要もない。ベンダーの思惑がないのが、うまく活性化させる秘訣なのかなと思います。
河原氏: それなら私も分科会に参加してみようかなと思うのですが、いろいろな「ケト」(注:Marketoのユーザー分科会は、○○ケトという名称で呼んでいる)が多すぎて、分からない…(一同笑)マルケトのほうから、もう少し、どんな分科会があるのか紹介していただければ、参加しやすくなるのかなと思います。
「どうすればいいか2カ月悩んでいたことが、他のユーザーとの会話で解決する」
――オンラインコミュニティーのほうは、分科会みたいな形にはなってはいないのですか?
山田氏: 難しい話と、簡単な話とを分けたほうがいいのでは?というアイデアをいただいたりするのですが、まだ早いかなと思っています。それよりも、今は投稿する人をもっと増やしたい。だから定期的に「超初歩的な質問でもいいからぜひ投稿してください」と投稿したりしています。それでコミュニティーへ気軽に入っていただければと思います。
嶋田氏: オンラインのいいところは、いつまでも検索できるところではないですか。過去、誰かがそのフェーズだった時の投稿を、検索すればいつでも見ることができる。あれはすごくいい。
――1つ質問したら、1つ答えてあげるみたいな自分ルールみたいなものってあるのですか?
嶋田氏: 分かるものから答えるみたいな感じですかね。別に、顔を合わせているわけではないのに、「この投稿は、山田さんが答えるかな?」って(一同笑)
山田氏: 私のほうも「これは嶋田さんに任せるかな」みたいに、まさに、あうんの呼吸のようになっていて(一同爆笑)

――コミュニティーに対するモチベーションを維持していく方法はありますか?
山田氏: 私の場合は、頑張りすぎないことですかね。変に使命感を持ちすぎると、長く続かなくなると思うのです。だから、その時々で、気分が上がってきたら投稿でもしようかなというラフな感じでやっています。水谷さんは?
水谷氏: 僕は、やりたいことをやって、話したいことを話しているだけです。Marketoのコミュニティー立ち上げ当初、コアなユーザーの方々と話していて、やっぱり他のユーザーの方々から得られるものは、すごく多いなということを体感しました。今まで自分が「これ、どうすればいいかな……」と2カ月悩んでいたことが、ユーザーの方々と会話して、PC開いて実践してみたら、その場で解決してしまう。あのスピード感と効率性が、僕の中ではすごく中毒のようになっていまして。つまりそれは、いろんな人とつながれば、その確率は確実に上がりますよね。
――ところで、みなさんはMarketo以外にもユーザー会に参加されていると思うのですが、他製品のユーザー会との違いは、どんなところでしょうか?

西田氏:私もいくつかのコミュニティーに参加していますが、Marketoは話しやすい雰囲気がありますね。なぜなのでしょうね?
水谷氏: 僕はやっぱり、ベンダーのスタンスが違うというのが大きいと思います。
西田氏: あぁ、それが理由なのかもしれないですね。ベンダー主導だと、ベンダーに乗っかっちゃえばいいや、みたいになって、聞き役に徹してしまう。
嶋田氏: 他のユーザー会だと、聞き出すだけ聞き出されて、私は何も得るものがない、と感じることがあります。「どうやって使っているのですか?」と質問ばかりされて、Marketoのようにキャッチボールをしようという雰囲気がないですね。
「使いたい海外のツールが、わずか10分でつなげられる。ビジネスのスピードは全然違う」
――Marketo自体の特徴についても教えてください。みなさん、ITreviewに投稿していただいたレビューでは、他のツールとの連携や拡張性をMarketoの良いところに挙げていらっしゃいますね
水谷氏:いろいろなツールとシームレスにつなげられるというのは、とても大きなメリットだと思います。現在、弊社でつなげているのは、SalesforceやBrightcove(動画配信)などですが、何かSaaSサービスを会社で導入するときには拡張性を重要視します。そういう観点でMarketoはWebフックという機能で、簡単にどんどん連携ができます。将来的にはBIとつなげるなど、マーケターのやりたいことの選択肢がすごく増える。これじゃないとダメという固定化された脳みそにはならない。自分がSaaSみたいになるというか。
嶋田氏:水谷さんの頭の中、SaaSなのですか?(笑)
水谷氏:いや、シームレスにいろんなものとつなげられて、発想もどんどん広がっていくというのがSaaSみたいだなと。

――嶋田さんも、マーケティング活動が変わっていく中で、ツール自体が固定化されていない、いわゆる拡張性が高い点をレビューで評価されています。
嶋田氏:はい。でも実は私、Marketoを導入した時に連携ができるって知らなかったのです。ユーザーコミュニティーに参加するにつれ、どうやらWebフックという機能があるらしいと気付きました。実際に使ってみると案外簡単で、Webフックがあるから、マーケティングの各フェーズで私がやりたいことに対し、Marketoがちゃんとついてきてくれるという経験をしました。
河原氏:そう、私も嶋田さんと同じで、最初はWebフックとかまったく知らない状態で、普通にセミナーメールを配信するなどに使っていました。使っていくうちに、例えばセミナー参加者がどれだけ集まっているかなどを定期的にチャットツールに飛ばしたいと思い始めて、そんな時、テクノロジーに詳しくない私でも調べればできた。そういったことをきっかけにGAS(Google Apps Script)やCSSも少し分かるようにもなりました。
メール配信だと、このセグメントの人にもっとこういった情報を届けると響くのでは? と思い付くことがあり、嶋田さんの会社のFORCASと連携し、より簡易的に個別最適したメールも送れるようになりました。こういうことをやってみたいなと思った時に、違うツールと連携できて、エンジニアがいなくてもラクにできるのがすごくいいなと思います。

西田氏:僕はMarketoを導入している企業をITの面から支援する立場です。MAを選定する時にも関わらせていただているのですが、将来、必ずいろいろなツールと連携したくなるので、連携に強いツールがいいと助言させていただいています。
山田氏:弊社の場合、今ぱっと頭に浮かぶだけで、十数個のツールとつなげていますね。私がツールを検討する際には、必ずワールドワイドで使えるかというところでまず検討を始めます。Marketoは、世界でもスタンダードとして認知されているツールなので、さまざまなツールと非常に接続がしやすい。加えて、弊社では、自社システムとの連携もかなりあります。Marketoは、汎用的にスクラッチで組み合わせるということもできるので、その両方ができるというところも大きなメリットですね。
水谷氏:最近、弊社が求めているマーケティング要件というのが、国内のツールではまかなえなくなっています。日本にはない海外のツールを使ってみると、当たり前のようにMarketoと連携できる。コネクターが普通にあり、プログラミングができなくてもどんどんつなげていける。これはもう、ビジネスのスピードは全然違うと思いますね。先ほど紹介したBrightcoveは作り込みでつなげるとなると、たぶんインプリだけで2~3カ月かかると思います。それが、ものの10分もあればできる。あれを見たときに、Marketo選んでおいてよかったなと思いました。
――みなさん、本日はユーザーコミュニティーからMarketoの拡張性の高さまで、貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
ITreviewにレビューとして提供いただいたIT製品の活用実績や利用体験は、現在、IT選びに悩む方の貴重な情報となっています。まだレビューを投稿されていない方はこの機会にレビューを投稿いただき、もっとITの選びやすい世界を一緒に作りませんか?
投稿 Marketoのユーザーコミュニティは、なぜ盛り上がるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 国産MAベンダーのシャノン、カスタマーサクセス実践1年で解約件数が7割減に は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>国内における導入実績数900以上、キャンペーン実績数は実に22万以上――。国産MAツールの「SHANON MARKETING PLATFORM」(以下 SMP)を提供するシャノンは、MAという呼称が登場する前から、イベント/セミナーソリューションをはじめとするマーケティングソリューションを提供し、国内では多くの顧客の支持を得ていた。しかし2015年頃から外資系MAベンダーが相次いで日本に進出。次第に他社に乗り換える顧客が増加していった。
その危機的ともいえる状況を救ったのが、カスタマーサクセスを実践する同社のアカウントセールス部だ。2018年度に、これまでの既存顧客担当組織が担う役割において方向性の舵を大きく切り、1年間、ほぼ全てのお客さまを対象にカスタマーサクセスへの取り組みを行った。その結果、前年比で実に7割もの解約数を低減することに成功したという。同社のアカウントセールス部のメンバーは、いかにして顧客の信頼を獲得していったのか? 陣頭指揮を執るアカウントセールス部 部長 高橋良介氏にお話を伺った。
日本のMA市場はブルーオーシャンからレッドオーシャンに。契約を維持/拡大するカスタマーサクセスに注力
――日本では、専門的にカスタマーサクセスの取り組みを行う部署がある企業はまだ少ないといえます。貴社の場合、カスタマーサクセスを実践するアカウントセールス部はどのような経緯で、いつ組織化されたのでしょうか?
高橋氏: 既存のお客さまを担当する営業部を、アカウントセールス部という呼称に変更したのは、ちょうど1年前の2018年です。シャノンの製品はイベント、セミナーで昔からよく使われており、月額費用のサービスでも、一度契約を結べば解約されることは比較的ありませんでした。ですから、カスタマーサクセスのような活動はしなくても、ビジネスは成長できたのです。ところが2015年あたりから、日本のMA市場に外資系の競合が進出。ブルーオーシャンがレッドオーシャンになり、少しずつ解約が目立ち始めてきました。そこで、月額契約の維持/拡大を主たるミッションとする部門として、アカウントセールス部が立ち上がりました。

――どのくらいの顧客数に対し、何人でカスタマーサクセスを実践されているのでしょうか?
高橋氏: 新規営業部門で受注したお客さまを私たちアカウントセールス部のカスタマーエンゲージメントマネージャー(以下 CEM)が引き継ぐのですが、お客さま数は総数でおよそ300ドメインです。1社で複数のドメインを持っていらっしゃるケースもあるので、お客さま数の単位はドメインとしています。その300ドメインを6人のCEMでカバーしていますので、1人当たり約50ドメインを担当していることになります。CEMはお客さまに対するSMPの活用支援を通じて、できるだけ長く使っていただくための活動をしながら、一方で毎月迎えるそれぞれのお客さまの契約更新のための提案活動を行っているので、結構忙しいですね。
――そのような状況の中で、貴社ではお客さまの声をどのように集めて、それをどのように活用していらっしゃるのでしょうか?
高橋氏: 6人のCEMは、その名の通り、お客さまとのエンゲージを深めていく役割を持ちます。比較的契約金額の大きな層のお客さまに対しては、月1回の定例のミーティングを設定するなどし、そこで直接ご意見やご要望を伺うようにしています。定期的なコンタクトでご支援するのは、全体で30ドメイン程度です。個別のお客さまの環境を把握した上で、マーケティング課題、施策を伺い、シャノンで可能な支援を文書にまとめて、お客さまと共有します。基本合意をしたら、3カ月に1回のスパンで「ご支援計画書」というアクションプランを作成しお客さまと合意するケースもあります。四半期ごとにご支援計画書の前四半期の実施結果のご報告と、次四半期の計画の立案、合意を行います。
その他、カスタマーサポートの窓口に頂戴するご意見も重要な情報源となります。CEMは、お客さまへの計画的な訪問に加え、サポート窓口にお問い合わせいただいたお客さまへも、内容によっては対応し、課題への解決策や新機能の紹介などを行っています。

――直接訪問しお客さまの声を伺うことの他に、お客さまとの日頃の接点を増やし、より多くの声を集めるために実施されていることはございますか?
高橋氏: シャノンユーザーカンファレンスというユーザーさま向けのイベントを年1回開催し、多くのユーザーさまにお越しいただいております。このカンファレンスでは、当社社長によるシャノンの向かう方向性のプレゼンに始まり、製品開発の方針/新機能紹介/ユーザーさまによる事例紹介などをアジェンダとして実施しています。その後、懇親会によるネットワーキングの場もご出席者の方にご提供しております。その他、月に2~3回の頻度でシャノン製品の研修をユーザーさま向けに実施しております。
――そのようにお客さまから集めた声を「プロダクトの改善に生かす」といったケースもあるのでしょうか?
高橋氏: もちろん、あります。お客さまからのご要望を製品化するプロセスとしては、2つあります。1つは「製品要望受付」になります。こちらは、比較的開発投資が大規模、中規模の案件について、経営の観点と全社的な見地で実装の優先順位が決められます。メンバーは製品企画と製品開発を行う技術部中心に選定され、最終的には経営会議で決議されます。もう1つは「エンハンス(改善要望)」になります。比較的小規模な開発で解決できるような内容は、月1回のエンハンス会議で議論され、製品への実装がなされます。こういった仕組みをベースに、SMPはこれまで800を超える機能を実装しております。
KGIは月額費用を維持、あるいはプラスにすること。カスタマーサクセス実践後、解約件数は7割減に
――貴社の場合、カスタマーサクセスのKPIはどこに設定していますか?
高橋氏: 月額費用の金額を維持する、あるいはプラスにする。これがまずKGIとして大目標になります。それを実現するためのKPIとしては、四半期ごとの「ご支援計画書」の合意を年何回行うとか、定例ミーティングを毎月行えたかどうかなどが指標になっています。当たり前のことですが、お客さまの契約更新は、お客さまの決算の時期とは必ずしも連動していません。そのため、お客さまの予算確保時期を全件確認する、決裁者はどなたかを確認するということは、KPIというよりは、必ず押さえなければならないポイントになります。結果的にCEMは、月額費用の維持/向上を最優先事項として、そのための活動に多くの時間を割いています。
――カスタマーサクセスの活動を行う前と、そのようなKPIを掲げて1年間活動を行った後では、どのような変化がありましたか?
高橋氏: カスタマーサクセスの活動を行う以前は、年間でかなりの解約がありました。1年間はほぼ全てのお客さまへのカバレッジを行ったので、目に見えて解約は減少しました。解約件数でいうと、およそ7割減。3分の1になりました。特に、比較的契約金額の大きなお客さまへのカバレッジ活動を厚く実践したので、この層の解約はほぼなくなってきました。これは明らかに、カスタマーサクセスを実践した成果であるといえるのではないでしょうか。

「使えない」になる前に――月額費用を下げてでも、お客さまからの信頼を取りに行くことも
――いかにカスタマーサクセスの実践が効果的といえども、活動を開始して1年でそこまでの成果はなかなか得られないと思います。何がポイントとして挙げられるのでしょうか?
高橋氏: 基本的な流れとして、当社の新規の営業部門が最初に受注し、導入までを担当します。導入後、お客さまはアカウントセールス部に引き継がれます。アカウントセールス部のCEMはEWS(Early Warning System)というお客さまの利用状況可視化の仕組みによって、導入されたお客さまの利用状況を把握することができます。契約上は利用可能なのに、その中で限られた機能しか使っていないお客さまに対して、CEMは、月額費用を維持/向上するというKPIがあるものの、契約更新時にあえて使用していない機能をダウングレードすることもあります。
たとえ月額費用が下がっても、お客さまがより長期間の利用を続けていただければ、会社としてはプラスになるという判断です。当社の方から進んで使っていない機能をダウングレードする提案をさせていただくような真摯な姿勢をお見せすることで、お客さまは「損得ヌキで、ユーザーのことを考えてくれている」と感じてくださり、さらなる信頼を勝ち得ることができ、結果的に解約を阻止できるポイントの1つになる、そう思っています。
――なるほど。目先の利益よりも、お客さまからの信頼が大切ということですね。逆に、貴社がカスタマーサクセスを実践する上で、課題と感じていらっしゃることはありますか?
高橋氏: 手探りの状態で始めてまだ1年ですから、課題はたくさんあります。アカウントセールス部の人手が足りていないので、新規営業からお客さまをタイムリーに引き継げないケースもあり、課題の1つとなっています。導入後、速やかに運用に入りませんと、お客さまのせっかく盛り上がった導入機運も下がってしまい、逆に経営層からは導入成果を求められるような状況になることがあります。初めてCEMが訪問した際に、いきなり解約の相談をお受けすることが実際にあります。そういった状況を打開し、速やかかつスムーズな引き継ぎを行うために、引き継ぎプロセスを標準化しました。また、毎月次で新規営業とアカウントセールス部のリーダーが案件状況を情報共有する会議も始めました。
また、誰がカスタマーサクセスを担当しても、お客さまに同じ品質で対応できるようにするというのも、これからの課題です。今までCEMは、個々のやり方で活動を行っていました。これを基本的な部分については、テンプレート化していこうとしています。カスタマーサクセスプロセスの標準化を進めることが、少ない人数で生産性を上げる策にもなると思っています。

ユーザーコミュニティーも2018年末に立ち上げ、次の1年は攻めのカスタマーサクセスを実践
――カスタマーサクセスを実践する企業は、ユーザー同士が交流できるコミュニティーという仕組みを持っているところが少なくありません。貴社の場合は、いかがですか?
高橋氏: 1年間活動を行ってみてカスタマーサクセスが効果的だと実感できたので、次の1年はさらに攻める年にしたいと思い、2018年末にユーザー会を立ち上げました。ユーザーさまとメーカーという視点だけでなく、ユーザーさま同士での情報交換を通じて、マーケティング活動にお役立ていただいたり、シャノン製品の活用度を向上したり。そのような場が必要というお客さまの声を踏まえて、このシャノンユーザー会を発足させました。コアとなるユーザーさまに幹事になっていただき、隔月でユーザー会を開催していく予定で、少人数でのディスカッションと勉強会を交互にやろうと計画しています。ツールも用意して、そこで「こんな使い方している」「こんな時はどうすれば?」など、ユーザーさま同士がシャノンを通さずにコミュニティーを活用され、ご利用を促進していただくことをイメージしています。
シャノンのCEMは、通常の営業活動に加えて、日々、運用相談などのご支援も行っております。そのようなご支援活動に加えて、ユーザー会におけるユーザーさま同士の情報交換、相互触発は、私たちにとって大きな財産になると考えています。先日、第1回のユーザー会を開催させていただきました。その場では活発な議論が繰り広げられ、当社としても手応えを感じているところです。
取材にご対応いただいたシャノンの製品レビューはこちら
ITreviewとは
ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。
ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?
投稿 国産MAベンダーのシャノン、カスタマーサクセス実践1年で解約件数が7割減に は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 カスタマーサクセスでなく“カスタマーエンゲージメント”。 マルケトの顧客との向き合い方と、人気のユーザーコミュニティーとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>「カスタマーサクセス」実践の基本は、顧客との接触(タッチ)だ。頻繁に打ち合わせを行い、顧客の成功のための戦略や指針をすり合わせるハイタッチの顧客もいれば、必要に応じてのみ直接打ち合わせを行うロータッチの顧客もいる。それら全ての顧客と効率的かつ効果的に接触できる仕組みとして、多くのITサービス事業者が構築しているのが「ユーザーコミュニティー」だ。
今回は、MAツールの「Marketo」を提供し、そのユーザーコミュニティーが話題となっている株式会社マルケトを紹介。よくあるコミュニティーとは一味も二味も違う「熱量のあるユーザーコミュニティー」とは? 同社のカスタマーサクセスをけん引する小川高史氏にお話を伺った。
永続的に、Marketoユーザーの成功を支援していく。だから、カスタマーエンゲージメント
――貴社では、「カスタマーサクセス」と言わずに、「カスタマーエンゲージメント」と呼称されています。それには、何か理由があるのでしょうか?
小川氏:一過性の成功ではなく「永続的に」お客さまの成功を支援していくのが私たちの役割。だから、一般的にはカスタマーサクセスですが、弊社では「カスタマーエンゲージメント」と再定義しています。私が担当している2つの部門、1つは、コンサルティング部門ですが、こちらはMarketoを導入していただいたお客さまが目的に合わせて使っていただけるようコンサルティングしていくことが役割です。
もう1つのカスタマーエンゲージメント部門は、お客さまと伴走しながら、よりMarketoの活用を進めていただき、永続的に成功を享受できるような支援を行うことが役割になります。

株式会社マルケト カスタマーエンゲージメント本部 カスタマーエンゲージメント&コンサルティング部長
――貴社がカスタマーエンゲージメント(カスタマーサクセス)に取り組むようになったのは、いつ頃からでしょうか?
小川氏:カスタマーエンゲージメントの思想は最初からありました。日本法人は2014年に事業をスタートしたのですが、2015年末にカスタマーエンゲージメントの専任者を置き、2016年度から具体的な活動を始めています。当時のミッションは、「ユーザーコミュニティーを活性化させる」というもので、カスタマーエンゲージメントを実践する環境は、ある程度整ったといえます。
――カスタマーエンゲージメントの実践には、顧客の声をどのように聞き、どうやって生かしていくかが鍵になると思います。その点、貴社は、どのように取り組んでいらっしゃるのでしょうか?
小川氏:これまでは、お客さまへ訪問しヒアリングを行い、その声を社内へフィードバックしていましたが、正直、体系的に取り組んでいたとはいえませんでした。その反省を生かし、現在は定型化した2種のアンケートを作成してお客さまの声を集めようとしています。1つは主にMarketo製品に対する満足度を測るアンケート、もう1つはお客さまの経営戦略や目標、達成度などをうかがえる内容を作成しており、お客さまのニーズに合わせきめ細かな提案ができるように整備しています。これらは今後本格的に稼働する予定です。
導入理由の1つに「ユーザーコミュニティー」を挙げるユーザーも。その理由は?
――カスタマーエンゲージメントを実践する環境として、貴社には「熱量のあるユーザーコミュニティー」がありますね
小川氏:そうですね。私も入社前は、「これだけユーザーグループが盛り上がっているのだから、よほどいい製品なんだな」と感じていました(笑)。カスタマーエンゲージメントは、Marketoを使っていただいている全てのお客さまが対象になります。しかし、全てのお客さまに、毎回訪問して支援していくことがなかなか難しい。申し訳ないことですが、個別に対応していくことが難しいお客さまについては、ユーザーコミュニティーという仕組みを中心に支援させていただいています。
面白いのは、日本法人のスタートアップ時には、日本でも勢いのあるお客さまにMarketoを使っていただいていたので、こちらが仕掛けなくても、ユーザーであるマーケターさま同士が自然とMarketoのノウハウを共有し始められたことです。あるお客さまが「こんな使い方して大丈夫かな?」とコミュニティーにアップすると、「大丈夫、大丈夫」と、私たちではなく、熟練したお客さまが答えてくれる。それは次第に、Marketoの使い方だけでなく、「そもそもマーケティングって、どうすれば成果が上げられるのか」といった本質な議論をする場として、このユーザーコミュニティーが活用され始めました。
それがさらに発展して、いまではユーザー分科会という業種別、テーマ別のワーキンググループもたくさんでき、それらの開催自体もユーザーさまが主導してくださっています。人材業界のマーケターさまが集い、競合企業であっても自社のナレッジを共有し合う「HRKETO(ハルケト)」、女性のマーケターさまが集う「FEMIKETO(フェミケト)」など種類はさまざま。このように、お客さま同士が自然と交流していただいているのは、とてもありがたいことだと感じています。

――ユーザーコミュニティーを立ち上げてもなかなか活性化しないことに課題を抱えている企業も多い中、なんともうらやましい話ですね
小川氏:Marketoの製品サポートに終始していたら、ここまで盛り上がっていないと思います。私たちの「お客さまのビジネスの成功に貢献したい」という本気の思いをマーケターの方々に受け取っていただき、その皆さまがMarketoを自分自身で使いこなして成功を実現されている。そしてその成功を独り占めするのではなく、ノウハウを仲間のマーケターに広げる基盤として積極的にコミュニティーをご利用いただいているのだと思います。
実際、Marketoユーザーとして実績を積み上げられた方が社内外でキャリアアップされているケースも出てきています。多くのMA製品の中からMarketoを選んでいただいた理由に、「熱量のあるユーザーコミュニティーがあるから」を挙げてくださるお客さまも少なくありません。
カスタマーエンゲージメントの行動プロセスを体系化。顧客支援の仕組みも、さらにもう1つ
――そんな活性化したユーザーコミュニティーをベースに、いま取り組もうとされていることは、何かありますか?
小川氏:2つあります。1つ目は、個別対応が必要なハイタッチのお客さまに対して、何を聞いて、どういうチェックをすれば課題が把握できて、それに対してどういった支援をすべきなのか、といったカスタマーエンゲージメントの行動プロセスを体系化しました。加えて半年に1回、お客さまの経営層に対し、Marketoを使って、当初の目標は達成されているか、どのような成果が上がっているかなどを、きっちりとビジネスレビューしていくことを実践しようとしています。
2つ目は、弊社には先に挙げたユーザーコミュニティーという優れた仕組みがありますが、それに加えて顧客支援の仕組みをさらに1つ準備しています。例えば、機能が多くて使いづらい、分かりづらいという声は少なからずあります。通常ですとカスタマーサポートサイトをご利用いただくことになるのですが、「いまやっているから、いま回答が欲しい。どこに情報があるか分からない」という方も多い。その困り事をカバーするために、チャットによるお問い合わせを受ける仕組みを用意しようとしています。何か困ったことがあれば、チャットですぐに解決策のサイトに誘導したり、ユーザーコミュニティーに記事があれば、それを紹介したりしていく予定です。

――SaaS型のサービスは、その顧客の利用状況が把握できる。例えば、顧客の声が挙がらなくても、利用状況を見ていれば、先んじた対応ができると思いますが、そのような取り組みはありますか?
小川氏:従来、お客さまの利用状況はモニタリングしていますが、それは機能を使われているかどうかという範囲に止まっていました。2018年には米国本社によって、機能ごとの利用度が解約とどう相関するのかが数値化され、解約に至らないためにモニタリングすべき6つのポイントが導き出されました。日本でもそのポイントを参照してカスタマーエンゲージメントに活用しようと試みているところです。
社会に出たら、まずカスタマーエンゲージメントを経験すべき
――最後に、これからカスタマーエンゲージメントに取り組もうとする企業や推進者に向けて、メッセージがあれば、お聞かせください
小川氏:カスタマーエンゲージメントに携わる人は、お客さまのビジネスを成功に導く役割を持つ人です。当然ですが、ある程度経験を積んだ人が実践していくということが、通常です。でも、私は逆の発想を持っており、キャリアの早い段階で、カスタマーエンゲージメントを経験したほうがいいと思っています。それは、カスタマーエンゲージメントの考え方や理念を早い時期に学んで、お客さまが自社の製品に対して、どういった意見を持っているのか、どういった課題があって、どうして解約に至ってしまうのと考える経験が、営業なり、コンサルタントなり、テクニカルサポートなり、そのあとのキャリアを進む上で重要な財産になると思っているからです。
お客さまと同じ方向を見ることの重要性に気付くのは、早ければ早いほどいいのではないかと感じています。実際、弊社は昨年、初の新卒採用の新人を迎えたのですが、その新人をカスタマーエンゲージメント部門に配属し、お客さまとのコミュニケーションを通じて、カスタマーエンゲージメントを体感するようにしています。

取材にご対応いただいたマルケトの製品レビューはこちら
ITreviewとは
ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。自社製品を掲載し、レビューを集めて活用していくことで、 顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。
ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?
投稿 カスタマーサクセスでなく“カスタマーエンゲージメント”。 マルケトの顧客との向き合い方と、人気のユーザーコミュニティーとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 事例:カスタマーサクセスの夜明け は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>従来、IT製品の提供形態はパッケージやハードなどの売り切り型が当たり前だった。それがビジネス環境の急速な変化に伴い、利用した分だけの対価を支払うサブスクリプションモデル型への転換が図られていることは、もはやいうまでもない。これに伴い、IT事業者と顧客との関わり方も大きく変わってきている。
米国ではすでに一大潮流となっている「カスタマーサクセス」という考え方。提供した製品やサービスによって顧客が獲得する成功を第一とし、製品/サービスを提供した側が、契約後も積極的に関与・伴走していくというものだ。日本でもサブスクリプションモデルを提供する事業者を中心に、このカスタマーサクセスを取り入れようとする動きが活発化している。まさに、日本のカスタマーサクセスは夜明けを迎えようとしているのだ。
本企画は日本においてカスタマーサクセスへの取り組みを始めている企業とその立役者を取り上げ、取り組み方や具体的な施策、苦労した点などの軌跡を紹介。カスタマーサクセス成功のためのTipsを連載形式で紹介していく。

RPAテクノロジーズのカスタマーサクセス事例――既存顧客の継続率95%超を維持するための策とは
BizRobo! のCSはユーザーコミュニティーの積極活用がカギに
RPAテクノロジーズ株式会社
2019.12.09

Slackのカスタマーサクセス事例――世界1000万人ユーザーの利用状況の把握方法とは?
グローバルカスタマーサクセス担当が来日、「お客さまの声は全社への声としてフィードバック」
Slack Japan 株式会社
2019.11.14

Dropboxのカスタマーサクセス事例――オンラインストレージからコラボレーションツールへと進化するために掲げるKPIとは?
顧客データを青、黄、赤の信号で見える化し、声なき声を把握
Dropbox Japan株式会社
2019.10.08

チャットプラスのカスタマーサクセス事例―毎日5件の製品改善で顧客の声をスピード反映
「製品の90%は、“顧客の声”でできている」月100件の契約を獲得する企業の戦術とは
チャットプラス株式会社
2019.09.03

ヤプリのカスタマーサクセス事例―1年でカスタマーサクセス組織を再構築、要となる全社の合意形成をどう作り上げたのか?
がむしゃらで失敗しながらも、チャーンレート1%前後を誇る実績に―1年の軌跡を追う
株式会社ヤプリ
2019.08.09


マツリカのカスタマーサクセス事例-顧客の売り上げを23.5%向上、その驚きの試みとは
営業支援ツールベンダーとして、顧客企業への営業コンサルティングまで徹底伴走
株式会社マツリカ
2019.06.25

イー・エージェンシーの日本流カスタマーサクセス、「おもてなし」の心を込める顧客対応とは?
自らの活動を「おもてなし」の観点からスコアリング、同社ならではの手触り感のあるカスタマーサクセス
株式会社イー・エージェンシー
2019.06.10

経理に携わる全ての人たちを、経営の“主役”に――freeeが挑む、もう1つのカスタマーサクセス
「ミスなくできて当たり前」の経理から、「経営にモノ申す」経理へ
freee株式会社
2019.05.24


ブイキューブ、カスタマーサクセスグループを業界特化組織へ分散――競合との差別化を図り、新体制へ
CS実施で解約率16.1%から11.7%を実現。1桁台の実現に向けた、新たな取り組みとは?
株式会社ブイキューブ
2019.04.18




ITreviewでカスタマーサクセスを実現しませんか?
ビジネス向けソフトウェア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、ソフトウェア・クラウドサービスの利用ユーザーのリアルな声を集めることが可能です。顧客の声を積極的に集め、真摯に向き合うことで、顧客満足度の向上、ブランディング、マーケティング、新規顧客獲得など、今までにないカスタマーサクセスが実現できます。
ITreviewを利用して、新しいカスタマーサクセスを実現しませんか?
投稿 事例:カスタマーサクセスの夜明け は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>