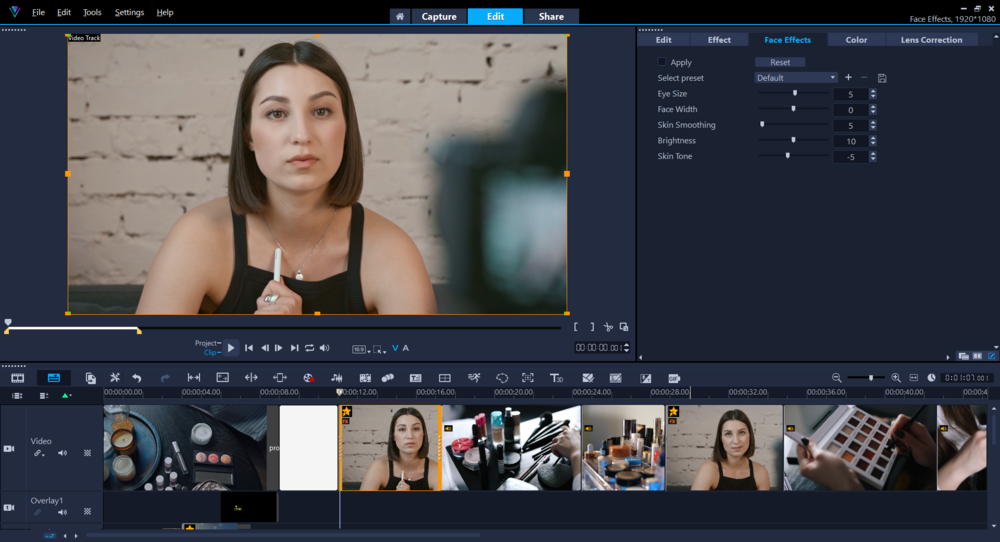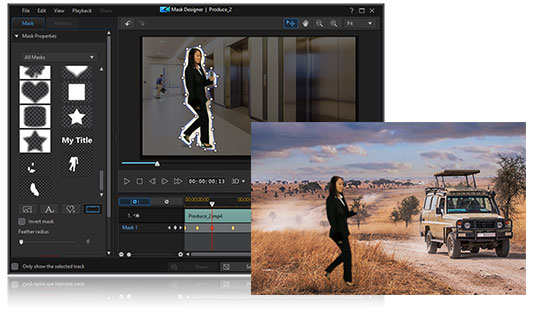投稿 OCRとは?仕組みやAI-OCRとの違い・活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>近年では、AIやディープラーニングの進化により、OCRの認識精度が向上し、業務のペーパーレス化やデータ入力の自動化を進める企業にとって、OCRは欠かせない技術となっています。
一方で、OCRの認識精度は文字の種類や書類の形式によって変動するため、利用目的に適したソフトやサービスを選定しないと、誤認識によるデータ入力ミスや業務効率の低下を招く可能性があります。
本記事では、OCRの仕組みやAI-OCRとの違いから具体的な活用事例、導入のメリットやデメリット、OCRソフトの選び方まで詳しく解説します。
OCRとは?
OCRとは、Optical Character Recognition(光学文字認識)の略称で、画像や紙の書類に書かれた文字をデジタル化し、編集可能なテキストデータに変換する技術のことです。
スキャナやカメラで撮影した文書をOCR処理することで、テキストデータとして編集・検索が可能になるもので、主に請求書や領収書データの自動入力などで活用されています。
近年では、AI(人工知能)技術を搭載したAI-OCRが登場し、従来のOCRでは認識が難しかった手書き文字や、書体・レイアウトが複雑な文書の認識精度が飛躍的に向上しました。
OCR技術は、企業における紙文書のデジタル化、業務効率化、そしてペーパーレス化を推進する上で重要な役割を果たしており、バックオフィス業務の自動化や情報活用において不可欠なテクノロジーとなっています。
OCRの仕組み
- ①:画像の前処理
- ②:文字の特徴の抽出
- ③:テキストへの変換
OCRの仕組みは、大きく分けて「画像の前処理」「文字の特徴の抽出」「テキストへの変換」の3つのステップで構成されています。
まず、画像の前処理では、スキャナやカメラで取得した画像を解析しやすくするために、傾き補正・ノイズ除去・コントラスト調整を行います。
次に、文字の特徴抽出の段階では、読み取る文字の形状、線の太さ、角の有無といった特徴を抽出し、あらかじめデータベースに登録された文字パターンと比較照合することで文字を特定します。
最後に、テキスト変換の段階で、認識された文字情報がデジタルデータとして出力され、検索や編集が可能になります。
従来のOCR技術とAI-OCRの違い
従来のOCR技術の特徴
従来のOCR技術は、パターンマッチングやルールベースの手法を用いて文字を認識する方式です。
特定のフォントやレイアウトで印刷された規則的な書類・帳票の活字認識では高精度を発揮するものの、異なるフォントや手書き文字、文字の配置によっては正確に読み取れないこともあります。
また、文脈を理解せずに単独の文字単位で認識を行うため、大量の書類処理には不向きです。そのため、一定のフォーマット内で活字を認識する用途に特化したものと言えます。
最新のAI-OCR技術の特徴
AI-OCRは、ディープラーニング(深層学習)を活用したOCR技術で、従来のOCRと比較して、手書き文字や複雑なフォーマットの文書にも高精度で対応できる点が特徴です。
AI-OCRは、単に文字を認識するだけでなく、文脈を考慮した解析を行います。そのため、フォントやレイアウトが崩れていてもより正確な認識が可能です。また、学習を重ねることで認識精度が向上していきます。
加えて、AI-OCRは画像補正やノイズ除去といった処理を自動で行うため、スキャナやスマートフォンで撮影した歪みのある画像からでも高精度な認識が可能です。そのため、手書きの書類や異なるフォーマットの帳票を扱う業務に適しています。
OCRの活用事例
- 経理や財務:請求書や領収書を自動入力する
- 物流や倉庫:各伝票や納品書を自動入力する
- 法務や契約管理:契約書や申込書を自動入力する
- 営業や顧客管理:先方の名刺をデジタル管理する
経理や財務:請求書や領収書を自動入力する
経理業務では、請求書や領収書のデータ入力をOCRで自動化することで、手入力による負担を軽減し、処理速度を向上させることが可能です。
従来は、請求書の金額や日付などは手入力で行っており、入力ミスが発生しやすいのが課題でした。しかし、OCRを導入すれば、紙の請求書をスキャンするだけで自動的にデータ化できるため、入力ミスを防ぎつつ作業時間を短縮できます。
さらに、AI-OCRを活用することで、フォーマットが異なる請求書にも対応できるため、取引先ごとに書類形式が異なっていても正確な処理が可能です。
物流や倉庫:各伝票や納品書を自動入力する
物流業界では、出荷伝票や納品書のデータ入力をOCRで自動化することにより、業務効率を大幅に改善できます。
従来は、配送業者が伝票情報を手作業で入力していましたが、OCRを活用することで、スキャンするだけで荷物の詳細情報をデジタルデータとして取り込めます。
さらに、AI-OCRを活用すれば、手書きの伝票やフォーマットが異なる納品書も高精度で認識できるため、多様な物流書類の処理を自動化し、業務全体の効率化を実現できます。
法務や契約管理:契約書や申込書を自動入力する
法務部門では、契約書や申込書の管理にOCRを活用することで、検索性を向上させ、業務の効率化を図れます。
従来は、契約書の内容を確認する際に、紙の書類を手作業で探す必要がありました。しかし、OCRで契約書をデジタル化し、テキスト検索を可能にすることで、必要な情報を迅速に取り出せます。
また、AI-OCRを活用すれば、手書きの契約書やスキャンしたPDFの内容も正確にデータ化できるため、契約管理の精度向上につながるでしょう。
営業や顧客管理:先方の名刺をデジタル管理する
営業部門では、名刺をOCRでデータ化することで、顧客情報の管理を効率化できます。
従来は、名刺情報を手入力する必要があり、大量の名刺整理に時間を要していました。しかし、OCRを活用することで、名刺をスキャンするだけで自動的にテキストデータに変換され、顧客管理システム(CRM)への登録も容易になります。
さらに、AI-OCRを活用すれば、手書きのメモが書き加えられた名刺でも高精度でデータ化できるため、営業活動の効率化が期待できます。
OCR導入のメリット
- データ入力を自動化できる
- 入力のミスを削減できる
- 入力のコストを削減できる
- データの検索が容易になる
データ入力を自動化できる
OCRのメリットの1つ目としては「データ入力を自動化できる」というものが挙げられます。
手作業でのデータ入力は時間がかかりますが、OCRを活用することで、紙の書類やPDFに含まれる情報を自動的にデジタルデータに変換でき、入力作業を大幅に削減できます。
例えば、請求書やアンケートのデータをOCRで取り込むことで、手入力の手間を省き、業務を効率化できます。特に、大量の書類を扱う業務においては、作業負担の軽減につながるでしょう。
入力のミスを削減できる
OCRのメリットの2つ目としては「入力のミスを削減できる」というものが挙げられます。
人が手入力を行う場合、数字や文字の誤入力は避けられません。しかし、OCRを導入することで、文字認識技術を用いてデータを正確に読み取れるため、入力ミスを防止できます。
例えば、顧客情報や受発注データをOCRで読み取ることで、転記ミスをなくし、正確なデータ管理を実現できます。
入力のコストを削減できる
OCRの3つ目のメリットとしては「入力のコストを削減できる」というものが挙げられます。
データ入力業務は、人的リソースと時間を多く要するため、コスト負担が大きくなりがちです。特に、大量の書類を扱う企業にとって、手作業の削減が直接的なコスト削減につながります。
例えば、経理部門での請求書データ入力をOCRで自動化することで、入力担当者の作業時間を削減し、人件費を抑制できます。
データの検索が容易になる
OCRの4つ目のメリットとしては「データの検索が容易になる」というものが挙げられます。
紙の書類やスキャンしたPDFは、必要な情報を探すのに手間がかかりますが、OCRでテキスト化することで、キーワード検索が可能になります。
例えば、契約書や報告書をOCRでデータ化すれば、検索機能を使って必要な箇所を素早く特定できるため、時間短縮と業務効率化につながります。
OCR導入によるデメリット
- 導入や運用にはコストが発生する
- 画像の誤認識が発生する恐れがある
- 継続的なメンテナンスが必要になる
導入や運用にはコストが発生する
OCRのデメリットの1つ目としては「導入や運用にはコストが発生する」というものが挙げられます。
OCRソフトやAI-OCRサービスを導入するには、初期費用や月額料金が発生します。また、システムとの連携や運用体制の整備にも追加コストが必要になる場合があります。
解決策としては、無料トライアルを活用して、自社の業務に適したOCRソフトを選定することや、初期費用を抑えられるクラウド型OCRサービスの利用を検討するのもよいでしょう。
画像の誤認識が発生する恐れがある
OCRのデメリットの2つ目としては「画像の誤認識が発生する恐れがある」というものが挙げられます。
OCR技術は進化しているものの、手書き文字や特殊なフォント、画質の低い画像など、読み取りが難しいケースが存在します。そのため、最終的に手作業での修正が必要になることがあります。
解決策としては、AI-OCRを活用し、学習データを増やして精度を向上させることや、OCR処理の前段階で画像補正処理を施し、入力データの品質を高めることが挙げられます。
継続的なメンテナンスが必要になる
OCRのデメリットの3つ目としては「継続的なメンテナンスが必要になる」というものが挙げられます。
OCRシステムを導入した後も、新しい書類フォーマットに対応したり、認識精度を維持・向上させたりするために、定期的なメンテナンスが欠かせません。特にAI-OCRの場合は、継続的に学習データを更新していく必要があります。
解決策としては、クラウド型OCRを選択し、ベンダー側による自動アップデートを利用することや、定期的にOCRの認識精度を評価し、必要に応じて設定を最適化することも重要です。
OCRソフトの選び方と比較のポイント
- ①:認識精度を確認する
- ②:処理速度を確認する
- ③:導入形態を確認する
- ④:対応ファイルを確認する
- ⑤:価格や料金体系を確認する
- ⑥:セキュリティ機能を確認する
- ⑦:外部システムとの連携を確認する
①:認識精度を確認する
OCRソフトの選び方の1つ目としては「認識精度を確認する」という方法が挙げられます。
OCRソフトの最も重要な要素は高い認識精度です。特に日本語や多言語対応が必要な場合、認識率の違いが業務効率に大きく影響します。
例えば、Google Cloud VisionやABBYY FineReaderは、多言語対応かつ高精度な文字認識が特長であり、企業利用において高評価を得ています。
②:処理速度を確認する
OCRソフトの選び方の2つ目としては「処理速度を確認する」という方法が挙げられます。
業務用途では、大量の書類を迅速に処理する高速性が求められます。処理速度が遅いと業務全体が滞り、生産性に悪影響を及ぼします。
たとえば、Adobe Acrobat ProやReadirisは、バッチ処理機能を備えており、大量書類の連続スキャンでもスピーディな処理が可能です。
③:導入形態を確認する
OCRソフトの選び方の3つ目としては「導入形態を確認する」という方法が挙げられます。
クラウド型とオンプレミス型があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。クラウド型は柔軟性が高く、アップデートが容易ですが、データ保護の観点でオンプレミス型が好まれるケースも多いです。
たとえば、クラウド型のMicrosoft Azure OCRはリモートから利用でき、オンプレミス型のABBYY FineReader Serverは社内完結のセキュリティを重視しています。
④:対応ファイルを確認する
OCRソフトの選び方の4つ目としては「対応ファイルを確認する」という方法が挙げられます。
PDFや画像ファイルだけでなく、ExcelやWord形式への出力対応も業務効率を大きく左右します。多様なファイル形式に対応しているか事前に確認が必要です。
例えば、Adobe Acrobat ProではPDFやWord、Excelに変換が可能であり、幅広いファイル形式に対応している点が特長です。
⑤:価格や料金体系を確認する
OCRソフトの選び方の5つ目としては「価格や料金体系を確認する」という方法が挙げられます。
コストパフォーマンスを意識した選択が重要です。月額制や買い切り型など料金形態が異なるため、自社の利用頻度に応じた選択が求められます。
たとえば、Google Cloud Vision APIは従量課金制であり、利用頻度が少ない企業に適している一方、ABBYY FineReaderは買い切りライセンスが魅力です。
⑥:セキュリティ機能を確認する
OCRソフトの選び方の6つ目としては「セキュリティ機能を確認する」という方法が挙げられます。
業務用途では機密情報の取り扱いが多く、データ保護が重要です。暗号化機能やアクセス制限機能があるかどうかを確認する必要があります。
例えば、DocuWareやReadirisでは、高度なセキュリティ管理が実現されており、データ漏えいリスクを最小限に抑えることが可能です。
⑦:外部システムとの連携を確認する
OCRソフトの選び方の7つ目としては「外部システムとの連携を確認する」という方法が挙げられます。
ERPやCRMなど他のシステムとスムーズに連携できるかは、業務効率を高めるために重要です。API連携やWebhook対応があるかも確認が必要です。
例えば、Microsoft Power Automateと連携できるAdobe Acrobat Proは、ワークフロー自動化が可能であり、企業システムと密接に統合できます。
OCRの誤認識を防ぐためのポイント
- 高品質な画像データを使用する
- OCRに適したフォントを使用する
- OCRの実施前に画像の補正を行う
高品質な画像データを使用する
OCRの誤認識を防ぐためのポイント1のつ目としては「高品質な画像データを使用する」というものが挙げられます。
OCRの精度は、画像の解像度やコントラスト、ノイズの有無によって大きく影響を受けます。特に低解像度の画像では、文字がぼやけたり、潰れたりしてしまい、誤認識が発生しやすくなります。
解決策として、最低でも300dpi以上の解像度でスキャンすることや、背景のノイズを減らすために白黒モードで撮影することが推奨されます。また、スマートフォンで撮影する場合は、手ブレを防ぎ、明るい環境で撮影することも重要です。
OCRに適したフォントを使用する
OCRの誤認識を防ぐためのポイントの2つ目としては「OCRに適したフォントを使用する」というものが挙げられます。
OCRは、シンプルなフォントで、文字が均等に配置されているものを正確に認識する傾向があります。一方、手書きのようなフォントや装飾の多いフォント、文字の間隔が不揃いなレイアウトは、誤認識を引き起こしやすくなります。
特に、業務でOCRを活用する場合は、ゴシック体や明朝体などの認識しやすいフォントを使用し、文字を均等に配置することが重要です。また、表形式やリスト形式の文書では、枠線や区切り線をはっきりとさせることで、誤認識を減らせます。
OCRの実施前に画像の補正を行う
OCRの誤認識を防ぐためのポイントの3つ目としては「OCRの実施前に画像の補正を行う」というものが挙げられます。
OCRの精度を高めるためには、事前にOCRソフトの画像補正機能を活用して、ノイズや歪みを取り除くようにしましょう。特に、斜めに撮影された画像や文字が傾いている場合、OCRが正しく認識できないことがあります。
加えて、スキャナー利用時は原稿を固定し、画像の歪みを抑えることも、誤認識を防ぐうえでは重要な要素のひとつです。
まとめ
本記事では、OCRの概要を解説するのとともに、OCRの仕組みや従来のOCR技術とAI-OCRの違い、導入によるメリット・デメリット、選び方のポイントまで詳しく紹介しました。
企業の業務効率化やデジタル化の推進において、OCRの活用は欠かせないものとなっています。特に、AI技術の発展により、OCRの認識精度や処理能力は今後さらに向上していくと考えられます。
今後もITreviewでは、OCRソフトのレビュー収集に加えて、新しいOCRソフトも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 OCRとは?仕組みやAI-OCRとの違い・活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 LPOとは?SEOやEFOとの違いから効果的な改善方法までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、LPOにはデザインの最適化やCTA(コール・トゥ・アクション)の調整、A/Bテストの実施など、多岐にわたる項目が存在しているため、適切に運用しなければ効果が表れにくく、広告費の無駄使いにつながってしまう可能性もあります。
本記事では、LPOの概要をわかりやすく解説することに加えて、導入によるメリット・デメリット、具体的な改善方法まで詳しく解説します。
この記事を読むことで、LPOの全体像を理解しながら成果につながる施策を実行できる知識が身につくため、Webマーケティング担当者や広告運用担当者には必見の内容です!
LPO(ランディングページ最適化)とは?
LPO(ランディングページ最適化)とは、Webサイトのランディングページ(LP)を改善し、コンバージョン率を高める施策のことです。広告効果を向上させ、ユーザーの意思決定を促すため、多くの企業が導入しています。
主に、A/Bテストやヒートマップ分析、UI/UX改善を活用し、訪問者の行動を可視化しながら最適化を進めます。例えば、CTAボタンの色や配置を変更したり、フォームの入力項目を減らすことで、コンバージョン率を向上させます。
具体的な施策としては、CTAボタンの配置変更やコピーの最適化、フォームの簡素化などが挙げられます。さらに、スマートフォン対応を強化し、ユーザーの離脱を防ぐことで、問い合わせ数や売上の増加につなげることが可能です。
LPOが注目されるようになった理由
- デジタルマーケティングの競争の激化
- デジタル広告費の高騰とROI向上の必要性
- ユーザー行動の活用とパーソナライズの進化
デジタルマーケティングの競争の激化
デジタルマーケティングが急速に広まり、さまざまな企業がオンラインでの顧客獲得に乗り出しています。
その結果、検索エンジンやSNS広告などでユーザーをランディングページへ誘導する施策が一般化し、競争が激化しました。
競争が激しい中で成果をあげるには、単に広告を出すだけでなく、訪問後のユーザーを確実にコンバージョンさせるため、ランディングページを効果的に改善・最適化する必要が生まれています。
デジタル広告費の高騰とROI向上の必要性
オンライン広告市場の拡大に伴い、広告出稿費用が大幅に上昇しています。企業は限られた予算内で最大限の成果(ROI:投資対効果)を上げることが求められています。
こうした状況で、広告費を無駄にせず、訪問ユーザーを効率よくコンバージョンに結びつける手法としてLPOが注目されるようになりました。
広告効果の最大化と費用対効果の改善を実現する手法として、LPOの重要性は今後も高まっていくでしょう。
ユーザー行動の活用とパーソナライズの進化
近年のマーケティングでは、ユーザー行動データの収集・分析技術が飛躍的に進化しました。
これにより、ユーザーの属性や興味関心に合わせてランディングページをパーソナライズする手法が可能になっています。
ユーザーごとのニーズに適した情報を提供することで、離脱率を下げ、コンバージョン率を高めるLPOが現実的な選択肢となったことも、LPOが注目を集める背景となっています。
LPOとSEO・EFOの違いとは?
| LPO | SEO | EFO | |
|---|---|---|---|
| 最適化対象 | ランディングページ(LP) | サーチエンジン(SE) | エントリーフォーム(EF) |
| 実施の目的 | コンバージョン率の改善 | 検索表示順位の改善 | 入力完了率の改善 |
| 施策の具体例 | ・クリエイティブを変更する ・CTAの色やテキストを変更する ・コピーの文言や配置を変更する |
・コンテンツの質を高める ・被リンク施策を展開する ・サイトマップ構造を見直す |
・入力項目を簡素にする ・エラー表示の視認性を高める ・フォーム入力の負担を軽減する |
LPOとSEOの違い
LPOとSEOの違いは、対象とするページの目的です。SEO(検索エンジン最適化)は、検索結果での上位表示を狙い、集客を増やすことを目的としています。
具体的には、適切なキーワードの選定やコンテンツの質の向上を行い、検索エンジンからの流入を増やします。一方で、LPOは、訪問者が成約(コンバージョン)しやすいページ設計を行うことが目的です。
例えば、SEOでは「特定のキーワードで検索結果の上位を狙い、流入数を増やす施策」を行います。一方、LPOでは「流入したユーザーの問い合わせ率や購入率を高める施策」を重視します。
LPOとEFOの違い
LPOとEFOの違いは、最適化する対象の範囲にあります。EFO(エントリーフォーム最適化)は、ユーザーが入力フォームで離脱しないように改善する施策です。
具体的には、「入力項目の簡素化」「エラー表示のわかりやすさ」「スマートフォンでの入力のしやすさ」などを最適化し、フォームの送信率向上を目指します。一方、LPOでは「ランディングページのデザインを改善し、ユーザーの関心を引き、行動を促す施策」に重点を置きます。
例えば、EFOでは「入力ミスの修正をしやすくする」「フォーム入力の負担を軽減する」などの施策を行います。一方、LPOでは「CTAボタンの色や配置を変更する」「ページのファーストビューを改善する」などの改善が主な施策です。
LPOのメリット
- コンバージョン率(CVR)を向上できる
- 広告の費用対効果(ROI)を改善できる
- ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる
- ページの離脱率や直帰率を低減できる
- 顧客のインサイトを把握しやすくなる
コンバージョン率(CVR)を向上できる
LPOのメリットの1つ目としては「コンバージョン率(CVR)を向上できる」というものが挙げられます。
LPOを実施することで、訪問者が必要とする情報を適切に提示し、行動を促しやすくなります。特に、CTA(Call To Action)の最適化やフォームの簡略化は効果的です。
例えば、A/Bテストを用いて、よりクリックされやすいボタンのデザインや文言を検証することで、エントリー率の向上が期待できます。
広告の費用対効果(ROI)を改善できる
LPOのメリットの2つ目としては「広告の費用対効果(ROI)を改善できる」というものが挙げられます。
適切にLPOを実施することで、広告から流入したユーザーのコンバージョン率を高め、無駄な広告費を削減できます。特に、ターゲットユーザーに最適化されたページを用意することで、広告の成果を最大限に引き出すことが可能です。
例えば、リスティング広告のキーワードごとに専用のランディングページを作成することで、クリック後のユーザー体験が向上し、広告費の投資対効果を高められます。
ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる
LPOのメリットの3つ目としては「ユーザーの体験(UI/UX)を向上できる」というものが挙げられます。
訪問者が求める情報を分かりやすく提供し、目的をスムーズに達成できるページ設計を行うことで、ユーザーの満足度が向上します。特に、直感的なデザインや読みやすいコンテンツは重要です。
例えば、ページの読み込み速度を改善したり、モバイル端末向けにレスポンシブデザインを導入することで、ストレスのない閲覧環境を提供できます。
ページの離脱率や直帰率を低減できる
LPOのメリットの4つ目としては「ページの離脱率や直帰率を低減できる」というものが挙げられます。
ランディングページの構成を最適化することで、訪問者が途中でサイトから離れてしまうリスクを減らせます。特に、視線誘導を意識したデザインや適切な情報配置が重要です。
例えば、ファーストビューに魅力的なキャッチコピーを配置したり、画面をスクロールせずに重要な情報を伝えたりすることで、ユーザーの興味を引きつけやすくなるでしょう。
顧客のインサイトを把握しやすくなる
LPOのメリットの5つ目としては「顧客のインサイトを把握しやすくなる」というものが挙げられます。
ランディングページの改善プロセスを通じて、ユーザーの行動データを蓄積し、ニーズを深く理解できます。特に、ヒートマップ分析やA/Bテストの活用は効果的です。
例えば、どのボタンがクリックされやすいのか、ページのどの部分でユーザーが離脱しやすいのかを分析することで、より成果につながるページ設計が可能になります。
LPOのデメリット
- 継続的な分析と改善が必要になる
- 専門的な知識やツールが必要になる
- 短期間では成果が出ない可能性がある
継続的な分析と改善が必要になる
LPOのデメリットの1つ目としては「継続的な分析と改善が必要になる」というものが挙げられます。
LPOは一度実施すれば終わりではなく、常にデータを分析しながら改善を続ける必要があります。特に、ユーザーの行動パターンや市場の変化に合わせて最適化していくことが求められます。
解決策としては、ヒートマップやA/Bテストを定期的に実施し、効果的な施策を自動化できるツールを導入することが有効です。継続的な運用体制を整えることで、最小限の工数で最大の成果を得ることが可能になります。
専門的な知識やツールが必要になる
LPOのデメリットの2つ目としては「専門的な知識やツールが必要になる」というものが挙げられます。
効果的なLPOを実施するためには、ユーザー行動の分析やページ設計に関する専門知識が求められます。また、A/Bテストやヒートマップ解析などを行うためには、専用のツールを活用する必要があります。
解決策としては、使いやすいLPOツールを導入し、マーケティング担当者が基礎的なデータ分析スキルを習得することが有効です。また、専門のLPOコンサルティングサービスを活用することで、より効率的に最適化を進めることも可能になります。
短期間では成果が出ない可能性がある
LPOのデメリットの3つ目としては「短期間では成果が出ない可能性がある」というものが挙げられます。
LPOはデータをもとに改善を重ねる手法であるため、即効性のある施策とは限りません。特に、最適なデザインやコンテンツを見つけるまでに一定の時間がかかることが課題となります。
解決策としては、短期間で効果を検証できるA/Bテストを積極的に活用し、小さな改善を積み重ねることが重要です。また、既存の成功事例を参考にすることで、効果的な施策をスムーズに実施しやすくなります。
LPOの効果的な実施手順
- ①:目的設定とKPIを決定する
- ②:現状分析と課題を特定する
- ③:改善方針を決定する
- ④:A/Bテストを実施する
- ⑤:効果検証と継続的な改善を行う
①:目的設定とKPIを決定する
LPOを成功させるためには、明確な目的設定とKPIの決定が不可欠です。LPOの目的は、主にコンバージョン率の向上ですが、具体的なゴールを明確にすることで、最適な施策を実施できます。
例えば、ECサイトなら「購入完了数」、リード獲得型なら「問い合わせ数」など、目的に応じたKPIを設定することが重要です。KPIは「クリック率」「直帰率」「フォーム入力完了率」など、測定可能な数値を設定し、改善の指標とします。
明確なKPIを設定することで、LPO施策の効果を適切に評価し、継続的な最適化を進められます。まずは自社のビジネスモデルに応じたKPIを定め、改善の方向性を明確にしましょう。
②:現状分析と課題を特定する
LPOを成功させるには、現状のデータを分析し、課題を特定することが重要です。どの要素がコンバージョンを妨げているのかを特定し、具体的な改善策を検討する必要があります。
Google Analyticsやヒートマップツールを活用し、直帰率・離脱率・クリック率などを確認しましょう。例えば、CTAボタンのクリック率が低い場合は、配置やデザインの変更が有効です。
また、ユーザーのフィードバックや行動データを活用し、定性的な分析を行うことも重要です。これらの情報をもとに、課題を明確化し、効果的な改善策を導き出しましょう。
③:改善方針を決定する
課題が明確になったら、具体的な改善方針を決定します。優先度の高い問題から取り組み、ユーザーの利便性やコンバージョン率向上につながる施策を検討しましょう。
例えば、CTAボタンのデザイン変更やフォームの入力項目削減など、ユーザーの負担を減らす施策が考えられます。また、ページの読み込み速度を改善することで、離脱率を下げることも可能です。
改善策は、仮説を立てて実施し、データをもとに効果を検証することが重要です。最適な手法を見極めながら、継続的にブラッシュアップしていきましょう。
④:A/Bテストを実施する
改善策の効果を正しく検証するには、A/Bテストの実施が必要です。異なるデザインやコンテンツを比較し、どの要素がコンバージョン率向上につながるのかをデータで検証します。
例えば、CTAボタンの色や文言、フォームの入力項目数、画像の配置などを変更し、ユーザーの反応を比較します。A/Bテストの実施には、専用のツールを活用することで、簡単かつ効率的にデータを収集できます。
テスト結果は、十分なサンプル数を確保したうえで統計的に分析し、確実な改善につなげることが重要です。データに基づいた意思決定を行い、効果的なLPへと最適化していきましょう。
⑤:効果検証と継続的な改善を行う
A/Bテストの結果をもとに、LPOの効果を検証し、継続的に改善を進めましょう。一度の施策で最適な状態になるとは限らないため、データを分析しながらPDCAサイクルを回していく必要があります。
具体的には、コンバージョン率や直帰率の推移を確認し、改善の成果を数値で把握します。仮説通りの効果が得られなかった場合は、別の要素を見直し、再度テストを行うことが有効です。
LPOは一度実施して終わりではなく、ユーザーニーズや市場の変化に合わせて継続的に最適化することが重要です。データに基づいた効果的な改善を積み重ね、成果を最大化していきましょう。
LPOの具体的な改善ポイント
- ファーストビューの最適化
- CTAやリンクボタンの最適化
- 問い合わせフォームの最適化
- 説得力のあるコンテンツの追加
- スマートフォンへの対応の強化
ファーストビューの最適化
「ファーストビューの最適化」は、LPOにおいて最も重要な要素のひとつです。訪問者がアクセスした瞬間に興味を引き、目的の行動へと誘導する必要があります。
最適化されていないとユーザーはすぐに離脱し、コンバージョン率が低下します。視線の動線を考慮したレイアウト、直感的なメッセージ、適切なビジュアルの活用が欠かせません。
例えば、「魅力的なキャッチコピー+目立つCTAボタン+信頼を高める要素(実績・ロゴ)」を組み合わせると効果的です。
CTAやリンクボタンの最適化
「CTAやリンクボタンの最適化」は、LPOの成果を大きく左右する重要なポイントです。CTAとは、購入・問い合わせ・資料請求などの行動を促すボタンやリンクを指します。
CTAが分かりにくい、目立たない、魅力がない場合、ユーザーのアクション率は低下します。そのため、「視認性の向上」「訴求力のあるテキスト」「配置の最適化」が必要です。
例えば、「目立つ色に変更」「アクションを具体化(例:無料で試す)」「視認しやすい位置に配置」することで、コンバージョン率が向上します。
問い合わせフォームの最適化
「問い合わせフォームの最適化」は、LPOにおいてコンバージョン率を向上させる重要な施策です。入力項目が多すぎる、分かりにくい、動作が遅いといった問題があると、ユーザーは離脱してしまいます。
コンバージョン率を上げるには、「入力負担の軽減」「直感的なUI」「信頼感の向上」がポイントとなります。具体的には、入力項目を最小限にする、リアルタイムでエラーを表示する、オートコンプリート機能の活用が効果的です。
例えば、「名前・メールアドレス・電話番号」のみに絞ったシンプルなフォームにすると、離脱率が低減し、コンバージョン率が向上します。また、プライバシーポリシーの明記やSSL対応を行い、ユーザーに安心感を与えることも重要です。
説得力のあるコンテンツの追加
「説得力のあるコンテンツの追加」も、コンバージョン率を向上させるには不可欠です。ユーザーは購入や問い合わせ前に「信頼できるのか?」と疑問を持つため、不安を解消する情報を提供する必要があります。
具体的には、「実績の紹介」「顧客の声」「データや数値による根拠」を活用することが効果的です。例えば、「導入企業数〇〇社」「満足度95%」「具体的な成功事例」を掲載すると、信頼を獲得しやすくなります。
さらに、ビフォーアフターの事例やFAQ(よくある質問)を掲載し、ユーザーの疑問を事前に解決することで、安心してCTAをクリックできる環境を整えることが重要です。
スマートフォンへの対応の強化
「スマートフォンへの対応の強化」も、LPOにおいて欠かせない要素の一つです。多くのユーザーがスマートフォンからWebサイトを閲覧するため、最適化されていないと直帰率が増加し、コンバージョン率が低下します。
最適化のポイントは、「レスポンシブデザインの採用」「読み込み速度の向上」「タップしやすいUI設計」です。例えば、「テキストやボタンのサイズ調整」「画像・動画の軽量化」「縦スクロールで快適に閲覧できる構成」といった施策が効果的です。
例えば、CTAボタンを親指で押しやすい画面下部に配置し、フォーム入力を簡単にすることで、スマートフォンユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョン率を向上できます。
LPOを社内でスムーズに進めるためのコツ
LPOの必要性を社内で理解してもらうには?
LPOの導入を社内で進めるには、データを根拠に説得することが重要です。特に経営層はROIを重視するため、数値で示すと効果的です。LPの直帰率やCVRを提示し、課題の明確化が必要になります。
「広告費を増やさずに売上を伸ばせる」点を強調すると、LPOの価値が理解されやすくなります。例えば、コンバージョン率が1%向上すれば、売上が大幅に増加する可能性があることを示します。また、他社の成功事例を示すことで、導入の決断を促せます。
経営層を説得する際は、改善のロードマップを示すことも有効です。施策のスケジュールや想定ROIを具体的に提示しましょう。
クライアントにLPOを提案する際のポイントは?
クライアントがLPOに投資するかは、ROIの明確さにかかっています。LP改善がCVR向上を通じて売上にどう直結するかを示し、データや事例を活用して説得力を高めることが重要です。
また、業種ごとにLPOのメリットを強調すると納得感が増します。例えば、ECサイトなら購入率向上、不動産なら問い合わせ増加など、具体的な成果を提示すると理解が深まります。
クライアントの不安を解消するには、低リスクな導入方法を提案すると効果的です。A/Bテストを一部のページで実施し、データに基づいた判断が可能であることを示すと、LPOの導入をスムーズに進められます。
LPO実施の社内リソースが不足している場合は?
LPOの実施には時間と労力がかかるため、社内リソースの確保が課題となります。まずは、スモールスタートで始め、ファーストビューやCTAの改善など、短期間で実施できる施策から取り組みましょう。
また、内製と外注の判断も必要になります。社内にリソースがあれば、データ分析やテストを自社で進められますが、不足している場合は外部支援を活用するのもおすすめです。
外注を検討する場合は、LPOコンサルやツールを活用すると効率的です。A/Bテストツールを利用すれば、負担を最小限に抑えつつ効果的に改善を進められます。
LPOツールの選び方と比較のポイント
- できることや機能面の充実度で選ぶ
- 導入や操作画面の使いやすさで選ぶ
- 価格やコストパフォーマンスで選ぶ
できることや機能面の充実度で選ぶ
LPOツールの選び方の1つ目としては「できることや機能面の充実度で選ぶ」という方法が挙げられます。
高度なLPOツールには、AIを活用した自動最適化機能や詳細な分析レポートが備わっているものもあります。これにより、ユーザー行動をリアルタイムで分析し、コンバージョン率を向上させる施策がスムーズに実施できます。
特に、マーケティングチームが頻繁にテストを行う場合、簡単に仮説検証できるA/Bテスト機能や視覚的なヒートマップがあると便利です。
導入や操作画面の使いやすさで選ぶ
LPOツールの選び方の2つ目としては「導入や操作画面の使いやすさで選ぶ」という方法が挙げられます。
特に、ドラッグ&ドロップでページ編集ができるビジュアルエディタや、コード不要でテスト設定ができる機能があると便利です。ノーコード・ローコード対応のツールであれば、マーケティング担当者がエンジニアに頼らずに改善施策を実施できます。
また、導入のしやすさを考慮するなら、既存のCMSや広告プラットフォームと連携しやすいツールを選ぶのもポイントです。
価格やコストパフォーマンスで選ぶ
LPOツールの選び方の3つ目としては「価格やコストパフォーマンスで選ぶ」という方法が挙げられます。
コストを抑えつつ運用するなら、必要な機能が揃ったシンプルなプランや従量課金制のツールを選ぶのがおすすめです。特に、小規模なサイト運営なら、基本的なA/Bテストやヒートマップ分析が使える無料プランでも十分な効果を得られる場合があります。
一方で、大規模なサイトや本格的にLPOを実施する企業なら、高度な分析機能やAIによる最適化機能が搭載された有料プランがおすすめです。
LPOのよくある質問
LPOの施策は、どのくらいの期間で成果が出ますか?
成果が出るまでの期間は施策内容やテスト頻度によりますが、一般的に効果が明確になるまで1〜3ヶ月ほどかかります。早期に小さな改善を繰り返すことが重要です。
LPOツールを使用せず、自社だけで実施できますか?
基本的な改善は自社でも可能ですが、効果検証やA/Bテストには専門ツールが必要です。データ分析や精度の高い改善を目指すならツールの活用をおすすめします。
LPOの施策で、特に効果が高いポイントはどこですか?
特に効果が高いのは、ファーストビューとCTAの改善です。ユーザーが最初に目にする部分を最適化すると、離脱率低下やCVR改善に直結します。
まとめ
本記事では、LPOの概要をわかりやすく解説するのに加えて、導入のメリット・デメリットや実施手順、改善ポイントまで、まとめて徹底的に解説しました。
近年、デジタルマーケティングの重要性が高まる中で、LPOは企業の成長に欠かせない施策となっています。特に、AIやパーソナライズ技術の進化により、今後もLPOの手法はさらに多様化し、効果的な最適化が求められるでしょう。
今後もITreviewでは、LPOツールのレビュー収集に加えて、新しいLPOツールも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 LPOとは?SEOやEFOとの違いから効果的な改善方法までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 FTPとは?ファイル転送の仕組みやメリット・使い方をわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>近年、クラウドストレージの普及やリモートワークの増加に伴い、大容量ファイルの転送やアクセス管理が必要な場面でFTPの利用が広がっています。
しかし、セキュリティの脆弱性や暗号化不足が課題であり、適切な設定をしないとデータ漏洩や不正アクセスのリスクがあります。
本記事では、FTPの基本的な仕組みを解説するのとともに、SFTPやFTPSとの違い、メリット・デメリット、導入時のポイントまで徹底的に解説していきます。
この記事を読むだけで、FTPの基礎から安全な運用方法まで理解できるため、ファイル転送を効率化したい方には必見の内容です!
FPT(File Transfer Protocol)とは?
FTP(File Transfer Protocol)とは、ネットワーク上でファイルを送受信するための通信プロトコルのことです。
FTPの利点は、シンプルな仕組みと高速なデータ転送能力です。専用ソフトを使えばドラッグ&ドロップといった直感的な操作でファイルを扱えます。さらに、コマンドラインを利用すれば、自動化による定期的なデータ送受信も可能です。
具体的な活用例として、Webサイトのファイル管理や企業間のデータ共有が挙げられます。WebサーバーへのHTMLや画像ファイルのアップロード、アクセスログの取得などにFTPが用いられています。
FTPと類似プロトコル(FTPS・SFTP・HTTP)の違い
| プロトコル | 暗号化 | 使用ポート | 特徴 |
|---|---|---|---|
| FTP | なし | 20/21 | シンプルな仕組みで、多くの環境で利用可能 |
| FTPS | あり(SSL/TLS) | 21/990(制御) | セキュリティが強化され、安全な通信が可能 |
| SFTP | あり(SSH) | 22 | SSHを活用し、高い安全性を確保しつつ単一ポートで通信可能 |
| HTTP | なし(HTTPS) | 80(443) | Webブラウザを利用したファイル転送が容易 |
FTPS(FTP Secure)
FTPSは、FTPにSSL/TLSによる暗号化機能を追加したプロトコルです。
基本的な通信手順はFTPと同じですが、データを暗号化することで第三者による盗聴や改ざんのリスクを軽減できます。
そのため、セキュリティが求められる環境ではFTPの代わりにFTPSが採用されることが多くなっています。
SFTP(SSH File Transfer Protocol)
SFTPは、SSH(Secure Shell)を利用してデータを暗号化しながらファイルを転送するプロトコルです。
FTPSと異なり、1つのポート(通常22番)を使用するため、ファイアウォールの設定が容易という利点があります。
また、認証方式にはパスワード認証のほか、公開鍵認証も利用可能であり、高度なセキュリティ対策が求められる環境に適しています。
HTTP(Hypertext Transfer Protocol)
HTTPは、Webサイトでデータをやり取りするための通信プロトコルですが、ファイルのダウンロードやアップロードにも利用されます。
FTPと異なり、Webブラウザを利用して直感的に操作できる点が特徴です。ただし、HTTPも暗号化が施されていないため、機密情報を扱う場合はHTTPS(HTTP Secure)を利用するのが一般的です。
FTPの仕組み
- データ転送の流れ
- クライアントとサーバーの関係
- アクティブモードとパッシブモードの違い
データ転送の流れ
FTP通信では、制御とデータ転送で別々のコネクションを使うのが特徴です。最初にクライアントがサーバーへ制御コネクションを確立し、ユーザー認証を行います。
次に、ファイルの送受信指示が出されると、データ転送用に新たなコネクションが確立されます。このコネクションを介して、実際のファイルのやり取りが行われる仕組みです。
転送完了後はデータコネクションが閉じますが、制御コネクションは維持されるため、複数のファイルを効率的に送受信できるようになっています。
クライアントとサーバーの関係
FTPでは、クライアントとサーバーがそれぞれの役割を分担して通信します。クライアントはユーザーが操作する側で、サーバーはクライアントからの要求に応じた応答を返す側です。
クライアント側はFTPソフトやコマンドを使いサーバーへ接続し、ディレクトリ参照やファイル転送を行います。サーバー側はユーザー認証後、要求されたファイルを送信、またはアップロードされたファイルを受信します。
また、サーバーにはアクセス制限や権限管理機能があり、ユーザーごとに特定のフォルダやファイルへのアクセス権を設定可能です。これにより、セキュリティを確保しながらファイル共有を実現できます。
アクティブモードとパッシブモードの違い
FTPには、アクティブモードとパッシブモードという2つの接続モードがあり、ネットワーク環境に応じて使い分けられます。
アクティブモードでは、クライアントが制御コネクションを確立した後、サーバーがクライアント側にデータ転送用の接続を確立します。しかし、クライアント側のファイアウォールが外部からの接続を遮断する場合、通信がうまくいかないことがあります。
パッシブモードでは、クライアントがサーバーに対してデータ転送用の接続要求を行うため、ファイアウォールによる制限を回避しやすくなります。現在では、セキュリティ上の理由からパッシブモードが推奨されるケースが多くなっています。
FTPの導入メリット
- 大容量ファイルを転送できる
- データを一括で転送できる
- 通信の自動化が実現できる
- ユーザーアクセスを管理できる
- オフライン環境でも使用できる
大容量ファイルを転送できる
FTPのメリットの1つ目として「大容量ファイルを転送できる」という点が挙げられます。
一般的なメール添付では送信できないサイズのファイルでも、FTPを使用すれば問題なく送受信できます。
例えば、数GBを超える動画データや設計ファイルなども、専用のFTPサーバーを利用することで安定した転送が可能です。クラウドサービスとは異なり、ファイルサイズの上限を気にする必要がありません。
データを一括で転送できる
FTPのメリットの2つ目として「データを一括で転送できる」という点が挙げられます。
複数のファイルやフォルダを一度にまとめてアップロード・ダウンロードできるため、作業効率が向上します。
例えば、Webサイトのデータをサーバーにアップロードする際も、FTPソフトを使用すればフォルダ単位で転送可能です。手作業で1つずつファイルを送る手間が省け、時間短縮につながります。
通信の自動化が実現できる
FTPのメリットの3つ目として「通信の自動化が実現できる」という点が挙げられます。
スクリプトや専用のFTPクライアントを活用することで、定期的なデータ転送を自動化できます。
例えば、業務システムのデータを毎日決まった時間にバックアップする場合、バッチ処理を構築することで、手作業を介さずに定期的な転送が可能です。これにより、人為的なミスを防ぎ、安定したデータ管理を実現できます。
ユーザーアクセスを管理できる
FTPのメリットの4つ目として「ユーザーアクセスを管理できる」という点が挙げられます。
FTPサーバーでは、特定のユーザーごとにアクセス権を設定し、重要なデータへの不正アクセスを防げます。
例えば、社内で部署ごとにフォルダへのアクセス権を設定することで、セキュリティを確保しながらファイル共有ができます。管理者は不要なアクセスを制限し、データの機密性を維持することが可能です。
オフライン環境でも使用できる
FTPのメリットの5つ目として「オフライン環境でも使用できる」という点が挙げられます。
クラウドストレージとは異なり、FTPサーバーはローカル環境に設置することで、インターネット接続がない状態でもファイル転送が可能です。
例えば、企業の内部ネットワーク内でFTPサーバーを運用すれば、インターネットの影響を受けずに安定したデータ管理ができるようになります。これにより、ネットワークの制約がある環境でも円滑な運用が可能です。
FTPの導入デメリット
- セキュリティのリスクが存在する
- 専用サーバーと管理が必要になる
- 転送速度が遅くなる可能性がある
- ファイアウォールとの相性が悪い
- 操作が複雑で初心者は扱いにくい
セキュリティのリスクが存在する
FTPのデメリットの1つ目としては「セキュリティのリスクが存在する」という点が挙げられます。
標準的なFTPは暗号化機能を備えておらず、通信内容が第三者に盗聴されるリスクがあるため、重要なデータのやり取りには適していません。
解決策としては、FTPS(FTP Secure)やSFTP(SSH File Transfer Protocol)を利用することで、通信を暗号化し、安全性を向上できます。
専用サーバーと管理が必要になる
FTPのデメリットの2つ目としては「専用サーバーと管理が必要になる」という点が挙げられます。
FTPを運用するには、専用のサーバーを用意し、適切に管理する手間がかかるため、一定の知識が求められるためです。
解決策としては、クラウド型のFTPサービスを利用することで、ハードウェアの管理負担を軽減できます。
転送速度が遅くなる可能性がある
FTPのデメリットの3つ目としては「転送速度が遅くなる可能性がある」という点が挙げられます。
FTPは、サーバーとクライアント間で複数の接続を確立するため、回線状況やサーバーの負荷によっては転送速度が低下する場合があるためです。
解決策としては、高速な回線を使用する、サーバーの負荷を軽減するために夜間や低負荷時間帯に転送を行う、圧縮ファイルを活用するといった方法があります。
ファイアウォールとの相性が悪い
FTPのデメリットの4つ目としては「ファイアウォールとの相性が悪い」という点が挙げられます。
FTPは、データ転送時に動的にポートを割り当てる仕組みを採用しており、企業のファイアウォールによっては通信がブロックされることがあるためです。
解決策としては、パッシブモードを使用する、またはFTPサーバーの設定を調整して特定のポートを開放することで、通信の安定性を確保できます。
操作が複雑で初心者は扱いにくい
FTPのデメリットの5つ目としては「操作が複雑で初心者は扱いにくい」という点が挙げられます。
FTPを利用するには、FTPクライアントソフトウェアのインストールや接続設定、ディレクトリ構造の理解などが必要となり、初心者にはハードルが高い場合があります。
解決策としては、直感的に操作できるWebベースのFTPクライアントを利用するか、クラウドストレージのようなシンプルなUIを持つサービスを選ぶのがおすすめです。
FTPの基本的な使い方
- ①:FTPクライアントソフトを用意する
- ②:FTP接続情報を準備する
- ③:FTPクライアントソフトからサーバーへ接続する
- ④:ファイルをアップロードする
- ⑤:ファイルをダウンロードする
- ⑥:FTP接続を終了する
①:FTPクライアントソフトを用意する
FTPを利用するには、専用の「FTPクライアントソフト」が必要です。まずは用途やOSに合ったFTPクライアントソフトを用意して、自分のPCにインストールしましょう。
FTPクライアントソフトの基本的な機能としては、以下のようなものが挙げられます。
- サーバーへの接続・認証(ホスト名、ユーザー名、パスワードを入力)
- ファイルのアップロード・ダウンロード(ドラッグ&ドロップで転送可能)
- ディレクトリ(フォルダ)の管理(新規フォルダ作成、ファイル削除)
- ファイルの権限設定(アクセス制限の変更)
- 転送状況の確認(進行状況・エラー通知)
FTPソフトは、初心者でも簡単に扱えるものが多く、直感的に操作できるものが主流です。
②:FTP接続情報を準備する
FTPを利用するには、FTPサーバーへ接続するための情報が必要です。この情報がなければ、サーバーにアクセスできず、ファイルのアップロードやダウンロードができません。
FTP接続情報には、下記の要素が挙げられます。
- ホスト名(FTPサーバーのアドレス)
- ユーザー名
- パスワード
- ポート番号(通常は21番、SFTPなら22番)
これらの情報をサーバー管理者やホスティング会社から事前に取得しておきましょう。
③:FTPクライアントソフトからサーバーへ接続する
クライアントソフトを起動し、接続画面で以下の情報を入力します。
- 「ホスト名」欄にFTPサーバーアドレスを入力
- 「ユーザー名」欄に自分のユーザー名を入力
- 「パスワード」欄に自分のパスワードを入力
- 「ポート」欄に指定のポート番号を入力(通常21、SFTPは22)
すべての情報を入力後、【接続】ボタンをクリックします。正常に接続されると、サーバーのフォルダやファイルが一覧表示されます。
④:ファイルをアップロードする
ローカル(自分のPC側)からサーバーへファイルを転送する方法です。
- 転送したいファイルやフォルダをローカル側の画面で選択する
- 選択したファイルをリモート(サーバー)側へドラッグ&ドロップする
- 転送開始後、進行状況が表示されるので完了を待つ
転送完了後はサーバー側に正常にファイルが存在するか必ず確認しましょう。
⑤:ファイルをダウンロードする
サーバーからローカル(自分のPC側)へファイルを転送する方法です。
- リモート(サーバー)側でダウンロードしたいファイルやフォルダを選択する
- 選択したファイルをローカル(自分のPC)側へドラッグ&ドロップする
- ダウンロードが始まるので、進行状況を確認しながら完了を待つ
転送完了後はダウンロードしたファイルが正常に開けるかも確認しましょう。
⑥:FTP接続を終了する
作業終了後は、必ずFTPサーバーとの接続を安全に切断しましょう。
ほとんどのクライアントソフトには「接続を切断する」ボタンが用意されていますので、それをクリックして接続を終了します。
FTPソフトの選び方と比較のポイント
- 操作性や使い勝手で選ぶ
- セキュリティ機能で選ぶ
- 転送速度や安定性で選ぶ
- 利用料金やコストで選ぶ
- サポート体制や評判で選ぶ
操作性や使い勝手で選ぶ
FTPソフトの選び方の1つ目としては「操作性や使い勝手で選ぶ」という方法が挙げられます。
ドラッグ&ドロップ操作やGUIを備えたソフトは、特に初心者におすすめです。一方、コマンドライン操作は上級者向けで、スクリプトによる効率的な運用が可能です。
業務利用では、複数サーバー管理に便利なブックマーク機能やタブ管理機能も重要です。自身のスキルや用途に合った操作性のソフトを選びましょう。
セキュリティ機能で選ぶ
FTPソフトの選び方の2つ目としては「セキュリティ機能で選ぶ」という方法が挙げられます。
安全なデータ通信のため、暗号化通信や認証方式への対応状況を確認しましょう。FTPSやSFTPに対応しているソフトを選ぶことで、データの盗聴や改ざんを防げます。
企業や組織での利用を考える場合、アクセス権限の管理機能も重要です。管理者がユーザーごとにアップロード・ダウンロードの制限を設定できるソフトを選ぶことで、不正なアクセスを防げます。
転送速度や安定性で選ぶ
FTPソフトの選び方の3つ目としては「転送速度や安定性で選ぶ」という方法が挙げられます。
特に大容量のファイルを扱う場合や、複数のファイルを一括で転送する場合は、スピードと安定性が求められます。転送速度を重視する場合は、マルチスレッド転送や並列処理機能を備えたソフトを選ぶと効率的です。
安定性の面では、転送エラー時の自動リトライ機能や中断からの再開機能があると便利です。不測の事態でもスムーズに作業を続けられます。
利用料金やコストで選ぶ
FTPソフトの選び方の4つ目としては「利用料金やコストで選ぶ」という方法が挙げられます。
無料ソフトは基本的な機能を持つものが多く、個人や小規模利用に適しています。一方、有料ソフトはセキュリティ強化や高速転送、充実したサポートなど、ビジネス用途に適した機能が豊富です。
企業で利用する場合は、ライセンス形態や料金プランも重要です。一括購入やサブスクリプションなど、長期的なコストを考慮して最適なものを選択しましょう。
サポート体制や評判で選ぶ
FTPソフトの選び方の5つ目としては「サポート体制や評判で選ぶ」という方法が挙げられます。
有料のFTPソフトであれば、メーカーによる公式サポートや問い合わせ対応が用意されていることが多く、安心して利用できます。また、無料ソフトでも、ユーザーコミュニティやFAQが充実していれば、トラブル発生時に役立ちます。
また、実際に利用したユーザーの口コミや評価も重要です。転送速度やセキュリティ、サポートの質など、実際に利用したユーザーの声を参考に、自分に合ったソフトを選択をしましょう。
FTPを安全に運用するポイント
- 暗号化されたプロトコル(FTPS・SFTP)を利用する
- パスワードやIP制限などアクセス制御を徹底する
- 定期的なログ確認やサーバーの整理を習慣化する
暗号化されたプロトコル(FTPS・SFTP)を利用する
FTPの安全性を高めるためには、暗号化されたプロトコルを利用することが不可欠です。標準のFTPは通信が暗号化されておらず、第三者にパスワードやデータを盗聴されるリスクがあります。
最低限の対策として、FTPS(FTP over SSL/TLS)の利用を推奨します。SSL/TLSによる暗号化を施すことで、データの盗聴や改ざんを防ぐことが可能です。
より強固なセキュリティを求める場合は、SFTP(SSH File Transfer Protocol)の利用が理想的です。SFTPは、認証・通信の暗号化が一体化しているため、より安全性が高くなります。
パスワードやIP制限などアクセス制御を徹底する
FTPを安全に運用するためには、適切なアクセス制御が重要です。特に、不正アクセスを防ぐために、強固なパスワード管理とIP制限の導入が推奨されます。
パスワード管理においては、長く複雑なパスワードを設定し、定期的に変更することが基本です。さらに、多要素認証(MFA)を導入することで、不正ログインのリスクをより低減できます。
加えて、IP制限を活用することで、許可されたIPアドレスのみがFTPサーバーに接続できるように設定できます。特に社内ネットワークやVPN経由のみのアクセスを許可することで、外部からの不正なアクセスを効果的に防ぐことが可能です。
定期的なログ確認やサーバーの整理を習慣化する
FTPのセキュリティを維持するためには、定期的なログ確認とサーバー整理を習慣化しましょう。ログを監視することで、不審なアクセスや異常なファイル操作を早期に検知できます。
具体的には、アクセスログや転送ログを定期的に確認し、不審なIPアドレスや異常なデータ転送がないかをチェックしましょう。
また、サーバーに不要なファイルやアカウントが放置されないように、定期的な整理と権限管理の見直しも実施することが重要です。
FTPのよくあるトラブルと対処法
- FTP接続ができない場合の原因と対処法
- ファイルが文字化けしてしまう場合の対処法
- ファイルの転送が途中で止まる場合の対処法
- アップロード・ダウンロードが失敗する場合の対処法
FTP接続ができない場合の原因と対処法
FTP接続ができない原因は、ネットワーク設定や認証ミス、ファイアウォールの影響などです。特に接続モードやポート設定の違いが影響することもあります。
| 原因 | 対処法 |
|---|---|
| ユーザー名・パスワードの入力ミス | 入力情報を再確認し、大文字・小文字の違いに注意する |
| サーバーのホスト名やポート設定の誤り | 正しいホスト名・ポートをサーバー管理者に確認する |
| ファイアウォール・ウイルス対策ソフトの制限 | 一時的にファイアウォールを無効化する、FTPの許可設定を行う |
| 接続モードの違い(アクティブ/パッシブ) | FTPクライアントの接続設定を切り替えて試す |
特に、ファイアウォールやセキュリティソフトがFTPの通信をブロックしていることが多いため、一時的に無効化して接続を試すのが有効です。
ファイルが文字化けしてしまう場合の対処法
FTPでファイルを転送すると文字化けが発生することがあります。これは文字コードの違いが原因で、クライアントとサーバーのエンコーディング設定の不一致によって起こります。
日本語を含むファイルは、バイナリモードで転送すると文字化けを防止できます。また、FTPクライアントのエンコーディングをUTF-8に変更すると改善することもあります。
ファイルの転送が途中で止まる場合の対処法
FTPのアップロード・ダウンロード失敗は、ファイルサイズ制限や権限不足が原因です。空きディスク容量の不足でもエラーが発生することがあります。
| 原因 | 対処法 |
|---|---|
| ネットワークが不安定になっている | 有線接続を利用する、Wi-Fiの再接続を試す |
| タイムアウト設定が短すぎる | FTPクライアントのタイムアウト設定を延長する |
| サーバー側で転送制限がある | 管理者に確認し、大容量ファイルの転送方法を調整する |
FTPクライアントのタイムアウト時間を延ばすと転送の途中停止を防止できます。また、大容量ファイルの場合は、分割して転送する方法も有効です。
アップロード・ダウンロードが失敗する場合の対処法
FTPの転送失敗はファイルサイズ制限や権限不足、空きディスク容量の不足が原因で発生します。
| 原因 | 対処法 |
|---|---|
| サーバーの空き容量が不足している | 不要なファイルを削除する、管理者に増設を依頼する |
| アップロード制限が邪魔をしている | 一度に転送するファイルサイズを小さくする |
| ファイルのアクセス権限が不足している | サーバー管理者に権限を変更してもらう |
特に、サーバーの空き容量が不足していると、新しいファイルのアップロードが失敗するため、不要なファイルを削除して、ディスクの空きを確保することが重要です。
まとめ
本記事では、FTPの概要を解説するのとともに、メリット・デメリット、安全な運用方法、よくあるトラブルと対処法まで詳しく紹介しました。
企業のファイル転送において、FTPの活用は依然として重要ですが、FTPSやSFTPなどの暗号化プロトコルを利用し、適切なアクセス制御を行うことが不可欠です。特に、サイバー攻撃の増加により、今後さらに安全対策の重要性が高まると考えられます。
今後もITreviewでは、FTPソフトのレビュー収集に加えて、新しいFTPソフトも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 FTPとは?ファイル転送の仕組みやメリット・使い方をわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 FAQとは?Q&Aとの違いやメリット・作成手順・分析方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>近年、カスタマーサポートの負担軽減や顧客満足度向上を目的に、多くの企業がFAQを導入しています。特に、AIやチャットボットと連携することで、24時間対応や迅速な問題解決が可能になりました。
しかし、FAQの内容が不十分で検索しにくいと、ユーザーの混乱を招き、問い合わせ増加や業務効率の低下を引き起こすリスクがあります。
本記事では、FAQの基本的な仕組みやメリット・デメリットに加えて、効果的なFAQの作成方法や最新のFAQシステムについて詳しく解説します。
FAQとは?
FAQとは「Frequently Asked Questions」の略称で、特定のサービスや製品に関するよくある質問とその回答をまとめたものです。
顧客対応や社内の情報共有の効率を高めるため、多くの企業がWebサイトや社内システムに導入しています。
FAQの導入により問い合わせ対応の負担を軽減し、顧客の自己解決を促せます。さらに、社内向けFAQは、業務マニュアルや社内ルールの一元管理に役立ち、新入社員の疑問を解消し、業務習得をスムーズに進められる点もメリットです。
FAQとQ&Aの違い
FAQとQ&Aはどちらも質問と回答をまとめたコンテンツですが、それぞれの目的や運用方法に違いがあります。
FAQは、あらかじめ想定される質問とその回答を体系的に整理したものです。企業のWebサイトやサポートページに掲載され、顧客や従業員が自己解決しやすい形で提供されます。
一方、Q&Aはユーザーからのリアルタイムな質問に対して個別に回答する形式を指します。SNSやフォーラム、企業のチャットサポートなどでよく活用され、FAQではカバーしきれない細かな疑問に対応できます。
FAQの種類
- 顧客向けFAQ
- 社内向けFAQ
- コールセンター向けFAQ
顧客向けFAQ
顧客向けFAQは、商品やサービスに関するよくある質問をまとめたものです。主に企業のWebサイトやECサイト、サポートページに設置され、顧客が自己解決できるように情報を提供します。
例えば、「支払い方法の変更」「返品・交換ポリシー」「商品の使い方」など、顧客から頻繁に寄せられる質問をFAQにまとめることで、問い合わせ対応の負担を軽減できます。
さらに、FAQの情報を適切に整理し、検索性やユーザビリティを向上させることで、顧客満足度の向上にも貢献します。特に、ナビゲーションや検索機能を強化し、直感的に情報へアクセスできる設計が重要です。
社内向けFAQ
社内向けFAQは、社員が業務をスムーズに進めるために必要な情報を集約したものです。新入社員向けの研修資料や、社内システムの使い方、福利厚生に関する質問などをまとめ、業務の効率化を促進します。
例えば、「経費精算の手順」「社内ツールのログイン方法」「勤怠管理のルール」といった情報をFAQに整理することで、総務部やIT部門への問い合わせを削減し、業務の負担を軽減できます。
さらに、社内FAQをナレッジ共有ツールと連携させることで、より効率的な情報管理が可能です。従業員が質問を投稿し、管理者が随時更新できる仕組みを整えることで、常に最新の情報を維持できます。
コールセンター向けFAQ
コールセンター向けFAQとは、オペレーターが顧客対応を円滑に行うための情報を集約したものです。顧客からの問い合わせに迅速かつ正確に対応するため、FAQが活用されます。
例えば、「トラブルシューティング手順」「製品の仕様」「契約プランの詳細」など、オペレーターが素早く回答できるように情報を整理し、応対品質の均一化や対応時間の短縮を実現します。
さらに、AIを活用したFAQシステムと連携することで、適切な回答を瞬時に検索できる環境を構築できます。これにより、新人オペレーターでもベテランと同等の対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
FAQの導入メリット
- 問い合わせ件数を削減できる
- 顧客満足度の向上につながる
- SEO対策への効果が見込める
- 顧客のニーズを可視化できる
- サポートの品質を統一できる
問い合わせ件数を削減できる
FAQのメリットの1つ目としては「問い合わせ件数を削減できる」というものが挙げられます。
顧客がFAQを活用することで、カスタマーサポートへの問い合わせ回数が減り、オペレーターの負担が軽減されます。例えば、ECサイトでは「配送状況の確認方法」「返品手続き」などの情報をFAQに掲載することで、問い合わせの大幅な削減が可能です。
また、社内向けFAQを導入すれば、従業員が総務部やIT部門に問い合わせる手間を省き、業務の生産性を向上できます。特に、新入社員の疑問を解決する手段としても有効です。
顧客満足度の向上につながる
FAQのメリットの2つ目としては「顧客満足度の向上につながる」というものが挙げられます。
多くの顧客は、できるだけ早く回答を得たいと考えており、FAQを活用することで問い合わせの待ち時間を短縮できます。特に、チャットボットや検索機能と組み合わせることで、FAQの利便性をさらに高めることが可能です。
また、FAQを充実させることでサポート対応の品質を均一化し、顧客体験の向上につなげられます。
SEO対策への効果が見込める
FAQのメリットの3つ目としては「SEO対策への効果が見込める」というものが挙げられます。
FAQページは、特定の質問に対する明確な回答を提供するため、検索エンジンに評価されやすい特徴があります。特に、「〇〇の使い方」「〇〇の解決方法」といった検索クエリに対応したFAQを作成することで、自然検索からの流入を増やすことが可能です。
さらに、Googleの「強調スニペット」に表示される可能性も高くなり、検索結果の上位を獲得できるチャンスが広がります。
顧客のニーズを可視化できる
FAQのメリットの4つ目としては「顧客のニーズを可視化できる」というものが挙げられます。
FAQの閲覧データを分析することで、どの質問が多いのか、顧客がどこでつまずいているのかを把握できます。例えば、「特定の製品の操作方法に関する質問が多い」と判明した場合、UIの改善やマニュアルの見直しが必要だと判断できます。
さらに、FAQを継続的に改善することで、顧客体験の向上だけでなく、商品やサービスの改良にも活用できます。
サポートの品質を統一できる
FAQのメリットの5つ目としては「サポートの品質を統一できる」というものが挙げられます。
FAQを適切に整備することで、オペレーターごとの回答のバラつきをなくし、一貫したサポート対応が可能になります。特に、コールセンター向けFAQを導入すれば、オペレーターがFAQを活用し、迅速かつ的確な回答を提供できるようになります。
また、新人オペレーターでもFAQを参照することでベテランと同等の対応が可能となり、研修コストの削減にも貢献します。
FAQの導入デメリット
- 適切ではない運用が形骸化を招く
- FAQだけでは解決できない問題がある
- ユーザーが離脱してしまうリスクがある
- 顧客との直接的なコミュニケーションが減る
適切ではない運用が形骸化を招く
FAQのデメリットの1つ目としては「適切ではない運用が形骸化を招く」というものが挙げられます。
FAQは一度作成して終わりではなく、定期的な更新と改善が不可欠です。しかし、多くの企業ではFAQの更新が後回しになり、古い情報が放置されるケースが少なくありません。
これを防ぐためには、FAQの閲覧データや問い合わせ内容を定期的に分析し、必要に応じて内容を見直す仕組みを構築することが重要です。FAQ管理ツールを活用し、適切な運用体制を整えましょう。
FAQだけでは解決できない問題がある
FAQのデメリットの2つ目としては「FAQだけでは解決できない問題がある」というものが挙げられます。
FAQは一般的な質問への対応には有効ですが、個別の契約内容や技術的なトラブルなどの複雑な問題には対応しきれず、十分な回答を提供できない場合があります。
そのため、FAQに加えて、チャットサポートや問い合わせフォームなどの別のサポート手段を併用することが重要です。さらに、FAQを充実させるだけでなく、必要に応じて有人対応ができる体制を整えましょう。
ユーザーが離脱してしまうリスクがある
FAQのデメリットの3つ目としては「ユーザーが離脱してしまうリスクがある」というものが挙げられます。
FAQが整理されておらず検索性が低いと、ユーザーが求める情報にたどり着けず不満を感じてしまいます。特にスマートフォンでは、操作しにくいFAQページがストレスの原因になります。
この問題を防ぐためには、FAQのデザインを最適化し、カテゴリ分けや検索機能を強化することが重要です。UXを意識したFAQページの設計を行い、誰でも簡単に情報を見つけられるようにしましょう。
顧客との直接的なコミュニケーションが減る
FAQのデメリットの4つ目としては「顧客との直接的なコミュニケーションが減る」というものが挙げられます。
FAQが充実すると問い合わせが減り、企業と顧客の接点が少なくなります。その結果、直接的なフィードバックを得る機会が減り、サービス改善のヒントを見逃す可能性があります。
これを防ぐためには、FAQと併せてアンケートやフィードバックフォームを設置し、顧客の意見を収集する仕組みを導入することが重要です。さらに、FAQの利用データを分析し、顧客ニーズを的確に把握することも求められます。
FAQの効果的な作成手順
- ①:FAQを作成する目的を明確にする
- ②:質問内容を分かりやすく整理する
- ③:ユーザーが読みやすい回答にする
- ④:定期的に質問の改善や更新を行う
①:FAQを作成する目的を明確にする
FAQ作成の1つ目のステップは「FAQを作成する目的を明確にする」ことです。
FAQの目的は、問い合わせ件数の削減、顧客満足度の向上、社内業務の効率化など、企業によって異なります。例えば、ECサイトでは「購入や配送に関する問い合わせを減らす」、社内向けFAQでは「従業員が業務をスムーズに進められるようにする」など、具体的な目標を設定しましょう。
目的が明確であれば、掲載すべき質問や適切な提供形式を判断しやすくなります。まずは、FAQを導入することで何を解決したいのかを明確にしましょう。
②:質問内容を分かりやすく整理する
FAQ作成の2つ目のステップは「質問内容を分かりやすく整理する」ことです。
FAQに掲載する質問は、顧客や従業員から頻繁に寄せられるものを中心に選定しましょう。過去の問い合わせ履歴やサポートチームの意見を参考にすることで、実際に役立つ質問を抽出できます。
また、質問をカテゴリごとに整理することで、ユーザーが知りたい情報に素早くアクセスできるようになります。例えば、ECサイトのFAQなら「注文・支払い」「配送・返品」「アカウント管理」など、明確な分類を設けると利便性が向上します。
③:ユーザーが読みやすい回答にする
FAQ作成の3つ目のステップは「ユーザーが読みやすい回答にする」ことです。
専門用語や社内用語を多用すると、ユーザーが内容を理解できず、FAQが十分に機能しなくなります。例えば、「アカウントのリカバリー」ではなく「パスワードを忘れた場合の対処方法」と表現することで、より分かりやすくなります。
また、Q&A形式で簡潔にまとめ、視認性を高めることも重要です。例えば、「〇〇する方法を教えてください。」ではなく「〇〇の方法は以下の手順で行います。」といった形で、質問と回答の形式を統一すると、ユーザーが情報を探しやすくなります。
④:定期的に質問の改善や更新を行う
FAQ作成の4つ目のステップは「定期的に質問の改善や更新を行う」ことです。
FAQは一度作成して終わりではなく、ユーザーのニーズに応じて継続的に更新することが重要です。例えば、新しい商品やサービスを導入した際には、それに関連する質問を追加する必要があります。
また、FAQの閲覧データを分析し、よく閲覧される質問を強調したり、必要な情報を追加することで、より有用なFAQへと改善できます。
FAQページの設置と運用の注意点
- ①:UXを考慮したデザインにする
- ②:CVにつなげる導線を設計する
- ③:質問への検索性を向上させる
①:UXを考慮したデザインにする
FAQページ設置・運用時の1つ目の注意点は「UXを考慮したデザインにする」ことです。
FAQページが使いにくいと、ユーザーが求める情報にたどり着けず、結果的に離脱してしまいます。特に、スマートフォンやタブレットでの閲覧が増えているため、レスポンシブデザインを採用し、デバイスに適したレイアウトを構築することが重要です。
また、アコーディオンメニューの活用やカテゴリーごとの整理、検索機能の導入により、情報を探しやすくする工夫が効果的です。FAQページは、シンプルで直感的に使えるデザインを意識しましょう。
②:CVにつなげる導線を設計する
FAQページ設置・運用時の2つ目の注意点は「CVにつなげる導線を設計する」ことです。
FAQを利用するユーザーは、疑問を解決しようとしているため、問題が解決すれば購入や申し込みへ進む可能性が高くなります。しかし、FAQページの設計が不十分だと、解決後にサイトから離脱してしまうこともあります。
そのため、FAQの各ページに「関連する商品ページ」や「お問い合わせフォーム」へのリンクを設置し、スムーズに次のアクションへ誘導することが重要です。特にECサイトでは、「支払い方法のFAQ」から購入ページへ遷移できる導線を整えることで、CV率の向上が期待できます。
③:質問への検索性を向上させる
FAQページ設置・運用時の3つ目の注意点は「質問への検索性を向上させる」ことです。
FAQがどれだけ充実していても、ユーザーが簡単に検索できなければ意味がありません。特に、質問数が多くなるほど、適切な情報を見つけるのが難しくなります。
また、FAQの質問文をユーザーの検索行動に合わせた形にすることも重要です。例えば、「ログインできない場合の対処法」ではなく、「ログインできないときはどうすればいい?」と自然な質問形式にすることで、検索しやすくなります。
FAQの効果測定・分析・改善方法
- ➀:FAQの効果を数値化し、データ分析を行う
- ➁:FAQのデータを活用し、インサイトを発見する
- ③:分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する
➀:FAQの効果を数値化し、データ分析を行う
FAQの成果測定・分析の1つ目のステップは「FAQの効果を数値化し、データ分析を行う」ことです。
特に、効果測定のためには、以下の指標をよくチェックするようにしましょう。
- FAQページのPV数・滞在時間(ユーザーがどの程度FAQを閲覧しているか)
- 検索回数や検索キーワード(よく検索される質問やニーズを把握)
- FAQからの離脱率(FAQを見た後にサイトを離れていないか)
- FAQページ経由の問い合わせ率(FAQで解決できなかった割合を分析)
これらのデータを活用し、どの質問がよく見られているか、どの情報が不足しているかを把握することで、適切な改善策を導き出せます。
➁:FAQのデータを活用し、インサイトを発見する
FAQの成果測定・分析の2つ目のステップは「FAQのデータを活用し、インサイトを発見する」ことです。
FAQの検索ワードや閲覧ランキングを分析することで、顧客がどのような疑問を持っているのか、どの部分でつまずいているのかを把握できます。
また、FAQの閲覧データをもとに、カスタマーサポートの対応方針を見直したり、製品開発やサービス改善のためのヒントを得ることもできます。データを積極的に活用し、顧客満足度向上につなげましょう。
③:分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する
FAQの成果測定・分析の3つ目のステップは「分析した結果をもとに、コンテンツを最適化する」ことです。
具体的な改善策としては、以下のようなアクションが考えられます。
- よく閲覧されるFAQを上位表示する(人気の質問を見つけやすくする)
- 検索キーワードに合わせて質問文を修正する(ユーザーが実際に使う言葉に最適化)
- FAQの回答を簡潔にする(長すぎる説明は、簡潔にわかりやすくまとめる)
- 関連するFAQを表示し、ナビゲーションを強化する(他のFAQへの誘導を工夫する)
こうした改善を繰り返すことで、FAQの利便性を高め、ユーザーの満足度向上につなげられます。
FAQシステムの選び方と比較のポイント
- ①:利用開始までのハードルで選ぶ
- ②:検索性や使い勝手の良さで選ぶ
- ③:AIや自動応答機能の有無で選ぶ
- ④:分析機能やレポート機能で選ぶ
- ⑤:導入コストと運用コストで選ぶ
①:利用開始までのハードルで選ぶ
FAQシステムの選び方の1つ目としては「利用開始までのハードルで選ぶ」という方法が挙げられます。
クラウド型のFAQシステムは、サーバー管理が不要で即時導入が可能なため、社内のITリソースが限られている企業に最適です。特に、ノーコードで設定できるシステムは、専門知識がなくても簡単に導入できるため、多くの企業で採用されています。
オンプレミス型のFAQシステムは、カスタマイズ性が高いものの、導入に時間とコストがかかるため、柔軟な設計を求める場合以外は慎重に選定することが重要です。
②:検索性や使い勝手の良さで選ぶ
FAQシステムの選び方の2つ目としては「検索性や使い勝手の良さで選ぶ」という方法が挙げられます。
ユーザーが必要な情報をすぐに見つけられるよう、キーワード検索やカテゴリ分類の機能が充実したシステムを選びましょう。特に、カテゴリ別のナビゲーションやサジェスト機能を備えたFAQシステムは、直感的に操作でき、迷うことなく情報へアクセスできます。
FAQの閲覧データを分析し、利用者の行動をもとに検索結果を最適化する機能があるシステムを導入することで、問い合わせ削減とユーザー満足度の向上が期待できます。
③:AIや自動応答機能の有無で選ぶ
FAQシステムの選び方の3つ目としては「AIや自動応答機能の有無で選ぶ」という方法が挙げられます。
AIを活用したFAQシステムは、ユーザーの質問の意図を理解し、最適な回答を提示できるため、カスタマーサポートの負担を大幅に軽減できます。特に、チャットボットと連携するFAQシステムは、リアルタイムでの対応が可能であり、ユーザー満足度を向上させます。
機械学習機能を備えたFAQシステムでは、ユーザーの利用データを学習し、FAQの精度を自動的に向上させることが可能なため、長期的に運用しやすいのが特徴です。
④:分析機能やレポート機能で選ぶ
FAQシステムの選び方の4つ目としては「分析機能やレポート機能で選ぶ」という方法が挙げられます。
FAQの閲覧状況を可視化することで、利用者のニーズを把握し、適切な改善を行えるシステムを導入することが重要です。特に、未解決の問い合わせ件数や検索ワードの分析機能が充実したシステムは、より効果的なFAQ運用が可能になります。
リアルタイムでデータを収集し、自動でレポートを生成する機能を持つシステムを導入すると、業務の効率化と戦略的な改善がしやすくなります。
⑤:導入コストと運用コストで選ぶ
FAQシステムの選び方の5つ目としては「導入コストと運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。
クラウド型FAQシステムは、初期費用が低く運用コストを抑えやすいのに対し、オンプレミス型は、導入費用が高いものの長期運用でコストを抑えられるのが特徴です。
無料トライアルを提供しているFAQシステムを活用し、導入後のコストパフォーマンスを事前に比較検討しましょう。
FAQシステムのおすすめ製品3選
- PKSHA FAQ
- sAI Search
- Helpfeel
PKSHA FAQ
PKSHA FAQは、株式会社PKSHA Communicationが提供する、AI技術を活用した高精度なFAQシステムです。
PKSHA FAQでは、自然言語処理技術を活用し、ユーザーの質問意図を的確に解析することで、最適な回答を提示できます。
sAI Search
sAI Searchは、株式会社サイシードが提供する、チャットボットと連携可能なFAQシステムです。
sAI Searchでは、質問文の入力途中でも適切な回答をリアルタイムでサジェストする機能を搭載し、ユーザーの自己解決をサポートします。
Helpfeel
Helpfeelは、株式会社Helpfeelが提供する、曖昧なキーワードでも高精度な検索が可能なFAQシステムです。
Helpfeelでは、独自の検索アルゴリズムを採用し、ユーザーの検索意図を推測して適切なFAQを表示します。
まとめ
本記事では、FAQの概要を解説するとともに、FAQの種類や導入によるメリット・デメリット、作成手順、運用のポイント、おすすめのFAQシステムまで詳しく紹介しました。
企業のカスタマーサポートや社内業務の効率化において、FAQの活用は欠かせないものとなっています。特に、AIや検索最適化技術の発展により、FAQの精度や利便性は今後さらに向上していくと考えられます。
今後もITreviewでは、FAQシステムのレビュー収集に加えて、新しいFAQシステムも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 FAQとは?Q&Aとの違いやメリット・作成手順・分析方法を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 WAFとは?サイバー攻撃を防ぐ仕組みやメリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>近年、SQLインジェクションやXSS等の攻撃増加に伴い、多くの企業がWAFを導入する一方、設定や運用には専門知識が必要であり、誤った設定をすると正規の通信までブロックしてしまうリスクがあります。
本記事では、WAFの基本的な仕組みや種類、メリット・デメリット、選定時のポイントまで徹底解説していきます。
この記事を読むことで、自社に最適なWAFを選定するための知識が身につくため、セキュリティ対策を強化したい企業担当者には必見の内容です!
WAFとは?
WAF(Web Application Firewall)とは、Webアプリケーションを保護するためのファイアウォールのことです。
一般的なファイアウォールはネットワークレベルでの通信を制御しますが、WAFはWebアプリケーションの脆弱性を悪用する攻撃(SQLインジェクションやXSSなど)を防ぐことに特化しています。
具体的には、HTTP/HTTPS通信を解析し、シグネチャ(不正な通信、不正な攻撃パターンをまとめた定義ファイル)とのマッチングを実行。不正なリクエストを検知してブロックすることで、Webアプリケーションをサイバー攻撃から保護します。
WAFとファイアウォールの違い
WAFとファイアウォールの最大の違いは防御する対象です。ファイアウォールはネットワーク層の通信を制御し、不正アクセスを遮断します。
例えば、ファイアウォールは特定のIPアドレスやポートをブロックできますが、攻撃コードを含むリクエストの内容までは検知しません。そのため、許可された通信経路を通じたWebアプリケーションへの攻撃は防げない場合があります。
WAFは、HTTP/HTTPS通信を詳細に分析し、不正なリクエストを検知してブロックします。そのため、ファイアウォールとWAFを組み合わせることで、より強固なWebセキュリティを実現可能です。
WAFとIPS/IDSの違い
WAFとIPS/IDSの最大の違いは解析対象にあります。IPS/IDSがネットワーク全体の通信を監視するのに対し、WAFはWebアプリケーションの通信内容に特化して解析するのが特徴です。
例えば、IPS/IDSはパケットのヘッダー情報や既知の攻撃パターンをもとに異常を検知します。しかし、Webアプリケーションの特定の脆弱性を狙った攻撃には対応が難しいケースもあります。
そのため、WAFとIPS/IDSを組み合わせることで、アプリケーション層とネットワーク層の両方を防御でき、より強固な多層防御のセキュリティ環境を構築できるでしょう。
なぜWAFが必要なのか?
- Webアプリケーションへの脆弱性対策
- サイバー攻撃の高度化と多様化への対応
- 法規制や新しいセキュリティ基準への対応
Webアプリケーションへの脆弱性対策
Webアプリケーションは、SQLインジェクションやXSSといったアプリケーション層の脆弱性を狙った攻撃に対して弱い側面が見受けられます。
これらの攻撃は、従来のネットワークセキュリティ対策では検知・防御が困難です。そのため、Webアプリケーションに特化したWAFを導入することで、脆弱性を悪用する攻撃の遮断が期待できます。
例えば、WAFはHTTPリクエストを解析し、不審なパターンを自動検知することで、アプリケーションの脆弱性が修正される前でも攻撃のリスクを軽減できます。
サイバー攻撃の高度化と多様化への対応
近年のサイバー攻撃はより巧妙化し、従来のセキュリティ対策では防ぎきれないケースが増えています。
標的型攻撃やゼロデイ攻撃、AIを活用した自動化攻撃など、新たな手法が次々と登場しており、従来のファイアウォールやIPS/IDSでは検知が困難です。
WAFは、リアルタイムでの脅威情報更新と最新の攻撃パターンへの対応に加え、AIや機械学習を活用した高度なWAFを導入することで、未知の攻撃に対する耐性を強化できます。
法規制や新しいセキュリティ基準への対応
企業がWebアプリケーションを運用する上で、個人情報保護やデータ管理に関する法規制への対応は不可欠です。
WAFを導入することで、Webアプリケーションに対する攻撃を未然に防ぎ、法規制に準拠したセキュリティ基準を満たせます。
特に、クレジットカード情報を取り扱う事業者は、PCI DSS(クレジットカード業界のセキュリティ基準)への準拠が求められており、WAFの導入は必須の対策とされています。
WAFの仕組み
- ブラックリスト方式
- ホワイトリスト方式
ブラックリスト方式
ブラックリスト方式とは、既知の攻撃パターンや悪意のあるIPアドレスをブロックする方式です。あらかじめ登録された攻撃のシグネチャを元に不正なリクエストを検出し、Webサーバへのアクセスを防御します。
この方式のメリットは、既知の攻撃を即座に遮断できる点です。例えば、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)などの一般的な攻撃手法に対して、定義済みのルールに基づき自動的に防御できます。
一方、デメリットとして新たな攻撃手法への対応が難しい点が挙げられます。未知の攻撃パターンやカスタマイズされた攻撃には対応できず、定期的なルール更新が不可欠です。
ホワイトリスト方式
ホワイトリスト方式とは、許可されたリクエストのみを通過させる方式です。正常なアクセスのパターンを事前に定義し、それ以外のリクエストはすべて遮断します。
この方式のメリットは、未知の攻撃に対しても高い防御性能を持つ点です。許可されたリクエスト以外は排除されるため、ゼロデイ攻撃(未知の脆弱性を狙った攻撃)にも対応できます。
一方で、デメリットは導入や運用に手間がかかる点です。通常の業務に必要なアクセスパターンを詳細に定義することが求められ、新しい機能やサービスを追加する際には、都度ルール変更が必須となります。
WAFが防御できる攻撃と効果
- SQLインジェクション
- クロスサイトスクリプティング(XSS)
- クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)
- ディレクトリトラバーサル
- その他の攻撃手法(DoS、リモートコード実行など)
SQLインジェクション
SQLインジェクションは、アプリケーションの脆弱性を悪用し、不正なSQLクエリを実行させる攻撃手法です。
WAFは、入力値のフィルタリングや不正なクエリパターンの検出により、SQLインジェクションを防御します。
SQLインジェクション対策としては、プリペアドステートメントの使用や入力値のバリデーションも重要です。特に、サーバーサイドでの適切なエスケープ処理や、ユーザー入力値のホワイトリスト化は有効な対策となります。
クロスサイトスクリプティング(XSS)
クロスサイトスクリプティング(XSS)とは、悪意のあるスクリプトをウェブページに埋め込み、利用者のブラウザ上で実行させる攻撃手法です。
WAFは、スクリプトタグ(<script>)やイベントハンドラ(onload, onclick)を含む不正な入力を検出し、ブロックすることでXSS攻撃を防御します。
XSS対策としては、サーバー側での適切なエスケープ処理や、Content Security Policy(CSP)の設定が重要です。特に、ユーザーが入力できるデータを制限し、信頼できないデータの出力時にはエンコード処理を行うことが効果的です。
クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)
クロスサイトリクエストフォージェリ(CSRF)とは、被害者の認証情報を悪用し、不正なリクエストを送信させる攻撃手法です。
WAFは、リファラーチェックや異常なリクエストパターンの分析を行い、不正なCSRF攻撃を防御します。また、CSRFトークンの有無を確認する機能を備えたWAFもあり、正規のリクエストと攻撃リクエストを区別することが可能です。
CSRF対策としては、トークンベースの認証(CSRFトークン)やSameSite属性を活用したCookie制限が有効です。特に、重要な操作を行うフォームには、ワンタイムトークンを付与し、外部からの不正なリクエストを防ぐことが推奨されます。
ディレクトリトラバーサル
ディレクトリトラバーサルとは、サーバー上の機密ファイルに不正アクセスするための攻撃手法です。
WAFは、不正なパス操作を検出し、攻撃をブロックすることでディレクトリトラバーサルを防御します。
ディレクトリトラバーサル対策としては、アプリケーション側での入力値の正規化やアクセス制御の適用が重要です。特に、ユーザー入力を直接ファイルパスとして使用しないようにすることや、サーバーの適切な権限設定を行うことが推奨されます。
その他の攻撃手法(DoS、リモートコード実行など)
DoS攻撃は、大量のリクエストを送信することでサーバーのリソースを圧迫し、正常なユーザーのアクセスを妨げる手法です。
WAFは、異常なトラフィックの検知やレートリミット機能を活用し、DoS攻撃の影響を最小限に抑えます。さらに、IPアドレスのブラックリスト化やボット対策機能を組み合わせることで、自動化された攻撃を効果的に防御できます。
リモートコード実行(RCE)は、攻撃者がサーバー上で任意のコードを実行し、不正操作を行う危険な攻撃手法です。WAFは、不正なコードパターンの検出や入力データのフィルタリングを行い、脆弱性を悪用した攻撃を未然に防ぎます。
WAFの種類と特徴
- オンプレミス型WAF
- クラウド型WAF
- パブリッククラウド提供のWAF
オンプレミス型WAF
オンプレミス型WAFは、自社のデータセンターやサーバーに設置して運用するWAFです。
専用のハードウェアやソフトウェアを導入し、企業のネットワーク環境に応じた高度なセキュリティ設定が可能です。
オンプレミス型WAFの特徴
- カスタマイズ性が高いため、自社のセキュリティポリシーに最適化できる
- 物理的な機器を設置するため、ネットワーク内で直接トラフィックを監視できる
- 定期的なメンテナンスやアップデートが必要で、運用負担が大きい
オンプレミス型WAFが向いている企業
- 金融機関や官公庁など、高度なセキュリティが求められる企業
- 専任のセキュリティ担当者を配置できる大規模な組織
クラウド型WAF
クラウド型WAFは、インターネット経由で提供されるWAFサービスです。
導入が容易で、迅速にウェブアプリケーションを保護できるため、近年多くの企業が採用しています。
クラウド型WAFの特徴
- 導入が簡単で、ハードウェアの設置が不要
- 運用・管理がプロバイダーに委託できるため、運用コストを削減できる
- 通信遅延が発生する可能性があるため、リアルタイム性が求められるサービスでは注意が必要
クラウド型WAFが向いている企業
- 初めてWAFを導入する企業や中小企業
- 迅速なセキュリティ対策を求める企業
パブリッククラウド提供のWAF
パブリッククラウド提供のWAFは、AWSやAzure、Google Cloudなどのクラウドサービスプロバイダーが提供するWAFです。
クラウド環境に最適化されており、既存のクラウドサービスと連携しやすいのがメリットになります。
パブリッククラウド提供のWAFの特徴
- クラウドインフラと統合されているため、管理が容易
- スケーラビリティが高く、負荷分散にも適している
- 特定のクラウド環境に依存するため、マルチクラウド環境では制約が発生する可能性がある
パブリッククラウド提供のWAFが向いている企業
- AWSやAzure、Google Cloudなどのクラウド環境を活用している企業
- スケーラブルなWAFを求める企業
WAFを導入するメリット
- サイバー攻撃の耐性が強化される
- DDoS攻撃への耐性を向上できる
- システムの脆弱性を補完できる
サイバー攻撃の耐性が強化される
WAFのメリットの1つ目としては「サイバー攻撃の耐性が強化される」というものが挙げられます。
Webアプリケーションは、SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)など、多岐にわたるサイバー攻撃の標的となりやすく、一般的なファイアウォールだけでは防御が困難です。
特に、ECサイトや金融サービスのように個人情報を扱うWebアプリケーションでは、情報漏洩を狙った攻撃が後を絶ちません。WAFを導入することで、これらの攻撃をリアルタイムに検出し、自動的に遮断することが可能になります。
DDoS攻撃への耐性を向上できる
WAFのメリットの2つ目としては「DDoS攻撃への耐性を向上できる」というものが挙げられます。
DDoS(分散型サービス拒否)攻撃は、大量のリクエストを送りつけることでWebサイトをダウンさせる手法ですが、WAFを活用することでその影響を最小限に抑えられます。
例えば、異常なトラフィックパターンを自動で検知し、特定のIPアドレスやリクエストをブロックすることで、不正なアクセスを抑制できます。さらに、CDN(コンテンツ配信ネットワーク)と組み合わせたクラウド型WAFを導入することで、DDoS攻撃のトラフィックを分散し、サーバーの負荷を軽減することが可能です。
システムの脆弱性を補完できる
WAFのメリットの3つ目としては「システムの脆弱性を補完できる」というものが挙げられます。
Webアプリケーションは、未知のゼロデイ攻撃や、修正が追い付かない脆弱性を抱えるリスクがありますが、WAFはパッチが適用されるまでの間、強力な保護層として機能します。
例えば、WAFはシグネチャベースの検知だけでなく、AIや振る舞い分析を活用した未知の攻撃防御も可能です。これにより、迅速なパッチ適用が困難な状況でも、セキュリティリスクを最小限に抑え、システムを安全に保てます。
WAF導入によるデメリット
- 初期導入や運用にはコストが発生する
- 誤検知による業務への影響が発生する
- 高度な設定には専門知識が必要になる
初期導入や運用にはコストが発生する
WAFのデメリットの1つ目としては「初期導入や運用にはコストが発生する」というものが挙げられます。
WAFの導入には、初期費用や月額料金がかかるため、特に中小企業にとっては負担が大きくなる可能性があります。
解決策としては、無料トライアルがあるクラウド型WAFの利用を検討することや、企業規模に応じた料金プランを選択することが有効です。
誤検知による業務への影響が発生する
WAFのデメリットの2つ目としては「誤検知による業務への影響が発生する」というものが挙げられます。
過剰なセキュリティ設定は、正常なリクエストを誤って遮断し、業務システムの稼働を妨げる可能性があります。
解決策としては、ログを定期的に分析し、誤検知が発生しやすいルールを適宜チューニングすることが重要です。
高度な設定には専門知識が必要になる
WAFのデメリットの3つ目としては「高度な設定には専門知識が必要になる」というものが挙げられます。
オンプレミス型WAFでは、最適なセキュリティポリシーの設定から継続的な運用に至るまで、専門的なIT知識を有する担当者の配置が必要になります。
解決策としては、運用管理が容易なマネージド型WAFの導入や、外部のセキュリティ専門家によるサポートサービスの利用が有効です。
WAFの選び方と比較のポイント
- ➀:導入形態(クラウド型/オンプレミス型)を確認する
- ➁:防御性能や対応可能な攻撃の種類を確認する
- ③:運用のしやすさや管理の機能を確認する
➀:導入形態(クラウド型/オンプレミス型)を確認する
WAFを選ぶ際のポイントの1つ目は「導入形態(クラウド型/オンプレミス型)を確認する」ことです。
クラウド型は導入・運用が容易なためセキュリティ担当者不在の企業に、オンプレミス型は高度なカスタマイズ性で高度なセキュリティを求める企業に適しています。
それぞれのメリットを比較し、自社のニーズに合ったWAFを選びましょう。
➁:防御性能や対応可能な攻撃の種類を確認する
WAFを選ぶ際のポイントの2つ目は「防御性能や対応可能な攻撃の種類を確認する」ことです。
Webサイトは日々さまざまなサイバー攻撃の標的になっており、SQLインジェクション・クロスサイトスクリプティング(XSS)・DDoS攻撃など、さまざまな脅威に対する防御機能が求められます。
また、AIや機械学習を活用するWAFは、未知の攻撃にも自動で対応しセキュリティを強化します。そのため、自社のセキュリティ要件に応じて、防御可能な攻撃を事前に確認し、最適なWAFを選定しましょう。
③:運用のしやすさや管理の機能を確認する
WAFを選ぶ際のポイントの3つ目は「運用のしやすさや管理の機能を確認する」ことです。
WAFの運用には設定変更・ログ監視・ポリシー更新などの作業が必要となるため、管理のしやすさは重要です。特に、直感的に操作できる管理画面や、設定の自動更新機能があるかどうかを確認しましょう。
クラウド型WAFはシンプルな管理画面で運用負担が少ないのに対し、オンプレミス型は細かい設定が可能ですが専門知識が必要です。自社の運用体制を考慮し、選定することが重要になります。
まとめ
本記事では、WAFの概要をわかりやすく解説し、種類や導入によるメリット・デメリットについて徹底解説しました。
近年、サイバー攻撃の高度化が進む中、企業にとってWAFの導入は欠かせないセキュリティ対策となっています。特に、クラウド型WAFやAIを活用した次世代型ソリューションの台頭により、今後も市場の成長が見込まれています。
今後もITreviewでは、WAFサービスのレビュー収集に加えて、新しいWAFサービスも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 WAFとは?サイバー攻撃を防ぐ仕組みやメリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 UTM(統合脅威管理)とは?機能や導入メリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>とはいえ、UTMは製品によって処理能力や機能に違いがあり、適切な製品選定や設定を行わなければ、かえってセキュリティ上の脆弱性が生まれるリスクがあります。
本記事では、UTMの主な機能や導入のメリット・デメリットに加え、UTMの選び方まで詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、UTMの全体像を理解し、自社に最適なセキュリティ対策を選ぶ知識が身につきます。企業の情報セキュリティを強化したいと考えている担当者にとって、必見の内容です!
UTM(統合脅威管理)とは
UTM(統合脅威管理)とは、企業ネットワークのセキュリティを統合的に管理するソリューションのことです。
従来のファイアウォールに加えて、侵入検知・防御(IDS/IPS)、ウイルス対策、Webフィルタリングなど、複数のセキュリティ機能を一元化することで、効率的な脅威対策が可能になります。
特に、中小企業や支社・拠点を持つ企業では、専門のセキュリティ担当者を配置せずに、包括的な防御を実現できる点が大きなメリットです。
具体的な活用例としては、インターネットゲートウェイでの脅威防御や、外部からの不正アクセスの監視、Webサイトのアクセス制限などが挙げられます。
UTM(統合脅威管理)が生まれた背景
UTMが生まれた背景には、サイバー攻撃の高度化と多様化があります。従来のセキュリティ対策では、マルウェア、フィッシング、DDoS攻撃などの新たな脅威への対応が困難になりました。
また、クラウドサービスの普及やリモートワークの増加に伴い、企業のセキュリティリスクが急増。特に中小企業においては、多層防御のために複数のセキュリティ製品を導入・管理する負担が大きな課題となっていました。
これらの課題に対処するため、統合的な脅威防御を可能にするUTMが登場し、企業のセキュリティ管理効率化に貢献しています。
UTM(統合脅威管理)とファイアウォールの違い
UTMとファイアウォールの違いは、提供するセキュリティ機能の範囲にあります。
ファイアウォールは、不正な通信を遮断し、ネットワークの入口を守ることに特化しています。一方で、UTMは、ファイアウォールの機能に加え、ウイルス対策、侵入検知・防御、Webフィルタリングなど、多岐にわたるセキュリティ機能を統合しています。
これにより、個別の対策を行うよりも管理の負担を軽減し、より強固なセキュリティ体制を構築できます。
UTM(統合脅威管理)の主な機能
- ファイアウォール
- アンチウイルス
- アンチスパム
- Webフィルタリング
- IDS/IPS(侵入検知・防御システム)
- その他のセキュリティ機能
ファイアウォール
ファイアウォールは、外部ネットワークと内部ネットワークの間で通信を制御するセキュリティ機能です。
ネットワークトラフィックを監視し、不正なアクセスや不審な通信を遮断することで、サイバー攻撃から企業のシステムを保護します。
例えば、特定のIPアドレスやポート番号によるアクセス制限に加え、次世代ファイアウォール(NGFW)では、アプリケーション制御や脅威インテリジェンスを活用した高度な防御も可能です。
アンチウイルス
アンチウイルス機能は、ネットワークを介して侵入するマルウェアやウイルスを検知し、駆除します。
リアルタイムスキャンにより、社内端末に脅威が到達する前に遮断することが可能です。クラウドベースのウイルス定義データベースを活用することで、最新の脅威にも対応可能です。
さらに、サンドボックス機能を搭載したUTMでは、疑わしいファイルを仮想環境で解析し、未知のマルウェアによる脅威を防御できます。
アンチスパム
アンチスパム機能は、不審なメールをフィルタリングし、フィッシング詐欺やスパムメールの侵入を防ぎます。
スパムメールは、情報漏洩やウイルス感染を引き起こす可能性があるため、適切な対策が必要です。
UTMのアンチスパム機能は、メールの送信元情報や内容解析による疑わしいメールの隔離と、ブラック/ホワイトリスト設定による必要なメールの保護を両立します。
Webフィルタリング
Webフィルタリング機能は、従業員のインターネット利用を管理し、特定のサイトへのアクセスを制限する機能です。
不正サイトへのアクセスを防ぐことで、マルウェア感染や情報漏洩のリスクを低減できます。
カテゴリ別のURLフィルタリングに加え、リアルタイムの脅威インテリジェンスを活用した動的フィルタリングが可能です。また、SNSや動画ストリーミングサイトの利用を制限することで、従業員の業務効率向上にもつながるでしょう。
IDS/IPS(侵入検知・防御システム)
IDS(侵入検知システム)とIPS(侵入防御システム)は、不正アクセスやサイバー攻撃をリアルタイムで検知し、場合によっては遮断する機能です。
ファイアウォールでは防ぎきれない高度な攻撃に対して有効な対策となります。
IDSは、攻撃の兆候を検知することに特化していますが、IPSは検知後に自動的に攻撃を遮断できます。また、機械学習やAIを活用した高度な分析機能を備えたUTMでは、未知の攻撃手法にも対応可能です。
その他のセキュリティ機能
UTMには、上記以外にもさまざまなセキュリティ機能が搭載されています。
例えば、VPN(仮想プライベートネットワーク)機能、DLP(データ漏洩防止)機能、アプリケーション制御機能などが挙げられます。VPNを活用することで、安全なリモートアクセス環境を構築し、テレワークのセキュリティを強化できます。
また、DLP機能を用いることで、機密情報が社外へ流出するのを防ぎ、企業の重要なデータを保護することが可能です。
UTM(統合脅威管理)を導入するメリット
- 複数のセキュリティ機能を一元管理できる
- 低コストで高いセキュリティを確保できる
- 新しい脅威に対しても迅速に対応できる
複数のセキュリティ機能を一元管理できる
UTMのメリットの1つ目としては「複数のセキュリティ機能を一元管理できる」というものが挙げられます。
UTMは、ファイアウォール、アンチウイルス、侵入検知・防御(IDS/IPS)などの機能を統合しており、複数のセキュリティ対策を一括で管理できます。
例えば、従来は各機能を個別のソフトウェアや機器で運用していたため、それぞれの設定や監視に手間がかかりましたが、UTMを導入することで管理負担を軽減し、セキュリティ対策の強化と一元管理が可能です。
低コストで高いセキュリティを確保できる
UTMのメリットの2つ目としては「低コストで高いセキュリティを確保できる」というものが挙げられます。
複数のセキュリティ機能を個別に導入した場合、それぞれのライセンス費用や運用コストが発生しますが、UTMは1つの機器に統合されているため、これらのコストを削減できます。
例えば、中小企業が限られた予算でセキュリティ対策を強化したい場合、UTMを導入することで必要な機能を低コストで利用でき、運用管理の負担も軽減できます。
新しい脅威に対しても迅速に対応できる
UTMのメリットの3つ目としては「新しい脅威に対しても迅速に対応できる」というものが挙げられます。
UTMは、クラウド連携やリアルタイムアップデート機能を備えており、新たなマルウェアやサイバー攻撃が発生した場合でも、自動的に最新のセキュリティ対策を適用できます。
例えば、ランサムウェアやゼロデイ攻撃など、従来のセキュリティ対策では防ぎにくい脅威に対しても、迅速に防御体制を強化し、企業の情報資産を保護できます。
UTM(統合脅威管理)導入によるデメリット
- 導入や運用の負担が増加する可能性がある
- ネットワーク速度が低下する可能性がある
- 保守運用コストが高額になる可能性がある
導入や運用の負担が増加する可能性がある
UTMのデメリットの1つ目としては「導入や運用の負担が増加する可能性がある」というものが挙げられます。
UTMは、多岐にわたるセキュリティ機能を統合しているため、設定や管理が複雑になり、IT部門の負担が増大する傾向があります。
解決策として、ベンダーのサポートが付くUTMや、クラウド型UTMの導入で管理負担を軽減し、導入時は業務内容に適した設計と運用ポリシーを策定することが重要です。
ネットワーク速度が低下する可能性がある
UTMのデメリットの2つ目としては「ネットワーク速度が低下する可能性がある」というものが挙げられます。
UTMは、多機能なセキュリティ対策が可能になる一方で、通信処理の増加がネットワーク速度に影響を及ぼす可能性があります。特に、トラフィック量の多い企業では、帯域幅の制約が顕著になります。
解決策として、企業の規模とトラフィックに合ったUTMを選び、適切な設定と最適化でパフォーマンス低下を最小限に抑えることが重要です。
保守運用コストが高額になる可能性がある
UTMのデメリットの3つ目としては「保守運用コストが高額になる可能性がある」というものが挙げられます。
UTMは、導入費用やライセンス費用が高額になるため、特に中小企業にとっては大きな負担となる場合があります。また、定期的なソフトウェア更新やハードウェアのメンテナンスにも追加コストが発生します。
解決策としては、クラウド型UTMの利用や、必要な機能を選択できる製品の導入が有効です。また、トライアルなどを活用し、自社のセキュリティ要件に合ったUTMを慎重に選定することで、不要なコストを削減できます。
UTM(統合脅威管理)の選び方と比較のポイント
- ①:セキュリティ機能の充実度で選ぶ
- ②:パフォーマンスと処理速度で選ぶ
- ③:管理や運用のしやすさで選ぶ
- ④:導入費用や運用コストで選ぶ
- ⑤:拡張性と将来のスケーラビリティで選ぶ
- ⑥:サポート体制とベンダーの信頼性で選ぶ
①:セキュリティ機能の充実度で選ぶ
UTMの選び方の1つ目としては「セキュリティ機能の充実度で選ぶ」という方法が挙げられます。
特に、ファイアウォール、IPS(侵入防御システム)、アンチウイルス、Webフィルタリング、メールセキュリティ、VPN機能などの充実度を確認することが重要です。
高度なUTMでは、AIを活用した脅威検出、サンドボックス機能、クラウド連携によるリアルタイム分析など、最新の攻撃手法に対応するための機能が搭載されています。
➁:パフォーマンスと処理速度で選ぶ
UTMの選び方の2つ目としては「パフォーマンスと処理速度で選ぶ」という方法が挙げられます。
UTMは多機能なセキュリティ機器であるため、処理能力が低いとネットワーク遅延が発生し、業務に支障をきたす可能性があります。
そのため、自社のネットワーク規模やトラフィック量に応じて、スループットや最大接続数を確認しましょう。特にクラウドサービスの利用が多い場合は、暗号化通信(SSL/TLS)の対応やVPN処理能力も重要なポイントです。
③:管理や運用のしやすさで選ぶ
UTMの選び方の3つ目としては「管理や運用のしやすさで選ぶ」という方法が挙げられます。
UTMは多機能であるがゆえに、設定や管理が複雑になりがちです。特に、IT担当者が少ない企業では、管理画面の使いやすさや設定の容易さが重要なポイントになります。
具体的には、直感的なGUIを備えたUTMを選ぶことで、設定やポリシー変更がスムーズに行えます。また、クラウド管理型のUTMなら、リモートからの監視やメンテナンスが容易になるため、外部拠点が多い企業におすすめです。
④:導入費用や運用コストで選ぶ
UTMの選び方の4つ目としては「導入費用や運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。
UTMの価格は、機能や性能によって大きく変動します。そのため、初期費用とランニングコストのバランスを考慮することが重要です。
ハードウェア型UTMは導入費用が高めですが、長期的な運用コストを抑えやすいのが特徴です。一方、クラウド型UTMは初期費用が低く柔軟に利用できるため、小規模企業やスタートアップにも適しています。
➄:拡張性と将来のスケーラビリティで選ぶ
UTMの選び方の5つ目としては「拡張性と将来のスケーラビリティで選ぶ」という方法が挙げられます。
企業の成長に伴いネットワーク環境も変化します。そのため、将来的な拡張が可能なUTMを選ぶことで、長期的に安定した運用が期待できます。
接続端末数やトラフィック増加時の対応として、ライセンス追加やハードウェア更新が容易なUTMの選定が重要です。また、SD-WAN対応のUTMを導入すると、複数拠点のネットワーク最適化にも容易に対応できます。
⑥:サポート体制とベンダーの信頼性で選ぶ
UTMの選び方の6つ目としては「サポート体制とベンダーの信頼性で選ぶ」という方法が挙げられます。
セキュリティ機器は、トラブル発生時の迅速な対応が不可欠です。したがって、サポートの質と提供元の信頼性を十分に考慮して選ぶ必要があります。
24時間365日のサポートや日本語対応の有無、およびファームウェアの定期更新やセキュリティ脅威情報提供の有無は、UTMの長期的な安全運用において重要な要素です。
まとめ
本記事では、UTM(統合脅威管理)の概要をわかりやすく解説するとともに、主な機能や導入のメリット・デメリットについて詳しくご紹介しました。
サイバー攻撃の高度化が進む中、UTM市場は世界的に拡大を続けており、AIやクラウドを活用した新たなセキュリティ対策も登場しています。今後も企業のネットワークを守るため、UTMの需要はますます高まることが予測されます。
今後もITreviewでは、UTM製品のレビュー収集に加えて、新しいUTMソリューションも随時掲載予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 UTM(統合脅威管理)とは?機能や導入メリットをわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 CDPとは?主な機能やマーケティングの活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>ECサイトやPOS、SNSなど、複数のチャネルから取得したデータを統合し、顧客の行動を詳細に分析することができるようになります。
しかし、CDPの導入にはコストやデータ統合の複雑さといった課題があり、適切な運用ができなければ期待する成果を得られないリスクもあります。
本記事では、CDPの概要をわかりやすく解説することに加えて、基本機能や導入のメリット・デメリット、選定のポイントまで徹底解説します。
この記事を読むことで、CDPの全体像を把握し、自社に最適な活用方法を理解できるため、マーケティング担当者やデータ活用を検討している企業の意思決定者にとって必見の内容です!
CDP(Customer Data Platform)とは?
CDP(Customer Data Platform)とは、企業が保有するオンライン・オフラインの顧客データを一元管理し、マーケティングや営業活動に活用するプラットフォームのことです。
様々なチャネルから取得した顧客データを統合し、顧客一人ひとりの詳細なプロファイルを作成することで、よりパーソナライズされた顧客体験の提供が可能になります。
具体的には、購買履歴やWeb行動、SNSの反応、CRMデータなどを統合し、顧客の属性や興味関心、行動履歴などを把握できます。
主な活用例としては、ECサイトでのレコメンド強化、広告配信の最適化、カスタマーサポートのパーソナライズなどがあり、企業のマーケティング戦略を大きく向上できます。
CDPとCRM・MAとの違いは?
CDPと、CRM(顧客関係管理)、MA(マーケティングオートメーション)は、それぞれ異なる役割を持つツールです。
CRMは、既存顧客の情報を管理し、営業やカスタマーサポートを支援するために活用されます。一方、MAは見込み顧客の育成を自動化し、メール配信やスコアリングを通じて購買につなげることを目的としています。
CDPをCRMやMAと連携させることで、それぞれのツールが持つ機能をさらに強化し、より高度なマーケティング戦略を展開できます。
CDPの主な機能と活用事例
- データの収集と統合
- 顧客プロファイルの作成
- データ分析とセグメンテーション
- マーケティング施策への活用
➀:データの収集と統合
CDPの主な機能の1つ目は「データの収集と統合」です。
CDPは、Webサイトやアプリ、CRM、POS、SNSなど、複数のデータソースから顧客データを一元的に収集し、統合します。これにより、バラバラに管理されていたデータを統一し、企業全体で一貫性のある顧客データを活用できるようになります。
例えば、ECサイトの購買履歴や閲覧履歴、カスタマーサポートの問い合わせ履歴など、異なるデータを統合することで、顧客の全体像を把握することが可能です。
➁:顧客プロファイルの作成
CDPの主な機能の2つ目は「顧客プロファイルの作成」です。
収集したデータをもとに、顧客ごとに詳細な統合プロファイルを作成し、購買履歴や行動パターン、興味・関心などを明確にします。これにより、個別の顧客ごとに最適なマーケティング施策の立案が可能です。
例えば、CDPを活用することで、ECサイトの利用履歴やメール開封履歴、SNSでの反応をもとに、ユーザーが好む商品やコンテンツを特定できます。
③:データ分析とセグメンテーション
CDPの主な機能の3つ目は「データ分析とセグメンテーション」です。
CDPは、統合した顧客データをもとに、AIや機械学習を活用した高度なデータ分析を行い、顧客を細かく分類(セグメント化)します。これにより、企業は特定のターゲットに向けた精度の高いマーケティング施策を実施できるようになります。
例えば、購買頻度の高いリピーター層や、一度だけ購入したが再訪していない顧客など、行動パターンごとに異なるマーケティング戦略を立案できます。
④:マーケティング施策への活用
CDPの主な機能の4つ目は「マーケティング施策への活用」です。
CDPは、統合データや顧客プロファイル、セグメントデータをもとに、各種マーケティングチャネルへ自動連携し、最適な施策を実行します。これにより、広告配信、メールマーケティング、SNSマーケティング、パーソナライズ施策などの効果を最大化できます。
例えば、過去の購買履歴をもとにリピーター向けのクーポンを発行したり、Webサイトの行動データを分析して離脱防止のポップアップを表示したりすることが可能です。
CDPの導入メリット
- データの一貫性を維持できる
- リアルタイム対応が可能になる
- データセキュリティを強化できる
データの一貫性を維持できる
CDPのメリットの1つ目は「データの一貫性を維持できる」というものが挙げられます。
CDPは統合されたデータ基盤を提供するため、異なる部署やシステム間でデータの不整合が発生するリスクを軽減できます。これにより、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、部門ごとに異なるデータを参照することなく、共通のデータを活用できます。
例えば、マーケティング部門が配信したキャンペーンに対する顧客の反応を、営業部門がリアルタイムで確認し、最適な営業アプローチを実施することが可能です。
リアルタイム対応が可能になる
CDPのメリットの2つ目としては「リアルタイム対応が可能になる」というものが挙げられます。
従来のデータ管理システムでは、データの更新に時間がかかり、迅速な顧客対応が難しい場合がありました。CDPを導入することで、顧客の行動データを即座に取得し、それに基づいた施策をリアルタイムで実行できます。
例えば、ECサイトで特定の商品をカートに入れたまま離脱した顧客に対して、すぐにリマインドメールや限定クーポンを自動配信し、購入率を向上させる施策が可能です。
データセキュリティを強化できる
CDPのメリットの3つ目としては「データセキュリティを強化できる」というものが挙げられます。
顧客データの取り扱いに関する法規制が厳しくなる中、企業はデータの管理と保護を徹底する必要があります。CDPは、データのアクセス制御や匿名化、暗号化といった機能を提供し、企業が法規制を遵守しながら安全にデータを活用できる環境を構築します。
例えば、GDPRやCCPAなどの規制に対応するため、顧客の同意管理やデータの保存期間を適切に設定し、コンプライアンスを維持することが可能です。
CDPの導入デメリット
- 導入や運用にコストが発生する
- データ統合に時間と労力がかかる
- 活用には専門的な知識が必要になる
導入や運用にコストが発生する
CDPのデメリットの1つ目としては「導入や運用にコストが発生する」というものが挙げられます。
CDPの導入には初期費用や月額料金に加えて、データの統合・運用に関する人的リソースも必要です。特に大規模なCDPを導入する場合、データ管理やシステム統合にかかるコストが増大します。
解決策としては、自社のビジネス規模に適したプランを選択することや、無料トライアルやデモ環境を活用して費用対効果を事前に検証しましょう。
データ統合に時間と労力がかかる
CDPのデメリットの2つ目としては「データ統合に時間と労力がかかる」というものが挙げられます。
CDPは顧客データを統合して活用するため、各種データソースとの接続設定やフォーマット変換が必要です。データクレンジングやタグ設計の見直しが必要になることもあり、短期間での導入が難しい場合があります。
解決策としては、既存システムとの連携が容易なCDPを選定することや、導入支援サービスを活用してデータ統合をスムーズに進めることが有効です。
活用には専門的な知識が必要になる
CDPのデメリットの3つ目としては「活用には専門的な知識が必要になる」というものが挙げられます。
CDPを効果的に活用するには、データ分析のスキルやマーケティングオートメーション(MA)との連携に関する知識が必要です。データを収集・統合するだけではなく、それを活用して顧客インサイトを導き出すことが求められます。
解決策としては、CDPのトレーニングを実施することや、専門家を採用・育成することが重要です。
CDPの選び方と比較ポイント
- ①:データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ
- ②:セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ
- ③:他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ
- ④:リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ
- ⑤:セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ
①:データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ
CDPを選ぶポイントの1つ目としては「データ統合の範囲と対応データソースで選ぶ」というものが挙げられます。
CDPはさまざまなデータを統合するためのプラットフォームですが、対応するデータソースが限定されている場合、運用に制約が生じます。幅広いデータソースと連携できるCDPを選択することで、より包括的なデータ管理が可能です。
例えば、SalesforceやGoogle Analytics、広告プラットフォーム、POSデータ、IoTデータなどの多様なソースに対応するCDPを選ぶことで、マーケティング施策の幅が広がります。
②:セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ
CDPを選ぶポイントの2つ目としては「セグメントの作成や分析機能の充実度で選ぶ」というものが挙げられます。
CDPは顧客データを統合するだけでなく、適切なセグメントを作成し、データを活用できる分析機能を備えているかが重要です。高度なセグメンテーションやAIを活用した予測分析が可能なCDPを選ぶことで、マーケティング施策の最適化が期待できます。
例えば、リアルタイムでセグメントを作成し、広告配信やメールマーケティングと連携できるCDPは、顧客の行動変化に素早く対応できます。
③:他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ
CDPを選ぶポイントの3つ目としては「他のマーケティングツールとの連携性で選ぶ」というものが挙げられます。
CDP単体ではなく、CRM、MA、広告管理ツールなどとスムーズに連携できるかが、実用性に大きく影響します。APIやノーコードでの連携機能が充実しているCDPを選ぶと、マーケティング施策の自動化が容易になります。
例えば、HubSpotやMarketo、Google広告、Facebook広告、LINEなどの複数チャネルとシームレスに接続できるCDPを選ぶと、データの一貫性を保ちながら施策を実行できます。
④:リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ
CDPを選ぶポイントの4つ目としては「リアルタイム処理の速度や対応の可否で選ぶ」というものが挙げられます。
顧客の行動データを即座に分析し、リアルタイムで施策に反映できるかがCDPの性能を大きく左右します。リアルタイム処理が可能なCDPを選ぶことで、ECサイトやアプリ上でのパーソナライズ施策がスムーズに実行できます。
例えば、顧客がサイトに訪問した瞬間に、最適なクーポンや広告を表示できるCDPは、購買意欲を高めるのに効果的です。
⑤:セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ
CDPを選ぶポイントの5つ目としては「セキュリティとデータガバナンス強度で選ぶ」というものが挙げられます。
個人情報や機密データを扱うCDPでは、セキュリティ対策やデータガバナンスの仕組みがしっかりしているかが重要です。特に、GDPRやCCPAといったプライバシー規制への対応が求められます。
例えば、アクセス権限の細かい管理、暗号化機能、データの匿名化が可能なCDPを選ぶことで、データ漏洩のリスクを軽減できます。
まとめ
本記事では、CDPの概要をわかりやすく解説するのに加えて、活用事例や導入によるメリット・デメリット、選定ポイントまで、まとめて徹底的に解説していきました。
CDPは、AIや機械学習の進化により、高度な予測分析やリアルタイムマーケティングの活用がさらに進むと予想されます。
今後もITreviewでは、CDPのレビュー収集に加えて、新しいCDPについても続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 CDPとは?主な機能やマーケティングの活用事例をわかりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 EDRとは?主な機能や導入メリット・選び方までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>近年、ランサムウェア攻撃やゼロデイ攻撃の増加を背景に、EDRの重要性が高まっており、対策を怠ってしまうと、情報漏えいやデータの改ざんなど、致命的なインシデントに発展してしまいます。
しかし、一般的なEDRシステムの多くは、初期導入や運用の負担が大きく、都度適切な設定や運用体制が整っていなければ効果を発揮しにくいということも事前に理解しておかなければいけません。
本記事では、EDRの主な機能解説に加えて、従来のセキュリティ対策との違いから、導入によるメリットやデメリットまで徹底的に解説していきます。
この記事を読むだけで、EDRの全体像をまるごと理解できるため、サイバーセキュリティ対策に課題を感じている企業担当者にとっては必見の内容です!
EDRとは?
EDR(Endpoint Detection and Response)とは、エンドポイント(PCやサーバー)へのサイバー攻撃を検知し、迅速に対応するためのセキュリティ対策手法のことです。
近年、サイバー攻撃の巧妙化によって従来のウイルス対策では、防御できない脅威が増加しており、このような状況に対応するのがEDRシステムと呼ばれるものです。
EDRは、リアルタイムで監視する機能や高度な解析機能を備えているため、エンドポイントにおける不審な活動を早期に発見および対応することを目的としています。
具体的な活用事例としては、未知のマルウェアを検出できることで、感染拡大を防ぐための対策や内部不正による情報漏えいの兆候を早期に発見することができます。
EDRが注目されるようになった理由
- サイバー攻撃の手段が高度化した
- ゼロトラストの考え方が普及した
- インシデントの重要性が高まった
サイバー攻撃の手段が高度化した
EDRが注目されるようになった理由の1つ目としては「サイバー攻撃の手段が高度化した」というものが挙げられます。
特に、近年のサイバー攻撃は単純なウイルス感染だけではなく、ランサムウェアの登場や標的型攻撃など、より巧妙かつ複雑な攻撃手法が増加してきています。
従来のアンチウイルスソフトでは防御できない攻撃が増加するなか、EDRはエンドポイント上の不審な挙動を検知し、迅速な対応を可能にするため、多くの企業で導入が進んでいます。
ゼロトラストの考え方が普及した
EDRが注目されるようになった理由の2つ目としては「ゼロトラストの考え方が普及した」というものが挙げられます。
ゼロトラストとは「すべてのアクセスを信用しない」という前提のもと、ネットワークの内外を問わず、常に監視・検証するセキュリティモデルのことです。
リモートワークの普及にともない、従来のセキュリティ対策では、内部端末からの脅威を防ぐことが難しくなっているため、エンドポイント単位での監視と対応が重要になっています。
インシデントの重要性が高まった
EDRが注目されるようになった理由の3つ目としては「インシデントの重要性が高まった」というものが挙げられます。
サイバー攻撃が発生した際に迅速な原因分析と対応が求められる中、EDRは攻撃の痕跡を詳細にログとして記録するため、適切なインシデント対応を支援します。
従来のセキュリティ対策では、攻撃の痕跡を見つけるのが困難でしたが、EDRを導入することで不正アクセスの経路や被害範囲を特定しやすくなるため、セキュリティレベル向上につながります。
EDRの主な機能
- リアルタイム監視
- 脅威検知アラート
- インシデント対応
- ログの収集と分析
リアルタイム監視
EDRの主な機能の1つ目としては「リアルタイム監視」が挙げられます。
EDRは、エンドポイントの動作を継続的に監視し、不審なアクティビティを検出することで、サイバー攻撃を未然に防ぎます。不正プロセスや疑わしいファイルの変更など、異常な挙動が確認されると、管理者に即時通知を行います。
脅威検知アラート
EDRの主な機能の2つ目としては「脅威検知アラート」が挙げられます。
EDRは、異常なプロセスの実行や不正アクセスの試行をリアルタイムで解析し、リスクの高い脅威を識別することができます。アラート発生時には、管理者は詳細なログを確認し、必要に応じて防御策を講じることが可能になります。
インシデント対応
EDRの主な機能の3つ目としては「インシデント対応」が挙げられます。
EDRは、マルウェア感染が確認された端末を隔離し、ネットワークから遮断することで、被害の拡大を防ぐことができます。感染の経路や影響の範囲を特定し、必要に応じてシステムの復旧や影響を受けたファイルの修復を実施します。
ログの収集と分析
EDRの主な機能の4つ目としては「ログの収集と分析」が挙げられます
EDRは、ファイルの変更履歴やプロセスの実行状況、ネットワークの接続情報などを詳細に記録します。これにより、セキュリティインシデントが発生したときには、攻撃の経路や影響の範囲を特定し、迅速な対応が可能となります。
EDRと従来のセキュリティ対策(EPPやアンチウィルスソフト)の違い
| EDR | EPPやアンチウイルスソフト | |
|---|---|---|
| 導入目的 | 検知・対応 | 予防・対策 |
| 検出手法 | リアルタイム監視 | シグネチャ検出 |
| 対応範囲 | インシデントの追跡 | ウイルス感染の防止 |
| 適用対象 | 高難度な脅威対策向け | 基本的な防御対策向け |
導入目的の違い
EDRは「検知・対応」を、EPPやアンチウイルスソフトは「予防・対策」を目的として設計されています。
EPP(Endpoint Protection Platform)やアンチウイルスソフトは、既知のマルウェアやウイルスをブロックすることを重視したセキュリティ対策です。
一方、EDRはエンドポイント上の挙動を継続的に監視し、不審な動きを検知・分析する機能を持ちます。ゼロデイ攻撃や標的型攻撃に対応するため、インシデント発生後の対応や根本原因の特定が可能となります。
検出手法の違い
EDRは「リアルタイム監視」が、EPPやアンチウィルスソフトは「シグネチャ検出」が主な検出の手法です。
EPPやアンチウイルスソフトは、既知のマルウェアをシグネチャと呼ばれる特定のパターンと照合し、検出・ブロックする仕組みで動作しています。
一方、EDRはエンドポイント上の挙動をリアルタイムで監視し、通常とは異なる異常な動作をAIや機械学習で分析します。そのため、未知の脅威やゼロデイ攻撃への対応が可能となり、攻撃の兆候を捉えることができます。
対応範囲の違い
EDRは「インシデントの追跡」が、EPPやアンチウィルスソフトは「ウイルス感染の防止」が主な役割です。
EPPやアンチウィルスソフトは、マルウェアやウイルスの侵入を防ぐことに特化しており、検出後の詳細な分析や対応には限界があります。
一方、EDRは攻撃を受けた後の調査や対応を重視し、感染経路や影響範囲を追跡できる機能を備えています。また、エンドポイントで発生した不審な挙動の記録を蓄積し、管理者が迅速に対応できるように支援します。
適用対象の違い
EDRは「高度な脅威対策」向け、EPPやアンチウィルスソフトは「基本的な防御」向けという違いがあります。
EPPやアンチウィルスソフトは、企業のセキュリティ対策の第一段階として広く導入され、ウイルスやマルウェアの侵入を防ぐことができます。
一方、EDRは標的型攻撃やゼロデイ攻撃への対応が求められる企業に向けた高度なセキュリティシステムです。導入には、リアルタイム監視やインシデント対応の体制が必要となるため、専門チームの運用が推奨されます。
EDRの導入メリット
- 高度な脅威を検知できる
- 影響の範囲を特定できる
- 詳細なログ分析ができる
高度な脅威を検知できる
EDRのメリットの1つ目としては「高度な脅威を検知できる」という点が挙げられます。
AIや機械学習を活用し、ゼロデイ攻撃や標的型攻撃をリアルタイムで検出できる点が強みです。シグネチャベースでは防げない未知の脅威にも対応し、企業のセキュリティ対策を強化できます。
影響の範囲を特定できる
EDRのメリットの2つ目としては「影響の範囲を特定できる」という点が挙げられます。
端末の動作履歴を詳細に記録し、攻撃の発生源や被害の広がりをリアルタイムで可視化できます。自動隔離機能を活用することで、被害を最小限に抑え、迅速なインシデント対応が可能です。
詳細なログ分析ができる
EDRのメリットの3つ目としては「詳細なログ分析ができる」という点が挙げられます。
攻撃の発生時に収集したログを基に、侵入経路や影響範囲を特定し、原因を分析できます。過去の攻撃データを活用し、将来的な攻撃への対策強化やセキュリティポリシーの改善に役立ちます。
EDRの導入デメリット
- 導入や運用のコストが発生する
- 誤検知が発生する可能性がある
- 監視体制を構築する必要がある
導入や運用のコストが発生する
EDRのデメリットの1つ目としては「導入や運用のコストが発生する」という点が挙げられます。
EDRは高度な監視機能を備えているため、初期導入費用やライセンス費用が比較的高額になる場合があります。解決策としては、クラウド型EDRを選択する、MDRサービスを活用するなど、コストを抑える方法があります。
誤検知が発生する可能性がある
EDRのデメリットの2つ目としては「誤検知が発生する可能性がある」という点が挙げられます。
端末の動作を詳細に監視するため、正常な業務プロセスも脅威と誤判断し、過剰なアラートが発生することがあります。解決策としては、ルールの最適化やAIによるアラート精度向上を行い、業務への影響を最小限に抑えることが重要です。
監視体制を構築する必要がある
EDRのデメリットの3つ目としては「監視体制を構築する必要がある」という点が挙げられます。
攻撃を検知しても、適切に分析し、即座に対応できる体制がなければ被害拡大を防ぐのが困難になります。解決策としては、SOCサービスの利用や社内のセキュリティチームの強化を図り、適切な運用体制を整えることが求められます。
EDRの選び方と比較のポイント
- ①:導入費用や運用コストで選ぶ
- ②:検知精度や対応範囲で選ぶ
- ③:使い勝手や運用負荷で選ぶ
➀:コストと導入費用で選ぶ
EDRの選び方の1つ目としては「導入費用や運用コストで選ぶ」という方法が挙げられます。
クラウド型EDRは、初期費用が安く、月額料金で利用できるため、コスト管理がしやすいのが特徴となっているため、主に中小企業への導入に適しています。
一方、オンプレミス型のEDRは、初期投資が高いものの、長期的な運用ではコスト削減が可能です。特に大企業では、独自のセキュリティポリシーを適用しやすく、安定した運用が期待できます。
➁:検知精度と対応範囲で選ぶ
EDRの選び方の2つ目としては「検知精度や対応範囲で選ぶ」という方法が挙げられます。
EDRの最大の特徴は、リアルタイムで脅威を検知し、即時に対応できるところにあります。そのため、機械学習を活用した高度な検知機能を持つ製品がおすすめです。
また、EDRにはエンドポイント単体で対応するタイプと、SIEM(Security Information and Event Management)と連携するタイプがあります。特に、ゼロデイ攻撃や標的型攻撃への対応を求める場合は、AI分析機能を備えたEDRが有効です。
③:使い勝手や運用負荷で選ぶ
EDRの選び方の3つ目としては「使い勝手や運用負荷で選ぶ」という方法が挙げられます。
EDRは、管理画面の使い勝手や管理運用のしやすさなどが導入の決め手となることも多く、インシデントを検知した後のスピーディな対応が重要となってきます。
また、SOC(Security Operations Center)との連携が容易なEDRを選ぶことで、運用負担をさらに軽減できます。セキュリティチームのリソースが限られている場合は、マネージドEDR(MDR)を活用する方法も選択肢の一つです。
まとめ
本記事では、EDRの主な機能解説に加えて、従来のセキュリティ対策との違いから、導入によるメリットやデメリットまで徹底的に解説していきました。
EDRは、ますます高度化を見せるサイバー攻撃に対しての有効な対応策として、今後はAIや自動化技術の進化により、検知精度や対応速度が向上すると期待されています。
今後も ITreview では、EDRのレビュー収集に加えて、新しいEDRサービスも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 EDRとは?主な機能や導入メリット・選び方までわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 BPaaSとは?導入のメリットからBPOやSaaSとの違いまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>「BPaaSとBPOやSaaSとの違いを知りたい」
BPaaSとは、業務プロセスをクラウドサービスとして提供するビジネスモデルのことで、企業が自社で業務システムを構築する従来までの方法とは異なり、外部のクラウドサービスを利用して業務効率化を実現できるのが特徴です。
BPaaSの導入によって、外部のクラウドサービスを経由して業務の委託を行うことができるため、生産性の向上とコストの削減を両立できることから、近ごろでは幅広い企業で導入が進んでいます。
しかし、BPaaSとは一口に言っても、IaaSやPaaSなどの似たような言葉が乱立しているうえ、そのビジネス領域は多岐に渡るため、いまいちピンと来ないという方も多いのではないでしょうか?
本記事では、BPaaSの概要解説に加えて、BPOやSaaSをはじめとする似た言葉との違いから、導入によるメリットやデメリットまで、まとめて徹底的に解説していきます!
AI記事要約*
- BPaaSとは?:BPOとSaaSを掛け合わせた業務プロセスを提供するクラウドサービス。
- 普及背景:労働力の不足やDXの推進、クラウド技術の進化により急速に拡大している。
- 市場規模:2032年には日本市場で約96億ドル、世界市場で約1,017億ドルに達する見込み。
- 活用事例:主に経理や人事、総務部門などのバックオフィス分野で幅広く活用されている。
※ ChatGPTを使用して記事の内容を要約しています。
BPaaSとは?
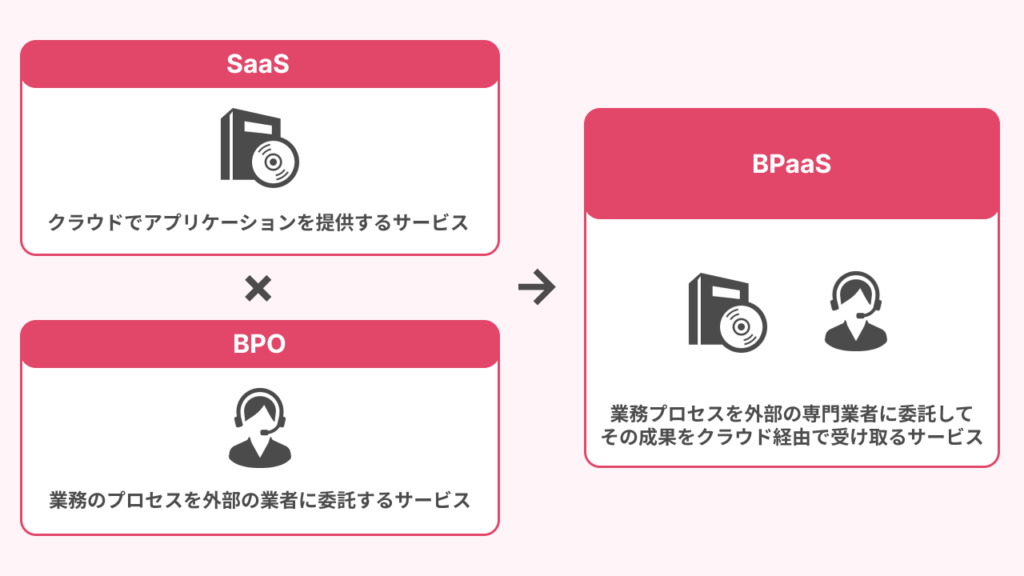
BPaaSの意味と読み方
BPaaS(Business Process as a Service)とは、業務の一部もしくはプロセス全体を外部の会社へ委託するBPO(Business Process Outsourcing)と、クラウドサービスで成果を受け取るSaaS(Software as a Service)を掛け合せた新しいアウトソーシングサービスです。読み方は「ビーパース」と発音し、2009年に米コンサルティング企業のガートナー社によって提案されました。
BPaaSの具体的な活用事例としては、クラウド型の会計ソフトや、アウトソーシングによる給与計算サービスなどが挙げられ、主に会計や給与計算、人事や顧客管理などのバックオフィス部門で活用されています。これらのサービスを活用することで、コスト削減と業務効率化を同時に実現できるでしょう。
BPaaSが解決できる課題
BPaaSは、企業が抱える業務効率の低下や、コストの増大といった諸々の課題を解決することができます。クラウドサービスとして業務プロセスを提供するビジネスモデルであるため、自社でシステムを保有・管理する必要がなく、初期導入の費用や運用コストを削減できるのが大きな魅力の一つです。
また、スケーラビリティにも優れており、業務量の増減に対しても柔軟に対応することができます。例えば、繁忙期には処理業務を拡張し、閑散期にはリソースを縮小することで、コストの最適化を図ることが可能です。生産性向上とコスト削減の両立こそ、BPaaSの最大のメリットといえるでしょう。
BPaaSと他のサービスとの違い
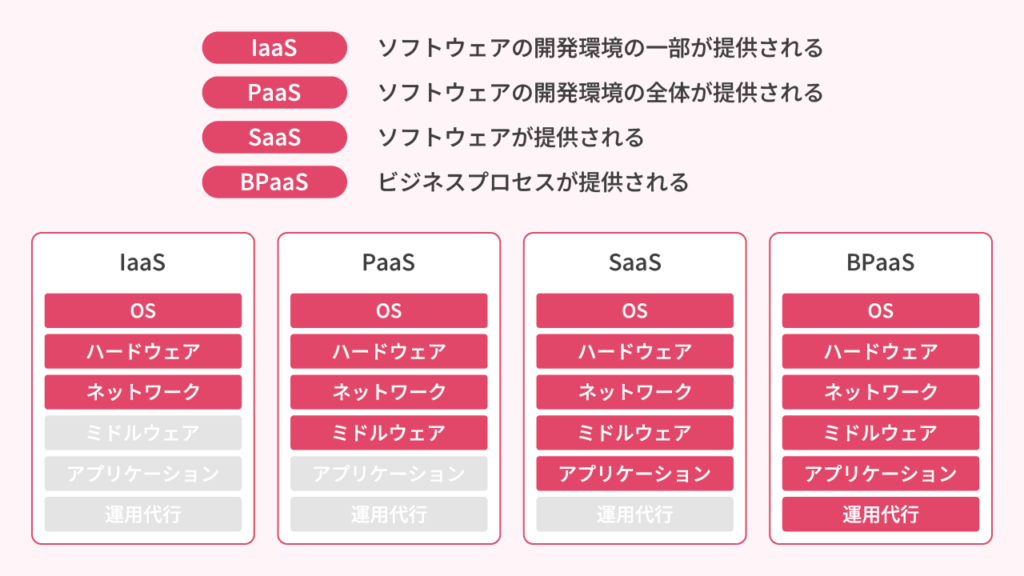
BPaaSとBPOの違い
| 項目 | BPaaS | BPO |
|---|---|---|
| 導入目的 | 業務をプロセスごと外部委託したい | 業務をプロセスごと外部委託したい |
| 提供形態 | クラウドサービス×人的リソース | 人的リソースのみでの業務代行 |
| 運用代行 | 〇 | 〇 |
| コスト効率 | 〇 | △ |
| 柔軟な対応 | △ | 〇 |
| 対象の業務 | 定型業務の代行に最適 | 非定型業務の代行に最適 |
BPaaSとBPO(Business Process Outsourcing)の違いについて、こちらは業務プロセスを外部委託する点では共通していますが、提供方法に違いがあります。BPaaSはクラウドサービスを通じて自動化された業務プロセスを提供するのに対して、BPOは人的リソースを活用して業務を代行するビジネスモデルです。
BPaaSはクラウドサービスによるコスト効率の高さがメリットとなるのに対して、BPOは人的リソースの消費による柔軟な個別対応がメリットとなるため、両者の性質は異なります。
例えば、定型業務の効率化にはBPaaSが適していますが、個別対応やカスタマイズが必要な業務ではBPOが適しているため、こちらは業務の性質に応じて、両者のサービスを使い分けることが重要です。
BPaaSとIaaSの違い
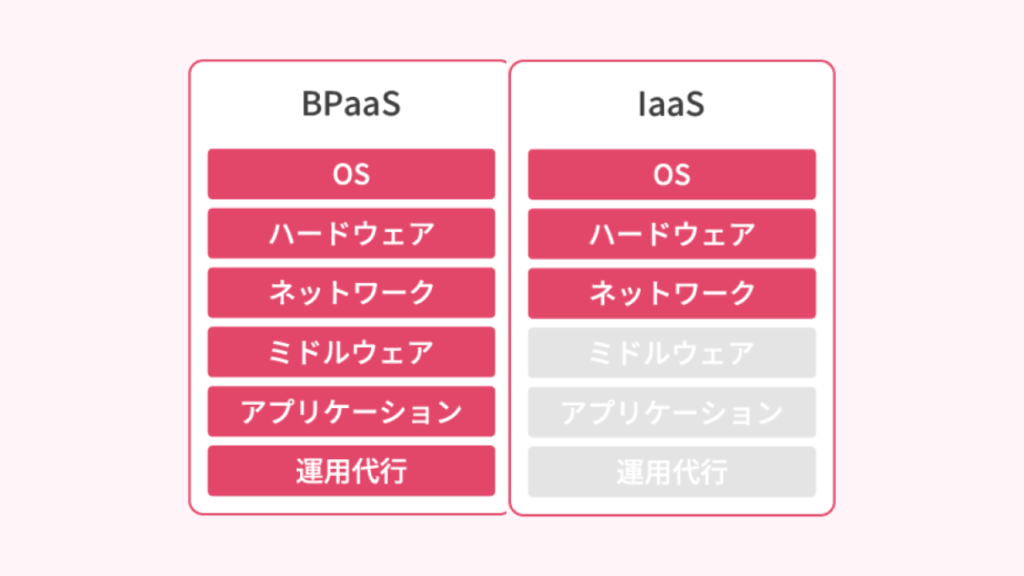
| 項目 | BPaaS | IaaS |
|---|---|---|
| 提供範囲 | ビジネスプロセス全体を提供 | 開発環境のみを提供 |
| 導入目的 | 業務プロセスそのものを効率化したい場合 | インフラの構築と運用を行いたい場合 |
| 運用代行 | 〇 | × |
BPaaSとIaaS(Infrastructure as a Service)の違いについて、こちらはクラウドサービスとして提供される範囲と目的に違いがあります。BPaaSは業務プロセスをクラウドで提供するサービスであるのに対して、IaaSはサーバーやストレージなどのITインフラや開発環境をクラウドで提供するビジネスモデルです。
業務プロセスそのものを効率化したい場合はBPaaSが適していますが、インフラ環境の構築や運用を柔軟に行いたい場合はIaaSが適しているため、こちらは目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。
BPaaSとPaaSの違い
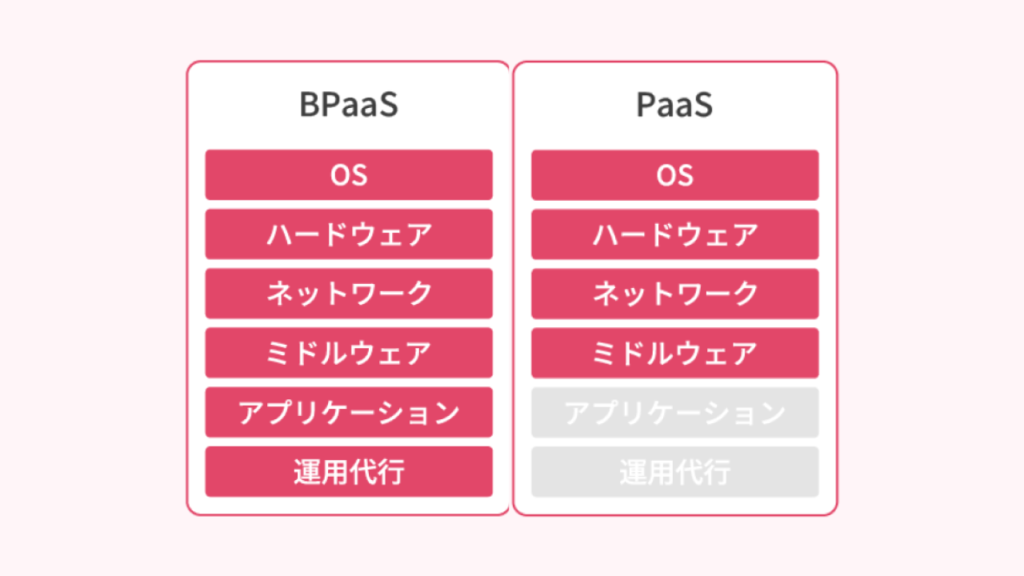
| 項目 | BPaaS | PaaS |
|---|---|---|
| 提供範囲 | ビジネスプロセス全体を提供 | 開発基盤のみを提供 |
| 導入目的 | 業務プロセスそのものを効率化したい場合 | 業務の効率化と自動化を図りたい場合 |
| 運用代行 | 〇 | × |
BPaaSとPaaS(Platform as a Service)の違いについて、こちらもクラウドサービスとして提供される範囲と目的に違いがあります。BPaaSは業務プロセスをクラウドで提供するサービスであるのに対して、PaaSはアプリケーションを開発するためのプラットフォームをクラウド上で提供するビジネスモデルです。
業務プロセスそのものを効率化したい場合はBPaaSが適していますが、アプリケーションなどの開発環境を整えたい場合はPaaSが適しているため、こちらも目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。
BPaaSとSaaSの違い
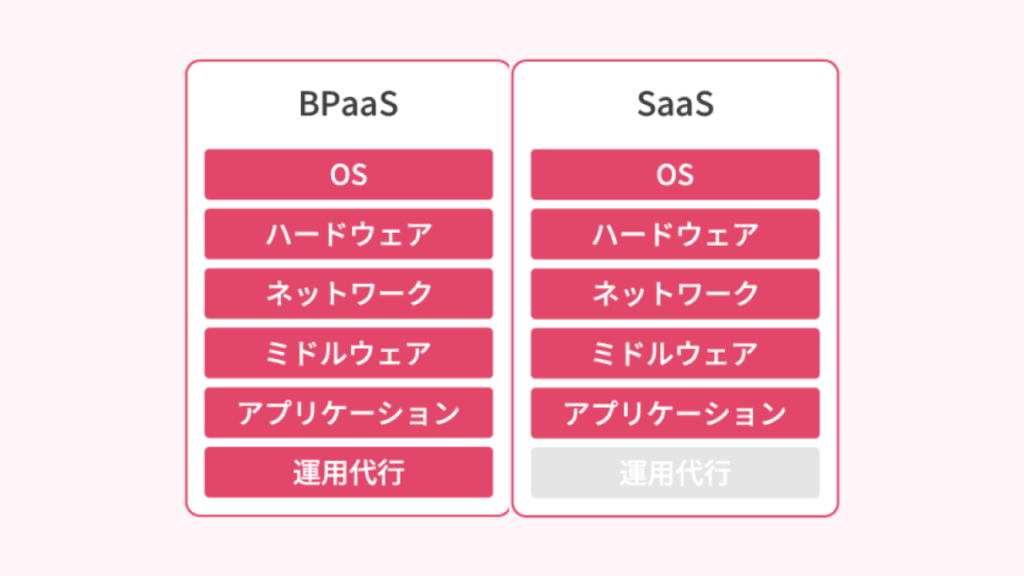
| 項目 | BPaaS | SaaS |
|---|---|---|
| 提供範囲 | ビジネスプロセス全体を提供 | アプリケーションのみを提供 |
| 導入目的 | 業務プロセスそのものを効率化したい場合 | 特定の業務を安価に効率化したい場合 |
| 運用代行 | 〇 | × |
BPaaSとSaaS(Software as a Service)の違いについて、こちらもクラウドサービスとして提供される範囲と目的に違いがあります。BPaaSは業務プロセスをクラウドで提供するサービスであるのに対して、SaaSは特定のソフトウェアやアプリケーションをクラウドサービスとして提供するビジネスモデルです。
業務プロセスそのものを効率化したい場合はBPaaSが適していますが、特定の業務アプリケーションを利用したい場合はSaaSが適しているため、こちらも目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。
BPaaSが注目されている背景
- 労働力不足と業務効率化のニーズの高まり
- デジタルトランスフォーメーションの推進
- クラウド技術とAI進化による利便性の向上
労働力不足と業務効率化のニーズの高まり
BPaaSが注目されている背景の1つ目としては「労働力不足と業務効率化のニーズの高まり」というものが挙げられます。
日本をはじめとする先進国では、少子高齢化による労働人口の減少が深刻化しており、企業は限られた人材で生産性を向上させることが求められています。
BPaaSは、業務プロセスをクラウド上で提供し、自動化や効率化を実現するため、人手不足の解消と業務効率の向上に大きく貢献するサービスとして期待されています。
デジタルトランスフォーメーションの推進
BPaaSが注目されている背景の2つ目としては「デジタルトランスフォーメーションの推進」というものが挙げられます。
昨今、政府主導のもと、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進しており、クラウドベースのサービスへの移行が急速に進んでいます。
BPaaSは、業務プロセスそのものをデジタルで提供するため、これまでアナログだった経理部門や人事業務の自動化を実現し、企業のDX推進を強力にサポートしています。
クラウド技術とAI進化による利便性の向上
BPaaSが注目されている背景の3つ目としては「クラウド技術とAI進化による利便性の向上」というものが挙げられます。
近年、クラウド技術やAI(人工知能)の進化によって、より柔軟でスケーラブルなBPaaSサービスの提供が可能となり、コスト削減と業務の高度化が進んでいます。
例えば、AIを活用したBPaaSは、顧客データの分析や業務の最適化などといった時間のかかる作業を自動化するため、企業はより戦略的な意思決定を行えるようになります。
BPaaSの市場規模
- 日本のBPaaSの市場規模:2032年には95億9,000万米ドルに到達する見込み
- 世界のBPaaSの市場規模:2032年には1,016億5,000万米ドルに到達する見込み
日本のBPaaSの市場規模
日本におけるBPaaSの市場規模は、2024年に約31億9,000万米ドルで、年平均成長率(CAGR)は14.8%で成長し、2032年には95億9,000万米ドルに達すると予測されています。
▶ 参照:2030年までの日本のビジネスプロセスサービス(Bpaas)市場のサイズと成長
世界のBPaaSの市場規模
世界におけるBPaaSの市場規模は、2024年に約650億3,000万米ドルで、年平均成長率(CAGR)は7.64%で成長し、2032年には1,016億5,000万米ドルに達すると予測されています。
▶ 参照:BPaaS(Business Process-as-a-Service)市場規模 分析 予測 2025-2030年【市場調査レポート】
BPaaSの活用事例
- 金融業界における業務プロセスの自動化
- 小売業界における販売プロセスの効率化
- 製造業界におけるサプライチェーンの最適化
金融業界におけるBPaaSの活用事例
BPaaSの活用事例の1つ目としては「金融業界における業務プロセスの自動化」というものが挙げられます。
金融業界では、口座開設やローン審査など多くの定型業務が存在しており、BPaaSサービスを活用することで既存の定型業務の効率化が進んでいます。
例えば、AIを活用したBPaaSでは、顧客データの自動収集や審査プロセスの迅速な処理などが実現でき、サービスの提供スピードの向上とコスト削減が可能になります。
小売業界におけるBPaaSの活用事例
BPaaSの活用事例の2つ目としては「小売業界における販売プロセスの効率化」というものが挙げられます。
小売業界では、オンラインとオフラインの販売統合が進むなか、BPaaSサービスを活用することで顧客情報の管理や注文処理の自動化が進んでいます。
例えば、AIチャットボットによる問い合わせ対応や、オンライン注文と在庫管理の自動連携によって、顧客満足度の向上と従業員の業務負荷の軽減が実現されています。
製造業界におけるBPaaSの活用事例
BPaaSの活用事例の3つ目としては「製造業界におけるサプライチェーンの最適化」というものが挙げられます。
製造業界では、調達から出荷まで多くの業務が複雑に絡み合っていますが、BPaaSを活用することで在庫管理や発注プロセスの一元化が進んでいます。
例えば、リアルタイムな在庫把握やAIによる需要予測により、過剰在庫や欠品リスクを最小限に抑え、これまでよりも生産性の高い生産体制の構築が実現されています。
BPaaSサービスの提供企業一覧
| 企業名 | 製品名 | 対象領域 |
|---|---|---|
| フリー株式会社 | freee人事労務アウトソース | バックオフィス |
| 株式会社うるる | うるるBPO | バックオフィス |
| 株式会社kubellパートナー | Chatwork アシスタント | バックオフィス |
| 株式会社シャノン | マーケティング運用代行パッケージ | マーケティング |
| 株式会社Migakun | Migakun | バックオフィス |
| トヨクモクラウドコネクト株式会社 | トヨクモクラウドコネクト | バックオフィス |
| バレットグループ株式会社 | KURAGE | マーケティング |
| BizteX株式会社 | BizteX BPaaS | バックオフィス |
| 株式会社リアルテック・コンサルティング | リアルテック・コンサルティング | バーティカル |
| AnyMind Group株式会社 | AnyMind | マーケティング |
経理や人事、総務などのバックオフィス部門をはじめとして、幅広い領域で導入が進んでいるBPaaSサービスの数々ですが、では一体どのようなサービスが導入されているのでしょうか?ここからは、ITreviewで掲載しているBPaaSサービス提供企業を数社ピックアップして紹介していきます。
フリー株式会社 | freee人事労務アウトソース

フリー株式会社が提供する『freee人事労務アウトソース』は、給与計算や入退社の手続き、年末調整などの人事労務業務をクラウドから一括して代行するBPaaSサービスです。
データがクラウドに蓄積されるため、内製化へのスムーズな移行が可能であり、労務知識が豊富なスタッフによる迅速な対応で、人的ミスの削減と業務効率化を実現します。
株式会社うるる | うるるBPO

株式会社うるるが提供する『うるるBPO』は、データ入力やリサーチ、コールセンター業務など、多岐にわたるバックオフィス業務を一括して代行するBPaaSサービスです。
多様なバックオフィス業務を一括してアウトソーシングすることができ、各分野の専門スタッフが業務を担当するため、業務品質の向上と業務効率の改善を実現します。
株式会社kubellパートナー | Chatwork アシスタント

株式会社kubellパートナーが提供する『Chatwork アシスタント』は、ビジネスチャットツールの「Chatwork」を活用した、オンライン秘書BPaaSサービスです。
Chatworkを活用した迅速なコミュニケーションが魅力で、日常的な事務作業を代行することもできるため、業務のスピードアップやコア業務への集中を実現します。
株式会社シャノン | マーケティング運用代行パッケージ

株式会社シャノンが提供する『マーケティング運用代行パッケージ』は、専門のマーケティング人材が企業にとって最適な戦略や施策を提案するBPaaSサービスです。
マーケティングや営業DXに特化したプロが適切な戦略を提供することはもちろん、必要なコンテンツやメールの作成も代行できるため、より高度な施策を展開できます。
株式会社Migakun | Migakun

株式会社Migakunが提供する『Migakun』は、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するための、コンサルティングに特化したBPaaSサービスです。
それぞれの企業の課題やニーズに合わせたカスタマイズ提案が可能で、最新のデジタル技術と戦略を駆使することによって、企業のDX移行を力強くサポートします。
BPaaSの導入メリット
- 業務の効率化が実現できる
- コストの削減が実現できる
- スケーラビリティが向上する
業務の効率化が実現できる
BPaaSの導入メリットの1つ目としては「業務の効率化が実現できる」というものが挙げられます。
BPaaSを導入することによって、標準化された業務プロセスをクラウド経由で簡単かつ素早く利用できるようになります。業務フローの自動化により、人為的なミスの削減や業務の迅速化が期待できます。
例えば、請求書の発行や給与計算などの定型業務をBPaaSに委託することで、従業員は重要なコア業務に専念できるようになります。業務の効率向上と生産性向上を実現できる手段として効果的です。
コストの削減が実現できる
BPaaSの導入メリットの2つ目としては「コストの削減が実現できる」というものが挙げられます。
BPaaSはクラウドサービスとして提供されるため、自社でシステム開発やサーバーの構築を行う必要がないのが特徴です。初期投資を抑えられるだけではなく、保守や運用コストの削減にもつながります。
例えば、オンプレミス型のシステムを維持する場合と比べて、BPaaSでは不要なハードウェアコストや人件費を削減することができます。コストの最適化とリソースの有効活用を両立できる選択肢です。
スケーラビリティが向上する
BPaaSの導入メリットの3つ目としては「スケーラビリティが向上する」というものが挙げられます。
BPaaSはクラウドベースのサービスであるため、企業の成長や業務規模の拡大に応じた柔軟なスケールアップが可能です。都度必要に応じてサービスの追加や削減をスピーディに実施することができます。
例えば、繁忙期には業務量の増加に合わせてリソースを拡張し、閑散期にはコストを抑えるような調整を都度柔軟に行うことができます。事業の変化に即応できる柔軟性を持つサービスとして有用です。
BPaaSの導入デメリット
- セキュリティのリスクが発生する
- 柔軟なカスタマイズには限界がある
- ベンダーロックインのリスクがある
セキュリティのリスクが発生する
BPaaSの導入デメリットの1つ目としては「セキュリティのリスクが発生する」というものが挙げられます。
BPaaSは、クラウド上で業務プロセスを管理するため、外部からの不正アクセスや情報漏洩のリスクが懸念されます。特に、顧客情報や財務データなどの機密情報を扱う場合は慎重な対応が求められます。
この問題への対策としては、信頼性の高い堅牢なセキュリティ対策機能を提供しているBPaaSプロバイダーを選定することが重要です。また、アクセス制御やデータ暗号化の実施、定期的なセキュリティの監査を行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。
柔軟なカスタマイズには限界がある
BPaaSの導入デメリットの2つ目としては「柔軟なカスタマイズには限界がある」というものが挙げられます。
BPaaSは、標準化された業務プロセスを提供するため、細かな業務フローや特殊要件に対応することは難しい場合があります。特に、非定型的な業務には適していないことも多いため、注意が必要です。
この問題への対策としては、導入以前に自社の業務要件とBPaaSの機能を綿密に比較し、必要なカスタマイズが可能か確認することが重要です。また、柔軟な設定変更が可能なBPaaSプロバイダーを選定することで、ある程度のカスタマイズにも対応することができます。
ベンダーロックインのリスクがある
BPaaSの導入デメリットの3つ目としては「ベンダーロックインのリスクがある」というものが挙げられます。
BPaaSは、特定のプロバイダーに依存してしまうと、将来的に他社のサービスへの乗り換えが困難になる場合があります。特に、独自のプロセスが採用されている場合には、移行のコストが高くなります。
この問題への対策としては、データのポータビリティが確保されているか確認し、移行可能なフォーマットでデータ管理を行うことが重要です。また、契約内容に解約時のデータ取り扱いについて明記されているかを事前に確認しておくことも、リスク回避に役立ちます。
BPaaSの選び方と比較の方法
- ①:自社が抱えている課題を整理する
- ②:必要な機能と選定基準を定義する
- ③:定義した機能から製品を絞り込む
- ④:レビューや事例を参考に製品を選ぶ
- ⑤:無料トライアルで使用感を確認する
①:自社が抱えている課題を整理する
BPaaSの選び方の1つ目のステップとしては「自社が抱えている課題を整理する」というものが挙げられます。
BPaaSは業務プロセスの効率化を目的としたサービスであり、自社のどの業務領域に課題があるのかを把握することが選定の第一歩です。例えば、経理業務の自動化、顧客対応の迅速化、または人事管理の効率化など、解決したい業務課題を明確にすることで、必要な機能や選定の基準が明確になります。
②:必要な機能と選定基準を定義する
BPaaSの選び方の2つ目のステップとしては「必要な機能と選定基準を定義する」というものが挙げられます。
自社の抱えている解決したい課題を整理した後は、それらの課題を解決するために必要な機能や具体的な要件を洗い出すことが重要です。例えば、データ分析機能やレポーティング機能の有無、API連携やユーザーインターフェースの使い勝手など、業務に直結する機能に注目してみると良いでしょう。
③:定義した機能から製品を絞り込む
BPaaSの選び方の3つ目のステップとしては「定義した機能から製品を絞り込む」というものが挙げられます。
サービスの選定基準と必要な機能を明確にした後は、それらの条件にマッチする製品をリストアップして比較検討することが重要です。各製品のホームページから機能を確認することはもちろん、ウェブ上に情報がないことも多いため、その場合は直接ベンダーへ問い合わせてみるのも良いでしょう。
④:レビューや事例を参考に製品を選ぶ
BPaaSの選び方の4つ目のステップとしては「レビューや事例を参考に製品を選ぶ」というものが挙げられます。
定義した機能から候補となる製品を絞り込んだ後は、それらのサービスのユーザーレビューや導入の事例を確認することが重要です。特に、自社と同業種・同規模の企業のレビューや事例は大きな判断材料となるため、どのような課題を解決できたのか、導入による効果などを把握することが大切です。
⑤:無料トライアルで使用感を確認する
BPaaSの選び方の5つ目のステップとしては「無料トライアルで使用感を確認する」というものが挙げられます。
BPaaS製品の多くは無料トライアルが提供されています。無料トライアルを活用することで操作性や機能性を事前に確認することが可能です。カタログスペックだけでは分からない各製品の特徴や使い勝手の違いなども、実際に使って試すことができるため、複数の製品を比較してみるのが良いでしょう。
【BPaaSサービス事業者様向け】自社のサービスを掲載しませんか?
本記事で紹介したような「BPaaSサービスを展開されている事業者」の皆さまへ、当サイトの『ITreview』に自社のサービスを掲載しませんか?
ITreviewには毎月多くのサービス検討者が来訪しており、製品レビューを閲覧することで、自社に適切な製品・サービスの比較検討に役立てています。
レビューや満足度を活用した自社サイトのPRも可能です。まずは下記リンクより無料掲載申請へお進みください。詳細はお気軽にお問い合わせください。
まとめ
本記事では、BPaaSの概要解説に加えて、BPOやSaaSをはじめとする似た言葉との違いから、導入によるメリットやデメリットまで、徹底的に解説していきました。
世界的にも急速な拡大を続けているBPaaS市場ですが、昨今ではAIやクラウドをはじめとする技術革新の背景もあり、今後もさらなる市場の拡大と発展が予測されています。
今後もITreviewでは、BPaaSサービスのレビュー収集に加えて、新しいBPaaSサービスも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 BPaaSとは?導入のメリットからBPOやSaaSとの違いまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【図解】VPNの4種類の違いをわかりやすく解説!自社に最適なサービスはどれ? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>「VPNの種類や接続方式ごとの違いを知りたい」
VPN接続サービスは、情報セキュリティの保護には重要なサービスです。とくに、リモートワークを推進している企業においては必須のサービスといえます。
しかし、一口にVPNとは言っても、接続方式や利用回線には多くの種類が存在するため、どのVPNを選ぶべきか判断に迷ってしまうことも少なくありません。
本記事では、VPNの代表的な4種類を解説しながら、それぞれがどのような企業に適しているのか、コストや通信品質の観点から徹底的に比較していきます。
▶ 関連記事:VPN接続とは?仕組みや種類からメリット・デメリットまでわかりやすく解説!
VPN接続とは?

VPN接続とは、英語の「Virtual Private Network」の略称であり、日本語では「仮想専用線」を意味する通信を安全に行うための手法のことです。
不特定多数のユーザーが利用するインターネットの空間ですが、VPNは名前の通り、送信側と受信側の間に仮想の専用線(トンネル)を設けることで、通信の内容を保護する仕組みとなっています。
また、実際に通信を行う場合には、正規の利用者であることを確認する認証フローがあったり、通信そのものを暗号化するVPNプロトコルがあったりなど、安全な通信を実現することができます。
VPNの種類ごとの違いを比較
| インターネットVPN | エントリーVPN | IP-VPN | 広域イーサネット | |
|---|---|---|---|---|
| 回線 | インターネット | 閉域網 | 閉域網 | 閉域網 |
| コスト | ◎ | 〇 | △ | △ |
| 通信品質 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 安全性 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 拡張性 | 〇 | △ | △ | ◎ |
| 帯域保証 | ベストエフォート | ベストエフォート | ギャランティ | ギャランティ |
| 導入企業 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | 専門企業 |
| 拠点数 | 1~3 | 3~5 | 5~10 | 1 |
| 活用場面 | 導入コストを重視したい | バランスを重視したい | セキュリティを重視したい | 高度なカスタマイズが必要 |
VPNの代表的な種類としては、主に「インターネットVPN」と「エントリーVPN」と「IP-VPN」と「広域イーサネット」の4つの種類に分類されています。
- インターネットVPN
- エントリーVPN
- IP-VPN
- 広域イーサネット
これら4種類のVPNでは、それぞれ構築される仕組みが異なるほか、運用コストや通信品質、セキュリティやカスタマイズの自由度などにも違いがあります。
インターネットVPNの詳細
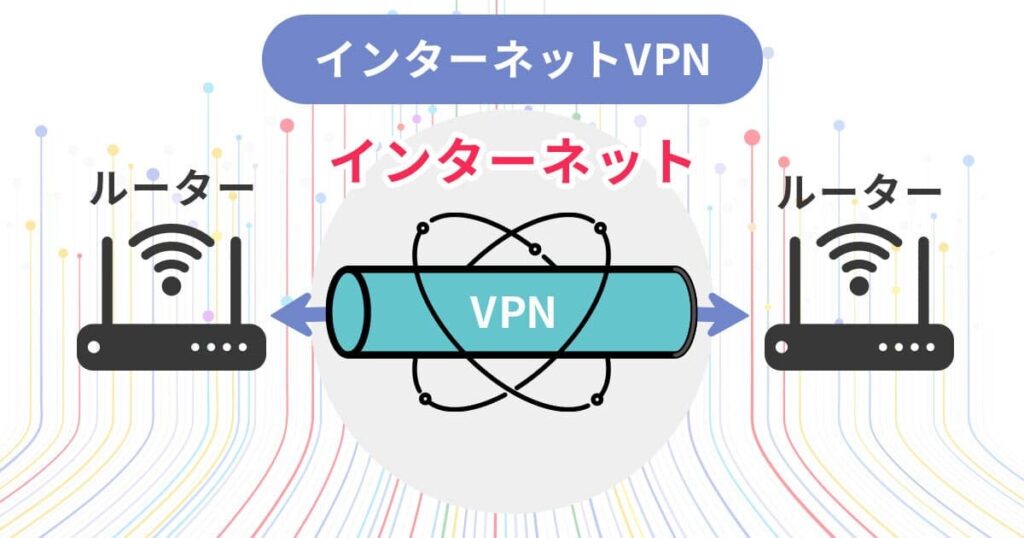
インターネットVPNとは、インターネット上に仮想のネットワーク環境を構築する接続方式です。
構築方法には、通信事業者から機器をレンタルする方法のほか、設定や保守点検を自社で実施できるのであれば、自社で構築することも可能です。
拠点数1~3拠点の小規模オフィス向けで、手軽にVPNサービスを導入したい、低コストでVPN接続サービスを利用したいという場合におすすめです。
インターネットVPNと他のVPNの違い
| | インターネットVPN | エントリーVPN | IP-VPN | 広域イーサネット |
|---|---|---|---|---|
| 回線 | インターネット | 閉域網 | 閉域網 | 閉域網 |
| コスト | ◎ | 〇 | △ | △ |
| 通信品質 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 安全性 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 拡張性 | 〇 | △ | △ | ◎ |
インターネットVPNのメリット
インターネットVPNのメリットとしては「安価に導入することができる」というものが挙げられます。
ルーターや固定IPを準備する必要はありますが、閉域IP網を構築する必要がないため、後述のIP-VPNや広域イーサネットよりも安価な導入が可能です。
また、インターネットを使用する接続方式となっているため、4種類のVPNでは唯一自社で構築することができるというところも大きなメリットの一つです。
インターネットVPNのデメリット
インターネットVPNのデメリットとしては「セキュリティの強度が低い」というものが挙げられます。
専用線を使用する閉域網とは異なり、オープンなネット回線を使用するため、外部からの不正アクセスやデータの盗み見などのセキュリティリスクがあります。
運用にあたっては、カフェなどの公衆無線では利用しないことはもちろん、利用のルールを設けたり、利用者のリテラシーを高めたりなどの対策が必要です。
インターネットVPNの料金相場
インターネットVPNの料金相場は「2万円~5万円程度」です。VPN接続サービスのなかでは、もっとも安価に導入することが可能です。
コストを抑えたい場合の導入シーンに最適であり、VPN対応ルーターと初期設定だけで導入することができるため、保守管理のためのランニングコストが少ないVPN種類です。
エントリーVPNの詳細
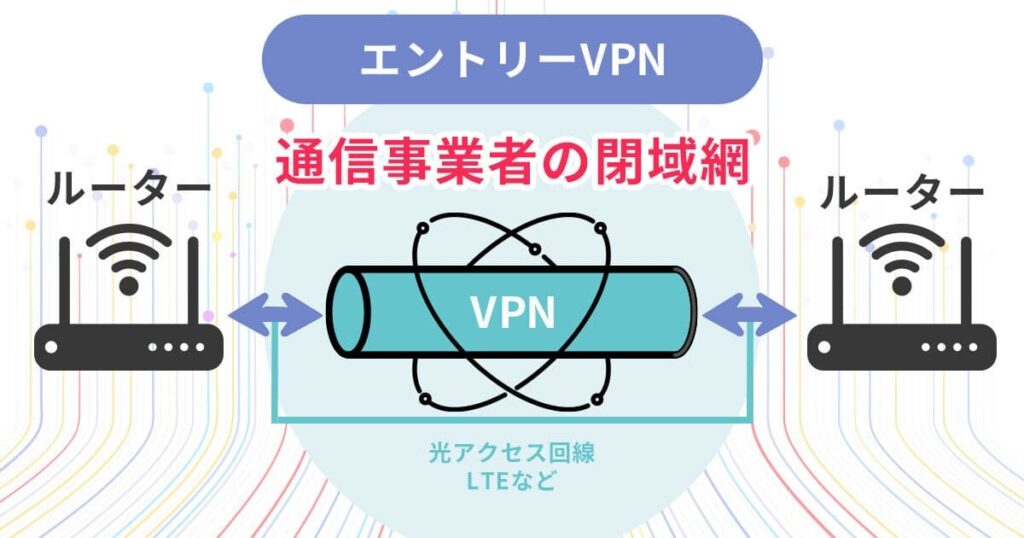
エントリーVPNとは、ADSLなどのインターネット回線を用いて閉域IP網を構築する接続方式です。
通信事業者の設置する閉域網を使用するため、インターネット回線を用いるインターネットVPNよりも、セキュリティの強度や信頼性に優れています。
拠点数3~5拠点の中規模オフィス向けで、バランスに優れたVPNを導入したい、低コストでVPN接続サービスを利用したいという場合におすすめです。
エントリーVPNと他のVPNの違い
| | エントリーVPN | インターネットVPN | IP-VPN | 広域イーサネット |
|---|---|---|---|---|
| 回線 | 閉域網 | インターネット | 閉域網 | 閉域網 |
| コスト | 〇 | ◎ | △ | △ |
| 通信品質 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 安全性 | 〇 | △ | ◎ | ◎ |
| 拡張性 | △ | 〇 | △ | ◎ |
エントリーVPNのメリット
エントリーVPNのメリットとしては「トータルバランスに優れている」というものが挙げられます。
インターネットVPNと同様、インターネット回線を利用する接続方式であるため、大規模な設備投資が不要で、導入のハードルが低いのが特徴です。
設備投資のコストやセキュリティなど、特筆して尖った部分はありませんが、そのぶんトータルでのバランスに優れた接続方式であるといえるでしょう。
エントリーVPNのデメリット
エントリーVPNのデメリットとしては「通信速度が遅くなる場合がある」というものが挙げられます。
使用する回線自体は光ファイバーなどのインターネット回線であるため、トラフィックの混雑状況によっては速度が遅くなる可能性があります。
安定した通信品質やギャランティ型の帯域保障を希望する場合には、より通信の安定したIP-VPNや広域イーサネットを利用するのがおすすめです。
エントリーVPNの料金相場
エントリーVPNの料金相場は「月額1万円~2万円程度」です。この月額費用に加えて、最初に5,000円程度の初期費用が発生することもあります。
インターネットVPNと同様、光ファイバーやADSLなどのインターネット回線を使用するため、VPN接続サービスのなかでは、比較的安価に導入することができるVPN種類です。
IP-VPNの詳細
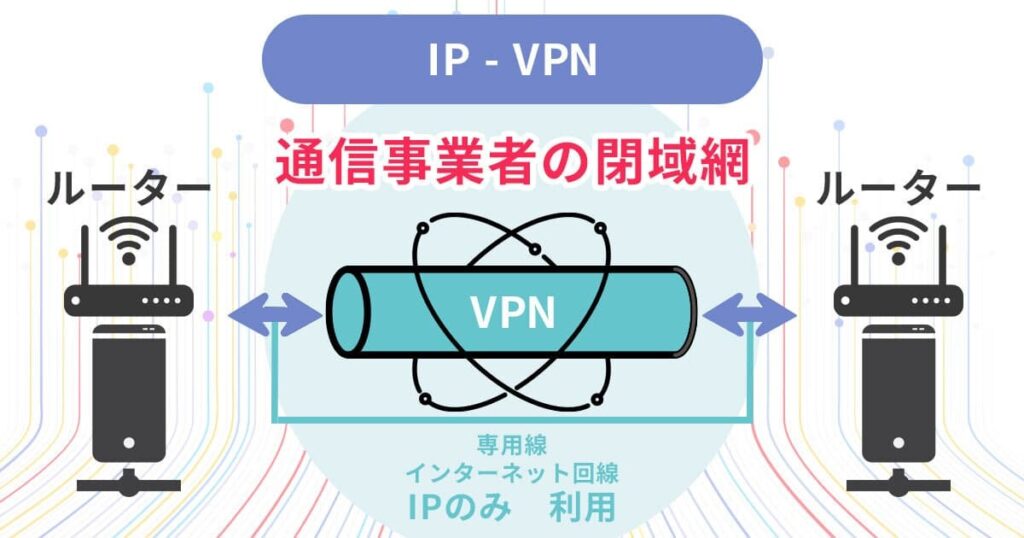
IP-VPNとは、通信事業者の閉域IP網を使用して仮想のネットワークを構築する接続方式です。
インターネットVPNやエントリーVPNとは異なり、閉域網を使用する方式であるため、高いセキュリティ強度で安全に通信することができます。
拠点数5~10拠点の大規模オフィス向けで、VPNのセキュリティを強化したい、複数の拠点間で安定した通信を行いたいという場合におすすめです。
IP-VPNと他のVPNの違い
| | IP-VPN | 広域イーサネット | エントリーVPN | インターネットVPN |
|---|---|---|---|---|
| 回線 | 閉域網 | 閉域網 | 閉域網 | インターネット |
| コスト | △ | △ | 〇 | ◎ |
| 通信品質 | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 安全性 | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
| 拡張性 | △ | ◎ | △ | 〇 |
IP-VPNのメリット
IP-VPNのメリットとしては「セキュリティの強度が高い」というものが挙げられます。
インターネットVPNとは異なり、通信事業者の設置する閉域網を利用するため、より専用線に近いセキュアな環境で通信することが可能です。
また、サービス品質保証(SLA)や遅延保証などの保証サービスが付いているため、大規模ネットワークでも安定した通信を行うことができます。
IP-VPNのデメリット
IP-VPNのデメリットとしては「導入の初期コストが高い」というものが挙げられます。
IP-VPNの導入には、通信事業者との契約が必要となるため、インターネットVPNやエントリーVPNよりもコストが高くなることが一般的です。
ただし、機器の準備から設定、保守点検まで通信事業者に依頼することができるため、拠点数が多く、自社構築が難しい企業にはおすすめできます。
IP-VPNの料金相場
IP-VPNの料金相場は「月額1万円~5万円程度」です。この月額費用に加えて、数千円~数万円の初期費用が発生することもあります。
インターネットVPNやエントリーVPNとは異なり、通信事業者の保有する閉域網を使用する仕組みとなっているため、回線使用料のコストが高くなりやすい傾向にあるVPN種類です。
広域イーサネットの詳細
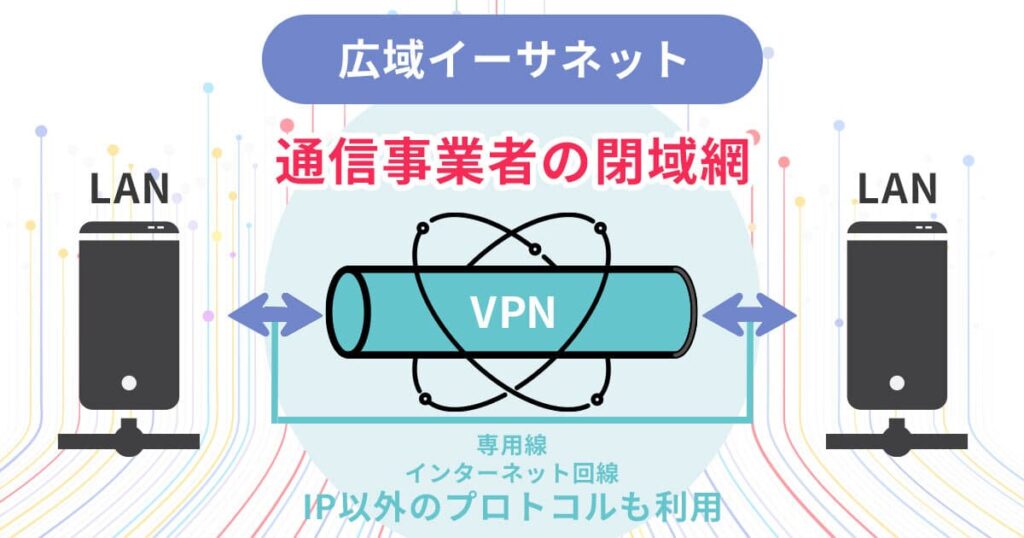
広域イーサネットとは、通信事業者の閉域網を利用して仮想のネットワークを構築する接続方式です。
IP-VPNと構成自体に大きな違いはありませんが、IP-VPNがIPのみの対応であるのに対して、広域イーサネットでは多様なプロトコルに対応しています。
IP以外のプロトコルに対応していることから、より高度なカスタマイズを行いたい、その他のルーティングプロトコルを使用したいという場合におすすめです。
広域イーサネットと他のVPNの違い
| | 広域イーサネット | IP-VPN | エントリーVPN | インターネットVPN |
|---|---|---|---|---|
| 回線 | 閉域網 | 閉域網 | 閉域網 | インターネット |
| コスト | △ | △ | 〇 | ◎ |
| 通信品質 | ◎ | ◎ | △ | △ |
| 安全性 | ◎ | ◎ | 〇 | △ |
| 拡張性 | ◎ | △ | △ | 〇 |
広域イーサネットのメリット
広域イーサネットのメリットとしては「カスタマイズの自由度が高い」というものが挙げられます。
使用できるプロトコルがIPのみに限られるIP-VPNに対して、広域イーサネットでは多様なルーティングプロトコル(RIPやOSPFなど)にも対応しています。
また、ギャランティー型と呼ばれる通信保証があることがほとんどであり、最大1Gbpsもの高速通信で安全なネットワークに接続することが可能です。
広域イーサネットのデメリット
広域イーサネットのデメリットとしては「ネットワークの設定が複雑」というものが挙げられます。
IPに依存しない接続方式であるため、IP以外のネットワークからスムーズな移行が行える一方、最初のネットワーク設定は複雑になってしまいがちです。
導入するための要件定義や保守運用への負担も大きくなりやすいため、基本的には拠点数が限られている企業にのみ適しているといえるでしょう。
広域イーサネットの料金相場
IP-VPNの料金相場は「月額10万円~20万円程度」です。この月額費用に加えて、数千円~数万円の初期費用が発生することもあります。
広域イーサネットは構築の難易度が高く、通信を行いたい拠点間の物理的な距離やエリア、保証する帯域速度などによっても費用は異なるため、料金幅の乱高下が激しいVPN種類です。
VPNプロトコルの種類ごとの違い
| SSL-VPN | IPsec-VPN | L2TP | PPTP | |
|---|---|---|---|---|
| 暗号化の速度 | 普通 | 速い | 普通 | 速い |
| 暗号化の強度 | 高い | 高い | 普通 | 低い |
VPNプロトコルとは、インターネットVPNによる拠点間通信を、より安全で高速なものにするための暗号化技術のことを指します。
VPNプロトコルの種類としては、主に「SSL-VPN」と「IPsec-VPN」と「L2TP」と「PPTP」の4種類が代表的なプロトコルの種類として挙げられます。
先述のVPN自体の種類とは異なり、VPNプロトコルはあくまでもVPNによる通信を暗号化するための技術のことであるため、混同しないよう注意しましょう。
SSL-VPNの詳細
SSL-VPNとは、クレジットカードや口座情報など、個人情報のやり取りに使用されるSSL技術を用いたプロトコルの種類です。
リモートアクセスに適しているうえ、低コストで導入できることから、VPNプロトコルのなかではメジャーなプロトコルといえるでしょう。
IPsec-VPNの詳細
IPsec-VPNとは、コンピュータへデータを送信するためのIPパケットを暗号化するセキュリティレベルの高いプロトコルの種類です。
さまざまなプロトコルのなかでも、安全性の高いプロトコルとなっているため、セキュリティを重視する場合に最適なプロトコルといえます。
L2TPの詳細
L2TPとは、それ単体では暗号化することができず、先述のIPsecと併用することで通信の暗号化ぞ実現するプロトコルの種類です。
ほとんどの場合、VPNに用いられるL2TPは、IPsecと併用して暗号化する「L2TP/IPsec」が一般的であり、単体で使用されることは多くありません。
PPTPの詳細
PPTPとは、IPネットワーク上にある機器同士の接続に、仮想の伝送路を設けることで通信を暗号化するプロトコルの種類です。
L2TPと同様、PPTP自体に暗号化の機能が備わっているわけではなく、他の認証方法と組み合わせて使用することでセキュアな通信を実現します。
VPN接続サービスのおすすめの種類
スクロールして全体を見る→
小規模企業でコストを重視したい
VPN接続サービスの導入にあたって、小規模企業(拠点数1~3拠点)でコスト面を重視したい場合には「インターネットVPN」の導入がおすすめです。
インターネットVPNは、インターネット回線を使用したVPN接続方式であるため、専用線や閉域網を構築する必要がなく、コストを抑えた導入が可能です。
小規模企業に人気のVPNおすすめ製品
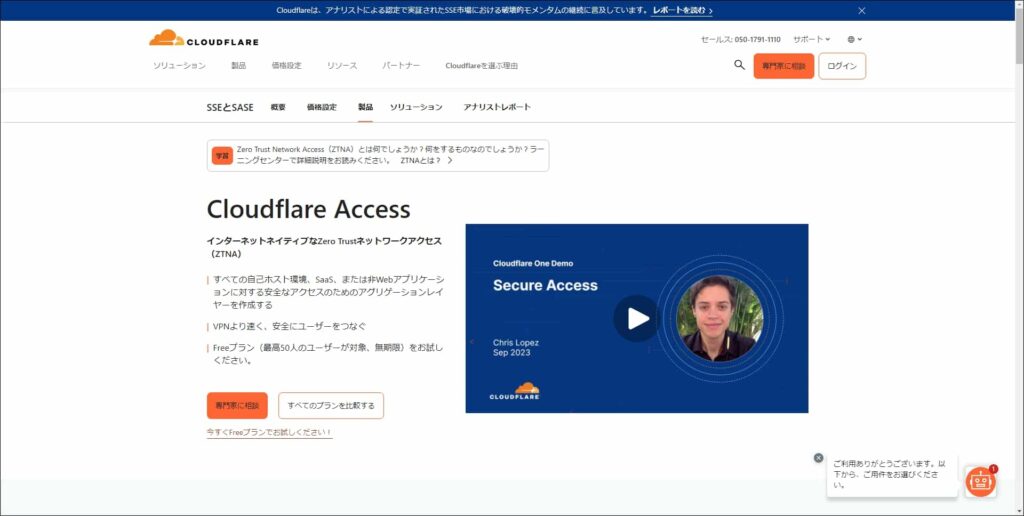
| 製品名 | Cloudflare Access |
| レビュー数 | 16 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.5 |
| 提供会社 | Cloudflare |
| 料金価格 | 調査中 |

メリット(良いポイント)
DNS/CDNとしてドメインを管理しているCloudflare経由で、ポチポチと設定するだけでドメイン内サイト・ページに認証機能をつけられる。

デメリット(悪いポイント)
ログインページのカスタマイズの自由度をもうちょっと上げてもらって、Cloudflareではなく自社ロゴを入れさせてくれるといいと思う。
▼ 企業名:株式会社サポートじまん
https://www.itreview.jp/products/cloudflare-access/reviews/53749
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:情報通信・インターネット
中規模企業でバランスを重視したい
VPN接続サービスの導入にあたって、中規模企業(拠点数3~5拠点)でバランス面を重視したい場合には「エントリーVPN」の導入がおすすめです。
エントリーVPNは、インターネットVPNと同様、インターネット回線を使用して、閉域網を構築する仕組みであるため、コストを抑えた導入が可能です。
中規模企業に人気のVPNおすすめ製品

| 製品名 | Cisco Meraki MX |
| レビュー数 | 25 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |
| 提供会社 | シスコシステムズ合同会社 |
| 料金価格 | 調査中 |

メリット(良いポイント)
クライアントVPNを設定する事で簡単にテレワーク環境を設置する事が出来ました。現在の状況から何時必要になるかわからないので設定しておけば心配ないと思います。

デメリット(悪いポイント)
DHCP構成であれば良いのでしょうが固定IP構成の場合設定に一ひねり必要なようです。単純にDHCPなしにしたら全パソコンがインターネット接続できなくなってしまいました。
▼ 企業名:株式会社エフビー
https://www.itreview.jp/products/meraki-mx/reviews/79248
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:その他製造業
大規模企業でセキュリティを重視したい
VPN接続サービスの導入にあたって、大規模企業(拠点数5~10拠点)でセキュリティ面を重視したい場合には「IP-VPN」の導入がおすすめです。
IP-VPNは、インターネットVPNとは異なり、通信事業者の閉域網を使用する仕組みであるため、強固なセキュリティで安定した通信を実現できます。
大規模企業に人気のVPN接続サービス
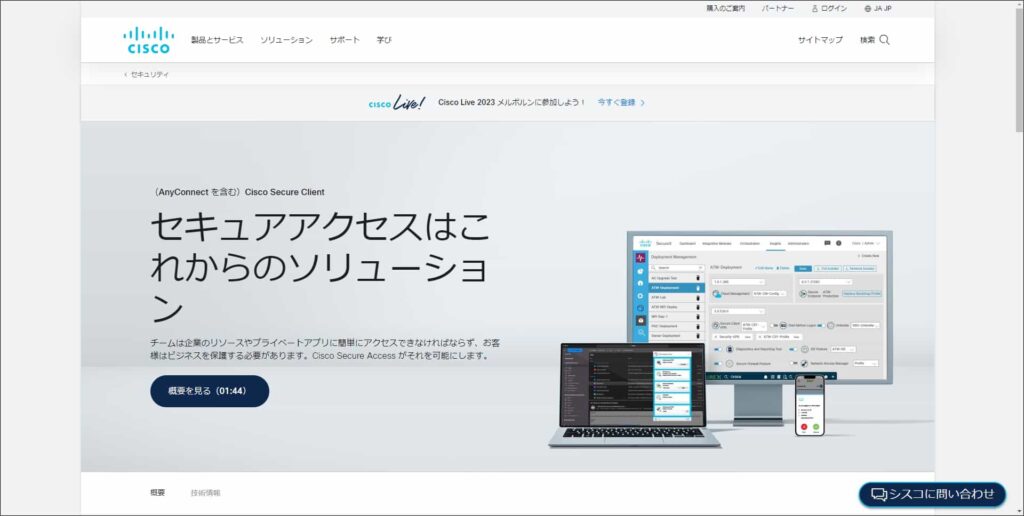
| 製品名 | Cisco AnyConnect |
| レビュー数 | 220 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
| 提供会社 | シスコシステムズ合同会社 |
| 料金価格 | 調査中 |

メリット(良いポイント)
プライベートドライブや会社の勤怠入力システムなど、厳重にアクセス管理をする必要があるものにアクセスする際に使用しています。パスワードを打ち込むだけなので操作も簡単です。

デメリット(悪いポイント)
短時間であっても、PCがスリープモードになると切断されてしまうことがあります。長時間接続されてることもあるので気まぐれですが、できれば切断されにくくなってほしいです。
▼ 企業名:コムテック株式会社
https://www.itreview.jp/products/anyconnect/reviews/159283
▼ 従業員規模:1000人以上
▼ 業種:ソフトウェア・SI
専門企業でカスタマイズ性を重視したい
VPN接続サービスの導入にあたって、専門企業(拠点数1拠点)でカスタマイズ性を重視したい場合には「広域イーサネット」の導入がおすすめです。
広域イーサネットは、IP以外の多様なプロトコルに対応しているため、RIPやOSPFなどのルーティングプロトコルを設定したい場合などに活用しましょう。
VPN接続サービスの選び方のポイント

①:月額の費用やコストで選ぶ
VPN接続サービスの選び方の1つ目としては「月額の費用やコストで選ぶ」という方法が挙げられます。
さまざまな料金で展開されているVPNサービスですが、インターネットVPNとエントリーVPNには安価なものが多いため、コストを抑えた場合に最適です。
IP-VPNと広域イーサネットは、通信事業者の閉域網を使用することから、料金が高い傾向にあり、コストを抑えたい場合には避けておくのが無難でしょう。
②:セキュリティの強度で選ぶ
VPN接続サービスの選び方の2つ目としては「セキュリティの強度で選ぶ」という方法が挙げられます。
とりわけ、IP-VPNと広域イーサネットに関しては、その他の接続方式よりもセキュリティの強度が高いものが多いため、安全性を重視する場合に最適です。
インターネットVPNやエントリーVPNは、コストが安い反面、オープンな回線を使用するため、セキュリティ重視の場合には避けておくのが無難でしょう。
③:通信の品質や保証で選ぶ
VPN接続サービスの選び方の3つ目としては「通信の品質や保証で選ぶ」という方法が挙げられます。
通信回線サービスには、通信速度を保証しないベストエフォート型と、ある程度の速度を保証するギャランティ型の大きく分けて2つの種類が存在します。
IP-VPNや広域イーサネットであれば、品質が安定しているうえ、速度保証に対応した製品も多いため、コストやバランスを踏まえたうえで検討しましょう。
④:サポートの体制で選ぶ
VPN接続サービスの選び方の4つ目としては「サポートの体制で選ぶ」という方法が挙げられます。
VPNに接続できないなどのトラブルに見舞われた場合、サポートの対応が遅かったり、復旧に時間がかかったりすると、事業に影響を与える恐れがあります。
自社構築が可能なインターネットVPNを利用する場合や、設定の難しい広域イーサネットを利用する場合には、サポートの品質も確認するようにしましょう。
⑤:海外利用の可否で選ぶ
VPN接続サービスの選び方の5つ目としては「海外利用の可否で選ぶ」という方法が挙げられます。
海外に拠点や支社がある企業の場合、導入予定のVPN接続サービスが、対象の国との拠点間通信に対応しているかは事前に確認しておく必要があります。
とくに、中国に拠点や支社がある場合には、中国当局の規制変更により、VPNサービスが利用できない可能性があるため、必ず事前に確認しておきましょう。
VPNの種類でよくある質問|Q&A

クラウドVPNとは?
クラウドVPNとは、クラウド事業者から提供されているVPN接続サービスのことであり、広義ではインターネットVPNの一種とされています。
通常、VPN接続サービスの導入にあたっては、送信側と受信側のそれぞれにネットワーク機器を設置する必要があるため、初期費用が少なからず発生します。
一方、クラウドVPNでは、導入に必要な環境がクラウド上に用意されているため、機器を設置する必要がなく、保守や運用のコストを抑えることが可能です。
閉域網と専用線の違いは?
閉域網とは、通信事業者の保有する「閉ざされたネットワーク(閉域網)」のことであり、通信事業者と契約した企業のみ利用することができることから、通信の安全性を担保するものです。
一方の専用線とは、対象の拠点間を「物理的あるいは論理的に1対1で接続」することであり、外部のユーザーの影響を受けないことから、通信の速度や品質などの安定性に優れています。
インターネットVPNよりもセキュリティの強度を高めたい場合には閉域網を、通信する拠点が限定的かつ大容量のデータをやり取りするような場合には専用線を利用するのがおすすめです。
無料で使えるVPN接続サービスはある?
VPN接続サービスのなかには、一部無料で利用できるものなども存在していますが、結論から言えば、これら無料のVPNサービスの使用は、可能な限り避けておくのが無難といえます。
なぜなら、無料のVPNサービスにはセキュリティレベルの低い製品も多く、なかにはサービスの管理者が利用者のデータを悪用するといったトラブルなども発生しているのが現状です。
とくに、一般的に知名度の低い製品や聞いたことのない製品を使用することは、セキュリティリスクの悪化を招く恐れがあるため、信頼の置けるサービスを利用するようにしましょう。
VPNの導入ではコストと機能の定義が重要!
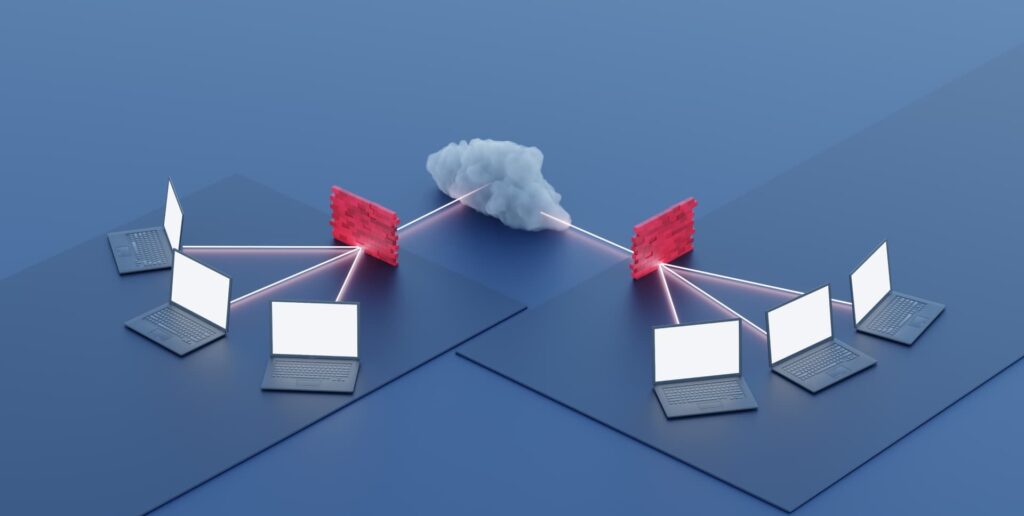
本記事では、VPNの代表的な4種類を解説しながら、それぞれがどのような企業に適しているのか、コストや品質の観点から徹底的に比較してきました。
企業の規模や拠点数、ニーズなどによっても適切なVPN接続サービスは異なるため、導入にかかる費用だけではなく、今後の運用や保守にかかるコストを考慮することが大切です。
VPN接続サービスを選定する場合には、まずは本社と通信を行いたい拠点数の確認を第一として、上限となる予算や必要な機能などをしっかりと定義しておくようにしましょう。
投稿 【図解】VPNの4種類の違いをわかりやすく解説!自社に最適なサービスはどれ? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【2024最新】コールセンターシステム17選を徹底比較!おすすめサービスと選び方のコツを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>「導入規模や用途目的ごとに最適なコールセンターシステムを比較したい」
コールセンターシステムは、コールセンターの運営をスムーズに行うためには、なくてはならない存在であるといっても過言ではないでしょう。
しかし、最適なシステムを選ぶには、料金や機能の比較はもちろん、導入形態や運用方法なども考慮する必要があるため、初心者にはハードルの高い作業です。
本記事では、コールセンターシステムおすすめ17選の徹底比較を通して、システム構成図や選び方のポイントなどについて、わかりやすく解説していきます。
この記事を読むだけで、コールセンターシステムについての基礎知識からサービス選定のコツまでまるごと理解できるため、担当者の方には必見の内容です!
コールセンターシステムとは?

コールセンターシステムとは、コールセンターで行われる日々の電話業務を効率化するためのシステムのことを指します。
例えば、顧客からの問い合わせに対応するインバウンドテレマの場合には、対応履歴の記録やポップアップによる番号表示機能などを実装しておくことで、対応業務を効率的に行うことができます。
また、顧客への営業活動を担当するアウトバウンドテレマの場合では、架電履歴の記録や見込みレベルによるフィルタリング機能などを実装しておくことで、営業活動を効率的に行うことが可能です。
コールセンターシステムの種類と構成図
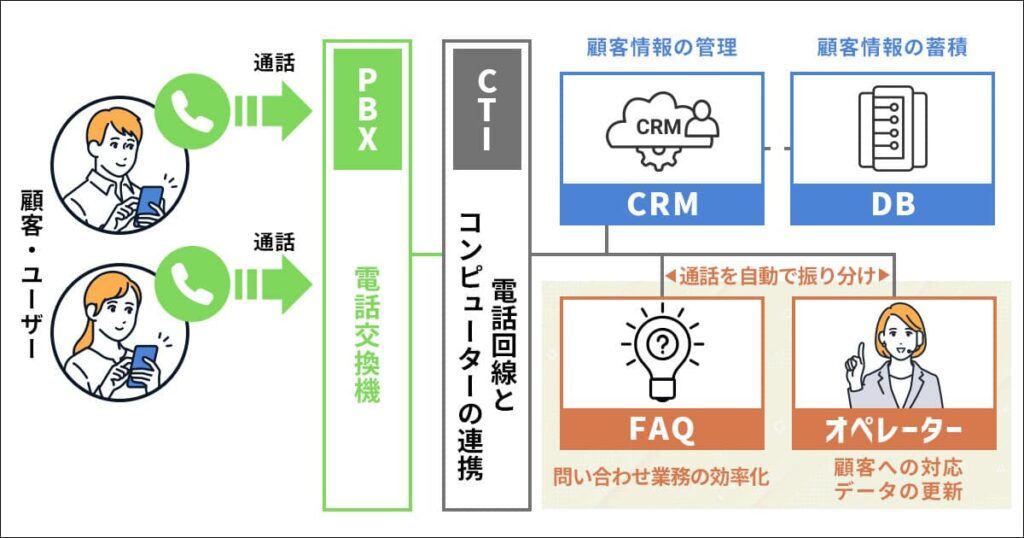
コールセンターシステムの種類には、主にCTIシステム、PBXシステム、CRMシステム、FAQシステムの4つの種類があり、これらを総称した言葉がコールセンターシステムと呼ばれています。
なかには、これらの機能が一つのシステムに集約されたオールインワン型のコールセンターシステムなどもあるため、規模や予算を考慮しながら、運用スタイルに合ったサービスを選ぶことが重要です。
上記のシステムのほかにも、あらかじめ録音した音声ガイダンスによって電話対応を自動化できる「IVRシステム(自動音声応答)」や、オペレーターの状況に合わせて入電を振り分ける「ACDシステム(着信呼自動分配装置)」などを併用する場合もあります。
CTIシステムについて

コールセンターにおけるCTIシステムとは、英語の「Computer Telephony Integration」の略称で、主にビジネスフォンや電話機、FAXなどの端末をPCと連携するための「業務効率化システム」を指します。
着信した番号を参照して、過去の対応履歴や顧客の個人情報などが担当者の画面上に表示されるようになるため、あらゆる電話対応の業務を、より効率的かつ高品質に遂行することが可能です。
CTIシステムの費用相場:月額4,000円~/1ユーザー
|
クラウド型CTI システムの料金相場 |
オンプレミス型CTI システムの料金相場 |
|---|---|
| 月額料金:約4,000円~10,000円 | 初期費用:約50万円~200万円 |
CTIシステムの料金相場は、おおよそ1ユーザーあたり月額4,000円前後で利用できる製品が多いです。
オプションで提供されている機能の追加によって金額の幅は異なりますが、安価な製品であれば月額3,000円前後から、中規模向けの製品で月額1万円~2万円前後で利用することができます。
PBXシステムについて

コールセンターにおけるPBXシステムとは、英語の「Private Branch Exchange」の略称で、主に内外線の転送や接続、発着信など、電話番号をコントロールするための「電話交換機システム」を指します。
一つの電話回線を複数のパソコン端末から操作できるようになるため、それぞれのオペレーターに対して個別で電話回線を割り当てるよりも、通信コストを安く抑えることが可能になります。
PBXシステムの料金相場:月額3,000円~/1ユーザー
|
クラウド型PBX システムの料金相場 |
オンプレミス型PBX システムの料金相場 |
|---|---|
| 月額料金:約3,000円~10,000円 | 初期費用:約300万円~1,000万円 |
PBXシステムの料金相場は、おおよそ1ユーザーあたり月額3,000円前後で利用できる製品が多いです。
通常の電話機能に加えて、自動録音やIVR機能、電話会議サービスなどのオプションを追加した場合には、月額の基本料金に加えて、約2,000円〜3,000円ほどの追加費用が発生します。
CRMシステムについて

コールセンターにおけるCRMシステムとは、英語の「Customer Relationship Management」の略称で、主に顧客の情報や属性、行動の履歴などを管理するための「顧客関係管理システム」を指します。
社内で収集した顧客情報を一元的に管理できるようになるため、案内の重複を回避したり、案件の引き継ぎをスムーズにしたりなど、顧客満足度の向上にも大きく貢献させることができます。
CRMシステムの費用相場:月額5,000円~/1ユーザー
|
クラウド型CRM システムの料金相場 |
オンプレミス型CRM システムの料金相場 |
|---|---|
| 月額料金:約5,000円~10,000円 | 初期費用:約50万円~200万円 |
CRMシステムの料金相場は、おおよそ1ユーザーあたり月額5,000円前後で利用できる製品が多いです。
ほかにも、自社の業務内容に合わせてカスタマイズする個別開発型のCRMの作成なども可能ですが、開発コストが高額になるため、必要な機能は事前に定義しておくことが重要になります。
FAQシステムについて

コールセンターにおけるFAQシステムとは、英語の「Frequently Asked Questions」の略称で、顧客からの「よくある質問」と「質問への回答」で構成されるナレッジベースのシステムのことを指します。
自社のWebサイトやLPに「よくある質問/お問い合わせ」として製品情報の詳細を公開しておくことによって、顧客満足度の向上や対応の省力化など、問い合わせ数の削減にも役立ちます。
FAQシステムの費用相場:月額8,000円~/1ユーザー
|
クラウド型FAQ システムの料金相場 |
オンプレミス型FAQ システムの料金相場 |
|---|---|
| 月額料金:約8,000円~50,000円 | 初期費用:約200万円~400万円 |
FAQシステムの料金相場は、おおよそ1ユーザーあたり月額8,000円前後で利用できる製品が多いです。
企業の規模や利用するユーザー人数、必要とされる機能などによっても料金の幅は異なるため、コストパフォーマンスを考慮しながら、最適なシステムを選定することが重要になります。
コールセンターシステムの比較一覧表
スクロールして全体を見る→
大手企業への導入実績なら『Zendesk』がおすすめ

| 製品名 | Zendesk |
| レビュー数 | 99 |
| 満足度 | ★★★☆☆ 3.6 |
| 提供会社 | 株式会社Zendesk |

メリット(良いポイント)
Zendeskの導入により、タグごとの集計ができ傾向のモニタリングか簡易的に可能。対応/未対応のステイタス管理もできるので対応漏れがなくなった。

デメリット(悪いポイント)
カスタマイズの自由度が高くていろいろ設定があるが、視覚的にわかりにくく習得に時間がかかる。問い合わせへの返信機能もあるが、保存中の返信内容がどこにあるのか?下書きの場所は?などがわかりにくい。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/zendesk/reviews/115379
▼ 従業員規模:1000人以上
▼ 業種:人材
中規模コールセンターへの導入なら『MiiTel』がおすすめ
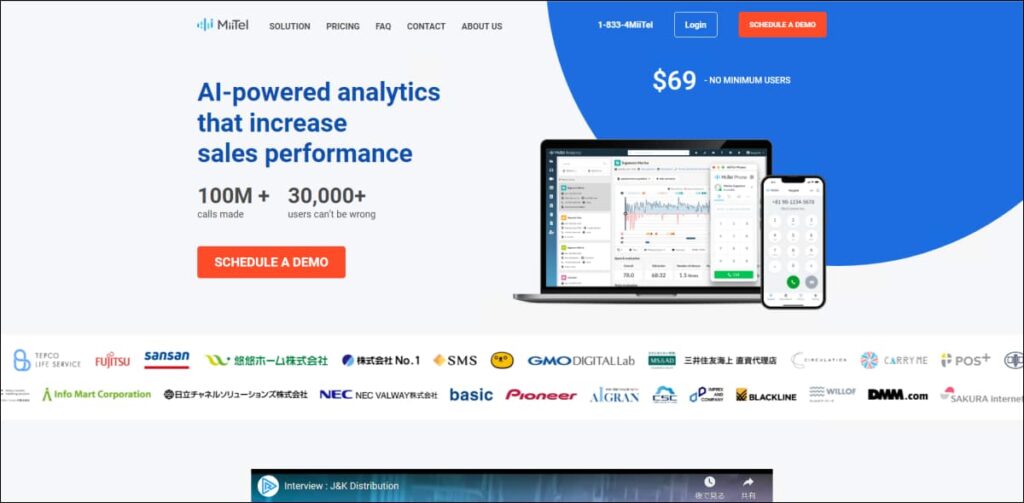
| 製品名 | MiiTel |
| レビュー数 | 62 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |
| 提供会社 | 株式会社RevComm |

メリット(良いポイント)
架電後に会話内容が文字起こしされているためメモの必要がなく会話に集中できる。入電時も登録されている番号は登録不要で氏名が表示される点も便利。

デメリット(悪いポイント)
スピーカーフォンがなく、ハンズフリーで使いたいときに不便。自分の履歴を絞り込む時がもう少し簡素になると使いやすい。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/miitel/reviews/175290
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:ソフトウェア・SI
小規模コールセンターへの導入なら『りもふぉん』がおすすめ

| 製品名 | りもふぉん |
| レビュー数 | 3 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.5 |
| 提供会社 | 合同会社クラウドエンジン |

メリット(良いポイント)
営業時間外の問い合わせに対する転送先の番号として取得、ガイダンスのアナウンスを導入しました。比較的安価に導入することができること、試用期間があることで決めました。

デメリット(悪いポイント)
アナウンスのAIの声質が、文章によって機械的で早口になります。テキスト作成時にスペース、記号を入れると「間をとれる」「抑揚をつける」などができれば、どのユーザーに対しても聞き取りやすく、高品質となるのではないでしょうか。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/remophone/reviews/169895
▼ 従業員規模:50-100人未満
▼ 業種:介護・福祉
インバウンドテレマへの導入なら『MediaCalls』がおすすめ

| 製品名 | MediaCalls |
| レビュー数 | 23 |
| 満足度 | ★★★☆☆ 3.4 |
| 提供会社 | メディアリンク株式会社 |

メリット(良いポイント)
個別の業務内容と受話状況、個別の受話の習熟度などの指標とすることができた。またお昼休みの時間や会議時間など人員調整もしやすくなった。

デメリット(悪いポイント)
個人別の会社部署ごとのスキルマップと連動出来るようにしてほしい。機能追加などの要望に対する改善レスポンスが遅い。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/mediacalls/reviews/10184
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:その他製造業
アウトバウンドテレマへの導入なら『Mostable』がおすすめ


メリット(良いポイント)
一定期間の録音が確認出来るので、聞き取り内容に不安があっても安心出来る。内線、外線転送が出来るのが便利。架電時にリスト内容の修正が出来る。

デメリット(悪いポイント)
今の所、特に不満があるわけではないが、操作が難しいわけではないが、多機能なので、管理者がしっかりと使い方を理解しておく必要があると思います。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/mostable/reviews/171776
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:情報通信・インターネット
CTIシステム比較:おすすめコールセンターシステム3選
スクロールして全体を見る→
カイクラ


メリット(良いポイント)
カイクラを導入することで、着信時にオーナーや車種情報もPC画面上ですぐにわかるため、電話対応が効率化した。通話も録音することが出来るため、聞き逃しても後から確認することが可能。

デメリット(悪いポイント)
通話内容をテキスト化において、相手の話し方も悪いのもあるが、精度が悪いときがあるので改善して欲しい。また、テキスト化した文章をビックデータ解析が出来るようになったら良い。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/kaiwacloud/reviews/113400
▼ 従業員規模:1000人以上
▼ 業種:自動車・輸送機器
サスケLead

| 製品名 | サスケLead |
| レビュー数 | 15 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.3 |
| 提供会社 | 株式会社インターパーク |

メリット(良いポイント)
シンプルで分かりやすいつくりになっているので、他ツールに比べると社内からの要望をすぐに形にして反映させることができる。

デメリット(悪いポイント)
名刺スキャン時の精度とスピードをもう少し向上してほしい。また、セールスの機能ももう少し自由が利くようになると嬉しいです。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/saaske-lead/reviews/53926
▼ 従業員規模:300-1000人未満
▼ 業種:その他の化学工業
List Navigator.

| 製品名 | List Navigator. |
| レビュー数 | 42 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |
| 提供会社 | 株式会社Scene Live |

メリット(良いポイント)
管理画面よりリスト管理ができる点で、作業工数が半分以下となり、他スタッフへの教育体制を整える等の時間を確保できるようになりました。

デメリット(悪いポイント)
現状のサービス内容で満足はしておりますが、他社システムやサービスとの連携が取れると尚使い勝手が良くなると感じます。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/list-navigator/reviews/177111
▼ 従業員規模:20-50人未満
▼ 業種:情報通信・インターネット
PBXシステム比較:おすすめコールセンターシステム3選
スクロールして全体を見る→
GoodLine

| 製品名 | GoodLine |
| レビュー数 | 13 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.4 |
| 提供会社 | 株式会社Good Relations |

メリット(良いポイント)
フルリモートワーク化に合わせて、初めてクラウドPBXを導入しましたが、サポートが分かりやすく、質問に対しての回答レスポンスが速くとても助かっています。

デメリット(悪いポイント)
サポートが現在ですと平日のみかと思いますので、土日祝日もサポートがあるとなお利用しやすいと感じました。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/goodline/reviews/164821
▼ 従業員規模:20-50人未満
▼ 業種:電気
トビラフォンCloud

| 製品名 | トビラフォンCloud |
| レビュー数 | 53 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |
| 提供会社 | トビラシステムズ株式会社 |

メリット(良いポイント)
通常であれば出社しなければ電話に応答できない上に、鳴る電話も一つしか紐づけないが、クラウドであるからこそ今の時代にぴったりであると感じています。

デメリット(悪いポイント)
クラウドであるため、有線の電話よりも音質に少し難がある。会話の内容が途中で途切れてしまうこともしばしばあるので、その点は改善いただきたい。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/tobilaphonecloud/reviews/159373
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:旅行・レジャー
Genesys Cloud CX

| 製品名 | Genesys Cloud CX |
| レビュー数 | 24 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |
| 提供会社 | ジェネシスクラウドサービス株式会社 |

メリット(良いポイント)
なんといってもオールインワンという点がとてもいいポイントです。オムニチャネルの一元管理、活用が出来るのはとても素晴らしいです。

デメリット(悪いポイント)
強いて改善してほしいポイントとしては、マーケティングのみならずセールスに繋げるツールを豊富に用意いただけるとよりいいものになると思います。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/purecloud/reviews/43275
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:電気
CRMシステム比較:おすすめコールセンターシステム3選
スクロールして全体を見る→
アクションリンク

| 製品名 | アクションリンク |
| レビュー数 | 19 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.6 |
| 提供会社 | 株式会社ファブリカコミュニケーションズ |

メリット(良いポイント)
メルマガ配信において予約投稿やセグメントの条件など初心者でもわかりやすく設定でき配信がスムーズにできるようになりました。

デメリット(悪いポイント)
HTMLエディタで作成していますが、初心者なので基本操作マニュアルに各設定の細かな説明などが充実するといいなと思います。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/actionlink/reviews/172945
▼ 従業員規模:1000人以上
▼ 業種:その他
Pipedrive


メリット(良いポイント)
企業の運用に合わせて、ステージ分けや一部自動で移動させることやアクティビティ設定、数値管理ができるのが嬉しいです。

デメリット(悪いポイント)
アクティビティで終了をマーク押してもう使わないって時も再設定の画面が出るので、不要な時は邪魔と感じる。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/pipedrive/reviews/167122
▼ 従業員規模:20-50人未満
▼ 業種:人材
Kairos3

| 製品名 | Kairos3 |
| レビュー数 | 96 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.4 |
| 提供会社 | カイロスマーケティング株式会社 |

メリット(良いポイント)
いい意味で余計な機能がついてないため、使い方で迷うことが少ない。また、それぞれの機能は使いやすくわかりやすい。

デメリット(悪いポイント)
メルマガの開封の判断に際し、セキュリティソフトによる自動開封をカウントしてしまうため、正確な開封実績データを取れない場合があるのは非常に残念だと思う。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/kairos3/reviews/174142
▼ 従業員規模:50-100人未満
▼ 業種:その他サービス
FAQシステム比較:おすすめコールセンターシステム3選
スクロールして全体を見る→
sAI Search
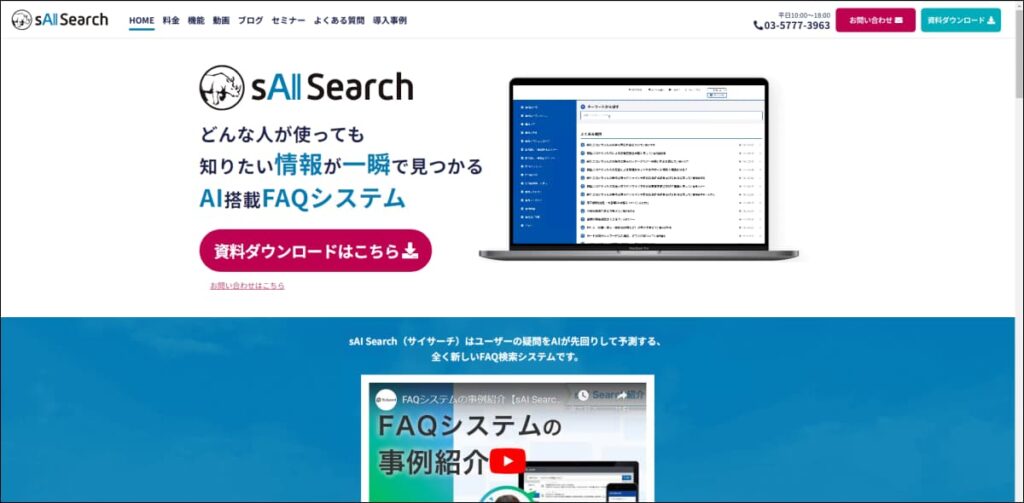
| 製品名 | sAI Search |
| レビュー数 | 39 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.4 |
| 提供会社 | 株式会社サイシード |

メリット(良いポイント)
検索方法がキーワードだけでなく、カテゴリ検索、タグを選ぶだけなど、さまざまな検索方法があり、ユーザーに合った探し方ができる。

デメリット(悪いポイント)
操作マニュアルがドキュメントとしてはなく、動画のみで、細かなマニュアルはないので、利用にあたっては社内でナレッジを蓄積していく必要がある。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/sai-search/reviews/159411
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:保険
PKSHA FAQ

| 製品名 | PKSHA FAQ |
| レビュー数 | 43 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |
| 提供会社 | 株式会社PKSHA Communication |

メリット(良いポイント)
新規施策リリースに伴い大量のFAQを登録することがありますが、CSVファイルを用いて一括で取り込むことができて便利です。

デメリット(悪いポイント)
一度に大量のFAQを登録する際にCSVファイルを活用して一括登録をしてますが、改行は反映されないため、一括処理後に各FAQの改行作業をしています。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/okbiz-for-faq/reviews/172522
▼ 従業員規模:1000人以上
▼ 業種:貸金業、クレジットカード
Tayori

| 製品名 | Tayori |
| レビュー数 | 23 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
| 提供会社 | 株式会社PR TIMES |

メリット(良いポイント)
アドレスを共有しなくてもグループの方々とプロジェクトを管理できるのはいい。またステイタスも確認できるのは便利。アンケート/フォーム入力機能も入力しやすく便利だと思います。

デメリット(悪いポイント)
UI、UXがやや不便。知りたい情報を検索したりするのがややわかりにくいため、改善してほしいです。検索窓で調べてもタグがついていないのか、ヒットしないことが多いです。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/tayori/reviews/138830
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:その他サービス
コールセンターシステムの選び方

業務の内容で選ぶ
コールセンターシステムの選び方の1つ目としては「業務の内容で選ぶ」というものが挙げられます。
コールセンターの業務には、顧客からの電話に対応する「インバウンド型」と、企業から顧客へ発信する「アウトバウンド型」の主に2種類の業務内容に分けられ、それぞれで必要な機能が異なります。
インバウンド型
インバウンド型のコールセンターは、顧客の電話に対応するのが主な業務内容です。
そのため、オペレーターの状況に合わせて着信を自動で振り分けるACD機能や、録音しておいた音声によって無人で電話に対応するIVR機能などが搭載されたシステムを選ぶのが良いでしょう。
アウトバウンド型
アウトバウンド型のコールセンターは、企業から顧客へ発信するのが主な業務内容です。
そのため、任意の番号へワンクリックで発信することができるクリックトゥーコール機能や、自動で架電することができるオートコール機能などが搭載されたシステムを選ぶのが良いでしょう。
導入の形態で選ぶ
コールセンターシステムの選び方の2つ目としては「導入の形態で選ぶ」というものが挙げられます。
導入形態としては、自社内のサーバーに対してシステムを構築する「オンプレミス型」と、ネット上のサーバーに対してシステムを構築する「クラウド型」の大きく分けて2つの方法があります。
オンプレミス型
オンプレミス型のコールセンターシステムは、自社内のサーバーに対してシステムを構築する形態です。
外部からの干渉や影響に強く、セキュリティの強度も高く保たれている反面、初期費用が数百万円~数千万円と高額になりやすいことから、大規模なコールセンターへの導入に適しています。
クラウド型
クラウド型のコールセンターシステムは、ネット上のサーバーに対してシステムを構築する形態です。
オンプレミス型と比較してセキュリティの強度は高くありませんが、月額料金は数千円~数万円と安価で初期費用も抑えられることから、小中規模のコールセンターへの導入に適しています。
料金や価格で選ぶ
コールセンターシステムの選び方の3つ目としては「料金や価格で選ぶ」というものが挙げられます。
前述の通り、コールセンターシステムには、主にクラウド型とオンプレミス型の二種類の導入形態があり、それぞれの導入形態によって、初期費用や月額料金は大きく異なってきます。
利用するアカウント数や回線数、オプションの機能などによっても、運用コストは異なるため、自社に必要な要件を整理しておくことで、予算に合ったシステムを選定することが重要です。
必要な機能で選ぶ
コールセンターシステムの選び方の4つ目としては「必要な機能で選ぶ」というものが挙げられます。
コールセンターシステムの機能としては、主にインバウンド向けとアウトバウンド向けの二種類の機能があり、コールセンターの規模や人数によって、必要な機能の種類や数は異なります。
あらかじめ自社の業務内容を確認しておくことはもちろんのこと、現状の稼働スタイルにおいて障害となっている部分を抜き出し、課題を解決できるような機能を模索することが重要です。
音声の品質で選ぶ
コールセンターシステムの選び方の5つ目としては「音声の品質で選ぶ」というものが挙げられます。
音声品質が悪い場合、双方の認識相違から言った言わないの水掛け論に発展してしまう可能性があるため、音声の品質についても、なるべく事前に評価しておくことを強くおすすめします。
とくに、コールセンターの運営においては、音声品質がクリアであることは顧客満足度を左右する重要な項目でもあるため、なるべく雑音やノイズの少ない製品を選んでおくことが重要です。
サポートの体制で選ぶ
コールセンターシステムの選び方の6つ目としては「サポートの体制で選ぶ」というものが挙げられます。
コールセンターシステムのトラブルは、事業そのものに大きな打撃を与えてしまう危険性があるため、価格や機能と同様に、サポート体制による比較も実施しておくことをおすすめします。
24時間でのサポート対応はもちろんのこと、障害が発生したときの連絡手段についても、社内で運用しているコミュニケーションツールに対応しているかも事前に確認することが重要です。
セキュリティの強度で選ぶ
コールセンターシステムの選び方の7つ目としては「セキュリティの強度で選ぶ」というものが挙げられます。
顧客の個人情報が外部に流出してしまうと、会社や事業そのものが立ち行かなくなってしまう可能性があるため、セキュリティ項目による比較や評価についてもキチンと実施しておきましょう。
IPアドレスによるアクセス制限を設けたり、暗号化通信技術を搭載した製品を選んだりなど、自社に必要なセキュリティ基準を明確にしておくことで安全性の高いサービスを選ぶことが重要です。
外部システムとの連携で選ぶ
コールセンターシステムの選び方の8つ目としては「外部システムとの連携で選ぶ」というものが挙げられます。
コールセンターシステムのなかには、必要に応じて外部のシステムと連携して使用できるサービスも決して珍しくはないため、連携に対応しているサービスの種類は事前に確認しておきましょう。
CRMやCTIなどのメジャーなシステムとの連携はもちろんのこと、現状利用しているシステムがある場合には、導入予定のサービスが使用中のシステムに対応しているかは事前に確認することが重要です。
コールセンターシステムの導入ステップ

①:必要な機能を洗い出す
コールセンターシステムの導入ステップの1つ目としては「必要な機能を洗い出す」というものが挙げられます。
システムのなかには、通話データの分析機能や新人教育のためのモニタリング機能など、スムーズな運営を助けるための便利な機能が搭載されているコールセンターシステムも数多く存在します。
もちろん、多機能なシステムほど料金も高騰していく傾向があるため、必要な機能と予算の兼ね合いを考慮しながらコストパフォーマンスを意識したシステム選定を意識することが重要です。
②:希望の予算を把握する
コールセンターシステムの導入ステップの2つ目としては「希望の予算を把握する」というものが挙げられます。
システムの料金相場は、月額制の場合であれば10,000~50,000円ほど、従量制の場合であれば1,000~6,000円ほどとサービスや導入形態によっても価格帯の上下幅にはバラつきがあります。
料金が高ければ良い、安ければ悪いと一概に言えるものではないため、まずは自社に必要な機能や要件を定義したうえで、なるべく安く維持できるシステムを選ぶことも重要なポイントです。
③:既存のシステムを確認する
コールセンターシステムの導入ステップの3つ目としては「既存のシステムを確認する」というものが挙げられます。
コールセンターシステムには、単体で完結できるパッケージ化されたシステムをありますが、別途CRMやCTIなどの外部のシステムと連携して使用できるサービスなども数多く存在しています。
そのため、すでに導入しているシステムや外部のサービスなどがある場合、既存のシステムと検討しているコールセンターシステムの連携が可能かどうかは事前に確認しておくのがおすすめです。
④:条件にマッチした製品を比較する
コールセンターシステムの導入ステップの4つ目としては「条件にマッチした製品を比較する」というものが挙げられます。
とりわけ、検討の初期段階では、案内された料金が相場に沿った適正な価格かどうかの判断が難しいため、そのままの状態で即決してしまうと業者の言い値で契約が進んでしまうリスクがあります。
他社の料金を交渉材料とすることで、場合によっては特別な割引やディスカウントを受けられる可能性もあるため、一番最初に商談をしたシステムで即決してしまうことは避けておくのが無難です。
⑤:試験導入から社内評価を実施する
コールセンターシステムの導入ステップの5つ目としては「試験導入から社内評価を実施する」というものが挙げられます。
サービスを絞り込んだからといって、すぐに本格的な導入へ移行しまうと、選定の過程では気付かなかった業務上のミスマッチや思いも寄らないトラブルを引き起こしてしまう要因となります。
まずは試験的な導入を通して、システムの使用感や実際に使った担当者のフィードバックを集めながら、そのシステムが自社にとってベストな選択かどうかを社内で評価することが重要です。
コールセンターシステムのメリット

コストの削減につながる
コールセンターシステムを導入するメリットの1つ目としては「コストの削減につながる」というものが挙げられます。
クラウドベースのシステムを利用することで、運営に必要な設備投資や物理的なスペースの確保が不要になるため、初期投資を抑えながら必要に応じたスケールアップが可能になります。
また、システムの導入によって、オペレーターのリモートワークにも対応できるようになるため、従業員の人件費はもちろん、オフィスの電気代や消耗品費などの削減効果も期待できるでしょう。
業務負担の軽減につながる
コールセンターシステムを導入するメリットの2つ目としては「業務負担の軽減につながる」というものが挙げられます。
システムの導入により、顧客情報への即時アクセスはもちろん、自動化された応答機能の使用も可能になるため、顧客からの問い合わせに対しても迅速かつ効率的な対応が可能になります。
また、通話記録の自動化や業務の進捗管理、レポートの作成など、日々の管理業務を効率化する機能なども提供しているため、コア業務への集中と全体的な業務負担の軽減が実現できるでしょう。
対応品質の向上につながる
コールセンターシステムを導入するメリットの3つ目としては「対応品質の向上につながる」というものが挙げられます。
顧客情報や過去の対応履歴をリアルタイムで確認できるようになるため、急な問い合わせに対しても電話を折り返すことなく、それぞれの顧客ニーズに沿った適切な対応が可能になります。
また、AIや機械学習を用いた自動化機能を利用することにより、一般的な問い合わせに対してはAIが回答し、より複雑な問題に対しては人間のオペレーターが対応できる環境を作り出します。
コールセンターシステムのデメリット

月額単位でのランニングコストが発生する
コールセンターシステムのデメリットの1つ目としては「月額単位でのランニングコストが発生する」というものが挙げられます。
とくに、クラウド型のコールセンターシステムの場合は、サブスクリプション制度による月額課金の料金形態で提供されているため、月々のランニングコストが高騰しやすい傾向にあります。
予算に制限がある小規模企業やスタートアップのコールセンターにとっては、財務上の負担となることが予想されるため、長期的なコスト管理と価格と機能のバランスを考慮することが重要です。
システムの定着に向けた研修が必要になる
コールセンターシステムのデメリットの2つ目としては「システムの定着に向けた研修が必要になる」というものが挙げられます。
いざ新しいシステムを導入したからといって、そのシステムをすべてのオペレーターが適切に運用していくためには、定期的なトレーニング研修の提供と習得のための時間が必要になります。
また、システムを導入した直後は、いつでも参照できるマニュアルを用意したり、従業員用のヘルプデスクを設置したりなど、普段よりもサポート体制を強化できるような施策を実施すべきです。
すべての問い合わせに対応できるとは限らない
コールセンターシステムのデメリットの3つ目としては「すべての問い合わせに対応できるとは限らない」というものが挙げられます。
コールセンターシステムのなかには、問い合わせへの対応を自動で行ってくれるIVR機能を搭載した製品などもありますが、あらゆる問い合わせに対して完全に対応できるサービスはないものです。
いくらシステムによる効率化を進めたところで、完全無人での電話対応は難しいため、対応業務そのものをゼロにしたいということであれば、別途電話代行サービスなどの利用を検討すべきです。
まとめ:コールセンターシステムの導入でコスト削減と業務効率化を実現!

今回は、コールセンターシステムおすすめ17選の徹底比較を通して、システムの構成図や選び方のポイントなどについて、わかりやすく解説していきました。
コールセンターシステムを導入することによって、通信コストの削減効果や業務負担の軽減、電話対応品質の向上など、さまざまなメリットを享受することができるようになります。
ただし、製品によって月々の費用や使える機能などは大きく異なるため、システム選びで失敗しないためには、必要な機能と予算のバランスを考慮する必要があるでしょう。
投稿 【2024最新】コールセンターシステム17選を徹底比較!おすすめサービスと選び方のコツを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 VPN接続とは?仕組みや種類からメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>近年、サイバー攻撃の増加やリモートワークの普及などの影響により、多くの企業でVPNの導入が進んでおり、拠点間通信やリモートワークにおける安全性の向上を実現しています。
しかし、VPNの仕組みは難解であるうえ、複数の種類が混在しているため、適切なサービスを選定できない場合には、通信速度の遅延や運用コストの増加といった問題を引き起こしてしまいます。
本記事では、VPNの基本的な仕組みや種類はもちろん、専用線との違いからメリット・デメリットまで徹底的に解説していきます。
この記事を読むだけで、VPNの全体像を把握できるため、セキュリティ強化や業務効率化に悩んでいる企業担当者には必見の内容です!
▶ 関連記事:【図解】VPNの4種類の違いをわかりやすく解説!自社に最適なサービスはどれ?
VPN接続とは?

VPN接続とは、インターネット上に仮想の専用ネットワークを構築することで、安全なデータ通信を実現する技術のことです。
インターネットを経由してプライベートネットワークにアクセスする場合、データの暗号化により、第三者からの盗聴やデータの改ざんを防止できます。
主に、リモートワークや拠点間通信におけるセキュリティ対策として活用され、外出先や自宅から社内のネットワークに安全に接続することが可能です。
具体的な活用事例としては、企業における社内システムへのアクセスやストリーミングサービスにおける地域制限の回避などが挙げられます。
VPN接続が必要になった理由
- リモートワークの普及
- サイバー攻撃の増加
- クラウドサービスの拡大
①:リモートワークの普及
VPN接続が必要になった理由の1つ目としては「リモートワークの普及」というものが挙げられます。
近年、リモートワークの導入が加速し、多くの企業が柔軟な働き方を推進している一方、インターネットを介した業務のやり取りが増え、セキュリティリスクも高まっています。
VPNを利用することで、企業のネットワークに対する安全なアクセスを確保し、業務のセキュリティを強化することができます。
②:サイバー攻撃の増加
VPN接続が必要になった理由の2つ目としては「サイバー攻撃の増加」というものが挙げられます。
近年、企業や個人に対するサイバー攻撃が急増しており、特にフィッシング攻撃やランサムウェアなどは、現代社会においても深刻な問題として認知されるようになりました。
VPNを利用することで、データ通信そのものを暗号化することができるため、不正アクセスのリスクを軽減することができます。
③:クラウドサービスの拡大
VPN接続が必要になった理由の3つ目としては「クラウドサービスの拡大」というものが挙げられます。
企業がクラウドサービスを活用する機会が増えた一方、インターネットを介したサービスであるため、通信の安全性が確保されていない場合、情報漏洩のリスクが高まります。
VPNを利用することで、業務に必要なクラウドサービスへの接続を安全に行い、情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。
VPNと専用線の違い
| 項目 | VPN | 専用線 |
|---|---|---|
| 接続方式 | ネットワークを利用した仮想の専用線 | 物理的に確立された専用の通信回線 |
| 導入コスト | コストが低い | コストが高い |
| 導入ハードル | ハードルが低い (回線工事が不要) |
ハードルが高い (回線工事が必要) |
| セキュリティ | 強度が低い (暗号化技術) |
強度が高い (物理的遮断) |
| 通信速度 | インターネット環境に依存 | 安定した高速通信が可能 |
| 利用目的 | ・拠点間通信 ・リモートワーク対応 |
・企業間通信 ・データセンター接続 |
➀:導入コストの違い
VPNと専用線の違いの1つ目としては「導入コストの違い」が挙げられます。
専用線は、通信事業者が提供する専用回線を使用するため、高品質な通信が可能な反面、回線敷設や保守にかかるコストが高額になりがちです。
一方のVPNは、既存のインターネット回線を活用するため、専用の回線を敷設する必要がなく、初期費用を最小限に抑えることができます。そのため、開業したてのベンチャー企業やスタートアップ企業などには最適なサービスといえるでしょう。
②:導入ハードルの違い
VPNと専用線の違いの2つ目としては「導入ハードルの違い」が挙げられます。
専用線は、通信事業者との契約が必要であり、回線工事や調整に時間がかかるため、導入開始までには数週間から数カ月の導入期間が必要です。
一方のVPNは、既存のインターネット回線を利用できるため、短期間で導入でき、リモートワークなど多様な働き方にも柔軟に対応できます。そのため、拠点数が変動する企業やグローバル展開する企業にとっては利便性が高いといえるでしょう。
③:セキュリティ強度の違い
VPNと専用線の違いの3つ目としては「セキュリティレベルの違い」が挙げられます。
専用線は、外部のネットワークと物理的に分離されている仕組みとなっているため、盗聴や不正アクセスのリスクが極めて低いのが特徴です。
一方のVPNは、インターネットを経由するため、適切な暗号化や認証技術を導入しなければ、セキュリティリスクが発生する恐れがあります。そのため、VPNを利用するときには最新の暗号化技術を採用した製品を選ぶことが重要といえるでしょう。
VPN接続の仕組み
- トンネリング
- カプセル化
- 暗号化
- 認証
トンネリング
トンネリングとは、インターネット上に仮想的な専用回線(トンネル)を構築することで、安全にデータを送受信する技術です。
送信されたデータは、トンネルの内部を通過する形で外部からは見えないように隠蔽されるため、安全性の確保やプライバシーの保護ができるというVPN接続の根幹とも言える技術です。
カプセル化
カプセル化とは、データを特定のフォーマットに包み込むことで、異なるネットワーク間でのデータ転送を可能にする技術です。
元のデータに新たなヘッダーを付け加えることで転送先の識別を可能にする技術で、社内ネットワークと外部ネットワーク間におけるデータ通信において重要な役割を果たしています。
暗号化
暗号化とは、データを読み取り不可能な特殊な形式に変換することで、第三者が内容を理解できないようにするための技術です。
暗号化方式としては、AESやRSAなどの高度な方式が利用されており、データの送信前に暗号化が実施されるため、受信側でしか元のデータに戻すことができない仕組みとなっています。
認証
認証とは、IDやパスワードによる本人確認によって、ユーザーやデバイスの正当性を確認し、不正アクセスを防ぐ仕組みです。
認証方法としては、パスワード認証やデジタル証明書認証のほか、二要素認証(2FA)などがあり、ワンタイムパスワードや生体認証を組み合わせることで、強度を高めることができます。
VPN接続のメリット
- セキュアな通信環境を確保できる
- 初期費用や運用コストを抑えられる
- リモートや在宅勤務にも対応できる
セキュアな通信環境を構築できる
VPN接続を導入するメリットの1つ目としては「セキュアな通信環境を構築できる」というものが挙げられます。
VPNは通信内容を暗号化することができるため、外部からの盗聴や第三者による不正なデータの改ざんなどを防止することができます。
特に、公共のWi-Fiや不安定なネットワーク環境においては、安全にインターネットを利用できるため、機密性の高い業務に適しています。
初期費用や運用コストを抑えられる
VPN接続を導入するメリットの2つ目としては「初期費用や運用コストを抑えられる」というものが挙げられます。
VPNは比較的安価なコストで導入できるうえ、ハードウェアや専用回線を必要としないため、初期投資を最小限に抑えることができます。
また、インターネットを利用した接続方法であるため、通信インフラの追加費用が少なく、運用コストを抑えられることも大きな特徴です。
リモートや在宅勤務にも対応できる
VPN接続を導入するメリットの3つ目としては「リモートや在宅勤務にも対応できる」というものが挙げられます。
VPNはオフィス外からでも安全に企業ネットワークにアクセスできる仕組みとなっているため、リモートワークをスムーズに行うことができます。
また、在宅勤務や出張先からでも、オフィスと同じように業務を行うことができるため、業務の効率化や生産性の向上といった効果も期待できます。
VPN接続のデメリット
- 通信の品質が悪化する恐れがある
- 設定や管理の手間が増えてしまう
- ネットワーク障害のリスクがある
通信の品質が悪化する恐れがある
VPN接続を導入するデメリットの1つ目としては「通信の品質が悪化する恐れがある」というものが挙げられます。
VPNはインターネットを経由する仕組みであるため、回線の混雑状況やサーバー負荷のレベルによっては、通信品質や速度が低下することがあります。
例えば、多数の従業員が同時にVPNを利用する場合には、ネットワークへのアクセス速度が低下し、実際の業務に支障をきたす可能性があります。
対応策としては、アクセスが集中する帯域を増強したり、高速なVPNプロトコルを選択したりなどの対策が有効です。
設定や管理の手間が増えてしまう
VPN接続を導入するデメリットの2つ目としては「設定や管理の手間が増えてしまう」というものが挙げられます。
VPNは適切な設定と継続的な管理が必要であり、特に、ITリテラシーが低い企業やサーバーの知識に乏しい企業にとっては負担となる可能性があります。
例えば、VPNの接続設定を誤った設定にしてしまうと、ネットワーク速度の遅延やアクセス制限などの問題を招いてしまう要因となってしまいます。
対応策としては、管理が容易なクラウドVPNを導入したり、保守運用に長けた人材を採用したりなどの対策が有効です。
ネットワーク障害のリスクがある
VPN接続を導入するデメリットの3つ目としては「ネットワーク障害のリスクがある」というものが挙げられます。
VPNは一元的なゲートウェイとして機能するため、万が一サーバーに障害が発生した場合、全てのユーザーのアクセスが停止してしまう恐れがあります。
例えば、VPNサーバーがダウンしてしまった場合、社員が業務に必要なデータにアクセスできなくなり、業務が停止してしまう可能性があります。
対応策としては、復旧手順が記載されたマニュアルを用意したり、予備のサーバーを用意したりなどの対策が有効です。
VPN接続の種類
| インターネットVPN | エントリーVPN | IP-VPN | 広域イーサネット | |
|---|---|---|---|---|
| 回線 | インターネット | 閉域網 | 閉域網 | 閉域網 |
| コスト | ◎ | 〇 | △ | △ |
| 通信品質 | △ | △ | ◎ | ◎ |
| 安全性 | △ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 拡張性 | 〇 | △ | △ | ◎ |
| 帯域保証 | ベストエフォート | ベストエフォート | ギャランティ | ギャランティ |
| 導入企業 | 小規模 | 中規模 | 大規模 | 専門企業 |
| 拠点数 | 1~3 | 3~5 | 5~10 | 1 |
| 活用場面 | 導入コストを重視したい | バランスを重視したい | セキュリティを重視したい | 高度なカスタマイズが必要 |
VPNの代表的な種類としては、主に「インターネットVPN」と「エントリーVPN」と「IP-VPN」と「広域イーサネット」の4つの種類に分類されています。
- インターネットVPN
- エントリーVPN
- IP-VPN
- 広域イーサネット
これら4種類のVPNでは、それぞれ構築される仕組みが異なるほか、運用コストや通信品質、セキュリティやカスタマイズの自由度などにも違いがあります。
インターネットVPN
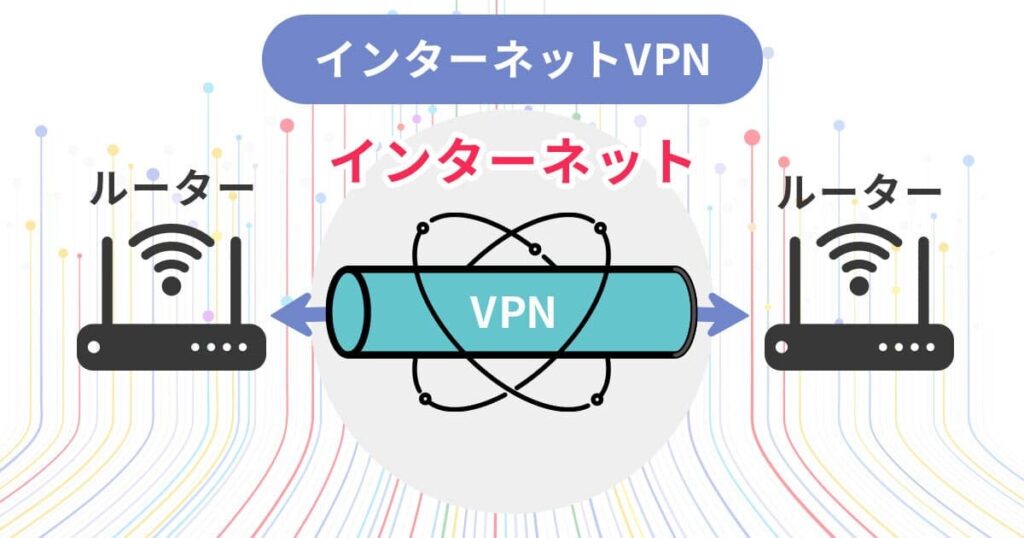
インターネットVPNとは、インターネット上に仮想のネットワーク環境を構築する接続方式です。
構築方法には、通信事業者から機器をレンタルする方法のほか、設定や保守点検を自社で実施できるのであれば、自社で構築することも可能です。
拠点数1~3拠点の小規模オフィス向けで、手軽にVPNサービスを導入したい、低コストでVPN接続サービスを利用したいという場合におすすめです。
インターネットVPNのメリット
インターネットVPNのメリットとしては「安価に導入することができる」というものが挙げられます。
ルーターや固定IPを準備する必要はありますが、閉域IP網を構築する必要がないため、後述のIP-VPNや広域イーサネットよりも安価な導入が可能です。
また、インターネットを使用する接続方式となっているため、4種類のVPNでは唯一自社で構築することができるというところも大きなメリットの一つです。
インターネットVPNのデメリット
インターネットVPNのデメリットとしては「セキュリティの強度が低い」というものが挙げられます。
専用線を使用する閉域網とは異なり、オープンなネット回線を使用するため、外部からの不正アクセスやデータの盗み見などのセキュリティリスクがあります。
運用にあたっては、カフェなどの公衆無線では利用しないことはもちろん、利用のルールを設けたり、利用者のリテラシーを高めたりなどの対策が必要です。
インターネットVPNの料金相場
インターネットVPNの料金相場は「2万円~5万円程度」です。VPN接続サービスのなかでは、もっとも安価に導入することが可能です。
コストを抑えたい場合の導入シーンに最適であり、VPN対応ルーターと初期設定だけで導入することができるため、保守管理のためのランニングコストが少ないVPN種類です。
エントリーVPN
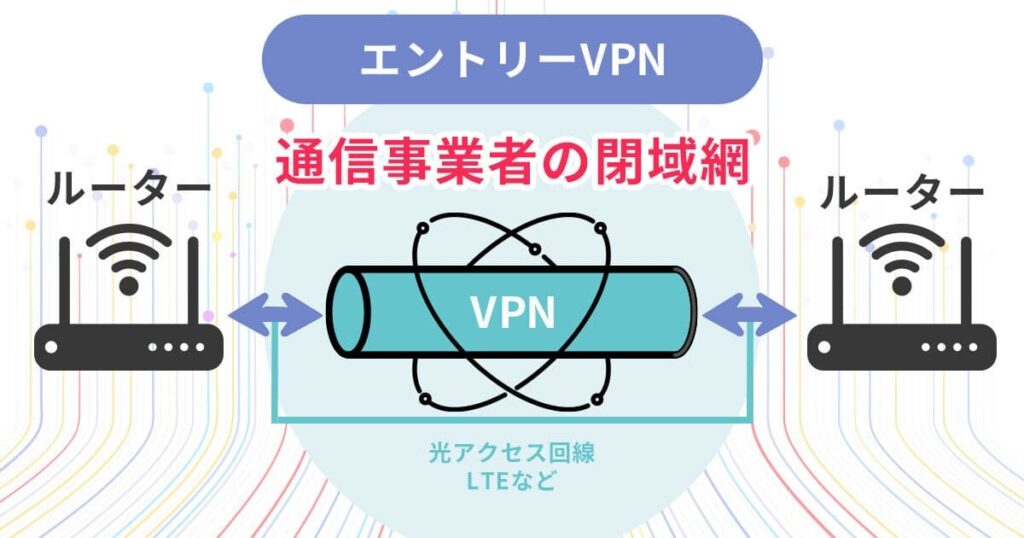
エントリーVPNとは、ADSLなどのインターネット回線を用いて閉域IP網を構築する接続方式です。
通信事業者の設置する閉域網を使用するため、インターネット回線を用いるインターネットVPNよりも、セキュリティの強度や信頼性に優れています。
拠点数3~5拠点の中規模オフィス向けで、バランスに優れたVPNを導入したい、低コストでVPN接続サービスを利用したいという場合におすすめです。
エントリーVPNのメリット
エントリーVPNのメリットとしては「トータルバランスに優れている」というものが挙げられます。
インターネットVPNと同様、インターネット回線を利用する接続方式であるため、大規模な設備投資が不要で、導入のハードルが低いのが特徴です。
設備投資のコストやセキュリティなど、特筆して尖った部分はありませんが、そのぶんトータルでのバランスに優れた接続方式であるといえるでしょう。
エントリーVPNのデメリット
エントリーVPNのデメリットとしては「通信速度が遅くなる場合がある」というものが挙げられます。
使用する回線自体は光ファイバーなどのインターネット回線であるため、トラフィックの混雑状況によっては速度が遅くなる可能性があります。
安定した通信品質やギャランティ型の帯域保障を希望する場合には、より通信の安定したIP-VPNや広域イーサネットを利用するのがおすすめです。
エントリーVPNの料金相場
エントリーVPNの料金相場は「月額1万円~2万円程度」です。この月額費用に加えて、最初に5,000円程度の初期費用が発生することもあります。
インターネットVPNと同様、光ファイバーやADSLなどのインターネット回線を使用するため、VPN接続サービスのなかでは、比較的安価に導入することができるVPN種類です。
IP-VPN
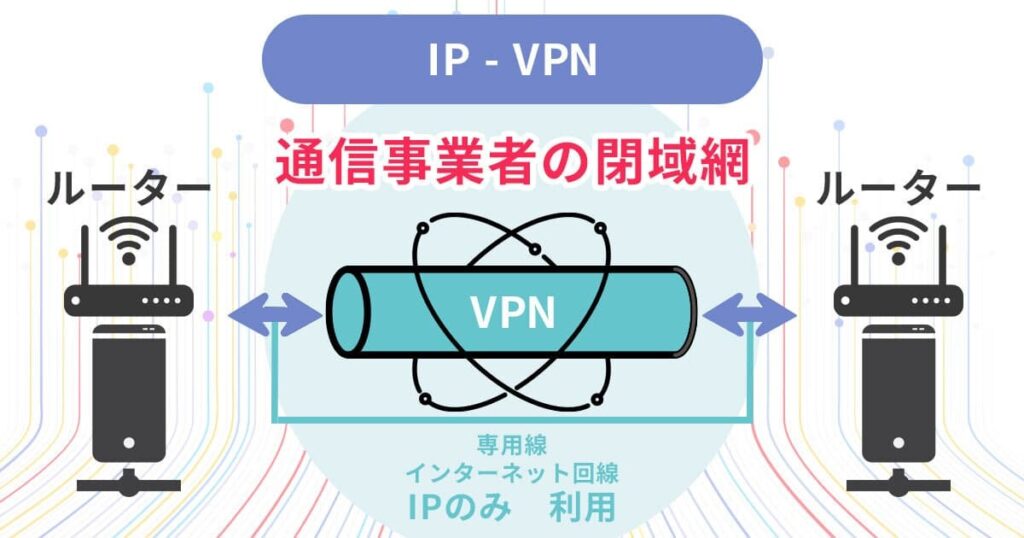
IP-VPNとは、通信事業者の閉域IP網を使用して仮想のネットワークを構築する接続方式です。
インターネットVPNやエントリーVPNとは異なり、閉域網を使用する方式であるため、高いセキュリティ強度で安全に通信することができます。
拠点数5~10拠点の大規模オフィス向けで、VPNのセキュリティを強化したい、複数の拠点間で安定した通信を行いたいという場合におすすめです。
IP-VPNのメリット
IP-VPNのメリットとしては「セキュリティの強度が高い」というものが挙げられます。
インターネットVPNとは異なり、通信事業者の設置する閉域網を利用するため、より専用線に近いセキュアな環境で通信することが可能です。
また、サービス品質保証(SLA)や遅延保証などの保証サービスが付いているため、大規模ネットワークでも安定した通信を行うことができます。
IP-VPNのデメリット
IP-VPNのデメリットとしては「導入の初期コストが高い」というものが挙げられます。
IP-VPNの導入には、通信事業者との契約が必要となるため、インターネットVPNやエントリーVPNよりもコストが高くなることが一般的です。
ただし、機器の準備から設定、保守点検まで通信事業者に依頼することができるため、拠点数が多く、自社構築が難しい企業にはおすすめできます。
IP-VPNの料金相場
IP-VPNの料金相場は「月額1万円~5万円程度」です。この月額費用に加えて、数千円~数万円の初期費用が発生することもあります。
インターネットVPNやエントリーVPNとは異なり、通信事業者の保有する閉域網を使用する仕組みとなっているため、回線使用料のコストが高くなりやすい傾向にあるVPN種類です。
広域イーサネット
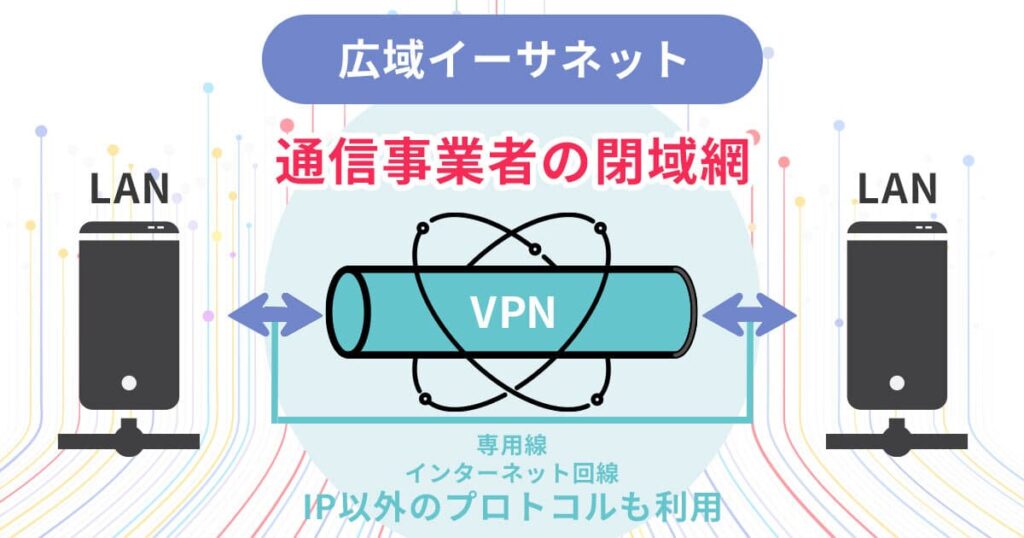
広域イーサネットとは、通信事業者の閉域網を利用して仮想のネットワークを構築する接続方式です。
IP-VPNと構成自体に大きな違いはありませんが、IP-VPNがIPのみの対応であるのに対して、広域イーサネットでは多様なプロトコルに対応しています。
IP以外のプロトコルに対応していることから、より高度なカスタマイズを行いたい、その他のルーティングプロトコルを使用したいという場合におすすめです。
広域イーサネットのメリット
広域イーサネットのメリットとしては「カスタマイズの自由度が高い」というものが挙げられます。
使用できるプロトコルがIPのみに限られるIP-VPNに対して、広域イーサネットでは多様なルーティングプロトコル(RIPやOSPFなど)にも対応しています。
また、ギャランティー型と呼ばれる通信保証があることがほとんどであり、最大1Gbpsもの高速通信で安全なネットワークに接続することが可能です。
広域イーサネットのデメリット
広域イーサネットのデメリットとしては「ネットワークの設定が複雑」というものが挙げられます。
IPに依存しない接続方式であるため、IP以外のネットワークからスムーズな移行が行える一方、最初のネットワーク設定は複雑になってしまいがちです。
導入するための要件定義や保守運用への負担も大きくなりやすいため、基本的には拠点数が限られている企業にのみ適しているといえるでしょう。
広域イーサネットの料金相場
IP-VPNの料金相場は「月額10万円~20万円程度」です。この月額費用に加えて、数千円~数万円の初期費用が発生することもあります。
広域イーサネットは構築の難易度が高く、通信を行いたい拠点間の物理的な距離やエリア、保証する帯域速度などによっても費用は異なるため、料金幅の乱高下が激しいVPN種類です。
VPN接続サービスの選び方と比較のポイント

①:月額の費用やコストで選ぶ
VPN接続サービスの選び方の1つ目としては「月額の費用やコストで選ぶ」という方法が挙げられます。
さまざまな料金で展開されているVPNサービスですが、インターネットVPNとエントリーVPNには安価なものが多いため、コストを抑えた場合に最適です。
IP-VPNと広域イーサネットは、通信事業者の閉域網を使用することから、料金が高い傾向にあり、コストを抑えたい場合には避けておくのが無難でしょう。
②:セキュリティの強度で選ぶ
VPN接続サービスの選び方の2つ目としては「セキュリティの強度で選ぶ」という方法が挙げられます。
とりわけ、IP-VPNと広域イーサネットに関しては、その他の接続方式よりもセキュリティの強度が高いものが多いため、安全性を重視する場合に最適です。
インターネットVPNやエントリーVPNは、コストが安い反面、オープンな回線を使用するため、セキュリティ重視の場合には避けておくのが無難でしょう。
③:通信の品質や保証で選ぶ
VPN接続サービスの選び方の3つ目としては「通信の品質や保証で選ぶ」という方法が挙げられます。
通信回線サービスには、通信速度を保証しないベストエフォート型と、ある程度の速度を保証するギャランティ型の大きく分けて2つの種類が存在します。
IP-VPNや広域イーサネットであれば、品質が安定しているうえ、速度保証に対応した製品も多いため、コストやバランスを踏まえたうえで検討しましょう。
④:サポートの体制で選ぶ
VPN接続サービスの選び方の4つ目としては「サポートの体制で選ぶ」という方法が挙げられます。
VPNに接続できないなどのトラブルに見舞われた場合、サポートの対応が遅かったり、復旧に時間がかかったりすると、事業に影響を与える恐れがあります。
自社構築が可能なインターネットVPNを利用する場合や、設定の難しい広域イーサネットを利用する場合には、サポートの品質も確認するようにしましょう。
⑤:海外利用の可否で選ぶ
VPN接続サービスの選び方の5つ目としては「海外利用の可否で選ぶ」という方法が挙げられます。
海外に拠点や支社がある企業の場合、導入予定のVPN接続サービスが、対象の国との拠点間通信に対応しているかは事前に確認しておく必要があります。
とくに、中国に拠点や支社がある場合には、中国当局の規制変更により、VPNサービスが利用できない可能性があるため、必ず事前に確認しておきましょう。
VPN接続サービスのおすすめ製品3選
スクロールして全体を見る→
小規模企業に人気のVPNおすすめ製品
VPN接続サービスの導入にあたって、小規模企業(拠点数1~3拠点)でコスト面を重視したい場合には「インターネットVPN」の導入がおすすめです。
インターネットVPNは、インターネット回線を使用したVPN接続方式であるため、専用線や閉域網を構築する必要がなく、コストを抑えた導入が可能です。
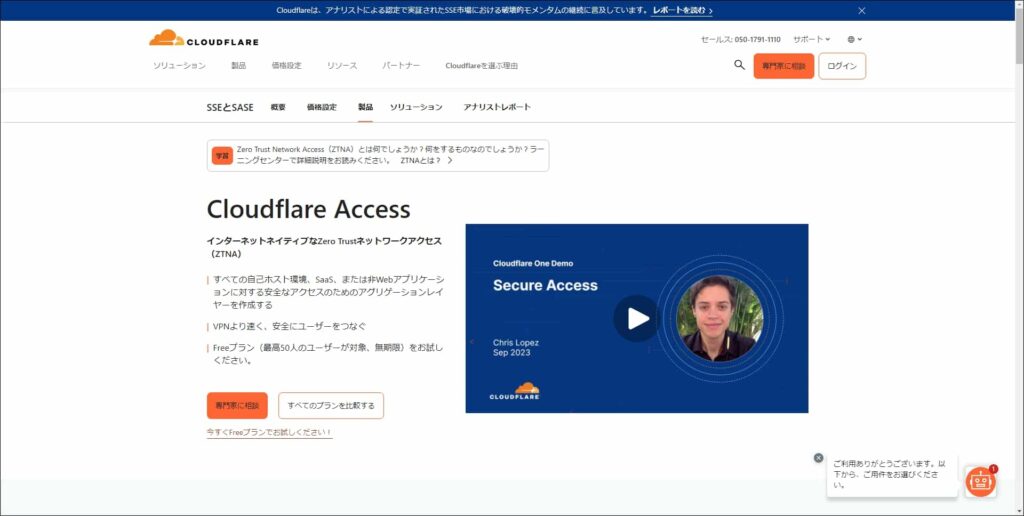
| 製品名 | Cloudflare Access |
| レビュー数 | 16 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.5 |
| 提供会社 | Cloudflare |
| 料金価格 | 調査中 |

メリット(良いポイント)
DNS/CDNとしてドメインを管理しているCloudflare経由で、ポチポチと設定するだけでドメイン内サイト・ページに認証機能をつけられる。

デメリット(悪いポイント)
ログインページのカスタマイズの自由度をもうちょっと上げてもらって、Cloudflareではなく自社ロゴを入れさせてくれるといいと思う。
▼ 企業名:株式会社サポートじまん
https://www.itreview.jp/products/cloudflare-access/reviews/53749
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:情報通信・インターネット
中規模企業に人気のVPNおすすめ製品
VPN接続サービスの導入にあたって、中規模企業(拠点数3~5拠点)でバランス面を重視したい場合には「エントリーVPN」の導入がおすすめです。
エントリーVPNは、インターネットVPNと同様、インターネット回線を使用して、閉域網を構築する仕組みであるため、コストを抑えた導入が可能です。

| 製品名 | Cisco Meraki MX |
| レビュー数 | 25 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |
| 提供会社 | シスコシステムズ合同会社 |
| 料金価格 | 調査中 |

メリット(良いポイント)
クライアントVPNを設定する事で簡単にテレワーク環境を設置する事が出来ました。現在の状況から何時必要になるかわからないので設定しておけば心配ないと思います。

デメリット(悪いポイント)
DHCP構成であれば良いのでしょうが固定IP構成の場合設定に一ひねり必要なようです。単純にDHCPなしにしたら全パソコンがインターネット接続できなくなってしまいました。
▼ 企業名:株式会社エフビー
https://www.itreview.jp/products/meraki-mx/reviews/79248
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:その他製造業
大規模企業に人気のVPN接続サービス
VPN接続サービスの導入にあたって、大規模企業(拠点数5~10拠点)でセキュリティ面を重視したい場合には「IP-VPN」の導入がおすすめです。
IP-VPNは、インターネットVPNとは異なり、通信事業者の閉域網を使用する仕組みであるため、強固なセキュリティで安定した通信を実現できます。
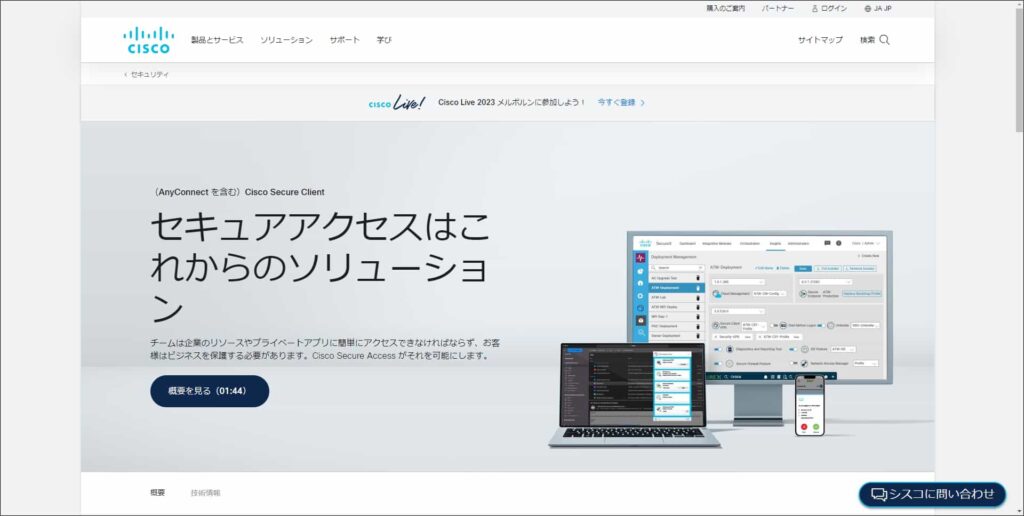
| 製品名 | Cisco AnyConnect |
| レビュー数 | 220 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
| 提供会社 | シスコシステムズ合同会社 |
| 料金価格 | 調査中 |

メリット(良いポイント)
プライベートドライブや会社の勤怠入力システムなど、厳重にアクセス管理をする必要があるものにアクセスする際に使用しています。パスワードを打ち込むだけなので操作も簡単です。

デメリット(悪いポイント)
短時間であっても、PCがスリープモードになると切断されてしまうことがあります。長時間接続されてることもあるので気まぐれですが、できれば切断されにくくなってほしいです。
▼ 企業名:コムテック株式会社
https://www.itreview.jp/products/anyconnect/reviews/159283
▼ 従業員規模:1000人以上
▼ 業種:ソフトウェア・SI
VPNの種類でよくある質問|Q&A

Q:クラウドVPNとは?
クラウドVPNとは、クラウド事業者から提供されているVPN接続サービスのことであり、広義ではインターネットVPNの一種とされています。
通常、VPN接続サービスの導入にあたっては、送信側と受信側のそれぞれにネットワーク機器を設置する必要があるため、初期費用が少なからず発生します。
一方、クラウドVPNでは、導入に必要な環境がクラウド上に用意されているため、機器を設置する必要がなく、保守や運用のコストを抑えることが可能です。
Q:閉域網と専用線の違いは?
閉域網とは、通信事業者の保有する「閉ざされたネットワーク(閉域網)」のことであり、通信事業者と契約した企業のみ利用することができることから、通信の安全性を担保するものです。
一方の専用線とは、対象の拠点間を「物理的あるいは論理的に1対1で接続」することであり、外部のユーザーの影響を受けないことから、通信の速度や品質などの安定性に優れています。
インターネットVPNよりもセキュリティの強度を高めたい場合には閉域網を、通信する拠点が限定的かつ大容量のデータをやり取りするような場合には専用線を利用するのがおすすめです。
Q:無料で使えるVPN接続サービスはある?
VPN接続サービスのなかには、一部無料で利用できるものなども存在していますが、結論から言えば、これら無料のVPNサービスの使用は、可能な限り避けておくのが無難といえます。
なぜなら、無料のVPNサービスにはセキュリティレベルの低い製品も多く、なかにはサービスの管理者が利用者のデータを悪用するといったトラブルなども発生しているのが現状です。
とくに、一般的に知名度の低い製品や聞いたことのない製品を使用することは、セキュリティリスクの悪化を招く恐れがあるため、信頼の置けるサービスを利用するようにしましょう。
まとめ
本記事では、VPNの概要をわかりやすく解説するのに加えて、仕組みや種類ごとの特長から、利用することによるメリットやデメリットまで、まとめて徹底的に解説していきました。
世界的にも拡大を続けているVPN市場ですが、昨今ではリモートワークの普及やゼロトラストセキュリティの概念が広がっており、今後もさらなる市場の拡大と技術革新が予測されています。
今後もITreviewでは、VPNサービスのレビュー収集に加えて、新しいVPNサービスも続々と掲載予定となっております。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 VPN接続とは?仕組みや種類からメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 PDFを編集する方法を徹底解説!WordやExcelへの変換手順と無料でできるやり方を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>「市役所へ提出する書類をPDFで加工したい」
PDFファイルの編集を行いたい場合、基本的には有料のPDF編集ソフトを導入する必要があるため、難しいと感じる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、無料でできるPDFファイルの編集方法を、それぞれの用途や目的、デバイスの種類(パソコンやスマホ)ごとに徹底解説していきます。
この記事を読むだけで、PDFファイルを編集する方法を最短で理解することができるため、PDF編集で困ったときの参考としてお役立てください!
PDFは初心者でも無料で編集・加工できる!

PDFファイルは、もともと「勝手に編集することができない」という特徴から、物理的な印刷物に最も近しいデータファイル形式と言われてきました。
しかし、近年のセキュリティ技術の向上により、最近では、誰でも簡単に編集することができるソフトやブラウザサービスなども数多く登場しています。
なかでも特にオススメの方法は、利用者が多く無料でPDFファイルを編集することができる「ブラウザ(オンラインサービス)を使った方法」です。
インストールの必要がないため、ネット環境とパソコン(WindowsもしくはMac)さえあれば誰でも簡単にPDFファイルを編集することが可能です。
PDFをブラウザで編集する方法(基本の編集)

PDFファイルをブラウザ(オンラインサービス)で編集したい場合、テキストの修正や新規追加などの基本の編集には「Smallpdf」の利用がオススメです。
ブラウザタイプのPDF編集サービスには機能性に乏しいツールも多いなか、本サービスでは既存の文章の削除や修正などの加工を行うことができます。
1.編集前のPDFファイルを読み込む方法

エディターページから、編集したい対象のPDFファイルを「読み込み(インポート)」します。
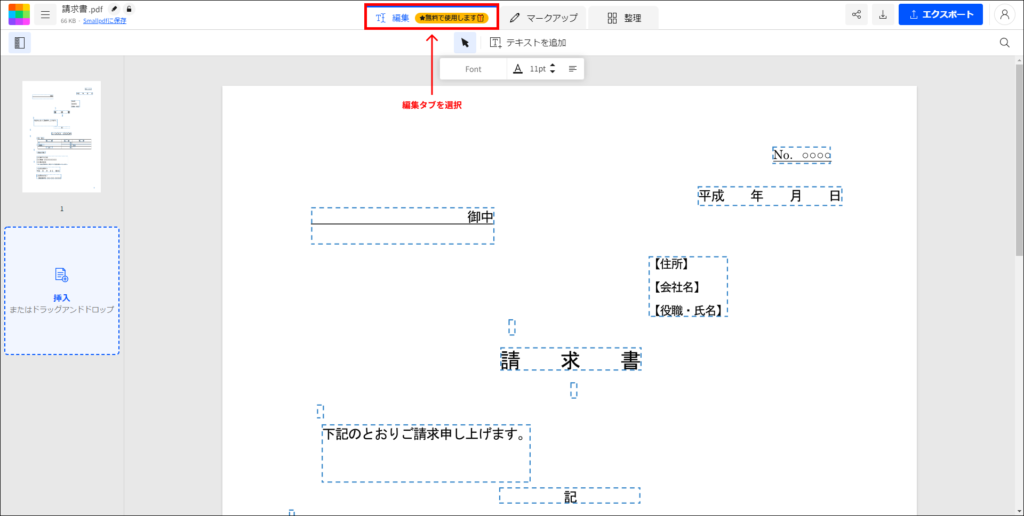
編集タブを選択して、実際にPDFファイル内部のコンテンツのテキストを編集していきます。
2.編集後のPDFファイルを保存する方法
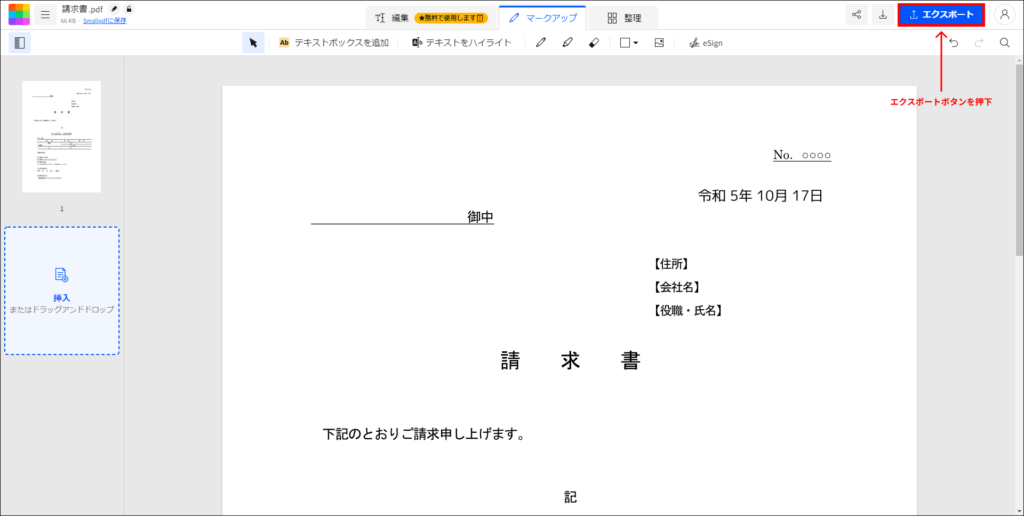
画面右上のエクスポートボタンを押下して、保存したいファイルの種類や拡張子の種類を選択します。
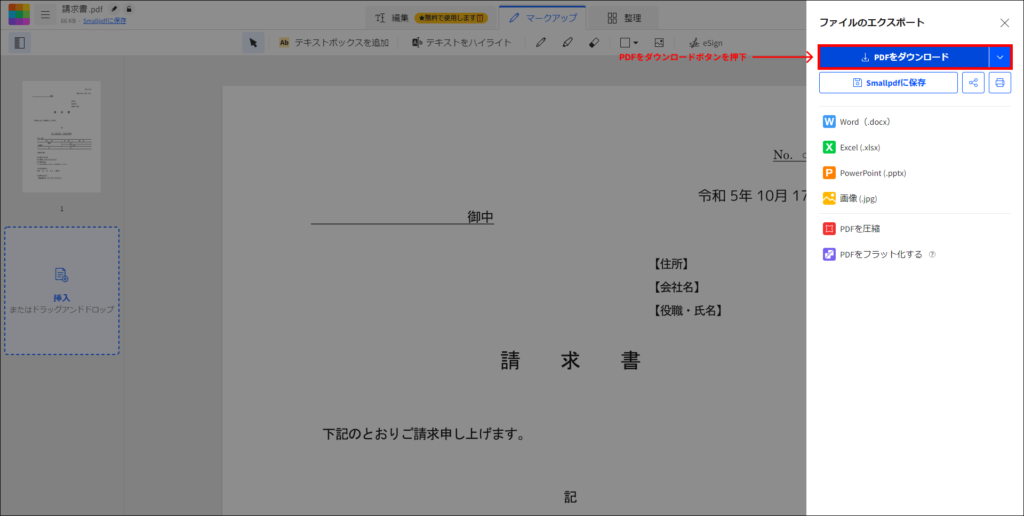
右側プルダウンからDropboxやGoogleクラウドなどのクラウドストレージへ保存することも可能です。
3.既存の文字(テキスト)を修正する方法
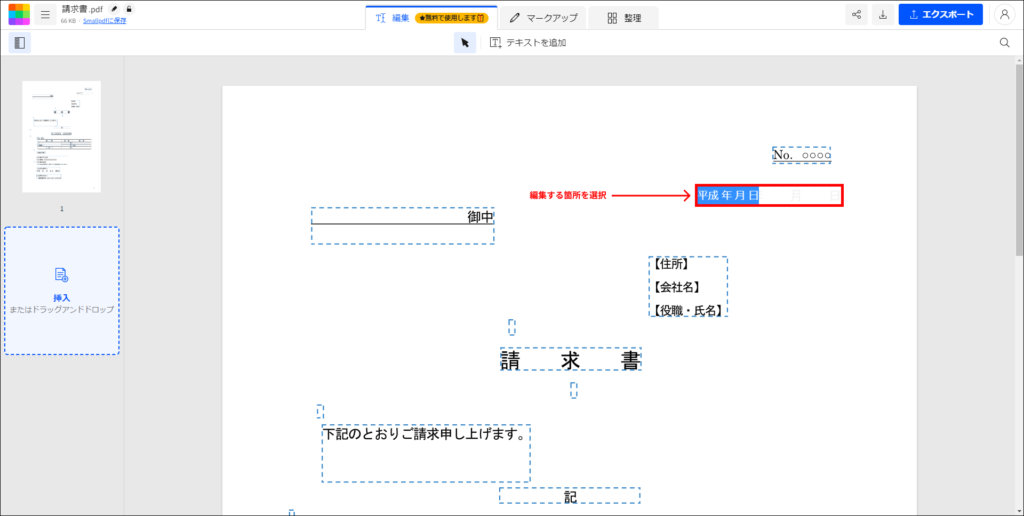
編集したい箇所のテキストボックスを選択します。
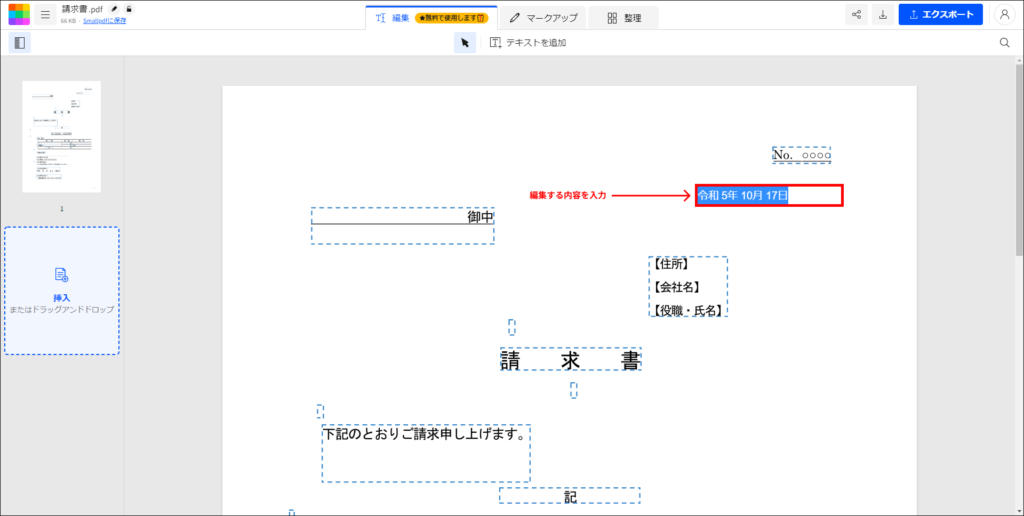
編集したい内容をテキストボックスに入力します。
4.新規で文字(テキスト)を追加する方法

上段の「テキストを追加」ボタンを押下します。
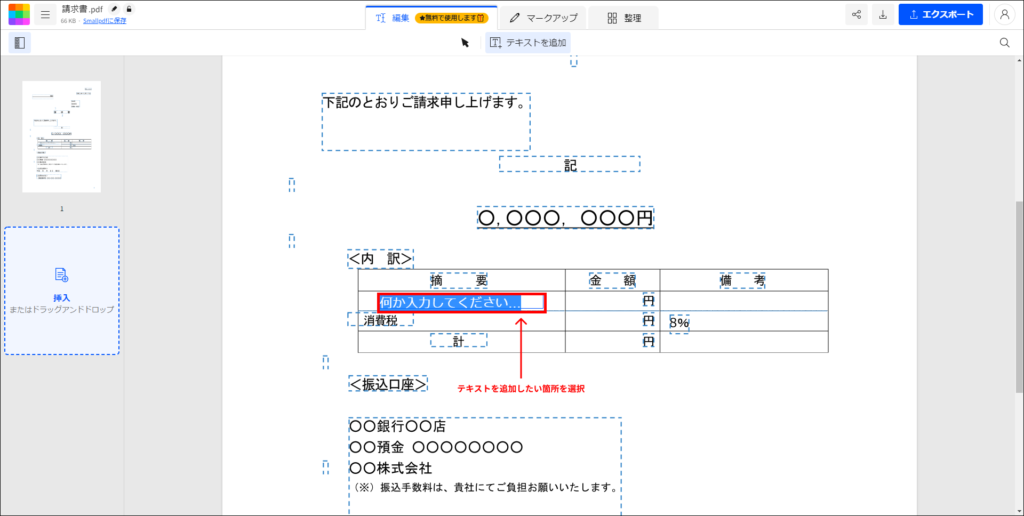
テキストを追加したい箇所を選択します。
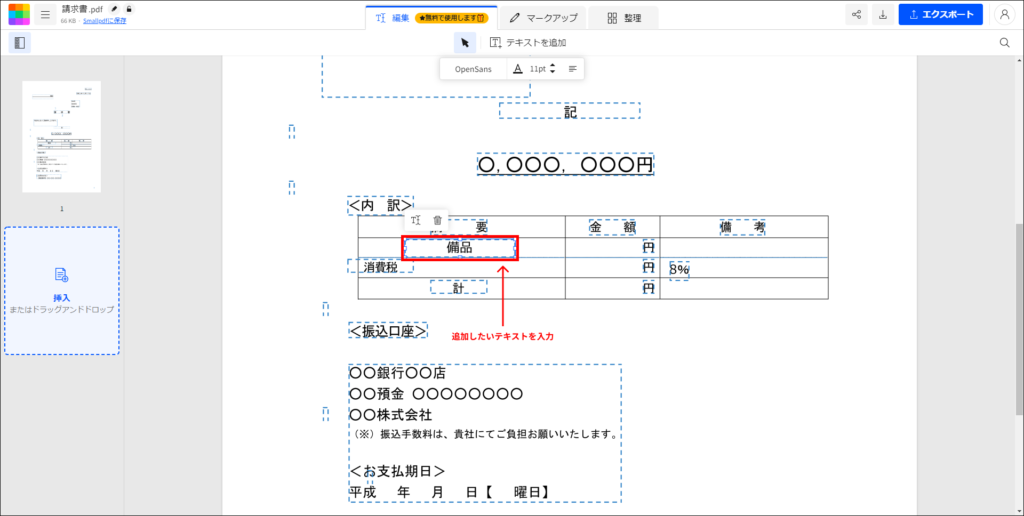
追加したいテキストの内容を入力します。
5.フォントやサイズを変更する方法
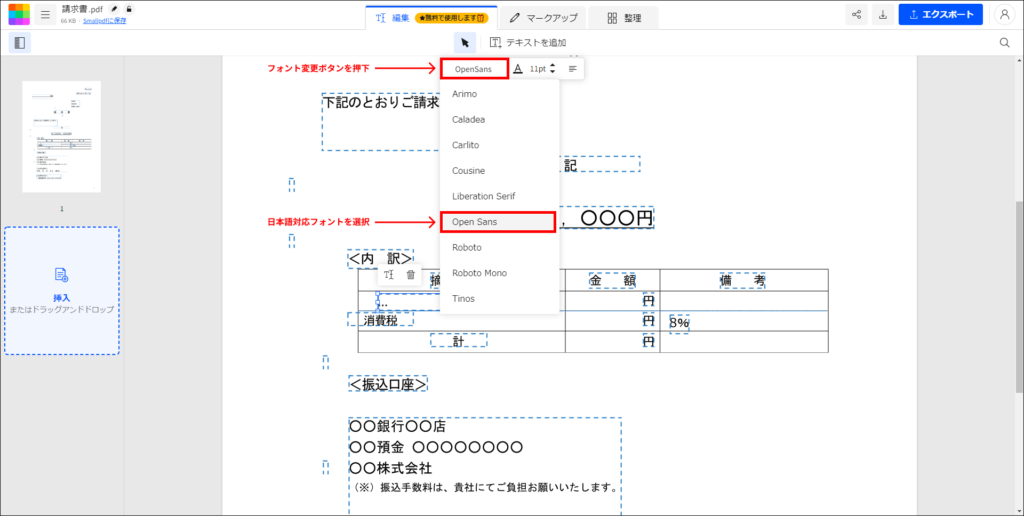
フォント変更ボタンから、日本語対応フォント(Open SansやRoboto)を選択します。
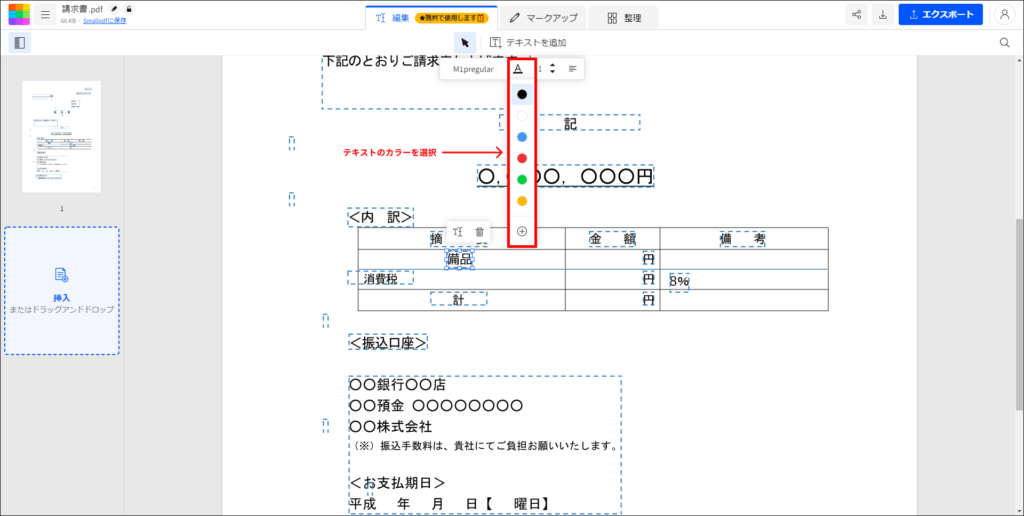
フォントのカラーは、フォント変更ボタンの右側メニューから変更することができます。
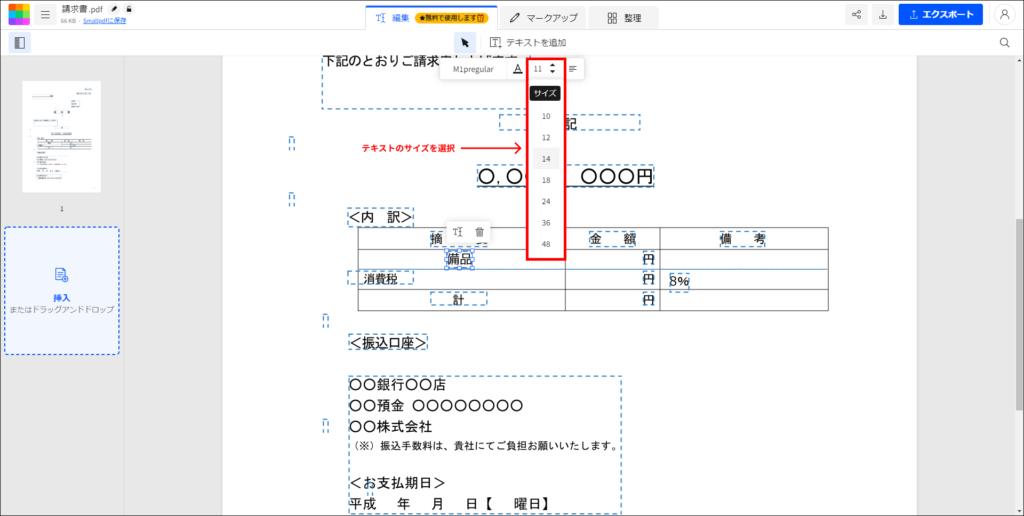
フォントのサイズも、フォント変更ボタンの右側メニューから変更することができます。
6.図形や画像を挿入する方法
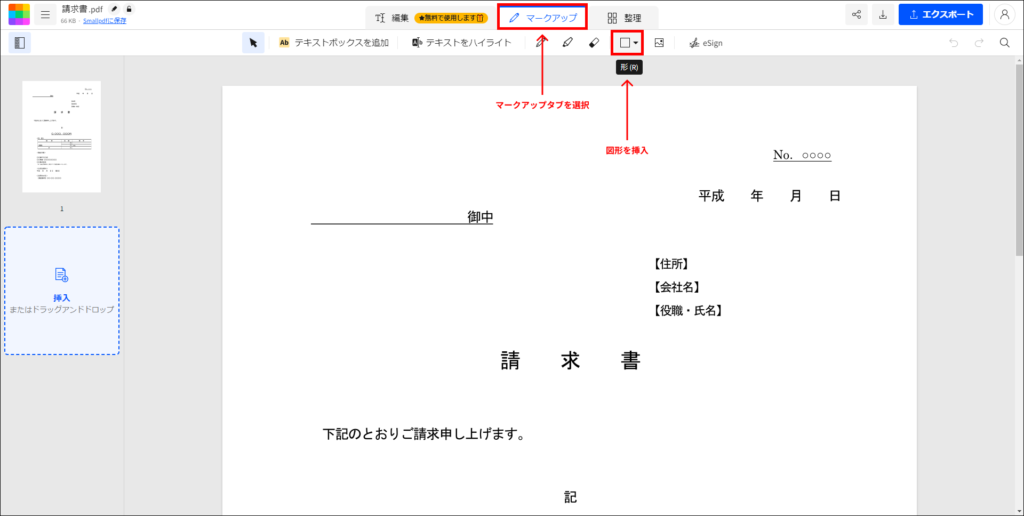
マークアップを選択後、図形の挿入ボタンを押下することで、任意の図形を挿入することができます。
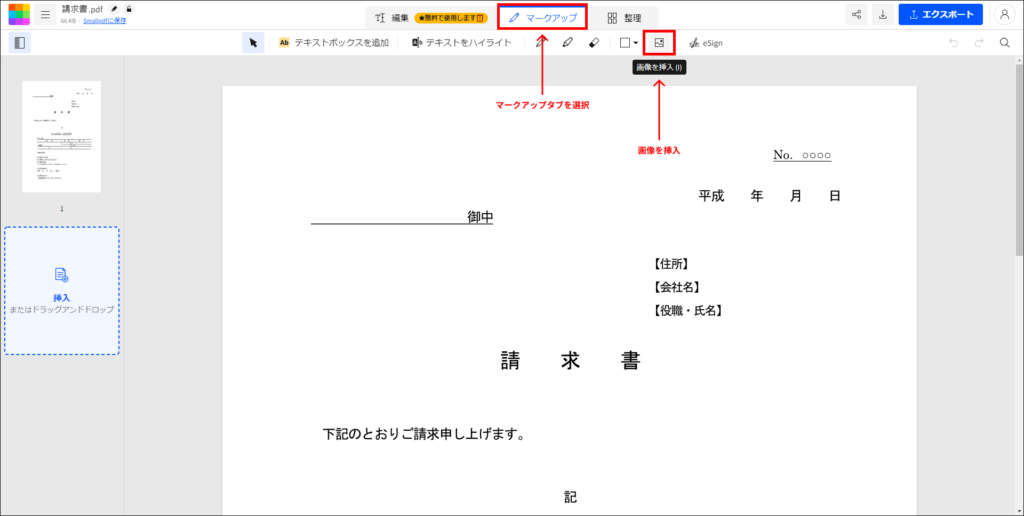
マークアップを選択後、画像の挿入ボタンを押下することで、任意の画像を挿入することができます。
7.ページの削除と追加する方法
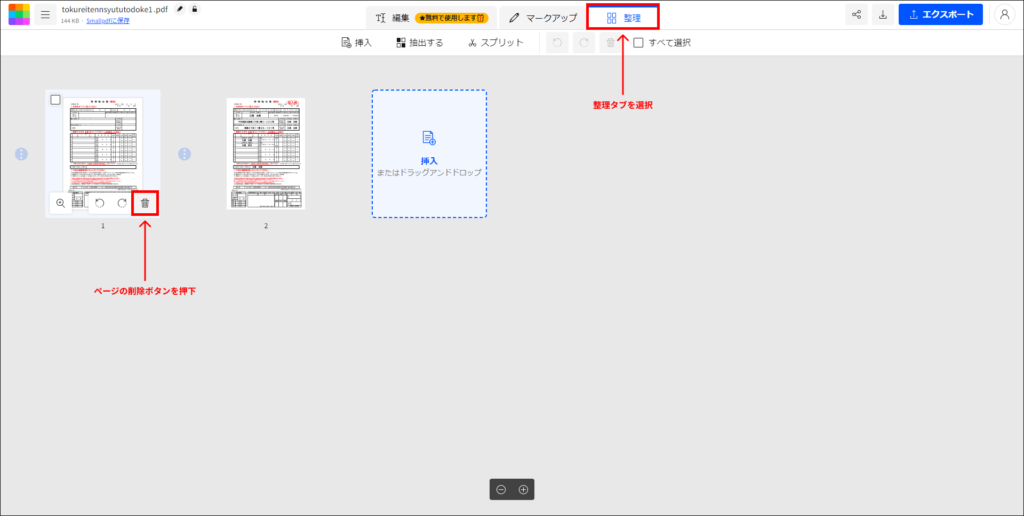
整理タブを選択後、対象のページにカーソルを合わせて削除ボタンを押下することで、任意のページを削除することができます。
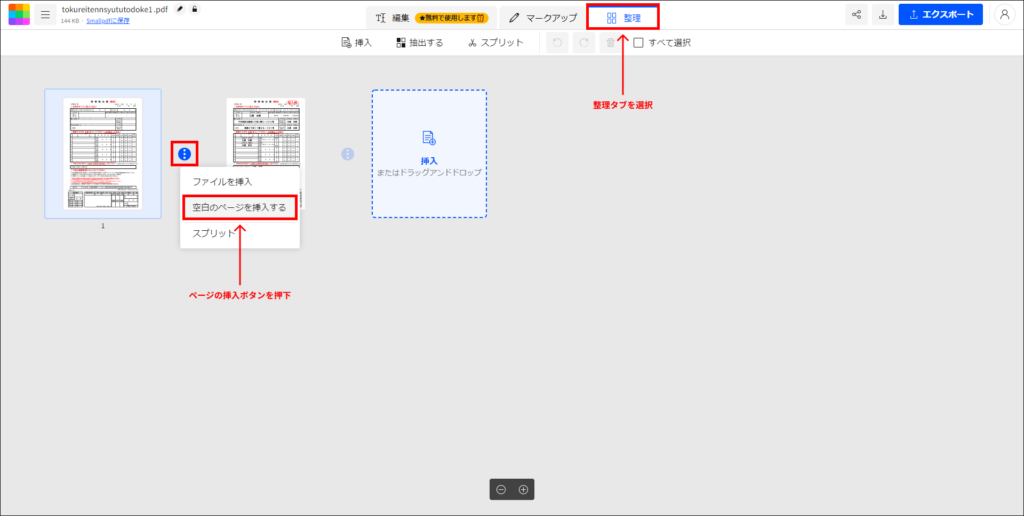
整理タブを選択後、対象の空白にカーソルを合わせて挿入ボタンを押下することで、空白のページを挿入することができます。
8.ページに番号を追加する方法

ページ番号の追加ページから、対象のPDFファイルを「読み込み(インポート)」します。

ページ内の番号を追加したい場所を選択して「ページ番号付け」ボタンを押下します。
PDFをブラウザで編集する方法(高度な編集)
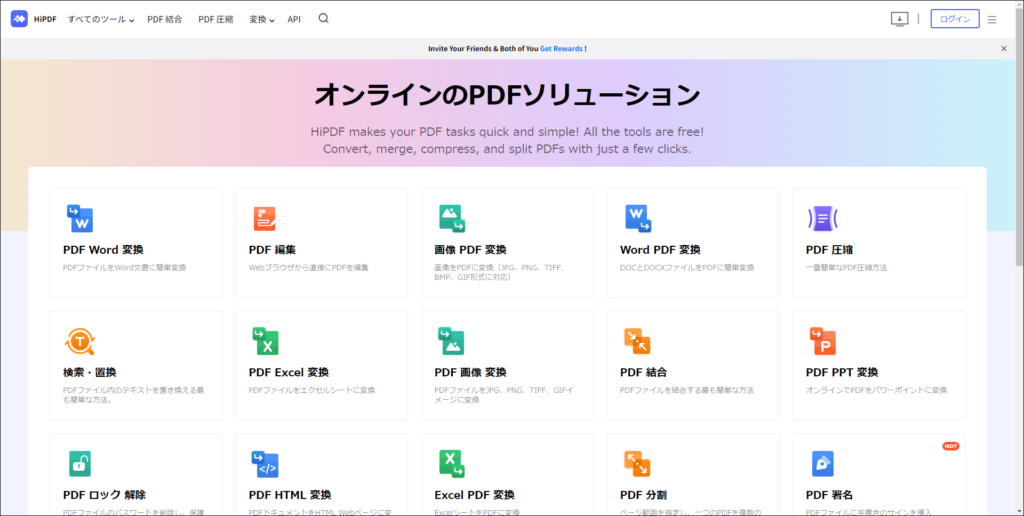
PDFファイルをブラウザ(オンラインサービス)で編集したい場合、墨消しやページ番号の付与などの高度な編集には「HiPDF」の利用がオススメです。
実際の編集画面についても、非常にシンプルなユーザーインターフェースで設計されているため、初心者の場合でも簡単かつ直感的な操作が可能です。
ただし、編集可能なファイルが限られており、ファイルサイズが10MB(メガバイト)を超えるものは編集することができないため、注意しておきましょう。
1.墨消し(黒塗り)する方法

PDFファイルの墨消し(黒塗り)は、こちらのページから行うことができます。
2.切り取り(トリミング)する方法
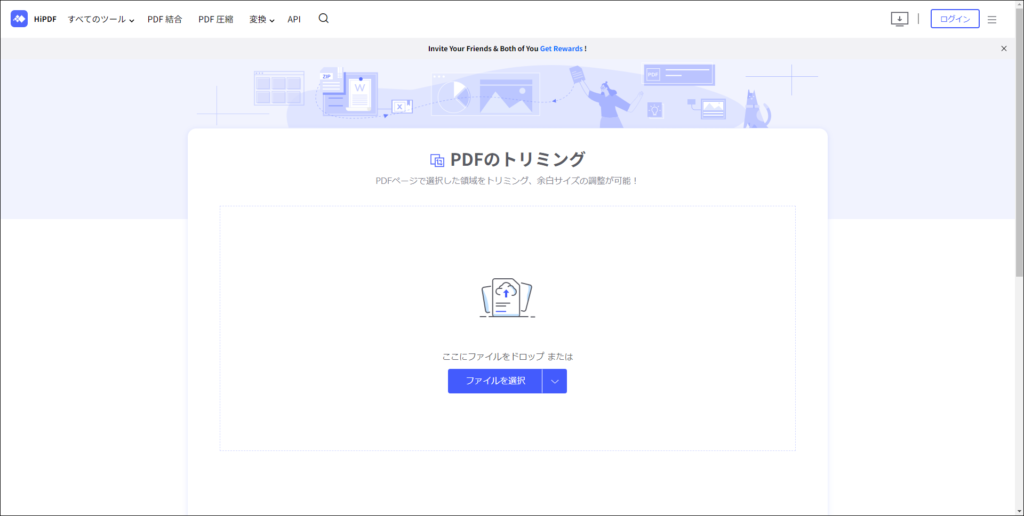
PDFファイルの切り取り(トリミング)は、こちらのページから行うことができます。
3.ページを分割する方法
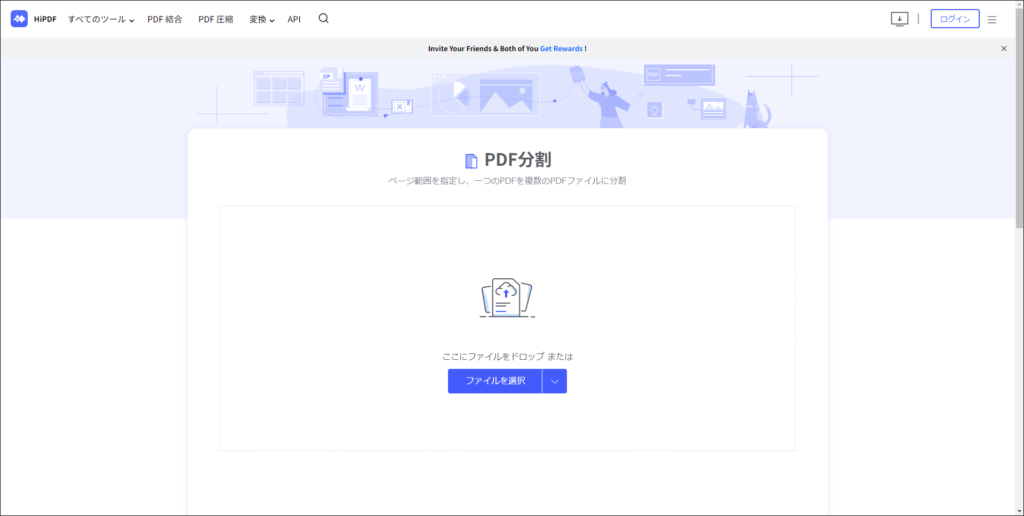
PDFファイルの分割は、こちらのページから行うことができます。
4.ページを結合する方法
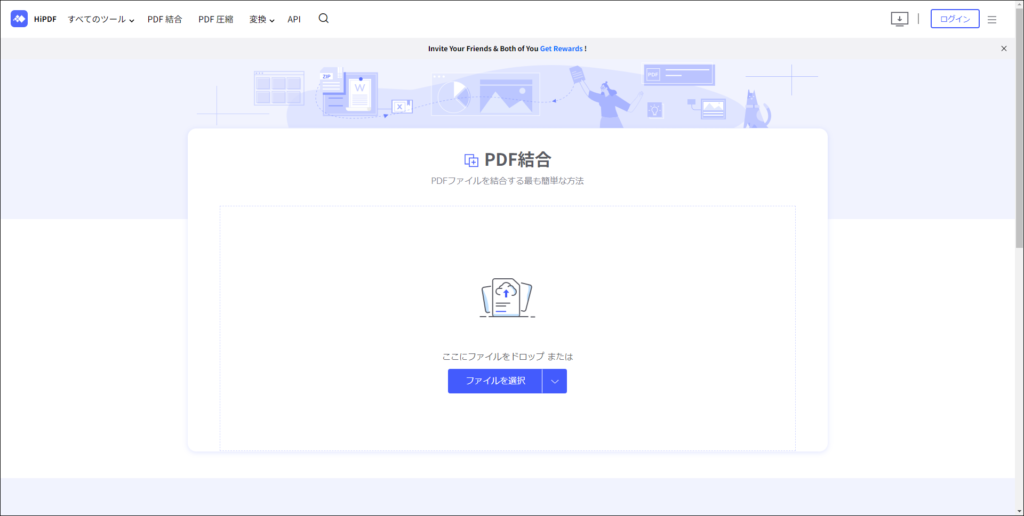
PDFファイルの結合は、こちらのページから行うことができます。
5.ページを圧縮する方法
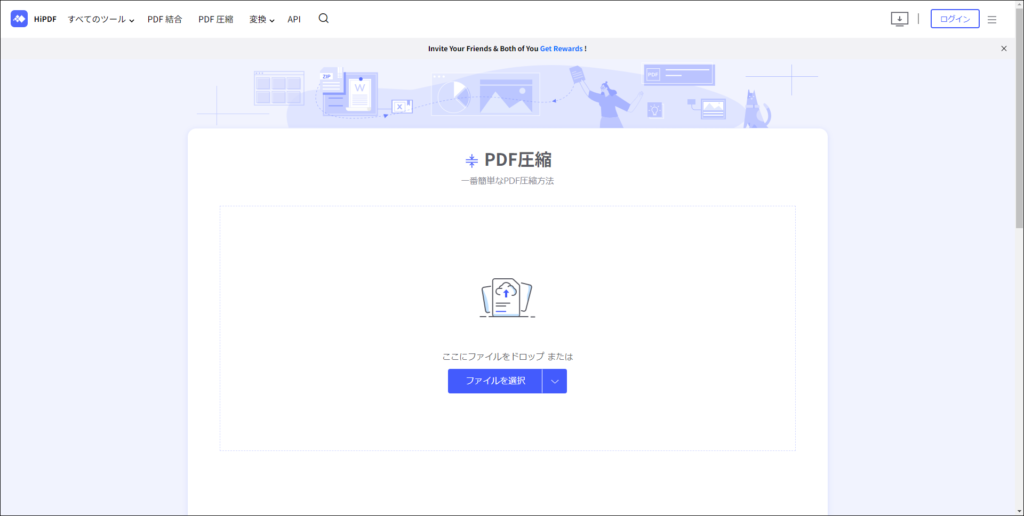
PDFファイルの圧縮は、こちらのページから行うことができます。
PDFを無料のフリーソフトで編集する方法
無料で使えるPDF編集ソフトには数多くの製品がありますが、今回はWondershare社の提供する「PDFelement」を使って解説します。
本製品には無料版と有料版の2つの種類がありますが、基本的な編集やページの結合など、無料版でも十分な機能を利用することが可能です。
1.フリーソフトの「PDFelement」をダウンロードする
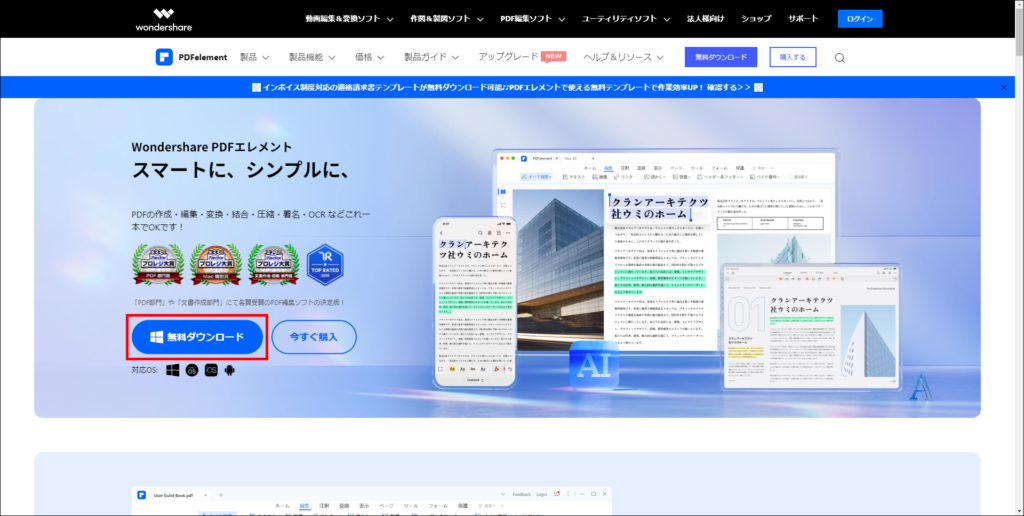
こちらのページから、製品の無料版をダウンロードします。
2.フリーソフトの「PDFelement」をインストールする

ダウンロードしたファイルを開き、パソコンへインストールします。
3.実際のファイル編集にはユーザーガイドを活用する
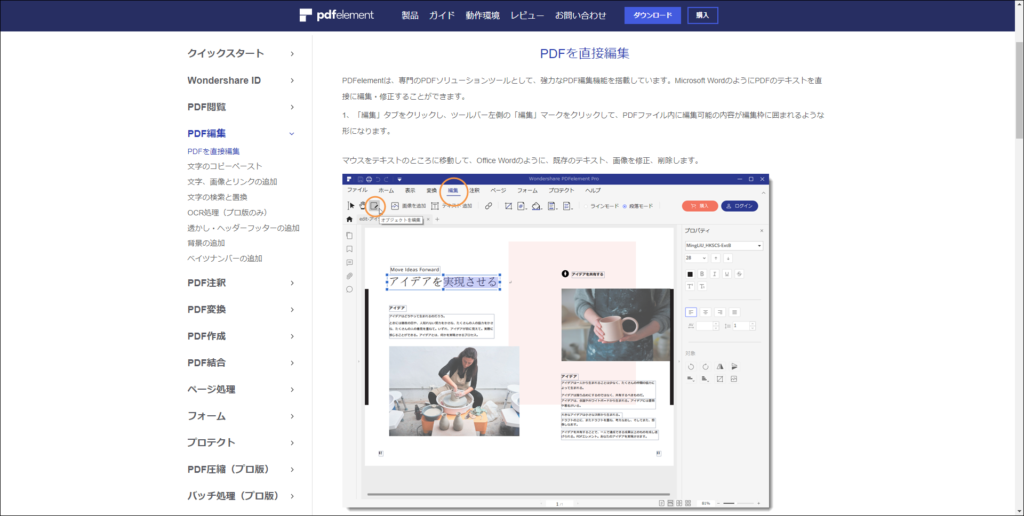
公式からユーザーガイドが配布されているため、編集操作で困った際には活用してみましょう。
4.スマホ(iPhone/Android)版も無料で利用できる

スマホ(iPhone/Android)版のアプリも用意されているため、パソコンを持っていない場合でも編集することが可能です。
▶ iOS版「PDFelement」はこちら
▶ Android版「PDFelement」はこちら
PDFをWord(ワード)へ変換する方法
すでにパソコン上にWordがインストールされている場合には、Wordを使った編集が便利です。
ソフトを新しくダウンロードする必要がないため、PDFファイルを簡単に編集することができます。
1.PDFファイルをWordファイルへ変換する

こちらのページから、編集したいPDFファイルをWordファイル(.docx)の形式に変換します。
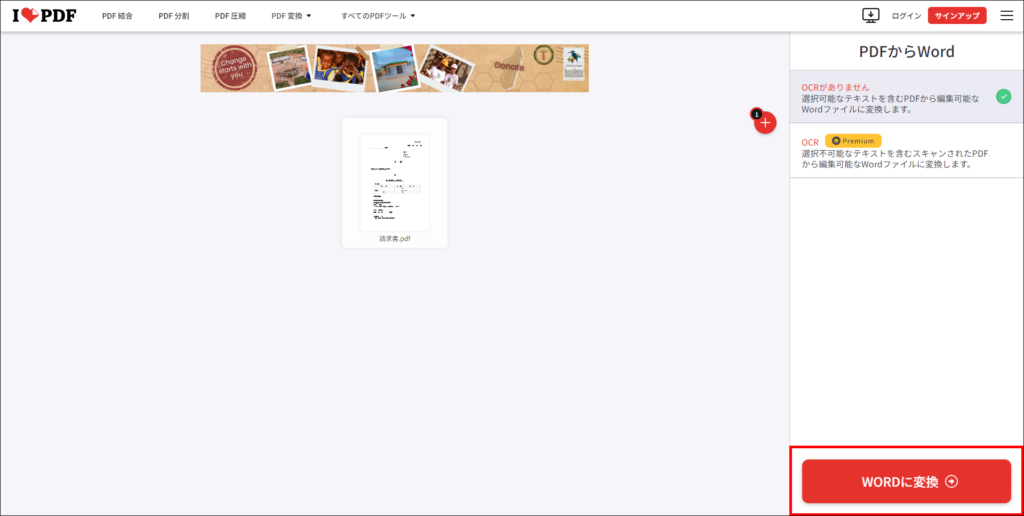
PDFファイルをドラッグ&ドロップで読み込ませ、右下の「WORDに変換」を押下します。
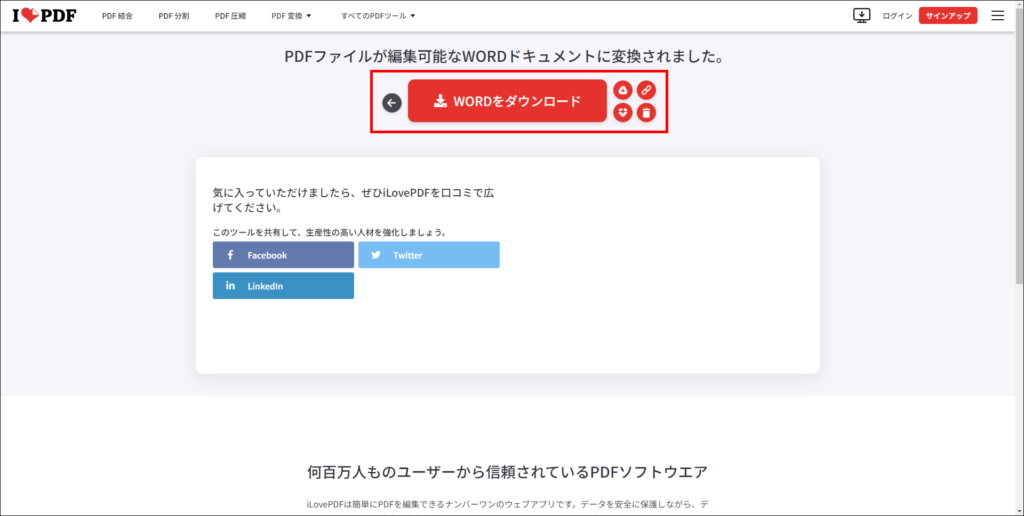
変換が完了したら、画面中央の「WORDをダウンロード」を押下し、ファイルを保存します。
2.対象の修正箇所をWordを使って編集する
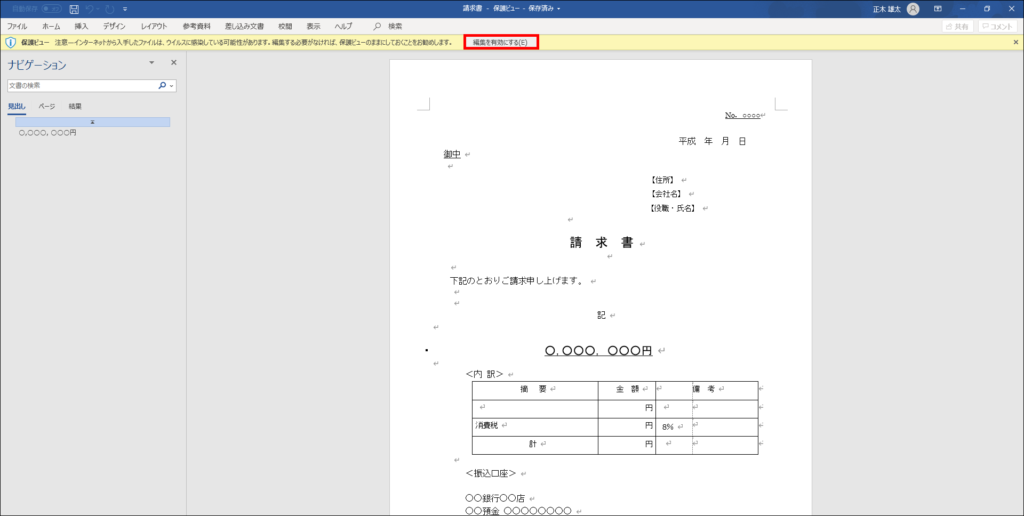
画面上部の「編集を有効にする」を押下し、Wordファイルの編集のロックを解除します。
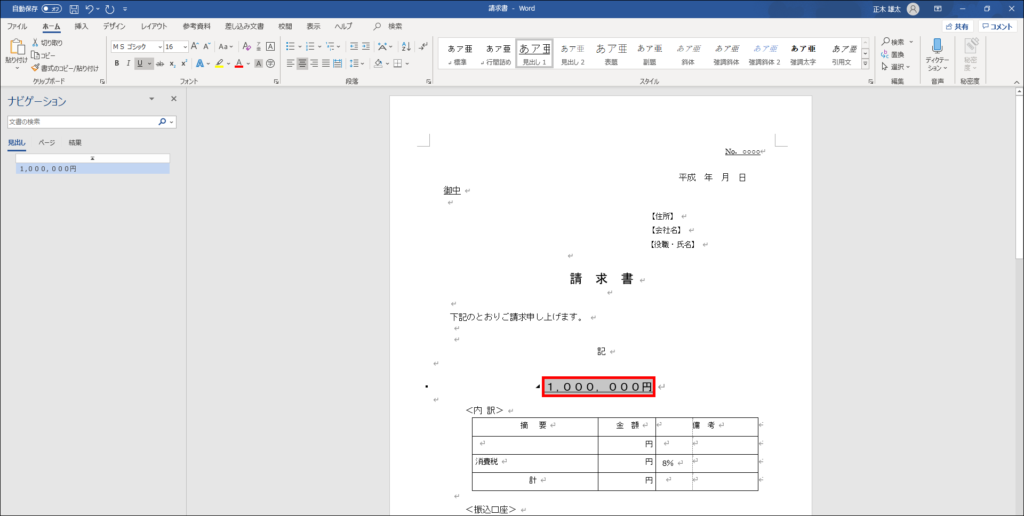
レイアウトが崩れていないかを確認して、Wordファイル内の任意の箇所を編集します。
3.WordファイルをPDFファイルへ変換する
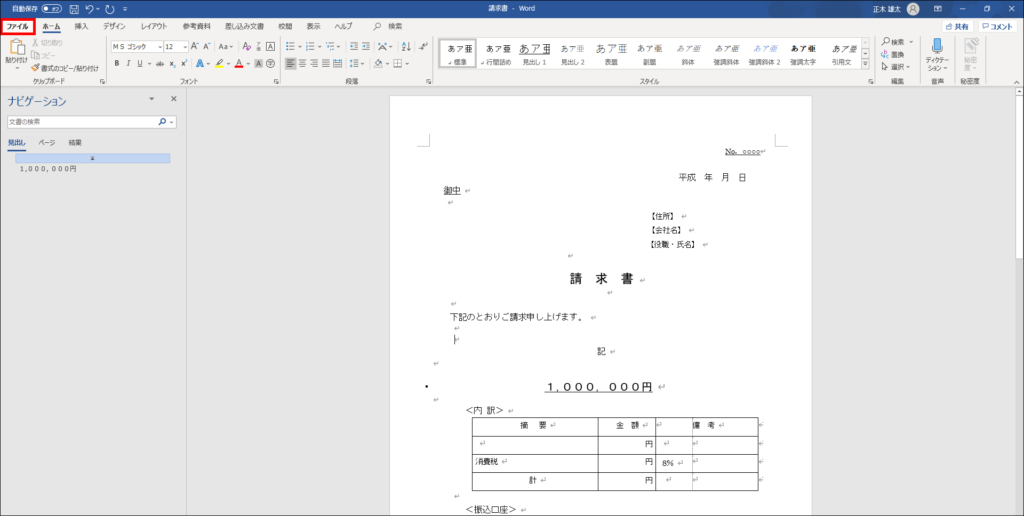
左上のファイルボタンを押下して「名前を付けて保存」を選択します。
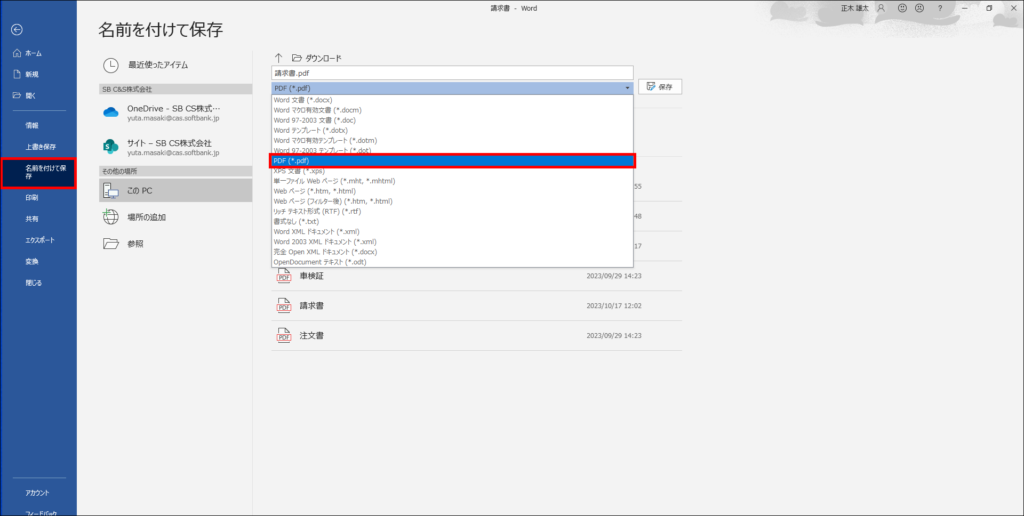
ダウンロード先を選択し、ファイル形式を「PDF」に変更して保存します。
PDFをExcel(エクセル)へ変換する方法
PDFファイル内にある複雑な表やテーブルなどを編集したい場合には、Excelを使った編集が便利です。
セルの結合や関数などを使用することができるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
1.PDFファイルをExcelファイルへ変換する
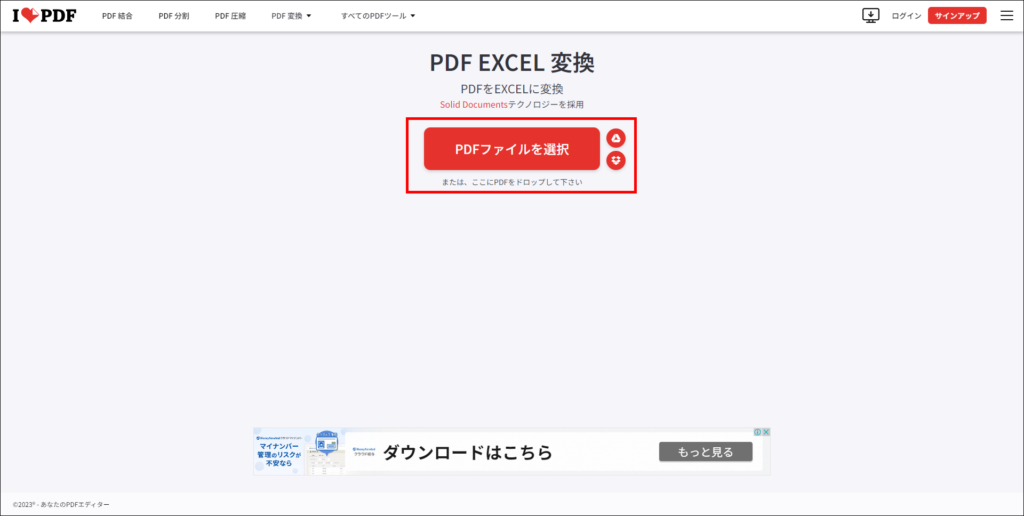
こちらのページから、編集したいPDFファイルをExcelファイル(.xlsx)の形式に変換します。

PDFファイルをドラッグ&ドロップで読み込ませ、右下の「EXCELに変換」を押下します。
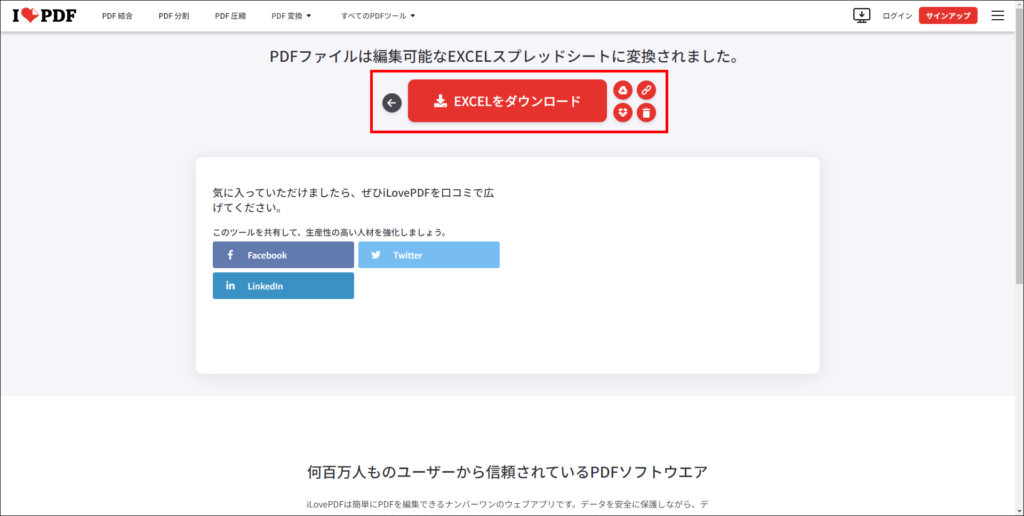
変換が完了したら、画面中央の「EXCELをダウンロード」を押下し、ファイルを保存します。
2.対象の修正箇所をExcelを使って編集する
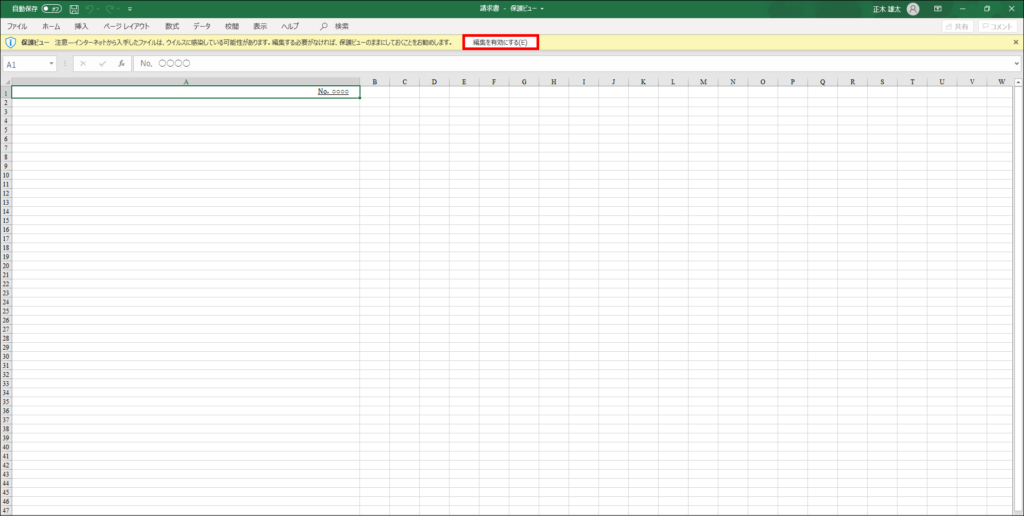
画面上部の「編集を有効にする」を押下し、Excelファイルの編集のロックを解除します。
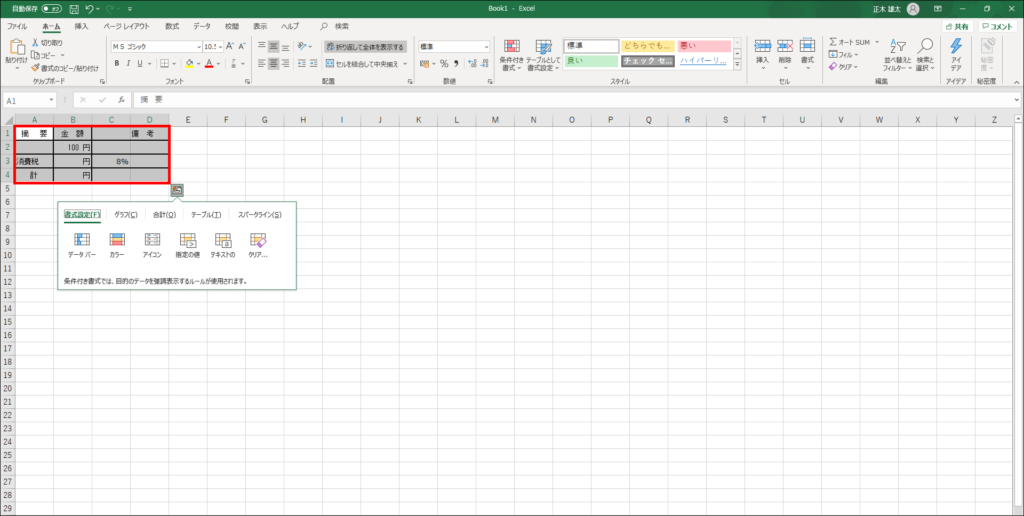
レイアウトが崩れていないかを確認して、Excelファイル内の任意の箇所を編集します。
3.ExcelファイルをPDFファイルへ変換する
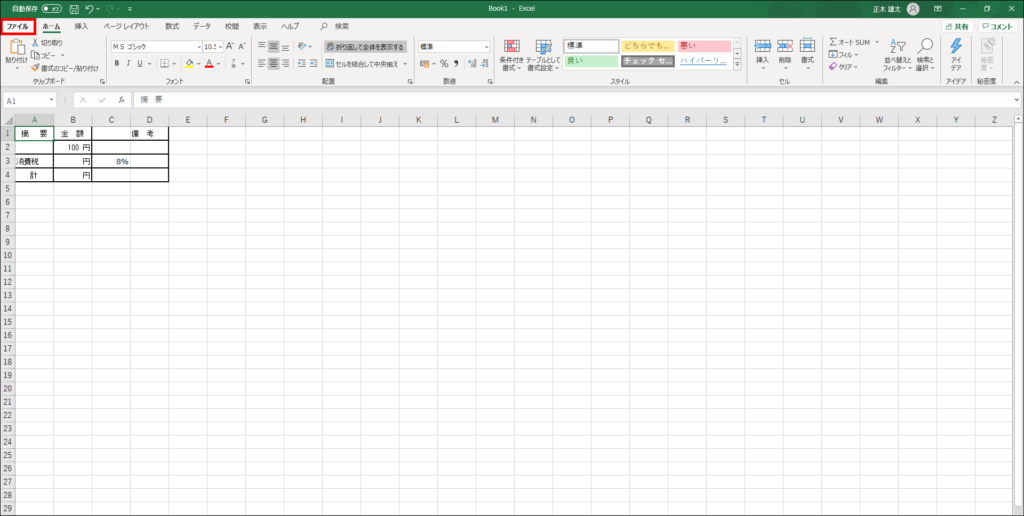
左上のファイルボタンを押下して「名前を付けて保存」を選択します。
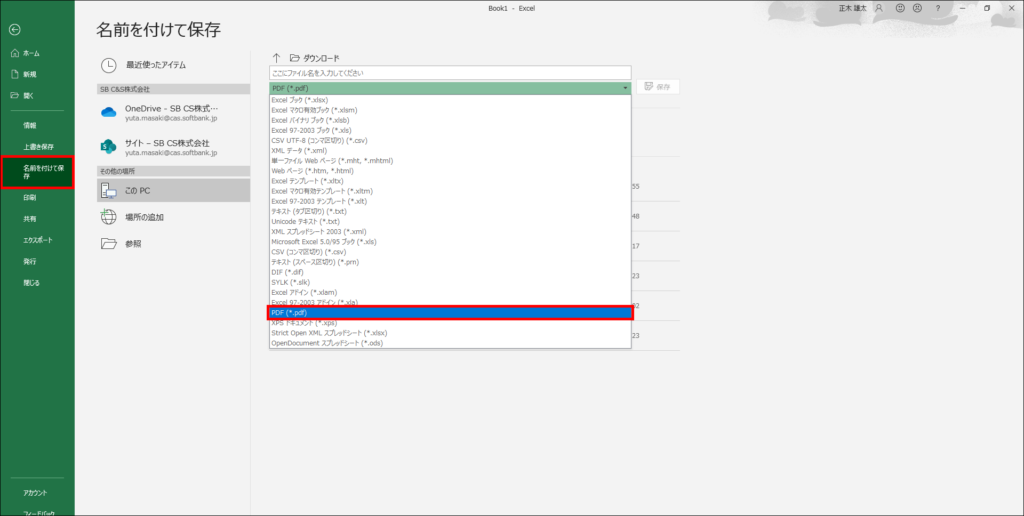
ダウンロード先を選択し、ファイル形式を「PDF」に変更して保存します。
PDFをPowerPoint(パワポ)へ変換する方法
PDFを編集する方法には、WordやExcelのほか、PowerPointを使ったパターンも存在します。
PDFで受け取った資料を流用してスライドを作成する場合などには、こちらも便利な方法です。
1.PDFファイルをPowerPointファイルへ変換する
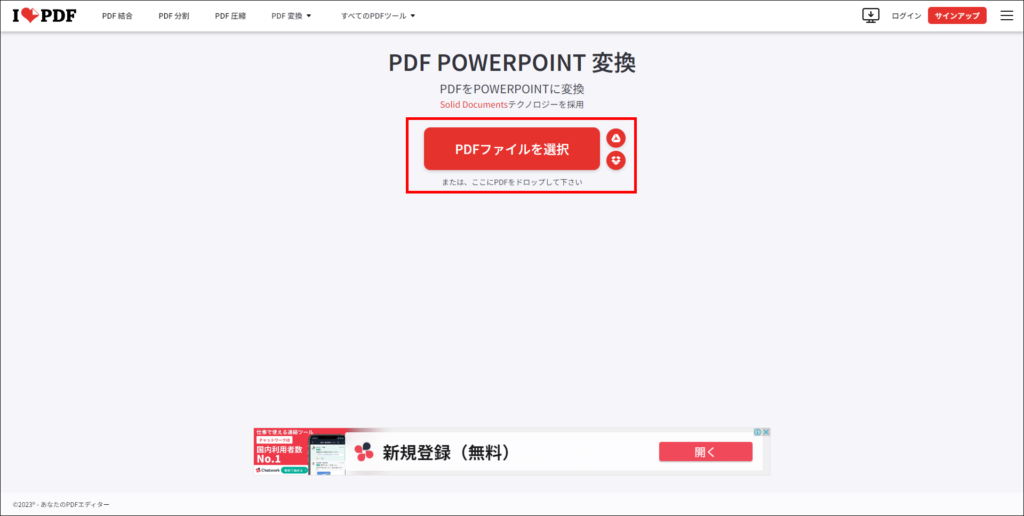
こちらのページから、編集したいPDFファイルをPowerPointファイル(.pptx)の形式に変換します。
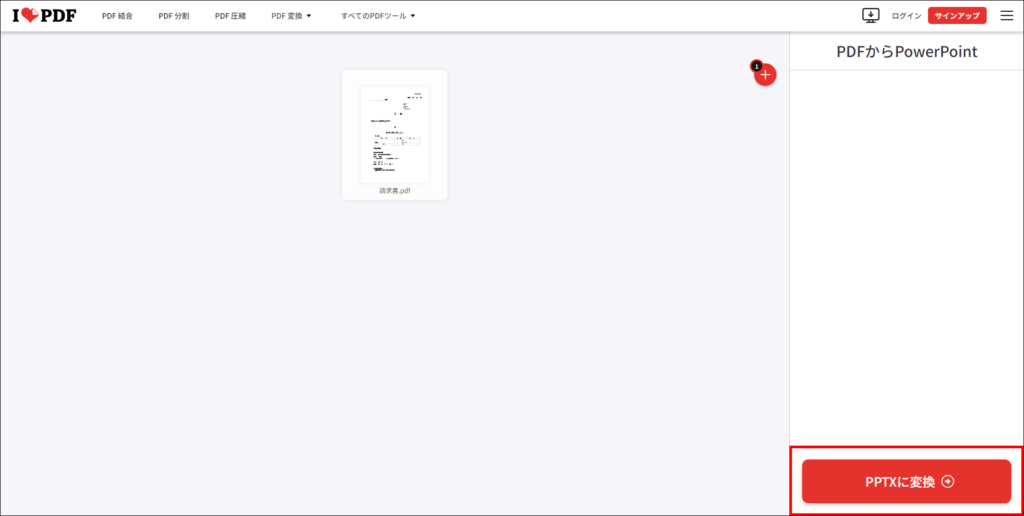
PDFファイルをドラッグ&ドロップで読み込ませ、右下の「PPTXに変換」を押下します。

変換が完了したら、画面中央の「POWERPOINTをダウンロード」を押下し、ファイルを保存します。
2.対象の修正箇所をPowerPointを使って編集する
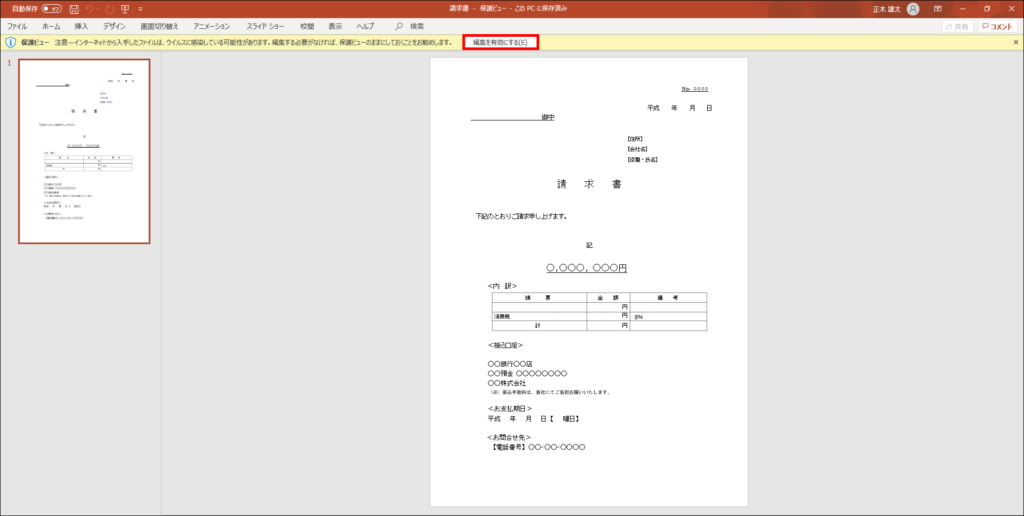
画面上部の「編集を有効にする」を押下し、PowerPointファイルの編集のロックを解除します。
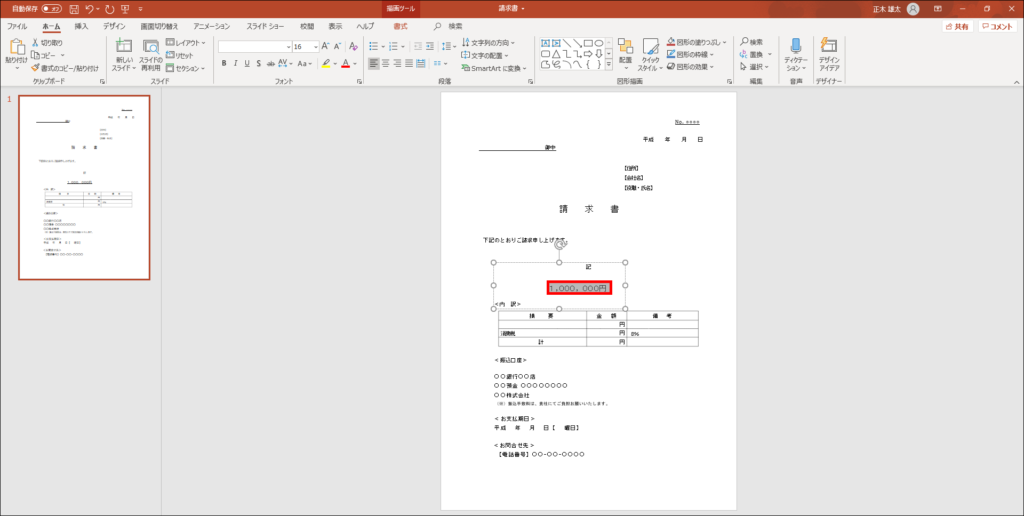
レイアウトが崩れていないかを確認して、PowerPointファイル内の任意の箇所を編集します。
3.PowerPointファイルをPDFファイルへ変換する
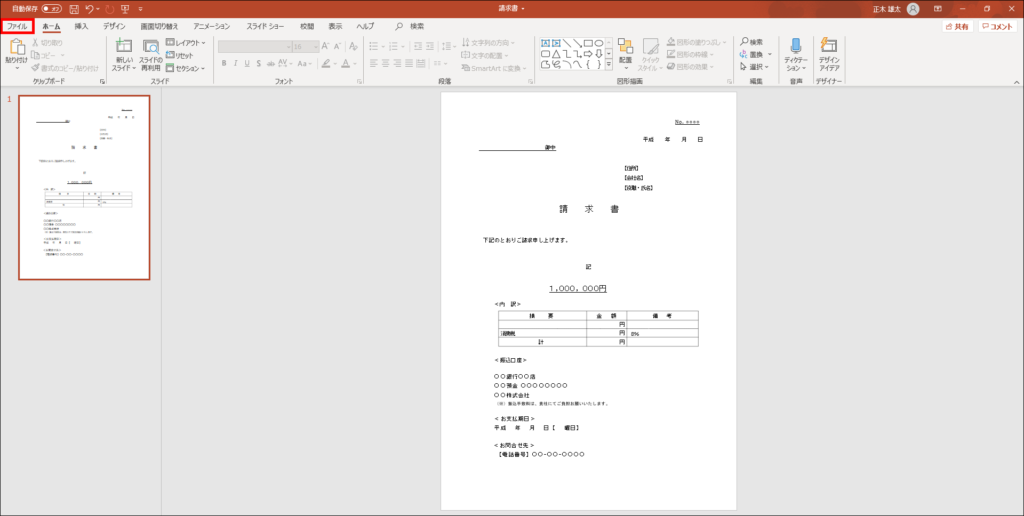
左上のファイルボタンを押下して「名前を付けて保存」を選択します。
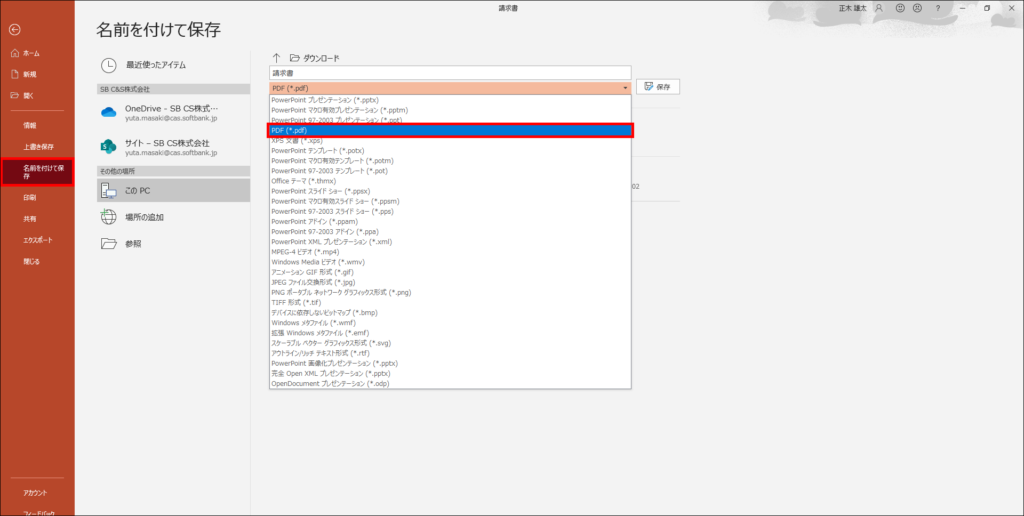
ダウンロード先を選択し、ファイル形式を「PDF」に変更して保存します。
PDFを編集するときの注意点

ロゴの透かしが入る場合がある
PDFを編集するときの注意点の1つ目としては「ロゴの透かしが入る場合がある」ということです。
無料で使えるソフトやサービスの場合、有償プランへのアップグレードを促す目的で、あえて製品ロゴの透かしを入れている製品も多くあります。
解決策としては、有料プランへのアップグレードを検討するか、もしくは編集したPDFファイルを一度jpegなどの画像ファイルへ変換して、画像編集ソフトで透かしを削除する方法などが挙げられます。
編集機能に制限が設けられている
PDFを編集するときの注意点の2つ目としては「編集機能に制限が設けられている」ということです。
先ほどの透かしと同様、無料で使えるソフトのなかには有料プランへの購入を促す目的で、あえて簡単な機能しか開放していない製品も多くあります。
解決策としては、分割やページの削除など、使いたい機能が無料で使えるソフトやサービスと併用して利用するか、使いたい機能だけを別途単品でオプションとして購入する方法などが挙げられます。
データ自体は黒塗りでは消えない
PDFを編集するときの注意点の3つ目としては「データ自体は黒塗りでは消えない」ということです。
情報を隠すための黒塗りですが、この方法は文字の上から黒い画像を被せているに過ぎないため、もともとの文字データは削除されないということです。
PDFファイルを印刷して提出する場合には大きな問題はありませんが、編集権限を付与してデータごと提出する場合、相手は黒塗りの中身の文字まで確認できてしまうため、取り扱いには注意しましょう。
レイアウトが崩れる可能性がある
PDFを編集するときの注意点の4つ目としては「レイアウトが崩れる可能性がある」ということです。
文章を作成したソフトとは異なるソフトを使用して編集した場合や、WordやExcelからインポートした場合にはレイアウトが崩れやすくなります。
また、文中のフォントが編集ソフトに存在しない場合、代替フォントに入れ替えられるため、レイアウトを崩したくない場合には、極力作成したときの環境で作業するように注意しましょう。
注釈は表示できない可能性がある
PDFを編集するときの注意点の5つ目としては「注釈は表示できない可能性がある」ということです。
メモやコメントを追記できる注釈ですが、この機能には厳密なルールが定められているわけではなく、ソフトによっては表示できない場合があります。
とくに、相手がスマートフォンからPDFを確認する場合、注釈が表示されないことも多いため、必ず目を通してもらいたい情報を注釈に記入することは、なるべく避けるようにしましょう。
PDFを編集できないときの対処法

Q:PDFの文字が入力できない
PDFファイルの文字が入力できない場合、PDFファイルにおける編集権限の保護モードが機能してしまっている可能性があります。
ツールによって操作は異なりますが、文字入力を可能にするためには、編集ソフトのセキュリティ項目からロックを解除する必要があります。
Q:PDFの文字がズレてしまう
PDFファイルの文字がズレてしまう場合、ファイル形式の変換により書類のレイアウトが崩れてしまっている可能性があります。
PDFからWordやExcelなど、別のファイル形式に変換したときに発生しやすい現象であるため、崩れてしまった箇所は手作業で修正する必要があります。
Q:PDFに手書きで書き込みしたい
PDFファイルに手書きで書き込みしたい場合、スマホやタブレットのアプリを使用することで可能になるケースもあります。
手書きでの文字入力に対応した無料のPDF編集アプリも数多く存在するため、用途や目的に合わせて自分の使いやすいツールを選ぶと良いでしょう。
Q:スキャンしたPDFを編集したい
スキャンしたPDFを編集したい場合、通常の文章データから編集可能なデータに変換する「OCR処理」を実施する必要があります。
通常「PDFelement Pro」などの有料ソフトを使用する方法が一般的ですが、一部「LightPDF OCR」などの無料ソフトでも代用が可能です。
Q:GoogleドライブにあるPDFを編集したい
GoogleドライブにあるPDFを編集したい場合、クラウドストレージから直接編集することは難しいというのが現状です。
まずは一度、HDDなどのローカルストレージにファイルをダウンロードして、ローカルな環境で編集、そこから再アップロードする必要があります。
【2024年8月】PDF編集ソフトおすすめ7選|レビュー・口コミ
PDF編集ソフトとは一口に言っても、多機能な有料ソフトから無料で使えるフリーソフトまで、さまざまな種類のサービスがあります。
ここからは、ITreviewに掲載されているPDF編集ソフト(2023年11月1日時点)から、おすすめの製品を7つほどピックアップして紹介していきます。
Adobe Acrobat DC

「Adobe Acrobat DC」は、PDFの生みの親でもあるアドビ社が提供しているPDF編集ソフトです。
クラウドサービスとなっているため、場所やデバイスを問わない編集作業が可能になるほか、作業プロセスをトラッキングすることもできます。
| レビュー数 | 1,055 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
| 提供会社 | アドビ株式会社 |
| 料金価格 | 1,518円~ |
| 製品種類 | インストール型 |
ワード、エクセル、パワーポイント等で作成した資料の印刷範囲をpdfに変換してファイル容量を圧縮して保管できるため、資料の配布や保管に便利です。
▼ 利用サービス:Adobe Acrobat DC
https://www.itreview.jp/products/acrobat-dc/reviews/172063
▼ 企業名:日本製鉄株式会社
▼ 従業員規模:1000人以上
▼ 業種:鉄・金属
CubePDF

「CubePDF」は、WordやExcelなどのOfficeソフトウェアからPDFを作成できるPDF編集ソフトです。
基本無料で利用できるため、個人や法人に関係なく編集することができます。また、仮想プリンタ形式を採用しているため、操作性にも優れています。
| レビュー数 | 324 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.1 |
| 提供会社 | 株式会社キューブ・ソフト |
| 料金価格 | 0円~ |
| 製品種類 | インストール型 |
プリンターに出力する感覚でファイルをPDF化することができます。そのため、Word・ExcelだけでなくWebサイトや基幹システムなどでも利用が可能です。
▼ 利用サービス:CubePDF
https://www.itreview.jp/products/cubepdf/reviews/154683
▼ 企業名:湖国精工株式会社
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:一般機械
DocuWorks
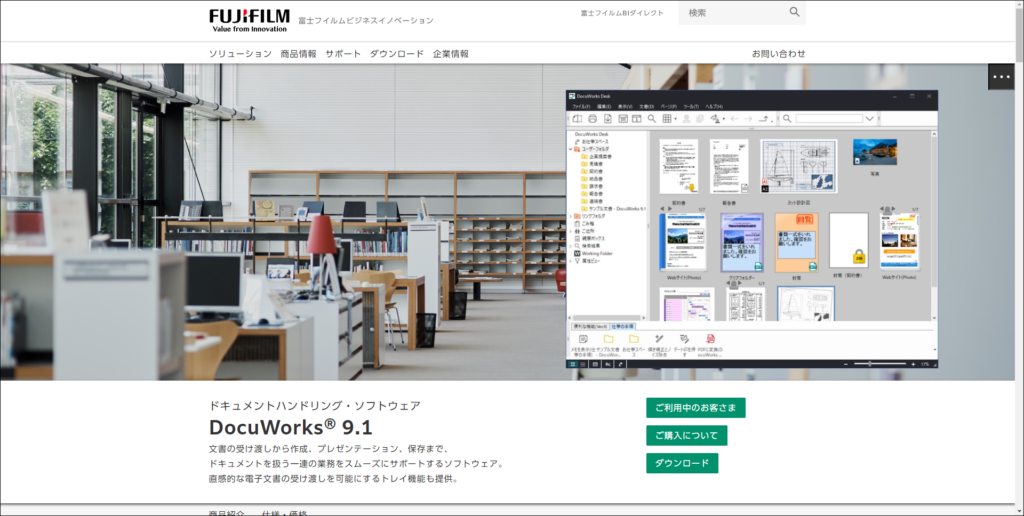
「DocuWorks」は、富士フイルムビジネスイノベーションから提供されているPDF編集ソフトです。
紙の書類を扱うような感覚で文章データを管理・編集することができるため、中小企業などの初めての導入シーンにもオススメできる製品です。
| レビュー数 | 173 |
| 満足度 | ★★★★☆ 3.9 |
| 提供会社 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 |
| 料金価格 | 800円~ |
| 製品種類 | インストール型 |
エクセルやワード、専門のプログラム等でアウトプットした文書データを一式にまとめる時に重宝しています。また、DocuWorks上でコメント追記等のある程度の編集機能が備わっており、編集ツールとしても使えます。
▼ 利用サービス:DocuWorks
https://www.itreview.jp/products/docuworks/reviews/149879
▼ 企業名:有限会社レン構造設計事務所
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:建築・鉱物・金属
CubePDF Utility
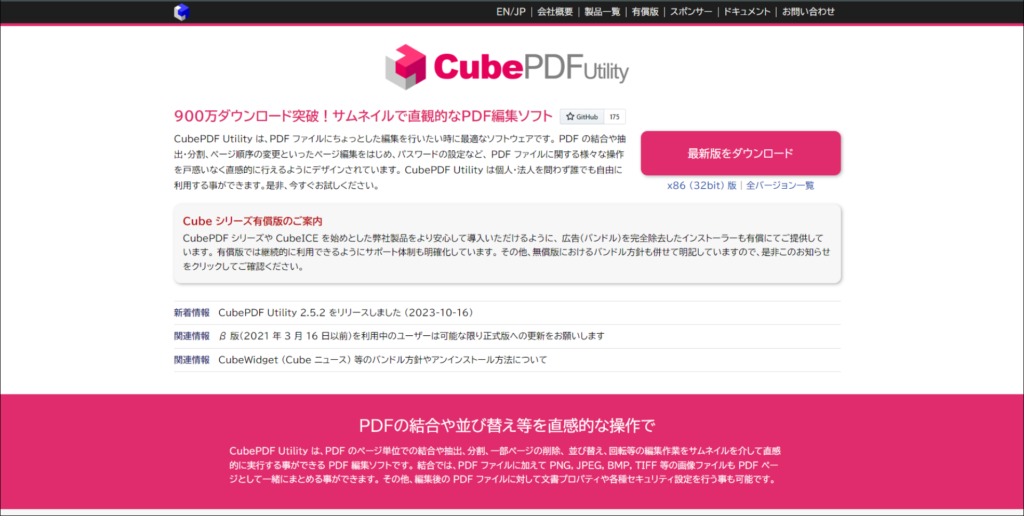
「CubePDF Utility」は、特定の箇所を少しだけ編集したい場合に便利に使えるPDF編集ソフトです。
ファイルの結合やページの分割、テキストの編集やパスワードの設定など、ピンポイントで修正したい機能だけを個別に利用することができます。
| レビュー数 | 168 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |
| 提供会社 | 株式会社キューブ・ソフト |
| 料金価格 | 0円~ |
| 製品種類 | インストール型 |
内容を確認しながらページ構成を触れる点が非常に使い易いです。なので縦横回転編集や、挿入削除の基本操作が効率的に行えます。あと、地味に自動バックアップは助かります。
▼ 利用サービス:CubePDF Utility
https://www.itreview.jp/products/cubepdf-utility/reviews/138383
▼ 企業名:株式会社システムライフ
▼ 従業員規模:50-100人未満
▼ 業種:情報通信・インターネット
Foxit PDF Editor

「Foxit PDF Editor」は、Adobeに次いで世界第二位のダウンロード数を誇るPDF編集ソフトです。
安定性や高速性はもちろんのこと、AIアシスタントの実装により、人工知能を活用した編集作業の効率化を実現させることができます。
| レビュー数 | 103 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |
| 提供会社 | 株式会社FoxitJapan |
| 料金価格 | 8,690円~ |
| 製品種類 | インストール型 |
PDFファイルの画像編集、文字修正により契約書等を紙に印刷することなくデータ上で必要事項を記入して相手に返送できます。会社印の画像ファイルを用意しておけば押印の手間も省けます。
▼ 利用サービス:Foxit PDF Editor
https://www.itreview.jp/products/foxit-editor/reviews/166512
▼ 企業名:ウインクレル株式会社
▼ 従業員規模:50-100人未満
▼ 業種:総合卸売・商社・貿易
いきなりPDF

「いきなりPDF」は、高性能と低価格を両立させたコスパに優れるPDF編集ソフトです。
国産のPDF編集ソフトとなっているため、操作マニュアルや各種サポート体制が充実しており、初心者の場合でも安心して利用することができます。
| レビュー数 | 102 |
| 満足度 | ★★★★☆ 3.7 |
| 提供会社 | ソースネクスト株式会社 |
| 料金価格 | 0円~ |
| 製品種類 | インストール型 |
数ページのPDFファイルの必要なページだけを残していらないページを削除したり、複数の違うPDFファイルの結合して、並べ替えることが簡単にできるので、書類編集に最適です。
▼ 利用サービス:いきなりPDF
https://www.itreview.jp/products/ikinaripdf/reviews/167774
▼ 企業名:Sekisui Integrated Research Inc.
▼ 従業員規模:20-50人未満
▼ 業種:その他製造業
PDF-XChange Viewer
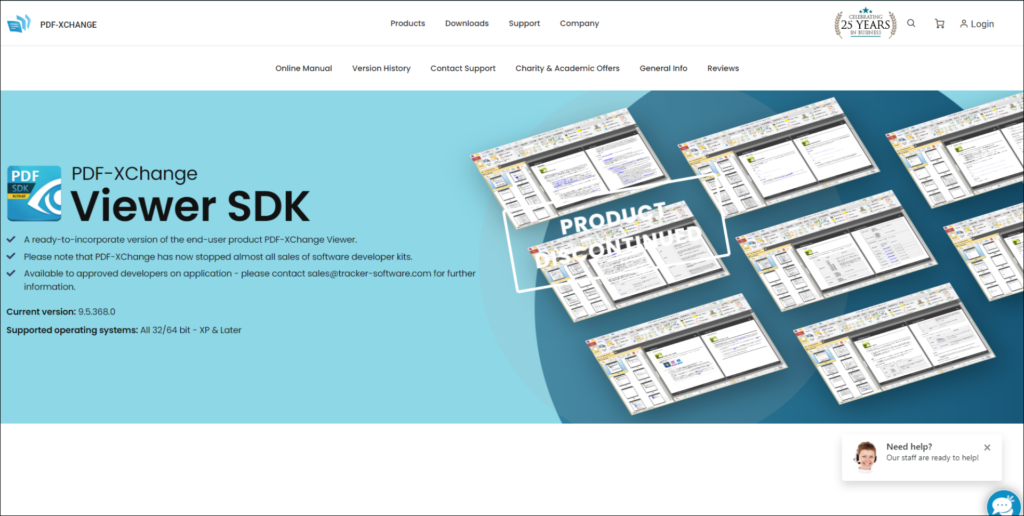
「PDF-XChange Viewer」は、PDFの閲覧から編集まで幅広く対応できるPDF編集ソフトです。
機能性に優れていることはもちろん、セキュリティ機能についても高い評価を得ているため、セキュリティを重視したい場合にもおすすめです。
| レビュー数 | 79 |
| 満足度 | ★★★★☆ 3.9 |
| 提供会社 | Tracker Software |
| 料金価格 | 0円~ |
| 製品種類 | インストール型 |
動作が軽いソフトなので、スクロールもあまりカクツキませず、文字入力などもスムーズにできます。表示の仕方を片面や見開きなどを1クリックで変えられる所も便利です。
▼ 利用サービス:PDF-XChange Viewer
https://www.itreview.jp/products/pdf-xchange-viewer/reviews/162478
▼ 企業名:有限会社レン構造設計事務所
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:専門(建設・建築)
商用なら有料のPDF編集ソフトがオススメ!

PDFファイルの編集はハードルが高いと思われがちですが、適切なソフトやサービスを利用することで、初心者でも簡単に編集することが可能です。
ただし、無料で使えるサービスのなかには、ファイルサイズや機能による制限が設けられている場合も多いため、ストレスを感じることもあるでしょう。
個人利用として一時的に使いたい場合には無料のサービスでも問題ありませんが、商用利用として継続的に使いたい場合には、有償のPDF編集ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか?
投稿 PDFを編集する方法を徹底解説!WordやExcelへの変換手順と無料でできるやり方を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【無料/有料】大容量ファイル転送サービスおすすめ15選!安全性や評判を徹底比較 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>「無料で使えるファイル転送サービスは安全なのかを知りたい」
ファイル転送サービスとは、メールでの添付が難しい大容量データを一時的に交換できるサービスのことです。画像や動画などの容量が大きいファイルを素早く安全に送受信することができるため、企業や個人を問わず、幅広いシーンで利用されています。
ファイル転送サービスには、主に無料版と有料版の2つの種類から提供されていますが、無料で使えるサービスの安全性は本当に大丈夫と言えるのでしょうか?
本記事では、大容量かつ無料で使えるファイル転送サービスの徹底比較に加えて、無料で使えるファイル転送サービスの安全性についても解説していきます。
ファイル転送サービスとは?
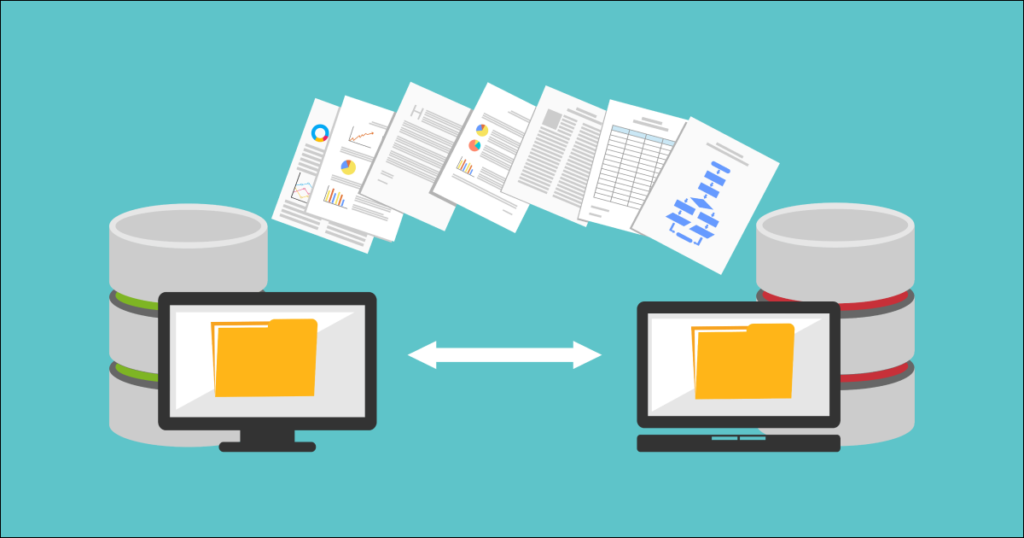
ファイル転送サービスとは、メールでの添付が難しい大容量データを一時的に交換できるサービスのことです。画像や動画などの容量が大きいファイルを素早く安全に送受信することができるため、企業や個人を問わず、幅広いシーンで利用されています。
ファイル転送サービスの仕組み
ファイル転送サービスの仕組みは比較的シンプルな構造となっており、初心者の場合であっても簡単に使い始めることが可能です。
- 送信側がファイルをアップロードするとダウンロードリンクが生成される
- 受信側は共有されたダウンロードリンクからファイルをダウンロードする
ほとんどのサービスでは、難しい操作や複雑な設定をする必要がないため、無料のサービスであっても迷うことなく利用することができるでしょう。
ファイル共有サービス(オンラインストレージ)との違い
| 特徴 | ファイル 転送サービス |
ファイル 共有サービス |
|---|---|---|
| 導入目的 | ファイルの転送 | ファイルの共有 |
| 有効期限 | 一時的 | 恒久的 |
| 転送速度 | 短い | 長い |
| 利用人数 |
限定ユーザー (自分と相手) |
複数ユーザー (チーム全員) |
| サイズ制限 |
大容量向け (1GB以上) |
中容量向け (1GB未満) |
| セキュリティ |
データに対して パスワードを設定 |
ユーザーに対して アクセス権を付与 |
ファイル転送サービスと似たサービスとしては、オンラインストレージやクラウドストレージとも呼ばれているファイル共有サービスの存在があります。
ファイル転送サービスは、主に大容量のファイルを送信することに特化しているため、転送されたデータの有効期限は一時的かつデータの保存には向きません。
ファイル共有サービスも、主に複数人でファイルを共有することに特化しているため、アップロード時間はファイル転送サービスよりも長くなってしまいます。
それぞれのサービスで想定される利用目的は異なるため、これらのツールを使用する場合には、それぞれのニーズに適したサービスを選択することが重要です。
無料で使える大容量ファイル転送サービス比較一覧表
| ギガファイル便 | firestorage | tenpu | データ便 | sDrop | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
 |
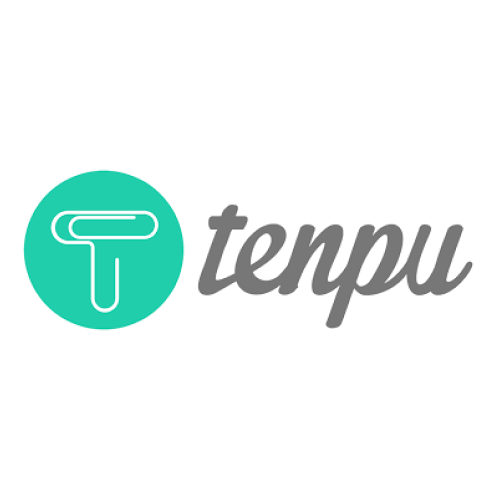 |
 |
 |
|
| 最大ファイルサイズ | 300GB/1ファイル | 40GB/1ファイル | 1GB/1ファイル | 2GB/1ファイル | 1GB/1ファイル |
| データの保存期間 | 最大100日間 | 最大7日間 | 最大3日間 | 最大14日間 | 最大72時間 |
| サービスの特長 | ファイル転送サービスの代名詞的な存在。1ファイルあたり最大300GBまでのファイルが転送可能。 | 1回あたり最大20個までのファイル転送に対応。一度に最大40GBまでのファイルが転送可能。 | 広告が表示されないビジネスモデル。シンプルなユーザーインターフェースと直感的な操作が特徴。 | 最大500MBまでのファイル転送に対応。無料の会員登録で最大2GBまでのファイルが転送可能。 | メールアドレスを登録して通知機能をオンにすることで最大1GBまでのファイルが転送可能。 |
| 価格 | 無料(0円~) | 無料(0円~) | 無料(0円~) | 無料(0円~) | 無料(0円~) |
| セキュリティ機能 | ✅ 国内サーバー ✅ アンチウイルス ✅ パスワード保護 ✅ ファイルロック |
✅ セキュリティ監視 ✅ ウイルスチェック ✅ パスワード保護 ✅ 暗号化通信対応 |
✅ 暗号化通信対応 ✅ パスワード保護 ✅ ファイル削除設定 ✅ VPCデータ管理 |
✅ 独自セキュリティ ✅ パスワード保護 ✅ 有効期限の設定 ✅ ダウンロード通知 |
✅ 自社サーバー ✅ 暗号化通信対応 ✅ パスワード保護 ✅ 自動ファイル削除 |
| 広告表示 | あり | あり | なし | あり | なし |
| 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
無料で使える大容量ファイル転送サービスおすすめ5選
GigaFile(ギガファイル)便

| 製品名 | GigaFile(ギガファイル)便 |
| 料金価格 | 無料 |
| 広告表示 | あり |
| 保存期間 | 最大100日間 |
| 対応ファイルサイズ | 300GB/1ファイル |
| 提供会社 | 株式会社ギガファイル |
GigaFile(ギガファイル)便は、株式会社ギガファイルから提供されているファイル転送サービスです。
ファイル転送サービスの代名詞的な存在として浸透しており、1ファイルあたり最大300GBまでのファイルを転送することができます。
firestorage
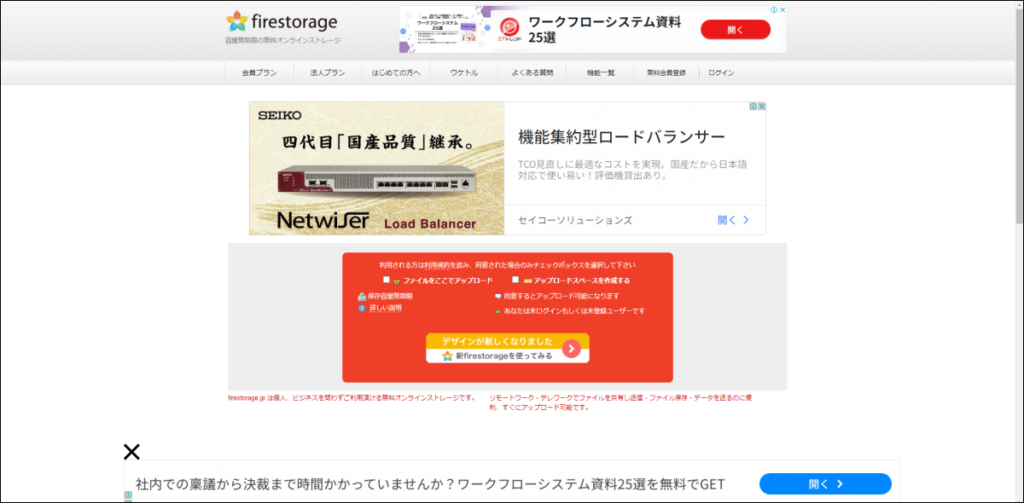
| 製品名 | firestorage |
| 料金価格 | 無料 |
| 広告表示 | あり |
| 保存期間 | 最大7日間 |
| 対応ファイルサイズ | 2GB/1ファイル |
| 提供会社 | ロジックファクトリー株式会社 |
firestorageは、ロジックファクトリー株式会社から提供されているファイル転送サービスです。
1回あたり最大20個までのファイル転送に対応することができるため、一度に最大40GBのファイルを瞬時に転送することができます。
tenpu
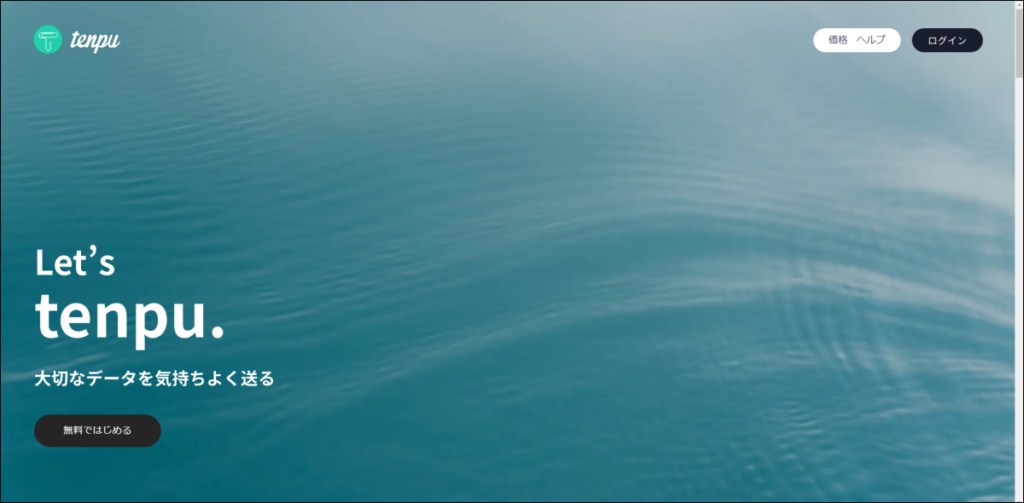
| 製品名 | tenpu |
| 料金価格 | 無料 |
| 広告表示 | なし |
| 保存期間 | 最大3日間 |
| 対応ファイルサイズ | 1GB/1ファイル |
| 提供会社 | 株式会社イノベーター・ジャパン |
tenpuは、株式会社イノベーター・ジャパンから提供されているファイル転送サービスです。
ファイル転送サービスとしては珍しく広告が表示されないビジネスモデルであり、シンプルなユーザーインターフェースが大きな特徴となっています。
データ便
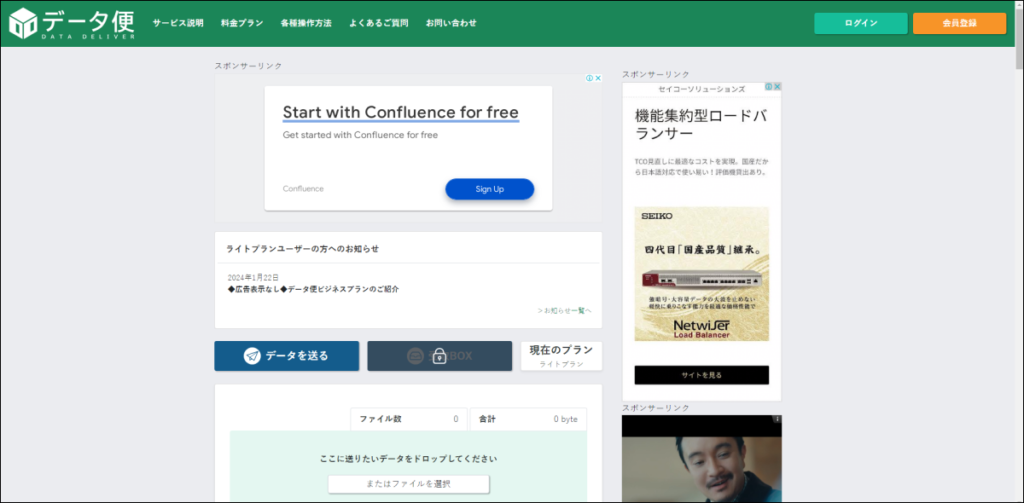
データ便は、株式会社ファルコから提供されているファイル転送サービスです。
会員未登録の場合には最大500MBまでのファイルに対応しており、無料の会員登録を行うことで最大2GBまでのファイルを転送することができます。
sDrop

| 製品名 | sDrop |
| 料金価格 | 無料 |
| 広告表示 | なし |
| 保存期間 | 最大72時間 |
| 対応ファイルサイズ | 1GB/1ファイル |
| 提供会社 | 株式会社パワーメディア |
sDropは、株式会社パワーメディアから提供されているファイル転送サービスです。
シンプルな操作画面が特徴であり、最大1GBまでのファイルを転送するには、メールアドレスを登録して通知機能を利用する必要があります。
無料で使えるファイル転送サービスは本当に安全?

無料のサービスはセキュリティのリスクがある
ファイル転送サービスは確かに便利な代物ですが、無料で使えるサービスのなかには、セキュリティリスクを含むものがあるということも忘れてはいけません。
とくに、無料のファイル転送サービスには、広告が表示されるサービスも多く、これらの広告がマルウェアやフィッシング詐欺の入口になることがあります。
また、無料のファイル転送サービスでは、有料のサービスと比較して、データの保護や暗号化レベルが低い傾向にあるため、機密情報の転送には不適切です。
ビジネス用途での利用なら有料サービスが安全
無料のファイル転送サービスのなかには、ユーザーの行動データを分析し、その情報を第三者へ販売することで収益を上げているサービスなども存在します。
無料で使える全てのファイル共有サービスが危険というわけではありませんが、プライバシーポリシーとセキュリティ機能の有無は事前に確認するべきです。
とくに、顧客の個人情報や機密情報を取り扱うビジネスシーンでの利用に関しては、より高度なセキュリティを備えた有料サービスの利用を検討しましょう。
ファイル転送サービスにおける無料版と有料版の違い

| 無料版 | 有料版 | |
|---|---|---|
| 対象ユーザー | 個人向け | 法人向け |
| 広告表示 | あり | なし |
| 転送速度 | 遅い | 速い |
| 保存期間 | 期限あり | 期限なし |
| セキュリティ | 単機能 | 多機能 |
| サポート体制 | 無人対応 | 有人対応 |
| ファイルサイズ | 制限あり | 制限なし |
ファイル転送サービスにおける無料版と有料版には、それぞれいくつかの違いがありますが、とりわけセキュリティとサポート体制では大きな違いがあります。
セキュリティの違い
無料のファイル転送サービスでは、基本的なセキュリティ機能は提供されているものの、パスワードやPINの設定ができるだけなど、その範囲は限定的です。
一方で、有料のファイル転送サービスでは、機密データの転送を安全に行えるように、エンドツーエンドの暗号化や多要素認証など、セキュリティが強固です。
サポート体制の違い
無料のファイル転送サービスでは、サポートは基本的なレベルに限定されており、オンラインFAQやコミュニティフォーラムによる自己解決に依存しています。
一方で、有料のファイル転送サービスでは、専門のカスタマーサポートが提供されており、電話やチャットを活用したリアルタイムサポートを実現しています。
法人向けファイル転送サービス比較一覧表
スクロールして全体を見る→
【容量・速度で選ぶ】法人向けファイル転送サービスおすすめ5選
DirectCloud

| サービス名 | DirectCloud |
| レビュー数 | 163件 |
| 満足度 | ★★★★☆ 3.9 |
| 提供会社 | 株式会社ダイレクトクラウド |
DirectCloudの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
5年ぐらい前から使用しております。最初はファイル置き場として利用しておりましたが、電子保存制度やインボイス制度に切り替わった際によりクラウドストレージの必要性を感じるようになりました。

デメリット(悪いポイント)
エクセルで大きいサイズの表を表示したときに、毎回全体表示から入るので、前回の倍率を記憶しておく機能などがあると助かります。
▼ 企業名:公益財団法人ソーシャルサービス協会
https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/171308
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:情報通信・インターネット
HULFT
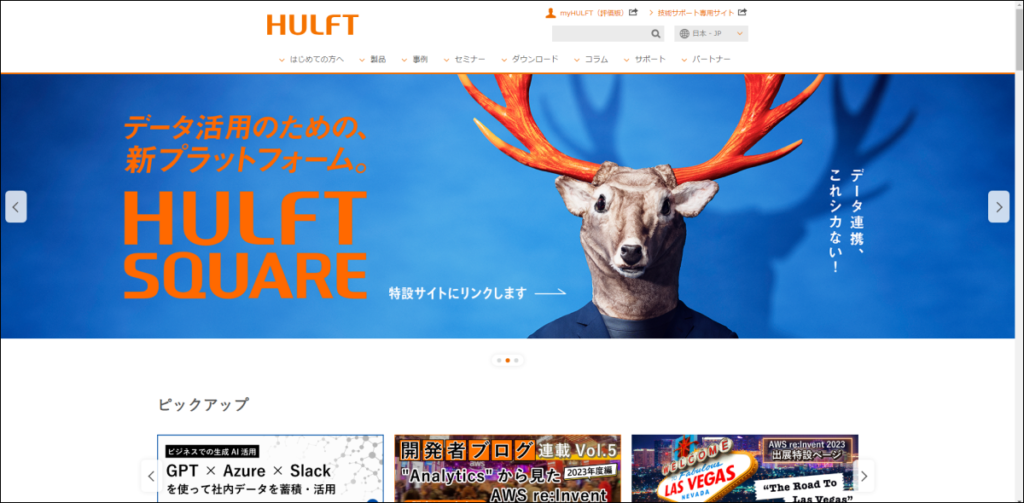
| サービス名 | HULFT |
| レビュー数 | 66件 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
| 提供会社 | 株式会社セゾン情報システムズ |
HULFTの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
機能の設定が容易で難しい設定が少ない。暗号化などもパラメータで設定可能。自分から自分への送信なども出来るため、検証なども簡単にできる。

デメリット(悪いポイント)
暗号化の機能はあるが、その暗号化レベルについては開示されていないため、セキュリティが厳しい会社では導入が難しい場合がある。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/hulft/reviews/135086
▼ 従業員規模:300-1000人未満
▼ 業種:ソフトウェア・SI
どこでもキャビネット

| サービス名 | どこでもキャビネット |
| レビュー数 | 26件 |
| 満足度 | ★★★★☆ 3.7 |
| 提供会社 | 株式会社大塚商会 |
どこでもキャビネットの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
とにかくシンプルなのでマニュアル要らずで利用できるのは良いポイントです。また、Windowsのエクスプローラーからもアクセスでき、また同期も行えるので使い勝手が良いです。

デメリット(悪いポイント)
ファイルビューアー機能がないためダウンロードしなくてはいけない点は可能であれば改善してほしいなと思います。PDFファイルなどブラウザから直接中身を確認したい場面がありますので。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/dokodemo-kyabinetto/reviews/146956
▼ 従業員規模:20-50人未満
▼ 業種:情報通信・インターネット
EASY FILE EXPRESS

| サービス名 | EASY FILE EXPRESS |
| レビュー数 | 12件 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.3 |
| 提供会社 | トーテックアメニティ株式会社 |
EASY FILE EXPRESSの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
新しく入ってきた社員に対して、特に使用方法の説明などを行わずとも使用できているので、使用方法が感覚的に分かりやすいのだと思う。

デメリット(悪いポイント)
ファイルの削除タイミング(デフォルト値)の変更ができるといいのになと思ったりします。当初、プランごとの条件値である「送信数」の概念がわかりづらかった。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/easy-file-express/reviews/134160
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:建築・鉱物・金属
AD FILE

| サービス名 | AD FILE |
| レビュー数 | 5件 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.5 |
| 提供会社 | 株式会社ビットツーバイト |
AD FILEの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
かれこれ数年にわたり使用しています。容量の大きいファイルや機密性の高いファイルを送るときに使用しています。

デメリット(悪いポイント)
もうすこし費用が安いと良いと思います。グーグルワークスペースの機能がアップした際に、グーグルのビジネスユースと迷った時もありました。
▼ 企業名:しゃんおずん
https://www.itreview.jp/products/adfile/reviews/137256
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:デザイン・製作
【セキュリティで選ぶ】法人向けファイル転送サービスおすすめ5選
GigaCC ASP

| サービス名 | GigaCC ASP |
| レビュー数 | 48件 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
| 提供会社 | 日本ワムネット株式会社 |
GigaCC ASPの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
ダウンロード画面をカスタマイズできる。設定した画像を背景に送ることでクライアントへの印象が大きく変わります。

デメリット(悪いポイント)
今でもバナーを設置できたり、背景を設定したり十分だがスタンプが送れたり、フォントのカラー変更ができたりもっと遊べたら面白い。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/gigacc-asp/reviews/154504
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:組合・団体・協会
Bizストレージ ファイルシェア

| サービス名 | Bizストレージ ファイルシェア |
| レビュー数 | 24件 |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.0 |
| 提供会社 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
Bizストレージ ファイルシェアの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
クリエイターとファイルをやり取りする際には容量が大きくなりがちなので、2GBまで対応というのがありがたいです。

デメリット(悪いポイント)
ファイルアクセスがより分かりやすくなるといいと思います。現状でも十分使いやすいですが、より簡潔なUIだといいと思います。
▼ 企業名:合同会社未来創造商事
https://www.itreview.jp/products/bizsutorejishea/reviews/176120
▼ 従業員規模:20人未満
▼ 業種:情報通信・インターネット
Smooth File
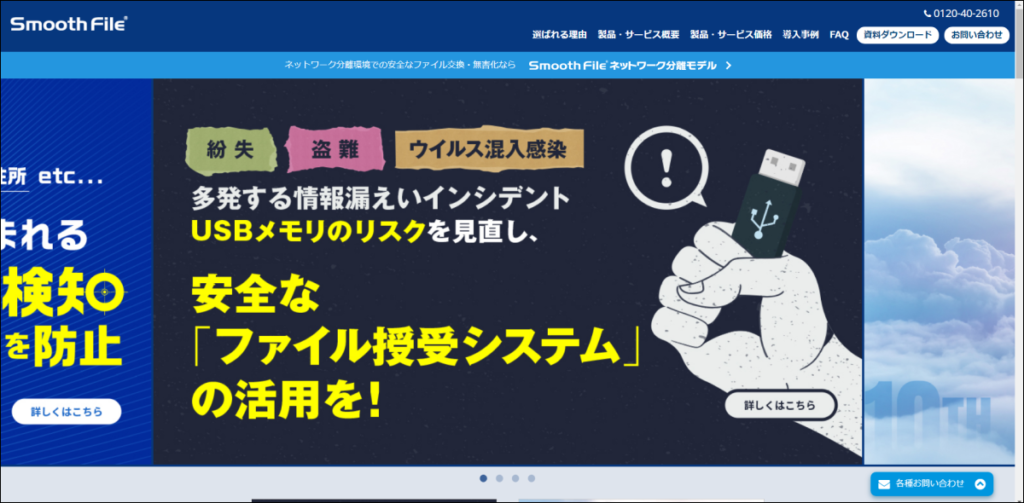
| サービス名 | Smooth File |
| レビュー数 | 10件 |
| 満足度 | ★★★☆☆ 3.4 |
| 提供会社 | 株式会社プロット |
Smooth Fileの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
相手のメールアドレスに対し、大容量のファイルを圧縮して送信することが可能。コンシューマー向けのサービスもあるが、信頼性を担保できるためこちらを利用。

デメリット(悪いポイント)
ファイルをアップロードする時に何回かやり直すことが多いため、UIをシンプルにしてほしい。ファイルを選択し、アップロードを確定させるのが少し手間で古く感じ、直感的でないので間違える。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/smooth-file/reviews/5016
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業種:広告・販促
SECURE DELIVER
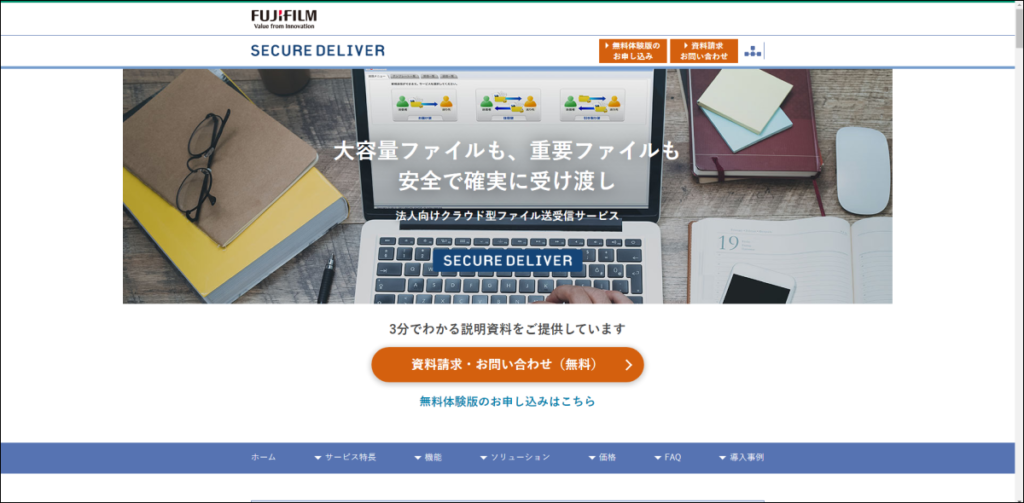
| サービス名 | SECURE DELIVER |
| レビュー数 | 9件 |
| 満足度 | ★★★★☆ 3.7 |
| 提供会社 | 富士フイルム株式会社 |
SECURE DELIVERの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
比較的簡単な操作でセキュアなデータ転送が可能になります。海外とのやり取りも多いですが、問題なく使用できます。

デメリット(悪いポイント)
時折サーバー側の事情でサービスが止まるときがあり、急ぎの際は少し困ることもあります。UIも特に分かりにくい点はないですが、もう少しモダンなデザインでもいいかなと思います。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/secure-deliver/reviews/160934
▼ 従業員規模:20-50人未満
▼ 業種:その他サービス
クリプト便

| サービス名 | クリプト便 |
| レビュー数 | 5件 |
| 満足度 | ★★★★☆ 3.9 |
| 提供会社 | NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 |
SECURE DELIVERの評判・口コミ

メリット(良いポイント)
クライアントと資料のやりとりをする際に使用しました。追加があると、メールでお知らせしてくれるシステムになっているため、最新の資料を見逃すこともありませんでした。

デメリット(悪いポイント)
インデックスが存在しないので、単にクライアントからの「お知らせ」から資料をダウンロードする必要があった点がやや不便ではありました。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/kuriputobin/reviews/137188
▼ 従業員規模:1000人以上
▼ 業種:その他サービス
ファイル転送サービスの選び方と比較のポイント

①:一度に送信できる最大容量を確認する
ファイル転送サービスの選び方の1つ目としては「一度に送信できる最大容量を確認する」というものが挙げられます。
ビジネス用途では、大容量のデータファイルを頻繁に送信する必要があるため、十分なファイルサイズをサポートしているかは事前に確認することが重要です。
とくに、写真や動画ファイル、大規模なプロジェクトファイルなど、大容量データの取り扱いが多い業務には高い容量制限を備えたサービスを選択しましょう。
②:ファイルやデータの転送速度を確認する
ファイル転送サービスの選び方の2つ目としては「ファイルやデータの転送速度を確認する」というものが挙げられます。
ファイルの転送速度は、ビジネスの生産性に直接影響する要素であり、データの転送に時間がかかりすぎてしまうと作業の遅延につながる可能性があります。
ファイル転送サービスを選定するときには、そのサービスのアップロード速度や性能を評価し、ビジネスの要求を満たしているかを判断することが重要です。
③:セキュリティ対策機能の有無を確認する
ファイル転送サービスの選び方の3つ目としては「セキュリティ対策機能の有無を確認する」というものが挙げられます。
ビジネスシーンでの使用を前提とする場合、顧客情報などの機密データが外部に漏れてしまうと、事業や会社そのものに甚大な影響を及ぼす可能性があります。
パスワードでの保護はもちろん、エンドツーエンドの暗号化や多要素認証など、高度なセキュリティ機能を提供しているサービスを選択するようにしましょう。
④:料金プランやランニングコストを確認する
ファイル転送サービスの選び方の4つ目としては「料金プランやランニングコストを確認する」というものが挙げられます。
ファイル転送サービスには、小規模ビジネス向けの製品から大規模ビジネス向けの製品まであり、提供される機能やサービス形態によって価格帯は異なります。
長期的なランニングコストや追加料金の可能性を考慮したうえで、自社のニーズを確認しながら必要な機能や予算に合わせて適切なサービスを選択しましょう。
⑤:内部統制に活用できる機能の有無を確認する
ファイル転送サービスの選び方の5つ目としては「内部統制に活用できる機能の有無を確認する」というものが挙げられます。
とくに、ファイルアクセスの監視機能や使用履歴の記録、ユーザー権限の管理機能など、いつ誰がどのファイルを操作したのかを確認できる機能は重要です。
ヒューマンエラーが発生した場合でも、原因を素早く特定することができるため、データのセキュリティとコンプライアンスの確保に役立てることができます。
ファイル転送サービスのメリット

データの送受信業務を効率的に実施できる
ファイル転送サービスのメリットの1つ目としては「データの送受信業務を効率的に実施できる」というものが挙げられます。
従来の方法では時間のかかった大容量ファイルの転送も、ファイル転送サービスを利用することで素早く行うことができるため、業務の効率化に貢献します。
また、直感的なユーザーインターフェースの製品も多く、技術的な知識がない従業員であっても簡単に操作できるため、マニュアル作成の手間も省略できます。
物理メディアよりもコストや手間を削減できる
ファイル転送サービスのメリットの2つ目としては「物理メディアよりもコストや手間を削減できる」というものが挙げられます。
CDやUSBドライブなどの物理メディアを使用する場合、購入や管理・配送に関連する作業が発生してしまうため、コスト効率を悪化させる原因となります。
ファイル転送サービスを使用することにより、例えば、遠隔地にあるオフィスやクライアントに送信したい場合であっても、低コストで行うことができます。
高いセキュリティで安全にデータを送信できる
ァイル転送サービスのメリットの3つ目としては「高いセキュリティで安全にデータを送信できる」というものが挙げられます。
ビジネス用途のファイル転送サービスのほとんどは、重要なビジネスデータでも安全に転送することができるよう、高いセキュリティ強度で設計されています。
エンドツーエンドの暗号化やデータの監査追跡機能、他要素認証をはじめとするセキュアなログインプロセスなど、データ漏洩のリスク軽減に貢献します。
ファイル転送サービスのデメリット

データを外部に送信することになる
ファイル転送サービスのデメリットの1つ目としては「データを外部に送信することになる」というものが挙げられます。
ファイル転送サービスを使用するということは、データが社外のサーバーを経由することになるため、機密性の高い情報を転送する場合には注意が必要です。
そのため、ファイル転送サービスを使用するときには、あらかじめサービスプロバイダーのセキュリティ基準と信頼性を慎重に評価する必要があるでしょう。
ログの管理ができないサービスが多い
ファイル転送サービスのデメリットの2つ目としては「ログの管理ができないサービスが多い」というものが挙げられます。
ファイル転送サービスのなかには、ログの管理機能が備わっていない製品も多く、誰がいつどのファイルにアクセスしたかの追跡が困難になることがあります。
とくに、規模の大きい会社ほど、コンプライアンスの観点から、ログ管理の機能不足は大きな課題となってしまうため、機能の有無は事前に確認するべきです。
相手のセキュリティ次第ではデータを開けない
ファイル転送サービスのデメリットの3つ目としては「相手のセキュリティ次第ではデータを開けない」というものが挙げられます。
高度なセキュリティ対策を謳うファイル転送サービスのなかには、特定の環境や設定下でのみデータを開くことができるよう制限を設けている製品も多いです。
例えば、特定の暗号化技術や特殊なソフトウェアが必要な場合、これらの要件を受信する端末が満たしていなければデータの開封が困難になる場合があります。
ファイル転送サービスを使用するときの注意点

①:ファイルの送信元を確認する
まずは、ダウンロードするファイルが安全であることを確認します。
出所が明記されていないファイルや信頼できない送信元からのファイルなどは、ウイルスやマルウェアの可能性が無視できないため、絶対にダウンロードしないように注意しましょう。
②:ファイルのサイズを確認する
次に、ダウンロードするファイルのサイズを確認します。
動画データなどの容量の大きいファイルは、端末の記憶領域やネットワークに負担をかける可能性があるため、他の従業員を邪魔しない時間帯にダウンロードするなどで対策しましょう。
③:ダウンロード先を選択する
最後に、ダウンロードするファイルの保存先を選択します。
このとき、ダウンロードしたファイルを見失ってしまわないためにも、フォルダの構造は極力整理しておくのがおすすめです。見失ってしまった場合はOSの検索機能を活用しましょう。
まとめ:無料のファイル転送サービスはセキュリティに注意が必要!
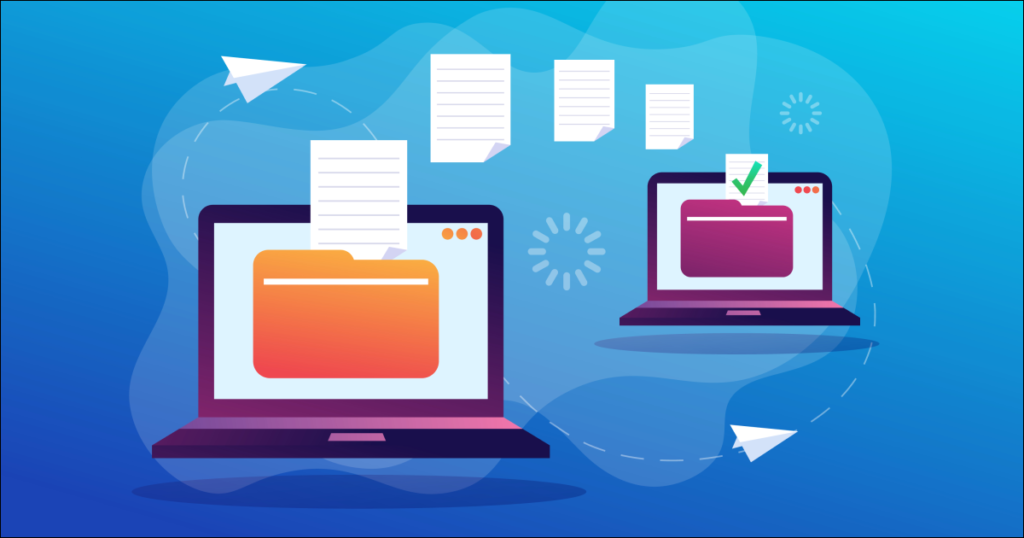
今回は、大容量かつ無料で使えるファイル転送サービスの徹底比較に加えて、無料で使えるファイル転送サービスの安全性についても解説していきました。
重たいファイルも瞬時に転送できる便利なサービスですが、無料のサービスは、セキュリティや転送速度に懸念が残ることから、絶対に安全とは言えません。
とくに、機密データを取り扱うようなビジネスシーンでの利用に関しては、より高度なセキュリティを備えた信頼できるサービスの利用を検討しましょう。
投稿 【無料/有料】大容量ファイル転送サービスおすすめ15選!安全性や評判を徹底比較 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 RPAとは?導入メリットや活用事例をわかりやすく簡単に解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進や労働力の不足を背景に、多くの企業がRPAの導入を推進しており、業務の効率化や生産性の向上を実現しています。
しかし、RPAは決して万能のツールというわけではなく、複雑な判断を要する業務や非定型的な業務には適していないため、適用範囲を正しく理解することが重要です。
本記事では、RPAの基本概念からAIとの違い、導入によるメリット・デメリットや活用事例まで詳しく徹底的に解説していきます。
また、ツールの選定ポイントや導入ステップについても紹介しているため、RPAの導入を検討している企業担当者には必見の内容です!
▶ 関連記事:RPAの無料製品9選|ツールの特徴や選定基準を紹介
▶ 関連記事:実績豊富なRPA製品10選|市場シェアや評判の高いツールを紹介
RPAとは?
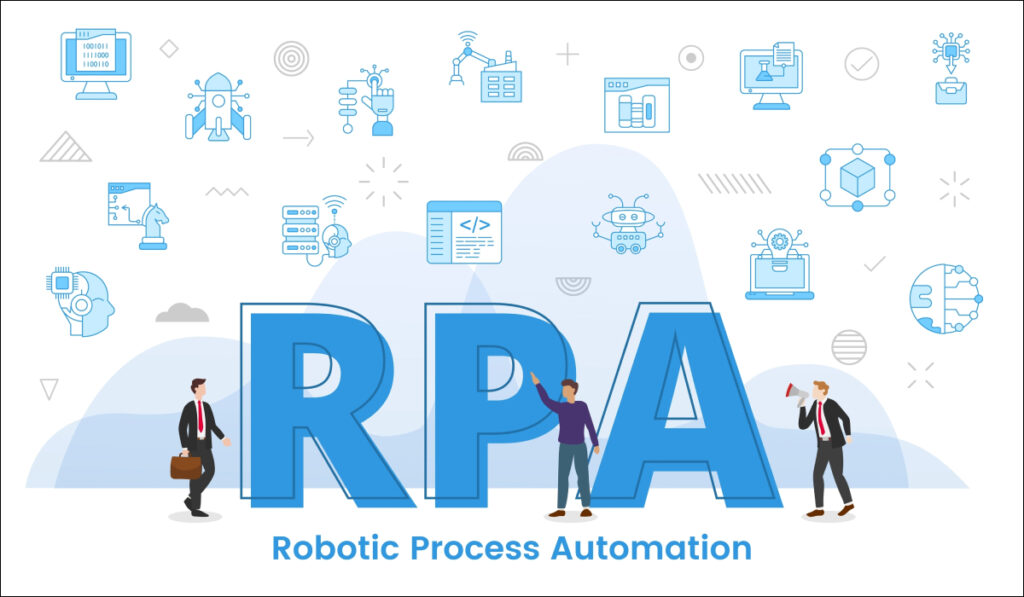
RPAとは、Robotic Process Automation(ロボティックプロセスオートメーション)の略で、ロボットを活用して定型業務を自動化する技術のことです。
主に、繰り返し発生するデータの入力作業や計算の処理、管理業務などを自動化することができ、企業の業務効率や生産性の向上に大きく貢献します。
また、ルールベースのタスクを自動で実行できるため、バックオフィスやカスタマーサポートなど、分野を問わず幅広い企業や業種で活用されています。
具体的な活用事例としては、経理部門では請求書の処理、人事部門では勤怠データの集計などが挙げられ、様々な業務を自動化できるようになります。
RPAが注目されるようになった理由
- 労働人口の減少によるニーズの拡大
- 働き方改革による業務効率化の加速
- AIやクラウドなどの先端技術の進化
労働人口の減少によるニーズの拡大
RPAが注目されるようになった理由の1つ目としては「労働人口の減少によるニーズの拡大」というものが挙げられます。
特に、少子高齢化が進む日本をはじめとする多くの先進国では、企業は深刻な人手不足に直面しており、限られたリソースで効率的に業務を遂行する能力が求められています。
RPAは、定型業務を自動化することができるため、例えば、経理や人事部門では、RPAを活用したデータ入力や書類作成業務を自動化することで、社員がより価値の高い仕事に集中できるようになります。
働き方改革による業務効率化の加速
RPAが注目されるようになった理由の2つ目としては「働き方改革による業務効率化の加速」というものが挙げられます。
政府が進める働き方改革や企業が行う生産性向上が加速するなかでは、業務の効率化が重要な課題となっており、とりわけ反復的かつ単調な事務作業の効率化が求められています。
RPAは、定型業務の自動化を実現するツールとしてニーズに合致しており、例えば、経費精算や請求書の処理といった業務を自動化することで、従業員はより戦略的な業務に専念できるようになります。
AIやクラウドなどの先端技術の進化
RPAが注目されるようになった理由の3つ目としては「AIやクラウドなどの先端技術の進化」というものが挙げられます。
昨今のRPAは、AIやクラウドといった先端技術の発展により、ますます高度な自動化が可能となっており、スケーラビリティやコストカットの観点でもメリットが増しています。
AIとの組み合わせにより、RPAは単なる反復作業の自動化だけではなく、例えば、売上の予測分析や意思決定の支援などの自動化も可能となっており、より複雑な業務にも対応できるようになっています。
RPAとAIの違い
| RPA | AI | |
|---|---|---|
| 導入目的 | 反復的な定型業務の自動化 | 問題解決や意思決定の支援 |
| 動作範囲 | ルールベース | 自然言語処理 |
| 導入費用 | 安い | 高い |
| 運用費用 | 高い | 安い |
| 学習能力 | あり | なし |
| 実行速度 | 速い | 遅い |
| 柔軟性 | 低い | 高い |
| 難易度 | 低い | 高い |
RPAはあらかじめ設定されたルールに従って作業を遂行するのに対し、AIは自然言語処理を用いた問題解決や意思決定の支援を得意とするツールです。
例えば、RPAは請求書処理やデータ入力などの作業を自動化しますが、AIは文書の内容を理解してリスクを検出するなどの高度な判断を可能とします。
RPAで自動化できる業務事例
| RPAの得意分野 | AIの得意分野 | |
|---|---|---|
| データの入力 | ◯ | ✕ |
| メールの送信 | ◯ | ✕ |
| 請求書の処理 | ◯ | ✕ |
| データの予測 | ✕ | ◯ |
| クリエイティブ | ✕ | ◯ |
| 問い合わせ対応 | ✕ | ◯ |
RPAが得意な業務(できること)
RPAは、繰り返し発生する業務やルールベース処理に適しており、データの入力や請求書処理、メール送信など、人手を介さずに一定のルールに従って実行できる業務が該当します。
具体的な業務内容としては、経理業務における仕訳の作成や人事の勤怠管理業務、営業の顧客データ更新などが挙げられます。
RPAが不得意な業務(できないこと)
RPAは、非定型業務や高度な判断が求められる業務には適しておらず、クリエイティブな作業や曖昧なデータの処理が必要な業務においては、RPA単体では対応することができません。
具体的な業務内容としては、顧客対応における複雑な問い合わせ対応や戦略的な意思決定がともなう業務などが挙げられます。
RPAツールの導入メリット
- 定型的な業務を効率化できる
- コスト削減効果が期待できる
- ヒューマンエラーを削減できる
定型的な業務を効率化できる
RPAのメリットの1つ目としては「定型的な業務を効率化できる」というものが挙げられます。
これまで手作業で行っていた業務や定型作業を自動化することができるため、業務の処理速度が向上し、戦略的な業務に集中できるようになります。
例えば、経理の請求書処理や営業のデータ入力をRPAで自動化することで、人的リソースを削減しながら業務のスピードを向上できるようになります。
コスト削減効果が期待できる
RPAのメリットの2つ目としては「コスト削減効果が期待できる」というものが挙げられます。
24時間稼働が可能なRPAは、時間外労働を減らすことができるため、業務スピードが向上するのと同時に、リソースの無駄を削減できるようになります。
例えば、手作業で行っていたデータ整理やシステムへの登録を自動化することで、業務負担を軽減しながらトータルコストを削減できるようになります。
ヒューマンエラーを削減できる
RPAのメリットの3つ目としては「ヒューマンエラーを削減できる」というものが挙げられます。
RPAは決められたプロセスを確実に実行するため、入力や集計業務などのミスが発生しやすい領域においては、精度の向上を実現できるようになります。
例えば、データ管理や契約情報の処理などをRPAで自動化することによって、正確性を向上させながらミスの発生を最小限に抑えられるようになります。
RPAツールの導入デメリット
- 導入や運用にはコストが発生する
- 定型業務の自動化には限界がある
- 管理やメンテナンスが必要になる
導入や運用にはコストが発生する
RPAのデメリットの1つ目としては「導入や運用にはコストが発生する」というものが挙げられます。
RPAの導入には、ソフトの購入やインフラの整備、運用維持にかかるコストが必要となるため、短期的には相応の導入運用コストが発生することを理解しておく必要があります。
ツールを選定するときには、クラウド型のRPAツールを選択したり、無料トライアルやフリープランを活用したりなど、費用を最小限に抑えるための工夫が必要です。
定型業務の自動化には限界がある
RPAのデメリットの2つ目としては「定型業務の自動化には限界がある」というものが挙げられます。
RPAは、あらかじめ設定されたルールにもとづいて業務の自動化を遂行するツールであるため、複雑な判断や非定型業務には対応できないことを理解しておく必要があります。
ツールを選定するときには、あらかじめ対応できる業務の範囲を確認したり、AIを搭載したツールを検討したりなど、業務の種類を考慮したツールの選定が重要です。
管理やメンテナンスが必要になる
RPAのデメリットの3つ目としては「管理やメンテナンスが必要になる」というものが挙げられます。
RPAは、システムや業務フローを変更した場合、アップデートやエラー対応が求められるため、定期的な保守とメンテナンスが必要であることを理解しておく必要があります。
ツールを選定するときには、メンテナンスパックがあるサービスを検討したり、変更しやすいサービスを選んだりなど、更新の手間を考慮したツール選定が大切です。
RPAツールの選び方と比較のポイント
- ①:使いたい業務に対応しているか
- ②:必要な機能は網羅されているか
- ③:料金やコストは予算の範囲内か
- ④:外部システムとの連携は可能か
- ⑤:セキュリティ対策機能は十分か
- ⑥:サポート体制は充実しているか
①:使いたい業務に対応しているか
RPAツールの選び方の1つ目としては「使いたい業務に対応しているか」というものが挙げられます。
RPAツールは、業務内容に合わせてカスタマイズできるものが理想的です。特に、特定の業務プロセスを自動化したい場合には、そのプロセスに合った最適なツールを選ぶことを心がけましょう。
例えば、定型業務を自動化したい場合には操作を模倣できるツールを、複雑な業務を自動化したい場合には高度に操作できるツールを選びましょう。
②:必要な機能は網羅されているか
RPAツールの選び方の2つ目としては「必要な機能が網羅されているか」というものが挙げられます。
ツールを選定する場合、必要な機能がツールに含まれているかを確認することが大切です。特に、データ入力やエラーハンドリングといった基本的な機能が含まれているかは、事前にチェックしましょう。
例えば、ロギング機能や監視機能が充実したツールを選ぶことで、トラブルの発生時でも迅速に対応できるため、機能の確認は慎重に行うべきです。
③:料金やコストは予算の範囲内か
RPAツールの選び方の3つ目としては「料金やコストが予算の範囲内か」というものが挙げられます。
導入にあたっては、初期費用やライセンス料だけではなく、運用コストも考慮することが重要です。特に、ツール選定にあたっては、投資対効果(ROI)が見込めるかは事前に検証するようにしましょう。
例えば、クラウド型は初期費用が少ないため、スモールスタートには最適です。反対にオンプレミス型は運用コストが少ないため、長期運用に最適です。
④:外部システムとの連携は可能か
RPAツールの選び方の4つ目としては「外部システムとの連携は可能か」というものが挙げられます。
RPAツールは、外部の業務システムやアプリケーションと連携することが重要です。特に、ERPシステムやCRMシステム、データベースとの連携が可能なツールは、効率的な業務自動化には欠かせません。
例えば、 API連携やデータベース接続を搭載したツールを選ぶことで、異なるシステム間でもデータの転送や処理をスムーズに行うことができます。
⑤:セキュリティ対策機能は十分か
RPAツールの選び方の5つ目としては「セキュリティ対策機能が十分か」というものが挙げられます。
業務によっては機密情報を扱うこともあるため、セキュリティ対策は非常に重要です。特に、クラウド型のRPAツールを利用する場合には、通信暗号化や認証機能の有無をチェックしておきましょう。
例えば、 認証機能やデータ暗号化機能が実装されているツールを選ぶことで、不正アクセスや情報漏洩のリスクを最小限に抑えることができます。
⑥:サポート体制は充実しているか
RPAツールの選び方の6つ目としては「サポート体制が充実しているか」というものが挙げられます。
運用支援がしっかりしているかを確認することは、トラブル発生時の迅速な解決に繋がります。特に、RPAに慣れていない企業では、ベンダーのサポート体制を事前に確認しておくことが重要です。
例えば、24時間対応のサポートやFAQ、トラブルシューティングガイドが充実しているツールを選ぶことで、万が一の問題にも対応しやすくなります。
RPA市場の動向と今後の展望
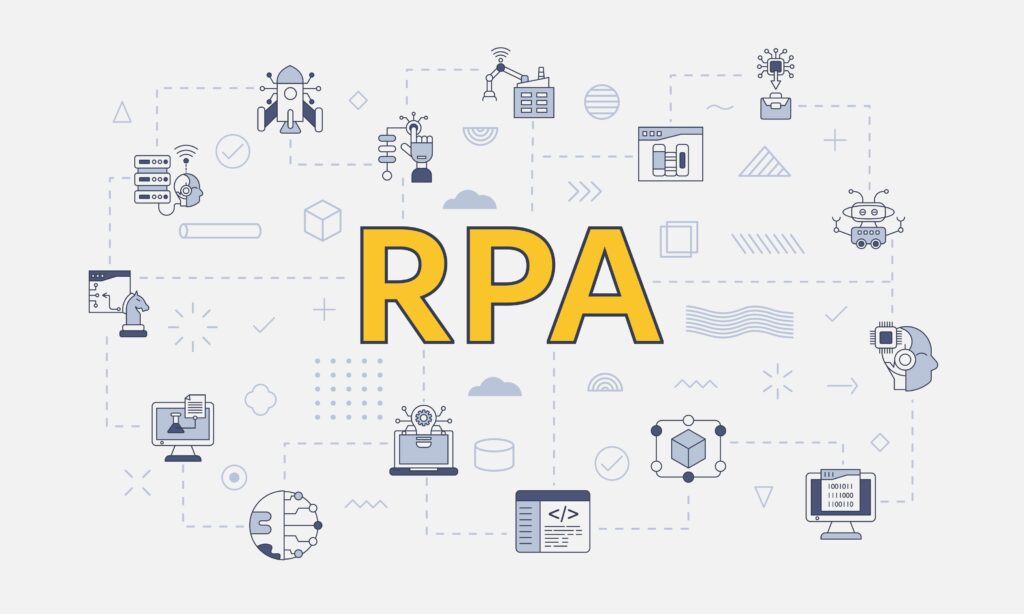
RPA市場の成長と普及の状況
RPA市場は急速に成長しており、多くの企業が業務効率化のために導入を進めています。
デロイトトーマツミック経済研究所の調査によると、2025年までに国内のRPA市場の規模は約1183億円に到達する見込みとなっており、さらなる拡大が予測されています。
出典:国内RPA市場は年10%超で堅調に推移、オンプレミス製品が9割|IT Leaders
AIとの融合による高度な自動化
近年のRPA市場では、AI技術との連携による高度かつ複雑な業務の自動化が進んでいます。
例えば、OCR技術とAIを組み合わせることで、手書き文書やPDFファイルの内容を読み取って、自動でデータ化を実行するなど、より高度な業務の自動化が実現しています。
まとめ
本記事では、RPAの概要をわかりやすく解説するのに加えて、導入のメリット・デメリット、業務分野別の活用事例、ツール選定のポイントまで、徹底的に解説しました。
世界的にも急成長を遂げているRPA市場ですが、昨今ではAIやクラウドとの連携が進み、より高度な自動化が可能になることで、今後もさらなる市場の拡大と発展が予測されています。
今後もITreviewでは、RPAツールのレビュー収集に加えて、新しいRPAサービスの情報を随時掲載する予定です。掲載をご希望のベンダー様は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。
投稿 RPAとは?導入メリットや活用事例をわかりやすく簡単に解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【無料】動画編集ソフトおすすめ10選!利用者の口コミも紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、動画編集ソフトの商用利用の概要と、無料・有料ツールの中でも法人利用におすすめの動画編集ソフトをご紹介します。業務で使う動画編集ソフトを探している方は、ぜひ参考にしてください。
動画編集ソフトの選び方とポイント
動画編集するパソコンと要求スペックに注意する
動画編集ソフトを選ぶ際には、使用するパソコンのスペックが非常に重要です。
データ処理が重い作業のため、ソフトウェアの要求する環境やスペックを満たしていないと、
・ソフトウェアが正常に動作しない
・動作が遅い
・頻繁にフリーズする
などの問題が発生する可能性があります。
1.まずはOSの確認
まず、動画編集ソフトを選ぶ前に、自分のパソコンがWindowsかMacかを確認し、対応しているOSとバージョンをチェックしましょう。
Windows専用、Mac専用のソフトも多く、また、OSのバージョンによっては、ソフトウェアが対応していない場合があるため、最新のOSであっても動作保証されているかを必ず確認してみてください。
2.要求スペックの確認
次に、パソコンのスペックを確認しましょう。
動画編集ソフトで要求されるスペックの基本的な項目として、システムメモリ(RAM)、CPU、GPUを抑えましょう。
例えば、無償版利用も可能な高機能の動画編集ソフト「DaVinci Resolve 18」の要求環境(HD画質レベルでの編集)は以下になります。
・システムメモリ(RAM)
Mac : 8GB
Windows : 16GB
・CPU
Mac : M1 Mac(M1 Mac(MacBook Air、MacBook、Mac mini、iMac)
Windows :指定なし(推奨は3GHz以上)
・GPU
Mac : M1 Mac(M1 Mac(MacBook Air、MacBook、Mac mini、iMac)Windows:4GBのVRAM
参考:「DaVinci Resolve 16 最新推奨マシン環境」
処理の内容(HD画質か、4K画質かなど)によって推奨環境は異なるので、目的に合わせて環境を確認しましょう。
また現在持っているパソコンが必要環境を下回る場合、機能がシンプルなソフトを選ぶか、パソコンのスペックアップを検討しましょう。
機能性および拡張機能
ほとんどの動画編集作業で必要とされる基本機能(カット、トリミング、トランジションの追加、テキスト挿入、エフェクト追加など)があるかは最低限確認しましょう。
その上で、目的に合わせた機能(例えばYoutube動画の場合は字幕機能が使いやすいかどうか)、プラグインによる機能拡張の充実度などを確認しましょう。
セキュリティ
動画制作には個人情報や機密性の高い内容が含まれることもあるため、セキュリティ面での信頼性は選定基準として欠かせません。
特に無料の動画編集ソフトを使用する場合、ウイルスやマルウェアのリスクが伴うことがあるため、以下の点に注意しましょう。
・開発元の信頼性:ソフトの開発元が信頼できる企業かどうかを確認します。大手企業や長年にわたって信頼されている開発元から提供されているソフトウェアは、セキュリティ面でのリスクが低い傾向にあります。
・ダウンロード元の安全性:公式サイトからのダウンロードを心がけましょう。非公式サイトからのダウンロードは、ウイルスやマルウェアが添付されているリスクがあります。
・ユーザーレビューと評判:他のユーザーのレビューや評判も参考にします。
・アップデートの頻度と対応:定期的にセキュリティアップデートが提供されているかも確認しましょう。
有料版の有無
無料の動画編集ソフトには、有料版の利用を前提とした無償版の提供がされているものが多くあります。
無償版で完結できれば問題ないですが、機能制限やウォーターマーク(透かしやロゴ)がつくものがあるなど、目的によっては使えない場合もあります。
まず無償版を利用してみて、ソフト自体が使いやすい場合は有料版での利用も検討しましょう。
また、有料の動画編集ソフトには継続的な支払いが必要な「サブスプリクション形式」と、一度きりの支払いで対応できる「買い上げ形式」があります。利用期間や予算上限を検討しつつ、無料ツールとの比較を行ってみましょう。
商用利用できる無料の動画編集ソフト3選
動画編集ソフトについて、まずはお得に利用できる無料ソフトを探している人も多いでしょう。そこでまずは、商用利用が可能であり、無料で使えるおすすめの動画編集ソフトをご紹介します。
DaVinci Resolve
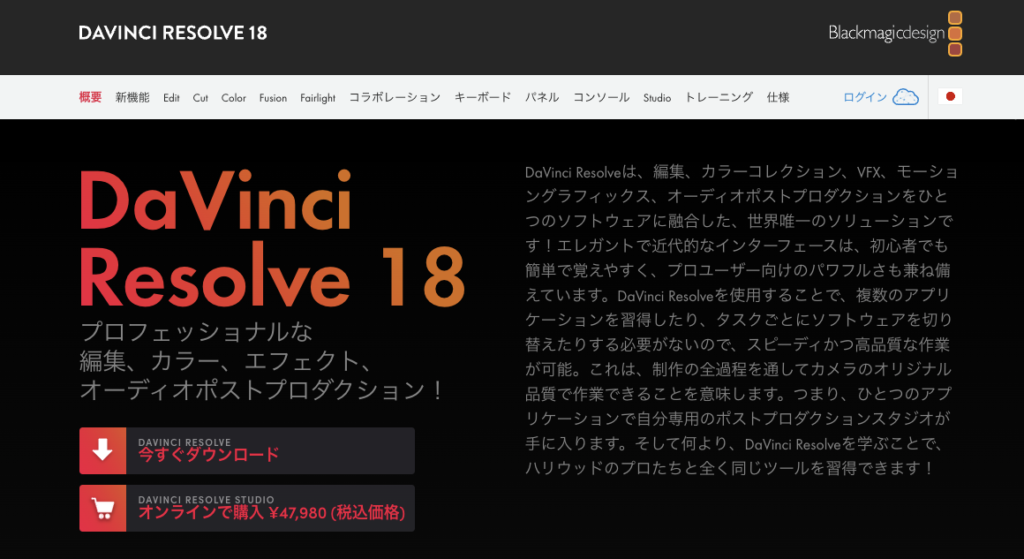
Davinci Resolveは、Blackmagic Design社が提供している動画編集ソフトです。プロ顔負けの動画編集が行えるほか、多彩な素材を商用利用できます。
作業データをクラウドで共有できることはもちろん、業務用として使用できるのが特徴です。有料版のDavinci Resolve Studioもありますが、無料版だけでも十分対応できるでしょう。そのため、まずは無料ツールからインストールするのがおすすめです。
DaVinci Resolveの参考レビュー、口コミ
動画編集を無料で始めるならばおすすめのソフト
有料版と無料版があるが、無料版でも十分な機能が使えます。
一部10bitの動画やエフェクトが一部制限されるなど無料版で出来ないことがありますが、通常使用する分にはほぼ使わないようなプロ級な機能ばかりです。
通常に動画編集や色調整等で使う分には無料で十分使える。
参考:https://www.itreview.jp/products/davinci-resolve/reviews/145236
無料で動画編集するなら間違いなくおすすめ
無料で十分すぎる機能が使えます。
初心者向けではないですが、どうせ本格的に編集するのであれば最初からこれを頑張って覚えることをお勧めします。
カットやフェード、テロップ等の基本的な編集だけでも十分価値はありますが、トラッキングやカラーグレーディングが本格的に行えます。無料で本格的に使用するのであればこれ以外の選択肢はありません。
参考:https://www.itreview.jp/products/davinci-resolve/reviews/134551
VideoProc Vlogger

VideoProc Vliggerは、Digiarty Software, Inc.が提供しているPC版の動画編集ソフトです。業務用動画の編集に必要なクロマキー合成や高画質出力にも対応しています。
また、提供されている素材はすべて商用利用でき、サイト内では初心者向けの編集チュートリアルも公開中です。
公式サイト:https://jp.videoproc.com/video-editor/
VideoProc Vliggerの参考レビュー、口コミ
動画の編集に利用
・トリミングと字幕しか使わないが、動画の編集が簡単だった。
その理由
・動画編集をこのアプリで初めて行ったが、それっぽいタブを選ぶだけで思い通りにできた。内視鏡の動画は撮影したPCのアプリでしか編集できないと思っていたが、問題なくできた。
編集した動画をさらに編集することができるのが良いと感じた。
参考:https://www.itreview.jp/products/videoproc/reviews/165417
作業時間が2割短縮
動画の編集もシンプルなものであれば、非常に簡単にできるので便利です。またサブスクタイプのソフトではありませんが、アップデートも頻繁に行ってくれており、少しずつ良くなっている印象です。特に動画の編集で抜き出しの作業をこちらのソフトでやるだけで作業時間帯が2割近く短縮できました。
参考:https://www.itreview.jp/products/videoproc/reviews/165417
VLLO
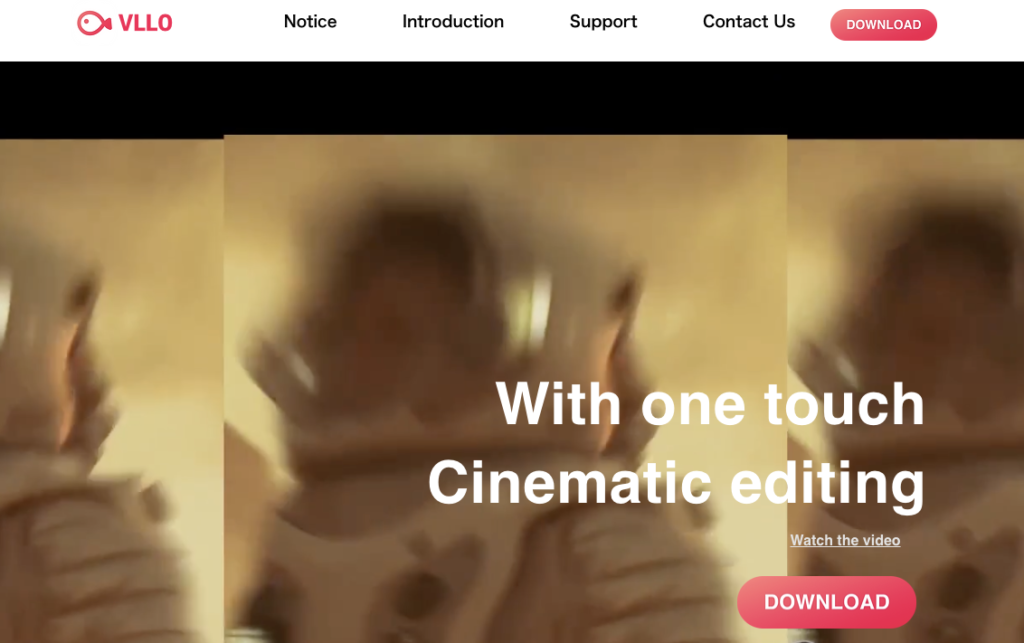
VLLOは、vimosoftが提供しているスマホ・タブレット版の動画編集ソフトです。PCで利用する動画編集ソフト顔負けの機能を有しており、画像分割や素材挿入をクリック操作で実現できます。
アプリ内に搭載されている素材は、基本的に著作権フリーです。また有料版にすると、さらなる素材や拡張機能を利用できます。無料ツールだけでも十分な編集が行えるので、スマホ・タブレット利用を検討している方におすすめです。
公式サイト:https://www.vllo.io/
商用利用できる有料の動画編集ソフト7選
法人利用するため、しっかりと有料動画編集ソフトの利用を検討している人もいるでしょう。次に、商用利用可能であり、無料ツールよりも機能性に優れている有料ツールをご紹介します。
Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Proは、Adobe社が提供しているPC版動画編集ソフトです。さまざまなクリエイティブソフトを提供しているAdobeが作成したツールということもあり、充実した機能を利用できます。
また、商用利用できる素材が豊富にあるほか、拡張機能として個人・法人が作成した素材もオープン化して提供しているのが特徴です。企業向け動画編集ソフトの中でも知名度が高く、高品質な編集環境を整えられます。
・Adobe Premiere Proの参考価格
法人向け単体プラン:4,380 円/月
・Adobe Premiere Proのユーザーレビュー
動画は結局プレゼンなので、どういうストーリー展開で落とし込んでいくかが大事。
引用:Adobe Premiere Proへのレビュー「動画作成ならプレミアプロ」より
撮影しただけでは、それをうまく表現できないので、動画を編集して分かりやすく重要な部分を目立たせ、落とし込みにつなげていく。
そういった作業が容易に効果的にpremiereなら行えている。
Filmora
Filmoraは、Wondershare Technology社が提供しているPC版の動画編集ソフトです。充実した素材が商用利用できることはもちろん、拡張機能として素材サイト自体を提供しているなど、バージョンアップするたびに動画の表現方法を増やせます。
初心者から中級者をターゲットにしており、直感的な操作で動画を編集できるとして世界8500万人にりようされているツールです。
・Filmoraの参考価格
ビジネス向け3ヶ月プラン:3,480円/月
・Filmoraのユーザーレビュー
ドラッグで簡単にデータをインポートできるし、編集することが可能。使用感としては説明書が不要なくらい簡単です。ボイスやバックサウンドなども併せて編集可能なのでオススメのツールになります。金額以上の評価は感じることができると思います。
引用:Filmoraへのレビュー「初心者も使える動画作成ツール」より
LetroStudio

アライドアーキテクツ社が手掛ける動画制作サービス「LetroStudio」では、インハウス動画制作に必要なツールを提供するだけでなく、企画から振り返りまでを含めた一気通貫のサービスとして提供しています。月額利用料金内で、専任のコンサルタントがつき、動画制作を1からサポートし、動画づくりのコツやテンプレートの活用法をレクチャーしてくれます。動画制作に関して社内に詳しい人がいないような企業にとっては大きな助けになるでしょう。
・LetroStudioの参考価格
お問い合わせ
・LetroStudioのユーザーレビュー
別の動画作成サービスからLetoroStudioに乗り換えた者の意見として、率直に言って非常に使いやすいです。
引用:LetroStudioへのレビュー「Web広告やフィード投稿目的の短尺動画作成に最適」より
サービス乗り換えにあたって同様の動画生成ツールの情報収集を行い、各種サービスのダッシュボードの操作感までを把握していますが、総合的に考えてLetoroStudio以上のツールは他にありませんでした。
VIDEO BRAIN
オープンエイト社がてがける「VIDEO BRAIN」は初心者でも作りやすい動画制作ツールを一式提供しています。シーン別やデバイスに選べるテンプレートを3,300本以上、動画に必要な画像やBGM、スタンプなどの素材は別のサイトと提携して1,000万点以上を用意。さらに、パワーポイントのデータを自動で動画用に再編集したり、音声字幕の自動生成などもプラン内で利用可能です。
・VIDEO BRAINの参考価格
お問い合わせ
・VIDEO BRAINのユーザーレビュー
テンプレートの種類がとても豊富なので動画を作成したことがない方でも、それっぽい動画が簡単に作成できます。
引用:VideoStudioへのレビュー「初心者でも簡単に動画を作れるツールです!」より
音声データの種類も多く、画像や動画素材も有料のものもありますが、ツール内で検索とアップが完結するのでありがたいです。パワーポイントを使用したことのある方であれば、感覚的に動画制作ができると思います。
ツールのアップデートも常に行われていてどんどん進化しているので、これからさらに使いやすくなるツールだと思います。困った時はご担当者様が親身になって相談にのってくださるので、安心してサービスを利用できています。
Video Studio
コーレル社が提供する「Video Studio」は、コストパフォーマンスに優れた動画編集ソフトとして人気を集めています。直感的な操作で動画編集ができるため、あまり動画編集をやったことがないという方でも無理なく思い通りに編集作業を完遂できます。
・Video Studioの参考価格
お問い合わせ
・Video Studioのユーザーレビュー
ECサイトを運営しており、商品の紹介動画をたくさん編集をします。その際にパートさんなど全くの動画編集初心者でもすぐに使いこなせるようになれるのが、多くの動画をつくる予定があるので大変助かります。慣れれば日に数十本仕上げられるようになるので売上向上には欠かせないツールになってます。
引用:Video Studioへのレビュー「格安簡単な動画編集ソフト」より
PowerDirector
PowerDirectorは、サイバーリンク社が提供する動画編集ツールです。かんたんな操作で初心者でもすぐに使いこなすことができ、カット、タイトル、トランジション、エフェクトに加え、PowerDirector365ではすぐに使える豊富なロイヤリティフリー素材を利用することができます。無料版も提供されているため、操作感を事前に試すことができます。
・PowerDirectorの参考価格
PowerDirector 365:6,200円(12か月/サブスプリクション版)
・PowerDirectorのユーザーレビュー
・スマホ版を使用しているが年3700円と格安。
PowerDirectorへのレビュー「スマホアプリを使用している。移動中も編集できてありがたい。」より
・効果音やデータセットもあって初めての人にとっても使いやすい仕様
・編集後の動画データもアプリからすぐにクラウドに保存できる
・youtubeや動画サービスに合わせた画面設定が可能
EDIUS
EDIUSは、Grass Valley K.K社が提供するPC版の動画編集ソフトです。映像業界に精通しているGrass Valleyは、撮影カメラやメディアワークフローなど充実した映像サービスを提供しており、EDIUS自体もプロ向けの機能を利用できます。
ただし、EDIUSの個人向け・ビジネス向けプランは商用利用の対象ですが、アカデミックプランは個人利用のみに対応しているので注意が必要です。
公式:https://www.ediusworld.com/jp/
動画編集ソフトを比較して納得の製品を導入しよう
動画編集ソフトは無料ツール・有料ツールによって価格や機能、拡張性が異なります。ただし、無料ツールの中にも有料ツール顔負けの機能が搭載されているのが特徴です。そこで、まずは気になる動画編集ソフトを抽出し、デモ版の利用を経て、どのソフトを導入すべきか検討してみましょう。
投稿 【無料】動画編集ソフトおすすめ10選!利用者の口コミも紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 CAD初心者におすすめな無料ソフト7選|2Dと3Dの練習に最適なソフトの選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、無料で利用できるCADソフトの中から、未経験でも習得しやすい初心者におすすめのソフトを3つご紹介します。用途や操作性などを比較検討して選択しましょう。
CADとは、設計図面や製図作成に使用されるソフト
CAD(キャド)とは、「Computer Aided Design」の略で、建築・住宅・自動車・服飾・家電などの設計図面や製図作成に使用されるソフトを指します。主に設計担当者やデザイナーの作業支援ツールとして活用されています。
かつては「ドラフター」と呼ばれる製図台を使用して手書きで製図作成が行われていましたが、CADの登場により素早く業務が行えるようになり、緻密な設計を必要とする業界で幅広く利用されるようになりました。
CADには大きく分けて、2種類が存在します。
- 2D CAD:平面・立面体の図面を線分や円弧を使って作成
- 3D CAD:立体形状の図面を直方体や円を使って作成
設備設計や建築(間取り設計)においては「2D CAD」が多く用いられ、製品や機械の設計においては立体的に確認できる「3D CAD」が用いられます。どちらのCADソフトを選定するかは、自社のニーズを考慮して選ぶ必要があります。
こちらの記事もチェック:いまさら聞けないCADとは?基礎知識やCAM、CAEとの違いを解説
CAD初心者がまず揃えるべきもの
- パソコン(ノート型でもOK)
- マウス
- プリンター
- CADソフト
初心者がCADを学ぶ上で、必要なアイテムについて見ていきましょう。使用するCADソフトによって動作環境は異なりますが、必ずしも最新のパソコンが必要な訳ではありません。一つの目安としては、メモリが8GB以上のモデルを選ぶとストレスなく作業を進めることができます。
またCADソフトの操作は、マウスを使う作業がほとんどです。長時間使用しても腱鞘炎にならないよう手にフィットするものを選びましょう。
プリンターに関してはCADソフトで作図したものを、実際に出力してみたい方にのみ必要です。コンビニなどのプリントサービスを利用することもできますので、必ずしも必要ではありません。
無料CADソフトの選び方とポイント
無料CADソフトといっても、さまざまな種類があります。自分に合ったソフトを手に入れるために、まずは選び方と押さえるべきポイントについて解説します。
2Dと3Dで目的に合わせた選択をする
CADソフトは大きく分けて2種類あり、使い方や用途が以下のように異なります。
- 2D CAD:平面・立面体の図面を線分や円弧を使って作成する
- 3D CAD:立体形状の図面を直方体や球体を使って作成する
2D CADとは、手書きの製図と同じように、立体を2D(二次元)で表現するソフトのことです。線分や円弧を使って、正面・平面・側面などの1視点から見た図面を平面上に描きます。手書きの製図作業をパソコン上で行うだけなので、初心者でも直感的に操作できるのがメリットです。
一方、3D CADとは、立体を3D(三次元)で表現するソフトのことです。直方体や球体を使って、全角度から立体的な造形物を描きます。立体形状のため360°いずれの角度からも形状や位置関係を確認でき、完成形をイメージしやすいのがメリットです。
設備設計や建築(間取り設計)においては平面的な図面を確認できる「2D CAD」が多く用いられ、製品や機械の設計においては立体的な形状を確認できる「3D CAD」が用いられます。2D CADと3D CADは描ける図面が異なるため、まずは自社でどちらが必要なのか判断してみてください。必要な図面を踏まえて、使用目的に合ったタイプのCADソフトを選びましょう。
資格取得が目的であれば試験に対応するソフトを選択する
CADの資格取得を目的に導入したいなら、受験する試験に対応した無料CADソフトを選びましょう。試験に対応するソフトを選択するためには、データ形式とインターフェースをチェックしておく必要があります。
たとえば、初級者向けの「オートデスク認定ユーザー」は、「AutoCAD」「Revit」「Fusion 360」のいずれかを使いこなせると証明する資格です。資格取得を目指したいなら、3つの中でも人気が高い「AutoCAD」「Fusion 360」のいずれかを選ぶとよいでしょう。「建築CAD検定試験」は「Jw_cad」「AutoCAD」などに対応しています。
次に、実技試験で作図の提出が求められる場合には、試験のデータ形式に対応しているソフトを選びましょう。CADソフトのデータ形式は、DXF・DWG・JWWなどさまざまです。CADソフトごとに扱えるデータ形式は異なりますが、たとえば「2次元CAD利用技術者試験1級」の実技試験では、DXFデータで保存した成果物の提出を求められます。DXFデータに対応しているのは「AR_CAD」「Jw_cad」などです。
日本語のマニュアルがあるソフト
CADソフト初心者は、日本語のマニュアルがあるソフトを選ぶのがおすすめです。無料CADソフトの中にはインターフェース自体が英語表記のソフトもあり、初心者が使いこなすには難易度が高いでしょう。日本語のマニュアルがあれば、使い方などを確認しながら操作できます。
利用するPC環境に対応しているかチェック
OSの確認
導入を検討している無料CADソフトが、自分が使用しているパソコンのOSに対応しているかチェックしましょう。無料でソフトをインストールしても、パソコンのOSに対応していなければ使用できません。
一般的に、パソコンのOSにはWindows・Macが使われています。無料CADソフトの多くはWindowsに対応しているものの、Macには対応していないケースも少なくありません。特にMacユーザーの方は、ソフトのOSを忘れずにチェックしてください。
PCスペックの確認
無料CADソフトをスムーズに操作できるように、自分のパソコンがソフト推奨のスペックをクリアしているか確認しましょう。
一般的に、2D CADソフトの要求スペックはそれほど高くありません。2D作図のみであれば、ノートパソコンでも操作が可能です。3D CADソフトを導入する予定がなければ、高スペックにこだわらず、ソフト推奨の動作環境を満たしているパソコンを選びましょう。メモリについては、8GB以上あると安心です。
3D CADソフトを使用する場合は、高スペックなデスクトップ型のパソコンを導入するとよいでしょう。特に3Dモデリングデータを扱う場合、グラフィックボードが重要です。CADの使用を前提に最適化されていることはもちろん、高スペックなボードを搭載したパソコンを選びましょう。メモリは、16GB以上が目安となります。
関連記事:CAD向けパソコンの選び方|2D/3D別・PCの推奨スペックとは
無料CADソフトのデメリットや注意点もチェック
無料CADソフトの導入にあたっては、デメリットや注意点もチェックしておきましょう。特にチェックすべきは以下の4点です。
商用利用できないことがある
ダウンロードと私的利用はOKであっても、商用利用を禁止している無料CADソフトもあります。営利目的で使用したい方は、のちのちトラブルにならないためにも、商用利用可能な無料CADソフトを選びましょう。
期限が設定されていることがある
無料CADソフトには、無料で提供しているフリーソフトと、利用期限を設定して無料体験版を提供しているソフトの2種類があります。後者を導入して引き続き利用したい場合、無料体験期間を終えると有料版に切り替えなくてはなりません。
機能が制限されていることがある
有料版もリリースしている無料CADソフトは、使用できる機能が一部制限されている場合もあります。ソフトごとに機能制限の範囲は異なるため、無料CADソフトでも必要な機能を網羅できているか確認しましょう。
有料アップグレード時の機能や価格を確認する
最初は無料CADソフトに搭載された機能で事足りていても、次第に満足できなくなる可能性があります。また、無料体験期間を利用する方は、終了すると有料版を購入するか決断しなければなりません。
有料版の価格はソフトごとに幅があるものの、1ヶ月1万円程度は費用が発生します。ライセンス取得となると、100万円を超えることも。無料CADソフトを導入するときは、仮に有料版を購入したりアップグレードしたりしても支払える金額なのかもチェックしておきましょう。
CAD初心者が上達する3つのポイント
これからCADを学んでいこうという初心者がいち早く上達するための、ポイントについてご紹介していきます。
1.無料ソフトをインストールしてとにかく触ろう!
初心者がCADを上達する方法として「教本」「セミナー」などがありますが、まずは実際にソフトを自分のPCにインストールして、触ってみるのがおすすめです。
初心者でも使いやすいソフトの多くは、直感的なインターフェースになっており、なんとなくでも作業を進めることができます。
こちらの記事もチェック:CAD向けパソコンの選び方|2D/3D別・PCの推奨スペックとは
その際に注意しておきたいのが、まずは無料のソフトを選ぶということです。「2D CAD」「3D CAD」ともにたくさんのソフトがあり、機能や使い勝手が異なります。初心者のうちに有料のソフトを購入してしまうと、ニーズと異なったものを選んでしまい再度別のソフトを購入する必要が出てくる可能性があります。
またできるだけ主要な無料ソフトを選ぶのも大切です。人気の高いソフトであれば、ちょっと使い方がわからない時に、「ツール名 使い方」などで検索をかければネット上でも有益な情報を手に入れることができます。
2.練習用の図面を使って作図してみよう!
CADソフトの基本的な触り方を学習したら、実際に作図をしてスキルアップをしましょう。練習用の図面は、様々なサイトで無料公開されているので、参考にしてみると良いでしょう。
また初心者向けのCAD教本を利用してみるのも良いでしょう。難易度別に練習問題が掲載されている本もあるので、自分のレベルごとに適切な問題を解くことができます。
大事なのは教本を読んで分かった気になるのではなく、実際にCADソフトで作図を繰り返すことです。
3.セミナーや講座を利用するのも一つの手
独学だと一度作業につまずくと、質問をする相手がいないのでなかなか次に進むことができません。その反面、セミナーや講習を利用すると講師にすぐに質問ができるので、短期間での上達に役立ちます。
CADセミナーや講座は、使用するCADソフトによって分かれていることがほとんどです。そのために事前にどのCADソフトを学びたいか決めておく必要があるでしょう。
形式も1〜2日で部分的に習得する「短期セミナー」や数ヶ月かけて体系的に習得する「長期セミナー」、オンラインで受講する「Web講座」など様々です。費用も形式によって異なりますが、3万円〜5万円(1ヶ月もしくは1回)が相場となっています。
【2D】初心者におすすめのCADソフト
初心者におすすめしたい無料で使える2D CADソフトをご紹介していきます。操作がシンプルながら実践でも使えるソフトもあり、上達するのに適している製品ばかりです。
AR_CAD(エーアールキャド)
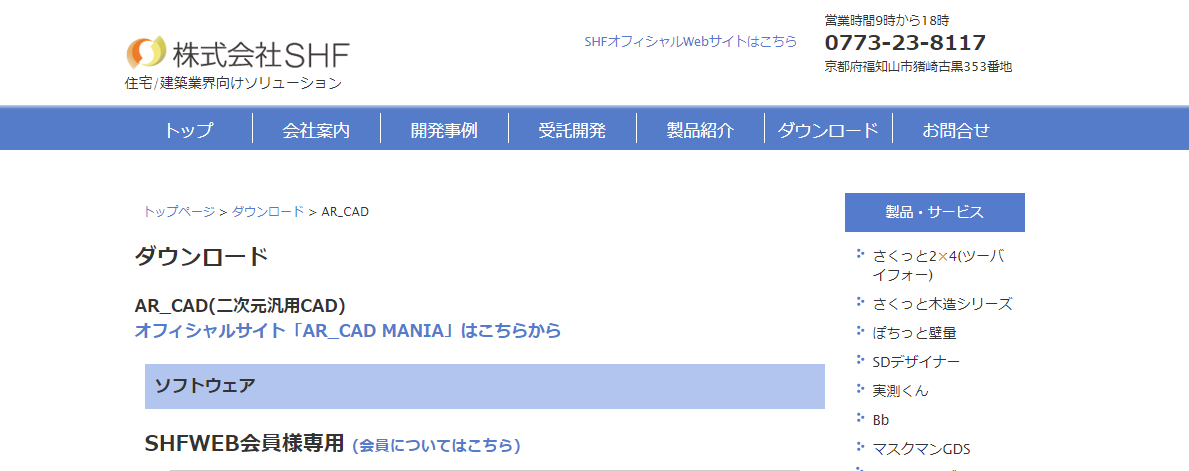
AR_CAD(エーアールキャド)とは、株式会社SHFが提供する2D汎用CADのフリーソフトです。
CAD初心者でも扱いやすい直観的なインタフェースで、手書き感覚で簡単に作図できるのが特長。本格的な建築図面の作成をはじめ、パンフレット作成などのビジネスシーンで必要な書類作成にも対応しています。
最大の魅力は、マウスとドラッグを中心とした操作で、画面上の操作をできるだけ抑えたシンプルな設計であること。一般的な「DXF」「JWW」「SXF」といったファイル形式にも対応しているため、他社製CADとのスムーズなデータ移行も可能です。
無料で使える幅広い機能性と分かりやすい操作性、各ファイル形式の連携対応にも優れたCADといえます。
AR_CAD(エーアールキャド)の特長
- 2D建築図面からビジネス向け書類まで幅広く対応
- シンプルな操作性で習得しやすい
- マウス&ドラッグでの手書き感覚で作図可能
- さまざまなファイル形式に対応
AR_CAD(エーアールキャド)の対応OS
- Windows
AR_CAD(エーアールキャド)の参考レビュー、口コミ
直感操作ができるCADソフト
メニューやアイコンなど分かり安く、直感的に作図できます。図面のコメントを付けたり、印刷するツールとして利用しています。
参考:https://www.itreview.jp/products/ar-cad/reviews/107335
簡単な図面の作成には使いやすい
マウスホイールでの視野移動・拡大縮小が感覚的に操作しやすいので、簡単な図面を描くのに使っています。
無料のCADソフトとしてJW_CADが有名ですが、そちらはデフォルトのマウス操作に癖がありストレスがたまりました。本職としてCADを扱う立場ではないので操作に習熟する手間を掛けたくないこともあり、操作がわかり易いAR_CADの方を立ち上げることが多いです。
参考:https://www.itreview.jp/products/ar-cad/reviews/70008
Jw_cad(ジェイダブリューキャド)

Jw_cad(ジェイダブリューキャド)とは、建築分野を対象とした無料の2D汎用CADです。Webサイト上で無料ダウンロードできる手軽さが魅力ですが、有料版にも引けを取らない充実した2D作図機能を備えているため、建築設計業務に携わる多くの方々に活用されています。
Windowsに対応し、マウスでの直感的な操作が可能なクロックメニューや、アイソメ図を作成できる2.5D機能、建具や設備のコマンドも豊富に搭載。建築図面の作成に便利な包括処理が一括でできるのもJw_cadの特長といえます。無料かつ高機能な2D CADを求める方に向いています。
Jw_cad(ジェイダブリューキャド)の特長
- 永久無料で商用利用も可能
- 建築分野に特化した機能が充実(天空図作成や日影図作成など)
- 直感的な操作で習得しやすい
- AutoCADと互換性のあるDXF形式に対応
Jw_cad(ジェイダブリューキャド)の対応OS
- Windows
Jw_cad(ジェイダブリューキャド)の参考レビュー、口コミ
無料でこの内容なら充分満足です。文句なし。
JWCADの優れた点は
①直感的なユーザーインターフェースと高度な機能の組み合わせで、様々な図面がかけます。
②操作性が高い・・・簡単なクリックとドラッグで効率的に図面を作成できます。
③設計プロセスが快適・・・豊富なカスタマイズオプションがあり、使用者は作業環境を自分好みに調整できます。
④これだけのパフォーマンスで無料は神。
参考:https://www.itreview.jp/products/jw-cad/reviews/177242
フリーで大満足
フリーなのにここまでできるのは凄いです。
長い間使用していますが、困ったことがほとんどないです。バージョンが上がっても画面回りに変化がないのも使いやすさではないでしょうか。
参考:https://www.itreview.jp/products/jw-cad/reviews/162765
RootPro CAD(ルートプロ キャド)
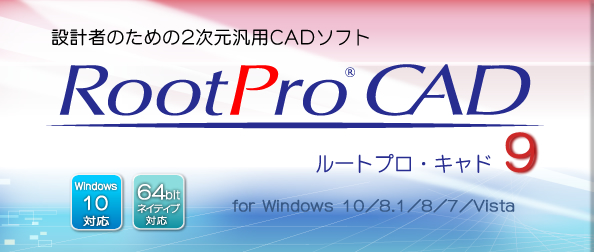
RootPro CAD(ルートプロ キャド)とは、株式会社ルートプロが提供する無料の2D汎用CADです。
設計者向けに開発されており有償版も展開されていますが、無料版では2D作図の基本的な機能を搭載しています。
特長は、CAD未経験者でも操作を行いやすい作図環境です。スナップ・グリッドなどの作図補助機能が充実しているほか、ビューコントローラー、ドッキングウィンドウなどにより、分かりやすくスピーディーに作図できます。また、AutoCADファイル形式のDWG、DXFや、Jw_cadのファイル形式からの読み込みもできて非常に便利です。
RootPro CAD(ルートプロ キャド)の特長
- 充実した補助機能でスピーディーな作図が可能
- DWGやSXFなどのさまざまなデータ読み込みが可能
- 分かりやすく快適な操作を追求したユーザーインタフェース
- 無料版が永久利用できる
RootPro CAD(ルートプロ キャド)の対応OS
- Windows
RootPro CAD(ルートプロ キャド)の参考レビュー、口コミ
有償版並みに使用できます
AUTO CAD経験者ですがLT並みに充実した機能は無償版で使用していますが、助かっています。互換性も高いので他のcadとの連携もとれています。
参考:https://www.itreview.jp/products/rootpro-cad/reviews/178605
直感的に使用出来るCAD
直感的に使用出来るCADだと思います。他のCADと比較しても必要な機能はひととおり揃っているので、使い勝手は良いです。価格も抑えられていて非常に使いやすいです。
参考:https://www.itreview.jp/products/rootpro-cad/reviews/10148
ZWCAD
ZWCADとは、ZWSOFT社が自社開発したハイコストパフォーマンス2D汎用CADです。200以上のサードパーティ製アプリケーションを提供しており、建築業・建設業・製造業など幅広い業界で利用されています。
高機能ながら、初心者でも操作しやすい作図環境が特長。AutoCADのダイナミックブロックと同等のフレキシブロックを導入しており、複雑なタスクも効率的に作業できます。独自機能であるスマートシリーズも搭載。一度に複数の画面をプロットでき、マウスジェスチャーにより頻繁に使うコマンドを簡単にトリガーできます。DWG・DXF・DWTといったさまざまなファイル形式に対応している互換性の高さも魅力です。
ZWCADの特長
- 直感的なインターフェースで習得しやすい
- DWG・DXF・DWTなどのファイル形式に対応
- 高機能のフレキシブロックにより作業の効率化を実現
- アクセス・管理・プロットを1つの画面で操作可能
ZWCADの対応OS
- Windows
ZWCADの参考レビュー、口コミ
機能性と価格に優れた2D・3D汎用CAD
・古いAutoCADからの乗り換えで導入しましたが、機能や操作性が遜色なく、ユーザーも抵抗感なく移行できました。
・APIが豊富で、メニューファイル、ショートカットやツールバーなどの互換性もあり、社内システムをスムーズに移植することができました。
参考:https://www.itreview.jp/products/zwcad/reviews/159965
低コストで導入することが可能である
直感的に使用出来るCADだと思います。他のCADと比較しても必要な機能はひととおり揃っ・オートCAD経験があれば操作に困ることはほぼ無いと思えるほど使用しやすいところが良いポイント。CADソフトではあるものの、そこまでPCのスペックが高くせずに導入できるのも良いポイントです。
参考:https://www.itreview.jp/products/zwcad/reviews/161638
【3D】初心者におすすめのCADソフト
AutoCAD
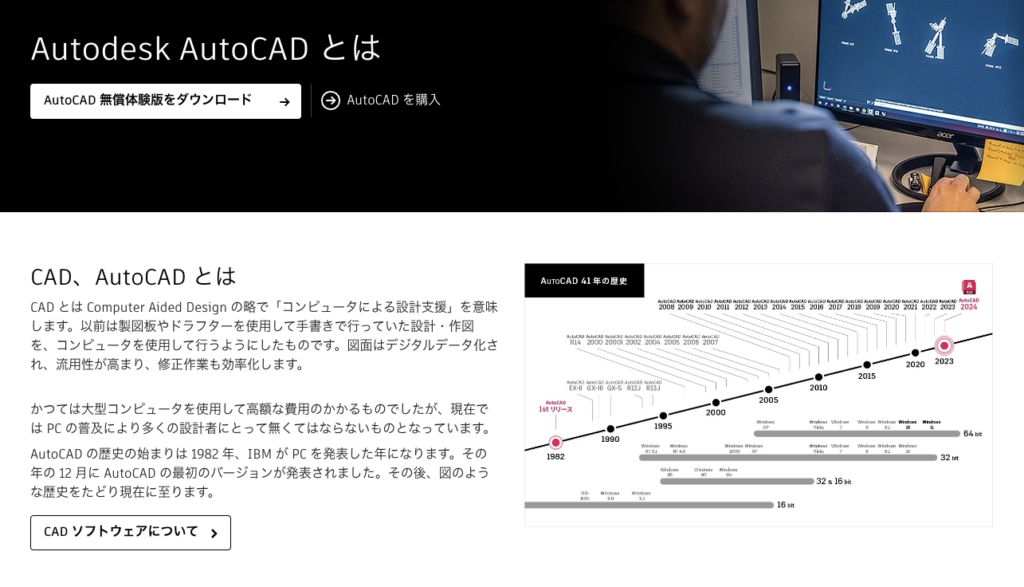
AutoCADとは、3D モデリングやビジュアライゼーション、データ書き出し、CAD 標準仕様や、API によるカスタマイズや、Express Tool が利用できる総合的なCADソフトです。建築・土木・機械分野など、さまざまな領域で利用されており、特に建築業界においてはトップシェアを誇る製品です。
AutoCADの対応OS
- Windows
- Mac
AutoCADの参考レビュー、口コミ
CADソフトはこれが王道
・使用している企業が多いため、ファイル形式で困ることは無いと言ってよい。
・あらゆるサイズの図面を描けるため、どの分野でも操作を知っていて困ることは無い。
参考:https://www.itreview.jp/products/autocad-lt/reviews/132809
Fusion 360
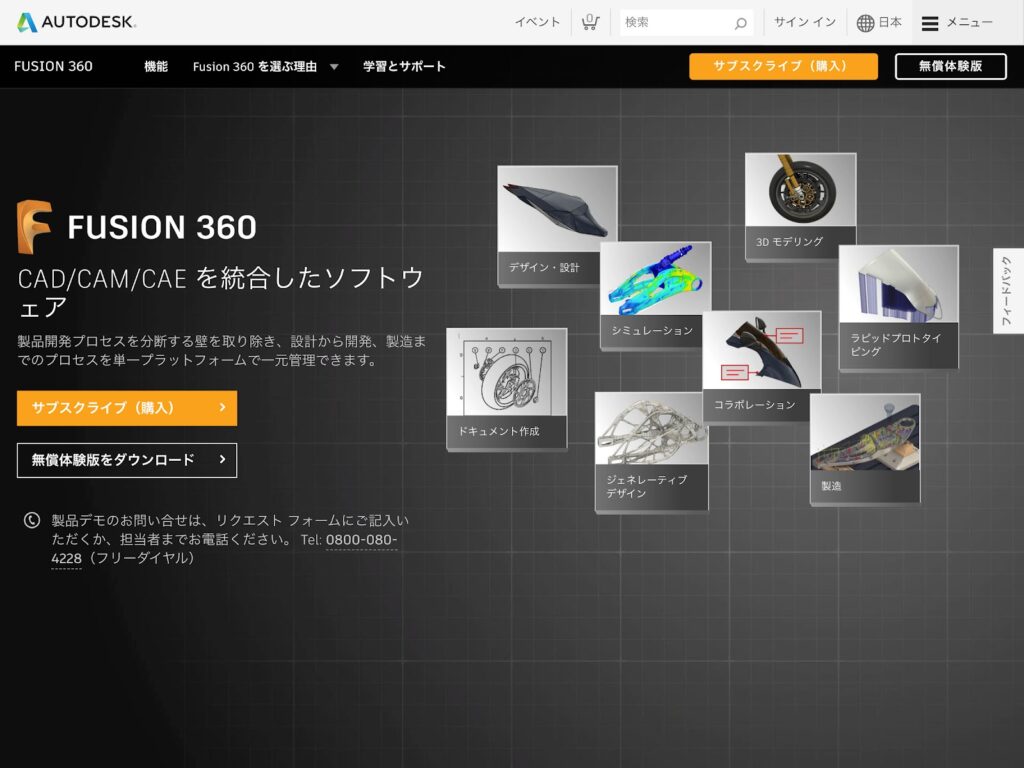
Fusion 360は、3DCADのモデリング、3DCAM、レンダリング、2次元図面などの機能が搭載されたCADソフトです。機械部品の設計やフィギュアなどの立体的な造形のモデリングなどに対応しており、プロダクトデザイン全般をひとつのソフトでまかなうことができます。
また、クラウド上にすべての機能が用意されているため、複数人での同時作業がしやすく、バックアップのモレなども防ぐことができる便利なCADソフトです。
Fusion 360の対応OS
- Windows
- Mac
Fusion 360の参考レビュー、口コミ
無料で使える3DCADをお探しならおすすめ
優れている点・好きな機能
・スケッチ機能が使いやすく、寸法拘束、幾何拘束でモデルを作ることが出来、後々の形状変更も数値の変更だけで済むため作業が少なくて良い。
・穴作成コマンドで普段使用するザグリ形状やタップを作成するとき、サイズを指定するだけで形状が作成出来るため簡単
参考:https://www.itreview.jp/products/fusion-360/reviews/146939
初心者にもオススメ!
容易に3Dモデルの解析を行うことができる点はすごく良いと思います。また、材質も数多くあり途中で変更することもできるので都合が良い点で気に入っています。
参考:https://www.itreview.jp/products/fusion-360/reviews/134032
ZW3D
ZW3Dは、ZWSOFT社が提供するall-in-one 3D CAD/CAE/CAM ソリューションです。製品開発の設計から製造までの全工程をサポートしており、低コストで市場までの投入時間を短縮できます。
CAD/CAE/CAMが統合されているため、データの受け渡し・管理の課題に悩まされることなく、シームレスな作業を実現可能です。
リーズナブルな「Lite」から高機能な「プレミアム」まで、7種類のバージョンを展開。直感的に操作できるUIを採用しており、日本語学習資料などによるサポート体制が充実しており、スムーズに導入・移行できます。
ZW3Dの特長
- 設計・シミュレーション・製造まで1つのプログラムで完結
- CAD/CAE/CAMを統合しておりシームレスな作業が可能
- 直感的で操作しやすいUIを採用
- 日本語学習資料、迅速的なサポートによりスムーズに導入可能
ZW3Dの対応OS
- Windows
ZW3Dの参考レビュー、口コミ
感覚的に扱いやすいソフト
出向先で過去につかっていたCATIAは、覚えることが多く習得までに時間がかなりかかったが、このソフトは、既にノウハウを持っていることを差し引いてもすぐに操作を覚えることができて、画面も見やすかった。
参考:https://www.itreview.jp/products/zw3d/reviews/153241
まとめ|操作性を考慮して初心者に最適なCADソフトを選ぶことが重要
CAD操作の習得を目的として無料CADソフトを選ぶ際は、コストだけでなく操作性や互換性を考慮して選ぶ必要があります。無料かつ操作が習得しやすい2D汎用CADには「Jw_cad」が挙げられますが、操作性が独自であるため、高機能な有料CADへ乗り換える場合には新たに操作を習得し直さなければならない場合があります。
また、互換性については、「JWW」「JWC」でのファイル形式はJw_cadのみで対応しているため、他製品のCADで開くにはファイル変換が必要となります。
一方、Jw_cadと並んでユーザー数の多い「AutoCAD」は、コマンド入力による高難易度の操作が必要となりますが、さまざまなファイル形式に対応しているため、他製品CADへのデータ移行がスムーズといえます。AutoCADと同じような操作性で作図できるCADも展開されているため、一度習得すれば他製品にも生かしやすいといえます。
習得後のCAD活用に向けて「取引先とのデータ移行がスムーズにできるか」「習得した操作を生かせるか」などを考慮して選ぶようにしましょう。
投稿 CAD初心者におすすめな無料ソフト7選|2Dと3Dの練習に最適なソフトの選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 個人利用でおすすめのオンラインストレージ(クラウドストレージ)8選!価格や容量は? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>筆者の周りでも、企業で働きながら週末は自分の理想とする取り組みに対しプロジェクトベースで参加するといった方も増えています。もちろん、仕事に限らず趣味や学校関係などでもさまざまな取り組みがなされるでしょう。
そんな「企業活動以外のプロジェクト」を進める際に課題となるのが「情報の共有方法」です。資料を共有する際、社内であればファイルサーバ等のインフラが構築されているためスムーズな対応が可能となりますが、個人同士がつながるプロジェクトでは、そのようなインフラはもちろん用意されていません。
そんなときに役立つツールが「オンラインストレージ」です。自前でサーバなどを準備することなくクラウド上のサービスを利用することで、だれでも手軽に情報共有を実現できます。
本記事では、企業活動以外のさまざまなプロジェクトで情報を共有する必要のある個人を対象に、気を付けるポイントや「個人利用でおすすめのオンラインストレージ」をご紹介していきます。
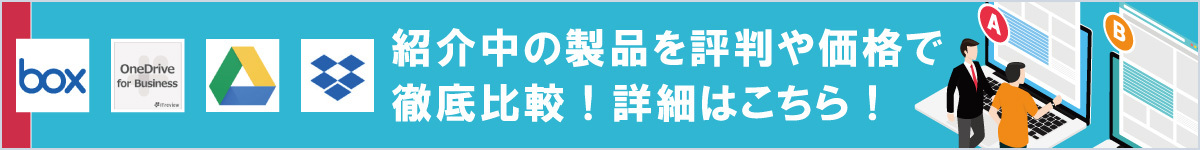
個人向けクラウドストレージの活用場面とメリット
1.複数デバイスでデータ共有できる
近年、デバイスの多様化により、スマホのみならず、PCやタブレットなど複数のデバイスを用途によって使い分けている方も少なくないでしょう。例えば、自宅やオフィスではPCで文書を作成し、電車での通勤時間にスマホでPCで作成した文書を見直すなどのようにです。
従来であれば、PCで作成した文書はメールでスマホに送信する必要がありました。しかし、クラウドストレージを使用すれば、スマホやPC、タブレットといった複数のデバイスから同じ文書や画像にアクセスでき、編集も可能です。
また、複数人がアクセスするデータを置いておくのにもクラウドストレージは便利です。様々なデバイスからアクセス権を付与された個人が自由にアクセスでき、新規のデータ作成や編集が可能です。
2.HDDなどのバックアップ作業が不要になる
通常、HDDにのみ保存されているデータは、PCやスマホ等のデバイスが故障した際に備えてバックアップが必要となります。しかし、クラウドストレージであれば、クラウド上にデータを保存できるため、デバイス故障に備えて小まめにバックアップを取る必要はなくなります。
また、バックアップ作業は時間がかかる上に、手間が多い作業です。そのため、日頃からクラウドストレージへの保存を心がけることで、バックアップにかかる工数の削減に繋がります。
3.無料もしくは安価で導入できる
クラウドストレージは、保存できる容量によって金額が異なるのが一般的です。しかし、比較的安価、もしくはある一定の容量までは無料で利用できるケースも多いです。
例えば、Googleが提供しているGoogleドライブは、15GBまでは無料で利用可能です。また、100GBまでは月額250円、200GBまでは月額380円と安価な料金で利用できます。
一方で、外付けHDDなどの物理的なストレージを購入した場合は、容量にもよりますが、数万円するものも普通にあります。また、破損してしまったらおしまいのリスクも伴います。そのため、無料もしくは安価に利用できるクラウドストレージの方がおすすめです。
4.デバイス買い替え時のデータ移行の手間がなくなる
スマホやPCは長く使用しているとバッテリーの性能が低下するため、数年おきに買い替える方が多いでしょう。
新しいデバイスにデータを移行する際、旧デバイスのHDD内にデータが残ったままであると新デバイスへのデータ移行に時間がかかってしまいます。データ量にもよりますが、データ量が膨大だと移行完了に数時間かかるケースもあります。
しかし、クラウドストレージを日頃から活用していれば、大切なデータはクラウド上に保存されているため、データ移行は短時間で完了するでしょう。
個人向けオンラインストレージを選ぶ際に気を付けるべきポイントは?
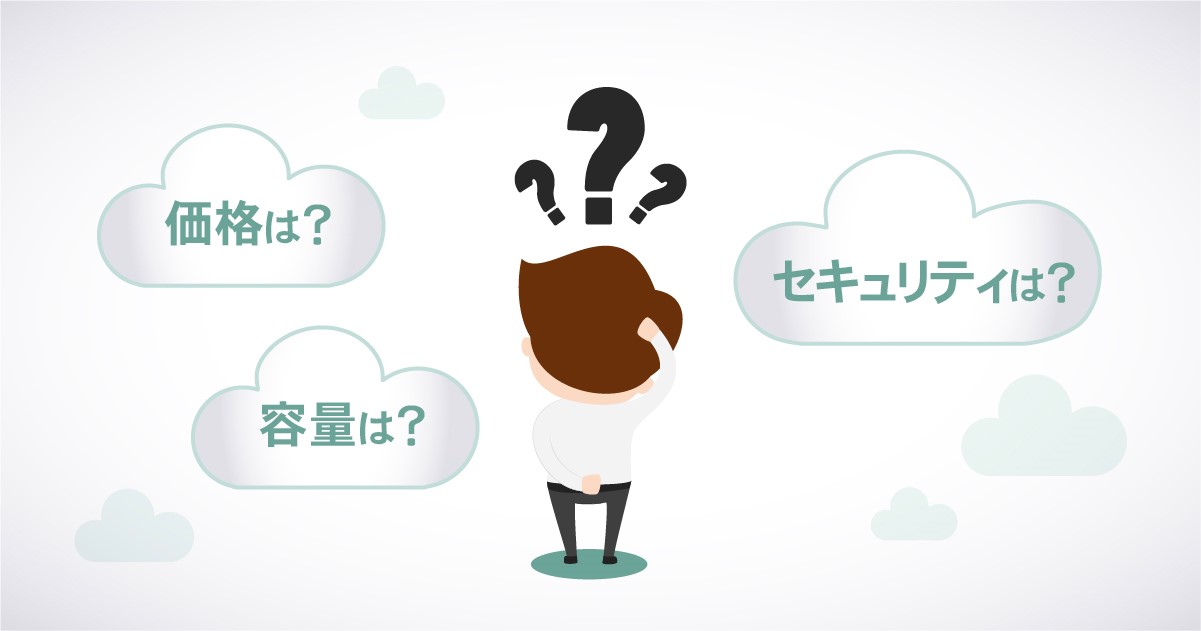
1. まずは無料プランを検討
オンラインストレージを個人で導入する場合、利用コストが気になるポイントです。
一般的にビジネスユースでオンラインストレージを活用する場合、セキュリティやサポートが脆弱な無料サービスは選択肢に入らないことが多いですが、個人利用の場合は、まずは無料で利用できるサービスを検討してみましょう。
個人利用であっても、スマートフォンやPCの利用方法が変わるなどで、無料で利用できる範囲を超えるストレージの環境が必要となる場合があります。
こんな場合におすすめなのが、無料プランも提供しているが、アップグレードで有料プランも提供しているサービスです。
ファイルが少ない方は無料プランを活用し、データ保有量が多くなってきた場合には有料プランに切り替えることで容量の状況に合わせてコストパフォーマンス良く利用することができます。
2.ストレージの容量
ストレージの容量は、多い方が安心です。しかし、個人利用の場合、利用コストが気になるところだと思います。
そこで、おすすめなのが、無料で使用できるストレージ容量が大きいクラウドストレージの選択です。無料で使用できるストレージ容量が5GB以上あると画像の保存や文書の保存に安心です。
具体的なサービスとしては、Googleドライブ(無料プランの保存容量:15GB)やOneDrive(無料プランの保存容量:5GB)、box(無料プランの保存容量:10GB)などがあります。もしも、無料プランでストレージ容量が足りない場合は、各種クラウドストレージの有料プランの料金と容量を比較して、最適なサービスを選びましょう。
3.セキュリティの強度
個人でオンラインストレージを利用するといっても、プロジェクト内だけの秘密にしておきたい情報を扱う場合も多いかと思います。そんな場合に気になるのが、セキュリティです。
企業が求めるような権限管理やアクセスログの取得といった機能は必要ないかもしれませんが、不正アクセスを受けて情報漏えいするような脆弱なオンラインストレージの利用は避けたいところです。
セキュリティレベルを判断する上では、利用している企業数や、サービス提供企業の技術力を基準にするのも一つの方法です。
4.データの保存期間
個人でオンラインストレージを利用する場合、無料プランで利用される方も多いかと思います。その場合、データの保存期間が決まっている製品があります。
無料ストレージでよく使われるfirestorageは、データの復元の対応を行っていないため、データのバックアップとして利用するのには適していないかもしれません。
5.機能性や利便性
機能面も重要な判断基準の一つです。特に「同期のタイプ」「共有機能」「ファイル管理の利便性」の3つの観点は、利用用途に応じて細かく確認しましょう。以下、それぞれの特徴について解説します。
始めに「同期のタイプ」に関しては、利用シーンに応じて「同期型」と「非同期型」のどちらが適しているかを見極めることが重要です。同期型オンラインストレージは、リアルタイムでのデータ同期が必要な場合に最適で、複数のデバイス間での作業をスムーズに進められます。これに対して、非同期型オンラインストレージは、特定のデータを任意のタイミングでアップロード・ダウンロードしたい場合、特に画像や動画などの大容量ファイルの管理に適しています。
次に「共有機能」では、第三者とのファイル共有の有無がポイントとなります。特定の人と編集を共有する場合は、編集権限を細かく設定できるオプションがあるサービスが便利です。また、一時的にファイルを公開する場合は、パスワード保護や有効期限の設定が可能なサービスが安心です。
最後に、「ファイル管理の利便性」も大切な要素です。特に、オンラインで直接ファイルを編集したり、プレビューする機能があるかどうかは、ストレスなく利用できるかに大きく影響します。文書やスプレッドシートを頻繁に使用する場合、これらをオンラインで直接編集できる機能は、作業効率を大幅に向上させられます。
6.デバイスとの親和性
オンラインストレージを選ぶ際には、使用しているデバイスとの親和性も大きなポイントとなります。なぜなら、親和性が高いほどデバイスとストレージ間の連携がスムーズになり、効率的運用と管理が実現できるようになるからです。
例えば、iPhoneやMacを主に使用している場合、iCloud Driveはシームレスにデバイス間でファイルを同期し、管理可能です。また、Windowsユーザーであれば、OneDriveがPC内のファイルと同じように扱え、既にシステムに統合されているため非常に便利です。AndroidユーザーやGoogleサービスを頻繁に使用する人には、Googleドライブがおすすめです。
デバイスの種類や使用頻度に応じて最適なオンラインストレージを選択することで、ファイルの自動バックアップや異なるデバイス間でのスムーズな同期が可能になります。
また、自分が普段から利用しているサービスやアプリケーションと連携しやすいオンラインストレージを選ぶことで、より効率的かつ快適にデータ管理を行えます。
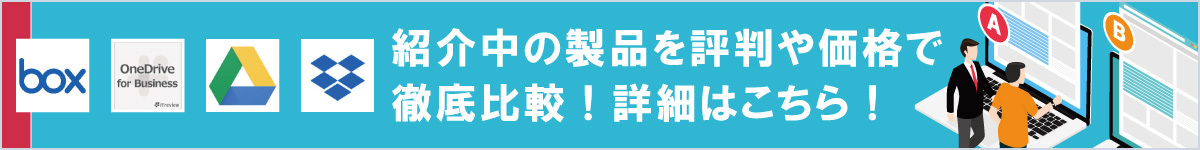
おすすめの個人向けオンラインストレージ8選
Dropbox

オンラインストレージの草分けともいえる「Dropbox」は、無料で気軽に使えるサービスです。無料プランのDropbox Basicは容量が2GBと少ないのですが、有料サービスにアップグレードすることも可能です。Dropbox Plusの場合、月額1,200円で2TBのストレージ容量を利用可能です。
また、ネットから即時に無料プランから有料プランにアップグレード可能なことから、容量が足りない時に簡単に容量アップが実現できる点も魅力です。
Dropboxは、法人ユーザーも多く、セキュリティも万全なことから、個人利用でもおすすめできるオンラインストレージです。
| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |
|---|---|---|
| Basic | 無料 | 2GB |
| Plus | ¥1,200/月 | 2TB |
| Essentials | ¥2,200/月 | 3TB |
| Business | 1ユーザーあたり¥2,400/月 | 1チームあたり9TB |
※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属
Dropboxの参考レビュー、口コミ
無料プランがあるのが嬉しい
優れている点・好きな機能
・無料プランでも2Gまで使える
・初めてでも直観的に操作ができる
その理由
・無料プランでも容量が大きくありがたい
・UIがシンプルで分かりやすい
参考:https://www.itreview.jp/products/dropbox-business/reviews/180536
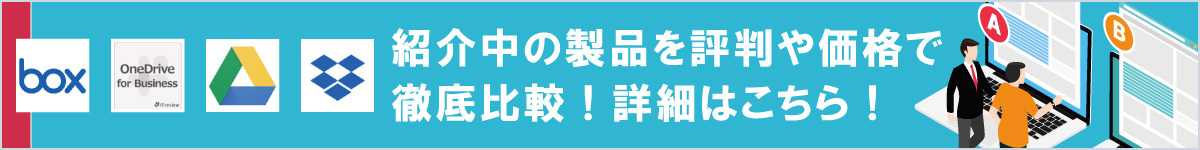
Google Drive

Googleからもオンラインストレージとして使える「Google Drive」が提供されています。Googleがリリースしているさまざまなアプリの中に含まれていることから、GoogleフォトやGmailと同じような感覚で気軽に使うことができます。
認知度の高いサービスであり、無料で15GBまで使えるので、導入しやすいサービスとなっています。もちろん有料アップグレードも可能です。Google Driveの有料版は何種類かのグレードがありますが、個人利用ではBasic(月額250円、容量100GB)、Premium(月額1,300円、容量2TB)がおすすめです。自分が使う容量に合わせてグレードを選ぶことができるのもうれしいですね。
| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |
|---|---|---|
| 個人向け (料金なし) | 無料 | 15GB |
| Google Oneベーシック | ¥2,500/年 | 100GB |
| Google Oneスタンダード | ¥3,800/年 | 200GB |
| Google Oneプレミアム | ¥13,000/年 | 2TB |
GoogleDriveの参考レビュー、口コミ
クラウドのドキュメント・データ管理はこれ1つで十分です!
クラウドのドキュメント・データ管理ツールとして十分すぎる機能がありますが、最も良いのはフォルダの階層分けのカスタマイズがしやすく、ファイルの移動もドラックアンドドロップでできるところです
参考:https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/180814
無くてはならないものになった
Googleのサービスだけあり、かゆいところに手が届き高レベルの満足度が得られるところが良い。ストレージの問題を解決して、どこからでもアクセスできるようになったので仕事の場所を選ばなくなり、また確認作業など大幅な時間短縮につながった。
参考:https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/180130
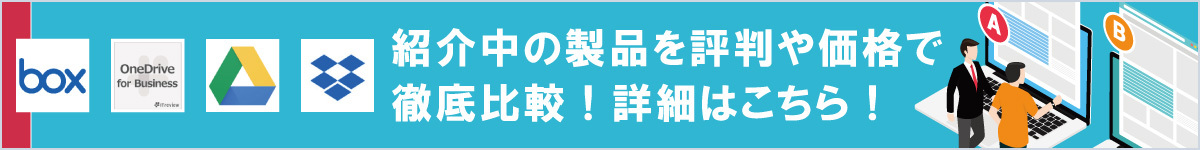
OneDrive

「OneDrive」はMicrosoftが提供しているオンラインストレージサービスです。標準でPCのエクスプローラーからファイル操作が可能となっており、使いやすさが魅力のサービスです。
無料の容量が15GBから5GBに減ってしまったようですが、同社が提供するOSのサブスクリプションサービス「Office365」を導入している場合、無料で1TBを使うことができます。OSでWindowsを採用している場合、心強いサービスです。
| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |
|---|---|---|
| Microsoft 365 | 無料 | 5GB |
| Microsoft 365 Basic | ¥2,440 /年 | 100GB |
| Microsoft 365 Personal | ¥14,900 /年 | 1TB |
| Microsoft 365 Family | ¥21,000 /年 | 1TB×6ユーザ |
※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属
OneDriveの参考レビュー、口コミ
Windwosとの相性良好
Microsoft製のクラウドドライブとして10年以上使っていますが、最近のものはエクスプローラーとの兼ね合いが安定してきました。※初期のものはバックグラウンドでの動作の異常終了が目立っていました。Office365に標準で1TBの容量が付与されていて、ユーザーファイルのバックアップ等に活用しています。
参考:https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/178209
約1年使用してのレビューになります。
Windowsに標準で搭載されています。エクスプローラ感覚でクラウドサーバーのデータをアップ、ダウンロードできること、共有できることが魅力です。無料で試用できるので、まずは使い勝手を確認してみて、それから本格使用に移ってもいいでしょうね。
参考:https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/177770
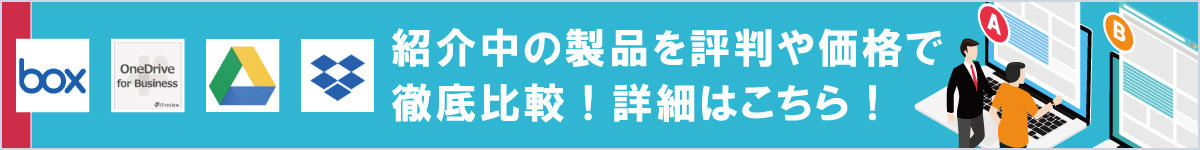
box
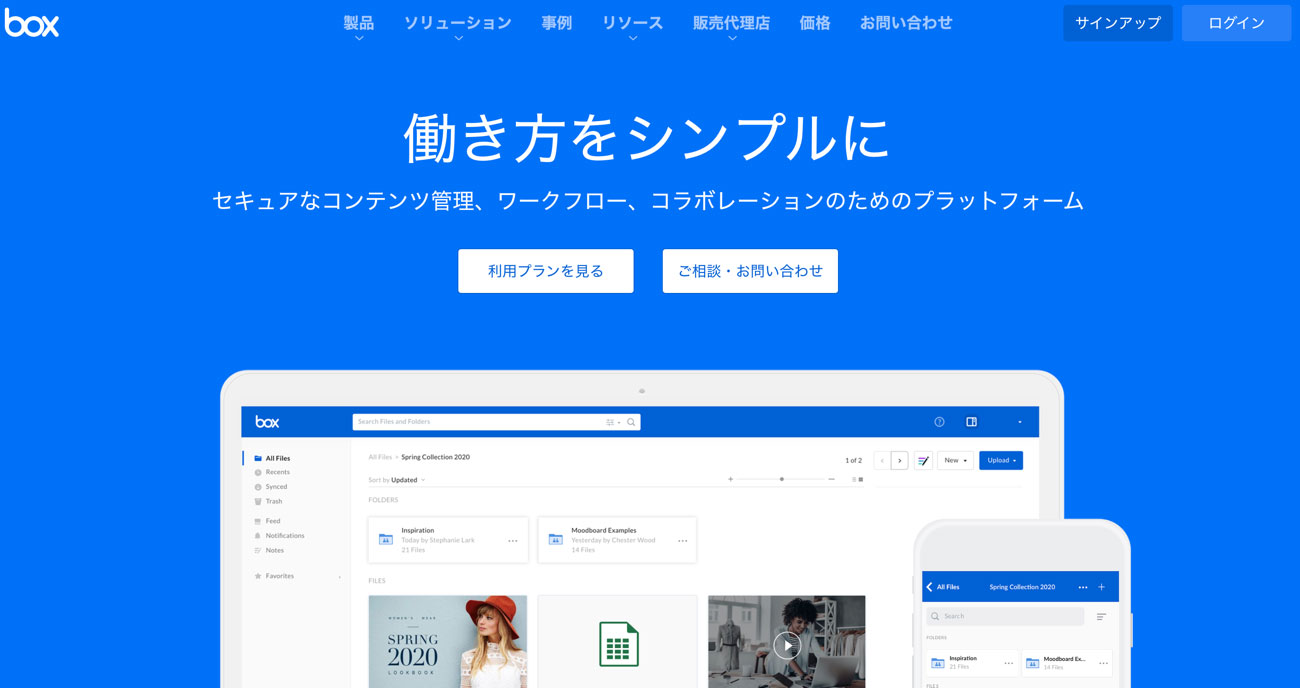
「box」はセキュリティ面で定評があるオンラインストレージです。共有リンクを使用して取引先とファイル共有する際っは、パスワードや有効期限を設定できます。さらに、高度なレポート機能があり、アップロードやダウンロード、閲覧といったアクセス履歴をワンクリックで確認できます。
容量無制限のコースは月額1,881円となっていますが、無料プランも用意されており、10GBの容量があります。無料での容量が大きく、有料版への移行もできることがおすすめのポイントです。
| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |
|---|---|---|
| box Businessプラン | 1ユーザーあたり15ドル/月 | 無制限 |
boxの参考レビュー、口コミ
操作性そのままに容量気にせずサクサク使える
クラウド保存であることからファイル保存容量を一切気にせず業務ができるのは大変ありがたい。またWebブラウザでも閲覧・利用・編集ができるため、部門メンバーで同じファイルを同タイミングで開き、MTG中にリアルタイムで編集などができるので業務が捗る。特に会議の議事録作成シーンではこの機能があることで、メンバー同士でフォローがリアルタイムでできるので良い。
参考:https://www.itreview.jp/products/box/reviews/181143
安全に使用できるオンラインストレージサービス
現在、社内のクライアントサーバーのクラウド化を検討しているが、オンラインストレージの中でも、普段からファイルの受け渡しやプロジェクトメンバー間での共有ツールとして利用している本製品が第一候補に挙がっている。
オンラインストレージサービスのシェアも高く、その分安心感がある。
参考:https://www.itreview.jp/products/box/reviews/177016
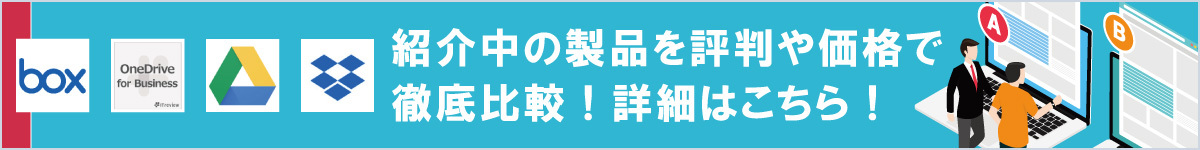
iCloud Drive

「iCloud」はiPhoneやiPadといったApple社の製品を利用されている方に付与されるデータストレージサービスです。
Apple IDがあればアクセスすることが可能で無料で5GBの容量を使うことができます。容量の追加も容易で50GBで月額130円、200GBで月額400円、2TBで月額1,300円と価格もリーズナブルです。
懸念されるのが非Apple製品ユーザーとの連携ですが、「Windows用iCloud」もリリースされていますので、ダウンロードすることでデータの共有も可能です。
| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |
|---|---|---|
| iCloud+5GBプラン | 無料 | 5GB |
| iCloud+50GBプラン | ¥130/月 | 50GB |
| iCloud+200GBプラン | ¥400/年 | 200GB |
| iCloud+2TBプラン | ¥1,300/年 | 2TB |
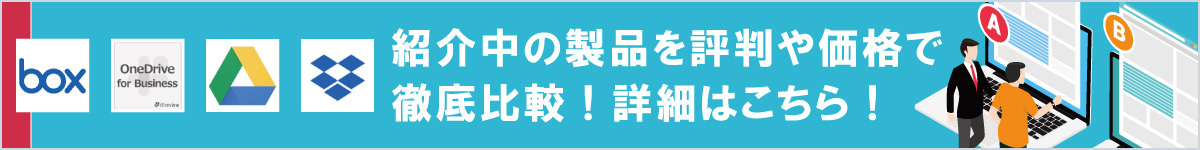
MEGA

MEGAは無料プランで20GB使える、容量が魅力のオンラインストレージです。ビジネス向けの「MEGA PRO I」は、容量1TBかつ最大ファイルサイズが無制限という大きな特徴があります。
共有フォルダとしても十分使用可能な容量ですが、最大ファイルサイズ無制限という特徴を踏まえると、「大容量のファイルの共有」において強みを発揮します。
有料プランの価格も、ストレージ量によって金額が細かく変わるので、使用容量によってコストを柔軟に変更させたい方向けのサービスです。
| プラン名 | 料金 | ストレージ容量 |
|---|---|---|
| フリー | 無料 | 20GB |
| Pro | ¥16,301〜¥48,907/年 | 2〜16TB |
| Pro Flexi | ¥2,445〜/月 | 3TB〜10PB |
※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属
MEGAの参考レビュー、口コミ
無償利用可能な大容量クラウドストレージ
優れている点・好きな機能
・上限50GByteまで使用可能なため、大量のデータを保管することができる。
・チーム内でファイルの共用が容易。
・MegaSyncアプリを使用すると、ローカルディスクとクラウドを自動で同期でき、手間いらず。
参考:https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/150787
DROPBOXと比較。大容量オンラインストレージ
DROPBOXが2GBの無料ストレージ容量でスタートし、友達に紹介することを通して最高16 GBに増えますが、MEGAは無料アカウントでも20GBもあります。
MEGAは、セキュリティ対策もしっかりしており「エンドツーエンド暗号化」を採用し、データが盗まれたとしても、暗号化されているので情報が漏れるリスクを軽減できるため、安心して使用する事ができ、ファイルの共有アクセスの許可の設定があるため、アクセス権限で読み取り専用、読み取り/書き込みなど共有者によって権限を変更する事ができるので役職や部署に応じて接続できるファイルを分ける事が出来ます。
参考:https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/165189
AOSBOX Home
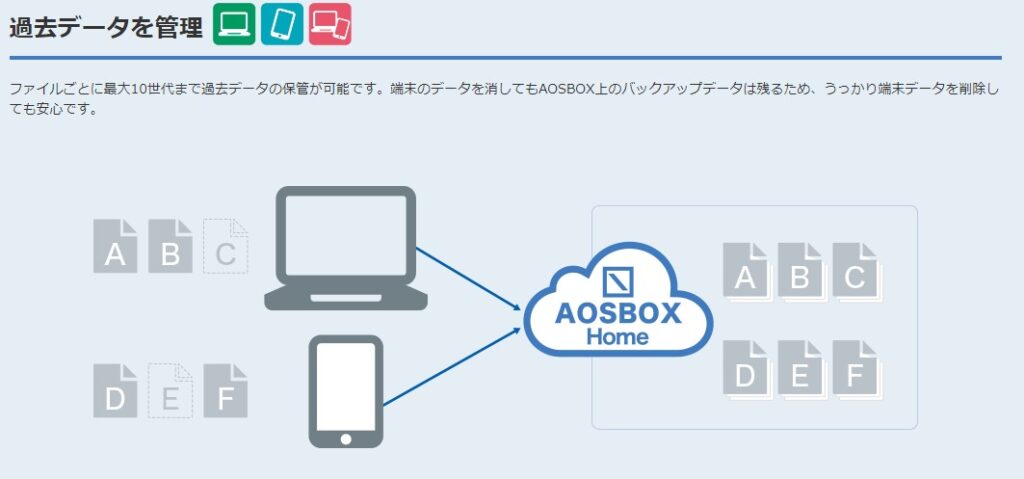
AOSBOX Homeは法人向けストレージを提供するAOSデータが個人向けに提供するプランです。月額500円から大容量のオンラインストレージを使うことができます。
パソコン1台のみ、もしくはモバイル3台であれば容量無制限(1ファイルの最大保存容量15GB、1ヵ月の最大保存容量が500GB以内の場合)で利用することができます。パソコン+モバイル各3台を接続して使う場合は100GBまでのストレージとなっています。
AOSBOXの参考レビュー、口コミ
操作が簡単で価格も抑えられる
価格が非常に安いと感じました。もともとはITベンダー経由でAzureにバックアップをしておりましたが、数か月分の費用で年間利用ができるため、回収までの期間が非常に短かったです。
特にコールドバックアップであれば、即時の復旧は出来ませんが、その分費用も抑えられているので、データの重要性によってプランが検討できます。
バックアップ対象の設定、リストア方法なども簡単なので、念のためバックアップなどに使うことも可能かと思います。
参考:https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/99853
手軽にクラウドバックアップを構築できる製品
優れている点・好きな機能
・簡単に設定ができる点
・通常ストレージorコールドストレージを予算や容量によりチョイスできる
・1度設定すれば、年次でライセンス更新さえすれば基本的にメンテナンス不要
その理由
・Windows環境のPCやサーバーにアプリケーションをインストール、対象データとスケジュールのみ設定すればあとは全自動でバックアップ可能という簡単な製品
参考:https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/160042
firestorage

オンラインストレージの老舗であるfirestorageは、無料で使える便利なサービスです。ただ、無料で利用できる分、広告が多く配置されているため、ややサイトが見づらい傾向があります。操作性が気にならないのであれば、気軽に使えるため候補のひとつに加えてもいいでしょう。
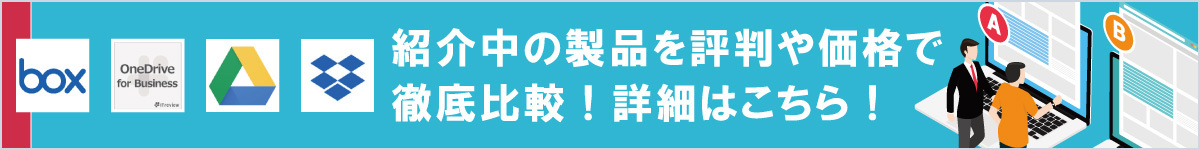
まとめ
本記事では、個人でオンラインストレージを選ぶ際のポイントとなる、「価格」や「ストレージ容量」、「セキュリティ」などを踏まえ、おすすめ個人向けオンラインストレージをご紹介しました。自分にあったオンラインストレージを選定する一助になれば幸いです。
また、個人で利用する方でも、特にセキュリティが気になる方は、法人向けのオンラインストレージを利用することをおすすめします。
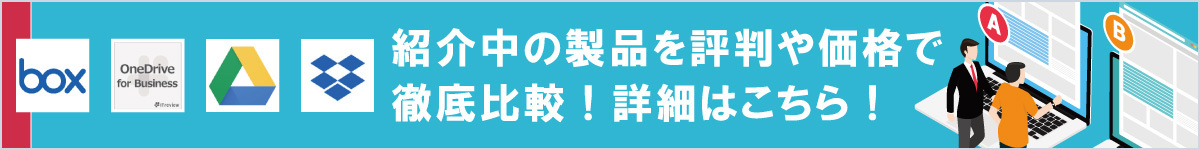
投稿 個人利用でおすすめのオンラインストレージ(クラウドストレージ)8選!価格や容量は? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 無料で使える3D CADフリーソフト7選|機能・特徴まとめ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、その機能性の高さがゆえに、購入には膨大なコストがかかってしまうことも事実。作業の進捗を左右するツールになり得るため、ソフト選びは慎重に進めたいところですが、まずは無料で使えるものを活用していきたいと考える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、無料で利用できる4つの3D CADソフトをご紹介し、その機能や特長について解説します。無料かつ高機能なソフトの活用で、さらなる作業の効率化を図りましょう。
3D CADソフトとは?
3D CADソフトとは、立体形状の図面を「長方形」や「円」を使って作成するソフトです。従来は平面上の図面を描く2D CADソフトが主流でしたが、3D CADソフトの登場により、立体的に図面を表現することが可能になりました。
より詳細な形状把握や、具体的な体積や重さも算出できるため、製造や建築といった業種で幅広く利用されています。
有料ソフトとフリーソフトの違い
有料ソフトとフリーソフトでは、使用できる機能に違いがあります。作図方法や他CADソフトとの互換性に制限がある場合があります。しかし、個人的な利用はもちろんのこと、業務で使用できる最低限のレベルではあるため、企業でもフリーソフトが導入されているケースが多々あります。
かつては高額だった3D CADソフトですが、最近では3Dプリンターの普及に伴い、個人でも3Dデータを扱う頻度が増えました。ベンダーからも、無料で使用できる3D CADソフトが多く提供されています。
3D CADソフトの導入を検討している場合は、まずはフリーソフトから使ってみると良いでしょう。
無料の3D CADソフトの選び方
まずは、自身のパソコンのOSに対応している無料3D CADソフトを選びましょう。無料でソフトをインストールしても、パソコンのOSに対応していなければ使用できません。無料3D CADソフトの多くはWindowsに対応しているものの、Macには対応していないケースも多々あります。また、営利目的で使用したい方は、商用利用可能な無料3D CADを選んでください。
OSなどを確認したら、自身に必要な機能を備えているかチェックしましょう。無料3D CADソフトは、機能やデータ形式が一部制限されていることがあります。使用したいソフトウェアと互換性のあるモデルを選ぶことも大切です。建築・機械設計などの用途も踏まえて、自社の業種に合致しており、必要な機能を搭載した無料3D CADソフトを選定してください。
ビギナーユーザーでも利用しやすいUIかどうか
3D CAD初心者は、ビギナーでも使いやすいUIを採用した製品を選びましょう。高機能なソフトを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。直感的に操作できるUIを採用したソフトなら、初心者でもスムーズに使用できます。
また、3D CAD初心者は、日本語に対応しているソフトを選ぶと安心です。未対応の場合は、日本語のマニュアルがあるソフトを選ぶとスムーズに操作できるでしょう。
無料で使える3D CADソフトのおすすめ7選
フリーで使用できる3D CADソフトの中でも、特に知名度や人気の高いものをご紹介します。気になったソフトは、実際にユーザーの口コミや評判をチェックしてみましょう。
Fusion 360
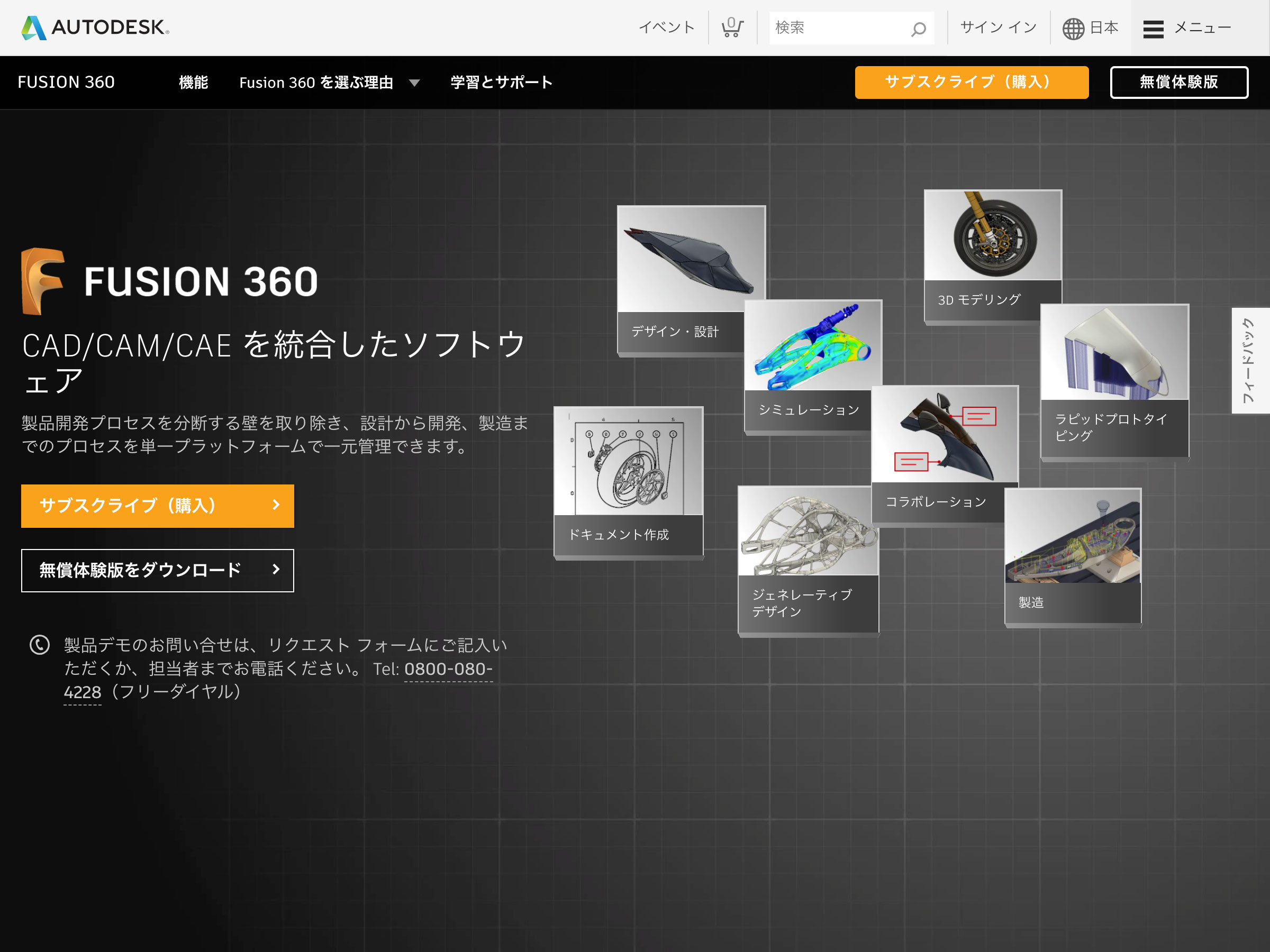
無料で使える3D CADソフトの中では、非常に人気度の高いソフトです。本来は有償ソフト(年間61,600円〜)ですが、使用期間を限定した無料体験版をダウンロードできます。
無料で使用できる期間は、非商用目的であれば1年間、商用目的であれば30日間です。なお教育目的であれば、3年間無料で使うことができるので、学生や教員の方におすすめです。
デザイン・設計といった基本的な機能に加えて、シミュレーション(CAE)や製造プログラミング(CAM)の機能も実装されており、製品開発プロセスをFusion360で一元管理が可能です。
Fusion 360の主な特長
- クラウド上での作動のため、インターネット環境にあればどこからでも接続可能
- CAD、CAM、CAEの統合ソフト
- 非営利目的の場合は無償で一定期間利用できる
- 高価なCADソフトに劣らない高機能性
- ファイルフォーマットが豊富で他CADソフトとの互換性が高い
Fusion 360の対応OS
- Windows、Mac
Fusion 360の参考レビュー、口コミ
無料で使える3DCADをお探しならおすすめ
優れている点・好きな機能
・スケッチ機能が使いやすく、寸法拘束、幾何拘束でモデルを作ることが出来、後々の形状変更も数値の変更だけで済むため作業が少なくて良い。
・穴作成コマンドで普段使用するザグリ形状やタップを作成するとき、サイズを指定するだけで形状が作成出来るため簡単
参考:https://www.itreview.jp/products/fusion-360/reviews/146939
初心者にもオススメ!
容易に3Dモデルの解析を行うことができる点はすごく良いと思います。また、材質も数多くあり途中で変更することもできるので都合が良い点で気に入っています。
参考:https://www.itreview.jp/products/fusion-360/reviews/134032
Creo Elements/Direct Modeling

PTC社が提供するCADソフト、<Creo Elements/Direct Modeling(クリオエレメンツ/ダイレクトモデリング)には、無料版としてCreo Elements/Direct Modeling Express(クリオエレメンツ/ダイレクトモデリングエクスプレス)がリリースされています。
スピーディーかつ柔軟に3Dモデルの作成を実現します。使用できる部品の数は60個と制限がありますが、高度な機能が豊富に搭載されておりユーザーから高い支持を得ています。
有料版では無制限の部品使用をはじめ、エクスポート機能やレンダリングの機能などを活用できます。
Creo Elements/Direct Modelingの主な特長
- 下書き線ツールが豊富で設計しやすい
- 設計データのリアルタイム修正
- 「カットアンドペースト」「プッシュアンドプル」「ドラッグアンドドロップ」といった編集機能で素早い設計が可能
- 最大60個の部品を持つ設計データが作成可能
- 有料版はプロ向けなので総合的に高度な機能が利用可能
Creo Elements/Direct Modelingの対応OS
- Windows
Creo Elements/Direct Modelingの参考レビュー、口コミ
操作性抜群
初めて3DCADを使用する方にもお勧めです。
私も初めての3DCADがCreoでしたが、操作も簡単で1週間程で覚えられます。
特に動作確認(CAD上で設計した物を自動で動かす)機能は簡単に行うことが出来
これにより設計ミスを減らすことが出来ます。
またこのCADの操作がわかれば仮に他のCADに変わったとしても直ぐに使用できると思います。
参考:https://www.itreview.jp/products/creo-elements-direct/reviews/95596
モデリングが非常に容易
タイトルの通りモデリングが非常に容易です。ワークプレーンと言われる下書きに実線を描き「プル」コマンドだけで3Dモデルが浮き上がります。そこから粘土細工で加工するように、形状を追加したり削ったりコマンドが用意されているので直感的な操作で機械設計が可能です。
参考:https://www.itreview.jp/products/creo-elements-direct/reviews/95976
Blender
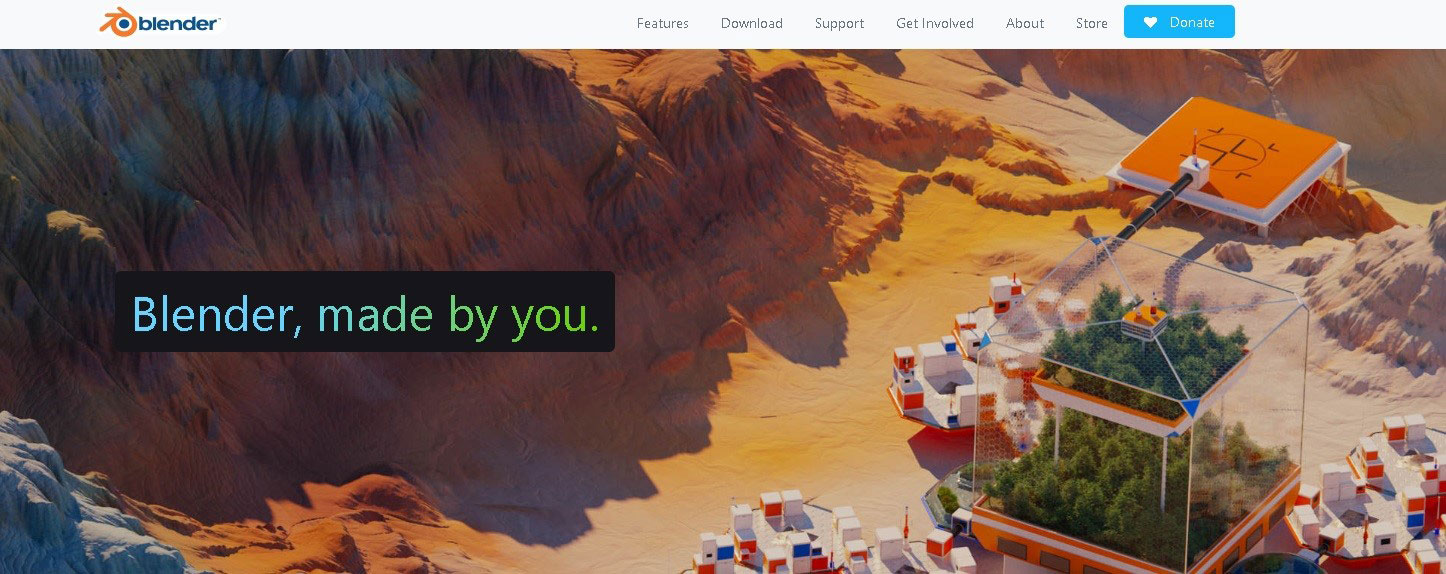
Blender(ブレンダー)は、ブレンダーファウンデーションが提供する多機能なフリーソフトです。
3D CGソフトとしてリリースされていますが、モデリングやレンダリング、スカルプティングなどといった機能を備えているため3D CADとしての役割も果たします。さらに3Dモデリングにかかわる機能は、一般的な3D CADソフトに劣らない操作性を誇ります。
アニメーションやVFX、ゲーム開発まで対応している機能の高さから、3D CG・3D CAD双方のユーザーより支持を得ています。
Blenderの主な特長
- ・完全オープンソースでアップグレード頻度が高いため、常に最新版を利用できる
- ・特徴的な独自UIはカスタマイズが可能
- ・アニメーションやゲーム、動画の作成も可能
- ・リアルなシミュレーションが得意
- ・マルチプラットフォーム対応
Blenderの対応OS
- Windows、Mac、Linux
Blenderの参考レビュー、口コミ
無料なのにできることが多いCGソフト
優れている点・好きな機能
・無料で使えるCG作成ソフトとしてはかなりクオリティーが高く、様々なアニメーションを柔軟に作ることができる。
・テンプレートなどが多く公開されており、それらを使うことで簡単に質の高いCGを作ることができる。
参考:https://www.itreview.jp/products/blender/reviews/136223
無料とは思えない機能の多さ
無料とは思えないほど多機能かつ、起動や操作時の速度、データに対する処理などの反映の速度、操作しやすさなど申し分がない。これ一つで直感的に3Dデザインを行えるため、初心者ならこれを勉強しておけばハズレがない。日本語にも対応している。
参考:https://www.itreview.jp/products/blender/reviews/136148
DesignSpark Mechanical

DesignSpark Mechanical(デザインスパーク メカニカル)は、デザインスパークが提供するWindowsベースの3D CADソフトです。
直観的に操作できる分かりやすいインタフェースで、初心者でも手軽に設計を開始できます。PCでの動作が軽いため、推奨されるPCスペックもさほど高くないことが特徴です。
3Dモデルライブラリも豊富で簡単にインポートできるので、柔軟な設計が可能です。オフライン環境でも利用でき、データはローカル保存になるため流出の心配はありません。
DesignSpark Mechanicalの主な特長
- 自動バックアップ機能
- 複雑な曲面も作成可能なブレンド機能
- dxfファイル対応により、Jw_cad(ジェイダブルキャド)等の2D CADからの移行も簡単
- STEP, STL, SKP, OBJ, AutoCAD DXF等のインポート、エクスポートに対応
- 拡張モジュールの導入で活用方法が広がる
- マウスジェスチャーベースのUIで直感的な操作が可能
DesignSpark Mechanicalの対応OS
- Windows
DesignSpark Mechanicalの参考レビュー、口コミ
初心者でも簡単に使えて重宝しています。
優れている点・好きな機能
・ある程度のCAD知識を持っている人なら3D設計初心者でも感覚で使えます。
・何種類かのデータを出力できるので、3Dプリンターでの製作以外でも色々流用出来ます。
その理由
・アイコンの絵や並びがとっても分かりやすいです。
・STLデータが出力出来るのでそのまま3Dプリンターで製作できる他、DXTやPDFも出力出来ます。
参考:https://www.itreview.jp/products/designspark-mechanical/reviews/146214
超直感的に使えて初心者にはうってつけ
とてつもなく分かりやすいのに無償で使えるのが一番のメリットです。私は参考書付きでこのソフトで3D-CADを学びましたが、1度も詰まることなく丸一日で参考書を学びきることができました。ブロックを作図し、くりぬいたり面取りをしたり、複製したり断面図を見たりと、全ての操作が直感的に行えます。このソフトを入れたことで世の中に出回っている3Dデータも簡単に参照できるようになったため、はじめの一歩に選んで本当によかったと思える3D設計ソフトです。
参考:https://www.itreview.jp/products/designspark-mechanical/reviews/95766
FreeCAD

FreeCAD(フリーキャド)は、FreeCADチームが提供するオープンソースの3D CADソフトです。
マルチプラットフォーム対応であらゆる機種やOSで利用できるほか、ユーザーによる高度なカスタマイズや拡張も可能です。
初心者には少々複雑なインタフェースですが、CAD利用経験のあるユーザーにとってはなじみのある操作で作業できます。建築設計向けワークベンチやスプレッドシート、ロボットシミュレーションなど、搭載機能も豊富です。
FreeCADの主な特長
- ・2D作図から3Dモデルの作成が可能
- ・STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAEなど多数のフォーマットに対応
- ・完全なパラメトリックモデル
- ・作成した製品の動きを確認するロボットシミュレーション機能
- ・多種多様なワークベンチ搭載
FreeCADの対応OS
- Windows、Mac、Linux
BricsCAD Shape

BricsCAD Shapeは、Bricsysが提供する構想設計用モデリングツールです。高速のモデリングエンジンを搭載しており、業界標準のDWG形式で図面やモデルを保存できます。シンプルなインターフェースを採用し、ドロップダウンメニューでほとんどのツールを選択できるのが特長です。
建築プロトタイプを素早く作成することに特化しており、クイックドローで部屋や建物全体の3Dレイアウトを作れます。Adobe Illustratorや、CNC工作機械用プログラミング製品の多くとコラボレーションできるのも便利です。
BricsCAD Shapeの主な特長
- 業界標準のDWG形式で図面やモデルを保存可能
- ドロップダウンメニューでツールを選択できるシンプルなインターフェース
- Adobe Illustrator・CNC工作機械用プログラミング製品とコラボ可能
- 初心者に分かりやすい教材をYouTubeで公開
BricsCAD Shapeの対応OS
- Windows、Mac、Linux
BricsCAD Shapeの参考レビュー、口コミ
簡単な現場配置レイアウト図を作成できる
BricsCADのバンドルソフト。会社ではBricsCAD Proを有償利用しているため、おまけにこちらのソフトも含まれている。基本無料なので、どなたでも利用できる。複雑な編集はできないが、.dwg、.dxfのビューワーとしては問題なく使用できる。いろんなマテリアルをあらかじめ用意してくれたため、部屋のレイアウト図などを簡単に作成できる。
参考:https://www.itreview.jp/products/bricscad-shape/reviews/146208
Onshape

Onshapeは、PTC社が提供するフルクラウドの3D CADプラットフォームです。図面作成はもちろん、部品とアセンブリのモデリング、サーフェシングとシートメタルなどの機能を利用できます。モバイルフレンドリーで、どこからでもアクセスできるのが特長です。
学生・教員なら有償のスタンダードプランを無料で使用できるほか、非商用プロジェクトなら無料で使用できます。なお、オープンソースのパブリック ワークスペース上にアップロードされるため、制作物を公開したくない方は有償版を購入しましょう。
Onshapeの主な特長
- 学生・教員、非商用なら無料で利用可能
- 図面作成・部品とアセンブリのモデリング・サーフェシング・シートメタルなどの機能を搭載
- モバイルフレンドリーでどこからでもアクセス可能
Onshapeの対応OS
- Windows、Mac、Linux
Onshapeの参考レビュー、口コミ
WEB上で3DCADが操作できる
この製品の一番の魅力は、WEB上で扱えるという事です。
外勤中にノートパソコンを使って閲覧や、家で操作が出来るのでとても便利です。
SOLIDWORKSの元開発者によって開発されたようなので、SOLIDWORKSを扱った事のある方であれば、すんなり入れるのではないかと思います。
それと無償版があり、基本的なCAD機能は扱えるのでお試しが出来る所もいいですね。しかし、誰でも閲覧のできる環境でしか保存が出来ませんので、趣味で扱うなら問題ありませんが、業務使用を目的としている場合は有償版が必須となります。
参考:https://www.itreview.jp/products/onshape/reviews/70540
まとめ|フリーの3D CADソフトでも充実した機能が利用できる
有料版の3D CADソフトは高度な機能を多数搭載しているため、ハイスペックなPCが必要かつ、高い導入コストを要します。
継続的に使う予定のない場合や従業員の教育用のみに利用したい場合は、無料版CADソフトの利用が効率的です。また、有料CADソフト導入後のスムーズな運用開始のためのお試しとしても活用できます。
3D CADソフトの導入を考えている方は、まずは手軽に運用できる無料版から利用してみてはいかがでしょうか。
投稿 無料で使える3D CADフリーソフト7選|機能・特徴まとめ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ウェビナーとは?今さら聞けない基礎知識からミーティングとの違いまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>「ウェビナーとウェブミーティングの違いを知りたい」
新型コロナの影響によりリモートワークが普及した昨今、各種セミナーや勉強会についても、オンラインで実施するウェビナーへと移行する流れが加速しています。
オフラインのセミナーよりも気軽に参加することができるウェビナーですが、具体的な開催手順や参加の方法がわからないという方々も多いのではないでしょうか?
本記事では、そんな今さら聞けないウェビナーの基礎知識の解説を中心に、通常のウェブミーティングとの違いからオススメのツールまで徹底的に解説していきます。
この記事は”こんなアナタ”にオススメです!
・これからウェビナーを開催しようと思っている法人担当者
・新しいウェビナーツールの導入を検討している企業担当者
ウェビナーとは?

ウェビナー(Webinar)とは、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を掛け合わせた意味の造語であり、インターネットを介して開催されるオンラインセミナーのことです。
新型コロナウイルスの流行を契機として、昨今では、企業によるマーケティング活動や製品のプロモーション紹介など、幅広い目的で広く活用されるようになりました。
ウェビナーは、オフラインのセミナーとは異なり、パソコンやスマートフォンを使ってリアルタイムに開催することができるため、物理的な会場の確保や移動の手間などが発生せず、場所を問わずに参加できるのが特徴です。
また、各種ウェビナーツールには、質疑応答機能やアンケート機能などが実装されており、双方向なコミュニケーションを行うことができるため、オフラインセミナーと同様の効果をオンラインでも実現することが可能です。
ウェビナーの仕組み

ウェビナーは、ZoomウェビナーやTeamsウェビナーなど、専用のプラットフォームを使用して開催・参加する仕組みとなっており、主催者側と参加者側で同じプラットフォームを使用する必要があります。
主催者は、参加者へ生成された招待リンク(URL)を伝達することで、ウェビナーを開催することができます。
参加者は、主催者から発行された招待リンク(URL)に接続することで、ウェビナーに参加することができます。
ツールによって若干の違いはありますが、基本的には難しい設定は必要ないため、簡単に利用することが可能です。
ウェビナーとミーティングの違い
| ウェビナー | ミーティング | |
|---|---|---|
| 参加人数 | 最大1,000人前後 | 最大500人前後 |
| 映像共有 | ホストとパネリストのみ | 参加者全員 |
| 音声共有 | ホストとパネリストのみ | 参加者全員 |
| 画面共有 | ホストとパネリストのみ | 参加者全員 |
| 参加者一覧 | ホストとパネリストのみ | 参加者全員 |
| チャット機能 | 〇 | 〇 |
| Q&A機能 | 〇 | × |
ウェビナーの特徴:一方向型
ウェビナーは、一方向型のコミュニケーション形式が特徴であり、大勢の参加者へ一度に情報を伝えることに向いています。
プレゼンターが一方的に情報を発信する形式で、各種セミナーや講義など、主に企業のマーケティング活動や教育セミナーなどのシーンで活用されています。
ミーティングの特徴:双方向型
ミーティングは、双方向型のコミュニケーション形式が特徴であり、少人数での詳細な話し合いや問題解決に向いています。
参加者全員が自由に発言できる形式で、ビジネスの会議やプロジェクトの打ち合わせなど、主に意見交換やディスカッションなどのシーンで活用されています。
ウェビナーの種類

ウェビナーには、リアルタイムでコンテンツの配信を行うリアルタイム型(生放送型)と、あらかじめ録画しておいたコンテンツを後日配信するタイムシフト型(録画放送型)の2つの種類が存在します。
一般的なウェビナー製品では、リアルタイム型とタイムシフト型の両方を利用することが可能なため、ユーザーのニーズやコンテンツの性質に応じて、配信スタイルを使い分けることが重要です。
リアルタイム型(生放送型)
リアルタイム型(生放送型)のウェビナーは、リアルタイムでコンテンツの配信を行うウェビナー形式です。主催者と参加者が同じ時間に接続するため、リアルなコミュニケーションを取ることができる点が特徴です。
リアルタイム型(生放送型)のメリット
リアルタイム型のウェビナーのメリットとしては、フィードバックや質問へ瞬時に対応できるという点が挙げられます。
リアルタイムでの交流により、参加者の関心やニーズに迅速に応えることができます。また、参加者とのインタラクティブな交流が強化されるため、臨場感のある視聴体験が提供されることも大きな特徴の一つです。
リアルタイム型(生放送型)のデメリット
一方、リアルタイム型のウェビナーのデメリットとしては、スケジュールの調整が必要になるという点が挙げられます。
全員が同じ時間に参加する必要があるため、時間の制約が発生することに加えて、技術的なトラブルが発生した場合、早急な対応が求められるため、ウェビナーの進行に遅延が発生してしまう可能性があるでしょう。
タイムシフト型(録画放送型)
タイムシフト型(録画放送型)のウェビナーは、事前に録画されたコンテンツを配信するウェビナー形式です。それぞれの参加者は自分の都合の良い時間に視聴することができるため、時間の制約が少ない点が特徴です。
タイムシフト型(録画放送型)のメリット
タイムシフト型のウェビナーのメリットとしては、各々の視聴者が自分のペースで学習できるという点が挙げられます。
放送を繰り返し視聴することができるため、内容をより深く理解できることに加えて、タイムシフト型では事前にコンテンツを制作しておくため、品質の高い資料やプレゼンテーションを提供することができます。
タイムシフト型(録画放送型)のデメリット
一方、タイムシフト型のウェビナーのデメリットとしては、コミュニケーションの要素が欠けるという点が挙げられます。
リアルタイムでの配信ではないため、参加者の質問やフィードバックが遅延してしまい、双方向のコミュニケーションが難しくなった結果、参加者の関心やニーズに即座に対応することが困難になってしまいます。
ウェビナーのメリット

開催のコストを抑えられる
ウェビナーのメリットの1つ目としては「開催のコストを抑えられる」というものが挙げられます。
移動にともなう交通費や宿泊費なども不要になるため、コストを抑えたウェビナー運営を実現できるでしょう。
日程の調整が自由にできる
ウェビナーのメリットの2つ目としては「日程の調整が自由にできる」というものが挙げられます。
録画型では、任意の日時で放送を視聴できるため、配信の参加率や視聴率の向上なども期待できるでしょう。
物理的な人数の制限がない
ウェビナーのメリットの3つ目としては「物理的な人数の制限がない」というものが挙げられます。
セミナーよりも多くの人々に情報を発信できるため、ブランドの認知度や知名度の向上にも貢献できます。
会場を移動する手間がない
ウェビナーのメリットの4つ目としては「会場を移動する手間がない」というものが挙げられます。
移動の手間がなく、時間と労力を節約できるため、参加者にとっても利便性の高い方法であるといえます。
座席による不公平感がない
ウェビナーのメリットの5つ目としては「座席による不公平感がない」というものが挙げられます。
全ての参加者が同じ画面から情報を受け取るため、座席による不公平感や不平等感がないことも特徴の一つです。
ウェビナーのデメリット

通信トラブルのリスクがある
ウェビナーのデメリットの1つ目としては「通信トラブルのリスクがある」というものが挙げられます。
多くの参加者が同時にアクセスするような場合には、サーバーの負荷が高まりトラブルが発生することがあります。
操作方法を覚える必要がある
ウェビナーのデメリットの2つ目としては「操作方法を覚える必要がある」というものが挙げられます。
初めて参加するユーザーにとっては、アカウントの作成や基本的な操作に時間がかかることがあるでしょう。
個別での相談や質問が難しい
ウェビナーのデメリットの3つ目としては「個別での相談や質問が難しい」というものが挙げられます。
多くの参加者がリアルタイムで視聴するため、個別での質問や相談に対応しきれないケースも多々あります。
参加者の反応がわかりにくい
ウェビナーのデメリットの4つ目としては「参加者の反応がわかりにくい」というものが挙げられます。
理解度の把握が難しくなってしまうと、適切なタイミングで内容を調整することが困難になってしまいます。
参加意識が低くなってしまう
ウェビナーのデメリットの5つ目としては「参加意識が低くなってしまう」というものが挙げられます。
リラックスした環境で視聴することが多いため、ほかの作業をしながら視聴することも容易になってしまいます。
【2024年8月】おすすめウェビナー3選|レビュー・口コミ
Zoomウェビナー

Zoomウェビナーは、Zoom社から提供されている、シンプルで使いやすいインターフェースが特徴のウェビナーツールです。
Zoomウェビナーでは、最大10,000人もの参加者をサポートしており、双方向のコミュニケーションを高品質な映像と音声で提供することができます。
| 製品名 | Zoomウェビナー |
| 満足度 | ★★★★☆ 4.2 |
| レビュー数 | 213 |
| 料金・価格 | 1,771円/月~ |
| 無料プラン | あり |
| 提供会社 | ZVC JAPAN 株式会社 |

メリット(良いポイント)
一番の特徴はインターフェースがわかりやすい点です。直観的になっており、よく使う画面共有ボタンがわかりやすくなっていていざ共有時にもわかりやすいと思います。

デメリット(悪いポイント)
1ユーザあたりのコストが少々高いと感じます。毎日利用するわけではないため、割高感はあります。もう少し金額が低くなると助かるのですが。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/zoom-webinar/reviews/189333
▼ 従業員規模:300-1000人未満
▼ 業界:プラスチック製品
Teamsウェビナー

Teamsウェビナーは、Microsoft社から提供されている、外部ツールとの連携のしやすさが特徴のウェビナーツールです。
外部ツールのなかでもOffice 365との統合がスムーズであり、リアルタイムのチャットやQ&Aを活用してインタラクティブな交流を行うことができます。
| 製品名 | Teamsウェビナー |
| 満足度 | ★★★☆☆ 3.8 |
| レビュー数 | 2,059 |
| 料金・価格 | 599円/月~ |
| 無料プラン | あり |
| 提供会社 | 日本マイクロソフト株式会社 |

メリット(良いポイント)
法人として利用が避けれないO365製品、これをパッケージとして一機能として使える事です。ITツールが乱立しない点および一製品にまとめてしまうコストメリットが大きいです。

デメリット(悪いポイント)
直観的な使いやすさやビジュアルでは、やはりGoogle製品に軍配が上がります。また検索エンジンに強い、Googleに比べると、検索機能では比較できない程、劣ります。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/microsoft-teams/reviews/188323
▼ 従業員規模:1000人以上
▼ 業界:情報通信・インターネット
Webexウェビナー
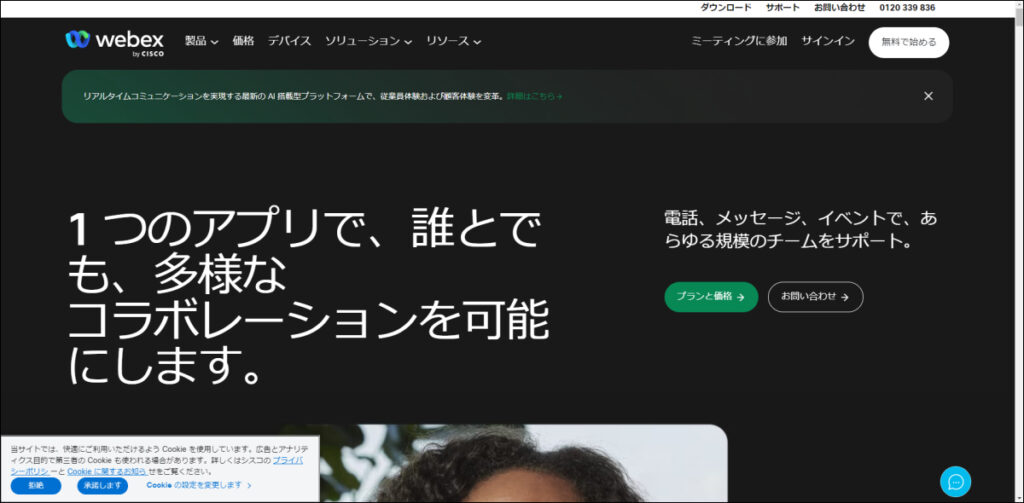
Webexウェビナーは、Cisco社から提供されている、迅速かつ安定した接続と高品質な映像音声が特徴のウェビナーツールです。
インタラクティブな機能として、チャットやQ&A、投票機能などを搭載しており、参加者とのリアルタイムなコミュニケーションを円滑に行うことができます。
| 製品名 | Webexウェビナー |
| 満足度 | ★★★☆☆ 3.4 |
| レビュー数 | 49 |
| 料金・価格 | 1,490円/月~ |
| 無料プラン | あり |
| 提供会社 | シスコシステムズ合同会社 |

メリット(良いポイント)
ウェビナーツールとしてイベント時などにセミナーなどを見ることができる。チャットやアンケート機能などもあるので、インタラクティブなセミナーにすることができるのが良い点。

デメリット(悪いポイント)
まれに映像が乱れてしまうことがあるので、ネット環境が良い環境でなくても、安定性が上がると使っていてストレスが少なくなって良いと思います。
▼ 企業名:非公開(企業確認済)
https://www.itreview.jp/products/cisco-webex-event/reviews/107111
▼ 従業員規模:100-300人未満
▼ 業界:広告・販促
ウェビナーの価格・料金・費用相場

参加人数によって料金は異なる
ウェビナーの料金は、利用できる機能や製品によっても大きく変動しますが、価格を左右する最大のポイントは、ウェビナーの最大参加可能人数です。
参加者が多いほど料金が高く設定される傾向にあるため、自社のターゲットとする参加者の人数を考慮しながら、適切なプランを選ぶことが重要です。
10~100人:無料で利用できる製品が多い
ウェビナーの参加者が100人までの場合、無料のトライアルプランでカバーできることが多いため、小規模なウェビナーであれば、まずは無料プランの利用をおすすめします。
ただし、無料プランでは、配信時間が数十分程度と制限を設けている製品が多いため、1時間以上のウェビナーを開催したい場合には、有料プランへの切り替えを検討しましょう。
100~300人:2,000円前後で利用できる製品が多い
ウェビナーの参加者が300人までの場合、2,000円前後の料金を設定している製品が多いため、中規模なウェビナーであれば、こちらのプランの選択をおすすめします。
この2,000円以上のプランでは、配信時間が数時間程度と緩和されている製品が多いため、コストパフォーマンスを重視したい場合に最適なプランであるといえます。
300~500人:10,000円前後で利用できる製品が多い
ウェビナーの参加者が500人までの場合、10,000円前後の料金を設定している製品が多いため、大規模なウェビナーであれば、こちらのプランの選択をおすすめします。
この10,000円以上のプランでは、AI翻訳機能やクラウドストレージが付随する製品が多いため、使い勝手や機能性を重視したい場合に最適なプランであるといえます。
ウェビナーの選び方と比較のポイント

①:料金や価格で選ぶ
ウェビナーを選ぶときの1つ目のポイントとしては「料金や価格で選ぶ」というものが挙げられます。
各ツールには様々な料金プランがあり、機能や参加可能人数によって異なります。製品によっては、長期契約や一括決済による割引があるものも多いため、コストパフォーマンスを重視しながら、自社の予算に合ったプランを選択するようにしましょう。
②:機能性や使用感で選ぶ
ウェビナーを選ぶときの2つ目のポイントとしては「機能性や使用感で選ぶ」というものが挙げられます。
まずは、画面共有やチャット機能、録画機能など、基本的な機能が網羅しているかを確認します。ユーザーインターフェースが直感的で操作しやすいかも重要な要素の一つとなるため、実際に使用してみて操作性や利便性を評価するようにしましょう。
③:セキュリティ対策で選ぶ
ウェビナーを選ぶときの3つ目のポイントとしては「セキュリティ対策で選ぶ」というものが挙げられます。
データの暗号化やアクセス制限など、セキュリティ機能が十分に対策されているかを確認します。とりわけ、企業の機密情報を取り扱う場合や個人のプライバシー情報を取り扱う場合には、セキュリティ対策が強固なツールを選定するようにしましょう。
④:サポートの体制や品質で選ぶ
ウェビナーを選ぶときの4つ目のポイントとしては「サポートの体制や品質で選ぶ」というものが挙げられます。
トラブルが発生した場合には、迅速に対応できるサポートが提供されているかを確認します。とくに、日本語対応のサポートや24時間対応のサポートがあるかも重要なポイントの一つとなるため、サポートの評判やレビューなども確認するようにしましょう。
⑤:無料プランやトライアルで選ぶ
ウェビナーを選ぶときの5つ目のポイントとしては「無料プランやトライアルで選ぶ」というものが挙げられます。
ツールを選定するときには、無料プランやトライアル版を利用して実際に利用してみることをおすすめします。無料プランから基本的な機能を確認することでツールの適性を判断できるため、試用期間を活用して実際の使用感や機能性を評価するようにしましょう。
ウェビナーの開催で注意すべきポイント

事前のテストは必ず実施する
ウェビナーの開催で注意すべき1つ目のポイントとしては「事前のテストは必ず実施する」というものが挙げられます。
ウェビナーは、インターネットを使用した配信サービスであるため、Wi-Fi接続の確認はもちろん、カメラやマイクなど、インフラなどの技術的な問題は必ず事前に解決しておきましょう。
課題に沿ったテーマを設定する
ウェビナーの開催で注意すべき2つ目のポイントとしては「課題に沿ったテーマを設定する」というものが挙げられます。
ウェビナーでは、参加者の確保が最初にして最大の障壁になります。ターゲットのニーズに合致したテーマ選定はもちろん、実益のある内容となるようにプレゼンは工夫して作成しましょう。
参加するメリットを提示する
ウェビナーの開催で注意すべき3つ目のポイントとしては「参加するメリットを提示する」というものが挙げられます。
ウェビナーでは、プレゼンの内容はもちろん、参加によってどのようなメリットがあるのかを訴求することが重要です。参加者が参加したくなるような特典なども検討しておきましょう。
チャットツールなどを活用する
ウェビナーの開催で注意すべき4つ目のポイントとしては「チャットツールなどを活用する」というものが挙げられます。
ウェビナーでは、リアルタイムでの質問受付や意見交換なども重要な要素となります。チャットやQ&A機能などを活用して、参加者との活発なコミュニケーションを促進していきましょう。
アンケートの記入時間を確保する
ウェビナーの開催で注意すべき5つ目のポイントとしては「アンケートの記入時間を確保する」というものが挙げられます。
ウェビナーでは、具体的な意見や改善点を求めることで、次回以降のウェビナーの質を向上させることができます。終了後はアンケートを実施してフィードバックを収集しておきましょう。
ウェビナーでよくある質問 | Q&A

ウェビナーのホストは、参加者の顔(カメラ)が見えている?
一般的なウェビナーツールでは、参加者のカメラ映像は見ることができないように設定されているため、参加者はホストや他の参加者から顔を見られる心配はありません。
ただし、ホストが特定の参加者をパネリストとして指名した場合には、指名されたパネリストの映像が表示されることがあるため、服装や格好には注意しておきましょう。
ウェビナーのホストは、参加者の声(マイク)が聞こえている?
一般的なウェビナーツールでは、参加者のマイクの音声はデフォルトでミュートに設定されているため、参加者はホストや他の参加者から声を聞かれる心配はありません。
ただし、Q&A機能やチャット機能を通じて質問を行う場合には、ホストが特定の参加者のマイクを解除することがあるため、私語や周辺の雑音には注意しておきましょう。
ウェビナーのミュートやカメラの切り替えボタンはどこにある?
一般的なウェビナーツールでは、マイクやカメラの切り替えボタンは、画面下部か上部に配置されているツールバーから行うため、基本的には発見しやすい位置に設置されています。
マイクのミュートボタンはマイクのアイコン、カメラの切り替えボタンはカメラのアイコンで表示され、ボタンをクリックすることで、音声や映像のオンオフを簡単に切り替えることが可能です。
まとめ

今回は、今さら聞けないウェビナーの基礎知識の解説を中心に、通常のウェブミーティングとの違いからオススメのツールまで徹底的に解説していきました。
コロナの流行によってオンライン文化が浸透した現在では、セミナーの開催についても、物理的な制約を受けないウェビナーを採用する企業が増加しています。
マーケティング活動やブランディング、ファンコミュニティの育成など、ウェビナーには幅広い用途が無限に存在するため、これを機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか?
投稿 ウェビナーとは?今さら聞けない基礎知識からミーティングとの違いまで徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 セキュリティログとは?今さら聞けないログの保管が必要な理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>なかでもセキュリティログは、不正アクセスやデータ漏洩などのインシデントの検出・対応に不可欠であるため、SaaSを導入するときには、ログ管理機能を備えたサービスを選ぶことが重要です。
本記事では、なぜセキュリティログを保管しているSaaSの選択が重要なのか、その理由と具体的なメリットや損害の大きさなどについて、わかりやすく解説していきます。
「世界一わかりやすい情報セキュリティ」連載記事はコチラから!
第1回:【SaaS利用者必見】話題の”セキュリティ評価”の重要性と対策方法を紹介!
第2回:【多要素認証とは?】パスワードのみの危険性とSaaSに必要な理由を解説!
第3回:知っていますか?IDSやWAFなどSaaS導入で確認すべきサイバー攻撃対策を解説!
セキュリティログとは?
セキュリティログとは、ソフトウェアで何が起きているのかを詳細に表示するものです。主に、アクセスログ・操作ログ・アプリケーションログ・エラーログなどの種類があります。
これらのログを適切に管理することで、不正アクセスやシステム障害の早期発見、インシデント発生時の原因解析や影響範囲の特定が可能となり、セキュリティ対策の強化につながります。
セキュリティログの種類
アクセスログ
アクセスログとは、ウェブサーバーやアプリケーションが受け取るリクエストの記録です。訪問者がアクセスした日時、IPアドレス、アクセスしたページのURL、ブラウザの種類などの情報が含まれます。
アクセスログを分析することで、ウェブサイトやサービスの利用状況を把握し、セキュリティ監視やトラフィックの分析、ユーザー体験の改善などに役立てることができます。アクセスログは、デジタルサービス運用における重要なデータのひとつです。
操作ログ
操作ログとは、システムやアプリケーション内でユーザーが行った具体的な操作の記録です。ファイルの開閉記録、データの入力や変更、設定の更新など、ユーザーが行ったアクション全般が含まれます。
操作ログを分析することで、システムの利用状況の把握、不正アクセスやエラーの原因究明、作業の追跡が可能となり、セキュリティ強化や業務効率の向上などに役立てることができます。操作ログは、システム管理における貴重な情報源のひとつです。
アプリケーションログ/エラーログ
アプリケーションログ/エラーログとは、アプリケーションの実行中に生成される記録です。エラーメッセージ、ユーザーの操作、システムの状態変更など、アプリケーションに関連する情報が含まれます。
アプリケーションログ/エラーログを分析することで、アプリケーションの問題点を特定し、パフォーマンスの最適化やユーザー体験の改善に役立てることができます。アプリケーションログは、開発者や管理者にとって重要なデバッグツールとなります。
セキュリティログの必要性と損害事例
セキュリティログはインシデントの迅速な検出に不可欠なものです。セキュリティログを取得していない場合、攻撃経路が調査できないため、根本的な解決が難しく、回復不能な損害をもたらすことがあります。ここからは実際に発生したサイバー攻撃の事例を紹介していきます。
半田病院の損害事例
徳島県にある町立半田病院では、ランサムウエア(身代金要求型ウイルス)による攻撃を受けたことによって、電子カルテなどの病院内のデータが暗号化され、利用不能になりました。これにより、2か月間にわたって新規患者の受け入れが止まり、災害級の被害を発生させました。
ログの保管が行われていなかったため、調査と対応が遅れ、長時間の診療停止につながりました。復旧と新たなシステムの構築、2か月間の診療停止により、2億円超の被害が発生したといわれています。
▶ 参考:https://logmi.jp/business/articles/329519
名古屋港の損害事例
名古屋港のコンテナターミナルでは、システムがランサムウェア(身代金要求型ウイルス)による攻撃を受け、約3日間におよび、コンテナの搬出入業務が停止するという事態に陥りました。これにより、港湾業務が多大な損失を被っただけでなく、国内の物流にも影響を及ぼしました。
また、名古屋港では、過去3日分のバックアップしか保持していなかったこともあり、ログを含めたバックアップデータをオフライン環境に保持しておくことも、定期的に実施していく必要があるでしょう。
▶ 参考:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01157/112900099
セキュリティログが保管されているSaaSを入れる価値
本記事では、なぜセキュリティログを保管しているSaaSの選択が重要なのか、その理由と具体的なメリットや損害の大きさなどについて、わかりやすく解説していきます。
セキュリティログが保管されているSaaSを利用することにより、不正アクセスやデータ漏洩などのセキュリティインシデントの早期発見が可能となり、迅速な対応が実現します。
さらに、コンプライアンス要件の遵守や、法的な証拠としての役割を果たすこともあり、ビジネスの信頼性と安全性を高めるうえでも非常に重要な役割を担っているのです。
投稿 セキュリティログとは?今さら聞けないログの保管が必要な理由 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 知っていますか?IDSやWAFなどSaaS導入で確認すべきサイバー攻撃対策を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そのため、情報システム部門やセキュリティ部門の担当者にとっては、サイバー攻撃への対策は、必須業務の一環として避けては通れないものとなってきています。
本記事では、SaaS導入時に確認すべきサイバー攻撃の対策方法について、いまさら聞けないサイバー攻撃の基本概要から具体的な対策方法までを解説していきます!
「世界一わかりやすい情報セキュリティ」連載記事はコチラから!
第1回:【SaaS利用者必見】話題の”セキュリティ評価”の重要性と対策方法を紹介!
第2回:【多要素認証とは?】パスワードのみの危険性とSaaSに必要な理由を解説!
サイバー攻撃とは?
サイバー攻撃とは、インターネットやその他のネットワークを介して、個人や組織のコンピューターシステムやネットワーク、またはデータに対して、意図的に害を及ぼす行為のことを指します。
これには、不正アクセスや情報の盗み出し、ウイルスやマルウェアの拡散、データの破壊や改ざん、DoS攻撃やDDoS攻撃などのサービス妨害など、さまざまな手法があります。
サイバー攻撃は、個人のプライバシーの侵害、経済的損失、企業や組織の信頼低下など、甚大な影響を及ぼす可能性があるため、セキュリティ対策の強化が非常に重要になっています。
とくに、SaaSの導入にあたっては、導入予定のSaaS提供会社がサイバー攻撃への対策を実施しているのか、自社のセキュリティ基準に則った事前チェックが必要不可欠です。
サイバー攻撃対策が重要な理由
①:サイバー攻撃の数が増加している
サイバー攻撃対策が重要な理由の1つ目としては「サイバー攻撃の数が増加している」というものが挙げられます。
日本におけるサイバー攻撃の件数は、年々増加している傾向にあり、日本国家より正式に許可を得て統計をとっているNICT(情報通信研究機構)の調査報告によると、日本におけるサイバー攻撃の件数は10年間で約50倍にも増加しているということで、セキュリティ対策の重要性が高まっています。
このように、日々増加しているサイバー攻撃に対処していくためにも、多要素認証の導入はもちろんのこと、ソフトウェアやOSの定期的な更新を実施したり、USBメモリの利用や持ち出しに制限を設けたりなど、企業や会社全体としても継続的なセキュリティ対策を講じていく必要があるでしょう。
| 年 | パケット 数 |
IPアドレス 数 |
IPあたりの パケット数 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 約128.8億 | 209,174 | 63,682 |
| 2014 | 約241.0億 | 212,878 | 115,335 |
| 2015 | 約631.6億 | 270,973 | 245,540 |
| 2016 | 約1,440億 | 274,872 | 527,888 |
| 2017 | 約1,559億 | 253,086 | 578,750 |
| 2018 | 約2,169億 | 273,292 | 806,877 |
| 2019 | 約3,756億 | 309,769 | 1,231,331 |
| 2020 | 約5,705億 | 307,985 | 1,849,817 |
| 2021 | 約5,180億 | 289,946 | 1,747,685 |
| 2022 | 約5,226億 | 288,042 | 1,833,012 |
②:個人情報の保護が厳格化している
サイバー攻撃対策が重要な理由の2つ目としては「個人情報の保護が厳格化している」というものが挙げられます。
サイバー攻撃による損害は、単に財務的な損失に留まらず、企業の信頼性の低下や顧客情報の漏洩による法的責任など、甚大な影響を及ぼすことがあります。
とくに、SaaSを利用する企業にとっては、ビジネスの継続性や顧客の信頼を守るためにも、サイバー攻撃への対策は欠かせないものであるといえるでしょう。
※参考:志布志市ふるさと納税サイトでクレカ情報漏えいか 脆弱性突かれ不正プログラムを設置される
サイバー攻撃の代表的な対策方法
①:DDoS攻撃の対策
サイバー攻撃のなかでも、まず優先的に対処しなければならないのが「DDoS攻撃の対策」です。
DDoS(Distributed Denial of Service)攻撃とは、複数のコンピュータを利用してターゲットのサーバーに大量のアクセスを行い、サービスを停止させる攻撃手法のことです。
このDDoS攻撃の対策には、大きく分けて「予防・検出・対応」の3つの段階があり、それぞれのフェーズごとに対策を講じる必要があります。
DDoS攻撃の予防
DDoS攻撃の予防には、トラフィックの分散を図るCDN(Content Delivery Network)や、不正なトラフィックをフィルタリングするWAF(Web Application Firewall)を導入する方法があります。
DDoS攻撃の検出
DDoS攻撃の検出には、トラフィックの異常な増加を即座に識別したり、ネットワーク内部の不審な活動や攻撃の兆候を検知するIDS(Intrusion Detection System)を導入する方法があります。
DDoS攻撃の対応
DDoS攻撃の対応には、攻撃を検出したときに自動的にクリーンアップするクラウドベースのDDoS対策サービスが効果的です。例えば、AWS ShieldやCloudflareなどが広く利用されています。
②:ファイアウォールを用いた対策
サイバー攻撃の代表的な対策方法の2つ目としては「ファイアウォールを用いた対策」が挙げられます。
ファイアウォール(FireWall)とは、ネットワークとインターネットの間に設置される、入出力するトラフィックを監視する仕組みのことです。
ファイアウォールを使用することで、許可された通信のみを通過させることができるため、ネットワーク内部のセキュリティを確保することができます。
具体的な製品としては、Cisco ASAやPalo Alto Networksなどのファイアウォールがあり、これらは企業のネットワークを守るために広く利用されています。
③:IDS / IPSを用いた対策
サイバー攻撃の代表的な対策方法の3つ目としては「IDS / IPSを用いた対策」が挙げられます。
IDS(Intrusion Detection System)またはIPS(Intrusion Prevention System)とは、ネットワーク内の不審な活動や攻撃の兆候を検知し、侵入を防御するシステムのことです。
IDS(侵入検知システム)は、ネットワーク内の不正な活動や攻撃の兆候を検知し、警告を発するシステムであり、主に監視と警告に特化しています。
一方のIPS(侵入防御システム)は、IDSの機能に加えて、検知した攻撃を自動的に防ぐ機能を持っており、侵入されてしまった後の防御に特化しています。
種類としては、ネットワークベースとホストベースがあり、IDSはネットワークトラフィックを監視し、IPSは特定のコンピュータのシステムコールやファイルアクセスを監視します。
具体的な製品としては、CiscoのFirepowerやPalo Alto NetworksのPanoramaなどがあり、これらは組織のネットワークを不正アクセスから保護するために広く使用されています。
④:WAFを用いた対策
サイバー攻撃の代表的な対策方法の4つ目としては「WAFを用いた対策」が挙げられます。
WAF(Web Application Firewall)とは、ウェブアプリケーションをサイバー攻撃から保護するためのセキュリティシステムのことです。
WAFは、ネットワークの入口でトラフィックを監視し、不正なリクエストを検出して遮断することで、ウェブアプリケーションを保護する役割を果たします。
具体的な製品としては、CloudflareのWAFやAWS WAFなどがあり、これらのサービスは、設定の容易さや柔軟なルール設定が可能なため、多くの企業で採用されています。
ファイアウォールには2種類ある?ステートフルとステートレスの違い
ステートフル(Stateful)ファイアウォール
ステートフルとは「通信の状態を記憶する処理方式」を指します。特にセキュリティ分野では、ステートフルファイアウォールがこの概念を利用しています。ステートフルファイアウォールは、通信セッションの開始から終了までの「状態」を追跡し、その情報を基にパケットが許可された通信かどうかを判断します。例えば、外部からの応答ではなく、内部からのリクエストにもとづく応答のみを許可するなど、より精密な通信制御が可能になります。
ステートレス(Stateless)ファイアウォール
ステートレスとは「通信の状態を記憶しない処理方式」を指します。ステートレスファイアウォールは、各パケットを個別に評価し、その時点での情報のみを基に通過を許可するかどうかを判断します。これは、通信の履歴やセッションの状態を考慮せず、パケットのヘッダ情報(送信元・宛先アドレス、ポート番号など)だけで判断するため、処理が高速であるという利点がありますが、ステートフルファイアウォールに比べると、セキュリティレベルは低くなりがちです。
ステートフルとステートレスの比較・使い分け
| 項目 | ステートフル | ステートレス |
|---|---|---|
| 通信の状態 | 記憶する | 記憶しない |
| 必要なリソース | 多い | 少ない |
| セキュリティの強度 | 高い | 低い |
ステートフルとステートレスの違いは、通信の状態をどのように扱うかにあります。
ステートフルは、通信のコンテキストを理解し、より高度なセキュリティ対策が可能な反面、相応のリソースが必要になります。
一方のステートレスは、処理が高速かつシンプルな反面、ステートフルよりもセキュリティのレベルは低くなる傾向にあります。
ファイアウォールを使用する場合には、環境や求められるセキュリティレベルに応じて、適切な方式を選択することが重要です。
サイバー攻撃対策を実施することによる価値
本記事では、SaaS導入時に確認すべきサイバー攻撃の対策方法について、いまさら聞けないサイバー攻撃の基本概要から具体的な対策方法までを解説していきました。
サイバー攻撃対策を実施することで得られる、最も直接的なメリットは、言うまでもなくセキュリティの向上にあります。しかし、それだけではありません。
企業の信頼性の維持、法規制への対応、ビジネスの継続性の確保など、企業価値を総合的に高める効果が期待できます。従業員や顧客の情報を守ることは、社会的責任の一環として重要なのです。
投稿 知っていますか?IDSやWAFなどSaaS導入で確認すべきサイバー攻撃対策を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【いまさら聞けない】Microsoft Azureとは?初心者にもわかりやすく簡単解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>自社のビジネスを発展させるうえでは強力な味方となり得るAzureサービスの数々ですが、そもそも導入によって、どういったメリットがあり、どのようなことができるようになるのでしょうか?
本記事では、Azureの概要説明から利用できる基本的な機能、メリットやデメリットなどについて、初心者にもわかりやすく解説していきます!Azure初心者には必見の内容です!
Azureとは?

Microsoft Azure(読み方:マイクロソフト アジュール)とは、世界的に有名なMicrosoft社が提供するクラウドコンピューティングサービスです。多様な機能と高い柔軟性を持っていることから、中小企業から大企業まで、幅広いビジネスシーンで利用されています。
Microsoft Azureの最大の特徴は、IaaS(Infrastructure as a Service)、PaaS(Platform as a Service)、SaaS(Software as a Service)の各種サービスを統合したところにあります。ユーザーはインフラの管理にかかる負担を軽減し、アプリケーションの開発やデータの管理に集中することができます。
また、Microsoft Azureはセキュリティの観点からも高い評価を受けており、多層のセキュリティ対策と世界中に分散されたデータセンターを利用することにより、企業の保有するデータの安全性を保証しています。このような特性が、ビジネス環境における信頼性を高める要因となっています。
IaaSとは
IaaS(Infrastructure as a Service)は、インフラストラクチャーをクラウド上で提供するサービスです。サーバーやストレージ、ネットワークなどの基本的なコンピューティングリソースを、インターネット経由で利用することができます。これにより、ハードウェアの購入や管理の手間が省けます。
PaaSとは
PaaS(Platform as a Service)は、ソフトウェア開発と展開のためのプラットフォームを提供するサービスです。開発ツールやデータベース管理などが含まれており、PaaSを利用することにより、開発者はインフラの管理にかかる負担を軽減し、アプリケーションの開発に集中することができます。
SaaSとは
SaaS(Software as a Service)は、インターネット経由でソフトウェアを提供するサービスです。ユーザーはソフトウェアを購入するのではなく、サブスクリプションベースでアクセスすることから、ソフトのインストールやメンテナンスの必要がなく、どこからでもアクセスすることができます。
Azureで何ができる?主な機能・サービス一覧

Microsoft Azureは、幅広い用途に対応するクラウドコンピューティングプラットフォームです。ビジネスのニーズに応じて、柔軟にリソースを調整できるのが大きな特徴です。
例えば、仮想マシンの作成やアプリケーションのホスティング、データの保存と分析などを行うことができ、オンプレミスのインフラストラクチャに依存せずに、効率的なビジネス運営が可能です。
| サービス名 | 概要説明 |
|---|---|
| Azure Portal | Azureのサービスを一元管理できるツール |
| Azure DevOps | AzureでDevOpsを実現できるツール |
| Azure Active Directory | クラウドサービスのアクセスを管理できるツール |
| Azure Functions | コードをサーバーレスで実行できるツール |
| Azure Virtual Machines | 仮想マシンを作成できるツール |
| Azure AI | AIソリューションを構築できるツール |
| Azure Storage | クラウドにデータを保管できるツール |
| Azure Information Protection | クラウドのデータを保護できるツール |
Azure Portal
Azure Portalは、Microsoft Azureのサービスを一元管理するためのユーザーインターフェースです。ここから、リソースの作成、管理、監視が行えます。直感的な操作でクラウドリソースを効率的に扱うことが可能です。
Azure DevOps
Azure DevOpsは、ソフトウェア開発プロジェクトのためのサービス群です。コードの共有、テストの自動化、ビルドとリリース管理が可能。開発チームが迅速に製品を市場に投入するのを支援します。
Azure Active Directory
Azure Active Directory(Azure AD)は、アイデンティティ管理とアクセス管理サービスです。クラウドベースのアプリケーションへの安全なアクセスを提供。ユーザー認証やグループ管理が容易になります。
Azure Functions
Azure Functionsは、イベント駆動型のサーバーレスコンピューティングサービスです。コードをトリガーに基づいて自動的に実行することができ、インフラ管理の手間を省けます。効率的なアプリ開発が可能です。
Azure Virtual Machines
Azure Virtual Machinesは、Azure上での仮想マシンサービスです。必要なOSやアプリケーションをインストールして、クラウド上でサーバー環境を構築できます。柔軟性とカスタマイズ性に優れています。
Azure AI
Azure AIは、人工知能(AI)関連のサービス群です。機械学習、ボットサービス、コグニティブサービスなどが含まれます。これらのツールを使って、スマートなアプリケーションを構築できます。
Azure Storage
Azure Storageは、高い耐久性と拡張性を持つクラウドストレージサービスです。ファイル、ディスク、キュー、テーブルなどのストレージソリューションが提供されます。ビッグデータの保管にも適しています。
Azure Information Protection
Azure Information Protectionは、データ保護とコンプライアンスを強化するサービスです。文書や電子メールにラベルを付け、適切なアクセス権限を設定することができます。情報漏洩を防止し、企業データのセキュリティを確保します。
Azureを使用するメリット

すべての機能がクラウドで動作する
Azureを使用するメリットの1つ目としては「すべての機能がクラウドで動作する」というものが挙げられます。サービスやアプリケーションをクラウド上で完全に動作させることができるため、ハードウェアの制約やメンテナンスの手間が削減されます。
既存システムとの連携や移行が簡単
Azureを使用するメリットの2つ目としては「既存システムとの連携や移行が簡単」というものが挙げられます。既存のシステムやアプリケーションとの連携や移行を簡単に行えるため、システムのアップグレードや拡張がスムーズに進みます。
セキュリティの強度やレベルが高い
Azureを使用するメリットの3つ目としては「セキュリティの強度やレベルが高い」というものが挙げられます。先進的なセキュリティ機能の搭載により、企業の保有するデータの安全性を確保し、リスクを最小限に抑えることができます。
Windows系サーバーとの相性が良い
Azureを使用するメリットの4つ目としては「Windows系サーバーとの相性が良い」というものが挙げられます。Microsoft系列の製品群との連携が強力であるため、Windowsベースのシステムには最適な環境を提供することができます。
日本円での支払いに対応している
Azureを使用するメリットの5つ目としては「日本円での支払いに対応している」というものが挙げられます。Microsoft Azureは、日本円での支払いにも対応しています。これにより、日本の企業が外貨の換算や手数料の心配なく利用することができます。
Azureを使用するデメリット

運用コストが発生する
Azureを使用するデメリットの1つ目としては「運用コストが発生する」というものが挙げられます。クラウドベースのサービスとなるため、毎月の運用コストは避けられません。サービスの利用量に応じた課金が行われるため、経費の見積もりと管理には注意が求められます。
専門的な知識が必要になる
Azureを使用するデメリットの2つ目としては「専門的な知識が必要になる」というものが挙げられます。Azureの導入において、クラウド環境のセットアップや運用には、特定の技術やスキルが必要になってくるため、トレーニングや人材確保の必要性が生じる場合があります。
ネット検索で自己解決しにくい
Azureを使用するデメリットの3つ目としては「ネット検索で自己解決しにくい」というものが挙げられます。Azureの複雑なシステムにおいて問題が発生した場合、インターネットの検索だけでは解決が困難な場合が多く、サポートや専門家への依頼が必要になることがあります。
Azureを導入する手順・フロー
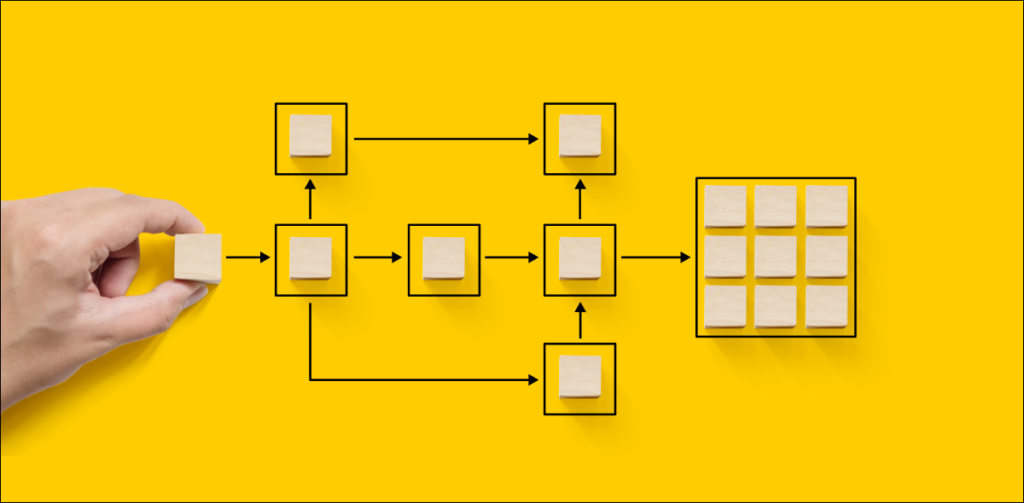
①:Microsoftアカウントを作成する
Azureを使用するための最初のステップは、Microsoftアカウントの作成です。このアカウントは、あらゆるMicrosoftのサービスへのアクセスに必要になります。公式ウェブサイトから簡単に登録することができます。
②:Azureアカウントを作成する
Microsoftアカウントを作成したら、Azureアカウントを作成します。Microsoftアカウントでサインインした後、Azureアカウントにサインインすることで、利用するサービスや料金プランなどを選択することができます。
③:Azureのポータルサイトへログインする
アカウントの設定が完了したら、Azureのポータルサイトにログインします。このポータル画面からAzureで提供される様々なサービスを管理することができます。使いやすいインターフェースで、直感的に操作することができます。
Azureの導入なら「導入支援・運用代行パートナー」がおすすめ!

本記事では、Azureの概要説明から利用できる基本的な機能、メリットやデメリットなどについて、初心者にもわかりやすく解説していきました。
Azureには、様々な機能を利用できる一方、その機能をフルに活用するためには、専門的な知識や技術の習得が必要になってくるため、初心者にはハードルの高い作業です。
自社だけでの構築や運用が難しいという場合には、ぜひこの機会に「Azure導入支援・運用代行パートナー(コンサル)」の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
投稿 【いまさら聞けない】Microsoft Azureとは?初心者にもわかりやすく簡単解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【2024年最新版】無料のおすすめオンラインストレージ4選を徹底比較! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、使い易さや安全性などを考慮しながら、無料でも利用できるオンラインストレージサービスをご紹介します。
特に、大容量の動画ファイルなどを共有、受送信したい方には役立つ内容となりますので、参考にしていただければと思います。
オンラインストレージとは?
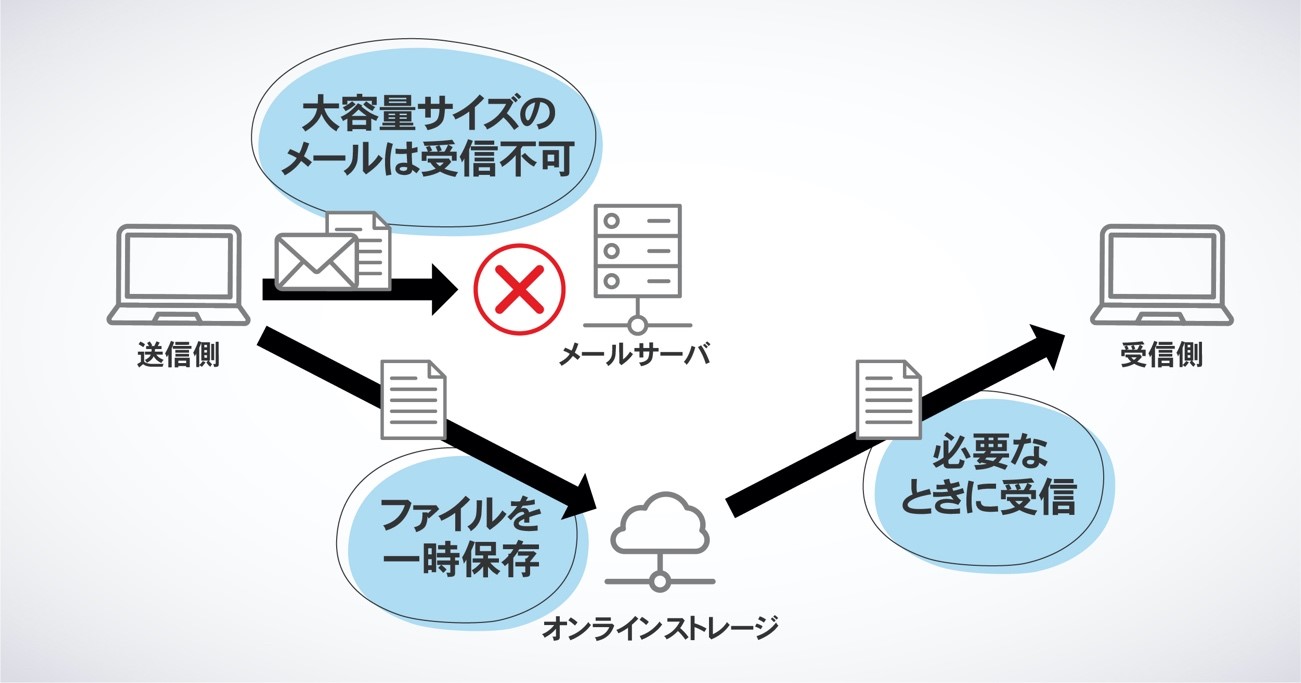
オンラインストレージ(クラウドストレージ)とは、インターネットを介してデータやファイルを保存・共有できるサービスです。
デバイス自身へのデータ保存とは異なり、場所を選ばずにどこからでもアクセス可能となるため、ビジネスの効率化や個人のデータ管理に法人個人幅広く利用されています。
無料オンラインストレージの機能やメリット
自動でデータのバックアップができる
クラウドにデータが保存されるため、パソコンの故障や紛失、災害などによるデータ損失のリスクが軽減されます。
また物理的なバックアップシステムを設置する必要がなく、その点においての初期投資や維持費用を削減できます。
ファイルの共有や編集が複数人でできる
データをURLでやりとりすることで、大容量のファイルを簡単に共有することができます。
また、ファイルの共有のみならず共同編集も可能で、複数の拠点にいる人々とリアルタイムで作業を進めることができるため、メールの送受信や外部メモリのような従来の方法による非効率なファイルのバージョン管理や混乱を避け、業務の効率化が期待できます。
コストを抑えて導入することができる
基本的な機能(ファイルの共有、ダウンロード、編集)であれば無料で使用できるサービスも多く、小規模であれば無料〜低コストで運用することができます。
また有料版の利用であっても、多くの場合はストレージ量や利用アカウント数に応じた従量課金となっており、利用規模のステージに合わせた柔軟なコスト運用ができるメリットがあります。
オンラインストレージの選び方
データの容量
無料で利用できるオンラインストレージサービスは多数存在しますが、提供するデータ容量はそれぞれ異なります。例えば、Google Driveは個人ユーザーに15GBの無料容量を提供しており、Dropboxは基本プランで2GB、MEGAは20GBの無料容量を提供しています。
オンラインストレージを選ぶ際には、まず必要とするデータ容量を確認しましょう。写真や文書などの個人的なデータのバックアップ用途であれば数GBの容量でも十分な場合が多いですが、動画ファイルや大量のデータや法人での利用の際には、有料版を検討する必要があります。
データの保存期間
無料で使えるオンラインストレージは、保存期間に制限があるものも多く、保存期間を確認して比較するようにしましょう。
特にビジネスで利用する際には、長期的な保管が必要なデータを保存するか、それとも一時的な共有のみの用途で利用するか、などに応じて選択が必要です。
例えば、電子帳簿保存法に基づくデータ保存を考えている場合は、要件を満たすか確認しましょう。
※法人で基本7年(最長10年)、個人事業主では原則5年(最長7年)
料金コスト
有料版のオンラインストレージを検討する際、ほとんどの場合で初期費用と月額料金のサブスクリプション型になっています。料金プランはサービスによって異なりますが、サービスによっては使い勝手が悪い場合もあり、プランによってはかえってコストが高くなってしまうこともあります。
有料版を選ぶ場合は、業務でどういった利用が想定されるかを確認し、運用に落としこんだ際のコストを把握しておく必要があります。
機能や操作性
容量や保存期間以外にも、機能や操作性も比較することが必要です。
例えば、ビジネス利用の場合、スマホアプリの有無やその使い勝手も重要で、ファイル共有や検索のしやすさ、プレビューの見やすさ、編集のしやすさなどがポイントになってきます。レビューを確認するほか、実際にアプリなどをインストールしてテストで利用してみるのも良いでしょう。
また、無料版の場合は機能制限があることも多く、効率が悪くなりかえって業務コストが高くなる場合もあります。
外出先であったり、社員同士で編集する場面など、シーンを想定して利便性の高いものを選びましょう。
サポート対応の有無
システム障害時や不具合の際などに問い合わせできる、サポート窓口を提供しているかどうかも重要なポイントです。
ただし、無料オンラインストレージではサポート体制が限られていることが多いため注意が必要です。
問い合わせ先があるか、マニュアルが整備されているかを確認し、場合によってはサポート体制のある有料サービスなども検討しましょう。
最大ファイルサイズもチェック
メールなどでは送信できない大容量ファイルのやりとりや共有をするには、トータルの容量だけの比較では不十分です。オンラインストレージサービスでは、データをアップロードする際のファイルサイズが制限されていることが多く、動画のようにサイズが大きなファイルはそもそもアップロードできないといったケースも発生するからです。
トータルの容量だけではなく、ご自身の利用シーンに合わせた「最大ファイルサイズ」をクリアしているかもぜひチェックしてみてください。
無料のオンラインストレージ4選
Dropbox
7億人以上のユーザー数を持つセキュアなオンラインストレージサービスです。無料プランでは2GBまでのデータ容量を提供しており、個人用途からビジネス用途まで幅広く利用できます。
ファイルの復旧やパスワード保護、透かしや閲覧履歴などのセキュリティ機能を備えている点が強みです。PCファイルの自動バックアップ機能があり、各デバイスでリンクすることができます。また、共有コンテンツの管理機能も充実しており、共同編集や権限共有管理なども可能です。
| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |
| Basic | 無料 | 2GB |
| Plus | ¥1,200/月 | 2TB |
| Essentials | ¥2,200/月 | 3TB |
| Business | 1 ユーザーあたり ¥2,400/月 | チームで9TB |
※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属
Dropboxの参考レビュー、口コミ
無料プランがあるのが嬉しい
優れている点・好きな機能
・無料プランでも2Gまで使える
・初めてでも直観的に操作ができる
その理由
・無料プランでも容量が大きくありがたい
・UIがシンプルで分かりやすい
参考:https://www.itreview.jp/products/dropbox-business/reviews/180536
ファイル保存サービスとして秀逸
Dropboxの良さはなんといってもメンバー間での資料共有が非常にスムーズになることです。クラウドファイル保存サービスの中でもシンプルなUI/UXのため初期ユーザーでもすぐに利用方法をマスターできる点も良いところです。無料会員でもそれなりの容量を保存できますが有料会員になると保存量も気にせずファイル収納できる点も良いです。
参考:https://www.itreview.jp/products/dropbox-business/reviews/178446
One Drive
「One Drive」はマイクロソフトのオンラインストレージサービスになります。Windows10/11には標準装備されており、無料で5GBまでのストレージが用意されています。
Windowsや関連製品(Excel、Word)との相性が良く、「Office365」を導入すると付属しているため、利用しているPCがWindowsの方や、MacOSでもExcelやWordを導入されている方にはおすすめです。
家庭向け
| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |
| Microsoft 365 | 無料 | 5GB |
| Microsoft 365 Basic | ¥2,440 /年 | 100GB |
| Microsoft 365 Personal | ¥14,900 /年 | 1TB |
| Microsoft 365 Family | ¥21,000 /年 | 1TB×6ユーザ |
※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属
法人向け
| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |
| OneDrive for Business (Plan 1) | ¥630 ユーザー/月 | 1TB |
| Microsoft 365 Business Basic | ¥750 ユーザー/月 | 1TB |
| Microsoft 365 Business Standard | ¥1,560 ユーザー/月 | 1TB |
※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属
Dropboxの参考レビュー、口コミ
Windwosとの相性良好
Microsoft製のクラウドドライブとして10年以上使っていますが、最近のものはエクスプローラーとの兼ね合いが安定してきました。
※初期のものはバックグラウンドでの動作の異常終了が目立っていました。
Office365に標準で1TBの容量が付与されていて、ユーザーファイルのバックアップ等に活用しています。
参考:https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/178209
約1年使用してのレビューになります。
Windowsに標準で搭載されています。
エクスプローラ感覚でクラウドサーバーのデータをアップ、ダウンロードできること、共有できることが魅力です。
無料で試用できるので、まずは使い勝手を確認してみて、それから本格使用に移ってもいいでしょうね。
参考:https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/177770
MEGA
MEGAは無料プランで20GB使える、容量が魅力のオンラインストレージです。ビジネス向けの「MEGA PRO I」は、容量1TBかつ最大ファイルサイズが無制限という大きな特徴があります。
共有フォルダとしても十分使用可能な容量ですが、最大ファイルサイズ無制限という特徴を踏まえると、「大容量のファイルの共有」において強みを発揮します。
有料プランの価格も、ストレージ量によって金額が細かく変わるので、使用容量によってコストを柔軟に変更させたい方向けのサービスです。
| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |
| 無料 | 無料 | 20GB |
| Pro | ¥16,301〜¥48,907/年 | 2〜16TB |
| Pro Flexi | ¥2,445〜/月 | 3TB〜10PB |
| ビジネス | ¥2,445〜/月 | 3TB〜10PB |
※有料プランにはその他プラン別の追加機能が付属
MEGAの参考レビュー、口コミ
無償利用可能な大容量クラウドストレージ
優れている点・好きな機能
・上限50GByteまで使用可能なため、大量のデータを保管することができる。
・チーム内でファイルの共用が容易。
・MegaSyncアプリを使用すると、ローカルディスクとクラウドを自動で同期でき、手間いらず。
参考:https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/150787
DROPBOXと比較。大容量オンラインストレージ
DROPBOXが2GBの無料ストレージ容量でスタートし、友達に紹介することを通して最高16 GBに増えますが、MEGAは無料アカウントでも20GBもあります。
MEGAは、セキュリティ対策もしっかりしており「エンドツーエンド暗号化」を採用し、データが盗まれたとしても、暗号化されているので情報が漏えるリスクを軽減できるため、安心して使用する事ができ、ファイルの共有アクセスの許可の設定があるため、アクセス権限で読み取り専用、読み取り/書き込みなど共有者によって権限を変更する事ができるので役職や部署に応じて接続できるファイルを分ける事が出来ます。
参考:https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/165189
Google One(Google Drive)
Google OneはGoogle Driveなどで管理しているファイルのストレージ拡張特化のサービスとなり、サブスクリプション形で容量を追加購入することができます。
Google Drive自体はGoogleアプリとして無料版がリリースされているため、GmailやGoogle フォト等などを活用する感覚で無料版を使用されている方も多いかと思います。
無料でも15GBのストレージがありますが、「Google Workspace Businessエディション」を使うと、1,360円/月で2TBの容量を得られるというコストパフォーマンスを誇ります。
| プラン名 | 料金 | ストレージ量 |
| 個人向け (料金なし) | 無料 | 15GB |
| Google Oneベーシック | ¥2,500/年 | 100GB |
| Google Oneスタンダード | ¥3,800/年 | 200GB |
| Google Oneプレミアム | ¥13,000/年 | 2TB |
| Google Workspace Businessエディション(Business Starter) | ¥1,360/月 | 2TB/ユーザ |
GoogleDriveの参考レビュー、口コミ
クラウドのドキュメント・データ管理はこれ1つで十分です!
クラウドのドキュメント・データ管理ツールとして十分すぎる機能がありますが、最も良いのはフォルダの階層分けのカスタマイズがしやすく、ファイルの移動もドラックアンドドロップでできるところです
参考:https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/180814
脱ファイルサーバー 中小企業のデータ管理にピッタリなツール
いままでオンプレのファイルサーバーでデータ管理を行っていたが、サーバーのランニングコストやメンテナンスコストが高いためクラウドサーバーを検討。さすが大手ということもあって、ユーザー側の操作のしやすさ・管理者側の設定のしやすさには文句なしです。また、googleアカウントにログインするだけで、どのデバイスからもアクセスできるのも便利。社用携帯はiphoneですが、アプリも使いやすいです。
参考:https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/180665
容量と最大ファイルサイズで選ぶおすすめオンラインストレージ5選
無料で利用できるもの以外にも、優良なオンラインストレージサービスは多くあります。「最大容量」、「最大ファイルサイズ」の2点で比較して5つ選んでみました。ビジネスでの活用を想定し、容量が100GB以上かつ月額1,000円台(1ユーザー当たり)で使えるオンラインストレージの中から10個のプランをご紹介します。
Box
Boxは、世界的に広く利用されているコンテンツクラウドで、どこからでも簡単にファイル共有や編集が可能、かつ使いやすいUIと、高度なセキュリティ、コラボレーション機能で多くの企業に導入されています。
個人からエンタープライズまで、さまざまなプランが提供されており、文書から大容量の動画やプレゼンテーションデータまでファイルを選ばず保存することができます。
特に容量については無制限となっており、「ファイルを残すか消すか」といったリソースコントロールの判断も不要となり、業務の効率化を図ることができるでしょう。
box Businessの料金プラン
・容量:無制限
・最大ファイルサイズ:5GB
・料金(1ユーザー):15ドル/月(最小3人)
boxの参考レビュー、口コミ
操作性そのままに容量気にせずサクサク使える
クラウド保存であることからファイル保存容量を一切気にせず業務ができるのは大変ありがたい。またWebブラウザでも閲覧・利用・編集ができるため、部門メンバーで同じファイルを同タイミングで開き、MTG中にリアルタイムで編集などができるので業務が捗る。特に会議の議事録作成シーンではこの機能があることで、メンバー同士でフォローがリアルタイムでできるので良い。
参考:https://www.itreview.jp/products/box/reviews/181143
安全に使用できるオンラインストレージサービス
現在、社内のクライアントサーバーのクラウド化を検討しているが、オンラインストレージの中でも、普段からファイルの受け渡しやプロジェクトメンバー間での共有ツールとして利用している本製品が第一候補に挙がっている。オンラインストレージサービスのシェアも高く、その分安心感がある。
参考:https://www.itreview.jp/products/box/reviews/177016
DirectCloud
初期費用無料で法人向けに提供されるクラウドストレージ・オンラインストレージサービスです。大容量ファイルの転送や社内外でのファイル共有、NAS・ファイルサーバのクラウド化を安全かつ簡単に実現します。
ビジネスプランでは容量3TB、最大ファイルサイズ15GB、料金は90,000円/月というプラン設定です。「DirectCloud」の特徴は、何といっても「ユーザー無制限」だということ。10人でも100人でも料金は変わりません。
100人で使えば、1人当たりの料金は900円なので、中規模企業や今後事業の拡大を計画しているベンチャー企業にとっては、費用の固定化を図れる大変使いやすいオンラインストレージです。
DirectCloud Businessの料金プラン
・容量:3TB
・最大ファイルサイズ:15GB
・料金:90,000円/月(ユーザー数無制限)
DirectCloudの参考レビュー、口コミ
高度な暗号化と認証に特化した保存場所に活用
容量課金なのでユーザー数無制限にて運用することができて、総合的にコストパフォーマンスが高いと思います。クラウドストレージとして必要な機能は一通り揃っていると考えていいと思いますし、操作感も問題ございません。感覚的に使用できるため、ユーザには特にマニュアルの準備等必要なく展開することができました。
参考:https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/153669
常に機能拡張がされており安心して使える
一番のポイントはユーザ単位の料金プランではない事。クラウドストレージを利用しようと思う企業は一旦導入してみても間違いない製品だと思います。また、日々機能拡張も行われており、他製品と比べても遜色ない充実度だと思います。
参考:https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/170935
QualitySoft SecureStorage
「QualitySoft SecureStorage」も「DirectCloud-BOX」と同様、「ユーザー数無制限」のオンラインストレージです。社内のスタッフだけではなく、顧客や協力会社を含めた社外の利用者が登録することで、急なプロジェクトの立ち上げのようなシーンで活用できます。
QualitySoft SecureStorageの料金プラン
・容量:100GB
・最大ファイルサイズ:2GB
・料金:10,000円/月(ユーザー数無制限)
QualitySoft SecureStorageの参考レビュー、口コミ
安価でも機能充実
利用アカウント数によらず、定額で必要最低限の機能を利用することができる。
ファイルの送信だけではなく、相手から大容量ファイルを安全に受け取る機能もあり、重宝している。
参考:https://www.itreview.jp/products/qualitysoft-securestorage/reviews/45020
業務効率化とセキュリティ対策
オンラインストレージを利用するにあたっての懸念点はセキュリティ対策でした。セキュリティ機能に優れた上で業務効率化にも貢献できるサービスだと思います。
参考:https://www.itreview.jp/products/qualitysoft-securestorage/reviews/12075
PrimeDrive
ソフトバンクが提供するオンラインストレージ「PrimeDrive」は、初期費用30,000円、容量100GBで180,000円と、価格だけ見ると高額なオンラインストレージです。
しかし、ユーザーは1万人まで追加費用なしで登録できるため、100人で使えば1ユーザー当たり1,800円で利用できます。法人向けに特化したオンラインストレージで、「ファイル送信前の上長の承認機能」、「ダウンロード期間・回数の指定」、「Active Directoryとの連携」など、他のオンラインストレージには見られない機能が利用できます。特に、従業員が多い大企業では喜ばれるサービスではないでしょうか。
PrimeDriveの料金プラン
・容量:100GB
・最大ファイルサイズ:5GB(ブラウザおよびモバイルアプリ経由では1.9GB)
・料金:180,000円/月(ユーザー数1万人まで追加費用なし)
PrimeDriveの参考レビュー、口コミ
大きな容量のファイルの送信にとても便利!
この製品の優れている点・好きな機能は、クライアントに大きな容量のファイル(例えば動画のファイル、PDFの画像など)を送らなければならないときに、簡単に共有ができることです。以前は細切れにして3,4回に分けてメールで送っていたファイルも、パスワードを付けて簡単に共有できるようになり、時間と労力が節約でき業務効率化に繋がりました。
参考:https://www.itreview.jp/products/primedrive/reviews/150865
セキュリティ対策に活躍
メールにて直接ファイル添付を嫌がる取引先様もあるなかで、ソフトバンクのシステムですので安心感もあるかと思います。
参考:https://www.itreview.jp/products/primedrive/reviews/177805
SugarSync
「SugarSync」は100GBプランを750円/月、250GBプランを1,000円/月で利用することができます。MEGAと同様に最大ファイルサイズが無制限(ブラウザ経由では300MBの制限あり)のオンラインストレージです。以前は使えていた無料版が終了してしまったという残念な点もありますが、「マジックブリーフケース」という機能があり、クラウドと同期しつつもあらかじめ指定したPCのローカルストレージと同期できる利便性が高く評価されています。
SugarSyncの料金プラン
・容量:100GB
・最大ファイルサイズ:無制限(ブラウザ経由では300MB)
・料金(1ユーザー):750円/月
SugarSyncの参考レビュー、口コミ
用途に合わせて使える大容量高速クラウドストレージ
10年近く契約していますが、クラウドに置くファイルとさらにローカル側におくファイルを指定する仕組み「マジックブリーフケース」という機能が大変便利です。マジックブリーフケースに入れたファイルは、クラウドと同期しつつも予め指定したクライアントパソコンのローカルストレージに保存することが可能です。この機能のメリットは、例えばWi-Fiなど通信環境が使えない状態でもマジックブリーフケースに入っているファイルは編集可能ですから、作業したいファイルはマジックブリーフケースに放り込んでおくことで、通信環境の有無に影響されることなく、いつでもどこでも作業を行うことができます。そしてクライアントPCのマジックブリーフケースで作業・変更が加えられたファイルは、通信可能な状況になれば即座にクラウドストレージに変更結果を反映されます。
参考:https://www.itreview.jp/products/primedrive/reviews/150865
オンラインストレージは利用用途を考えて比較しよう!
今回は、無料で使えるオンラインストレージサービスの紹介と、ビジネスでの活用を想定し、容量が100GB以上かつ月額1,000円台(1ユーザー当たり)で使えるオンラインストレージの中からおすすめのものを厳選してご紹介しました。
オンラインストレージといっても各サービスやプランそれぞれに特徴があるので、まずは自社の利用用途をしっかりと考えた上で比較していただくことが、満足度の高いオンラインストレージ導入につながります。
投稿 【2024年最新版】無料のおすすめオンラインストレージ4選を徹底比較! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【パスワード管理どうする?】安全な管理方法とおすすめのアプリを解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>新型コロナウイルスの影響でテレワークが推進される中、パスワードの管理方法に悩んでいる企業も多いのではないでしょうか。特に近年は多種多様なサイバー攻撃が出現しているため、適切なパスワードの作成や管理方法が求められます。
この記事ではパスワード管理の重要性や管理方法の種類、情報漏えいによって起こり得る被害について詳しく解説します。
パスワード管理の重要性
テレワークの普及によるパスワード管理の必要性の高まり
テレワークをきっかけにさまざまなクラウドサービスを導入する企業が増えたことで、パスワード管理の必要性が高まっています。覚えておくべきパスワードが増えると、メモや付せんに書き留めて管理する人もいるでしょう。またパスワードの使い回しも発生しやすくなります。さらにテレワークでは、カフェやコワーキングスペースなど自宅以外の不特定多数の人が出入りする場所で作業する機会も増加します。管理が徹底されていない場合、第三者に盗み見され不正アクセスされるリスクもあり得るでしょう。パスワードは第三者に推測されにくい複雑なものを用いたうえで、適切に管理していく必要があります。
NISC公開の資料で正しい知識を身につける
インターネットの安全・安心ハンドブック
パスワード管理を含むセキュリティ担当者の基本知識として、公的機関が制作した資料を確認し正しい知識を身につけましょう。
内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)より、「インターネットの安全・安心ハンドブック」が公開されています。
このハンドブックは、サイバーセキュリティに関する普及啓発活動の一環として提供され、インターネット社会を安心して利用できるようにするためのものです。
インターネットの基本的なリスクやトラブル、サイバーセキュリティの基礎、サイバー攻撃の手口、SNSの使い方、災害時の対策、スマホやパソコンの安全な利用方法、パスワードの重要性、中小組織向けのセキュリティ向上の重要性など、全般的な項目をカバーしています。
また、一般利用者向けだけでなく中小組織向けの抜粋版も提供されており、社内のサイバーセキュリティの知識を広めるための参考資料として活用できます。
参考:内閣サイバーセキュリティセンター「インターネットの安全・安心ハンドブック」
安全なパスワードを設定するには?
危険なパスワードとは?
パスワードの重要性が高まっている昨今においても、まだ単純な文字列を使用しているユーザーは多いです。たとえばアメリカのサイバーセキュリティ企業NordPassの調査結果によると、情報漏えいで流出したパスワードの第1位は「123456」でした。
推測されやすいパスワード設定を避けることで、安全性を高めることができます。総務省の情報セキュリティサイトによると、危険なパスワードの例として以下のようなものがあげられています。
危険性の高いパスワードの作成例
1.自分の名前や家族・ペットなどの名前、誕生日
takanashi、taro0505、19850202
2.同じ文字の羅列やわかりやすい並び、短すぎる文字
111111、12345678、asdf、aa
3.辞書にある単語利用
password、apple、thisismypass
安全性の高いパスワードの作成方法
安全なパスワードを設定するには、パスワードがサイバー攻撃によってどんな風に狙われるかを知っておくことも重要です。手口を知ることで現在の管理方法の問題点がわかり、より適切にパスワードを管理できるようになります。
もっとも多い手口が総当たり攻撃です。総当たり攻撃とは予測できるパターンを総当たりで試し、合致する組み合わせを見つける攻撃手法になります。「user」「password」「1234」のように簡単な文字列で構成されたパスワードを設定していた場合、比較的短時間で破られやすくなります。
前述の危険性の高い要素の使用を避けつつ、以下の点にも注意して設定することで、より安全性の高いパスワードを設定しましょう。
- 10桁以上
- アルファベットは大文字小文字両方を利用する
- 記号も利用する
使用する文字列の種類(大文字、記号)や桁数を増やすことで、文字列のパターンが指数関数的に大きくなるため、推測の難易度が上がり安全性が高まります。
参考:内閣サイバーセキュリティセンター「インターネットの安全・安心ハンドブック」
Google Chromeのパスワード機能を使うときは注意
Google Chromeのパスワード保存機能は一度登録したら入力する手間が省け、異なるデバイス間でもパスワードが共有できるなどのメリットがあります。すべて暗号化されているため漏えいのリスクも低いでしょう。しかし、ユーザーの管理の仕方によっては以下のような危険もあります。
- 目を離したすきに他人にデバイスを操作され、不正ログインされる
- エクスポート機能によってパスワード一覧のファイルを盗まれる
上記のような危険を防ぐには、パスワード漏えいの警告が出たらすぐに値を変更することが重要です。またパスワード管理ツールやアプリを併用し、Google Chromeの機能に依存しすぎないようにしましょう。利用者本人が日ごろから適切に管理する意識をもつ必要があります。
パスワード管理方法の種類
パスワードの管理方法は主に3つあります。それぞれメリット・デメリットと併せて解説します。
紙にメモする
Yahoo!JAPANが2020年に実施した「パスワード管理方法に関するアンケート」によると、約50%のユーザーが「メモや手帳など紙に書く」と回答したことがわかりました。それだけ現在も多くの人がアナログな方法でパスワードを管理しています。
紙にメモするメリットは簡単に管理でき、インターネット上で漏えいする心配がない点です。スマートフォンやPCで管理しているときのように、不具合や故障でデータがなくなる恐れもありません。一方で、ほかの書類と混ざって誤廃棄してしまったり、紛失や盗難に遭ったりといったリスクもあります。鍵付きの引き出しや金庫に保管するなどの対策が必要です。
Excelなどのファイルで管理する
Excelやテキストエディターなどで管理する方法です。デジタルのため、紙と違ってパスワードの入力や更新がしやすいのがメリットでしょう。
しかし、ファイルでパスワードを一括管理している場合、流出した際の影響が大きくなります。またPCの故障などでデータが消失する可能性もあります。そのため次のような対策を行うとよいでしょう。
- パスワードファイルをデスクトップなど目につく場所に保存しない
- ファイル名をわかりにくくする(「パスワード」のような安易な設定にしない)
- 定期的にバックアップをとる
- ファイル自体にもパスワードをかけ、閲覧制限を行う
パスワード管理ツールやアプリを使用する
パスワード管理ツールやアプリを利用するのもおすすめです。紙やファイルと違い、指紋認証や二段階認証を使ったセキュリティ対策も実現できます。
管理ツール・アプリのメリットは、パスワードを管理する負担を大きく低減できる点です。パスワードの自動生成機能があり、自分で考えなくても英数字や記号などをランダムに並べた長いパスワードが生成されます。またパスワードの入力フォームに自動入力されるため、メモやファイルを毎回開いて入力する手間も省けます。一方で、セキュリティレベルは製品に依存するというデメリットもあります。またサービス提供元で障害が起きると、データが喪失する可能性もあるでしょう。できる限りセキュリティ対策やサポートが充実した製品を選ぶことをおすすめします。
パスワード管理するときの注意点
二段階認証やSSOで管理体制を強化
企業がパスワード管理をするときは、従業員個人のセキュリティ意識に任せず、企業側で管理体制を強化しておくことが重要です。特定の利用者だけがアクセスできるように設定するだけでは足りません。正規の利用者のアカウント情報を窃取して、クラウドサービスなどへ不正アクセスを試みる攻撃が近年増加しているからです。パスワードを厳格に管理するとともに、漏えい時に備えて強力な認証方法を導入しておくことが重要です。
たとえば二段階認証やシングルサインオン(SSO)などが挙げられます。二段階認証とは、ID・パスワードの入力以外にアプリでも本人確認を行ったり、セキュリティコードを入力したりと本人確認のセキュリティを高める方法です。またSSOは一度ID・パスワードで認証を行うだけで、複数のシステムやアプリケーションにログインできる仕組みです。上記のような技術を取り入れることで、従業員のパスワードを一元管理しつつセキュリティリスクを防げるでしょう。
ツールやアプリに頼りきりにならない
ツールやアプリを利用することで、使い回しを防いで強固なパスワードを設定できます。しかし、ツールに依存していると以下のような問題も起こり得ます。
- ツールやアプリのセキュリティに脆弱性が見つかる
- サイバー攻撃によって大量のデータが流出する
- 突然サービスが終了して使えなくなる
万が一の事態に備え、自分でも複雑なパスワードを設定するなどセキュリティ対策を心がけましょう。また定期的にバックアップをとっておくことも欠かせません。
パスワードを利用するWEBサイトに注意する
パスワードを管理する際には、事前に利用するWEBサイトが正当なものかを必ず確認しましょう。
サイトの正当性を確認せずに安易にユーザ情報やパスワードを登録してしまうと、その情報が悪用される恐れがあります。
偽サイトではないWEBサイトであっても、パスワードの入力が必要なものについては、初めて利用する前に必ずWebサイトの運営者情報やサービス自体が問題なく運用されているかなどを事前調査しホワイトリストに入れておくことが重要です。
パスワードの窃取や詐取に注意する
フィッシングに注意
フィッシング詐欺では、本物のサイトと見分けがつかないほど巧妙に作られた偽サイトが存在します。
メール経由で案内されることが多いですが、メールに記載されたリンクを直接クリックするのではなく、ブラウザで正規のURLを直接入力する、あるいはブックマークを利用するなどして正しいWEBサイトにアクセスしましょう。
不審なメールが届いた場合や、URLをクリックしてしまった場合の対処法も知っておくことが重要です。パスワードを入力してしまった場合は、直ちにパスワードを変更するなどの対策を講じる必要があります。セキュリティ意識を高く持ち、日々のパスワード管理に注意を払いましょう。
フィッシングの手法は日々進化しており、同時にキャッチアップをしておくことが重要です。
フィッシング対策協議会(https://www.antiphishing.jp/)のウェブサイトを利用し、最新事例などを確認しておくようにしておきましょう。
物理的な対策も必要
外出先などで、第三者にPCやスマホを覗き見されることでパスワード情報が流出することがあります。
カフェや外出先などの不特定多数がいる場所でのパスワード利用をそもそもしない、利用する場合でも周りを確認してから行う、などの注意が必要です。
複数のサービスで使い回さない
サイバー攻撃の手口の中には、1つのサービスから流出したIDやパスワードを使用し、ほかのサービスへの不正ログインを繰り返すものがあります。銀行口座やクレジットカードなどの重要情報を利用しているサービスのパスワードを使い回していた場合、パスワードが漏えいすると情報にアクセスされてしまいます。身に覚えのない請求がくる、顧客情報が流出して企業の信頼を著しく損ねるなどのリスクが考えられるでしょう。複数のサービスで使い回しせず、1つのサービスに固有のパスワードを割り当てることが重要です。
定期的に変更しすぎない
従来はパスワードを定期的に変更することが安全性を保つ方法となっていました。しかし、米国国立標準技術研究所(NIST)のガイドラインによると「パスワードを定期変更する必要はなく、流出した場合に速やかに変えることが重要」と公表されています。つまり「パスワードを乗っ取られた」「サービス側で流出の可能性があった」などの理由がない限り、定期的にパスワードを変更する必要はありません。頻繁に変えることでパスワードが安易な文字列になったり、使い回したりする方が問題です。必ずそれぞれのサービスや機器に固有のパスワードを設定するようにしましょう。
参考:米国国立標準技術研究所「電子認証に関するガイドライン」
パスワード漏えいによって起こり得る被害
個人の場合
個人がパスワードを漏えいした場合、以下のような被害に遭う可能性が高いです。
- クレジットカードの不正利用
- インターネットバンキングの不正利用
- 通販サイトでの不正利用による高額請求
- なりすまし
特に多いのがなりすましです。業者のメールアドレスはフィルタリングで弾かれることがほとんどですが、正規のメールアドレスが手に入ればスパムメールの送信元に利用できます。ウイルスを添付したメールや、攻撃サイトへの誘導メールを勝手に知人に送信されるリスクがあるでしょう。「クレジットカードの利用明細に身に覚えのない請求があった」などの不審な点を感じたら、すぐにカード会社に連絡してカードを無効にしてもらうなどの対応をとりましょう。
企業の場合
企業でパスワードの流出が起きた場合、次のような被害が考えられます。
- 社会的信用の喪失
- 株価への影響
- 企業のイメージダウン
- 損害賠償の請求への対応
特に企業で情報漏えいが発覚した場合、ネットニュースやテレビで大々的に放送されるケースが多いです。自社のサービスや商品の売上が大きく下がったり、取引先から契約を打ち切られたりといった可能性もあるでしょう。また情報漏えいの原因を突き止め、システムの復旧や改善をするには、多くのコストや人的リソースを費やすことになります。業務にも多大な影響が出てしまうでしょう。
上記のような被害を未然に防ぐためにも、パスワード管理ツールやアプリを使用して適切にパスワード管理を行う必要があります。
パスワード管理ツール・アプリの選び方
パスワード管理ツールやアプリを選ぶ際は、次の5つのポイントに注目しましょう。それぞれ詳しく解説します。
1.便利な機能があるか
以下のような便利な機能があるものを選ぶことをおすすめします。パスワードを管理する工数を削減できる上、セキュリティの向上も期待できます。
- 自動生成機能
- パスワードチェック機能
- 自動登録機能
- データの自動消去機能
自動生成機能があると、パスワードを設定するときにアルファベットや記号、大文字小文字などを混在させて考える必要がなくなります。またツールによっては、パスワード生成ルールを入力すればそれに適したパスワードが作成されるので便利です。さらにパスワードチェック機能があれば「パスワードが複雑か」「推測されやすい安易な文字列ではないか」などがチェックされ、セキュリティを高められます。
またデータ消去機能では、本人以外の人間がツールを開こうとした場合にデータを削除できます。ただし、本人が複数回間違えてログインに失敗した場合も消去されてしまう可能性があります。入力ミスを防ぐために、ほかの保管方法と組み合わせるなどの工夫が必要です。
2.OSやデバイスが対応しているか
Windows、MacOS、Linux、Android、iOSなどに対応している製品がほとんどですが、念のため事前に確認しましょう。複数のOSやデバイスに対応しているツールなら、デバイス間で簡単に同期できます。どの端末でも同じようなログイン操作や管理をすることが可能です。まずは社内で利用されているOSやデバイスをリストアップし、それに対応しているツールを探すようにしましょう。
3.セキュリティレベルが高いか
セキュリティレベルの高いツール・アプリを選ぶのも重要なポイントです。生体認証や二段階認証のように強度な本人確認を行える仕組みがあれば、不正アクセスのリスクを軽減できるでしょう。またIDの使用ログを取得できる機能があると、漏えいが発生したときも対象を特定しやすくなります。
できるだけ企業への導入実績が豊富で、セキュリティの高さに定評のある製品を選びましょう。無料の管理ツールも多くありますが、万が一機密情報が社外に流出したときのことを考慮して高機能な有料版を導入することをおすすめします。
4.バックアップ機能があるか
バックアップ機能が備わっていると、誤操作でパスワードを削除してしまった場合も安心です。自動的にパスワードがバックアップされていれば、誤って削除した場合も速やかに復旧できます。「多くのシステムやサービスのパスワードを一括管理したい」という企業ほど重要なポイントです。現在はほとんどのパスワード管理ツールにクラウドへの自動バックアップ機能がついていますが、念のため確認しておきましょう。
5.操作性がよいか
日常的に使用するツールなので、以下のような操作性のよさにも注目しましょう。
- 管理画面がシンプルで見やすい
- 直観的な操作で各機能を使える
- サイトを開いたときにワンクリックでIDやパスワードを入力できる
パスワード管理ツールの中にはお試し版を提供しているものもあります。まずは使いやすさを確認してから導入を検討するのがよいでしょう。
おすすめのID・パスワード管理ツール5選
実際にID・パスワード管理ツールを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのパスワード管理ツールを紹介します。
CloudGate UNO
「ITreview Grid Award 2020 Summer」のSSO部門にて、No.1の評価を獲得したクラウドサービスです。スマートフォンアプリの「Pocket CloudGate」を利用することで簡単に生体認証でき、在宅勤務やテレワークなど社外からサービスを利用する際のセキュリティリスクを軽減します。シングルサインオン機能を採用しているため、一度のIDとパスワードのログインで複数のクラウドサービスに安全にアクセス可能です。また認証方式もパスワード認証・多要素認証・パスワードレス認証の3種類あり、ユーザー側でどれを利用するか選べるのもメリットでしょう。料金はスタンダードプランの場合、1ユーザーあたり220円/月です。
CloudGate UNOの参考レビュー、口コミ
細かな設定が可能
管理画面もシンプルで、操作性が良い。ダッシュボードでは一覧で状況をすぐに把握できる。セキュリティレベルも細かく設定できるのでユーザーの切り分けも細かく設定可能。
参考:https://www.itreview.jp/products/cloudgate-uno/reviews/173007
安定したSSOシステム
優れている点・好きな機能
・UIの見やすさ
・サポートの充実
その理由
・UIが分かりやすく、分かりやすいため設定が比較的容易だと感じます
・ユーザーが加入できるコミュニティサイトがあり、気軽に質問等が出来る
参考:https://www.itreview.jp/products/cloudgate-uno/reviews/172696
HENNGE One
約1900社のさまざまな業種や業態で利用されているセキュリティサービスです。ID・パスワードの一元管理に加え、デバイス証明書やワンタイムパスワードの多要素認証も充実しています。パスワードをよりセキュアに保護することが可能です。また導入前にはコンサルタントが顧客環境に最適なサポートを行ってくれるのも魅力。導入後もサポートメンバーに運用やサポートを支援してもらえます。製品のコミュニティサイトがあるため情報収集もしやすいです。料金は1ユーザーあたり150円~/月になります。
HENNGE Oneの参考レビュー、口コミ
クラウドセキュリティの必須サービス
Microsoft 365 等クラウドサービスに必須なセキュリティサービスです。不正アクセスを制限できるだけではなく、メールの誤送信対策や、メール添付ファイルの自動暗号化等の機能も備えています。
参考:https://www.itreview.jp/products/hde-one/reviews/144743
機密情報の高いファイルのやり取りに便利
お客様と機密情報の高い容量の大きいファイルをやり取りする場合に上長などのチェックが入り、信頼性が保たれた状態で安心して送信できるので重宝しています。
参考:https://www.itreview.jp/products/hde-one/reviews/132212
トラスト・ログインbyGMO
国内登録者数No.1のID管理サービスです。IT管理者がアプリケーションのパスワードを設定し、従業員に割り当てられる機能があります。個人任せのパスワード管理をなくせるので、パスワードの複雑性を統一できるでしょう。また従業員と各アプリを紐づけられるため「従業員が退職後に業務アプリにアクセスできないようにする」ケースにも容易に対応でき、セキュリティホールをなくせます。プロプランの料金は1IDにつき330円/月。無料で利用できるプランもあるため「まずはパスワード管理機能がどんなものか確かめてから導入したい」企業におすすめです。
トラスト・ログインbyGMOの参考レビュー、口コミ
難しいパスワードを暗記して入力する作業から解放されました
各種ウェブサイトの管理画面、Zoom、社内システム…
独自のアプリも簡単に登録できるため、あらゆるものを登録しています。
当社では社内システムにログインをする際に単純にパスワードとIDを入力するだけでなく、もう1手間かかるのですが、そちらも対応できるようにしていただきました。
WordPressのログイン画面が同じドメインで複数あるのですが、chromeのパスワード管理だと1つしか記憶できないため、とても重宝しています。
参考:https://www.itreview.jp/products/trust-loginbygmo/reviews/148069
セキュアで便利なツールです
優れている点・好きな機能
・ポータル機能
その理由
・シングルサインオンとしてセキュリティを確保しつつ、煩雑なログインパスワードを記憶させることができること
参考:https://www.itreview.jp/products/trust-loginbygmo/reviews/97725
LastPass
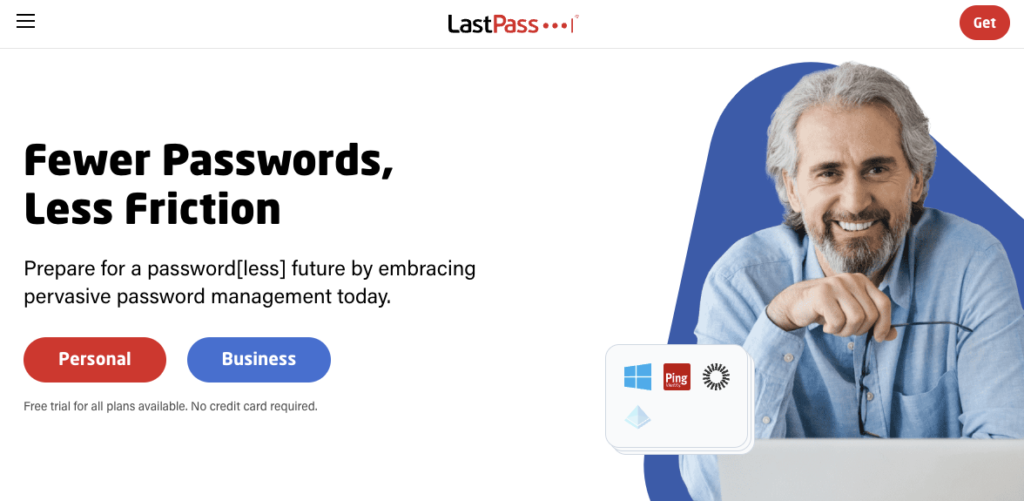
操作性がよく簡単にパスワードを管理できるツールです。サイトへのログイン時に自動的に登録するか聞かれ、「追加」を選択するだけで簡単にパスワードを登録できます。Chrome、FireFox、Safari、Opera、Edgeなど主要なブラウザに対応。モバイルはAndroid、iOS、iPadOS、watchOSをサポートしています。Webブラウザ版は日本語非対応なので注意が必要です。料金は1ユーザーあたり$3/月で、14日間の無料トライアル版もあります。
LastPassの参考レビュー、口コミ
超簡単なパスワード管理Tool
マスターIDの登録のみで、WEBサイト上で登録している各個人パスワードの管理が簡単にできる点はとても便利です。
参考:https://www.itreview.jp/products/lastpass/reviews/44214
chromeの拡張機能で管理でき、非常に便利
GoogleChromeの拡張機能として使っています。複数のパスワード管理が、ログインするだけで利用できるので重宝しています。
参考:https://www.itreview.jp/products/lastpass/reviews/53954
1Password

10万社以上の導入実績があるパスワード管理サービスです。マスタパスワードに加えてSecret Keyがあり、マスタパスワードが万が一漏えいしてもKeyを知らなければアクセスできない二段構えの仕様。またパスワード漏えいチェック機能もあり、社内で管理しているドメインを事前に登録することで、漏えいが発生したアドレスを検出することが可能です。対象のユーザーに早急にパスワード変更を促せるので、影響を最小限に抑えられるでしょう。料金はビジネスプランの場合1ユーザー7.99ドル/月。14日間の無料トライアルもあります。
1Passwordの参考レビュー、口コミ
安心・安全なパスワード管理に
優れている点・好きな機能
・デバイス間で同期が可能な点
・セキュリティアラート機能
その理由
・同期をすることで、スマホやタブレットなどの複数端末から情報を確認できるから。
・アラート機能があることで、アプリに保存したデータが侵害されたり、パスワードを再使用してしまったときに
すぐに確認・訂正することができるから。
参考:https://www.itreview.jp/products/1password/reviews/155589
アップデートされて使いやすくなった
・セキュリティに強いパスワードを簡単に生成できる
・パスワード管理が楽になる
・スマホでもPCでもシームレスに利用ができる
参考:https://www.itreview.jp/products/1password/reviews/139463
ITreviewではその他のID・パスワード管理ツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。
まとめ
テレワークの普及やサイバー攻撃の多様化により、企業におけるパスワード管理の重要性がますます高まっています。安全なパスワードの作成方法や攻撃手口の種類を知ったうえで、適切に管理していくようにしましょう。
パスワード管理をする際は複数のサービスで使い回さない、1つのサービスに1つのパスワードを設定する、などの対策が必要です。パスワード管理ツール・アプリを選ぶときは、機能の豊富さや対応OS、セキュリティレベル、バックアップ機能などに注目しましょう。また導入実績が多く、サポートが充実している製品だとより安心して利用できるでしょう。
投稿 【パスワード管理どうする?】安全な管理方法とおすすめのアプリを解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【定番】建築CAD5選|2D・3D・フリーソフトの特徴や機能 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>一般的な汎用CADと比べて、建築分野に実用性の高いツールが備わっているため、設計業務の効率化に向けて導入を検討してみましょう。本記事では、建築分野で活用されているCADを5つご紹介します。
建築CADとは?
建築CADとは、建築設計に特化したCADのことです。ビルや住宅などの建築時に必要な基本設計図・実施設計図・施工図・構造図・設備図などの図面を設計できる機能を備えています。ドア・窓・壁などを簡単に作図したり、テンプレートを使用したりできるなど、建築設計する上で便利な機能を搭載しているのが特長です。
従来の手書きではなく建築CADを利用することで、図面の作成や修正の時間を短縮できます。データで管理できるため、Webで図面を共有しやすいのもメリットです。
CADの種類
CADといっても、さまざまな種類があります。それぞれ可能なことや特長が異なるので、CADの種類と建築業界における使われ方を解説します。
2D CADと3D CAD
2D CADとは、立体を2次元(2D)で表現するCADのことです。線分・円弧を用いて、平面図・立面図などを描きます。建築業界では、建築物の間取りなどを作図するときに使用されています。一方、3D CADとは、立体を3次元(3D)で表現するCADのことです。直方体や球体を用いて、立体的な造形物を描きます。建築業界では、建築物の完成図などを作成するときに使用されています。
3D CADのほうが2D CADより実現できることが多いものの、どちらかが優れているわけではありません。建築物の仕上がりをイメージしたいときや、体積・表面積を算出したいときは3D CAD、建築物の断面図を切り出したいときには2D CADというように、用途によって使い分けられています。
汎用CADと専用CAD
汎用CADとは、どの分野の設計・製図にも通用する機能を備えたCADのことです。対して専用CADは、特定分野の設計・製図に特化した機能を備えたCADを指します。専用CADに当たるのは「機械設計CAD」「電気CAD」などで、建築CADも専用CADの1つです。
たとえば、専用CADの1つである「機械設計CAD」には部品表を自動で作成する機能、「電気CAD」には電気配線専用コマンドなどが備わっています。同様に「建築CAD」には、壁・階段を自動で挿入する機能などが備わっています。汎用CADにも基本的機能は備わっているものの、業界に特化した設計・製図を行いたいのであれば、専用CADを使用したほうが効率的に作業を進められるでしょう。
建築系3D CADの種類
建築系3D CADには、ハイエンドCAD・ミッドレンジCAD・ローエンドCADの3種類があります。3つの主な違いは、備わっている機能です。
ハイエンドCAD
- 高い機能を備えた3D CADで、複雑な設計を高速で処理できる。
- 部品数が多い航空業界・自動車業界などで使用されている。
- 高額かつ独学での習得は難しい。
ミッドレンジCAD
- ハイエンドCADほどではないが、多くの機能が備わっている。
- 機械業界・家電業界などの幅広い業界で使用されている。
- ハイエンドCADより低価格で、直感的に操作しやすい。
ローエンドCAD
- 基本的な機能は備わっているが、実務で使うには不十分である。
- 個人ユーザーやCAD初心者に使用されている。
- 無料ソフトもあり、ビギナーでも操作しやすい。
建築設計の実務に使用したいなら、ミドルレンジCADが向いているでしょう。ただし、3D CADに不慣れな方や、これから習得したい方は、ローエンドCADを導入して操作に慣れるのもおすすめです。
建築CADソフトの選び方
まずは、自身が使うパソコンのOSに対応している建築CADを選びましょう。多くの建築CADはWindowsに対応しているものの、Macに対応していないケースも少なくありません。また、自分のパソコンがソフト推奨のスペックをクリアしているかも確認しましょう。
特に3Dモデリングデータを扱う場合は、グラフィックボードが重要です。CADの使用を前提に最適化されていることはもちろん、高スペックなボードを搭載したパソコンが推奨されます。
次は、自身に必要な機能が備わっているか確認しましょう。建築CADは高機能なほど高額な傾向にあり、不要な機能があると費用が無駄になります。資格取得が目的で建築CADを導入したい方は、試験内容や指定ソフトを確認してください。
たとえば「建築CAD検定試験」は建築専用CADでは受験できず、汎用CAD「AutoCAD」「Jw_cad」「AutoCADLT」「Vectorworks」が指定されています。
「オートデスク認定ユーザー」は「AutoCAD」「Revit」「Fusion 360」のいずれかを使いこなせると証明する資格なので、いずれかのソフトを選ぶとよいでしょう。資格取得する場合には、実技試験にも考慮することが重要です。
「2次元CAD利用技術者試験1級」の実技試験では、DXFデータで保存した成果物の提出を求められます。DXFデータに対応しているのは、「Jw_cad」「AR_CAD」などです。
最後に、建築CADの中には海外製もあります。特に初心者の場合、日本語に対応しているソフトや日本語マニュアルがあるソフトを選ぶと安心です。加えて、営利目的で使用したい方は、商用可能な建築CADを選びましょう。
業界で多く利用されているものもチェック
どのソフトを導入しようかと迷っている方は、建築業界で多く利用されているCADを選ぶのも1つの方法です。建築業界で普及しているということは、実務で利用する可能性が高いということ。建築業界のみならず幅広い業界で広く普及しているのが、AutoCADです。人材不足の現代においてはマッチング率を高めるため、AutoCADの使用経験を採用時の応募資格とするケースも少なくありません。
また、AutoCADは有名なので、操作方法に関する書籍が多く学びやすいのもメリットです。就職先で使用する可能性も高いため、ソフト選びに迷ったらAutoCADを導入するのも1つの方法でしょう。
AutoCAD

AutoCAD(オートキャド)とは、オートデスク株式会社が提供するCADです。世界基準のCADとして幅広い分野で導入されており、高度な2D作図から3Dモデリング、ビジュアライゼーションまで充実した機能が備わっています。その中で業種別に最適なツールセットが選べるようになっており、建築設計やドキュメント作成に特化した「AutoCAD Architecture(オートキャドアーキテクチャ)」があります。
単一図面において既設図面や解体図面などを用いた改築図面が表示できる「リノベーション機能」をはじめ、8,000以上にも及ぶドアや窓などの要素を、建築オブジェクトとして利用することも可能です。建築製図に便利なライブラリやキーノートツールを活用することで、規格に基づいた寸法設計や注釈付けが容易となり、よりスピーディかつ効率的に設計図面を作成できます。
AutoCADの特長
・AutoCADの標準機能に加え、建築設計に特化した機能を搭載
・豊富なオブジェクトを使用した、設計図面やドキュメントを作成可能
・既設、解体、新設を単一図面で調整できる「リノベーション機能」
・2D断面図や立面図を平面図から作成できる
・「Roombook機能」で同じ部屋の内装を複数管理できる
AutoCADの対応OS
Windows
AutoCADの参考レビュー、口コミ
ド定番CADソフト
利用者が多いので、問題があっても答えてくれる人が多い。同業に転職する人もAutoCADを使える人が多いので、使えるようになっておいた方が良いソフトです。
コマンド操作が優秀で、コマンド操作のみで簡単な図形が描けるし、さらに突き詰めていけばある程度の自動化も可能。
参考:https://www.itreview.jp/products/autocad/reviews/66742
業界標準あっての安定さ
これまでフリーソフトCADで図面を見る事が多くありましたが、ズレや未対応もあったりで困る事があったためAutoCADを導入しました。年々アップデートしてるのもあり、操作性もよいです。特に3D機能が年々強化されているためこれまでは、アレコレしていたのが、不要になっており、活躍度が高くなっています。
参考:https://www.itreview.jp/products/autocad/reviews/67055
Vectorworks Architect

Vectorworks Architect(ベクターワークスアーキテクト)とは、エーアンドエー株式会社が提供する建築設計向けのCADです。基本製品である「Vectorworks Fundamentals(ベクターワークスファンダメンタルズ)」が2D CADと3D CADが備わった汎用CADであるのに対し、本製品は建築設計、内装、設備、BIMなどに活用できる専門機能が加わっています。
ドアや窓の作成をはじめ、カーテンウォールや屋根の軸組作成などの機能を豊富に搭載。3Dデータを活用したインテリア設計、BIMに対応した空間計画も可能です。作成したモデルはワークシートに集計して活用できるため、設計工数の削減や施工ミスを防ぎ、建築設計プロセスを効率化します。BIM活用に向けた建築設計機能を必要とする現場に適しています。
Vectorworks Architectの特長
・スペース機能によりBIMに活用可能
・展開図を一括生成できるビューボード機能
・データのタグ付けによる作業の効率化
・3Dモデルの2D図面化がカスタマイズ設定により可能
Vectorworks Architectの対応OS
Windows、Mac
Vectorworks Architectの参考レビュー、口コミ
初心者にも扱いやすいCAD
JWWなどと違って、インターフィスがわかりやすく初心者からでも使い方をマスターし易いCADソフトだと思います。今まで使用していたCADソフトと違って、色付けや写真の貼り付けがめちゃくちゃ簡単です。DXFへのインポート・エクスポートも簡単にできます。
参考:https://www.itreview.jp/products/vectorworks-architect/reviews/179915
SketchUP

SketchUP(スケッチアップ)とは、米国Trimble社が開発・提供する建築向け3D CADです。3Dモデル作成がブラウザ上でできる無料版がありますが、有料版では建築や住宅設計に特化したプロ向けの「SketchUP Pro(スケッチアッププロ)」が提供されています。
SketchUP Proの魅力は、基本の2D作図から3Dモデリングだけでなく、CGやVR技術を活用したモデル表示機能が備わっていることです。作成したモデルをHMDでVR再生できるため、住宅販売やプレゼンテーションの現場で役立てられます。
また、CADデータはクラウド上で保存されるため、大容量データをデスクトップに抱える必要がなく、プロジェクトの共同作業を効率化します。豊富な3Dツールを直感的な操作で扱えるため、建築向けCADの入門用として適しているでしょう。
SketchUPの特長
・直感的操作で3Dモデルを簡単に作れる
・CGやVR技術によるVRモデル表示が可能
・プロジェクトを独自仕様にカスタマイズ可能
・クラウド上で保存、共有が可能
・豊富な拡張機能
SketchUPの対応OS
Windows
SketchUPの参考レビュー、口コミ
CADになれていない人が多い企業におすすめ
建物の数量を確認して積算する仕事をしています。私の部署はCADに触れたこともない人が多いですが、シンプルな操作方法の為、使いやすいです。数量の確認も簡単にできます。
参考:https://www.itreview.jp/products/sketchup/reviews/136033
ARCHITREND ZERO

ARCHITREND ZERO(アーキトレンドゼロ)とは、福井コンピュータアーキテクト株式会社が提供する建築・土木分野の3D CADです。部屋の間取りや屋根といった2D図面データからすばやく3Dモデルを作成し、設計業務に必要な図面作成や書類、建築CGパースなどを一貫して作成できます。
特に注力しているのは、CGパースを活用した多彩なプレゼンテーションです。内観や外観だけでなく、ウォークスルーしながら日当たりなどをシミュレーションできる「ARCHITREND リアルウォーカー」や、CAD作成したモデルをVRで体験できる「ARCHITREND VR」などがあります。
完成形を見ることができない注文住宅やリノベーションなどの提案・プレゼンに役立てられるでしょう。その他、建築にかかわる法改正に対応した書類作成や、省エネ計算なども可能となり、あらゆる設計スタイルにおいて建築プロセスを効率化できます。
ARCHITREND ZEROの特長
・建築CGパースを活用した多彩なプレゼン機能
・実施設計から確認申請まで、あらゆる業務にすばやく対応
・S造やRC造に対応した構造設計が可能
・プランデータの集計&積算による徹底した利益確保
ARCHITREND ZEROの対応OS
Windows
ARCHITREND ZEROの参考レビュー、口コミ
直感的でわかりやすい
営業担当の方に利用してもらっています。ドラッグアンドドロップだけである程度の間取りが表現できるため、プレゼン作成にかかる時間が大きく短縮できます。
パース出力もできるため、商談の多い営業担当の方から好評です。
参考:https://www.itreview.jp/products/architrendmodelio/reviews/180583
ArchiCAD
ArchiCAD(アーキキャド)とは、ハンガリー企業のグラフィソフトが開発・提供している建築向け3D CADです。3Dモデリング機能のほか、部材や各要素の情報をモデルにインプットして設計を行う「BIM」に対応しています。設計の流れに沿って自然にBIMデータを格納できるほか、設計段階で必要な情報をその都度追加できるため、効率を落とさず設計が可能です。
BIMデータで各要素に属性を持たせることで、さまざまな角度から図面を切り取れるほか、設計構造が視覚的に認識しやすくなる、各図面の整合性が保てるなどのメリットが得られます。設計図面の作成ミスや手戻りを減らせるため、設計プロセスの効率化が期待できるでしょう。
また、作成したモデルには複数人が同時にアクセスできるほか、タブレットを利用するなど、各チームや取引先とのコミュケーションも円滑化します。BIMを活用したCADソフトで設計フローの改善を目指す企業に適しています。
ArchiCADの特長
・BIM対応による正確かつ整合性のある設計
・3Dモデルや図面からあらゆる情報を抽出、活用可能
・意匠設計と構造設計のワークフローを効率化
・レイヤーの概念で操作できるため習得しやすい
・モバイル端末でも3Dモデルデータを扱える
ArchiCADの対応OS
Windows、Mac
ArchiCADの参考レビュー、口コミ
非常に優秀なCADソフト
既存オブジェクトの利用が非常に便利。
柱や梁等、自由な寸法で気軽にモデリングすることができる。レンダリングの質感も悪くない。
参考:https://www.itreview.jp/products/archicad/reviews#review-8496
建築業界の課題クリアに向けたCAD導入
設計フローの効率化に欠かせないCAD。しかし、これまで設計業務に使用されていた「2D CAD」だけでは課題点も多く存在しています。
2D CADでは、施工段階にならないと設計上のミスに気付きにくく、迅速に修正や変更ができないなどの課題があります。手戻りによって工数が増えることで工事が長期化し、利益確保ができないなどのリスクも考えられるでしょう。
複雑化する設計フローを効率化するためには、建築分野のニーズに対応したCADが必要です。特に必要性が高いとされるのは、図面やドキュメント作成の時間を短縮する自動作成機能をはじめ、3D CADによる視覚的な構造把握、関係者とのリアルタイムな情報共有を可能にするネットワーク連携などです。
こうしたニーズに向けて、近年では上記の機能を備えた「3D CAD」が主流化しつつあります。同時に、3D CADのさらなる活用に向けて「BIM 」活用の概念も新たに登場しています。今やCADは、建築図面の作成だけでなく、施工に至るまでの建築分野全体に欠かせないツールといえるかもしれません。
建築CADの選定において、現状の課題やニーズを把握することはもちろん、設計スピードや品質の向上、コスト管理による生産性向上なども視野に入れて選ぶべきといえるでしょう。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適な建築CAD製品を選ぼう!
投稿 【定番】建築CAD5選|2D・3D・フリーソフトの特徴や機能 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MAツールのMarketo(マルケト)とは?できることからメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>マーケティング施策を実施するうえで強力な味方となり得るマルケトですが、では一体、その特徴やメリット・デメリットなどは、どのようなところにあるのでしょうか?
本記事では、マルケトの特徴から利用できる基本的な機能、料金プラン、口コミや評判からわかったメリット・デメリットなどについて、まとめて徹底解説していきます!
Adobe Marketo Engage(マルケト)とは?

マルケト(Adobe Marketo Engage)とは、世界6,000社を超える企業で導入されている、世界的なMA(マーケティングオートメーション)ツールのことです。
現在では「Adobe Marketo Engage」の名称で展開されていますが、もともとは米Marketo社が開発を行っており、2018年10月にはAdobe(アドビ)社が大型買収を行ったことでも話題になりました。
既存の顧客から見込み顧客、匿名のサイト訪問者まで、幅広いユーザーのインテントデータを収集することができるため、より効果的かつ戦略的なマーケティング施策に活用することができます。
MAツールとは?
MAツール(Marketing Automation)とは、営業などの現場において、リード顧客から成約までのマーケティング業務を自動化し、マーケティング活動そのものを効率化するツールのことを指します。
▶ 関連記事:【MAとは?】マーケティングオートメーションの機能・特徴・選び方を徹底解説!
Adobe Marketo Engage(マルケト)の特徴
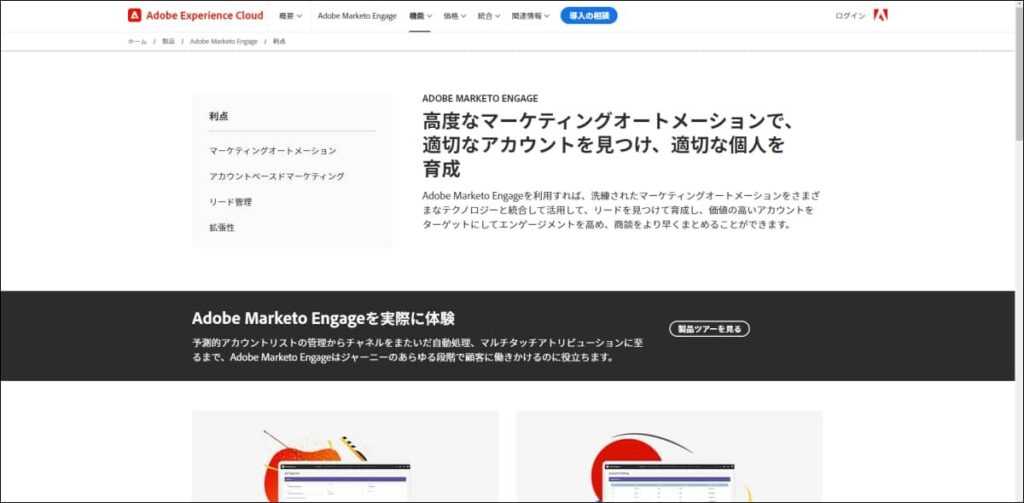
リード獲得を支援できる
マルケトは、マーケティングツールにおける、多様な機能を統合したプラットフォームです。ランディングページやフォームの作成、リードスコアリング、自動化されたキャンペーンなど、豊富な機能を活用することで、効果的なリード獲得活動を支援することができます。
見込み顧客を育成できる
マルケトは、リード獲得だけではなく、見込み顧客を育成するための機能も充実しています。顧客の行動や興味にもとづいたパーソナライズされたコンテンツの配信、ターゲティングされた電子メールキャンペーンなど、見込み顧客との良好な関係構築に役立ちます。
ワークフローを改善できる
マルケトは、顧客の獲得以外にも、ワークフローを改善するための機能も提供しています。ワークフローエディタを使用したマーケティングプロセスの自動化やA/Bテスト、リアルタイムのアナリティクスなど、ワークフローの効果を評価し、最適化することが可能です。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の機能
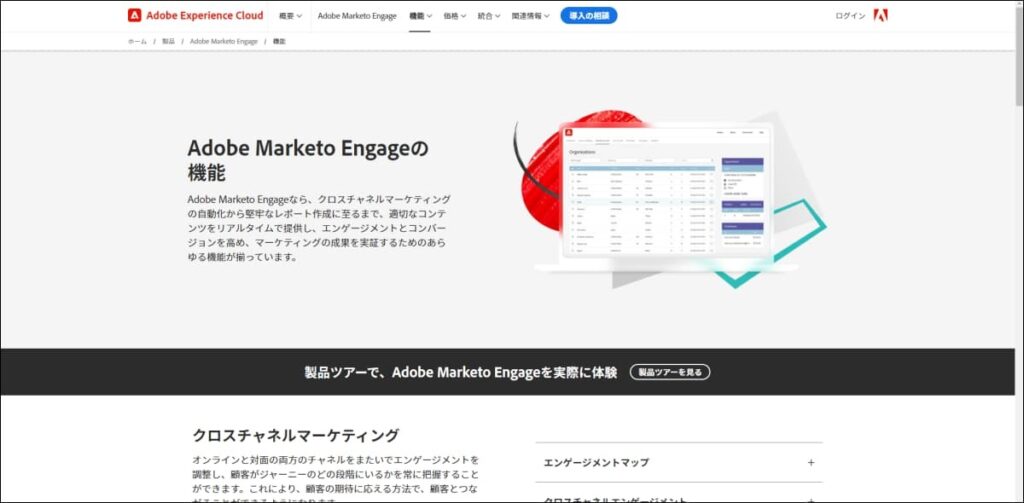
マルケトの大きな特徴の一つとして「10個の機能(アプリケーション)」の存在が挙げられます。活用することにより、効果的なリードの獲得と顧客のエンゲージメントを実現することができます。
マーケティングオートメーション
マーケティングオートメーション(MA)に役立つ機能です。リードの生成から顧客のナーチャリング、顧客関係管理(CRM)まで、マーケティング活動におけるプロセス全体を自動化することができます。
メールマーケティング
ユーザーごとにパーソナライズされたメールキャンペーンを作成する機能です。リアルタイムな追跡と詳細な分析を行うことによって、メールマーケティングの成果を最大化することができます。
モバイルマーケティング
モバイルデバイスへのターゲティングやパーソナライゼーションを実施する機能です。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末に向けて、リーチとエンゲージメントを最適化することができます。
ソーシャルマーケティング
ソーシャルメディアプラットフォームでのマーケティング活動を支援する機能です。ソーシャルリスニングやターゲティングを行うことによって、サービスやブランドの知名度を高めることができます。
デジタル広告
自社の獲得したいターゲットオーディエンスに対して効果的な広告を配信する機能です。デジタル広告の管理と最適化を実施することにより、企業のROI(投資利益率)の最大化に貢献することができます。
Webパーソナライゼーション
ウェブサイトの訪問者に対して個別にカスタマイズされたアプローチを提供する機能です。匿名の訪問者に対して適切なアプローチを行うことにより、コンバージョンの増加に貢献することができます。
アカウントベースドマーケティング
アカウントベースでエンゲージメント率が高いユーザーをリストアップする機能です。重要なアカウントに対してパーソナライズされたアプローチを実現し、ビジネスチャンスを追求することができます。
マーケティングアナリティクス
実施したマーケティングキャンペーンの効果を迅速に評価する機能です。リアルタイムなデータ分析と可視化によって、どのキャンペーンが効果的なのか、戦略的な意思決定を支援することができます。
プレディクティブコンテンツ
ユーザーの行動と関心にもとづいて次に表示するコンテンツを予測する機能です。それぞれのユーザーごとにレコメンドするコンテンツを選択し、パーソナライズされた体験を提供することができます。
プレディクティブオーディエンス
ユーザーの行動履歴と属性にもとづいて将来の消費行動を予測する機能です。AIによる顧客セグメンテーションによって、ターゲティングとマーケティングメッセージの最適化を行うことができます。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の料金
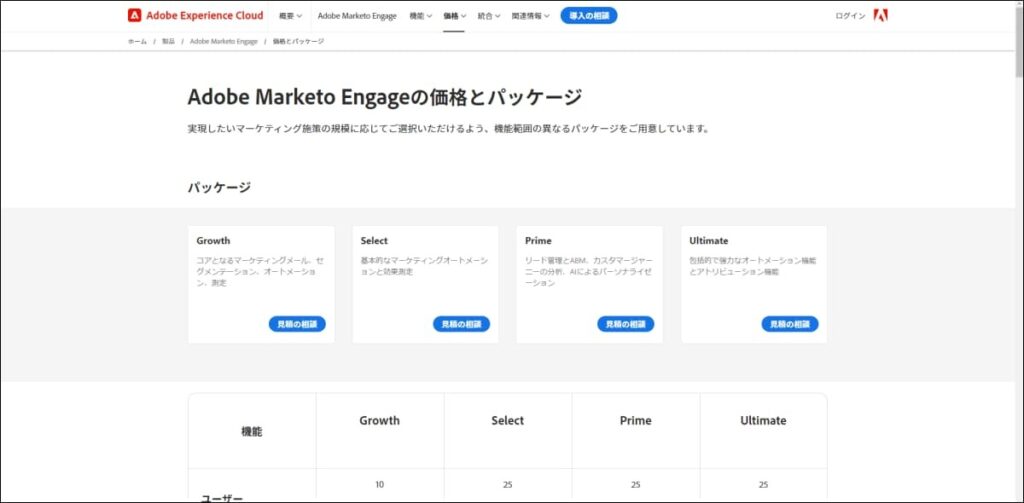
マルケトには、主に下記の4つの料金プランが存在します。各プランの詳細な価格は公式HPには明記されていないため、詳細な料金情報についてはAdobeの担当者への見積もり相談が必須になります。
- Growthプラン
- Selectプラン
- Primeプラン
- Ultimateプラン
また、それぞれのプランごとで、対象となる法人ユーザーや利用できる機能などは異なるため、導入するときには、自社の従業員規模やニーズにマッチしたプランを選択するようにしましょう。
Growthプラン
Growthプランは「小規模なビジネス向けのエントリープラン」です。主な機能には、基本的なマーケティングオートメーション機能やリード管理機能、アナリティクスでの分析機能などが含まれています。
Selectプラン
Selectプランは「中規模の企業向けのミドルプラン」です。マーケティングオートメーション機能やリード管理機能はもちろん、ソーシャルメディア管理などの高度なマーケティング機能が含まれています。
Primeプラン
Primeプランは「大規模な企業向けのハイエンドプラン」です。ABM(アカウントベースドマーケティング)や高度なアナリティクス、カスタマイズ機能など、さらに高度な機能とサポートが提供されます。
Ultimateプラン
Ultimateプランは「複雑なマーケティングニーズを持つ企業向けのカスタムプラン」です。このプランでは、包括的なマーケティング機能や専任のアカウントマネージャーサポートなどが提供されます。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の導入事例
導入企業①:コクヨ株式会社

コクヨ株式会社は、マルケトを導入し、マーケティングプロセスの効率化と顧客エンゲージメントの向上に成功しました。
マルケトを活用することで、コクヨは顧客の行動や興味にもとづいた、パーソナライズされたコンテンツを提供し、リード獲得から顧客育成までのプロセスを自動化することができました。
導入企業②:LINE Pay株式会社

LINE Pay株式会社は、マルケトを導入し、ユーザーエンゲージメントの向上とマーケティング効果の最大化を実現しました。
マルケトを活用することで、LINE Payはユーザーの行動データを分析し、ターゲットに合わせたパーソナライズされたマーケティングキャンペーンを展開することができました。
導入企業③:株式会社日立製作所
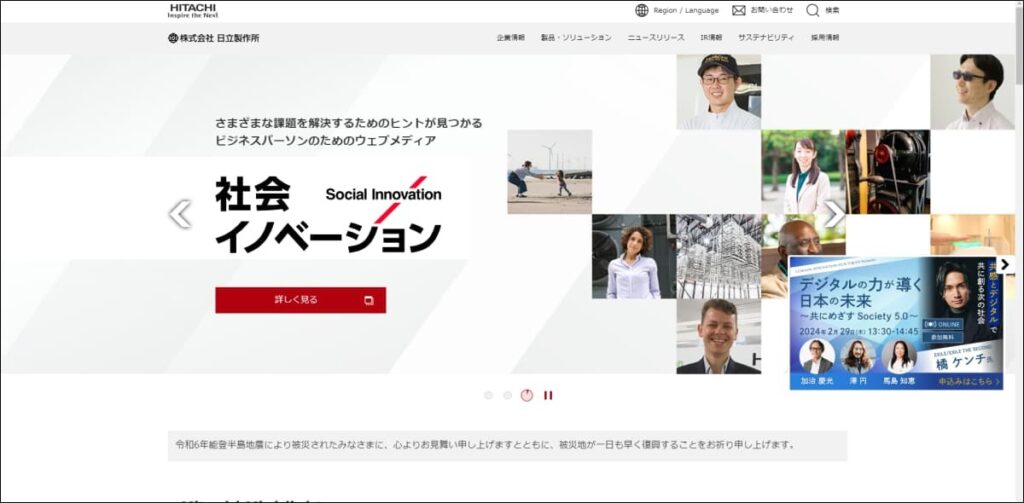
株式会社日立製作所は、マルケトを導入し、グローバルなマーケティングプロセスの統合と効率化を実現しました。
マルケトを活用することで、日立は世界中の顧客とのコミュニケーションを統一し、一貫したブランドメッセージの発信と有益なコンテンツを提供することができました。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の口コミ・評判
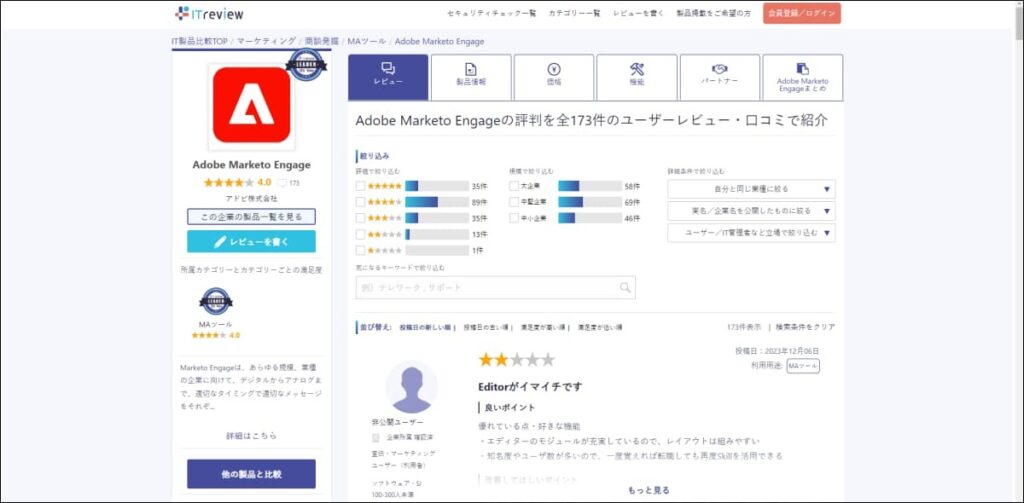
Marketo(マルケト)の良い口コミ・評判

あらゆるマーケティング業務をこれ1つでできる
今まではメール配信用、リード管理用、LP作成など業務によってツールを使い分けており連携性もなくログインも面倒で業務が煩雑でしたが、Marketoはそれらをつでできるので業務負荷をかなり削減できました。
企業名:コムテック株式会社
従業員規模:1000人以上
業種:ソフトウェア・SI

いまのマーケティング活動には不可欠
メール、Web、広告など、複数のチャネルに分かれつつ、利用する画像やPDFなどのアセットは共通で管理できるなど、効率的にマーケティング活動が可能となっている。マーケターが”作業”する時間を少なくできるので、本来考えるべきことに集中できる。
企業名:ソフトバンク株式会社
従業員規模:1000人以上
業種:情報通信・インターネット

マーケティング分析に役立つ
なかなか人力では難しい実用的なマーケティング分析を自動的にしてくれるので、ビジネスマーケティングの世界において実用的です。顧客がどこから流入し、何に興味を持っているのかジャーニーを把握できるので、質の高い情報が得られます。
企業名:Horaanna
従業員規模:20人未満
業種:日用雑貨
Marketo(マルケト)の悪い口コミ・評判

便利な点もなるが、とてつもなく不便な点もある
モバイル対応したメールテンプレートやランディングページテンプレートはあるが、細かな修正が全くできない。きちんとしたものを作ろうとすると、HTMLやCSSでゴリゴリに編集しないといけないので、全く使い物にならない。この点は、本当にAdobeがベンダーなのかと疑うレベルで質が低く、自由度の高いHubspotと比べるとその差は天と地ほどある。
企業名:非公開(企業確認済)
従業員規模:20-50人未満
業種:ソフトウェア・SI

必要な機能がほぼ揃っているが使い勝手とコストは悩ましい
コストの上がり方は使い続ける中でいずれぶつかる壁。機能網羅性の弊害ともいえるが、ユーザビリティも直感的とは言えない。
企業名:コムテック株式会社
従業員規模:1000人以上
業種:ソフトウェア・SI

Editorがイマイチです
とにかく、日本向けにフォントなど改行位置なども仕様が整っていないため、汚く見えてしまい、フォントは明朝ゴシック一択なので、イケてない見た目になってしまう。ここを何とかまずしてほしい。
企業名:非公開(企業確認済)
従業員規模:100-300人未満
業種:ソフトウェア・SI
Adobe Marketo Engage(マルケト)のメリット

利用できる機能が豊富
マルケトのメリットの1つ目としては「利用できる機能が豊富」というものが挙げられます。
マルケトは、マーケティングオートメーションからメールマーケティング、ソーシャルメディア管理、デジタル広告まで、多岐に渡る豊富な機能を利用することができます。
本来であれば複数のSaaSを導入して並列に使用なければならない部分まで、さまざまな機能が網羅されているため、マルケト単体で包括的なマーケティング戦略を展開することができます。
外部ツールとの連携が簡単
マルケトのメリットの2つ目としては「外部ツールとの連携が容易」というものが挙げられます。
マルケトは、同じAdobe製品との機能連携はもちろんのこと、SalesforceやZoom、Slackなど、他社の外部ツールやプラットフォームとのシームレスな連携をサポートしています。
ビジネスには必須のCRMシステムやデータ分析ツール、顧客データプラットフォームなど、さまざまなツールとの統合が容易になることで、マーケティング活動の効率化を実現することができます。
ユーザーコミュニティが活発
マルケトのメリットの3つ目としては「ユーザーコミュニティが活発」というものが挙げられます。
マルケトは、ユーザーコミュニティが非常に活発なことでも有名であり、ユーザー同士の知識共有や情報交換など、業界や業種を問わずグローバルな交流が盛んに行われています。
公式コミュニティフォーラムやイベント、ウェビナーなどを通じて、最新のトレンドやベストプラクティスを学ぶことができるため、マーケティング戦略の改善や効率化に役立てることができます。
Adobe Marketo Engage(マルケト)のデメリット

競合の製品と比較してランニングコストが高い
マルケトのデメリットの1つ目としては「競合の製品と比較してランニングコストが高い」というものが挙げられます。
マルケトは、豊富な機能が特徴となっている反面、導入費用やライセンス料、カスタマイズやサポートにかかる費用は、競合の類似製品と比較して、高額になりやすい傾向にあります。
とくに、中小企業や予算が限られている企業にとっては、導入コストが障害となることも多いため、全体的な価値やROI(投資利益率)を事前に評価し、費用と期待される効果を試算することが重要です。
扱える機能が多く初心者には操作が難しく感じる
マルケトのデメリットの2つ目としては「扱える機能が多く初心者には操作が難しく感じる」というものが挙げられます。
マルケトは、マーケティングオートメーションから分析、コンテンツ管理まで幅広い機能を提供している反面、なんでもできることが、かえってストレスとなってしまう可能性があります。
これらの多様な機能を理解し、適切に操作することは初心者にとっては難しい場合があるため、操作方法や機能の使い方については、公式のトレーニングやサポートを受ける必要があるでしょう。
英語表記が多く日本語の対応が不十分な場面がある
マルケトのデメリットの3つ目としては「英語表記が多く日本語の対応が不十分な場面がある」というものが挙げられます。
マルケトは、グローバルなマーケティングプラットフォームであり、英語表記が主流となっているため、日本語のドキュメンテーションやサポート体制が不十分な場合があります。
わからない機能や単語に遭遇したときには、公式のサポートに問い合わせるか、外部の翻訳サービスなどを利用して自力で解決する必要があるため、使い勝手が悪いと感じるユーザーも多いようです。
MAツールを選定するときのポイント

①:利用の目的はBtoB向けかBtoC向けか
MAツールを選定するときのポイントの1つ目としては「利用の目的はBtoB向けかBtoC向けか」というものが挙げられます。
BtoB向けのツールは、企業のビジネスプロセスや顧客関係管理をサポートする機能が重視されますが、BtoC向けのツールは、大量の消費者データを処理し、個々の顧客との関係を構築する機能が重要です。
②:現場の従業員が使いやすい操作性であるか
MAツールを選定するときのポイントの2つ目としては「現場の従業員が使いやすい操作性であるか」というものが挙げられます。
MAツールは、現場のマーケティング担当者や営業担当者が使いやすいことが重要です。直感的なインターフェースやカスタマイズ可能なダッシュボードなど、使い勝手の良さは生産性の向上に直結します。
③:自社の導入目的と機能がマッチしているか
MAツールを選定するときのポイントの3つ目としては「自社の導入目的と機能がマッチしているか」というものが挙げられます。
例えば、リードの獲得や顧客エンゲージメントの向上を目指す場合には、それらをサポートする機能が必要です。自社のニーズと選定候補の機能がマッチしているかは、あらかじめ確認しておきましょう。
④:自社と同規模の会社への導入実績はあるか
MAツールを選定するときのポイントの4つ目としては「自社と同規模の会社への導入実績はあるか」というものが挙げられます。
自社と同規模の会社への導入実績がない場合、導入前後での運用や効果予測が難しくなってしまうため、同程度の会社への実績がないサービスについては、なるべく導入を控えておくのが無難でしょう。
⑤:セキュリティやサポートは充実しているか
MAツールを選定するときのポイントの5つ目としては「セキュリティやサポートは充実しているか」というものが挙げられます。
データのトラブルや障害発生時における迅速な対応は、安定した運用を実現するうえでは不可欠です。MAツールのセキュリティやサポート体制が充実しているかどうかは、事前に確認しておきましょう。
Adobe Marketo Engage(マルケト)の導入なら運用・導入支援パートナーがおすすめ!

本記事では、マルケトの特徴から利用できる基本的な機能、料金プラン、口コミや評判からわかったメリット・デメリットなどについて、まとめて徹底解説していきました。
もはやデファクトスタンダードともいえるMAツールのマルケトですが、利用できる機能が多い一方で、初心者には扱いが難しいというデメリットも見えてきました。
自社だけでの構築や運用が難しいという場合には、ぜひこの機会に「運用・導入支援パートナー(コンサル)」の導入を検討してみてはいかがでしょうか?
投稿 MAツールのMarketo(マルケト)とは?できることからメリット・デメリットまでわかりやすく解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【多要素認証とは?】パスワードのみの危険性とSaaSに必要な理由を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>MFAとも表記される多要素認証ですが、銀行のATMでも使用されている本人確認の方法でもあり、身近な存在として浸透しています。
本記事では、いまさら聞けない多要素認証の基礎基本や仕組みについて、認証方式の特徴から二段階認証との違いまで徹底解説していきます。
また、SaaSの導入における多要素認証の必要性についても解説しているため、これから導入する方などはぜひ参考として役立ててください。
“世界一わかりやすい情報セキュリティ”連載記事はコチラから!
▶ 第1回:【SaaS利用者必見】話題の”セキュリティ評価”の重要性と対策方法を紹介!
多要素認証とは?

多要素認証(MFA:Multi-Factor Authentication)とは、セキュリティにおける本人確認方法の一つです。
本人だけが保有する要素(知識情報・所持情報・生体情報)のうち、2つ以上の情報を組み合わせて認証する認証方式のことを指します。
- 知識情報:本人だけが知っている情報
- 所持情報:本人だけが持っているモノ
- 生体情報:本人だけの身体的な特徴
従来までの本人確認の方法としては、主にユーザーIDやパスワードなどの知識情報を使用した認証が一般的な方法とされてきました。
しかし、パスワードの流出や紛失といった管理の難しさから、それら以外を使った多要素認証(二要素認証)の重要性が高まっています。
知識情報(本人だけが知っている情報)
知識情報とは、本人だけが知っている情報を利用して本人確認を行うための要素を指します。パスワードやPINコードなどが知識情報に該当します。
複雑な設定や物理的な専用端末が不要であり、多くのシーンで取り入れやすい方式であるため、クラウドサービスではスタンダードな認証情報となっています。
多くのユーザーにとって扱いやすい認証要素である反面、そのぶん流出や悪用などのリスクも高く、パスワードの管理には注意しておく必要があります。
所持情報(本人だけが持っているモノ)
所持情報とは、本人だけが持っているモノを利用して本人確認を行うための要素を指します。スマートフォンやICカードなどが所持情報に該当します。
仮想MFAデバイスなどから本人確認を行う方式であり、モノを持ってさえいれば本人確認ができるため、こちらもスタンダードな認証情報となっています。
こちらも便利な反面、モノを紛失してしまうと、たとえ本人であっても認証が困難になってしまうため、盗難や紛失のリスクには気をつける必要があります。
生体情報(本人だけの身体的な特徴)
生体情報とは、本人だけの身体的な特徴を利用して本人確認を行うための要素を指します。顔認識や指紋、声紋や虹彩などが生体情報に該当します。
スマートフォンのロック解除やオフィスエントランスなどにおいて、顔認証や指紋認証が利用されているケースも多いため、身近に感じる人も多いでしょう。
生体情報は複製が難しく、知識情報のように忘れることもなければ、所持情報のように紛失のリスクもないため、昨今需要が高まっている認証要素の一つです。
二要素認証と二段階認証の違い
| 二要素認証 | 二段階認証 |
|---|---|
| 本人確認に使う要素のうち 2つ以上の要素で認証する |
本人確認に使う要素のうち 1つの要素で2回認証する |
| パスワード認証(知識情報) × 指紋認証(生体情報) |
パスワード認証(知識情報) × 暗証番号認証(知識情報) |
| 安全性が高い 認証の”種類”を増やすことでセキュリティを強くする |
安全性が低い 認証の”回数”を増やすことでセキュリティを強くする |
二段階認証とは、認証の回数を増やすことでセキュリティを強くする対策方法です。
二段階認証は、いったん知識情報が流出してしまった場合、認証の回数を増やしたところで簡単に不正アクセスが可能になってしまうため、安全性が低い認証方式であるといえます。
一方の二要素認証とは、認証の種類を増やすことでセキュリティを強くする対策方法です。
二要素認証は、たとえ片方の認証情報が流出してしまったとしても、もう片方の認証情報が揃わなければアクセスすることはできないため、二段階認証よりも安全性が高い認証方式であるといえます。
多要素認証が重要視される背景

パスワードの限界
多要素認証が重要視される理由の1つ目としては「パスワードの限界」というものが挙げられます。
例えば、皆さんも一度は自分の名前や生年月日などを組み合わせてパスワードを設定した経験があるかもしれませんが、そのような方法で設定している利用者も多く、とくにSNSなどから個人の情報を収集しやすくなった現代においては、セキュリティリスクの高い手法であるといえます。
また、ウイルスバスターなどのセキュリティソフトを提供しているトレンドマイクロ社の実施した調査報告によると、およそ8割以上の利用者が複数のサービス間で同じパスワードを使いまわしているということで、パスワードの設定によるセキュリティ強度の担保には大きな課題があるといえます。
▶ 出典:『パスワードの利用実態調査 2023』
https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/press-release/2023/pr-20230831-01.html
サイバー攻撃の増加
多要素認証が重要視される理由の2つ目としては「サイバー攻撃の増加」というものが挙げられます。
日本におけるサイバー攻撃の件数は、年々増加している傾向にあり、日本国家より正式に許可を得て統計をとっているNICT(情報通信研究機構)の調査報告によると、日本におけるサイバー攻撃の件数は10年間で約50倍にも増加しているということで、セキュリティ対策の重要性が高まっています。
このように、日々増加しているサイバー攻撃に対処していくためにも、多要素認証の導入はもちろんのこと、ソフトウェアやOSの定期的な更新を実施したり、USBメモリの利用や持ち出しに制限を設けたりなど、企業や会社全体としても継続的なセキュリティ対策を講じていく必要があるでしょう。
| 年 | パケット 数 |
IPアドレス 数 |
IPあたりの パケット数 |
|---|---|---|---|
| 2013 | 約128.8億 | 209,174 | 63,682 |
| 2014 | 約241.0億 | 212,878 | 115,335 |
| 2015 | 約631.6億 | 270,973 | 245,540 |
| 2016 | 約1,440億 | 274,872 | 527,888 |
| 2017 | 約1,559億 | 253,086 | 578,750 |
| 2018 | 約2,169億 | 273,292 | 806,877 |
| 2019 | 約3,756億 | 309,769 | 1,231,331 |
| 2020 | 約5,705億 | 307,985 | 1,849,817 |
| 2021 | 約5,180億 | 289,946 | 1,747,685 |
| 2022 | 約5,226億 | 288,042 | 1,833,012 |
▶ 出典:『NICTER観測レポート 2022』
https://www.nict.go.jp/press/2023/02/14-1.html
多要素認証をクラウドサービスで使うべき理由

企業では顧客の個人情報を扱っている
多要素認証(二要素認証)を使うべき理由の1つ目は「企業では顧客の個人情報を扱っている」というものが挙げられます。
SaaSが普及していくなか、zoomやslackといったコミュニケーションツールの内容が漏れてしまうと、大切な顧客情報や従業員の個人情報などが外部に流出してしまいます。
また、Google WorkspaceやMicrosoft 365、githubのようなソースコードを管理するツールなどの情報が外部に流出してしまうと、企業や事業そのものに甚大な影響を及ぼしてしまいます。
ログインに必要な情報は予測しやすい
多要素認証(二要素認証)を使うべき理由の2つ目は「ログインに必要な情報は予測しやすい」というものが挙げられます。
通常のパスワード認証では、ユーザーIDとパスワードを一致させることで本人確認を実施するものであり、そのユーザーIDの多くは社用のメールアドレスが使用されています。
しかし、社用のメールアドレスは名刺やSNSに記載されていることも多く、わからない場合でも「名前+ドメイン」といった規則性があるため、簡単に入手することができてしまいます。
多要素認証が利用できるSaaSを導入しよう!

本記事では、いまさら聞けない多要素認証の基礎基本や仕組みについて、認証方式の特徴から二段階認証との違いまで徹底解説していきました。
従来までのパスワードによる本人確認方法は、解読のしやすさや漏えいのしやすさといった観点から、大きな脆弱性を抱えていることがわかりました。
そのため、SaaSやクラウドサービスを導入する場合には、多要素認証が実装されたサービスを導入することで、大切なデータを保護することが重要です。
“世界一わかりやすい情報セキュリティ”連載記事はコチラから!
▶ 第1回:【SaaS利用者必見】話題の”セキュリティ評価”の重要性と対策方法を紹介!
投稿 【多要素認証とは?】パスワードのみの危険性とSaaSに必要な理由を解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【SaaS利用者必見】話題の”セキュリティ評価”の重要性と対策方法を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>「SaaSのセキュリティ対策を推進していきたい」
システム構築が不要かつ低コストで早期導入することができるSaaSやクラウドサービスの数々ですが、近ごろでは、SaaSサービスにおけるセキュリティの問題が指摘されるようにもなってきました。
SaaSのセキュリティ評価を軽視して導入を決定してしまった場合、最悪「顧客情報の漏えい」や「外部からの不正アクセス」など、致命的なインシデントを引き起こしてしまう原因となってしまいます。
この連載では、SaaSの導入時におけるセキュリティ評価の重要性と具体的な評価の方法について、全10回の記事連載に渡って初心者の方でもわかりやすいように徹底解説していきます。
“世界一わかりやすい情報セキュリティ“連載記事はコチラから!
▶ 第2回:【多要素認証とは?】パスワードのみの危険性とSaaSに必要な理由を解説!
SaaS選定におけるセキュリティ評価の重要性

SaaSやクラウドサービスを選定するときには、対象サービスのセキュリティが十分か否か、担当者による事前の評価が必要不可欠です。
なぜなら、導入前のセキュリティ評価を怠ってしまうと、アカウントの乗っ取りという問題や情報流出という問題が発生してしまうからです。
例えば、先日の報道でもあったように、岡山大学病院では、フィッシング詐欺による情報流出というトラブルがあったことで、管理体制への批判を呼んでしまいました。
また、トヨタコネクティッド株式会社では、クラウドサービスの誤設定というトラブルが発生したということで、SaaSをめぐるトラブルは決して珍しいものとはいえません。
このようなことから、SaaSやクラウドサービスの導入では、コストや機能による比較はもちろんのこと、セキュリティ項目による評価や比較についても事前に実施しておくべきです。
▶ 出典元:https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/news/detail284.html
▶ 出典元:https://company.toyotaconnected.co.jp/news/press/2023/0512/
約4割の企業がセキュリティ評価を実施していない
以下のデータは、アイティクラウド独自のアンケート調査による『企業におけるSaaSセキュリティ評価の実態』について、それぞれの回答結果をグラフとしてまとめたものです。
自社固有のチェックシートで事前評価を実施している
最も少なかった回答が「自社固有のチェックシートで事前評価を実施している」というもので、全体の約28%という結果でした。
自社でセキュリティシートを持っている企業の場合、自社で重視すべきセキュリティ項目に沿ったチェック内容となっているため、クラウドサービスのリスクの把握だけではなく、自社の基準に沿ったセキュリティ評価を実現できているといえます。
クラウド関係のガイドラインで事前評価を実施している
次に少なかった回答が「クラウド関係のガイドラインで事前評価を実施している」というもので、全体の約29%という結果でした。
各種ガイドラインに沿った評価は実施できているものの、クラウドサービスは導入の目的により、利用する範囲やサービスの特性が異なることなども多いため、自社で重視するべき評価基準を設けておくことは非常に重要な対策であるといえます。
そもそもセキュリティにおける事前評価を実施していない
最も多かった回答は「そもそもセキュリティにおける事前評価を実施していない」というもので、全体の約37%という結果でした。
セキュリティ評価の重要性を認識していない、もしくは大事なプロセスだと認識してはいるものの、セキュリティの専門家がいないことや、サービスの導入数が少ないことなど、さまざまな事情から事前評価を実施できていないという意見が多く見られました。
SaaSにおけるセキュリティ評価の対策方法4選
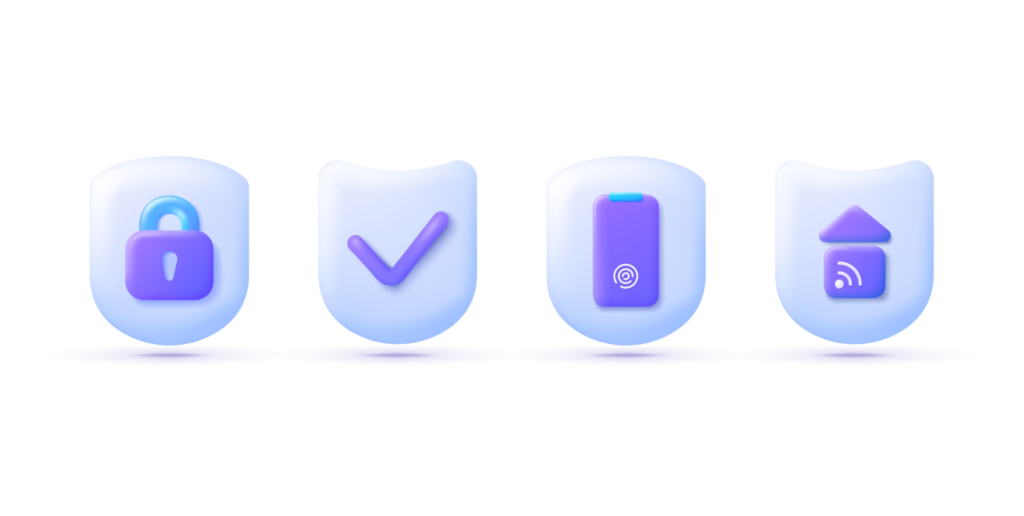
①:Pマークをはじめとする外部認証の有無を確認する
SaaSにおけるセキュリティ評価の対策方法の1つ目としては「Pマークをはじめとする外部認証の有無を確認する」という方法が挙げられます。
Pマークをはじめとする外部認証の有無は、SaaSベンダーが一定のセキュリティ基準を満たしているかを把握することができるため、信頼性の高いサービス選定に役立ちます。
また、これらの認証を持つサービスは、定期的な監査を受けているため、セキュリティ対策が常に更新されているという意味でも、Pマークなどの外部認証の有無は事前に確認するのがおすすめです。
②:各種ガイドラインを参考にしたチェックシートを作成する
SaaSにおけるセキュリティ評価の対策方法の2つ目としては「各種ガイドラインを参考にしたチェックシートを作成する」という方法が挙げられます。
総務省や経済産業省、IPA(情報処理推進機構)やNIST(アメリカ国立標準技術研究所)などが提供するガイドラインを参考にセキュリティチェックシートを作成する方法が有効です。
自社に必要なセキュリティ機能を理解することで、ニーズに合わせたセキュリティ項目のカスタマイズが可能になるため、より効果的なセキュリティ管理を実現することができるようになります。
▶ 参考:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01cyber01_02000001_00149.html
③:自社の基準に沿ったセキュリティチェックシートを作成する
SaaSにおけるセキュリティ評価の対策方法の3つ目としては「自社の基準に沿ったセキュリティチェックシートを作成する」という方法が挙げられます。
このプロセスでは、企業のビジネスモデルや法規制の遵守、過去に自社や同業他社で発生したインシデントの事例をもとに、より具体的かつ特定の要件を考慮に入れる必要があります。
自社の基準に沿ったセキュリティチェックシートは、具体的なリスク評価と効果的なリスク対策の計画に大きな効果を発揮するため、業界や業種を問わず事前に作成しておくことのがおすすめです。
④:必要機能の把握に役立つセキュリティ評価サービスを導入する
SaaSにおけるセキュリティ評価の対策方法の4つ目としては「必要機能の把握に役立つセキュリティ評価サービスを導入する」という方法が挙げられます。
例えば、ITreviewの提供する「SaaSセキュアチェック」の場合、各SaaSベンダーが実施しているセキュリティ対策が掲載されており、簡単にセキュリティ評価を実施することが可能です。
また、ITreview固有のセキュリティ評価結果を確認することができるため、セキュリティの専門家や担当者が不在の企業でも安全なサービス選定を実現できるようになります。
12月1日より『SaaSセキュアチェックサービス』の提供が開始
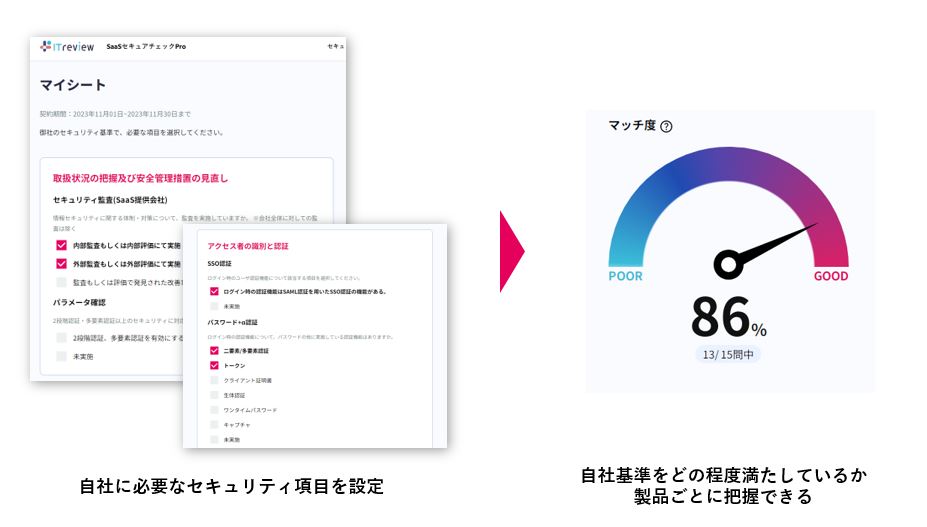
ITreviewでは、2019年10月にBtoBに特化した口コミプラットフォームとしてサービスのローンチを行い、以降『IT選びに、革新と確信を』をモットーに、企業がテクノロジーを活用するうえで“信頼できる声”や“確かな情報”の集まる場を創出し続けてきました。
そして、2023年12月1日『確かな情報』の一つとして『セキュリティ評価情報』を取り上げ、新サービス『ITreview SaaSセキュアチェック』をローンチする運びとなりました。
本サービスの導入によって、SaaSのリスクを事前に把握するだけではなく、自社が評価すべきセキュリティ対策に対して、最適なクラウドサービスかどうかを検討することができるようになります。
自社の運用や体制、クラウドサービスを導入する目的などに合わせて適切なリスク評価を設定することができるため、自社の基準に沿ったベストなクラウドサービス選定を実現することができます。
また、約8,000のクラウドサービスを掲載するITreviewの強みを生かした「プラットフォーム型セキュリティ情報」の提供により、クラウド製品のセキュリティ情報を調べる・探す手間を軽減し、比較検討時のスピードUPを支援します。
まとめ

本記事では、SaaSの導入におけるセキュリティ評価の重要性を解説することに加えて、適切なセキュリティ評価の方法や事前にできる対策方法などについて、わかりやすく解説していきました。
低コストかつスピード導入が可能なことから導入が加速しているSaaSですが、手軽さの反面、アカウントの乗っ取りや情報流出などのリスクがあることから、セキュリティ評価は不可欠といえます。
大半の業務がSaaSに置き換わりつつあるなか、コストや機能と同様に、セキュリティ評価を確実に実施することで、初めて安全かつ適切な運用を実現することが可能です。
アイティクラウドでは、これからセキュリティ評価対策を推進する企業向けサービスとして「ITreview SaaSセキュアチェックPro」を提供しています。SaaSのセキュリティ対策に悩んでいる企業は、ぜひご検討ください。
“世界一わかりやすい情報セキュリティ“連載記事はコチラから!
▶ 第2回:【多要素認証とは?】パスワードのみの危険性とSaaSに必要な理由を解説!
投稿 【SaaS利用者必見】話題の”セキュリティ評価”の重要性と対策方法を紹介! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 RDB(RDBMS)とは? 導入メリットやデータベース選定のポイントをチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>RDBとは?
RDBとは、「Relational Database(リレーショナル・データベース)」の略です。日本語では「関係データベース」と訳されます。複数の表で管理されたデータ同士を関連づけることで、複雑な処理を実現するデータベースのことです。
RDBはデータベースそのもののことであり、管理・構築のためには、「RDBMS(Relational Database Management System:データベース管理システム)」というシステムが求められます。
NoSQLデータベースとRDBの違い
RDBの比較対象として、NoSQLというデータベースが挙げられます。
NoSQLとは、「Not Only SQL」の略であり、データベース用の言語であるSQLを使わない新しい方式です。広義では、RDB以外のデータベースはすべてNo SQLに該当します。
NoSQLデータベースは、RDBよりもデータの格納・取得が最適化されている点が特徴です。RDBに対して、処理速度、拡張性に優れますが、検索性の弱さが欠点として挙げられます。
RDBMS(データベース管理システム)の基本機能
RDBを運用するためには、RDBMS(データベース管理システム)が必要です。データベース管理システムは、データに関する次のような処理を行います。
定義
データベース管理システムにはデータベースの「スキーマ」を定義する機能が搭載されています。スキーマとは、データベースの構造のことであり、設計図のような存在です。データベース管理システムを利用すると、DDL(Data Definition Language:データ定義言語)を用いて、スキーマを定義できます。
操作
データの登録、読み出し、更新、削除、といったデータに対する操作は、データベース管理システムの代表的な機能です。DML(Data Manipulation Language:データ操作言語)というSQLの一種を使って、この処理を行います。
制御
ユーザーによる操作の裏で、データの安全性や信頼性を維持するのもデータ管理システムの役割です。次のような機能が制御の機能として分類されています。
・排他制御:データを同時編集する際に矛盾が生じないように調整する
・機密保護:不正アクセスからデータを守る
・障害回復:データベースの障害が起こった際に復旧を行う
RDB導入のメリットとデメリット
データベースとしてRDBを選択すると、次のようなメリット・デメリットがあります。
RDB導入のメリット
1.データの一貫性
RDBはデータの一貫性が評価されています。ここでいう一貫性とは「処理が正しく実行されればその結果が表示され、処理が正しく実行されなければ前の状態が表示される」という性質のことです。この性質は、RDBの設計におけるルールである「ACID特性」によって実現されています。
2.処理コストの低減
RDBは複数のテーブルを活用することで処理コストを低減しています。テーブルとは、データベース内でデータを管理する単位のことです。RDBでは各テーブルが連結されており、追加・削除・更新といった処理に発生するコストを最小限に抑えています。
3.SQLによる標準化
RDBで使用されているSQLは、ISOで規格化された安定した言語です。複雑なデータの処理も、SQLによって標準化され、正確に実行できます。
RDB導入のデメリット
1.処理速度が遅い
RDBはプログラムが複雑化する傾向があり、処理が遅くなりやすい点がデメリットとして挙げられます。特に、膨大なサイズのデータを処理する場合は、業務効率に影響するほど速度が遅くなることも少なくありません。
上述したNoSQLデータベースは、RDBの処理の遅さを解消するために開発されたデータベースです。
2.拡張性が低い
RDBはサーバ1台で実行するように設計されている関係上、あとから拡張することは困難です。データの読み込みに関わる部分は比較的簡単に拡張できますが、書き込みに関わる部分の拡張は時間やコストの問題から現実的ではありません。
RDBMSの活用事例
RDBMSを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
フロントエンドのシステムの軽量化が可能
「歴史が長いだけあって、書籍やWeb、各ドキュメントマニュアルなど技術情報が多くあり、情報を入手しやすい。SQLを書く側にとっては利便性の高い、PL/SQLも機能として充実しており、DBにある程度のビジネスロジックを埋め込むこともでき、フロントエンドのシステムの軽量化が可能になっている。ハイパーフォーマンスかつ可用性が高いDBのため、業務アプリケーションの安定化と高速化が可能になった」
https://www.itreview.jp/products/oracle-database-12c/reviews/4030
▼利用サービス:Oracle Database 12c
▼企業名:ソフトバンクコマース&サービス株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:ソフトウェア・SI
構築コストを低くシステム構築ができた
「GUIで管理できるので比較的初心者でも扱える。DBMS利用のとっかかりにはいいです。ただ動かすだけ(レスポンスチューニング等をしないの)であれば、それほどスキルがなくてもDBの構築・管理がおこなえます。ライセンスコストだけでなく、構築・管理工数等含めたトータルでの構築コストを低くシステム構築ができた」
https://www.itreview.jp/products/sql-server-2017/reviews/12639
▼利用サービス:SQL Server 2017
▼企業名:株式会社LIXIL ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:鉄・金属
複雑な設定無しで手軽に利用
「中小規模のプロジェクトで手軽に利用することが出来るデータベース。社内向けのツールやプロトタイプを作成するときに使う場合が多いが、場合によってはそのまま採用するケースもある。元々エクセルなどでを使用していた社内情報の管理が煩雑になってきたため、簡易な社内向け管理システムを構築した際に、複雑な設定無しで手軽に利用することが出来た」
▼利用サービス:MySQL Enterprise Edition
▼企業名:株式会社ネクシジョン ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
https://www.itreview.jp/products/mysql-enterprise-edition/reviews/16947
データベースの選び方のポイント
現在は多くのデータベースシステムが提供されています。単にサイズだけを取り上げても、個人利用を想定した小規模なものから、企業用の膨大な規模のものまでさまざまです。また、機能やカスタマイズの幅もシステムによって異なります。自社に合ったデータベースを導入するために、以下のような選び方のポイントを意識してください。
コスト
データベースに限らず、システム選びにおいてコストは重要な要素です。データベースの場合は、ライセンス、ハードウェアの費用が代表的なコストとして挙げられます。その他、構築に発生するコストや運用開始後のコスト、人件費、利用する担当者の教育コストなど、トータルのコストを考えることが大切です。初期コストが低くても、運用後のコストがかさんでしまうケースもあります。
データベースの性能とコストの関係についても覚えておきましょう。処理できるデータ量、同時に操作できるユーザー数、動作の安定性、動作効率などはコストによって変わってきます。少しでもコストを抑えたい場合は、自社が何人でデータベースを操作するのか、どの程度の規模のデータを扱うのか、といった点をあらかじめ細かく検討しておくことが大切です。
また、データベースにはトラブルが起こり得るため、トラブル時のコストを見越しておくことも大切です。導入しただけで予算を使い切ってしまうような場合は、トラブル時のコストを負担できないケースがあります。
業務とのマッチング
業務ごとにマッチングのよいデータベースは異なります。どの業務にデータベースを導入するのか検討したうえで、最適なデータベースを選んでください。
現在は、特定の業務での利用を想定したデータベースが多数リリースされています。膨大な顧客情報管理用のデータベースなどが代表例です。実際の業務を意識して設計されているため、導入して簡単なカスタマイズを済ませれば、すぐに実務で利用できます。
また、複数の業務を統合できるデータベースのパッケージ製品もあります。業種によってマッチングが異なるため、同業他社の間ではどんな製品が評価されているのか調べてみましょう。上述した専門的なデータベースと比較すると構築の手間がデメリットとなりますが、運用開始後、業務に定着すれば大幅な効率化とコストダウンが期待できます。
提供形態
データベースの活用を想定しているビジネスモデルによっては、パッケージの製品ではカバーできないケースがあります。基盤となるデータベースから、業務に合わせてシステムを拡張していくことができれば理想です。その際には、ベンダーとのパートナーシップが求められます。データベースそのものに加え、ベンダーがシステム構築のサービスを提供しているか、信頼できるスキルをもっているか、といった点にも注目しましょう。
RDBの業界マップ
RDBのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューを元に生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
RDBMS製品おすすめ5選
実際に、RDBを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのRDBを紹介します。
(2022年1月5日時点のレビューが多い順に紹介しています)
PostgreSQL
「PostgreSQL」は、オープンソースタイプのRDBMSです。Linux、macOSのほか、Windowsでも利用できます。ソースが公開されており、無料で利用できることから、世界的に人気の高いデータベースです。機能面も非常に充実しており、商用のデータベースと比較してもひけを取りません。シェアが大きいことから情報を見つけやすく、日本語の参考資料が多い点も魅力です。
Oracle Database 12c
「Oracle Datab 12c」は、アメリカのオラクル社が手がけるRDBMSです。Oracle Databeseは世界初の商用RDBMSであり、市場ではトップシェアを占めています。12cは5年半ぶりのメジャーアップデートであり、世界初のクラウド対応を見越して設計されたデータベースとして注目されています。新しく実装された「Oracle Multitenant」により、データベース内に仮想的なデータベースをさらに構築可能です。
Oracle Database 12cの製品情報・レビューを見る
SQL Server 2017
「SQLServer 2017」は、マイクロソフト社が提供しているRDBMSです。Windowsとの相性がよいことから、Widows Serverでは一般的に利用されています。言語としてSQLに独自に拡張を加えた「Transact-SQL(T-SQL)」を使用するのが大きな特徴です。SQLに習熟している場合は、延長線上の感覚でさらに高度な操作を実施できます。また、通常の操作自体も直感的でシンプルなため、慣れていないユーザーでも比較的扱いやすいデータベースです。
MySQL Enterprise Edition
「MySQL Enterprise Edition」は、データベースのデファクトスタンダードである「MySQL」に開発・管理・解析・バックアップをサポートするさまざまな機能を追加したパッケージ製品です。安定性・速度が世界中の企業から高く評価されています。MySQL自体は無料ですが、こちらはエンタープライズ向けのパッケージとしてサブスクリプション形式で提供されています。WebサイトやWebアプリケーションの開発・運用では世界的に普及しているサービスです。
MySQL Enterprise Editionの製品情報・レビューを見る
Amazon Relational Database Service
「Amazon Relational Database Service」は、クラウド上のセットアップ、運用が可能なRDBです。AmazonのAWS(Amazon Web Service)上で提供されています。「Amazon Aurora」「Postgre SQL」「MySQL」「MariaDB」「Oracle」「SQL Server」など、6つのRDBMSから選択できる点が大きな特徴です。「従量課金」「定額制」という2種類の料金体系があり、利用状況に応じて選ぶことでコストを削減できます。
Amazon Relational Database Serviceの製品情報・レビューを見る
ITreviewではその他のRDBも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながらRDBツールを検討することができます。
RDB (リレーショナルデータベース)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧
まとめ
データベースを導入すると、データを安全に管理することが可能になります。社内システムを構築する際は、自社に合ったデータベースを導入することでシステム構築や業務を効率化できるでしょう。RDBはデータの一貫性や処理コストに優れています。コストや業務とのマッチングを考慮して、バランスのよいRDBパッケージをお選びください。
投稿 RDB(RDBMS)とは? 導入メリットやデータベース選定のポイントをチェック は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ERPとは?基幹システムの違いやERP導入のメリットを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>ERPとは?
ERPとは「Enterprise Resource Planning(企業資源計画)」の略で、企業がもつ資源をシステムで効率的に管理する取り組みを意味します。一般的には、この取り組みのために使用されるシステムそのものを指して用いられる呼称です。
ERPで管理する企業の資源とは、すなわち「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」のこと。これらは、どの企業でも例外なく資源として有効活用することが求められています。つまり、人材の管理、在庫の管理、財務の管理を1つのシステムにまとめることで効率化するのがERPです。
そして、このERPの概念を実現・管理するシステムとして「ERPパッケージ」というアプリケーションが発展しました。現在ではERPという言葉そのものがERPパッケージを指すことが多くなっています。
ERPの導入によって、「会計」「販売」「物流」「生産」「人事」などを統合的に管理した情報に基づき、業務の効率化や迅速な経営判断が可能になります。
このようなメリットからERPを導入する企業は増え続けています。
基幹業務システムとの違い
ERPと混同されやすいのが、基幹業務システムです。基幹業務システムとは、企業で発生する主要業務をサポートするシステムのこと。「バックオフィス系システム」「業務系システム」などと呼ばれています。
混同されるのは、ERPと基幹業務システムで処理する業務の多くで重複していることが理由です。ただし、基幹業務システムでは、勤怠管理、会計、受発注、在庫管理といった業務によってシステムが独立しています。対して、ERPは複数のシステムが統合されており、データを一元管理できるほか、各業務の連携性に優れる点が特徴です。
ERPは基幹業務システム以上にデータのやり取りがスピーディーになるため、企業が保有している資源の状況をリアルタイムで把握できます。基幹業務システムよりも資源の有効活用にフォーカスしているシステムがERPであるといえるでしょう。
ERPの基本機能
ERPは、一般的に次のような機能を搭載しています。
財務・会計に関連する機能
会計管理機能
仕訳帳や総勘定元帳、残高試算表など、会計業務の書類を作成する機能です。
経費精算機能
従業員が使用した経費の申請受付、集計、承認までのフローを処理する機能です。製品によっては、振込の機能も利用できます。
決算処理機能
決算書、内訳書、概況書、青色申告書などの作成をサポートします。キャッシュフローを自動で可視化することも可能です。
資産管理機能
固定資産の管理や減価償却を支援します。税務申告書などの作成も可能です。
人材・人事・給与に関連する機能
人事管理機能
雇用している従業員の情報や、扶養家族、社会保険、マイナンバーなどの付帯情報を管理します。
人材管理機能
各人材が従事している業務や、持っている資格、異動の履歴、受講済みの研修、といった情報を管理します。
勤怠管理機能
従業員の出退勤の時間、残業時間、有給休暇の消化状況など、勤怠情報を管理します。
給与計算機能
勤怠情報をもとに、給与を自動計算します。賞与の計算や明細書の発行、振込までシステム上で完結可能です。
税務関連機能
所得税、住民税、年末調整、源泉徴収票などの計算・書類作成をサポートします。
販売・購買・在庫に関連した機能
販売管理機能
受注情報、売上情報、入金情報を管理する機能です。請求書をシステム上で作成・発行する機能もあります。
購買管理機能
発注、納品書の作成、支払いといった購買業務をサポートします。
在庫管理機能
品目や数量など、在庫情報を管理します。システムによっては有効期限や棚卸しのタイミングでアラートを出す設定も可能です。
債権管理機能
売掛金の回収残高、回収期日などを管理します。
債務管理機能
買掛金の支払残高、支払期日などを管理します。
生産・原価に関連した機能
生産管理機能
製品の型番、製造工程の進捗、外注の利用状況などの情報を一括で管理します。
原価計算機能
予定原価と実際の原価の差分を確認・分析する機能です。原価をシミュレーションすることもできます。
品質管理機能
製品テストのデータなどを管理し、品質保証をサポートします。
ERPの種類
ERPには次のような種類があります。それぞれに特徴があるため、自社に合った種類の製品を選ぶのが大切です。
| クラウド型ERP | クラウド上に構築されたシステムにインターネット経由でアクセス |
| オンプレミス型ERP | 自社内に設備を設置し、システム運用を内製化 |
| パッケージ型ERP | あらかじめ企業の資産管理に必要となる一般的な機能を搭載 |
| フルスクラッチ型ERP | パッケージ型ERPとは対照的にゼロから構築 |
クラウド型ERP
クラウド型ERPは、クラウド上に構築されたシステムにインターネット経由でアクセスするタイプのERPです。自社でサーバなどを用意する必要がないため、工数や導入スピード、コストの面で優れています。
インターネット上に企業の情報をアップロードするため、以前はセキュリティ面が懸念されていました。しかし現在は、各ベンダーが強固なセキュリティ体制を整えているため、それほど不安視する必要はないと考えられています。
オンプレミス型ERP
オンプレミス型ERPは、自社内に設備を設置し、システム運用を内製化するタイプのERPです。クラウド型が台頭する以前は、スタンダードなタイプでした。現在もセキュリティ面の安心感、カスタマイズ性に優れていることから、オンプレミス型のERPを運用している企業は少なくありません。
問題は、初期費用や運用コストがかかる点です。また、社内に専門の人材がいないと運用が難しいことから、中小企業で選ばれることはあまり多くありません。
パッケージ型ERP
パッケージ型ERPとは、あらかじめ企業の資産管理に必要になる一般的な機能を搭載したERPです。クラウド型のERPは、大半がこのパッケージ型に該当します。導入した時点で機能が揃っているため、スムーズに運用開始できます。一方で、一般的ではない独特のオペレーションが採用されている場合は調整が難しいというデメリットがあります。ちなみにここで言う「パッケージ型ERP」の呼称は、総称として使われる「ERPパッケージ」とは意味が異なります。
フルスクラッチ型ERP
フルスクラッチ型ERPとは、パッケージ型ERPとは対照的にゼロから構築するタイプのERPです。求める機能を自由に実装できます。基幹業務に企業独自の慣習がある場合も、フルスクラッチ型であれば対応可能です。ただし、開発期間が長いことと、かかるコストが大きい点がデメリットとして挙げられます。
ERPを導入する際の流れ
ERPを導入する際は、以下のような一般的な流れで行うとスムーズです。
1.目的を明確にする
最初のプロセスとして、ERPの導入目的を明確にします。上述した「ヒト」「モノ」「カネ」の管理においてどういった課題があるのか、またシステム導入によってどの課題を解決したいのか明らかにします。目的を設定しておけば、ERPパッケージを選定しやすくなります。
2.プロジェクトの推進者を選定し、各部署の担当者と打ち合わせる
ERPに統合する業務に関わる人材や、導入を先導できる人材をプロジェクトの推進者としてアサインします。各業務の代表者を集められれば理想ですが、広範囲の業務をカバーできる少人数の推進者を選定しても構いません。部署間を横断的に発言できる人材が適任です。
3.業務プロセスなどについて棚卸ししておく
ERPに移行する業務を具体的に洗い出しておく必要があります。各業務で現状はどのツールが使用されているのか把握しておきましょう。現実的にERPへの移行が可能なのかどうかも検討してください。
4.新しい業務フローを構築する
ERPの導入によって業務フローに影響が出ることがあります。業務プロセスを棚卸しした結果をもとに、どこまでERPでカバーするのか決定し、決定内容に沿って新しい業務フローを構築してください。
5.試験運用を行う
ERPの試験的な運用を開始します。既存システムと併用しながら、問題なく運用できるか慎重に確認しましょう。また、本格運用に向けて社内マニュアルを整備しておくこともおすすめします。
6.本格運用を始める
試験運用で問題が確認されなければ、本格運用を開始しましょう。運用開始後も、見つかった改善点に応じて柔軟にシステムを調整していくことが大切です。
ERP導入のメリットとデメリット
まず、上述した「クラウド型」「オンプレミス型」「パッケージ型」「フルスクラッチ型」には、それぞれ次のようなメリット・デメリットがあります。
| 導入形態 | クラウド型 | オンプレミス型 | パッケージ型 | フルスクラッチ型 |
| メリット | ・コストが低い・導入が簡単 | ・セキュリティ面で安心・カスタマイズ性が高い | ・最初から一般的な機能がまとまっている | ・自由に機能を追加できる |
| デメリット | ・サービス継続性に不安・カスタマイズ性が低い | ・コストが高い・運用が手間になる | ・独自のオペレーションに対応できない | ・運用開始までに手間と時間がかかる |
以下では、ERP導入に関する一般的なメリット・デメリットについて解説します。
ERP導入のメリット
1.データの横断的な利用が可能になる
業務ごとに使用していたシステムが1つに統合され、データが横断的に利用できるようになります。部門をまたいだリアルタイムなデータ共有も可能です。
2.スピーディーな経営判断ができる
営業状況や売上をリアルタイムで可視化するダッシュボード機能は、経営判断に役立ちます。経営陣の必要としている情報がわかりやすくまとめられているため、経営判断がスピーディーになります。
3.経営資源の活用状況を把握できる
経営分析機能により「ヒト」「モノ」「カネ」という資源の活用状況がわかりやすく可視化されます。各資源の状況をリアルタイムで分析してデータを生成するため、情報の集積や資料作成といった手間がかかりません。
4.無駄な工数が削減される
ERP内のシステムに情報を入力すると、同じ情報を共有しているすべてのシステムのデータが更新されます。業務ごとに別のシステムを使っている場合のような二重入力の手間は発生しません。
5.ガバナンス・コンプライアンスを強化できる
情報の分散は、情報漏えいや不正利用のリスクを高めます。ERPを導入すると、データの管理が統合されるため、ガバナンスの強化が実現可能です。また、各データの利用状況も管理・監視できるため、コンプライアンスの強化にもつながります。
ERP導入のデメリット
1.導入・保守・教育にコストがかかる
ほかのシステムと同様、導入には初期コストが発生します。オンプレミスの場合、導入後の保守・運用コストも決して無視できない要素です。社員が使い方を習得するまで時間がかかるため、導入後しばらくは期待していた効果が出ないこともあります。
2.選定に時間がかかる
現在は展開されているERPの種類もさまざまで、選定に時間がかかってしまいがちです。社内全体に影響を与えるシステムのため、急いで決めるのはおすすめできません。必要な機能を見極めたうえで、自社に適した製品を慎重に選ぶ必要があります。
3.導入時のデータ整理に手間がかかる
ERPの導入時には、それまで各システムで管理していたデータを入力します。業務ごとに異なるルールで管理されていることが多いため、ERPへの統合に際してはデータの標準化が必要です。この整理作業に手間と時間がかかってしまうケースがあります。
ERPの活用事例
ERPを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
他部門との連携がスムーズに
「単なる会計システムではなく、購買や製造とリンクしているため他部門との連携がとりやすいシステムだと思います。他の会計システムの場合だと、経理処理に偏っていて他部門との連携が図れなかったのがスムーズにできるようになりました。決算処理もかなりスピーディーに行えるようになりました」
https://www.itreview.jp/products/sap-erp/reviews/15961
▼利用サービス:SAP ERP
▼企業名:クリプトリーム株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
ペーパーレス化と情報の速度の高速化が図れた
「OBICに給与のシステムが変更となり、社員一人一人にアカウントが付与され、給与の明細がネット上で閲覧ができるようになったことで、過去の給与の記録も源泉の用紙も自分で得られることができるので、ペーパーレス化に非常に良い影響を与えている。全体の管理が一つのシステムで賄われていえることによって、社内のペーパレス化と情報の速度の高速化が図れたと思われる。経理的なものは、置いておくが社員としては、使いやすくなったのではないかと感じる」
https://www.itreview.jp/products/obic7/reviews/26900
▼利用サービス:OBIC7
▼企業名:株式会社文化工房 ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:放送・出版・マスコミ
進捗が一目瞭然で業務効率の改善につながった
「社風やビジネスモデルに沿った基幹システムを構築できるため、会社全体の動きが止まらないかつ混乱せずに導入できた。またシステムのプロセスを進めるのにどの証憑、誰の承認が必要かが可視化されるため申請者にとってわかりやすく、会社全体の内規や会計監査、内部監査への意識が高まったように思います。システム導入前は売上計上のための証憑(契約書等)の進捗が記録に残らず、月次決算の段階で慌てて契約書を締結するなど進捗確認に非常に工数がかかっていました。システム導入後は証憑の有無や進捗が一目瞭然であるので業務効率の改善につながったと思います」
https://www.itreview.jp/products/roboterp-tsubaiso/reviews/61524
▼利用サービス:RobotERPツバイソ
▼企業名:エヴィクサー株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
ERPパッケージの業界マップ
ERPのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
ERPの選び方のポイント
導入後のミスマッチを防ぐため、ERPの製品選びでは次のようなポイントを意識してください。
既存業務とのマッチング
フルスクラッチで導入する場合を除き、ERPが既存業務に100%マッチすることはありません。導入に際して、少なからず業務プロセスを変更する必要があります。その負担を少しでも軽減するため、既存業務とのマッチングに注目しながら各製品を比較検討しましょう。
拡張性やカスタマイズ性
システム側の業務プロセスを合わせられないケースもあるでしょう。その場合は、システムの拡張やカスタマイズが必要です。拡張・カスタマイズの可否やコストにも注目してください。
導入形態
クラウド型のERPが主流になっていますが、企業によってはオンプレミス型導入による恩恵が大きい場合もあるでしょう。争点となるのは主にカスタマイズ性とコストのバランスです。
オンプレミスはカスタマイズ性に優れますが、初期コストの負担がネックになります。クラウド型は一般的にコストとカスタマイズ性が低いといわれています。しかし、近年は各ベンダーが積極的に機能追加を行っているため、特殊な業務慣習がない限り不自由を感じることはほとんどないでしょう。
セキュリティ性能
セキュリティ性能にも注目しましょう。かつては「オンプレミスはセキュリティが堅牢で、クラウドはセキュリティ機能が低い」という意見が定説でした。しかし、近年では各ベンダーの努力により、クラウドのセキュリティ性能も高まっています。社内の意識や体制に依存するオンプレミスよりもクラウドのほうが安全だ、という声も少なくありません。
ERPパッケージ製品おすすめ5選
実際に、ERPパッケージを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのERPパッケージを紹介します。
(2022年1月5日時点のレビューが多い順に紹介しています)
SAP ERP
「SAP ERP」は、購買、製造、セールス、人事、財務など、企業における各部門の業務と統合するERPパッケージです。特に会計機能の評価は高く不正防止などに活用されています。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの3タイプから選べる点も特徴です。
SAP ERPの製品情報・レビューを見る
OBIC7
「OBIC7」は、会計業務を基盤にして、人事、給与、販売、生産管理など企業で発生するさまざまな管理業務をカバーする総合基幹業務システムです。各業務のデータを1つのデータベースで管理することで、シームレスな情報共有を実現します。クラウド型でありながら、拡張性に優れている点も強みです。
RobotERPツバイソ
「RobotERPツバイソ」は、Salesforceを基盤としたクラウド型ERPパッケージです。財務、業務プロセス管理のほか、顧客管理や従業員のタレントマネジメントの生産性向上に貢献します。ベンダー側のコンサルタントがユーザー企業の課題をヒアリングし、拡張機能の選定をサポートしている点が特徴です。
GRANDIT
「GRANDIT」は、複数社のノウハウを結集し、日本の商習慣に合わせて開発されたERPです。13社のコンソーシアム企業と約60社のパートナー企業が連携し、積極的な機能強化を行っています。業務モジュール単位での導入が可能なため、さまざまな規模の企業で活用されています。
multibook
「multibook」は、多言語に対応しており、海外拠点や海外子会社の管理も可能なクラウド型ERPです。海外拠点管理での「不正が心配」「駐在員が報告業務に追われている」といった悩みを解決します。海外拠点を含めた経営状況がリアルタイムで把握できるため、海外市場での競争に必要なスピーディーな経営判断を実現できます。
ITreviewではその他のERPも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながらERPを検討することができます。
ERPパッケージの比較・ランキング・おすすめ製品一覧はこちら
まとめ
ERPを導入すれば、社内のデータベースに散財している「ヒト」「モノ」「カネ」の情報が統合され、管理が一元化されます。各業務で使用しているツールは業務を効率化します。しかし、データの共有・統合という点では複数のツールの存在が弊害になることも少なくありません。資源情報管理の最適化を図りたい場合は、ERPの導入をぜひ検討してください。
投稿 ERPとは?基幹システムの違いやERP導入のメリットを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Web会議とテレビ会議の違いとは?導入のポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>Web会議システムの導入を検討しつつも、上記のような悩みで踏み切れない企業も多いのではないでしょうか。
Web会議システムならインターネット環境やヘッドセット、パソコンなどのデバイスを揃えるだけで、どこからでも会議を行えます。移動コストや会議準備の手間を削減できたり、意思決定のスピードが速くなったりと多くのメリットが得られるでしょう。
この記事では、Web会議システムの機能やメリット・デメリット、システムを選ぶときのポイントについて詳しく解説します。
Web会議とは ?
Web会議の概要や提供形態、テレビ会議との違いについて解説します。
時間や場所を問わず会議を行えるツール
Web会議とは、インターネット経由で遠隔地にいる相手と会議できるツールです。リアルタイムで音声や動画、資料の共有ができ、近年は社内会議や商談、採用面接、会社説明会、セミナー、忘年会など人数の大小に関係なく幅広いシーンで活用されています。
必要な機材はパソコン・スマートフォン・タブレットなどのデバイスと、Webカメラやヘッドセットだけ。専用の機器は不要でアプリを使用するため、時間や場所を問わずWeb会議を行えます。
提供形態
Web会議システムにはクラウド型とオンプレミス型の2種類があります。基本的な違いは以下の表をご覧ください。
| 形態 | 概要 | メリット | デメリット |
| クラウド | ベンダーのサーバにアクセスして利用する | ・すぐに利用できる・利用規模が変わっても柔軟に対応できる・メンテナンスの手間を削減できる | カスタマイズしにくい |
| オンプレミス | 自社内にサーバを構築して運用する | ・自社のセキュリティポリシーに合わせられる・ランニングコストを削減できる | ・サーバ構築の専門知識が必要・導入費用やメンテナンスのコストがかかる |
自社のセキュリティポリシーに合わせたり、機能を柔軟にカスタマイズしたりと自由度の高いシステムを使いたい企業はオンプレミス型がおすすめです。逆に「提供されている機能でよいので、運用負荷や導入コストを減らしたい」という場合はクラウド型が適しているでしょう。
テレビ会議との違い
Web会議とテレビ会議のシステムの違いを次の表にまとめました。
| 種類 | 動作環境 | 安定性 | 機能 |
| Web会議 | ・インターネット環境とデバイスがあればどこでも会議に参加可能 | 多人数になると安定しない場合もある | 映像、音声、画面共有、チャットなど |
| テレビ会議 | ・専用の機器や回線を利用する・特定の場所で行う必要がある | 専用回線なので安定している | 映像、音声 |
テレビ会議は専用の機器や回線を利用するため、通信が安定しており、映像や音質の品質が高いのが特徴です。その分、導入コストがWeb会議よりも割高というデメリットもあります。
Web会議システムは会議室を用意しなくても会議を開催でき、機能も豊富です。その一方で、人数が多くなるほど音声や映像が不安定になるケースもあります。有料版なら安定性も確保できるうえ、セキュリティ対策やサポートも充実している場合が多いです。
テレワークの普及によるWeb会議の必要性の高まり
2019年末頃からWeb会議のニーズが急激に高まっています。実際に2020年度のWeb会議市場は前年度の2倍強に成長しています。
その理由として、新型コロナウイルスの影響でテレワークを導入する企業が増加したことが挙げられるでしょう。テレワーク環境下でも、従業員や取引先企業との迅速なコミュニケーションが求められます。Web会議を利用することで、これまで対面で行っていた社内会議や採用面接、商談などを、非対面に切り替えられるようになりました。
また働き方改革によってテレワークが推進されたことも理由の1つです。従業員1人ひとりに合った労働環境を提供するには、会社という1カ所の場所にとらわれないことが重要です。Web会議なら移動や準備の時間を削減でき、より効率的な働き方を実現できるようになります。
Web会議システムの機能
Web会議システムの基本的な機能について解説します。
音声・映像の共有機能
参加者の音声と映像を共有し、リアルタイムにコミュニケーションできる機能です。1人ひとりの反応を見聞きしながら進められるため、テレワークでもスムーズな会議を行えるようになります。
ファイル共有機能
会議資料を参加者全員に共有したいときに便利な機能です。メールで資料を送付する場合には宛先漏れがないか確認する手間がかかりますが、共有機能を使えばWeb会議の最中にその場で一斉配布できます。資料の配布漏れもなくなるため、会議主催者も参加者も安心です。
ホワイトボード機能
参加者全員が同じ画面を見ながらテキストや図形を使ってコミュニケーションがとれる機能です。マウスやキーボードだけでなくペンタブレットも使えます。対面で議論するときと同じようにフローチャートなど視覚的な情報を共有できるため、認識誤りを減らし、より効率のよい会議を行えるでしょう。
デスクトップ共有機能
ほかの参加者が見ている画面を自分のパソコンに表示する機能です。操作の許可を得ることで、相手の画面をリモートで操作できます。システムの操作方法を教えたり、トラブル発生時に状況説明したりと、メールや電話だけで対応するのが難しいシーンで役立つでしょう。
録音・録画機能
Web会議上でのやり取りを録音・録画できる機能です。会議や研修に欠席した従業員がいる場合、あとから内容を共有するのは時間がかかるもの。録画機能があれば議事録を作成する必要もなく、正確に議論内容を把握してもらうことができます。また録画した映像を新人研修やセミナー用に配信すれば、講師や準備担当者などの時間やコストを削減することも可能です。
チャット機能
会議中に参加者同士でテキストメッセージを共有できる機能です。発言者の名前と日時が表示されるため、会議の議事録を作成しやすくなります。またWebサイトのURLを送って共有することも可能。「通信環境が悪い」「外出中で声が出しにくい」という状況下でも、柔軟に意見を伝えることができます。
Web会議システムを導入するメリットとデメリット
Web会議システムを導入するメリットとデメリットについて解説します。
Web会議システムを導入するメリット
導入するメリットは主に5つあります。それぞれ見ていきましょう。
1.交通費や移動時間のコストをカットできる
拠点が複数ある企業が会議を開くと、多くの従業員が1カ所に集まるためのスペースを借りる費用や交通費がそれだけ膨大になってしまいます。Web会議システムの場合、インターネット環境があれば時間や場所にかかわらずWeb会議を行えるので、場所やコストの制約がなくなります。その時間や費用をほかの業務に当てれば、生産性向上にもつながるでしょう。
2.優秀な人材を採用しやすくなる
Web会議の運用体制がしっかり整備されていれば、オフィスの所在地に関係なく、テレワークでどこからでも働くことが可能になります。日本国内だけに限らず、世界中のどこからでも働ける企業として求人を出すことができます。自由な働き方が実現できるため、それだけ優秀な人材を確保できる機会が増えるでしょう。
3.働き方改革を推進できる
「営業担当者が出先から会議に参加してそのまま直帰する」といった働き方改革も推進できます。自宅が遠くても社内ミーティングに参加できるので、時間をかけて通う負担がなくなります。その分を子育てや家族の介護、自分の時間に当てるなど有効に使うことが可能です。働きやすい職場環境を実現でき、従業員のモチベーションアップも期待できます。
4.意思決定のスピードが速くなる
Web会議システムならどこからでも手軽に会議を開催できるため、決めるべきことをスピーディーに確定しやすくなります。また意思決定者が多忙で社内にいる時間があまりなくても実施できるので、スケジュールに合わせて社内会議を開催するといった調整の手間がなくなります。
5.感染症拡大や災害時にも対応できる
緊急事態が起きると公共交通機関がまひしたり、電話がつながりにくくなったりします。Web会議システムならパソコンやスマートフォンの画面で相手と顔を合わせつつ、どのような状況下にいるかなど安否確認ができます。また資料の共有機能やホワイトボード機能を活用することで、遠隔地にいても的確な指示を出せるでしょう。このように、Web会議システムはパンデミックや自然災害が起きた場合のBCP(事業継続計画)対策にも有効です。
Web会議システムを導入するデメリット
導入するデメリットは主に2つあります。
1.セキュリティリスクがある
Web会議システムはインターネットを介すため、不正アクセスやアカウント流出による情報漏えいが懸念されます。この問題を防ぐには次のような対策をとることが有効です。
| 不特定多数が利用する無料Wi-Fiを使わない |
| 会議室ごとにセキュリティコードを発行し、部外者の侵入を防ぐ |
| Web会議システムにアクセスできるIPアドレスを指定する |
参加者1人ひとりがデバイスを外に置き忘れない、会議室のURLを外部に漏らさないなどの危機管理意識をもつことも欠かせません。
2.会議の雰囲気を読みにくい
Web会議には、参加者が場の雰囲気に流されずに発言しやすくなるというメリットもあります。しかしその反面、雰囲気を読めないので発言者の意図を正確に把握しにくくなるともいえるでしょう。「そんなつもりで言ったわけではないのに」と、ほかの参加者に誤解されてしまうケースもあります。
対策としては「今の発言は〇〇という理解で合っていますか?」のように確認を入れること。参加者が「Web会議は正確に意図が伝わらないこともある」と理解したうえで、伝わりやすくなるような振る舞いを心がけるとよいでしょう。
Web会議システムの活用事例
Web会議システムを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
初心者でも安心してWeb会議ができる
「なかなか実際に会えない時にたやすく会議を実施できた(初めての方もURLを送付することで会議に参加することができた)。外部に公開できない会議について,パスワードを利用することで安心して会議をすることができた。オンライン会議だと使用が困難な資料の提示について,資料を表示して議論することができた」
▼利用サービス:Zoom Meetings
▼企業名:諏訪坂法律事務所 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:その他https://www.itreview.jp/products/zoom/reviews/86948
業務効率を大きく向上させてくれた
「多(他)拠点にいるメンバーとの会議が多くなり、Teams会議をはじめとしたweb会議がとても多くなっています。その点で重宝します。また、会議後にファイル共有する際もTeamsチャット欄への貼付で済ますことも多く、今からこのツールがなくなったらと考えると、業務効率の大幅な低下を招くことしか考えられません」
https://www.itreview.jp/products/microsoft-teams/reviews/86405
▼利用サービス:Microsoft Teams
▼企業名:オムロン株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:電気・電子機器
世界中で会議ができ、移動コストの削減に
「移動コスト・時間コスト削減。世界中どこにいても会議が出来るので、海外の企業様への簡単な打ち合わせなら直接会わなくてもweb会議で充分ですので、移動コストの削減につながりました。また、社内でも複数拠点で同時につなぐことが出来るので、一か所に集まる必要がなくなり、時間の削減にもつながっています」
https://www.itreview.jp/products/cisco-webex-meetings/reviews/38763
▼利用サービス:Webex Meetings
▼企業名:Hightec Technology & Engineering(Thailand)Co.,Ltd. ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:電気・電子機器
短時間で建設的な議論が可能になった
「短期間で、問題を解決が必要な問題に関して、会議を招集し、建設的な議論を短時間で成し遂げることができた。プレゼン資料以外に適宜必要な資料を表示して深い意味のある議論ができた」
https://www.itreview.jp/products/hangout-meet/reviews/48656
▼利用サービス:ハングアウト Meet
▼企業名:国立大学法人信州大学 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:大学
URL一つですぐにWeb会議を始められる
「相手の連絡先を知らなくても、URL一つですぐにミーティングできるため、問題解決速度が向上した。電話などよりもチャット画面を共有できるため、お互いに理解がしやすくなった」
https://www.itreview.jp/products/appear-in/reviews/30687
▼利用サービス:Whereby
▼企業名:まんがたり ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:広告・販促
Web会議の業界マップ
Web会議システムのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
Web会議システムを選ぶポイント
Web会議システムを選ぶときに重要な5つのポイントについて解説します。
接続が安定しているか
Web会議システムを選ぶときは、どんなインターネット環境でも安定した接続ができることが重要です。音声や映像が途切れ途切れになると会議にストレスを感じるでしょう。また、伝えたはずが伝わっていなかったなど重大なミスを引き起こしかねません。こういった問題は品質の高いシステムを導入することで改善されやすくなります。
セキュリティ対策が万全か
インターネットを利用するためのセキュリティ対策が徹底されていないと、共有する機密情報や顧客情報の漏えいの危険性があります。
どんなセキュリティ対策がとられているのかを必ず確認しましょう。主なセキュリティ対策には、暗号化通信、IPアドレスによるアクセス制限、会議ルームへのセキュリティコード付与などがあります。よりセキュアな環境を整備したい企業にはオンプレミス型のWeb会議システムがおすすめです。
同時接続できるアカウント数が多いか
同時に接続できるアカウント数は、300人までのシステムもあれば、最大1,000人まで利用可能なもので、Web会議システムによって異なります。
そのため、あらかじめ使用用途を洗い出しておくことが重要です。大人数の研修やセミナーを頻繁に行う企業なら、同時接続数が多いシステムを選ぶことをおすすめします。
直観的に操作できるか
Web会議システムは社内だけでなく、取引先など外部の人も参加する場合があります。誰でも簡単に利用できるものがよいでしょう。操作画面がシンプルで直感的な操作ができるものなら、ストレスなく会議を進められます。
また、多機能なシステムでも使いづらいと社内に浸透しにくく、導入コストが無駄になってしまうケースもあります。使用感が心配な場合は、無料で試用版を提供しているところを選んでみてください。
マニュアルやサポートが充実しているか
わかりやすいマニュアルがない場合、システムを導入する際に従業員に説明する時間が必要になります。また「起動するとブラウザが落ちてしまう」「ミーティングルームになぜか入れなくなった」などの状況が起きたときにサポートに頼れないと、自分で調べなければならないため、業務にも影響が出てしまうでしょう。24時間365日サポートや電話での対応を行っているWeb会議システムがおすすめです。
おすすめのWeb会議システム5選
実際にWeb会議システムを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの製品を紹介します。
(2021年12月27日時点のレビューが多い順に紹介しています)
Zoom Meetings
ユーザーの参加は最大1,000人、ビデオ画面の表示は最大49人まで対応しているWeb会議システムです。クリアな映像と音質で会議を続けられるため、「途中で音が途切れてしまった」といった事態も起きにくいでしょう。OutlookやGoogleカレンダーなどと連携できるため、外出先でもモバイル端末のカレンダーからすばやくミーティングに参加することが可能です。また暗号化、捜査権限設定、パスコード保護、待機室利用などのセキュリティ機能があるので、安全なミーティングを行えます。グループミーティング無制限のプロプランの場合、料金は2万100円/年/ライセンス。無料版もあります。
Microsoft Teams
もっとも人気の高い「Microsoft 365 Business Basic」プランなら、最大参加者300人で最長30時間まで会議を行えます。会議のレコーディングや文字起こしなど便利な機能も。ExchangeやOneDrive、OutlookなどOfficeアプリも利用可能です。ストレージは1人あたり1GBと大容量。サポートは電話とWebの両方をいつでも利用できるため、トラブル発生時も安心して利用できます。1カ月間無料の試用版や、無料版(最長60分、1つの会議参加者最大100人などの制限あり)もあります。
Webex Meetings
すべての通信に強力な暗号化が施されるため、会議中も安心してデータのやり取りができます。またユーザー認証があるので、メッセージやファイルの共有もより安全に行えるでしょう。さらに100以上の言語へのリアルタイム翻訳が利用可能。最新のAIによる強力なノイズ除去機能で、自宅の雑音やキーボードの打音などを消してくれるの会議に集中することができます。またアイコンが感情を表現するジェスチャ認識機能なども装備。GoogleやSlack、Salesforceなど業界のメジャーなアプリ100種類以上とシームレスな連携も可能です。
EnterPriseプランならチャット・電話によるサポートに加え、専属の担当者もつきます。無料で始めることもできるので、まずは操作性を知りたい企業におすすめです。
Google Meet(旧称:ハングアウト Meet)
Googleの他サービスと同じユーザー情報保護機能と、プライバシー保護機能が適用されています。会議中の通信もすべて暗号化されるうえ、乗っ取り防止機能や2段階認証にも対応。内部情報をより安全に保ちたい企業におすすめです。またネットワーク速度に応じて設定が自動調整されるので、どんな場所にいても品質の高いビデオ通話を実現できるでしょう。Google Workspace Enterpriseプランなら24時間365日対応のオンラインサポートを受けられます。ストレージも無制限で利用可能。料金は問い合わせが必要です。
Whereby
アカウントの登録不要、アプリのインストール不要で手軽にWeb会議を始められるツールです。操作画面の言語は英語のみで日本語非対応ですが、シンプルな画面なので直観的に操作できます。ミーティングのURLの文字をカスタマイズできるため、ミーティング内容別にわかりやすいURLにすることも可能。ITツールの利用に不慣れなユーザーでもURLをクリックするだけで参加できるので、日常使いしやすいのがメリットです。無料版は参加者が100人までで、一部の機能に利用制限あり。Businessプランは9.99ドル/ライセンス/月です。
ITreviewではその他のWeb会議システムも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながらWeb会議システムを検討できます。
まとめ
Web会議システムはコロナ禍や働き方改革の影響もあり、急速に普及しているツールです。時間や場所を問わず会議を行えるため、交通費や移動時間を削減できるうえ、優秀な人材を採用しやすくなるなどのメリットもあります。アフターコロナの世界でもテレワークの重要性は高まっていくことが予想されるので、今からWeb会議システムを導入しておくことをおすすめします。
Web会議システムを選ぶ際は、接続が安定しているか、セキュリティ対策が万全か、同時接続できるアカウント数が多いかといった点に注目しましょう。また新入社員や取引先企業などさまざまなユーザーが利用することを想定し、直観的に使いやすいものを選んでください。さらにマニュアルやサポートが充実している製品なら、急なトラブルが発生したときも迅速に対処できるでしょう。
投稿 Web会議とテレビ会議の違いとは?導入のポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 CPA(顧客獲得単価)とは?計算方法から改善のアイデアまで解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、CPAの意味から計算方法や改善方法、類似の指標について解説します。
CPAとは?
CPAは「Cost Per Acquisition」もしくは「Cost Per Action」の略で、「顧客獲得単価」や「コンバージョン単価」と呼ばれ、新規顧客を獲得するために費やしたコストを示します。一般的には1人の顧客や1件の成約を獲得するためにかかった広告費を指します。
CPAは広告の費用対効果を把握できる指標なので、たとえば広告の出稿量が増えたとしても、CPAが低ければ費用対効果が高く広告費以上のリターンを得ていると判断できます。
このときのリターンとは、商品・サービスの購入や入会、サンプルや資料の申し込みを示します。
なぜ、CPAが必要か?
広告の費用対効果を数値で確認できなければ、その広告の運用を継続すべきかどうか、あるいは強化すべきかどうかの判断ができません。
そのため、CPAを使用して、広告でコンバージョンが獲得できているかどうかを確認する必要があります。
コンバージョン(Conversion)とは「変換」や「転換」「交換」を表す英語ですが、マーケティングでは広告によって商品・サービスの購入や、入会や資料取り寄せなど、広告主にとって価値のある行動に至ることを意味します。
CPAの値が小さければ、少ない広告費で多くのコンバージョンを獲得できたことを意味します。逆にCPAの値が大きくなることは、コンバージョンを獲得するための広告費がかさんでおり、費用対効果が低いことを意味します。
したがって、CPAの値が大きい場合は、広告の運営に関して改善すべき点があること判断して見直しを行う必要があります。
CPAの計算方法
CPAはコンバージョン1件当たりの広告費を求める次の式で算出できます。
CPA = 広告費 ÷ コンバージョン件数
たとえば、ある月に広告費を50万円投入した結果として新規顧客を5人獲得できていれば、
CPA = 50万円 ÷ 5人 = 10万円
とCPAが10万円になります。そして次の月に70万円の広告費を投入した結果、新規顧客を10人獲得できていれば、
CPA = 70万円 ÷ 10人 = 7万円
とCPAが7万円になります。
この結果から、前の月のほうが広告費は安く済んでいますが、費用対効果はあとの月のほうが高かったことになり、効果的な広告運用ができたことがわかります。
目標CPAの決め方
費用対効果の高い広告運用を行うために、目標CPAを算出しておく必要があります。
目標CPAを設定するためには、商品原価や人件費、広告費などを算出しておきます。
広告は利益を上げるために行う施策ですから、目標CPAは利益が出ることを前提に設定します。そのために、採算が合わなくなる限界CPAをあらかじめ算出しておく必要があります。
しかし、コンバージョンに直接利益が出ない資料請求や無料トライアルの申し込みなどを設定している場合は、必ずしも直接的な利益が出る設定をする必要はありません。
以下、限界CPAと目標CPAについて解説します。
限界CPAとは?
限界CPAは、コンバージョン1件にかけられる広告費の上限です。式は次のとおりです。
限界CPA = 売上単価 - 原価 - 経費
たとえば、売上単価が2万円で原価が7,000円、経費が3,000円だとすると、限界CPAは1万円になります。1万円はあくまで上限値ですから、この上限まで広告費をかけては利益がなくなってしまうことに注意が必要です。
また、限界CPAは損益分岐点ですから次の式でも算出できます。
限界CPA = 顧客単価 × 利益率
前出の例をこの計算方法に当てはめると、顧客単価は2万円で利益率は50%でしたから、やはり限界CPAは1万円になります。
ただし、会員登録や資料請求、無料トライアルなど、直接利益が出ないコンバージョンを設定している場合は、成約率を加味した計算式になります。
限界CPA = 顧客単価 × 利益率 × 成約率
目標CPAとは?
目標CPAはコンバージョン1件あたりにかけられる費用の目標額なので、計算式は次のとおりです。
目標CPA = 限界CPA - 確保したい利益
たとえば、限界CPAが1万円で7,000円の利益を確保した場合の目標CPAは3,000円となります。
つまり、利益の何%を広告費に当てるのかによって目標CPAを設定するので、次の計算式にもなります。
目標CPA = 限界CPA × 広告費の割合
たとえば、2万円の商品で利益率50%の限界CPAは1万円です。この中から確保したい利益が70%だとすると、広告費には30%を当てられるので、目標CPAは3,000円となります。
売上が成果となる場合の目標CPA
コンバージョンが売上になる場合の目標CPAは比較的シンプルに算出できます。
たとえば、商材の価格が3万円、製造原価が9,000円、人件費が6,000円の場合、
限界CPA = 売上単価 - 原価 - 経費 = 3万円 - 9,000円 - 6,000円
なので、限界CPAは1万5,000円となります。
確保したい利益が8,000円だった場合、
目標CPA = 限界CPA - 確保したい利益 = 1万5,000円 - 8,000円
なので、目標CPAは7,000円となります。
直接売上にならない場合の目標CPA
コンバージョンが直接売上にならない場合の目標CPAは次のように算出できます。
たとえば、コンバージョンが資料請求で、成約率が資料請求者の50%とします。商材は8万円で製造原価が3万円、人件費などの経費に1万円かかっている場合、限界CPAは次の式で求められます。
限界CPA =(売上単価 - 原価 - 経費)× 成約率 =(8万円 - 3万円 - 1万円)× 50%
したがって限界CPAは2万円となります。
目標とする利益を1万円とした場合、
目標CPA =(限界CPA - 確保したい利益)× 成約率=(2万円 - 1万円)× 50%
ですので、5,000円となります。
CPAの改善方法
広告の費用対効果を高めるためにはCPA改善する必要があります。つまり、CPAを低く抑えるのです。
以下、CPAを改善する方法を解説します。
1.クリック当たりの広告費を下げる
CPCは「Cost Per Click」の略で、クリック当たりの広告費を表し「広告費用 ÷ クリック数」で算出できます。つまり、CPCの値が小さいほど、低い広告費で多くの反応を得られたことになり、費用対効果が高いことを示します。
広告の費用対効果を高めてCPCを下げるためには、ユーザーの注意や興味を引くクリエイティブ(広告用に作成した成果物)になっているかどうか、あるいはターゲットに届いているのかどうかを見直す必要があります。
また、一度効果があったからといって同じクリエイティブを使用し続けると新鮮さが失われてくるため、CPCが高まってしまう可能性もあります。クリエイティブは定期的に新しくすることが望ましいでしょう。
特にリスティング広告では「品質スコア」を上げることでGoogle広告における評価が上がり、表示順位によい効果があります。品質スコアを上げるためには、キーワードと広告の関連性を見直したり、移動先のランディングページの利便性(見やすさや読み込み速度など)を見直したりする必要があります。
さらに、広告の掲載順位を決める要素である入札単価の上限を低く設定することでも広告コストが下がり、CPCを下げる可能性があります。ただし、この方法では同時に掲載順位と露出度が下がってしまうリスクもあるので、慎重さが必要です。
2.広告の文章を改善する
長期間広告文を変更せずに使用していると、広告文がターゲットやキーワードに合わなくなってしまい、コンバージョンを減らしてしまうことがあります。ターゲットを取り巻く環境などが変化することで、ターゲットが興味をもつ対象も変化し、競合の増加と競合の戦略の変化によりキーワードの重要性が変化するためです。それを防ぐためにも、広告文は定期的に見直す必要があります。
3.キーワードを変更する
広告がクリックされても成約につながっていない場合は、商材を購入する動機をもつユーザーが求めているキーワードと関連性が薄いキーワードを設定している可能性がありますので、見直しが必要です。
その場合は、関連性の薄いキーワードを除外設定することも検討してみます。無駄にクリックされることを防ぐことで、広告費の無駄を削減できる可能性があります。
一方、クリック自体が少ない場合は、適切なキーワードが設定されていない可能性があります。キーワードを新たに選定し直すことも検討すべきです。
4.ターゲットを再確認する
広告文やキーワードを見直した結果、クリックはされるようになったが成約には至らない、という場合は、そもそものターゲットの選定に問題がなかったかを見直します。
つまり、実際にクリックしているユーザーが想定していたターゲットと異なっていたり、あるいは想定していたターゲットのニーズと商材が応えられるニーズが適合していなかったりする可能性もあります。その場合は、たとえクリックされるような広告文やキーワードが選定されていても、肝心の商材の特性がターゲットに響いていない可能性があります。
5.移動先の再確認
広告がクリックされているにもかかわらず成約率が上がらない場合は、クリックした移動先が適切かどうかを見直す必要もあります。
たとえば、ダイエットサプリの広告に興味をもってクリックしたのに、健康食品全般を扱うECサイトのトップページに誘導されても、ユーザーは困惑したり面倒に思ったりして離脱してしまう可能性があります。
6.LPの改善
LP(Landing Page:ランディングページ)とは、広告をクリックした直後にユーザーが閲覧するWebページを示します。つまり、ユーザーが着地する(landing)ページを示します。
LPには通常、広告で紹介した商品の説明ページや会員登録を促すページ、あるいは資料を請求するページなどが作成されます。
このとき、LPが広告に興味をもったユーザーにとって違和感がなく、コンバージョンに結びつく内容になっているかを見直す必要があります。
広告運用ツールでCPA改善
インターネットでの広告には、Web検索サイトやSNSなどさまざまな媒体があり、これらの媒体への広告出稿や分析などの運用を手作業で行っていたのでは効率が悪くなります。
そこで、これらの運用管理や分析を自動化することで、広告担当者の労力を削減し、運用コストを抑えるために、広告運用ツールを活用することが考えられます。
広告運用ツールの比較検討を行うためにも、ITreviewの「広告運用の比較・ランキング・おすすめ製品一覧」をぜひ、参考にしてください。
CPAに類似の指標の比較
広告を運営するに当たって、CPA以外にも覚えておきたい類似の指標がありますので紹介します。
| CPO | 広告費 ÷ 受注件数 |
| CPR | 広告費 ÷ 登録や申し込み件数 |
| CPC | 広告費 ÷ 獲得したクリック数 |
| ROAS | 売上 ÷ 広告費 × 100 |
| CTR | クリック数 ÷ インプレッション数 × 100 |
| CVR | コンバージョン数 ÷ サイトへのアクセス数(訪問数) × 100 |
CPO
CPOは「Cost Per Order」の略でOrderは注文の意味ですから、1件の受注を得るためにかかるコストを表します。計算式は次のとおりです。
CPO = 広告費 ÷ 受注件数
たとえば、20万円の広告費をかけて5件の受注をすればCPOは4万円です。
CPAがコンバージョンあたりの広告費であったのに対し、CPOは受注当たりの広告費となります。コンバージョンには問い合わせや資料請求などを設定することもできますが、受注を設定した場合はCPAとCPOは同じになります。
CPR
CPRは「Cost Per Response」の略で、Responseとは無料の登録や申し込みなどの反応を示します。つまり1件の登録や申し込みを得るためにかかるコストを表します。計算式は次のとおりです。
CPR = 広告費 ÷ 登録や申し込み件数
たとえば、10万円の広告費をかけて4件の無料サンプルの申し込みを獲得できた場合のCPRは2万5,000円となります。コンバージョンに無料登録や無料サンプル申し込み数を設定した場合は、CPAとCPRは等しくなります。
CPC
CPCは「Cost Per Click」の略で、ユーザーからのクリックを1回得るためにかかる費用を表します。計算式は次のとおりです。
CPC = 広告費 ÷ 獲得したクリック数
たとえば、30万円の広告費を費やして獲得したクリックが2,000回だったとき、CPCは150となります。これは、1回のクリックを獲得するために150円の広告費を費やしたことを表します。
注意しなければならないのは、クリックしたユーザーが必ずしも商品やサービスを購入したり無料サンプルの申し込みをしたりするわけではないため、CPCが下がったからといって、広告の効果が高かったとは評価できないことです。
ROAS
ROASは「Return On Advertising Spend」の略で、広告費の回収率を表します。計算式は次のとおりです。
ROAS = 売上 ÷ 広告費 × 100
たとえば、60万円の広告費をかけて120万円の売上があったとき、ROASは200%となります。つまり、広告費に費やした金額の2倍の売上があったことを示します。
ROASは、総合的な広告の効果を示す指標といえます。
CTR
CTRは「Click Through Rate」の略で、インプレッション数(ユーザーに広告が表示された回数)に対して、クリックされた回数の割合を表します。CTRの計算式は次のとおりです。
CTR = クリック数 ÷ インプレッション数 × 100
たとえば、広告が1万回表示された内、クリックされた回数が200回の場合は、CTRは2%となります。また、商品の購入ページやイベントの申し込みページのURLを記載したメールを2万件配信したときに、URLをクリックしたユーザーが500人いた場合、CTRは2.5%となります。
CVR
CVRは「Conversion Rate」の略で、顧客転換率と呼ばれます。Webサイトへのアクセスの内、登録や申し込みなどのコンバージョンが発生した割合を示します。計算式は次のとおりです。
CVR = コンバージョン数 ÷ サイトへのアクセス数(訪問数)× 100
たとえば、無料サンプルの申し込みサイトへのアクセス数が2万だったときに、実際に申し込まれた数が500件の場合、CVRは2.5%となります。
CPAを下げる際の注意点
CPAの低さだけに注目してしまうと、広告効果を正しく把握できない場合があります。
近年、カスタマージャーニーが複雑になってきています。カスタマージャーニーとは、ユーザーが商品やサービスを認知することから検討、そして購入へ至るまでの顧客体験を示します。
たとえば、自社の製品を購入した顧客は、検索で見つけたリスティング広告をクリックしたことで自社オウンドメディアを閲覧することになり、その結果表示されるようになったリターゲティング広告をクリックしてたどり着いたLPから商品を購入したかもしれません。
しかし、ここでCPAを算出すると、LPに対するコスト評価しかできません。実際には、リスティング広告が決め手だったのかもしれませんし、オウンドメディアで醸成された信頼感が購入に踏み切らせたかもしれないのです。
このようにCPAというのは、直前の広告の効果しか測れないことを理解しておく必要があります。
まとめ
CPAは広告を運営するうえで費用対効果を把握するためには重要な指標です。しかしCPAを下げることだけに固執すると、コンバージョンと売上を下げてしまう可能性もあります。
広告を評価する際には、CPOやCPR 、CPC、ROAS、CTR、CVRなどの指標にも注意を払いつつ、さらにカスタマージャーニーも考慮したうえで、複合的な検証を行う必要があります。
投稿 CPA(顧客獲得単価)とは?計算方法から改善のアイデアまで解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 採用管理とは?採用業務の課題を解消する採用管理システムのメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>今さら聞けない採用管理の基本
まずは採用管理の概要について押さえておきましょう。定義や目的など、採用管理に関する基本的な情報について説明します。
採用管理とは?
採用管理とは、企業が外部から人材を雇用するための施策および計画のことです。また、内定後の人員配置や部署間の異動など、バランス調整も採用管理に含まれます。新しい人材を積極的に採り入れ、企業の力を維持していくためには重要な取り組みです。
採用活動を行う目的
採用活動の代表的な目的として「不足している人材の確保」と「新しい人材の追加による企業の活性化・ステップアップ」の2点が挙げられるでしょう。
事業規模の拡大や新事業の開拓などにより、企業の人材が不足してくるケースがあります。近年は労働人口の減少により、新しい人材の獲得が難しくなってきているのが現状です。ITなど特定の業界ではすでに深刻な人材不足が起きており、人材の確保を急いでいる企業は少なくありません。
加えて、国内外の市場で生き残っていくために、企業の活性化・ステップアップを余儀なくされています。これらを実現するための優秀な人材の獲得は、企業にとって急務になっており、多くの業界で人材獲得の競争が激化しています。
採用管理はこれらの目的を踏まえ、効率的で安定した採用活動を行うための取り組みといえます。
採用活動の具体的なステップ
採用活動を無計画に進めると無駄な時間やコストがかかってしまいます。事業計画から逆算して、順序立てて計画していくことが大切です。以下では、採用活動の具体的なステップをご紹介します。
1.採用計画の立案
まず、採用計画を明確にする必要があります。採用計画において決めるべきポイントは、大きく分けて「採用人数」「雇用形態」「採用のタイミング」の3つです。
採用人数については、予算や業務量から算出するのが一般的です。予定している事業の戦略から、概算で必要な人数を割り出すこともあります。
雇用形態として選ばれることが多いのは自社雇用です。ほかに、派遣社員の雇用やアウトソーシングなどを選択肢として加えておくと、計画の幅が広がります。
採用のタイミングについては特に慎重な判断が必要です。新しい人材は企業に参加した直後から力を発揮できるわけではありません。その人材に活躍してほしい時期から逆算して採用のタイミングを決める必要があります。
2.採用戦略の策定
続いて、自社に必要な人材を獲得するための採用戦略を検討します。
まずは必要な人材をイメージし、その人材に対して自社をどのようにアピールできるのか検討しましょう。単に新しい人材に望む知識やスキルをイメージするだけでは十分でありません。悩みやキャリアプランを仮定するなど、具体的な「ペルソナ」まで定義することが大切です。緻密な採用戦略を策定しておくことで、その後の施策に一貫性が生まれます。
3.採用手法の選定
採用戦略で定義したペルソナに対し、どの媒体でどのようにアプローチしていくのか検討します。以下のような手法が代表的です。
- 求人サイト
- エージェント
- スカウト
- リファラル採用
- SNS採用
それぞれに強みがあり、かかるコストも異なります。ペルソナがどんな媒体を利用しているのか検討したうえで、リーチしやすい手法を選びましょう。また、複数の施策を組み合わせることも一般的です。
4.募集活動の開始
採用手法を決めたあとは、募集活動に着手します。各媒体の利用手続きのほか、掲載する募集要項・スカウトのテキスト作成を行います。
募集要項は、「必要事項」と「歓迎事項」を分けて記載するのが一般的です。「求めている人材」の解像度が高いほど、求職者にとっては自分に合った求人案件なのか判断しやすくなります。企業の理念についても、あらかじめ求職者と共有しておくことが重要です。
企業側から能動的に転職を検討している人にアプローチする「スカウト」は、近年ではスタンダードな採用手法になりつつあります。テンプレートを使うと多くの人材にアプローチできるため効率的ですが、本当に欲しい人材に対しては個別に書いたテキストのほうが効果的でしょう。
5.選考
一定の応募が集まった段階で選考・面接を開始します。面接時は、必要条件・歓迎条件を踏まえて、評価基準を明確に設定しておきましょう。担当する面接官によって採用基準が異なるケースが生じるためです。
また、スカウトや紹介の場合は選考をスキップして面談に進んでもらうなど、柔軟に対応することも大切です。
6.内定・入社フォローの実施
内定を出したからといって、その人材を獲得できるとは限りません。入社までは、内定者の不安や疑問の解消に努める必要があります。こうしたフォローが不十分だったために辞退されるケースは少なくありません。入社後のミスマッチを防ぐためにも、内定者が求めている情報は隠さず正確に伝えましょう。
採用管理には、入社した人材がスムーズに活躍できる仕組みづくりも含まれます。社内SNSへの参加案内、マネージャーとの1on1ミーティングの実施といった取り組みで、新入社員が組織になじめるように誘導しましょう。
企業が直面している採用業務の課題
採用は企業にとって欠かせないタスクです。しかし、多くの企業が以下のような採用業務の課題に直面しています。
採用状況の把握が難しい
一度に大人数を採用する新卒採用は、複数人の人事スタッフで取り組むのが一般的です。業務的にも非常に忙しいため、情報共有が困難になります。内定者の数が把握できない、それぞれの応募者がどの採用ステップまで進んでいるのかわからない、といった問題が起こりやすくなります。
対応ミスで信用を落としてしまう
多くの応募者に対応していると、連絡の遅れや情報の取り違いといった対応ミスが頻発します。契約までは、応募者も企業を吟味している段階です。対応ミスによって信用を落とせば、優秀な人材を逃してしまうことがあります。
セミナー・面接の調整に手間がかかる
セミナーや面接のスケジュール調整は採用業務の中でも特に煩雑です。人事スタッフのリソースの多くが消費されてしまいます。
求める人材と採用する人材のミスマッチが起こる
採用戦略が十分に検討されていない場合、求める人材と採用する人材のミスマッチが起こりがちです。採用した人材も企業に不安や違和感を抱くため、離職者が増えてしまいます。
求人ページの情報が不足し求職者に訴求できない
募集要項のテキスト作成スキルや作成経験がないことから、十分な情報を提供できないケースがあります。「お気軽にお問い合わせください」という記載だけでは、企業や仕事のアピールにはなりません
採用管理システムの導入で採用の課題解決
上述した課題を解決するため、多くの企業では「採用管理システム」が導入されています。以下では、採用管理システムの概要や代表的な機能を紹介します。
採用管理システムとは?
採用管理システムとは、採用業務を効率的に処理するためのシステムのことです。求職者への情報発信、採用スケジュールの管理、応募者情報の管理などをシステム上で処理できます。特に大規模求人を出している場合や複数の媒体を利用している場合に力を発揮するツールです。
採用管理システムの機能
採用管理システムの主な機能を紹介します。
応募者情報管理
各媒体から送られる応募者の情報を一元管理できる機能です。履歴書に記載される基本情報のほか、採用の進捗などを管理できます。
採用タスク管理
採用活動において処理すべきタスクを管理する機能です。書類選考、面接、最終選考といったタスクを配置することで、それらの抜け落ちを防ぐことができます。
採用スケジュール管理
面接、セミナー開催などのスケジュールを管理する機能です。空いている日時が可視化されるため、応募者を交えたスケジュール調整が容易になります。
採用状況分析
媒体や施策ごとの採用状況を分析する機能です。採用しやすい媒体やかかるコストに対する予想応募数・採用数などがわかるため、媒体の選定などに役立ちます。
採用ページ作成
自社の採用ページを作成する機能です。多くの採用管理システムではテンプレートが用意されており、簡単に自社のイメージに合ったデザインの採用ページを作成できます。
採用管理システム導入のメリット・デメリット
採用管理システムの導入には以下のようなメリット・デメリットがあります。双方を理解したうえで導入することが肝要です。
採用管理システム導入のメリット
1.採用業務の効率化につながる
情報が1つのシステムにまとめられることにより、採用業務が効率化します。限られた採用担当者のみが情報を管理している場合、フローを進めるたびにその担当者に確認をとらねばならず、非効率です。採用管理システムを使えば、複数人がアクセスできるため情報共有が容易になります。
2.より効果的な採用戦略を策定できる
採用管理システム上で過去に実施した採用活動の内容や結果を記録しておくことができます。施策による応募数の増減、面接以降の辞退率といったデータを分析することが可能です。こうしたデータは、次回の採用戦略の策定に役立ちます。
3.対応ミスを減らせる
多くの採用管理システムに搭載されているタスク管理機能は、細かな業務の抜け落ち防止に役立ちます。応募者への連絡漏れ、連絡ミスなどは自社の信用を大きく落とすことにつながるため、可能な限り防止しなければなりません。採用管理システムによっては、こうしたミスを防止するためのアラート機能が搭載されたものもあります。
4.求人サイトと連携できる
採用管理システムは一般的に求人サイトとの連携が可能です。特に複数の求人サイトを利用している場合は、各サイトからの応募情報管理が煩雑を極めます。採用管理システムには求人サイトからの応募情報が自動で反映されるため、情報把握が大幅に効率化されるでしょう。
採用管理システム導入のデメリット
1.コストがかかる
採用管理システムを導入する場合、初期費用のほかにランニングコストが発生します。月々5万~10万円程度が目安です。Excelなどの管理と比較すると大幅にコストアップしてしまう点がデメリットです。採用の規模が小さい企業では、コストに対して十分な恩恵を感じられないかもしれません。
2.自社と相性のよいシステムを探す必要がある
採用管理システムの操作感や搭載機能は製品によって異なります。自社と相性の悪いシステムを導入すると無駄にコストがかかってしまうため、導入する製品は慎重に選ばなければなりません。
3.社内で定着するまで時間がかかる
採用管理システムは人事スタッフ、面接担当者など多くの社員が利用することになります。導入によって各社員の業務が変わることになるため、事前の準備は不可欠です。情報共有やマニュアルの整備、研修、権限付与といった準備が必要になります。実際に導入したあとも、明確な効果を感じるまでは時間がかかるでしょう。
採用管理システムの活用事例
採用管理システムを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
年間で数百時間の工数削減に繋がっています
「弊社は中途採用が中心の為、導入に際してはかなり迷いがあったのですが、自動化機能による業務工数削減を最優先にてSONARを導入しました。以前はHRMOSを利用していましたが、面接日程の調整メール、確認メール、SPIの受検登録~依頼などが完全自動化し、年間で数百時間の工数削減に繋がっています。工数削減だけではなく、面接官が判定した瞬間から日程調整に進められるため、リードタイムも若干ではありますが縮めることに繋がっています。
https://www.itreview.jp/products/sonar/reviews/70880
▼sonar ATS
▼企業名:BCホールディングス株式会社 ▼従業員規模:300-1000人未満▼業種:経営コンサルティング
管理業務の時間削減に役立っている
「応募者や採用関係者が何年増えていく中で管理業務に時間を割く時間が増えてきていましたが、SONAR ATSでは候補者への連絡・面接予約などの設定や一括連絡が容易になっており、管理業務の時間削減に役立っていると感じています。結果的に、本来時間を割くべき候補者とのコミュニケーションに時間を取ることができていると感じています。
https://www.itreview.jp/products/sonar/reviews/65528
また、近年様々な採用媒体ができていますが、それらとのAPI連携を非常に積極的に実施いただいている(=SONAR ATSで一元管理できる)のも大変助かっています。今後更に連携先が増えることを期待しています」
▼利用サービス:sonar ATS
▼企業名:三井化学株式会社 ▼従業員規模:1,000人以上 ▼業種:その他の化学工業
採用業務が迅速にすすめられました
「人事部から事業部門への求人情報の共有、連絡、進捗把握が明瞭になる素晴らしいツールです。旧来はExcel、メール、チャットを組み合わせて状況把握していたものが一か所に集約され選考過程の状況が明確です。大勢の面接を同時に並行していく際に状況がよく分かるため採用業務が迅速にすすめられました」
https://www.itreview.jp/products/hrmossaiyoukanri/reviews/87212
▼利用サービス:HRMOS採用
▼企業名:株式会社ハンモック ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
採用管理システムの業界マップ
採用管理システムのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
採用管理システムの選び方のポイント
自社に合った採用管理システムを見つけるためには、以下のようなポイントを意識しましょう。
操作性
実際にシステムを操作する社員がスムーズに使えるように、直観的な操作ができる製品を選ぶのがおすすめです。また、画面の遷移スピードなどの細かなレスポンスも業務効率に影響します。ストレスなく利用できるか判断するため、無料のトライアルを活用しましょう。
導入・運用コスト
各システムのコストについても注目してください。大規模で多機能なシステムほどコストが高くなります。無駄にコストを増大させないためにも、自社の規模に合ったシステムを選ぶことが大切です。
分析機能
頻繁に採用活動を行っている場合は、分析機能が充実した採用管理システムがおすすめです。分析機能を利用して採用活動の実施と改善を繰り返すことで、優秀な人材を効率よく獲得できるようになっていきます。
外部システムとの連携
人事関連システムをすでに導入している場合は、外部システムとの連携可否について確認が必要です。連携できない場合は担当者が手作業でデータを入力する必要があり、工数が増えてしまいます。
採用管理システムおすすめ比較5選
実際に、採用管理システムを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの採用管理システムを紹介します。
(2021年12月23日時点のレビューが多い順に紹介しています)
i-web
「i-web」は、充実した機能とシンプルな操作性で、多くの企業に評価されている採用管理システムです。基本機能のほか、進行している採用活動の状況を可視化する統計機能が搭載されています。効果検証機能も優秀なため、採用活動を着実に改善していけるシステムです。
sonar ATS
「sonar ATS」は、選考状況を見える化する機能や、連絡の自動化機能が高く評価されている採用管理システムです。対応している採用手法が豊富なため、年度によって手法を変える場合もシステムを切り替える必要はありません。使った分だけ費用が発生するクラウド型のため、コスト削減効果も期待できます。
RPM
「RPM」は、年間100人以上の大規模採用を行う企業に向けて開発された採用管理システムです。350以上の求人サイトから、応募者情報を自動取得できます。オンライン面談、LINEによる応募者とのコミュニケーション、応募者自身による面接予約など、大規模採用の負担軽減につながる機能が豊富です。
HRMOS採用
「HRMOS採用」は応募者情報管理、採用業務の進捗管理、採用活動のデータ分析など基本的な機能を網羅した採用管理システムです。クラウド型のため、複数人での情報共有が容易になります。転職支援サービスを運営している株式会社ビズリーチが提供しており、人材採用関連のサポートを受けられる点も特徴です。
HERP Hire
「HERP Hire」は、Slack、Chatworkとの連携により、スピーディーな情報共有を実現するツールです。応募の通知や応募者との連絡は各コミュニケーションツール上に表示されます。「Find Job!」「SCOUTER」「YOUTRUST」など、IT企業に広く利用されている求人サービスとの連携が可能な点も強みです。
ITreviewではその他の採用管理ツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
採用管理システム(ATS)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧はこちら
まとめ
採用業務による負担を問題視している企業は少なくありません。将来的には多くの業界が人材不足に陥ることが予想されているため、採用業務を効率化し、競合よりも先に人材を獲得することは重要です。
採用管理システムの導入によって、業務負荷の改善、人材不足問題への対応の双方を実現できます。ぜひ、自社に合った採用管理システムを探してみてください。
投稿 採用管理とは?採用業務の課題を解消する採用管理システムのメリットを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 eラーニングとは?導入のメリット・デメリットから導入ポイントを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>eラーニングとは?
eラーニングとは?
eラーニングとは、オンライン上で教育するためのツールです。eラーニングは今や幅広い分野で利用されており、企業だけでなく学校などの教育現場でも利用されています。具体的には、学習者(eラーニングで学ぶ人)は教員(eラーニングで教える人)から配布される学習教材(文章や動画など)を使い、オンライン上で学ぶ流れになります。
eラーニングが生まれた背景
| 1950年代 | CAI(Computer Aided Instruction)が登場 |
| 1990年代 | CAIからCBT(Computer Based Testing)へと発展 |
| 2000年代 | eラーニングへと発展、流用されるようになる |
eラーニングの始まりは、1950年代にCAI(Computer Aided Instruction)が登場したことがきっかけです。当時のCAIは、プログラム学習として利用されていました。プログラム学習とは、学習者にプログラム化された課題や問題を出し、それを学習者が解き、採点・評価をするというものです。
そんなCAIが1990年代にはCBT(Computer Based Testing)へと発展。CBTとはパソコンやスマートフォンで出題・解答する仕組みのことで、テキストだけでなく、動画や音声などを課題に組み込むことができます。課題作成に限らず、解答結果を電子データに変換し、管理することが可能です。
そして、2000年代になるとCBTからeラーニングへと発展しました。eラーニングへ発展したきっかけはスマートフォンやタブレット端末の普及にあります。スマートフォンなどのデバイスの普及率が上がるにつれ、学習環境にも変化が生じました。多くの人がオンライン環境に気軽にアクセスできるようになったため、オンライン上で学習する機会が増加していきました。そして2000年代にeラーニングが登場します。
テレワークの普及によりeラーニングの重要性が高まる
働き方改革の実現に向け、働く場所を問わないテレワークを導入する企業が増加しています。また近年はコロナ禍の影響もあり、テレワークが急速に普及しています。ただ、テレワークは多くのメリットがある反面、コミュニケーションや教育・研修がやりにくくなるというデメリットもあります。
テレワークでは集合研修が難しいのはもちろん、何気ない日常の会話から生まれる情報共有やOJTもおろそかになりがちです。こうした課題を解決する対策として期待されているのがeラーニングです。
eラーニングは、インターネット環境とパソコンやスマートフォンなどのデバイスがあれば会社にいなくても学習できるため、教育・研修の代替手段としての期待が高まっています。時間や場所の制約がないeラーニングは、テレワーク時代と相性のよい教育・研修の手段といえるでしょう。
eラーニングを構成する2つの要素
eラーニングは「LMS(Learning Management System):学習管理システム」と「学習教材」の2つの要素で構成されています。どちらが欠けても成立しないので、両者をよく精査したうえでどのようなeラーニングを活用するか検討しましょう。
1. LMS(学習管理システム)
一般的なLMSには、受講者が学習するための学習機能だけでなく、「受講者と教材の管理」や「学習進捗の管理」といった講師や教育担当者などの運営管理者をサポートする機能があることが大きな特徴です。インターネットを利用していない時代のeラーニングでは、受講生の学習理解度の把握は困難でした。しかし、現在のeラーニングでは、学習の進捗や成績をLMSでリアルタイムに把握することが可能になりました。
また、LMSには、オンプレミス型とクラウド型の2種類のシステムがあるため、導入する際はどちらのシステムを使用するかを決めます。
オンプレミス型
オンプレミス型は教員側(eラーニングの運営側)が物理的にサーバを設置し、eラーニングの管理を行います。オンプレミス型は物理的にサーバを設置するための場所が必要になりますが、現在はクラウド型に移行しつつあります。
クラウド型
クラウド型はオンプレミス型とは違い、物理的にサーバなどを設置する必要がなく、クラウド上でeラーニングの管理を行います。クラウド型はサーバなどを用意する必要がないため、手軽に始められるというメリットがあります。
2. 学習教材
eラーニングを運用する環境が整ったら、次に必要になるのが学習教材です。たとえLMSを導入しても、学習効果のある教材がなければ意味がありません。
学習教材の準備には、以下の4つの方法があります。
学習教材を準備する4つの方法
1.既製品を購入する
学習内容が決まっているのであれば、既製のパッケージ商品を購入してもよいでしょう。市場にはプロが作った品質の高い教材がたくさんあります。
2.既製品をカスタマイズする
既製品だけでは十分でないと考えた場合、ベンダーによってはその一部を自社向けの内容にカスタマイズすることもできます。制作部門を抱えているベンダーであれば相談してみるのもよいでしょう。
3. 教材をオーダーメイドする
教材コンテンツをオリジナルで制作する方法です。教材設計やコンテンツ制作について、プロのノウハウを生かしながら自社オリジナルの教材を制作できるのは大きなメリットです。制作費はかかりますが、理想的な教材を作りたいと考えるのであればオーダーメイドが一番よいでしょう。
4. 教材を自社で制作する
「教材作成ツール」を使って教材コンテンツを自社で制作します。教材作成ツールは、通常オーサリング(テキスト・画像・音声・動画などを組み合わせてコンテンツを作成すること)を自動で行うツールで、プログラミングの知識がなくてもeラーニングの教材コンテンツを作ることができます。
学習教材にはどういった種類があるのか?
学習教材の種類には、動画配信型や資料配布型など多岐にわたります。企業では以下の5種類の学習教材がよく利用されています。
資料配布
資料配布は、集合研修で利用していたような資料をそのままデータ化し、オンライン上で使用する教材です。手軽に用意できる点がメリットといえます。必要に応じて音声やアニメーションを組み込んだうえで文章や画像を記載した資料をデータとして学習者に配布し、学習者はその資料をもとに学習します。
アニメーション
アニメーションは、オンライン上でPowerPointを使用し、学習者に配布する教材です。PowerPoint以外にもGoogleスライドなどを使用した学習教材もあるため教材を作成しやすいというメリットがあります。
動画配信
動画配信は、学習者に学習してもらいたい内容を動画で伝える教材です。動画配信は新人研修や解説などで利用される機会が多く、作成時間はかかりますが、内容の濃い教材作成が可能です。最近は動画配信が非常に増えており、eラーニングの主流となりつつあります。
ドリル
ドリルは、穴埋め形式の教材です。学校などでよく見る算数ドリルや漢字ドリルのように、重要な部分を学習させるのに適した教材になっています。必ず学習してほしい箇所などを区別できるため、学習者のモチベーション維持にもおすすめです。
LIVE配信
LIVE配信は、生放送で学習者と教員をつなげる教材です。LIVE配信であれば学習者からの質問などにその場で答えることができるため、学習スピードがもっとも高い教材といえます。ただし、リアルタイムで学習できる反面、時間に縛られるデメリットがあるため、学習時間を考慮する必要があります。
eラーニング学習の始め方
eラーニング学習を始めるにあたっては、下記の3つを重点におき運用していきます。
学習者を登録する
最初に学習してもらいたいユーザーをeラーニング内に登録します。eラーニングツールによっては登録できる学習者に限りがあるため、あらかじめ登録する学習者の人数を確認しておきます。
教材を登録する
学習してもらうユーザーの登録が終わったら、次に学習教材を登録します。学習教材は教員が作成するか外注するかを選択できますが、ユーザーにわかりやすく扱いやすい教材を作成することが大切です。特にYouTubeなど動画コンテンツに慣れた若い世代の研修用教材には、動画配信型がおすすめです。
学習スケジュールを立てる
最後に学習者側のスケジュールを設定します。1日のノルマや学習時間の目安などを決め、効率よく学習できるよう誘導する必要があります。たとえば新人研修の場合は、1日20分の学習を3~5セットにします。人間の集中できる時間は個人差がありますが、おおよそ30分前後とされているため、20分に区切り、適宜休憩を挟むことで集中力を継続させることができます。学習者が飽きずに続けられるようモチベーションを維持することがもっとも大切なので、時間・日程ともに学習者が継続していくサポートを行いましょう。
eラーニングの基本機能
eラーニングにはさまざまな機能が備わっていますが、その中から主な基本機能を紹介します。
| ユーザー(学習者)管理 | ・グループ管理機能・属性管理機能 |
| 教材プログラム作成 | ・作業手順プログラム機能・修了設定機能 |
| 研修管理 | ・申込み受付の管理・登録機能・受講後の評価・記録機能 |
| 通知管理 | ・お知らせ機能・学習者への連絡機能 |
| 問い合わせ | ・FAQ作成機能・サポート管理機能 |
ユーザー(学習者)管理
グループなどを問わず、学習者の属性(特徴)を自由な名称で登録できる機能
教材プログラム作成
・作業手順プログラム機能
PowerPointなどからe-ラーニング教材を作成できる機能
・修了設定機能
学習者が教材の最後まで学習した際に修了することができる機能
研修管理
・申込み受付の管理・登録機能
研修者や学習者の申込み受付の管理や登録ができる機能
・受講後の評価・記録機能
学習者の受講修了時に、学習内容の評価・記録を行う機能
通知管理
・お知らせ機能
学習者に通知したいお知らせを一括で通知できる機能
・学習者への連絡機能
学習者に直接連絡が取れるよう連絡先を管理・登録できる機能
問い合わせ
・FAQ作成機能
FAQ作成でよくある質問などを学習者全員が閲覧できる機能
・サポート管理機能
継続しやすいスケジュール設定のため、学習者のログインや問い合わせなどを一括で管理する機能
eラーニングのメリットとデメリット
テレワークによるオンライン学習の普及に伴い、特に教育現場ではeラーニングのメリットを肌で感じている人も多いかもしれません。しかし、その裏にはオンラインならではのデメリットもあるので注意が必要です。
※図表入る
eラーニングのメリット
1.時間に縛られない
オンライン上に登録された課題や授業を学習するため、学校などの授業とは違い、時間に縛られない学習が可能です。
2.場所に縛られない
オンライン上で学習するため、会場やオフィスなど場所の確保が必要ありません。学習者は自宅でも外出先でもどこでも自由に学習できるため、場所に縛られない学習が可能です。
3.教材の用紙代や印刷代の削減
オンライン上に学習教材を作成し、登録するだけなのでプリントアウトしたり印刷用の用紙を用意したりする必要がないので用紙代・印刷代の削減につながります。
4.交通費や移動時間の削減
場所に縛られないメリットがあるため、移動する際にかかる交通費や時間の削減ができます。移動時間を学習時間にあてることができるため、学習効率を上げることにもつながります。
5.進捗状況を一括で管理可能
オンライン上で学習・評価などを行うため、学習者の進捗状況を一括で管理することができます。従来の学習方法では学習者の進捗状況をまとめて管理することができませんでしたが、eラーニングは進捗状況を一括で管理できるため、管理側の負担を軽減することができます。
6.学習の質を均一化できる
従来の学習では、教員や講師によってその学習内容に差異がありましたが、eラーニングは学習者全員が同じ内容の教材を学習できるため、学習の質を均一化することが可能です。学習の均一化ができると、管理や進捗状況の確認も容易になります。
7.教材作成後は繰り返し使用可能
eラーニングはオンライン上に学習教材を登録すれば、その教材を繰り返し使用することが可能です。学習者が増えた際も以前登録した教材を配布するだけで新しい教材を作成する必要がありません。そのため、教材費や教材作成時間の削減につながります。
eラーニングのデメリット
1.ネット環境が必要
eラーニングはオンライン上で学習するため、ネット環境がないと学習することができません。学習者にネット環境があるかどうかの確認をしておきましょう。
2.モチベーション維持が不安定
eラーニングは時間や場所の縛りがないため、学習者の好きな時間、好きな場所で学習できる点がメリットです。しかし、学習者の自主性や主体性に委ねられやすいので、eラーニングを導入する際は学習者のモチベーション維持も考慮する必要があります。
3.教材作成にコストや時間がかかる
eラーニングは学習者に学ばせたい内容を教員が学習教材として作成しなければならないため、コストや時間がかかってしまいます。教材を業者に依頼し作成してもらうことで時間を削減することも可能ですが、そのコストが増えてしまいます。
eラーニングツールの活用事例
eラーニングを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
※各活用事例の小見出し以外のレビュー本文~業種情報まで引用の設定でお願いします。
教育・育成のゴールがぶれずに進められる
「弊社では社内の営業パーソンの育成はもちろんのこと、社外のお客様の研修実施にも活用させていただいております。その際、習熟度を可視化し見える化することで、受講者自身の振り返りはもちろんですが、フィードバック者も結果を元にしたアドバイスが可能になります。またお互いのゴールを明確化した上で研修を進めることができるため、教育・育成のゴールがぶれずに進められる点がメリットと考えています」
https://www.itreview.jp/products/umu/reviews/75506
▼利用サービス:UMU
▼企業名:株式会社営業ハック ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:経営企画
トレーナーの作業効率が格段に改善
「マニュアルの作成手順が非常に明確で分かり易いです。マニュアルに使用する画像の編集も機能が充実しており、重要なポイントをより伝えやすく加工することが可能です。属人的な業務の標準化、店舗ごとにやり方の違った業務の平準化が進んでいます。また新入社員のトレーニングの第一歩としてTeachmeBizのマニュアルを読み込んでもらうことで、トレーナーの作業効率が格段に改善しています」
https://www.itreview.jp/products/teachme-biz/reviews/67619
▼利用サービス:Teachme Biz
▼企業名:株式会社共和コーポレーション ▼従業員規模:300ー1000人未満 ▼業種:経営企画
イメージ通りのマニュアルが完成
「ビジュアル化された業務マニュアルを誰でも簡単に作成することができるので、得意な人や専門の人に依頼するよりもイメージ通りのマニュアルが完成します。また、編集も簡単なので、仕様の変更があった際もスピーディーに対応できます」
https://www.itreview.jp/products/teachme-biz/reviews/41022
▼利用サービス:Teachme Biz
▼企業名:株式会社ソウルウェア ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
eラーニングの業界マップ
eラーニングのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
※eラーニングのITreview Gridを追加
eラーニングを選ぶ際のポイント
eラーニングを選ぶ際に失敗しないためのポイントを紹介します。
※図表入る
1.提供形態で選ぶ
eラーニングはオンプレミス型かクラウド型のどちらの形態を導入したいかで選びましょう。オンプレミス型はサーバの設置が必要ですが、故障やトラブルの原因が見つかりやすい特徴があります。クラウド型はトラブルの原因を特定するのに時間がかかりますが、サーバの設置は不要というメリットがあります。自社の環境に合う型で選びましょう。
2.自社リソースを考慮した操作性で選ぶ
自社で扱えるツールか、そのツールで求める利益が本当に発生するかを判断して選びましょう。導入する予定のツールは自社にどのようなリソースを与えるか、またそのツールを自社で扱うことは可能かどうかを考慮することも大切です。
3.価格で選ぶ
自社にとって妥当なコストかどうかで選びましょう。eラーニングは提供形態や扱う教材によって価格が変動します。そのため、自社に必要な型と教材を決め、妥当なコストかどうかを考慮してから選びましょう。
4.教材コンテンツで選ぶ
自社でオリジナル教材を作成する
学習者に学ばせる教材を自社でオリジナル教材として作成するかどうかで選びましょう。オリジナル教材を作成する場合は、教材にもよりますが作成に時間がかかってしまいます。早い段階でeラーニングを取り入れたい場合は、提供されている教材も便利です。
提供されている教材を使用する
eラーニングツール内の提供されている教材を使用するかどうかで選びましょう。あらかじめ提供されている教材を使用する場合は、円滑に学習を開始することができるため、求める教材がツール内にある場合は提供されている教材も活用しましょう。
教材を外注する
自社が求める教材を外注する場合は、時間と費用がかかってしまいます。しかし、質の高い教材を作成することができるため、質の高い教材を求める場合は教材を外注してみるのもよいでしょう。
5.セキュリティおよびバックアップ体制で選ぶ
機密情報などを扱う場合、セキュリティが万全かどうかで選びましょう。eラーニングのツールによってセキュリティおよびバックアップ体制が異なるため、それらの機能が充実しているeラーニングツールを選ぶと、トラブルが発生した際にも迅速に対応できます。
6.対応デバイスで選ぶ
学習者が扱うデバイスに対応しているかどうかで選びましょう。学習者が使用しているデバイスとeラーニングツールで対応しているデバイスが違えば、学習者はeラーニングツールを使用することができません。そのため、学習者とeラーニングツールが対応しているデバイスで選びましょう。
eラーニングツールおすすめ4選
実際に、eラーニングツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのeラーニングツールを紹介します。
(2022年1月5日時点のレビューが多い順に紹介しています)
Teachme Biz
「Teachme Biz」は、マニュアルの作成や共有、運用などマニュアル作成機能が充実しており、サポート体制も整っています。ほかにもセキュリティ機能やトレーニング機能といった知識定着率を上げる機能があります。5万円からeラーニングの導入が可能です。
UMU
「UMU」は、学習者によるアウトプット重視のインタラクティブな学習教材です。動画配信型や資料配布型など、多くの学習教材から選択することが可能です。無料で使用できるeラーニング教材もあり、初めての方におすすめできるツールとなっています。
学び~と
「学び~と」は、セキュリティ機能を重視したeラーニングツールです。24時間365日の監視やIPS(不正侵入防止システム)による不正侵入防御などがあり、安全性に長けています。無料トライアルでeラーニングを利用することが可能です。
CAREESHIP
「CAREERSHIP」は、学習に関する機能はもちろん、従業員のスキルを可視化するなどタレントマネジメントに活用できる機能も備えた統合型LMSです。多機能でありながら柔軟性の高いシステムが評価され、日本有数の大企業に、社内教育のプラットフォームとして採用されています。
ITreviewではその他のeラーニングツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
eラーニング・LMSの比較・ランキング・おすすめ製品一覧はこちら
まとめ
自社の戦力となる優秀な人材を輩出していくためには、eラーニングを上手に活用して、効果的な学習体制を構築しなければなりません。現在、eラーニングには大規模運用が可能なものから、専門分野に特化したものまでさまざまなLMSがあります。
効果的な学習を可能にするeラーニングは、人材育成の課題を解決する大きな手段となります。eラーニングの導入に必要なLMSと学習教材を把握するとともに、学習の目標・目的を明確にすることが、よりよい教材コンテンツを見つけるカギとなるでしょう。
投稿 eラーニングとは?導入のメリット・デメリットから導入ポイントを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 日報とは?作成のポイントから社内共有におすすめ日報アプリ3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>日報を書くメリット
毎日の作業やその工程を記録した報告書のことを「日報」といい、社員の業務内容の可視化や、現場のトラブルを即座に把握するために活用されます。日報は、業務の効率化や生産性の向上を目的とし、日報を社員間で活用・共有することで社員同士のコミュニケーションや士気を高める意味合いがあります。
日々の課題や改善すべきポイントを把握しやすい日報は、社員1人ひとりの成長にもつながります。また社員間のコミュニケーションを円滑にさせることにも寄与します。
日報作成のポイント
日報の作成方法には気をつけるべきポイントが2点あります。
1.テンプレートを作成
日報の作り方は、まずテンプレートを作成し、目標や結果・課題や改善点などを組み立て、自社に必要であるとされる内容をどんどんリストアップしていきます。そのあとはカテゴリーごとに項目を当てはめていくことで、短時間に多くの業務を進めることができます。
2.シンプルかつ正確に
すべての項目において、あまり長すぎる文章は求めないことが大切です。日報を書くために本来の業務時間を削ることは、企業にとって決して望ましいことではないからです。そのため、シンプルかつ正確に記入を行うことのできるテンプレートであることも重要です。
日報を共有する方法
日報を共有するためには、以下の3つの方法があります。メールやチャット・グループウェアは従来の共有法として利用されてきましたが、現在では多くの企業が日報アプリにシフトしています。
1.メール ・チャットツール
これまで使用されていた日報の共有方法の1つです。メールやチャットツールは気軽に使えるというメリットがありますが、日報としての利便性はあまり高くはありません。
2.グループウェア
グループウェアを使用して日報を共有するのも1つの手段です。しかしコストがかかるという側面もあるため、導入目的を明確にする必要があります。
3.日報アプリ
近年、多くの企業で活用されている日報アプリは、複数の社員に日報の共有を行うことが容易なため導入が進んでいます。また誰にでも比較的扱いやすく、費用もリーズナブルなアプリが数多くリリースされており、非常に需要の高いツールとなっています。
日報アプリとは?
日報アプリとは、パソコンやスマートフォンから日報を作成したり、社員間で共有を行ったりすることのできる管理アプリのことをいいます。日報アプリには、以下の3つの方式があります。
日報特化方式
日報の作成や提出などに特化したアプリ。日報がメインのシンプルな構造のため、初めて利用する人であってもわかりやすいのが特長です。
データベース方式
自動入力を活用することにより、データの集計を行うことができるデータベース型の日報アプリ。データ集計を目的とする企業におすすめです。
コミュニケーション方式
社員間のコミュニケーションに特化しており、社内での意見交換や情報共有を目的とする企業に相応しい日報アプリ。
日報アプリの基本機能
日報アプリには、数多くの機能が搭載されています。従来であれば社員の負荷となっていた業務も日報アプリの導入・活用により軽減され、人件費の削減や業務効率の促進を達成できます。
日報作成機能
テンプレートから日報を自由に作成できます。
日報提出機能
パソコンやスマートフォン・タブレットなどの各端末から日報を提出できます。提出に関するリマインド機能も搭載されています。
検索機能
過去の日報を検索することで探し出します。検索方法は、日付や社員の名前・顧客といった条件から行います。
データ集計機能
売上や業務時間・訪問件数などの各データを日報から収集し、項目ごとにデータを集計します。また、労働時間の自動集計も行うことができます。
コミュニケーション機能
日報にコメントを入力できたり、リアクションを残したりすることができ、チャットや社内SNSを活用することも可能です。
業務サポート機能
タイムカードの勤怠報告やタスク管理・工数管理、目標達成における管理が行えます。
管理者用機能
日報の閲覧権限を管理し、日報を一度にダウンロードできます。
連携機能
Googleカレンダーなどの外部カレンダーアプリとの連携が可能です。
日報アプリ導入のメリット・デメリット
日報アプリを導入することには、多くのメリットがあります。デメリットも併せて紹介します。
日報アプリ導入のメリット
1.人件費の削減
これまで人が自ら行っていた作業が自動に変わることにより、人的負担、すなわち人件費の削減に大きく貢献します。
2.コストの削減
これまでの書面型での管理では、紙代や印刷代などの細かな費用が負担となっていました。日報アプリを利用すると、それらの費用を大幅に削減できます。
3.業務の効率化
日報アプリの利用による人件費やコストの削減は、社員がほかの業務に集中できるということでもあり、作業の効率化を大きく促進することへつながります。
4.情報の一元化
日報アプリ内にあるキーワード検索により、自社の求める情報を簡単に見つけられます。また検索情報は蓄積されていくため、情報の一元化にも役立ちます。
5.円滑なコミュニケーション
多くの日報アプリには、社員間で活用できるコミュニケーション機能があります。社内での質問やフィードバックに寄与することにより、業務がさらにスムーズになるでしょう。
6.時間と場所問わず作成可能
パソコンやスマートフォンなどがあるだけで、どこにいても普段どおりのフォーマットで作成することができます。
日報アプリ導入のデメリット
1.慣れるまで時間がかかることも
日報アプリを扱う社員によっては、使いこなすまでにある程度時間がかかることもあります。しかし、アプリ自体がやさしい構造のため、講習やトレーニングが必要というほどではないでしょう。
日報アプリの活用事例
日報アプリを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
パソコンで日報を書く時代は既に終わった
「このサービスの優れたポイントはスマホから日々アクセスしながら、帰宅時など、片手間でレポートが作成出来、更にKPIを設定しつつ、その日々の活動が積み重なることで、ターゲットが達成可能な仕組みが構築出来てしまう事です。ビジネスという観点では、社員の生産性が向上したのではと思っています。PCで日報を書く時代は既に終わっていて、スマホで気軽に記述提出し、その上でKPIにも貢献できる一石二鳥のツールを使うことで、帰宅時間が早くなる、効率的に業務がこなせるなど、メリットは大きいと感じております」
▼利用サービス:gamba!
▼企業名:ペガジャパン株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:ソフトウェア・SI
https://www.itreview.jp/products/gamba/reviews/48585
社内コミュニケーションが活性化
「ユーザーはスマホから日報を送信することができるので、通勤時間を有効活用して日報報告することが可能な点。日報のテンプレートを登録することができるため、必要な部分だけ編集しながらすばやく報告できる点。報告された日報に対してコメントなどコミュニケーションを取ることができる点です。毎日実施報告を求める際、紙ベースで報告していたが、オンライン化することで、すばやく情報を確認できたり、過去のデータを見つけやすくなり、日報の確実な運用が実現しました」
https://www.itreview.jp/products/gamba/reviews/19174
▼利用サービス:gamba!
▼企業名:エクセルブートキャンプ ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
日報アプリ導入のポイント
新しい製品の導入や比較には、どの企業も頭を悩ませてしまうものです。日報アプリを導入する前に、以下のポイントを押さえるとスムーズに選定しやすくなります。
シンプルな構造であるか
誰にでも扱いやすい日報アプリであることはとても大切です。できる限りシンプルで容易に操作可能な構造の製品を選ぶと、導入後に後悔することもないでしょう。
権限管理は快適か
公開範囲をごく一部にとどめておきたい場合には、自由度の高い権限管理を備えている日報アプリを選定する必要があります。
セキュリティ対策は万全か
重要データなどがきちんと暗号化されているかどうかや、アクセスログ取得の有無などのチェックを行い、高セキュリティで安心できる日報アプリを選びましょう。
端末問わず操作可能か
リモートワークの普及により、自社が新たに端末を揃える可能性もあります。そのような状況にも対応できるよう、幅広い端末に対応可能であるかどうか確認を行います。
おすすめ日報アプリ
日報アプリを実際に活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの日報アプリを紹介します。
(2022年1月7日時点のレビューが多い順に紹介しています)
AppSuite
「AppSuite」は、メールや表計算ソフトで人的リソースにより行っていた現場作業を容易に効率化させる、カスタムメイドタイプの日報アプリです。システムの設計や構築・運用やデータ分析などをシンプルに完了できる、利便性の高い仕様となっています。
gamba !
「gamba!」は、日報をベースのアプリにコミュニケーションシステムを導入した、社内ソーシャルネットワークサービス型の日報アプリです。このアプリを活用することにより、社内のコミュニケーション不足を解消することにも大いに役立ちます。
コロコロ日報
「コロコロ日報」は、書面に記録する従来型の日報をペーパーレス化し、初心者にも扱いやすい操作性であることにこだわった日報アプリです。サイコロ型のデバイスを活用することで、通常業務に関するデータ化や可視化を実現。業務の効率化を促します。
ITreviewでは、その他の日報アプリも紹介しています。紹介ページでは、製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。
まとめ
テレワークの推進に伴って在宅勤務が増え、従業員の作業進捗やモチベーションを把握したり、コミュニケーションをとったりすることが難しくなったという弊害も出ています。テレワーク時代において、日報は従業員の業務を管理するうえで必要不可欠であるといえます。
しかし、現場では日報の作成に意義を見出せず、不満を抱くことも少なくありません。そのような側面からも日報の手間を減らし、より円滑なコミュニケーションを促進させられる日報アプリは大変有意義なツールです。
日報アプリの導入は日報作成の工数を削減できるだけでなく、業務の進捗状況が素早く行えるため業務推進にもつながります。
数ある日報アプリの中から、自社に最適な日報アプリはどの製品であるのか、さまざまな日報アプリの中から自社に合う強みやメリットをもつアプリを選定し、類似する他社製品とよく比較を行いましょう。
投稿 日報とは?作成のポイントから社内共有におすすめ日報アプリ3選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MEOとSEOの違いとは?対策のポイントからMEOツール4選を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>MEOとは?
MEOは「Map Engine Optimization」の略で、「地図エンジン最適化」と訳されています。自社や店舗の情報をGoogleマップの検索結果(ローカル検索)で、より優位に露出させるための対策を示します。また、MEOはGoogleマップ上の表示だけでなく、Google検索の結果の表示のされ方にも影響を与えます。
そのため、特にローカルなビジネスにおいては、必須の対策と考えられるようになっています。近年は外出先でスマートフォンを使って会社や店舗を検索する需要が増加しているため、MEOを重視する事業者が増加しています。
ちなみにMEOは日本独自の呼び方で、海外では同じ施策に対してLocal SEOという呼称が使われています。そのため、海外のクライアントとMEOの話をする際には、用語の使い方に注意が必要です。
MEOとSEOは何が違うのか?
| SEO | MEO | |
| 立地 | 検索場所に応じて最適な検索結果を表示するアルゴリズムが組み込まれている | Googleビジネスプロフィールに登録された位置情報が軸となり、検索結果に表示 |
| 口コミ(レビュー) | 口コミそのものが存在しない | Googleビジネスプロフィール上に投稿された口コミの件数や評価。投稿された文章の内容などが検索順位に影響を与える |
| 評価されるページ | 対象のページやホームページ全体が評価の対象 | Googleビジネスプロフィール上の情報が評価対象 |
SEOは、基本的には世界中のどの端末で検索しても同じになることを前提に対策が行われます。しかし、実際に日常的な検索では地域により異なる結果が表示されることが多くあります。
たとえば「ラーメン店」と検索すれば、検索した人の所在地が神奈川県と千葉県では異なる検索結果が表示されます。それぞれ検索者の所在地周辺で営業しているラーメン店が検索結果として表示され、各店舗の所在地を示す地図も表示されます。
これは「ローカル検索」と呼ばれる機能です。Googleが検索者にとってより実益がある検索結果を返しているのです。実際、神奈川県でラーメン店を探している人に、北海道や九州の名店を表示しても、役に立たないことが多いでしょう。
このようなローカル検索でより上位に表示されることをめざして行う施策がMEOです。そのため、MEOではSEOでは行わない、地域性に関わる対策が必要になります。
なぜ、MEOを重視するのか?
実店舗や地域に根ざした事業を行っている事業者にとっては、商圏外の検索者に知られることよりも商圏内の検索者に知られることのほうがビジネスに有利です。そのため、商圏内の検索者が検索した結果としてGoogleマップと共に店や事業所の情報が表示されることは、マーケティング上有益です。
場合によっては、ローカル検索で初めてその店舗や事業所の存在に気づく検索者も多いと考えられます。このことは、潜在顧客へアプローチできることを示します。また、ローカル検索は、SEOと比較して地域性が加味される分、検索結果の競合が少ないことも有利に働きます。
特に近年では、パソコンよりもスマートフォンで検索する利用者が増加しているため、MEOの重要性はさらに増してきています。また、SEOはGoogle側のアップデートにより検索順位が変動する可能性が大きいですが、MEOではSEOほどの大きな変動が起きる可能性は今のところ低いと考えられます。
MEO対策のポイント
MEO対策の大きな方針は、Googleビジネスプロフィール内「Google のローカル検索結果のランキングを改善する方法」で紹介されていますが、ビジネスプロフィール情報の拡充と更新性になります。ここでは、MEO対策のポイントを紹介します。
未登録であることを確認する
まず、登録したい店舗名や法人名をGoogleマップで検索します。下図のように店舗名や法人名で表示されていれば、すでに登録されていることになります。Googleマップでまだ確認できない場合は、Googleビジネスプロフィールの登録を行います。
Googleビジネスプロフィールを登録する
MEOはGoogleビジネスプロフィールを登録することから始まります。Googleビジネスプロフィールは無料のツールで、Googleでの検索やGoogleマップでの検索時に、自店舗や自社の情報を表示させるために必要です。
情報は正確に登録してください。特に名称、住所、電話番号は正確に登録します。名称や住所の表記が自社のWebサイト上の表記やポータルサイト上の表記などとブレがないように統一します。
GoogleビジネスプロフィールはGoogleマップの検索フィールドに店舗の住所を入力し、左側のメニューをクリックして表示されるメニューから「自身のビジネス情報を追加」をクリックし、質問に答えていくことで登録されます。
MEO用のキーワードを決める
MEO用のキーワードを決めます。キーワードは、近くのユーザーがどのようなキーワードを使ったときに店舗や事業所が表示されてほしいかを考えます。
Googleビジネスプロフィールを充実させる
Googleビジネスプロフィールを登録したら、情報を充実させます。情報を充実させることでキーワードとの関連性も高めます。また、情報が充実しているほど、Googleの評価も高くなります。
業種のポータルサイトに登録する
MEOはGoogleビジネスプロフィールへの登録で終わりではありません。外部のポータルサイトに掲載することもMEOとして効果があります。その際、店舗名や住所などは、Googleビジネスプロフィールと統一するようにします。
自社のサイトを立ち上げる
MEOとして、自店舗や自社のWebサイトも立ち上げます。Googleビジネスプロフィール以外のサイトに同じ情報が掲載されていることで、MEOの評価が高くなります。また、自店舗や自社サイトが立ち上げてあれば、より詳しい情報を求めているユーザーからの信頼性が高まります。
投稿する
Googleビジネスプロフィールの投稿機能を使って、テキストや写真を積極的に投稿することがMEOとして評価されます。
口コミの投稿を増やす
口コミの投稿を増やすことは、Googleからユーザーの支持を得ていると評価され、表示順位に影響を与えます。また、ほかのユーザーにとっても重要な情報となります。それを見たユーザーの行動を促すことになります。
よい口コミを増やすためには、ユーザーに評価される質の高い商品・サービスを提供することがもっとも基本的なことです。この基本を押さえたうえで口コミを促さなければ、かえって悪い評価を書き込まれてしまうリスクが高くなります。なお、ユーザーの好意による口コミをお願いすることは問題ありませんが、なんらかのインセンティブを付与して口コミを集めることは禁止されていますので注意してください。
順位をチェックする
MEOを実施したあとは、定期的に表示順位を確認します。順位を上げるための施策を行ったあとで順位が下がっていれば、その施策は効果がなかったことになるので中止すべきですし、順位が上昇していれば、その施策は有効だったことになるので継続的に実施する必要があるとわかります。
MEO対策を行うメリットとデメリット
MEOを実施する際のメリットとデメリットを紹介します。
MEO対策を行うメリット
1.店舗に来られる距離にいるユーザーに訴求できる
店舗の近くにいるユーザーの検索結果に自店舗が表示されることは、今すぐ来店する顧客の獲得につながりやすくなります。この効果をSEOでめざすことは非常に難易度が高くなります。また、リスティング広告で同じ効果を得ようとすると、高い費用がかかります。
2.ローカル検索の結果で上位に表示されやすくなる
MEOを行うと、Googleマップに登録されている店舗や事業所の検索順位を上げるだけでなく、「地域+業種」などのローカル検索が行われた際にも順位が上がりやすくなります。
3.SEOより短期間で上位表示される可能性がある
SEOで検索結果の上位表示を狙った場合、サイトの内部構造に手を入れたりコンテンツを充実させたりするなどのコストや手間がかかり、表示順位に反映されるまでに半年から1年ほどかかります。しかし、MEOの場合は低コストで手間もかからず、早い場合は1週間ほどで表示順位に反映されます。
4.外出中のユーザーに訴求できる可能性がある
日本では情報を検索する際、デスクトップパソコンよりもスマートフォンなどのモバイル端末による割合が圧倒的に多くなっています。ドイツのSISTRIX社が2021年3月に公開した調査結果(※)によると、日本で検索が行われているデバイスはデスクトップパソコンが24.9%でモバイル端末が75.1%です。米国やフランス、ドイツ、スペイン、イギリスでのモバイル端末の割合はそれぞれ64.9%、62.1%、64.1%、65.1%、66.4%といずれも6割台でした。つまり、日本においては外出先での検索のニーズが大きいため、MEOの重要性がより大きいといえます。
出典:『The proportion of mobile searches is more than you think – What you need to know – SISTRIX』
出典(※):『The proportion of mobile searches is more than you think – What you need to know – SISTRIX』
5.検索意図とマッチしやすい
たとえば「新宿+フランス料理」と検索するユーザーは、検索結果を参考にして実際に行動する可能性が高いといえます。そのため、ローカル検索としてのMEOの実施は、「地域+業界」という検索ニーズにマッチしやすいと考えられます。
6.無料で始められる
MEOは専門的なスキルがなくても始められます。また、Googleビジネスプロフィールへの登録は無料で、テキストや画像の投稿、口コミへの返信も無料です。
7.SEOよりまだ競合が少ない
今や多くの企業がSEOに取り組んでいます。そのため多くの競合と検索順位を争うことになります。一方、MEOはまだ取り組んでいる店舗や企業が少ないため、実施した分だけ効果を出しやすいといえます。また、全国規模で検索順位を競うのではなく、ローカル検索で優位になることをめざすので、手続もシンプルです。さらに、MEOは自力で実施することができるので、SEOに比べて費用負担が少なく済みます。
MEO対策を行うデメリット
MEOはぜひ実施したい施策ですが、デメリットについても確認しておきましょう。
1.口コミへの対応が必要
Googleビジネスプロフィールを登録したあとは、投稿された口コミの管理を行う必要があります。評価が高い口コミへの迅速なお礼も重要ですが、それ以上に低評価の口コミへの対応は迅速かつ慎重に行う必要があります。過度に悪質な口コミに対しては、削除できることもあるので、こまめなチェックを心がけましょう。
2.風評被害のリスクもある
Googleビジネスプロフィールに口コミ投稿が可能なことは、反面、ネガティブな投稿が行われるリスクがあることを意味しています。中には悪意ある第三者により事実ではないクレームが書き込まれるなどして風評被害に遭う可能性もあります。たくさんの口コミが書かれているにもかかわらず、すべてが高評価の場合もユーザーから怪しまれるので、必ずしもネガティブな口コミが業績に悪影響を及ぼすとは限りませんが、このような口コミにも真摯に対応することで、接客の丁寧さをアピールすることが大切です。
MEOツールとは?
MEOツールとは、Googleマップから店舗情報や事業所情報へのアクセス状況を解析するツールです。たとえばアクセス数やキーワードの順位、どのようなキーワードで検索してきたのかなどを分析します。これらの分析結果は、グラフや表に表されて可視化され、視覚的にアクセス状況を把握することができます。
MEOツールの基本機能
MEOツールにはさまざまな機能が備わっていますが、ここでは主な基本機能について紹介します。
自動順位計測
MEOツールには、登録したキーワードごとに自店舗や他店舗の検索順位を計測して一覧表示する機能があります。順位で明らかになった競合店の商品・サービス内容を確認することで、自店舗の商品・サービス内容の見直しに生かすことなどができます。
レポーティング
MEOツールには、MEOの効果を集計・分析し、レポートとして出力する機能があります。このレポートで、チェーン店の状況を本部に報告する業務を効率化したり、MEOの効果を関係者間で共有したりすることができます。
分析/比較機能
MEOツールは、Googleビジネスプロフィールの内部分析や競合分析を行い、上位表示のための最適化の手がかりを得ることを支援します。
インサイトデータ
MEOツールは、過去のインサイトデータを確認し、MEOの効果や季節要因による変動、前年比などを定量的に確認することができます。
複数店舗のビジネスプロフィール管理・一括編集
MEOツールには複数店舗のビジネスプロフィールを一括で管理できる機能が備わっているものがあります。複数店舗のメニューや投稿、営業時間などを一括で編集することができます。
MEOツールの活用事例
MEOツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
結果がすぐに出はじめました
「結果がすぐに出始めた。そしてそれを確認できました。GMOに依頼してから、検索して来ました。というお客様が来店されました。普段利用されない客層のお客様が急に必要になった場合、検索して上位表示されている当店舗にご依頼頂き高額案件でした。幅広いお客様層に有効です」
https://www.itreview.jp/products/meo-dashboard/reviews/69050
▼利用サービス:MEO Dashboard byGMO
▼企業名:買取専門 大吉 シーマークスクエア店 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:その他サービス
ポータルサイトに登録するよりMEO対策の方が効果が高い
「WEBでの検索において、MEOは常に1ページ目の上段に表示される。また、地図も表示されるので、どのあたりにあるのかが分かりやすい。口コミも掲載されるので、初めて利用しようとする際の参考になる。検索ページの1ページ目の上段に名称が口コミ込みで記載されるというのは、非常に大きな宣伝効果となる。例えば、ポータルサイトに登録したとしても、検索ページに自社の名称が乗るわけではなく、ポータルサイトを開いてその中で何番目・・・といったような感じ。効果がないわけではないが、自社名が表示されるまでに2アクション以上必要となるので効果としてはMEO対策の方が高いと感じられる。
▼利用サービス:MEO Dashboard byGMO
▼企業名:K’sデンタルクリニック ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:歯医者
https://www.itreview.jp/products/meo-dashboard/reviews/75097
MEO対策の改善に繋がり役にたった
「順位表示の際にGoogeビジネスプロフィール内の何が影響して上位表示になっているのかが、簡単にわかって、MEO対策の改善に繋がり役にたった。Googleビジネスプロフィールの「運用代行」を行う上で、毎月の作業内容と順位レポートが簡単に提出できるのでとても便利です。しかも一度設定してしまうと毎月クライアント様に自動送信してくれるのもありがたいです」
▼利用サービス:Gyro-n MEO
▼企業名:株式会社FotoReise ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ITコンサルタント
https://www.itreview.jp/products/gyro-n-meo/reviews/88942
MEOツールの業界マップ
MEOのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
おすすめのMEOツール4選
実際に、MEOツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのMEOツールを紹介します。
(2021年12月23日時点のレビューが多い順に紹介しています)
MEO Dashboard byGMO
「MEO Dashboard」は、MEOの順位計測管理ツールです。キーワード別に毎日の自店舗や競合店舗の順位測定を行います。また、Googleビジネスプロフィールのインサイト情報を閲覧・分析できます。さらに、基本情報や投稿情報の更新管理なども行えます。
MEO Dashboard byGMOの製品情報・レビューを見る
MEOチェキ
「MEOチェキ」は、ローカルビジネスを行っている事業主様のMEOおけるGoogleビジネスプロフィールやYahoo!プレイスの順位計測・効果測定・運用効率化・分析などができます。
Knowledge Graph
「Knowledge Graph」は、店舗の位置や営業時間、キャンペーン、商品、メニュー、駐車場、専門家の資格情報など、検索される可能性のある企業やブランドに関するあらゆる公開情報を一元管理することで、公式情報の更新や配信を容易にします。
Canly
「Canly」は、Googleビジネスプロフィールや各SNSで使用している店舗アカウントを一括管理するクラウドシステムです。そのことで管理・運用コストを軽減し、データ分析により店舗運営上の課題を明らかにします。
ITreviewではその他のMEOツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。
まとめ
MEOはSEOに比べて取り組みやすいうえに効果が出やすいという特徴があります。適切なMEO対策を行えば、地域での知名度を高められ、継続的なビジネス成長にも期待がもてるでしょう。
BtoBビジネスを行う企業にとって、Googleビジネスプロフィールへの登録・活用はメリットの大きい施策です。特に増加しているモバイル端末ユーザーを取り込むためには、ぜひGoogleマップにおける自店舗や事業所の検索上位をめざしたいところです。
投稿 MEOとSEOの違いとは?対策のポイントからMEOツール4選を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ROEとは?ROAとの違い、計算方法から経営指標としての見方を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、ROEの算出方法からROAとの違い、ROEが高いことの意味、そしてROEの注意点について解説します。
ROE(自己資本利益率)とは?
ROEは「Return On Equity」の略で、「自己資本利益率(株主資本利益率)」と訳されています。ROEは株主が投資した資金である自己資本を使ったことで、どれくらいの利益を生み出しているのかを示す指標です。つまり、企業の「稼ぐ力」を示します。ROEが高ければ投じた資金に対して稼ぎ出した利益が大きいと判断されるため、投資リターンが大きい企業であると評価されます。
このことから、機関投資家や投資信託などは、企業を評価する際にROEを重視しているのです。また、ROEが高い企業には高いリターンが期待できるため、投資資金が集まりやすくなり、自己資本が増加しやすくなります。自己資本が増え、さらなる投資が行えることで利益を稼ぎ出し、業績を向上させるという好循環が生まれやすくなります。この好循環により、株価が上昇を続ける可能性が高くなります。
ROEで何がわかるのか?
ROEは企業の稼ぐ力、つまり収益性を表す指標ですが、ROEから何がわかるのかについて 説明します。
倒産の可能性
ROEは自己資本比率の大きさで変化します。資本調達により集めた返済不要の自己資本比率が大きければ経営が安定しますし、小さければ不安定になります。一般的には、自己資本比率が70%以上であれば理想的な安定した企業で、40%以上であれば倒産しにくい企業といわれています。
成長速度
自己資本比率が100%の企業は無借金経営の状態にあるので、倒産リスクは小さく安定しています。一方で、自己資本比率を下げずに経営している状態であれば、利益も一定の範囲に止まります。自己資本比率が急に倍増することは難しいため、成長も緩やかになります。借入を行うことで新規ビジネスに挑んだり、既存のビジネス規模を拡大したりすれば、自己資本比率は下がるものの、成長速度は大きくなります。
株価
ROEが高い企業は安定した収益が期待できるため、投資家から好感されます。その結果、株価が上がる傾向があります。
当期純利益率の確認も重要
優良企業の条件は、ROEが高いだけでなく、業績が伸びていることや当期純利益率が高いことです。そのため、ROEを確認する際には、当期純利益率も合わせて確認する必要があります。
ROEの算出方法
ROEを算出する計算式は以下の通りです。
ROE(%) = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100
式中の自己資本とは返済する必要のない資金です。たとえば株主が出資した分や事業で得た利益累計額、あるいは自社株式を購入した分などです。これらの資金を使って稼ぎ出した金額が当期純利益です。つまり、当期純利益が自己資本の何%になるのかを算出したものがROEです。たとえば自己資本が10億円で当期純利益が2億円だった場合のROEは20%ということになります。
当期純利益
ROEの計算で使われる当期純利益は、法人税までを支払った最終的な利益です。利益には営業利益や経常利益がありますが、株主や投資家へのリターンの1つである配当金の原資である当期純利益が、ROEの計算に使われます。
自己資本
自己資本はほぼ純資産を示します。正確には以下の計算で算出されます。
自己資本 = 純資産 - 新株予約権 - 非支配株主持分
純資産から新株予約権と非支配株主持分が除かれているのは、それぞれが未来の株主や連結子会社の資本のうち親会社の持分ではない分を示し、現在の株主とはいえないためです。
ROEとROAの違い
ROEに似た指標にROAがあります。ROE(Return On Equity)が返済する必要のない自己資本で、どれだけ効率よく利益を得ているのかを示す指標であるのに対し、ROA(Return on Assets)は、返済する必要のある他人資本も含めた総資産に対してどれだけ効率よく利益を上げているかを示す指標です。
つまり、ROEは投資家や株主から集めた自己資本を使ってどれだけ効率よく稼ぐ力があるかを示しているので、投資家や株主に重視されます。
これに対して、ROAは負債である他人資本も含む総資産を使ってどれだけ効率よく稼ぐ力があるかという総合的な経営効率を示しているので、経営者や従業員、債権者などに重視されます。このことから、ROEは異業種間の比較にも用いられますが、ROAは異業種間での比較には用いられません。
<出典:『ROE(自己資本利益率)、ROA(総資産利益率)とは? これらの数値から分かることとは?|転職ならdoda(デューダ)』
ROEの目安
ROEは企業を評価するうえで重要な指標ですが、その目安の値はどれくらいでしょうか。日本の上場企業がめざすべきROEは8%といわれています。しかし自己資本が少ない業種ではROEが高くなりやすいため、業種により標準値は異なってきます。
一般的には、10%を目標にする企業が多い傾向にあります。そのため、15%を超えれば優良企業と評価されます。また、日本企業のROEは他国の企業と比べると低めです。その理由は、内部留保の大きさが株主資本を大きくしているためだと考えられます。
<出典:経済産業省『事務局説明資料 2019年11月 経済産業政策局産業資金課』p7「日米欧上場企業のROE・ROAの推移」
ROEが高い企業で起きていること
ROEが高い企業は、どのような状態にあると考えられるのかについて解説します。
無駄な資産を利益に変えた
ROEが高くなった企業は、利益を生まない資産を見直して利益化している可能性があります。
例として、以下のような施策を実施していると考えられます。
| 受取手形に応じない |
| 売掛金を早めに回収している |
| 貸付金や未収入金、立替金などを積極的に回収している |
| 不良在庫を処分してる |
| 不要な資産を現金化あるいは損金化している |
コストを削減した
ROEが高くなった企業は、相当なコスト削減の工夫や努力を行っている可能性があります。その結果ROEの分子である利益を向上させているのです。
例として、以下のような施策を実施していると考えられます。
| 仕入れ先の競争を促したり、仕入れ先を集中させたりすることで仕入コストを削減している |
| 業務の自動化やプロセスの見直しにより人員を削減している |
| 費用対効果を確認できない広告宣伝費を削減している |
売上が伸びた
ROEが高くなった企業は、売上を伸ばしている可能性があります。
例として、以下のような施策を実施していると考えられます。
| 販売速度を上げることで仕入から販売までの期間を短縮している |
| 売上に貢献していない資産を処分している |
借入が増えた
ROEが高くなった企業は、借入を増やしている可能性があります。つまり、借入金や社債の割合を高めて自己資本の何倍もの総資本を事業に投下している状態では、自己資本の割合が低くなるためROEの分母が小さくなります。
このような経営状態を「財務レバレッジが上がった」と表現します。財務レバレッジを上げることは、より多くの他人資本を活用して利益を上げることなので、自己資本が少なくても大きなビジネスを展開できます。そのため、ROEを評価する際には、財務レバレッジを競合他社や同じ会社の過去の実績と比較するなどして、総合的な判断が必要になります。
利益率が上がった
ROEが高くなった企業は、利益率が上がっている可能性があります。
例として、以下の施策を実施していると考えられます。
| 付加価値を高めることで客単価を上げている |
| 仕入方法や仕入れ値を見直すことで原価率を下げている |
| 経費や役員報酬などを見直すことで販管費を下げている |
ROEが高ければ優良企業とは限らない
ROEは株主や投資家が企業を評価する指標として重視していますが、注意しなければならない点もあります。実はROEが高ければ優良企業であると単純には評価できません。それは、ROEの分子や分母は、業績がよくなっていないときでも変化するためです。
具体的に見ていきましょう。
ROEが高い理由が、借入金額が大きい場合
企業が借入による他人資本で資金を調達して利益を上げている場合もROEは高くなります。この場合の評価としては、借入金を用いながらもビジネスを大きくして利益も上げていることは経営効率がよいと評価できますが、借入が増えていることによるリスクを注視する必要があります。
ROEが低い理由が、株主資本が大きい場合
ROEが低くても、安定した企業はあります。たとえば株主資本が大きい場合はROEの分母が大きくなるためROEは低くなります。特に創業年数が長い企業ほど内部留保も大きくなり、株主資本が大きくなりROEが低くなる傾向があります。
ROEが低い理由が、一時的に当期純利益が小さくなった場合
本業では大きな利益を出していても、一時的に当期純利益が小さくなったことでROEが低下する場合があります。たとえば自然災害などで特別損失を計上したときなど、企業側の事情ではない事象によるROE低下はやむを得ない現象といえます。
ROEが低い理由が、節税対策の場合
企業が節税対策として法人税を少なくするために、法人保険などを利用して当期純利益を会計上で小さくすることがあります。この場合、簿価上の利益が減ることで、ROEが低くなります。したがって、実際の利益とは乖離したROEとなります。
ROEを改善する方法
ROEを改善するには利益率を上げる以外にも方法があります。
資産の見直し
資産の見直しを行うことでROEを上げることができます。具体的には以下の施策を行います。
・滞留したままになっている売掛金や貸付金、未収入金、立替金などを回収する
・受取手形を受け取らない
・棚卸しを行い、不良在庫を処分する
・固定資産を早期に償却する
・不要な資産を現金化する
利益率の向上
ROEを上げるためには利益率を上げます。利益率を上げるためには商品・サービスの付加価値を高めて販売価格を上げる必要があります。
具体的には以下の施策を行います。
・顧客ニーズを調査し、その結果を反映させた商品・サービスの企画・開発を行う
・利益率の高い商品・サービスの販売に注力する
コストの削減
コスト削減することで利益率を上げ、ROEを上げることができます。
具体的には以下の施策を行います。
・技術力を高めることで製造原価を抑え、歩留まりを改善する
・仕入れ先の競争や集中化で仕入れコストを下げる
・業務の自動化を進めることで人員を削減する
総資産回転率の向上
総資産回転率を上げることでROEを上げることができます。総資産回転率とは「売上高÷総資産」ですから、売上を伸ばしながら、有給資産を処分するなどして総資産を減らすことで上げることができます。
財務レバレッジの向上
財務レバレッジを上げることでROEを上げることができます。財務レバレッジを上げるためには、積極的に借入を活用して、自己資本が少なくても事業を展開して収益性を高める必要があります。ただし、財務レバレッジを上げることは財務の健全性を損ない、利息の支払が増えるリスクへの注意も必要になります。
当期純利益の向上
当期純利益を上げることでROEを上げることができます。
当期純利益を上げるためには、以下の施策があります。
・販売単価を上げる
・仕入れ単価を下げる
・経費を節減する
・役員報酬を見直す
投資を積極的に行う
ROEは分母である自己資本を減らすことで上がります。そのため、設備投資などに積極的な投資を行うことで、自己資本を減らしてROEを上げることができます。しかし、ROEを上げるために設備投資が過度になってしまっては、財政基盤が弱くなるので本末転倒です。
配当を増やす
ROEの分母である自己資本を減らすには、株主や投資家に対する配当を増やす方法があります。配当を増やしてROEを上げることは、投資家に歓迎される施策です。
自社株買いを行う
自己資本を減少させる手法に、自社株買いがあります。自社株買いとは、市場に流通している自社の株を購入する手法で、資金が株主に戻る効果を持ちます。このとき、資金が株主に戻った分、自己資本が減少するため、ROEが増加します。ただし、純資産が減少することで経営基盤が弱体化するリスクがあります。
高収益企業を買収する
ROEの分子を増やすために、収益力のある企業をM&Aにより買収する方法があります。M&Aにより収益が上がるだけでなく、新しいビジネスが展開されるなどの相乗効果も期待できます。
まとめ
ROEは投資家を中心に、企業を評価するための重要な指標として注目されています。ただし、企業の評価はROEだけで決まるものではありません。ROEが上がっている場合は、なぜ上がっているのかまで見極めることで、総合的に評価する必要があります。
投稿 ROEとは?ROAとの違い、計算方法から経営指標としての見方を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 クラウドソーシングとは?活用するメリットや注意点を受注・発注側から解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>クラウドソーシングとは?
クラウドソーシングとは、Crowd(群衆)とSourcing(調達)を合わせた造語で、企業や個人がインターネット上で不特定多数の人に業務を依頼するビジネス形態を指します。
・関連記事
BPOとは?アウトソーシングとの違いは?注目される背景と導入時のポイント
クラウドソーシングという言葉が使われはじめたのは、2000年代に入ってから。クラウドソーシングの名づけ親は、米国の雑誌「WIRED」の編集者ジェフ・ハウ氏とされています。2006年6月に同誌の記事で、科学課題解決コミュニティサイトや写真素材提供サイトなどが、ビジネスや研究開発に多大な影響を与えていることを紹介し、この現象をクラウドソーシングという言葉で表現しました。
クラウドソーシングで受発注されている業務の種類は非常に幅広く、代表的なものは以下です。
・IT系…Webサイトデザイン、アプリ開発、システム開発、サーバ構築
・デザイン系…イラスト作成、ポスターデザイン、映像編集、写真撮影
・オフィス系…経理代行、翻訳・通訳、データ入力
・アイデア系…ネーミング、商品企画
・その他…記事作成、テープ起こし
クラウドソーシングに注目が集まる理由
クラウドソーシングは、従来の雇用や外注方法の課題を解消する手段として注目されています。企業は専門性をもった人材を雇用することによって、ビジネスや研究開発における優位性を担保してきました。一方で人材の確保が困難であることやコストがかかることがデメリットでした。
しかし、インターネットの発展とともにネットワークを活用して業務委託者を幅広く募ることが可能となり、クラウドソーシングで業務内容に見合ったコストで最適な労力・スキルを確保できるようになったのです。専門性の高い人材を雇用せずとも自社業務に活用できます。社外の人材の力を借りることで、効率的な経営課題の解決につながり、採用や雇用継続にかかる費用を抑えて組織をスリムに保つことも可能です。
フリーランス人口の増加も、クラウドソーシングが普及した理由の1つでしょう。インターネットやテクノロジーの進化で、より多くの人が在宅勤務できるようになりました。これまでさまざまな事情でオフィスで働けなかった人たちが、フリーランスとして活躍しやすくなりました。クラウドソーシングは、地方在住者が都市部の仕事を受注したり、日本にいながら世界中の案件を獲得したり、ライフスタイルに合わせた働き方を実現できる新しい業務形態として注目を集めています。
クラウドソーシングの仕事の特徴
業務内容はさまざま
クラウドソーシングで受発注する業務には主に3つの形式があります。1回完結の「タスク形式」、長期間のやりとりが必要な「プロジェクト形式」、複数の提案からより高品質なものを採用する「コンペ形式」です。いずれの業務もインターネットを介して作業、納品するものがほとんどです。システムやアプリ開発のようなIT系はもちろん、動画編集、デザインや翻訳、データ入力なども募集されています。多くの分野で業務の受発注が可能です。
1億総クラウドワーカーの時代
副業・兼業奨励やジョブ型雇用が注目される中、企業に所属するしないにかかわらず、すべての人がフリーランス感覚をもつことが求められています。今後は、自分のスキルや経験を証明し、それを武器にビジネスチャンスを獲得していくことが必要となります。クラウドソーシングが普及したことで、インターネットとパソコン、場合によってはスマートフォン1台あれば仕事ができる時代になりました。これまでさまざまな事情で通勤や定時勤務が難しかった人たちも、時間や場所を問わず、自分の専門性やスキルをもとに活躍できる時代になりつつあります。
「クラウドソーシングは単価が安い」のは本当か?
クラウドソーシングには業務ごとの相場がほとんどなく、同じ業務レベルでも報酬には差があります。クライアント側から見れば、スキルや人となりが見えない状態で依頼するため、なるべくリスクを回避したいという事情もあり、比較的安価な依頼に偏ってしまうという面もあります。
また、一見して単価が高くても工数が多かったり、不慣れなために時間がかかったりして、時給換算では安くなってしまうことも。しかし継続依頼を受けたり、地道に信頼関係を構築したりしていくことで、より重要で高額の案件を紹介してくれるケースも少なくありません。最初は収入面で厳しいかもしれませんが、着実に案件を完了していくことが大切です。自分がもつスキルや実績をプロフィールやポートフォリオにまとめておくなど、自ら発信する姿勢も必要です。
どのぐらい稼げるのか?
請け負う業務内容や受注量、必要なスキルによっても異なるため、収入金額には個人差があります。スキルがあり成果物の品質が高い場合、同じクライアントから継続依頼が見込めるほか、高評価が集まれば次の案件につながり、収入が増える傾向にあります。クラウドソーシングサイト内で実績を重ねるまでは単価や時給が低い可能性も。しかし、着実に高評価を獲得し、ポートフォリオを作成する、過去の実績をプロフィールに盛り込むなど、さまざまな工夫を続けていけば、収入アップも期待できます。
クラウドソーシングの3つの形式
クラウドソーシングにおける業務の遂行形式は主に「プロジェクト形式」「コンペ形式」「タスク形式」の3つがあります。報酬についてはサイトの信頼度を保つために、業務着手前の仮入金となる場合がほとんどです。マッチングしたワーカー(受注者)が滞りなく業務を完了した際には支払われ、何らかの事情で未完了に終わった場合にはクライアント(発注者)に返金される仕組みです。
プロジェクト形式
長期の依頼、事前の説明や作業中のやりとりが必要な依頼、修正対応が発生する依頼はプロジェクト形式がおすすめです。限られた人数と契約して、段階的に業務を進めていきます。サイトやバナー制作、アプリ開発、システム構築などが代表例です。
タスク形式
修正の必要がなかったり、フォームだけで作業が完結できたりする依頼はタスク形式を利用します。スキルや経験不問の単純作業で、多数の作業が必要な場合に向いています。データ入力、アンケート回答、記事作成などがタスク形式の主な業務です。
コンペ形式
クライアントが多くの人に依頼して「なるべくたくさんのアイデアから気に入ったものを選びたい」という場合に使われます。あらかじめ要件が決まっているため、ワーカーはクライアントの要望に沿ったものを提案します。たとえば、ロゴデザインやチラシ・ポスター作成、キャッチコピーなどが該当します。
クラウドソーシングの仕事概要
クラウドソーシングを具体的に始める際に知っておきたい仕事の概要を、発注者側と受注者側の立場から説明します。
発注者側にとってのクラウドソーシングとは?
・仕事を依頼する方法
依頼したい業務のカテゴリ内に、新規案件のタイトルと詳細内容を記載します。業務を任せたい、相談したいワーカーが決まっている場合には、ワーカーに直接働きかけることも可能です。
・仕事の依頼形式
依頼したい業務によって「プロジェクト形式」「コンペ形式」「タスク形式」の中から適切な依頼方法を選びます。
・依頼オプション料金
依頼の応募率を上げたり、応募ワーカーの質を担保したりするため、案件の上位掲載や特定のワーカーに対してのみ募集するなど、さまざまな有料オプションがあります。
・仕事の発注相場一覧表
発注相場を一覧にして公開しているサイトがほとんどです。あくまで一例ですが、値付けの参考になるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
・支援サービス
依頼内容に合わせて、スキルがあり評価の高いクラウドワーカーを紹介してくれるマッチング支援サービスもあります。自社に合うワーカーの探し方がわからない、該当者が多く迷ってしまうなど、人選に困ったときに利用すると便利です。
受注者側にとってのクラウドソーシングとは?
・仕事を受注する方法
サイトへのプロフィール登録を済ませたら、興味のあるカテゴリから仕事を探します。受注形式や報酬額、報酬形式など、細かく条件を付加しての検索も可能です。気になる案件が見つかったら応募します。
・仕事の受注形式
長期間にわたる「プロジェクト形式」、テーマに沿って提案を提出して採用を待つ「コンペ形式」、単純作業に多い「タスク形式」の3つが一般的です。
・ワーカーシステム利用料
多くのサイトが登録から受注まで無料で利用でき、ワーカーの確定報酬から天引きする形でシステム利用料を支払います。
・安心・安全への取り組み
各サイトで、悪質なクライアントの取り締まりを強化し、ワーカーの労働力搾取の防止措置を講じています。たとえばマルチ商法やネットワークビジネスなどの悪質案件に関する対策や、優良クライアントの可視化、適正報酬での取引推進など、さまざまな対応がなされています。
クラウドソーシングの仕事の流れ
クラウドソーシングは、サービスごとにシステムや使い方に多少の違いはありますが、進行上の基本ルールは共通です。クライアント(発注者)側とワーカー(受注者)側の立場で、登録から掲載・応募、業務遂行、報酬の支払いと受け取りまでを説明します。
クライアント(発注者)側の発注の流れ
・クラウドソーシングサイトを選び、利用登録をする
・発注したい業務の詳細を掲載する
・ワーカーから送られてきた提案内容、見積もりを検討する
・業務を依頼するワーカーを選び、発注する
・業務途中のチェックをし、修正を依頼する
・納品物を受領、検収する
・報酬を支払う
・ワーカーを評価する
ワーカー(受注者)側の受注の流れ
・クラウドソーシングサイトを選び、利用登録をする
・職歴や実績などのプロフィール、受注したい業務の詳細を掲載する
・クライアントが掲載している募集内容、予算を検討する
・業務を選び、契約する
・業務途中の修正依頼、修正作業を行う
・クライアントへ納品、検収してもらう
・納品が完了したら報酬を支払ってもらう
・クライアントを評価する
クライアント(発注者)側のメリットとデメリット
クライアント(発注者)が、クラウドソーシングを通じて業務を委託するメリットとデメリットを紹介します。コスト削減や幅広い人材活用ができる一方で、余分な手間がかかる可能性やトラブルの危険性も秘めています。
※図表入る
発注者側が利用するメリット
1.必要なときのみ利用できる
2.従業員を抱える費用や人材育成コストが抑制、削減できる
3.自社にない専門スキルを利用できる
4.柔軟かつスリムな組織運営が実現できる
5.海外人材や地方人材も活用できる
6.ワーカーの評価制度により客観的な採用が可能
発注者側が利用するデメリット
1.社内人材の成長機会が損なわれる
2.細かな仕様設定や進捗管理が必要となり、余計な工数がかかる可能性がある
3.情報漏えいのリスクがある
4.知的財産権トラブルの危険性がある
5.スキルやコミュニケーション面における、ワーカーのミスマッチが起こる可能性がある
ワーカー(受注者)側のメリットとデメリット
ワーカー(受注者)にとって、クラウドソーシングを利用して仕事を得るメリット・デメリットは以下のとおりです。時間や場所にとらわれず、自分のスキルを生かして報酬を得られる点は大きなメリットですが、クライアントとの信頼関係構築、収入の安定には時間がかかります。信用できるクライアントかどうかを見極める目も重要です。
受注者側が利用するメリット
1.ライフスタイルに合わせた仕事ができる
2.副業がしやすくなる
3.本業以外でのスキルアップ、経験値の蓄積が可能になる
4.家事や育児、障害などで自宅から出られなくてもできる
5.隙間時間を有効に使える
6.仕事量や時間を選べる
受注者側が利用するデメリット
1.収入が安定しづらい
2.外部の信頼を得にくい
3.知的財産権トラブルの危険性がある
4.クライアントの信頼性における担保がない
5.安価な仕事が多い
6.スキルや要望とマッチした仕事があるとは限らない
クラウドソーシング導入のポイント
企業がクライアントとしてクラウドソーシングを導入する場合のポイントを解説します。特筆すべきは、2023年10月1日からスタートするインボイス制度です。取引先がインボイス(適格請求書)を発行しない場合、企業は消費税の仕入額控除を受けられなくなります。クラウドワーカーには課税売上1000万円以下の個人の免税事業者が多いため、適格請求書発行事業者になる予定があるか確かめておくとよいでしょう。継続的に取引したい免税事業者がいる場合は、課税事業者と分けて管理する必要も出てきます。
適切な発注方法を選ぶ
依頼したい業務が「プロジェクト形式」「コンペ形式」「タスク形式」のうち、どの形式での発注が適しているか検討します。それぞれの発注形式でメリット・デメリットが異なるため、適切な発注方法の選択はワーカーや成果物の品質に直結します。
ワーカーと機密保持契約を結ぶ
ワーカーが個人であることも多いクラウドソーシング。情報漏えいリスクについては念入りに注意したいものです。紙媒体のコピーや記録デバイスの持ち出し、紛失をはじめ、依頼内容に関する機密情報を口外してしまう、SNSの個人アカウントからの情報漏えいなど、情報管理トラブルの例は枚挙にいとまがありません。機密保持契約(NDA)を結び、情報の取り扱いについて確認と同意を得たうえで業務の依頼を進めるようにしましょう。
成果物に対するチェック体制を構築する
クラウドソーシングの最大の特徴は、不特定多数の人と気軽に広くつながれる点です。専門性の高い仕事を適任者に任せたり、質の高いアイデアを効率的に収集できたりとメリットが大きい反面、ワーカーのスキルや経験値には大きく差があり、一般的な採用フローのようにじっくり調べられないことも事実です。
成果物や納品物の品質がまちまちだったり、盗作や著作権侵害の危険性があったり、さまざまなトラブルも予想されます。品質に関する評価基準を明確にする、著作権に関する取り決め、チェックルールを構築するなど、クラウドソーシング導入前に社内でのチェック体制や項目をつくっておきましょう。
適格請求書発行事業者登録の有無を確認
2023年10月に始まるインボイス制度は、インボイス(適格請求書)がないと仕入税額控除が受けられなくなる制度です。これまでは確定申告の際に無条件で仕入税額控除を受けることができましたが、インボイス制度導入後に今までどおり確定申告をした場合、本来の税率より消費税を多く納める必要があります。
適格請求書を発行できるのは課税事業者のみなので、免税事業者がワーカーの多数を占めるクラウドソーシングでは注意しなければなりません。契約前に適格請求書発行事業者登録がされているか、または今後対応する予定があるかを確認しておくことが大切です。
クラウドシーシングの発注で失敗しないポイント
クライアントがクラウドソーシングの発注で押さえるべきポイントを解説します。気軽に受発注できる分、ワーカーのスキルや人柄のチェック、仕事内容の確認は基本的に自己責任と捉えて臨むことが大切です。トラブルの可能性は前もって摘み取る工夫も必要になります。
※図表入る
1.クラウドワーカーのスキルを確かめる
ワーカーのスキルチェックは基本中の基本です。プロフィールを読み込み、ポートフォリオや個人サイト、ブログなどがあれば確認しましょう。近年はSNSで情報発信しているワーカーも多いので、アカウントの記載があれば、どのような発信がされているのかを見るのもおすすめです。多少なりとも人となりが垣間見られる貴重な資料となります。
2.金額で決めない
安価な見積もりは魅力的ですが、その裏には実績や経験が乏しいケースも多いので注意が必要です。ワーカーの提示金額はあくまで見積もりで、契約締結前であれば交渉余地があるため、掲載された提示金額だけで決めずに、ヒアリングや相談を重ねることがワーカーや成果物とのマッチング精度を上げるコツです。
3.サポートを重視する
個人商店の集まりともいえるクラウドソーシングでは、サポートの手厚さに関しても千差万別です。納品後の相談やサポートが皆無だと、何かトラブルがあったときに困ります。特にアプリ開発やサイト制作、システム構築などは、納品後の運用が重要です。運用保守サポートの有無や費用なども確認しておきましょう。
4.スケジュールを確認する
希望納期に合わせて対応可能なワーカーを選ぶことも重要です。特に急ぎの業務に関しては事前のやりとりで合意をとることが大切です。また、ワーカーが提示してきた納期が守られるかどうかに保証はありません。過去の評価を参考にするほか、こまめな進捗確認、バッファをもった期限設定、要件定義を念入りにして手戻りを防ぐなど、できる限りの工夫を凝らすべきです。
5.契約内容を確認する
クラウドソーシングでは正式に契約書を交わす機会が少ないため、業務内容や注意事項、責任範囲など、あらゆるリスクを想定して契約しましょう。機密保持契約(NDA)や独自の契約書など、必要に応じて追加対応をすることが重要です。ワーカーと個別に契約書を交わす際にはクラウドソーシングサイトの規約を守って行いましょう。
クラウドソーシングの受注で失敗しないポイント
ワーカーがクラウドソーシングで仕事を受注する際に確認すべきポイントを解説します。目の前の案件を獲得したいがために見過ごしてしまう点も、トラブル回避、将来につながる可能性を考えて判断したいものです。
1.単価と仕事内容を見極める
業務にかかる時間と報酬が適正かどうかは非常に重要な判断基準です。クラウドソーシングの報酬体系は、稼働時間分だけ報酬が得られる時間単価制と、成果物に対して一定報酬が支払われる固定報酬制に分かれます。固定報酬制の場合、一見すると高単価の案件も、詳細をよく読んで実際の作業をシミュレーションしてみると割に合わないことが多々あります。未経験だったり、経験が浅かったりして判断に迷う場合には、まず少量から始めて、だいたいの工数を測ってみるとよいでしょう。
2.「よいクライアント」を選ぶ目を養う
クラウドワーカーにさまざまなレベルの人がいるように、クライアントの発注者としてのスキルや経験もまちまちです。中には良識の欠けたクライアントも、残念ながら存在します。
・クラウドソーシングサイトを通さず、直接取引を持ちかける
・仮入金前なのに作業を要求してくる
・外部サイトへの登録、有料資料や情報商材購入を促す
・契約内容とは異なる作業を過剰に追加してくる
・ワーカーからの評価が低い
など、ワーカーの労働力を搾取しようとしたり、規約違反をして一方的に取引をもちかけたりする傾向があります。発注者としての経験が乏しく配慮が行き届かない場合や、サービスに不慣れなために誤解しているケースもありますが、契約締結は慎重に行い、少しでも不安があればサイトのサポート窓口に相談しましょう。
3.自分にとって都合の悪いことも誠実に伝える
自分のペースを守りながらの仕事が、質の高い成果物を継続して提供できることにつながります。育児や介護、障害、病気といった事情は前もってクライアントに伝えておきましょう。良識のあるクライアントであれば、無理強いはしてこないはず。長く良好なつき合いができる関係を築くためにも、特別な配慮が必要と思われる事情は共有すべきです。
4.報酬額より「スキル」を生かせる仕事を選ぶ
報酬にばかり目がいってしまうと、自分のスキルと案件にミスマッチが生まれる可能性があります。スキルが生かせる仕事であれば、スピーディーに質が高い成果物を提供でき、スキルアップにもつながります。
しかしスキルと見合わない場合、時間がかかるだけでなく、品質にも不安が残るかもしれません。いくら報酬が高額でも時間単価は低かったり、よい評価が得られなかったりしては本末転倒です。今後スキルを伸ばしたい、経験を積みたいなど、将来に向けた投資にあたる仕事を選ぶことが大切です。
5.契約前に疑問点は残さない
仕事の条件や内容に関して疑問や不明点がある場合、契約前に必ず確認することが重要です。どんな作業をどの手順で行うのか、評価基準はどうなっているのか、修正作業はあるのかなど、仕事内容を十分に理解してから契約に進みましょう。
まとめ
これまでビジネスチャンスが都心部に集まっていたことから、地方在住者は仕事の獲得面で不利とされてきました。また、企業に雇用され、決まった時間と場所に縛られるワークスタイルや、介護や育児、自身の病気など、さまざまな事情により難しい人も多数います。
しかしクラウドソーシングを活用すれば、場所や時間の制約を取り払って働くことが可能です。自分の専門性を生かして仕事ができるため、受注することでさらなるスキルアップや市場価値の向上につなげられます。デメリットや注意すべきポイントを踏まえつつ、クラウドソーシングを上手に活用して、自分に合った働き方を探してみてはいかがでしょうか。
投稿 クラウドソーシングとは?活用するメリットや注意点を受注・発注側から解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 クラウドとは?環境やサービスなど基礎知識を分かりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>クラウドサービスはインターネット環境や対応するデバイスがあれば、外出先や自宅からでも社内の情報に安全にアクセスできます。また社内で運用するリソースやコストの削減につながったり、災害時にも事業継続性を確保できたりと多くのメリットを得られます。
この記事ではクラウドの種類やメリット・デメリット、クラウドサービスの選び方について詳しく解説します。
クラウドとは?インターネット上でサービスを利用できる仕組み
クラウドとはユーザーがサーバやストレージなどのインフラやソフトウェアをもっていなくても、インターネット経由でサービスを利用したい分だけ利用できる仕組みのことです。パソコンやスマートフォン、Webブラウザ、インターネット環境など、最低限のデバイスとツールを用意するだけですぐに使えるのが特徴です。自社でサーバを構築している場合と異なり、ソフトウェアやデータがどこのサーバに保存されているかを意識せずに利用できます。クラウドという名称の由来は「Cloud(雲)=クラウド」で、インターネットの向こう側に存在するサービスを利用していることからきています。
従来はハードウェアを購入し、ソフトウェアをパソコンにインストールしなければサービスが使えませんでした。利用者自身でソフトウェアやデータを管理する必要があったのです。しかし、クラウドが誕生したことで機材の購入やソフトウェアのインストール、システム構築、運用保守などの管理をしなくても利用できるサービスが普及しました。これをクラウドサービスといいます。
たとえばメールソフトでいうと、Googleの「Gmail」やYahoo!JAPANの「Yahooメール」などが挙げられるでしょう。アカウントを作成すればすぐに利用開始できるサービスです。逆にクラウドではないメールソフトの例としては、インストールが必要なOutlookやWindows Liveメールなどがあります。
物理サーバとクラウドサーバとの違い
「物理サーバ」は物理的な実体があるサーバ、「クラウドサーバ(仮想サーバ)」は物理的な実体がないサーバのことです。
物理サーバはデータセンターなどにラックを借り、サーバを企業がセットアップして管理します。自社で管理できるため、ユーザー数やアクセス数が増えて負荷が高くなった場合は台数を増やすなどその都度強化できるのが特徴です。ほかのサーバから影響を受ける心配もありません。コストはかかりますが、障害が発生しても自社内の環境に限定されるので、影響を最小限に食い止められます。デメリットは、サーバ自体が5年ほどで劣化する点です。
一方、クラウドサーバは仮想サーバともいわれ、物理的な1台のサーバ上で仮想化技術を用いて稼働します。物理サーバに専用のソフトウェアをインストールし、その上で複数の仮想サーバが稼働するようにしているのです。仮想サーバごとに違うOSやソフトウェアをインストールして、まったく異なる環境として利用できます。たとえば一方にはWindowsOS、もう一方にはLinuxOSのように分けて使うことが可能です。
「クラウドサーバには物理的な実体がない」と記載しましたが、前述したとおりメインとなる物理サーバは存在しています。そのため物理サーバに障害が発生すると、複数のOS環境に被害がおよび、影響が大きくなりやすいです。あらかじめ物理サーバを複数台用意しておき、仮想サーバを安全な物理サーバ上へ移行して再起動できるように準備しておくことが重要になります。
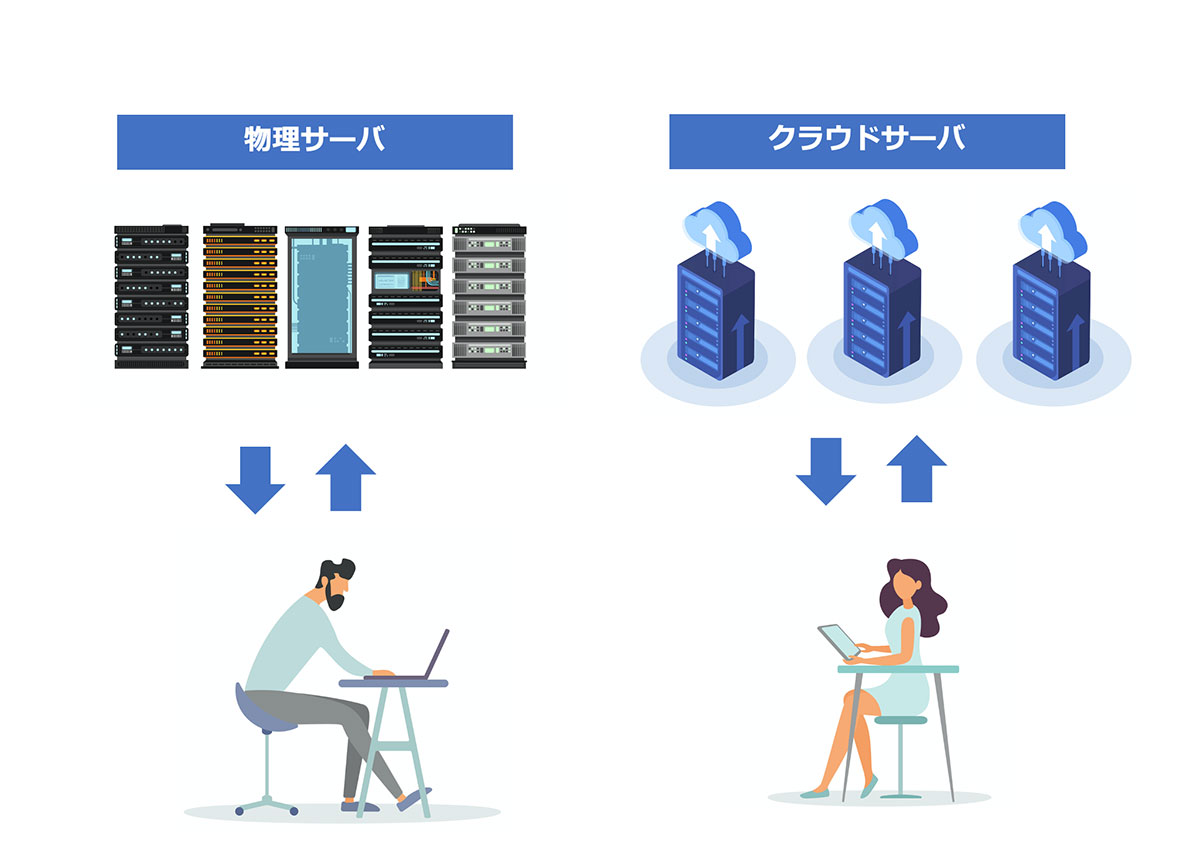
クラウドが生まれた背景
「クラウド」すなわち「クラウドコンピューティング」という言葉は、2006年にGoogleのCEOであるエリック・シュミット氏が提唱した言葉といわれています。そもそもなぜクラウドコンピューティングが生まれたのか、コンピュータの歴史を交えて解説します。
コンピュータの歴史は次の4つの時代に分けられます。
・メインフレーム時代(1950~1990年頃)
・クライアント・サーバ時代(1990~2000年頃)
・Webコンピューティング時代(2000~2010年頃)
・クラウドコンピューティング時代(2010年頃~)
まず1950年頃に世界初の商用コンピュータであるUNIVACが登場し、メインフレーム時代が始まりました。メインフレームとは超大型コンピュータのことで、会社の一部屋を占めるほどの大きさでした。全機能をメインフレームが担っており、複数のユーザーが同時に利用するのが主流になっていたのです。またGUI上で直接操作することはできず、すべて文字ベースで行っていました。
1990年代にクライアント・サーバ時代に入り、大型コンピュータに代わって小型で安価なコンピュータが普及。低価格で購入できるようになったため、企業は大量のコンピュータを設置するようになりました。1台のクライアント上で複雑な処理やGUIでの操作が可能になったのです。
1990年代後半にはさらに低価格でコンピュータを購入できるようになり、ネットワークの速度も改善されました。しかし、コンピュータの利用台数が増えすぎたため、各コンピュータにアプリケーションやデータを配布するのが困難になったのです。そこでWebブラウザを通じてサーバへアクセスすることで、全コンピュータに配布する手間や管理を省けるようになりました。
ところが、利用するサービスが増えるほど多くのサーバが乱立し、サーバを管理する負荷が高まってしまいます。そこで2006年にクラウドコンピューティングが誕生し、1台の物理サーバに複数台のサーバを仮想的に構築することが可能になったのです。クラウドコンピューティングならサーバやネットワーク機器を管理するデータセンターを集約でき、サーバの統合に相応しいとされています。
リモートワーク普及によるクラウドサービスのニーズの高まり
近年は働き方改革の促進や新型コロナウイルスの影響もあり、リモートワークが急速に普及しています。
リモートワーク中はオフィスで対面しているときと違い、情報やファイルの共有、迅速なコミュニケーションなどが行いにくくなります。「メールにファイルを添付して送り、確実に目を通してもらえるように電話をかける」といった手間が繰り返し発生すると、業務に専念できず生産性が低下してしまうでしょう。
クラウドサービスを導入することで、リアルタイムでのコミュニケーションや、クラウドストレージの利用によるファイル共有・管理などが容易になります。さらにセキュリティの強化にもつながるので、管理者の負荷を削減することにもなります。そのためクラウドサービスはリモートワークには欠かせないツールとして、多くの企業でニーズが高まっています。
クラウド環境の種類
クラウド環境の実装モデルの種類と、それぞれのメリットについて解説します。
プライベートクラウド
プライベートクラウドとは、企業が自社専用に構築して運用するクラウド環境のことです。社内のさまざまな部署やグループ会社に環境を提供できます。従来の社内システムと同じように、企業内でシステムの設計や管理を行えるので、社内環境に合わせてサービス設計をしたい場合に最適です。
たとえば、特殊なシステムを利用しなければいけない業務がある企業に向いているでしょう。セキュリティ面でも独自のセキュリティポリシーを適用できるので、強固なセキュリティ対策を行えます。
さらにプライベートクラウドは以下の2種類に分けられます。
| オンプレミス型 | 自社でインフラの構築~運用までを実施する |
| ホステッド型 | クラウドサービスを利用して自社用のクラウド環境を構築する |
パブリッククラウド
「パブリッククラウド」とはリソースを共有するタイプのクラウドサービスのことです。ハードウェアを用意しなくても、利用者が必要なときに必要な分だけサーバやリソースを利用できます。さまざまな企業や個人に対してクラウド環境を提供しているので、ユーザー全体で共有して使うのが特徴です。オンラインで申し込めばすぐにサービスを使用でき、導入の手間もかかりません。
リソースを共有している分コストを抑えられるので、小規模から始めたい企業におすすめです。また従量課金制のため、ユーザー数などに合わせて柔軟に利用できるのもメリットでしょう。ベンダーがサーバの運用保守を行うので、システム担当者の負担を低減することも可能です。
ハイブリッドクラウド
「ハイブリッドクラウド」とは、プライベートクラウドとパブリッククラウドの混合型の環境のことです。社外のクラウドサービス(パブリッククラウド)・社内のクラウド環境(プライベートクラウド)・物理サーバなど、複数の環境を組み合わせて利用します。それぞれタイプの異なるサーバを組み合わせて使用するので、メリットを享受しつつデメリットをカバーできるのが特徴です。
たとえば、プライベートクラウドは強固なセキュリティを施したり、自社環境に合わせて柔軟にカスタマイズしたりすることが可能です。その分、単体ですべてをまかなおうとするとコストが増大してしまいます。そこでパブリッククラウドも導入することでコストや負担を抑えられるのです。また重要なデータをそれぞれに分散して物理的に違う場所で保管しておけば、万が一マルウェアの攻撃や自然災害に遭遇した際も素早く復旧できるでしょう。
マルチクラウド
「マルチクラウド」とは、複数のクラウドサービスを組み合わせ、自社に最適な環境を実現する運用形態のことです。たとえば次のような使い方が挙げられます。
・本番環境やバックアップ環境はパブリッククラウドを使って安価で構築する
・1つの業務を「情報収集」や「分析」など複数のフェーズに分け、フェーズごとに最適なクラウドサービスを利用する
マルチクラウドなら異なるベンダーのサービスを同時利用するので、自社に適した環境にカスタマイズしやすくなります。また1つのベンダーの機能や技術に依存しないため、他サービスや製品に柔軟に乗り換えることが可能です。ただし、ベンダー間のセキュリティレベルが大きく異なると、システム全体のセキュリティ強度が統一されず低下してしまう恐れもあります。
クラウドサービスの種類
クラウドサービスには「SaaS」「PaaS」「IaaS」の3種類があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
SaaS(Software as a Service)
パッケージとして提供していたアプリケーションを、インターネット上で利用できるサービスです。読み方は「サース」です。端末に直接インストールしなくてもインターネット経由で容易に利用できます。Microsoft365やGmail、iCloudなどがSaaSにあたります。
クライアントのアカウントごとにソフトウェアが提供されるので、自宅や外出先など場所を問わずサービスにアクセスできます。データはインターネット上に保存され、パソコンからスマートフォンなどデバイスを変えても同じアカウントを使えばそのままサービスを使い続けることが可能です。複数のユーザー間でドキュメントを同時に編集・管理できるのもメリット。リモートワークに欠かせないサービスといえるでしょう。
ベンダー側が随時ソフトウェアをアップデートするため、個人で実施する手間がかかりません。常に最新の状態が保たれるのでセキュリティ面でも安心です。
PaaS(Platform as a Service)
アプリケーション開発に必要なミドルウェアやプログラミング言語、サーバOSなどのソフトウェアを、インターネット経由で提供するサービスです。「パース」と読みます。
開発に必要な基盤やツールが揃っているため、自社で開発環境を整備する手間を大幅にカットできます。またサーバに負荷がかかった場合のリソースを増強したり、OSをアップデートしたりするメンテナンス要員やコストを削減できるのもメリットです。PaaSの例としてAmazon Web Service(AWS)やMicrosoft Azureなどが挙げられます。
「PaaSとは」記事へのリンクを追加(URL未定)
IaaS(Infrastructure as a Service)
サーバ・ストレージ・ネットワークなどのハードウェアやインフラを、インターネット経由で提供するサービスです。読み方は「イアース」または「アイアース」。前述したAmazon Web Service(AWS)やMicrosoft AzureはIaaSでもあります。
PaaSがアプリケーション開発に必要な機能を提供するのに対し、IaaSではサーバやネットワーク機器といったリソースが利用可能です。CPU・メモリ・ストレージなどのスペックを自由に選択でき、機能の拡張や縮小も柔軟に行えます。
従来はシステム構築をする際に、サーバやソフトウェアを購入してメンテナンスも行う必要がありました。しかし、IaaSならハードウェアがなくてもインターネット経由で必要なだけサーバ・ストレージ・ネットワークリソースなどを利用できます。
料金は安価で従量課金制のため、コストパフォーマンスが優れているのもメリットでしょう。一方で、自由度が高い分、インフラ設計やサーバ運用についての専門知識が求められます。
クラウドのメリット・デメリット
クラウドのメリットとデメリットについて、それぞれ解説します。
クラウドのメリット
クラウドのメリットには次のようなものがあります。
1.初期費用が安価
2.データセンターの運用保守が不要
3.サーバの拡張が容易
4.柔軟な働き方が可能
5.システムのバックアップ体制を強化
特別に機材を導入したりシステム開発を行ったりする必要がなく、サービスに申し込むとすぐに利用できるので導入コストを抑えられることがメリットです。自社でサーバを運用管理すると専門知識をもった担当者が必要ですが、クラウドを利用すればベンダー側に管理を一任できます。
またインターネット環境さえあれば場所やデバイスを問わずサービスを利用でき、オフィスと同様に作業することが可能です。災害時や感染症が拡大する中でも出社する必要がないなど、柔軟な働き方を実現できます。
社内でサーバを運用している場合、災害発生時に物理的な損傷を負ってデータが破損する可能性もあります。しかし、クラウドサービスならデータがクラウド上に保管されているため、事業を継続できます。マルチクラウド環境を構築して複数のサービスを利用しておけば、バックアップやリカバリーが速やかに行えるでしょう。
クラウドのデメリット
逆にクラウドのデメリットは以下が挙げられます。
1.カスタマイズが自由にできない
2.システム障害による社内業務の停止
3.サービスが停止されるリスク
4.セキュリティレベルをベンダーに依存
ベンダーが提供するサービスの機能を利用するので、細かくカスタマイズができない製品もあります。事前に柔軟に変更できるタイプどうか、確認しておくことが重要です。自社でサーバを運用しつつ一部でクラウド化するなど、ハイブリッド環境を検討してみるのもよいでしょう。
またベンダーに大規模なシステム障害が発生した場合、その影響で社内システムも停止せざるを得なくなるリスクがあります。実際に2021年にはAWSのサーバ冷却システムが電力喪失状態になり、数時間にわたりサービス停止するという障害も起きています。
さらにクラウド環境のセキュリティレベルはベンダーに依存するので、十分な対策がとられていない製品だと情報漏えいなどのリスクがあるでしょう。事前にしっかり確認しておくことに加えて、社内でアカウントやパスワード管理を徹底することも欠かせません。
クラウドサービスの活用事例
クラウドサービスを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
人的リソースや管理コストをカットできた
「各クライアントPCにソフトをいちど入れるだけであとはすべてのバックアップ管理を一か所でおこなえるので+ファイルサーバ不要ということで、人的面での管理コストが下がった。3Tierのバックアップという高度なことができるわりにダッシュボードもわかりやすいので、日常的に「なにか問題が起きていないか」とチェックする余裕が生まれたのもうれしかった」
https://www.itreview.jp/products/acronis-backup/reviews/69142
▼利用サービス:Acronis Cyber Backup
▼企業名:合同会社ネットスピン ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
直感的で使いやすく、管理者側の負担を軽減
「弊社では顧客向けの大容量ファイルの共有時に利用するサービスとして採用したが、利用者からの問い合わせが少なく直感的で使いやすいツールです。アカウント数無制限で定額であることも導入を検討する上でわかりやすい。顧客とのファイル共有のルートを統一することができました。メディアやUSBの書き出しのニーズが激減し、IT管理者側も統制が取りやすくなりました」
https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/57486
▼利用サービス:DirectCloud-BOX
▼企業名:山田コンサルティンググループ株式会社 ▼従業員規模:300~1000人未満▼業種:経営コンサルティング
機能豊富でコストパフォーマンスがよい
「ライセンス費用がそれほど高額でないにも関わらず、バックアップやリストアの機能が非常に豊富であり、幅広いハードウェアメーカーのストレージと連携することができることや、クラウドとの連携も兼ね備えている点を踏まえると非常にコストパフォーマンスがよい製品といえます。現在毎日フルバックアップを取得しているが、メンテナンス時間に終わらないといった問題を抱えている方にはぜひ導入し、バックアップ時間の改善を実感していただきたいです」
https://www.itreview.jp/products/veeam-backupandreplication/reviews/31969
▼利用サービス:Veeam Backup & Replication
▼企業名:ソフトバンクコマース&サービス株式会社 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:ソフトウェア・SI
拡張性が高く、運用の手間も削減可能
「必要なバックアップファイルやフォルダを指定できる点が良いです。また、拡張性が高くデータ容量も増やせるので良いと感じました。セキュリティ面に関しても安心して使用できるので良いと思います。安定したバックアップを取得出来ているので、安心です。また、運用も容易なので手間も軽減されていると感じます」
https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/53765
▼利用サービス:AOSBOX Business
▼企業名:株式会社ハイブリッチ ▼従業員規模:20~50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
クラウドサービスを選ぶときの5つのポイント
クラウドサービスを選ぶ際には、次の5つのポイントを押さえておきましょう。
自社に必要な機能があるか
クラウドサービスによって提供している機能が異なります。自社に必要な機能を洗い出したうえで選ぶことをおすすめします。
特にテレワークを促進したい場合は、パソコンやスマートフォンなどマルチデバイスに対応しているサービスがよいでしょう。さらにアクセス権限を細かく設定したり、さまざまなサービスと連携できたりと汎用性の高い機能があると業務効率化に役立ちます。自社で現在利用しているサービスやソフトウェアと互換性があるかもチェックしてください。
OSやデバイスが対応しているか
OSやデバイス、アプリケーションの種類が自社に適しているかどうかも重要なポイントです。ほとんどのクラウドサービスはWindowsOSやLinuxOSに対応しています。しかし、中にはどちらか片方にしか対応していない可能性もあるため、事前に利用できるOSを確認しておきましょう。特に働き方改革を促進したい場合は、さまざまなOSやデバイスに対応しているサービスを選ぶことをおすすめします。
セキュリティレベルが高いか
クラウドサービスを利用するときは、企業の重要情報をインターネット上に保存することになります。そのため暗号化通信やIPアドレス制限、端末認証などセキュリティ対策が厳重にされている製品を選びましょう。単純に料金の安さだけで決めてしまうと、セキュリティが不十分で不正アクセスや情報漏えいの被害を受ける可能性もあります。
そのため、次の点をチェックしましょう。
・国際基準に則っているか
・セキュリティポリシーが自社の求めているレベルに達しているか
・サポート体制が充実しているか
サポート体制が充実しているサービスなら、トラブルが発生した際も速やかに対応してもらえるので業務への影響を軽減できるでしょう。
バックアップ機能があるか
バックアップ機能は必須です。クラウドのバックアップ先はベンダーにより異なりますが、基本的に複数拠点にバックアップセンターを設置してあります。さらに冗長化(多重化)によって災害時にも速やかに復旧できるような体制になっていることがほとんどです。万が一自社が災害に遭ってもデータは保管されているため、早期に立て直せるでしょう。
またクラウドでバックアップすることで、オンプレミスのように自社で保守管理する負荷がなくなり、人的リソースやコストを削減することが可能です。もしデータ量が増大しても、容量を増やして拡張すればすぐに対応できます。
操作性がよいか
画面の見方や機能の使い方がわかりやすく、直観的に操作できるサービスを選びましょう。機能が豊富でも操作が複雑なサービスを導入してしまうと「社内で浸透せず、結局従来のやり方に戻してしまった」という事態にもなりかねません。導入コストが無駄になってしまわないよう、実際に利用する従業員の意見も取り入れるとよいでしょう。
クラウドサービスの中には無料の試用版を提供しているところもあります。まずは無料トライアルで画面構成や操作感を確認してから検討することをおすすめします。
まとめ
クラウドはインターネット経由でアプリケーションやインフラなどのサービスを利用できる仕組みのことです。オフィス外でも時間や場所を問わず業務を遂行でき、リモートワークには欠かせない環境といえます。
クラウドの実装モデルやサービス形態には複数の種類があるため、それぞれの特徴や違いを知ったうえで自社に適した環境を選定しましょう。実際に製品を選ぶ際は、機能やセキュリティレベルの高さ、操作性などに注目して比較検討することをおすすめします。製品の中には無料試用版を提供しているものもあります。導入前に使いやすさを確認しておくのがよいでしょう。
投稿 クラウドとは?環境やサービスなど基礎知識を分かりやすく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 BtoBとは?BtoCとの違いやマーケティングのポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、BtoBとは何なのか、BtoCやCtoCとの違い、BtoBを展開している企業の事例、そしてマーケティング手法まで、BtoBに関する知識を網羅的に解説します。
BtoBとは?
BtoBは「Business to Business」の略で「B2B」とも表記され、企業と企業(官公庁なども含みます)が取引を行うビジネスモデルを示します。たとえば自動車メーカーが部品メーカーから部品を購入したり、スーパーなどの小売店が食品加工メーカーから食料品を仕入れたりすることもBtoBです。あるいは企業向けのソフトウェアを開発している企業からソフトウェアを購入することもBtoBです。さらに、物質としてのモノ以外にも、経営コンサルティングやクラウドサービスの売買もBtoBに含まれます。
つまり、企業が自社だけではまかなえないモノや解決できない課題のソリューションを売買する取引がBtoBです。
BtoBとBtoCの違い
BtoBの理解を深めるために、BtoCを比較しながら、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。
BtoCとは?
BtoBと比較されやすいビジネスモデルにBtoCがあります。
BtoCは「Business to Consumer」の略で、企業が個人に対して商品やサービスを提供するビジネスモデルです。BtoCの代表的な売り手は、スーパー、百貨店、ホームセンター、家電量販店、自動車ディーラー、アパレル専門店などの小売業や、レストランやカフェ、居酒屋などの飲食店です。ほかにもホテルやリラクゼーション、遊園地、病院などもBtoCです。
BtoCは、住宅や高級車のような例外もありますが、BtoBと比較すると個々の取引金額は低いことが特徴です。
BtoBとBtoCの違い
BtoBとBtoCの違いについて、4つのポイントで解説します。
◆電子商取引での比較
| BtoB | BtoC | |
| 市場規模 | 大(334.9挑円) | 小(19.3兆円) |
| 取引金額 | 大(数百万円~数億円) | 小(数百円から数十万円程度) |
| 取引の継続性 | 安定(継続性が高い) | 不安定(変動要素が多い) |
| 決済者 | 企業・組織 | 消費者個人 |
市場規模の大きさ
BtoBとBtoCは、市場の規模が異なります。経済産業省の調査によると、2020年の日本国内のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模が19.3兆円だったのに対し、BtoB-EC(企業間電子商取引)市場規模は334.9兆円と約17倍の違いがあります。
取引金額の大きさ
BtoBは1回の取引で動く金額がBtoCに比べて大きくなります。BtoCでは、1回の取引で動く金額は数百円から数十万円程度です。もちろん、例外的に車や住宅など、数百万円から数千万円の取引もありますが、決して日常的に行われる取引ではありません。
しかし、BtoBでは数百万円から数億円の取引が日常的に行われています。たとえば1つひとつは数百円単位の部品や材料でも、一度の取引で扱われる数が膨大なため金額も大きくなります。
取引の安定さ
BtoBはBtoCに比べて取引が継続的で量の変化も少なく安定しています。BtoCの場合は、たとえば服であれば、その季節の流行や気候、競合の状況、消費者の懐具合などにより売上は大きく変化します。また、消費者は常に同じ店から定期的に服を購入する傾向は小さく、継続的な取引が行われる可能性は小さくなります。
企業間の取引であるBtoBでは、購入者があらかじめ計画した予算を確保しているため、取引金額は比較的安定しています。また、取引相手を決めるまでに時間と労力がかかる一方で、一度取引が成立すれば継続的な取引が行われることが一般的です。
決裁者の違い
BtoBとBtoCでは購買の意思決定者が異なります。BtoCでの決裁者は消費者個人ですから、意思決定のプロセスは非常にシンプルです。商品やサービスによっては家族や友人たちなどと相談することもありますが、基本的には購入者1人の意思により購入が決定されます。たとえば服を買う、食品を買う、電化製品を買うなど、購入者は自分1人の意思で購入を決定します。住宅や車などは、購入を決める際に共有する家族の合意を得る必要がある場合もありますが、それでもプロセスはシンプルです。
一方、BtoBの場合は、購入者が企業であり、一度取引を始めると継続することが多く、さらに動く金額も大きくなり、その取引内容が企業の業績に影響を与えることから、購入決定者には大きな責任が生じます。そのため、新規の取引開始の意思決定を担当者の一存で行うことができず、稟議を起案して上層部の承認を得るなど、相応の手続きと時間が必要になります。
BtoB、BtoC以外のビジネスモデル
BtoB、BtoCと類似の表記がされるビジネスモデルについて紹介します。
例として具体的な企業名も紹介します。
BtoE(企業→従業員)
BtoEは「Business to Employee」の略で、企業が自社の従業員に対して製品やサービスを提供するビジネスモデルです。もっとも身近な例としては、社員食堂や社内コンビニ、社員寮、スポーツクラブの優待などがあります。近年ではオフィスでも気軽におやつを購入できる「オフィスグリコ」や、会社が一括購入できる「オフィスでヤクルト」など、他社が提供するサービスを導入する例もあります。
元来は福利厚生の意味が強く、社員の定着率や人材確保に結びつける目的が中心でしたが、近年では従業員も消費者であるとの考えから、自社商品やサービス、企業のファンになってもらい、評判が自発的に拡散されることを期待している企業も増えてきています。
BtoG(企業→行政)
BtoGは「Business to Government」の略で、企業が国や自治体などの公的機関を相手に行うビジネスモデルです。たとえば公共事業において、入札を通じて企業が参加する取引があります。また、省庁内のインターネットインフラの構築やホームページの制作運用も増えています。
近年では、ふるさと納税へのプラットフォーム提供や返礼品の選定など寄付者への業務を代行している楽天株式会社の例や、自治体向けの広告事業を展開している株式会社ホープの例があります。ホープ社は広報誌やホームページ、公務員の給与明細の裏面を広告媒体として活用するなどの事業を展開しています。
DtoC(メーカー→消費者)
DtoCは「Direct to Consumer」の略で、メーカーが消費者に直接販売するビジネスモデルです。DtoCは以前からもカタログ販売や通信販売として行われてきたビジネスモデルですが、インターネット上で決済できるようになったことで、多くの企業が自社ECサイトを立ち上げて参入するようになりました。
また、SNSを活用したマーケティング手法を駆使することも近年のDtoCの特徴です。DtoCでは、顧客からのフィードバックが直接得られるため、顧客のニーズを製品やサービスに迅速に反映させることができることや、中間マージンを省くことで利益率を高めることができます。
DtoCの成功ブランド例としては、ビジネスウェアのカスタムオーダーサービスのFABRIC TOKYO、メンズコスメのベンチャー企業であるバルクオム、クラフトチョコレートをカカオ豆の仕入から製造・販売まで一貫して行っているミニマル、植物由来のヘアケア・スキンケア・ボディケア用品などを製造販売しているボタニストなどがあります。
GtoC(行政→消費者)
GtoCは「Government to Consumer」の略で、国や自治体が企業や個人に向けてサービスを提供することです。2019年5月に「デジタルファースト法」が国会で可決されるとGtoCの注目度が高まりました。同法は行政手続きを電子申請に統一することをめざす法律だからです。
たとえば住民票の電子申請やワクチンパスポートの発行、e-Taxによる税金のオンライン申告、道路や水道の整備、学校や図書館の運営、公共施設の電子予約などが挙げられます。少子高齢化が進み、地方創生の機運が高まっている中、GtoCの需要は高まると考えられます。
CtoC(消費者→消費者)
CtoCは「Consumer to Consumer」の略で、個人間取引を示します。インターネット上でCtoCのプラットフォームが普及したことで、不特定の消費者同士が気軽に取引を行える環境が整いました。CtoCの例として、ヤフオク!のようなネットオークションやメルカリのようなフリーマーケットがあります。個人のスキルを売買するココナラなどもCtoCの一種といえます。
BtoBマーケティングとは?
BtoBでは高額な取引が多く、提案から受注までに数年といった長い期間を必要とする場合もあります。しかし、一度契約されるとリピートされることが多く、長期的かつ継続的な取引が行われる期待ができます。また、一度取引が始まった顧客からは、オプションの購入やアップセル商品・サービスが購入される確率も高くなります。
そのため、BtoBは顧客の母数が限られていますが、長期的かつ継続的な取引が見込めるため、より多くのリード獲得と既存顧客のフォローが重要になります。
BtoBマーケティングが注目されている理由
これまでBtoBを経営の軸にしてきた企業の多くはマーケティングの専門部門をもつことは少なく、営業部門などがマーケティングに近い機能を内包していることが一般的でした。しかし、市場がグローバル化し、需要が飽和状態となった成熟市場では、商品やサービス自体での差別化が難しくなったため、従来の顧客へのアプローチ方法では顧客の囲い込みと売上の両方を伸ばすことが難しくなってきました。
しかも、インターネットによる情報収集が容易になり、顧客自身が積極的に商品やサービスを比較検討することができるようになったことからも、従来の営業手法の有効性が薄れてきています。そこでマーケティングの重要性が増してきました。
顧客の情報収集の変化
顧客がインターネットで直接情報収集できる現在、営業が訪問時に持ち込む情報によって差別化することが困難になってきました。顧客はむしろ、Webサイトやメールマガジン、ホワイトペーパーなどから情報を得ることに利便性を感じるようになってきています。そのため、Webサイトやメールマガジン、ホワイトペーパーを使って顧客にアプローチできるマーケティング部門がリード(見込み顧客)と接触する機会を増やすことが重要になってきました。
サービスモデルの変化
クラウドサービスの普及に象徴されるように、ハード製品も含めてあらゆる商品やサービスがインターネット上のサービスと連携するようになりました。このことは、顧客は常に他社の商品やサービスに乗り換えることが容易な状況をつくり出しています。したがって、一度契約した顧客に対しても、継続的に有意義な情報を提供したりサポートを行ったりすることで、良好な関係を維持する必要があります。
購買プロセスの変化
インターネットが普及したことで、顧客の購買プロセスが変わってきています。顧客は、自社の課題解決のために能動的に情報収集を行うことが容易になってきました。そのため、従来型の営業であるプッシュ型アプローチよりも、マーケティングによるプル型のアプローチが有効になってきました。
BtoBマーケティングの特徴
ここではBtoBマーケティングの特徴を、BtoCと比較しながら解説します。
BtoBマーケティングの特徴(BtoCマーケティングとの比較)
| BtoB | BtoC | |
| 取引期間 | 長期的 | 短期的 |
| 売上 | 継続的 | 単発的 |
| 対象顧客 | 限定的 | 無制限 |
| 市場開拓 | 長期 | 短期 |
| 商材単価 | 高い | 低い |
1.長期的な取引が見込める
BtoCマーケティングでは、商品がヒットすれば一時的に売上が急伸しますが、市場が変化しやすいため、売上が安定しません。一方、BtoBマーケティングでは、一度契約した顧客とは長期にわたって安定した取引が継続される傾向が強いため、トータルでは高い収益性を見込めます。
2.継続的な売上が見込める
BtoCでは、顧客が個人の消費者であるため、1つの商品・サービスに対する取引量が小さく、また短期間で商品・サービスを乗り換えられてしまうことも頻繁に起こり得ます。一方、BtoBでは基本的に企業などの法人が顧客で計画的な予算をもとに取引が行われるため、1つの商品・サービスに対する取引量が大きく長期にわたって取引が継続されやすくなります。その結果、継続的な売上が見込めます。
3.対象顧客数が有限
BtoCの顧客としては訴求すべき対象は世界中の人々となり、ターゲット数を予測することは困難です。一方、BtoBの顧客は、主に特定の業界や規模に限られるため、ターゲットは数百~数千に絞られます。
4.新規開拓までに時間がかかる
BtoBでは、新規開拓に時間がかかります。見込み顧客に対して、自社を知ってもらうプロセスがあります。1件の新規顧客を獲得するためには、見込み顧客の開拓、アポ取り、訪問、情報収集、提案のプロセスを経なければなりません。このプロセスを通じて、自社や営業担当者への信頼を得る必要があります。また、意思決定や決裁の権限をもっている担当者にたどり着き、信頼関係を構築する必要があります。
また、企業や組織の課題解決や経済的合理性を検討するため、課題の認知から製品・サービスの導入までに、念入りな情報の精査と複数の意思決定者の調整など、購入するまでに要するプロセスが多く、期間も長くなります。
一方、BtoCでは顧客である消費者は自身の一存で商品・サービスの購入を即決することができます。そのため、BtoCにおける広告では、感情を刺激するコピーやイメージが使われることも多くあります。
5.商材の単価が大きいため、リスク管理の責任が大きい
BtoCの商材は、個人の消費者の予算で購入できる価格設定であるのに対して、BtoBの商材の価格は企業の予算で購入できる価格設定になっているため、金額が大きくなります。そのため、ときには単独の決裁者が決裁できる金額を超えることもあり、その場合は複数人が承認しなければ契約できません。大きな金額が動くため、販売担当者にとっても購入担当者にとっても、リスク管理の責任が大きくなります。
BtoBマーケティングのプロセス
そこで、BtoBマーケティングが必要になってきます。ここではBtoBマーケティングのプロセスについて解説します。
BtoBマーケティングは、営業に引き渡して契約にたどり着くまで、リードジェネレーションとリードナーチャリング、リードクオリフィケーションの3つのステップを踏みます。
リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)
BtoBマーケティングは新規リードの獲得から始まります。新規リードの獲得とは、自社の製品・サービスを購入する可能性のある企業の担当者情報を獲得することです。担当者の情報には、企業名、部署、連絡先などがあります。このように、見込み顧客の情報を獲得する活動をリードジェネレーションと呼びます。
リードジェネレーションは顧客情報を獲得するマーケティングで、以下のような活動があります。
・メディア露出(PR)
・オウンドメディア
・広告
・SEO
・SNS運用
・展示会
・各種イベント
リードジェネレーションでは見込み顧客を獲得するため、その後の営業活動の効率を高めることができます。このとき、見込み度が低い顧客を獲得した場合は、次のリードナーチャリングが有効になります。
リードナーチャリング(見込み顧客の育成)
リードを獲得した後は、リードナーチャリングと呼ばれる見込み顧客の育成段階に入ります。獲得した見込み顧客の自社製品・サービスに対する購買意欲を高めるために、顧客に有意義な情報を提供し続けることで継続的な接点をもち続けるようにします。
リードナーチャリングは、獲得した顧客の購買意欲を高めるために顧客を育成するマーケティングで、以下のような活動があります。
・メールマガジン
・オウンドメディア
・テレアポ
・訪問営業
・カンファレンス
・セミナー
・イベント
・SNS運用
リードクオリフィケーション(見込み顧客の選別)
リードクオリフィケーションとは、顕在化したリード(見込み顧客)から購入可能性の高い見込み顧客を選別することです。主に下記のような活動があります。
・シナリオ設計
・スコアリング
・データマネジメント
・履歴や属性の分析
このようなリードクオリフィケーションをすることによって、商品やサービスに関心がある確度の高い見込み顧客からコンタクトを取ることで、効率よく営業にバトンタッチし、商談・契約につなげることができます。
リードクオリフィケーションで成果を出すには、まず事前に「シナリオ設計」を考えておく必要があります。シナリオ設計とは、顧客が商品やサービスと接点を持ち、商談・契約に至るまでのリードジェネレーション、リードナーチャリングも含めた一連のプロセスの設計を指します。これら3つの活動は連動しているため、シナリオ設計を明確にしておかないと、リードクオリフィケーションでよい結果を出すことができません。
購入の可能性が高い見込み顧客を絞り込む方法としては、見込み顧客のアクションや属性などに点数をつける「スコアリング」という手法を用います。スコアリングでは、高い点数がついた見込み顧客を購入可能性が高い見込み顧客として考えます。
「データマネジメント」とは、データを適切に管理してあらゆる業務に活用するための知識です。データマネジメントではデータの正確性、データが最新情報で更新されているか、データの細かさが揃っているかが求められます。
最後は結果の良し悪しを含めた蓄積された履歴や属性のデータを分析しながら、精度を上げていきます。
BtoBマーケティング施策
BtoBのマーケティング方法について、リードジェネレーションとリードナーチャリングの主な施策について紹介します。
リードジェネレーション
メディア露出(PR)
新聞やテレビ、ラジオ、Webなどのメディアに取り上げられることがメディア露出です。メディア露出による効果は以下の通りです。
メディア露出(PR)の意義
- 広く認知される:メディア露出のもっとも大きな効果は広く認知されることです。しかも、これまで接点がなかった潜在顧客に認知される可能性が大きくなります。
- 信頼度が上がる:メディアに露出すると、「メディアが取り上げたほどだから信頼できるだろう」と受け止められやすくなります。また、メディアに取り上げられたことがSNSで拡散される可能性が高まります。
- 第三者の意見を知ることができる:メディアに取り上げられると、メディアを通じて第三者による評価を知ることができます。
- 社員の意欲が高まる:メディアで紹介されることで、社員が自社の製品・サービスに誇りをもち、仕事への意欲を高める可能性があります。
- 人材を集めやすくなる:メディアに取り上げられると、求職者への認知が高まることと、就職先としての信頼感が増すため、求職者に選ばれやすくなります。
オウンドメディア
近年では、顧客は製品・サービスの購入を検討する際に、まずWeb上から情報収集を行うので、当然、製品・サービスを提供している企業の公式サイトあるいはオウンドメディアをチェックしています。そのため、自社サイトで製品・サービスの掲載情報を充実させたり、ホワイトペーパーのダウンロードを可能にしたりしておくことは、大変重要な施策となります。
また、オウンドメディアはリードジェネレーションだけでなく、リードナーチャリングにおいても非常に重要な役割を果たします。オウンドメディアは認知獲得のみならず、リードの興味・関心を維持し、ファン化するためには欠かせない施策となっています。
広告
顧客が製品・サービスの情報をキャッチするのはWebメディアである可能性が高いため、インターネット上の広告対策が重要となります。具体的には以下のような広告の種類があります。
広告の種類
- リスティング広告:検索エンジンで特定のキーワードの検索が行われた際に、検索結果の画面上に表示されるテキスト形式の広告です。コンテンツのSEOよりも即効性があり、予算に合わせた柔軟な運用が行えることがメリットです。
- ディスプレイ広告:バナー広告とも呼ばれ、Webサイトの広告枠に表示されるテキストや画像、動画を利用した広告です。凝った作り込みができるためインパクトのある広告を表示することができますが、リスティング広告に比べてコンバージョン率は低くなる傾向があります。
- ターゲティング広告:自社サイトや広告から製品・サービスのランディングページ(LP)を訪れたユーザーをcookieで認識して、その後ユーザーが閲覧するさまざまなサイトで自社製品・サービスの広告を表示させる手法です。BtoBでは製品の検討期間が長期になりやすいため、接触回数を増やすことが有効だと考えられます。
- SNS広告:SNS広告とは、FacebookやTwitter、LINE、Instagramなどで配信される広告を示します。SNSでは利用者の属性情報が登録されているため、ターゲットを絞り込んだ訴求が行えます。
SEO
SEO(Search Engine Optimization)は自社のコンテンツサイトが、検索エンジンで上位表示されるために行う対策です。オーガニックな検索結果において上位表示されたサイトは閲覧される機会が増え、信頼度もユーザーのニーズとのマッチ度も高くなります。SEOとして重要なことは、良質なコンテンツを高頻度で継続的に発信を続けることと、検索エンジンに高評価されるコンテンツやサイトの作り込みを行うことです。ただし、SEOはリスティング広告のような即効性はないので、長期的なマーケティング戦略として取り組む必要があります。
SNS運用
最近では、多くの企業がTwitterやfacebook、InstagramなどSNSを運用するのが当たり前になっています。企業の情報収集の手段がオンライン化したことによって、SNSによる情報発信が極めて重要になっています。SNSマーケティングを行うことで得られる効果としては、潜在顧客の獲得、見込み顧客への定期的な情報提供、関係性構築などがあります。SNSで効果的なマーケティングを行えば、自社の商品やサービスを提供できる潜在的な顧客との接点をつくることができます。
展示会
展示会は、顧客ごとに訪問しなくても自社製品・サービスに興味をもった見込み顧客が自ら足を運んでくれるため、営業部員を増員しなくても効率よくコンバージョン数を増やすことができます。しかも、対面営業ができるだけでなく、自社製品を体験してもらえるメリットがあります。ただし、展示会を開催するためにはコストがかかる点に注意が必要です。また、来場者が同時に問いかけてくる場合に備えて、自社製品・サービスに詳しい人員を待機させておく必要があります。
各種イベント
自社が主催するセミナーやカンファレンスをはじめ、他社が主催する外部イベントへの協賛や出展、あるいは登壇することもBtoBマーケティングに効果があります。出展や登壇をすることで、もともと自社の製品・サービスを目的としていなかった潜在顧客にアピールできますし、営業担当者が参加していればその場で商談への足がかりを得られる可能性も高まります。また、自社の認知度が低かった場合は、集客力のある外部イベントに出展や登壇することは、認知度を上げる機会となります。
リードナーチャリング
メールマガジン
BtoBマーケティングではさまざまなインターネット上の訴求方法が生まれてきましたが、メールは今も有効なマーケティングツールです。その理由は、以下の通りです。
さまざまな情報を告知できる
メールは固定されたWebサイトと異なり、都度さまざまな情報を発信することができます。新製品情報やアップデート情報、イベント情報、お役立ち情報、ニュースなどです。
定期的なフォローが行える
BtoBにおいてはリードナーチャリングの期間も購入検討期間も長くなる傾向があります。そのため、自社から定期的にフォローすることにより、関係性を維持する必要があります。このためのツールとしてメールは有効です。
確度の高いリードの絞り込みに使える
リード(見込み顧客)の中には、まだ購入意欲が低い段階のリードもいれば、購入意欲が高まっている段階のリードもいます。このとき、メールで案内したURLのクリック率などをもとにリードを購入意欲の高さで分類することで、アプローチ方法を使い分けることができます。たとえば購入意欲が高まっているリードだけを絞り込めれば、無駄な架電を省くことができます。
テレアポ
テレアポはテレフォンアポイントメントの略で、顧客に電話で営業をかける手法です。顧客からのアプローチを待つのではなく、積極的に顧客獲得を行います。オンラインマーケティングが普及したことで、テレアポに古さを感じる人は増えていますが、すべての顧客が自らICTを駆使して能動的に情報収集をできているわけではありません。このような顧客にはテレアポは有効なアプローチ方法です。
テレアポはその段階ですぐに商談につながることはありませんので、長く話すことは逆効果です。手短にポイントを押さえたトークを行うべきです。一方、テレアポは直接顧客とコミュニケーションがとれるため、顧客の課題や状況をヒアリングすることで潜在層へのアプローチを可能にします。
ただしテレアポを行う人は、相手から冷たくあしらわれたり、理由を告げられずに切られてしまったりすることも少なくありません。あらかじめ気の持ち方や対処方法を準備しておく必要があります。
訪問営業
テレアポが取れたら訪問営業を行います。訪問営業は顧客と対面で課題やニーズを聞き出すことができる貴重な機会ですから、行き当たりばったりで営業するのではなく、事前に顧客の業界動向や顧客企業の現状などについて調べておきます。顧客の業界や企業について相手と共通の知識を持つことで信頼を得やすくなり、効率よく顧客のニーズや課題を引き出すことができます。
カンファレンス
カンファレンスでは、専門家や実践者が登壇して参加者と議論したりするため、自社が提供する製品やソリューションについて、より説得力のある訴求を行えます。しかもカンファレンスは明確なテーマを掲げて開催されているので、そのテーマに興味をもっていたり、関連する課題を抱えていたりする人が集まります。さらに、カンファレンスでは一度に多くの来場者を集めることができます。これらのことから、カンファレンスは継続的に新規リードを獲得できるマーケティング施策の1つであるといえます。
BtoBマーケティングを成功させるポイント
BtoBマーケティングを成功させるためには、いくつものポイントがあります。プロセスに沿って確認しておきましょう。
ニーズを把握する
商品・サービスを販売するためには、ニーズをもったターゲットにアプローチしなければなりません。しかし、潜在顧客の中には、自らのニーズに気づいていない場合があります。そのようなニーズを掘り起こすためにもマーケティングは必要です。BtoBには意思決定者が複数であることや検討期間が長いこと、印象や衝動ではなく経済的合理性がなければ購入しないなどの特徴があります。そのため、ターゲットのニーズを的確に把握する必要があります。BtoBはBtoCに比べて母数が小さいこともあり、ターゲットを取りこぼさないことが重要です。
差別化を図る
差別化とは、競合他社や同業他社に比べて、自社の製品・サービスがどのように優れているのかを具体化することです。差別化は、価格が安いことや単に異なっているということではなく、高くても競争優位になる差異があることでなければなりません。
信頼を得る
BtoBでは購入までの検討期間が長期間になることが一般的です。その間、Webサイトやメールマガジン、展示会、セミナーなどさまざまな検討機会が訪れ、他社の情報を得る機会も増えます。そのため、販売者は購入者との間に信頼関係を構築しておかなければ、ささいなきっかけで競合他社に顧客を奪われてしまう可能性があります。また、企業は経済的合理性により購入を決定しますが、その中には販売価格が信頼できる妥当性をもっていることや、アフターフォローがしっかり行われることに対する信頼感の強さも含まれます。
タイミングを狙う
BtoBにおいては、顧客のニーズが明らかになり、自社製品・サービスがそのニーズに応えられると判明しても、タイミングが合わなければ契約に至ることは難しい場合があります。BtoBでは取引金額が大きくなるため、顧客側で予算を確保できているかどうかを見極めることが重要になります。このタイミングを見極めないままで闇雲に売り込みをかけると、敬遠されてしまう可能性があります。
ロイヤルティを高める
顧客のロイヤルティ(信頼・愛着心)を高めるために、営業であれば足繁く通う必要がありましたが、BtoBマーケティングではICTツールを利用してより効率的に働きかけることができます。ロイヤルティが高い状態で商談に入るタイミングをつかむことができれば、商談は受注までスムーズに進む可能性が高まります。また、ロイヤルティが高ければ、契約後も長期的な利益を出し続けることができます。同時に、競合他社への乗り換えを防げる可能性も高まります。
キーマンを押さえる
BtoBでは企業を相手にするため、意思決定者であるキーマンにたどり着くことが重要です。キーマン以外の人にいくらアプローチしても、無駄な労力を費やしてしまいます。また、キーマンは1人とは限りません。競合製品のリサーチをしている人もキーマンですし、製品・サービスの導入を推進する担当者もキーマンです。そして、決裁権をもち最終的な意思決定を行う人もキーマンです。これらのキーマンを押さえて各人に有益な情報を提供し、効率的なマーケティングを行う必要があります。
営業と連携する
多くの企業ではマーケティング部門とインサイドセールス、フィールドセールス、そしてカスタマーサービスなどが十分な情報共有を行えず、連携もとれないまま活動していることがあります。情報共有が十分に行われていないと、マーケティング部が獲得してナーチャリング(育成)したリードが、営業によりクローズされたのか、アップセルされたのかといったフィードバックが行われず、確度の低いリードを獲得し続けてしまう可能性があります。BtoBマーケティングを成功させるためには、各部門との情報共有と連携が欠かせません。
BtoBマーケティングの支援ツール
実際に、BtoBマーケティングの支援ツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのBtoBマーケティングの支援ツールを紹介します。
(2022年1月5日時点のレビューが多い順に紹介しています)
ABM(アカウントベースドマーケティング)
ABMは、BtoB企業におけるマーケティング戦略の1つです。自社にとって有益な顧客を選び、それぞれに合わせた戦略を立てて利益を最大化することがABMの手法です。
FORCAS
「FORCAS」は150万社以上の企業データから、自社製品・サービスと相性のよい企業をリストアップするターゲティングを行うことで、確度の高い潜在顧客へのアプローチを効率化できるBtoB向けの顧客戦略プラットフォームです。
uSonar
「uSonar(ユーソナー)」は、さまざまな顧客情報を統合管理するクラウド型のツールです。DMPやMA、CRM、SFAなどと連携することでマーケティングのDX化を実現します。
BowNow
「BowNow」は機能を厳選して使いやすくしたMAツールです。特にリストアプローチの自動化により、コストパフォーマンスの高いマーケティングを行えます。
SFA
SFAとは、「営業支援システム」です。企業の営業活動における情報収集や業務プロセスを自動化することで、情報全般をデータ化して、蓄積・分析することができるシステムを指します。
SFAについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
SFAとは?CRMとの違いや導入のメリット・おすすめツール5選
Salesforce Sales Cloud
「Salesforce Sales Cloud」は外出先でも素早く顧客にアプローチ。AIが組み込まれたCRMは、営業プロセスにあわせて柔軟にカスタマイズでき、あらゆる局面でセールスをサポートできます。営業管理、サポート状況、マーケティングデータを1カ所に集約。営業にまつわるプロセスをまとめることで、どのチャネルからでも、すべてを関連づけて観察できます。
Salesforce Sales Cloudの製品情報・レビューを観る
Senses
「Senses」は営業支援サービスで、蓄積された営業に関わるあらゆる情報を効率的に管理し、現場の営業担当者が効果的な営業活動を行えるように支援する高度なAIエンジンを搭載しています。
Knowledge Suite
「Knowledge Suite」は、統合ビジネスアプリケーションのクラウドサービスで、集計・分析ツールから問い合わせ管理、SFA、CRM、グループウェア、そして他のシステムとの連携機能などを搭載しています。
MA(マーケティングオートメーション)
MAは、収益向上を目的としてマーケティング活動を自動化するツールです。MAを導入することで、見込み顧客の興味関心に合わせたコミュニケーションが可能となります。
MAについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
MA(マーケティングオートメーション)とは?おすすめMAツール7選まで完全網羅
SHANON MARKETING PLATFORM
「SHANON MARKETING PLATFORM」はMAツールで、新規リードの獲得からナーチャリング、行動履歴の管理などマーケティング業務に必要な作業を自動化します。
SHANON MARKETING PLATFORMの製品情報・レビューを観る
Salesforce Pardot
「Salesforce Pardot」はクラウド型のMAで、マーケティング活動とセールス活動を連携し、さらにSalesforceが提供するさまざまなツールとも連携することで、営業の効率化と成果の最大化を支援します。
Salesforce Pardotの製品情報・レビューを観る
Adobe Marketo Engage
「Aobe Marketo Engage」は、世界39カ国以上の企業で採用されているMAです。BtoB、BtoCを問わずあらゆる規模と業種において、ユーザーの1人ひとりと適切なタイミングや内容、手段でコミュニケーションをとることができます。
Adobe Marketo Engageの製品情報・レビューを観る
CRM
CRMは顧客との関係性、コミュニケーションを管理し、自社の従業員と顧客との関係を一元的に把握できるようにするツールです。情報の一元化によって顧客をより深く理解することで、営業活動の向上、サービス、マーケティング、経営戦略などに生かすことができます。
CRMについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
Salesforce Sales Cloud
「Salesforce Sales Cloud」はSFAとCRMが統合されたシステムで、新規顧客の発掘からナーチャリング、そして早期受注を実現するためにあらゆる機能が備わっています。
Salesforce Sales Cloudの製品情報・レビューを観る
Senses
「Senses」は、営業管理や分析などの機能の使いやすさにこだわりがあります。蓄積された過去の営業情報から現在の営業活動に役に立つノウハウを活用できるよう、高度なAIエンジンを兼ね備え、導入企業は不動産や人材、広告代理店など多岐にわたります。
Zendesk
「Zendesk」は、メールやWebフォーム、ソーシャルメディアなどのさまざまなチャネルからの問い合わせを一元管理し、ワークフローのオートメーションやサポートのパフォーマンス測定などを行えるヘルプデスクソフトウェアです。
メールマーケティング
メールマーケティングは、メールを活用したマーケティング全般を指します。特にBtoB企業では、SNSが普及した今日もメールを中心にコミュニケーションが行われるので効果的な方法といえます。
Twilio SendGrid
「Twilio SendGrid」は、クラウド型のメール配信サービスです。開封やクリックなどの配信状況のトレースやメールが届かなかったバウンスの自動処理、配信停止管理などを効率的に行え、他システムと連携するためのAPIも豊富です。
MailChimp
「MailChimp」は、直感的な操作でメールマガジンを配信できるツールです。HTMLメールもエディターで簡単に作成でき、開封率やクリック率などのレポート機能も充実しています。
配配メール
配配メールは、メールマガジンやステップメールを配信できるメールマーケティングツールです。直感的な操作と必要最低限の機能、専任スタッフの手厚いサポートが特徴です。
Webサイト制作
Webサイト制作とは、ホームページやオウンドメディアなどのWebサイトの制作を指します。1人でも始められますが、ページのデザイン、画像の作成、サイト制作の進行管理など、分業して制作を行うことが多いです。
Adobe XD
「Adobe XD」は、Webサイトやモバイルアプリのデザインを支援するUX/UIソリューションで、共同編集が可能なためチームによる作業を効率化できます。Adobe CC・Creative Cloudと連携ができ、直感的な操作が可能です。
Dreamweaver
「Dreamweaver」は、Webサイトのデザインからコーディング、ファイル管理を視覚的に行えるソフトです。
Sketch
「Sketch」は、WebサイトやアプリのUIデザインツールです。機能の豊富さに加え、プラグインでカスタマイズすることもできます。エンジニアとの連携を効率化するコラボレーションツールやプロトタイプ作成ツールにも対応しています。
CMS
CMSは、Webサイトのコンテンツを構成するテキストや画像、デザイン・レイアウト情報などを一元的に保存・管理するシステムのことです。CMSが必要に応じて情報を取り出して、Webページを自動的に生成してくれます。
CMSについて詳しく知りたい方はこちらの記事をご確認ください。
CMSとは?メリットや導入ポイント、活用事例、おすすめツール5選を紹介
WordPress
「WordPress」はWebサイトを構築・運営するためのオープンソースのCMSです。個人のサイトから企業のサイト、Webマガジンやニュースサイトまで幅広く利用されています。また、デザインテンプレートやプラグインも豊富です。
おりこうブログ
「おりこうブログ」は、Webサイトの作成やアクセス解析、メッセージ配信、カタログ作成などのツールが豊富なCMSです。
Movable Type
「Movable Type」は、安全で効率的なWebサイト運用を可能にするCMSプラットフォームです。豊富な機能で、大規模なコーポレートサイト、メディアサイトの構築・運用が可能です。
Web接客ツール
Web接客ツールは、Webサイトに訪れたユーザーに対して、その属性や閲覧履歴などといった情報をもとに、Webページ上で適切な対応・案内を行うツールのことをいいます。顧客データベースを参照しながら、個々人に最適なコンテンツ提供やサポートを実施するCXプラットフォームへの発展も進んでいます。
ChatPlus
「ChatPlus」は自由度が高いデザイン機能やチャットボットの挙動設定の多さが特徴です。すべてのAPIが開放されていることで、訪問者情報から行動属性まであらゆるデータを送受信できるため、柔軟なシステム連携を実現します。
Flipdesk
「Flipdesk」はチャット対応やクーポン発行、お知らせ配信など、訪問者の状況に自動的に対応することでリアル店舗のような接客をネットショップで実現します。
KARTE
「KARTE」はCX(顧客体験)プラットフォームです。Webサイトやスマートフォンアプリを利用している顧客1人ひとりの行動データを可視化し、適切なタイミングで適切なアクションを行えます。
SEOツール
SEOツールとは、特定キーワードにおける検索エンジンの表示順位を上げるための支援ツールです。SEOツールは主に適切なキーワードの選定やコンテンツの最適化、キーワードごとにおける競合サイトとの順位比較などの機能をもちます。
Google Search Console
「Google Search Console」は、Googleでの検索におけるインプレッション数やクリック数、掲載順位などを計測できるSEOツールです。
Google Search Consoleの製品情報・レビューを観る
SEARCH WRITE
「SEARCH WRITE」は誰でもSEOのPDCAを回せるように支援するツールです。CV獲得に貢献するキーワードがわかったり、キーワードごとに検索上位の記事見出しを自動で取得して上位表示される記事の書き方を示したりします。
Keywordmap
「Keywordmap」は、SEOのための競合分析や広告調査、コンテンツ作成などに活用できる日本語ビッグデータプラットフォームです。
ヒートマップ
ヒートマップは、Webサイト上でのユーザーの行動をサーモグラフィによる温度分布のように色の濃淡で可視化して表す分析手法です。Web解析では、マウスの動きを追跡し、そのマウスのログからヒートマップを作り出しています。
EmmaTools
「EmmaTools」はSEOライティングツールです。対策キーワードで上位表示させるための関連キーワードを提案したり、コンテンツ内で不足しているテーマを知らせたりなどSEO観点から改善点を明らかにします。
Ptengine
「Ptengine」はサイトに1つのタグを設置するだけで、データ収集からインサイト取得、施策実行そして効果の検証を行えるサイト運営プラットフォームです。
User Insight
「User Insight」は、Webサイトの訪問者がコンテンツのどこを見ているかやどこをクリックしているかを可視化してUI/UXの改善に役立たせるヒートマップツールです。トラフィック情報からユーザーの属性を推測することも可能です。
まとめ
本記事では、BtoBとはどのようなビジネスモデルか、BtoBマーケティングとはどのような施策かについて解説しました。BtoBは取引規模が大きくなり継続性が高くなる傾向があります。また、BtoCに比べてサイクルの短い流行の影響を受けにくいのが特徴です。
一方で取引開始までの意思決定プロセスが複雑で長期化しやすい傾向があるため、BtoBに適したマーケティングが必要になります。BtoBをすでに行っているが、より成果を出したい、あるいはこれから事業を立ち上げようとしているという方は、上記の特徴を踏まえたうえで、戦略を立てる必要があります。
投稿 BtoBとは?BtoCとの違いやマーケティングのポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 コラボレーションとは?コラボレーションツール導入メリットと注意すべき点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>コラボレーションとは?
一般的にコラボレーションとは、異なる立場の人々が共同で作業したり、何かを生み出したりといった行動や、その成果物を指します。分野や職種が異なる人同士が組むことで、お互いの知識や経験、能力、スキルの違いを生かしながら、独創的なアウトプットをめざします。意外性や新規性を持った付加価値を創造するという点で、商品開発や販売促進などでよく見られる手法です。
コラボレーションツールは、チームや部署など、組織内での共同作業をスムーズに行うためのツールです。あるプロジェクトが進行する過程では、社内やチーム内の従業員だけでなく、社外メンバーのような多様な人とのコラボレーションが生まれます。スケジュール調整や普段のやりとり、Web会議開催、ファイル共有、タスク進捗確認など、共同作業に必要なツールを一括管理できるのがコラボレーションツールなのです。
コラボレーションツールが注目される背景
ビジネスの現場でコラボレーションツールが注目される理由は、組織のコミュニケーション活性化が、従業員の心理的安全性や労働意欲、生産性の向上につながり、ひいては顧客満足度や企業価値の向上に寄与すると、多くの企業が理解しているためです。テレワークや副業のような新しい働き方が普及しつつある現在、組織のコミュニケーション密度をいかに高めるかに苦慮する企業は多いといえます。
コラボレーションツールの利用は、距離があることによる作業のしづらさ、従業員の孤独感を軽減します。プロジェクトに関わる全員が一体となって、共通目的の達成に行動できるようになるのです。情報を積極的にやりとりすることで、コミュニケーションが活性化するだけでなく、業務効率化にもつながります。変化の激しいビジネス環境下で、企業の柔軟な変容やスピーディーな価値提供が求められる一方、日本社会全体が慢性的な人手不足を抱えています。組織内のコミュニケーションを増やすことは、生産性や効率性を高め、労働力不足を補う一面もあるでしょう。
コラボレーションツールの種類と機能
多数のコラボレーションツールが提供されており、それぞれが独自の工夫や特徴を設けています。多機能ほどよいということではなく、あくまで自社の課題解決に必要な機能が揃っているか、想定イメージに近い使い方ができるかの判断が必要です。コラボレーションツールの種類と、代表的な機能について紹介します。
コラボレーションツールの種類
包括型コラボレーションツール
組織コミュニケーションに関する機能を総合的に搭載しているコラボレーションツールを指します。メールシステム、ビジネスチャット、ファイル共有、スケジュール管理、Web会議など、多くを網羅している点が特徴です。多少の仕様に違いはあれど、最近のコラボレーションツールは包括型のほうが一般的といえます。
特化型コラボレーションツール
ビジネスチャットやWeb会議、オンラインストレージといった、特定のサービスに特化したコラボレーションツールです。多様化するユーザーのニーズに応えるため、最近は特化型でも周辺機能を備えるツールが増えています。特化型と包括型の境界線は曖昧になりつつありますが、包括型に比べるとサービス内容が限定されている点で特化型とされます。
コラボレーションツールの機能
包括型・特化型のコラボレーションツールの機能には大きく分けて二つの機能があります。社内のやり取りを円滑に行うための連絡機能である「コミュニケーション関連機能」と社内の情報やチームのタスク状況などの情報を共有出来る機能である「情報共有関連機能」になります。
コミュニケーション関連機能
・ビジネスチャット
インスタントメッセージによる、リアルタイムでのコミュニケーションが可能です。ビジネスメールの件名や宛名、挨拶文、署名などを省けることで、メールよりも気軽にテンポよくコミュニケーションできます。資料や動画像の添付も容易で、スピーディーかつ密度の高い情報共有を実現できる機能です。ビジネスチャットのやりとりは時系列順に記録され、簡易議事録代わりになることや、検索性が高い点もメリットといえます。
・グループウェア
情報共有やコミュニケーションをサポートし、業務効率を上げるツールの総称です。スケジュール管理やファイル共有、メール、日報などの機能が1つのシステムに統合されている点が特徴です。単なるコミュニケーション活性化だけでなく、ワークフロー申請や会議室予約など、バックオフィスとの連携をスムーズにする機能が備わっている場合もあります。
・チームコラボレーション
チームや部署内のコミュニケーション活性化を通じて、従業員の所属意識や貢献意欲を高める、生産性や効率性を向上することを目的としています。機能群はグループウェアと重なる部分が多いものの、チームコラボレーションは共同作業の推進を重視しています。同時編集やナレッジ共有など、双方向の関与をサポートする機能が多い点が特徴です。
・メールシステム
独自ドメインが使用可能なビジネスメール機能です。特定のメールクライアントや自社サーバを利用せずに、気軽にメール導入ができます。独自のメール整理機能、大容量のメールアーカイブ保管などを特徴とするコラボレーションツールが目立ちます。
・バーチャルオフィス(仮想オフィス)
バーチャルオフィスとは、オンライン上につくられた仮想オフィス空間のことです。組織のメンバーがアバターなどの形で仮想オフィスに出勤し、実際のオフィスと同じように共同で作業をしたり気軽にコミュニケーションしたりできます。
情報共有関連機能
・カレンダーソフト
お互いの予定を共用カレンダーで共有し、誰がいつ何の予定があるのか把握できるようになります。必要に応じて参照することで、メールや電話で確認する手間を省き、スピーディーに会議や打ち合わせなどを設定したり、予定調整をしたりできます。
・Web電話帳
従業員や取引先、顧客の連絡先情報を登録し、組織内で共有できます。PCのWebブラウザやスマートフォンアプリから閲覧・使用できるので、場所を問わず必要に応じて連絡先を確認できる利便性、端末紛失時の情報漏えい防止につながります。プライベートとビジネスの連絡先を分けて管理できる点もメリットです。
・日程調整
カレンダー機能と連携して、日程候補の提案、空いている時間に予約受付できる機能です。メールや電話による日程調整は時間がかかるうえに確実性にも欠けるため、日程調整時のデメリットや負担を解消できる機能として注目されています。日程調整完了後は自動でカレンダーに追加され、手動の誤登録や登録漏れ、予定の重複を防いでくれます。
・Web社内報
会社の最新情報や新商品、サービスのリリースなどをリアルタイムでスピーディーに伝えられます。紙媒体と異なり、閲覧数やページ変遷などアクセス解析が行える点がWeb社内報の大きな特徴です。従業員が興味関心を持っている内容がわかるため、効果的な社内報制作に活かすことができます。
コラボレーションツールのメリットとデメリット
コラボレーションツールを効果的に活用するためには、メリットとデメリット両方の把握が重要です。メリットはもちろんのこと、デメリットについてもよく理解したうえでツール選定や運用ルール設定を行いましょう。

コラボレーションツールを導入するメリット
1.コミュニケーションを円滑にできる
2.場所や時間を問わず利用できる
3.複数のデバイスで利用できる
4.運用や管理が手軽
5.生産性、作業効率の向上につながる
6.セキュリティを強化できる
7.会議にかかるコストの削減
コラボレーションツールを導入するデメリット
1.情報過多になりやすい
2.既存システムとの連携
3.業務効率が下がる可能性もある
コラボレーションツールの選び方と導入時の注意点
コラボレーションツールを導入する場合、どのようにして自社に合うサービスを選べばよいのでしょうか。メリットを生かし、できるだけデメリットを回避するための選定ポイントを解説します。
必要な機能が揃っているか
自社のビジネスや課題を通じて、どのような機能が必要か明確にすべきです。組織やプロジェクトが小規模なうちは、ビジネスチャットやファイル共有で事足りるケースが多々あります。テレワークを推進している企業は、加えて同時編集機能やWeb会議システム、仮想オフィス機能が必要になるかもしれません。
使いやすさ、わかりやすさ
コラボレーションツールは組織全体のコミュニケーション活性化や共同作業の推進が目的です。なるべく多くの従業員を巻き込む必要があり、全社で同じツールを利用している状態が理想です。どんなに多機能でも、とっつきにくいUI、わかりにくいマニュアルは定着や普及を遅らせます。自社の従業員のITリテラシーレベルに応じたツール選びが大切です。
サポート体制
提供事業者からのサポートはどのような体制か確認しておきましょう。従来のメールやチャットによる個別サポート以外に、マニュアルやヘルプページ、ユーザーコミュニティによる自助的なものに留まるケースも増えています。営業日や対応言語などもチェックしておきましょう。導入にあたり従業員向けのセミナー実施や使い方のサポートがあるかも確認しておくと便利です。
機能性・拡張性
基本機能の充実に加えて、拡張機能や他システムとの連携範囲も事前にチェックしておきたい点です。機能や仕様のカスタマイズ、他システムとの連携ができるものを選んでおくと、企業規模やビジネス規模に変化があった場合に柔軟な対応ができます。
利用可能なデバイス
自社の従業員がよく利用する端末に対応しているか確認しておきましょう。オフィス出勤時にだけ使う場合、PCのWebブラウザのみでも問題ないかもしれませんが、外勤や在宅勤務を伴う場合は、スマートフォンやタブレットも対応しているほうが便利でしょう。
ランニングコスト
初期費用の安さに目がいきがちですが、継続利用するうえでランニングコストは非常に重要です。ツールによってユーザー1人あたりに課金されるもの、一定人数ごとに課金されるものなど、さまざまな利用料金プランがあります。将来的なユーザー増減や予算との兼ね合いで選びましょう。月額と年額がある場合は、年額料金のほうが安価なケースも多いので、支払い方法も考慮するとコスト削減につながります。拡張機能の追加、サポート利用などに関わる費用も要確認です。
セキュリティ
コラボレーションツールの多くがインターネット上のクラウドサービスを利用しています。セキュリティは企業の生命線です。機能やコストに満足できても、情報の安全性が担保できないツールは検討候補から外すべきです。提供事業者ごとにセキュリティ体制を公開しているので、十分にチェックしましょう。
社内での目的周知
コラボレーションツールは導入してからがスタートです。多くの従業員に活用してもらうことで真価を発揮します。導入目的が不明瞭なままでは社内に浸透していきません。目的を明確にすることと、従業員に広く周知すること、理解と賛同をしっかり得ることで、スムーズな運用とメリット活用が実現します。
運用ルールの設定と周知
本格的な利用開始前に、従業員に最低限の使い方を覚えてもらわなければなりません。また、運用ルールを共有しておかなければ、せっかくの機能を使いこなせなかったり、想定した使い方ができなかったりするおそれがあります。たとえば、どのような場合にビジネスチャットを使い、メール利用範囲をどのようにするかなど、従業員の目線に立ち、新しいツールに対する抵抗感や不安などを、できる限り取り除いてから運用開始しましょう。
コラボレーションツールの活用事例
コラボレーションツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
過去ログを掘り返して探し出す手間がなくなった
「チームメンバー各々が開発を行う上で必要となった、あるいは勉強になった内容などを社内Wikiとして残していける。必要になる情報を過去のメールやチャットを掘り返して探し出すような手間がなくなります。メンバー間でスペースを作成し、情報のやり取りを行えているため、プロジェクトメンバーに必要な知識や業務をアサインすることができるようになった。フォームのテンプレートなどもあるので、初めて利用する際には雛形に沿って書き始められて利用しやすかった」
https://www.itreview.jp/products/confluence/reviews/88271
▼利用サービス:Confluence
▼企業名:株式会社ワールドインテック
▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:人材
コスト削減と従業員の意欲向上、生産性向上を実現
「クラウドで一覧的に情報が管理でき、チーム内で共有できることができる。現在Teamプランを利用しているが、書類のアップロードも(2020年6月現在)無制限に行うことができる。また、パブリックで制作したページを公開できる機能もあり、気軽に情報公開ができるのが良い。とにかく機能が多いため、最初になれるのが大変だが慣れるとできることが多く使いやすい。これまで複数のサービスを利用していたが、Notionですべてが完結できるため他のサービスの利用を停止しました。その結果コスト的にも、時間的にもコストダウンできるたと感じています。また、洗礼されたデザインで社内の士気も高まりアイデアが集めやすくなりました」
https://www.itreview.jp/products/notion/reviews/44222
▼利用サービス:Notion
▼企業名:株式会社muku.▼従業員規模:20人未満 ▼業種:デザイン・製作
社内のナレッジを一元管理して業務効率が向上
「社内で共有される文書管理をシンプルにする必要がありました。共有ドライブや、様々なツールの中に上がっていたり、チャットの中で埋もれてしまっていたりしました。社内でよく聞かれることは、NotePMに書いておけばチャットでリンクを送るだけで完了するのでとても助かっています。業務委託のメンバーにも一部だけ共有できる仕組みがあるので業務報告やドキュメントをまとめてもらっています。PPTやEXCELでもいいのですが、更新が気軽にできるので最新情報に保っておくことが簡単です。基本的にNotePMに書くようにしたので文書が探しやすくなりました。」
https://www.itreview.jp/products/notepm/reviews/43022
▼利用サービス:NotePM
▼企業名:株式会社チュートリアル
▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
非対面でも社内のコミュニケーション温度を上げてくれる
「エビデンスを残すため、社内の会話の半分以上はSlackです。スタンプ機能はコミュニケーションを充実させる上で役に立っています。必須の機能ではないですが、事務的になりがちな文字のコミュニケーションを少しホップにし、気軽に感情を伝えやすくする効果があると思います。Slackでだれかがメッセージを発信し、そのメッセージに対してコメントするまでもないけど、何かしらリアクションしたい。アピールしたいときにスタンプ機能を利用すると、気軽にアクションがおこせます。Slackで会話をしてみるとよくわかりますが、この機能があるのと無いのでは文字上でコミュニケーションをする上での、相手とのつながり感が全然ちがいます」
https://www.itreview.jp/products/slack/reviews/40308
▼利用サービス:Slack
▼企業名:株式会社Ginco
▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
日程調整にかかる工数を大幅に削減して生産性アップ
「URLを一つ発行するだけで使い回しが可能=顧客との日程調整のための連絡工数が大幅削減、社内メンバー複数人との日程調整URLもすぐに発行可能、当日朝をはじめとした充実したリマインドなど、日程調整のための連絡工数削減や確認漏れを防ぐことに大きく貢献。普段から打ち合わせの数が多い営業現場には特にオススメです。複数人で日程調整したい際、簡潔に行うことができます。今まで「メールに日程記載→先方へ送付→先方が返信→(昨今オンライン打ち合わせなので)会議システムURLを発行して、、、」と1アポあたり数分工数がかかっていたところ「URLの送付→先方がURLから日程登録」と1通のメッセージでアポが組めるようになりました。」
https://www.itreview.jp/products/choseiapo/reviews/73925
▼利用サービス:調整アポ
▼企業名:株式会社RECCOO
▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:人材
おすすめのコラボレーションツール
実際に、コラボレーションツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのコラボレーションツールを紹介します。
(2021年12月21日時点のレビューが多い順に紹介しています)
日報アプリ
クラウド上で日報の作成・管理を行うことができるサービスです。日報は1日の終わりに業務の報告するための資料を指します。日報アプリではそれをクラウド上で作成することができるため、いつでもどこでも報告することが可能になりました。
ビジネスチャット
ネットワークを介したリアルタイムコミュニケーションを実現するチャットツールで、ビジネス用に特化したものを指します。単純な連絡手段としてだけでなく、業務の効率化を図るために有効なツールとして多くの企業で利用されています。
ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。
ビジネスチャットツールを徹底比較! ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選
グループウェア
企業などの組織内のメンバーがスケジュールやタスク、業務に用いる資料、アイデアやノウハウなどを共有するためのシステムです。自社の業務に合わせた案件管理や日報といった独自のシステムをデータベース上などで作成できる機能を備えたものもあります。
グループウェアの詳しい解説はこちらをご覧ください。
グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア比較、活用事例も紹介
チームコラボレーション
チームメンバー間のコミュニケーションを促進するための効率的な“スペース”を提供するためのツールです。グループでの話し合い、メンバー同士でのメッセージ送受信、コンテンツの共有といったさまざまな機能を提供します。
メールシステム
サービス事業者側のクラウド環境にあるメールサーバへ、企業内からインターネット接続して利用するメールサービスのことです。メール誤送信防止やアンチウイルスなどのセキュリティ対策をセットにしたメールシステムも多くあります。
仮想オフィス(バーチャルオフィス)
仮想空間に疑似的なオフィスをつくり、テレワーク環境でも実際に出社しているような感覚でテレワークができるツールです。テレワーク環境でもチームメンバーと近い距離間で仕事しているように感じ、コミュニケーションが取りやすくなることが最大の特徴です。
仮想オフィス(バーチャルオフィス)の詳しい解説はこちらをご覧ください。
バーチャルオフィスとは?テレワーク時代の社内コミュニケーションを担う新しい働き方
プロジェクト管理
プロジェクトの目標やスケジュール、プロジェクトチームのタスクを管理するシステムのことです。作業量や作業負荷の可視化をはじめ、生産性の監視、リソースの最適化などのツールによって構成されています。
プロジェクト管理とは?プロジェクトの視覚化で組織はどう変わるのか?
タスク管理
個人のタスクや仕事を管理し、毎日のワークフローやその進捗状況を整理しやすくするツールです。個々の作業の概要を明示するとともに、チーム全体で利用することで、チーム内のメンバーのタスクも可視化、管理できるようになります。
タスク管理で押さえるべき3つのポイント!おすすめのタスク管理ツール5選を紹介
オンラインストレージ
インターネット上で利用できるファイル保存のためのディスクストレージサービスです。作成したファイルをパソコンや外付けHDD等に保存することなく、クラウド上でのデータ保存が可能になります。膨大なデータの容量を気にせず保存でき、複数人が同時にファイルを閲覧・編集できることから、企業の情報共有や作業効率向上を後押しするサービスとして導入されています。
オンラインストレージとは?おすすめオンラインストレージ7選まで全解説
カレンダーソフト
予定やタスク、目標などを登録し、視覚的にわかりやすく整理してほかの社員と共有するためのツールです。スケジュールの登録・変更、日・週・月・年などの表示切り替えといった基本的な機能に加えて、会議予約(設備予約)、グループでのスケジュール管理、メールやプッシュ通知などリマインドなどの機能を備えています。
Web電話帳
企業や組織内でメンバーや顧客/取引先などの連絡先情報を一括して管理したり、共有したりできるツールです。スマートフォンで活用すれば、端末内の電話帳を使わずに済むため、紛失時の情報漏えいリスクを最小化したり、プライベート用とビジネス用を分けて連絡先を管理できます。
日程調整
社内あるいは社外の相手との打ち合わせや訪問、面談などのスケジュール調整を自動化するツールです。打ち合わせや会議などの日常的なビジネス活動のほか、営業先や商談相手への訪問、さらには採用活動における多人数との面談など、さまざまな日程調整に活用できます。
Web社内報
社内広報を行うためのツールとして作成された冊子や映像などの媒体を指します。これをWebを活用し、発信することをWeb社内報と呼びます。デジタル化の流れの一環でWebで社内報を作成する企業が増えてきています。
ITreviewではその他のコラボレーションツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
まとめ
ビジネスの業績向上にはコミュニケーションと情報共有が不可欠です。コラボレーションツールを適切に活用することで、積極的なコミュニケーションと綿密な情報共有が実現され、生産性向上や効率性向上が期待できます。
テレワークにおける従業員の孤独感を軽減し、組織としての一体感を高められれば、心理的安全性の確保やモチベーション向上にもつながります。自社の課題や現状を考慮したコラボレーションツールの選定と運用を行い、より成果を上げられる組織にしていきましょう。
投稿 コラボレーションとは?コラボレーションツール導入メリットと注意すべき点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 オンラインストレージのメリットとは?基本機能から導入のポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>オンラインストレージとは?
オンラインストレージとは、自社のサーバを使わずにデータの共有や管理ができるサービスです。クラウド上でデータを保存するので、いつでもどこからでも必要なときにアクセスしてダウンロードや閲覧ができます。
オンラインストレージのベンダーがクラウド内に用意したストレージにログインすることにより、ファイルの保存を行います。パソコンのSSDやハードディスクと同様に大量のデータを保存することが可能で、専用サーバが不要なため、導入コストをほとんどかけずに利用できます。
また、データを一元管理できるため、データ共有する際の工数を省けます。これまではメールやUSBなどのデバイス経由でデータ共有を行っていた作業を、オンラインストレージに格納すればいつでも必要な情報を取り出せます。 特に拠点が複数ある企業にとっては、情報共有を大幅に効率化できます。
導入企業は増加傾向
自宅のパソコンからデータをアップロード・ダウンロードでき、いつでも最新の情報を得られるオンラインストレージ。その需要は働き方改革やコロナ禍によるテレワークの普及に伴い、ますます増加しています。無料で提供するサービスも多く、最近はセキュリティ面での機能も強化されてきており、個人用・法人用問わず、数多くの企業に導入・活用されています。
オンラインストレージでできること
クラウド上にファイルを同期できる仕組みとして構築されているのが、オンラインストレージです。ファイルの更新や同期が自動で行われるので、いつでも最新のデータにアクセスすることができます。複数のデバイスからのアクセスが可能で、複数人でのファイルの共有・編集・閲覧などもリアルタイムで行えます。
オンラインストレージの基本機能
オンラインストレージには、主に以下の基本機能が備えられています。どれもオンラインストレージを上手に活用する際に必要不可欠な機能です。オンラインストレージの基本機能を理解しておけば、どんなサービスが自社の求める最適なものであるかを見極める判断材料になるでしょう。
写真・動画を保存
写真や動画などの大容量のデータは送受信やダウンロード・アップロードに時間がかかりますが、これをオンラインストレージで保存することにより、大幅に時間を短縮できます。通常であれば写真や動画をデータとして保存・蓄積することから、サーバの容量を圧迫することも気になりますが、オンラインストレージではシンプルな工程を踏むだけで容量を増やすことができます。
自動バックアップ
ハードディスクなどにデータを保存していると、機器が破損する可能性もあります。修理・復元をすれば当然コストがかかり、確実に復元する見込みもありません。オンラインストレージではデータを自動的にバックアップしてくれるため、手動で行う必要がなく、データ削除などの不安も軽減できます。
ファイルの共有
オンラインストレージにファイルを保存しておくことにより、アクセス権限があれば複数人でファイルを共有することが可能です。インターネット環境さえあればパソコンやスマートフォンなど、いつどこにいても共有や閲覧・編集ができるため、自宅や社内外などで快適に利用できます。
ファイルの転送
たとえばファイルのサイズが大きすぎると、メールでは送信不可なことがあります。そのような膨大なデータ量のファイルは、オンラインストレージにアップロードして送信相手にダウンロードURLを連絡するだけで転送が完了します。その後、送信相手がファイルをダウンロードすることで、データのやり取りも円滑に進みます。ダウンロードにはパスワードが設定可能で期限も定められているため、セキュリティ面でも比較的安心です。
オンラインストレージを導入するメリットとデメリット
ファイルの保存や共有が容易にできるオンラインストレージは、個人・法人を問わずさまざまなメリットがあります。その一方で、パスワード管理に注意が必要であるというデメリットもあります。メリット・デメリットの双方を理解して、有益な製品の選定に役立てましょう。
オンラインストレージを導入するメリット
1.データの一元管理が可能
オンラインストレージは、インターネット上にデータ保存して一元管理できるサービスです。データの一元管理により、担当者の負担を軽減できます。複数のデバイスからアクセスができ、1つのファイルを複数人で共有することも大変スムーズです。
2.管理業務の負担を削減
社内にサーバを置くような従来型の方法において、サーバ管理と運用は欠かすことのできない作業でした。またトラブル対応などもすべて社内で行う必要がありました。オンラインストレージの登場によって、管理と運用にかかる時間と手間が不要になったことから、管理業務の負担を大幅に削減します。
3.ストレージの拡張性
オンラインストレージサービスは容量次第で費用が決定するシステムです。必要に合わせて自由に容量を切り替えることができます。また導入前の無料トライアルの段階で容量不足となっても、プランを切り替えることで容量を増加させられるのもオンラインストレージサービスの魅力の1つです。
4.大容量のバックアップ
オンラインストレージサービスは自動でバックアップを行ってくれるため、わざわざ人的にバックアップをとる必要がなく、誤ってデータを削除したりする心配も不要です。
5.複数デバイスでアクセス可能
インターネット環境さえあれば、いつどこからでもオンラインストレージサービスにアクセスできます。もちろん複数のデバイスからアクセスすることも可能なため、一元管理を行う際や社内でデータ共有を行う場合にも有益で、業務の効率化にもつながります。
6.コストの削減に寄与
オンラインストレージサービスは、初期費用が無料で利用できるものもあります。製品の選定におけるプロセスでは、通常いくつか無料トライアルを受けた中から選定を行うことが多いでしょう。導入後の初期費用も無料であると、さらなる費用の削減を実現できます。
7.ほかのユーザーと共有可能
アクセス権限さえあれば、複数人でデータの共有ができるのもオンラインストレージサービスの特徴です。たとえば、1つのファイルに対し複数人でアクセスを行うことで、それぞれ離れた場所にいてもファイルを閲覧しながらオンライン会議などもできます。
オンラインストレージを導入するデメリット
1.パスワードの管理に注意
オンラインストレージは、アカウント情報がわかれば誰でもアクセスすることができます。そのため、パスワードの管理には日頃から十分に気をつける必要があります。また注意喚起として社員への啓蒙活動や運用規定を定めるなど、ある程度の時間や手間が必要となることも覚えておく必要があります。
オンラインストレージの活用事例
オンラインストレージを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
管理業務の負担削減に寄与・業務効率化も実現
「資料共有の手間が減りました。また、資料を同時編集することで、別々の場所にいる時に、一つの資料を確認・編集しながら、議論することで、議論の効率が上がりました」
https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/81355
▼利用サービス:Google Drive
▼企業名:株式会社野村総合研究所 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:ソフトウェア・SI
大容量のクラウドサービスと秀逸な共有機能
「自前の共有フォルダサーバーを構築しなくて済んだ点。大容量クラウドサービスで、サービス稼働時間も長く安定しているサービスである点。閲覧、編集という機能レベルでの権限設定機能。複数名でファイル共有をするのも優れており、権限設定も簡単に設定出来る点もなお良しです」
https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/86362
▼利用サービス:Google Drive
▼企業名:株式会社POL ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
サイズの大きいファイルを簡単にシェアできる
「サイズの大きいファイルをクラウドにあげることができ、簡単にシェアできる。うちの会社は基本的に在宅勤務なので、これなしでは仕事にならない。共有が楽です。大きなサイズのファイルやりとりでいつも苦労していました。またバックアップもHDに落としたり苦労をしていましたが、今はその苦労がないです」
https://www.itreview.jp/products/dropbox-business/reviews/16700
▼利用サービス:Dropbox Business
▼企業名:有限会社アカウンティング・サービス ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:会計・税務・法務・労務
紛失や盗難リスクを考えてもセキュリティ上安心
「当社はデスクトップPCをメインに使用していたが、コロナ対策で外出先からでも仕事ができる環境を作ることを目的に、営業社員向けにモバイルPCを導入しました。社内サーバーで管理していたデータもONEドライブ側に移行することで、リモート先からも業務継続できることができました。ONEドライブのメリットはセキュリティ上も安心です。PCの紛失、盗難リスクを考えると、PC側にデータを保存するよりクラウドを利用する方がメリットがあります」
https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/85885
▼利用サービス:OneDrive for Business
▼企業名:軽急便株式会社 ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:運輸
オンラインストレージ導入のポイント
現在、多くのオンラインストレージサービスがリリースされています。サービス選定の際は、知名度や人気で判断するよりも、自社にとって必要な機能を備えたサービスを選ぶことが何より大切です。以下の導入におけるポイントを押さえたうえで他社製品との比較を行うことにより、自社にもっとも相応しい製品を選定しやすくなります。
自社に必要な機能であるか
検討しているオンラインストレージサービスに、自社にとって必要な機能が用意されているのか確認を行います。たとえば費用が格段に安価という理由から導入をしても、自社が必要とする機能が備えられていなければサービスにかけたコストは無駄になります。
コストの確認
利用する人数や容量・機能数が増加するごとにコストも上昇していきます。自社で活用する人数や容量・機能数などから、自社に最適であるとされるオンラインストレージサービスを選定しましょう。あまりに安価な製品は、容量や機能面が十分でなかったりする可能性があります。まずは無料トライアルでいくつかのサービスを試してみることをおすすめします。
セキュリティ対策は万全か
情報漏えいなどのトラブルを予防するためには、強固なセキュリティ対策に定評のあるオンラインストレージサービスを選ぶことが万全の対策です。セキュリティ対策で重要となるのが、定期的にサーバ内のウイルスチェックを実行しているか、ファイル情報暗号化のためのSSLに対応しているかなどです。また、サーバ上の行動記録を行うログ機能が搭載されているかなどの確認を行うことも必要です。
サポート体制に問題はないか
オンラインストレージサービスのサポート体制が万全であるかどうかチェックしましょう。メールやチャットなどどういった方法からサポートをしてくれるのかということも、重要なポイントです。特に急ぎの場合も電話ですぐに対応してくれるかどうかは、製品を導入するうえでとても重要です。海外仕様の製品であれば、日本語の電話サービスがあるのかも確認をしておきましょう。
データ容量の確認
オンラインストレージを導入する前のプロセスにおいて、自社に必要な容量はどのくらいであるのかを確認します。製品次第では大容量プランや無制限プランなどがあったり、容量不足時に増量することができたりします。データ容量以外にもファイルの送受信に必要な容量がどれほどであるのか、導入前にきちんと確認しておきましょう。
オンラインストレージの業界マップ
オンラインストレージのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
おすすめのオンラインストレージ7選
実際にオンラインストレージを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのオンラインストレージツールを紹介します。
(2021年12月24日時点のレビューが多い順に紹介しています)
Google Drive
Googleの提供するオンラインストレージツールであり、Googleの個人用ストレージとしても利用できます。Googleのオフィススイート製品の一部として利用可能な点も大きな特徴です。安全性に優れ、共有やバックアップ・ドライブファイルストリームにモバイルデバイス管理なども行えます。
Dropbox Business
扱いやすく、ファイルの共有により生産性の向上を期待できるツールです。オンラインストレージ初心者の方にも使いやすい仕様となっています。
Box
国内外で広く活用されているグローバルメジャーなオンラインストレージツールで、ファイルの共有や編集・保存・Box Captureやログの取得などが行えます。Box Captureを利用すると、写真・音声・動画などをそのままオンラインストレージツールへアップロードできます。
OneDrive for Business
マイクロソフトが提供し、オフィススイート「Office365」の一部として活用できます。「Office365」は、OneDriveのほか、Outlook、Word、Excel、PowerPoint、OneNote、SharePoint、Microsoft Teams、Yammer などのアプリケーションと各種サービスがパッケージされています。
OneDrive for Businessの製品情報・レビューを見る
DirectCloud
ユーザー数が無制限で完全にクラウドで保存できる企業向けクラウドストレージです。SSL、ウイルスリアルタイム検知、データ暗号化、IPアドレス制限、複数バックアップ、パスワード強化ポリシーなどの強固なセキュリティ機能を標準装備。
AOSBOX Business
シンプルな操作性と豊富なプランを用意するオンラインストレージツールです。バックアップファイルの世代数を任意に変更することができます。ほかの同期型クラウドバックアップとは異なり、誤って削除や修正してしまったデータのバックアップがクラウド上から削除されることがなく復元が可能で、災害や故障、ウイルス対策にも有効です。
HENNGE One
さまざまなクラウドサービスに対してセキュアなアクセスとシングルサインオン(SSO)機能などを提供するSaaS認証基盤(IDaaS)です。各クラウドサービスと緊密に連携し、情報漏えい対策やデバイス紛失対策、不正ログイン対策を実現します。
ITreviewではその他のオンラインストレージも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
まとめ
オンラインストレージを利用することにより、社内で時間や手間を費やしていた運用や管理といった業務を大幅に削減し、効率化を実現できます。それだけでなくセキュリティの強化も図れることから、より高い安全性にも寄与します。
デジタルデータの容量の増加に伴い、今後オンラインストレージサービスを導入する企業もますます増えていくことでしょう。自社にもっとも必要な製品の選定を行う際にはいくつか無料トライアルを試し、他社製品との比較を行ったうえでの導入をおすすめします。
投稿 オンラインストレージのメリットとは?基本機能から導入のポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 KPIはなぜ必要?|KGIとの関係やOKRとの違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>KPIとは?
KPIとは「Key Performance Indicator」の略語で、「重要業績評価指標」を表します。読み方は「ケーピーアイ」です。KPIは、企業の目標や組織の目標が達成されるために、各業務においてどの程度のパフォーマンスを出せばよいのかを示す指標です。
たとえば営業部が掲げた目標を達成するために、訪問件数や受注件数などを数値で評価できるように、指標として設定するのがKPIです。目標達成にどの程度近づいているのかを客観的に把握することができるようになります。もしKPIが設定値に達していなければ、パフォーマンスが落ちているプロセスを見つけやすくなります。
あらゆる業務に使えるKPI
KPIというと、営業の訪問件数や目標受注件数、企業全体であれば財務指標などが思い出されるかもしれませんが、実際にはあらゆる業務やプロセスに利用できます。たとえば営業担当者の顧客訪問回数や受注件数などのほかに、研修の回数やクレーム件数などにも設定できます。あるいは製造現場であれば、在庫率や不良品の発生率などに設定できます。
組織や個人が行うあらゆる業務プロセスでKPIが設定されることで、会社や組織の目標に対する状況把握ができます。なんとなく進んでいるといった曖昧な状態ではなく、どのプロセスがどの程度達成できているのか、達成度が低いプロセスがどの工程なのかが明らかになります。
わかりやすくして形骸化を防ぐ
KPIはあらゆる業務プロセスに設定できます。しかし、複雑に設定したり目標との因果関係が希薄なままに数値設定したりすると、KPIはとりあえず設定しただけの指標になってしまい形骸化してしまいます。このような形骸化を防ぐためには、目標との因果関係が明白なプロセスに絞ってKPIを設定し、実行者が理解できる範囲に抑えます。
また、KPIは一度だけ設定すればよいというわけではありません。組織の目標の変化や戦略の変化に応じて、柔軟に変更していく必要があります。さらにKPIを変えるたびに、従業員の理解を深めるための教育プログラムが必要になります。
KPIを設定するメリット
KPIを設定することには多くのメリットがあります。
KGI達成までのプロセスが明確になる
KGIは「Key Goal Indicator」の略で、「重要目標達成指標」を表します。たとえば「自社の今期の売上を10億円にする」などがKGIです。このKGIの達成に必要な業務プロセスのパフォーマンスを可視化するのがKPIです。KPIの設定により、各業務プロセスの達成度がKGIの達成にどの程度貢献できているのかを確認することができます。
1.各人の目標が定まる
KGIだけでは大まかすぎて各人の行動の指針は明確にできません。そこで各業務のプロセスでどのような成果を出すべきかを示すKPIの設定が必要になります。何をどれだけ行うべきかが明らかになるので、組織全体のパフォーマンスが高まります。同時に、組織の成果が出なかった場合に何を改善すべきかが明確になり、PDCAサイクルを効率よく回すことができるようになります。
2.必要なアクションが明らかになる
組織が目標を成し遂げる際に各人が何をすべきかを明らかにするためにKPIを設定します。その結果、各人は努力の方向性で迷わなくなります。たとえば営業部の売上目標を成し遂げるために、1人当たりがめざす訪問数や成約率が明確になります。
3.評価基準が明確になる
評価基準を明確に統一するためにKPIを設定します。たとえば営業部員1人の月の売上が500万円と設定された場合、それが達成できたかできなかったかは金額という数値で明かになります。KPIとして月の訪問数や成約率を数値で設定していれば、目標が達成されなかった場合も、理由が訪問件数不足だったのか、あるいは訪問件数は達成していたが、成約率が低すぎたのかが明らかになります。このように、各人を評価する際の曖昧さが減り、客観性が高まり公平性が担保されます。
4.組織のモチベーションが高まる
KPIが定められると各人の目標を共有できるため、組織全体のモチベーションが高まります。たとえば業務プロセスにおいて課題が発生した場合でも、組織内の共通の課題として共有し、メンバー全員が自分ゴトとして解決に向かいます。このことで結束力が強まりモチベーションも高まります。
5.PDCAを回しやすくなる
目標達成のための業務が細分化され、行動した結果がKPIにより評価できるようになれば、改善点が明確になるためPDCAを回しやすくなります。その結果、各人のパフォーマンスが高まり、組織全体としてもより大きな成果を出すことができます。
KPIに関連する指標
KPIと混同されやすいKGIとKFSという指標について説明します。
KGIとは?
KGIは「Key Goal Indicator」の略で、「重要目標達成指標」を表します。特定の期間で達成すべき目標を数値化することを示します。たとえばある企業が、「今期は売上を大きく伸ばすぞ!」と目標を立てたとします。しかし、このような大まかな目標では、販売部門の目標が定まりません。
そこで具体的な指標として、「売上1兆円を達成するぞ!」と設定します。このようにKGIが設定されれば、販売部門は売上1兆円を実現するためには月間何件を受注すればよいのかがわかり、そのために何件訪問すればよいのかも決まってきます。これがKPIです。ほかにも、「利益率を○○%に改善する」というKGIが設定されれば、商品の販売数や仕入れの値引きを目標としたKPIが設定できます。
KFSとは?
KFSは「Key Factor for Success」の略語で、「重要成功要因」を表します。ビジネスが成功するためのカギとなる要因がKFSです。たとえば、あるサービスの売上目標を達成したい場合に、必要となる要因は集客数や価格設定だとすれば、それぞれがKFSとなります。そして、これらのKFSを指標化したものがKPIだといえます。
KPIとKGI、KFSはどのような関係にあるのか?
KPI(重要業績評価指標)、KGI(重要目標達成指標)、KFS(重要成功要因)がどのような関係にあるのか解説します。
KGIとKPIは何が違うのか
KGIは最終目標です。これに対してKPIは、KGIを実現するための中間目標です。たとえばKGIとして自社のECサイトの今月の売上を2000万円にした場合、月間のECサイトへのセッション数の目標値を決めたり、新たに販売を開始する新規商品の点数を決めたりすることがKPIです。
KGIとKFSは何が違うのか
目標を示すKGIを実現するための要因がKFSです。逆にいえば、KFSに取り組むことによってKGIが達成されます。KFSが不明確なままKGIをめざしても闇雲に努力することになり、組織や個々人のモチベーションが低下します。たとえば自社ECサイトで○月の売上を○○万円にするというKGIが設定された場合は、アクセスを伸ばすことがKFSの1つとなります。
KFSとKPIは何が違うのか
前項のように、ECサイトの売上目標額をKGIとしたときのKFSの1つが、ECサイトへのアクセス数だと分析できた場合、KPIは具体的に必要なアクセス数を示します。このKFSはさらに細分化できます。つまりアクセス数を延ばすために必要な月当たりのサイト更新回数や新商品の取り扱い頻度、広告の露出頻度などの見直しを行い、それぞれをKPIとして数値化します。
OKRとの違いとは?
OKRとは?
OKRは「Objectives and Key Results」の略で、「目標と成果指標」を示します。会社が定める目標と社員の目標を関連づける目標管理方法です。OKRではまず、会社の目標と、その目標を達成した際の成果を明確にします。そして、この目標を達成して成果を得るためには、チームや個人はどのような目標をめざして成果を出すべきか紐づけていきます。
たとえば、以下のようなOKRが考えられます。
| 企業の目標(Objectives) | 3年後に業界シェア○○%を獲得 |
| 企業の成果指標(Key Results) | 利益率○○%獲得リピート率○○%獲得 |
| チームの目標(Objectives) | 新規顧客○○%獲得リピート率○○%獲得 |
| チームの成果指標(Key Results) | 上半期に集客イベントを行う今月中にWeb広告のキーワード見直し |
| 個人の目標(Objectives) | 自社サイトのリニューアル |
| 個人の成果指標(Key Results) | SEO実施広告キーワード見直し |
OKRとKPIの違いとは
KPIが目標に対する現在の行動の状況を客観的に測定する指標であることに対し、OKRは目標を達成するプロセスを見える化して共有する仕組みだといえます。また、KPIでは実現可能な数値を設定するので100%達成することをめざしますが、OKRではプロセスを重視しますので、可能な限り近づくことをめざします。
たとえばダイエットにたとえるなら、半年後までに6キロ痩せることを目標にした場合、毎日ウォーキングと食事制限する方法を選ぶことがOKRで、「ウォーキングは1日に○○キロ歩き、食事は○○キロカロリー以内に」と定めるのがKPIです。
KPIを設定する手順
KPIをいきなり設定することはできません。まず、KGIを設定する必要があります。
以下、手順を紹介します。
1.KGIを設定する
KPIを設定するためには、先に企業や組織の最終目標であるKGIを定めます。KGIはただ高ければよいのではなく、現実的に達成できる数値で示します。たとえば売上であれば金額を明確にします。また、KGIはできるだけ社員やチームメンバーからの意見を募り、全員で納得できる数値を決めることで、各人が合理的に納得できるKPIを設定できるようになります。
2.KGIを分解してKFSを引き出す
KGIが定まったら、次にKGIをKFS(重要成功要因)に細分化します。たとえば自社のECサイトからの売上を上げることがKGIであれば、KFSは「サイトの見やすさ」や「SEO対策」「コンテンツの品質の高さ」「SNSとの連携」「効果的な広告出稿」などが考えられます。
3.KFSを選ぶ
プロセスを細分化してKFSを洗い出すことができたら、KFSを特定します。KFSを決める基準は、まずそのプロセスがコントロール可能かどうかです。次に、目標達成に対する影響の大きさです。この2つの基準によりKFSを特定します。
4.KFSからKPIを設定
KFSを選定したら、KPIを設定します。前述の「サイトの見やすさ」や「SEO対策」「コンテンツの品質の高さ」「SNSとの連携」「効果的な広告出稿」であれば、それぞれ「検索流入数」や「サイト内滞在時間」「SNSからの流入数」「広告からの流入数」となります。つまり、KFSの達成度を客観的に評価できる指標を数値で示すことになります。
KPIの設定例
KPIは各社ごとの業務プロセスを定量的に評価する指標です。そのため、業種ごとのKPIとしての数値が規格として用意されているわけではありません。しかし、業種ごとによく使われるKPIの例はありますので、以下に紹介します。
セールスのKPI例
セールス部門でもっとも困るのは、「今月の売上○○円の達成のためにがんばれ!」という激励です。これでは何をどのように「がんばれ」がよいのかわかりません。そこで、各部署でどういった役割でどこに力を入れるかを明確になるKPIを設定します。
たとえば、インサイドセールス部署であれば、リード創出のために「アポ数」や「商談化数」をKPIに設定すると有効でしょう。またフィールドセールスであれば、受注数を上げるために「案件化数」や「受注率」といったものがKPIに設定されます。
よく使われる例は以下のとおりです。
| 架電数 | アポ数 | 訪問数 | 新規リード獲得数 |
| 平均顧客単価 | 案件化数 | 受注数 | 受注率 |
システム開発のKPI例
システム開発において、品質保証のための「エラー件数」や「標準化率」や納期厳守を実現するために「進捗率」や「稼働率」がKPIの設定として有効です。
よく使われる例は以下のとおりです。
| エラー件数 | 標準化率 | 進捗率 |
| 稼働率 | 生産性 | テスト終了件数 |
製造業のKPI例
製造業では利益、生産性向上の基本をQuality(品質)、Cost(費用)、Delivery(納期)のQCDとしています。KPIは、原料費の管理や稼働効率、品質の維持、あるいは現場の安全性を確保するために有効です。
たとえば、費用を抑え、生産効率を高めるために「総合設備効率」や「時間稼働率」「稼働率」「不良率」をKPIとして設定することが有効です。
その他よく使われる例は以下のとおりです。
| 原材料歩留差異 | 収率差異 | 工数差異 | 設備稼働差異 | 設備稼働率 |
| 時間稼働率 | 総合設備効率 | ライン編成効率 | 稼働率 | 不良率 |
| 事故発生件数 | 度数率 | 製造リードタイム |
人材採用のKPI例
人材採用のKPIは、選考フローの効率化やミスマッチの防止などに有効です。
たとえば、採用者数を増やすために「母集団形成」から「応募人数」「面接突破率」「内定率」などをKPIとして設定します。
よく使われる例は以下のとおりです。
| 母集団形成 | 応募人数 | 面接設定率 | 一次面接人数 |
| 最終面接人数 | 説明会・インターンへの参加人数 | 書類選考数の通過率 | 内定率 |
| 内定承諾率 | 採用達成度 | 1人あたりの採用コスト | 職場定着率 |
購買のKPI例
購買におけるKPIは、品質の維持と原価低減、納期厳守に有効です。
たとえば、購入した資材の品質を高めるために「受入不良率」や「VOS(Voice of Supplier:取引先評価)」がKPIとして設定されます。
よく使われる例は以下のとおりです。
| 受入不良率 | 原価低減率 | CR(コストダウン)率 |
| 納期遵守率 | VOS(Voice of Supplier:取引先評価) |
KPIを設定するポイントとなるSMARTとは?
KPIを設定するコツとして、「SMART」を意識する方法があります。SMARTとは、以下の頭文字です。
それぞれを見ていきましょう。
Specific(明確な)
「Specific」は「明確な」を意味します。KPIは誰が見てもわかる指標になっていなければなりません。人により解釈が変わってしまうような曖昧な設定はKPIとはいえません。明確にすることで、KPIを見れば各業務における目標を達成できたかどうかが客観的に判断できます。
Measurable(測定可能な)
「Measurable」は「測定が可能なこと」を意味します。KPIは数値化できる業務プロセスに設定しなければ、達成度を客観的に判断できません。数値化できれば課題も発見しやすくPDCAを回しやすくなります。
Achievable(達成可能な)
「Achievable」は「達成可能なこと」を意味します。KPIを設定する際、「目標は高いほどよいだろう」と現実的ではない数値を設定してしまうと、従業員は「どうせ無理」と諦めてしまい、「あくまで理想だろう」と実際に達成する意欲が削がれてしまい、モチベーションが下がってしまいます。そのため、KPIを設定する際には、達成の可能性が高い数値を設定します。
Related(関連性)
「Related」は「関連性」を意味します。KGIと関連しないKPIを設定して達成しても、企業の目標達成に貢献することができません。場合によってはKPIの達成のための労力やコストが企業にとってマイナスに作用する可能性もあります。したがって、KPIは必ずKGIと関連させます。
Time-bound(期限を定めた)
「Time-bound」は「期限を定めた」を意味します。KPIを設定する際には、期限を設定しなければなりません。期限が決められていないと、業務は漫然と進められてしまいます。期限が決められることで、行動に具体性が生じます。
KPIを運営するコツ
KPIは一度設定してそれきりというものではありません。企業や組織の目標が達成されるためには、継続的なKPIの運営が必要です。
ここでは、KPIを運営するコツについて紹介します。
KPIはシンプルに
KPIを継続的に運営するためには、KPIの設定をシンプルにする必要があります。項目が多すぎたり測定方法が複雑すぎたりすると、KPIの運営に多くのリソースとコストを投入することになってしまいます。結果的に、いつのまにかKPIは単なるスローガンになってしまいます。KPIは重要な項目に絞り、シンプルな測定が可能な内容にしておきます。
評価を明確に
KPIを設定して測定できていたとしても、評価基準が定まっていなければ次の行動への指針となりません。KPIを企業の目標達成のための加速器として活用するためには、評価基準を明確にしておく必要があります。
定期的に見直す
KPIは固定されるべき指標ではありません。定期的に軌道修正を行う必要があります。日々の進捗度合いを評価し、KPIの設定を見直します。適切なKPIを設定することで、業務改善への効果を発揮できます。
KPI管理に役立つツール
各業種でKPI管理に役立つツールを紹介します。
SFA
営業向けにはSFAツールがKPI管理におすすめです。SFAは営業プロセスの自動化や、効率的に業務を遂行するための営業支援です。見込み顧客の獲得から訪問や商談・クロージングまでのフローを可視化することにより、アポイント獲得数や受注率などの営業プロセスを把握できます。これにより、課題の解決に役立てられます。
SFAの詳しい解説はこちらをご覧ください。
SFAとは?CRMとの違いや導入のメリット・おすすめツール5選
プロジェクト管理
プロジェクト管理ツールは、システム開発やWeb制作の現場で用いられているKPI管理ツールです。作業量・作業負荷の可視化、生産性の監視、リソースの最適化などの各種ツール群によって構成されています。
「プロジェクト管理」記事へのリンク追加(URL未定)
採用管理(ATS)ツール
採用の現場では、採用管理ツールがKPI管理で用いられています。採用管理システム(ATS)とは、企業が行う人材採用活動において、応募者の情報管理や採用スケジュールの進行管理など、人材採用に関する業務を一元管理できるシステムになります。
BIツール
さまざまな業種でKPI管理として活用できるのがBIツールです。BI(ビジネスインテリジェンス)とは、企業における各種業務データや市場データなどを収集し、分析・可視化を行うことでビジネスの現状や過去の傾向を把握する手法です。
BIツールの詳しい解説はこちらをご覧ください。
BI(ビジネス・インテリジェンス)とは? 導入のポイントからおすすめのBIツール5選
BI(ビジネスインテリジェンス)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧
まとめ
ビジネスに限らず、目標が達成されるためにはKPIは必須となる指標です。KPIは行動指針となるだけでなく、組織全体のモチベーションを高めることも期待できます。
本記事ではKPIの意味からほかの指標との違いと関連性、設定手順や運営上のコツまでを解説しました。自社のビジネスに合ったKPIを設定・運営することで、目標達成を実現してください。
投稿 KPIはなぜ必要?|KGIとの関係やOKRとの違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 PaaSとは?IaaS、SaaSとの違いやメリット、活用方法を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>この記事ではPaaSの基本的な特徴や機能、利用するメリット・デメリット、主要なPaaSツールなどを紹介します。
PaaSとは?
まずはPaaSについての基本知識を押さえておきましょう。
PaaSの意味
PaaSとは「Platform as a Service」の略で、「パース」と読みます。従来自社のサーバ内などで構築していたアプリケーションソフトや、それを稼働させたりするためのプラットフォーム一式を、インターネット上で提供するサービス形態です。いわゆる「クラウドコンピューティング」の一形態となります。
もともとエンドユーザー向けにオンラインを通じてサービス提供するSaaSがありましたが、PaaSは開発プラットフォーム自体を外部に開放しています。企業をはじめとしたユーザーは、その環境の中で自社に合ったサービスを構築して、展開することが可能です。
代表的なPaaS
世界的に有名なPaaSのサービスには、次のようなものがあります。
・Amazon Web Services(AWS)
・Microsoft Azure
・Google Cloud Platform(GCP)
AWSはAmazonが手がけるPaaSで、世界最大級の通販サイトであるAmazonの知名度やブランド力を生かしてシェアを拡大してきました。いくつかの機能、役割によってさまざまなサービスが用意されています。
・AWSの主なPaaSサービス
| Amazon EC2Amazon CloudWatch | サーバ、リソースの管理やモニタリング |
| Amazon S3 | データストレージサービス |
| Amazon CloudSearch | 検索機能の設定、管理サービス |
Microsoft AzureはMicrosoft社が提供するPaaSです。.NET、Java、PHPなどさまざまな開発用言語が使えるほか、仮想マシンにWindowsサーバが選べるといった点はMicrosoftらしいサービスになっています。
・Microsoft Azureの主なPaaSサービス
| Virtual Machines | オンライン上に展開された仮想マシンを利用できる |
| Azure Storage | クラウド上でファイルやデータの保管または共有をする機能 |
| Mobile Apps | モバイルアプリケーションの設計、構築をアシストする機能 |
PaaSが求められている背景
PaaSは次に紹介するような、企業を取り巻く環境変化に対応し、またビジネスを効率化するために有効であることから、注目を集めています。

災害やトラブル、犯罪対策に適している
災害やトラブル、犯罪などが起きたときにどのように事業を継続するかまとめたものをBCPといいます。BCPとは「Business Continuity Plan」の頭文字を取った言葉で、「事業継続計画」のことです。実際には「災害やトラブルに見舞われても、事業を通常通り継続できる体制を整える」ということもBCPに含む形で、各社は対応を強化しています。
震災や新型コロナウイルスの感染拡大などを受けて、決まった場所にだけデータを蓄積し、オフィスからしかアクセスできないビジネス環境は、BCP上リスクが高いと見られるようになってきています。そのため、BCP対策の一環として、オンライン上にプラットフォームを構築し、非常事態時にもビジネス継続がしやすいPaaSに注目が集まっているのです。
初期費用を抑えることができる
開発工程の多さにもよりますが、従来はアプリケーション開発を自社内で行うとなると、ある程度まとまった費用が必要となるのが一般的でした。そのため、スタートアップや中小企業は開発費用の捻出に苦慮しがちでした。大企業でもシステム開発費用がコスト上の課題になることも少なくありませんでした。
その点、PaaSは初期費用が小さく、「従量課金モデル」を採用しているケースが多いため、ランニングコストはかかっていくものの、初期費用を抑えることができます。企業のコスト管理という点で相性がよく、PaaSの利用が進む理由の1つとなっています。
リモートワークなど多様な働き方に対応できる
セキュリティ上の対策は別途施す必要がありますが、極論をいえばPaaSはインターネットに接続できる環境があれば、どこからでもアクセスしてサービスの開発・運用を継続できます。
新型コロナウイルスの感染拡大を機に、テレワークの環境を整備する企業が急速に増えました。そのときにインターネット上でプラットフォームを提供するPaaSならではの特徴が、改めて注目を浴びました。
PaaSとIaaS、SaaSの違い
PaaSと同様に近年普及したのが、IaaS、SaaSです。いずれもクラウドサービスの一種ですが、それぞれクラウド事業者が管理する範囲、つまりサービス上でできることの範囲が違います。
3つの提供形態
SaaSは「Software as a Service」、IaaSは「Infrastructure as a Service」の略です。PaaSと同様にクラウドサービスの一種で、似たようなサービスを示します。それぞれの違いはクラウド事業者が運用、管理を行う範囲で、次の図のようになっています。
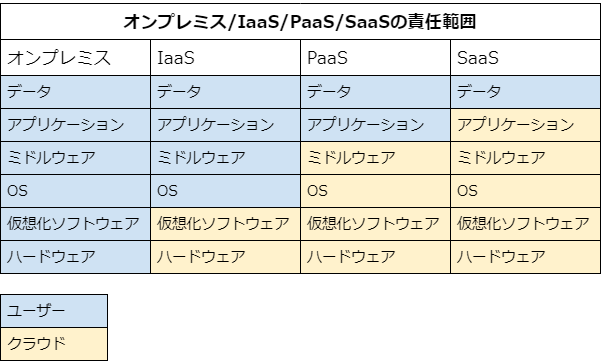
SaaSは、事業者が開発したソフトウェアをインターネット経由で提供するサービスです。
・データをインターネット上に保存
・パソコン・スマートフォン・タブレットなど端末を選ばずにデータにアクセス
・複数の人間が同一データを共有・編集できる
このようにサービス自体は事業者が開発したものをそのまま利用する形態となっています。
PaaSは開発するためのプラットフォーム自体がクラウド上に展開されています。そのため、サービスを利用する企業は、自社が必要とするアプリケーションサービスを、プラットフォーム上で柔軟に開発することが可能です。より多様な機能をクラウド上で開発・管理できるのです。
IaaSは、システム開発や運用に必要なサーバなどの機材とネットワークだけを用意して、オンライン上で提供しているものです。そのため、自分でOSなどを自由に選定して、プラットフォームを構築したうえで、自社の必要とするサービスを開発できます。
PaaSの機能一覧
PaaSにはさまざまな機能が備わっています。ここでは代表的なものを紹介します。
容易な設計・開発の支援
| 機能 | 提供内容 |
| 開発ツールの提供 | コードの記述、コードの編集、構文、デバッグ、またはフレームワーク利用のためのツールを提供 |
| 開発環境の提供 | ソースコードの共有、進行状況の追跡、アプリケーションの展開を管理する統合開発環境を提供 |
| アプリケーションの配置 | アプリケーションを構築、展開、または統合するツールを提供 |
| 言語サポート | Java、C言語、Pythonなどの各種プログラミング言語や、HTML、CSS、JavaScriptなどの各種フロントエンド言語をサポート |
| テスト環境の提供 | アプリケーションの機能をテストし、アプリケーションの問題を診断・検出する機能を提供 |
| クロスプラットフォーム開発の支援 | パソコンやモバイルデバイスなど複数のプラットフォームに対応するための開発オプションを提供 |
このように、アプリケーションソフトを設計、開発するさまざまな機能が備わっています。システム開発に精通した人材を活用すれば、PaaSサービス上で新しいソフトの開発を完結させられます。今ではノーコード・ローコードでの開発が可能な機能が備わっているサービスもあります。
各種ミドルウェア機能
ソフトウェアの開発・管理をするうえで欠かせない膨大なデータベースの管理や分析、破損した際などに備えたバックアップやリストアの機能も備わっています。
| 機能 | 提供内容 |
| データベース管理サービス | さまざまなタイプのデータベースオブジェクトや、管理ツールなどをサポート |
| アナリティクスサービス | データの分析とマイニングを行うアナリティクスサービスを提供 |
| バックアップ/リストア | アプリケーションとデータのバージョン管理、データのバックアップ/リストア機能を提供 |
インフラ・ライフサイクル管理
| 機能 | 提供内容 |
| 自動スケーリング | サービスやデータを自動的、または必要に応じて拡大/縮小するツールを提供 |
| ストレージの提供 | さまざまな形式のデータをスケーラブルに扱えるクラウドストレージを提供 |
| ネットワーク機能の提供 | プロビジョニング、コンテンツ配信、負荷分散、トラフィック管理が行えるネットワーク機能を提供 |
| ライフサイクル管理 | Webアプリケーションのライフサイクル全体を管理する |
開発したアプリケーションを運用する中で発生するデータのストレージや、ライフサイクル管理などをサポートする機能も付与されています。
PaaSを導入するメリットとデメリット
PaaSにはメリット・デメリットがともにあります。それぞれを比較したうえで、自社にとってメリットがより魅力的だと感じるのであれば、導入を検討するとよいでしょう。
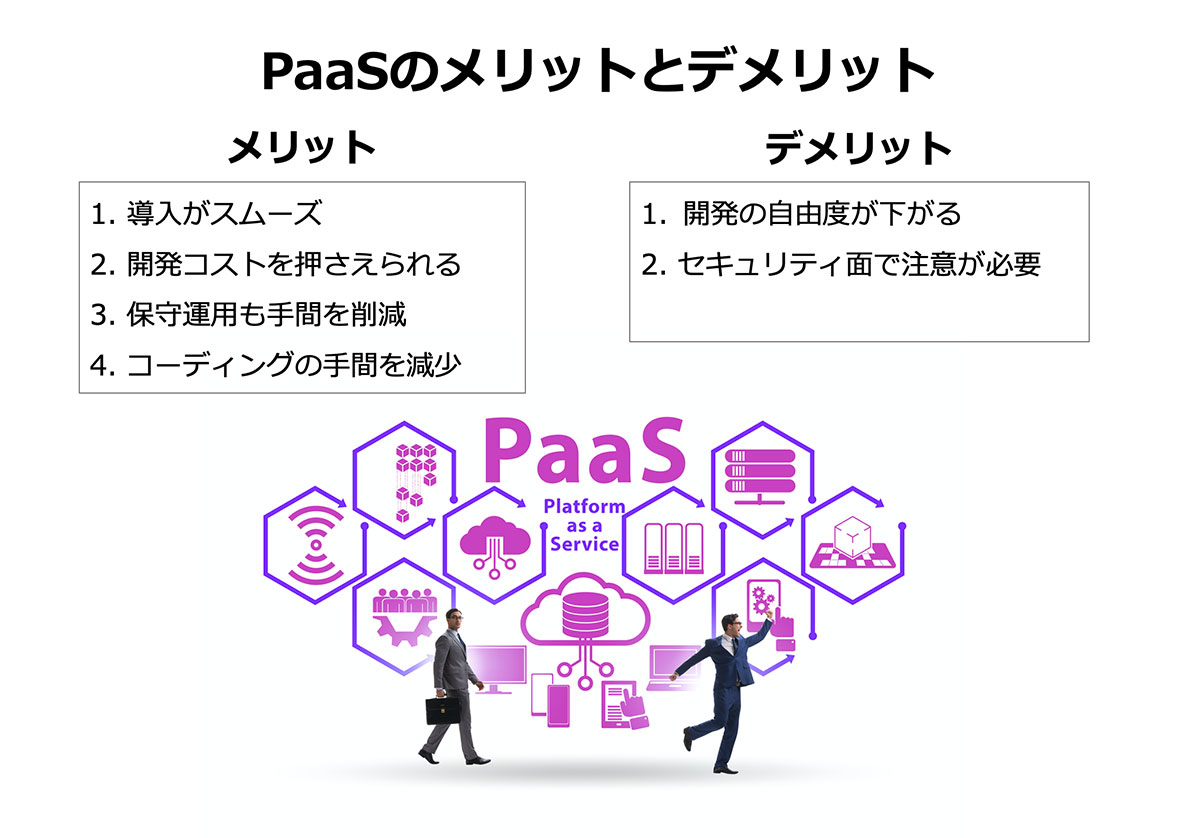
PaaSを導入するメリット
PaaSのメリットは主に次の3点です。
・導入がスムーズで開発コストを抑えられる
PaaS上ではOSやデータベースなどのミドルウェアに相当するシステムはすでに構築済みであり、そこがIaaSとの違いです。そのため、開発者は導入後、すぐアプリケーション開発に着手できます。手間が省けるというのもありますが、プラットフォームを整備するためのコストを抑制できる点もメリットです。
・保守運用の手間を削減
開発したアプリケーションの保守・運用が効率化できます。プラットフォームやハードウェア自体の管理はクラウド事業者が行うため、企業はサービス本体の管理に集中できます。
・コーディングの手間を減少
中にはローコード・ノーコードでアプリケーション開発ができるプラットフォームをもつものもあります。これらのプラットフォームを活用すれば、コーディングにかかる手間も削減できます。
PaaSを導入するデメリット
一方で、PaaSには次のようなデメリットもあります。
・開発の自由度が下がる
プラットフォームは事業者が設定したものを利用することになるため、当然開発環境の自由度は下がります。また、ミドルウェアや使用可能なプログラミング言語も限定されるケースが多いです。より自由な開発環境が求められる場合にはIaaSを検討するとよいでしょう。
・セキュリティ面で注意が必要
セキュリティ面については注意を払う必要があります。パソコンからクラウドネットワークにアクセスする際のセキュリティに注意を払うのは大前提として、クラウド上に置かれるデータのセキュリティは、事業者の質に依存する点でより注意が必要です。
PaaSの活用事例
PaaSを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
誰もが構築可能なデータベースになりうる
「案件管理にて利用開始。この時点では特にレクチャーを受けなくても非常に簡単にデータベースが構築できた。現在ワークフローを検討中。さすがにベンダーからのレクチャーを受けたが、プログラムを書けないスタッフでもやりたい事が10時間程度で構築できた」
https://www.itreview.jp/products/kintone/reviews/73356
▼利用サービス:kintone
▼企業名:株式会社コジマ ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:自動車・自転車
リモートワークに最高のプラットフォーム
「とてもカスタマイズがしやすく、企業にとって最適化された状態に作り込むことができる。非エンジニアでなくてもとてもカスタマイズしやすいUI/UXで素晴らしい」
https://www.itreview.jp/products/salesforce-lightning-platform/reviews/29196
▼利用サービス:Salesforce Lightning Platform
▼企業名:Peach株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:人材
少し高いがサーバの知識がなくてもとりあえず使い始められる
「サーバ管理者がいなくても気軽にアプリケーションの運用をすることができるが、知識がない分お金をかけて管理をするという雰囲気です。サーバやデータベースを物理的にスケールさせることを考えずひとまずアプリを動かすということができます」
https://www.itreview.jp/products/salesforce-heroku/reviews/49987
▼利用サービス:Salesforce Heroku
▼企業名:株式会社言語社 ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
GCP上の連携でさまざまなことができる
「Webアプリケーションのインフラを整えなくても簡単に開発ができるのがいい。Google Cloud Platform上の他機能(Cloud Storageなど)と連携することで複雑なシステムを構築することも可能です」
https://www.itreview.jp/products/google-app-engine/reviews/7564
▼利用サービス:Google App Engine
▼企業名:セーバー株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
パワーポイントのようにwebアプリを作れる
「プログラミングの知識がなくても、スマホで動作するアプリを作ることができるものです。ただし、if文などの簡単な条件分岐などの設定は必要となってきますので、プログラミングの知識が少しは必要になりますので気をつけてください」
https://www.itreview.jp/products/azure-web-apps/reviews/46717
▼利用サービス:Azure Web Apps
▼企業名:北洋銀行 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:銀行
PaaSを導入する際のポイント
せっかく導入するならPaaSの機能を最大限に活用したいものです。次のようなポイントを意識してPaaSを導入するかどうかや、どのサービスを選ぶかを検討するとよいでしょう。
自社のソフトウェアリソースに合ったものを選ぶ
まず、大前提として、ソフトウェアリソースがそろっているかどうかです。これらが適合していない場合は、かえって開発の手間が増大したり、希望するサービスが開発。運用できなくなったりするリスクがあるため、どのようなリソースのもと開発を進めるのか整理しておきましょう。
ソフトウェアリソースにおける主なポイント
| OS(オペレーティングシステム) | WindowsかLinuxが準備されているケースが多い |
| ミドルウェア | PostgreSQL、MySQL、Oracleが一般的だが、Amazon RDSやMongoDBを使うことのできるサービスもある |
| 開発言語 | 代表的なものにはRuby、Java、Python、PHP、Node.jsなどがある。中には独自言語を提供しているサービスもあるので注意 |
| ウイルス対策 | そもそも対策ソフトが用意されているかを確認 |
開発目的にあったものを選ぶ
PaaSはユーザーのターゲット層を絞り込んでいるケースが珍しくありません。
・大規模な商用向け
・スタートアップ向け
・開発初心者でも扱いやすい
・個人開発者向け
また、Webサイト・業務アプリケーション・モバイル・ソーシャルなど、得意分野もPaaSサービスによって異なります。自社の規模や業態と開発するサービス内容を踏まえて、適したものを選ぶことが大切です。
SLA(サービス品質保証)の締結
PaaSはネットワーク上の仮想システムを使うため、セキュリティやサービスに関する責任が曖昧になりがちです。しかし、PaaSのプラットフォームを利用したがゆえに発生したトラブルは、やはりPaaS事業者に責任を負ってもらう必要があるでしょう。
そこで、PaaS導入においてはSLA(サービス品質保証)を締結するのがおすすめです。裏を返せば、SLAの締結がしにくいサービスの導入は避けるのが望ましいといえます。
PaaSの活用・定着させるためのポイント
導入したPaaSをうまく活用する方法や、社内のメンバーに定着させるためには、次の3点に留意しましょう。
コスト管理の徹底
コスト削減を主目的にPaaSを導入するケースも多いと思います。PaaSは利用するサービスの数や規模などに応じて料金が変化する従量制であることが多いため、不用意に多くのサービスを利用するとコストがかかってしまいます。
うまく効果を得るためには、コスト管理を徹底して、効率的にサービスを利用することが大切です。また、導入前とコストを比較して、もっとも大きな効果が得られるサービス利用の仕方を検討しながら活用していくとよいでしょう。
セキュリティ対策を万全に
セキュリティ対策は、質の高いPaaSサービスであれば事業者側でも十分な対策がされています。しかし、多くの場合、他社と同じ仮想空間を共有する共有型のサービスとなっているため、情報漏えいのリスクを完全になくすことはできません。
また、接続するパソコンやネットワークのセキュリティが低ければ、アカウントの乗っ取りなどリスクが高くなります。長期的に安定運用するためには、自社のセキュリティ対策を万全に施しておく必要があるのです。
Paasを活用できる高い開発・運用スキルをもつ人材をチームに入れる
PaaSではアプリケーションの開発や運用は自社で行う必要があります。そのため、ある程度ソフトウェア開発に精通したメンバーを雇っておくのがおすすめです。
今では、ノーコードで開発ができるサービスも出てきていますが、たとえコーディングが不要でも適切なアプリケーション開発は素人が容易に行えるものではありません。専門性の高い人材を配置しておいたほうが無難でしょう。
PaaSの業界マップ
PaaSユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
PaaSに関する製品を比較検討するならぜひITreviewのPaaSページをご覧ください。
まとめ
クラウドサービスの一種であるPaaSは企業のシステム開発コストや手間を削減できるだけでなく、BCP(事業継続計画)の観点でも有効であるなど、メリットの多いサービスです。セキュリティ管理などの注意点もありますが、システム開発の環境に課題を感じている企業は、自社に合ったPaaSサービスの導入を検討してみるとよいでしょう。
投稿 PaaSとは?IaaS、SaaSとの違いやメリット、活用方法を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 マーケティングオートメーション(MA)とは?おすすめツール7選をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、今後MAの導入を考えている方にもわかりやすく、MAの基礎からメリット・デメリット、導入ポイントやおすすめのMAツールまで、MAについて詳しく解説します。
MA(マーケティングオートメーション)とは?
MA(マーケティングオートメーション)とは、マーケティング活動を自動化することにより、見込み顧客を育成するツールやソフトのことをいいます。株式会社矢野経済研究所による「DMP/MA市場に関する調査」によると、MAのマーケット規模は年々拡大を続け、2021年のDMP/MA市場規模は600億円となることが見込まれています。
インターネットの普及により、さまざまな情報に溢れた現在は、顧客の興味はより複雑化し、ニーズの抽出が困難な時代となっています。そんな中、MAは最良のコンテンツの提供や営業による最適なアプローチを行うために導入・活用されています。MAが果たす役割には、主に以下の4つが挙げられます。
- 情報の収集
マーケティング戦略はユーザー情報の収集からスタートします。メールやWebサイト・動画やSNSなどバリエーションに富んだ情報の中、顧客のライフスタイルの多様化に合わせ、マーケティング戦略も細部まで丁寧な対応が求められます。
- 情報の蓄積
顧客から収集した情報は、それに相応しい方法で蓄積を行います。
- 見込み顧客の育成
ユーザー情報の収集・蓄積後、見込み顧客の育成を行います。近年注目されているOne to Oneコミュニケーションを実現するためには、見込み顧客のリスト登録や招待メールの配信・テレアポなどの業務が欠かせません。見込み顧客の求める情報を最適なタイミングで提供できれば、購買意欲を育てることにもつながります。
- マーケティング戦略の分析
メールの開封や未開封・自社サイトへの訪問など、個々の顧客のオンラインアクションを追跡することで、顧客行動などの情報を一元化することができます。一元化した情報は、マーケティング戦略や収益過程などの効果測定にも利用できます。そのため、PDCAサイクルもスピーディーに回すことが可能になります。
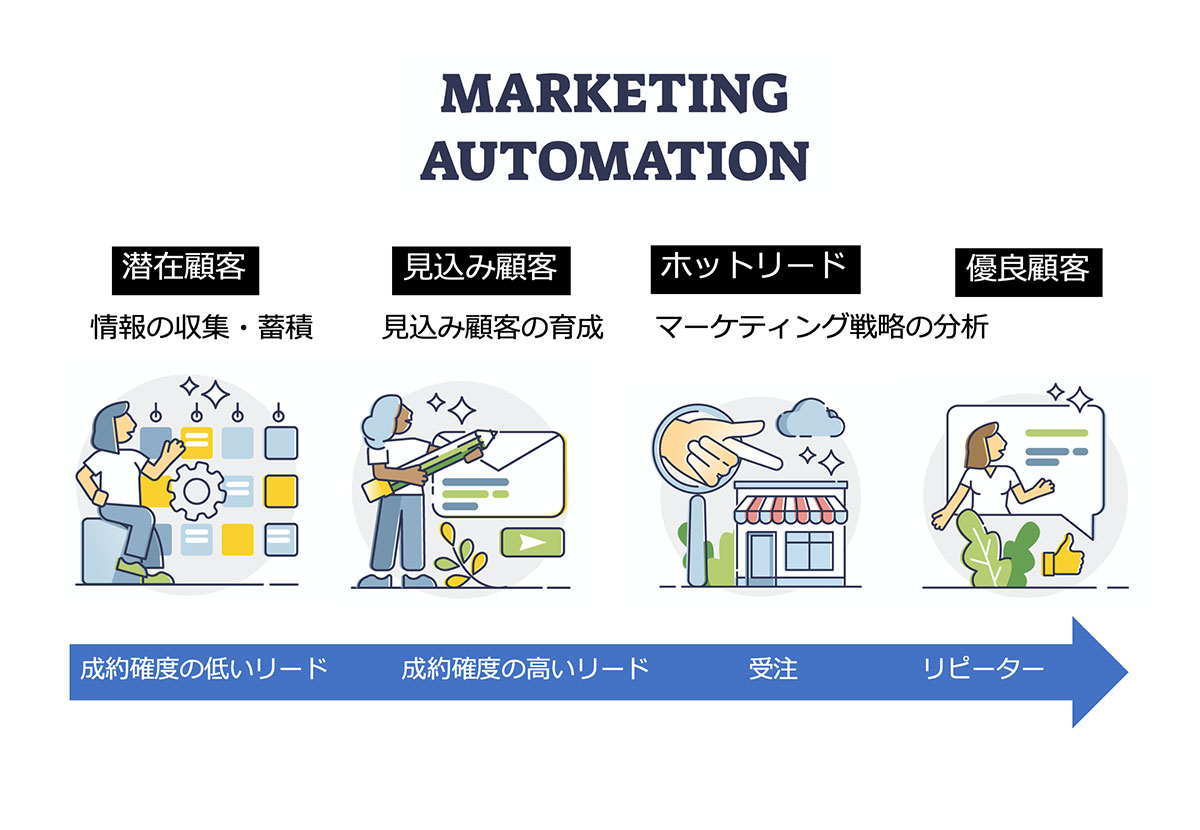
また、MAツールはBtoBだけでなく、BtoCでも利用できるように設計されています。BtoBのツールでは、名刺管理やセミナー・イベントなどの受付管理と連携できるものが増加しています。BtoCルールは、見込み顧客の一元化が可能であり、顧客優先のマーケティングを支援します。
MAツールの基本機能
MAを導入・活用により得られるメリットは数多くあります。BtoB・BtoC問わず、MAを導入する企業は増加傾向にありますが、システムを十分に扱えていないと感じるケースも出てくるでしょう。見込み顧客のアクションログに対し、最適なタイミングでマーケティング戦略を行うために必要な機能について紹介します。
リード(見込み顧客)管理機能
名刺やデータの履歴・資料請求や取引履歴などを一元管理できる機能のことをいいます。情報を得たルートがまったく異なることから、個々に管理されやすい情報も、MAを導入・活用することでリード(見込み顧客)の特性を生かしながらアプローチすることが可能となります。
スコアリング機能
見込み顧客が受注までに至る確度を計算することをスコアリングといい、割り出されたスコアは高い見込み顧客であるかどうかの可能性を知る指標になります。これを自動計算する仕組みを、スコアリング機能といいます。ツールであらかじめ定められた規定に基づき点数が割り出されます。
メール作成機能
メールを作成する機能のことをいいます。テンプレートも豊富に用意されているツールが多くメールの作成が苦手な社員であっても、シンプルでわかりやすく扱いやすい機能となっています。
メール配信機能
メールを配信する機能のことをいいます。メール配信機能は、リード管理機能やシナリオ作成機能などと結びつけて活用することができます。そのため、顧客の特徴や状態に応じた配信が可能です。
シナリオ作成機能
リードの行動を予測したうえでそのアクションに対し、実行する行動作成機能のことをいいます。顧客と自社とをつなぐ信頼関係構築のために必要な機能です。あらかじめシナリオを作成しておくと、メールの配信や電子クーポンの配布というような誘導の一部分をMAが自動で行います。
LP作成機能
広告をクリックしたユーザーが見るページのことを、LP(ランディングページ)といいます。自社の商品やサービスを紹介することにより、ユーザーのアクションを促すために必要な機能です。LP作成を通して得たユーザー情報はリード情報として記録され、見込み顧客の育成に活用されます。
フォーム作成機能
自社のWebサイトへの問い合わせや、資料請求をする場合に名前や電話番号・メールアドレスなどの個人情報を入力する欄のことをいいます。自社とユーザーが出会う契機となることから、重要な機能であるといえます。フォーム作成で得たユーザー情報もリード情報として記録され、その後の育成に活用されます。
レポート・分析機能
正確な誘導を行い、受注につなげて顧客を増加させるために必要となる機能のことをいいます。レポート・分析機能でアクセス解析を活用ことにより、顧客の企業規模や業界まで幅広い情報を把握することができます。問題なく戦略を実行するためにも、顧客情報を詳細まで知ることはとても大切です。
メディア連携機能
TwitterやInstagramなどのSNSと連携を行う機能のことをいいます。目的とするユーザーにアプローチする場合にも、この機能を活用することが効果的です。さまざまなメディアを一元管理し、どのような顧客がどれほどクリックしているなどの分析を行うことができます。
システム連携(SFA・CRMなど)機能
SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)などのシステムと連携可能な機能のことをいいます。マーケティング部門の育成した顧客を、SFAを通して営業部門がチェックするような活用法になります。顧客情報や案件情報から結果としてのマーケティング活動評価に結びつけられる仕組みも導入されています。
MAツールを導入するメリットとデメリット
MAの導入・活用により、営業活動の最適化や小規模でも効果を生むマーケティング戦略が可能となります。MAのメリットや効果を最大限に引き出すためには、オペレーションや明確な目的をもとにした設計を行うことが大変重要になります。
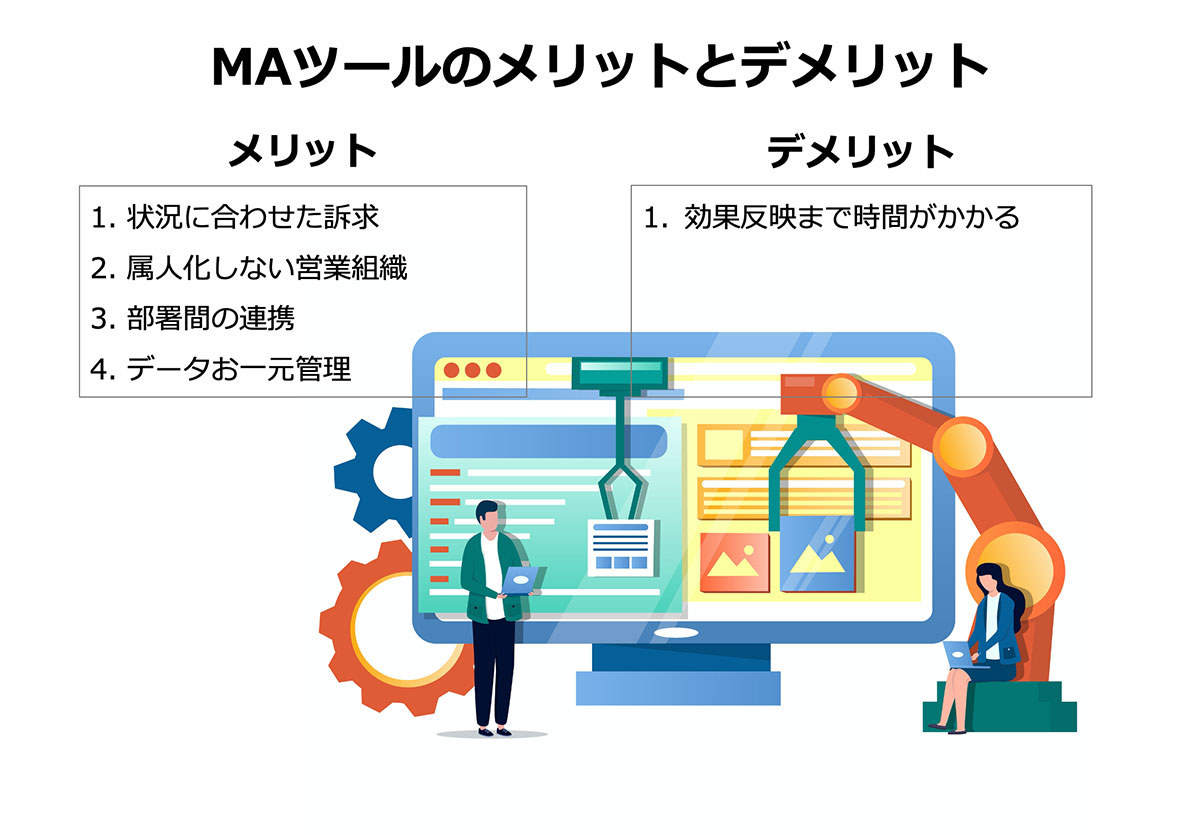
MAを導入するメリット
・見込み顧客の状況に合わせた訴求ができる
MAでは見込み顧客の行動履歴をもとに、自動で状況に応じたアプローチができます。シナリオ設定をして見込み顧客の状況に合わせた訴求をすることで、属人的な手間を省くことが可能です。
すべての問い合わせ客やメルマガ購読者が必ずしも自社製品に興味をもっているとは限りません。見込み顧客は毎日膨大な量の情報を受け取っているため、適切なタイミングで適切な情報を届ける必要性があります。しかし、マーケターや営業が個別に状況を把握し、その状況に合ったアプローチをし、コミュニケーションをとるのは困難です。
見込み顧客のケアを人的作業で行うことには限界がありますが、放置すれば他社の顧客となる可能性もあります。MAを導入・活用すると、見込み顧客の情報を一元化してメール配信やコンテンツ提供などから連絡をとり続けることができます。このような方法により、見込み顧客の流出を防ぐことができます。
MAで見込み顧客の行動変容が把握できれば、製品・サービスに興味があることや、どういった情報を求めているのかまでがわかります。見込み顧客の状況に合わせた訴求により、取りこぼしのないようにアプローチするためにも、MAはとても有効な手段だといえます。
・属人化しない営業組織をつくれる
アウトバウンドが前提だった時代の営業は、属人的な側面がとても強かったといえます。営業の受注率の高さは、各々の性格や能力、経験によって左右されていました。しかし、欲しい情報や商品がオンライン上で簡単に購入できる現代では、営業が直接売り込むアウトバウンドの機会が減少しています。MAはオンライン上で接点のある見込み顧客に持続的コミュニケーションをとることができるため、インバウンドでスムーズなコミュニケーションを具現化できます。
MAを導入してマーケティング部隊が見込み顧客のフィルタリング(選別)とナーチャリング(育成)を終えたところで営業部に見込み顧客をパスすれば、営業の能力に依存せずに営業組織全体の生産性を上げることができます。
また、MAでは経験や勘に頼らずに客観的な判断軸でアプローチをすることができます。“オートメーション”の名の通り“自動化”を推進することで、情報共有が容易になり、属人化した営業活動に頼ることなく効率的なアプローチが可能になります。
・営業とマーケティングで連携しやすくなる
営業は顕在化した確度が高い見込み顧客へのアプローチに注力しがちなので、潜在ニーズ層へのアプローチはどうしても後回しになってしまいます。しかし、それでは潜在的な顧客を逃してしまうリスクもあります。
MAを導入するとマーケティング施策の履歴やWebサイトの閲覧状況などがまとまって管理されるため、マーケティングと営業の間で、状況の共有がよりスムーズにできるようになります。
見込み顧客の検討段階がわからないと、的外れなタイミングや内容でアプローチをしてしまう可能性が高いですが、MAを使って見込み顧客の行動ログに合わせた情報を提供することで、“かゆいところに手が届く”アプローチが可能になります。つまり、マーケティングと営業が連携することで、ニーズが顕在化していない見込み顧客へのアプローチも放置せずに効率よく行うことができるようになるのです。
・見込み顧客のデータを一元管理できる
多くの施策を実施し、管理する情報が増えると、見込み顧客の情報の管理がバラバラになりがちです。MAを使うことで、見込み顧客のデータを一元管理することができます。MAにはデータ分析機能があり、見込み顧客ごとに、資料のダウンロード履歴やセミナーの参加状況、Webサイトの閲覧状況などのデータから戦略の効果を測定することもできます。受注確度の高い見込み顧客を抽出することで、より生産的なアプローチも可能となります。
MAツールを導入するデメリット
・効果反映まである程度の時間が必要
MA導入後は繰り返しPDCAを実行し、戦略を練り続けることが必要となります。またMAを活用するにはコンテンツの制作費やメール配信のための設計により出費が増える可能性があります。そのため、短期的な視野に捉われることなく、時間をかけて効果を上げていくことが重要です。
MAとSFA・CRMの違い
MAのほかに注目を集めるツールとして、SFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)があります。MAがマーケティング活動を自動化するツールであるのに対し、SFAは営業担当者を支援するツールです。またCRMは、顧客との信頼関係構築のためのツールとなっています。これら3つのツールにそれぞれ異なる点があるように、得意とする分野にも以下のプロセスにおいて明確な違いがあります。
MA・・・リードの育成や選定
SFA・・・商談から契約に至る過程
CRM・・・優良顧客との関係維持・改善
一連のフローを通じて、プロセスごとに必要となる取り組みを支援するのが、これら3つのツールの特徴です。自社の求めるツールの選別には、以下の課題解決法を知る必要があります。
| MAツール | 集客への迷いがあるケースには、リードの育成や選定を行いたい場合に最適 |
| SFAツール | 営業知識の蓄積不足のケースでは、商談情報の共有と業務効率化に有益 |
| CRMツール | 優良顧客の維持・改善不足のケースには、優良顧客の育成に効果的 |
MAツールの活用事例
MAツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
円滑なコミュニケーションと生産性の向上を実現
「現状の弊社の管理項目との突き合わせや提案など親身になって調整や提案をしていただきスムーズな導入に結び付いた。資料請求を処理する業務部署と、その後のアプローチをかける営業部とのやりとりがシームレスに行えています」
https://www.itreview.jp/products/saaske-lead/reviews/54121
▼利用サービス:サスケLead
▼企業名:株日本ビスカ株式会社 ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:デザイン・製作
セミナーの参加率が増加、顧客の好みも可視化
「当社の強さであった営業マン主導の顧客関係維持は、移動制限、実の営業が制限されるコロナ下では、属人化されたものであると問題視されました。シャノンマーケティングプラットフォームを使い、属人化した顧客情報をSMPを使い組織的に共有し、顧客主導の顧客関係維持に変革しました。これまで、製品紹介セミナーの案内も営業マンが主導でしたが、SMPを活用して行いました。結果として、セミナーの参加率が増加、顧客の好みも可視化されました。より顧客が求めるニーズの把握にもつながり、増収増益にもつながる事になりました」
https://www.itreview.jp/products/shanon-marketing-platform/reviews/71780
▼利用サービス:HANON MARKETING PLATFORM
▼企業名:イスクラ産業株式会社 ▼従業員規模:100-300人未満 ▼業種:医薬品
マーケティングに必要な全てを達成可能
「2020年のMarketo Masterです。レベニューモデルを構築し実施できるツールはMarketo Engageだけです。顧客の獲得から、育成、インサイドセールスにパスをして、商談化、営業がクローズした受注情報までも取り込むことで、一気通貫でマーケティングに必要な情報を管理、運営、可視化まですることができるツール。メールの送信、イベントの管理をする”だけ”のマーケティングオートメーションではなく、SalesforceなどのCRMともシームレスに連携をすることができるので、全ての情報をMarketoの中で管理し、マーケティング活動を行うことができるのがMarketo Engageの最大の価値だと考えています。売上を最大化するために必要なマーケティングを実施することができるのは、Marketo Engageがあってこそです」
https://www.itreview.jp/products/marketo/reviews/50335
▼利用サービス:Adobe Marketo Engage
▼企業名:株式会社エイトレッド ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
MA初心者にもおすすめ!
「ステップメールやシナリオメール機能を使って、営業がフォローしきれない顧客のフォローを実施しています。また、シナリオメール配信の途中でHOTになった顧客は営業にパスできるように自動通知メールを送っています。結果的に、放置してしまう顧客がいなくなったことで機会損失が減り、逆に確度の高い顧客だけを営業にパスできるようになったので営業の無駄アポも減りました。副次的な効果かもしれませんが、営業担当と企画担当の関係性も良くなったように感じます」
https://www.itreview.jp/products/kairos3/reviews/49936
▼利用サービス:Kairos3
▼企業名:株式会社リクルート ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:人材
業務効率化や効果の数値化に寄与「カスタマーリングス」
「メルマガの到達率が上がりました。今まで何らかのエラーで配信ができなかったお客様も自動で届くまでアプローチしてくれるので、エラーで配信できなかった人の数が減りました。分析データは、条件の掛け合わせがたくさんできるので、複雑なデータ分析が効率よく簡単に抽出できるようになり、楽になりました」
https://www.itreview.jp/products/customer-rings/reviews/30112
▼利用サービス:カスタマーリングス
▼企業名:関西鉄工株式会社 ▼従業員規模:50-100人未満 ▼業種:50-100人未満
MAツール導入のポイント
近年、多くのMAツールが登場していますが、機能や操作性・費用面は個々のツールによってまったく異なります。ツールを導入する際に大切なことは、他社製品との比較を行ったうえで自社に合う最良のMAツールを選ぶことです。導入後問題なく活用していくためには、以下の8つのポイントを押さえておきましょう。
導入目的を明確に
MAツール導入前のプロセスとして、どういう機能のある製品でどういったマーケティング戦略を実現したいのか明確にしておきましょう。MAツールは機能が多岐にわたるものから限定的なものまで幅広くあります。自社の導入目的を定め、必要な機能と不必要な機能とに分類を行い、選定を進めていきます。
自社のリード情報をチェック
ナーチャリングの対象であるリード(見込み顧客)を自社でどれほど保有しているかということも、導入前に把握しておくべき情報です。また自社と顧客との関係の確認も、顧客ごとに適切な戦略実行のために必要です。関係の確認をすることによって、導入後の誘導設計を行いやすくなります。
マーケティング戦略の構築
導入前のプロセスとして顧客にどういう課題があり、解決のためにどういったコンテンツが必要であるのかなどの戦略を組み立てるための指標を出します。しかし、目的を設定して戦略を実行しても、必ずしもすぐに効果が反映されるとは限りません。そのため、常に先の状況を想定しながら次なる戦略を立てる必要があります。
確実に自社に合う製品を選定
自社に最適なMAツールを選ぶことは、導入前にさまざまな対策を講じるうえでも大切なことです。自社の目的から逸れることなく、他社ツールとの比較を上手に行いながら選定をすることを心がけましょう。
課題解決に必要な機能の確認
自社の抱える課題を解消してくれるツールを導入することは必然ですが、導入前に想定していた施策があとで変更される可能性も否定できません。そうしたこともあらかじめ想定して、必要になりそうな機能をしっかり考えたうえでツールを導入することも視野に入れておきましょう。
運用プロセスの調整
導入後も順調にMAツールを運用してくためにも専任の担当者を定めておきましょう。効果は顧客の求めるニーズによっても変化するので、動向を常に把握し確認や変更を繰り返すことが大切です。戦略の促進とより円滑なコミュニケーションには、PDCAサイクルを上手に活用する担当者の存在が必要不可欠です。
他部門との緊密な連携
MAツールを導入・活用した結果として、受注率の増加に成功していることが求められます。そのため、営業部門との強固な連携が欠かせません。また具体的な連携内容を、マーケティング部門で確認可能な仕組みを整えることも重要です。社内で積極的に情報共有ができれば、課題の解決や改善にも寄与します。
SFA・CRMといった他ツールとの連携
SFAやCRMなどのほかのツールと連携を行うことにより、企業のデータ管理をより最適なものにできます。また高い精度の効果測定や検証も可能となるだけでなく、部門ごとの社員のスキルを高めることにもつながります。マーケティング部門と営業部門の連携不足と思われる企業は、SFA・CRMなどとの連携をすることを検討しましょう。
MAツールの業界マップ
MAツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
おすすめのMAツール7選
実際にMAツールを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのMAツールを紹介します。
(2021年12月4日時点のレビューが多い順に紹介しています)
SHANON MARKETING PLATFORM
あらゆる業務の効率化・自動化・データ管理から、スムーズな情報伝達を可能にするクラウドアプリケーションです。目的や工程を明確にしたマーケティング活動のサポートや、セミナー・イベント運営の拡張によりリードの獲得に向けるバーチャルイベント等、幅広い業務をサポートしています。
SHANON MARKETING PLATFORMの製品情報・レビューを見る
Adobe Marketo Engage
デジタルからアナログまで最適な瞬間にメッセージを届けるマーケティングエンゲージメントプラットフォームです。BtoBやBtoC・業種問わず、国内外に5000社以上の導入実績をもつマーケタ―に向けたプラットフォームを提供しています。
Adobe Marketo Engageの製品情報・レビューを見る
Kairo3
扱いやすさに焦点を置いたクラウド型MAサービスです。営業とマーケティングを1つに結びつけることでニーズを把握し、高品質な営業活動を支援します。豊富なサポート体制と、リーズナブルな費用で利用できます。
ホットプロファイル
名刺管理と見込み顧客発掘・SFAを融合させることで生産性や売上の向上を目的としたクラウド型の営業サポートツールです。データベースを中心として営業戦略と顧客のリアクションを一元化し、リアルタイムで情報を可視化できることでスムーズな営業戦略を具現化します。
カスタマーリングス
顧客データを分析し、メール配信や郵送DMなどの方法での接客を実現するツールです。ECサイトの在庫情報と連携を行うと、在庫の少なくなったタイミングで通知できます。ある程度検討期間の長い業界を中心にさまざまな国内企業で活用されています。
BowNow
シンプルで使いやすくローコスト、リストアプローチ業務の自動化が可能なツールです。高いコストパフォーマンスを発揮できるマーケティング戦略を立てられます。マーケターと営業の両者が共通認識を持ち、最適なタイミングでピンポイントに見込み客にアプローチをすることで、効率的にマーケティング施策の成果を出すことができます。
サスケLead
見込み客を管理・育成するためのクラウドサービスです。リードデータを一元管理できるだけでなく、名刺や書面資料のデータ化やパソコンからの電話受発信可能なCTI機能などのほか、クリック率やアクセス解析といったシステムも備えています。多くの企業に導入・活用されています。
ITreviewではその他のMAツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
MA(マーケティングオートメーション)の比較・ランキング・おすすめ製品一覧
まとめ
MAツールを導入・活用するときには、当然のことながらコンプライアンスを遵守しながら活用する必要があります。システムを適切に扱うことさえできれば、会社の利益にもつながっていきます。またスムーズな運用を実現するためには、導入前から慎重に施策を練ることが重要です。
MAツールを運用する際には、運用コストに対し結果が伴っていることも重要です。そのためには人的リソースや将来的なビジョンまで見通したうえで、現実的な運用計画を構築しましょう。他社製品との十分な比較も行いながら、自社に最適なツールを選ぶことが必要となります。
投稿 マーケティングオートメーション(MA)とは?おすすめツール7選をピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 働き方改革とは何か?その背景から関連法、実施内容と課題まで は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで政府が打ち出した施策が「働き方改革」です。しかし働き方改革は労働基準法や労働安全衛生法など複数の法律にまたがる改革であるため、具体的な取り組みがわかりにくい面があります。本記事では、働き方改革が提唱された背景から関連する法律、メリット・デメリットなどを解説し、取り組みに役立つツールを紹介します。
働き方改革とは?
「働き方改革」とは、人々がそれぞれの事情に対応した柔軟な働き方や、理想とする暮らし方の実現に可能性を与える働き方を自分で選べることで、誰もが働き続けることができる社会をめざす考え方です。現在の日本は少子高齢化と人口の減少により、生産年齢人口が減少を続けています。そのため、働ける人を増やすことが急務とされ、これまでの働き方を抜本的に見直さなければならない段階にあります。
働き方改革が提唱された背景
2017年3月、内閣官房に「働き方改革推進会議」が設置され、労働制度の抜本改革を行い、働く人の1人ひとりがより良い将来の展望を持ち得ることをめざした「働き方改革実行計画」がまとめられ、ロードマップが示されました。翌年の2018年になると、「働き方改革関連法案」が可決・成立しました。そして2019年4月1日からは、「働き方改革関連法案」の一部が施行されています。
労働人口の減少
日本の人口は2008年をピークに減少し、少子高齢化が進み続けています。そのうち労働力として数えられる15~64歳の生産年齢人口のピークは1995年で、その後減少を続けています。そのため、現在では多くの業界で人手不足となっていますが、今後はさらに、育児や介護などによる離職や休職も深刻化するとみられています。
このことから、企業の生産性が下がり、GDPも低下することが予想されます。こういった状況を打開する対策として、働く意欲のある人が働ける環境を整え、1人当たりの生産性を高めるために、国と企業の連携として「働き方改革」を推進する必要が生じました。
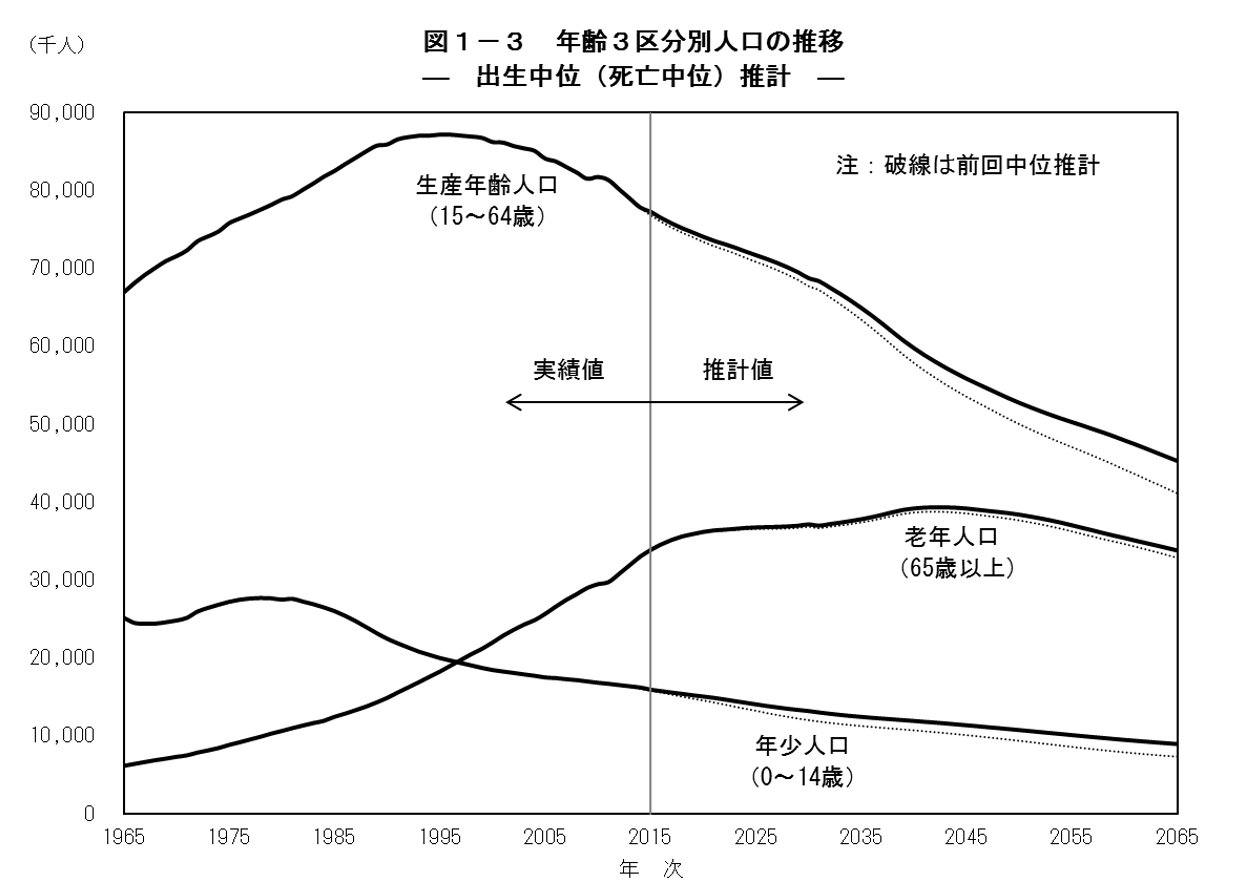
<出典:国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口(平成29年推計)』の図1-3 年齢3区分別人口の推移―出生中位(死亡中位)推計―>
生産性の低さ
労働者1人当たりが生み出す成果や1時間当たりに生み出す成果を「労働生産性」と呼びます。労働生産性は、国の経済成長に寄与するといわれます。ところが現在の日本の労働生産性は、主要先進国が加盟するOECD(経済協力開発機構)の中では特段に低く、公益財団法人日本生産性本部が発表した『労働生産性の国際比較 2020』によれば、日本の時間当たりの労働生産性は47.9ドルとOECD加盟国の37カ国中21位でした。
<出典:『労働生産性の国際比較 2020』p9「(図7)OECD加盟諸国の時間当たり労働生産性(2019年/37カ国比較)」>
また、日本の1人当たりの労働生産性は8万1183ドルで、OECD加盟国中の26位でした。
<出典:『労働生産性の国際比較 2020』p4「(図3)OECD加盟諸国の労働生産性」>
このように先進国中ではかなり低くなっている労働生産性を高めるためにも、働き方改革が必要とされています。
長時間労働による健康状態の悪化
日本では高度成長期に、従業員がプライベートよりも仕事を優先して休日出勤や超過勤務を行うなど、長時間労働を拒みにくい、あるいは率先して行うことが評価されやすい土壌がつくられており、令和時代に入った現在もまだ、企業側や従業員側の双方に影響を与えています。
そのため、長時間労働に起因する心身への悪影響や家庭環境の悪化は現在でも生じており、過労死や自殺まで引き起こした可能性があることがメディアに取り上げられ、国民の感心を高めました。このような企業文化は長時間労働を常態化させやすく、生産性の低い日本では社会や経済にマイナスの影響をもたらしていると考えられます。このことを改善するためにも、働き方改革が必要とされています。
働き方改革の3つの柱
前項の背景となった諸問題を解決すべく、働き方改革は以下の3つの柱で成立しています。
1. 労働時間の是正
長時間労働を是正するために、罰則付きの労働時間規制や休暇取得の義務化、そして長時間労働に対する割増賃金率の引き上げについて法改正がなされています。
2.正規雇用と非正規雇用の格差の改正
非正規労働者の割合は約4割を占めます(2021年3月時点)。労働改善を行うために、非正規労働者の不合理な待遇差を禁止する法改正がなされています。
3.柔軟な働き方の実現
従業員がワーク・ライフ・バランスを保つために、長時間労働の是正だけでなく、テレワークの推進など、働き方の多様性を実現する法改正がなされています。
それでは1つずつ見ていきましょう。
長時間労働の是正または解消
長時間労働を解消しなければ、働き方は変わりません。長く働くことを評価するのではなく、限られた時間の中でより生産性を高める働き方を評価する企業文化の醸成が必要です。そのためには休日出勤の禁止や残業の事前申請制、フレックスタイムの導入などの対策も必要になります。また、有給休暇の取得率を高めるためのルール作りも重要です。
非正規・正規の格差解消
多くの会社では正規雇用従業員と非正規雇用従業員が混在して業務に当たっています。その中で、同じ業務を行っているにもかかわらず、賃金や通勤手当の有無、派遣切りなど待遇の差があることで、非正規雇用にはマイナスのイメージが生じていました。
この不平等や格差を解消すべく、働き方改革による取り組みが進められています。具体的には非正規雇用の従業員の有給休暇に関して就業規則に盛り込まれることで休みがとりやすくなったり、正社員への登用が進んだりする取り組みが行われています。
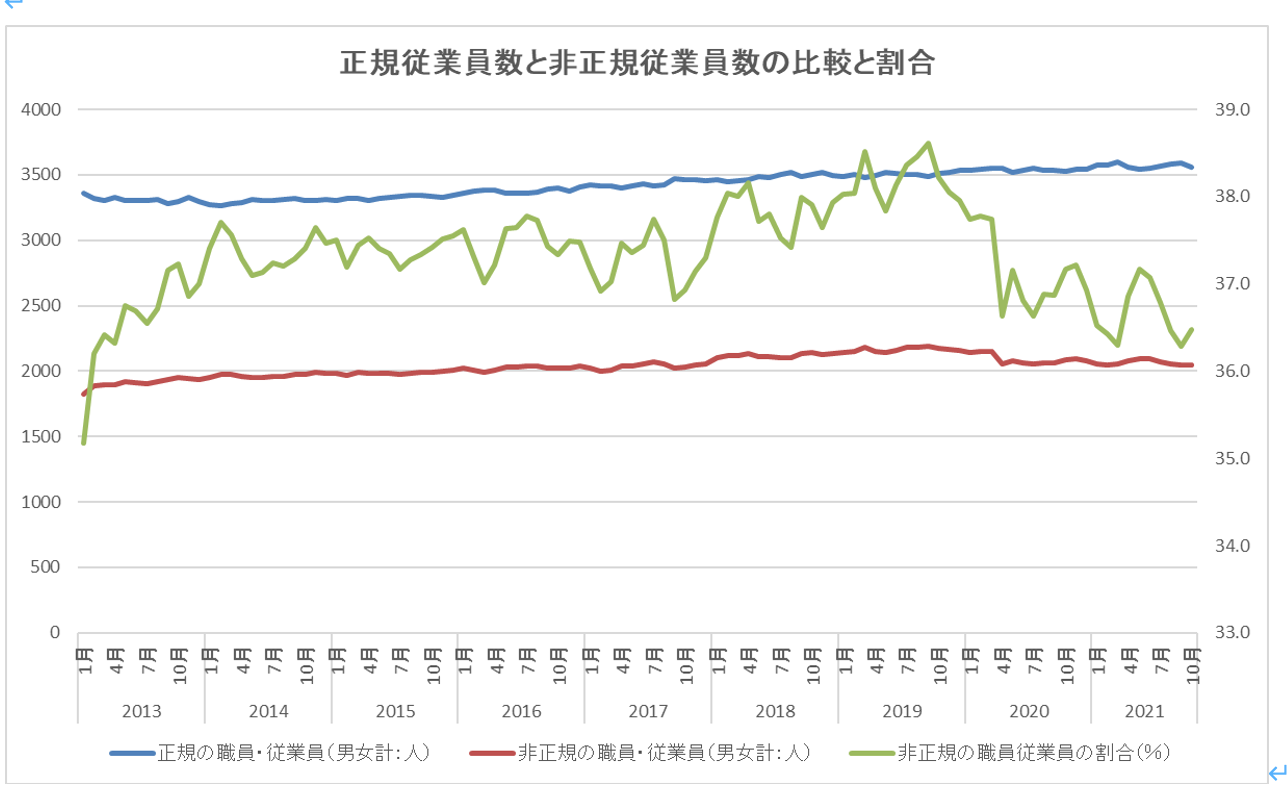
※グラフは総務省統計局『労働力調査 長期時系列データ』(役員を除く雇用者【「正規の職員・従業員」,「非正規の職員・従業員」】(エクセル:43KB))のデータを基に作成
柔軟で多様な働き方の実現
新型コロナウイルスの感染拡大がテレワークの導入をはじめとする働き方の多様化を加速させました。従業員は1人ひとりがさまざまなライフスタイルをもち、それぞれに異なる事情を抱えています。また、少子高齢化が進む中で、出産や育児、介護等のライフイベントが働き方を左右します。このように多様な暮らし方が必要とされる中で労働参加率を高めるためには、働き方の多様性を実現する環境を整備しなければなりません。
たとえば、出産や育児、介護と仕事を両立できる環境の整備。テレワークや在宅勤務、あるいは短時間勤務制度の導入などです。さらに、職場にキッズスペースを併設して子ども連れ出勤を可能にしたり、副業や兼業を認めたりすることも柔軟で多様な働き方の実現に寄与します。
働き方改革関連法とは?
「働き方改革関連法」の正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」で、働き方改革を実現するための法律を示します。ただし、働き方改革関連法は新たに成立した法律ではなく、従来の労働関連法規を改正したものです。
改正された内容と対象となった法律は以下の表の通りです。
| 内容 | 適用時期 | 改正された法律名称 |
| 時間外労働の上限規制 | 大企業:2019年4月 中小企業:2020年4月 |
労働基準法 |
| 年5日の年次有給休暇の取得義務 | 2019年4月 | 労働基準法 |
| 勤務間インターバル制度導入の促進 | 2019年4月 | 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 |
| 割増賃金率の引き上げ | 中小企業:2023年4月 | 労働基準法 |
| 労働時間の客観的把握 | 2021年4月 | 労働安全衛生法 |
| 同一労働・同一賃金の原則 | 大企業:2020年4月 中小企業:2021年4月 |
パートタイム・有期雇用労働法 |
| フレックスタイム制の拡充 | 2019年4月 | 労働基準法 |
| 産業医・産業保健機能の強化 | 2019年4月 | 労働安全衛生法等 |
表中の各内容について見ていきます。
時間外労働の上限規制
時間外労働の規制が設けられました。平時の残業時間の上限が月に45時間、年360時間に制限されます。しかも、これまでは残業時間が上限を超えても行政指導が行われるだけでしたが、2019年4月からは30万円以下の罰金や半年以下の懲役が科せられるようになりました。
年5日の年次有給休暇の取得義務
年間で10日以上の有給休暇を与えられる労働者は、年に5日間の有給休暇を確実に取得しなければなりません。これは労働者の希望の有無にはかかわらず、違反すれば30万円以下の罰金が科せられます。
勤務間インターバル制度導入の促進
労働者の健康を維持するため、終業から次の始業までの間に一定時間のインターバルを設けることが努力義務となりました。これは、始業時間が固定の場合に、残業した翌日に睡眠不足のままで仕事に臨まないようにという配慮です。退勤後から翌日の出社時刻までに、9~11時間程度の間隔を空けることが定められています。
割増賃金率の引き上げ
時間外労働が月に60時間を超えた場合は、超過時間分の割増賃金は50%以上に引き上げることが義務となります。以前は適用対象が大企業に限られましたが、2023年4月以降は中小企業も適用となります。違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
労働時間の客観的把握
2019年4月より、雇用するすべての従業員の労働時間を、客観的な記録に基づいて把握することが義務化されました。大企業と中小企業共に対象となります。
同一労働・同一賃金の原則
同じ企業や団体の中で、正規雇用者と非正規雇用者の間に賃金や福利厚生などにおいて不合理な待遇の差がある場合には、是正しなければなりません。適用時期は、大企業は2020年4月から、中小企業は2021年4月からです。
フレックスタイム制の拡充
労働時間を柔軟に調整できるフレックスタイム制の精算期間が1カ月から3カ月に拡大されました。たとえば、これまでは6月中のフレックスタイムによる労働時間は6月中の合計が総労働時間に満たなければ欠勤扱いで、超えていれば割り増し賃金の対象でした。これが6月に働き過ぎた分は8月までに短時間勤務にすることで調整できるようになったのです。
高度プロフェッショナル制度の新設
アナリストや研究者など、高度な知識を有して一定水準以上の年収を得ている厚生労働省令指定の業務に従事する労働者を対象に、労使の合意がある場合は労働時間や休日、割増賃金などの規定を適用しない制度です。つまり、裁量労働を認めることになります。
産業医・産業保健機能の強化
従業員の健康リスクを回避するために、従業員がいつでも産業医による健康相談や指導を受けられるように、事業者が体制を強化する制度です。従業員が50名以上の企業への適用は2019年4月からでしたが、2021年4月からはすべての中小企業が対象となっています。
働き方改革によるメリットとデメリット
働き方改革が推進されることで、従業員や企業にとってどのようなメリットとデメリットがあるのか解説します。
従業員にとってのメリット
・長時間労働が是正され、ワーク・ライフ・バランスが実現します。
・出産や育児、介護などのライフイベントに合わせた働き方を選べます。
・同一労働同一賃金が推進され、雇用形態の違いによる待遇の格差がなくなります。
・有給休暇を取得しやすくなります。
従業員にとってのデメリット
・長時間労働ができなくなるため、生産性の向上や業務効率化を行う負荷がかかります。
・業務効率化ができなかった場合に、隠れ残業が増える可能性があります。
・時間外労働が縮小されることで、収入が減る可能性があります。
・高度プロフェッショナル制度が乱用され、業務量過多になる可能性があります。
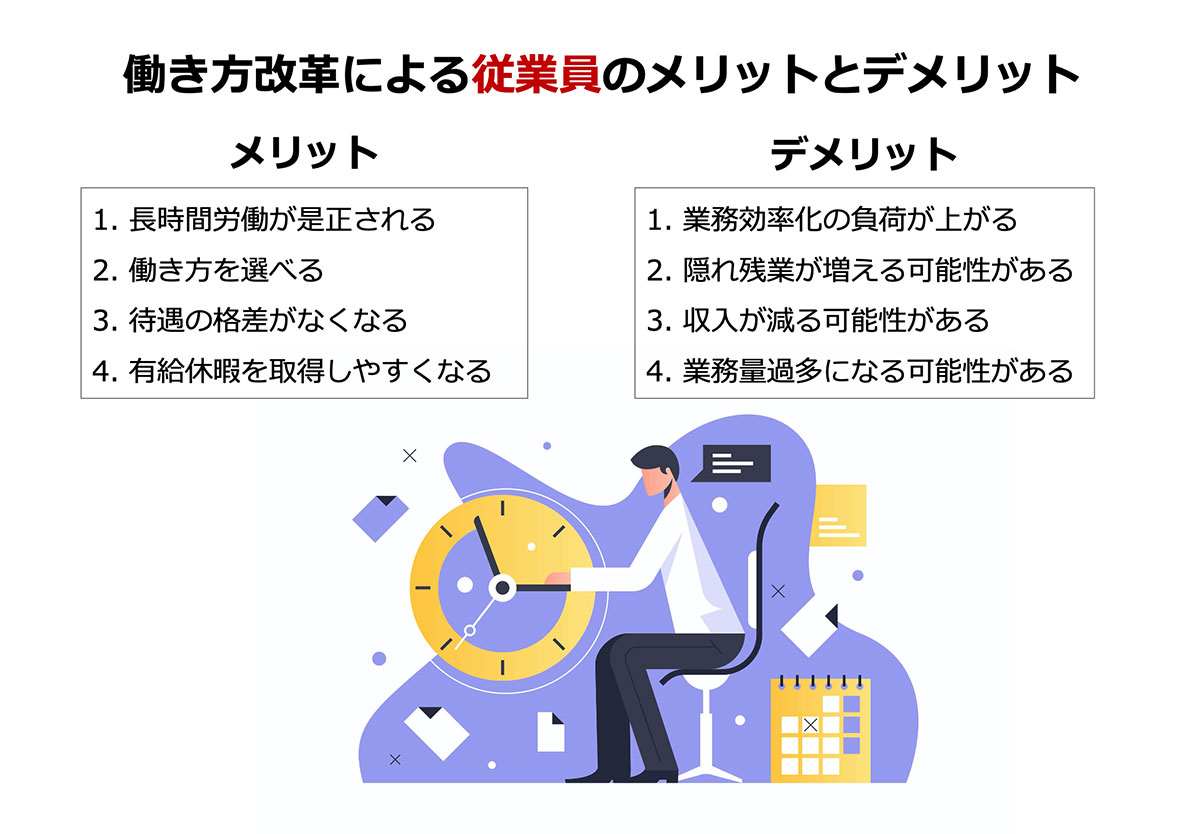
企業にとってのメリット
・業務の効率化が促進され、人件費が削減されます。
・労働環境が改善されることで、人材の離職率が低下します。
・柔軟な働き方に対応することで、人材を採用しやすくなります。
・有給休暇が取得しやすくなることで、求職者に好感をもたれます。
・働き方改革に取り組んでいることで、企業イメージが高まります。
企業にとってのデメリット
・規制が先行して業務改善が追いつかないと、作業が期日までに完了されないなど、機会損失リスクが生じる可能性があります。
・労働環境改善のために、ツールの導入費や人事育成費などのコストが増大します。
・社内規約の見直し負荷がかかります。怠ると行政指導が入る可能性があります。
・賃金格差を是正するために、人件費が増加する可能性があります。
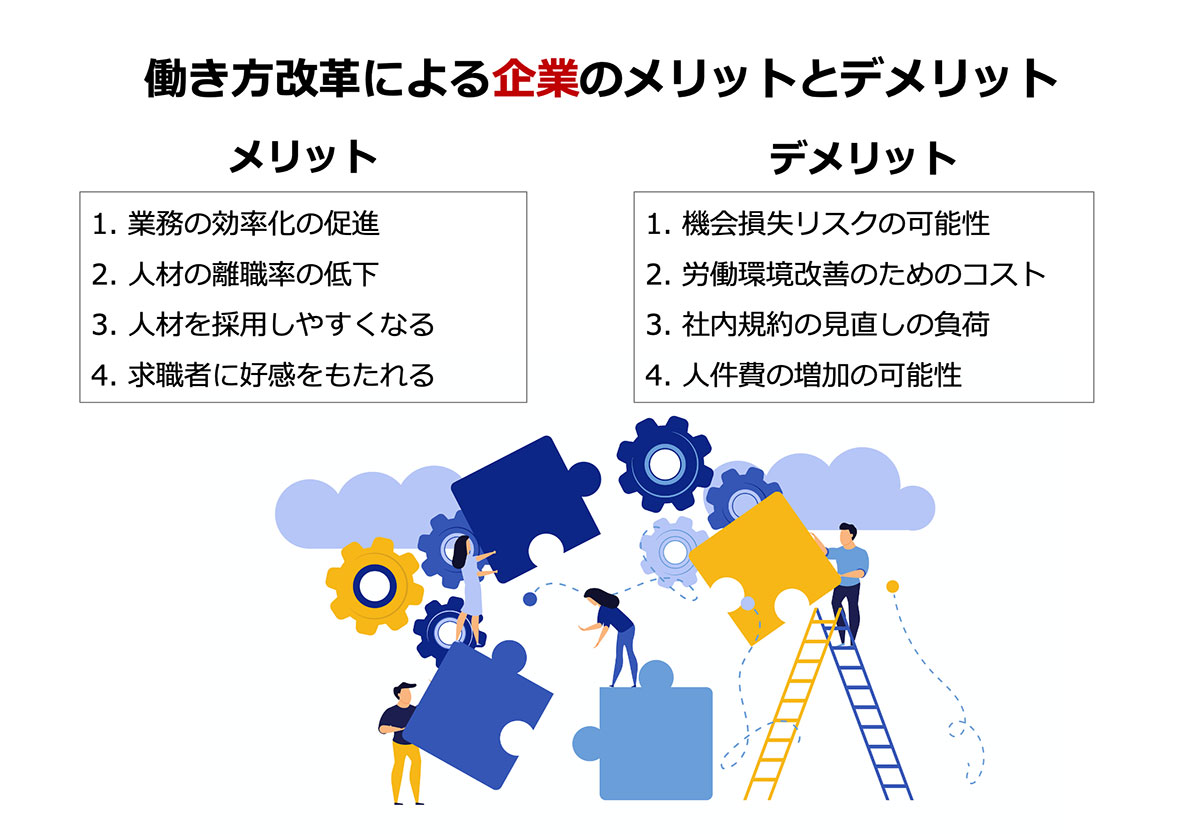
働き方改革を推進するうえでの課題
働き方改革を推進するうえでの課題について解説します。
勤怠管理のコストが増加
時間外労働の上限規定を守るためには、出退勤時間の客観的な記録と、数カ月間の平均労働時間のモニタリングを行わなければなりません。また、有給休暇の消化状況と残りの日数をモニタリングしなければなりません。さらに、テレワークで在宅勤務をしている従業員の勤務時間もモニタリングが必要です。これらの課題に対処するためには、自社に適した勤怠管理システムの導入が必要です。
人材確保
残業の削減や有給休暇の消化率を高めること、出産や育児、介護などによる勤務時間短縮や休業で、従業員各人の労働時間が減少します。しかし、会社全体の業務量を減らすことができない場合は、新たに人材を確保する必要が生じます。
意識改革
残業の上限や有給休暇の取得率を高めることは、従来の仕事量を減らすことができない従業員にとっては迷惑に感じることがあります。また、これまで残業代も重要な収入であった従業員にとっては、事実上の減収となります。このようなことから従業員が不満をもち、仕事へのモチベーションを低下させてしまう可能性があります。このことに対処するためには、会社と従業員にとって、なぜ働き方改革が必要なのか合理的な説明を行うことと、残業時間を削減しても生産性を高めて成果を出せている従業員を正当に評価できるように評価制度を見直すことが必要になります。
デジタル化の整備
働き方改革を推進するためには、書類の電子化やテレワークの導入、勤怠管理システムの導入に伴い、さまざまなITツールを使いこなすスキルが従業員に求められます。その結果、ITリテラシーの格差が生じる可能性があります。このことに対処するためには、従業員1人1台のデジタル端末の整備、VPNやクラウドサービスの整備、ITスキル習得のための教育体制の整備が必要になります。
従業員間の不公平感
テレワークやフレックスタイム制の導入により働き方の多様性に対応することで、従業員の間に、業務負荷の偏りや働き方の自由度の差など、不公平感が生じる可能性があります。このことに対処するために、社内規定や評価制度の見直し、従業員間のコミュニケーションの円滑化を進める必要があります。
人件費の増加
同一労働同一賃金が義務化されることで、従来の賃金差を解消するために、人件費の負担が増加します。このことに対処するために、企業は従業員1人当たりの生産性を高めるための業務プロセスの見直しやデジタルツールの導入を推進するなど、業績を高めるためのより一層の努力が求められます。
働き方改革を進める際に検討すべきこと
何も準備をせずに働き方改革を見切り発進してしまうと、すぐに問題が発生してしまう可能性があります。このことを防ぐために、大きく3つの面から準備を行います。
現状の課題を分析する
働き方改革の推進を機に、自社の現状の課題を洗い出します。具体的には作業現場の事情調査を行うことで改善点を洗い出します。また、部門やチームごとの生産性を把握しておき、働き方改革の推進後に生産性の変化を確認できるようにしておきます。
ワークフローの見直し
テレワークの導入や残業時間の削減、有給休暇取得の義務などを実施しても会社全体の生産性が下がらないように、事前に現状の業務フローを見直し、無駄な工程や作業があれば改善しておきます。
ツールの導入
テレワークの導入や残業時間の削減、有給休暇取得の義務などを実施することで、在宅勤務でも生産性を高められるツールや勤怠管理が行えるツール、各従業員の作業時間が短縮されても生産性を下げないために業務効率を高めるツールなどの導入を行います。
企業の働き方改革とDX
働き方改革を推進するためには、業務のデジタル化を行わなければ生産性が下がってしまうリスクがあります。そこで、自社のDX(Digital Transformation)推進が必要になります。
DXとは
DXとは「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略語です。ITを活用して社内の業務改革やビジネスモデルの変革を促し、企業の競争優位性を確立して収益を上げることをめざします。DX化は、働き方改革を推進するためにも必要不可欠です。
DXについての更なる詳細はこちらをご覧ください。
DX推進と働き方改革の関連性
DXと働き方改革の関係について例を挙げます。
・テレワークの導入
多様な働き方の1つとしてテレワークを導入するためには、在宅勤務を行う従業員がオフィス勤務時と遜色のない業務を行える環境の整備が必要です。具体的にはチームのコミュニケーションやプロジェクト管理、勤怠管理、情報共有などをオンライン化します。
・単純作業の自動化
残業時間の上限規定や有給休暇の取得義務、同一労働同一賃金を実現するためには、現在手作業で行っているデスクワークをRPA(Robotic Process Automation)により自動化して効率を高める必要があります。
働き方改革の実現をサポートするために必要なツール
働き方改革を推進するために欠かせないITツールについて紹介します。
Web会議ツール
在宅勤務中の従業員とのコミュニケーションだけでなく、取引先との打ち合わせや商談、支社・支店との会議など、さまざまな場でWeb会議ツールを活用する機会が増えています。
ビジネスチャット
Web会議ツールと同様、在宅勤務中の従業員とのコ間だけでなく、取引先との打ち合わせや商談、支社・支店との間など、さまざまな場でタイムリーなコミュニケーションや情報共有を行うためには、グループ単位やプロジェクト単位で簡潔なやりとりが行えるビジネスチャットの活用が有効です。
グループウェア
社内や在宅勤務中のメンバーで、連絡や情報交換、ファイル共有、タスク管理、ナレッジ共有などを行うためには、グループウェアの活用が必須になります。
ファイル共有
在宅勤務中や出張中、あるいは移動中でも常に最新のファイルをチームで共有するためには、クラウド上でファイルを共有できるツールの活用が必須です。
「オンラインストレージの比較・ランキング・おすすめ製品一覧」
リモートアクセスツール
在宅勤務中や出張中、あるいは移動中でも社内のサーバだけで管理している書類やファイルが必要になることがあります。このようなときに外部から社内サーバにアクセスできるリモートアクセスツールが必要になります。
バーチャルオフィス
在宅勤務中はほかのメンバーが何をしているのか、どのような状況にあるのか把握しにくくなります。また、自分もメンバーとともに働いている連帯感を得にくく、孤独感が生じることもあります。このような問題を解消するために、離れていてもお互いの状況を把握し合えるバーチャルオフィスが有効です。
勤怠管理ツール
在宅勤務中の従業員の勤怠管理や残業時間、有給休暇の取得状況などをリアルタイムで正確に把握するためには勤怠管理ツールの活用が必須です
情報共有ツール
働き方改革を推進するためには、在宅勤務中の従業員だけでなく、社内においても企業内に蓄積されたナレッジの共有を効率化する必要があります。このときに活躍するのが情報共有ツールです。
「マニュアル作成・編集の比較・ランキング・おすすめ製品一覧」
RPA
働き方改革を推進するために、残業上限の規定や有給休暇の取得義務など、従業員の働く時間が短縮されても生産性を落とさないためには、デスクワークの自動化が必須です。このときに活躍するのがRPA(Robotic Process Automation)です。
まとめ
働き方改革を推進することは、少子高齢化が進む中で誰もが働き続けられる社会をつくるという、社会的な要請に企業が取り組むことです。しかし、働き方改革を安易に進めてしまうと、企業の生産性を下げてしまうリスクがあります。
一方、働き方改革への取り組みを、従来の業務プロセスやビジネスモデルの見直しの機会として捉え、課題の洗い出しや生産性を高めるためのITツールの導入、社内規定の改定やビジネスモデルの開発などを行うことで、企業としての競争優位を獲得することができます。
十分に準備を行えば、働き方改革への取り組みを自社の成長につなげることができるでしょう。
投稿 働き方改革とは何か?その背景から関連法、実施内容と課題まで は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 テレワークと在宅勤務は違う?ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>在宅勤務とは?
在宅勤務とは、オフィスに出社せずに自宅で勤務する働き方です。ただし、まったく出社せずに勤務するとは限らず、決まった曜日だけに出社したり、必要に応じて出社したりするなど、さまざまなパターンがあります。近年の働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大の影響により、在宅勤務を導入する企業が増えています。主にパソコンなどの端末で作業できる業務を中心に導入が進められています。
働き方改革についての詳細はこちらからご覧ください。
テレワークと在宅勤務の違い
テレワークはICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を活用した、時間や場所に制約されない働き方を示します。したがって、自宅のみならずカフェやコワーキングスペース、ホテル、あるいは交通機関での移動中に働くことを示します。そのため、テレワークにはモバイルワークやサテライトオフィスワークが含まれます。
在宅勤務も自宅で勤務することを示しているので、モバイルワークと同様にテレワークの一形態であるといえます。そして、テレワークが働き方の概念を示す際に使われる傾向があることに対し、在宅勤務は働き方の形態を示す際に使われる傾向があります。また、テレワークが会社員や個人事業主など、雇用形態は問わないことに比べ、在宅勤務は「勤務」という言葉が含まれているように、企業に雇用されている人の働き方を示すことが一般的です。
在宅勤務のメリットとデメリット
在宅勤務制度の導入を検討されている企業は増えてきていますが、導入を検討するにあたり、在宅勤務のメリットとデメリットを確認しておきましょう。
ここでは、働く側と企業側に分けて解説します。
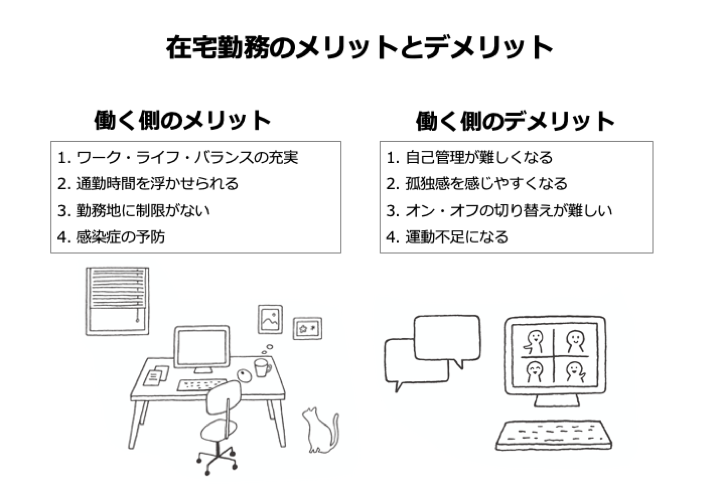
在宅勤務がもたらす従業員のメリット4つ
1.ワーク・ライフ・バランスの充実
在宅勤務制度が導入されていると、育児や介護をしながらでも働きやすくなり、家庭で不測の事態が生じた際にも柔軟に対応できます。その結果、ワーク・ライフ・バランスの充実につながります。
2.通勤時間を浮かせられる
在宅勤務になれば、バスや電車、あるいは自家用車を使用しての通勤がなくなるか、減らすことができます。その結果、通勤に費やしていた時間を節約できるうえ、ストレスも軽減されるため、精神的にも肉体的にも余裕が生まれるでしょう。それにより、趣味や自己啓発などを充実させることができます。
3.勤務地に制限がない
在宅勤務制度が導入されれば、通勤時間や距離の制約がなくなるため、居住地の選択の幅が広がります。子育てや介護などにより適した環境を選んだり、配偶者の転勤に伴って転居しやすくなったります。
4.感染症の予防
在宅勤務により通勤電車やオフィスなど、人と密に接する機会が減ることで、新型コロナウイルスやインフルエンザといった感染症のリスクや不安・ストレスを軽減できます。
在宅勤務による従業員のデメリット4つ
1.自己管理が難しくなる
自宅で作業をしていると集中できる反面、誰からも見られていないため、休憩する頻度が高くなったり業務以外のことに気を取られやすくなったりする可能性があります。自己管理ができなければ生産性が下がってしまいます。
2.孤独感を感じやすくなる
在宅勤務では1人で作業をしており、同僚や上司などがともに働いている姿を見たり気配を感じたりすることがありません。また、同僚や上司と気軽に声をかけ合うこともなくなります。そのため、孤独感を感じる人が出てきます。
3.オンとオフの切り替えが難しい
自宅で作業を行っていると仕事とプライベートの境界が曖昧となり、仕事のオン・オフの切り替えが上手くできずに生産が低下したり、ストレスが増えたりする可能性があります。
4.運動不足になる
通勤やオフィス内での移動がなくなり、自宅で椅子に座ったままの状態で過ごす時間が長くなるため、運動不足になりがちです。
在宅勤務がもたらす企業側のメリット4つ
1.光熱費などのコストを削減できる
在宅勤務を導入することで、オフィスの光熱費や通勤費などのコストを削減することができます。また、スペースの削減も可能になるため、より賃貸料の安いオフィスへの移転も検討できるでしょう。
2.業務を効率化できる
在宅勤務では各人が自宅で作業を行うため、電話への対応や来客への対応、予定外の打ち合わせなどにより業務を中断することが少なく、作業効率が高まり生産性が上がります。
3.人材を確保しやすい
在宅勤務を前提にしていれば、人材を採用する際に居住地の制約がなくなるため、地域に縛られずに広く人材を求めることができます。また、育児や介護などにより休職や退職を検討している社員に在宅勤務を提案することで、離職率を下げることができます。
4.緊急時における事業の継続性
各人が自宅で勤務していることで、自然災害や感染症拡大などの緊急事態発生時に、事業を継続しやすくなります。また、緊急事態時に障害が発生して業務が中断しても、早期に復旧できる可能性が高まります。
在宅勤務による企業側のデメリット4つ
1.勤怠管理を見直す必要がある
従来の勤怠管理方法では、オフィス勤務と在宅勤務という異なる勤務方法で働いている従業員や、同じ従業員でもオフィス勤務の日と在宅勤務の日が混在している状態を管理することはできなくなります。在宅勤務制度を導入する際には、新しい勤怠管理システムを導入する必要があります。
2.生産性が低くなる可能性
在宅勤務ではオフィスに出勤している際の雑務がなくなる分、生産性が高くなることが期待されます。しかし、人によっては自宅で仕事をすることで怠けやすくなったり、家族に干渉されやすくなったり、あるいは家庭の用事に気を散らされたりするなど、生産性が下がる可能性もあります。
3.コミュニケーションが不足する
各人が離れて仕事をしていると、オフィスという空間を共有して仕事をしているときに比べ、チーム内のコミュニケーションが不足します。気軽に相談し合ったり、雑談を交わしたりすることで補われていた情報交換や励まし合いなどが減ってしまいます。そのため、お互いの進捗状況や負担の軽重を確認し合うことが難しくなります。
4.セキュリティリスクが高まる
在宅勤務では社外で端末を使用することになり、情報漏洩やサイバー攻撃、端末の盗難などセキュリティリスクが高まります。
5.従業員の精神面のケアが難しくなる
オフィスで同僚や上司が空間を共有して仕事をしているときには、気軽に相談や励まし合うことができました。また、働いている姿を確認できたため、体調や精神状態の変化に気づきやすい環境でした。しかし在宅勤務では孤立した状態で仕事を行うことになるため、精神面での不調に気づきにくくなり、サポートも難しくなります。
在宅勤務を導入する際の注意点
在宅勤務制度を導入する際には、企業側で注意すべき項目があります。
在宅勤務の相談窓口を用意する
在宅勤務制度を導入する際には、在宅勤務を行う従業員に不安や疑問が生じます。このとき、在宅勤務者用の相談窓口を決めておかないと誰に相談してよいのかわからず、詳しそうな従業員に相談が集中してしまいます。結局不安も疑問も解消できないまま在宅勤務が始まってしまったり、相談されやすい人の業務に支障が生じたります。このような事態を避けるために、在宅勤務の相談窓口を用意しておきます。
全社的なセキュリティ対策を強化する
在宅勤務では社外の端末で作業が行われるためセキュリティリスクが高まります。これに対して個々に対策が行われることを当てにしてしまうと、セキュリティ対策の程度にばらつきが出てしまい、結果的にはリスクが高いままになってしまいます。そのためセキュリティ対策は全社的に対応しなければなりません。ルールを決め、従業員にセキュリティ教育を徹底し、全社的なセキュリティシステムを構築する必要があります。
勤怠に関するルールを整備する
在宅勤務時の勤怠ルールを決めておかないと、従業員によって勤怠に対する解釈や姿勢の差が出て、労働時間の管理が困難になります。また、ルールを決めないでいると、在宅勤務者の勤怠姿勢がゆるく感じられ、オフィス勤務者に不公平感を与えてしまう可能性もあります。
移行期間を設ける
業務内容に関わらず在宅勤務を一斉に導入してしまうと、さまざまなトラブルが同時に発生して、対処が間に合わない状態が続き生産性が下がってしまいます。また、業務上の不備も生じてしまう可能性があります。このような事態を避けるために、比較的在宅勤務に適してる部門から導入を始め、トラブルや課題を解消しつつ順次ほかの部門への導入を進めていきます。
コミュニケーションツールを導入する
在宅勤務を導入して各従業員が離れて仕事をしていても、常に円滑なコミュニケーションが維持できるように、Web会議ツールやチャットツール、グループウェア、あるいはプロジェクトやタスクを管理するツールなどを整備します。
対面でのコミュニケーション機会を設ける
在宅勤務中は、さまざまなツールで円滑なコミュニケーションを維持するように努めますが、それでも各人の負荷の差や精神面での不調などを把握しきれない可能性があります。これを補うために、ある程度は対面で会話できる機会を設けたり、チームが集まれる機会を意識的に設定しておきましょう。
評価制度を見直す
在宅勤務では、オフィス勤務のときのように管理者が部下の業務プロセスや仕事への姿勢などを把握することが難しくなります。そのことでオフィス勤務者との間や在宅勤務者同士の間で評価に対する不公平感が生じやすくなります。そのような状況を防ぐために、あらかじめ在宅勤務者への合理的な評価を行う仕組みを整備しておく必要があります。
出社と在宅のハイブリッド型も検討する
在宅勤務を導入する際、すべての勤務日を在宅勤務にすることで業務に支障が生じることがあります。それを防ぐため、決まった日だけをオフィス勤務とするハイブリッド型の在宅勤務を採用するなど、柔軟な制度導入を検討する必要もあります。
在宅勤務の業務をサポートするITツールを導入しよう
多くの企業が在宅勤務制度を導入し始めています。在宅勤務を導入する際には、メリットとデメリットを理解し、労務関連の規定を見直す必要があります。また、多くのツールを活用することで在宅勤務を効率化するだけでなく、従業員のメンタルヘルスにも注意を払う必要があります。
在宅勤務の導入に成功すれば、人材の確保や維持、生産性の向上、そして企業イメージの向上など、いくつものポジティブな効果が期待できるでしょう。
投稿 テレワークと在宅勤務は違う?ポイントを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 アウトソーシングとは?人材派遣との違いは?メリットと注意点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>アウトソーシングとは?
アウトソーシングは、業務に必要な人やサービスを外部(アウト)から調達(ソーシング)することを意味する和製英語です。自社の外から購入する経営資源すべてが対象で、自社の関連会社やグループ会社へ業務委託をする場合も含まれています。しかし一般的には、主に外部から「業務を担う人」あるいは「人に付随するサービス」を調達するときに、アウトソーシングという言葉が使われます。
土台となる考え方は1960年代、アメリカのIT分野で誕生したといわれています。特に当時のIT分野は設備投資や運営費がかさみ、問題となっていました。そして、1989年にイーストマン・コダック社が自社の情報システム運用をIBM社に委託 したことが話題となり、アウトソーシングの認知度が高まったのです。同年、セブン-イレブン・ジャパン社が野村総合研究所と情報システムに関するアウトソーシング契約を結び、日本で一番早くアウトソーシングを取り入れた事例として知られています。
もともとは情報システムの関連業務を外部委託する際に用いられていたアウトソーシングでしたが、近年では人事、経理、営業、物流など、あらゆる分野が対象。急速なビジネス環境の変化に社内人材の教育が追いつかない、自社の社員をコア業務以外に割く余裕がない、むやみに人件費を増やせないなど、さまざまな理由が複合的に絡んでいます。
アウトソーシングは、自社の特定業務を外部の専門企業に発注することで、コスト削減と業務クオリティ向上の両立をめざすものです。また、貴重な人的資源である自社社員をより重要なコア業務につけるため、それ以外の付加価値が低い業務をアウトソースすることが普通になってきています。戦略的なアウトソーシングの活用が、企業競争力を高めることにつながるのです。
なぜアウトソーシングの需要が高まっているのか?
株式会社矢野経済研究所が2021年に発表した調査結果によると 、2020年度の国内BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービス市場規模は、事業者売上高ベースで4兆4307億8000万円円となっています。さらに同社の予測では、2021年度の国内BPOサービス市場規模は2.0%増の4兆5314億9000万円を見込んでいます。大きく分けて「ビジネスのグローバル化と多角化経営」「少子高齢化に伴う労働人口減少と人材不足」「働き方改革やDXの進展」の3点を背景に、アウトソーシング市場は今後も堅調な成長が続く予想です。
ビジネスのグローバル化・多角化経営の広がり
国内の市場規模縮小、海外市場への販路拡大、安価な人件費など、さまざまな背景からビジネスのグローバル化が進んでいます。自社のもつ技術や経験を活用し、リスク分散や複数の収入源を確保する目的で、多角化経営をめざす企業も増えてきました。技術進歩やグローバル化が急速に進む国際市場で競争力を高めるため、より一層のコア業務集中と差別化が求められています。事業規模を広げたり、新しい事業を展開したりするためには、既存の業務クオリティを維持しながら、効率化を図る必要があります。自社の社員が優先すべき業務に専念できるよう、アウトソーシングが注目されているのです。
慢性的な労働力不足
少子高齢化により労働人口は減少を続けており、業種や業態を問わず、あらゆる分野で労働力不足が問題となっています。人材獲得競争が激化する一方で、事業の多角化により業務量は増加傾向です。限られた社員数で幅広い業務を遂行することが求められ、利益に直結する、優先度の高い業務に集中しきれない現状が課題となっていました。マーケティングやリサーチなど専門性が高い業務や、サポート業務のようなノンコア業務をアウトソースして、自社にとって重要な業務に人的リソースを投下する戦略が主流になりつつあります。
働き方改革・DXの推進
働き方改革やDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるにあたり、業務効率化や業務変革をめざす企業が増えたことも、アウトソーシングの需要を高めています。また、2020年に発生した新型コロナウイルス感染拡大で、外出自粛によるテレワークが普及したことも、業務の外注化を加速させました。
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?意味・定義の解説と企業が取り組むべき理由
アウトソーシングと人材派遣、SESとの違い
アウトソーシングと人材派遣、SES(システム・エンジニアリング・サービス)は、外部リソースに業務委託するという点で共通しているため混同されがちです。ここではアウトソーシングと人材派遣、SESの違いを紹介します。
業務の遂行方法
アウトソーシングの場合、業務そのものをアウトソーシング企業が代行します。人材派遣とSESは人材を供給して、委託元企業で働いてもらいます。SESはソフトウェアやシステムの開発・保守・運用など、エンジニアが技術サービスを提供しますが、人材派遣との違いは、人材派遣がプロジェクトごとに複数の企業を移動することが多いのに対し、SESは1つの企業に常駐する点です。
対価の発生方式
アウトソーシングは、業務が行われたことや、出来上がった成果物に対して支払われます。人材派遣とSESは、人材自体を提供するサービスなので、その人材の労働に対して対価が発生するのです。
委託元との関係(スタッフへの指示命令系統)
アウトソーシングとSESは、委託先のアウトソーシング企業やSES企業に、指示命令権があることが特徴です。委託元がスタッフに直接指示や依頼が出せない点に注意が必要です。一方で人材派遣は、委託元である派遣先企業に指揮命令系統があるので、派遣スタッフに対して自社社員と同じように指揮監督できます。
| アウトソーシング | 人材派遣 | SES | |
| 業務の遂行方法 | アウトソーシング企業が、委託された業務を遂行する | 人材派遣会社が、委託元で業務を遂行する人材を派遣する。プロジェクト毎に他企業に移動する場合が多い | SES企業が、委託元で技術的サービスを提供するエンジニアを派遣する。ひとつの企業に常駐する |
| 対価の発生方式 | 業務の遂行、成果物の納入 | 人材の派遣、派遣先企業(委託元)での労働 | エンジニアの派遣、派遣先(委託元)での労働 |
| スタッフへの指揮命令系統 | アウトソーシング企業が指揮監督する | 派遣先(委託元)企業が指揮監督する | SES企業が指揮監督する |
さまざまなアウトソーシングの種類と形態
ひとくちにアウトソーシングといっても、さまざまな種類や形態があり、自社が抱える課題や経営スタイルによって、適切なアウトソーシングは異なります。
アウトソーシングの種類
・BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)
BPO(Business Process Outsourcing)は業務プロセスのアウトソーシングを指し、企画や設計から実施まで、業務プロセスの上流に関わる委託が可能です。BPOの対象となる分野は、人事、総務、経理が多く、専門性が高い企業にアウトソースすることで、コストと自社リソース削減、業務クオリティ向上を両立させることが目的です。経営資源を適切に配置するため、戦略的に採用する企業が増えています。
→BPOの詳しい解説はこちらをご覧ください。
・ITO(インフォメーション・テクノロジー・アウトソーシング)
ITO(Information Technology Outsourcing)は、自社の情報システム関連業務をアウトソースすることです。ITOに適している業務は、システム運用や管理の中でも、定型的で汎用性の高い業務です。コスト面やクオリティ面と同時にセキュリティ面の観点から、専門企業に依頼したほうが、自社で対応するよりも効率が良いケースが多々あり、ITOの広がりを後押ししています。
・KPO(ナレッジ・プロセス・アウトソーシング)
KPO(Knowledge Process Outsourcing)とは知的業務に関するアウトソーシングです。医療品開発や航空機設計、データ分析など、専門性が高い知的生産活動を外部に委託します。多くのKPO企業が、インドや中国に拠点を構えており、高い教育を受けた多数の優秀な人材に、比較的低賃金で委託できる点が特徴です。
アウトソーシングの形態
・コソーシング
コソーシング(Co-sourcing)とは、アウトソーシングの委託企業と受託企業が対等の立場で、協働することです。従来型のアウトソーシング契約とは異なり、コソーシングでは自社の社員も一緒に業務を行います。受託企業側のスキルやノウハウを吸収して、自社の知識や知見を積み重ねることができます。事業成功により計画値を上回って利益が出た場合、受託企業は追加報酬を得られる仕組みになっており、これまでのアウトソーシング契約のデメリットを解消する形態として、コソーシングの認知度が高まりつつあります。
・マルチソーシング
マルチソーシング(Multi-Sourcing)とは、業務分野ごとに最適な受託企業を選んで、複数の企業とアウトソーシング契約を結ぶことです。特定の1社に幅広い業務領域を任せる従来の方法は、業務コントロールが困難になったり、コストが膨大になったり、多くの課題がありました。マルチソーシングは、課題ごとにアウトソーシング企業を選別し、判断を重ねていくため、目的意識の徹底と管理強化が期待されています。
・クラウドソーシング
クラウドソーシング(Crowdsourcing)とは、インターネット経由で、不特定多数の人的ネットワークから人材を探して業務を任せることです。通常のアウトソーシングとの違いは、人材レベルに大きく幅がある点です。そのためデータ入力業務など、簡易かつ定型の業務に向くとされてきました。近年は働き方改革や副業解禁の流れに伴い、クラウドソーシング市場は急速に拡大しており、対象となる分野や業務も多岐にわたってきています。
→クラウドソーシングの詳しい解説はこちらをご覧ください。
・オフショアアウトソーシング
オフショアアウトソーシング(Offshore outsourcing)とは、海外に拠点があるアウトソーシング企業に委託することです。特にIT分野でのプログラム開発で用いられます。人件費が安価かつ労働力が豊富であることから、コストをかけずに能力の高い人材を確保できる点が魅力です。
・シェアードサービス
シェアードサービス(Shared Service)とは、複数のグループ企業がある場合に、共通部門の業務を1か所に集約する方法です。経理や人事、総務、法務、情報システムなど、本来はグループ企業それぞれに存在する機能をグループ内の1社がまとめて担います。多角化経営が進み、グループ企業が増えた結果、共通部門で人件費やオフィス、システムなど、重複してコストがかさむ問題を解消すべく導入する企業が増えています。自社の関連会社でアウトソーシングを行う一例といえます。
アウトソーシングのメリットとデメリット
アウトソーシングを活用することで期待できるメリットとデメリットを解説します。
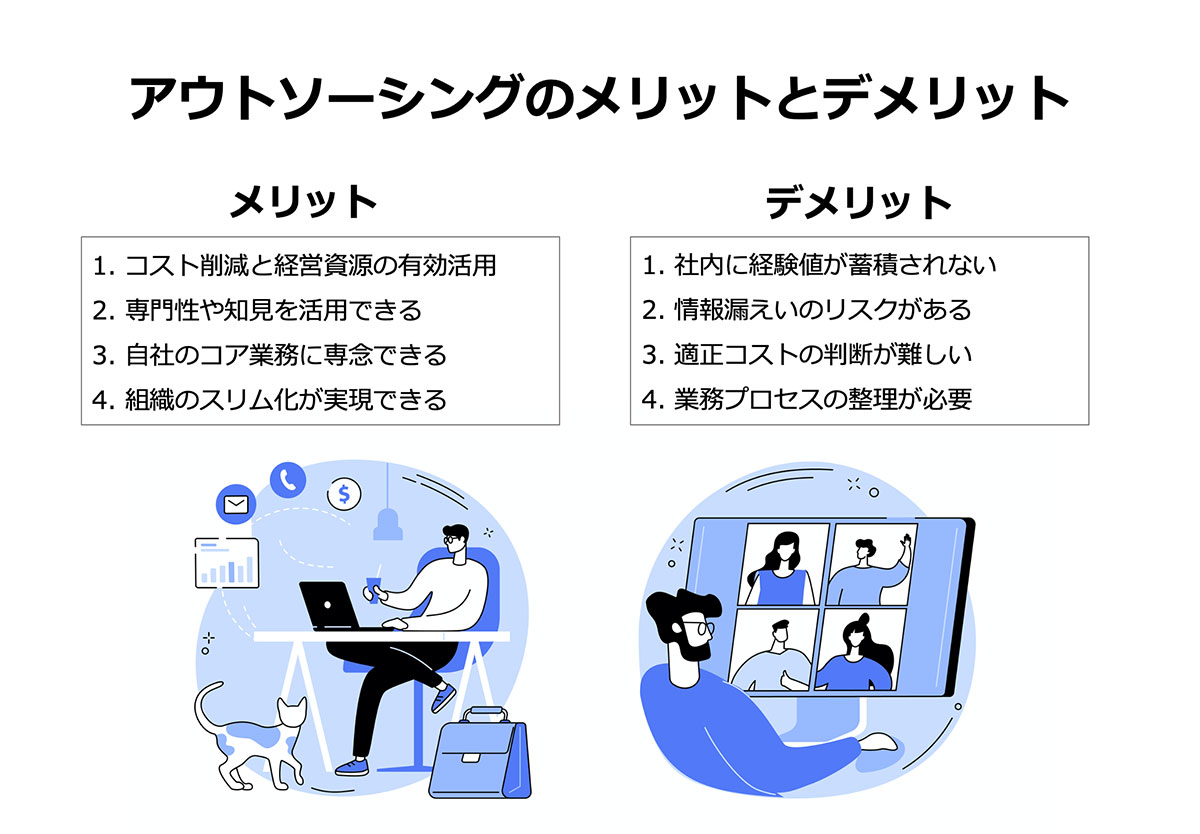
アウトソーシングを活用するメリット
1.コスト削減と経営資源の有効活用が両立できる
| 人件費を抑えられる |
| 設備投資にかかる固定費用を抑えられる |
| 求人、採用、教育にかかる時間や費用を抑えられる |
| 業績の増減に応じて柔軟な費用変動ができる |
アウトソーシングでは、人材や設備投資にかかる固定費を削減し、そのうえ変動費に転換できます。業績や環境変化に応じて、必要なときに必要な分のリソースやサービスを外部に求められます。限られた労働力や資金、時間を優先順位の高いコア業務に集中投下し、企業競争力を強めることが可能です。
2.アウトソーサーの専門性や知見を活用できる
アウトソーサーとはアウトソーシングの委託先企業を指します。アウトソーサーは専門分野に関する知見が豊富で、最新の情報収集やツール導入にも積極的です。過去の実績から提案力に長けている場合も多く、経験やノウハウを即時活用できるメリットも。専門性と経験値の高いアウトソーサーほど、業務精度やスピード、効率に優れているため、自社の社員に任せるよりも費用対効果が高くなる可能性があります。
3.自社のコア業務に専念できる
企業が競争力を高めて優位に立つためには、コア・コンピタンスが重要です。コア・コンピタンスとは、価値提供の面で競合他社を圧倒する能力の核を指し、企業独自の技術やスキル、ノウハウなどがあたります。コア・コンピタンスを強化するためには、自社の本業に自社リソースを集中して投入しなければなりません。しかし、昨今の労働力不足が足かせとなり、既存業務を滞りなく進めながらの人材育成は困難を極めます。ノンコア業務はアウトソーシングを活用できれば、付加価値の高いコア業務の業務遂行と人材育成に専念できるでしょう。
4.組織のスリム化が実現できる
事業拡大の過程で発生しやすい問題として、組織の肥大化が挙げられます。組織をコンパクトに抑えて業績を上げていくために、コア業務以外をアウトソースする方法がとられます。大企業など、すでに組織が肥大化してしまっている場合によく見られるのは、間接部門を切り出して、アウトソーサーとして独立分社させる経営手法。親会社は人員最適化とコスト削減を実現できるでしょう。分社側は親会社をメインの顧客としながら、独立企業として外販強化、スキルとノウハウの蓄積を経て、高度な専門企業となっていきます。親会社がなくても収益を出せるようになり、グループ全体の業績に貢献できるようになるのが最終的な理想形です。アウトソーシングは、組織の再構築を図る際にも活用できることがわかります。
アウトソーシングのデメリット
アウトソーシングにおけるデメリットと、導入検討時の注意点について解説します。リスクを十分に知った上で活用することが重要です。
1.社内に経験値が蓄積されない
アウトソーシングでは、外部の技術やノウハウを活用することで、時間とコストを節約していきます。一方で、自社内にはスキルや経験が蓄積されません。優先度の低い業務とはいえ、自社内である程度は情報を把握しておくべきです。さまざまな事情により自社での業務対応に戻す場合や、アウトソーサーの倒産、サービス撤退など、あらゆるリスクに備えておきましょう。
2.情報漏えいのリスクがある
アウトソーシングの対象業務によっては、機密情報や個人情報をアウトソーサーと共有する必要が生じ、情報が漏えいするリスクも高まります。
・人事関連業務
・コールセンター業務
・情報システム構築
・カスタマーサポート
上記のように重要な情報を扱う業務を依頼する場合、アウトソーサーが使用するツールやシステム上に高度なセキュリティ対策が施されていても、所属スタッフの意識が甘ければ意味がありません。アウトソーシング導入検討の際は、情報漏えいリスクを十分に考慮し、アウトソーシングの実行是非、アウトソーサー選定を慎重に行いましょう。
3.適正コストの判断が難しい
アウトソーシングにより、コストが逆にかさむリスクも考えられます。業務進捗や状況把握など、委託元の管理が困難になるため、確認や手戻りに伴う余分な作業工数が発生する可能性があるからです。また、自社で効率化が進んでいた業務を依頼した場合、効率が落ちるケースもありえます。アウトソーシング活用で期待できる効果を合理的に見定める、業務内容や成果物に対する認識共有、報告頻度のすり合わせを入念に行うなど、事前準備が重要です。
4.要件定義のため、業務プロセスの整理が必要になる
アウトソーシング導入の適切な判断、効果的な活用ができるよう、対象業務の項目や流れを整理する必要があります。導入後も、うまく軌道に乗るまでは細かな管理や情報整理が必要となるでしょう。自社の業務方式が標準的なやり方から外れている場合は、アウトソーサーが慣れるまで時間とコストがかかります。ノンコア業務でも独自のものは自社で行うか、アウトソーシング導入を機に標準化することがおすすめです。
アウトソーシングを導入する際のポイント
業務量がオーバーしているという理由だけで短絡的にアウトソーシングに踏み切ると、メリットを生かしきれないばかりか、失敗のリスクが高まります。人材派遣やインソーシング(内製化)のほうが有効な場合も多々あります。さまざまな観点で比較検討して、ベストな判断を導きましょう。アウトソーシングを導入する際の判断ポイントと、人材派遣・インソーシングに適した業務例を紹介します。
判断ポイント①収益の柱となるコア業務か
まずはアウトソーシング検討対象の業務が、自社の収益構成でどのような位置にあるか確認します。収益の柱となるようなコア業務の場合、アウトソーシングは慎重に行うべきです。自社技術やノウハウを外部に漏らすことになるほか、品質低下の可能性もあるでしょう。自社の競争優位性の根幹に関わるものは除外し、構成タスクを細分化した際に定型業務に落とし込めるものがあれば、アウトソーシングの検討対象になり得ます。現状はコア業務といえなくても将来的に柱としたい事業や、自社に経験値を貯めていきたい業務は、インソーシングを進めるべきです。
判断ポイント②戦略面での意思決定を伴うか
戦略策定や意思決定など、企業の方向性を決める業務はアウトソースすべきではありません。自社の経営陣しかアクセスできないような機密情報を扱う業務も、企業戦略に大きく関わる可能性が高いため、自社で行うべきです。ただし非戦略的業務の中でも、自社の専門性や強みに直結する業務のアウトソーシング利用は、慎重に進める必要があります。
人材派遣に向いている業務
・自社社員の指示、管理のもとで遂行すべき業務
・頻繁にルール変更、イレギュラーが発生しやすい業務
・業務手順が煩雑、またはマニュアル化できない業務
・増員、人員確保が必要な業務
・少人数でこなせる業務
インソーシングを進めるべき業務
・社内に経験値やノウハウを蓄積するべき専門業務
・自社のコア業務
・戦略策定が必要となる経営判断業務
アウトソーシングを推奨する業務
・マニュアル対応ができる定型業務
・規則的に発生する業務
・マニュアル化され、かつ多くのリソースが必要な業務
・利益に直結しないノンコア業務
・戦略策定が不要な業務
・自社の非専門業務
・多くの設備投資が必要とされる業務
アウトソーシングできる業務例
アウトソーシングをする場合は、自社に置き換えたときにどのような意味をもつ業務なのか、客観的に分析して判断することが大切です。
IT関連
IT関連業務のアウトソーシングでは、サーバやOSなど、主にインフラの運用のみ委託するケースと、上流計画から運用までを依頼するケースがあります。パソコンやタブレットなどデジタルデバイスの調達や管理、システムに関する社内外のヘルプデスク対応をアウトソースすることも可能です。
人事・採用(RPO)
採用活動の成功に向けて、採用計画策定をはじめ、応募の管理などを代行します。面接官の教育や研修を行うアウトソーサーもあるので、自社の採用課題を棚卸しして、どこまで委託するか決めることが重要です。採用業務のアウトソーシングはRPO(Recruitment Process Outsoursing)と呼ばれ、企業が求める人材を効率よく採用する手法として近年注目されています。
主な採用業務としては以下のような業務があります。
・採用計画の立案
・母集団形成
・応募の管理
・応募者選定、面接日程調整
・レジュメ管理
・採用ページ、求人媒体の管理
・採用人事の教育、研修実施
RPOサービスを導入することで具体的には以下の2つのメリットがあります。
・煩雑なオペレーション負荷を軽減できる
煩雑なオペレーション業務を外部パートナーに任せることで、採用担当者が自社社員にしかできないコア業務に専念できる環境になります。
・採用成果を向上させるスキームを構築できる
慢性的な売り手市場の中、自社のやり方だけでは成果が出ないケースも少なくありません。外部の専門パートナーの知見を得ることができ、採用力強化を図ることができます。
経理・法務・総務などバックオフィス業務
定型業務の多いバックオフィスに関する業務もアウトソーシングに向いています。正確性や専門性が必要な分野であり、特に総務や法務は、法改正による影響が大きい業務。専門性が高いアウトソーサーに委託して、最新の法令に沿った業務遂行を図る企業が増えています。
コールセンター
アウトソーサー側でコールセンターを設けて、業務指示から実際の電話対応まで代行してもらいます。電話窓口対応や予約・問い合わせ対応などのインバウンド業務、顧客の新規開拓や既存顧客のフォローなど架電を伴うアウトバウンド業務に分けられます。
営業・営業代行
営業アウトソーシングは営業職の即戦力を自社リソースとして活用できます。単なる人員補充ではなく、アウトソーサーの知見やノウハウを生かして従来の営業活動でリーチできなかった新規顧客層を狙ったり、人件費や教育費の削減を図ったりできます。近年ではインサイドセールスに特化した営業代行サービスなども増えています。
商品の製造・販売
代表的なものにOEM(他社ブランド製品の製造代行)があります。D2Cのトレンドも高まり、商品企画や開発は自社で行い、製造のみアウトソースするといった柔軟な運用を行う企業が増えています。
オンライン秘書
アポイント管理やスケジュール調整、メール対応、資料作成などの秘書業務をオンラインでアウトソーシングできるサービスです。対応範囲には一般的な秘書業務以外に、経理や総務関連業務、簡易的なデザイン作成、マーケティング業務なども含まれており、幅広い分野のノンコア業務を任せられます。優先順位が低い業務をアウトソースすることで、クライアントが重要な業務に集中できるのです。
・秘書業務(予定管理、書類作成、メール・電話・顧客対応、出張手配、振込など)
・経理業務(請求書発行、記帳代行など)
・デザイン
・HP作成、更新
・SNS運用
・マーケティング業務
・営業代行
・翻訳業
まとめ
今後も少子高齢化による労働力不足やビジネス環境の変化は加速していくでしょう。アウトソーシングは、メリット・デメリットや導入ポイントをしっかり踏まえて活用できれば、コスト削減や生産性向上、企業競争力向上などを実現できる、強力な手段となります。短絡的にアウトソーシングを選ぶのではなく、なぜ自社に必要なのか、活用した先で何を実現したいのかを客観的に判断して、人材派遣やインソーシングなどと適切に使い分けることが重要です。
投稿 アウトソーシングとは?人材派遣との違いは?メリットと注意点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 VPN接続のメリットや種類を詳しく解説 選び方・おすすめツールも紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>働き方改革やリモートワーク推進のために、VPNの導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。VPNを利用することで通信の安全性が強化され、さまざまなセキュリティリスクを回避できます。
この記事ではVPNの仕組みや種類、メリット・デメリットについて詳しく解説します。最後まで読めばVPN接続ツールの選び方やおすすめ製品までわかるので、ぜひご覧ください。
VPNとは?
VPNとは「Virtual Private Network」の略で、仮想の専用線を意味します。インターネット上に仮想のネットワークを設定し、特定の利用者だけに使用 できます。接続したい拠点(支社)に専用のルーターを設置するだけで簡単に相互通信ができるようになります。
テレワーク環境でVPNを使わずに自宅のWi-Fiやテザリングなどで直接インターネットに接続すると、社内のセキュリティ対策が適用できません。マルウェア感染や情報漏えいなどさまざまなリスクが生じる可能性があります。またフリーWi-Fiの場合は個人情報を盗み見されたり、データを改ざんされたりするリスクがあります。
しかし、VPN接続を利用すれば社内の重要なデータをセキュリティ的に安全にやり取りができます。
VPNの仕組み
VPNには「トンネリング」「暗号化」「認証」などの仕組みがあります。
「トンネリング」とはデータの送信者と受信者の間に仮想的なトンネルを作成して通信する技術です。しかし、トンネリングだけではトンネルの中に入り込まれてしまうと情報が筒抜けになってしまいます。そこで「暗号化」によって、やり取りをするデータを読み取れない文字列に変換して鍵をかけ、不正アクセスや改ざんを防ぐのです。さらに「認証」という方法で送信者と受信者がお互いに本人であることを確かめ、より安全な通信を実現します。
上記のような仕組みによってセキュリティが強化され、安全なデータのやり取りを実現しているのです。
専用線との違い
VPNが普及する前は専用線と呼ばれる、通信事業者が提供する通信サービスを利用する必要がありました。専用線は本社と拠点に物理的に回線を設け、独占して利用できるものです。1社で1本の回線を使うため安全性が高く、大容量の通信も可能というメリットがあります。その一方で、回線を引いた本社と拠点間だけでしか通信できず、距離が長くなるほど高額になるのが欠点です。
これに対し、VPN接続では専用線に近いものを共有ネットワークの中に仮想的に構築できます。物理回線を設置するのと違って工事は不要なので、回線の増減も簡単。コストも安価なので導入のハードルも低いでしょう。また拠点同士の通信も可能になり、国内に複数拠点を持つ企業でもセキュリティを維持しながら導入できます。
VPNの導入用途
VPNを導入する用途と利用シーンには次のようなものがあります。
1. 企業の拠点間を接続
本社や拠点間で売上や業務資料などのデータをやり取りしたい
2. 個人のモバイル端末と企業ネットワークとの接続
リモートワークなどオフィス外から企業のネットワークへアクセスし、業務データを送受信したい
3. 自宅にある個人所有の端末と企業ネットワークとの接続
在宅勤務の際に、自宅にある端末から安全に企業ネットワークへアクセスしたい
VPNを導入することでリモートアクセス環境の安全性が高まり、自宅や外出先からでも社内のイントラネットへの安全な通信が可能になります。
テレワークの普及によるVPNの必要性の高まり
新型コロナウイルスや働き方改革の影響で、テレワークの普及が加速しています。中でもVPNはセキュリティリスクを抑える手段の1つとして利用する企業が増えています。
企業内で業務するときは、ファイアウォールやセキュリティ装置によってウイルスなどの脅威から保護されています。しかし、テレワークでは従業員が保護されていないネットワークを使う可能性もあり、通信内容やパソコンの情報が第三者に丸見えになってしまうリスクがあるのです。特にカフェやレストランなどのフリーWi-Fiを利用すると、暗号化されていないため悪意ある人間がマルウェアの感染経路として悪用する可能性もあります。
VPNはこのようなセキュリティリスクを減少させる解決策の1つとなるため、必要性が高まっているのです。
VPNを導入するメリットとデメリット
VPN接続を使用するメリットについてそれぞれ解説します。

VPNを導入するメリット
VPNを導入するメリットは次のようなものがあります。
1.通信の暗号化で安全性を強化
2.リモートで社内ネットワークにアクセス
3.導入コストが安価
4.複数の拠点間でスムーズに通信
VPNはトンネリングや暗号化など、高度なセキュリティを意識したネットワーク構造になっています。そのため、自宅や社外からでも社内サーバやシステムに安全にアクセスが可能です。アクセスが匿名化されるため第三者にIPアドレスなどの情報を知られる心配もありません。
またパソコンだけでなくモバイル端末からも簡単にアクセス可能です。距離も関係ないため海外拠点からも利用でき、場所や時間にとらわれない働き方が実現できるでしょう。
VPNを導入するデメリット
逆にVPNを導入するデメリットは次のとおりです。
1.情報漏えいの可能性がある
2.通信速度が遅くなるケースがある
3.多機能な製品だと導入コストがかさむ
VPNはセキュリティリスクを低減します。しかし、インターネット環境を利用する限り、情報漏えいの可能性はゼロにはなりません。VPNの設定を適切に行わなかった場合、IPアドレスが漏えいするケースもあります。VPNを過信してそれ以外の対策がおろそかにならないよう注意してください。
またインターネットVPNの場合、公衆回線を利用することがほとんどなので、通信速度が遅くなる可能性があります。その場合、ローカルにファイルをダウンロードして作業するなどの工夫が必要になるでしょう。
VPNの4つの種類と特徴
VPNの接続方法は主に4種類あります。VPN接続サービスを企業で導入するにあたり、それぞれの特徴を理解しておいてください。
インターネットVPN
インターネットVPNとは、既存のインターネット回線を利用してVPN接続する方式です。インターネットに接続できる環境ならすぐに使い始められるので、低コストで回線を構築できます。通信速度や品質は利用中のインターネット環境の影響を受けるため、ほかのVPN接続よりも安全面に少し不安があるといえるでしょう。拠点数が少なく、自社構築でコストを抑えたい企業におすすめです。
エントリーVPN
エントリーVPNとは、インターネットを使わず、ブロードバンド回線と閉域網でネットワークを構築します。限られた利用者しか使えないので不正アクセスといった脅威を低減でき、セキュリティ的にも安心です。さらに比較的低コストで導入できるのも魅力でしょう。
しかし、使用している光ブロードバンドには帯域保証がありません。通信する際はインターネットVPNと同じく、ネットワーク速度が不安定になるというデメリットもあるのです。
IP-VPN
IP-VPNとは、通信事業者が独自に用意したネットワーク上でVPN接続する方式です。インターネット回線から完全に切り離されており、通信事業者と契約者しか利用できません。そのため暗号化を行わなくてもセキュリティレベルの高い通信が可能です。
一定の通信帯域が確保されているので通信速度は安定していますが、その分コストが高い傾向があります。「データのやり取りを行う拠点を多く抱えているので、安全性を強化したい」という企業に向いているでしょう。
広域イーサネット
広域イーサネットとは、通信事業者の専用線を使って自由にネットワーク構築できるVPNです。ほかの種類のようにインターネットプロトコルの通信に限定されません。さまざまなネットワーク設計が可能なため、企業のIT担当者が自社に最適なネットワークシステムをつくることもできます。またインターネットを使わないのでセキュリティレベルも高くなるうえ、通信の高速化も期待できるでしょう。
しかし、提供事業者によって通信できる帯域の範囲が限られている、回線の費用が高いなどの特徴もあります。
VPNの活用事例
VPN接続ツールを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
単純な認証画面でWebアプリを安全に使用できる
「外部サイトにおいているCMS、Webアプリケーション、もともと認証機能のない単純なページ」などに信頼性の高い認証機能をつけるというのがもともと課題としてあった。いずれの場合もアカウントを共通化して、外注先などに随時アカウントを発行・無効化したりする機能をつけるとなるとけっこうハードルが高い。Cloudflare Accessでは、これを一か所の管理画面から実現でき、しかも導入する際にコードレスでOKという点が助かった」
https://www.itreview.jp/products/cloudflare-access/reviews/79983
▼利用サービス:Cloudflare Access
▼企業名:SEO株式会社 ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
現場から事務所に発注書の即時印刷が可能に
「普段から外回りでの営業や業務が多い弊社ですが、どうしても会社の共有ストレージに保存しているデータが必要な時が発生します。今までは家庭用VPNルーターを利用していましたが、ルーターがボトルネックとなり、スループットがひどい状況に。そこで、ストレージサーバーに本ソフトを導入。ストレージサーバー兼VPNサーバー化として運用を開始。すると、スループットが10倍に向上し、業務PC/業務タブレットにてVPN接続が可能に。非常に快適に利用できております。現場から事務所に対して発注書の即時印刷(事務員横プリンタへ遠隔出力)が可能となり、モバイルプリンター・ネットプリントの廃止に伴うコスト削減で、非常に助かっております」
https://www.itreview.jp/products/softether-vpn/reviews/12779
▼利用サービス:SoftEther VPN
▼企業名:hhcネットワーク ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:電器
リモートワークに欠かせないVPNツール
「個人pcの社外での利用の際に、イントラサーバーに簡単にアクセスできる。操作も簡単で、在宅勤務などモバイル環境に便利なツール。ノートパソコンを在宅勤務や社外打合せで使用する際、社内サーバにある資料にすぐにアクセスできる事で、場所にとらわれない働き方ができる様になった」
https://www.itreview.jp/products/anyconnect/reviews/36332
▼利用サービス:Cisco AnyConnect
▼企業名:株式会社LIXIL ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:その他製造業
個別に接続するより手間が少なく、スピード・安定性も高い
「コロナ中、一部スタッフが集まるリモートワーク施設を事務所とつなげる必要が生じたので利用。個別にソフトウェアVPNで接続するよりずっと手間が少なく、しかもスピード・安定性も高かった。業務に耐える品質だと思う」
https://www.itreview.jp/products/flets-vpn-wide/reviews/55720
▼利用サービス:フレッツ・VPN ワイド
▼企業名:メッシュ・ネット合同会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
上記のようにノートパソコンやモバイル端末からでも安全に社内ネットワークにアクセスできるため、時間や場所がとらわれない働き方ができている利用者が多いです。VPN接続ができるツールは、これからのリモートワークの時代には欠かせないといえるでしょう。
VPNを選ぶ際の5つのポイント
VPN接続ツールには無料・有料の2種類がありますが、セキュリティ面や通信速度などを考慮しても有料のほうが優れています。ここでは主に有料のVPN接続ツールを選ぶ際に重要な点を解説します。
①セキュリティの強度が高いか
VPN接続ツールを選ぶ際にもっとも重要な選定基準は、安全性の高さです。強力な暗号化通信ができる製品かどうかに注目しましょう。基本的には「256ビットAES」という方式が採用されている製品がおすすめです。世界中の政府や軍隊が極秘情報を守るために使用しています。
またログなしポリシーや信頼性の高いプロトコルが使われているかも確認してください。「OpenVPN」がもっともセキュリティの高いプロトコルなので、採用している事業者を選ぶのがよいでしょう。
②運用保守・サポートが充実しているか
運用保守やサポートが充実しているかも、選ぶ際の重要なポイントです。万が一のトラブルが起きたときに即座に対応してもらえるか否かで業務への影響度が大きく変わります。
たとえば以下のような観点でチェックすることをおすすめします。ウェブサイト上に記載がない場合は問い合わせてみましょう。
・障害対応を任せられるか
・問題の切り分けから対策まで行ってもらえるか
・対応がスピーディか
・24時間365日体制か
・死活監視サービスやトラフィックレポートがあるか
・日本語対応しているか
あらかじめトラブル発生時に「どのような対応なら自社にとってベストなのか」を考慮したうえで比較検討してください。
③通信速度が維持できるか
サーバの拠点数が多いほどアクセスが一点集中しないように分散しており、通信速度が落ちません。高速で安定したネットワーク通信が可能になるでしょう。
日本で利用するなら日本・中国・韓国などにサーバをもつ事業者をおすすめします。
帯域幅は無制限の製品がよいです。一度に大量のデータの送受信ができるので、時間帯やアクセス数を問わず通信速度を維持できるでしょう。
④多くのデバイスに対応しているか
さまざまなデバイスに対応しているVPNのほうが柔軟な働き方が可能になります。Windows、MacOS、iOS、Android、Chrome、Firefox、Linuxなど、自社の業務上必要なデバイスの種類をリストアップし確認しましょう。
デスクトップ版、スマホ版などのアプリの有無も確認しておくことをおすすめします。
⑤利用料金やコストが適切か
料金やコストが自社に適しているかも確認します。単に安さだけで決めると、「通信速度が遅くなった」「しっかりしたサポートを受けられなかった」などの問題が起きるケースもあるのです。
まずは「VPN接続ツールを導入することで自社が達成したい目的」を明確にしましょう。どんな機能があればよいかを洗い出しておくことが重要です。そのうえで、初期導入費用や月々の利用料金と、サービス内容をしっかり比較してください。契約更新や解約にどれくらいの費用がかかるかも押さえておきましょう。
VPN製品の中には無料お試し版を提供しているものもあります。一度性能や使用感を確認してから決めるのがよいでしょう。
VPN接続ツールの市場業界マップ
VPN接続ツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
おすすめのVPN接続ツール
実際に、VPN接続ツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心におすすめのVPN接続ツールを紹介します。
(2021年11月16日時点のレビューが多い順に紹介しています)
SoftEther VPN
「SoftEther VPN」は、無償で利用できるオープンソース型のVPN製品です。WindowsやMacOSはもちろん、Linux、FreeBSD、Solarisなど多様なOSやCPU上で利用できます。さらにiPhoneやAndroid といったモバイル端末でも簡単に接続可能。パソコン間・拠点間・リモートアクセスなど、どんなに距離が離れていても快適でスピーディなVPN接続が実現できるでしょう。「複数の地点にちらばっている顧客のパソコンやプリンタを管理しやすくしたい」といったケースでも、顧客のパソコンにインストールすることでトラブル時の対応が容易になります。
Cloudflare Access
「Cloudflare Access」は、最大50ユーザーまで無料プランで利用できるVPN接続サービスです。Enterpriseプランでは14ドル/ユーザーで、最大250カ所のロケーションに対応しています。また6カ月までアクティビティログを取得でき、ログイン・ログアウトだけでなく対象アプリケーションで行われたすべての行動をログに記録することが可能です。緊急時は1時間以内に初動対応しており、電話・メール・チャットで優先的に対応してもらえます。サポート内容が充実したVPN接続ツールを探している企業におすすめでしょう。
Cloudflare Accessの製品情報・レビューを見る
SmartVPN
「SmartVPN」は、ソフトバンクが提供するクラウド型のVPN接続サービスです。レイヤー2だけでなくレイヤー3にも対応しており、企業のニーズに応じてより簡略化した構成にすることが可能です。また「Twinアクセス」を併せて導入することで、モバイル通信が不安定になりやすいエリアでも安定したやり取りを行えるようになります。「ホワイトクラウド」の各種サービスともシームレスに接続できるため、すでに同社の製品を使用している企業におすすめといえるでしょう。
Meraki MX
「Meraki MX」は、クラウド型のUTM(統合脅威管理)でありSD-WANVPN接続ツールです。煩わしい設定はほとんどなく、ダッシュボードを数回クリックするだけで拠点間のVPN接続を構成できます。また固定グローバルアドレスが不要のため、拠点の台数ごとに固定のグローバルアドレスを取得する負担やコストを削減可能です。本社や拠点、リモートワークなど、ネットワーク環境や場所を問わず1つのダッシュボードで一元管理できる管理のしやすさも魅力でしょう。30日間の無料トライアルもあるので、一度管理画面や接続状況などを確認してから導入したい企業におすすめです。
ITreviewではその他のVPNも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。
まとめ
現在は働き方改革や新型コロナウイルスの影響などで、リモートワーク環境への移行が進められています。セキュリティ対策が万全ではない社外からでも安全にデータのやり取りを行うには、VPNの利用が欠かせません。
VPN接続ツールを選ぶ際には、自社の通信環境やコストなどを事前にしっかり確認しましょう。そのうえでセキュリティ強度やサポートの充実度などをよく比較して決めることをおすすめします。製品によっては無料のお試し版を提供している事業者もあるため、まずは使用感や操作性などを体験してみるとよいでしょう。
投稿 VPN接続のメリットや種類を詳しく解説 選び方・おすすめツールも紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 OCRとは? あらゆる書類や画像を素早くテキスト化して業務を効率化 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>OCRとは?
OCRとは、日本語で「光学文字認識」といい、英語で「Optical Character Recognition」の頭文字をとった略称です。複合機やスキャナーなどで文字を画像で読み取り、その画像から自動で文字のみを抜き、コンピュータで利用可能なデジタルデータで認識させるという技術が開発されました。
日本でのOCR誕生は、1968年の郵便番号を導入したことが起源です。郵便局内での業務の自動化を推進するため、郵便番号を読み取って、集配局別に仕分けができるOCR機械が生まれました。また、1980年代になると、パソコンの廉価化やパッケージ化などが進んだことから、法人だけでなく個人向けにも活用可能なレベルのOCRサービスが浸透するまでに至ります。しかし、文字認識率の制度は決して高いわけではなかったため、読み取り後のデータを目視で確認・修正する必要がありました。
また2000年代になるまでは、日本語が難解であるという問題がありました。英語圏の言語であれば、アルファベットと数字で判別可能ですが、日本語には、ひらがなやカタカナ、漢字も存在します。また漢字は画数や類似する形態も多く複雑なため、OCRの精度には限界がありました。そのため、OCRの文字認識において、文字判別のソースとなる情報を事前にデータベースに蓄積し、データベース内の情報と読み取った情報とをマッチングさせて文字を判別しなければならなかったのです。
そんな中、2012年に開催されたILSVRC(コンピュータによる画像認識技術に関するコンペティション形式の研究集会)が、OCRに変化をもたらします。カナダのトロント大学の研究チームが膨大な画像データから対象物を認識するコンテストにおいて、優勝しました。この研究チームが導入していたものが、ディープラーニング(AIの深層学習)を活用した画像認識システムであり、これが世界中で注目されるようになります。研究開発も各国で進み、AIの進化を推し進める形となったのです。そしてこのAIとOCRとをコラボレーションさせたものを、AI-OCRといいます(後述)。
OCRを導入するメリットとデメリット
ペーパーレス時代において、OCRはビジネスに欠かせないツールとなっています。まずはOCRを導入するメリットとデメリットを理解しておくことが、最適なOCRツールを選ぶコツとなるので、ここはキチンと抑えておきましょう。
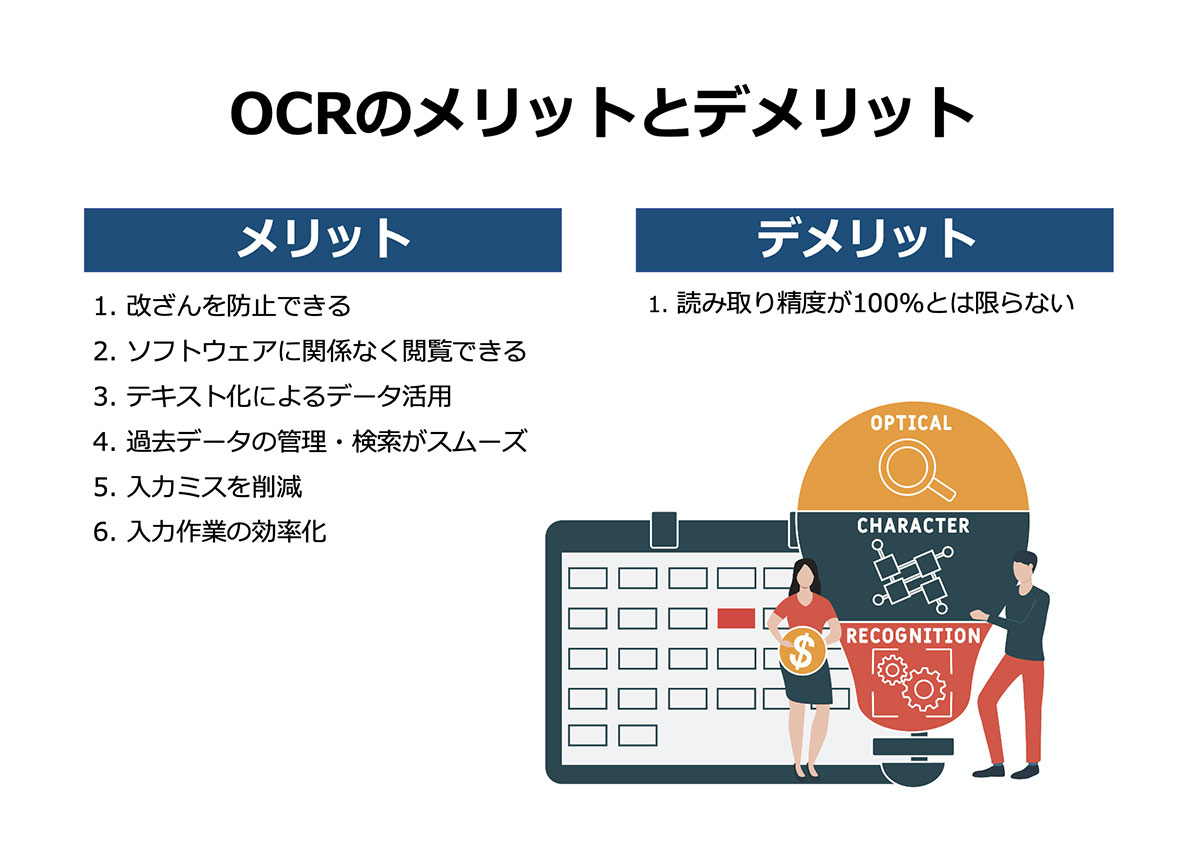
OCRを導入するメリット
1.改ざんを防止できる
悪意をもって紙の文書に手を加える人も存在するでしょう。また、いつ誰がどのように手を加えたのかわからないのが紙の文書の難点です。対してOCRは何かしらの変更がなされた際にはきちんと履歴が残るため、変更箇所が容易に把握できるようになっています。またパスワード設定があることで誰かが勝手に編集することを防ぎます。
2.ソフトウェアに関係なく閲覧できる
文書作成ソフトなどで作成されたファイルを閲覧する場合には、基本的にそのソフトを利用して見るか、あるいは相性のよいものを利用する必要があります。OCRは、ソフトウェアを問わず閲覧することが可能となっているのも大きなメリットの1つです。
3.テキスト化によるデータ活用
資料や書籍をテキスト化することによって、文字情報の一部を変更したり、追記したりすることができます。文字情報の一部が変更・追記可能であるということは、検索で求める情報をすぐに見つけられるというメリットにつながります。
4.過去データの管理・検索がスムーズ
情報を紙の書類や画像として保存しているときに、膨大な量になれば保管をしたり、過去のデータが必要になったときに探し出したりするのはひと苦労です。そのような場合にOCRを活用し、文字データ化をしておけば情報管理も楽になり、パソコン上で求めている情報をスムーズに検索・閲覧することができます。
5.入力ミスを削減
手入力では日常的なケアレスミスも起こりやすくなりますが、OCRを活用するとソフトが自動でスキャンした文字画像から文字を認識するため、入力ミスを大幅に減少させることができます。
6.入力作業の効率化
入力作業には常に正確さと素早さが求められますが、アナログ情報をデジタル情報に変換するという付加価値の低い単純作業であるとされています。こうした付加価値の低い作業を自動化できる技術がOCRです。自動化で得られる最大のメリットは業務効率化を実現できる点といってよいでしょう。
OCRを導入するデメリット
1.読み取り精度が100%とは限らない
OCRの文字認識精度は、必ずしも100%とは限りません。すべての文字が正しく認識するわけではありません。特に以下のような文字の場合は誤認識する可能性があります。
- ・特殊文字
- ・手書き文字
- ・文字間が詰まった文字列
AI OCRとは?
OCRにはいわゆるAI OCRと呼ばれる処理方法があります。OCRとAI OCRとの違い、そしてAI OCRの役割とメリットについて説明します。
AI OCRとは?
AI OCRとは、手書きの書類や帳票の読み取りなどからデータ化されたOCRにAIを利用するまったく新しいOCR処理のことをいいます。AI OCRは、AIの研究開発が進む中で、深層学習(ディープラーニング)の効果を利用し、OCRで紙の書類や帳票などのレイアウト解析(認識範囲の特定)精度の改善や向上を目的に、幅広く活用することで導入範囲が増加していきます。RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)との互換性もよく、OCRで紙の書類や帳票を自動で読み取り、認識結果をRPAで利用することによって、業界を問わずいろいろな領域での業務改善に役立てられます。
OCRとAI OCRの違い
OCRとAI OCRの異なる点は、「OCR技術にAI技術を結合させたもの」であるといえます。従来のOCRでは、手書き文字は際限なく存在するので、それらの特徴すべてを登録することは不可能であったため、正確な認識が難しい状況にありました。そこで登場した新しいAI OCR技術は文字ごとに違う独自性を自動抽出するので、さらに正確な文字認識ができるようになっています。
AI OCRのメリット
・文字識字率が高い
従来のOCRは、すでに保有するロジックの範囲内で定められた形式でのみ識別することができましたが、AI OCRはAIに深層学習をさせることで、一度読み取りミスをしてもデータAIがミスから学ぶことにより文字認識率を向上させられます。
・フォーマットの違う帳票にも対応
帳票をOCRで読み取るときは、従来であれば読取位置や項目といった細かい位置づけを行う必要がありました。しかし、AI OCRはAIの読取位置や項目を自動的に抽出することが可能なため、紙の書類などの資料をスキャンすれば文字を認識してくれるようになりました。
・RPAや情報システムとの連携で業務効率化を実現
読み取った情報項目や業務システムの入力に必要とされる情報を自動抽出し、生成が可能なため、入力などの単純作業を大きく効率化させることが可能です。このような情報の意味づけから、RPAとの連携により、さらに業務効率を向上させることができます。
OCR/AI OCRの活用事例
OCR/AI OCRを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
自動認識して画像補正でメモより簡単
「以前まではメモ帳でホワイトボードの内容を書き留めていましたが、スマホのカメラで記憶する事を覚えて大分楽に情報を管理する事ができるようになりました。ただ、カメラだと撮影時にうまく撮影できない場合がありました。そこでOffice Lensを使用すると枠を自動認識して画像補正をかけてくれる。これは予想以上の出来です。」
https://www.itreview.jp/products/office-lens/reviews/56171
▼利用サービス:Office Lens
▼企業名:株式会社トヤマデータセンター ▼従業員規模:50-100人未満 ▼ソフトウェア・SI
ミーティング資料をすぐに電子化する習慣がより強固になった
「紙・ホワイトボード・名刺などをスマホのカメラでスキャンして、きれいに矩形補正してくれる。対象被写体の認識から矩形補正までがフルオートなところがすばらしい。また、ビジネス用途に向いているのは、撮影終了後の映像を画像形式以外にPDF形式やOneNote向けにも出力できるところ。複数枚のプレゼン資料のPDF化を出先で済ます、といったことが手軽にできる。」
https://www.itreview.jp/products/office-lens/reviews/44792
▼利用サービス:Office Lens
▼企業名:bizlink合同会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼情報通信・インターネット
”手書き”の文字も見事な精度で読み取り
「ここ最近、OCRの分野には、スタートアップ系が台頭してきてAIを利用した文字認識の製品・サービスが発表されています。この製品に関して何が一番すごいのかというと、日々進化していることです。月に数回アップデートされており、進化(成長)し益々と精度が高くなっていることです。当然ですが、”手書き”という、様々な字体があるものも見事な精度で読み取ります。恐らく過去にOCRを利用してみたが、精度が上がらなかったところは、この製品を見ると”開いた口がふさがらない”状態になるのではないでしょうか!」
▼利用サービス:DX Suite(AI OCR)
▼企業名:株式会社システムソフト ▼従業員規模:100-300人未満 ▼情報通信・インターネットnull
https://www.itreview.jp/products/dx-suite-ai-ocr/reviews/21371
OCR/AI OCRを選ぶポイント
OCR/AI OCRを選ぶ際に押さえておきたい5つのポイントについて解説します
1. 文字の読み取り精度
課題の解決を最優先し、システムの精度を見極めることは重要です。ここでの精度とはAI OCR技術を含む読み取り精度のことを指します。読み取り精度は高ければ高いほど効率的であるため、精度の高さを見極めることは大変重要です。高解像度でスキャンすることによってOCRが文字を認識しやすくなり精度が上がります。あまり高解像度にしてもデータの読み取りに時間がかかりすぎてかえって非効率になるので、一般的には300dpi以上であれば問題ありません。
2.専門知識を持たない社員でも使いやすいか
使い勝手の良さも、OCR/AI OCRツール選定において大切なポイントです。帳票などの読み取り業務では、適応範囲をユーザー側で拡大できれば業務効率化にも直結します。専門知識をもたない社員で使いやすい操作性がシンプルなOCR/AI OCRを選びましょう。
3.RPAなど他のシステムと連携
さまざまなRPAとの連携や、ほかのシステムとの連携が可能であるかどうかも重要です。また頻繁に利用するシステムがAPIとして備えられていることも大切です。APIがあればプログラムを組む必要もないため、必要に応じてAPIを利用し、円滑な作業を進められます。
4.データのセキュリティ対策
ツールを提供するベンダーが「Pマーク」や「ISMS」を取得しているかどうかは、強固なセキュリティ対策を施す上で必要不可欠なチェックポイントです。実際にセキュリティ対策の認証を得ているのかどうかは、事前にしっかり確認するようにしましょう。
5.サポート体制が万全か
サポート体制が万全であるかどうかということも、ツールを選ぶ際の重要なポイントです。また日本全国規模、あるいは海外に拠点のある企業の場合には、全国の社員のために説明会を行うケースもあります。説明会開催のためのサポートをするなど、会社固有のニーズに合う対応をしてくれるかについても、ツール選びの材料となります。
OCR/AI OCRの業界マップ
OCRツールのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度が掛け合わされた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
OCR/AI OCRツールおすすめ5選
実際に、OCR/AI OCRツールを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのOCR/AI OCRツールを紹介します。
(2021年11月25日時点のレビューが多い順に紹介しています)
※製品ページへのリンクは新規タブで開くリンク設定でお願いします。
Office Lens
マイクロソフト社が提供する無料のスキャナーアプリです。名刺や書類などをスマートフォンで撮ることにより、文書や画像をデジタル化して保存したり、共有したりすることが可能です。同社のOneDriveの利便性がさらに高まり、名刺を独自管理したい際や、会議資料を社内で共有したい場合に利用されています。
読取革命
書類などのスキャン画像等文字画像を、テキストデータに変換できるツールです。手書き文字や低品質文字認識などの読み取りを得意とし、OCRエンジンの精度の高さには一定の評価があり、業種問わず、広く導入されています。開発は、パナソニックソリューションズテクノロジー株式会社と、ソースネクスト株式会社が手がけています。
DX Suite(AI OCR)
AI inside株式会社が開発を手がけ、高精度でデジタルデータ化を実現しました。手書きや活字・写真やFAXなど、撮影した書類まで、入力の手間がなく、仕分けもすべてAIが行います。まとめてアップロードした書類などは、種類別に自動で仕分けられて便利です。
HGPscanServPlus
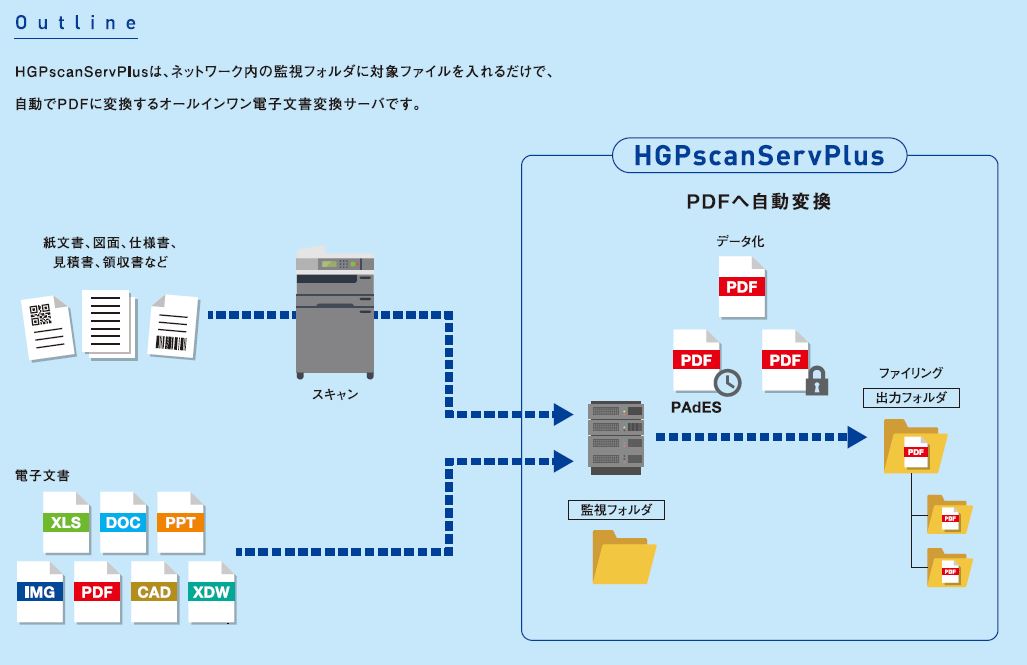
手入力なしで業務効率化を推進できる電子化自動システムを搭載、デジタルドキュメントの作成から保存・保護における一連のフローも自動化するデジタル・ファイリング・オートメーション仕様です。開発は、株式会社ハイパーギアが手がけました。
AIRead
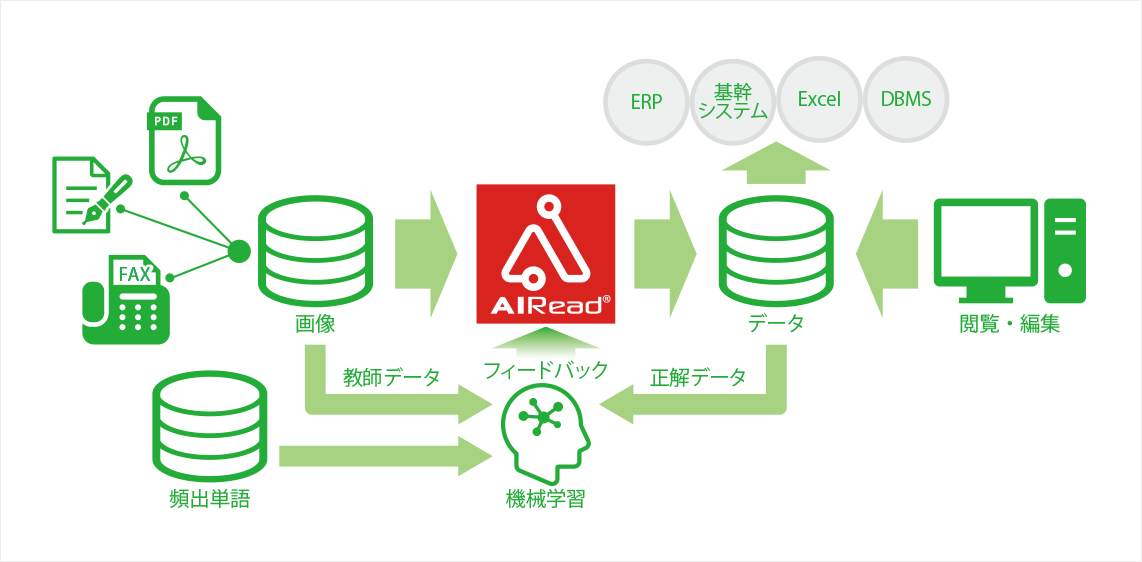
アライズイノベーション株式会社が開発した、スタンドアロン型やクラウド型、サーバ型など、あらゆる形式で利用可能なAI OCRです。AIを利用した手書き文字認識から、定型・非定型の帳票の読み取り、そしてデータ化を行うことができるツールです。
ITreviewではその他のOCRも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。
まとめ
業務効率や働き方改革のツールとして、改めて注目されるOCR。ITの進歩によって、かつては想像もできなかったような高度化したOCRやAI OCRの需要は、日に日に増しています。OCR/AI OCRを軸にしたデジタイゼーションは、ペーパーレス化の大きな一歩です。OCR/AI OCRをどのように活用するかをしっかりと検討することが、最終的には企業のDXを進めるうえでカギを握ることでしょう。
投稿 OCRとは? あらゆる書類や画像を素早くテキスト化して業務を効率化 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア、活用事例も紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>社内のデジタル改革(DX)を推進する役割も期待されるグループウェア。コロナ禍の影響でテレワークの普及が加速する昨今、グループウェアのニーズはますます高まっていくことは間違いありません
グループウェアとは?
グループウェアとは、複数人で作業をする際にスムーズなコミュニケーションを図り、やり取りができるツールやソフトウェアの総称です。テレワークなどで離れた場所にいる社員同士が円滑に連絡をとり合えるほか、お互いのスケジュールやタスク管理など、業務に欠かせない便利な機能を利用できます。
グループウェアは、業務にあたり複数人でのやり取りがスムーズにでき、かつ業務上必要な機能を兼ね備えたツールやソフトウェアです。どのようなグループウェアを導入するかは企業によって異なりますが、コミュニケーションの円滑化や業務効率化につながります。
グループで作業をする際、テレワークなどで1人ひとりが別の場所にいる場合、どのように作業を進めるのがよいでしょうか。電話やメールをはじめ、LINEなどのコミュニケーションアプリも存在しています。しかし、これらのツールでコミュニケーションはとれても、業務効率化にはつながりにくいでしょう。お互いが抱えるタスクやスケジュールを把握するのは難しいからです。
そこで活用したいのが、グループウェアです。グループウェアは、コロナ禍におけるテレワーク環境の整備にも対応でき、円滑な業務遂行を可能とします。
グループウェアの基本機能
グループウェアには利用者側の機能と管理者側の機能に分かれています。それぞれどのような機能が備わっているかを見ていきましょう。
利用者側の機能
グループウェアを利用する従業員は主に次のような機能が利用できます。
・スケジュール管理
スケジュール機能は全従業員の予定を共有したり追加したり、ユーザーごとの予定を確認してタスクを振り分けられます。
・施設の予約
施設の予約機能は、会議室や社用車などの空き情報をグループウェア上で確認し、予約ができます。グループウェアによっては施設だけでなく、社内の備品などモノに対する予約も可能です。
・社内ポータルの作成、表示
業務に関する情報をひとまとめにした社内ポータルは、グループウェア上で作成できます。グループウェアの各機能にアクセスするためのリンクもまとめられるため、業務効率化につながるでしょう。
・掲示板
従業員同士でメッセージのやり取りをする掲示板や、特定の部署やグループ単位で情報を伝えられる回覧板機能があります。相手が確実にメッセージに目を通したことがわかる閲覧確認機能など便利な機能も備わっています。
・ファイル管理機能
会議資料などの文書をプリントアウトして提出しなくても、グループウェア上で共有できるファイル管理機能も欠かせません。検索機能もあり、目的のファイルをスムーズに見つけられるのもメリットといえるでしょう。
・電子会議室(ビデオ)
グループウェア上ではテキストのやり取りだけでなく、ビデオ機能がついた電子会議室も利用できます。コロナ禍のテレワーク中でも、時間や場所に縛られずやり取りでき、安全な情報共有が可能です。
・ワークフロー
ワークフロー機能を利用すれば、経費処理や承認を受けなければならない書類もグループウェア上で申請できます。これまでのように紙の書類を用意して押印をする手間もかからず、ペーパーレスになりコストダウンにもつながるでしょう。
・アドレス帳、ユーザー名簿
ユーザーはもちろん、社内の部門や役職など任意のグループごとにアドレス帳を作成し、アクセス権や運用管理者を設定できます。
・電子メール
グループウェアの中には、メールソフトのようなユーザーインターフェースの製品もあります。パソコン版だけでなくモバイルデバイスにも対応したツールやモバイルアプリがあるツールなら、スマートフォンなどのモバイルデバイスでもスムーズに利用できます。これまで利用してきたシステムと比較しながら、使いやすいツールを選ぶとよいでしょう。
管理者側の機能
複数人で利用するグループウェアは、トラブルが発生しないよう管理する必要があります。
・ユーザー情報の管理
グループウェアを利用する従業員の情報を一括登録したり、組織情報を付加したりできる管理機能です。新たな従業員が入ってきた場合に追加したり、部署替えがあった際に情報を変更・付加したりします。
・アクセス権限の設定
グループウェア上にあるすべての情報を、すべての従業員に公開するわけにはいかないため、アクセス権限の設定も可能です。組織ごと、役職ごと、ユーザーごとにアクセス制限をかけられます。
・社外アクセス管理
社外からのアクセスにも制限をかけられます。登録していないデバイスからアクセスできないように設定したり、反対に社外のデバイスでもアクセスを許可したりすることも可能です。
・ユーザーアカウントの利用停止
従業員が退職したあとは、情報流出などのトラブルを防ぐためにも、そのユーザーのアカウントも利用停止しなければなりません。ユーザーアカウントを利用停止し、これまでに登録された情報はそのまま保持できるのも管理者側機能の1つです。
・ログ管理
グループウェアへのアクセスや操作ログなどを保管・管理できるため、万が一不正なアクセスなどがあった場合、その記録を確認できます。
こうしたさまざまな機能を使い、管理者側は従業員がスムーズに業務を進められるよう、環境を整えましょう。
グループウェア導入のメリットとデメリット
ここからは、グループウェア導入によって得られるメリットとデメリットをそれぞれ紹介します。
グループウェア導入のメリット
グループウェア導入には主に4つのメリットがあります。
1.情報共有による仕事の効率化
グループウェアの導入によって情報共有がしやすくなるため、仕事の効率化につながります。グループウェアなしで電話やメールなど別のツールを用いた情報共有をすると、タイムラグが発生したり、確認作業に時間がかかったりします。しかし、グループウェアであれば文章が残る、ファイル共有が同時にできるなど、情報共有がスムーズにできるメリットがあります。
2.タスクや予定の「抜け」「漏れ」を防止
従業員がそれぞれ抱えているタスクや予定の「抜け」「漏れ」を防止します。部署内にスケジュール表を設けている企業も多くありますが、変更があった場合も手書きで書き直す必要がなく、リアルタイムで更新されます。お互いの予定を確認し合えるため、ダブルブッキングの可能性も低く、“うっかりミス”を減らせるのがメリットです。
3.コミュニケーションの活性化
グループウェアでのやり取りにより、従業員同士のコミュニケーションが活性化します。グループウェアの掲示板はテキストのやり取りだけでなく、メッセージを読んだことを意味する「スタンプ」機能があります。メールではスタンプ機能は利用できず、電話では何度も尋ねるのは難しいでしょう。
しかし、グループウェアであればテキストですぐにメッセージが送れるため、小さな疑問もすぐに質問できます。すれ違いをなくし、円滑なコミュニケーションを可能にします。
4.ペーパーレス化によるコスト削減
グループウェアを利用するとペーパーレス化につながり、コスト削減にも貢献します。会議のたびに資料を印刷し、提出する書類に押印していた作業が、グループウェアであればすべて簡略化できます。資料はWordやPDFなどの電子ファイルで送付でき、押印する手間もかかりません。大人数に配布するために印刷する必要もなく、ファイル共有もクリック1つで完了します。
グループウェア導入のデメリット
グループウェア導入によって起こり得るデメリットを見てみましょう。
1. 導入には予算がかかる
グループウェア導入には費用がかかります。どのグループウェアを利用するか、また従業員の数や利用する機能によっても変動するため、大人数ですべての機能を使おうとすると費用がかさむといえるでしょう。
2.教育が必要
グループウェアを使いこなせるように教育が必要となります。すべての従業員がスムーズにグループウェアを使えるわけではなく、デジタルに疎い従業員へのフォローも欠かせません。操作に慣れるまではなかなか足並みが揃わず、時間がかかることも考慮しておきましょう。
3.適切なツールを選ぶのに迷う
従業員が本当に使いやすいグループウェアを選びたい、しかし会社としては予算との兼ね合いがある、従業員の規模や求める機能など、さまざまなことを考慮したツール選びが必要です。
グループウェアの選び方
グループウェアの種類は多いため、自社がどんな目的でどのような機能を求めているのかを明確にすることで、スムーズな選定につながります。
オンプレミス型とクラウド型
まず、オンプレミス型とクラウド型のどちらを使うか、導入形態を決めます。
・オンプレミス型
オンプレミス型は、サーバを自社内に設置するタイプを指します。カスタマイズ性に優れている特徴がありますが、クラウド型よりも費用や、導入までの手間がかかりやすい点に注意しましょう。
・クラウド型
クラウド型は、クラウドベンダーが提供するシステムを借りて利用するタイプを指します。すでにあるシステムを使うため導入までがスムーズな一方、カスタマイズの自由度はオンプレミス型と比べて劣ります。
つまり、自社運用のオンプレミス型を選ぶか、他社のシステムを借りるクラウド型を選ぶかということです。
使いやすさ
多くの機能があり、デザイン性の高いグループウェアであっても、使いにくければ意味がありません。実際にグループウェアを使う従業員が使いやすいと感じられるものを選びましょう。たとえば、パソコンだけでなくモバイルデバイスにも対応したグループウェアは外出先でも使いやすく、業務効率化につながります。
コストパフォーマンス
コストパフォーマンスの高さは重要なポイントです。機能性に優れるなど魅力的なグループウェアも、費用対効果が低いと導入するメリットが小さくなります。オンプレミス型とクラウド型で費用は異なりますが、どちらのほうがメリットが大きくなるかを検討しましょう。
運用にかかる手間
業務にグループウェアを利用する従業員だけでなく、それを取りまとめる管理者側の負担も考慮しましょう。トラブル発生時にすぐ対応しやすいグループウェアや、サポート体制が整っているものを選ぶのがおすすめです。
カスタマイズ性
会社ごとにグループウェアに求める機能は違うため、カスタマイズ性に優れたグループウェアがおすすめです。ただし、基本的な機能のみで問題ないという場合は、別の点を考慮して決めるとよいでしょう。
他製品との連携
グループウェアは日常の業務に用いるため、そこから派生して生まれる別の業務にも使えるよう、他製品との連携を図れるものがおすすめです。たとえば、給与計算システムと連携できれば、グループウェア上で給与明細を各自に送付することもできます。
ツールごとの違いを把握する
各グループウェアにメリット、デメリットがあるため、それぞれの違いを把握してもっとも自社に適したものを選びましょう。ツールごとの違いを把握し、従業員が求めている機能を備えたグループウェア選びが大切です。
導入する形態を把握する
グループウェアにはオンプレミス型とクラウド型があると上述しましたが、導入する形態それぞれの特徴を理解しておきましょう。カスタマイズ性、費用など双方にメリット、デメリットがありますが、オンプレミス型にするとトラブル発生時にすぐ対応できるのかどうか、利用後のことを考えて選んでください。
導入時に必要なものを確認する
導入時にどれくらいの費用がかかるのか、従業員にグループウェアの使い方マニュアルを配布するなど、何を準備すればよいのかを確認しておきましょう。いざ導入するというときに従業員が利用できないということがないよう、スムーズな導入のためにも必要なものをピックアップしておきます。
グループウェア活用事例
グループウェアを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
全社員のスケジュール管理、ペーパーレスに貢献
「コロナ禍以前より導入しておりますが、全社員のスケジュール管理、各種申請書、プロジェクト管理など仕事で使うべきツールがすべて入っており、外出が多い営業やエンジニアなどクラウド版を利用すれば外出先からも利用可能で業務効率が格段と上がります。こういうものはお金を生むツールではないので簡単に誰でも利用できる必要がありますが、サイボウズOfficeにおいては直感的に操作可能であり、他のツールよりも一歩抜き出た感じがします」
https://www.itreview.jp/products/cybozu-office/reviews/53177
▼利用サービス:サイボウズ Office
▼企業名:KMソリューションズ栃木株式会社 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
他人の「予定表示」が非常に便利
「仕事上どうしても自分だけでなく他人のスケジュール調整などもしなければならない場合に、サイボウズであれば「他人の予定表示」などが簡単なので非常に便利である。また客からの問い合わせ対応の時などにも、他人の予定が見れるというのは非常に便利」
https://www.itreview.jp/products/cybozu-office/reviews/40819
▼利用サービス:サイボウズOffice
▼企業名:三ツ輪技研 ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
異なるネットワーク間でのファイルの交換や共有が容易に
「本県には2系統のネットワークがある。そのうち県庁wanはセキュリティレベルが非常に高く、インターネットは仮想空間上で行っている。もう一方のネットワークは教員用のそれであり、セキュリティレベルはやや低い。管理職は両系統のネットワークを使うことになるのだが、ガルーン導入以前はネットワーク間でのファイルの交換や共有が非常にやりにくかった。ガルーン導入によりこれが円滑になった。そればかりかスケジュール管理もできるようになった」
https://www.itreview.jp/products/garoon/reviews/59422
▼利用サービス:Garoon
▼企業名:兵庫県教育委員会 ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:小学校・中学校・高校
社内のアサイン状況を外出先からもお手軽に確認
「スケジュール・施設予約機能を中心に普通に不便なく利用できています。モバイル用の無料アプリも色々なところからリリースされており、他人や場所を含めたアサイン状況を外出先からもお手軽に確認できます」
https://www.itreview.jp/products/garoon/reviews/38583
▼利用サービス:Garoon
▼企業名:ピー・シー・エー ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:ソフトウェア・SI
文書の社内共有や同時アクセスが便利
「共有ドライブは簡単に閲覧・編集可能者の選別ができるので、チームや案件ごとにフォルダ作成したり、メールでは送れないような大きいファイルをアップロードできるので、対個人で一時的に使用したり。と、離れた拠点でもスムーズにやり取りができるようになりました。スプレッドシートやドキュメント系は、お客様や他拠点の社員との打ち合わせ時にリアルタイムで同じものが共有できるので、会話の理解度が上がりとても助かります」
https://www.itreview.jp/products/rakumo/reviews/64699
▼利用サービス:Garoon
▼企業名:株式会社BlueCORE ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:その他サービス
グループウェアの業界マップ
グループウェアのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップで、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
おすすめのグループウェア5選
実際に、グループウェアを活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのグループウェアツールを紹介します。
(2021年11月30日時点のレビューが多い順に紹介しています)
サイボウズOffice
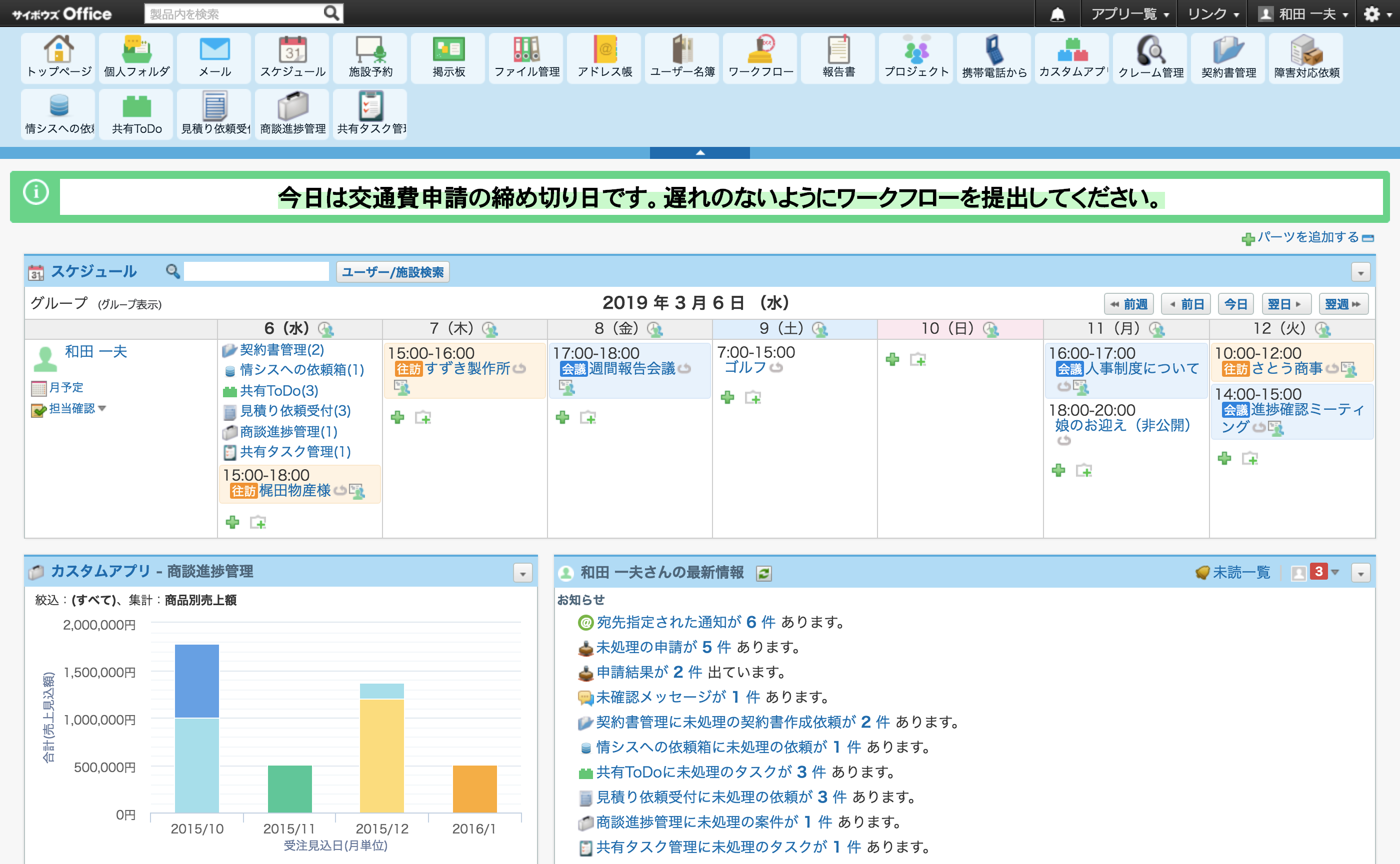
「サイボウズOffice」は、これまで延べ6万7000社以上のユーザーが利用している中小企業向けのグループウェアです。クラウド型とオンプレミス型(パッケージ版)の両方があり、それぞれの企業に合わせた柔軟な導入が可能。クラウド版であれば1ユーザー月額500円から利用でき、サポート体制が充実しているのも魅力といえるでしょう。
Garoon

「Garoon」は、掲示板や社内メール、ファイル管理などの基本的なグループウェア機能に加え、タイムカードやメモ帳など便利な機能を備えたグループウェアです。コメントには「いいね」をつけられるため、従業員同士のコミュニケーションを図る場としても重宝されています。また、拡張性が高く、他製品と柔軟に連携するAPIが用意。仕様やガイドラインは開発支援サイトで公開されており、カスタマイズ性に優れているのが特徴です。
rakumo(Google Workspace版)
「rakumo」は、GoogleのグループウェアであるGoogle Workspaceの既存機能を拡張したクラウド型サービスです。rakumoシリーズは2000社以上に利用されており、Google Workspaceにはない、電子稟議や勤怠管理などの業務領域もサポートしています。
desknet’s NEO

「desknet’s NEO」は、27のアプリケーションを標準搭載したグループウェアで、累計4450万のユーザーに利用されています。社内業務をシステム化できるアプリ作成ツールは、特別なIT知識がなくても利用可能です。クラウド型、オンプレミス型(パッケージ版)の両方があり、中小企業から官公庁まで導入実績があります。
SharePoint
「SharePoint」は日本マイクロソフトによるグループウェアで、高いセキュリティやMicrosoft Officeとの連携がスムーズにできる点が特徴です。マルチプラットフォームに対応しているためどこからでも情報にアクセスでき、権限管理によって閲覧者や編集者の管理もスムーズにできます。
ITreviewではその他のグループウェアも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討できます。
まとめ
グループウェアは、コロナ禍によるテレワークをはじめ、あらゆる状況での業務遂行に役立つツールやソフトウェアです。
導入には費用や手間がかかる一方、導入後は従業員同士でコミュニケーションを図り、スムーズな情報共有ができるなどメリットも非常に多く、業務効率化につながります。導入にあたり、自社が何を優先しているのか、費用や導入形態などを検討しながらベストなグループウェアを選びましょう。
投稿 グループウェアとは?大手企業も使うおすすめのグループウェア、活用事例も紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 テレワークとは?テレワーク導入で働き方はどう変わるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>すでにテレワークを導入した企業では、さまざまな課題と直面しており、その対策に取り組んでいます。また、まだテレワークの導入を検討している段階の企業では、導入後に生じるであろう課題を事前に調査し、準備を整えつつあります。
この記事では、テレワークの意義やメリット・デメリット、そして課題への解決方法などについて解説します。
テレワークとは?
テレワークは「tele(遠隔地)」と「work(働く)」の複合語で、ICT(Information and Communication Technology)を活用して時間や場所の制約を受けない柔軟な働き方を示します。
総務省では、テレワークを「雇用型」と「自営型」に分類しています。
| 雇用型 | 在宅勤務 | 自宅を就業場所とするもの |
| 企業に勤務する被雇用者が行うテレワーク | モバイルワーク | 施設に依存せず、いつでも、どこでも仕事が可能な状態のもの |
| 自営型 | 施設利用型勤務 | サテライトオフィス、テレワークセンター、スポットオフィス等を就業場所とするもの |
| 個人事業者・小規模事業者等が行うテレワーク | SOHO | 主に専業性が高い仕事を行い、独立自営の度合いが高いもの |
| 内緒副業型勤務 | 主にほかのものが代わって行うことが容易な仕事を行い、独立自営の度合いが薄いもの |
雇用型
雇用型は企業に勤務する人が行うテレワークで、さらに「在宅勤務」と「モバイルワーク」「施設利用型勤務」に分類されます。
・在宅勤務
自宅を就業場所として業務に従事する働き方です。
・モバイルワーク
場所と時間を固定せずに業務に従事する働き方です。
・施設利用型勤務
サテライトオフィスやコワーキングスペースなどを利用して業務に従事する働き方です。
自営型
自営型は個人事業者や小規模事業者などが行うテレワークで、「SOHO」や「内職副業型勤務」に分類されます。
・SOHO
「SOHO」とは「Small Office Home Office」の略語で、小さなオフィスや自宅を仕事場とする働き方、またはその仕事場、物件のことを指します。専業性が高く、独立自営の度合いが高い仕事に向いています。特定の事業に従事し副業というより、個人事業主や起業家としての意識が高い傾向にあります。SOHOの拡大は、時間やコストの削減に貢献するとされています。
・内職副業型勤務
データ入力やアンケート回答、事務作業の補助など、専業性や独立性が比較的低く、容易な業務を中心に行うスタイルの自営型テレワークを内職副業型勤務といいます。専業主婦が隙間時間を利用したり、会社に勤務しながら副業として行ったりする人も多く、ほとんどの場合は自宅で仕事を行います。
テレワークと在宅勤務の違い
テレワークと在宅勤務はあまり区別されずに使われる用語ですが、正確には在宅勤務はテレワークの一種に分類されます。通勤の必要がなく自宅で働けるため、育児や介護などと両立しやすい働き方です。
さらに在宅勤務は、「終日在宅勤務」と「部分在宅勤務」に分類されます。終日在宅勤務は、1日の業務をすべて自宅にいながら遂行します。部分在宅勤務は自宅での勤務をベースとしながらも、週の何日かは出勤したり、会議や顧客との折衝のために外出したりすることがある働き方です。
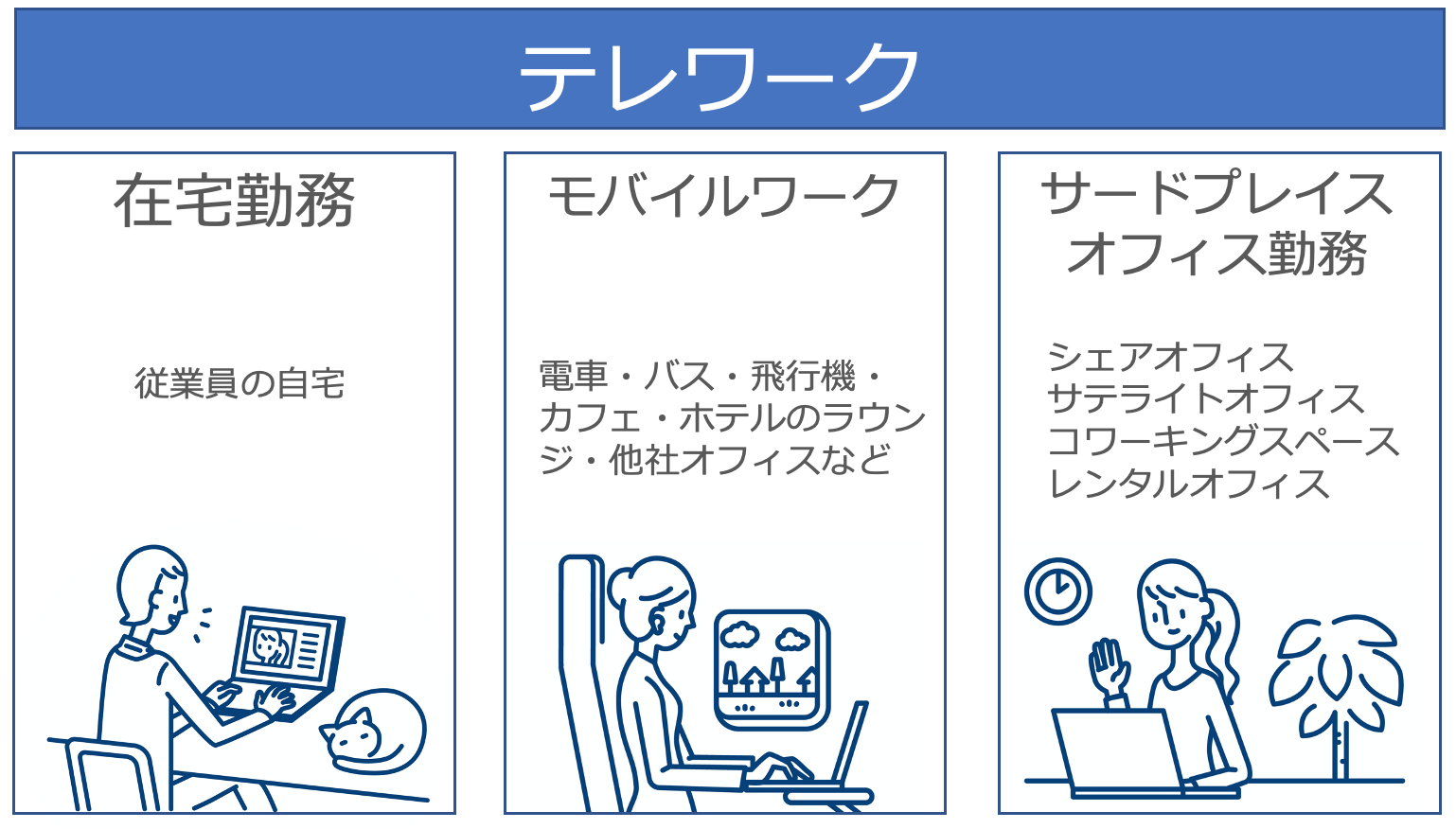
参考サイト:「総務省|テレワークの推進|テレワークの意義・効果」
関連記事:
テレワークの社会的意義や効果
テレワークが急速に普及しつつある背景には、働き方の多様化が求められている社会的な意義があります。以下、総務省のWebサイト「総務省|テレワークの推進|テレワークの意義・効果」に記載されている説明に沿って解説します。
少子高齢化対策の推進
テレワークは、少子高齢化による人口構造の急激な変化の中で、各人が能力を発揮できる働き方に寄与できます。また、性別や年齢、障がいの有無による就業機会の差をなくし、「出産・育児・介護」と「仕事」のどちらかを選ばなければならない状況を緩和します。
以上のことから、テレワークは労働人口の減少をカバーできる働き方だと指摘しています。
ワーク・ライフ・バランスの実現
テレワークは家族が共に過ごす時間を増やしたり、自己啓発のための時間を確保したり、安心して子育てできる環境やスキルアップの機会増加を実現できます。
地域活性化の推進
テレワークは、UJIターンや2地域居住、あるいは地域の企業を通して地域の活性化に寄与することができます。UJIターンとは、以下の3つの「ターン」の形をアルファベット文字の形になぞらえています。
| Uターン | 地方から都市に移住した後で、再び地方に戻ってきて移住すること |
| Jターン | 地方から別の地域の都市部に移住した後で、元に住んでいた地方の中規模な都市部に移住すること |
| Iターン | 都市から地方へ移住する(逆のケースも有り)ことや、地方から別の地方に移住すること |
環境負荷軽減
テレワークは、通勤を行わないことやオフィスを使用しないことにより地球温暖化防止に寄与します。たとえば国土交通省の『テレワークの効果に関する調査の概要―テレワークの定量的な効果測定の試み―』は、テレワークの実施によって321~442万トンのCO2が削減されるという試算を紹介しています。
有能・多様な人材の確保生産性の向上
テレワークは柔軟な働き方を実現することで、有能な人材や多様なスキルを持った人材を確保しやすくすると同時に、人材の流出を防ぎます。
営業効率の向上・顧客満足度の向上
テレワークは営業職などをオフィスを拠点にしなければならない環境から解放されることで、顧客訪問回数や顧客滞在時間を増やすことができ、より迅速で機敏な顧客対応も可能にします。
コスト削減
テレワークが定着することで、オフィスの光熱費やスペースの節約、紙の消費削減、通勤交通費の削減などのコスト削減が実現します。
非常災害時の事業継続
テレワークにより従業員の仕事場が分散することで、災害時などへの対応や復旧が迅速に行え、感染症拡大などからのリスクも低減できます。
テレワークのメリットとデメリット
以上のように社会的意義の大きなテレワークですが、企業や労働者にとっても直接的なメリットがあります。デメリットとともに確認しておきましょう。
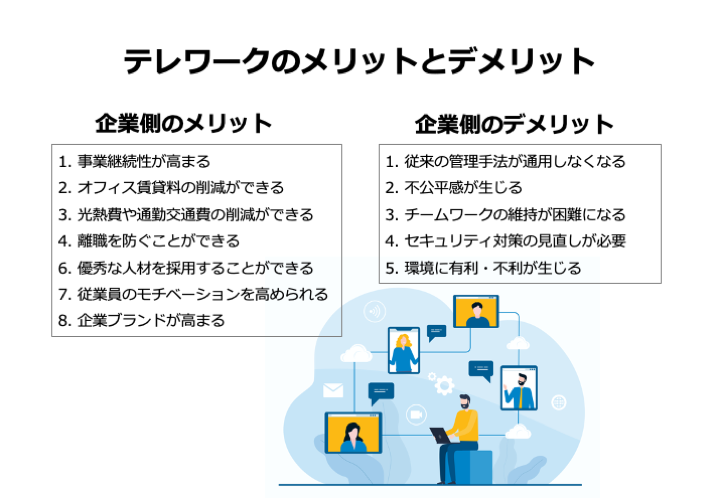
企業側のメリット
・勤務地を分散することで、災害などによる緊急時においても事業を継続できる可能性が高まる。
・勤務地を分散することで、災害などのダメージからの復旧を迅速化できる可能性が高まる。
・オフィスのスペースを縮小することで賃貸料の削減ができる。
・オフィス勤務で発生する光熱費や紙代の削減、通勤交通費の削減ができる。
・育児や介護などのライフイベントによる離職を防ぐことができる。
・地域の制約を超えて優秀な人材を採用することができる。
・ワーク・ライフ・バランスを向上させ、従業員のモチベーションを高めて生産性を上げることができる。
・テレワークを導入したことで社内外からの企業評価が上がり、企業ブランドが高まる。
従業員側のメリット
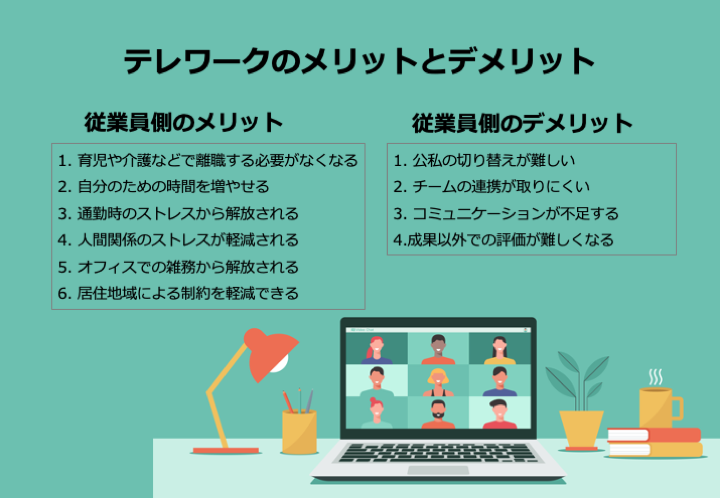
・育児や介護などを理由に離職する必要がなくなる。
・通勤時間の削減により自分のための時間を増やせる。
・通勤時のストレスから解放される。
・人間関係のストレスが軽減される。
・オフィスに滞在することで発生する雑務から解放される。
・就職や転職の際に居住地域による制約を軽減できる。
・シェアオフィスやコワーキングスペースなどを利用することで、他業種・他業界の人材との交流が生まれ、仕事上の可能性を広げたり、クリエイティブな刺激を受けたりする機会が増える。
従業員側のデメリット
・公私の切り替えが難しく仕事に集中しにくいときがある。
・リアルタイムでのチームの連携が取りにくい。
・上司や同僚とのコミュニケーションが不足する。
・成果以外での評価がされにくくなる。
テレワーク導入のポイント
これからテレワークを導入する際に、検討しておくべきポイントを紹介します。
労務管理
テレワークでも通常勤務同様に労働基準法関係法令が適用されます。そのため、以下のような措置を講じなければなりません。
・労働条件を明示する
テレワークを導入する際には、社員に給与や所定労働時間を明示するとともに、テレワーク時の就業場所を明示します。モバイルワークで就業場所が都度変わる場合には、就業場所の許可基準を明示します。また、就業時間が変動する場合には、始業時間や就業時間の変更が可能であることを就業規則に明記します。
・労働時間の管理
企業側はテレワーク時の従業員の労働時間を正確に把握しなければなりません。そのため、テレワーク時の勤務状態を客観的に記録できる仕組みを導入する必要があります。また、「事業場外みなし労働時間」や「裁量労働制」「休憩時間」「時間外・休日労働」に関する取り決めも必要です。
テレワーカーの作業環境
テレワークで働く従業員の自宅での作業環境について、プライバシーに配慮したうえでのルールを策定しておく必要があります。長時間ディスプレイを見るデスクワークとなるため、厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の「作業環境管理」で指導されている「照明及び採光、情報機器等を使用する作業(椅子も含む)、騒音の低減措置」に注意を払う必要があります。
テレワーク導入の際に検討したいツール・サービス
テレワークではさまざまなツールが活躍します。その種類はあまりに多いため、どのツールが自社に適しているのか判断が難しい面もあります。
コミュニケーション
・ビジネスチャット
ビジネスチャットとは、ビジネス用に特化されたチャットツールです。各従業員が離れて業務を遂行するテレワークでは、オンライン上で円滑なコミュニケーションを行う必要があります。
メールでは都度業務上の挨拶から始まり、業務上必要なやりとりに限定されやすいため、オフィスにいるときのような気軽な情報交換や相談、雑談を行いにくい面があります。
一方、チャットツールでは挨拶を繰り返さずに会話ライクなやりとりを行えるので、オフィスにいるときのような感覚でコミュニケーションが図れます。
また、メールでは添付ファイルのデータサイズに制限があり、ファイルを確認する手間もかかります。しかしチャットツールでは画像や動画などサイズの大きなファイルを共有したり、必要に応じてビデオ通話機能を使ったりすることができます。
→ビジネスチャットの詳しい解説はこちらをご覧ください。
https://www.itreview.jp/blog/archives/8491
グループウェア
・グループウェア
グループウェアとは、組織内のメンバーが業務遂行に必要な情報を共有するためのソフトウェアです。
オフィス内では資料を紙で共有したり、お互いの予定を確認できるホワイトボード上のスケジュールで確認したりしていました。また、ちょっとした伝達は口頭で行えていました。しかし、お互いに離れているテレワークではできません。
これらの利便性をクラウド上で実現するために、グループウェアが必要になります。グループウェアには主にスケジュールや掲示板、ファイル共有、メール、施設予約などの機能がパッケージとして提供されています。
・プロジェクト管理
プロジェクト管理ソフトウェアとは、プロジェクトのスケジュールや進捗状況、メンバーの進捗状況などが可視化されて管理できるツールです。
テレワークではメンバー同士が離れて業務を行っているため、リーダーやメンバーがプロジェクトの進捗状況を把握できなくなります。その結果、タスク漏れやスケジュールの遅れへの対応が遅れてしまいます。この問題を解消するために、進捗状況が可視化されるプロジェクト管理ツールは非常に有効なツールとなります。
・タスク管理
タスク管理ソフトウェアは、各従業員の仕事を管理するツールです。
オフィスで働いているときは少し会話をするだけでわかる仕事の進み具合や負荷のかかり具合、そしてお互いのリマインドが、テレワークになると困難になります。そこでメンバー全員のタスクを可視化して、スケジュールや進捗状況を管理できるタスク管理ソフトウェアが必要になります。
・オンラインストレージ
オンラインストレージとは、インターネット上のクラウドサービスとして提供されるストレージサービスです。
テレワークで働くことになると、各人の端末に保存されている文書などのデータを共有することができず、社内に設置されたサーバで共有していたデータも入手することができなくなります。この問題を継承するためには、どの端末からでもアクセスでき、データを共有できるクラウド上のオンラインストレージが必要となります。
セールス
・名刺管理
名刺管理ソフトウェアとは、名刺をスキャナーやスマートフォンの撮影で画像データ化し、OCR(Optical Character Reader)機能で印刷されている文字を認識してテキストデータとして抽出してデータベースで管理するソフトウェアです。
テキストデータからは氏名や社名、所属部署、肩書き、連絡先が分類され、パソコンやスマートフォンなどの端末から検索できるようになります。名刺管理はSFA(Sales Force Automation)やCRM(Customer Relationship Management)と連動させて利用されることが増えています。
→名刺管理の詳しい解説はこちらをご覧ください。
http://itreview.jp/blog/archives/8512
・CRM
CRM(Customer Relationship Management)とは、顧客管理ソフトウェアです。顧客情報を全社的に活用し、営業や保守に活用することで顧客満足度を高めることができます。CRMにはSFAの機能を搭載した製品も増えています。
・SFA
SFA(Sales Force Automation)とは、顧客情報や案件情報、商談の進捗状況などを管理する営業支援ソフトウェアです。従来、属人的なスキルに依存していた営業活動を、組織的な情報共有を行うことで成約率を高めるために利用されます。SFAにはCRMと融合された製品が増えています。
バックオフィス
・労務管理
労務管理システムとは、従業員の労働時間や賃金、福利厚生などを管理するソフトウェアで、労働基準法などの法令に基づいて従業員などの適切な管理を支援します。勤怠管理や給与計算、人事評価を支援する機能を備えたソフトウェアも増えています。
・勤怠管理
勤怠管理システムとは、従業員の出・退社時刻や就業日数、残業時間などを管理するツールです。テレワークの導入が増えていることから、オフィス外の端末から業務開始・終了の時刻を申請させたり、端末のオン・オフ時刻を自動的に取得したりして就業時間を記録する仕組みも搭載されています。
・会計ソフト
会計ソフトとは、ビジネスに関わる金銭の動きの記録から仕訳や財務諸表の作成までを自動化して、会計業務の効率化を支援するツールです。
セキュリティ
・仮想デスクトップ
VDI(Virtual Desktop Infrastructure)とは、サーバ上のデスクトップ環境をクライアント端末に転送して利用する仕組みです。VDIを活用することで、端末にデータが残らないため、ウイルスに感染して情報が漏えいするリスクが減少します。
また、アプリケーションもサーバ上で管理されるため、ユーザー各人が個々に不正なアプリケーションをインストールしてしまうリスクを防ぎます。さらに、OSのアップデートやセキュリティ対策ソフトのアップデートもサーバ側で一括管理できるため、管理者とユーザーの負担を軽減できます。一方、DaaS(Desktop as a Service)とは、VDIがクラウド上に構築された仕組みです。
●VPN
VPN(Virtual Private Network)とは、仮想で専用回線によるアクセスの安全性を確立する技術です。社内セキュリティの強化のためにVPNを利用する企業は増加しています。VPNを利用するためには通信事業者との契約が必要で、VPNルーターを用意する必要があります。
・シンクライアント
シンクライアント「Thin Client」とは、仮想デスクトップで使用することに特化した端末です。端末自身ではアプリケーションのインストールやデータの保管も行わないため、ハードディスクや光学ドライブなどの記憶装置を搭載していません。
OSやアプリケーションのアップデートはサーバ側で行うため、保守コストが軽減できます。また、データの保存やセキュリティ対策もサーバ側で行うため、データ漏えいのリスクも抑えられます。
・UTM
UTM(Unified Threat Management)は「統合脅威管理」と訳されます。ファイアウォールや、アンチウイルス、アンチスパム、そしてWebフィルタリングなどのセキュリティ対策機能が統合された製品です。すべてのセキュリティ対策を一元管理できるため、管理者の負担を軽減できます。
人材活用
・クラウドソーシング
クラウドソーシングとは、仕事を発注したい個人や企業と、仕事を受けたい個人や企業をマッチングさせるクラウド上のサービスです。クラウドソーシングの「クラウド」は「crowd」で群衆を示し、クラウドコンピューティングの「クラウド」の「cloud(雲)」とは異なります。また、似た用語にアウトソーシングがあります。アウトソーシングは特定の業者に仕事を依頼するのに対し、クラウドソーシングでは不特定の個人や企業に仕事を依頼します。
ワークプレイス
・仮想オフィス
仮想オフィス(バーチャルオフィスツール)とは、インターネット上に仮想のオフィスを設置することで、自宅でテレワークをしていても出勤している感覚を持てるツールです。実際のオフィスを再現したレイアウト上の座席にチームメンバーのアイコンを表示したり、3D空間のオフィスの中でメンバーのアバターが動いたりすることで、テレワーク中もチームメンバーと共に働いている感覚を得られます。
・コワーキングスペース
コワーキングスペースとは、さまざまな個人事業主や企業の社員たちなど、多様なバックグラウンドを持つ人たちが仕事スペースを共有できる施設です。
設備を共有することで、家賃や光熱費、プリンタなどの機器の経費を削減することができます。また、業種を超えた交流から新しいビジネスチャンスが生まれることもあります。今はコロナ禍で市場が停滞気味となっていますが、今後はテレワークの普及とともにまたニーズが高まっていくと考えられます。
→コワーキングスペースの詳しい解説はこちらをご覧ください。
https://www.itreview.jp/blog/archives/8542
テレワークに向いている職種

テレワークを導入する際、全社的に一気に導入することは難しいかもしれません。テレワークには導入しやすい業務と導入しにくい業務があるためです。まずは導入しやすい業務から実施し、そこで生じた課題を解決しつつ、順次ほかの業務に導入していくことも検討の価値があります。
テレワークが導入しやすい業務は、オフィスや工場でなければ設置できないような特殊な設備を必要としないデスクワークで、かつチームのメンバーと直接会っていなくてもオンラインでコミュニケーションが取れれば基本的には単独で遂行できる内容のものです。
ここでは、テレワークを導入しやすい業務を挙げてみました。
事務
事務職は使用するソフトも、単独作業用にはオフィス系のソフトをインストールし、部門内で共有が必要な作業はクラウド上のサービスを使用できます。
システムエンジニア
システムエンジニアはチームでの共同作業も、クラウド上のプロジェクト管理ツールやWeb会議システム、ファイル共有ツールを使用すれば十分に対応できます。
プログラマー
プログラマーは作業指示も口頭よりドキュメントによるほうが伝達ミスを削減できるため、ほとんどの業務はネットワーク上で処理できます。
Webデザイナー
Webデザイナーは、クライアントとの打ち合わせや企画会議などに参加する以外は、1人で作業できる職種であるため、テレワークに向いています。打ち合わせも、Web会議ツールを使えば、自宅で対応できます。
Webライター
WebライターもWebデザイナーと同様に、クライアントとの打ち合わせや企画会議などもWeb会議ツールを使えば自宅で対応できます。
カスタマーサポート
カスタマーサポートは、顧客からの問い合わせに対応する職種ですが、やりとりは電話かメール、チャットを介しますので、近年はテレワーク化が進められています。
営業
営業は一見テレワーク化が難しい職種に思われますが、実際には顧客を訪問していることが多いため、自社のオフィスに滞在している時間はどの部署の従業員よりも短いことが一般的です。オフィスで行っている業務も、見積書や請求書の作成、アポ取り、提案資料の作成、日報作成など、テレワークでも対応できる作業がほとんどです。むしろ、オフィスに出勤しなければ直接顧客を訪問して自宅に直帰できることで、時間を効率的に活用できるようになります。
管理職
管理職は部下を管理したり、働きぶりを確認したりする必要がありますが、その部下がテレワークに移行していれば、管理職もオフィスに出勤する必然性はなくなります。テレワークで働いている部下の管理は、ネット経由で行いますので、管理職自身もテレワークに移行しやすいと言えます。
テレワークを導入しにくい職種

次に、現時点でテレワークを導入することが難しい職業を挙げます。一般的に医療従事者、運送・配送に携わるドライバー、公務員や介護・福祉等の分野で働く人、スーパー等の店員、教員、保育士など、エッセンシャルワーカーと呼ばれる職業・仕事はテレワークが難しいとされます。
生産・製造
製造現場や生産現場に従事する社員のテレワーク化は困難です。それは、業務遂行のために個人の自宅には設置できない規模の専用の設備や道具が必要であり、流れ作業には固定された作業スペースが必要なためです。また、同じ製品をチームワークで造り上げるため、チームメンバーは同じ施設内で働く必要があります。
接客・販売
接客や販売に携わる従業員はテレワーク化することが困難です。百貨店やスーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、銀行、役所など、来店した顧客に従業員が直接対応しなければならない現場では、まだまだテレワーク化は難しいでしょう。一部、コンビニエンスストアの無人店舗化や、化粧品売り場の接客をディスプレイ越しに遠隔で行うなどの試みも始まっていますが、まだ緒に就いたばかりといえます。
医療・福祉
医療や福祉もテレワーク化は困難です。いずれも対面で相手の様子を見たり会話をしながら対応したりする必要がありますし、触診や介護では直接身体に触れる必要もあるため、テレワーク化はまだ困難といえます。また、院内でなければ使えない特殊な設備や医薬品を必要とすることも、テレワークを難しくしています。
ただし、問診のみやカウンセリング、アドバイスを行うなどの一部の行為であれば、テレワークの導入の可能性もあります。また、5Gによる通信速度の飛躍的な高速化と手術ロボットの発達により、遠隔地からのオンライン手術やオンライン診断への期待が高まっています。
コロナ禍が加速させた働き方の変化
2020年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大は世界中に及び、人々の生活様式や働き方を大きく変え、ニューノーマルの時代が到来したといわれました。職場においても3密を避ける工夫が施されました。コロナ禍は働き方をどのように変えたのでしょうか。
勤務の仕方を多様化させた
職場では3密を避けるために、可能な限り従業員同士が接触しない勤務方法を導入しました。主な導入形態は次の通りです。
●テレワークで従業員同士が接触しないようにする。
●時間差通勤で通勤ラッシュ時の密を避ける。
コミュニケーションのオンライン化
従業員同士や顧客、協力先との接触機会を減らすために、コミュニケーションのオンライン化が進められました。主な手段は次の通りです。
・会議や打ち合わせ、商談をWeb会議ツールで行う
・プロジェクト管理をクラウド上のプロジェクト管理ツールで行う
・スケジュール管理や情報共有などをグループウェアで行う
・相談や連絡などをチャットツールで行う
・ファイル共有をクラウド上のストレージで行う
テレワークの課題と解決策
メリットが多いテレワークですが、課題もあります。ここでは課題と解決方法について解説します。
従業員の間に不公平感が生まれやすくなる
同じ社内でもテレワークを認められた部門と認められない部門が出てきます。これは、全部門を一度にテレワーク化することは困難なため、テレワークを導入しやすい部門から様子を見ながら導入するためです。
しかし、テレワークで働いている従業員は、出勤している従業員から見れば自由度がかなり高いと感じられることがあります。また、上司や同僚との人間関係によるストレスや、通勤ラッシュのストレスなどが軽減されていることも羨ましく感じられるでしょう。
さらに、電話対応や来客者への対応、荷物の受け取り、清掃など、テレワークで出勤しない従業員の分まで出勤者の負担が増えることもあるため、忙しさが増し、場合によっては残業が増えるなどしてますます不公平感が強まります。
このような場合は、テレワークの導入には順序があることや、テレワーク化が困難な業務があることをしっかり説明し、場合によってはテレワークの対象になった社員との待遇に差をつけるなどの対応を検討する必要があるかもしれません。
同時に、社内のコミュニケーションを円滑にするためにビジネスチャットツールを活用して気軽に意思疎通を図れるようにしたり、お互いの仕事ぶりを見える化できるグループウェアやプロジェクト管理ツール、タスク管理ツールを導入したりすることも有効です。
・関連するツール
テレワークではモチベーションが下がりやすい
テレワークは通勤時間の節約ができたり家族とのコミュニケーションが豊かになったりすることで仕事へのモチベーションを高める場合がありますが、一方で、本来はプライベートな空間である自宅にいるために、仕事と私生活のけじめがつけにくくなり、オン・オフの切り替えが難しくなる場合もあります。
また、オフィスと異なり上司や同僚が働いている姿が見えないことや、逆に自分も見られていないことから、勤務時間中であることの緊張感を保つことが難しい場合もあります。
さらに、オフィスにいるときのように気軽に上司や同僚に相談したり、お互いの進捗状況を把握したりすることが難しいことも、仕事へのモチベーションを下げてしまう一因となるかもしれません。
これらの問題を解決する方法として、上司や同僚の存在感を感じたり、気軽にコミュニケーションを取れたりするように、仮想オフィスやビジネスチャットを導入することが考えられます。
・関連するツール
人事評価を行いにくい
テレワークの課題の1つとして、上司が部下の働きぶりを把握しにくいことが挙げられます。そのため、部下の管理や評価が困難になります。また、部下の評価が難しくなることで、どのように人材育成を進めればよいのかも判断が難しくなります。
一方、テレワークを導入することで部下の管理や人事評価、人材育成がより合理化されるケースもあります。したがって、テレワークの導入は、部下の管理や人事評価、人材育成のあり方について見直す機会であると捉え、勤怠管理システムや人事評価・OKR(Objective and Key Result)システムを活用することを検討してもよいでしょう。
・関連するツール
テレワークの環境が整わない
テレワークで働いている従業員の中には、自宅の環境がテレワーク向きではない場合もあります。スペースが確保できなかったり、通信環境が整っていなかったり、あるいは小さな子どもがいて落ち着かないといったこともあるでしょう。
通信環境については会社が環境整備の費用を提供することや、技術的なサポートを提供することができますが、スペースの拡張や子どもの面倒を見るといった支援は現実的ではありません。その場合は、コワーキングスペースの利用を許可したり、会社のサテライトオフィスの利用を認めたりするなどの対策を検討する必要があります。
・関連するツール
労働時間の管理がしにくい
テレワークで自宅勤務をしている従業員に対して、会社は労働時間の管理が困難になります。テレワークでは、労働時間の状況は従業員の自己申告に頼らなければなりません。
そこで、自己申告の内容に可能な限り客観性を持たせるために、端末の使用時間から始業時刻と終業時刻を取得するなどの方法が検討されます。勤怠管理システムを導入することで、テレワーカーだけでなく出勤している従業員も対象とした全社的な勤怠管理を一元的に行うことができるようになります。
・関連するツール
セキュリティリスクが高まる
テレワークでは、自宅のみならず、サテライトオフィス、コワーキングスペース、カフェなど、さまざまな場所でモバイル端末を使用する可能性があります。そのため、ネットワーク接続に伴うセキュリティリスクが高まります。テレワーク導入に際してのセキュリティ対策では3つのポイントを押さえる必要があります。
①テレワーク時のルールを策定し、周知させる
テレワーク時のセキュリティリスクがどこに潜んでいるのかを会社側と従業員の間で共有し、セキュリティツール導入の必要性や、許可されていないソフトのインストールを行わないなどのルールを守ることの重要性の認識を共有します。
②セキュリティリスクの危険度を共有する
セキュリティリスクに関する研修などを行うことで、情報漏えいなどが起きた場合に会社や顧客がどのような損失を被るのか、従業員にどのような責任が生じるのかなど、セキュリティリスクの危険の重大性についての認識を社内で共有します。
③セキュリティツールの導入
テレワークを導入する際には、セキュリティツールの導入も必須になります。セキュリティツールには、IDS(Intrusion Detection System:不正侵入検知システム)やIPS(Intrusion Prevention System:不正侵入防御システム)、Webフィルタリング、アンチウイルス、アンチスパムなどがありますが、これらを統合して一元運営できるUTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)の導入も有効です。
・関連するツール
ハイブリッドワークとは?
コロナ禍によって一気に加速したテレワークですが、うまく機能せずにコロナ禍の収束とともに出社型の勤務スタイルに戻る企業も少なくありません。
ただし、出社型と言っても以前のような完全出社型ではなく、必要に応じて出勤したり、週に1~3日を出勤したり、あるいは月の第1月曜日と第2月曜日を出勤日とするなど、テレワークと出勤を併用した「ハイブリッドワーク」を採用する企業が多くなると予想されます。
すでにテレワークを体験した企業では、会社側と従業員側が、それぞれテレワークのメリットとデメリットに気づいているため、テレワークと出勤型のよいとこ取りをしたワークスタイルが検討されているでしょう。
また、ハイブリッド型には、1人の従業員がテレワークと出勤型をミックスするタイプのほかに、同じ部門でも完全テレワークの従業員と出勤型の従業員が混在するハイブリッドワークも考えられます。これは、性格上の理由やICTツールとの相性のよさから完全なテレワークが向いている従業員や、家庭の事情からテレワークにせざるを得ない従業員がいる一方で、オフィスでなければ業務に集中できない従業員や自宅の環境がテレワークに適していない従業員などが混在しているためです。
以上のことから、今後は、より生産性が高いワークスタイルを選べる働き方の多様性が求められる結果として、あらゆる面でハイブリッドの概念を取り入れる企業が増えると予想されます。
まとめ
少子高齢化による労働人口の減少が進む中で、より優秀な人材を確保し流出を防ぐためには、より柔軟な働き方を選べる多様なワークスタイルを認めることが、企業の競争力やブランド力を高める結果になります。そのためにも、可能な限り多くの部門でのテレワークの導入を検討する必要があります。
テレワークは、インフラの整備や関連法への対応、社内規定の策定など、導入開始段階では人的・金銭的なコストがかかります。この負担は、中小企業にとっては大きな経営判断となるでしょう。
しかし、長期的に見れば、多様な働き方を取り入れることは、優秀な人材確保と生産性の向上、創造力の向上によるイノベーションが起きる可能性をもたらすことが期待できます。
裏を返せば、今対応しなければ、近い将来競争力を失い、経営悪化に直結する可能性もあります。テレワークの導入を業績の向上につなげるためにも、導入のポイントを押さえておく必要があります。
投稿 テレワークとは?テレワーク導入で働き方はどう変わるのか? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ビジネスチャットとメールは何が違う?ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>ビジネスチャットとは?
ビジネスチャットとは、社内や社外の人と連絡をとることのできるコミュニケーションツールのことをいいます。メールであれば、挨拶文などを記載しますが、ビジネスチャッではそれらを省いて要件のみを端的に伝えるのが慣例です。また、あえて返信する必要のないと考えられる内容のメッセージに対し、絵文字だけで返信することも当たり前。このようにビジネスチャットは、メールよりもフランクかつストレートに伝えられるという特徴があります。
個人向けチャットとの違い
個人向けチャットとビジネスチャットが大きく異なるのは、個人向けチャットは完全にプライベートで利用するツールであるのに対し、ビジネスチャットはその名のとおり「ビジネス向け」であるという点です。また個人向けチャットは、セキュリティ面において脆弱であり、情報漏えいリスクは常につきまといます。ビジネスチャットはセキュリティ面においても本格的なビジネス利用に特化したツールといえるでしょう。
ビジネスチャットとメールの特徴
| ビジネスチャット | メール | |
| スピード | ・手軽・迅速 ・一度やり取りした相手にはすぐメッセージを送れる |
・形式的で時間を要する ・宛先メールアドレスの入力が必要 |
| コミュニケーションの確認 |
・同じグループでのコミュニケーションは1つの場(スレッド)に残るのでスクロールして確認できる | ・1通1通開いて確認する必要がある |
| 資料の共有 | ・リアルタイムにやり取りができる ・音声通話・ビデオ通話のあるツールやプランもある |
・メールに添付することができる ・後で確認する場合、添付したメールを探さなくてはいけない |
| コミュニケーション | ・フランクなやり取りがしやすい | ・リアルタイム性に乏しい |
| 心理的距離 | ・リアルでないことに距離感を感じる人と気楽に感じる人が二極化している | ・チャットに比べてフォーマルなやり取りに向いている |
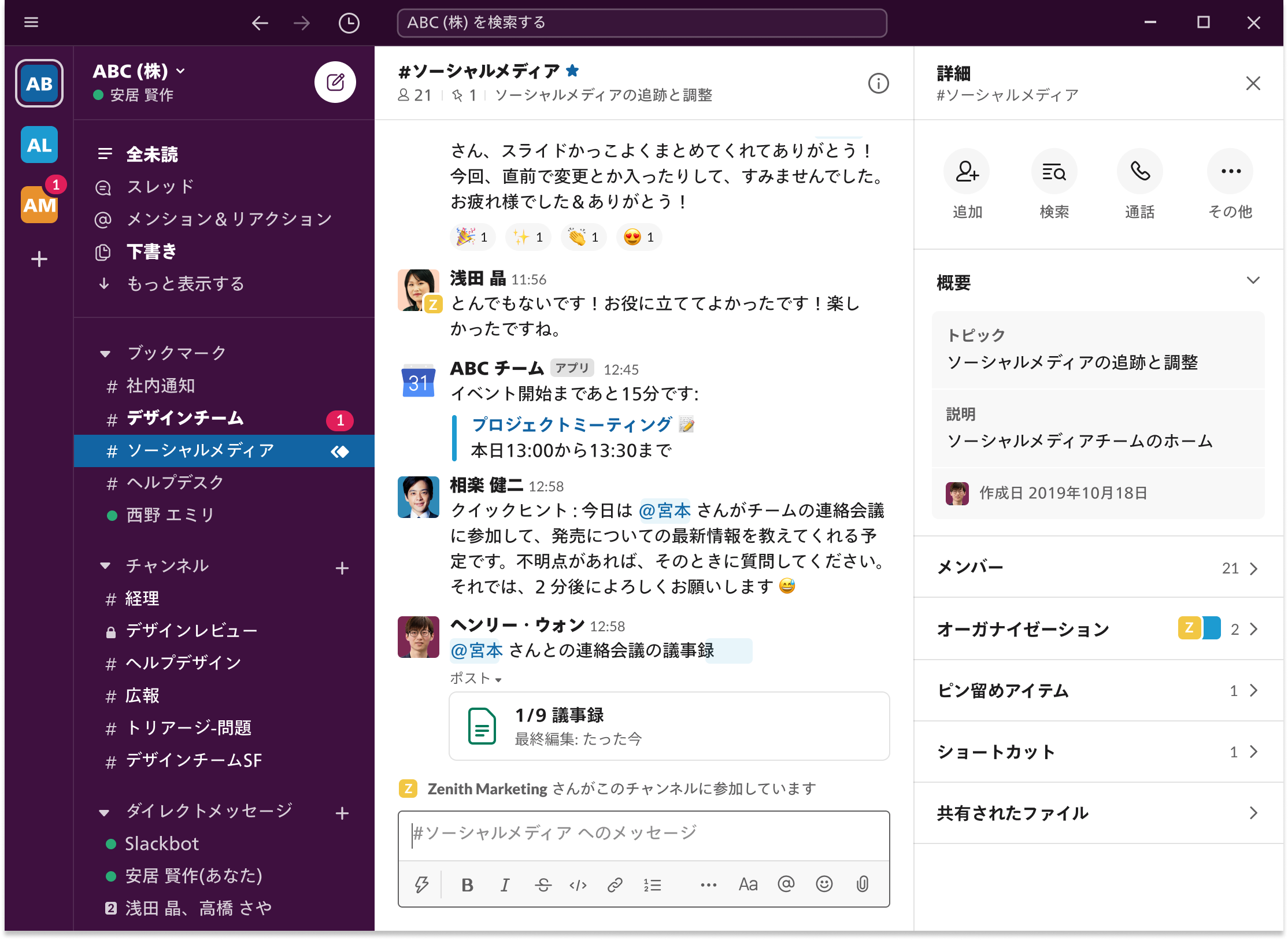
アメリカのSlack Technology社が開発・運営するSaaS型のビジネスチャットツールです。「チャンネル」というグループチャット機能を軸としたメッセージプラットフォームで、ツールを1つにまとめて業務効率化の実現。日本でも法人・個人問わず、生産性の向上を目的とする多くの企業が導入しています。
Slackの製品情報・レビューを見る
Chatwork
日本国内での利用数が最大の中小企業向けビジネスチャットツール。スムーズな情報共有で意思決定でき、業務の効率化により費用の削減を実現します。IDがあれば社内外を問わずすぐにやり取りができるので、社外の人とのやり取りや営業ツールとして広く活用されています。
Microsoft Teams
Microsoft 365やOffice 365 Business Essential/Premiumプランに提供されているツール。チャット・通話機能の他、ビデオ会議機能、ファイル共有機能、Officeアプリとの連携機能があり、Microsoftアカウントがあれば無料での利用も可能です。
LINE WORKS
LINEと同じ使い勝手で、導入したその日から誰でもすぐに使えるビジネスツールとして開発。ユーザーインターフェースやスケジュール管理、ファイルやフォルダを共有・管理可能です。LINEおなじみのチャットやスタンプは、多くの現場で楽しい職場づくりをサポート。LINEや他社のLINE WORKSユーザーとのトーク機能で、さらに社外とのつながりも広がります。
Team Viewer
初めて使う人でも専門の知識がなくても使えるセキュリティの高いリモートデスクトップツール。ネットワーク設定などを極力排した簡単な操作で利用でき、セキュリティなどの安全面も意識する必要がありません。専門的な知識がなくても使いやすいのが、人気の最大の理由といえます。
Team Viewerの製品情報・レビューを見る
ITreviewではその他のビジネスチャットツールも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
ビジネスチャットの比較・ランキング・おすすめ製品一覧
まとめ
ビジネスチャットツールは、社員同士がコミュニケーションを円滑に進めていくうえで欠かせないツールです。まずは自社がどんな目的でどのツールを選びたいのかを明確にし、それぞれのビジネスチャットの特徴を把握することが肝心です。目的に合った機能を備えたツールを選ぶことが、業務の効率化につなげる第一歩といえるでしょう。
投稿 ビジネスチャットとメールは何が違う?ビジネス利用でおすすめのチャットツール5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 情報セキュリティの初歩。脅威の事例や対策方法を詳しく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そのような悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。情報セキュリティについて適切に理解することが、さまざまな脅威から大切な情報資産を守ることにつながるのです。
この記事では情報セキュリティの知識を得たい人に向けて、具体的な内容や脅威の種類、情報セキュリティ対策に欠かせない要素を解説します。最後まで読めば、実際の脅威の事例から検討すべきセキュリティシステムまで、よくわかるようになるでしょう。
情報セキュリティとは?
情報セキュリティとは、「データが破損したり情報が漏えいしたりせず、使いたいときに常時アクセスできる環境を維持する」ことです。顧客情報やファイル、電子メールデータといった企業の情報資産を守ることにつながります。
インターネットやコンピュータを安心して使い続けるためには、情報セキュリティ対策が欠かせません。情報資産は機密情報の漏えい、不正アクセス、サービス停止、データ改ざんなど、さまざまな脅威を受ける可能性があるからです。

日本製品の規格を定める日本工業規格(JIS)や、国際標準化機構のISOでは、組織が保護すべき情報資産について、(1)機密性(Confidentiality)(2)完全性(Integrity)、(3)可用性(Availability)の3つを維持し、改善することが定められています。
上記のポイントを継続的に維持・改善していくことで、強固なセキュリティ対策を実現できるでしょう。
「テレワークセキュリティガイドライン」の活用を
社会全体でテレワークの導入が推進されるにつれて、情報セキュリティの重要性も増してきています。
総務省が定める「テレワークセキュリティガイドライン」では、テレワーク環境で必要なセキュリティ対策やトラブル事例、解決策などが掲載されています。これからテレワーク導入を検討している、もしくはより活用できる環境を構築していきたい企業は目を通しておくとよいでしょう。
情報セキュリティにおける3つの脅威
情報セキュリティには3つの脅威が存在します。それぞれの内容や、脅威を防ぐための対策について見ていきましょう。
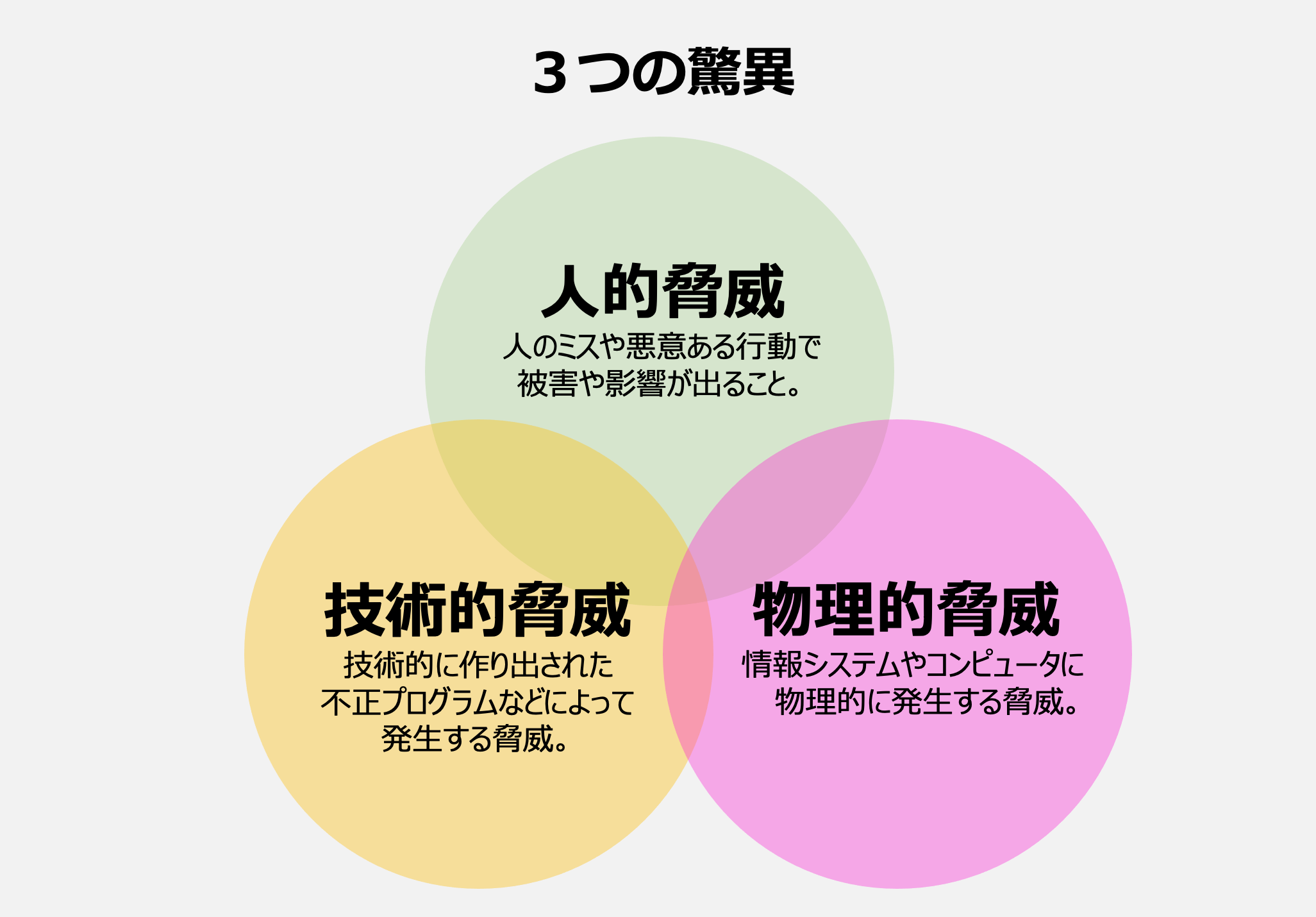
1. 人的脅威
人のミスや悪意ある行動で被害や影響が出ることです。次のように、システムの誤操作や不注意による不具合などがあります。
ヒューマンミスの代表例
・メール誤送信
・サーバ内のデータ削除
・パソコンやSDカード、USBメモリの紛失
・システム脆弱性の見落とし
・情報漏えい
対策としては、次のようにミスや不正行為を防止する仕組みを構築することです。
不正予防の観点
・情報を閲覧・操作できる人を制限する
・情報利用者の情報に対するモラルの教育を徹底する
・社内でルールを決めて体制を整えていく
2. 技術的脅威
技術的に作り出された不正プログラムなどによって発生する脅威です。この脅威を受けると、情報の盗難や改ざんにつながる恐れがあります。
特にコンピュータウイルスなどのマルウェアによる被害が有名でしょう。マルウェアとはウイルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェア、ランサムウェア、フィッシング詐欺など、悪意のあるプログラムやソフトウェアを総称する言葉です。
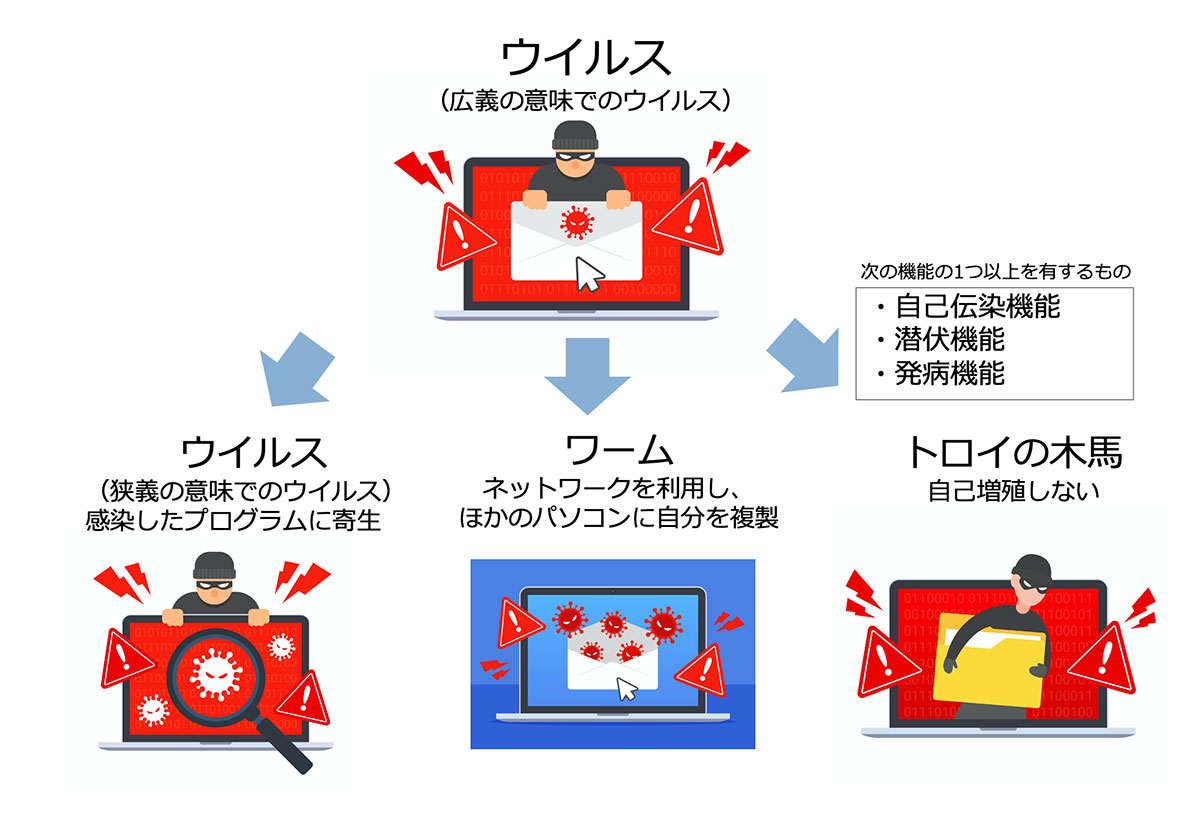
対策としては、被害を受けないための環境を構築することが重要になります。まずはセキュリティ製品を設置するのがおすすめ。さらに送信元の不明なメールを開かないなど、情報使用者の危機管理教育も欠かせません。
3. 物理的脅威
情報システムやコンピュータに物理的に発生する脅威のことです。機材の老朽化や、自然災害・事故による機材破損、悪意を持った破壊・盗難、施設への不正侵入などがあります。
物理的脅威を防ぐには、以下のような対策が有効です。
・定期的に機材をメンテナンスする
・自然災害を想定して機材環境を整備する
例)サーバを複数拠点に分散し、どこかが停止しても稼働を続けられるようにする
・機材のある部屋にアクセス制限をかける
情報セキュリティ対策で意識すべき7つの要素
企業や組織は情報資産を保護するために、次の7つに関する脅威を防ぐ必要があります。
1. 機密性
許可された人だけが情報を閲覧できるように保護・管理をすることです。情報を容易に外部に持ち出せないようにすることで、高い機密性を保持できます。企業内の人間が誰でもアクセス可能な環境の場合は、機密性が低い状態といえます。
機密性を高めなければならない主な情報は、社員の個人情報や顧客情報、システムのパスワードなどです。
このような情報を保護するには、次の対策が有効でしょう。
・非許可の利用者はコンピュータやデータベースへのアクセス不可にする
・閲覧できても書き換えはできないようにする
・推測されやすいパスワードを使用しない(123、abcなど)
2. 完全性
情報の中身が欠けることなく、正確かつ最新の状態に保たれていることを意味します。完全性が失われた場合、情報の正確性や信頼性がなくなり利用価値が下がってしまうでしょう。たとえば「顧客情報の電話番号が間違っていた」などが挙げられます。
完全性を保つには、下記のような対策を取り入れましょう。
・情報へのアクセス履歴・変更履歴を残す
・手順書やマニュアルの入力方法を規定する
・データを暗号化して保管する
3.可用性
アクセスを許可された人がいつでも情報にアクセスできるようにすることです。「可用性を維持する=情報を提供するサービスが常時動作している」ことにつながります。たとえば地震発生後にサービスが提供できなくなった場合は、可用性がない状態といえます。
可用性を保持し続けるには、下記のように対策するのがよいでしょう。
・データをバックアップしすぐ復旧できるようにする
・システムの冗長化を行う
・復旧マニュアルを作成する
4. 真正性(完全性)
情報使用者がなりすましではなく、間違いなく本人である状態のことです。たとえば情報処理のプロセスが「不正に個人情報をだましとるような偽物ではない」などが挙げられます。真正性の対策としては、IDとパスワードで本人しかアクセスできないようにすることが効果的。また、ハッシュ関数やデジタル署名で情報制作者を明確にするのもよいでしょう。
5. 責任追及性
誰が情報へのアクセスや操作を行ったかを明らかにすることです。情報管理やシステム運用に関して保安上の脅威となるインシデントが発生した際に、利用者やシステムの責任を説明できるようにしておく必要があります。アクセスログや操作ログを記録しておくことがもっとも効果的でしょう。
6. 信頼性
情報処理が不具合なく行われることを指します。行った操作に対して正しい情報や結果が返ってくる、システムに故障がないといった状態です。たとえばネットショップの商品購入画面で、「商品をカートに入れているのに表示されない」場合は信頼性がないといえるでしょう。システムやソフトウェアにバグが出ないように設計・構築をするのが主な対策です。
7.否認防止
情報を操作・作成した人が、あとからその事実を否定できない環境にすることです。否認防止の対策としては、文書ファイルやメールにデジタル署名をつけ、制作者をはっきりさせることが有効です。さらにシステムログを記録することで、情報の改ざんや破壊した人間が責任逃れできない環境になります。
実際に起きた脅威の事例
ランサムウェアやテレワーク環境を狙った標的型攻撃など、2020年中にも多くの企業が被害に遭っています。ここでは情報処理推進機構(IPA)が公表した「情報セキュリティ10大脅威 2021」における「組織部門」のランキング上位3位の結果をもとに、3つの事例を紹介します。

ランサムウェアにより業務が一時停止
2020年でもっとも多い被害です。大手ゲームメーカーのサーバがランサムウェアに感染し、約11億円を要求される事件もありました。
ランサムウェア攻撃は、下記のようにメールなどを利用してウイルスに感染させ金銭を要求。データが暗号化されてしまうため、メールやファイルが使えなくなります。その結果、業務を一時停止せざるを得なくなり多大な影響が出てしまうのです。
・メールの添付ファイルを開かせる
・改ざんしたWebサイトを閲覧するようにメールで誘導する
・管理用のリモートデスクトップでサーバに不正アクセスし、ウイルスを実行させる
標的型攻撃により機密情報を盗まれる
ランサムウェアと同様、メールやWebサイト経由でウイルスに感染する企業が相次ぎました。ある電機メーカーでは防衛事業部門のサーバに侵入され、2万7445件のファイル情報に不正アクセスされるという被害もありました。
標的型攻撃では次のような手口でパソコンをウイルスに感染させ、組織内部に侵入します。そして長期間にわたって感染範囲を拡大させ、機密情報を盗み取るのです。
・メールの添付ファイルを開かせる
・標的組織がよく利用するWebサイトを調べ、閲覧したら感染するように改ざんする
テレワーク環境の管理体制不備が狙われる
新型コロナウイルスの影響で、テレワーク環境が増加したことを狙った攻撃です。2020年8月には仮想プライベートネットワーク(VPN)の脆弱性が悪用され、約900件の認証情報がインターネット上で公開される事件も起きました。
主に以下のような管理体制の不備につけ込み、不正アクセスして情報を盗み取るケースがほとんどです。
・テレワーク用ソフトウェアがアップデートされていない
・セキュリティ対策が十分に施されていない私用パソコンを利用する
上記のような被害を未然に防ぐためにも、適切な知識や対策方法を知っておく必要があります。記事の後半で解説しているので、ぜひご覧ください。
リスクアセスメントで脅威を防ぐ
リスクアセスメントとは「保有している情報のリスク」と「リスクの発生頻度や影響度」を確認し、対応を判断することです。以下の3つの対応について、それぞれ解説していきます。
リスク回避
リスクが発生する原因をゼロにする方法です。原因自体がなくなれば、そもそも発生後の対応や影響を考える必要もありません。たとえば外部とのネットワークを遮断して不正アクセスを防止するなどです。また極秘プロジェクトの情報を削除してしまい、別の管理方法に変えるのも効果的といえます。
リスク回避のデメリットは、外部とのネットワークを遮断することで一般ユーザーからもアクセス不可になる点です。企業にとって大きな機会損失につながる恐れがあるでしょう。
リスク低減
リスクの発生頻度や影響度を低減させる方法です。たとえばリスク回避のように外部とのネットワークを完全にシャットアウトすると、事業を継続することが困難なケースも多いでしょう。その場合は、代わりの対策を講じてリスクを最小限に抑えていく必要があります。
例としてはIPS(Intrusion Prevention System)・WAF(Web Application Firewall)などのセキュリティ装置の利用が挙げられます。インターネットとの接点に設置することで、外部からの不正アクセスといった脅威をブロックすることが可能です。特に通販サイトなどを運営している企業なら、一般ユーザーからのアクセスは維持しつつサービスを続けていけるでしょう。
ただし、攻撃を受けるリスクを完全になくせるわけではないので、低減にとどまります。
リスク移転
リスクを自分で負わずに他社に移す方法です。リスクを移転することで、セキュリティ事故が起きたときの経済的な損失などを軽減できます。たとえばサイバー保険。加入していれば、セキュリティ事故発生後に損害賠償金や訴訟費用を補償してもらえます。つまり、セキュリティ事故による経済的な損失リスクを、保険会社に移転していることになるのです。
リスク移転のデメリットは、すべてをリスク移転できるわけではない点です。たとえサイバー保険で補償できたとしても、企業への社会的な信用度は落ちる可能性があります。
「リスクを移転しても最終的な責任は自社にある」という意識をもつことが重要です。
すぐに実施すべき6つの情報セキュリティ対策
これから情報セキュリティ対策を始めたいと考えている企業に向けて、最初に実施すべき対策を紹介します。
1. OSやソフトウェアを常にアップデートする
OSやアプリケーションなどのソフトウェアは、時間が経つと不具合が発見されることがあります。放置していると、ウイルス対策ソフトを入れても感染したり、ウイルスメールが社内の人間に自動送信されたりする可能性があるのです。
ソフトウェアの自動アップデート機能の利用がおすすめ。修正プログラムの有無を定期的に確認し、自動的に適用してくれます。修正プログラムの適用を忘れることもなくなり、脆弱性を防げるでしょう。利用できる状態になると「アップデートの準備ができました」などのメッセージが表示されます。クリックして画面上の指示に従い操作してください。
2. ウイルス対策ソフト+セキュリティ装置を導入する
ウイルス対策ソフトを導入することで次のようなメリットがあります。
・スパムメールを自動的にごみ箱などに振り分け、悪質サイトにアクセスする可能性を防ぐ
・パソコンだけでなく外部メディアをスキャンし、マルウェア感染の可能性をチェック
・感染発覚した場合も悪意あるプログラムの駆除が可能
ソフトを選ぶときは、マルウェアからの保護性能が高いものがおすすめです。また24時間365日サポート体制が整っており、問題発生時も迅速に対応してもらえる製品がよいでしょう。
またUTM(Unified Threat Management)と呼ばれる、総合的に脅威を管理する装置を入れるとより効果的です。インターネットとの接点に導入すれば、ウイルスや不正アクセスなどのさまざまな脅威からシャットアウトします。システム担当者が少ないことが多い中小企業でも運用負荷を軽減できるでしょう。
3. パスワードを複雑化し使い回さない
パスワードは最低でも10桁以上にし、英数字や記号を含めましょう。辞書に載っている単語や「123、abc」など推測されやすい文字列は使わないでください。できる限り、複数のサービスで使い回さないことも重要です。
「定期的に変更すれば安全なのでは?」と思われる方もいるのではないでしょうか。しかし、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)のハンドブックでは、「定期的な変更よりは、使い回しのない固有なものを設定する」ことが推奨されています。頻繁に変えることでパスワードの構成がワンパターンになり、推測しやすい文字列になるほうが危険なのです。
4. データの共有設定を変更する
テレワークの推進によりファイル共有が必須となってきていますが、セキュリティ対策がおざなりになっているケースも多く見られます。
共有フォルダを使用している場合はアクセス権を設定しましょう。機密性の高いデータを閲覧できる人を限定することが重要です。ユーザーごとにアクセスできる範囲を変えたい場合は、フォルダの階層別に権限を設定してください。
オンラインストレージ(OneDrive、GoogleDrive、Dropboxなど)を使うなら、二段階認証機能があるサービスにしましょう。オンラインストレージサービスは基本的に高レベルなセキュリティ対策が施されていますが、不正アクセスの可能性はゼロではありません。
最新の脅威や手口の種類を知っておく
さまざまな情報源から情報を入手し、最新の脅威の動向や対策などの情報を得るようにしてください。定期的に収集する習慣をつけることが大切です。
たとえば、以下のようなものから入手できます。
・IPAなどのセキュリティ専門機関のWebサイト
・利用中の製品やサービスの提供者が行っている注意喚起
・官公庁やセキュリティ企業が公表するレポート
特にIPAが毎年公表する「情報セキュリティ10大脅威」をチェックするのがおすすめです。昨今の手口や、注意すべき脅威の情報がすぐにわかります。
データを暗号化する
重要情報を保管するために暗号化技術は欠かせません。
暗号化とは、符号やルールによって可読的な文字列情報を変換し、読み取れないようにする技術のことです。万が一暗号化された情報が外部に漏れても読み取りできないので、被害を抑えられるでしょう。
暗号化ソフトを導入する際は、「自社の課題を解決できる機能があるか」を軸に選ぶことをおすすめします。データベース・ファイル・メールなど、暗号化の範囲はさまざまです。暗号化したい対象をはっきりさせておきましょう。
企業が検討するべき情報セキュリティシステム
企業が検討するべき情報セキュリティシステムの種類をご紹介します。
認証システム
認証システムとはユーザーが正当かどうかをチェックし、アクセスの許可・拒否を行うシステムのことです。ID管理、SSO、多要素認証などがあります。
認証システムではサーバに本人を特定するためのデータが保持されており、認証を受けたいユーザーは自分が本人であるとわかる証拠を提出します。提出された証拠とサーバに保持されたデータが一致したら認証が許可される、という仕組みです。
たとえばSSO(シングルサインオン)を使うと、一度IDとパスワードで認証するだけで複数のアプリケーションやサービスにアクセスできます。サービスごとにログインし直す手間が省けるため、業務効率化にも役立つでしょう。
ネットワークセキュリティ
ネットワークセキュリティとは、情報資産を保護するためにサイバー攻撃を検知して防御する防衛策のことです。
もっとも代表的な製品がUTM(Unified Threat Management)です。UTMとは、ファイアウォールやアンチウイルス、アンチスパムといったセキュリティ対策機能を統合した製品になります。複数のセキュリティ対策が1台で実現、管理者の運用負荷を軽減できるのが大きなメリットです。
ほかにも不正侵入防御システム(IPS)や不正侵入検知システム(IDS)もあります。
IDSはインターネット上の通信を監視し、あらかじめ登録してある検出ルールに沿わない不正通信があった場合に管理者へ通知するシステムです。IPSはIDSの機能に加えて不正や異常な通信をブロックできるため、よりスピーディーな対処が可能になります。
セキュリティ運用
セキュリティ運用とは、セキュリティ機器の導入後に不正アクセスやサーバの脆弱性などを適切に監視し、セキュリティ対策を維持し続けていくことです。
機器を導入したにもかかわらず、ウイルスの標的となってしまった被害は多くあります。入り口対策を徹底したうえで、侵入されたときに早期発見につなげるような運用体制が求められるのです。
たとえばSIEM(Security Information and Event Management)は、社内に設置したセキュリティ機器などのログを収集・蓄積し、リアルタイムに分析するシステム。未知の脅威や怪しいアクセスを検知できます。
また、複数の危機から集めたイベントログを相関分析できるのも大きなメリットです。「利用時間外の時間帯に入室ログがあった」「システムへのログインがあった」などのイベントを掛け合わせ、怪しい挙動を見つけ出してくれます。
エンドポイントセキュリティ
エンドポイントセキュリティとは、ネットワークに接続されているパソコンやサーバ、スマートフォン、タブレットなどの端末機器に保存している情報を、サイバー攻撃から保護するためのセキュリティ対策のことです。
テレワークの増加により以下のようなケースが増えたため、重要性が高まっています。
・マルウェアが仕込まれたUSBメモリを使用してしまった
・感染しているノートパソコンからネットワーク接続し、ほかのデバイスに被害が拡大した
たとえばEDR(Endpoint Detection and Response)は、エンドポイント端末(利用者の端末)向けのセキュリティソリューションのこと。端末を徹底的に監視し、侵入してきたサイバー攻撃を検出します。端末の隔離やシステム停止も行えるので、重要システムへの影響を最小限に抑えることが可能です。
シンクライアントシステムで対策を強化しよう
シンクライアントとは、端末自体にデータやアプリケーションをインストールせず、サーバ側で一括管理するシステムのことです。クライアント端末にはデータが保管されず、利用機能も制限されます。OSやアプリケーションをサーバ側でまとめて管理しているので、利用者端末が分散することもありません。有効なサイバー攻撃対策といえるでしょう。
クラウド・Webセキュリティ
クラウド・WebセキュリティにはSWG(Secure Web Gateway)、WAF(Web Application Firewall)、CASB(Cloud Access Security Broker)などがあります。たとえばSWGは、URLフィルタリング、アンチウイルス、サンドボックスなど、複数のセキュリティ機能を搭載したクラウド型のプロキシサービスのことです。
オンプレミス型のプロキシだと、社内ネットワークから特定のWebサイトへのアクセス制御など、リスクへの対応範囲が狭くなる傾向があるでしょう。さまざまなサイバー攻撃からプロキシだけで情報を保護するのは困難です。クラウド型のSWGを利用することで、アクセス元のデバイスなどを意識せずにユーザーを制御することが可能になります。
情報セキュリティ関連の認証制度
情報セキュリティに関する認証制度の内容や、取得するメリットについて解説します。
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)とは、会社が持っている情報がどのようなものかを整理し、起こり得るリスクに対応する仕組みのことです。技術的な対策だけでなく、従業員の教育や訓練、組織体制の整備も含まれます。
次の認証制度の基準を満たすことで、「情報を管理する仕組みができている」といえるでしょう。社外に、情報セキュリティ対策をしっかり行っている企業だとアピールできます。
制度①:ISMS認証
ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証とは、「企業のISMSが適切に運用・管理されているか」をISMS認証機関が審査して証明することです。次のような目的があります。
・日本の情報セキュリティ全体の向上に貢献する
・外国からも信頼を得られる情報セキュリティレベルを達成する
ISMS認証を取得するには、ISMS認証機関に申請して審査を受ける必要があります。取得するメリットは、社内のセキュリティ向上をめざせる点です。また顧客や取引先に対し、「情報セキュリティ対策を徹底しており、継続的に改善している」と客観的に示すことができます。
制度②:プライバシーマーク
プライバシーマークとは、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が個人情報を適切に保護している国内の事業者を評価し、プライバシーマークの使用を認める制度です。個人の情報管理を対象としているため、通販サイトやスマホアプリなど一般ユーザー向けの事業を展開している企業は取得して損はないでしょう。
プライバシーマークを取得するには、「個人情報保護マネジメントシステムに基づいて適切に個人情報が扱われていること」など、複数の条件を満たす必要があります。
取得するメリットは、取引先や消費者に対して信頼性の高い事業者であることをアピールできる点。また社内の個人情報に対する意識も高まり、情報漏えいなどが発生しにくい体制を構築していけるでしょう。
まとめ
情報セキュリティ対策は構築して終わりではなく、時代や最新の手口に合わせて検討を重ね、アップデートしていくことが重要です。一度セキュリティ事故を起こすと社会的な信用を失い、会社に大きな損害が出てしまうでしょう。
まずは脅威の種類やセキュリティ対策で意識すべき要素を知ったうえで、自社に適したセキュリティシステムを導入する必要があります。さらに認証制度の取得も検討し、取引先や消費者からの信頼性を高めることも意識していきましょう。
投稿 情報セキュリティの初歩。脅威の事例や対策方法を詳しく解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 名刺管理ソフトとは? 法人・個人でおすすめの名刺管理ソフトを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>名刺管理ソフトとは?
スマートフォンやスキャナーから名刺を取り込み、データ化することで一元管理するツールのことを「名刺管理ソフト」といいます。散らばりやすい名刺をデータとして1箇所に集約しておくことができるため、社内での共有もしやすいのが特徴です。製品によっては、名刺交換をした取引先で人事異動があった場合に知らせてくれたり、顧客情報管理システム(CRM)や営業支援システム(SFA)などと連携することにより商談管理ができたりします。
名刺管理ソフトの基本機能
名刺管理ツールには主に以下の4つの基本機能があります。
名刺情報を読み取り
カメラやスキャナーを使用して、名刺情報を読み取ることが可能。OCRを使用して読み取った情報が文字データとして保存され、データは会社名や部署、名前や電話番号などの適切な情報に細かく分類されます。
名刺情報をデータ化
読み取った情報は、名刺管理ソフト上でデータとして保管されます。CSV形式やExcelなどのファイルを名刺管理ソフトにインポートすることも可能です。
マルチデバイス対応
クラウド型の名刺管理ソフトであれば、名刺の情報はスマートフォンやパソコンなどで検索し、閲覧することもできるます。いつどこにいても名刺管理ができることも大きなポイントです。
名刺情報の検索
データ化された名刺の情報は、名刺管理ソフト上で簡単に検索できます。また検索条件を指定すると、目的の名刺情報をすぐに探し出すことも可能です。
名刺管理ソフト導入のメリットとデメリット
名刺管理ソフト導入のメリット
・営業活動の効率化
名刺の一元管理とデータベース化が容易にできるため、検索にも手間がかかりません。もちろん名刺を保管する場所も必要ないので、スマートフォンアプリに対応していれば社外にいても閲覧可能。そのため、名刺データを社内で共有することで営業効率を上昇させ、商談の成功率を高めることにもつながります。
・登録データの二次利用が可能
名刺情報を登録すれば、蓄積データをCSV形式などで抽出し、ダイレクトメール(DM)やメールマガジン、年賀状などの配信に活用するなど登録データの二次利用を行うことができます。
・見込み顧客を一元管理
メールやウェブサイトを通して見込み顧客の情報を獲得し、一元管理することで自社に有益とされる見込み顧客を抽出可能。また、名刺管理ソフトによっては、見込み顧客の受注確度を含めリード名簿を制作してくれるツールも存在します。
・顧客情報入力の効率化
名刺管理ソフトの活用で入力の手間が解消されることから、入力ミスも確実に減少させることができます。
名刺管理ソフト導入のデメリット
・導入コストがかかる
活用するソフトにもよりますが、名刺管理ソフトを導入する際にはそれなりのコストが発生します。後で後悔しないためにも、活用したい名刺管理ソフトがある場合には費用の確認もしっかりと行うことが大切です。
・データ化に工数がかかる
名刺管理ソフトは名刺のデータ化に工数を費やしたり、ほかのシステムにデータを転記したりする必要があります。ただし、事前に文字認識(OCR)機能や入力代行を行ったり、連携機能を備えた名刺管理ソフトを利用したりすれば、かかる工数を減らすことができます。
・顧客管理システムとの重複
名刺管理ソフトの選び方を間違えてしまうと、名刺管理ソフトと顧客管理システムとで情報が重複したり、併用によって余計な手間がかかったりすることがあります。名刺管理ソフトを選ぶ際には、事前にソフトの詳細をよく確認しましょう。
名刺管理ソフトの活用事例
名刺管理ソフトを導入したことで得られるメリットについて、ITreviewに集まったレビューをもとに活用事例を紹介します。
今まで煩雑になっていた名刺管理が簡単に
「1ヶ月で50枚ほど名刺交換をするのですが、今までは社内に持ち帰ってからファイリングして必要になったら確認するというような状況だったが、全ての名刺をクラウドで管理でき、社内外問わず確認も出来る点はセキュリティ面でみても助かっています。新規営業を進めていくにあたって、先方担当がどんな役職で名前が何なのかが事前にわかるので、アプローチがかけやすくなった」
▼利用サービス:Sansan
▼企業名:株式会社ネオキャリア ▼従業員規模:1000人以上 ▼業種:人材
https://www.itreview.jp/products/sansan/reviews/50919
交換した名刺が未来につながるようになりました
「交換した名刺をスキャンすることで企業名、氏名、連作先などの情報がクラウド上で管理できる。それを会社でシェアできることです。SANSANを導入するまでは、お客様や協力会社様のご連絡先がすぐに取り出せず「A社さんの携帯番号知ってる人いる?」と社内の人に聞きまわっていました。しかし、SANSANを導入してからは、社名を検索するだけで該当の連絡先がすぐに手に入り連絡もすぐできて仕事スピードが上がりました」
https://www.itreview.jp/products/sansan/reviews/32616
▼利用サービス:Sansan
▼企業名:株式会社関通 ▼従業員規模:300-1000人未満 ▼業種:倉庫
精度の高い名刺管理サービスが無料で使用できるのはありがたい
「企業と企業のつながりというよりもその中の個人と個人のつながりを大切にしていきたい場合に使用したいアプリ。いくつも名刺交換を行い、今まで紙ベースで保管していたものがいつでも持ち歩ける携帯に全てを保管しておけるところはとても強みだと思う。いつどこでも対象の人に連絡することができる。紙ベースで保管していた名刺を全て携帯で持ち運べるようになったところ、また他のサービスと違い読み取り精度が高く修正の頻度が少ないところ」
▼利用サービス:Eight
▼企業名:株式会社エンラボ ▼従業員規模:20-50人未満 ▼業種:介護・福祉
https://www.itreview.jp/products/eight/reviews/79844
シンプル、だがそこがいい名刺管理サービス
「運営はLINE。搭載機能はこの分野ですでに先行している大手よりもシンプルで、名刺を両面スキャンして保存、個人用に保管するか他ユーザーと共有するか指定する…程度しかない。とはいえ必要十分。ソーシャル接続機能も最低限で、オプトインしない限りまったく働かない。そこが顧客の個人情報を秘匿できるという安心感につながっていて逆にありがたい」
▼利用サービス:myBridge
▼企業名:株式会社アクセスビルダー ▼従業員規模:20人未満 ▼業種:情報通信・インターネット
https://www.itreview.jp/products/mybridge/reviews/42717
名刺管理ソフト導入のポイント
名刺管理ソフトを導入・活用する際には、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
1. セキュリティ対策を事前に確認
名刺には企業名や部署名・名前や連絡先などの多くの個人情報が記載されています。外部への情報漏えいといった重大トラブルを決して引き起こさないためにも、名刺管理ソフトのセキュリティ対策は万全である必要があります。事前にセキュリティ対策はきちんとチェックしておきましょう。
2. スマートフォン・パソコン・他サービスとの連携機能を確認
CRMやSFAを導入している場合、それらのシステムとの連携をチェックすることも重要です。システム連携を行うと、顧客情報の獲得やアプローチの履歴、顧客へのサポート内容などの情報を一元管理できます。
3. 名刺情報の登録の正確性とスピードをチェック
名刺管理ソフトを導入する際は、その名刺管理ソフトの読み取り精度が高く、素早く読み込んでくれるソフトであるかどうか、事前にきちんと確認をしておきましょう。読み取り精度が90~95%、読み取り速度が1枚当たり3〜5秒程度の名刺管理ソフトであれば間違いないでしょう。
4. 名刺情報は定期的に入力、メンテナンス
名刺管理ソフトの効果を最大化し営業効率を高めるためにも、名刺情報は定期的に入力を行い、メンテナンスをするよう心がけましょう。名刺管理ソフトの入力とメンテナンスを含む新しい業務工程やルールの確定を実行することにより、現場での浸透率を上昇させることにもつながります。
名刺管理ソフトの業界マップ
名刺管理ソフトのユーザーからの評価を知るには、ITreview Gridが便利です。ITreview Gridは、ITreviewに集まったユーザーのレビューをもとに生成された4象限の満足度マップです。このマップでは、顧客満足度と市場での認知度を掛け合わせた結果が、4象限上でのポジショニングとして確認できます。
おすすめの名刺管理ソフト
実際に、ビジネスチャット活用されている企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめのビジネスチャットを紹介します。
実際に名刺管理ソフトを使った企業の方々のレビューが多い製品を中心に、おすすめの名刺管理ソフトを紹介します。
(2021年11月23日時点のレビューが多い順に紹介しています)
<法人向け名刺管理ツール>
Sansan
法人向けに開発された名刺管理ソフトである「Sansan」は、クラウド型サービスであり、名刺をスキャンあるいはスマートフォンで撮るだけで自動的に人脈データベースを作成します。スキャンされた名刺データは組織全体で共有でき、顧客との関係づくりにも生かすことができます。さまざまな業界で導入されており、大企業から中小企業、官公庁など7000を超える組織に広く導入されています。
Eight企業向けプレミアム

「Eight」の有料プランとなるこのソフトは、名刺情報をデータ化して、ユーザーのもつ名刺情報を共有・一元管理することが可能です。企業資産として活用することもできるため、利用価値が高いといえます。
Knowledge Suite
営業日報の入力のみで商談情報などを一元管理でき、ユーザー数無制限で活用可能なクラウド型オールインワンビジネスアプリケーションです。営業報告と顧客情報のみで営業工程を視覚化し、PDCAサイクルの高速化を図っています。グループウェアとCRM・SFAが連携しており、テレワークにも対応するなど自社の業務内容に見合う項目のカスタマイズもできます。
<個人向け名刺管理ツール>
Eight
スマートフォンで名刺を撮影すると、名刺データを容易に管理できます。AIを活用し、トップレベルの開発技術でデータ化を行い、生産的で正確な名刺管理を支援。名刺交換は紙の名刺に限ることなく、デジタル上でも交換が可能です。いくつもの名刺を同時に撮ることもできるクイックスキャン機能なども搭載されています。基本機能は無料のため、低価格で活用をしたいという企業はもちろん、個人にもうれしい名刺管理ソフトです。
myBridge

OCRとオペレーターによる手入力で、正しい名刺情報のデータ化を行えます。いつどこにいても必要な名刺情報の検索が可能で、スマートフォン着信時には、名刺情報がすぐ表示されます。社内で共有可能な共有名刺帳や無料名刺スキャン代行サービスなどがあり、個人情報の暗号化などセキュリティ対策も万全です。すべての機能が無料で利用可能となっています。
ITreviewではその他の名刺管理ソフトも紹介しており、紹介ページでは製品ごとで比較をしながら導入ツールを検討することができます。
まとめ
名刺管理ソフトは、名刺を一元管理して企業資産として活用するために必要不可欠のツールです。個人・法人ともにCRMやSFAと連携をして商談管理が可能なソフトなどもあり、営業活動の効率化やマーケティングに生かすことのできる製品が多いのも、名刺管理ソフトの特徴です。
どの名刺管理ソフトを導入するかでお悩みの方や、ほかのソフトとの比較をしてみたいという方は、ぜひ本記事を参考に最適なソフト選びを実現しましょう。
投稿 名刺管理ソフトとは? 法人・個人でおすすめの名刺管理ソフトを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 オンラインストレージMEGAとは?料金や評判、使い方を徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>オンラインストレージをビジネスにおいて使うなら、容量を気にせずに使いたいもの。さらに、誰でも使いやすい操作性やファイル共有機能、権限管理機能など、オンラインストレージとして必要な機能も欲しいところでしょう。
最近では多彩なオンラインストレージが提供されています。その中でもMEGAは50GB(※注1)ものデータ容量を無料で提供していることから、とても魅力的に感じます。しかし、実際のところビジネスに適したオンラインストレージなのか気になるところです。
そこで本記事では、オンラインストレージMEGAの特徴や使い方、評判について解説していきます。
※注1) 15GB(アカウント取得時) + 35GB(30日間限定 初回登録ボーナス)
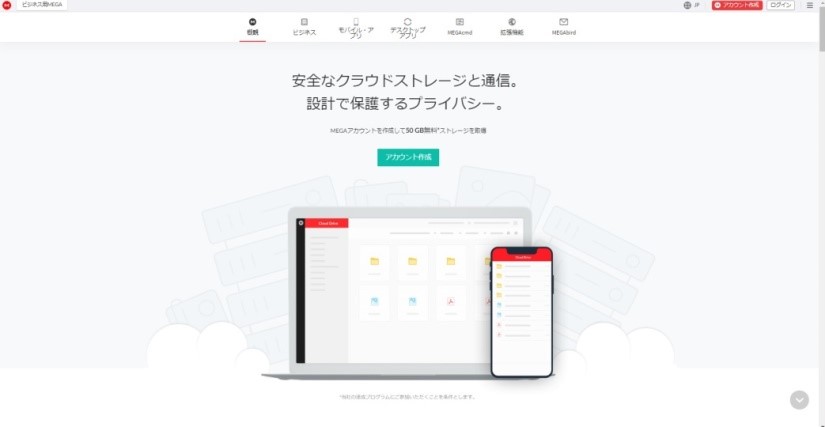
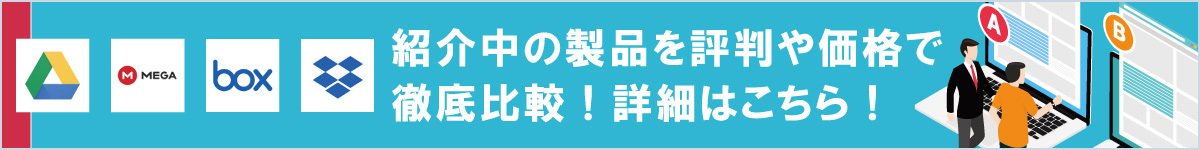
オンラインストレージMEGAとは
ニュージーランドに本社を持つMega Limited が提供するオンラインストレージサービスです。1億6千万人もの登録者数(2019年12月現在)を誇り、日本語をはじめ多くの言語に対応しています。

オンラインストレージMEGAの5つの特徴
さまざまな機能を持つMEGA。その中でも利用者側からの視点も含めて、気になる5つの特徴についてご紹介します。
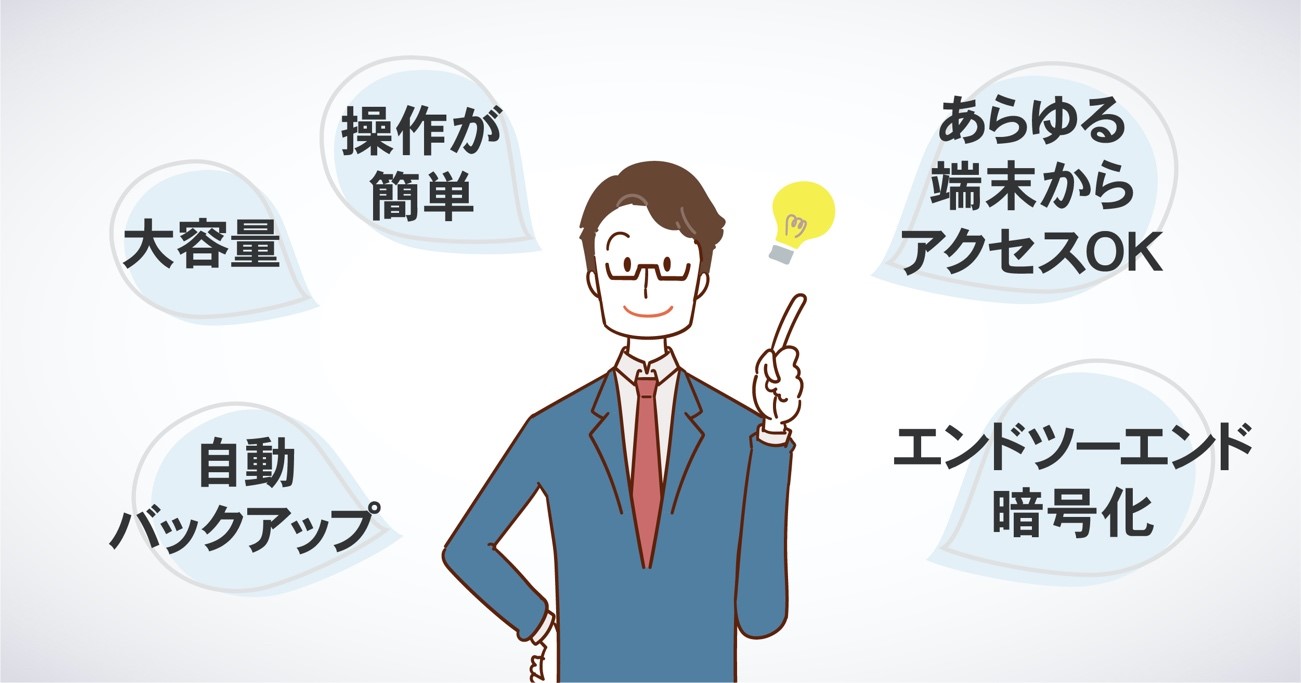
1. 大容量プランが多い
各プランの特徴として容量が50GBから無制限までと「大容量プラン」が多いことです。無料プランでありながら50GB(※1)が利用できる他、プロ・ライトなら400GB、プロ1なら2TB、プロⅡなら8TB、プロⅢなら16TB、ビジネスプランなら無制限(※2)で利用できます。
※2 最小ユーザー3人からの契約条件。
2. 操作が簡単
わかりやすくて、シンプルな画面です。ファイルをアップロード&ダウンロードする場合、どちらもドラッグ&ドロップでOK。また、ファイル共有の設定においても難しい操作がなく、社内外の関係者との共同作業もスムーズに行えます。
3. あらゆる端末からアクセスが可能
Windows、Mac、Linuxに対応したデスクトップアプリやAndroid やiPhoneにも対応したモバイルアプリが用意されています。インターネットに接続できる環境であれば、いつでもどこからでも利用できます。
4. 自動バックアップ
Android やiPhone で撮影した動画や写真は、MEGAアプリをインストールしておけば、自動で同期をしてくれます。大切なファイルを保存し忘れても困ることはありません。
5. 「エンドツーエンド暗号化」を採用
MEGAで扱うファイルは、すべてエンドツーエンド暗号化(英語ではE2EEと表記される。利用者のみが鍵を持つことで、第三者が通信内容を盗聴できないようにする仕組み)されるので、安心してファイルのやりとりができます。万が一、データが盗まれたとしても、暗号化されているので情報漏えいのリスクを軽減できます。
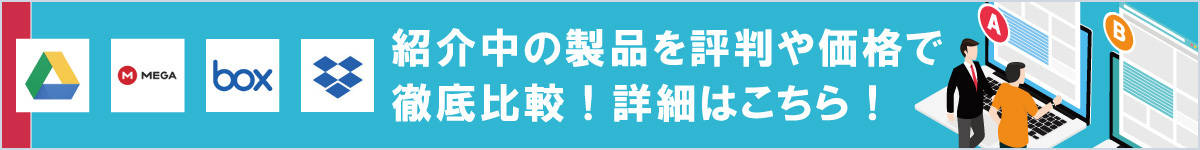
どんな料金プランがあるのか?

◎無料プランの場合、15GBまで利用できます(※注1)。
◎プロ・ライトの場合、4.99ユーロ/月 (605円)。400GBまで利用可能。
◎プロ1の場合、9.99ユーロ/月 (1,211円)で2TBまで利用可能。
◎プロⅡの場合、19.99ユーロ/月 (2,424円)で8TBまで利用可能。
◎プロⅢの場合、29.99ユーロ/月 (3,637円)で16TBまで利用可能。
※料金プラン、価格は、2019年12月20日時点。
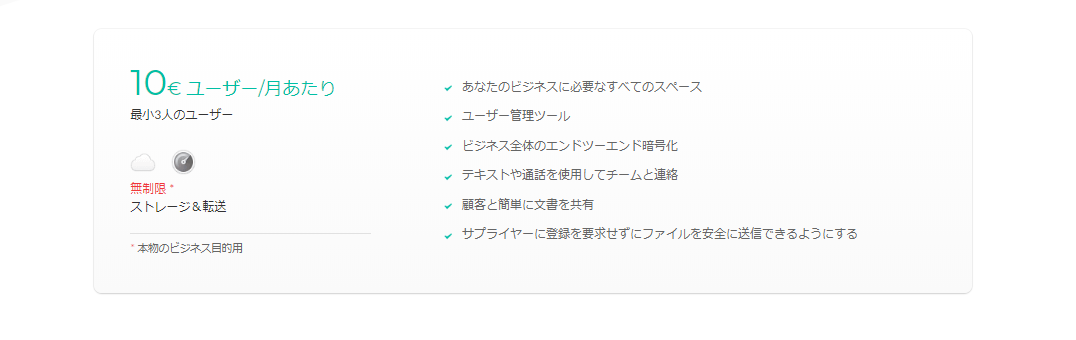
◎ビジネスプランの場合、10ユーロ/月 (約1,212円)で容量無制限のストレージを利用できます。ただし、最小3人のユーザーの使用が契約条件となっています。
※1ユーロ121.2円(2019年12月20日時点のレート)で計算。
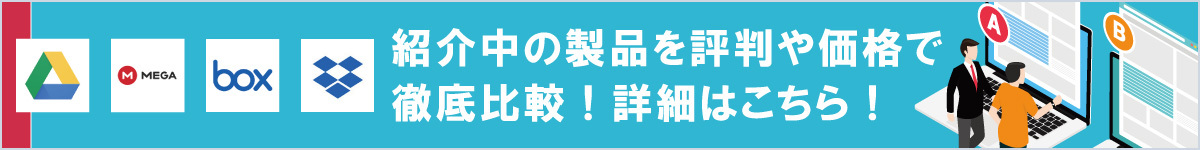
どのような使い方ができるのか?
PCやタブレット、スマートフォンなど複数のデバイスに対応しているので、データをMEGAに集めておくと、どの端末からでもアクセスできます。
ファイルはもちろん、フォルダレベルで共有できるため、共有リンクを発行し相手方にリンクを送るだけで、サイズが大きめの文書ファイルのやりとりなどもできます。
なお、連絡したい相手のメールアドレスを登録しておくと、相手がMEGAアカウントを持っていれば、その時点でファイル共有が成立します。相手にMEGAアカウントがない場合には、MEGAに参加するための招待メールが自動に送信されます。
もし、文書ファイルのやりとりで詳細な設定をしたい場合は、「プロ」プランを契約すれば、ユーザー管理機能としてパスワードの保護や公開ファイル用の有効期限の設定などもできます。 オンラインストレージサービスでありながらチャット機能(MEGAchat)も装備。このチャット機能を使うと、メッセージの交換だけではなく、ファイルの共有、音声通話(グループ通話含むやビデオ通話も可能。例えば、プロジェクトチームの音声会議に利用すれば、ファイル共有しながらタイムリーな情報交換ができそうです。
◎気を付けたいポイント
・サイト内の解説など、日本語の表現がわかりにくい箇所があります。
・無料プランは、MEGAに3カ月以上アクセスをしなかった場合、アカウントが削除されます。普段使いをするなら特に気にする必要はありませんが、たまにしか使用しない場合は定期的にログインすることをおすすめします。
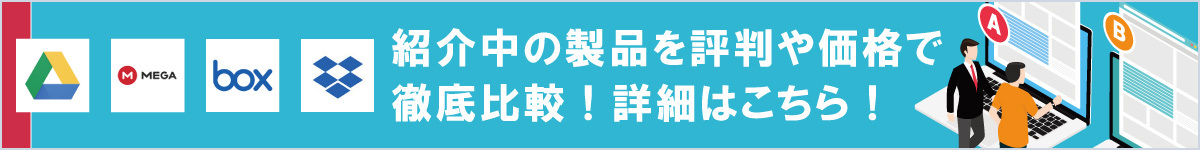
実際にMEGAを利用しているユーザーの評判は?
ITreviewに投稿されたMEGAユーザーのレビューをご紹介します。
なんといっても他のオンラインストレージと比べ、50GBもの無料ストレージ領域を使用することができます。大量の動画や大きなファイルを保管しておくのに大変重宝しています。共有したい相手に共有リンクを生成することもできるので、データの共有もはかどります。
(経営・経営企画職/情報通信・インターネット業)
https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/11152
容量・速度とともに十分用意されており、ストレージ用途としてありがたいスペック。容量無制限が他社類似サービスに比べてお安い。ソースコードの開示といった試みもおもしろいし、支持したい。(法務・知財・渉外職/会計、税務、法務、労務業)
https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/18884
50Gの大容量ストレージが無料で提供されています。
https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/13619
後述する通り、継続的に使うには難ありですが、ちょっとこの大きなファイルは特別に短期間だけ共有したり配布したいな、メインのクラウドストレージには影響を及ぼしたくない、分離して管理したい、というユースケースでは重宝するでしょう。(その他専門職/ソフトウェア・SI業)
日本語訳がすこし変な部分があります。「フォルダ8こ」など普通の日本企業ならありえないようなちょっとした変な表記があります。ただ、大半の部分に理解不能な日本語はないのでそこまで問題はないと思いますが気になる人は気になるかも。そのせいか50GBが期間限定ということに全然気づきませんでした。普通の日本企業であれば十分周知させているはずと思いましたね。(経営・経営企画職/情報通信・インターネット業)
https://www.itreview.jp/products/mega/reviews/31003
上記以外にも、実際にMEGAを利用しているユーザーの方々から評価レビューが投稿されています。ぜひ、リアルな声を一読されることをおすすめします。
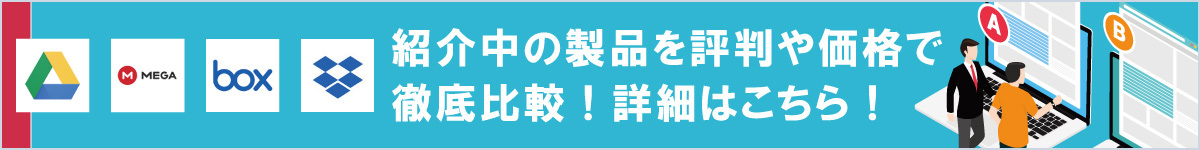
MEGAはとにかく大容量
無料でも50GB(※注1)と容量が大きく、機能がシンプルなMEGA。ファイル共有が簡単で、エンドツーエンド暗号化で保護されている等、ビジネス利用にうれしい機能が搭載されています。そうはいっても実際に利用してみて、使い勝手を実感してみたいというのが正直なところでしょう。ただし、初回登録時の35GB分は、30日間限定ボーナスなのでご注意ください。30日後には通常の15GBの提供となりますが、まずは、MEGAの「無料プラン」に登録して試してみてはいかがでしょうか。
投稿 オンラインストレージMEGAとは?料金や評判、使い方を徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 人気のMAツール11選|マーケティングオートメーションツールの特徴や機能を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>リードの情報管理や、営業プロセスの支援が必要となる現場において活用されていますが、ツールによって注力している点が異なるため、競合の有無や商品の特長をつかんだ上で適切に選びたいところです。
本記事では、企業への導入実績の多い代表的なMAツールを厳選しました。実際に使用している担当者のレビューを交えながら、ツールの特徴や強み、機能解説を行います。自社の課題と照らし合わせ、最適なMAツールを見つけてください。
マーケティングオートメーション(MA)は業務を自動化し、見込み客への適切なアプローチを可能にする

マーケティングオートメーション(MA)とは、従来は手作業で行なっていたリード獲得〜育成〜分類のプロセスを自動化し、適切なタイミングで適切なアプローチを可能にすることで、見込み顧客の自社製品への関心や購入意欲を効率よく高めることです。
マーケターの業務の効率化が図れると共に、受注確度の高いリードを抽出できるので、営業部門のリソースを無駄なく、適切に配分を可能にします。「リードをうまく可視化できていない」「営業活動が成約に結びつかない」といった課題を抱えている企業は、MAツール導入を検討すると良いでしょう。
しかしMAツールは、何を導入しても良いという訳ではありません。それぞれのツールで、搭載している機能が異なるので、自社の取り扱う製品やサービスによって適切なものを選ぶ必要があります。
MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方
MAツールの選び方

MAツールと一言でいっても、ベンダーの提供しているツールごとに特色があります。
自社に適したMAツールを選ぶためにも、以下の点を確認するようにしましょう。
- BtoB向けとBtoC向けどちらに向いているか
- CRMなどのシステムと連携できるか
- 幅広いチャネルに対応しているか
- サポート体制が充実しているか
BtoB向けとBtoC向けどちらに向いているか
自社のサービスや製品が「BtoB向け」「BtoC向け」なのかで選ぶべきMAツールが異なってきます。
BtoB向けのMAツールは、一元管理できるリードの数が1万件程度なのに対して、BtoC向けのMAツールは、10万件程度を管理できます。一般的に取り扱うリード数の多いBtoC向けのサービスや製品を展開している企業は、管理ができるリード数に着目すると良いでしょう。
また、BtoB向けのMAツールには、セミナー・イベント等への集客機能や名刺管理機能が実装されているツールもあります。オンラインのみならず、オフラインでのリード獲得を実施・検討している企業は、これらの機能が備わっているMAツールを選定しましょう。
CRMなどのシステムと連携できるか
現代のマーケティングでは、自社製品を利用・購入した顧客に対して、いかにリピートやファン化を促進できるかが重要になってきます。そのため、CRM(顧客関係管理)ツールと相互に連携できるかを確認する必要があります。
MAツールの中には、自社のCRMツールと連携できるものや、サードパーティのCRMツールと連携できるものが展開されています。
幅広いチャネルに対応しているか
メール配信に限らず幅広いチャネルでのアプローチに対応しているかを確認しておく必要があります。
最近では、LINEやFacebookといったSNSとの連携が可能なMAツールも増えています。従来のメルマガやWebコンテンツではアプローチできなかった層にも、サービスや製品を訴求ができます。
サポート体制が充実しているか
MAツールを初めて導入する場合は、サポート体制が充実しているかを確認しましょう。導入初期には、正確にデータを計測するために設計や各種設定を行う必要があります。
ベンダーによっては、24時間365日対応のオンラインサポートや導入・運用支援のサポートを実施しています。有償になる場合もあるので、事前に確認が必要です。
代表的なMAツール11選
1. Marketo Engage(マルケト エンゲージ)

(参照元:https://jp.marketo.com/)
「BtoB」「BtoC」問わずに、全世界で5,000社以上の導入実績があるアメリカ発のMAツール「Marketo Engage(マルケト エンゲージ)」。日本国内でも大企業から中小企業・スタートアップまで業界や業種を問わずに導入されており、MAツール導入の第一候補とも言えるツールです。
ユーザーへのメール配信以外にも社内のオペレーション改善やメール以外のアクションを簡単に設定できるので、組織のオペーレーション改善にも有効です。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | FUJIFILM(製造・化学/電子) ロート製薬(製薬) LINE(IT・サービス) PASONA(人材サービス) Panasonic(製造・電気機器)など |
| 他システムとの連携 | ◯(CRMとの連携) |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | 無料と有料のサポート体制が充実 |
| 月額料金 | 個別に見積もり |
| 主な機能 | マーケティングオートメーション、メール、モバイルマーケティング、ソーシャル、デジタル広告、ウェブ、アカウントベースドマーケティング、マーケティングアナリティクス、プレディレクティブコンテンツ、Marketo Sales Connect |
長期的な顧客との関係性を気づく統合型プラットフォーム

(参照元:https://jp.marketo.com/company/)
顧客とのエンゲージメント向上を目的に設計されており、見込み客の認知から自社製品の購入、実際に製品を購入した顧客がファン化や再購入に至るまでの長期的な関係構築が可能な統合型のプラットフォームになっています。
機能の網羅性が高いことや外部システムとの連携がしやすいことから、一貫性を持ったマーケティング施策を打ち出すことができるのが特長です。
2. SATORI

(参照元:https://satori.marketing/ )
「あなたのマーケティング活動を一歩先へ」をミッションとしている、株式会社SATORIが提供している国産のMAツールです。900社以上の導入実績があり、国産ならではの迅速なサポート体制が整っています。
また、匿名リードのデータ管理や蓄積も可能な「アンノウンマーケティング機能」を搭載し、実名リード獲得への施策を打てるという特長があります。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | USEN(情報・通信) ユニ・チャーム(化学) アデランス(ビューティ・ヘルス) ログミー(IT・サービス) オノヤ(リフォーム・不動産)など |
| 他システムとの連携 | kintone、Salesforce Sales Cloudなど |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・広告) |
| サポート体制 | オンラインサポートデスクや無料の利活用セミナーを用意 |
| 月額料金 | 初期費用:30万円~ 月額費用:14.8万円~ |
| 主な機能 | リード管理機能、リードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーション、オートメーション、レポート、データ提供(オプション)、独自ドメイン(オプション) |
初心者マーケターにおすすめのシンプルで直感的な操作性

(参照元:https://satori.marketing/features/)
ウェブサイトに計測タグを埋め込むだけで即日からの運用が可能。日本語のインターフェースで視認性の高いグラフが表示させるので、初めてMAツールを運用するマーケターでも操作や効果測定がしやすいのが魅力です。
また、セミナーや個別説明会の実施や導入ユーザーのコミュニティを形成するなど円滑な運用へのサポート体制も充実しています。
3. b→dash(ビーダッシュ)

(参照元:https://bdash-marketing.com/)
業界シェアNo.1を誇り、業種業界を問わずに大企業からベンチャー企業まで多数の導入実績を持つ統合型のMAツールです。非常に多くの機能を搭載しているのが特徴で、データ統合やメール配信だけでなくWeb接客やアプリPUSHといった機能も含まれています。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | 阪急百貨店(百貨店) KIRIN(飲料) 楽天イーグルス(スポーツ) クレディセゾン(金融) UNDER ARMOUR(衣料品)など |
| 他システムとの連携 | ― |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | 運用サポートあり |
| 月額料金 | ライトプラン:5万円/月 スタンダードプラン:要相談 |
| 主な機能 | データパレット、データ統合(CDP)、メール/MA、Web接客、BI、LINE連携、広告連携、SMS配信、レコメンド、CMS(フォーム)、CRM、Push通知 |
マーケティングに必要な機能を全て網羅したAll in Oneツール

(参照元:https://bdash-marketing.com/)
LINE連携やSMS、アプリPUSHといった多様なチャネルで見込み客へのアプローチが可能。アプリやWebサイトに訪れたユーザーに対して、デモグラフィックデータや行動情報に基づいたクーポン配布や告知などWeb接客機能も備えています。
また、自社製品やサービスの利用購入後の顧客との関係性を管理するCRM機能も搭載。長期的な視点で顧客ロイヤリティを高める施策を実行することもできます。
4. SHANON MARKETING PLATFORM

(参照元:https://www.shanon.co.jp/products/)
デジタルとアナログの顧客データを統合管理できる国産MAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」。国内の導入実績は900社以上、キャンペーン実績は22万件以上を誇ります。オンラインのリード管理だけでなく、オフラインが開催されるイベントやセミナーの管理に関する機能も充実しているのが特長です。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | SB C&S NTTソフトウェア NTTコミュニケーションズ 野村総合研究所 時事通信社など |
| タイプ | 統合型 |
| 他システムとの連携 | ◯ |
| サポート体制 | 提案から設定、コンサルティングまでトータルサポートが可能 |
| 月額料金 | ― |
| 主な機能 | リード管理、ランディングページ/WEBフォーム、セミナー管理、イベント管理、ソーシャルマーケティング、キャンペーンマネジメント、Webトラッキング、シャノンコネクト |
イベント・セミナー運営に関する煩雑な作業を効率化

(参照元:https://www.shanon.co.jp/products/event/)
実名でのリード獲得に効果的なオフラインでのイベント開催やセミナー運営の効率化をはかることによって、作業時間を約50%削減できます。また未申込者に対してフォローやリマインドを行うことで、集客力のアップも期待できます。
5. Synergy!

(参照元:https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/)
「伝えたいメッセージを、顧客にきちんと届けるために」をコンセプトとした、最適な顧客管理を行うCRMシステムです。正確にはMAツールではありませんが、メール配信やLINE連携・フォーム作成などの機能と組み合わせて使用すれば、マーケティング活動の効率化につながります。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | 阪急阪神不動産(不動産) ブラザー(電機メーカー) 仙台銀行(金融) ヤクルトスワローズ(スポーツ)など |
| 他システムとの連携 | - |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | 活用支援サービスあり |
| 月額料金 | 利用機能によって異なる |
| 主な機能 | データベース、フォーム、アンケート、メール配信、LINEへの配信、広告連携、Web |
安全・安心の最新セキュリティー

(参照元:https://www.synergy-marketing.co.jp/cloud/synergy/)
IDとパスワードを入力するだけでアクセス可能な一般的なMAツールと異なり、クライアント証明書(デジタル証明書)をインストールしたPCからのみログインができる設計になっています。第3者のなりすましなど不正アクセスを防げます。
6. Probance

(参照元:https://www.probance.jp/ )
株式会社ブレインパッドが提供するBtoC事業向けのMAツール「Probance(プロバンス)」。強みは、AI(機械学習)を活用し、顧客のニーズを予測した的確なコミュニケーションを実行できることです。
| 向いている形態 | B to C |
|---|---|
| 導入実績 | OZ mall(ITサービス) マイナビ転職(IT・人材) クラウドワークス(ITサービス) WOWWOW(放送)など |
| 他システムとの連携 | ― |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | 活用支援サービスあり |
| 月額料金 | スタートプラン:180,000円〜 プロ:375,000円〜 |
| 主な機能 | データベース、フォーム、アンケート、メール配信、LINEへの配信、広告連携、Web |
AIが膨大なデータを分析し、顧客行動を予測
AIによる顧客データの分析を基に行動を予想することにより、顧客にとって心地良いアプローチが可能となり、新規顧客の獲得やリピーターの育成、休眠顧客の掘り起こしなどをサポートします。
顧客と持続的に良好な関係を築きたい企業や、エンゲージメントの構築によるリピーター獲得を目指す企業に適しています。
7. Salesforce Pardot

(参照元:https://www.salesforce.com/jp/products/pardot/overview/)
「SFA(営業支援システム)」や「CRM(顧客関係管理)」において世界トップシェアを誇る米国のセールスフォースが提供するクラウド型MAツール。同社のSFAシステムである「Sales Cloud」とシームレスに連携できることにより、見込み客の創出ら育成、営業活動に至るまで包括的に管理できます。
Webサイトやフォームを活用したリードジェネレーションをはじめ、CRMへの接続、ROIレポート作成などを活用することにより、確度の高い見込み客に対して効果的に販売を促進します。マーケティングチームと営業チームのワークフローを同期し、効果的なBtoBマーケティングを支援します。
| 向いている形態 | B to B |
|---|---|
| 導入実績 | パーソルキャリア(人材) RIZAPグループ(ヘルスケア) セブン&アイ・ホールディングス(小売)など |
| 他システムとの連携 | ◯(CRM、SFAシステムとの連携) |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯ |
| サポート体制 | 電話、メール、訪問によるサポート |
| 月額料金 | 月額費用:150,000円〜 |
| 主な機能 | ― |
Sales Cloudとの連携が可能
営業の効率化のために非常に多くの企業で導入されている「Sales Cloud」。このツールとの連携によって、リード獲得からナーチャリング、営業への引き渡しをスムーズに行うことが可能になります。
8.Hubspot Marketing hub

(参照元:https://www.hubspot.jp/products/marketing)
コンテンツの作成やリードへの転換、ROIの測定までできる統合型のマーケティングプラットフォームです。営業効率化を図る「Sales hub」とカスタマーサポートの支援をする「Service hub」との連携を行うことができます。
ツール内で、誰でも簡単にコンテンツ作成が可能。書式やフォーマットを手軽に変更できるので、ユーザーの読みやすい魅力あるコンテンツを作り出せます。
またリアルタイムでSEOに関するアドバイスを確認できるので、専門的な知識がなくても検索エンジンでの上位表示に結びつけることが可能。自社製品やサービスへの関心を集めることができます。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 |
YAHOO! JAPAN(IT) |
| 他システムとの連携 | ◯(CRM、SFAシステムとの連携) |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯(メール・SNS・広告) |
| サポート体制 | ◯ |
| 月額料金 | 月額費用:6,000円〜(Starterプラン) |
| 主な機能 | ブログ、ランディングページ、Eメール、マーケティングオートメーション、リード管理、アナリティクス、パーティション化、SNS、SEO、広告、 Call-to-Action、Salesforceとの連携 |
9.Kairos3

(参照元:https://www.kairosmarketing.net/marketing-automation)
マーケティングと営業に必要な機能を備えた、MAツール兼SFA(営業支援)ツールです。「始めやすさ・使いやすさ」に定評があり、難しいマニュアルがなくても簡単に扱うことができます。
名刺管理アプリとの連携やセミナー管理にも対応しており、オフラインでのマーケティング活動のサポートが可能です。関連セミナーへの誘導やセミナー後のフォローアップを通じて、見込み顧客の育成に貢献します。
加えて営業活動の状況を管理できるので、マーケティング・営業の部門間連携による売上アップにも期待できます。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 |
リクルートライフスタイル(サービス業) |
| 他システムとの連携 | ◯(SFAシステムとの連携) |
| 幅広いチャネルへの対応 | ― |
| サポート体制 | ◯ |
| 月額料金 | 初期費用:10,000円 月額費用:15,000円〜 |
| 主な機能 | リード管理、メール配信、フォーム作成、スコアリング、ホットリード、リードナーチャリング、セグメンテーション、オフライン接点管理、マーケティング分析、名刺管理アプリ連携、セミナー管理、シナリオ、独自ドメイン、SFA(営業支援)、Kairos3 API |
10. List Finder

(参照元:https://promote.list-finder.jp/)
株式会社イノベーションが提供するMAツール。月額3.98万円~と比較的安価から始められ、利用の面でも専任のコンサルタントが支援してくれることから、MA初心者でも安心のサービスです。
基本的なMA機能を包含しシンプルな操作性が特徴です。また、コンテンツとしてPDFを活用でき、ユーザーによ閲覧の分析が可能です。導入アカウント数も国内で1,600アカウントを超えているツールです。
| 向いている形態 | B to B / B to C |
|---|---|
| 導入実績 | 三菱電機システムサービス株式会社 東洋インキ株式会社 など |
| 他システムとの連携 | Salesforce(CRM・SFA)、Sansan(名刺管理)など |
| 幅広いチャネルへの対応 | メールのみ |
| サポート体制 | ○ |
| 月額料金 | 3.98 万円~ |
| 主な機能 | 名刺データ化代行、企業属性付与、フォーム作成、メール配信、アクセス解析、PDF閲覧解析、セミナーページ作成、スコアリング、優先リード通知、アプローチ管理 など |
11. Oracle Marketing Cloud

(参照元:https://www.oracle.com/jp/cx/marketing/)
日本オラクル株式会社が提供する米国のMAツール。リードの属性や行動などのデータを生かしたパーソナライズを強みとしており、可能性が高いリードに対して最適なアプローチを実行します。BtoBとBtoCの双方の現場において、ブランドのロイヤリティ向上や新規顧客の創出につなげます。
営業活動に活用できる自動スコアリング機能や、セキュリティを高める厳しい権限設定も可能なため、幅広い商材を持つ企業や、膨大なデータを迅速に処理・分析して生かしたい企業に適しています。
| 向いている形態 | B to B/B to C |
|---|---|
| 導入実績 | ― |
| 他システムとの連携 | ◯ |
| 幅広いチャネルへの対応 | ◯ |
| サポート体制 | ― |
| 月額料金 | ― |
| 主な機能 | リード管理、セグメンテーション、スコアリング、ナーチャリング |

まとめ|自社に最適なMAツールを導入して、質の高いマーケティングを実現
MAツールにはいくつかの種類がありますが、企業によって必要となる機能は異なります。BtoBあるいはBtoC事業向けであるかどうかをはじめ、集客や誘導、分析の有無、顧客育成などさまざまな特徴があるため、機能の必要性を見極めることが重要です。また、MAツールの効果を最大限に生かすためには、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客関係管理)とシームレスな連携も欠かせません。
海外メーカーは圧倒的なシェアを誇りますが、国内メーカーはある分野に特化したMAツールも多いため、自社の用途やニーズに応じて比較検討しましょう。
※各製品の価格や特徴は掲載時点のものとなります

投稿 人気のMAツール11選|マーケティングオートメーションツールの特徴や機能を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 ヘッドレスCMSとは?定義やメリットを徹底解説!ツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]> しかし、開発チームに聞いてみれば、従来のコンテンツマネージメントシステム(CMS)の首(ヘッド)を切り落とすことに賛成するかもしれません。それは、コンテンツの管理と配信に潜在的に無限の可能性をもたらすからです。
この記事の要点
1.ヘッドレスCMSとは?デカップルドCMSとヘッドレスCMSの違い
2.ヘッドレスCMSの機能とメリット
3.おすすめのヘッドレスCMS3選
~この記事はおよそ10分で読めます~
ヘッドレスCMSとは?
従来のコンテンツマネジメントシステム(CMS)の「頭」(ヘッド)は、フロントエンドフレームワークやテンプレートシステムなどのフロントエンドコンポーネントのことを指します。
ヘッドレスCMSは、これらのフロントエンドコンポーネントを取り除くことにより、生の未公開コンテンツを開発チームが自由に使えるようになります。開発者らはコンテンツを配信するためのデフォルトのフロントエンドシステムひとつに縛られないので、コンテンツを表示するためのヘッドをいくつでも好きなだけ作ることができます。APIの力を少しでも利用すれば、Webサイト、アプリ、スマートウォッチなど、さまざまなプラットフォームにコンテンツを配信することができます。
一方、従来のCMSには、すでにフロントエンドの配信レイヤーが組み込まれています。つまり、コンテンツは1つのプラットフォームにしか表示されないのです。
デカップルドCMSとヘッドレスCMSの違いは何ですか?
この2つのCMSタイプの主な違いは、アーキテクチャタイプにあります。デカップルドCMSではアクティブなアーキテクチャを採用しており、コンテンツが公開されると即座にページに表示されます。ヘッドレスCMSはリアクティブなアーキテクチャで、つまり、ユーザーからの問い合わせがあった時にのみコンテンツがページに表示されます。
ヘッドレスCMSの機能
ヘッドレスCMSの機能は以下の通りです。
API機能
ヘッドレスCMSを従来のCMSから分けるのはAPIです。APIは様々な言語やフレームワークとの連携が可能です。様々なフロントエンド配信システムをAPI上に構築することで、ヘッドレスCMSはあらゆるプラットフォームにコンテンツを配信することができます。
コンテンツモデルの作成
CMSは、あらかじめ定義されたコンテンツモデルに制限されている。ヘッドレスCMSはそうではなく、コンテンツを配信するための独自のプラットフォームを柔軟に作成することができます。
アセットマネジメント
アセットマネジメントでは、ファイルをクラウド上に保存し、1つのシステムで管理することができます。ローカルに保存したコンテンツも、クラウドに保存したコンテンツも、同じプラットフォームで管理することができます。ヘッドレスCMSでは、自分でコンテンツを作成、閲覧、更新、削除することができます。
多言語でのコンテンツ公開
ヘッドレスCMSの最大のメリットのひとつは、複数のプラットフォームでコンテンツを公開できることです。そのため、時には、異なるプラットフォーム上のコンテンツを異なる言語で表示しなければならないこともあります。ヘッドレスCMSのコンテンツは、どのようなフロントエンドフレームワークにも配信できるため、APIの助けを少し借りれば、必要であればどのような言語でも公開することができます。
ヘッドレスCMSのメリット
すでに述べたように、ヘッドレスCMSの最大のメリットは、開発者らがコンテンツを配信するヘッドを複数も構築できることです。これこそが、この種のコンテンツ管理ソリューションを従来のCMSと異なるものにする主な要素です。しかし、このソフトウェアに検討する価値を与える特徴はそれだけではありません。
実装が簡単
従来のCMSでは、コンテンツを別のプラットフォームにアップロードしたいと思うたびに、ツールを再実装する必要がありました。ヘッドレスCMSには、フロントエンドの配信システムが含まれていないため、このような再実装の必要がありません。
ユーザーフレンドリー
従来のCMSはウェブサイトの上に構築されており、そのためには多くのコードやコンテンツが必要となります。ヘッドレスCMSは少しのコードで立ち上げることができるため、従来のCMSよりもはるかに使いやすくなっています。Forbes誌によると、「ビジネスチームが新しい機能を作るのにも、より迅速に対応できます。例えば、マーケティング部門が新シリーズの製品ミニサイトを作成したい場合、CMSに直接アクセスしてすぐにコンテンツの作成を開始することができます」
迅速な導入
前述したように、ヘッドレスCMSの有益な特徴は、さまざまな作業を無駄のない迅速なものにできることです。その一つが、コンテンツ制作者と開発者がヘッドレスCMSを使って二人三脚で作業できることです。従来のCMSではコンテンツを作成する前にシステムを完全に開発する必要があリましたが、この機能があれば従来のCMSよりも早くコンテンツを立ち上げることができます。
オムニチャネル対応
オムニチャネルマーケティングは、あらゆる形態の小売業に変革をもたらしています。ヘッドレスCMSのコンテンツは反応性が高いため、数多くのチャネルでコンテンツを再利用することができます。それは、ソーシャルメディア、モバイル、VR、そして、顧客やユーザーがいるあらゆる場所を含みます。
ヘッドレスCMSの事例
ヘッドレスCMSの領域はまだ発展途上であり、それはいくつかのビッグネームがまだ姿を現していないことを意味しています。ここでは、米国G2 Crowdで波紋を広げ始めている領域で、最高のヘッドレスCMSプラットフォームと考えられる製品をいくつか紹介します。
1. 最高のヘッドレスCMS「Contentstack」
Contentstackは、Web、モバイル、IoTなどの複数のデジタルチャネルにおけるコンテンツ管理を迅速化・簡素化するヘッドレスCMSです。ワークフローや承認、デジタルアセット管理、多言語展開などの機能を備えています。
Contentstackには3種類のプランがあり、1つ目はContentstackが提供するすべての機能を評価できる無料トライアル。2つ目の選択肢はビジネスプランで、規模の拡大を計画しているような企業に最適です。月額3,500ドルで提供されています。最後は、カスタム価格で提供されるエンタープライズプランです。詳細については、Contentstack社にお問い合わせください。
2. オープンソースのヘッドレスCMS「Contentful」
Contentfulは、ヘッドレスCMS機能を備えたWebコンテンツ管理システムです。このツールにより、編集者はコンテンツを管理し、開発者はコンテンツをモバイルやウェブアプリケーションに配信することができます。Contentfulは、作成したコンテンツをプログラム可能にすることで、開発者の生産性を高め、新しいプラットフォームでのイノベーションを可能にすることを誇りとしています。
ユーザーレビュー:
APIで柔軟にコンテンツ配信ができるモダンなCMS
WordPressよりは開発者向けのサービスのような気がしますが、自由度の高いCMSです。APIを利用してJSON形式でコンテンツのデータをリクエストすることができるので、フロントエンドが開発できるのであれば、柔軟にサイトを構築することができると思います。
https://www.itreview.jp/products/contentful/reviews/15113
Contentfulの評判はこちら!https://www.itreview.jp/products/contentful/reviews
3. 日本製ヘッドレスCMS「microCMS」
microCMSはAPIベースの日本製のヘッドレスCMSです。
もう社内向け編集/管理画面を自作する必要はありません。
開発・運用コストを大きく下げることでビジネスを加速させます。
コンテンツ管理のためのサーバ管理は一切不要で、サインアップするだけですぐにサービスを利用開始できます。
また、APIを作成するとデータ入稿用の管理画面が自動生成され、誰でも簡単にコンテンツを作成・管理できます。
さらに、コンテンツはAPI経由で取得可能なためエンジニアやデザイナーはさまざまなプラットフォームでコンテンツを利用できます。
ユーザーレビュー:
サイト運営にかかる時間・コストともに半分以下になった
機能ごと・メンバー毎で権限管理できるので、運用がとにかく楽。テスト環境での社内のステークホルダーへの確認だったり、機能ごとの使い分けが簡単にできるのが便利。
また、予約投稿機能があるので、ページの開始・終了時間を自由に設定できるのも結構助かっている。
https://www.itreview.jp/products/microcms/reviews/49328
microCMSの評判はこちら!https://www.itreview.jp/products/microcms/reviews
※この記事は、https://learn.g2.com/headless-cmsを翻訳し、国内向けに再編集しています。
投稿 ヘッドレスCMSとは?定義やメリットを徹底解説!ツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 企業でのYouTubeチャンネルの活用に!Youtuberが使っているおすすめ・無料の動画編集ソフトを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>YouTubeが誕生して15年近くになりますが、すでにYouTubeが存在する以前の生活を想像することは難しくています。YouTubeに最初にアップロードされた動画は、YouTubeの共同設立者であるジョード・カリムが動物園に行ったときの様子を記録したものでした。動画の長さはわずか18秒で、カリムは明らかに動画編集ソフトを利用していませんでした。
本記事では企業でのYouTubeチャンネルの活用におすすめのYoutuberが使っている動画編集ソフトや、無料プランや無料トライアルでの使用が可能な動画編集ソフトを紹介します。
この記事の要点
1.YouTubeの持つ影響力と企業チャンネルでの活用方法
2.YouTuberが使っている動画編集ソフト
3.無料プランもしくは無料トライアルが可能な動画編集ソフト
~この記事はおよそ17分で読めます~
YouTubeの持つ影響力と企業チャンネルでの活用方法
今やYouTubeは10億人以上のユーザーを抱えるようになりました。The ArtificeによるとYouTubeには毎分300時間分の動画がアップロードされていて、61の言語で動画を見ることができ、71の国で利用できるとのことです。YouTubeで最も視聴されている動画のトップ10は、いずれも28億回以上の再生回数を記録しています(今でも記録更新中です)。
YouTubeの影響力は、今ではユーザーのキャリアをスタートさせるのに役立っていると言っても過言ではないところまで来ています。ジャスティン・ビーバーは、アッシャーによってYouTube上で発掘されたことで有名です。もっと最近でいえば、スティーブン・スピルバーグ監督が「ウエスト・サイド物語」のリメイク版に出演するマリアを発掘したのも、彼女のYouTubeチャンネルがきっかけでした。
以上の影響力に加え、YouTubeの収益化により、YouTubeに企業アカウントを開設し、広報ツールとしてYouTubeを活用することは、もはや当たり前となりつつあります。
ユーザーインタビューといった事例紹介や自社サービスの紹介といったものから、料理メディアによるレシピ動画、自社ウェビナーの録画配信など企業が配信するオリジナルコンテンツは多岐にわたります。
一流のスタジオや音響設備を持っていない企業の提供する動画といえど、多くのフォロワーを獲得するためには、YouTuberのように、ユーザーに最適な視聴体験を提供する必要があります。カリムのような粗い映像と貧弱な音質ではもううまく行きません。それに加えて、低品質の動画では、高度に洗練された動画の存在感に対抗することはできません。YouTuber達は動画編集ソフトを駆使して最高の動画を作れるように準備を整えています。
以下のビデオ編集ソフトウェアは、米国の人気YouTuber達が自身のコンテンツの編集に使用してきたものです。
人気のあるYouTuberが使っている動画編集ソフトは?
プロのYouTuberはYouTubeで生計を立てています。そのため、彼らはフォロワーに次の動画を見るためにチャンネルに戻って来てもらえるようなコンテンツを作れる動画編集ツールを選んでいます。以下のツールは、YouTuber達がよく使っているものです。
YouTuber:ジェイク・ポール
ジェイク・ポールは、元Vineスターで、ディズニースターからYouTuberに転身した人物です。1,700万人以上のフォロワーを誇る彼のYouTubeチャンネルは、歌とブイログで構成されています。ジェイク・ポールは、編集にはPremiere Proを使用していると明言しています。
ポールが選んだソフトウェア:Premiere Pro
Premiere Proとは、Web向け動画コンテンツの編集ツールです。AIと機械学習が備わったAdobe Senseiを活用しているため、タスクやワークフローの高速化を実現。Adobeのさまざまなツール(After Effects、Audition、Adobe Stockなど)やサービスと連動することで、洗練された動画を完成させることができます。短い動画から長編映画まで、あらゆるフォーマットの編集を可能とします。その他、コンテンツ管理にも優れており、スマートフォンやタブレットでの編集やSNSへの投稿が可能。Creative Cloudで利用できるため、快適な情報共有ができます。
評価の高いユーザーレビュー:
人気ユーチューバーも挙って使うプロ仕様の映像編集ソフト
なんといってもプロ並みの作業ができる多機能さ。premiere proとaftereffectを使えば、世の中にある映像作品でやっていることはほぼすべてできるといっても過言ではないはず(スキルがあれば)
私自身すべて使いこなしているとはいいがたいが、それでも素人っぽさから抜けだした映像に仕上げることはできるので多機能なソフトの力だと思う。
https://www.itreview.jp/products/premiere-pro/reviews/54361
Premiere Proの評判はこちら!
https://www.itreview.jp/products/premiere-pro/reviews
YouTuber:ケイシー・ナイスタット
ケイシー・ナイスタットは、1,000万人以上の購読者を持つライフスタイル系YouTuberです。ナイスタットはApple製品について熱く語っていて、彼はYouTube動画の編集にはFinal Cut Pro Xを使用しています。(以下ではFinal Cut Pro Xの後継製品である、Final Cut Proについて紹介します)しかし、彼はオールラウンドな動画編集ソフトとしてはPremiereの方が優れていると思うが新しいシステムを学び直す時間がないとも語っています。
ナイスタットが選んだソフトウェア:Final Cut Pro
Final Cut Pro(ファイナルカットプロ)とは、ノンリニアビデオ編集を目的としたApple社が開発・販売するソフトウェアです。macOSのみ利用が可能で、編集したビデオをその場で素早くエンコーディング、配信できます。文字入力、エフェクト編集のみならず、非常に高度なプロ向けの色調整(カラーグレーディング)や、サウンドエフェクト編集、360度ビデオの編集も可能です。映像制作の入門ソフトであるiMovieからFaisal Cut Proへの移行もスムーズに行えます。簡単なビデオ編集から高度なレベルまで対応可能であるため初心者からプロフェッショナルまで幅広く利用されています。
評価の高いユーザーレビュー:
高性能な映像編集ソフト
Macにおいて高品質な映像編集を行うならばFinal Cut Proがおすすめです。
ひと昔前の話ですが、iMovieで映像編集してもどこか映像に安っぽさが感じていましたがFinual Cutではできることが増えるため、操作に慣れるまで時間が少しかかるかもしれませんが、ネットで調べた情報だけでも十分に高品質な映像を仕上げることができます点が良いです。
https://www.itreview.jp/products/final-cut-pro/reviews/45103
Final Cut Proの評判はこちら!
https://www.itreview.jp/products/final-cut-pro/reviews
YouTuber:Unbox Therapy
YouTuberのルイス・ジョージ・ヒルセンテさんは、Unbox Therapyの顔でもあります。有名なYouTuberになる前、ヒルセンテさんはコンピュータ修理店で働いていました。店でテクノロジーに関する無数の質問に答えていた彼は、自分の才能をYouTubeに生かすことができると気づきました。Unbox Therapyでは、ヒルセンテさんがハイテク製品の箱を開けて、その製品に対する彼のリアクションを伝える動画を公開しています。動画の制作には、Adobe After Effectsを使用しています。
Unbox Therapyが選んだソフトウェア:After Effects
After Effectsで多彩な映像表現を!
映画のようなタイトル、イントロ、トランジションを作成できます。クリップからオブジェクトを除去したり、炎を出したり雨を降らせたり、ロゴやキャラクターをアニメーションにすることができます。モーショングラフィックスとVFXの業界標準ツールであるAfter Effectsなら、あらゆるアイデアを思い通りに表現できます。
評価の高いユーザーレビュー:
プロと同じツールをこの価格で使えるのはすごい
動画用のエフェクトを作成・編集できます。自分で作れなくても他の人が作ったエフェクトを購入して使用することができます。プロの動画制作現場でも使われるだけあって性能が凄い。機能も多くバージョンアップもとても速いので使える機能がどんどん増えていきます。
https://www.itreview.jp/products/after-effects/reviews/35946
After Effectsの評判はこちら!
https://www.itreview.jp/products/after-effects/reviews
無料プランもしくは無料トライアルが可能な動画編集ソフト
上記で紹介した製品は以外にも、もう少し予算を抑えたい、まずはお試しで使いたいという方もいるかと思います。上記で紹介したFinal Cut Pro、After Effectsはそのような方のために無料プランもしくは無料トライアルでの利用が可能となっています。
その他の無料プランもしくは無料トライアルでの利用が可能な製品から、一部を抜粋して紹介します。
Adobe Premiere Rush
Premiere Rush は、プロが作成したようなビデオを素早く撮影、編集して、YouTube や Facebook などのソーシャルチャンネルに共有できるオールインワン型のビデオ作成ツールです。
プロジェクトはモバイルおよびデスクトップのデバイス間で自動的に同期されるので、ユーザーはデバイス間をシームレスに行き来でき、いつでも中断したところから作業を再開できます。デスクトップでもモバイルデバイスでも一貫した使い勝手を実現する Premiere Rush は、場所を選ばず使用できます。
評価の高いユーザーレビュー:
どこでも手軽に動画編集
premierProも使っていますが、こちらは機能を絞り込んでいる分起動が早く、操作感もProと比較すると軽いです。デバイスに依存せず、スマホやタブレットでも編集できるのが魅力です。
https://www.itreview.jp/products/adobe-premiere-rush/reviews/44851
Adobe Premiere Rushの評判はこちら!https://www.itreview.jp/products/adobe-premiere-rush/reviews
Adobe Animate
ゲームやTV番組、web向けにインタラクティブなアニメーションをデザイン。アニメやバナー広告に生き生きとした効果をもたらします。アニメーションの落書きやアバターを作成することも可能。eラーニングコンテンツやインフォグラフィックにも動きをつけることができます。Animateなら、あらゆるフォーマットで複数のプラットフォームへ手軽に配信し、デバイスを問わず幅広いユーザーにリーチできます。
評価の高いユーザーレビュー:
様々なプラットフォームに対応
Flashから名称が変わり、機能的にもiPhoneを含めた様々なプラットフォームに対応したアニメーションを制作できるようになりました。
IllustratorやPhotoshopとの連携も強く、レイヤーを維持したまま素材を読み込んだり、animateの中でイラストを作ることもできます。
https://www.itreview.jp/products/adobe-animate/reviews/44852
Adobe Animateの評判はこちら!
https://www.itreview.jp/products/adobe-animate/reviews
RICHKA
成果フォーカスの動画開発ツール「リチカ クラウドスタジオ 」なら、誰でも簡単に成果が出るプロクオリティの動画を制作できます。また、専門コンサルが成果が出るまで徹底的に支援します。大手事業会社から代理店まで、400社以上の導入、Facebook、Yahoo!などのプラットフォームの公式パートナーに選ばれる、圧倒的な実績と高い専門性があります。無料トライアルもありますので、是非ご検討ください。
評価の高いユーザーレビュー:
かんたんに動画を作成できるクラウドツール
動画広告用や簡単な商品紹介の動画など、ブラウザ上でかんたんに動画を生成できるツール。動画のテンプレートがあり、そこに画像とテキストを入力するだけで動画がつくれてしまう。プランによってはオリジナルなテンプレートをつくることも可能なので、動画を利用したマーケティングを幅広くサポートしてくれるサービス
https://www.itreview.jp/products/richka/reviews/10230
RICHKAの評判はこちら!
https://www.itreview.jp/products/richka/reviews
無料プランもしくは無料トライアルが可能な動画編集・作成の製品一覧はこちら!
https://www.itreview.jp/categories/video-editing/free_product_lists
動画編集・作成の製品一覧、比較はこちら!https://www.itreview.jp/categories/webinar
動画編集ソフトの紹介、いかがだったでしょうか?
ITreviewでは上記を含め、28製品の動画編集ソフトを紹介しています。
価格や機能など、皆さんのニーズに合わせ様々なポイントで比較ができるので、企業でのYouTubeチャンネルの活用に向け、以下から自社に最適な製品をご確認ください。
動画編集・作成の製品一覧、比較はこちら!
https://www.itreview.jp/categories/webinar
※この記事は、https://learn.g2.com/what-video-editing-software-do-youtubers-useを翻訳し、国内向けに再編集しています。
投稿 企業でのYouTubeチャンネルの活用に!Youtuberが使っているおすすめ・無料の動画編集ソフトを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 VDIとは?リモートワークへの活用方法とメリットを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]> 週に一度リモートで業務を行うチームや、外出中の営業担当者が様々なデバイスを使って仕事をしている場合など、企業はこうしたユーザーの日々の業務をサポートするために、何らかのバーチャルな環境の構成を必要としています。
この記事の要点
1.VDIとは?VDIとデスクトップ仮想化、リモートデスクトップソフトウェア(RDS)、仮想マシン(VM)の比較
2.VDIの5つのコンポーネントと機能、ワークスタイルごとの活用例
3.VDIの導入方法、メリットとデメリット
4.おすすめVDIソリューション5選
VDIとは?
VDI(Virtual Desktop Infrastructure)とは、企業がリモートデスクトップやラップトップなどの業務システムにアクセスすることを可能とするためのソフトウェアです。デスクトップ仮想化の一形態である VDI は、データ センターの中央サーバーが様々なデスクトップをホストし、認証されたユーザーのアクセスを可能とします。
基本的に、VDI ソフトウェアを使用することで、いつでも、どこでも、どのデバイスからでもデスクトップにアクセスが可能です。現代のデジタルワークプレイスでは、VDIにより、従業員は必要なアプリケーション、オペレーティング システム、情報に安全なポータルを介してアクセスでき、セキュリティを心配することなく、生産性とアクセシビリティを向上させることができます。
VDIとデスクトップ仮想化の比較
デスクトップ仮想化とは、デスクトップをハードウェアから切り離す技術を総称したものを指します。つまり、デスクトップ仮想化とは、中央サーバー以外のどこからでも仮想デスクトップにアクセスできるようにするものです。
VDIはデスクトップ仮想化の一種であり、デスクトップ仮想化はリモートデスクトップソフトウェアのように他の方法でも実現可能です。
VDI(仮想デスクトップサービス)・DaaSの製品一覧、比較はこちら!https://www.itreview.jp/categories/vdi
VDIとRDSの比較
繰り返しになりますが、VDIはユーザーがコンピューターのオペレーティングシステム全体にリモートでアクセスすることを可能とし、他のデバイスの配信サービスとして機能します。
対して、リモートデスクトップソフトウェア(RDS)は、ユーザーがインターネットや社内ネットワークを介して、別の場所にあるコンピューターに接続して操作できるようにするものです。
どちらもユーザーが遠隔地からデスクトップにアクセスできるという点では同じですが、VDIとRDSでは使い方が異なります。RDSでは、複数のユーザーが同じ環境にアクセスできるため、デスクトップ・インスタンスはカスタマイズ可能ですが、特定のユーザーのために指定されているわけではありません。
一方、VDIユーザーは、自分の物理的なPCや仮想マシンへのアクセスが与えられるか、共有の仮想マシンにアクセスすることになります。
VDIとVMの比較
仮想マシン(VM)とは、独自のCPU、メモリ、ネットワーク・インターフェースを持つ、コンピュータ・システムの仮想バージョンのことです。VMは、実際のコンピューターのすべての機能と性能を備えており、ある意味、仮想マシンを作成することは、コンピューター上にコンピューターを作成するようなものです。
仮想デスクトップは、仮想マシンにホストされているため、仮想マシンはマスターコンピュータのようなもので、仮想デスクトップはマスターの元で稼働しているコンピューターと考えられます。
仮想マシンがないと仮想デスクトップは稼働しませんが、仮想デスクトップなしでも仮想マシンは稼働します。
VDIの5つのコンポーネント
VDIには5つの主要なコンポーネントがあり、これらの要素はすべて、認証されたユーザーに安全なポータルを介して仮想デスクトップを提供するために重要な役割を果たしています。
1. 仮想化
仮想化とは、何かの仮想バージョンを作ることだけでなく、ユーザーが一度に複数のオペレーティングシステムをコンピューター上で動作させることができる技術も意味します。
VDIに適用される仮想化とは、オペレーティング システムを複数のレイヤーに分割する機能を指し、これにより、システムのハードウェアが万が一故障しても、すべてが仮想化されているため、保存されているデータが完全に失われることはありません。
2.ハイパーバイザー
仮想化は、オペレーティング システムをハードウェアから分離するソフトウェアであるハイパーバイザーなしでは実現できません。ハイパーバイザーは、仮想デスクトップをホストする仮想マシンもホストします。
このツールは仮想環境を構築し、ハードウェアを複数の異なる仮想マシンに分割すると共に、それぞれに独自のオペレーティング システム、構成、およびアプリケーションを割り当てることができます。VDIでは、ハイパーバイザーが「デスクトップ・インスタンス」を作成します。これは基本的に、ユーザーが操作および保守できる個別のデスクトップとなります。
3. コネクションブローカー
コネクションブローカーとは、リソースへの接続を管理するソフトウェアである。VDIの場合、コネクションブローカーはユーザーを目的のデスクトップ・インスタンスに接続します。
コネクションブローカーは、ユーザーをリモートデスクトップに割り当て、すべてのユーザーが認証されていることを確認するために資格情報をチェックし、アクティブおよび非アクティブのデスクトップ・インスタンスを追跡する役割を担っています。
4. デスクトッププール
デスクトッププールとは、仮想マシン上でホストされている、同じ構成のデスクトップのグループのこと。デスクトップのグループをプールすると、特定の設定やアプリケーションを一度に複数のデスクトップに適用できるため、管理者のプロセスを自動化するのに役立ちます。
例えば、セールス部門とカスタマーサクセス部門が同じソフトウェアを多数使用している場合、それぞれのデスクトップをプールしておき、一度に両方に変更を適用することが可能です。
5. アプリケーションの仮想化
アプリケーションの仮想化とは、アプリケーションがインストールされているコンピューターとは別のコンピューターからアプリケーションにアクセスできるようにする技術のこと。VDIに関しては、IT部門がサーバー上にアプリケーションを設置し、他の様々なエンドユーザーにも利用を提供することで、エンドユーザーもそのアプリケーションにアクセスすることができます。
例えば、企業のIT部門が社内のサーバーにツールをインストールした場合、そのアプリケーションを必要とするすべての人のデバイスにインストールする代わりに、アプリケーション仮想化によって他のエンドユーザーのデスクトップにもインストールすることができます。どちらのユーザーにとっても、エクスペリエンスはまったく同じです。
VDIはどのように機能するのか?
仮想デスクトップインフラを実現するための様々な要素がわかったところで、実際にどのようにそれぞれが機能するのかを見てみましょう。
まず、仮想デスクトップインフラを利用しようとする企業は、ハイパーバイザーを使ってすべてを仮想化する必要があります。そのハイパーバイザーが仮想マシンをホストし、その仮想マシンが仮想デスクトップをホストすることになるのです。
ユーザーが仮想デスクトップにログインすると、コネクションブローカーがユーザーを認証し、仮想デスクトップ・インスタンスに接続します。アクセスを維持するためには、エンドユーザーは常に中央管理のサーバーに接続している必要があります。
ユーザーが目にする仮想デスクトップイメージは、すべてのアプリケーションがインストールされているマスターデスクトップのクローンです。つまり、マスターデスクトップ上のアプリケーションは、仮想デスクトップ上で作業するユーザーが利用できるということを意味します。
企業に同じアプリケーションを必要とするユーザーが多数いる場合は、デスクトッププールを作成することで、アプリケーションの仮想化を自動化することができます。
仮想デスクトップの個人やグループが非アクティブになった場合、コネクションブローカーは、非アクティブになった仮想デスクトップをオフにすることで、サーバーの容量を増やし、よりアクティブなユーザーに対応することができます。
VDIの導入オプション
デスクトップにリモートでアクセスすることは誰にとってもメリットがありますが、組織が使用するVDIの導入方法によって、関連するメリットが変わることになる。VDI導入には、永続的なものと非永続的なものの2種類あります。
永続的VDI
永続的VDIでは、ユーザーが個人用の仮想デスクトップを作成することができます。この展開では、ユーザーは毎回同じ仮想デスクトップイメージにログインすることになり、ユーザーがデバイス上のデータやアプリケーションに加えた変更は、すべてそのデスクトップ・インスタンスに保存されます。
ユーザーがデバイスを切り替える必要がある場合、永続的VDIを導入していれば、作業内容を失う心配なくデバイスを切り替えることができます。永続的VDIは、ユーザーが定期的に同じデスクトップを使用する必要があるビジネスや学校の環境で最も一般的です。
非永続的VDI
一方、非永続的VDIでは、ログインするたびに同じ仮想デスクトップに接続できるとは限りません。ログイン時には、毎回同じデスクトップに接続されるかもしれませんし、同じデスクトッププールの他のデスクトップに接続されるかもしれません。
いずれにせよ、再起動すると変更は保存されません。つまり実質的に変更を保存する必要がないため、IT部門は異なる複数の仮想デスクトップを管理する必要がなく、コスト削減とデータ管理の簡素化が可能となります。
非永続的VDIは、公共のコンピュータラボ、図書館、キオスクなど、ユーザーが個人情報の保存を望まない場所でよく使用されています。
どのタイプのVDIを導入すべきかを決める際には、次の質問を自問するのが良いです:「ユーザーが必要とするのは単発のデスクトップへのアクセスなのか、それとも物理的なパーソナル・コンピュータが提供するすべての機能を必要としているのか?」
組織内の対象者がログインしてコンピューターのアプリケーションを使用するだけで、個人情報やカスタマイズ可能なものにはアクセスしない場合は、非永続的VDIの導入が最適な選択となります。しかし、組織内のデバイスを自分のパーソナル・コンピュータのように扱うのであれば、永続的VDIを導入することで、必要な機能を提供することが最適な選択です。
5つのVDI使用例
VDIで仮想デスクトップにリモートアクセスしたユーザーは、オペレーティング システム、アプリケーション、およびデータをすべて保存しているコンピューター (この場合は仮想マシン) があたかも目の前にあるかのように操作が可能となります。
多くの人が安全にバーチャルでコンピューターのコンテンツにアクセスしたいと考えています、現代のデジタル世界で VDI が使用される一般的な使用例は次の5つです。
1. リモートワーカー
現在、リモートで働く人の数が急増しています。自宅はもとより、外出先などオフィス以外の場所で仕事をしていても、デスクトップ アプリケーションにアクセスできる必要があります。
幸いなことに、VDI を使えば、リモート ワーカーは、いつでも、どこからでも、どのデバイスからでも、同じデスクトップにアクセスでき、しかも、それを企業のIT部門が管理できます。
ヒント:VDIシステム内のコネクションブローカーがユーザー認証を行いますが、サイバー犯罪が増加の一途である現在、常にセキュリティの重層化を図ることが重要です。その一つとして、シングル・サインオン・ソフトウェア(SSO)を採用して、仮想デスクトップ上でホストされている情報が安全であり、意図されたユーザーにしか表示されないようにすることがあります。
2. シフト制勤務
シフト制勤務とは、24時間体制で業務を行うための雇用形態です。コールセンターなどのシフト制勤務を実施している企業では、VDIを導入することで、IT部門が使用中のすべてのデスクトップを管理し、必要なツールを1カ所から提供することを可能とします。
シフト制勤務の従業員は通常、共通のパーソナル・コンピュータにより業務をします。出勤すると、デバイスにログインして自分の仮想デスクトップにアクセスし、通常通りの業務を行い、ログオフすると、次の人が全く同じデバイスで同じ作業を行うことが可能です。
3. ヘルスケア
前述の通り、VDIでは、特定の仮想デスクトップにアクセスしようとするユーザーを認証するために、コネクションブローカーが必要となります。ヘルスケア業界のようにプライバシーが重視される業界では、VDIは各仮想デスクトップのアクセス許可をカスタマイズし、認証された担当者のみアクセスを許可することができます。
VDIを使うことで、医療従事者はオフィス内のどのデバイスからでも、仮想デスクトップを使って患者の記録にアクセスすることが可能となります。
4. 教育
学校が今日の技術的進歩に適応するにつれて、生徒一人一人に対応できるだけのデバイスが無い問題に直面するようになっていいます。VDIを使えば、そのような問題も解決可能です。
生徒は自分のログイン認証情報を得ることができ、学校内のどのデバイスからでも自分の仮想デスクトップにアクセスすることが可能です。生徒が進級し、卒業を迎えたりした際には、IT部門が生徒の仮想デスクトップを削除することで、新たに入学してくる生徒ユーザーのためのスペースを確保することができます。
その上、IT部門は生徒がアクセスできるコンテンツを中央コントロールで制限できるので、ウェブサイトやアプリケーションの制限をすべてのデバイスに適用する必要がありません。
5. 複数のデバイスを持つユーザー
従業員が仕事用に複数のデバイスを使っていることも珍しくありません。業務の必要性から複数台を保有しているケースでも、VDIを導入することで、従業員はどのデバイスからでも仮想デスクトップにアクセスが可能です。
VDIを導入する
この章では組織にVDI(仮想デスクトップサービス)・DaaSを導入するにあたり、実際のフェーズに即して導入方法を紹介します。
ユーザー・ニーズの理解
まず初めに、組織で VDI を利用するユーザーの固有のニーズを理解する必要があります。
実際に、カスタマイズ可能なデスクトップを必要としているか?それとも一般的なデスクトップで十分でしょうか?容量とアプリケーションの観点から、仮想デスクトップ・インスタンスには何が必要となるでしょうか?
組織がVDIをどのように利用するのか、さらにはVDIが提供する仮想デスクトップ・インスタンスをどのように使用するのかを決定することが、導入の第一歩となります。
製品の選択
組織のユーザーがVDIに求めている機能を理解したら、ITreviewで、製品の選択肢を確認しましょう!
すべてが実際のユーザーレビューに基づいてランク付けされているので、実際に使用しているユーザーの評価により、利用可能な機能、市場セグメント、ユーザー満足度などを考慮に入れ、あなたのビジネスニーズに合った製品を見つけられます。
ネットワークの準備
ツールを念頭に置きながら、次はネットワークを準備する必要があります。VDIのパフォーマンスは、ネットワークのパフォーマンスに依存するため、VDIを導入する際には使用量がピークになる時間帯を把握し、ネットワークがそれに対応できるかを確認する必要があります。
テストをする
他の新しいソフトウェアの導入時と同様、導入前にテストを実施します。帯域が十分に確保されていることを確認し、必要に応じて調整を行います。見逃している問題に気付いている可能性もあるので、組織内の他のユーザーのフィードバックを求めることを忘れないようにしましょう。
VDIのメリット
VDIは、いつでも、どこからでもオフィスのすべてのコンテンツへのアクセスを可能とするユーザーエクスペリエンスを提供します。
VDIは、外出の多いユーザーやパソコンを持っていないユーザーにとって、ネットワークから切断されたように感じる苦痛を和らげることができます。今日のデジタル・ワークスペースでは、VDIは「あると便利」ではなく「必要不可欠なもの」となっており、そのメリットは多種多様です。
リモートアクセスを可能とする
何よりもまず、多くの人がVDIを利用する主な理由は、ユーザーが任意のデバイスからリモートでデスクトップにアクセスすることを可能することにあります。
さらに、ユーザーが仮想デスクトップにアクセスする際に使用する機器の種類に関わらず、同じようなユーザーインターフェースを使用できます。これにより、ユーザーが特定のデバイスで初めて仮想デスクトップにログインしたときの問題を回避し、習熟の期間を短縮できます。
セキュリティの向上
人々がVDIを使用するもう1つの理由は、個人のデスクトップ・インスタンスには世界中のどこからでもアクセスできるにもかかわらず、その中のデータは安全に保たれているという安心感を持てることにあります。
ユーザーがアクセスできるすべての情報は、現在使用されているデバイスではなく、仮想マシンのサーバーに全て保存されます。アクセス可能な場所と実際にデータが保存されている場所は異なる。繰り返しになるが、デスクトップ・インスタンスは中央のサーバーに保存されているので、個々のデバイスを使ってアクセスしても心配する必要はありません。
また、セキュリティに関しても、通常はIT部門に所属する管理者が、ユーザーが仮想デスクトップ上で何にアクセスできるかをコントロールすることが可能です。そのため、ポリシーが変更された場合など、アプリケーションや特定のデータへのアクセスを許可するかしないかも簡単に実施可能です。
コストの削減
VDIはユーザーにとってのメリットだけでなく、ITコストや時間のロスといった問題も解決します。
まず、IT部門はユーザーごとにデバイスを購入してセットアップする必要がありません。代わりに、組織が使用する各ツールのアプリケーションやアップデートは、使用するデバイスごとではなく、一度だけインストールすることとなります。
これにより、IT部門がより緊急性の高い問題に集中できるようになるだけでなく、継続的にハードウェアを購入して改善する必要もなくなります。
VDIのデメリット
組織にVDIを導入すべき理由は多くあります。多くのメリットがある一方で、VDIを導入しない方が良い理由もあります。こうした問題点は、VDIの利用を思いとどまらせるためではなく、むしろ今後対処する必要が出てくるであろう問題として取り上げられています。
また、VDIソリューションを選択する際には、これらの欠点を念頭に置いておく必要があります。そうすることで、今後直面するであろう問題に対して、より効率良く対処可能な製品が見付かる可能性もあるからです。
高い導入コスト
VDIのデメリットの一つに、導入・管理コストの高さがあります。
ネットワーク機器やハードウェアを絶えずアップグレードすることにかかる費用は、時間の経過とともに増加し、やがては組織内の全員に新しいパソコンを購入するのと同じくらいの費用がかかるようになる可能性もあります。
システム全体のエラーの可能性
問題が生じたときに、組織内で使用されている多くのデバイス個々への対応は必要とされず、一箇所でトラブルシューティングができる便利性がありますが、VDIはシステム全体のエラーを引き起こすリスクを抱えます。
このような問題が発生すると、中央のVDIサーバーに接続しているすべてのユーザーが仮想デスクトップにアクセスできなくなり、生産性が低下します。1つの問題が発生すると、職場は一瞬にして停止してしまいます。
部門独自の課題
VDI にアクセスするユーザーのニーズはさまざまであり、IT 部門にとって頭痛の種になる可能性があります。
独自のプログラムやアプリケーションのセットが必要な場合は、IT 部門が介入して個別のデスクトップ イメージを作成する必要があります。多くの人がパーソナライズされたデスクトップを必要とする場合、IT部門の帯域幅はもちろんのこと、ストレージの制限を超えてしまう可能性があります。
ネットワーク要件の増加
VDIを導入する前に、ネットワーク要件に対応できるかどうかを確認する必要があります。
VDIユーザーがスプレッドシートやその他ドキュメントを中心に作業している場合は、VDIネットワークの負荷をあまり気にする必要はありません。しかし、グラフィックを扱ったり、大量のビデオストリーミングをしたりする場合は、トラフィック管理するためのサーバーの準備が必要となります。
おすすめのVDIソリューション
これまでの情報を念頭に置けば、ビジネスのためのVDIソリューションを導入する準備は万全です。
以下ではITreviewに掲載中のVDI・DaaS(仮想デスクトップ)製品から5選を紹介します。
1. VirtualBox
VirtualBoxとは、Oracleが提供する x86 ベース・システム用のクロスプラットフォーム仮想化ソフトウェアです。Windows、Linux、Mac OS X、さらに Solaris x86 コンピュータにインストールができ、同じコンピュータ上で同時に複数の OS を実行する複数の仮想マシンを生成できます。例えば、Mac 上で Windows とLinux 、Windows PC 上で Linux と Solarisという組み合わせも可能です。Windows、Linux、Mac OS X、Solaris に対するオープンソースまたはビルド済みバイナリとして導入が可能です。
評価の高いユーザーレビュー:
開発環境やサーバー用途に
web開発時のテスト環境や、ソフトウェアのライセンスサーバー用途に仮想OSを起動させて使用することができます。管理の容易さ、扱いやすさ、汎用性の高さどれを見ても一級品のソフトウェアだと思います。
https://www.itreview.jp/products/virtualbox/reviews/33039
VirtualBoxの評判はこちら!https://www.itreview.jp/products/virtualbox/reviews
2. Amazon WorkSpaces
Amazon WorkSpacesとは、どのデバイスからでも、いつでもどこでもデスクトップにアクセスできる、マネージド型でセキュアなクラウドベースのデスクトップサービスです。
WindowsまたはLinuxのデスクトップが数分でセットアップでき、素早くスケールすることで世界中のたくさんの従業員にデスクトップを提供できます。月単位または時間単位のいずれかで支払うことができ、従来のデスクトップやオンプレミスのVDIソリューションに比べ低コストを実現。ハードウェアの資産管理、OSバージョンやパッチ、複雑なVDIの管理作業からも解放されます。導入企業の業界は幅広く、あらゆる業界/業種/規模の企業で導入されています。
評価の高いユーザーレビュー:
1日でインフラ設定完了
コロナ対応で、デスクトップ利用者がノートPCの調達なしに自宅のPCから安全にアクセス可能なリモートワーク環境を、「即座」に構築できるインフラとして最適。新規投資も設定工数除けば0円。利用料のみで、不要になればすぐに課金が不要となる、理想的なリモート環境が構築できる。
https://www.itreview.jp/products/amazon-workspaces/reviews/49305
Amazon WorkSpacesの評判はこちら!https://www.itreview.jp/products/amazon-workspaces/reviews
3. VMware Horizon 7
VMware Horizon 7とは、デスクトップとアプリケーションの仮想化に必要なあらゆる機能のツール群を統合的に提供するプラットフォームです。クライアント端末やUSBメモリ等の盗難および紛失による情報漏えい、クライアント端末導入費用の増加、クライアント端末の故障に伴う長時間の業務中断など、クライアント端末の運用管理における諸課題を解決します。データセンターにて、1台の仮想PCを1人の利用者で利用する仮想PC方式と、1台のサーバを複数人の利用者で共有して利用するSBC方式の2種類のシンクライアントソリューションを提供。導入企業の業界は幅広く、あらゆる業界/業種/規模の企業で導入されています。
評価の高いユーザーレビュー:
VDI製品の導入を検討する際のベースライン
・VDIを稼働させる仮想基盤(vSphere)から日々の運用を支える機能(展開方式やアプリケーション配信、稼働状況の可視化)に至るまで非常に多くのコンポーネントを包含していることから、VDI製品の選定において最も多くの要件に適合できる製品である。
・構築手順もシンプルであり、管理画面は日本語対応。
・製品の歴史も古く、ドキュメントやナレッジベースなどの情報も豊富。
https://www.itreview.jp/products/vmware-horizon-7/reviews/117
VMware Horizon 7の評判はこちら!https://www.itreview.jp/products/vmware-horizon-7/reviews
4. VMware Workstation Pro
VMware Workstation Proとは、VMware Horizon 7と同様、ヴイエムウェア株式会社が提供しているVDI・DaaS(仮想デスクトップ)製品。ITreviewでのユーザー評価は4.1となっており、High performerのバッジを受けています。レビューの投稿数は14件となっています。
評価の高いユーザーレビュー:
仮想環境立てる際に無くてはならない存在
チャットサポートでユーザーから問い合わせを受けることが多く、その際にユーザー環境に合わせるために各OS環境が必要になります。
本製品を使用することにより、気軽に複数OSの仮想環境を立てることができるため、ユーザー支援の際に非常に役立っております。
https://www.itreview.jp/products/vmware-workstation-pro/reviews/50664
VMware Workstation Proの評判はこちら!https://www.itreview.jp/products/vmware-workstation-pro/reviews
5. Vagrant
Vagrantとは、HashiCorp,が提供しているVDI・DaaS(仮想デスクトップ)製品。ITreviewでのユーザー評価は3.8となっており、High performerのバッジを受けています。レビューの投稿数は11件となっています。
評価の高いユーザーレビュー:
フルスタックな仮想環境を手軽に試すツール
仮想環境というと最近はDockerなどのcontainerdベースのツールが人気ですが、DockerはネットワークやディスクのIsolationが不十分にしか仮想化できないという点が弱点でした。VagrantはVirtualBoxなどのもう少し多くのレイヤーを仮想化した仮想環境を、手軽に構築することができるツールです。どうしても手元に本番環境などとほぼニアリーイコールな環境を構築したいケースがありますが、Dockerではその需要は半分くらいしか満たせません。とはいえもう少しきちんとした仮想環境を構築しようとするとそれなりに大変になります。VagrantはDSLベースで設定を記述すると手軽に仮想環境を構築できる、という点が最大の良いポイントだと思います。
https://www.itreview.jp/products/vagrant/reviews/20925
Vagrantの評判はこちら!
https://www.itreview.jp/products/vagrant/reviews
まとめ
ソフトウェアは、組織内の人々の生産性を向上させるためにあり、仮想デスクトップインフラはまさにそのために機能します。世界のどこにいてもパーソナライズされたデスクトップにアクセスできるというのは、まさに現代の贅沢です。だからといって組織のユーザーがそれを手に入れてはいけないわけではありません。あなたのワークスタイルに最適なソリューションを導入しましょう。
※この記事は、https://www.g2.com/articles/vdiを翻訳し、国内向けに再編集しています。
投稿 VDIとは?リモートワークへの活用方法とメリットを徹底解説! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 CRM導入で何が変わる?これまでの顧客管理との違いや評価の高いツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>紙での顧客管理は誰でも扱いやすいものの集計には向いておらず、なにより場所を取る。Excelでの顧客管理は根強い人気を保っているが、誤入力による上書き、複数人での同時入力・作業のやりにくさ、データ破損に備えたバージョン違いのファイル管理の煩雑さなど課題もある。また、従来の顧客管理システムは使い勝手が悪く、せっかくの顧客データをうまく活用できていないことが多いようだ。
本記事では、従来の顧客管理と比較をしながら、CRMツール導入によって何が実現できるのかを考察していく。
1. そもそも、CRMツールとは?
CRMはCustomer Relationship Managementの略で、日本語では「顧客関係管理」などと訳される。
「顧客と長期的に良好な関係性を築くことで自社の売上拡大を図る経営手法」が元来の意味だが、現在ではそれを実現するためのツール自体をCRMと指すことが一般的である。
見込み客からリピーターまで全ての顧客情報を管理・分析し、顧客に応じたきめ細かい対応をすることで顧客満足度を高め、「LTV:Life Time Value(顧客生涯価値)」の最大化を目指すことが目的である。
CRMを導入することで、これまで各部門に点在していた顧客情報が一元管理、可視化でき、企業全体での有効な活用につながる。
営業部門では、商談内容を共有することで効果的な営業戦略を立て、営業活動の効率化を図ることができ、マーケティング部門では、蓄積された情報を分析し、戦略的なマーケティングに活用することができる。商品開発部門では、顧客からの問い合わせ履歴を分析し、次の商品開発に役立て、カスタマーサポート部門では、これまでの問い合わせを踏まえた質の高いサポートを提供することで顧客満足度の向上が可能となる。
CRMは、顧客との接点を持つ全ての部門で活用できる、企業活動の中心となるデータベースでもあるともいえる。

2. CRM導入で実現できる顧客管理の効果とは?
現在、CRMを導入していなくとも、何らかの方法で顧客管理を行っている方がCRMを導入することで、どういった課題解決の効果を得られるのかを具体例と共に見ていきたい。
・顧客情報の更新を効率的にミスなく行いたい
Excelで顧客管理を行っている場合、複数人での情報更新に悩まれる方が多い。
Excelは最新の状況を一目で確認する分には優秀だが、複数人が同時入力するには行える操作に制限があり、また、一度データを書き換えてしまうと前回訪問の記録情報や、以前の担当者情報などは消えてしまう。それを防ぐために、「前々回の訪問日時」「以前の担当者」などと情報を追加すると、日に日にリストは巨大なものになってしまい、容量は重く、使い勝手が悪くなる。また、新しい顧客情報を各自が追加していく場合には、重複した情報が蓄積されてしまうこともありうる。一度連絡をしているにも関わらず別の営業担当からも連絡をしてしまい、クレームになることも珍しくはない。
CRMを導入すると、複数人での同時作業ができ、顧客情報の検索や更新がスムーズになる。さらに登録された顧客情報に重複がある場合にも、名寄せ機能により情報を一つに統合することができる。
・蓄積した顧客情報をマーケティングに活用したい
手間暇をかけて顧客情報を蓄積しても、活用されなければ意味がない。
Excelでのリスト化や名刺管理ソフトへの取り込みなどにより顧客情報を有している方は多い。しかし、日々の企業活動の中で積み重なる見込み客について一斉配信メールに利用するなど限定的な活用になっていたり、フォローは営業部門任せで、その後の状況がどのようになっているかマーケティング部門では把握できていなかったりということがあるのではないか。
CRMを導入することで、自社の顧客の傾向をさまざまな角度から容易に分析することができ、その結果をもとに、適切なターゲットに向けたマーケティング活動をCRMの管理画面から直接行う事ができる。顧客情報の獲得方法やその後の購買履歴を記録している場合、どの方法にどのくらいのコストをかけ、結果的にどれだけの売上を生み出すことができたのか、費用対効果を正確に把握し、今後のマーケティング活動への投資に活用することが可能となる。
・営業の日々の情報入力を効率化したい
顧客管理において、正確な情報をリアルタイムに反映されるようにすることは非常に重要である。しかし、Excelや独自の顧客管理システムを利用している場合、入力を社内で行わなければならず、情報が更新されるまでにタイムラグが生じる事が多く見られる。
営業担当が訪問していたにも関わらず、顧客情報を更新していなかったことで、カスタマーサポートに問い合わせがあっても適切な対応がとれず、クレームに繋がるということも珍しくない。
CRMを導入することで、営業担当が訪問直後にスマートフォンから、商談情報や次回の商談予定を入力し、関係者への情報共有をその場で完了することが可能となる。営業の役割はひとつでも多くの商談を行うことにあり、入力の効率化は避けては通れない課題である。課題を解決すれば、営業は今まで以上に多くの顧客先を訪問し商談することができ、売上拡大はもちろん、顧客満足度の向上、リピート率の向上に繋がる。
・報告会議を戦略会議へ変えていきたい
Excelなどで顧客管理を行っている場合、日々の活動管理に必要な情報をあれもこれもと追加しがちなため、気が付くと列が増えてしまっているということはないだろうか。結果的にそのままでは報告資料として使用できないため、会議の前には必要な情報のみを抜き出して加工し印刷する、といった手間がかかってしまう話は珍しくない。
また、せっかく会議が始まっても、初めてその資料を目にする上長に説明するために、ひとりずつ現状と次のアクション、着地予想を発表するだけの場となってしまっていることもある。
CRMを導入すると、膨大な情報から必要な情報だけをレポート化することが容易になる。さらに各自の営業状況はわかりやすくグラフ化され、管理者がリアルタイムで確認でき、会議を待たずに部下に対して適切な指示を行う事が可能となる。
過去の商談履歴もすぐに確認できるため、御用聞き営業になってしまっていないか、今訪問すべきところではなく、訪問しやすいところになってしまっていないか、など営業活動を分析し、効果的な営業会議が行えるようになる。
・お客様からの問い合わせを他部門でも把握したい
CRMを導入していない場合、お客様からの問い合わせは部門ごとに管理され、カスタマーサポート部門だけが把握している、または営業担当だけが把握しているということも珍しくない。営業とカスタマーサポートとの連携がうまくいかずにクレームに繋がるといった、部門を跨いだトラブルは絶えない。
CRMを導入すると、全ての問い合わせは一元管理されるために、どのような問い合わせがあり、今はどのような状況にあるのか、誰がいつ対応を行ったか、全て記録に残すことができる。営業担当は対応情報をいつでも確認できるため、対応状況を確認後にお詫びのご連絡を入れるといった、これまで以上のアクションを取れるようになり、顧客満足に繋げていくことができる。
3. CRMの具体的な機能について
CRMは単なる顧客データベースではありません。「Relationship」と名前が示すとおり、顧客との関係性を深めるためのさまざまな機能を併せ持っている。ここではCRMの主な機能について具体的に見ていく。
・顧客情報管理
CRMの最も基本であり、最も重要な機能が顧客管理機能である。
CRMを導入すると、現在の管理方法にくらべて管理できる情報の幅は大きく広がる。顧客の名前(会社名や担当者名)、住所、電話番号、メールアドレスなどの基本情報に加えて、これまでの商談履歴や、商談の際に提出した提案書や見積書、契約(購買)履歴、お問い合わせやクレームの履歴など、さまざまな顧客との接点をまとめて管理できる。項目をカスタマイズすることで、自社の戦略に合った独自の情報を記録することも可能だ。
顧客の情報を深く知ったうえで適切な営業活動や問い合わせ対応が行えるだけではなく、蓄積された膨大な情報を分析することで、効率的な営業活動や、効果的なマーケティング、顧客のニーズにあった商品開発など、さまざまな業務に活用することができる。
・見込み客(リード)管理
企業の売上拡大に、新規顧客の開拓は必要不可欠である。ホームページからのお問合せ、代表番号への電話、イベントやセミナーへの参加、展示会での名刺交換など自社製品に興味を持った見込み客情報を入手しても、適切なフォローをしなければ顧客に転換していくことはできない。CRMを導入すると、問い合わせフォーム連携・名刺読み取りなどによって情報を効率的に取り込める他、優先度の高い見込み客の特定、最適な営業担当の割り当て、フォローアップメールの自動送信、その後の商談管理など、さまざまな支援機能を活用し、見込み客の効率的な顧客化を進めていくことができる。
・営業支援
多くのCRMツールは、SFA(Sales Force Automation:営業活動自動化)の機能を併せ持っている。CRMを導入することで、営業活動に関するさまざまな情報共有が可能になるほか、標準的なプロセスを登録し、各フェーズで行うべきタスクの表示や優先順位の判断をしてくれるなど、属人化しがちな営業活動を、スキルの偏りなく効率的に行う事ができるようになる。また、営業担当は外出先からスマートフォンを利用して外出中のすき間時間で活動報告を行えるため、日報入力のために帰社する必要はなくなる。
蓄積された情報はさまざまな角度から確認をする事ができ、書類作成や報告のための時間も削減され、営業担当にとって心強い機能である。
・マーケティング支援
CRMには最新の顧客情報がリアルタイムに蓄積されていくため、そのデータを様々なマーケティング活動に利用することができる。その方法はさまざまであるが、もっとも基本的な活用法としてメール配信が挙げられる。メールを希望する全員に向けて一斉配信するメールマガジン、一定期間購入のない顧客や「製品Aを購入した顧客」などターゲットを絞って配信するターゲティングメール、購入日などの日付を起点としてストーリー性のあるメールを段階的に送るステップメールなど、柔軟で効果的なメール配信を行う事が可能である。
メールの他にも、アンケートを作成し収集した結果を顧客属性や購入情報と掛け合わせた高度な分析を行う、蓄積されたデータをもとに効果的なインターネット広告を配信する、マーケティングの費用対効果を測定するなど、ツールによってさまざまなマーケティング支援機能が用意されている。
・問い合わせ管理
電話、メール、お問い合わせフォームなど、カスタマーサポート部門には顧客からさまざまな方法でお問い合わせが寄せられる。CRMを導入することで、各チャネルからのお問い合わせを一元管理することができる。1つの画面上で全てのお問い合わせをまとめて確認し、それぞれに担当者を割り当てることで、対応漏れや二重対応を予防することができる。また、未対応や優先順位の高いものなどを容易に把握でき、他の担当者への引継ぎやエスカレーション作業をスムーズに行うこともできる。他にも、良くあるお問い合わせをテンプレート化する機能や、自社ホームページ上にチャットによる問い合わせ受付機能を増やすなど、さまざまな支援機能があります。
製品を選定する際は、どのような経営課題を解決したいのかを明確にした上で、各製品で実現することができるのかを十分に検証し、最適な製品を選択してほしい。
4.評価の高いCRMシステムとは?
CRMと称するツールは数多く市場に展開されており、さまざまなタイプの製品がそれぞれの特徴をアピールしながら販売している。大量の製品の中から自社に合ったツールを選定するのは何か選定の基準がないと難しいだろう。ここでおすすめしたいのが、ツールの「顧客満足度」を1つの指標にすることだ。
IT製品を導入する際よく起こる問題の1つが、現場で浸透せず使われなくなってしまう、といったようなことだ。これは現場のユーザーにとって使いづらかったり、現場業務の痒いところに手が届かない、サポートが十分でないといったことが原因となっているケースが多い。
顧客満足度は既に利用中のユーザーからの評価そのものであり、満足度が高い製品はこれらの問題が起きない事が多いといえる。 ITreview では、実際にCRMを利用中のユーザーから高い評価を得ているツールをCRMのLeader製品、High Performer製品として分かりやすくバッジを付けて紹介している。
今回は、多くのCRM製品の中から、上記のLeader製品とHigh Performer製品を紹介していこう。それぞれの製品のレビューも確認できるため、どんな方がそのツールを活用しているのか、ぜひ確認していただきたい。
1.Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、もともと営業支援のSaaSとして市場に投入され、普及と発展を遂げてきた。今日では、SFAとCRMの機能を併せ持つクラウドサービスとして企業に広く浸透しており、日本を含む世界で最もシェアの高い※ ツールとされている。
機能としては、既存顧客管理、見込み客管理、案件管理、売上予測、レポート/ダッシュボード生成などの機能を備え、最近ではマーケティングオートメーション(MA)機能も一部サポートしている。こうした Salesforce Sales Cloud の活用によって、潜在顧客を発掘から見込み客を育成し、案件の早期受注を図るプロセスが効率化できるという。
さらに近年ではAI(人工知能)の機能も組み込まれている。このAIの働きによって、購入確率の高い顧客・案件・正確な売上予測などを簡単に把握することができるという。
Salesforce Sales Cloudのユーザーや活用方法は?レビューをチェックする
※『IDC, Worldwide Semiannual Software Track er, October 2018』調査による
2.Intercom
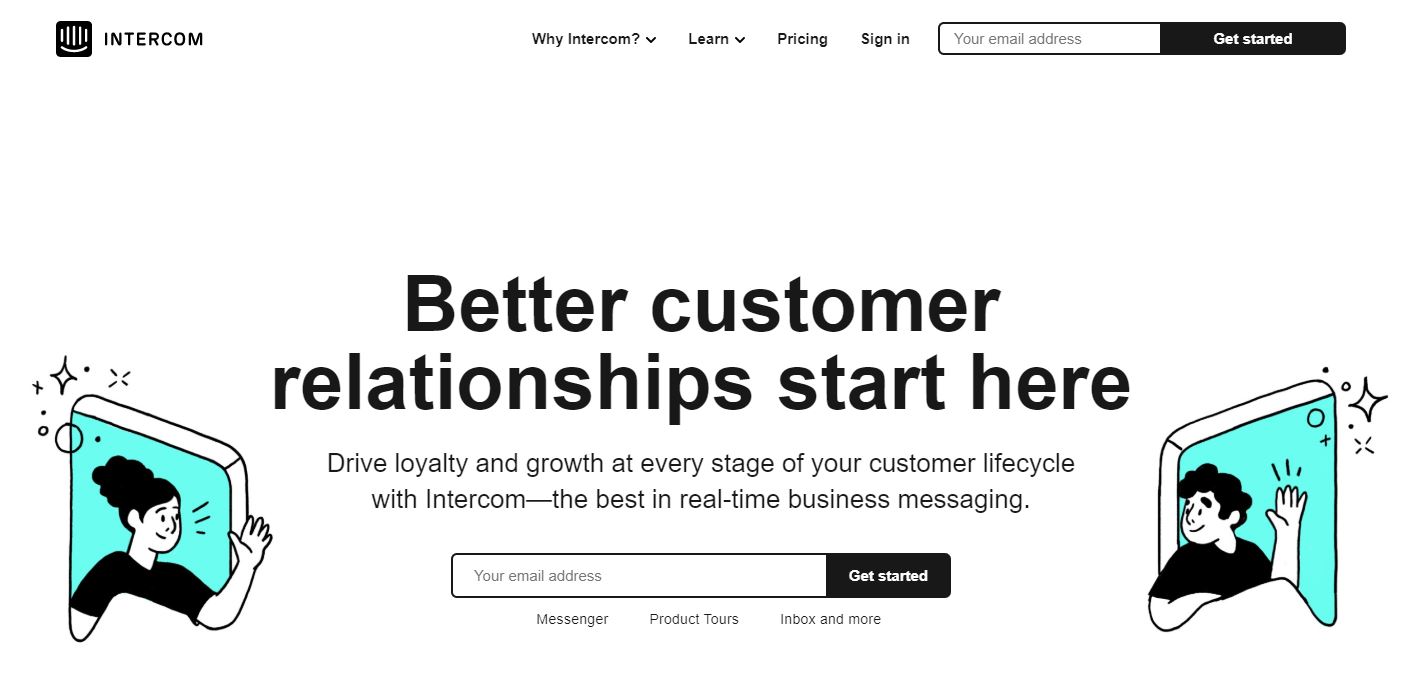
Intercom(インターコム)は、ビジネスメッセージング(メール/チャット)を通じた顧客とのパーソナルな対話を、営業活動やマーケティング活動、カスタマーサービスの効率化に役立てるタイプのクラウドCRMシステムである。Webサイト/Webサービスを運営する企業に向けた統合型CRMシステムとして提供されており、海外製品のために日本ではそれほど有名ではないが、開発・提供元のインターコム社(2011年設立)のサイトによれば、すでに世界で3万社を超える企業が Intercom を活用しているという。
Intercomを使うことで、例えば、Webサイト来訪者の行動を自動で追跡して見込み客を特定し、最も商談成立の可能性の高い見込み客とリアルタイムにチャットで対話すること可能になる。また、特定の顧客行動をトリガーにしてターゲティングメールを自動的に送信することもできる。
さらに、カスタマーサービス業務の効率化に向けて、チャットボットの機能を使いつつ、顧客からの問い合わせにチャットで、効率的に対応する機能も提供しており、対応時には、問い合わせをしてきた顧客が誰かを瞬時に特定し、その情報を表示させる機能も備えている。さらに、顧客による自己解決を可能にするヘルプデスクの機能も提供している。
Intercomのユーザーや活用方法は?レビューをチェックする
3.Synergy!

Synergy!(シナジー)は、実店舗、Web、メール、スマートフォンアプリ、SNSなど、さまざまな顧客接点からの情報を一元管理し、個別化されたマーケティング施策に活かすための国産クラウドCRMシステムである。CRMの扱いに慣れていない担当者でも短期間で使い方が習得できる高い操作性と、あらゆる業種・業態にも対応できる自由度の高い設計を大きな特徴としている。
Synergy! は、顧客情報の一元管理と分析の機能を提供するデータベース機能と、顧客情報を収集するためのフォーム/アンケートの作成支援機能、さらには顧客の育成や販促のための情報をターゲットに伝える機能(メール配信/LINE配信/広告連携)から構成される。
データベースでは、顧客の基本プロファイルをはじめ、メールマガジンのクリックや実店舗でのクーポン利用、購買履歴といった顧客行動とタッチポイントでのログを一元的に管理することができ、顧客行動をメール配信などのアクションのトリガーとして使うこともできる。また、データベースの項目から「絞り込みリスト」を作成し、ターゲティングメールの施策に活かせるほか、CSVフォーマットを使ったデータのインポート/エクスポートにも対応しており、Excelなどの外部のデータソースからの、必要なデータを簡単に取り込むことができる。
さらに、SNS広告やGoogle広告、DMPとの連携により、CRM活動で獲得した顧客のデータを広告配信の最適化に活用することも可能としている。
Synergy!のユーザーや活用方法などレビューをチェックする
4. Zoho CRM

Zoho CRMは、CRMとSFA、さらにはMAの機能が一体化されたクラウド型のCRMシステムである。業務形態に合わせた柔軟なカスタマイズが可能であるほか、シンプルなインタフェースによる使いやすさ、コストパフォーマンスの良さを特徴としている。ZohoCRMの主な機能としては、下記が挙げられる。
・顧客情報の一元管理と分析
・セールスパイプラインの管理
・メール配信などの業務フローの自動化
・Google AdWordsとの連携によるリスティング広告の効果測定
・統合されているMA機能( Zoho Campaigns )以外のMAツールとの連携機能
このうち顧客情報の管理では、顧客の基本プロファイルや取引実績のほかに、電話やメール、SNS、チャットなど、さまざまな方法で行われる顧客とのコミュニケーションを一元管理することができる。また、メールの開封状況やWebサイトの訪問履歴から、顧客の興味を把握することも可能だ。
さらに、営業チームのKGI(重要目標達成指標:Key Goal Indicator)/KPI(重要業績評価指標:Key Performance Indicator)に沿って、達成度を計測して可視化する機能も備えている。このほか、見込み客の発見や、顧客のメール内容に応じた返信内容の最適化、連絡タイミングの最適化などを自動化するためのAIも組み込まれている。
Zoho CRMのユーザーや活用方法をレビューでチェックする
投稿 CRM導入で何が変わる?これまでの顧客管理との違いや評価の高いツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Azureへの接続にVPNを利用して安全に使うには?|価格はどれくらいかかる? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>Microsoftが運営するクラウドサービス「Microsoft Azure」もその1つです。そうしたクラウドサービスを、インターネットを通して利用する場合、通信経路上での盗聴などのセキュリティリスクが存在します。
本記事ではMicrosoft Azureのクラウドサービスに接続する際にVPNを活用し、インターネット経由で安全に使う方法をお伝えします。料金についても具体例を交えてお伝えします。
Azureとは?

Microsoft Azure(以下、Azure)とはMicrosoftが運営するパブリッククラウドサービスです。定額制のサービスではなく、サービスを使った分だけ月毎に支払う従量課金方式を採用しています。Azureは、ストレージ、データベースをはじめ、AIや機械学習を使っての分析など100を超えるサービスを提供しています。
AzureはMicrosoftのサービスなので、Office 365などの製品を既に利用している場合には連携が容易です。
一例としては、Azureサービスの1つ、Azure AD(Azure Active Directory)とOffice365との連携が挙げられます。Azure ADは、ID・パスワード管理によりセキュリティを確保しながら、簡単にアプリにアクセスできるサービスです。Azure ADにより、IDの入力など面倒な操作を、大幅に減らすことができます。
Azure ADには、「Free」「OFFICE 365 アプリ」「PREMIUM P1」「PREMIUM P2」の4つのエディションがあり料金が異なります。そのうちの1つ「OFFICE 365 アプリ」は、Office 365ユーザーのためのエディションで、追加料金なし(Office 365のライセンス料金のみ)で使用できます。
つまりOffice 365ユーザーは、Azure ADにより追加料金なしで、AzureのオンプレミスやクラウドのID・パスワードを一元管理できるのです。
このように連携によるメリットがあるため、Microsoft製品を主として使っている企業では、クラウドサービスの移行先としてAzureが選択される傾向にあります。
Azureの世界シェアは2019年時点で13.8%(※注1)のぼり、成長率が高いクラウドサービスの1つとされています。
(※注1)引用:Synergy Research Group クラウドプロバイダーの勢力図」 参照
(※引用:https://www.srgresearch.com/articles/chasing-pack-gain-market-share-q1-amazon-maintains-clear-lead?fbclid=IwAR16ifQorrOkgJ2lQj8HVPuAOUSfM5qzp_OWaHEQ0aAicIb1n3Lf6ILLyRg)
Azureは、クラウドサービスの中でも「IaaS」に分類されます。IaaSとは、「Infrastructure as a Service(サービスとしてのインフラ)」の略で、クラウド上でサーバやネットワークを提供するサービスです。Azure以外の「IaaS」サービスは、Amazonが提供する「AWS」やGoogleが提供する「GCP」などがあります。
AzureにVPN接続するには?

AzureやAWS(Amazon Web Services)などのIaaSでは、ストレージサービスやデータベースサービスといった粒感で契約ができ、その各サービスを相互に接続することで、社外に「仮想ネットワーク」を構築できます。
社外の仮想ネットワークと社内に既に設置しているサーバなどのオンプレミス環境を接続し、一体で運用することを「ハイブリッドクラウド」と呼びます。ハイブリッドクラウドを構築することで、1つのネットワーク上にあるシステムとして運用できることが利点として挙げられます。
また、ハイブリッドクラウドでは、社内のオンプレミス環境に「不足しているものだけ」を、ピンポイントでIaaSサービスから補うことができます。そのため、コスト削減にも一役買うことが期待されています。
一般的なIaaSでは、ハイブリッドクラウド構築のために社外の仮想ネットワークと社内のオンプレミスを接続する方法は大きく分けて2種類あります。インターネットを経由せず通信事業者の専用回線で接続する方法と、インターネットは経由するが暗号化を使用してVPN接続を行う方法(インターネットVPN)です。
専用回線を使って接続する場合は、帯域を保証されるため信頼性や速度の安定性において優れていますが、利用料は高額になります。一方で、インターネットVPN方式で接続する場合には、帯域が保証されていないため、遅延が発生する可能性があります。ただし、専用回線に比べると低価格で利用可能です。
ちなみに、Microsoftのサービスだけで「Azure 仮想ネットワーク」へ接続する場合は、「VPN接続」に限定されます。「専用線による接続」を行うためには、接続プロバイダーと別途契約が必要です。しかし、VPN接続は、取引先などが利用する「Azure 仮想ネットワーク」へもセキュリティを保ちながら手軽に接続できるメリットがあります。
AzureにVPN接続するには、「Azure VPN Gateway」というサービスを利用します。このサービスを使うと、インターネットVPN方式でハイブリッドクラウドが構築可能です。Azureのハイブリッドクラウドでは、専用回線を使わなくてもAzure上のリソースを社内LANの延長線上にあるかのように使用できるのです。
「Azure VPN Gateway」で構築したハイブリッドクラウドのうち、クラウド上のAzure側の部分は「Azure 仮想ネットワーク」と呼ばれています。「Azure VPN Gateway」により、Microsoft ネットワークを経由して複数のAzure 仮想ネットワーク間をVPN接続することもできます。
「Azure 仮想ネットワーク」の導入により、同じく「Azure 仮想ネットワーク」を導入している取引先などとVPN接続が可能となり、活用の幅が広がります。
補足:Azureは専用回線を使った接続方式を提供しておらず、接続プロバイダーが提供するプライベート接続を介して閉域網を提供する「ExpressRoute」というサービスを提供しています。
「Azure VPN Gateway」を使用してAzure仮想ネットワークに接続する方法
「Azure VPN Gateway」を使用して、Azure仮想ネットワークに接続する方法は、以下の3種類あります。
1.ポイント対サイトVPN接続
PCなどのデバイスから、Azure仮想ネットワークにVPN接続する方法です。使用可能なVPNプロトコルは「SSTP」「IKEv2」「Open VPN」の3種類です。
2.サイト間VPN接続
社内ネットワークから、Azure仮想ネットワークにVPN接続する方法です。この接続には、社内ネットワーク側に、パブリックIPアドレスを持ったVPN装置(VPNサーバ、VPN対応ルーター等)が必要です。そしてVPN装置は、IPセキュリティ(IP Sec)に対応している必要があります。
3.VNET間VPN接続
Azure仮想ネットワークから、VPN経由で他の仮想ネットワークへ接続する方法です。Azure仮想ネットワーク同士を接続する場合や、「AWS」など他の仮想ネットワークと接続する場合など、さまざまなバリエーションがあります。
「Azure VPN Gateway」の料金
「Azure」の料金は、世界の地域ごとに定められています。日本国内では東日本と西日本で異なる地域として別々の料金が設定されていますが、大きな違いはありません。以下、東日本の料金を示します。
1.VPN Gateway使用料
Azure仮想ネットワーク側に設置されるVPN Gatewayが作成されてからの経過時間に対して課金される料金です。VPN Gatewayは、使用する帯域幅によって6種類あり値段が違います。
6種類ごとに、P2Sトンネル数(ポイント対サイトVPN接続に使用)、S2Sトンネル数(サイト間VPN接続に使用)の上限が定められています。S2Sトンネルは10個まで、P2Sトンネル数は128個まで、それぞれ無償で使用可能です。無償使用分を超えると別途料金が発生します。
(1)Basic:1時間あたり4.04円
帯域幅:100Mbps
S2Sトンネル数:最大10
P2Sトンネル数:最大128
(2)VpnGw1:1時間あたり21.28円
帯域幅:650Mbps
S2Sトンネル数:最大30(※1)
P2Sトンネル数:最大250(※2)
(3)VpnGw2:1時間あたり54.88円
帯域幅:1Gbps
S2Sトンネル数:最大30(※1)
P2Sトンネル数:最大500(※2)
(4)VpnGw3:1時間あたり140円
帯域幅:1.25Gbps
S2Sトンネル数:最大30(※1)
P2Sトンネル数:最大1,000(※2)
(5)VpnGw4:1時間あたり235.2円
帯域幅:5Gbps
S2Sトンネル数:最大30(※1)
P2Sトンネル数:最大5,000(※2)
(6)VpnGw5:1時間あたり408.8円
帯域幅:10Gbps
S2Sトンネル数:最大30(※1)
P2Sトンネル数:最大10,000(※2)
(※1)S2Sトンネル数で10を超えた分は、1トンネルあたり1.68円/時間
(※2)P2Sトンネル数で128を超えた分は、1接続あたり1.12円/時間
2.データ転送料金
データ転送容量によって課金される料金です。Azure仮想ネットワークに接続する方法によって料金が異なります。
(1)送信仮想ネットワーク間データ転送(サイト間VPN接続、VNET間VPN接続)の場合
Azureデータセンターに入ってくるデータは無料で、出て行くデータのみ料金が発生します。
・出て行くデータの転送料:10.08円/GB
(2)送信P2S(ポイント対サイト)VPNデータ転送の場合
Azureバーチャルネットワークに入ってくるデータは無料で、出て行くデータのみ料金が発生します。料金は、以下の通り転送量ごとに変わり、増えるほど割安です。
・最初の5GB/月:無料
・5GB~10TB/月:13.44円/GB
・10TB~50TB/月:9.520円/GB
・50TB~150TB/月:9.184円/GB
・150TB~500TB/月:8.96円/GB
・500TB以上/月:お問い合わせ
引用元:https://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/vpn-gateway/
「Azure VPN Gateway」の料金計算例
実際の料金計算例として、1つの企業の社内ネットワークからAzure仮想ネットワークへ、サイト間VPN接続した場合を見てみます。
VPN Gatewayは、VPN Gateway「Basic」プランを利用し、1カ月(30日間)使用可能な状態で維持したとします。また、Azureデータセンターから出ていくデータ量の合計が500GBと想定します。この場合の料金を計算すると、以下となります。
(1)VPN Gateway使用料
4.04円×24(時間)×30(日)=2,908円
(2)送信仮想ネットワーク間データ転送の料金
500(GB)×10.08(円/GB)=5,400円
合計金額は以下となります。
(1)+(2)=8,308円
まとめ
本記事では、Azureにインターネット経由でVPN接続する方法をご紹介しました。
Azureをご利用中の場合には、「Azure VPN Gateway」を使うことで、オンプレミス環境とAzure 仮想ネットワーク間で安全な通信を行うことができることがお分かり頂けたのではないかと思います。
しかし、社内の全てのデジタル資産をAzureなどのクラウドサービスに移行できている企業は、まだまだ少ないのが現状です。オンプレミス環境が残っている場合には、社内のサーバに接続するために、別途VPNサービスが必要になります。
企業向けのVPNサービスもさまざまなタイプがあります。検討される際には、以下の満足度マップで市場で評価の高いVPNサービスとその口コミをチェックしてみてください。
投稿 Azureへの接続にVPNを利用して安全に使うには?|価格はどれくらいかかる? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 RPAの導入は難しい?失敗例から学ぶ成功のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>RPAは「Robotic Process Automation /ロボティック・プロセス・オートメーション」の略語で、ホワイトカラーのデスクワークをPCやサーバの中にあるソフトウェア型ロボットが代行・自動化する概念です。
RPAは定型的な業務を人間に代わってロボットが行い、人間はもっと価値のある業務に集中できるようになる魔法のツールのようにいわれており、そのメリットを謳う記事は多く見受けられますが、デメリットはないのか? また本当に効果が出るのか不安を持つ人も多いのではないでしょうか。
ここからは、RPAのデメリット、導入・運用時によくある失敗と原因を紹介し、RPA導入の必要性を見極めるポイントなどを紹介していきます。
1.RPAのデメリットとは?
RPAは最初に人間が定義したルールを「忠実」に守り、休みなく処理を自動的に繰り返してくれるツールです。「忠実」であるがゆえに「気の利かない」RPAが引き起こすデメリットは、次のようなものが挙げられます。
・誤った処理に気付かないままRPAが処理を続けてしまう
前述の通り、RPAは人間が定義した処理ルールを自動的に反復していきます。そのため、誤った作業であってもその妥当性の判断は行わず処理を続けてしまうため、処理ルールの作成段階に誤りがあると、想定した正しい結果を得られません。
また、RPAはさまざまなシステムからデータを集めて処理を行うことができますが、データを提供するシステムの仕様が変更された場合でも、同じルールで処理を続けてしまいます。データを提供するExcelシートの行が一行ズレただけでも、望んでいたものとは全く違う結果を出力し続けることになるのです。
・RPAのロボット開発に工数がかかりすぎてしまう
RPAベンダーのWebサイトを見ると、「RPA導入は至って簡単」、「すぐにでも自動化できる」といった印象を受ける方も多いと思います。しかしながら、これは「自動化できる業務が適切に選定され、業務フローが可視化されており、漏れなくダブりなく整理されていれば」という前提条件があることを忘れてはいけません。
特に長年続いている業務はその時々の担当者によって作業が追加され、結果、煩雑に変わっているものが多くあります。これを機に業務の目的を改めて再確認し、ムダな処理や複雑な処理の見直しを行うことが重要です。そうでないと、本来は必要のないムダな業務まで自動化の対象にしてしまい、ロボット開発の工数がかかってしまうといった弊害が発生してしまいます。
2.RPA導入・運用時によくある失敗と、その原因とは?
「さあRPAの導入!」――その前に、ここではRPAの導入時と運用時のよくある失敗例をもとに、その原因と対策を見てみましょう。
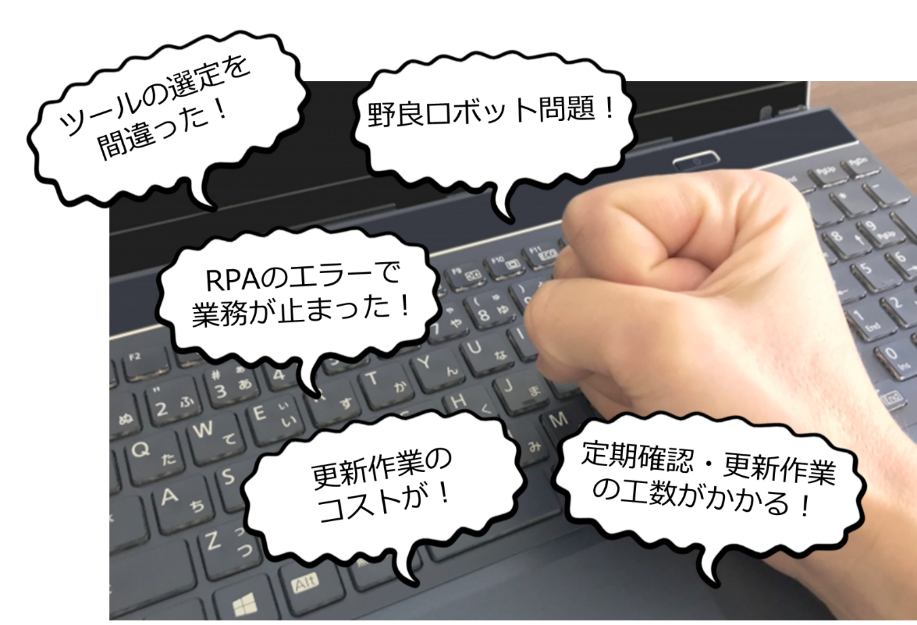
導入時の失敗例1:ツールの選定を誤ってしまい、ツールの変更を余儀なくされる
原因:RPAを導入することが目的になってしまい、自動化したい業務に合ったツール選定の検討が不十分であった。
対策:導入段階で、全社対象なのか部門対象なのか、どの業務にRPAが適しているのかなどを十分な検討した上でツール選定を行いましょう。現在、RPAベンダーが続々と増えています。各社のツールの強みや弱みを比較検討した上で、自社の業務に適したものを選定していきましょう。自社での比較が困難な場合、独立した第三者に客観的に選定してもらうことも一案です。
運用時の失敗例1:RPAのエラーを解消できず業務が停止してしまった
原因:RPAで業務を自動化した結果、その業務がブラックボックス化し業務内容を理解している人がいなくなっていた。
対策:予期せぬエラーでRPAの処理が止まった時に、手動で処理を進められるよう対策を講じる必要があります。誰もが理解できるマニュアルを作成しておくこともその1つです。特にその処理が止まることで他の業務に大きな影響があるものは必ず準備をしましょう。
運用時の失敗例2:RPAの更新作業が自社でできず、ベンダーの作業コストがかさむ
原因:RPAの実装をベンダーに丸投げしたため、RPAの変更に関するノウハウが蓄積されず、自社で何もできなくなっていた。
対策:一般にRPAはノンプログラミングで開発できるケースが多く、プログラミングの専門家でなくても実装できるといわれています。複雑な処理はベンダーに任せるとしても、シンプルな業務は自社で変更できるように、人材教育の時間を確保してくことが懸命です。
運用時の失敗例3:RPAの定期的な確認・更新作業に時間がかかり業務が止まってしまう
原因:変更の多い業務やイレギュラーの発生しやすい業務などRPA導入に適さない業務を選定してしまった。
対策:RPAは導入すれば終わりではなく、定期的な確認作業や更新作業が必要です。そのため、あまり複雑なものはつくらず、複雑な業務であっても作業工程を分割して単純化して自動化すると有効です。
・運用時の失敗例4:「野良ロボット」がいくつも存在し、ITガバナンスが効かなくなる
原因:RPA導入・運用に関して管理者の設定や開発ルール、運用ルールを構築していなかったため、誰も自動化の内容を把握できない「野良ロボット」がいくつも存在してしまった。
対策:ITへの投資・効果・リスクを継続的に最適化するための組織的な仕組みが維持されるように、全社的なシステム管理者(通常は情報システム部)は部門独自のRPAの管理ルールを明確にし、各部門はそれを守って導入していくことが必要です。ベンダーから開発や運用ガイドラインのひな形を提供してもらうのも有効です。
3.自社でのRPAの必要性を見極めるポイント
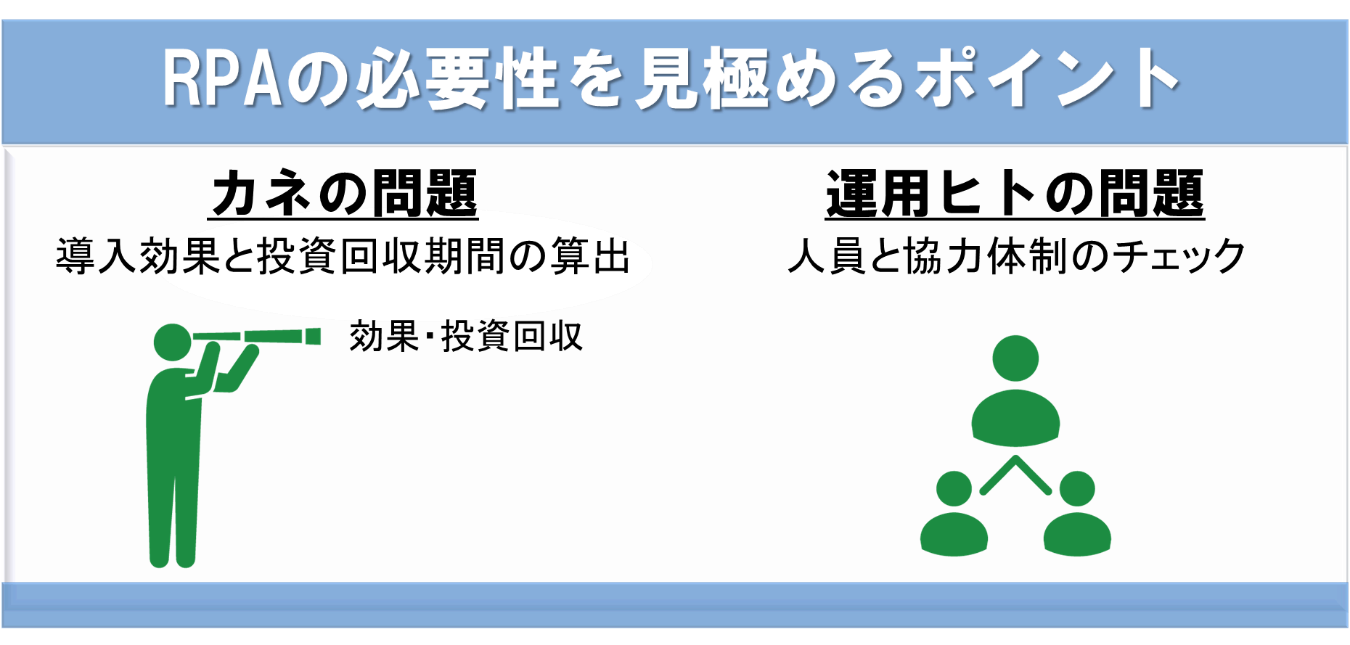
さて、これまでRPA導入・運用時の失敗例、原因と対策をみてきました。ここでは「そもそも自社にRPAが必要であるか」という妥当性の検討について考察していきます。判断基準のポイントは2つ、「コストの問題」と「ヒトの問題」です。
RPAの導入効果と投資回収期間を算出してみる
最も重要なポイントであるコストの問題は、年々の「導入効果」と「投資回収期間」の2つに分けることができます。まず、RPAの導入効果は毎年(毎月の場合もあり)のRPAによる人件費削減効果とRPAの運用費用で算出されます。
導入効果(円/年) = 人件費削減額(円/年) - 初期費用+運用費用(円/年) > 0
上記で算定される導入効果がプラスにならない場合は、残念ながらRPAの導入によるコスト削減の効果はありません。現行通り、人手で処理した方が安上がりとなります。
次にRPAの投資回収期間はRPAの導入効果とRPAの初期費用で算出されます。なお、ここでは話を簡略にするために、毎年の導入効果は同額で、割引計算による現在価値は無視します。
投資回収期間(年) = 初期費用(円/年) ÷ 導入効果(円/年)
上記で算定される投資回収期間は、短ければ短いほど魅力的な投資と言えます。例えば、RPAの初期費用が100万円で毎年の導入効果が50万円であれば、RPAの投資は2年で回収できます。一方で、毎年の導入効果が10万円であればどうでしょうか。RPAの投資は回収に10年もかかってしまうことになります。投資の回収期間が長くなればなるほど、投資の魅力は低くなるのがお分かりいただけるでしょう。
運用体制が構築できそうか人員と協力体制をチェックする
2つ目のポイントであるヒトの問題は、RPAの運用体制が自社およびRPAベンダーと構築できるか否かです。ITシステムに不具合はつきものです。テストを十分に実施しても不測の事態が起こる可能性はゼロではありません。不測の事態に陥 った場合に、業務をいかに止めずに済むかを考慮する必要があります。
例えば、
「月末の金曜日の夕方、今まで順調に動いていたRPAが止まってしまった」
「さて、どうしよう。情報システム部に連絡だ」
「RPAのロボットを組んだ担当者の見立てでは、RPA製品そのものに不具合があるのではないかと」
「じゃあ、ベンダーに連絡だ」
「連絡は取れたが、現行の保守契約では平日の9時から17時までの対応条件なので、調査は週明けになるとのこと。いやいや、これから月末の大量作業が控えているのに、対応が週明けでは困る。なんとかならないか……」
上記の例では、社内の開発担当者は確保できたものの、ベンダーとの保守契約がネックになり、週内の解決は難しそうです。コア業務に関わるRPAツールはベンダーと24時間365日契約を結んでおくことが懸命です。
また、社内担当者が対応できる体制を構築している場合も、1人ではなく複数人の体制をつくらなければ、出張等不在時や、最悪、退職していた場合などは業務復活まで多くの時間を要することになることは想像に難しくありません。自社で解決できる人材も、計画的に育成しておく必要があることがお分かりでしょう。このようなリスクの想定を行い、RPAの運用体制が構築できるか否かも重要なポイントです。
4.RPA導入に進む方のための次ステップ
RPAの必要性を見極めるポイントを踏まえた上で、自社に導入する場合、次にどのようなことを考えるべきかを見ていきます。
押さえておくべきRPAの選定基準、選定時にチェックすべき項目
RPA選定のポイントは、ツールごとの違い(サーバ型RPAかデスクトップ型RPAか)、価格形態や契約形態、オプションの有無などが挙げられます。また、ツールごとに機能の有無など異なる点がありますので、RPAで実現したい業務フローをイメージして機能をチェックすることが必要です。RPAの主な機能としては、以下の通りです。
| ・RPAの処理設計 ・フロー図によるシナリオ作成 ・ レコード機能 ・ プログラミング言語によるルール設計 ・文字と図形や色の判別 ・自動処理の設定 ・スケジューリング ・トリガー設定 ・ワークフロー ・エラー処理 ・ロボット管理 ・ダッシュボード ・複数ロボットの制御 ・ログ管理 |
また、どんな企業でどう活用されているか、満足度が高いツールは何かといった実績を把握することも大切です。導入する企業規模が大企業なのか中堅企業、中小企業なのかで得意とする製品も異なってきます。
下記はITreviewに集まったユーザーの口コミ(レビュー)をもとに満足度と認知度を軸としたポジショニングマップです。各製品の具体的なレビューを是非チェックしてみてください。
5.RPA導入が向かない企業が検討すべき業務効率化の手段
ここまでRPAのデメリット、失敗例、原因とその対策、RPAの必要性を見極めるポイント、導入に進むためのステップなどを述べてきました。いかがでしょうか。導入するにはハードルが高いと感じれた方もいらっしゃるかもしれません。
それでは他に業務効率化の手段はないのでしょうか。そんなことはありません。業務効率化の手法としては昔からあるものでBPM(Business Process Management)があります。 IT用語辞典 e-Wordsによると 『企業などで業務の流れ(ビジネスプロセス)を把握・分析し、継続的に改善・最適化していくこと。また、専用の情報システムを用いてそのような改善活動を実施すること。』とあります。
進め方としては、既存の業務の可視化を行い、非効率なプロセスを洗い出し改善する全社的なプロジェクトとすることが一般的です。これによって部分最適化に陥っている業務に対して、全体最適化を図ることが可能になります。
また、単なる業務システム間の連携については、システム改修という手段やEAI(Enterprise Application Integration)といったデータ連携ツールの導入など、すでに実績が十分なソリューションも多数あります。
さらには、RPAに向いている膨大な定型業務の処理は、その業務自体を丸ごとアウトソーシングするという手段もあります。この場合、該当する業務をRPAで実装するコストとアウトソーシングするコストを比較して判断することになります。
RPAの導入にしても、その他の手段にしても、業務を効率化し人手不足を解消するという目的を達成するためには、まずは現状の業務の可視化をされてみることをお勧めします。今まで当たり前のように処理してきた業務が可視化されることによって、気が付かなかった処理のムリやムダが見つかる、漏れやダブりが見つかる、そのような可能性は高いのではないでしょうか。
投稿 RPAの導入は難しい?失敗例から学ぶ成功のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 いま求められるのは「クラウドへの接続性」クラウド型VPNサービスを使うメリットとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>また昨今、多くの企業で日々の業務で扱うデータ量が拡大している傾向にあり、情報資産の保存・管理が負担となっているケースも少なくありません。
そこで近年、導入が進んでいるサービスの1つが「クラウド」です。これからVPNを導入する企業では、選定時のポイントとしてこのクラウドサービスとの接続性を重要視した方が良いでしょう。本記事では、クラウドにおけるVPN接続の重要性や、クラウド対応のVPNサービスを利用するメリットを解説します。
加速するクラウド化、VPNからの接続が重要な理由
これまで、企業のITインフラを構築する方法として、社内に物理的なサーバを保有(オンプレミス)することが一般的でした。しかし、業務で扱う膨大なデータを自社サーバやPCに保存・管理することは企業にとって運用負荷が大きく、システム障害や破損などのトラブルがあった際、データ損失やシステム再構築が必要になるなどの問題点がありました。
こうした問題に対し、新たな通信技術として登場したのがクラウドサービスです。クラウドでは、ハードウェアを自社に設置・構築することなく、インターネット経由でサーバやストレージなどのインフラ環境を利用することが可能です。必要なリソースを必要な分だけ利用でき無駄なハードウェア投資を省けることから、クラウドサービスを活用する企業が増えてきているのです。
そこで課題となるのがクラウドへの接続性です。通常のインターネット回線を利用しクラウドサービスへ接続するだけでは、通信時の安全性に問題が出てきます。業務データをクラウドに保管する以上、接続時にデータの盗み見やウイルス感染による情報漏えいなどのリスクを防ぐ必要があります。そこで通信の暗号化を行いながらクラウドへ接続するVPNが不可欠といえるでしょう。
企業におけるクラウド活用が拡大・多様化している中、従来、支社間といった拠点間通信をVPN行うだけでは十分とはいえません。しかし、VPN接続の回線や設備を増やすのも簡単なことではありません。そこで比較的簡単に導入でき、自社ネットワークのように接続できる「クラウド型VPNサービス」が有効といえるでしょう。
クラウド型VPNサービスを利用するメリット
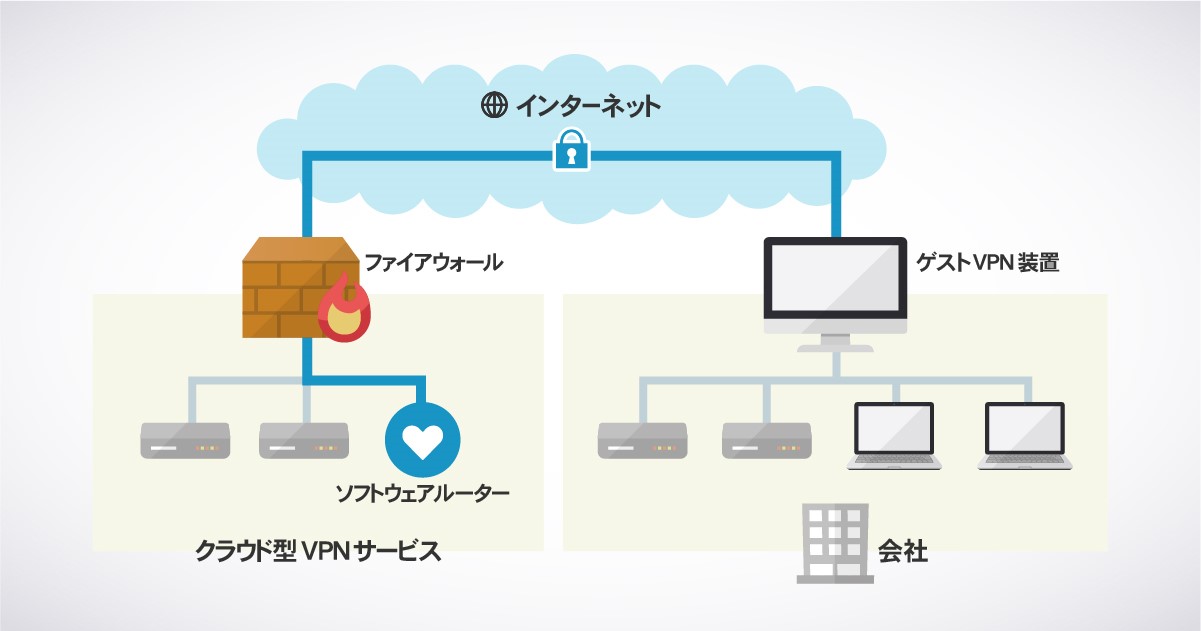
VPN導入を検討しているものの、利用までの設定や運用管理、コストなどを懸念して導入に踏み切れない企業も少なくありません。クラウド型VPNサービスを利用すれば、簡単かつ低コストで導入できるだけでなく、大きく2つのメリットがあります。
1.VPNルーターの設定・更新作業が不要
拠点数が多い企業やさまざまな地域に拠点を持つ企業では、VPNの導入設定や運用に大きな負担がかかることでしょう。クラウド型VPNサービスを利用すれば、機器を各拠点に設置するのみで、VPN接続の設定・管理はVPN事業者が対応してくれます。
VPN接続に必要な設定情報はクラウド上のセンターに集約されているため、接続先情報の変更やパッチの配布、OSのアップデートなど更新作業もセンターで実施されます。自社で行う設定はほとんどなく、運用のためのスタッフを各拠点に用意する必要もありません。
また、実際の拠点では設定作業を行う必要がないため、各拠点でスピーディーにVPNを始められるという利点もあります。
2.故障・災害時に早急に対応できる
日々の業務で利用するVPNは、万が一の故障やトラブルに対する迅速な対応が欠かせません。クラウド型VPNサービスの場合、各拠点にあるVPN機器の稼働状況をクラウド上のセンターで常に監視しています。そのため、障害や不具合にいち早く気付くといったメリットがあります。また、復旧作業もVPN事業者側で実施してもらえるため、運用工数の軽減につながります。
VPNサービスの導入で、クラウドを活用した事業基盤を実現
クラウド型VPNを利用すれば、自社サーバがクラウド環境に存在していても、社内外からVPNを通じて安全にアクセスすることが可能です。通常のインターネット回線を経由することなくクラウド環境へアクセスできるため、通信の安全性が大幅に向上するでしょう。
クラウドサービスを利用した事業基盤の構築に向けて、このようなクラウド対応VPNは、社内ネットワークの安全性を高めるために重要な要素です。
VPNサービスを選定する際には、安全性やコストを重視するだけでなく、クラウドとの接続性、運用管理を任せられるサポート体制なども踏まえて検討しましょう。
いま企業に人気のVPN製品は?
また、ITreviewではVPNがどのような企業に利用されているか、どのような評価がなされているかが分かる口コミを公開しています。さらに、どの製品の人気が高いかがひと目で分かる比較表なども公開中です。ぜひ下記のポジショニングマップから気になる製品をチェックください。
投稿 いま求められるのは「クラウドへの接続性」クラウド型VPNサービスを使うメリットとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 さあ、はじめましょう RPA開発-ツールの種類や開発方法など、色々なことを考えなければいけないあなたへ- は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そうです、最新のITツールを導入しようとすると、どのツールを使えばいいのか、開発・運用は誰にお願いすればいいのかなど、まだまだリサーチすることがたくさんあり、それが新たな壁として立ちはだかってきます。
この記事では、RPAツールの種類や開発・運用方法を導入と開発の流れに沿って、事例を交えて紹介していきます。
(1)RPA導入と開発の流れ
RPAの導入において大切なことは、「しっかりとした導入目的の設定」、「適切なRPAツールの選定」、「ガバナンス体制の構築」の3つです。この3つに気を付けて、「小さく始めて大きく育てる」考え方のもとで慎重に導入を進めていけば、必ずやRPAをうまく使いこなし、会社の業務効率化を飛躍的に向上させることができます。
RPAの具体的な導入手順は、次の5つのステップです。各ステップについて詳しく見ていきます。
1.RPAの適用範囲(対象業務)の決定~導入目的の設定
2.対象業務のプロセスや業務量の可視化
3.RPAの運用ルールの整備~ガバナンス体制の構築
4.RPAの開発、動作テスト・検証~RPAツールの選定
5.RPAの実運用開始
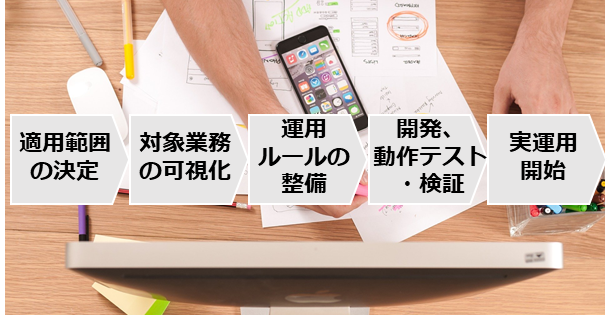
1.RPAの適用範囲(対象業務)の決定
はじめに、対象業務がRPA導入にふさわしい業務か否かを見極めます。判定基準としては、RPA導入による効果が見込めること、業務の手順が複雑でないことなどがあげられます。繰り返し行う定型業務や業務手順が複雑でなく、ルール変更も少ない業務が特に適しています。
2.対象業務のプロセスや業務量の可視化
RPAが担当する業務範囲を決定するために、現行業務の可視化を行います。業務フローや工数が明確にわかるよう可視化すると、RPA導入後のモニタリングがしやすくなります。また、可視化をすることで現行の無駄な作業が見つかる場合があります。その際には、業務フロー自体の見直しをすることをお勧めします。
3.RPAの運用ルールの整備
RPAは現場の担当者に開発、保守・運用を任せるケースが出てきます。しかし、IT部門を介さず個々の部署が自由裁量でロボットを導入すると、担当者の異動や退社で管理者が不在となった「野良ロボット」を生み出してしまい、全社のシステム負荷やセキュリティ面などに問題が生じるなど、収拾がつかなくなる恐れがあります。RPA利用にあたり、社内的なガイドラインを設けるべきです。ガイドラインで定められた権限の範囲で個々の部署がRPAを活用し、業務の効率化をはじめ、本来の責務が全うできるように制度を整備しましょう。
4.RPAの開発、動作テスト・検証
RPA開発の方法としては、RPAベンダーに一括依頼する方法と、社内開発する方法の2つがあります。RPAベンダーに開発を一任すると一般的に短納期で開発できます。またクリティカルな基幹業務の自動化などは、社内で開発するより安心して任せられます。ただし、社内開発に比べて、すぐに改修できない、業務自動化のノウハウが自社に蓄積されないというデメリットがあります。
RPAは今後の業務自動化を推進するうえで社内に必要不可欠なツールになると考えるのであれば、自社主体で開発するべきです。しかし、一定のITスキルがないと、効果的なロボットの作成や改修は難しいため、現場部門での開発はバグ、エラーなどの不具合が起きやすく、RPAに任せた業務が不安定になりがちです。自社で開発をする場合にもベンダーのサポートをしっかり受けて進めることが大切です。
開発したロボットは、単純なエラーや誤動作を起こさないかなどの動作テストや検証を行います。意図した通りの動作をロボットが実行し、業務の分岐点がある場合にはきちんと手順通りに進むか検証テストを行います。
5.RPAの実運用開始
RPAの運用開始後はロボットによる業務処理のモニタリングと評価を定期的に行い、必要に応じて改修・改善を行っていきます。IT技術者(システムエンジニアなど)が開発する業務システムと違い、RPAならば業務変化に応じてすぐに改修が可能なのがRPA導入のメリットの一つです。
(2)RPAツールの種類
一言でRPAツールと言っても、実際には様々な種類があり、企業規模や効率化したい業務によって選択すべきツールは異なります。
ここでは、ロボット作成の難易度から「簡易型」と「開発型」の2つを説明します。
簡易型(画面操作記録型)
普段通りのパソコン作業をするだけで動作を記録することができる「記録型」の機能が搭載されているRPAツールです。あくまでも人の動作を記録するだけなので、極めてシンプルな作業の自動化が主となりますが、最近のRPAツールは「簡易型」と「開発型」の境界があいまいになってきており、複雑でない判断処理であればプログラミングの知識がなくても組み込むことが可能となってきています。ソフトウェアの開発経験がないようなユーザー部門が自らRPAツールを導入し運用管理を行うなど、小規模な運用を想定しているケースであれば「簡易型」のRPAツールがおすすめです。
開発型(コーディング型)
ロボットに繰り返し処理などの複雑な処理を実行させるためには、処理手順をフロー図で示したシナリオを作成しなければなりません。
RPAツールの開発画面には、ライブラリと呼ばれる様々な機能がデフォルトで用意されており、必要な機能をライブラリから選択してロボットの動きを指示するシナリオを作ります。しかしながら、デフォルトで用意されている機能だけでは実現できない高度なシナリオに対しては、機能を自分で作る必要があります。例えば、WinActorではライブラリに用意されていない機能を「VBScript」というプログラミング言語を使うことで自作でき、webページの操作、フォルダやファイルの操作、メール送信などの機能をライブラリに追加できます。
全社での大規模運用を見据えてRPAツールを活用していくようなケースでは「開発型」のRPAツールがおすすめです。ただし、運用管理は専門部署をおいて高度なスキルを持った担当者を用意することが必要になるでしょう。
(3)RPA開発の手法
ここでは(2)の「簡易型」と「開発型」の分類をもとに、RPA開発の主な手法を説明するとともに自社開発のメリットを説明します。
簡易型(画面操作記録型)の開発手法
簡易型(画面操作記録型)では、ノンプログラミング開発といわれている通り、画面操作の記録によりRPA開発が可能です。一般的には繰り返しや条件分岐の処理を追加するためには、プログラミングが必要になることが多いですが、「WinActor」は、ノンプログラミングで業務内容に応じた繰り返しや条件分岐などを追加したシナリオ作成が可能です。
1.業務の自動化方法~ロボットを作成する~
まずは自動化したい作業をWinActorに記録します。WinActorを起動して、記録モードに設定したら、あとはいつも通りPC上で操作を行うだけ。操作の内容をWinActorがフローチャート化し、シナリオを作成します。
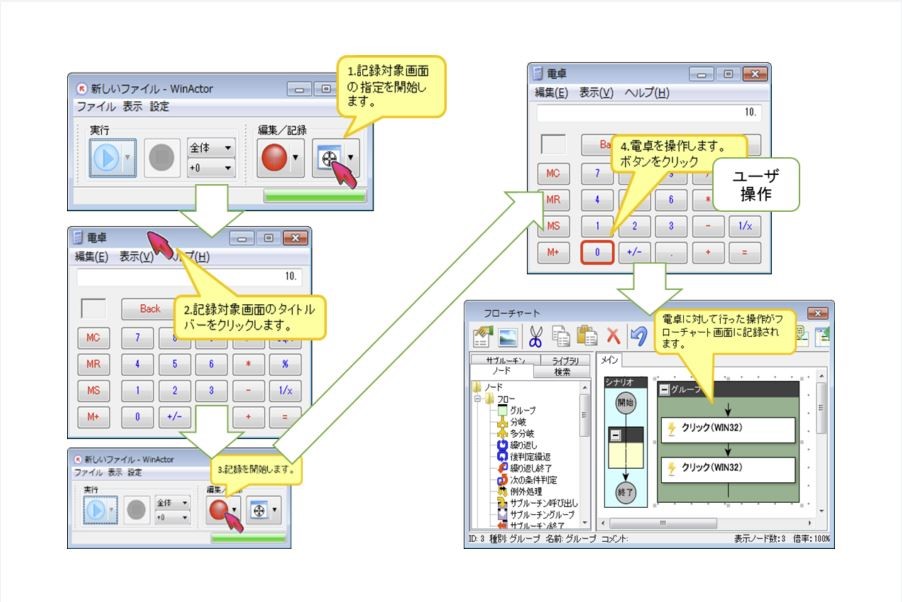
2.業務の自動化方法~ロボットを編集する~
自動記録で作成したシナリオに対し、部品を追加して操作内容の拡張をして呼び出すデータを個別に設定することが可能です。業務の内容に応じて判断処理や繰り返し処理を増やすことでよりユーザーの普段の操作を忠実に再現することができます。よくある操作を実現する部品「ライブラリ」も豊富に取り揃えておりますので、一から全てて記録をせずにシナリオを作成することもできます。実行内容がフロー化されますので、どんな操作をしているのか1つずつ名前を付けて可視化し、誰にでも分かるように編集できることも大きな特長です。
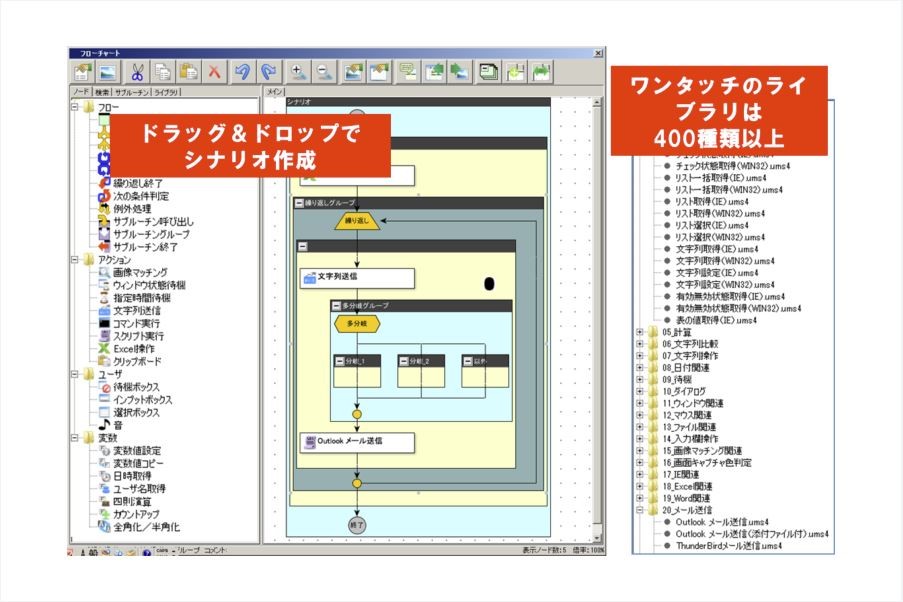
3.業務の自動化方法~ロボットを実行する~
シナリオを作成したら、後は実行ボタンを押すだけでWinActorがユーザーの代わりに作業を実行してくれます。タスクスケジューラでのスケジューリング実行はもちろん、WinDirectorを導入することでWinDirectorがユーザーの代わりにWinActorを動かしてくれます。実行速度も選択できますので、スピード重視での実行も可能です。
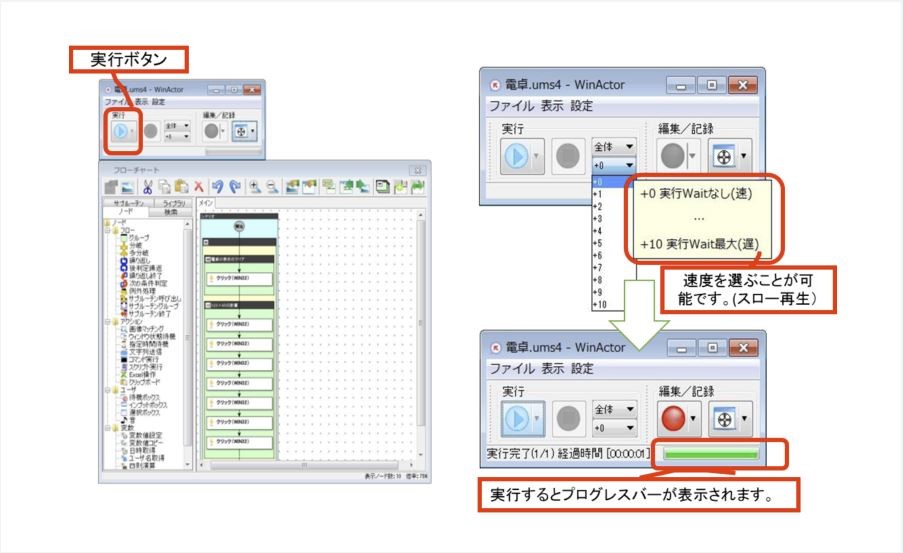
開発型(コーディング型)
開発型(コーディング型)とは、簡単に言うと一般的なプログラミング言語を使った開発手法となります。JavaやC言語等の開発言語を利用し、自動化するためのプログラムを組んでいく必要があり、ソフトウェア開発経験がないと難易度は高いとされています。
システム開発の手法の1つに、「アジャイル型開発」 ( * ) というものがあります。「ウオーターフォール型開発」 ( * ) の手法とよく比較されて取り上げられますが、RPA開発には、このアジャイル型開発の方が向いているといわれています。ウオーターフォール型開発では、開発の途中で仕様変更などを臨機応変に取り込むことが難しいですが、アジャイル型開発では、小単位で開発し、現場の業務担当者の声を反映しながら進めます。RPAの場合、多くはすでに人が行なっている業務ですから、現場の担当と小まめに確認しながら開発するアジャイル型開発の方がリスクも少なく、かつ短期間で開発できます。
( * )アジャイル型開発:仕様や設計の変更が当然あるという前提に立ち、初めから厳密な仕様は決めず、おおよその仕様だけで細かいイテレーション(反復)開発を開始し、小単位での「実装→テスト実行」を繰り返し、徐々に開発を進めていく手法
( * )ウオーターフォール型開発:システムの開発工程を「要件定義」「外部設計」「内部設計」「開発実装」「テスト」などの工程に分けて、1つ1つを完了させ、順番に進行する手法
自社開発のメリット
複雑なロボット開発をRPAベンダーに支援してもらう一方で、自社内の人材で開発できないか、そのような考えを持つ企業も多いと思います。ここでは、RPA開発を自社で行う3つのメリットを説明します。
1.思い立った時にロボット化できる
一番のメリットは、定型業務を今すぐ自動化したい、と思った時にすぐに着手できる点ではないでしょうか?自分の業務内容について一番熟知しているのは自分自身です。これを一からRPAベンダーに説明して、正しく伝わったか確認して、修正指示をだして・・・といった多くの行程が不要になります。
2.ロボットの動作をすぐに変更できる
ロボットが行っている作業をすぐに変更できる点も大きなメリットです。ちょっとしたフローの変更においても保守を担当しているRPAベンダーに変更依頼を出さないといけない、改修してもらう日が何日後になってしまう、といった不便さが解消されます。
3.業務を見直すアイデアが生まれる
担当者が自分の業務を見直す機会を得るという点もメリットの一つです。自分でロボットを開発するとなれば、業務の可視化を自分自身で行います。いつも行っている業務に対して、見直すべき点、新しいアイデアなどの発見につながるかもしれません。
どのような場合にRPAベンダーにロボット開発を依頼すべきか
では逆に、どのような場合にRPAベンダーにロボット開発を依頼すべきでしょうか?
まず考慮することは、改善対象の業務がコア業務かノンコア業務かという点です。つまり、絶対に止めることのできないコア業務(企業の基幹業務に関わるもの)は、やはり専門家としての知見が多いRPAベンダーの支援を仰ぐ方が安心です。また、自社に初めてRPAを導入する場合も、RPAベンダーの支援が必要でしょう。開発要員を集めても、RPAの導入が初めてであれば、社内では解決できない技術的な問題にも直面して、思わぬ時間のロスにつながる可能性もあります。
RPA導入に当たっては、自社とRPAベンダーの共同開発チームを作り、徐々に自社の要員で保守・運用していく体制を作るのが理想です。
(4)RPA開発の事例
ここでは、実際のRPA開発の事例を紹介します。まずは、ITコンサルティング会社と自社社員が一緒になってRPA開発チームを立ち上げ、徐々に自社社員で運用できる体制に移行していく事例です。
静岡トヨペット株式会社、現場社員が中心となりRPA開発・運用。社員工数の約1,858時間を削減
自動車販売会社の静岡トヨペット株式会社(以下、静岡トヨペット社)は、2018年6月から、ITコンサルティング会社の株式会社エル・ティー・エス(以下、LTS社)からRPA導入支援サービスを受けて、業務効率化に取り組んでいます。
近年、同社はクラウドサービスやペーパーレス化などのIT技術の活用により、管理業務の効率化を実現してきました。今回、さらなる業務効率化を目指すべく、RPAの導入と先進IT技術を活用できる人材育成を実施。社内にRPAを自社運用していくための開発チームを立ち上げました。
RPA開発チームは、LTS社から、自社社員の人材育成や運用体制の基盤構築のための支援を受けることで、立ち上げ当初は静岡トヨペット社とLTS社の2社共同で取り組みを進め、徐々に静岡トヨペット社による自社運用に移行してきました。
RPA開発チームのメンバーは、経理や人事など、RPA化対象業務部署の社員を中心に構成されており、業務を熟知する社員が保守・運用することによって、改修やトラブルなどの際、迅速な対応が可能となりました。使用したRPAツールはWinActorです。
RPA導入の成果としては、対象業務に関わる社員工数の1,858時間を削減。それにより創出された工数を更なる業務改善に投入できるようになりました。
(出典:PRTIMES)
(URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000032743.html)
(5)主要なRPAツールで開発に必要となる知識(スクリプトなど)
最後に自社でRPAツールを開発する可能性を模索しているユーザーを対象に、国内で導入事例の多い「WinActor」「UiPath」の2つのRPAツールについて、カスタマイズ時に必要となるプログラミング言語(スクリプト)について紹介します。

WinActor:VBScript
VBScriptを一言で言い表すならば、「Windows上で動くプログラミング言語」です。「VBS」「VBスクリプト」と書かれることもあります。その歴史は1996年に当時主流だったインターネットブラウザのInternet Explorer 3.0に実装されたのが始まりです。
JavaScript、Perl、Python、PHP、Rubyなどと同じようにコンパイル ( * ) が必要のないスクリプト言語です。
( * ) コンパイル:プログラミング言語で書かれたコンピュータプログラム(ソースコード)を、コンピュータ上で実行可能な形式(オブジェクトコート)に変換すること。
VBScriptの特徴は、
・メモ帳(テキストエディタ)だけでプログラミングができる
・プログラミングが簡単
といったところがあげられます。
UiPath:VB.Net
VB.NETも「Windows上で動くプログラミング言語」の1つです。正式名称は「Visual Basic .NET」です。旧来のVisual Basic(バージョン6.0まで、VB6)の後継として2002年にリリースされました。
VB.NETの特徴は、
・初心者でも学びやすい言語
・さまざまなアプリケーションの作成が可能
といったところが挙げられます。UiPathではこのVB.NETを使ってロボットにさせたい動作を記述することができます。
以上、「WinActor」「UiPath」についてカスタマイズ時に必要となるプログラミング言語(スクリプト)について紹介しました。どちらもプログラミング言語の知識があると、より現場に則した高度なRPA開発が可能となります。
ここまで、自社の業務改善につながるRPA開発手法の基本的な知識をまとめてきました。一般的にRPAはプログラミング言語を知らずともロボットを作成し、自部署の業務効率化を実現できるとされています。しかしながら、プログラミング言語を知っていれば、より高度な作業をロボットに指示できます。また、ロボットの管理は個々の部署が行うより、I T部門などを通して全社単位で管理するほうが安心です。
RPA開発に当たっては早期導入と目的達成のために、RPAベンダーの支援を仰ぐことが有効ですが、将来を見据えて社内人材を育成することも大事です。
RPA導入にあたって、自社開発または外部への開発依頼のいずれの選択が適しているか、さまざまな面から検討してみてください。
投稿 さあ、はじめましょう RPA開発-ツールの種類や開発方法など、色々なことを考えなければいけないあなたへ- は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 実績豊富なRPA製品10選|市場シェアや評判の高いツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、RPAの導入を検討するにあたって、「たくさんあるRPAツールのどれを選んでよいか分からない」「導入したら本当に楽になるのか?既に導入した企業の事例を参考にしたい」といった悩みをお持ちではないでしょうか。
RPAは、一度導入すると他のRPA製品に乗り換えることは大変です。そのため、導入の失敗を避けるためにも、まずは多くの企業で導入実績のあるメジャーなRPA製品を把握したいところではないでしょうか。本記事では、国内で実績豊富な RPA を10製品紹介します。自社に合った製品を探すのにお役立てください。
また、自社に合った製品を探すに当たり、導入企業はどのような業務にRPAを適用してどれくらいの効果を出しているのか、各製品の特長と活用事例を紹介します。これらを参考に失敗のない製品選びを進めましょう。
RPA導入のメリット
そもそも、RPAとはどのような製品なのでしょうか。RPAを日本語に訳すと「ロボットによる業務の自動化」となります。ロボットというと、人の形をした機械を思い浮かべるかもしれませんが、RPAは、コンピューターの中で働く「デジタルロボット」です。
では、その「デジタルロボット」は、どんな仕事を手伝ってくれるのでしょうか? 彼らは、受注時の伝票記入、請求書の発行業務、ダイレクトメールの送信、社内の申請書のチェックなど、繰り返しの多い作業・データ量の多い作業で活躍しています。RPAの導入によって、業務部門では、作業の効率化・省力化、作業スピードの向上、そして作業ミスをなくすことによる品質の向上といった効果が期待できます 。
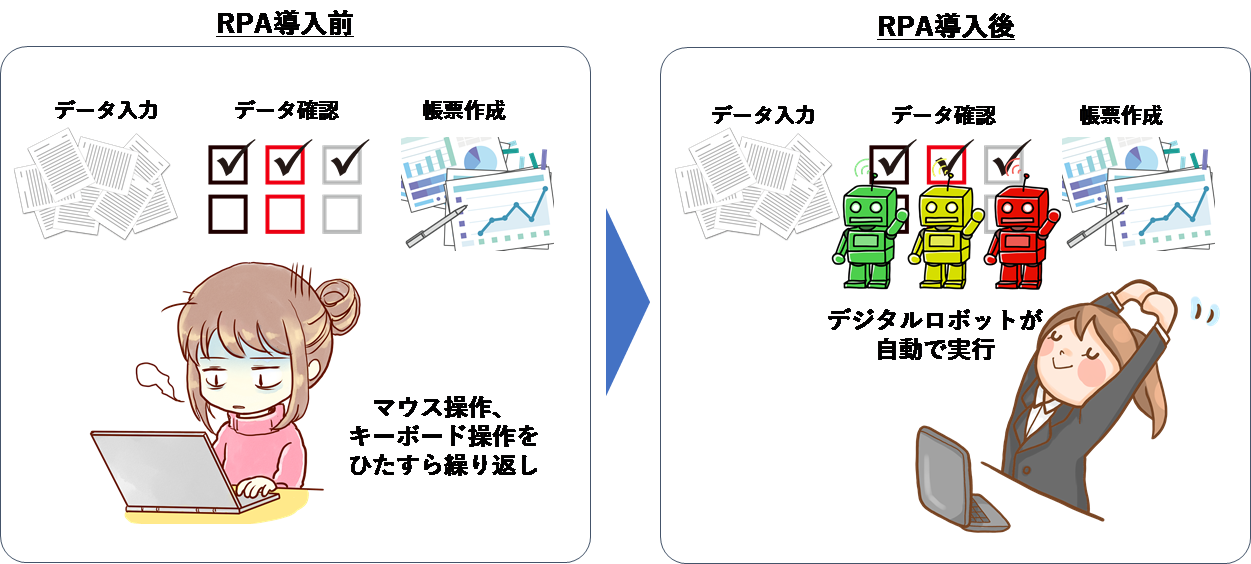
RPAの導入は、情報システム部門にとってもメリットがあります。多くのRPAでは、PCの画面上で人が行っていたマウスやキーボードでの操作を再現することで、デジタルロボットに仕事をさせます。Excelのマクロ機能もこれまで多くの繰り返し業務を効率化してきましたが、ExcelマクロはExcelでしか動きません。しかし、企業の業務は複数のシステムを操作しながら行うことが多く、その中には、過去に構築された古いシステムも存在しています。
RPAは人間の操作のように複数システムにまたがって操作できるため、情報システム部門による既存のアプリケーションの改修なしに、業務の自動化を実現できるのです。
RPAは、従来は自動化が困難とされていたホワイトカラーの業務を代替し、働き方改革を実現する切り札として期待されています。単純な繰り返し作業や作業量が膨大で人手ではできない作業は「デジタルロボット」に任せることで、よりクリエィティブな生産性の高い業務に社員のリソースを当てることができるのです。
実績豊富なRPA Top 5
それでは、国内で実績豊富なRPAベンダーTop 5とその企業で展開するRPAツールを、IDCジャパンの調査結果*2をもとにランキング形式でご紹介していきます。
※2 IDC Japan 株式会社 2019年10月7日「2018年 国内RPAソフトウェア市場シェアを発表」
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ45572319
1位NTTデータ:国内シェアトップクラスの実績を持つ純国産RPAツール WinActor

ITreview Grid Award 2020 Winter Leader 受賞
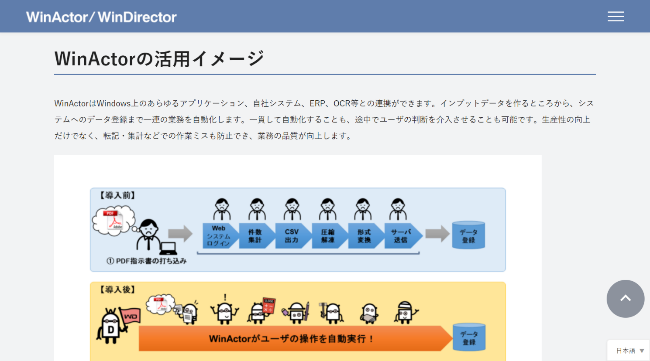
■ 製品の特長
WinActorは、エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社により開発・利用されてきた長い歴史と豊富な導入実績を持つ純国産のRPAツールです。操作の容易性、価格に加えて、純国産の安心感が幅広いユーザーに支持されています。WinActorでは、Windows上のアプリケーションの操作をプログラミング不要で学習させ、自動実行することができます。またWinActorを一元的に管理・統制するための運用ツールWinDirectorも提供されています。
■ 導入企業
公共分野をはじめ、サービス業、製造業、ソフトウェア・通信業、金融業など幅広く、約1,900社の企業で導入されています。東京ガス、J.フロントリテイリング、ヤフーなどでの利用事例があります。
■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価
NTTドコモ(情報通信業):「プログラミング不要で構築 構築後の仕様変更や追加も容易に行うことができる。外部の企業にシステム開発を委託して費用を発生させることなく、業務を実際に行っているスタッフが要件を定義してシナリオを作成したため短時間で運用を開始することができた。」
2位 UIPath:スケーラビリティに優れた外資系RPA UiPath

ITreview Grid Award 2020 Winter Leader 受賞

■ 製品の特長
UiPathはルーマニアで生まれ、2017年に日本法人を設立したベンダーです。現在は日本市場を注力市場としています。ドラック・アンド・ドロップでコーディングすることなく視覚的に開発できる開発のしやすさに加えて、拡張性、管理のしやすさなどがユーザーに支持されています。
開発環境であるUiPath Studio、管理機能を持つOrchestrator、実行機能を持つRobotなどを提供し、デスクトップ型とサーバ型、クラウド版を提供し、それらがシームレスに連携することで小規模から大規模まで幅広く対応できる高いスケーラビリティを持つ製品です。
■ 導入企業
金融業、製造業、情報・小売業、サービス業など、幅広い業界での採用実績があり、日本で約1,300社が導入しています。三井住友信託銀行、リコー、サイバーエージェントなどの事例があります。
■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価
ギンガシステム株式会社(情報通信業)「要件に合えば無償から使用することができ、使い勝手もとてもよく、RPAに興味を持った人へのおすすめのツールです。」
3位 富士通株式会社:働き方改革を支援するRPAツール 富士通 FUJITSU Software Interdevelop Axelute
ITreview 満足度:4.0/5.0(2020年2月時点)
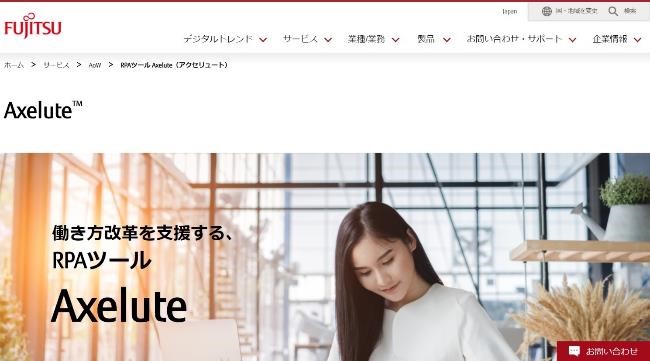
■ 製品の特長
富士通のRPAツール Axelute(アクセリュート)は、デスクトップ型とサーバ型の両方を提供しています。視覚的な画面操作で作業を記録し、画面へのデータ入力や検索結果の取得など、Windows上で行った定型作業を記録し、自動化することができます。手順書を自動で生成し、業務の引き継ぎや見える化に活用したり、エビデンスとして残したりすることもできます。
■ 導入企業
製造業、流通業などで利用事例があります。
■ITreviewに寄せられた導入企業の評価
(ソフトウェア・SI業)「他ツールに無い特色として、記録した内容からマニュアル(Excel)を自動作成できる。画面スクリ-ンショットに加え、操作部分が赤枠線で囲われ、簡単な日本語説明も付くので、業務引継ぎに活用できるだろう。」
4位 Automation Anyware:大規模エンタープライズに強い業界のリーダー Automation Anywhere

ITreview Grid Award 2020 Winter Leader 受賞
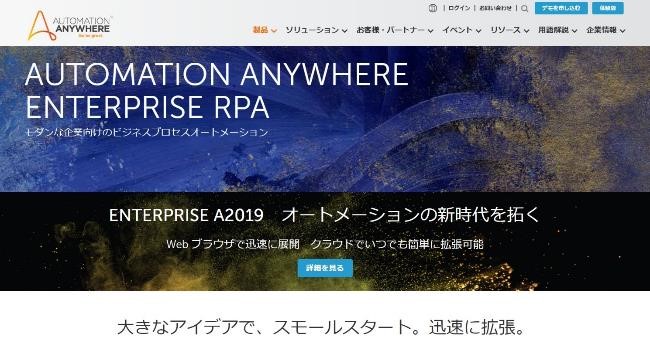
■ 製品の特長
Automation Anywhereは、簡単に使える直感的な操作、すぐにダウンロード可能な500種類以上のロボットの提供、RPAとAI/アナリティクスを組み合わせた機械学習による非定形業務の一部までを自動化する豊富な機能の提供に特徴があります。クラウド型での提供もあり、セキュリティ面、監査対応など、大規模なRPA導入を得意としています。2018年には日本法人を設立、日本市場への注力をコミットしています。
■ 導入企業
横河電機、シスコ、シーメンス、スズキ、日立製作所など、大企業を中心に、世界90ケ国以上にわたり3,500社以上の導入実績があります。
■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価
ソフトバンク株式会社(情報通信業)「定型化された作業を自動化することができ、社内の工数削減に貢献できます。」
5位 RPAという言葉を生んだ業界の老舗 Blue Prism

ITreview Grid Award 2020 High Performer 受賞

■ 製品の特長
Blue Prismは、RPAという言葉を考案したRPA業界のパイオニアです。ロボットが使うパスワードの自動変更など、高度なセキュリティを保持する機能があり、金融機関や医療機関など高いセキュリティを求められる業界での導入実績が豊富にあります。また、GoogleやIBMなどが提供するAI処理を組み込むことができ、高度な業務自動化をすることも可能です。
■ 導入企業
金融業、医療機関など、高いセキュリティとコンプライアンスが求められる業界での導入実績が豊富です。日本では、第一生命保険社、日鉄興和不動産、株式会社島津製作所、ディー・エヌ・エーなどでの利用事例があります。
■ 価格
年間約120万円~ (本番環境での最大同時実行数1つあたり)
■ITreviewに寄せられた導入企業の評価
曙ブレーキ工業株式会社(製造業)「RPAでROIを求めるなら、ロボット作りの効率化は欠かせないはず。それを実現しやすいのがBlue Prismだと実感しています。」
(https://www.itreview.jp/products/blueprism/reviews/29445)
曙ブレーキ工業株式会社(製造業)「RPAでROIを求めるなら、ロボット作りの効率化は欠かせないはず。それを実現しやすいのがBlue Prismだと実感しています。」
利用中のユーザーに評判の高いRPA 5選
ここまで紹介した5製品の他にも、それぞれ特徴を持ったRPAがあります。ここでは、ITreviewによせられたユーザーレビューの中で、評価の高いものをご紹介していきます。
国内RPAツールのロングセラー BizRobo!

ITreview Grid Award 2020 Winter Leader 受賞

■ 製品の特長
BizRobo!はRPAの概念が確立する以前からの老舗製品で、数多くの国内導入実績があります。ドラッグ・アンド・ドロップで、コーディングすることなく、視覚的な開発をすることができます。本製品は、実績豊富なRPAカテゴリーに含まれる製品と考えてよいでしょう。
■ 導入企業
サービス業、金融業、情報・通信業、官公庁など幅広い業種の国内1,560社以上の現場でさまざまな業務に適用されています。大同火災海上保険、ダイワボウ情報システム、西友、三菱重工業などでの利用事例があります。
■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価
株式会社グッドライフ(不動産業)「2~3日の研修と学習をすることで、プログラミングスキルのなかった現場が使いこなせるようになった。他のツールとは違い、見た目も作り方もわかりやすい。」
(https://www.itreview.jp/products/bizrobo/reviews/23329)
株式会社グッドライフ(不動産業)「2~3日の研修と学習をすることで、プログラミングスキルのなかった現場が使いこなせるようになった。他のツールとは違い、見た目も作り方もわかりやすい。」
無料で始められる驚きのRPA WorkFusion
ITreview 満足度:4.0/5.0(2020年2月時点)

■ 製品の特長
WorkFusion(旧RPA Express)は無償プランも提供しているRPAベンダーです。無償版のExpressプランは、全世界で25,000以上のダウンロード実績があります。有償版では、集中型管理自動化、タスクスケジューリングなど追加機能が使えるようになります。また、OCR機能でPDFや画像、HTMLなどの電子ファイルからデータを入手することも可能です。上位のEnterprise版では、AI技術が搭載され、ルールベースのRPAでは処理が難しい非定型業務の自動化もサポートしています。
■ 導入企業
無償版のExpressプランは、全世界で25,000以上のダウンロード実績があります。
■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価
株式会社スプーン(製造業)「RPA関連のサービス・ソフトウェアを、無料でまず始めたいという方には、使ってみることをおすすめします。ベンチマークの一つとして必ず入れておいたほうが良いと思います。」
(https://www.itreview.jp/products/pra-express/reviews/22012)
国内初のクラウドRPAとしてグッドデザイン賞を受賞 BizteX cobit
ITreview 満足度:3.7/5.0(2020年2月時点)

■ 製品の特長
BizteX cobitは、クラウド型RPAのため、すくに利用することができます。アカウント発行数も無制限で、全社で自動化を推進できます。直感的な簡単操作で、誰でも作業ロボットが作成でき、業務の作業スピードのアップと品質向上が実現できます。
■ 導入企業
広告業、人材サービス業、不動産業、クラウドファンディングなど、サービス業を中心に導入が進んでいます。JTBコミュニケーションデザイン、SBペイメントサービス、マクアケ、廣済堂などでの利用事例があります。
■ 価格
初期費用:30万円、ロボット稼働ステップ数別に月額プラン(エントリープラン 10万円/月~、スタンダードプラン 20万円/月~、プロフェッショナルプラン 30万円/月~)
■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価
トラベルブック株式(情報通信業)「非エンジニアでも利用できる直感的なUIと、料金の手軽さが導入の決め手になりました。社内メンバーに触ってもらった際も、「これならできそう」という第一印象をもつ人が多いようです。」
必要な自動化機能だけを選んで導入できる Autoブラウザ名人、Autoジョブ名人、Autoメール名人
ITreview 満足度:3.5/5.0(Auto ブラウザ名人、2020年2月時点)

■ 製品の特長
Autoジョブ名人は、PC操作を自動化するツールです。ブラウザ操作を自動化するAutoブラウザ名人、メール操作を自動化するAutoメール名人と合わせ、定型的なルーティンワークを自動化することで、生産性と作業品質の向上を実現する業務自動化ソリューションです。必要な製品だけを購入することで、低価格から導入できます。
■ 導入企業
RPAソリューションの導入企業数は800社以上。国分ビジネスエキスパート、兵庫県公園緑地課、ヤクルト、LIFULLなどでの利用事例があります。
■ 価格
Autoジョブ名人;開発版 年間60万円~、実行版 年間18万円~ 他
Autoブラウザ名人:開発版 年間28万円~、実行版 年間8万7千円~ 他
Autoメール名人;開発版 年間14万円~、実行版 年間24万円~ 他
■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価
伊藤忠丸紅鉄鋼(商社)「 Autoブラウザ名人 は、Web操作の記録・ロボット実行による自動化が進めることが出来るため、単純な作業となりがちなWebでの業務が効率化出来る。」
コストパフォーマンスに優れたRPAツール JobAuto
ITreview 満足度:4.5/5.0(2020年2月時点)
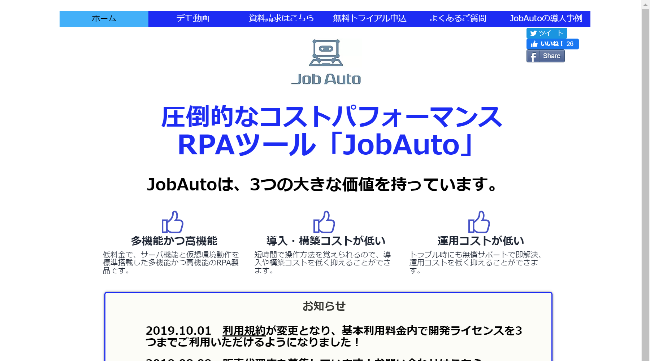
■ 製品の特長
画面上で操作したい箇所を選択し、操作手順を設定するだけで、普段PCを使った業務手順の自動化を実現できます。初期費用が無料で運用月額料金内に標準でロボットのソース管理、スケジュール管理、実行ログ管理などのサーバ機能もついており、導入コストを低く抑えることができます。
■ 導入企業
アイドマ・ホールディングス、東海時計商事などでの利用事例があります。
■ 価格
80,000円/月~
■ ITreviewに寄せられた導入企業の評価
(人材サービス業)「今まで人力で毎日おこなっていた単純業務をロボットに実行させることで、工数を劇的に削減することに成功しました。」
(https://www.itreview.jp/products/jobauto/reviews/35514)
(人材サービス業)「今まで人力で毎日おこなっていた単純業務をロボットに実行させることで、工数を劇的に削減することに成功しました。」
RPA導入を失敗しないための選定ポイント
さまざまなRPA製品を紹介してきましたが、ここで留意すべきことがあります。他のITツールと同様、RPAもまた、「魔法の箱」ではないということです。RPA導入の効果をあげるには、まず自社内の業務分析が必要です。
どんなシステムを使い、どんな作業をすることで業務を回しているのか、現状のプロセスを可視化し、その中でどの部分に作業工数がかかっているか、ボトルネックは何なのかを分析し、どこにRPAを適用して自動化するのが効果的なのかを検討します。場合によっては、プロセスの見直しも重要です。RPAを適用した業務が明確にしたうえで、その対象業務に適したRPAを選定することが必要です。

RPAの選定ポイントとしては、次の点に留意してください。
1. 自社で整理した業務フローが実現できる製品か?
単純作業の膨大な繰り返しに威力を発揮するRPAですが、一般に人の判断が求められる作業や、ルールが明確に定まっていない業務は苦手です。例えば、条件によって行う処理を分岐させることはできるか、例外が発生して停止した場合はきちんと通知が届くか、判断が求められるところでは制御を人間に渡すことができるか、といった点を確認しておきましょう。
また、RPAとAIの組み合わせでより高度な自動化を行うなどの取り組みも進んでいます。RPA以外のツールとの連携も含めて、自社で整理した業務フローが実現できる製品なのか否かを見極めることが必要です。
2. 自社で作成・運用できそうなロボットの開発、メンテナンス方法を提供しているか?
各業務部門で日々行われているさまざまな業務を自動化することで、全体で大きな作業時間の削減が期待できます。そのため、RPAの開発を業務部門が担うケースも多くなります。情報システム部門に比べて、専門知識に乏しい業務部門の担当者が簡単な画面操作で開発ができるか、また自動実行などの運用が容易にできるかを、あらかじめ調べておきましょう。
業務部門に開発を任せる場合にも、環境構築は情報シスが担う、全社で共通に使う部品は提供する、各部門で開発するためのガイドラインや活用テクニックを共有するなど、再利用性を高めて開発効率をあげたり、将来のメンテナンスを容易にする工夫も重要です。
3. デスクトップ型/サーバ型/クラウド型 など、自社の環境とコストに見合うものはどれか?
RPAを動作させる環境は、製品によって違いがあります。デスクトップ型は、PCごとにRPAツールをインストールして個々のPC上で動作させます。PC1台からRPAを導入できるため、小規模での導入に向いていますが、開発したロボットの社内での共有が難しい面があります。
一方サーバ型は、各人のPCにインストールする必要はなく、サーバ上でデータを処理します。開発した多くのロボットを一括で管理できるため、全社で大規模に展開するのに向いていますが、一般にデスクトップ型よりも初期導入コストは高くなります。自社でサーバを準備しなくても、クラウド上に動作環境を用意しているRPAもあります。自社の環境とコストに見合った製品を選択しましょう。
4. 自社での展開拡大に見合った拡張性を持った製品か?
RPA導入に際しては、小さく始めて大きく育てるアプローチが効果的です。特定の部門で導入して、その効果を示すことで、他部門での導入機運が高まります。最初の部門導入の後に全社展開することを見越して、規模の拡大が容易にできる製品なのか、将来的な全社展開時のコストはどうなるのかなど、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
自社に適切なツールを絞り込んだうえで、自社要件に合うかベンダーとのすり合わせを!
本記事では、RPAの国内市場の動向、実績豊富なRPA 10製品の特長、導入時に留意すべきポイントなどについてお話してきました。これらのポイントに留意しながら、自社にあったRPA製品の絞り込みを行い、仕様や要件の確認ができる準備をしたうえでベンダーとのすり合わせを行うことが重要です。
ベンダーからの売り込み文句をうのみにせず自社に最適なツールを選定することが、導入・開発、そして本番後の運用を含めて、RPA導入後にかえって余計な作業が増えてしまうトラブルを防ぐことにつながります。
また、RPAが一定の普及をした現在、今度は、「野良ロボット」の保守・障害対応が問題になり始めています。エラーになって動いていない、間違った動きをしているのに誰も気がつかない、担当者が異動した後に誰も知らないままに勝手に動いてメールを発信してしまったなど、デジタルロボットの管理が不十分だとさまざまな問題が発生します。
サポートの有無や開発や運用ガイドラインのひな形の提供など、製品の機能以外のサービスについても、ベンダーからよく話を聞いて、より効果的なRPA導入を進めるとよいでしょう。
RPAの効果的な活用を通じて、「デジタルロボット」を適材適所で使いこなし、人手不足の解消を目指しましょう。
RPAツールの評判をチェックする
紹介したRPAツール以外にもどのような製品があるか、また顧客満足度の高いツールは何かを具体的に知りたい方は、下記のITreview Grid(顧客満足度の高い製品が分かる四象限マップ)から気になる製品をチェックしてみてください。
投稿 実績豊富なRPA製品10選|市場シェアや評判の高いツールを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【初心者向け】VPNでセキュリティを強化する仕組みとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>VPNは、大きく分けて「インターネットVPN」と「IP-VPN」の2種類に分かれます。「インターネットVPN」は、公衆のインターネット回線を利用する仕組みです。一方の「IP-VPN」は、専用回線を複数の法人・個人で共有する仕組みです。
本記事では、より一般的でコストの低い「インターネットVPN」がセキュリティを強化する仕組みを詳しく解説します。最初に、インターネット通信が抱えるセキュリティリスクを見てみましょう。
インターネット通信におけるセキュリティリスクは?
インターネット通信におけるセキュリティリスクは、大別すると2つあります。「機密情報が盗聴されるリスク」と「サイバー攻撃を受けるリスク」です。
1.機密情報が盗聴されるリスク
ネットワーク上を流れる情報の盗聴はプロの手にかかれば難しいことではありません。ネットワーク上を流れるパケット(通信データを細かく分割したもの)は、パケットスニファリングという技術を用いれば、盗聴することが可能です。そのため、インターネットを経由して送受信した機密情報が盗聴され、情報漏えいするリスクがあります。
2.サイバー攻撃を受けるリスク
インターネット通信では、通信データ内に「接続元のIPアドレス」と「接続先のIPアドレス」が含まれています。そのため、データを送る途中で、悪意を持ったサイバー犯罪者に傍受された場合、データの内容だけでなくIPアドレスが知られてしまいます。
デバイスのIPアドレスが分かると、機密情報を抜き取られることに加え、ウイルスを含む不正なファイルを送りつけられるといったサイバー攻撃を受ける可能性があります。
通信の傍受を防ぐトンネリング技術とは?
これらのインターネット通信の抱えるリスクを軽減して、セキュリティを強化するために期待されているのが、VPNのトンネリング技術です。トンネリングとは、データの送信元(自分)と送信先(相手)のIPアドレスを含めたデータ(手紙の内容)を暗号化することです。
トンネリングにより、通信が傍受された場合でも、データの内容もちろん、送信元と送信先も分からないので、サイバー攻撃のリスクは大幅に軽減されます。また、トンネリング技術により通信を暗号化することを、カプセル化といいます。通信データが、暗号化カプセルで保護されているイメージです。
トンネリングに欠かせないVPNサーバとは?
カプセル化によるトンネリングを行うためには専用の機器が必要です。その機能を担うのがVPNサーバです。VPNサーバは、VPN中継サーバとも呼ばれデータのカプセル化と同時に、送受信データの中継をする役割を果たします。
前述の通り、VPNサーバでのデータのカプセル化により、送信元と送信先のIPアドレスも暗号化されます。そのため、このままでは「宛先のない手紙」と同様、目的地にたどり着けません。
そこで、VPNサーバでは、新たに自分(送信元VPNサーバ)のIPアドレスと、送信先VPNサーバのIPアドレスが追加されます。
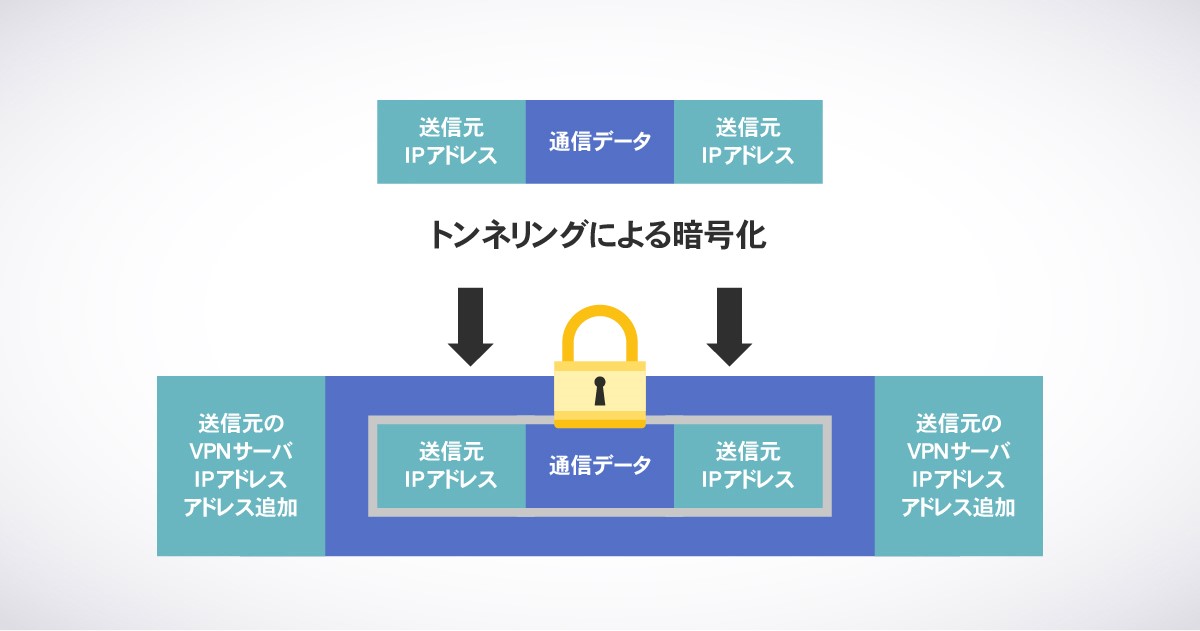
VPNによる通信では、送信元だけでなく送信先にもVPNサーバの設置が必要です。尚、VPNサーバを設置する場合は、ルーターにVPNサーバとしての機能を持たせるのが一般的です。
VPNによる通信では、送信元だけでなく送信先にもVPNサーバの設置が必要です。尚、VPNサーバを設置する場合は、ルーターにVPNサーバとしての機能を持たせるのが一般的です。
VPNを企業などの法人で使用する場合、本社と全国の支社など、各拠点にVPNサーバを設置することで、拠点間のVPN通信が可能となります。
実際にどうやって通信するの?
では、VPNサーバを使ってどのように通信が行われるのでしょうか。東京に本社があり福岡に支社を持つ企業が、本社と支社にそれぞれVPNサーバを設置した場合を見てみます。福岡支社の鈴木さんが、東京本社の「顧客データ管理サーバ」に接続して、顧客データの修正を行っているとします。
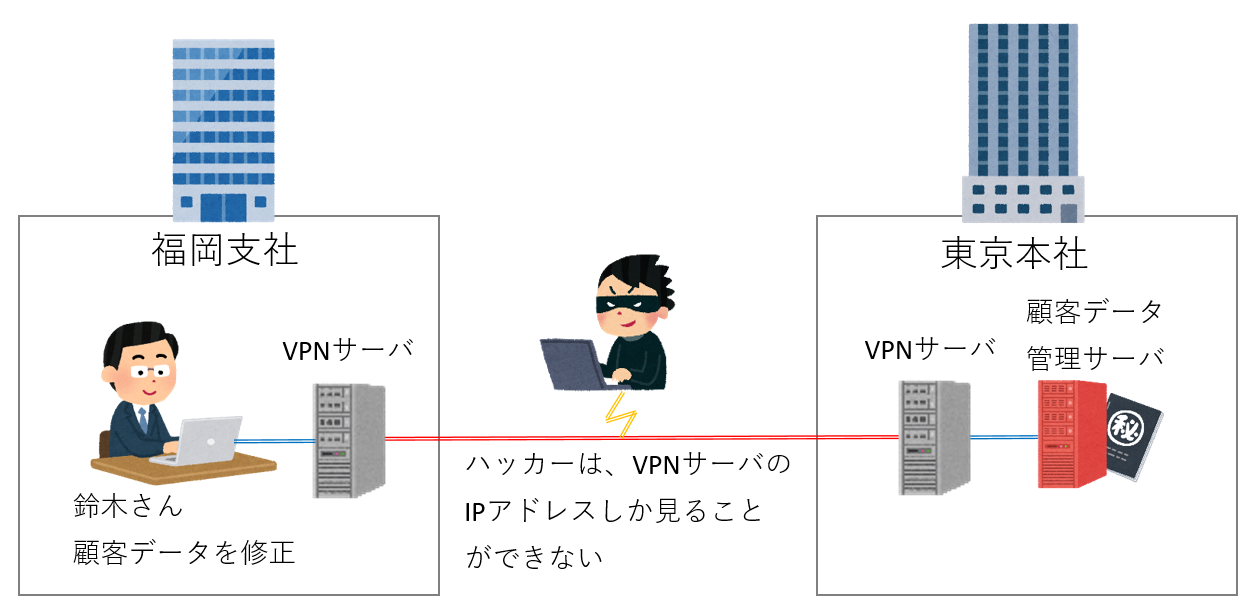
鈴木さんのPCから送信される「顧客データ」は、社内LAN経由で福岡支社のVPNサーバに送られます。そしてVPNサーバで、カプセル化(暗号化)されて、インターネット経由で送り出されます。
従って、万一インターネット上でサイバー犯罪者がこの「顧客データ」を傍受した場合でも、カプセル化されている「顧客データ」を見ることはできません。同様に、「顧客データ」の改ざんも不可能です。
サイバー犯罪者が分かるのは、東京本社と福岡支社に設置された“VPNサーバ”のIPアドレスだけです。犯罪者には、データとして何が送信されたのか、その内容が機密情報かどうかも分かりません。同時に、機密情報が保存されている顧客データ管理サーバのIPアドレスも外部に漏れることはありません。
カプセル化によりサイバー攻撃を受けなかった「顧客データ」は、東京本社のVPNサーバに到着後、暗号化を解かれて復元されます。そのデータは、安全な社内LAN経由で「顧客データ管理サーバ」に送られます。
この事例の通信経路で、社内LANで構成されているのは、東京本社内と福岡支社内のみです。しかし、VPNによるセキュリティ確保で、仮想的に東京本社と福岡支社の両方を含めた大きな社内LANがあると見なすことができるのです。
また、テレワークなどで社外の社員が使用するPCにVPNソフトをインストールすれば、送受信データをカプセル化(暗号化)でき、企業にあるVPNサーバまでVPN接続することが可能です。
IPアドレスを隠して情報漏えいのリスクも軽減
VPNを使用すると、万一、通信を傍受されてもその送信元と送信先のIPアドレスは特定されません。傍受された場合に判明するのは、通信を中継するVPNサーバのIPアドレスだけです。機密情報が保管されているサーバのIPアドレスは暗号化されているため特定されることはありません。
機密情報が保管されているサーバのIPアドレスを保護することは、セキュリティを強化する上でも重要な要素です。なぜなら機密情報が保管されているサーバのIPアドレスが分かると標的型攻撃の対象になり、情報漏えいのリスクが高まるからです。
まとめ
インターネット通信では、「機密情報が盗聴されるリスク」と「サイバー攻撃を受けるリスク」があります。
しかし、VPN接続を行うことで、送受信データの内容と各デバイスのIPアドレスを保護することができるので、上記のリスクを軽減することが可能です。
インターネットを経由して個人情報などの機密情報を送受信する場合には、必ずVPNを利用しましょう。
また、VPNサービスを選定する際には、セキュリティ機能だけではなく、管理機能のしっかりとした「ビジネス向け」のVPNサービスをおすすめします。ビジネス向けのVPNの評判や口コミは以下にまとめてご紹介しておりますのでご確認ください。
また、 ITreviewではVPNがどのような企業に利用されているか、またどのような評価がなされているかが分かる口コミを公開しています。またどの製品の人気が高いかがひと目で分かる比較表なども公開中です。ぜひ下記のポジショニングマップから気になる製品をチェックください。
投稿 【初心者向け】VPNでセキュリティを強化する仕組みとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 法人向けオンラインストレージをチェック!管理機能の充実とコスパがいいのはどれ? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そんな時に便利なのがオンラインストレージ。オンラインストレージはインターネット上にデータを保管することで、自社でファイルサーバ等の保存環境を構築することなくデータの保存、共有が可能となります。
現在、各社からさまざまなオンラインストレージサービスが提供されています。無料・有料、提供される機能もサービスにより千差万別です。これから自社でオンラインストレージの導入を検討されている方は、「どのような機能が必要か」「どのくらいの費用が掛かるのか」といったところで悩まれるのではないでしょうか。
本記事では人気のオンラインストレージを管理機能とコストで比較していきます。
法人向けオンラインストレージに必要な管理機能は?
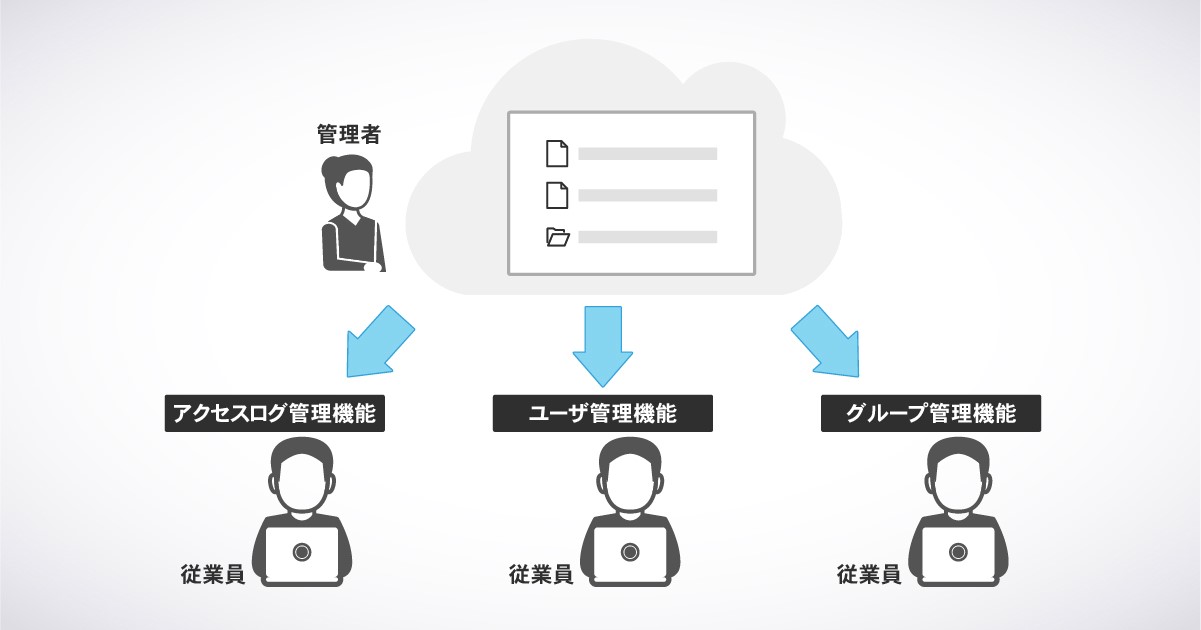
法人向けのオンラインストレージでは、ほとんどの場合「管理者」と「ユーザ」を設定することができます。情報システム部門がある企業では、情報システム部門の方が「管理者」として、利用者である従業員を「ユーザ」を管理することになるでしょう。
オンラインストレージは、データを自社ではなくサービス提供者が運営しているデータセンターに保存し、クラウド経由でサービスにログインするという特性上、ユーザや権限の管理が重要になります。
そのような特性を踏まえ、企業でオンラインストレージを導入する上で必要となる管理機能をまとめました。
1.ユーザ管理機能
企業でオンラインストレージを導入する際に最も気を付けなければならないのが、社外への情報漏えいのリスク対策です。
企業では新入社員や退職者等の従業員の出入りも発生します。例えば、退職者から適切なタイミングでユーザ権限を剥奪しないと、情報漏えいが発生するかもしれません。また、従業員数が多い企業でオンラインストレージを導入する場合、ユーザ登録を一括で行えないと登録作業に大きな負担がかかってしまいます。企業でオンラインストレージを導入するには、スムーズなユーザー登録、権限管理ができるサービスをおすすめします。
2.グループ管理機能
企業の規模によってはユーザー管理に加え、部署毎の「グループ管理」も必要な機能となります。重要度の高い開発や人事など機密情報については、アクセスできる部署を限定したい場面が多々あります。アクセス権の管理をユーザー毎に行うと作業負担がかかり、ミスも発生するかもしれません。しかし、部署毎に一括で権限管理できれば、その心配はありません。企業でオンラインストレージを導入する際には、グループ毎に細かなアクセス権限を設定できることも選定のポイントになります。
3.アクセスログ管理機能
企業でオンラインストレージを利用するなら、管理者がコンソール画面などで誰がどのファイルにアクセスしていたかを確認できる「アクセスログ管理機能」も欲しい機能です。アクセスログを確認できれば、万一の情報漏えいやデータ消失などが起こった際の原因追及をスムーズに行うことができます。
また、オンラインストレージを使って、社外の方とのファイル共有を行うケースでも、アクセスログを確認できれば安心です。
法人向け人気のオンラインストレージの管理機能とコストを紹介
ここからは、以上のポイントをふまえたうえで、法人向けに人気があるオンラインストレージについて管理機能とコストを比較して、ご紹介していきます。
1.Google Drive
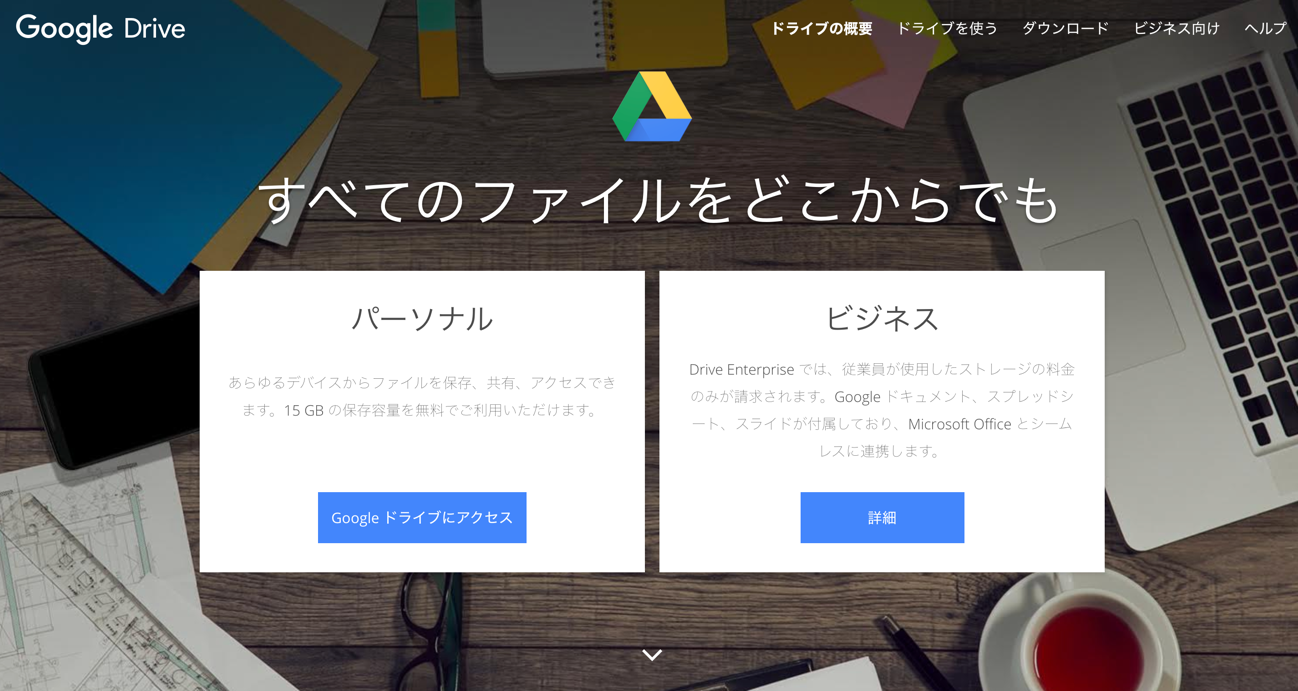
GoogleからリリースされているオンラインストレージであるGoogle Driveは個人利用されている方も多いのではないでしょうか。G Suiteと呼ばれる法人用オンラインストレージを提供しており、ユーザーあたり月額680円からと、リーズナブルな価格設定となっています。
一元化された管理コンソールを利用したユーザーの追加削除や、グループの設定によるユーザー管理が可能です。コンソールからセキュリティ機能の設定やエンドポイント(どのデバイスからアクセスしているか)といった情報を管理可能です。
価格は、1ユーザーあたり、Basic月額680円、Business 月額1,360円、Enterprise 月額3,000円となっています。なお、アクセスログの管理機能はEnterpriseプラン以上に実装されます。
2.Box Business
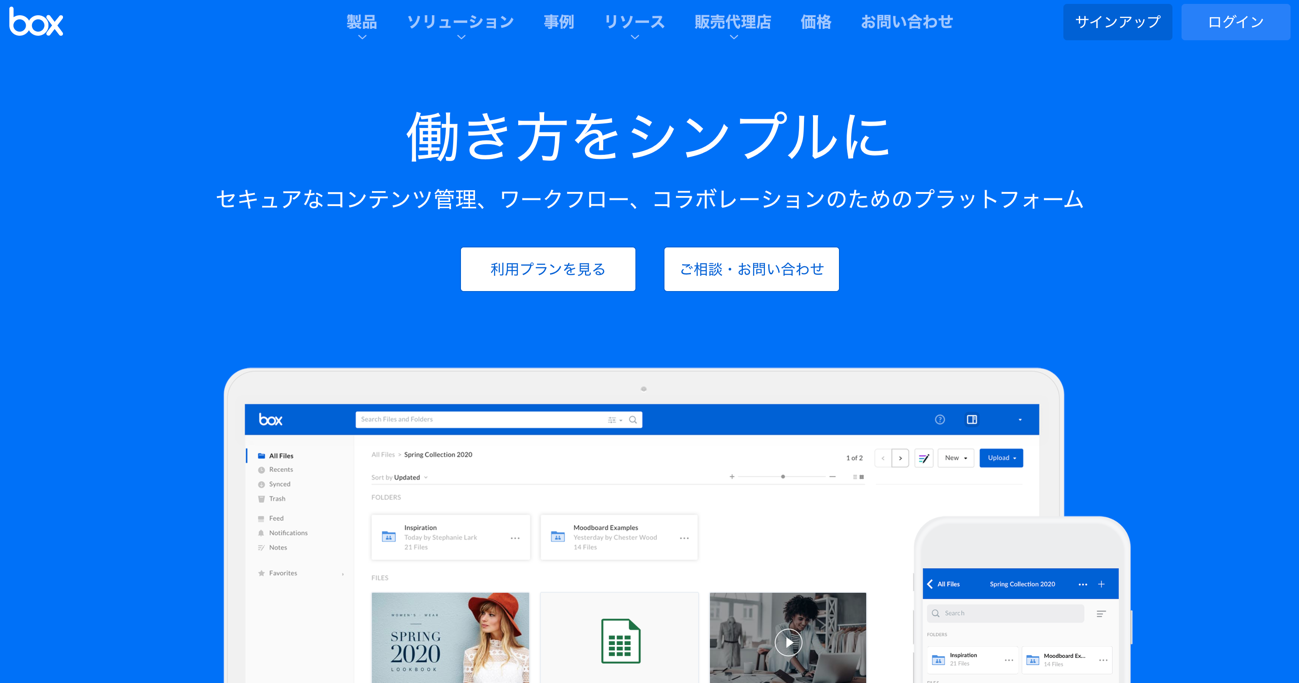
法人向けのBusiness以上のプランでは容量無制限、最大ファイルサイズ5GBと大容量ストレージを利用できます。また、セキュリティ機能に定評のあるオンラインストレージです。
管理機能面としては、リストファイルのアップロード、ダウンロードによるユーザーの一括編集、グループ管理者の設定による権限移譲(グループ内の権限管理についてはグループ管理者に任せる)ことが可能となっています。一方、アクセスログ管理の機能としては標準で提供されておらずBusiness Plus以上の上位プランのみでの提供となっています。
価格は、1ユーザーあたり、Business 月額1,800円、Business Plus 月額3,000円、Enterprise 月額4,200円となっています。
3.DropBox Business

オンラインストレージの草分けともいえる「Dropbox」は、無料で気軽に導入可能なサービスです。法人利用を想定した「Business Standard」と「Business Advanced」の2種類がリリースされています。
ユーザーの追加削除といった基本的な機能はどちらのプランにもついていますが、閲覧者履歴やアクセスログ管理、管理者役割の階層化といった機能はAdvancedプランのみの提供となります。
価格は、1ユーザーあたり、Standard 月額1,250円、Advanced 月額2,000円となっています。
4.AOSBOX Business

AOSBOX Businessは、ユーザー単位の契約ではなく、ストレージの容量単位で契約するスタイルのオンラインストレージです。
ユーザー登録については、メールで招待、手動で追加に加えCSVファイルをアップロードすることで一括登録も可能です。
管理者側からコンピュータやユーザーを一時停止、削除することが可能となっており、万一の盗難時などの対応も万全です。
また、ファイルへのアクセスや削除など、ユーザーが実行した操作ログを管理者が閲覧できる監査機能も利用できます。「スマートレポート機能」で、把握しておきたいストレージの状況をメールで定期的に通知することもでき、管理者の負担を軽減させることができます。
価格は100GBで10名まで使えるコースが月額1,666円と、利用人数によっては非常にお値打ちに使えるサービスとなっています。
5.DirectCloud

DirectCloudはユーザー数無制限のオンラインストレージです。価格が30,000円/月~と、少し高めですが、利用人数が10人でも100人でも価格は同じなので、例えば100人で使えばなんと一人当たりのコストは300円となります。
管理機能としては、ユーザー登録はCSVファイルによる一括登録ができ、アクセスログ管理では業界トップクラスの162種類のログを取得できます。さらにスタンダードプラン以上を利用する場合には、Amazon OpenSearch Service(注1)の機能を使って、大量のアクセスログを瞬時に表示することが可能です。
※注1)Amazon OpenSearch Serviceは、ログ分析、リアルタイムのアプリケーションモニタリングなどを利用できる分析エンジン。
価格プランは、スタンダード(500GB 月額30,000円)、アドバンスド(1TB 月額50,000円)、ビジネス(3TB 月額90,000円)、プレミアム(10TB 月額180,000円)、エンタープライズ(30TB 月額300,000円)の5種類です。
10名以下のスモールビジネスの場合、他のサービスに比べ割高となる可能性がありますが、従業員数が多い企業であれば、管理機能の充実度も高くおすすめのサービスといえます。
法人でオンラインストレージを使うなら管理機能が充実したサービスをおすすめします。
本記事では、企業でオンラインストレージを選ぶ際のポイントとなる「管理機能」「コスト」について5つのサービスの比較を行いました。やはり、企業でオンラインストレージを使うなら、さまざまなリスクに備えて、管理機能がしっかりしたサービスを利用することをおすすめします。
コスト面においては、一見割高にみえるプランも、自社の状況によってはお値打ちに使える場合もあります。用途や利用人数にあったオンラインストレージを選びましょう。
下記では、ご紹介した5つのサービス以外の法人向けオンラインストレージもご紹介しています。ぜひ参考にしてください。
投稿 法人向けオンラインストレージをチェック!管理機能の充実とコスパがいいのはどれ? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 無料Wi-FiでもVPNを使うと安全安心! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]> 引用元:2017年 公衆無線LANサービス利用者動向調査(株式会社ICT総研)
https://ictr.co.jp/report/20170921.html
また、近年の訪日外国人旅行者の増大の影響もあり、無料のWi-Fiスポットは今後も増加することが予想されます。しかし、無料Wi-Fiにはさまざまなリスクが潜んでいます。
本記事では無料Wi-Fiを使用する上でのリスクとその解決方法をご紹介します。あわせて、記事の後半では無料のWi-Fi環境でも利用できるVPNサービスもご紹介します。
無料Wi-Fiを使用するリスク
商業施設や病院、宿泊施設などで開放されているWi-Fiスポットの大半は、安全に考慮されていますが、提供元が特定できないような正体不明のWi-Fiスポットでは、通信データが暗号化されていない可能性があります。
無料Wi-Fiを使用する上で気を付けるポイントが2つあります。
1.盗聴
インターネットはオープンなネットワークなので、ネットワーク上に流れるデータは第三者に盗聴される可能性があります。ネットワーク上のデータを盗聴するスニファリングという手法を使えば、情報を盗み取ることが可能です。プロの手にかかれば難しい作業ではありません。例えば、ECサイト利用者が入力したIDやパスワード、クレジットカード番号といった情報が丸見えになってしまう危険があります。
2.悪意のあるアクセスポイント
悪意のある第三者が設置したアクセスポイントに接続することで、通信内容をのぞき見される危険性があります。例えば悪意のある人物が、実在する無料Wi-Fiと同名または類似したSSID名(それぞれのWi-Fiを区別する名前)のアクセスポイントを設置したとします。あなたが誤ってそのWi-Fiに接続してしまうと、悪意のある人物のPCから全ての情報を盗聴される可能性があるのです。
また、悪意のあるアクセスポイントは、アカウント情報を不正に入手する目的で、実在するWebサイトの認証画面を表示させることがあります。この方法はフィッシングといわれ、IDやパスワード等を搾取する詐欺行為の一種です。搾取されたIDやパスワードがネットバンキングのものであった場合には、多額の金銭的被害に合う恐れもがあります。
無料Wi-Fiのリスク回避方法
このように無料Wi-Fiでは、常に上記のようなリスクがあります。従って、外出先でインターネットに接続したい場合には、スマートフォンのテザリング機能を使って携帯キャリアの回線に接続するか、自前の無線ルーターを活用し、原則として無料Wi-Fiは使わない方がよいでしょう。
しかしどうしても無料Wi-Fiを使用しなければならない時は、以下の事を心掛けるようにしましょう。
1.暗号化されているWebサイトのみ閲覧する
無料Wi-Fiでサイトを閲覧する際は、ブラウザのアドレスバーに注目しましょう。
ブラウザのアドレスバーが「http:」で始まる場合は暗号化されていないので、同じWi-Fiネットワークにいる他人が、スニファリングなどの手法を使って盗聴することが可能になります。
一方、ブラウザのアドレスバーが「https:」で始まる場合は暗号化されているため、同じWi-Fiネットワークにいる他人が盗聴することはできなくなります。
GoogleのWebブラウザ「Google Chrome」は暗号化されていない「http:」接続のサイトを開いたときに、「保護されていません」という警告がアドレスバーに表示されます。警告がアドレスバーに表示された時には、接続しないように注意しましょう。
2.PCのファイル共有機能を無効にする
ネットワーク経由でPCに保存されているフォルダやファイルにアクセスするために便利なのが「ファイル共有機能」です。このファイル共有機能が無料Wi-Fiを利用する場合に有効になっていると、PC内に保存されているフォルダやファイルを読み取られたり、ウイルスを仕掛けられた不正なファイルを送りこまれたりする可能性があります。無料Wi-Fiを利用する場合には、ファイル共有機能を無効にしておきましょう。
3.VPNを使用する
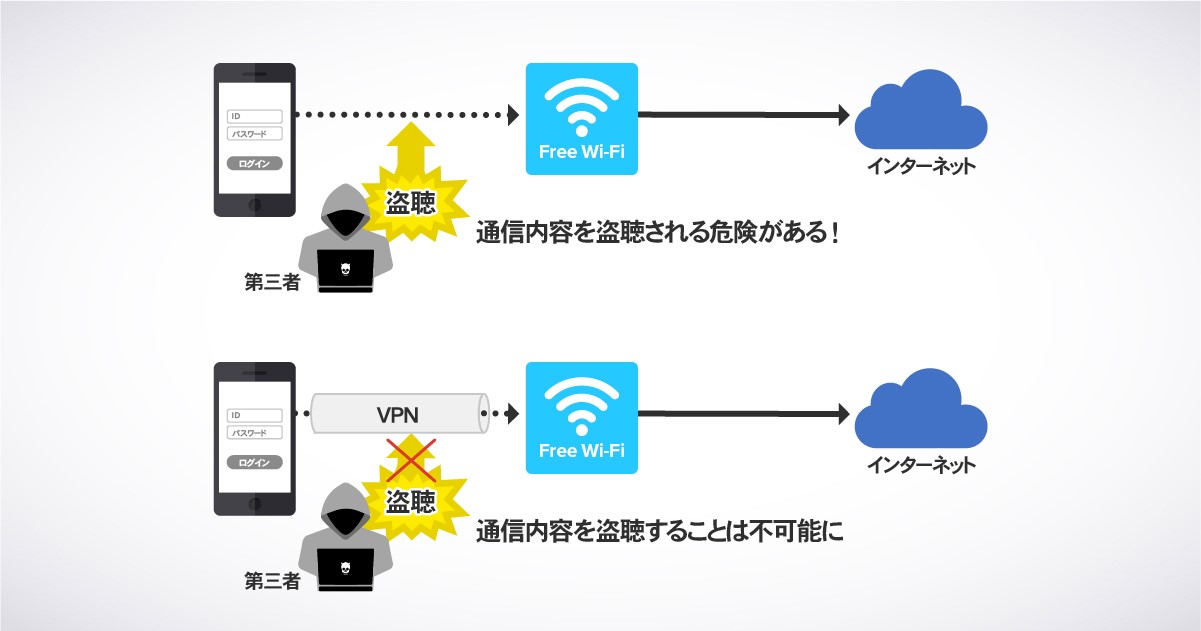
VPNを使用すると、ブラウザやアプリが個別に暗号化通信を行うのとは別に、通信経路を丸ごと暗号化することができます。自身のデバイスとVPNサービス側で用意した中継用サーバ間の通信経路が暗号化されるため、盗聴の心配はなく、偽サイトに誘導される恐れも軽減できます。
「暗号化されているWebサイトのみ閲覧する」ことや「PCのファイル共有機能を無効にする」ことは操作を忘れてしまう可能性があります。しかしVPNを使用すれば、常に通信経路が暗号化されているので、人の手による操作忘れの可能性はありません。
絶対に情報漏えいすることができない、ビジネス利用の場合には、無料Wi-FiをVPNサービス経由で利用することをおすすめします。
無料Wi-Fiからでも接続できるおすすめVPNサービス
無料Wi-Fiからでも接続できるビジネス向けVPNサービスを、導入のしやすさを基準に2つご紹介します。
1.Wi-Fi Security for Business

アルプス システム インテグレーション株式会社が提供する「Wi-Fi Security for Business」は、「フリーWi-Fiをセキュアに安心して使える時代へ」のキャッチコピーにあるように、無料Wi-Fiに接続できるVPNサービスです。
Windows、iOS、Androidに対応しており、価格は、200円/月(1デバイスあたり、税別。※20デバイスから契約可能)と、導入しやすいプランになっています。
オプションでプライベートサーバを利用することも可能です。プライベートサーバを利用すると、利用中のクラウドサービス側でIPアドレスによるアクセス制限ができ、よりセキュリティを高めることが可能です。
この製品の最大の特徴は簡単でクライアントベースなため、コストがエンタープライズビジネス向けにも関わらず、投資効果が高い事です。また、業務の一環として、お客様に於ける海外サイトのプロジェクトや海外出張にて、フリーWi-Fiを使用する機会か多々あるのですが、様々なデータを扱う際に、この製品によりクライアントサイトから暗号化する方式が取れることで、安心して業務に集中できるのもポイントかと思ってます。
引用元:https://www.itreview.jp/products/wi-fi-security-for-business/reviews/36985
と、コストメリットを評価する声が投稿されています。
2.SoftEther VPN
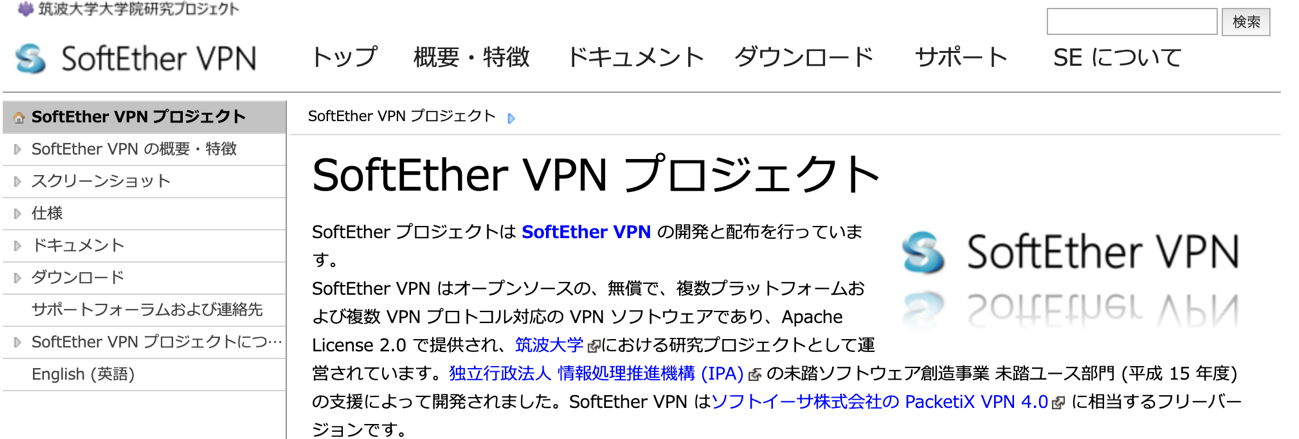
SoftEther VPNは、筑波大学大発のベンチャー企業であるソフトイーサ株式会社で開発と配布を行っている無償のVPNサービスです。
SoftEther VPNを利用するために必要なのは、専用のVPNサーバソフトウェアがインストールされた社内のサーバと、リモートアクセスを行うデバイスにインストールしたVPN クライアントソフトウェアのみです。どちらも無償で使うことが可能です。
無料で使えるだけでなく、特定のネットワーク機器ベンダーのハードウェアを用意する必要がないので、導入しやすいVPNサービスといえるのではないでしょうか。
SoftEther VPNユーザーからは、
社内のネットワーク管理でハードウェアのネットワーク機器を利用することなくVPNを設定できる優れた製品である。設定も簡単である。
引用元:https://www.itreview.jp/products/softether-vpn/reviews/18293
と、導入の容易さを評価する声が投稿されています。
無料Wi-Fiを利用する場合にはVPNサービスを利用することをおすすめします。
無料Wi-Fiを利用する場合のリスクと回避方法についてお伝えしました。無料Wi-Fiは便利ですが、盗聴などのリスクがあります。ビジネスで利用しているデバイスから無防備に利用することは避けるべきです。
ただし、無料Wi-Fiを利用する場合でも、VPNサービスと併用することで情報漏えいのリスクを下げることが可能です。今回は、導入しやすさの観点からビジネスでも利用できるVPNサービスを2つご紹介しました。
ビジネス向けのVPNサービスは他にも多く提供されています。自社に合ったVPNサービスを導入して、無料Wi-Fi環境でもVPNを使って、安全安心な通信環境を整えてみてはいかがでしょうか。
投稿 無料Wi-FiでもVPNを使うと安全安心! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 【法人対応】ファイル共有に便利なオンラインストレージ5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>メールの場合には、一旦送ってしまうと送信の取り消しができないため、送信先の間違いによる情報漏えいのリスクがあります。また、USBやCDなどの記録媒体は紛失する可能性もあり、使用を禁止している企業も増えています。
そこで、注目されているのがオンラインストレージによるファイル共有です。大容量データでもオンラインストレージを使えば、簡単にファイル共有することが可能です。
オンラインストレージを使ってファイル共有するには、まず送信したいデータファイルをオンラインストレージにアップロードし、ファイル共有リンクを取得します。多くのオンラインストレージでは、ワンクリックで取得可能です。さらに、ファイル共有リンクを作成する際には、アクセスできるユーザーの選択、パスワードや有効期限、ダウンロードを無効にするなどの設定を行うことができます。ファイル共有リンクの設定が終われば、あとは、データを渡したい相手に取得したファイル共有リンクを送るだけです。
メールの場合には、一度送ってしまえば相手にファイルが届いてしまい、取り消すことができません。しかし、オンラインストレージを使ってファイル共有した場合には、ファイルはオンラインストレージ上に保存されたままなので、ファイル共有リンクを送る宛先を間違えても、取り消すことが可能です。
最近は、オンラインストレージのサービスやプランが多くてどの様に選べば良いかわからないといった声もよく聞くようになりました。本記事では、法人でファイル共有する場合に人気のオンラインストレージを5つ紹介します。まずは、ファイル共有に使うオンラインストレージサービスを選択する上で検討が必要な6項目についてみていきましょう。
ファイル共有用のオンラインストレージを導入する前に検討が必要な6つのこと
法人でファイル共有する場合には、次の6項目を検討した上でオンラインストレージサービスを選択することをおすすめします。
1. 利用するストレージ容量
オンラインストレージサービスには、さまざまなサービスやプランがあります。一般的に無料プランのオンラインストレージサービスは利用できるストレージ容量に制限があります。無料プランのまま利用し続けるとストレージ容量が不足して、ファイル共有ができないなど、ビジネスに支障をきたす可能性があります。
法人であれば、業務に支障のない十分なストレージ容量を使用できるサービスやプランを利用するべきでしょう。あらかじめ、使用するストレージ容量がどのくらいになるのか予測を立てることが必要です。
2. 利用するユーザー数
法人の場合多くは、自社や協力会社のプロジェクトメンバーで仕事をしています。すべての関係者に対してファイル共有するとなると、多くの利用者登録が必要となる場合もあります。社内だけでなく社外メンバーも含めて、利用者数が何人になるか確認しましょう。
3. 情報セキュリティポリシーとの適合性
法人では新商品・サービスの情報など外部に漏れてはならない機密情報を所有しています。この場合、共有するファイルのアクセス権限を社内と社外のメンバーで別々にしなければなりません。
社員と社外メンバーでアクセスできるデータに制限を設ける、担当部署以外の社員は閲覧できるが編集はできないようにするといった、ファイルやユーザーごとにアクセス権を管理する必要があるかもしれません。
また、誰がどのような操作をどのファイルに対して行ったか確認するためのアクセスログの保管も必要かもしれません。
オンラインストレージサービスはプランによって、セキュリティ対策や管理機能が異なります。どこまでのセキュリティ機能が必要かは、自社の情報セキュリティポリシーを確認しましょう。
4. 利用するデバイス
営業職などは外出先から、オンラインストレージを利用するメンバーもいるでしょう。これらのメンバーがインターネットを介してアクセスする場合に、どのようなデバイスでアクセスするのか確認する必要があります。
インターネットブラウザ経由でオンラインストレージを利用も可能ですが、スマートフォンやタブレットに対応するアプリを利用した方が利便性が高い場合があります。デバイスによってはアプリが用意されていない場合もあるため、利用するデバイスを確認しましょう。
5. 操作性
ファイルのアクセス権設定やアプリなどの操作が難しいと、せっかく導入したオンラインストレージの機能をうまく活用できない場合があります。また、導入時に社内教育にコストがかかる場合もあります。
したがって管理者コンソールの使い勝手やファイル共有を直感的に行えるサービスであるかどうかを事前に検討することをおすすめします。操作性を確認するだけなら、まずは無料プランを試用してみるのも一つの方法です。
6. コスト
法人でオンラインストレージを導入する場合に、気になるのはやはりコストです。オンラインストレージを利用するには、月額の使用料だけでなく、管理者やユーザーの教育、利用できるデバイスの用意、インターネットに接続できる回線に費用がかかる場合もあります。
オンラインストレージの導入時には各要素にかかるコストをよく検討し、自社の必要とする機能とコストのバランスの取れたサービスを導入することをおすすめします。
法人でファイル共有をする際に人気のオンラインストレージサービス5選

法人でファイル共有するために人気のオンラインストレージサービスを5つ紹介します。
1. Box
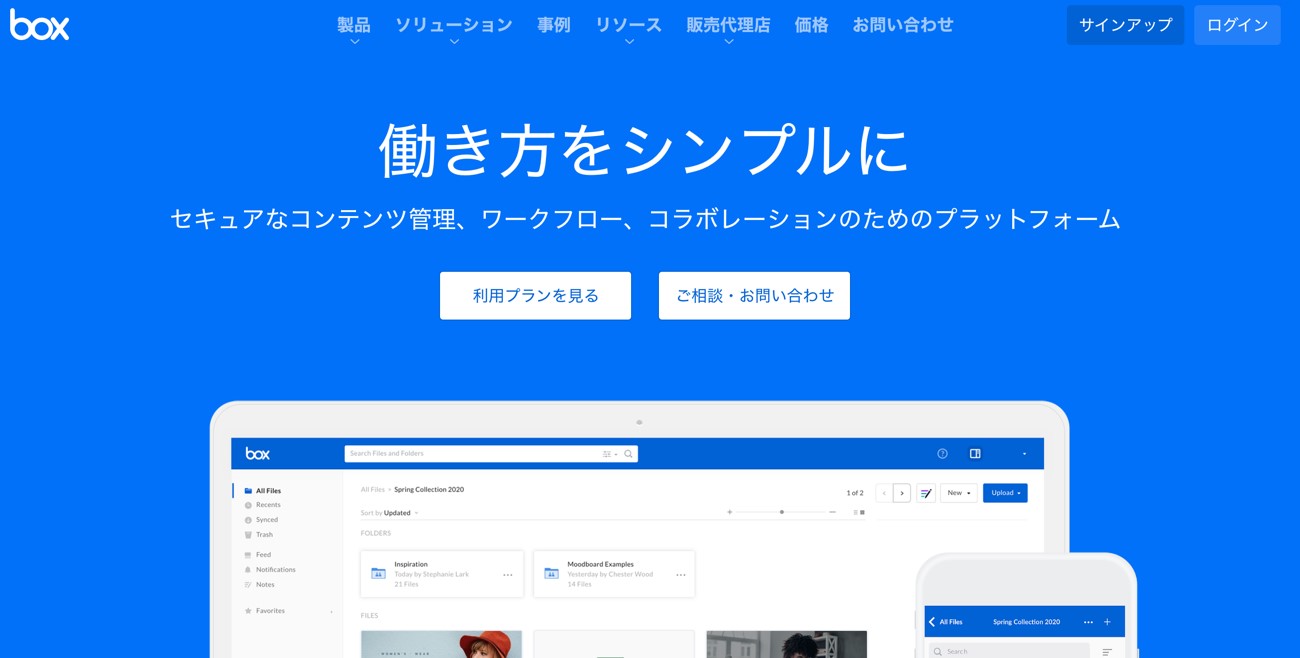
BoxはBox社が提供するオンラインストレージサービスです。セキュリティ面での機能が高く、データ容量が無制限のプランがあるなど主に企業を中心に採用されています。
各プラン別の選択基準に従った特徴は次の通りです。
| プラン名 | Starter | Business | Business Plus | Enterprise |
| ストレージ容量 | 100GB | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ユーザー数 | 最小3人~最大10人 | 最小3人~上限なし | 最小3人~上限なし 社外コラボレータ無制限 | 最小3人~上限なし 社外コラボレータ無制限 |
| 情報セキュリティ、権限管理機能 | ・ユーザーごとのアクセスレベル設定 ・バージョン追跡 ・SSL暗号化 |
※Starterの機能に加え ・データ損失防止 ・ユーザー統計と追跡 |
※Businessの機能に加え 管理役割の委任 カスタムサービス利用規約 |
※Businessの機能に加え 文書の電子透かし埋め込み パスワードポリシーの施行 |
| 対応デバイ操作性 | デスクトップ、モバイルアクセス可能 | Active Directorとシングルサインオンを統合 | メタデータ機能による検索フィルタ | ワークフロー自動化 |
| コスト | 550円 ユーザー/月 |
1,800円 ユーザー/月 |
3,000円 ユーザー/月 |
契約内容による |
(上位のプランは、下位のプランの機能がすべて含まれます)
2. DirectCloud

DirectCloud は、ユーザー数が無制限で、かつ管理者機能が充実したリーズナブルなオンラインストレージとして利用者数が増加しているサービスです。
各プラン別の選択基準に従った特徴は次の通りです。
(情報セキュリティ以降の項目については右のプランは左の機能がすべて含まれます)
| プラン名 | スタンダード | アドバンスド | ビジネス | プレミアム | エンタープライズ |
| ストレージ容量 | 500GB | 1TB | 3TB | 10TB | 30TB |
| ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 情報セキュリティ、権限管理 | ワンタイムパスワード(二要素認証) アクセスレベル設定(17段階) 大量ログ情報の表示 | 国内DC利用 サービス品質保証(SLA) AES、SSL暗号化 ウイルス検知 不正アクセス監視 操作ログ監視 | 管理者操作ログ | ||
| 対応デバイス、操作性 | ワークスペースによるデータ共有可能 エクスプローラによるファイルの直接編集 | リンクを使ったファイル送受信 | 社内拠点および社外とのファイル共有 既存システムとのAPI連携 Active Directory認証、 シングルサインオン認証 プライオリティサポート(電話、遠隔操作) 副管理者権限 | ||
| コスト | 30,000円/月 | 50,000円/月 | 90,000円/月 | 180,000円/月 | 300,000円/月 |
(上位のプランは、下位のプランの機能がすべて含まれます)
3. Dropbox Business

Dropboxは全世界で5億人が使用しており、世界的なシェアを誇るオンラインストレージサービスです。使いやすく、シンプルなデザインと、情報共有がスムーズで同期が高速なところが評価されています。
Dropboxは無料版もありますが、データ容量が2GBしかなく、法人には向いていません。法人向けには有料版のDropbox Businessをお勧めします。
各プラン別の選択基準に従った特徴は次の通りです。
| プラン名 | Standard | Advanced |
| ストレージ容量 | 5TB | 必要に応じ増加可能 |
| ユーザー数 | 3人~ | 3人~ |
| 情報セキュリティ、権限管理 | 256ビットAES暗号化 SSL/TLS暗号化 180日データ復元 | デバイスの承認 閲覧者履歴 管理者役割の階層化 ファイルイベント監査ログ |
| 対応デバイス、操作性 | デスクトップ、モバイルアクセス可能 共有・共同作業ツール 電話サポート | 代理ログイン シングルサインオンとの統合 |
| コスト | 1,250 円 ユーザー/月 | 2,000円 ユーザー/月 |
(上位のプランは、下位のプランの機能がすべて含まれます)
4. OneDrive for Business

OneDriveはMicrosoftが提供するオンラインストレージサービスです。Microsoftが提供するサービスであるため、WindowsやOffice365との連携や共同編集機能にすぐれ、初心者でも使いやすいインタフェースを持っているのが特徴です。個人向けの無料版がありますが、法人向けには有料のOneDrive for Businessが用意されています。
各プラン別の選択基準に従った特徴は次の通りです。
| プラン名 | Plan1 | Plan2 | Office365 Business Premium |
| ストレージ容量 | 1 TB | 無制限 | 1TB |
| ユーザー数 | 1人~上限なし | 3人~上限なし | 1人~300人 |
| 情報セキュリティ、権限管理 | セキュリティを維持しながら組織内外の相手とのファイル共有可能 | Plan1に加えて データ損失防止(DLP) インプレースホールドを使用した削除済み、編集済みドキュメントの保持 | Plan1に加えて 法人メールホスティングと50GBのメールボックス 独自ドメインのメールアドレス設定可能 |
| 対応デバイス、操作性 | デスクトップ、モバイルアクセス可能 Office.comによるブラウザ上でのドキュメントの作成と編集 ローカルPCの同期とオフライン編集機能 組み込み検索、検出ツール 24時間電話/Webサポート | Plan1と同じ | Plan1に加えて Officeソフトユーザー1名あたり5台のデバイスにインストール可能 Outlook、Word、Excel、PowerPoint、OneNote (Access と Publisher は Windows PC のみ) |
| コスト | 540 円 ユーザー/月 | 1,090円 ユーザー/月 | 1,360円 ユーザー/月 |
5. Google Drive
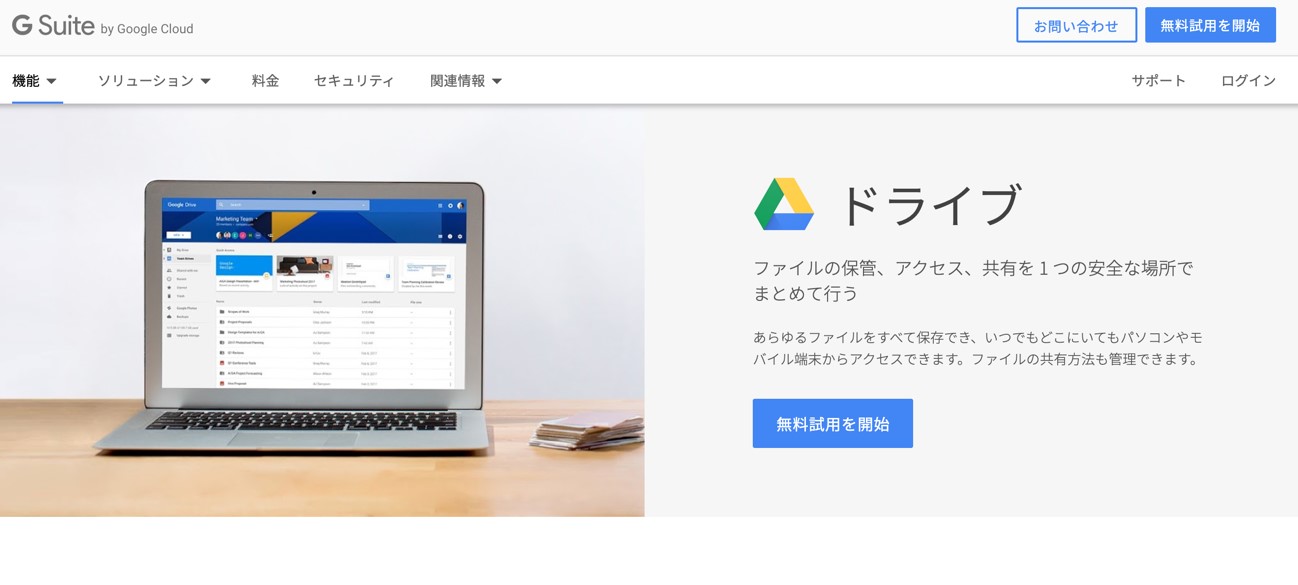
Googleが提供するオンラインストレージサービスです。Googleが提供するGmailやカレンダー、Googleドキュメントやスプレッドシート、チャットツールの「Hangout Chats」、ビデオ会議ツールの「Hangout Meet」との連携が可能です。
法人向けには、前述のツールと管理コンソール、オンラインストレージを一体で提供する「G suite」としてサービスを提供しています。
各プラン別の選択基準に従った特徴は次の通りです。
| プラン名 | Basic | Business | Enterprise |
| ストレージ容量 | 30GB | 無制限 | 無制限 |
| ユーザー数 | 5名~100名 (同時音声会議参加者数) | 5名~150名 (同時音声会議参加者数) | 5名~250名 (同時音声会議参加者数) |
| 情報セキュリティ、権限管理 | 128 ビット以上の AESによる暗号化 SSL暗号化 管理コンソールによる高度な保護機能 | VALUTによるデータ保持機能 監視レポート機能でユーザーのアクティビティを確認 | データ損失防止(Gmail、ドライブ) BigQueryによるログ解析 高度な保護機能プログラム |
| 対応デバイス、操作性 | 24時間電話、メール、オンラインサポート Googleアプリケーションが使用可能 モバイルデバイスをリモートで管理するエンドポイント管理 | G suiteを横断的に検索するSmart Search機能 | Cloud Identity Premium によるユーザー、デバイス、アプリの管理 |
| コスト | 680円 ユーザー/月 | 1,360円 ユーザー/月 | 3,000円 ユーザー/月 |
オンラインストレージ選びは慎重に!
法人でオンラインストレージを選ぶ際は、月額コストやユーザー数、データ容量だけで決めるのではなく、使用目的に合ったセキュリティや権限の管理、ユーザーの操作性や対応するデバイスについても慎重に検討する必要があります。
自社に最適なオンラインストレージサービスを選択するには、スペックを比較するだけではなく、すでにサービスを導入したユーザーの口コミを確認することもおすすめします。
投稿 【法人対応】ファイル共有に便利なオンラインストレージ5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 初めてのZoomの使い方| Zoom会議に必要な設定手順を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>速習!Zoomとは何か?
人が「Zoomで会議を行う」と言うときの、「Zoom」とは、「Zoom Meetings」のことを指している。Zoom Meetingsは、シリコンバレーのベンチャー企業ズームビデオコミュニケーションズによって開発され、2013年からサービスが開始されたクラウド型Web会議システムである。
今日、日本国内の販売パートナーも6社にまで拡大し、すでに市場で2桁のシェアを獲得していると見られ、急成長を持続しているとされる。
Zoom Meetingsは、クラウド型のサービスなので、利用のために特別な機器を導入する必要はない。インターネットに接続できるPCとWebブラウザ、音声で相手と対話するためのマイクとスピーカー、そして自分の映像を撮るためのWebカメラがあれば、Zoom Meetingsによる会議が行える。ちなみに、今日の可搬型PC(ノートPC)には、大抵の場合、マイクやスピーカー、Webカメラが内蔵されている。ゆえに、「Zoom Meetingsを使うのには、PCがあればOK!」と言えなくもない。
また、Zoom Meetingsでは、スマートフォンやタブレット用のアプリが提供されており、それをインストールすれば、スマートフォン/タブレットからもZoom Meetingsを使うことが可能になる。
Zoom Meetingsでできること
次に、Zoom Meetingsの基本機能─つまりは、Zoom Meetingsで、どのようなことが可能になるかを見ていくことにしたい。
Zoom Meetingsの基本機能(サービス)は、大きく以下の3つに分けることができる。
(1)Web会議
(2)画面共有
(3)チャット(テキストチャット)
それぞれの概要は次の通りである。
(1)Web会議
Web会議は、Zoom Meetingsのメインのサービスで、最大1,000人のユーザーが同じ会議に参加することができ、最大49人の映像を1台の端末画面に表示させることができる。また、Zoom Meetingsの場合、無料版も用意されており、40分という制限時間内であれば、最大100人が参加するWeb会議を催すことができる。
(2)画面共有
Zoom MeetingsでのWeb会議の参加者は、各自のアプリケーションや文書の画面を全員で共有して見ながら、お互いにコメントを入れるなど、共同作業を効率的に進めることができる。
(3)テキストチャット
Zoom Meetingsでは、LINEのような感覚でテキストメッセージをやり取りできる「チャット」機能も提供している。
このほか、Zoom Meetingsでは、ファイルの共有やコンテンツ検索の機能を提供しており、その閲覧を許可するメンバーを限定したプライベートグループ(非公開)を作成することもできる。
Zoom Meetings活用、初めの一歩
Zoom Meetingsのユーザーの評価は高く、とりわけ「使いやすさ」には定評がある。実際、ITreviewに寄せられたユーザーのレビュー(口コミ・評判)を見ても、「使いやすい」「簡単」という声が非常に多い。
ならば、どれほど簡単なのだろうか。その実際について簡単にチェックしてみたい。ここではWindows PCで、Zoom Meetingsを使う(Zoom Meetingsを使って会議を催す)ことを想定して、その導入手順について確認することにする。
参加に向けた導入の手順
先ほど述べた通り、Zoom Meetingsには無料版が用意されており、それを使うことでZoom Meetingsの基本機能を点検することが可能である。
導入手順(1)アプリのインストール
仮に、無料版のZoom Meetingsを使ってWeb会議を主催してみたいと考えるならば、Zoom Meetingsのクライアント用アプリ「ミーティング用Zoomクライアント」をダウンロードして、Windows PCにインストールすることから始める必要がある。
そのためにはまず、ZoomのWebサイト(https://zoom.us)にアクセスして、ブラウザ画面の最下部にある「ダウンロード」をクリックする。すると、以下のような「ダウンロードセンター」画面が表示される。

ここで、「ミーティング用Zoomクライアント」の「ダウンロード」ボタンをクリックし、インストーラーをダウンロードする。そして、インストーラーを起動してZoomクライアントアプリをインストールすれば、作業は完了となる。ちなみに、インストールが完了すると、Windowsのスタートメニューに以下のようなZoom Meetingsの起動アイコンが追加されるはずである。

導入手順(2)アカウントの作成
初めてZoomを利用する場合は、アプリをインストールしたのちに、自分専用のアカウントを作成する必要がある。それには、WindowsのスタートメニューからZoomを起動し、開いた画面の「サインイン」をクリックする。

この画面で、「無料でサインアップ」をクリックすると、以下のようなZoomのWebページが表示される。

会議の始め方(主催の方法)
Web会議を主催するには、まず、Zoomのクライアントアプリにサインインする。サインインしたアプリ画面のメニューアイコンから、「新規ミーティング」をクリックして、さらに「スケジュール」をクリックする。

それによって表示された画面で、Web会議の「ミーティング名」「ミーティング開始日時」「ミーティング時間」を設定する。
これにより、ミーティングIDを割り振ったURLが発行される。例えば、ミーティングIDが「123456789」だった場合、「https://zoom.us/j/123456789」というURLが自動的に生成される。そのURLをメールやチャットなど任意の方法で参加者に通知することで、Web会議に招待することができる。
会議に参加する手順
上に示した手順は、Zoom Meetingsを使って、会議を主催するのに必要な作業である。
実を言えば、Zoom Meetingsによる会議に(PCから)参加するだけではあれば、上述したような手順は不要である。要するに、Zoom Meetingsのアカウントを持たないユーザーでも、Zoom MeetingsによるWeb会議に参加できるというわけだ。
その参加のプロセスを非常に簡単で、Web会議の主催者から送られてきた招待メールにあるリンクをクリックすると、Zoom Meetingsの画面が自動的に立ち上げり、会議への参加が可能になる。
こんな使い方も!Zoomの便利機能
Zoom Meetingsには上述した基本機能のほかにも、便利な機能がさまざまにある。Zoom Meetingsの基本機能に慣れて“勘所”がつかめてきたなら、それらの機能を使い、Web会議の利便性をより高めることができる。
例えば、「画面レコーディング」は、便利な機能の1つだ。この機能を使うことで、Web会議の内容を録画もしくは録音することができる。レコーディングされた内容は、議事録作成用の資料として役立つほか、社内講習の教材、講義の振り返り、プレゼンテーションなど、アイデア次第で応用の幅を広げることができる。
また、Zoom Meetingsユーザーの間では、「Googleカレンダー連携」の機能に対する評価が高い。例えば、WebブラウザとしてGoogle ChromeやFirefoxを使っている場合、Webブラウザ用のZoom拡張機能を利用することで、GoogleカレンダーからWeb会議のスケジューリングを行ったり、スケジュールを削除・変更したりすることができる。
こうしてZoomの扱いに慣れていけば、「明日の会議はZoomで」と言われたときに、慌てるどころか、安堵するようになるかもしれない。
投稿 初めてのZoomの使い方| Zoom会議に必要な設定手順を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 業務の自動化に!マクロ・RPA・AIの違いと選定ポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>ここでは、自社の業務の自動化を検討している方のために、業務の自動化の方法や事例、自動化方法の選定ポイントについて説明します。業務を自動化するにはどのような方法があるのか、マクロとRPA、AIはどう違うのか、しっかり把握して自社に合ったツールを選び、業務の改善につなげましょう。
1. 業務自動化の必要性
近年、多くの企業で人手不足が深刻化、採用活動や賃金などに大きな影響を与えています。さらに、総務省「平成29年版 情報通信白書」では我が国の人口の推移として、15~64歳の生産年齢人口が減少を続けることが示されており、今後も人手不足の傾向は続くことが予想されています。
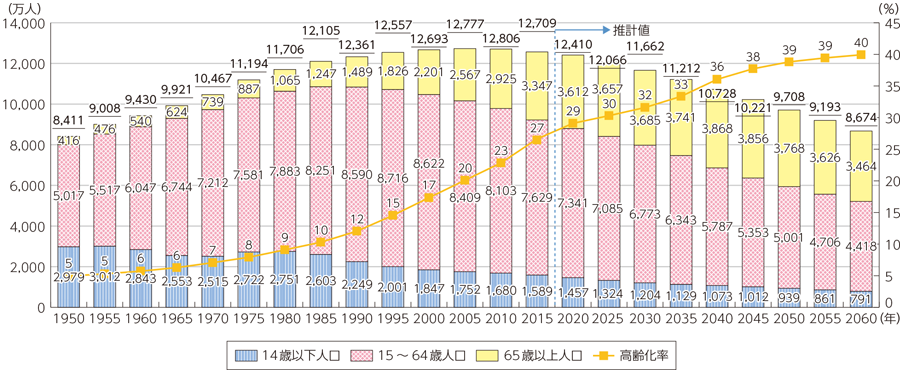
引用元:https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h29/html/nc135230.html
生産年齢人口の減少に加えて、育児や介護との両立を求める人が増加するなど労働者のニーズは多様化、過大な残業時間など労働者の労働環境の改善も求められています。これらの課題を解決しながら生産性を高め、経済を改善させるための対応として、日本政府は2019年4月1日から「働き方改革関連法」を施行しました。大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から、従業員の残業時間に罰則付きの上限規制がかけられることになり、企業は従業員の労働時間を削減しながら生産性を高めることが求められています。
この対応として有効な手段が、業務の自動化です。定型業務を正確に繰り返すことを得意とするロボットやAIと、状況に応じて柔軟に判断しながら業務を推進できる従業員、異なる得意分野を持った両者が、それぞれの特性を活かせる業務に注力することで、「残業時間の削減」と「業務効率の向上」を同時に実現することが可能となります。
2. 業務を自動化する方法(マクロ、RPA、AIの違い)
業務の自動化を検討するにあたって、よく聞かれるキーワードとして「マクロ」「RPA」「AI」の3つが挙げられます。まずは、それぞれの機能と適用業務について見ていきましょう。
(1)マクロ
マクロとは、Microsoft OfficeなどのOfficeソフトに標準搭載されている自動化技術で、Excel等の入力・集計作業の効率化の手段として利用されています。VBA(Visual Basic for Applications)というプログラム言語でプログラミングすることによって、複雑な処理も対応できる一方で、「マクロの記録」という機能を使うことでプログラムが生成されるため、簡単な処理であればプログラミングスキルが低いユーザーでも繰り返し処理を自動化することが可能となります。プロでもアマでも使える機能として、1990年代から現在に至るまで使われ続けています。
ボタン一つクリックするだけで、Excelのデータからグラフや表などを入れた報告用資料の原型を作ったり、Excelで作った宛先リスト全件にOutlookからメールを送信したり、といった使い方ができます。勤怠管理システムから出力したテキストファイルやCSVファイルを、Excelの人事情報と突き合わせて管理職は残業をゼロ扱いして給与システムで給与を算出するためのデータに変換する、といった処理を行う事も可能です。複雑な処理もVBAによるプログラミングで自動化が可能であることはメリットですが、実現するためには相応のITスキルが必要となること、自動化の対象は基本的にWord やExcel、PowerPoint、OutlookなどのOfficeアプリケーションに限定されること、といったデメリットもあります。
(2)RPA
RPA(Robotic Process Automation)は、「ロボットによる処理の自動化」と訳され、人間がPC上で行う操作を記憶して実行する技術を指します。人間を補完して業務を遂行するため、「デジタルレイバー(仮想知的労働者)」と呼ばれることもあります。業務フローを作成するような画面上の設定で作業の手順を事前に定義しておき、処理を実行すると、定義された手順に沿って作業が自動的に行われます。RPAは日本では2015年~2016年あたりから注目されるようになり、近年はツールの種類も広がってきています。RPAのツールがリリースされたのは、アメリカでは2000年代前半が多く、日本では2013年に国産製品として代表的な「WinActor」がリリースされました。
RPAツールで処理が特定の時間に実行されるようにスケジュールしておくと、定義された処理を自動的に実行してくれます。例えば、特定のWebサイトで自社製品を検索して市販価格のリストを作成したり、クラウドシステムから社内の業務システムにデータを転記したり、といったPC上で行う作業を、アプリケーションの制約なく実行することができます。
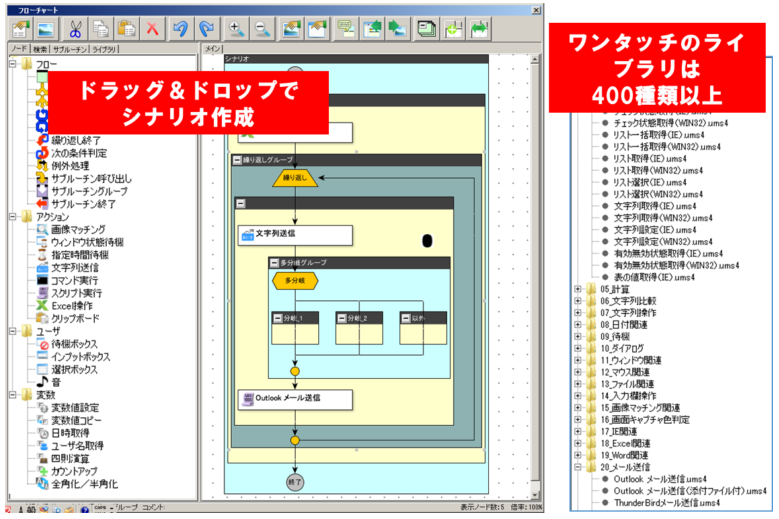
上図のイメージのように業務フローや画面上の設定で処理を自動化できるため、RPAはプログラミングスキルを必要としないのが特徴です。注意点としては、順調に稼働するようになるまでは試行錯誤の連続で意外と手間がかかることです。例えば、特定のフォルダやファイルを使用する処理では、フォルダ名やファイル名が微妙に変わったり、他の人がファイルを開いていたりといったことによって処理が止まってしまうこともあるため、運用ルールの整備や遵守の徹底が必要となります。また、特定のWebサイトや業務システムを扱う場合、レイアウトや入力欄の仕様が変わると誤作動や処理停止につながるため、仕様変更に対応してRPAの設定変更を行うメンテナンスも必要です。対象業務の選定では、頻度が高い、あるいは作業量が多い業務、これらに加え技術を必要としない単純な作業など、自動化効果の高い業務を選ぶことが重要です。
(3)AI
AI(Artificial Intelligence)は、「人工知能」と訳され、機械学習や深層学習(ディープラーニング)といった技術によってデータから学習することや、学習した情報を基に自ら考えて判断することができる存在です。AIの概念は1950年代から存在しますが、近年になってコンピュータの処理能力が高まったこと、ビッグデータが普及したこと、さらに先述の機械学習や深層学習の技術が発展したことにより、大きく発展しました。
今回、マクロやRPAと比較していますが、実はAI自体に業務を自動化する機能はありません。自動化のために活用する場合は、一般的にRPAと組み合わせたシステムとして、RPAの処理の中で必要となった判断処理にAIを使う、という方法が取られます。例えば、手書きの申込書を読み取って記載内容をデータ化してデータベースに転記するような業務をRPAで自動化する場合、どうしても人によって癖の異なる手書きの文字を正確に読み取るということは困難です。そのため、読み取りの処理の中で光学文字認識機能(OCR)にAI技術を取り入れた機能(AI-OCR)を活用し、文字をAIが判定・学習しながら読み取ることで高い識字率を実現するといった使われ方をします。
3. RPAによる業務自動化事例
業務の自動化、および効率化の実現の参考として、2つの事例を紹介します。
(1)事例①:異動時の職員情報の入力手続きの自動化(経済産業省)
経済産業省では、人事異動や担当事務変更などの情報を人事院が運営管理する「人事・給与システム」へ登録する作業を手作業で行っていました。経済産業省本省の職員約4,000人の中で、毎年約1,300人が異動し、兼務などを含めると「人事・給与システム」の登録件数は年間2,000件と膨大な件数になります。登録作業は、人事異動の都度、作業が必要になるため、定期的に作業が発生すること、ピーク時には数人がかりの作業になること、単純作業であるがミスが許されないこと、などの理由からRPAの適用が有効と判断され、RPAツール「BizRobo! Mini」が導入されました。
従来、同省では確定した人事情報をExcelファイルで管理しており、これを担当者が確認した後、職員が手入力で「人事・給与システム」へ登録し、辞令を作成していました。この「人事・給与システム」への入力作業について、まずは管理職級職員を対象とした約900件のデータを対象にRPAによる代替を行った結果、1件の登録で10分、900件で150時間の削減につながり、作業を行っていた職員は他の業務充てる時間を創出できるようになりました。手入力の時に発生していた転記のミスもなくなり、辞令交付前の確認にかかる負担も軽減されたといいます。
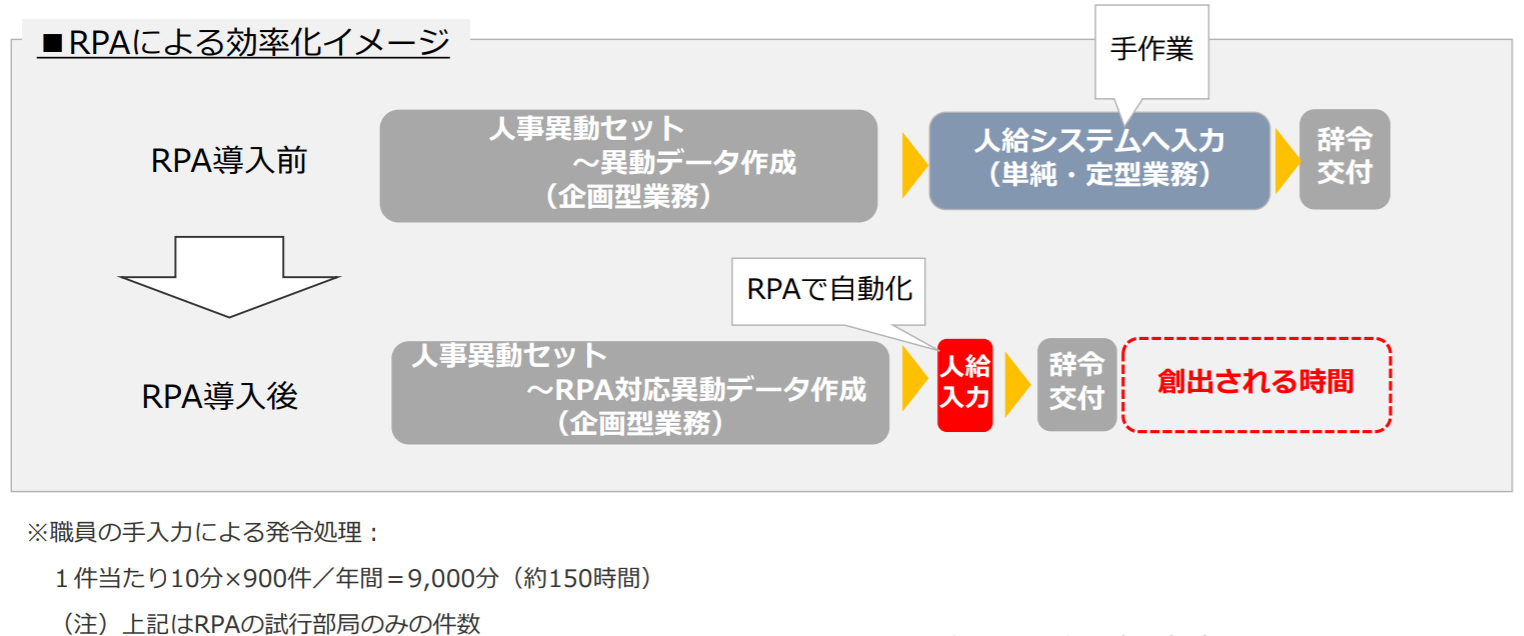
人事情報のExcelファイルは、人が登録することを想定していたため項目の分類が厳密ではなく、自由記入欄や未記入も許容されていましたが、そのままではRPAツールで処理する場合はエラーの原因となります。この対応として、導入に先立ってExcelファイルの様式をRPAツールが処理しやすい形式に変更し、データを修正する準備作業を行った上で処理が実行されました。Excelファイルが新しい様式で運用されるようになれば、形式の変更やデータの修正が不要となるため準備作業も不要となり、「人事・給与システム」への入力作業に充てていた時間の全てを他の業務に振り向けることができるようになると見込まれています。
(参考)https://rpa-technologies.com/case/case021/
(2)事例②:FAX送信業務の自動化(株式会社ウェルクス)
株式会社ウェルクス(従業員262名、資本金1,200万円)は、台東区で保育士や栄養士の人材紹介を行う企業です。登録された保育士に希望の勤務地や条件などの聞き取りを行った上で条件に合う求人があれば紹介しますが、なかった場合は条件に合う施設にFAXを送信し、施設からの問合せを受けて面接につなげています。
従来は、求職者のリストと条件を基に、事務員1名が表計算ソフトを使って数十項目の条件設定を行ってFAXを送信していました。条件設定には、送付するべき事業所の種類(保育園、幼稚園、託児所)、送付先に含める市町村、さらに送付NGな事業所はあるか、といったものがあり、求職者ごとに10回近くのフィルターを行って事業所を絞り込むという単純かつ大量の作業が必要です。作業時間は1件につき平均10分程度かかり、1月で1,042件の処理が必要で、毎月約174時間、フルタイム従業員1名の月間労働時間に匹敵する作業量があります。しかし、大量な単純作業にやりがいが見いだせず、従業員が退職してしまい、その後、社長自らが担当するも、毎日4時間の時間を作業に費やす深刻な負担となりました。
この対応として、RPAツール「Robostaff」が導入されることになり、月174時間を必要とするFAX送信の一連の作業を自動化、社長の負担も大幅に軽減されました。これまで時間を捻出できず、実施できなかった各グループの責任者との定期的なミーティングも実現し、その影響もあってRPAの導入後、同社の売上高は2.5倍に増加したといいます。
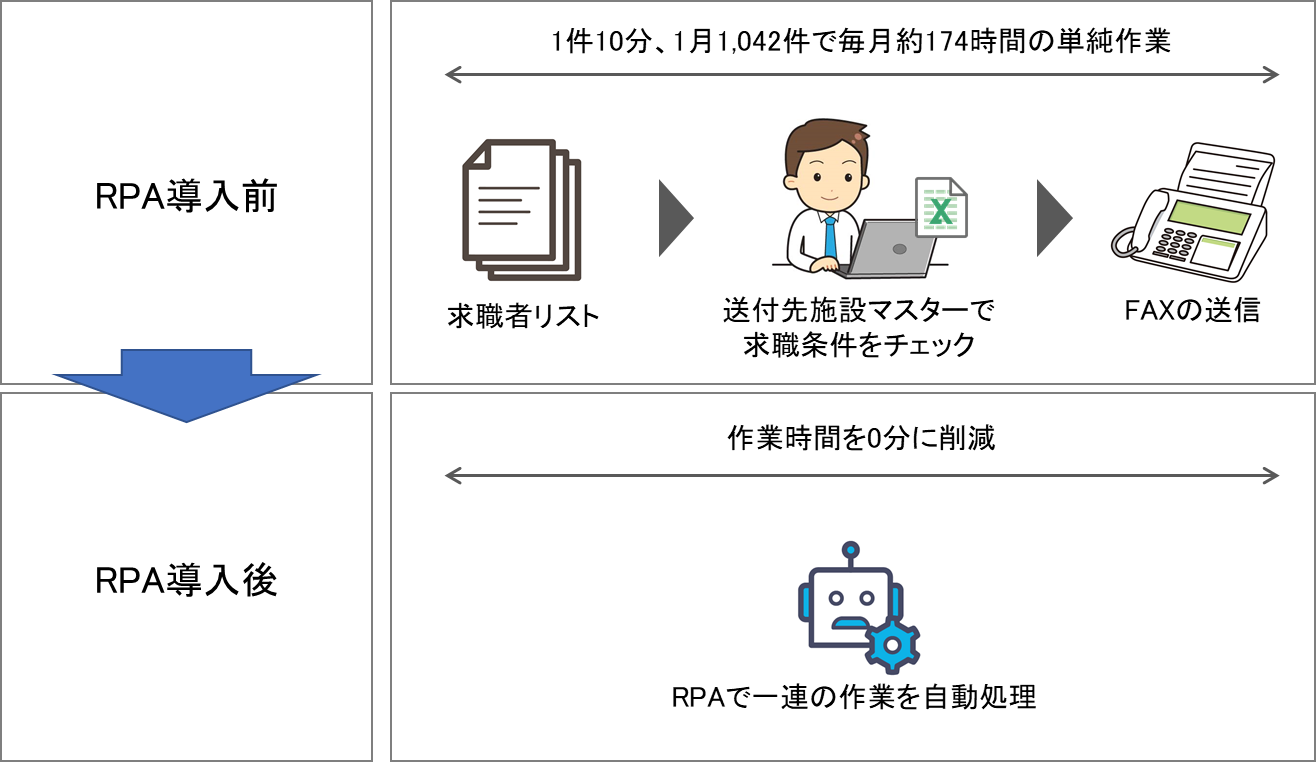
その後、同社では勤怠情報の修正、個人情報の削除処理等へとRPAの導入を拡大し、さらに営業支援システムや顧客管理システム、会計システムとの連携などにも活用していく構想を持っています。
(参考)https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/h30/html/b2_4_4_2.html
https://seleck.cc/782
4. 業務を自動化する方法の選定のポイント
これまで、主に機能的な面からマクロ・RPA・AIについて見てきました。選定においては、さらに導入コストや必要なITスキルなども考慮して検討する必要があります。
(1)導入にかかるコスト
マクロはOffice製品の標準機能であるため、ソフトウェアとして追加の費用は発生しません。VBAのプログラミングができる社員がいれば、外部に支払う費用を抑えることができます。
RPAは、ツールによって料金体系は異なり、年間50万円くらいから利用できる製品もありますが、年間コスト100万円前後の製品が多いです。
AIの場合、AIそのものを開発するためにはPythonなどのプログラム言語による本格的なシステム開発やAIに学習させるための大量データを準備する必要があります。コストは実現する機能や規模によって異なりますが、数百万円のコストは想定しておく必要があるでしょう。
(2)必要なITスキル
マクロでは、先に述べた通り、複雑な処理もVBAによるプログラミングで自動化することが可能ですが、実現するためには相応のITスキルが必要となります。
RPAでは、業務フローや画面上の設定で処理を定義できるため、プログラミングスキルを必要としません。
AIではシステム開発に加え、開発後も常時検証と改善を繰り返す必要があり、高いITスキルが必要となります。
(3)マクロ・RPA・AIの比較
最後のまとめとして、下表にマクロ・RPA・AIの違いを整理します。自社で自動化を検討している業務に含まれる操作が、Officeソフトのみの操作であればマクロ、Office以外のPC操作も含まれるのであればRPAを検討するのが基本です。さらに、RPAの方が求められるITスキルは低いこと、コストは自社で対応できるのであればマクロが安いことなども考慮して、総合的に判断するのが良いでしょう。
| マクロ | RPA | AI | |
| 自動化の範囲 | Office上の操作 | PC上の操作 | 特定の判断処理 |
| 対応可能な処理の複雑さ | 中 | 低 | 高 |
| 必要なITスキル | 中 | 低 | 高 |
| 導入期間 | 1日~1週間 | 1カ月~数カ月 | 数カ月~数年 |
| 導入コスト | 0円~ | 50万円~/年 | 数百万円~ |
人手不足解消の一手として、注目されている「業務の自動化」についてマクロ、RPA、AIを紹介してまいりました。「自動化」という目標は同じでも、ツールとしては明確に異なることをご理解いただけたと思います。
「自動化」という心地よい言葉に、あれもこれもと対象業務が増えてくことがよくありますが、最近では作っても使われずに放置されている「野良ロボット」が増えており、「業務の自動化」に踏み出せない方も多くいます。
導入に際しては、現在の業務の中でロボットが得意な業務はどの部分か?を見定め、それに適したツールを選定しましょう。
投稿 業務の自動化に!マクロ・RPA・AIの違いと選定ポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 オンラインストレージを法人利用する前に確認すべき8つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>平成30年度情報通信白書によると、クラウドサービスの普及率は2013年の33.1%から、2017年には56.9%になるなど、約5年間で約1.7倍の増加率となっています。
クラウドサービスのうち、利用しているサービスの内容は、「ファイル保管・データ共有」が(51.2%)とオンラインストレージサービスが最も多くなっています。
引用元:平成30年度情報通信白書https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd252140.html
多くの企業が導入を進めているオンラインストレージサービス。導入を検討されている方も多いかと思います。
普及が進む一方で、自社のサーバではなくオンライン上にデータを保管することで、さまざまなリスクも発生します。リスクを回避しオンラインストレージサービスを便利に使いこなすためにはどうすればいいのでしょうか?
本記事では、オンラインストレージサービスを法人利用する前に気を付けるべき8つのポイントをお伝えしていきます。
オンラインストレージサービスを法人利用する際に気を付けるポイントは8つ
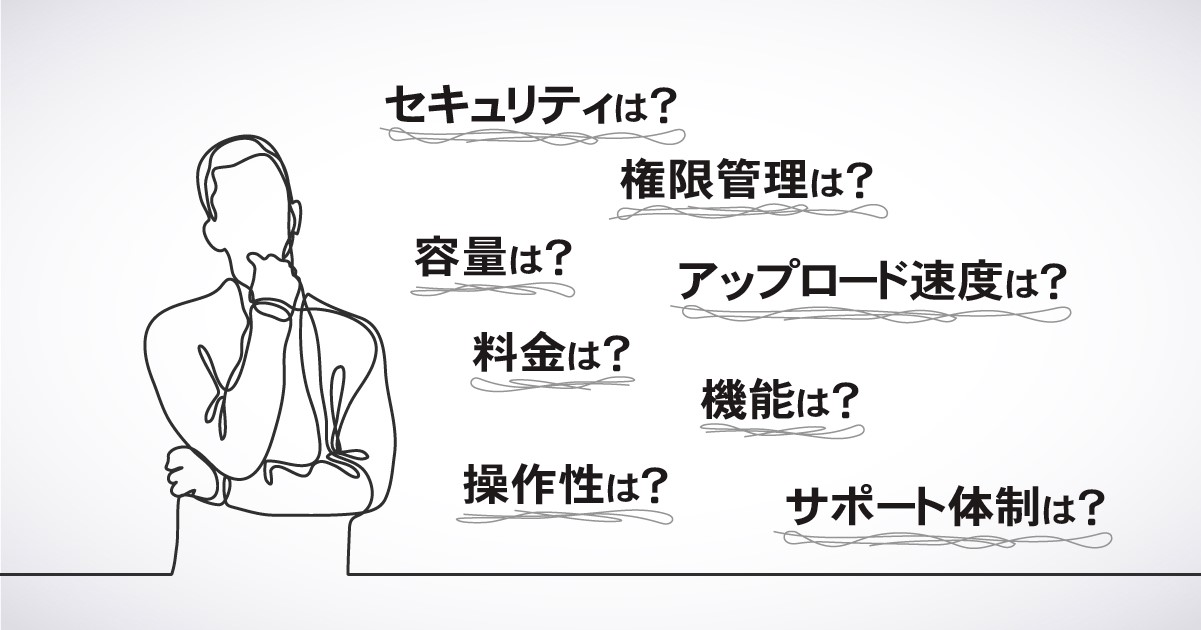
オンラインストレージサービスの法人利用で気を付けるポイントは、以下の8つがあります。
1.セキュリティ
2.権限管理
3.容量
4.アップロード速度
5.料金
6.機能
7.操作性
8.サポート体制
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1.セキュリティ
2019年に「無料データ転送サービス」が不正アクセスされて、大量の個人情報が流出したという事件が発生しました。同サービスではパスワードの暗号化などの対応が不十分で、大きな被害が発生しました。
個人情報や、機密情報の漏えいを防ぐため、セキュリティがしっかりしているかどうか確認することが重要となります。
オンラインストレージサービスのセキュリティリスクは、次の3種類に分けられます。
a.サイバー攻撃による情報漏えいリスク
b.サーバダウン等によるデータ消失リスク
c.サーバ所在地によるカントリーリスク
これらのリスクと対策については、以下の記事をご確認ください。
オンラインストレージサービスを利用するうえでセキュリティリスクはゼロではありませんが、セキュリティリスクをしっかり認識して対策をすることが重要です。
2.権限管理
人事異動や昇格の度にアクセス権限を変更していく必要があります。きめ細かい権限管理が可能かどうか確認しましょう。多くの法人向けオンラインストレージサービスでは、特定のメンバーは閲覧可能、ダウンロードは不可といった設定が可能です。
また、ユーザーや部署の階層管理を行える法人向けのオンラインストレージサービスもあります。企業の規模により必要な機能は異なりますので、「自社の使い方に合わせた権限管理が可能かどうか」を事前に確認してスムーズな導入を目指しましょう。
3.容量
利用できるストレージ容量も重要な要素です。使用人数、扱うファイルの種類(ドキュメント系か、動画など大容量ファイルか)、また利用用途等で必要な容量は変わってきます。
利用用途としては「プロジェクトなどでの作業データ共有」、「PCのバックアップファイルの作成」などが想定されます。
特に、動画などを共有する際には、解像度やビットレート(1秒間のデータ量)などによっては、1つのファイルが大容量になってしまうケースもあります。
事前に「扱うファイルの容量」、「共有するファイル数」等を想定して、オンラインストレージサービスを選ぶと安心です。
4.アップロード速度
大容量のファイルをオンラインストレージサービスにアップロードする際、なかなか完了せずにイライラした経験はありませんか?
スムーズにデータを共有し、快適に仕事を進めるにはアップロード速度も気になるところです。
特に、10MB以上のファイルを頻繁にアップする方はアップロード速度にもこだわってサービスを選定するとよいでしょう。
5.料金
料金も気になるところではないでしょうか。ユーザー数に応じて料金が決まるサービスや利用できるストレージ容量によって価格が決まるオンラインストレージサービスなど、料金体系もさまざまです。自社にあったオンラインストレージサービスとプランを採用しましょう。
また、無料で使えるオンラインストレージサービスもありますが、法人利用ではお勧めできません。なぜなら、セキュリティ対策が十分ではないケースもあり、万一のトラブル時対応にも不安があるからです。
Google Drive、Dropboxといった無料から使えるオンラインストレージサービスでも法人向けの有料プランにアップグレードが可能です。
6.機能
容量やセキュリティといった基本的な機能に加えて、サービス毎にさまざまな「便利な機能」が実装されています。
例えば、外出先からデータが簡単に閲覧できる「スマートフォン対応」やサービスに加入していない方にもファイルのリンクを送付可能な「ダイレクトリンク機能」などがあげられます。
また「デスクトップアプリ」では、自分のPC上のフォルダとオンラインストレージが同期して、あたかもPC上のフォルダやファイルのように扱うことが可能です。
法人でオンラインストレージサービスを利用する際には、社員(ユーザー)がどのような利用方法を想定しているかを確認して、必要な機能があるサービスを選びましょう。
7.操作性
オンラインストレージサービスを選定するうえでは操作性も重要です。特に法人利用では、クラウドサービス自体に不慣れな方も簡単に使えるような操作性の良いオンラインストレージサービスを選定することをおすすめします。
操作性は、普段のPCのフォルダと似た使用感のある画面配置になっているといった「使いやすい画面表示」や「わかりやすいボタン配置」といった点もポイントとなります。本格導入前に、無料プランで操作性を確かめてみることも必要かもしれません。
8.サポート体制
最後のポイントはサポート体制の充実度です。個人利用とは違い、多くの社員が利用する法人でのオンラインストレージサービスではサポート体制の充実度も重要となります。
特に海外ベンダーがリリースしているサービスでは、サポートが英語のみとなっているケースがあるなど、十分なサポートが期待できないケースもあるため注意が必要です。
法人向けのオンラインストレージはさまざまな角度から自社にあったサービスを選びましょう
オンラインストレージサービスを法人利用する前に確認すべき8つのポイントについてお伝えしてきました。
以下のサイトでは、多くのオンラインストレージサービスの性能や口コミなどの情報を提供しています。是非ご覧いただき、自社にあったオンラインストレージサービスを選択することをおすすめいたします。
投稿 オンラインストレージを法人利用する前に確認すべき8つのポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 オンラインストレージとは?法人で利用するメリット・デメリットを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこでこの記事では、オンラインストレージを検討される企業担当者に向けて、知っておきたいメリット・デメリットについてご紹介します。
オンラインストレージとは
オンラインストレージとは、インターネット上で文書や画像などのファイルが保存・共有できるサービスです。例えるなら、「インターネット上のファイル保存庫」のようなものです。外付けHDDや、社内でサーバを設ける必要がなく、ビジネスに必要なファイルが簡単に自動保存できます。
多くのオンラインストレージサービスは、インターネット経由で申し込みをすることができて、簡単にはじめることができます。また、オンラインストレージの導入にあたり社内システムを変更する必要もありません。利便性も高く、ドラッグ&ドロップでファイルが格納できるなど、使い勝手も良好です。
企業がオンラインストレージを導入するメリットとは?

時間・場所を選ばずアクセスが可能
インターネット環境が整っていれば、「いつでも」「どこからでも」アクセスが可能。ビジネスで必要なファイルをオンラインストレージに格納しておけば、外出先から自由に確認・出し入れができます。
またPCだけでなく、スマートフォンやタブレットなど利用デバイスも問わないので、シームレスなファイル管理もできます。
ファイルの共有、同時編集ができる
オンラインストレージは、複数人のアクセスが可能です。ファイルをUSBメモリで手渡したり、メールに添付して送信したりすることなく、ファイルの共有・同時編集ができるので作業効率の向上も期待できます。
ファイルの一元化管理ができる
複数の拠点を持つ企業や部署間のファイルのやり取りが多い企業にとって、「ファイルの一元化」は悩ましい課題ではないでしょうか。オンラインストレージを活用すれば、ファイルの一元管理が可能です。オンラインストレージ上に、単一のファイルを格納しておくことで、ファイルの重複や不一致が解消されます。
アクセス制限が設定できる
機密情報を含むファイルを扱うのであれば、閲覧可能な人数は最小限にすることが望まれます。また外部とファイルを共有する場合でも、関係者しかアクセスできないように工夫したいところです。オンラインストレージなら、フォルダの階層ごとに詳細なアクセス権限を付与することができるため、必要な人に必要な権限を付与することが可能です。
サーバ管理の手間やコストを軽減
もし、自社でサーバを所有していた場合、必要となるのが管理・運営するための手間やコストです。しかし、オンラインストレージを利用すれば、自社でサーバのメンテナンスをする必要はありません。さらに、ソフトウェアをアップデートすることなく、常に最新バージョンを利用できるメリットもあります。
常に最新のセキュリティ対策に守られる
インターネットは、不正アクセスやウイルスなど新しい脅威にもさらされています。もし、自社サーバを利用していれば、常に最新のセキュリティ対策を意識しなければなりません。企業として維持し続けるのは、情報収集から対策まで大変な手間といえます。オンラインストレージなら程度の差はありますが、各サービスとも強固なセキュリティ対策がなされているので安心です。
ファイルのやりとりの手間やコストを軽減
ファイルを関係者に届けたい場合、これまでならCDに焼いたり、USBメモリなどに格納したりして渡していたかもしれません。しかし、これでは一連の作業に対して手間と時間、コストだけでなく、紛失したときのセキュリティ面も不安があります。オンラインストレージを利用すると、そういった面倒な手間やコスト、紛失の心配は軽減されるので、効率よくビジネスが進められます。
企業がオンラインストレージを導入するデメリットと対策
カスタマイズのコスト
現在、各社から提供されているオンラインストレージの多くは、それぞれのサービスにおいて仕様が決められています。つまり、自社に添ったカスタマイズをするには、コスト高と感じることがあります。
そこでオンラインストレージの選定時には、複数のサービスを比較し、自社にふさわしい機能を備えたサービスを選びましょう。
(複数人の利用など)情報漏えいのリスク
インターネットを利用する上では、サイバー攻撃や不正アクセスなどによる情報漏えいの脅威は避けて通れません。そのため、オンラインストレージには高いセキュリティ対策が施されています。事実、多くの有料オンラインストレージには、十分なセキュリティ機能が実装されているといえるでしょう。
リスクが高いのは、オンラインストレージを利用する従業員による情報漏えいかもしれません。企業における営業秘密の管理実態及び流出実態の調査を行った「経済産業省平成24年度 人材を通じた技術流出に関する調査研究調査」によれば、情報漏えいの経路は以下の結果となっており、人為的な要因が大きいと報告されています。
中途退職者(正規社員)によるもの・・・・・・ 50.3%
現職従業員等のミスによるもの・・・・・・・・ 26.9%
金銭目的等の現職従業員等によるもの・・・・・ 10.9%
オンラインストレージは、便利な反面、適切な管理をしないと人為的な情報漏えい事件につながる危険性も否定できません。
そのため、アクセス制限の管理をしっかりと行い、従業員や退職者のアクセス権限管理を徹底していきましょう。
引用元:経済産業省平成24年度 人材を通じた技術流出に関する調査研究調査
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/shiryou3.pdf
障害対応のリスク
オンラインストレージは、提供する会社で運用から保守、セキュリティまで行ってくれます。その一方で、もし運営側で何らか障害が起こった場合、全てを委ねているため利用側の企業としては手だてがありません。
これからオンラインストレージを利用する場合、機能だけでなく、万が一の障害発生時の対応についても確認しておくと良いでしょう。
オンラインストレージのメリット・デメリットを踏まえた導入をおすすめします。
いかに効率よくビジネスを遂行するかは、企業にとって大きな課題といえます。その点、オンラインストレージを導入することで、作業の効率化が図れる強力なツールになり得るでしょう。
ただし、オンラインストレージを導入すれば解決するのでもありません。メリット・デメリットを踏まえ、サービスを提供している各社サービスの特徴を比較して、検討することをおすすめします。
投稿 オンラインストレージとは?法人で利用するメリット・デメリットを徹底解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Web会議はいつ使う?テレビ会議との違い、必要な機材を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>Web会議とは?
Web会議とは、インターネットとWebを介して会議を行うことを意味する言葉である。また、そうした会議を実現する仕組みが、「Web会議システム」と呼ばれ、インターネットとWebを使って映像/音声によるミーティングを可能にする機能を提供している。
Web会議が必要となる場面とは?
ならば、実際のビジネスにおいて、Web会議システムが便利に使えるのは、どのような場面なのだろうか─。そうした場面はさまざまに考えられるが、以下では代表的な2つのユースケースを紹介したい。
利用シーン-1:遠隔地にいる複数の仕事仲間とミーティングを行う
Web会議が重宝される代表的なケースの一つは、離れた場所にいる複数の仕事仲間とミーティングを行う場面である。
例えば、ともにプロジェクトを進める仕事仲間が2人いて、その2人が、自分のオフィスからドアツードアで1時間程度の距離にある仕事場で働いているとしよう。そして、自分のオフィスに2人を集めて30分程度の会議を行うとする。
この場合、仕事仲間の2人は、会議の場所と自分たちの働く場所との往復でそれぞれ約2時間ものときを「移動」に費やす計算になる。
また、2人の仕事場もドアツードアで1時間程度の距離にあるとすると、3者のどの仕事場で会議を行ったとしても、3人のうち2人は約2時間を移動に費やさなければならない。つまり、30分の会議のために、3人のチームは4時間もの貴重な時間を移動という非生産的な業務に使ってしまうことになるのである。
それが、Web会議システムを使うことで、3人は、各人のオフィスでPCを使いながら(場合によっては、自席にいながらにして)会議が行えるようになる。それだけで2人分の移動時間約4時間がセーブされ、チームの生産性が高められることになる。もちろん、30分の会議のためにミーティングの場所を探したり、3人の都合を調整したりする手間も減ることになる。
利用シーン-2:忙しい関係者を集めてアドホックな会議を開く
一方、社内の部門・部署においても、何らかの意思決定やブレインストーミングのために、アドホックに関係者を集めてミーティングを行いたいときがあるはずである。ところが、関係者全員が日々の業務に忙殺されていると、全員の都合調整や会議の場所の確保に手間取り、なかなかミーティングが行えず、時宜を逸してしまいそうになるケースが往々にしてある。
Web会議システムは、そんな場面でも便利に使える。というのも、Web会議システムがあれば、会議の参加者全員が物理的に一つの場所にいる必要はなく、仕事の都合上、どうしてもその場所にいることのできない人は、外部からモバイルPCやスマートフォンなどを使って会議に参加することが可能になるからである。これにより、会議に向けた参加者の都合調整や場所の確保は柔軟になり、スピードアップされるはずである。
Web会議に必要な機能とは?
以上の記述からも分かる通り、Web会議システムは、会議というアクティビティーから、時間と場所の制約を取り払うためのITといえる。また、そのように考えると、Web会議システムに必要とされる機能が何かもすぐに理解できる。それは、実世界で会議を行うのに近い環境を、インターネット上で創り出すための機能である。
例えば、実世界の会議では、次のようなことが行われている。
1.参加者全員が互いの顔を見ながら意見を交わす
2.参加者全員が同じ会議資料を手元で見ながら意見を交わす
3.会議の主催者などが会議資料を使ってプレゼンを行う
4.ホワイトボードを使って適宜アイデアを出し合ったり、メモしたりする
5.誰かが、議事録を取る
Web会議システムは、これらの行動を仮想世界で実現する機能を次のようなかたちで提供している。
| 実会議の基本 | Web会議システムにおける機能実装 |
| ①参加者全員の互いの顔を見ながら意見を交わす | ビデオ通話 |
| ②参加者全員が同じ会議資料を手元で見ている | ファイルの共有 |
| ③会議の主催者などが資料を使ってプレゼンを行う | デスクトップ画面の共有 |
| ④ホワイトボードを使う | ホワイトボードの共有 |
| ⑤誰かが、議事録を取る | 会議の収録/録画 |
また、実世界で会議を行う際には、「さあ、会議ですよ」と周囲に呼び掛けたりするが、Web会議システムでも、会議の開催を知らせるコールを参加者に通知するための機能を標準的に備えている。同様に、会議の招集をかけたり、参加を呼び掛けたりする機能も、Web会議システムが基本機能として備える一つだ。
一方、遠隔から会議に参加する際には、周囲の環境から、なかなか音声で会議の議論に加わりにくいことがある。そのような場面を想定して、ビジネスチャットとの連携機能を提供し、チャットを通じた会議への参加を可能にしているWeb会議システムも多い。
また、在宅勤務者などがビデオ会議に参加する場合、自分の周囲の風景をあまり見せたくないことがある。そうしたニーズに対応するために、自分の周囲の風景をぼやかして表示させることができるマスキングの機能を提供しているWeb会議システムもある。
同様に、自分の撮像/声をオフにしたり、ミュートしたりしたい場合があるが、大抵のWeb会議システムはそのための機能を提供している。
このほか、会議における海外(外国人)との意思疎通をスムーズにするために、リアルタイム翻訳の機能を提供しているWeb会議システムもある。翻訳の精度はそれほど高くはないものの、同じ会社で働き、ビジネス上の文脈を共有化できている海外スタッフとの会議であれば、多少粗い翻訳でも、意思疎通の効率化には十分有効とされている。
Web会議システムとテレビ会議システムとの違いとは?
ところで、Web会議システムと似た機能を提供する仕組みとして、「テレビ会議システム」と呼ばれる仕組みが従来ある。
会議相手の映像をリアルタイムに確認しながら、対話できるという点で、Web会議システムと従来のテレビ会議システムはよく似ている。ただし、両者には異なる点がいくつかある。
まず、Web会議システムはもともと、インターネットやPC/スマートフォン、Webブラウザなど、世の中に広く普及している汎用的なネットワーク、機器、ソフトウェアを使い、低コストでビデオ/音声通話を実現するために登場した。その最大の利点と言えるのは、専用のネットワークや設備、機器を導入することなく、「いつでも、どこからでも、遠隔にいる相手とビデオ通話/音声通話が行えるようになる」という手軽さである。
それに対してテレビ会議システムは、公衆回線のインターネットではなく、キャリアが提供する専用ISDNサービスや広域LAN/IP-VPNサービスをネットワークとして使用し、専用のソフトウェアや機材(撮像用カメラ、収音マイク、スピーカー、多地点接続装置など)を通じて会議を実現する仕組みである。その主目的は、特定の地点と地点をセキュアで性能の高い専用ネットワークで結び、品質の高い映像/音声による会議を実現することにある。そのため、例えば、本社と支所の会議室を相互に結び、多対多でのミーティングを行うのに適した仕組みといえる。
こうしたテレビ会議システムの大きな利点の1つは、セキュリティレベルの高さにある。例えば、先に触れた通り、テレビ会議システムのネットワークには、大抵の場合、インターネットのような公衆回線ではなく、プライベートな“閉域網”が使われる。そのため、盗聴などのセキュリティ侵害のリスクが低い。また、システムのOSも専用的で特殊性が高いことから、ウイルス感染の危険性も少ない。
さらに、テレビ会議システムは、高品質の映像と音声による通信を主目的としていることから、Web会議システムに比べて音声・画像の品質が総じて高いというアドバンテージがある。
一方、テレビ会議システムの最大のデメリットといえるのは、コストの高さである。Web会議システムに比べると、テレビ会議システムは高価であり、設置にも相応の費用がかかる。また、通常のインターネットに比べて、専用のISDN回線やIP-VPN/広域LANサービスの使用料金は圧倒的に高額である。そうしたことから、1つの会社が、テレビ会議システムを数多く導入し、拠点の全ての会議室に配備して、現場での活用を促進するといったケースはほとんど見受けられず、経営幹部と国内外の各支所長による定例ミーティングなど、限定的な用途に使われるのが一般的といえる。
テレビ会議との比較で見たWeb会議システムのメリットとデメリット
Web会議システムは、上述したようなテレビ会議システムの限界を打ち破り、“映像・音声を使った会議”を、現場で働く各人にとって、より身近な存在にしたITといえる。
インターネットへの接続が可能でマイクによる音声入力とスピーカーによる音声出力、Webカメラ、Webブラウザの機能を備えたPCがあれば、それだけでWeb会議が始められる。また、最近のWeb会議システムの多くは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、それを使えば、スマートフォンから会議へ参加することも可能だ。
ただし、一般的なWeb会議システムで使われるインターネットは公衆回線であり、不特定多数が共用する通信インフラである。ブロードバンド化の流れによって通信速度は従来に比べて飛躍的に高まったとはいえ、常に一定のスピード(帯域)が確保される保証はない。ゆえに、会議中での映像/音声の品質が高いレベルで保たれる保証もないことになる。
また、前述した通り、ネットワークにインターネットを使う以上、Web会議のセキュリティにも細心の注意を払わなければならない。その点も、テレビ会議システムに比したWeb会議システムのデメリットといえる。
もう1つ、セキュリティの観点から見た、Web会議システムのデメリットといえるのは、あまりにも導入が簡単であるがゆえに、情報システム部門による管理の目が届かないところで、社内各部門・各部署での活用が勝手に進んでしまう可能性が高いことである。
会議(ビジネスミーティング)の場で話し合われる内容は、多くが関係社外秘の情報であるはずである。そうした情報が飛び交う場の管理は、やはり、情報システム部門や総務部門が一手に引き受けるべきといえる。その意味でも、Web会議システムの「シャドウIT」化は回避するのが無難であり、そのためには、自社のセキュリティポリシーに沿った運用管理が行えるWeb会議システムを全社的に導入し、それを社内標準のツールとして定めて、活用ルールの統制をきかせたほうがよいといえる。
Web会議に必要な環境・機材を確認
Web会議システムとテレビ会議システムとの違いについて確認したところで、次にWeb会議に必要とされる環境と機材について改めて確認しておきたい。
すでに述べた通り、Web会議に最低限必要される環境・機材は下記の通りである。
1.インターネットへの接続環境
2.Webプラウザ
3.スピーカー、マイク、Webカメラ
4.PC(またはMac*1)
*1 以下ではMacも便宜上、PCに含まれると見なす
今日のノートPCは、大抵の場合、インターネットへの接続が可能で、上記「1」「2」の機能を内蔵している。ゆえに、ノートPCがあれば、Web会議のために特別な機材を導入する必要は特にない場合が多い。
ただし、デスクトップPCの場合、Web会議で使うことを想定していない機種が以外と多くある。というのも、Web会議システムは、「場所を選ばず、自分の好きなところで会議ができる」といった“モビリティ”を大きなメリットの1つとしているからである。そのため、最新の機種であっても、デスクトップPCの中には、Webカメラやマイクによる音声入力の機能を備えていないものがある。
従って、仮に自席や自宅のデスクトップPCをWeb会議に使いたい場合には、Webカメラや音声入力のデバイスを別途用意する必要に迫られることがある。
また、オフィスの自席などでWeb会議を行うときに、会議で発言している自分の声がうるさく周囲に迷惑がかかるのでないかと気にして、迷惑をかけない方法をあれやこれやと思案する場合がある。こうした周囲への気遣いは大切だが、気にしすぎる必要は実のところない。というのも、オフィスでは、全員が電話に対して、自分の声で対応しているはずだからである。Web会議での対話もそれと同じと考えればよい。
もっとも、電話で相手と話す場合と同じように、周囲の雑音を気にせず、かつ、あまり大声を出さずにWeb会議を行いたいと思うことがある。そのような場合には、ヘッドセット等のマイクロフォン付きヘッドフォンを別途購入して使うのが適切といえる。
一方、Web会議システムを使って、テレビ会議のようなスタイルの会議を行いたい場合もあるに違いない。例えば、会議参加者の大半はオフィスの会議室に集まり、大画面を共有して会議を進め、数人は社外からWeb会議システムを通じて会議に参加するといったスタイルである。
こうしたスタイルの会議を、Web会議システムで実現するには、テレビ会議システムと同じような機器が別途必要になるはずである。
例えば、会議室にいる全員の姿を捉えるカメラや、それぞれの声をクリアにひろうマイク、さらには遠隔からの参加者の声を会議室にいる全員にクリアに伝えるスピーカーなどが、そうである。もちろん、大型モニターを通じて、ホワイトボードや会議資料、各自のデストップの切り替え表示もスムーズに行えるようにしなければならない。言い換えれば、Web会議システムを使ったテレビ会議システムの構築が必要になるということである。
今日、こうしたシステム作りを効率化するために、特定のWeb会議システム専用のテレビ会議システム(会議室システム)が提供されている。例えば、GoogleのWeb会議システム「ハングアウト Meet」専用のテレビ会議システムとして、「Chrome devices for meetings」と呼ばれるシステムが、各社から提供されている。これは、「Chrome OS」を搭載した専用端末「Chromebox」と、カメラやマイクなどテレビ会議に必要なデバイスがセットになったシステムだ。
また、シスコシステムズでは、Web会議システム「Cisco Webex Meetings」を包含した「Cisco Webex Teams」を使い、高品質のビデオ会議/音声会議をワイヤレスで実現するシステム「Cisco Webex Board」を提供している。このシステムでは、専用の大型モニターに4Kカメラ、マイクが一体化されているほか、ホワイトボード/資料を共有する機能や会議室にいるメンバーのデバイスを自動で認識する機能などを備えている。
さらに、Web会議の機能を備えたマイクロソフトのグループチャットツール「Microsoft Teams」専用のテレビ会議システムも、各社から提供されている。
Web会議システムを選ぶポイント
今日、Googleやシスコシステムズ、マイクロソフトのほかにも、多くのベンダーからWeb会議システムが提供されており、選択肢は多岐にわたる。よって、数ある製品(サービス)の中から、適切なシステムを選ぶ際のポイントをおさえておくことも大切である。以下、そのポイントについて確認しておきたい。
【ポイント①】使いやすさ
使いやすさは、Web会議システムを選ぶうえで最も重要なポイントの1つだ。というのも、Web会議システムは、自社内だけで使うものではなく、社外のビジネスパートナーとの対話にも使う可能性が大きいからである。従って、特別な教育やマニュアルがなくても、会議への参加が簡単に行えるものであることが重要となる。
もっとも、ときおり、「顧客との商談にもWeb会議システムは便利」というフレーズを目にすることがあるが、普通に考えれば、自社が利用しているWeb会議システムを使って、顧客と商談を進めるようなケースはまずないはずである。そのようなことを行うのは、自社の会議室に顧客を呼びつけて、商談を行うのと同じ行為だからである。
従って、Web会議システムをえり抜く際に、顧客のITリテラシーについて考えを巡らす必要はあまりなく、逆に、「このWeb会議システムに参加してほしい」と顧客から要請されたときに、自分たちはしっかりと対応できるかどうかのほうを心配したほうがよいといえる。
【ポイント②】コストパフォーマンス
Web会議システムは、多くがクラウドサービスとして提供され、アカウント単位での月額使用料金が設定されている。当然のことながら、製品(サービス)によって料金は異なる。ゆえにまずは、機能と料金のバランスが適切かどうかを見定めることが必要とされる。また、アカウント当たりの月額料金を見て、その料金の支払いに見合うコスト削減の効果(あるいは、生産性向上の効果)が得られそうなのは、社内の誰か(あるいは、どの部門・部署か)をシミュレートし、どの製品(サービス)の、どのプランを選ぶのが適切かを判断するのも一手といえる。
【ポイント③】会議の最大規模
Web会議システムでは、製品(サービス)によって、会議参加者の上限数が異なる。従って、Web会議システムによって、最大、どの程度の規模の会議を催す可能性があるかを想定しておき、その規模感に適合した製品(サービス)を選ぶことが大切である。
【ポイント④】セキュリティレベル
今日のWeb会議システムは、大抵の場合、暗号化による通信内容の保護や会議のロックなど、のセキュリティ機能をサポートしている。ただし、製品(サービス)によってセキュリティの機能やセキュリティ管理の機能が微妙に異なるので、どの製品が、自社のセキュリティポリシーに適合しうるか、あるいは、セキュリティポリシーに則った運用が簡単に行えるかを点検しておくべきである。
【ポイント⑤】音声品質
先に触れた通り、Web会議システムでは、公衆回線のインターネットをネットワークで使うことを前提にしているため、映像/音声の品質の確保にどうしても限界がある。ただし、その中でも、映像/音声の品質は、製品(サービス)ごとに違いがある。従って、無料のトライアルや無料版を使って品質をチェックしたほうが無難といえる。特に重要なのは、音声の品質だ。映像の動きが多少悪くても、音声さえクリアであれば、オンラインでの会議は滞りなく進むからである。逆に、映像がスムーズに動いていたとしても、音声の品質が悪いと会議参加者のストレスがたまり、会議の進行に支障をきたす可能性がある。
実利用者の評価でつかむWeb会議システムの使いどころと実力
Web会議システムが、実際にどのようなもので、製品(サービス)ごとにどのような利点があるかを知るうえでは、実際の利用者が、各製品(サービス)をどう評価しているかをつかむことも大切である。
その観点から、ITreviewでは、Web会議システムの実際の利用者のレビュー(評価・口コミ)に基づきながら、製品の比較・ランキング・おすすめ製品をリストアップしている。また、市場で評判の高いツールを一目で確認できる「Web会議のITreview Grid」も提供している。当Gridは、Web会議のカテゴリーページで掲載されているので、ぜひ、製品選びの参考にされたい。
投稿 Web会議はいつ使う?テレビ会議との違い、必要な機材を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 無料で使えるWeb会議のおすすめ6選|利用上の注意、有料製品との違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>無料で使えて評判のWeb会議システムとは?
Web会議システムは、インターネットを介して音声・ビデオによる会議を可能にするシステムことである。本記事では、無料と有料のWeb会議システムの違いにフォーカスを当てる。
ということで、まずは、無料で使えて、評判の高いWeb会議システムを6つほどリストアップしてみたい。
1.Zoom Meetings
アカウント不要で誰とでもすぐにWeb会議ができる人気ツール

Zoom Meetingsは、マルチデバイス対応のビジネス向けビデオ会議&チャットツール。アカウントを作成することなく、URLの発行のみで、誰とでも手軽にビデオ会議やチャットが行える点を特徴とする。
無償の「基本(ベーシック)」版と、有償の「プロ」版、その上位の「ビジネス」版、最上位の「企業(エンタープライズ)」版をラインアップ。無償版でも、HDビデオをサポートし、ローカルディスクへの会議のMPEG-4録画をサポートするほか、100人の参加者までのホストが可能。SSL 暗号化やAES 256ビット暗号化による通信内容の保護も実現している。
ただし、無償版ではグループミーティングの時間が40分までに制限されているほか(プロ版以上は実質無制限)、ユーザー管理(ロールの追加、削除、割り当てなど)の機能や使用状況レポートの生成、高度なミーティング管理機能、クラウドへのMPEG-4/M4Aムービー記録といった機能はサポートされていない。
2.Whereby
手軽さ、簡単さを特徴とするWeb会議ツール

Whereby(旧称appear.in)とは、Zoom Meetingsと同様に、URL発行のみでビデオチャットができるWeb会議ツールだ。ホストがアカウント登録を行えば、ゲストはURLをクリックするだけで会議に参加できる。
また、画面共有、マイクとカメラのオン/オフ、テキストチャット、部外者が参加しないためのLock機能、画面上にスタンプを表示させるStickerなど、Web会議システムの標準的な機能も網羅的にサポートしている。
無料版の「Free」と有料版の「Pro」「Business」の3つのライセンス形態があり、無料版では1対1でのミーティングのみが行え、グループでのWeb会議が行いたい場合には、Pro以上のライセンスが必要とされる。なお、Proではグループミーティングの参加者が4人までに制限されているが、Businessでは、参加者に制限はない。
3.Cisco Webex Meetings
画像の滑らかさやノイズを低減した音声の聞き取りやすさが特徴

Cisco WebEx Meetingsは、アプリのダウンロードやプラグインが不要で、デバイスに関係なく、いつでも誰とでも会議が行えるWeb会議システム。画像の滑らかさやノイズを低減した音声の聞き取りやすさを特徴とする。Zoom Meetingsと同じく、会議のMPEG-4録画もサポートするほか、資料の共有、ホワイトボード機能、アンケート機能を備える。
無料版と小規模チーム向けの「Starter」、中規模チーム向けの「Plus」、大規模チーム向けの「Business」という4つのライセンス形態があり、無料版でも通信内容・録音ストレージのAES 256 ビット暗号化、「Personal Room 」のロックといったセキュリティ機能を持つ。
ただし、無料版では会議参加者の数が最大50名までに制限されているほか、使用可能なクラウドストレージが1GBまでにグループミーティングの時間も40分にそれぞれ制限されている。有料版のStarterでも、会議参加者の数は50名までとなっているが、グループミーティングの時間に実施的な制限はなく、クラウドストレージの容量も5GBまで利用できる。さらに、Cisco WebEx Meetingsでは、Business版で200名参加の会議が催せるほか、オプションで最大1,000名参加の会議が催せるという拡張性も特徴としている。
4.ハングアウト Meet
グループウェアG Suiteを構成するGoogle純正のビデオ会議ツール

ハングアウトMeetは、Googleが提供するWeb会議システムで、グループウェア「G Suite」を構成する機能の1つ。会議を設定して、URLを参加メンバーに共有するだけでビデオ会議が行える。会議への参加メンバーにはアカウントやアプリは必要ではなく、Webブラウザを通じて、誰でも会議に参加できる。
G Suiteは有料のサービスで、無料版は用意されていない。無料試用も14日間とどちらかといえば短い。ただし、無料の Google アカウントから、ハングアウトMeetの基本機能は使いことができ、最大10人までのビデオ会議(ビデオ通話)が行える。とはいえ、無料のGoogleアカウントでは、管理機能(ユーザー管理やセキュリティ管理など)は使うことはできない。あくまでもパーソナル、あるいはビジネスパーソナルでの用途を想定した仕様になっている。
5.Chat&Messenger
「無料でも多機能」が売りのビデオ会議機能付きグループウェア

Chat&Messengerは、G Suiteと同様の統合型グループウェアで、機能の一つとしてWeb会議の機能を提供している。この機能はモバイルデバイスにも対応し、ビジネスチャットと連携したビデオ通話、デスクトップ画面共有などの機能を備えている。また、クライアントユーザーの自動認識機能もサポートされている。
Chat&Messengerは大きくオンプレミス版とクラウド版に分かれ、ともに無料版と有料版が用意されている。クラウド版では、無料版と、有料の「Standard」「Enterprise」「Ultimate」という計4つのエディションが用意され、無料版でも、ビジネスチャット、ビデオ通話、ファイル共有・文書管理、掲示板、回覧板などの機能が利用できる。
ただし、無料版では、1対1でのビデオ通話にしか対応しておらず、3人以上の人数でのビデオ会議には有料版の使用が必要とされる。また、チャットルームについても、無料版では合計 5 つまでしか利用できない。このほか、ユーザー管理・施設予約、暗号化キー指定、IPアドレス制限などの機能も有料版からのサポートとなる。
6.Blizz Collaboration Companion
国際標準規格ISO2001認証

Blizz Collaboration Companionは、パソコンやモバイルデバイスにアプリをインストールして使うタイプのWeb会議システムである(会議に参加者するだけであれば、アプリは不要)。ビジネスチャットと一体化されており、会議のスケジューリングや会議における4K画質での画面共有といった機能を備えている。国際標準規格のISO2001の認証を受けており、AES256ビット暗号化による通話内容の保護も実現している。
ライセンスの形態は、無料版と有料の「CORE」「CREW」「COMPANY」の4つに分かれている。無料版ではグループミーディングの人数が5名までに制限され、ユーザー管理の機能も有料版のみにサポートされる。
無料のWeb会議システムを使ううえでの心構え
ご承知の通り、物事には全て理由があり、無料のWeb会議システムが無料で提供されているのにも、もちろん理由がある。その理由を考えていくと、無償のWeb会議システムを選び、使ううえでの留意点も見えてくる。
言うまでもなく、Web会議システムの開発・提供元は、ほぼ全てが営利企業であって、非営利団体ではない。ゆえに稼がなければならず、Web会議システムを無料で提供するにしても、それが収益につながらなければ意味はない。そのため、無料のWeb会議システムは、多くの場合、有料版の“試供品”といえるような作りになっている。要するに、有料版の良さを訴求しつつ、有料版に移行したくなるような機能制限がかけられているのが通常ということである。逆にそうだからこそ、有料製品/サービスの無料版には、一定の機能・性能も期待できる。理由はシンプルで、無料版の機能・性能が劣悪であれば、有料版に移行しようという利用者の意欲は喚起できず、それどころか、有料版の評価も落とし、無料版の提供が逆効果をもたらす結果になるからである。
もちろん、無料版はあくまでも“試供品”なので、それをビジネスに本格的に使おうとすると、さまざまな機能の不足や問題に気付くはずである。
では、無料版のWeb会議システムには、総じて、どのような機能の制約や問題があるのだろうか。次にその辺りを確認しながら、有料版を使うメリットについて考えていきたい
有料のWeb会議システムを選ぶメリット
無料版のWeb会議システムに共通して見られる制約の一つは、会議人数の制限である。なかには、1対1のビデオ通話の機能しか提供していないものもある。また、ビデオ会議の時間についても制約を設けているシステムもある。
Web会議システムを使うそもそもの利点は、場所や時間の制約を受けずに会議をしたいメンバーと自由にビジネスミーティングが行えることにある。その意味で、無料版のWeb会議システムを使い続けている限り、そうした利点をほとんど活かせないことになる。
さらに、無料版のWeb会議システムの場合、ユーザー管理の機能を持っていないのが一般的である。
Web会議システムを利用するユーザーの登録/削除、ID/パスワードの管理といたユーザー管理の機能は、システムの使い勝手を増すものではないが、会社がシステム利用の統制やセキュリティを確保するうえでは大切な仕組みといえる。例えば、ユーザー管理の機能がないと、会社を辞めた人間のアカウントを消去し忘れるといった管理上の単純な漏れやミスも起こりやすくなる。ゆえに、有料のWeb会議システムの大多数は、ユーザー管理の機能を備えているが、無料版ではその機能が提供されていないことが通常なのである。
ちなみに、社内に設置されたリアルなミーティングスペースや会議室は、物理的に外部から切り離され、特にルールを設けなくても、利用者は自ずと従業員に限定され、第三者が勝手に出入りすることはほぼ不可能で、会議の内容が盗聴されたり、盗み見されたりするリスクも低い。ところが、Web会議システムによって仮想的に創られたインターネット上のミーティングスペースは、暗号化やユーザー認証による情報の保護策を講じないと、第三者による侵入・盗聴のリスクが大きくある。それゆえに、Web会議システムでは、無料版においても通信の暗号化といったセキュリティ機能を提供しているものが多いが、有料版との間で相応の機能差があるシステムもある。その意味でも、無料版ではなく、有料版のWeb会議システムを導入したほうが安全であり、安心といえるである。
ITreviewでは、そうした点を踏まえたうえで、Web会議システムのカテゴリーページでは、人気の高いシステムと、そのレビュー情報を豊富に紹介している。これからもぜひ、ご活用いただきたい。
投稿 無料で使えるWeb会議のおすすめ6選|利用上の注意、有料製品との違いを解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 中小企業の満足度・認知度が高いオンラインストレージ5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>上記の図は、ITreviewに集まったオンラインストレージのレビュワーによる満足度評価と市場の認知度を、独自のアルゴリズムで掛け合わせた四象限(Grid)マップです。以下のページでは企業規模で表示をすることができるため、導入を検討する際には非常に参考になります。
また、「ユーザーの声(口コミ・評判)」では、サービスの良い点だけでなく、改善してほしい点も記載しています。メリット・デメリットのユーザーの声を知ることも、これから導入を考えている方には、検討材料として有効な情報となるでしょう。
そこで今回は、「中小企業に満足度の高いオンラインストレージ」上位5社(2020年2月時点)の「ユーザーの声(口コミ・評判)」および、「容量と料金」をご紹介します。
中小企業の満足度・認知度が高いオンラインストレージ5選
Google Drive

Gmail やGoogleドキュメント、スプレッドシート、カレンダーなど、Googleアプリが利用できるため、チームでの情報共有・共同作業が円滑に進みます。G Suite の Business エディションと Enterprise エディションなら、容量無制限のストレージが利用可能です。
●ユーザーレビュー
利用者情報/社内情報システム(開発・運用管理)、会社規模100-300人未満
PC、スマホどこからでもアクセスでき、編集も可能。共有の設定もいろいろ選べるので社外の人とも共有可能。だいたい要件を満たしているので、細かい点でいうとスマホからだとPCより若干操作(編集)がしづらいですが、それは慣れが必要なのかな。
https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/38302
利用者情報/営業・販売・サービス職、会社規模20人未満
写真やテキスト、その他共有するべきデータをドライブで管理しています。他のサービスとの連携も整っているので、非常に使いやすいです。また、無料で15GBの利用が可能なのも良いです。改善してほしい点は、ファイル数が多いとアップロードが遅い気がする。個人的にはUIがもう少し改良されるとうれしい。無料での容量をもう少し増やして欲しい。
https://www.itreview.jp/products/google-drive/reviews/36164
●容量/料金
・容量:1TB(ユーザー数が 5 人以上の場合は無制限)
・最大ファイルサイズ:5TB
・料金(1ユーザー):1,360円/月
Dropbox Business
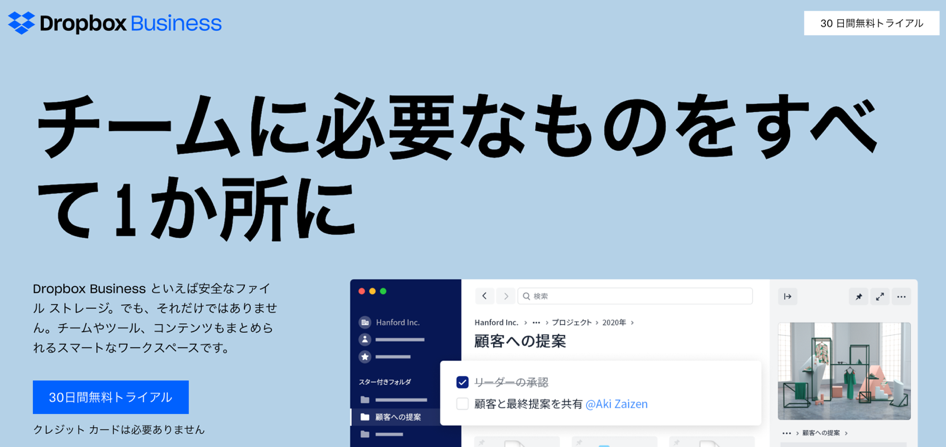
ユーザーに高い支持を誇るDropboxの法人版オンラインストレージです。直感的に操作できる管理画面のほか、多層構造のセキュリティ対策や負荷分散型のサーバ構成により、安心して企業利用が可能。リテールや出版、不動産など、規模や業種に関わらず世界中の企業で採用されています。
●ユーザーレビュー
利用者情報/経営・経営企画職、事業規模20-50人未満
周囲の利用者が多いため、ファイルの共有がスムーズ。さらにアカウントを持っていないユーザーにも共有可能なので間違って消してしまったファイルも復元できるので、助かります。ローカルフォルダとの自動同期の細かい設定が、少しややこしい気がしています。数台のデバイスを使用していますが、各デバイスの同期したローカルフォルダが生成されてローカルデーターが重複する感じがしますので、もう少し分かり易くして欲しい。
https://www.itreview.jp/products/dropbox-business/reviews/38191
利用者情報/営業・販売・サービス職、事業規模20人未満
とにかく簡単・分かりやすいインターフェイスで、社内・外部とファイルやフォルダの共有ができる。また、スマートフォンと同期できるのも使いやすい。
https://www.itreview.jp/products/dropbox-business/reviews/36209
改善してほしい点は、ファイル同期処理がたまに不安定。数人でファイルを開いたときに、読み取り専用モード等に自動に切り替わるなどしてほしい。競合ファイルができてしまう。
●容量/料金
・容量:5TB
・最大ファイルサイズ:50GB ・料金(1ユーザー):1,250円/月(最小3人)
OneDrive for Business

マイクロソフトOffice365を導入すると付属してくるオンラインストレージです。WordやExcel、PowerPointなどの共有もスムーズ。組織内外の相手との共同作業に貢献します。また、容量無制限プラン(サブスクリプション契約5人以上の場合)も用意されています。
●ユーザーレビュー
利用者情報/経営・経営企画職、会社規模20人未満
デスクトップアプリを有効にすれば自動的にバックアップが出来、かつWindows標準ともいえるサービスなので、安心して利用できる。また、管理も他マイクロソフト製品に準拠している。時に、バックグラウンドで起動している際、とてつもなくメモリを消費していることがある。他のソフトウェアが一切起動しなくなるくらい重たくなるので、改善してほしい。
https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/37099
利用者情報/情報システム関連職、会社規模50-100人未満
Office365に付随してきましたが、使ってみるとファイルの保存、分類が非常に使いやすくアップロードも閲覧もローカルフォルダのように使えます。大切な書類をローカルとOneDriveを同期させ保存が可能。ファイルの振り分けもWindows PCのローカルで作業しているかのようで、とても使いやすい。
https://www.itreview.jp/products/onedrive-for-business/reviews/36704
改善点は特になく、操作性の簡便さはどのクラウドより勝っていると思われます。その分クラウド感はあまりないのですが、スマホやタブレットなどPC外で使う際もGoogleドライブよりアクセスしやすく、PC上ではまるでローカルフォルダのよう。Appleユーザはどうなんでしょう。iPhoneやMacのPCでは使用したことがなく。
●容量/料金
・容量:無制限(サブスクリプション契約5人以上の場合)
・最大ファイルサイズ:15GB
・料金(1ユーザー):1,090円/月
Box

Office 365やGoogle Suite、Adobe、Slackなど、1,000以上のアプリと接続が可能。情報をシームレスに管理、参照、共有できます。また、強固なセキュリティ、きめ細やかな管理機能を備えていることから、企業を中心に95,000社が利用しています(2019年12月時点)。
●ユーザーレビュー
利用者情報/会計・経理、会社規模20-50人未満
容量無制限かつ目的別に複数のメンバーでデータを共有出来ます。また、細かく権限設定が出来たりログ監視機能もあるのでセキュリティ面もしっかりしていると思います。現状あまり問題なく使えているのでこれというものは思い当たりませんが、たまに動作が遅いなと感じる時があります。
https://www.itreview.jp/products/box/reviews/38549
利用者情報/宣伝・マーケティング、会社規模20人未満
社内用の資料共有・編集用で使用していました。共有先も部門等を指定して閲覧制限をかけたり、編集の際は最終編集者がわかるため、セキュリティがしっかりしていて安心できました。
https://www.itreview.jp/products/box/reviews/38448
容量の大きい資料のアップロード・ダウンロードの際は非常に時間がかかる。複数の資料をアップしようとする際のエラーが散見される。
●容量/料金
・容量:無制限
・最大ファイルサイズ:5GB
・料金(1ユーザー):1,800円/月(最小3人)
AOSBOX business

「低コスト」「安全」「簡単」を打ち出しているAOSBOX business。利用できるストレージ容量は、100GBから無制限のオンラインストレージまでと充実しています。クラウドインフラには信頼性の高いAWSの国内サーバを採用し、セキュリティには定評があります。
●ユーザーレビュー
利用者情報/営業・販売・サービス職、会社規模20人未満
AOSBOX Businessの良い点としては、以下の通りです。
https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/36037
①バックアップ元にアプリをインストールして、簡単な設定するだけで自動バックアップが取られる点。
②AWSを活用している為セキュリティレベルが高い。
③差分バックアップの為サーバディスク消費が少ない。
社内サーバーのデータをクラウドへバックアップとして活用しておりますが、特に不自由なく利用しております。社内サーバーのバックアップと世代管理もされている為、何かあった際にもすぐに復元できるため非常に助かっています。
利用者情報/営業・販売・サービス職、会社規模20人未満
インストール後初期設定のみで、その後は全自動でバックアップが取られる為、非常に簡単。データ復元についても見た目で操作でき、料金が定額である事。現在、クライアントPCのバックアップで利用していますが特に不満はありません。不具合もなく利用しています。
https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/35087
●容量/料金
・容量:100GB
・最大ファイルサイズ:無制限
・料金:1,666円/月(ユーザー10名まで)
オンラインストレージの選定はレビューを参考に、自社にあったサービスを!
中小企業に満足度と認知度の高いオンラインストレージ5つのユーザーレビューをご紹介しました。使用者の評価は、とても貴重な情報となったのではないでしょうか。オンラインストレージを選定する際には、ぜひこれらのレビューを参考に、自社にあったサービスを見つけてください。
なお、上記で紹介した以外にも、さまざまなオンラインストレージのレビューを公開しています。こちらもぜひご一読ください。
投稿 中小企業の満足度・認知度が高いオンラインストレージ5選 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 FreeのVPNに潜むリスク。安全に使うために知っておきたい3つのこと は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、Free VPNを使用する前に知っておきたい3つのリスクについて解説します。
安全なVPNだけではない
企業活動にインターネットが不可欠となったいま、多くの企業や団体でVPNの普及が進み始めています。暗号化通信によって盗み見や情報漏えいのリスクを防ぐだけでなく、本社と各支店を結ぶ拠点間通信によって、業務効率の向上も期待されています。
同時に、VPNサービスを提供する事業者も増えてきており、企業向けから個人向け、有料版や無料版まで多種多様なVPNが利用できる環境となりました。しかし、Free VPNのなかには適切に運営されていないものもあり、本来のVPNとしての機能を活用できていないケースが見られます。
毎日多くの情報をやりとりする企業では、情報セキュリティ対策が顧客や取引先との信頼関係にも影響します。セキュリティが十分に確保された信頼できるVPNを選ぶことは、経営の観点からも重要なことといえるでしょう。コストを安く抑えられるFree VPNですが、その危険性やセキュリティレベルについて理解しておくことが大切です。
Free VPNを利用する際に知っておくべき3つのこと
公開されているFree VPNのなかには、以下のようなリスクがあります。
1. マルウェアの感染・サイバー攻撃のリスクがある
Free VPNには、セキュリティ面の脆弱性が懸念されます。VPN自体が悪意を持って作られている場合もあれば、セキュリティ上の弱点を狙ってサイバー攻撃を仕掛けてくる危険性もあります。知らないうちにマルウェアに感染しているケースもあるため、社内の重要な情報を抜き取られることや、データを改ざんされるといったトラブルを招きかねません。
また、利用デバイスのデータ悪用や、遠隔操作によって犯罪に巻き込まれる可能性もあります。企業の資産を守るため、犯罪に巻き込まれないためには、こうしたリスクを最小限に抑えられる信頼性の高いVPNを選ぶことが大切です。
2. 暗号化されていない可能性がある
VPN通信では、暗号化技術によって通信内容が傍受されないように作られていることが基本です。しかし、一部のFree VPNでは通信が暗号化されていないケースが報告されており、プライバシー保護や個人情報保護といった権利が脅かされています。
また、暗号化がされているVPNであっても、選択するプロトコルによって暗号化の強度が異なります。現時点でセキュリティレベルの高い「OpenVPN」でないプロトコル(PPTPなど)を使用する場合は、第三者による盗み見や改ざんが起きるリスクが高いといえます。
機密情報を扱う企業にとって、こうしたセキュリティの低いVPNを使用することは非常にリスクの高いことといえるでしょう。
3. ログデータが利用される可能性がある

VPNの安全性を図る手段として、「ノーログポリシー」が挙げられます。VPNログとは、ユーザーがVPN経由で閲覧したサイトや通信履歴といったデータのことです。多くのVPNでは、プライバシーや個人情報保護の観点からこのログを保持しないよう宣言していますが、Free VPNのなかにはログを取得しているサービスも存在します。
IPアドレスや通信データ量などの接続ログに加え、訪問したサイトやファイルまで保存されている場合もあります。こうして保存されたログデータは、第三者に転売されてしまう可能性があるため、プライバシーが守られているとはいえないでしょう。
Free VPNを使用する判断基準とは?
Free VPNが必ずしも良くないと断言はできませんが、有料版と比べ、無料版はセキュリティの脆弱性を狙ったトラブルに巻き込まれるリスクが高いといえます。企業のセキュリティポリシーに反する可能性が高いため、使用の際は慎重に判断しましょう。
特に、プライベートで社用のノートPCを利用する際や、企業データが入ったスマホやタブレットでFree VPNを使う場合は危険です。社内に強固なVPNを構築していても、セキュリティの弱いFree VPNを利用すれば、たちまち危険にさらされます。
企業活動にはできるだけ有料版を使用し、社用のデバイスで無料版に接続しないよう社内へ呼びかけましょう。やむなく使用が必要な際は、プロバイダーのプライバシーポリシーに加え、「最新プロトコルを使用しているか」「VPNプロバイダーの信頼性が高いか」「ログを保持していないか」などを確認しておくことも大切です。
投稿 FreeのVPNに潜むリスク。安全に使うために知っておきたい3つのこと は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 スマホでもVPNを使うべきシーンとメリットとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、PCとは対照的にセキュリティ面にあまり注意が向けられないのが、スマホ(スマートフォン)のセキュリティ対策です。
本記事ではスマホの抱えるセキュリティリスクと、その解決策としてのVPNについて取り上げます。
スマホでの機密情報の取り扱いに注意
仕事でスマホを使う場合には個人情報などの機密情報を扱う場合も多く、PCと同様にセキュリティ対策が必要です、例えば、以下のスマホアプリでは、機密情報の取り扱いが予想されます。
1.メールアプリ
無料で使用できるアプリもあります。外出先でもメールチェックができるので便利です。しかし、メールアドレスをはじめ、多くの個人情報が含まれています。特に、本文や添付ファイルに機密情報が含まれる場合は、注意が必要です。
2.名刺管理アプリ
名刺交換したその場で、相手の名前や連絡先などを取り込めるので便利なアプリです。しかし、名刺には電話番号や住所など多くの個人情報が含まれているため、注意が必要です。
3.タスク管理アプリ
外出先でも、仕事のスケジュールや進捗状況など、確認できるので便利です。しかし、仕事上の機密情報や、会議出席者の個人情報などが含まれる場合は、注意が必要です。
4.業務効率化アプリ
業務効率化アプリを使われている方も多いのではないでしょうか。例えば、会議室のホワイトボードやメモ書きなどの画像をデータとして取り込むアプリがあります。こういったアプリでも機密情報を扱う可能性があるので注意が必要です。
5.顧客管理アプリ
外出先でも顧客管理がスムーズにできるので、便利なアプリです。しかし、顧客情報には住所や電話番号など多くの個人情報が含まれている場合が多く、注意が必要です。
以上、仕事で使用する代表的なアプリの例をあげました。スマホで個人情報や機密情報を取り扱う機会が多いことに、改めて気付かれた方も多いのではないでしょうか。
そして、スマホで機密情報を扱う場合に注意が必要なのが、フリーWi-Fiの利用です。
フリーWi-Fiに潜むセキュリティリスク

一般的なスマホ契約では、パケット通信料の上限を超えると速度制限がかかります。ついパケットを使いすぎてしまった場合など、動作が遅くなってもどかしい思いをされた方も多いのではないでしょうか。通常速度で通信するとなると追加料金がかかるので、フリーWi-Fiスポットを探す方もいるでしょう。
料金を節約するためにパケット定額のコース契約にしていない方は、できればフリーWi-Fiを使いたいところです。さらに、通信電波が弱い場所では、契約に関わらずフリーWi-Fiを使用せざるを得ません。
このように、スマホでフリーWi-Fiスポットを使うケースは意外に多いものです。
しかし公共のフリーWi-Fiスポットには、危険なわなが潜んでいます。そこで、主な2種類のフリーWi-Fiについて、その危険性を見ていきます。
暗号化されていないフリーWi-Fi
最も危険なものが、暗号化されていないフリーWi-Fiです。この中には、情報を盗み取ることを目的とした、悪意を持ったWi-Fiスポットが存在する場合があります。このようなWi-Fiに接続してしまえば、情報漏えいのリスクは極めて高くなります。
暗号化されていないフリーWi-Fiが情報漏えいのリスクが高い理由は、簡単に無線LANルーターを検出して接続できるからです。接続したPCにネットワークの管理のための分析ツールなどをインストールして悪用することで、第3者によるパケット盗聴が可能です。
このように、フリーWi-Fiスポットの中には安全に見せかけて、悪意を持ったWi-Fiが紛れ込んでいる場合があるので注意が必要です。情報漏えいを防ぐためには、サービス提供者が不明なフリーWi-Fiには、接続しないことが大切です。
また、Wi-Fi自体に悪意がない場合も、無料でハードルが低く不特定多数の人がアクセスするため、情報漏えいのリスクは高くなります。誰でも簡単に接続できるため、パケット盗聴などのサイバー犯罪目的のユーザーがいる可能性が高いからです。不特定多数の人が集まる繁華街などで、スリなどの犯罪が多いのと同様です。
共通のパスワードで暗号化されたフリーWi-Fi
カフェやビジネスホテルなどで提供されている、共通のパスワードで接続できるフリーWi-Fiです。サービス提供者もはっきりしているので、パスワードがないものに比べると、セキュリティリスクは低減されます。
しかし、パスワードが公開され、誰でもログイン可能なため、悪意を持った使用者が接続する可能性は否定できません。こうした、提供者がはっきりしたフリーWi-Fiのセキュリティレベルは千差万別です。
フリーWi-Fiのセキュリティレベルが低い場合は、悪意を持った使用者により、メールアドレスやパスワード、クレジットカード情報を盗まれることもあります。また、スマホの通信先を不正に変更して、詐欺サイトへ誘導される危険もあります。
スマホで機密情報を扱う場合はVPNが安全
このように、フリー無料Wi-Fiは悪意を持った利用者が接続する可能性から、情報漏えいの恐れがあります。そのため、サービス提供者がはっきりしている場合も、注意が必要です。悪意を持った利用者が、 スマホから仕事上の情報を盗み取った場合、企業への「標的型攻撃」に発展する危険性があります。
企業などの組織を対象にした「標的型攻撃」は年々増加しており、情報処理推進機構(IPA)が発表した「情報セキュリティ10大脅威 2019」ではワースト1位です。
参考:IPA「情報セキュリティ10大脅威 2019 組織編」https://www.ipa.go.jp/files/000072147.pdf
一例としては、 スマホから企業のメールアドレスを盗まれた場合、標的型攻撃メールの被害に遭うリスクが発生します。
そこで、仕事用アプリを使用する場合など、フリーWi-Fiで安全に通信するために、有効なのがスマホ用VPNです。スマホ用VPNを利用すると、スマホから送信されるデータを暗号化して、情報漏えいのリスクを低減することが可能です。
スマホ用のVPNは、VPNの種類のうち「クラウドVPN」および「リモートアクセスVPN」に分類されます。
クラウドVPNとは、クラウド上のVPNサーバを利用して、PCなどのデバイスとインターネットをVPN経由で安全に接続するための仕組みです。
リモートアクセスVPNとは、ノートPCなどのモバイルデバイスを、屋外で安全に使用するために開発された仕組みです。テレワークでも利用が始まっており、働き方改革の推進にも一役買うことが期待されています。
この「クラウドVPN」と「リモートアクセスVPN」の仕組みを応用したのが、スマホ用VPNです。スマホ用VPNを利用すると、スマホの通信セキュリティを、テレワーク用のPCと同様のレベルに高めることが可能です。
スマホで利用できるVPNサービスの口コミ・評判は、以下をご覧ください。
Wi-Fi Security for Business

■サービス概要
Wi-Fiセキュリティ強化のための、クラウドVPNに特化したサービスです。世界各国にVPNサーバを設置しており、公衆Wi-Fi利用時のセキュリティ強化に活用できます。
・対応するOS
iOS、Android、Windows
・料金
1デバイス当たり200円/月
・利用可能なVPNサーバ
世界25カ国に3000台以上
・オプションサービス
契約者専用のVPNサーバ(プライベートサーバ)を設置して、固定IPアドレスの使用可能
AnyConnect

AnyConnectのVPN製品で、リモートアクセスVPNを構築することで、スマホから社内LANなどへVPN接続するサービスです。また、「Always-On機能」により、スマホから社内に設置したVPN装置を経由して、社外のインターネットサイトへも接続できます。
・対応するOS
Windows、Mac OS、Linux、iOS(Apple iPhone、iPod touch、iPad)、Android、Cisco Cius
・Always-On機能
スマホやPCなどのモバイルデバイスが、社内にあるか社外にあるかを自動で判別する機能です。デバイスが社内にある場合は、VPNを経由せず直接社内LANへ接続します。社外にある場合は、VPNを経由して社内LANに接続します。この機能により、社外のスマホからVPNと社内LANを経由して、インターネットサイトへも安全に接続できます。
・料金
別途、お問い合わせ。
SoftEther VPN

■サービス概要
SoftEther VPNは、筑波大学の学生が修士論文の研究で作成した、学術研究目的のVPNソフトウェアです。SoftEther VPNは、SSL VPN、OpenVPN、L2TP、EtherIP、L2TPv3 および IPsec の全てに対応しているのが特徴です。
SoftEther VPNをスマホで利用する場合、リモートアクセスVPNとして、社内とVPN通信ができます。「SoftEther VPNサーバ」を社内LANのサーバコンピュータに、「SoftEther VPN」をスマホに、それぞれインストールすることで、社内LANとスマホ間でWi-Fiを通じたVPN通信ができます。
・対応するOS
Android、iPhone、iPod Touch、iPad、Windows、Mac OS X
・料金
学術研究目的のためライセンス費用は無料
通信キャリアのWi-FiにもVPNがおすすめ
通信キャリアのWi-Fiを利用される場合も、スマホ用VPNは利用価値があります。もちろん、大手通信会社が提供する通信キャリアは、高い安全性を誇ります。しかし、どんなに安全性が高い通信ネットワークでも、セキュリティに「絶対」はありません。
サイバーリーズン・ジャパン株式会社によると、2018年にグローバル通信事業者を標的としたAPT攻撃の存在が確認されています。この攻撃は、価値の高い特定のデータに狙いを定めており、標的のネットワークが完全に乗っ取られたことが確認されています。
参考:サイバーリーズン・ジャパン㈱
「通信事業者を狙った世界規模のサイバー攻撃」
https://www.cybereason.co.jp/blog/cyberattack/3694/
日本の大手通信会社が、こうした攻撃のターゲットにされることが「絶対にない」とは言い切れません。もしターゲットにされた場合、通信キャリアの機密情報が「価値の高いデータ」と見なされて狙われる可能性もあります。
こうした不測の事態に備えて、通信キャリアが提供するセキュリティレベルの高いWi-Fiを使用される場合も、機密情報を扱う場合はVPNの併用がおすすめです。通信キャリアとVPNの、それぞれのセキュリティ対策の相乗効果で、情報漏えいのリスクをさらに低減できます。
ビジネス向けのVPNの口コミ・評判は以下をご参照ください。
投稿 スマホでもVPNを使うべきシーンとメリットとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 無料で使える日本語対応CRM7選|有料版との違いや注意点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>CRMツールに乗り換えとなると多くは有料のため、導入にあたって最初の壁になっている方も多いと思います。本記事では、これまでのExcelによる顧客管理方法に限界を感じている方や、年度末の売上達成に向けてCRMを活用したいと考えられている方が、まずCRMを体験できる無料で利用可能なCRMをご紹介します。
導入前にここだけは抑えたい、CRMの機能
いくら無料とはいっても、新しいツールを導入するのは手間や時間がかかるものです。せっかく導入したものの使いたい機能が備わっていなかったということがないよう、本項では無料のCRMツールを試していただくにあたり、抑えておきたい機能を紹介していきます。
顧客管理機能
CRMの基本であり、一番重要な機能です。顧客情報は顧客の名前や住所などの基本情報以外にも、企業によって蓄積したい情報はさまざまです。試行にあたっては、現場目線での「入力のしやすさ」「見やすさ」の他、「項目のカスタマイズはいくつできるか」「操作権限をユーザーによって変えられるか」など管理者としての観点でも確認をしましょう。
分析機能
蓄積された情報を活用するために、重要となるのが分析機能です。
「どんな分析機能を持っているのか」「これまでExcelで出力していた情報と比べて不足はないか」「出力内容をカスタマイズできるか」といった点について確認しましょう。
営業支援機能
CRMに蓄積される情報の多くは営業部門が収集したデータになると思います。そのためCRMツールの多くはSFA(営業支援システム)の機能を併せ持っています。「案件管理」「予実管理」「カレンダー連携」「モバイル対応」など、営業活動の助けになる機能について、機能の多さだけではなく現場から見た使いやすさも合わせて確認することがポイントです。
マーケティング支援機能
蓄積された情報については、マーケティングに活用されたいと考えられる方が多いと思います。これまでMA(マーケティングオートメーション)ツールをすでに利用されている場合には、利用中のMAツールと連係できるかどうか確認してください。また、これまでMAツールを利用されていない場合は、CRMツールでどのようなマーケティング活動を行えるか(メールマーケティングやソーシャル連携など)を確認しましょう。
無料版と有料版の違いとは?機能の充実ぶりやサポート体制にあり
無料版で使えるCRM製品の中には、有償版にすることで機能を拡充できたり、サポート体制が強化されるものがあります。例えばHubSpot CRMでは基本機能が無料となっており、上位機能をプラスする場合は有料プランへのアップグレードが必要になります。しかし、基本機能だけでも十分であれば無料版でも十分事足りるでしょう。有償版との比較は以下のとおりです。
無償版
- コンタクト、取引、タスクの管理
- Eメールのトラッキングとエンゲージメント通知
- Eメールのテンプレート作成とスケジュール設定
- ドキュメント共有
- ミーティングのスケジュール設定
- ウェブチャット
- 見積書の作成
アップグレードにより追加できる機能は以下の通りです。
有償プラン(Starter)
- 無料ツール+各種上限の引き上げ
- フォームの自動化
- Eメールの自動送信
- HubSpotのロゴを削除(フォーム、Eメールマーケティング、ランディングページ、ウェブチャット)
- Eメール、アプリ内のチャットサポート
といった内容です。有償プランはグレードが分かれているため、上位プランを選択すればさらに多くの機能やサービスを享受することができます。このように、無償版でも業務に役立てられますが、多少なりとも利用にあたっての制限がかかることを覚えておきましょう。
日本語対応可能!無料で使えるCRM7製品をピックアップ!
ここでは、無料で利用できるCRMツールを具体的に紹介します。ご紹介する製品は、主に「無料プランがあるもの」「無料トライアル期間があるもの」にわけられます。なお、無料で利用できるCRMツールはさまざまなものがありますが、本項ではクラウド型(インストールすることなくインターネット経由で利用できるサービス)かつ日本語のサービスページがあるツールに絞り紹介していきます。
1.HubSpot CRM:無料でも機能は十分。直感的に使いやすいシンプルUIが魅力

「HubSpot CRM」は使いやすいユーザーインタフェースの評価が高く、無料プランから始めて必要に応じ有料の機能を追加することができるCRMツールです。
無料プランでもユーザー数・利用期限・登録データ数に制限はなく、顧客情報管理や案件管理、レポート作成などCRMとして必要とされる基本的な機能は十分に備えています。ただし、カスタムレポートの作成が行えず、またメールの送信数が2000通/月に制限されるといった制限があり、マーケティング・営業・カスタマーサービスに特化したそれぞれの機能を追加したい場合には、有料の「Marketing Hub」「Sales Hub」「Service Hub」へとアップグレードする必要があります。
このため、「HubSpot CRM」はあまり多くの機能を必要としない中小企業や、スタートアップ企業がまずは無料でCRMを導入したいという場合にお勧めのツールです。有料プランは一部のユーザーのみアップグレードをするといった使い方もできるため、まずは無料プランで利用を始め、段階に応じて徐々に活用する範囲を広げていきたいという使い方も可能です。
管理画面が見やすいため、導入に時間がかかりませんでした。Webマーケに必要なモジュールがすべて入っているため、ワンストップで導入でき、データ連携利用も問題ありません。このおかげで、ワークフローを一元管理することができ、運用負担が軽減されました。
https://www.itreview.jp/products/hubspot-crm/reviews/5855
無料であるにもかかわらず、CRMとしての機能はほぼ全て実装されています。使い方も簡単で、あっという間に覚えられました。
https://www.itreview.jp/products/hubspot-crm/reviews/31758
2.Zoho CRM:有料版もコストパフォーマンスの良い中小企業向けCRMツール

「Zoho CRM」は、有料プランも低価格で利用ができ、そのコストパフォーマンスの高さが魅力のCRMツールです。
無料プランでは利用期限はないものの、利用できるユーザーは3ユーザーまで、かつ登録可能なデータ数も5000件までという制限があります。しかし顧客管理、案件管理、レポート作成など基本的な機能は備えており、ワークフローを設定し一部の処理を自動化するといった機能についても試すことができます。「HubSpot CRM」が無料プランでは機能を潔く制限しているのに対し、「Zoho CRM」はさまざまな機能を少しずつ利用できるという違いがあります。
ユーザー数の制限が大きいことや、既存データのインポートについても1000件/バッチといった制限があるため、スタートアップ企業がこれから顧客情報の蓄積を行いたいという場合や、有料プランも踏まえて製品選定を行いたい企業が、基本機能について時間をかけて確認したいという場合におすすめです。
同種の管理ソフトと比較して非常に安価な位置付けのため、導入しやすかったことが良いポイントでした。かといって機能面で特に劣っているという事もなく、コストパフォーマンスに優れています。
https://www.itreview.jp/products/zoho-crm/reviews/22601
顧客管理を一元管理したい、顧客へのフォローを強化したいという課題に適しています。あらかじめワークフローを設定しておけば、その顧客にやるべき対応が自動的に作成されるので、作業効率がアップします。
https://www.itreview.jp/products/zoho-crm/reviews/28795
3.Salesforce Sales Cloud:大企業も利用する世界シェアナンバーワンCRMツール

「Salesforce Sales Cloud」はCRM導入を検討した際にまずその名前を聞かないことはない、世界シェアナンバーワンのCRMツールです。そんな「Salesforce Sales Cloud」も無料トライアル期間が設けられているため、製品検討の際には一度は利用されることをおすすめします。
無料トライアル期間は30日間で、機能は有料版と同じものを利用することができます。
「Salesforce Sales Cloud」の特徴はなんといってもそのカスタマイズ性の高さです。無料で利用できる期間が長いため、自社の現状に即した環境を構築し、実際に営業担当に触ってもらうところまで試すことをおすすめします。大企業だけではなく、自社にあったシステムをしっかり構築し、長く活用したい全ての企業におすすめのツールです。
豊富な機能で、組織として必要な機能全てをブラウザ上で完結させる。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/38529
顧客情報、商談情報、マーケティング情報、その他もろもろのワークフローなども1つのツールで対応できるので便利。
CRMの王道。長年アップデートされてきた歴史から、やりたいことはほとんどできる、カスタマイズ性が一番の特徴になるかと思う。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/36900
4.Zendesk Support:顧客からのお問い合わせ管理に特化したCRMツール

「Zendesk Support」は顧客からのお問い合わせ管理に特化した、無料トライアル期間のあるCRMツールです。「Zendesk Support」にはさまざまな有料プランがありますが、無料トライアルではそのうちの「Professional」版の機能を14日間体験することができます。
特徴はさまざまな方法で寄せられた顧客からの問い合わせを「チケット」化して、誰がいつどのような対応を行ったのか管理・情報共有をすることができることにあり、レポートもこのチケットを基準とした統計情報を確認することができます。
顧客管理の中でも特にカスタマーサポート部門向けで、顧客との接点を管理し顧客満足度を強化したい企業におすすめのCRMツールです。
顧客からの問い合わせに対する返答のクオリティー向上。返答までの時間が見える化できる、かつ過去の問い合わせをナレッジとして蓄積することができるので、会社の資産としても考えることができる。
https://www.itreview.jp/products/zendesk-support/reviews/29729
以前は別の他のサービスを利用してましたが、お問い合わせの蓄積しか出来なかったため乗り換えました。こちらサービスだとひとつひとつのお問い合わせにタグ付けをすることができ、お問い合わせの種別を分析することができます。
https://www.itreview.jp/products/zendesk-support/reviews/11997
5.FlexCRM:基本機能は全て無料。テンプレートから気軽に始められるCRM

「FlexCRM」は無料プランのあるCRMツールで、目的や業種によってあらかじめテンプレートが用意されているために、自社に合わせたシステムを簡単に構築し利用開始することができます。無料プランでは広告表示がありますが、ユーザー数、利用期間に制限はありません。機能としては顧客管理、案件管理、予実管理、日報作成など、CRMとして必要な基本機能以外にもSFA(営業支援)向けの機能も利用することができます。一方でストレージが1GBまで、無料メールや電話でのサポートも受けられないといった制限があるため、組織全体で利用するには物足りなさを感じるかもしれません。一部の部門内など小規模のチームで利用する場合や、有料版の導入も検討している企業が機能確認のために利用する場合におすすめです。
6.Ambassador Relations Tool(ART): マーケティングに長けたCRMツール

「Ambassador Relations Tool」はマーケティングに特化したCRMツールです。無料プランでは登録可能データ数は10,000件までという制限ありますが、顧客情報管理、MA、マーケティングメール、顧客分析等の機能の他、クーポンを発行する機能も備えています。
利用できるユーザーは1名のため、主にマーケティング担当者が利用することになるでしょう。1回あたりのメール送信可能数は10,000通と十分な数のメールを送信することができ、ECサイト運営業、小売業や飲食業などの店舗業におすすめしたいツールです。
7.フリーウェイ顧客管理 : 簡単に複数のデータベースを作成・共有可能

「フリーウェイ顧客管理」はシンプルな画面デザインで誰でも簡単にデータベースを作成できるCRMツールです。無料プランでは利用期限はありませんが、ユーザー数3名まで、登録可能データ数は1000件までという制限があります。また操作に関するサポートを受けることができません。任意の「データベース」を複数作成し、それぞれで設定したフォーマットに従い、情報を蓄積(既存のExcelデータ等があればアップロードも可能)していくことができるため、顧客情報に限らず、商品情報や在庫情報など、これまで社内でリスト管理していたさまざまな情報をクラウドで共有管理を行うことが可能です。ただしレポート作成や分析機能等は備えていないため、蓄積したデータを活用する場合には各データベースの情報をダウンロードして利用する必要があります。社内に点在するさまざまなリストを、一定のフォーマットでクラウド管理したい場合にはおすすめのツールです。
無料製品利用時の注意点
前項にて無料で利用することができるCRMツールをご紹介しましたが、無料の製品を企業活動で利用するにあたり、気を付けたいポイントがいくつかあります。
機能
無料の製品を利用する場合、利用できるユーザー数や機能に制限があることがほとんどです。無理に制限内で利用しようとして、これまでの管理方法より作業効率が落ちてしまっては本末転倒です。製品選定は、CRMの検討を行うきっかけとなった企業の課題を解決することができるのか、現場にとって使いやすいものかどうかといった視点を忘れずに確認しましょう。
サポート
無料で利用する場合、サポートの制限があることが多いです。サポートサービス自体がない場合、問い合わせ方法や受付時間などに制限がある場合などさまざまです。データに突然アクセスできなくなったなど、利用に際して困った場合にどのようなサポートを受けられるか、事前にしっかり確認しておきましょう。
サービスの信頼性
クラウド型のサービスを利用するにあたって、サービスが突然終了することは何よりも避けたいことです。しかし無料版は収益性がないため、有料版と比べてこのリスクは必然的に高くなります。選定の際には利用規約を必ず確認し、そのサービスが信頼のおけるサービスかどうかを確認しましょう。
データの引継ぎ
当初は無料の製品を利用していても、情報の増加、社員の増加、サービスの追加など、さまざまな理由によって、将来、他の製品や有料版へ移行をすることも考えられます。蓄積したデータを他製品や有料版にそのまま移行することができるのか、ダウンロードはどのような形式で行えるのかについても確認しましょう。
冒頭でも書いた通り、無料版の製品はこれまでCRMツールを利用されたことがない方が体験したり、または全社展開する前にトライアル利用したりするには非常にお勧めです。一方で、有料版は無料版と比較して、機能面はもちろん、信頼性という点でも優れている場合がほとんどです。企業活動の基盤となる重要な情報である顧客情報を、自社の強みとして経営に役立てるために、CRM導入の目的、目的を達成するために必要な機能等を明確にし、最適なツールを選定してください。
当ITreviewのカテゴリーページでは、有料版も含め顧客満足度の高いCRM製品を紹介しています。CRMの導入について興味を持たれた方は、ぜひ一度ご覧ください。
投稿 無料で使える日本語対応CRM7選|有料版との違いや注意点を解説 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 オンラインストレージAmazon Driveとは?法人でも利用できる? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>Amazon Driveとは

Amazon Driveはネット通販大手の「Amazon」が提供するオンラインストレージサービスです。Amazon会員であれば容量5GBまで無料で利用できます。Amazonへの会員登録は無料でできます。
なお、5GB以上の容量を利用したい場合は有料となり、その料金体系は次の通りとなります
(参考:https://www.amazon.co.jp/photos/storage/plans)
| 容量 | 価格(1年間) |
| 100 GB | 2,490円 |
| 1 TB | 13,800円 |
| 2 TB | 27,600円 |
| 3 TB | 41,400円 |
| 4 TB | 55,200円 |
| 5 TB | 69,000円 |
| 6 TB | 82,800円 |
| 7 TB | 96,600円 |
| 8 TB | 110,400円 |
| 9 TB | 124,200円 |
| 10 TB | 138,000円 |
| 20 TB | 276,000円 |
| 30 TB | 414,000円 |
Amazonプライム会員(年間4,400円)であれば、写真の保存容量が無制限となるAmazon Photosのサービスも利用できます。写真以外のファイルについてはAmazonプライム会員であっても無料で利用できる容量は5GBとなります。
Amazon Driveは法人利用に適しているか
ここではAmazon Driveのメリットとデメリットについて述べ、法人利用に適しているのかどうかを検証していきます。
Amazon Driveのメリットとデメリットについては次の通りです。
メリット
●Amazon会員に登録さえすれば誰でも利用できる。
Amazon会員に登録すれば、自動的に5GBの容量が付いてきます。会員登録は無料ですので、無料で5GBの容量が使えます。
●使い方が簡単
ブラウザでAmazon Driveのページに移動し、Amazon会員のアカウントでログインするだけで利用ができます。ファイルのアップロードは、ブラウザ画面にファイルをドラッグアンドドロップするだけで可能です。
また、ダウンロードはファイルを選択して「ダウンロード」をクリックするだけで利用できます。スマートフォン(iOS、Android)用のアプリも用意されており、スマートフォン上でもファイルのやり取りや閲覧が可能です。
デメリット
●PC用のアプリがAmazon Photosしかない
最近のオンラインストレージサービスは、専用アプリをインストールすることでクラウド上のファイルもPC上でシームレスに扱えるようになっています。
しかし、Amazon DriveではPC用アプリはAmazon Photosのものと兼用になっており、画像や動画ファイル以外のファイルに対しての操作性はあまりよくありません。
また、PC用Amazon Photosアプリでは、Windowsのエクスプローラーと同期させることや、MacにAmazon Driveをマウントして同期させることもできません。
●権限管理ができない
Amazon Driveも、他のオンラインストレージと同じようにファイルごとにURLリンクを生成し、それを共有したい相手に送付することでファイル共有することができます。
しかし、Amazon Driveにアップロードしたファイルに対しては、閲覧制限などの設定ができません。したがって、誤った相手にファイル共有リンクを通知してしまった場合には、本来見せたくない相手にも見られてしまいます。これでは、誤送信による情報漏えいのリスクが高く、機密情報を含むファイルを共有することはできません。
法人利用には限界がある
Amazon Driveは誰でも使える便利なサービスではありますが、管理機能やPC利用、そして大容量のストレージを使いたい場合の価格体系を考えると、あくまでも個人向けであり、法人利用に適しているサービスとは言えません。
法人向けの場合、Amazonが提供するオンラインストレージサービスであれば、Amazon Driveよりも AmazonS3のほうが適しているでしょう。
AmazonS3とは

AmazonS3(Simple Storage Service)はAmazonがAWS(Amazon Web Services)の1つとして提供しているクラウドストレージサービスです。
その特徴としては次のものがあります。
・99.999999999%のデータ堅牢性
・ファイル、ユーザーごとの細かなアクセス権限設定が可能
・完全従量課金制でデータ容量無制限
・サーバ側、クライアント側の暗号化サポート
・ストレージデータを利用したビッグデータ解析が可能
ただし、Amazon S3を法人で利用する場合には次のようなデメリットもあります。
●課金体系が複雑すぎる
容量、保管期間、アクセス頻度だけでなく、アクセス数やデータリクエスト回数、データの送受信回数や分析、レプリケーションなどファイルの操作に対し課金体系が細かく設定されており、あらかじめどのように利用するか明確にしておかないと、コストがどれだけかかるかわからない面があります。
Amazon S3の課金体系については以下のURLを参照してください。
https://aws.amazon.com/jp/s3/pricing/?nc=sn&loc=4
●設定が複雑である
通常のオンラインストレージサービスと違い、Amazon S3はAWSの1つのサービスとして提供されているため、AWSとの連携機能が充実しています。しかし、連携機能を確実に利用しようとするとS3だけでなく他のAWSサービスの設定も必要となります。
ビッグデータ解析等のAWSサービスと連携するのであればともかく、単純にバックアップやファイル共有をしたい場合のオンラインストレージとしてはAmazon S3では機能や設定項目が高度すぎて、あえて使うメリットはありません。
法人利用に適したオンラインストレージサービス3選
ここではAmazon DriveやAmazon S3に比べ、一般的な法人利用に適したオンラインストレージサービスを3つ挙げ、それぞれのサービスについて説明します。
1.Dropbox Business
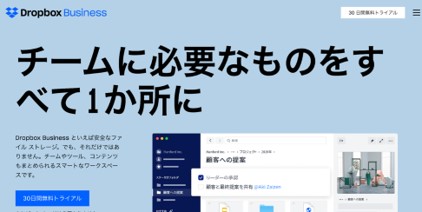
Dropbox Businessは全世界で5億人が使用しており、世界的なシェアを誇るオンラインストレージサービスであるDropboxの法人向け有料版です。
シンプルなインタフェースによる操作性の良さやPCとの自動同期、暗号化、ファイルの復元とバージョン履歴、デバイスのデータ遠隔削除、2 段階認証(2FA)の有効化に加え、チーム管理のための管理コンソールや外部アプリケーションとの連携などの機能を備えています。
2.Box
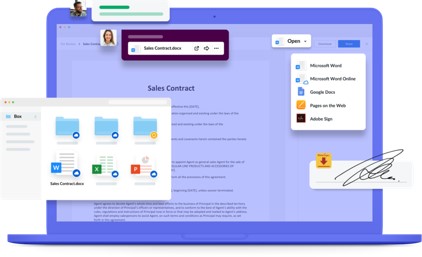
BoxはアメリカのBox社が提供するオンラインストレージサービスです。セキュリティ面での機能が高く、主に企業を中心に導入が進み95,000社にて利用されています(2019年12月時点)。その内の70%がフォーチュン500企業です。日本でも多くの上場企業や大学などで利用されています。
Boxには容量無制限のプランや、100種類の拡張子に対応したファイルプレビュー機能、豊富な権限設定とコンテンツ共有機能、高度な暗号化によるセキュリティや使用ログのレポート確認機能などが付いています。
3.OneDrive for Business

OneDrive for BusinessはMicrosoft社が提供するオンラインストレージで、WindowsやOffice365との連携機能が充実しており、WordやExcelなどのドキュメントの共有がスムーズにできる点が評価されています。
OneDrive for Businessのプランには、サブスクリプションユーザーが5人以上という条件をクリアすると、容量無制限で利用できるものもあります。このプランでは高度なデータ損失防止機能も持っており、不正アクセスに備え、削除済みや編集済みのデータも保持しています。
法人で使うならAmazon Driveではなく、ビジネス向けのオンラインストレージをおすすめします。
今回はAmazon Driveの機能紹介と法人利用の可能性について解説しました。Amazon Driveは容量やセキュリティ、共有機能であまり法人利用には適しているとはいえません。
Amazonが提供する他のストレージサービスAmazon S3もAWSとの連携を前提としな
いのであれば、ファイル保存・共有のオンラインストレージとしては高機能、且つコスト高となります。
ご紹介した3つの法人利用に適したオンラインストレージサービス以外にも、法人で使えるオンラインストレージを多く紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
投稿 オンラインストレージAmazon Driveとは?法人でも利用できる? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Salesforce(セールスフォース)の特徴は? 競合CRMツールとの違い は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>CRMの導入を考えた際に候補として一度は名前が挙がるのが、世界シェアナンバーワンであるSalesforce(セールスフォース)だ。
本記事では、多くの企業が利用する「Salesforce Sales Cloud」の機能や特徴を、他のCRMとの比較や、当ITreviewに寄せられたレビューなどから解説する。
CRMの成り立ちとSalesforceについて
顧客管理の重要性と、CRM誕生
顧客情報は商売にとって欠かせないものであり、その管理を大切に行うという概念は、近年始まったものではない。
マーケティングについて学ばれた方であれば、「江戸時代の商人は、大福帳(だいふくちょう:当時の顧客台帳)に顧客ごとの取引内容を記録し、顧客ごとに異なるニーズに対応していた。火事になれば大福帳は井戸に投げ込んで守られ、そのために紙は水に漬かっても文字が消えないように特殊なノリで加工されているという徹底ぶりであった。顧客情報さえあれば商売は再開することができるために、大福帳は商人にとって何よりも重要なものとされていた」という話を聞いたことがあるのではないだろうか。
それをコンピュータで実現しようとCRMが生まれたのは1990年代後半、米国でのことだった。消費者の暮らしの変化に伴い、それまでの大量生産・大量消費を前提とした「マスマーケティング」の効果が薄れつつある中、消費者の嗜好の多様化に対応するために「One to Oneマーケティング」の必要性が高まりつつあった時代である。
当時のCRMは「統合型CRM」とも言われ、単なる顧客情報を管理するためだけのものであり、また、システム規模も大きいために導入のハードルは高く、主に大企業を中心に利用されていた。
しかし、その後の時代の移り代わりに合わせてCRMは進化を続け、さまざまな業界の業務プロセスに適したさまざまなツールが、インターネットの爆発的な普及やクラウドサービスの発展により、安価かつ手軽に利用できるようになった。近年ではAIの活用により、これまで以上に顧客一人一人に合わせたコミュニケーションを実現できるようになっている。
Salesforce.com(セールスフォース・ドットコム)はどんな会社?
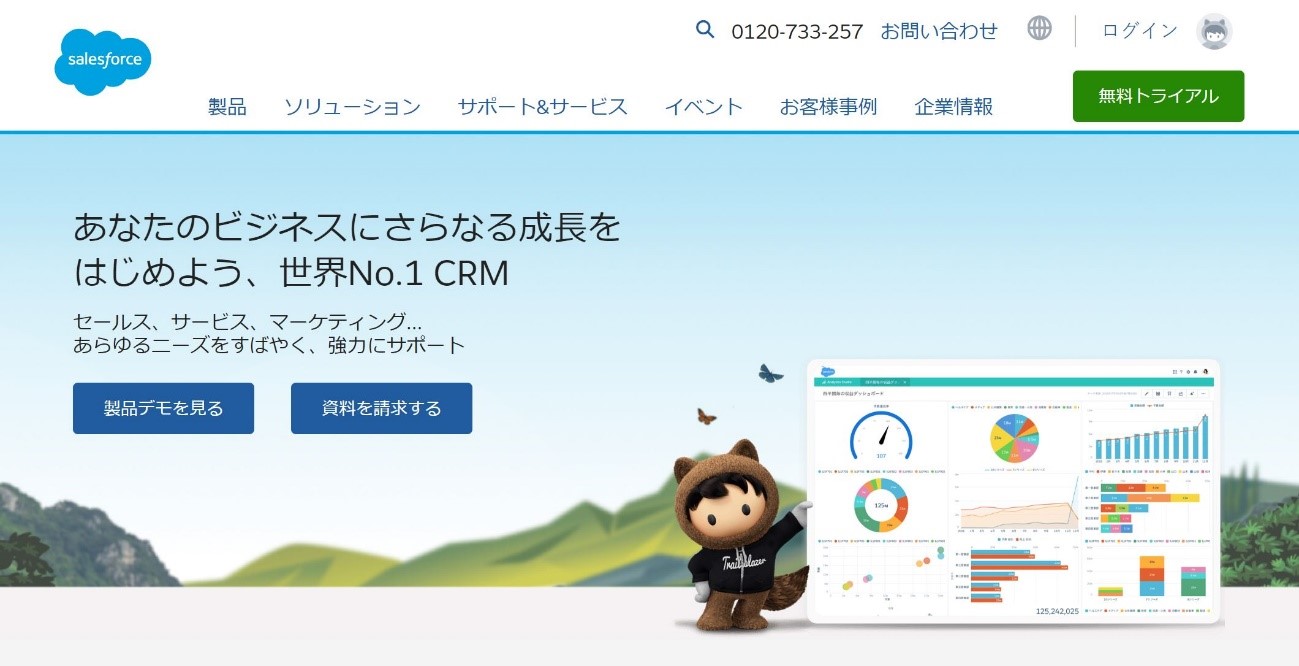
セールスフォース・ドットコムは、1999年にアメリカのカリフォルニア州に設立された。前項でも簡単に触れたが、当時のCRMは巨大なコストをかけてシステム構築をする必要があった。これに対する企業の不満を解決するために生まれたのがセールスフォース・ドットコムである。
セールスフォース・ドットコムのサービスは全てクラウド型で提供されており、サーバなどの初期費用が不要で、インターネット環境があれば場所を問わず、月額費を払うことで常に最新版のサービスを利用することができる。
セールスフォース・ドットコムはSaaSと呼ばれるこのビジネスモデルのバイオニアで、営業支援・CRMツールの企業としては世界シェアナンバーワンを誇る。
日本においても株式会社セールスフォース・ドットコムが2000年に設立され、大企業から従業員数名の企業まで、さまざまな企業が利用をしている。日本においても株式会社セールスフォース・ドットコムが2000年に設立され、大企業から従業員数名の企業まで、さまざまな企業が利用をしている。
Salesforceの多彩なサービス
セールスフォース・ドットコムはさまざまなサービスを提供しているため、いざ検討をしようと思っても、初めて製品群を目にした際には戸惑われたのではないだろうか。
セールスフォーム・ドットコムのサービスは、主に2つに分かれる。
1つは、アプリケーションだ。
営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、各製品がテーマとする領域における包括的な機能を持ったアプリケーションがあらかじめ用意され提供されている。ユーザーは全てのアプリケーションを利用する必要はないため、自社の課題に合ったものを選択して利用することができる。
もう1つ、セールスフォース・ドットコムでは、アプリケーションを構築するためのプラットフォームそのものも提供している。
自社の業務効率化のための独自アプリケーションや、顧客に提供するためのアプリケーションなど、ニーズにあわせたさまざまなアプリケーションを開発することが可能だ。
| 製品名 | 概要 |
| Sales Cloud | 営業支援に特化したサービスで、組織の営業力を高めるための機能を提供 |
| Service Cloud | カスタマーサービスに特化したサービスで、高いサポートを行うための機能を提供 |
| Marketing Cloud | マーケティングに特化したサービスで、One to Oneマーケティングを実現するための機能を提供 |
| Pardot | BtoB向けのマーケティングオートメーションツール |
| Commerce Cloud | BtoC、BtoBに向けた電子商取引(EC)サイトの運営機能を提供 |
| Heroku | 社外の情報と連携させたアプリケーションの開発 |
| Salesforce Platform | 社内向けの独自アプリケーションの開発 |
| MuleSoft Anypoint Platform | Salesforceをはじめとしたあらゆるシステムを接続して1つに統合 |
| Einstein Analytics | CRMと連携したデータ分析やAIによる拡張分析 |
| Community Cloud | 社内をはじめ、顧客・代理店・パートナーとのオンラインコミュニティの構築 |
| myTrailhead | 自社独自のオンライン学習コンテンツの作成 |
| Quip | 文書やスプレッドシート、スライドなどのドキュメントの共同管理 |
| Chatter | 社内SNSの構築 |
Salesforce Sales Cloudの機能紹介
前項でセールスフォース・ドットコムが提供するさまざまなサービスをご紹介したが、本項からはその中でも営業活動支援に特化した「Salesforce Sales Cloud」について具体的に解説していきたい。
「Salesforce Sales Cloud」は、世界トップシェアを誇るCRM/SFA※サービスである。
世界トップシェアの名はだてではなく、特に評価が高いのは、機能の豊富さとカスタマイズ性の高さである。
営業活動に限らず、社内のさまざまな情報を一元管理することができるため、あらゆる企業活動を効率化させ、売上向上に繋げていくことが可能なサービスだ。
※CRM(Customer Relationship Management):顧客管理システム
SFA(Sales Force Automation):営業支援システム
顧客管理機能
顧客管理機能では、取引先企業の住所、担当者の連絡先といった基本情報から、現在進行中または過去の商談の状況や金額、お問い合わせ履歴、過去に参加いただいたセミナー、社内メモ、提出した提案書・見積書など、顧客に関するあらゆる情報を一元管理することができる。
企業情報には、営業が入力した情報以外にも、株価情報やGoogle Mapなど外部のWebサイトと連携させ情報を表示することも可能だ。担当者情報には、担当者の趣味や組織図上での立ち位置なども記録できるため、企業や担当者をより深く理解した上で商談に臨むことができる。
また、「Salesforce Sales Cloud」では、自社サイトからお問い合わせフォームや資料請求、セミナー申し込みなどがあった場合に、見込み客として自動的に情報を取り込むことができる。受付後すぐに自動返信メールを送信したり、担当営業を自動的に割り振ったりすることもできるため、「誰が担当するのか」といった無駄な手間を減らし、素早く見込み客にコンタクトを取ることができる。
案件管理
案件管理機能では、現在進行中の案件や、過去に完了した案件の情報を全て管理することができる。
案件情報は、案件の規模、種別、確度、完了予定日などの情報のほか、競合相手の情報も記録することが可能だ。
案件に関連した活動予定や履歴も表示され、案件を受注するために誰がどのように商談を進めたのか全ての履歴が残るため、インサイドセールスからフィールドセールスへのスムーズな引継ぎや、二重コンタクトによるクレームを防ぐこともできる。
案件は受注に至ったものだけではなく、失注した案件についても情報が蓄積されるため、営業活動を分析し、今後の戦略策定に役立てることも可能だ。
情報はモバイル端末からも利用することができるため、外出先でスマートフォンから顧客の情報を確認し、商談が終わった後の移動時間に更新を行えるほか、電話会議に参加するなど、会社に戻らずとも外出中の隙間時間を有効活用することができる。
売上予測
担当者別や営業部門全体の売上予測を一目で把握することが可能である。
通常、集計は個々の営業担当が入力した売上予測データを用いて行われるが、この数字は営業担当によって高めであったり、低めであったりする場合がある。このため、担当者や管理者は、売上予測金額を調整し、上書きすることができる。
他のマーケティングツール等との連携
「Salesforce Sales Cloud」で蓄積された顧客情報は、「Salesforce Marketing Cloud」や「Salesforce Service Cloud」、「Salesforce Community Cloud」などと連携させ、社内全体で活用することができる。Salesforceは機能ごとにアプリケーションが分かれているため、最初は必要最低限の構成で始め、段階的にアプリケーションを追加していくといった方法を取ることが可能だ。
また、自社製品以外との連携もさまざまな方法で行う事ができるため、これまで利用していたシステムとの連携なども行うことができる。
前項で「Salesforce Sales Cloud」の機能を紹介したが、他社のCRMサービスでも同様の機能を持っているために、判断に迷われることも多いだろう。
Salesforce Sales Cloudと他社のCRM製品との比較
前項で「Salesforce Sales Cloud」の機能を紹介したが、他社のCRMサービスでも同様の機能を持っているために、判断に迷われることも多いだろう。
本項では、前項で紹介した各機能を軸に、「Salesforce Sales Cloud」と他社のCRMツールとの比較をしたい。
顧客管理機能
| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |
| 企業情報管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 担当者情報管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 名刺取り込み | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 項目カスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 見込み客管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| キャンペーン管理 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メール一括送信 | 〇 | △ 最大1000/日 |
「Salesforce Sales Cloud」は顧客との関係性を構築するためのさまざまな機能を備えており、見込み客を顧客に変換するまでの包括的なサービスを提供している。
「eセールス マネージャー Remix Cloud」はCRMツールの中でも営業の現場支援に重きを置いているため、それ以外の機能については若干物足りなさを感じるかもしれない。
「Zoho CRM」は高機能ではあるが、プランによって利用できないものやカスタマイズ可能な数に制限がある。
案件管理
| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |
| 案件管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 活動管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 日報作成 | 〇 | 〇 | ||
| カレンダー共有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ワークフロー機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データ分析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| モバイル対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 他通貨対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
案件管理機能については各社で大きな機能の差はないが、「Salesforce Sales Cloud」は多くの機能が用意されてる一方で海外製のために使いづらいという声が見られることがある。一方で「eセールス マネージャーRemix Cloud」は日本の営業活動支援に合わせて作られているなど、おもにUIの面で違いを感じることが多いだろう。
売上予測
| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud |
Zoho CRM | |
| 売上目標設定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 予実管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 売上予測金額調整 | 〇 | |||
| データ分析・AIによる売上予測 | 〇 拡張機能 |
〇 | 〇 エンタープライズのみ |
どのツールも売上目標に対する予算に対する実績や見込みを一目で確認することができ、担当者別、期間別などさまざまな切り口から分析を行う事ができる。
「Salesforce Sales cloud」は、入力された売上予測を集計するだけではなく、AIによる売上予測も表示することができ、管理者はさまざまな情報を加味した上で売上予想金額に調整を行い、よりシビアな分析を行うことができる。
他のマーケティングツール等との連携
| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |
| 自社マーケティングツール連携 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 他社マーケティングツール連携 (API連携) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 機能拡張 (プラットフォーム) | 〇 AppExchange |
〇 Oracle Cloud Marketplace |
〇 Zoho Marketplace |
「Salesforce Sales Cloud」は「Salesforce Marketing Cloud」などの自社製品との連携の他、他社ツールとの連携や「AppExchange」というアプリケーションプラットフォーム(App Storeのセールスフォース版のようなもの)を利用して、無料・有料のアプリケーションの中から、有用なアプリケーションを自由にダウンロードして機能を拡張することもできるため、実現できないことはまずないといわれるほどである。
蓄積されたデータをマーケティング等で利用する他、これまで利用していたシステムとの連携を行いたい場合や、導入後にもカスタマイズや機能拡張を行っていきたい場合には特に有効だ。
金額
| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |
| 無料プラン | 無料プラン 0 円 / 3ユーザーまで | |||
| 導入プラン | Essentials (10人まで) 3,000 円 /ユーザー/月 Professional 9,000 円 /ユーザー/月 | Professional Edition 7,800 円 / ユーザー/月 | スタンダード 1,440 円 / ユーザー/月※ | |
| 標準プラン | Enterprise 18,000 円 /ユーザー/月 | Standard Edition 12,000 円 / ユーザー/月 | 基本ライセンス 6,000 円 / ユーザー/月 | プロフェッショナル 2,400 円 / ユーザー/月 ※ |
| 上位プラン | 36,000 円 /ユーザー/月 | Enterprise Edition 24,000 円 / ユーザー/月 | エンタープライズ 4,200 円 / ユーザー/月※ |
※年間払い月額換算金額
「Salesforce Sales Cloud」は他のツールに比べると割高に見えるが、カスタマイズ性
が非常に高いため、自社の業務プロセスに合わせて自由に変更を加えることができる。
一方で「eセールス マネージャー Remix Cloud」は利用したい機能によってオプションを
追加する必要があるため最終的に運用コストが高くなる可能性がある。また、「Zoho CRM
」は安価な一方、ストレージの容量や各機能で利用できる数に制限がある。
初期導入費用や運用コストが安価な製品であるかどうかだけではなく、費用対効果に見合
う製品かどうかで判断をする必要があるだろう。
サポート
| Salesforce Sales Cloud | Oracle Sales Cloud | eセールス マネージャー Remix Cloud | Zoho CRM | |
| 問い合わせフォーム/メール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 有料プランのみ |
| 電話 | △ ベーシックサポート: 平日9:00~17:00 ※全ユーザに影響を与える重大な問題のみ プレミアサポート: 平日9:00~18:00 |
〇 9:00~19:00 (12:00~13:00及び土日祝日は除く) |
||
| FAQサイト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
サポートについては、国産のサービスか海外産のサービスで大きく異なり、純国産の「eセールスマネージャーRemix Cloud」は専任チームが定着までサポートを行ってくれるなど、手厚いサポートは評価が高い。
一方「Salesforce Sales Cloud」は電話の問い合わせは、通常プレミアサポートに限定されてしまっている。しかし問い合わせフォームからの返信は早く、また、ヘルプサイトが充実しており、ドキュメントや動画で不明点を確認する、コミュニティでエキスパートにアドバイスをもらうといったことが可能である。
Salesforce Sales Cloudのレビュー紹介
本項では、「Salesforce Sales Cloud」について当ITreviewに寄せられたユーザーからのレビューをピックアップしてご紹介する。
顧客管理機能
営業管理をExcelから脱することができた。またデータ管理となったため進捗管理の方法も属人化しないようになり生産性も30%以上向上した。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/647
スマートフォン、PCどこからでもリアルタイムで顧客情報や営業メンバーの動きが確認できるため、顧客管理だけに留まらず、社内の情報共有のスピードも格段にアップした。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/1504
多くのクライアント様をシンプルで分かりやすい操作画面で管理する事が出来る。海外拠点と一緒に使用する場合も、その国の言語設定が出来る為、海外拠点と同じデータを活用でき、紐づけることが出来る。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/10863
案件管理機能
価格設定や社内承認など、見積もり・請求に関するプロセスも自動化できて、煩雑な作業が減りました。また、営業部門・営業担当はさらにすばやく商談をまとめられるようになりました。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/1401
営業活動や案件進捗、取引情報や製品資料など多くの情報が集約されており、何か困ったらとりあえずSalesforceで検索してみる、という使い方も出来る便利なアプリ。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/7015
携帯アプリも使いやすく、むしろPCからよりも多く利用している。
営業用CRMとして基本的な機能が全て備わっている。リードからナーチャリング、顧客化等、各フェーズにおいてどのようなステータスなのか一目で把握できるため、夫々のステータスに応じた施策を打てる。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/4788
売上予測
Salesforce Sales Cloudを導入することで、複数でのエクセル管理が無くなりました。一番の課題解決は、月末に向けての売上実績・予測や、月次収支、クライアント別収支等を、レポート機能を活かしてリアルタイムで見れるようになりました。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/4728
年間の受注パイプラインおよび売上パイプラインが見える化するので、着地数字が予想できるのと、現在の状況を透明化することができる
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/27356
他のマーケティングツール等との連携
有名なサービスなのでサードパーティー製品が多いのが一番のポイント。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/978
また、カスタマイズすることで希望のシステムが実現しやすい。
標準オブジェクトの充実度も去ることながら、アプリマーケット「AppExchange」も充実しており、必要な機能はサードパーティーアプリで補完できるように設計されている。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/14366
金額
費用面を改善してほしい。ベンチャー、スタートアップには導入ハードルが高い。また初期設定ハードルが高いため、初期の支援を強化してほしい。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/4852
CRMとしては優れていますので仕方のない部分はありますが、価格について改善がなされるといいと思います。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/21399サポート
サポート
ヘルプが難解なことがあり、独自に学ぶことが難しい(ただし、サポートは即レスで的を射た返事をしてくれるので非常に好感触)
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/10834
サポートが手厚い。
https://www.itreview.jp/products/salesforce-sales-cloud/reviews/8777
営業は契約期間がある程度たつとメールや電話で使用状況についてヒアリングしてくれる。
レビューの中では、「解決された課題」として、これまでExcelで管理されあちこちに点在していた顧客情報やあらゆるビジネス活動が一元化され、業務改善や管理コスト削減に繋げることができたという声が多く見られた。営業活動で主に活用されているが、コールセンターや購買管理など、営業に限らず広く利用されている。
見える化がされたことで、部門全体のモチベーション向上や、社内の異なる部署でのコミュニケーションが円滑されるなど、得られる効果は営業効率化に限らずさまざまな面で見られた。
一方で「改善してほしいポイント」として見られるのは「価格の高さ」についてであった。
カスタマイズ性に優れ、実現したいことはおよそ全てのことは実現することができるが、反面その環境を構築するために、ライセンス費に加えて構築のためのコストが発生することもある。また、カスタマイズをすればするほど利用開始までにかかる時間は長くなってしまう。
これらのことから、「Salesforce Sales Cloud」は、スタートアップやベンチャー企業よりも、大企業や、大企業でも採用するような信頼性・拡張性の高い製品を長期に渡って利用したい中小企業に向いているといえるだろう。
投稿 Salesforce(セールスフォース)の特徴は? 競合CRMツールとの違い は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Macにもセキュリティ対策は必須!最適なVPNをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>Macをターゲットにしたコンピュータウイルスが少ない要因は、MacのOSシェアがWindowsと比較して低いことです。2019年12月時点でのOSシェアは、Windowsが77.7%であるのに対して、Mac(macOS)は17.04%です。サイバー犯罪者側は、Mac(macOS)よりもシェアの大きいWindowsをターゲットにしたコンピュータウイルスを、積極的に開発する傾向があるとみられます。
参照元:StatCounter Global Stats「デスクトップオペレーティングシステムの世界シェア」
https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide
さらに、Apple社の公式サイトでなどで「Macはセキュリティソフト不要」と宣伝していた時期があることも、セキュリティ面で強いことを印象付けています。そのため、「Macには積極的にセキュリティ対策を行っていない」という方も多いのではないでしょうか。しかし実際には、Macにもセキュリティリスクは存在します。
特に法人でMacを利用されている場合は、しっかりとしたセキュリティ対策が必要です。そこで本記事では、Macのセキュリティリスクとその対策としてのVPNについて取り上げます。
Macにもセキュリティ対策が必要なワケとは?

冒頭で説明した通り、MacはWindowsに比べてセキュリティ面で強いイメージがあり、「Macはコンピュータウイルスに感染しない」という俗説もありますが、それは大きな間違いです。実際には、Macをターゲットにしたランサムウェアなどの脅威も存在します。
そして、法人や組織を対象にしたサイバー攻撃でも、Macは脅威にさらされています。情報処理推進機構(IPA)が2019年に発表した「情報セキュリティ10大脅威」では、組織向けの脅威のワースト3は次のようになっています。
1位:標的型攻撃による被害
2位:ビジネスメール詐欺による被害
3位:ランサムウェアによる被害
これら3つの脅威の主要な侵入経路は不正メールとなっており、その対策が重要です。不正メールは、WindowsとMacの種別に関係なく侵入します。そして不正メール対策を強化する上で忘れてはならないのが、インターネットからの不正アクセス対策です。
なぜなら、不正アクセスで会社情報が盗み取られることが、より巧妙なビジネスメール詐欺につながるからです。また、不正アクセスにより社内PCのIPアドレスを知られることで、PCが直接サイバー攻撃を受けるリスクも高まります。
Macを対象としたサイバー攻撃が増えつつある現在、インターネット経由の不正アクセス対策は重要性が高まっています。そこで、Macの不正アクセス対策として、最も有効な手段の1つがVPNです。VPNの使用によりMac PCのデータとIPアドレスを守り、不正アクセスを防止することが、セキュリティ強化につながります。
会社の規模に応じた最適なVPNとは?
法人でVPNを使用する場合、主に「インターネットVPN」と「クラウドVPN」の2つに分けられます。インターネットVPNが、複数の拠点を持つ社員数の多い会社に適しているのに対して、クラウドVPNは、社員数の少ない会社に適しています
インターネットVPN
インターネット回線をVPN通信に利用する方式です。インターネットVPNでは、セキュリティを確保するために、本社や支店など各拠点にVPNルーターを設置します。そして各拠点の社内LANは、設置したVPNルーターを介してインターネットに接続されます。
VPNルーターには、主に「データの暗号化」と「暗号化されたデータの復号」の2つの役割があります。社内LANから他の拠点にデータを送信する場合は、「データの暗号化」を行います。逆に、他の拠点からデータを受信する場合は、「暗号化されたデータの復号」をした後に、社内LANに送ります。
つまり、インターネットVPNでは、VPNルーターの設置により、インターネット上の全通信データを暗号化することで、セキュリティを強化します。通信データの暗号化により、仮想的に「複数の拠点を含めた大きな社内LAN」を構築できます。
インターネットVPNは、VPNルーターの設置・設定が必要なので、主に国内の会社がサービスを提供しています。
クラウドVPN
インターネットVPNの一種ですが、各拠点にVPNルーターを設置せずに、クラウド上のVPNサーバを使う方式です。拠点に設置したPCにVPNソフトを導入することで、PCとVPNサーバ間の通信を暗号化してセキュリティを高めます。
VPNルーターを会社で持つ必要がないため、導入費用とメンテナンス費用を軽減できるメリットがあります。少人数でも手軽に導入できるので、社員数の少ない会社に向いています。
クラウドVPNは、日本よりも海外のほうが発達しています。その背景にあるのが、海外のインターネット犯罪率の高さです。日本よりも犯罪率が高い海外では「自分の身は自分で守る」という意識が高いことは知られていますが、インターネット犯罪でも同様です。
海外では、個人がインターネット犯罪から自分の身を守る手段として、クラウドVPNが大きな役割を果たしています。クラウドVPNが発達している海外には、安全性や価格面などで日本よりも優れたサービスが多くあります。
優れた海外クラウドVPNサービスの多くは、セキュリティを高めるため世界各国に多くのVPNサーバを設置しています。クラウドVPNは、VPNサーバの選択肢が多いほど、サイバー攻撃のリスクを低減できます。さらに、そうした優れた海外サービスは、世界各国の多くのユーザーにサービスを提供することで、効率化による低価格化も実現しています。
Macに対応した日本のVPNサービス
複数の拠点を持ち社員数が多い法人向けの、Macに対応した国内のVPNサービスを2つご紹介します。
1. SmartVPN(ソフトバンク)

SmartVPNは、ソフトバンク運営する、複数の拠点間の通信を安全に行うためのインターネットVPNサービスです。
・対応するアプリケーション
Mac以外で対応するアプリケーションは、PCではWindows、タブレットではiPhoneとiPadです。
・サービス内容と料金
拠点とVPNとの接続には、4つのメニューがあります。拠点ごとに取り扱いデータに適したメニューを選ぶことができます。
(1)ギャランティータイプ(0.5Mbps~1Gbps)
最も品質を重視した、帯域確保型のアクセス回線サービスです。
初期費用:70,000円 月額料金:48,000円〜
(2)スピードタイプ(100Mbps/5Mbps〜300Mbps/100Mbps)
サーバを設置したデータセンターなど、上りの通信量が多い拠点向けのアクセス回線サービスです。
初期費用:70,000円 月額料金:210,000円〜
(3)バリュータイプ(100Mbps/5Mbps〜300Mbps/100Mbps)
営業所や支店など、下りの通信量が多い拠点向けのアクセス回線サービスです
初期費用:70,000円 月額料金:87,000円〜
(4)ベストエフォートタイプ(100Mbps、300Mbps)
ソフトバンクの直轄回線を利用した、高品質・広帯域なアクセス回線サービス
初期費用:70,000円 月額料金:39,800円〜
・WindowsとMacを併用する企業におすすめ
Macは、フリーランスの方のユーザーが多いイメージがありますが、最近は企業でもMacの採用が進んでいます。今までWindowsを使っていた企業が、Macを導入して併用する場合、Mac向けの新たなセキュリティ対策が必要です。
SmartVPNは、WindowsとMacに対応しているので、両方のセキュリティを効率的に保つことができます。SmartVPNは、Macを導入した場合の新たなセキュリティ対策費用を、抑えることができます。
「SmartVPN」のユーザーレビューは、以下のサイトをご参照ください。
2. beat/activeサービス(富士ゼロックス)

beat/activeサービスは、コピー機やプリンタなど大手総合複合機器メーカーとして有名な富士ゼロックス運営するVPNです。会社の各拠点にbeat-box(VPN装置)を設置することで、拠点間のVPN通信を行うサービスです。
・対応するアプリケーション
Mac以外で対応するアプリケーションは、PCではWindows、スマートフォンではiOSとAndroidです。
・サービス内容と料金
VPNを使うためには、「基本サービス」と「インターネットVPN」の両方への登録が必要です。インターネットVPNは、通常プラン(システム管理者配置)と、システム管理者を配置できない少人数拠点向けのプランがあります。
(1)基本サービス
・beat/activeサービス:12,800円/月
・beat/active初期登録サービス:60,000円/件
※active移行補助ツール作業付の場合は、90,000円/件
(2)インターネットVPN(通常プラン:システム管理者を配置する拠点)
・beat/active VPN接続サービス:1,000円/月
・beat/active VPN接続設定サービス:30,000円/件
(3)インターネットVPN(システム管理者が配置できない少人数の拠点向けのプラン)
・beat/active branch-lite接続追加サービス:10,000円/月
・beat/active branch-lite接続追加設定サービス:30,000円/件
・beat/branch-lite サービス:7,800円/月
・beat/branch-lite 初期登録サービス:50,000円/件
・Macにおすすめの理由
beat/activeサービスは、システム管理者が配置できない小規模の拠点にも対応しているのが特徴です。Macユーザーは、デザイナーやエンジニアなどのクリエイティブ職種の方が多い傾向があります。beat/activeサービスは、少数精鋭型のクリエイティブ関連の会社でも、システム管理者に人件費をかけることなく導入可能です。
Macは、フリーランスの方
「beat/activeサービス」のユーザーレビューは、以下のサイトをご参照ください。
Macに特化した海外サービス
社員数が少ない法人におすすめのMacに特化した海外サービスを2つご紹介します。
1. ExpressVPN

・本社所在地
ExpressVPNは、法的にデータ保持の義務がないイギリス領バージン諸島に本社を置いています。
・ログの取得
利用規約のプライバシーポリシーでは、閲覧履歴やトラフィックの宛先、データコンテンツ、またはDNSクエリを収集・記録しないことを明示しています。
・対応するアプリケーション
Mac以外で対応するアプリケーションは、PCではWindowsとLinux、スマートフォンではiOSとAndroidです。
・サーバ数と所在地
サーバは94カ国160カ所に、合計3,000台以上設置されています。設置場所は、南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東、アフリカの世界各地におよびます。日本の設置箇所は4カ所です。
・VPN通信方式
対応可能なVPN通信方式は、サーバごとに違います。最もセキュリティの高い「Open VPN」には、ほとんどのサーバが対応可能です。
※日本国内のVPNサーバは、一部「Open VPN」未対応。
・通信できる端末数
1つのサブスクリプションで、同時に接続できる端末(デバイス)数は、5台です。
・料金
料金は長期契約になるほど割安で、30日返金保証があります。
1カ月契約:12.95ドル/月(約1,411円/月)
6カ月契約: 9.99ドル/月(約1,089円/月)
1年契約 : 6.67ドル/月(約727円/月)
※1年契約には、3カ月無料特典が付きます。
※1ドル=109円換算
※2020年1月時点
・Macにおすすめの理由
ExpressVPNのMacOS向けアプリは、高いセキュリティと通信速度を誇ります。セキュリティ面では、「256ビットAES暗号化」の採用をはじめ「DNS/IPv6漏れの保護」、「キルスイッチ」、「スプリットトンネル」の機能を備えています。通信速度では、VPNプロトコルにOpenVPNを選択可能なほか、無制限の帯域幅は無制限で通信量制限もありません。
2. NordVPN

・本社所在地
NordVPNは、ログやデータに関する法的規制がない、パナマに本社があります。
・対応するアプリケーション
Mac以外で対応するアプリケーションは、PCではWindowsとLinux、スマートフォンではiOSとAndroidです。
・ログの取得
利用規約で、厳格なログなしポリシーの保証を明示しています。
・サーバ数と所在地
サーバは58カ国に合計5,567台設置されています。設置場所は、南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中東、アフリカ、インドの世界各地に及びます。日本における設置台数は140台です。
※2020年1月時点
・「Double VPN」による二重の暗号化
設置されたVPNサーバの多くで、「Double VPN」と呼ばれる独自の二重暗号化技術により、セキュリティを強化しています。
・通信できる端末数
1つのサブスクリプションで同時に接続できる端末(デバイス)数は6台です。
・料金
料金は、長期契約になるほど割安で、30日返金保証があります。
1カ月プラン:11.95ドル/月(約1,302円/月)
1年プラン : 6.99ドル/月(約761円/月)
2年プラン : 4.99ドル/月(約543円/月)
3年プラン : 3.49ドル/月(約380円/月)
※1ドル=109円換算
※2020年1月時点
・Macにおすすめの理由
Macは、Windowsと比較すると、画面がシンプルで直感的に操作できるという点で、多くのユーザーの好評を得ています。NordVPNは、Macと同様にシンプルで直感的な操作ができ、わずか数クリックで通信の保護が可能です。
NordVPNは、セキュリティ面でも優れていて、軍事レベルの暗号化を誇っています。保護できるデバイス数が多いのも特徴で、1つのカウントで6台のデバイスを保護できます。10名以内(10デバイス以内)の会社であれば、2アカウントの契約で、通信の保護ができます。
MacでもVPNを使って情報漏えいを防ぎましょう
今回は、Macの抱えるセキュリティリスクとその対策としてのVPNについて取り上げました。Macのセキュリティ対策に、VPNの他にウイルス対策ソフトの導入があります。しかしMacもWindows同様、ウイルス対策ソフトだけでは不十分です。
なぜならウイルス対策ソフトは、ウイルスがPCに入ってきた時点で対応するので、駆除できないリスクがあるからです。そこで、Macの場合もVPNを利用することで、インターネットを経由してウイルスが侵入する脅威を「入口」で遮断できます。
城に例えれば、VPNが「外堀」でウイルス対策ソフトが「内堀」です。VPNとウイルス対策ソフトの「二重の堀」で防御することで、「本丸」であるMac PC本体の守りを強化できます。
冒頭で触れた通り、MacユーザーはWindowsユーザーに比べて、セキュリティ対策への認識が甘い傾向があります。そのため、今後もMacを対象としたサイバー攻撃の増加も懸念されます。しっかりとVPNで防御態勢を築いて、情報漏えいを防ぎましょう。
投稿 Macにもセキュリティ対策は必須!最適なVPNをピックアップ は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 無料VPNの意外な落とし穴とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、無料VPNの「落とし穴」について、危険度が高い順に「悪意を持ったVPN運営者の存在」、「サイバー犯罪目的のユーザーの可能性」、「無料VPNのデメリット」の3点を取り上げます。
無料VPN 3つの落とし穴
1.悪意を持ったVPN運営者の存在

無料VPNを使用する上で、危険度が高い「最悪の落とし穴」といえるのが、VPN事業者側からデータを盗み取られる可能性です。利用者の情報を盗み取るなどの「悪意を持ったサイト運営者」が存在するのと同様に、「悪意を持ったVPN運営者」の存在も、否定はできません。現に、海外ではそのようなVPN事業者からの情報漏えいがあった調査も発表されています。
「悪意を持ったVPN運営者」が存在した場合、利用者の情報を盗み取り、売却する目的などでVPNを設置すると推測されます。万が一、そうしたVPNに引っ掛かってしまった場合、懸念されるのが顧客情報を盗み取られるなどの被害です。
そして、顧客情報が流出して悪用された場合、企業の信用問題にも発展し、取り返しのつかない重大な損失にもなりかねません。
VPN運営者に悪意があるかどうかを見分ける大きなポイントは「ログを保持していないか」と「運営費用の出どころがはっきりしているか」の2点です。
ログを保持していないか
仮に、「悪意を持ったVPN運営者」が存在した場合、データを盗み取るための手段としてログを保持することが考えられます。ログを保持しているVPNは、運営者に悪意がない場合でも、利用者の情報を商業目的で使用している可能性が高くあります。ログからさまざまな情報の取得が考えられますが、カード情報などのより深い個人情報を、盗み取られる可能性も否定できません。
そこで、顧客・個人情報の悪用を防ぐためのVPN選びをするには、最初に「ノーログポリシー」など、ログを保持しないと宣言しているかどうか、確認することが重要です。
運営費用の出所がはっきりしているか
悪意を持ったVPN運営者は、顧客・個人情報の売却などの不正な方法で運営費用を賄っています。そのため、後述の「広告収入で運営費用を賄っている場合」や、「有料VPNのお試し無料」など、収入源がはっきりしているものに比べて、運営費用を明示しない傾向があります。
運営費用の出どころがはっきりしない無料VPNは、選択肢から外すのが望ましいでしょう。
2.サイバー犯罪目的のユーザーの可能性
無料VPNの運営元に悪意はなくても、サイバー犯罪目的の悪意を持ったユーザーが少なからず存在するのも事実です。なぜなら、無料VPNは有料VPNに比べると利用ハードルが低いため、不特定多数の人がアクセスするからです。
また無料VPNは、有料VPNと比較してセキュリティが低い傾向があります。使用料を徴収しない分、セキュリティに十分予算をかけられないからです。そこで、そのセキュリティ面の弱点を、サイバー犯罪者に狙われやすい傾向があります。
その点で有料VPNは、サイバー犯罪目的に使用されることが無いとは言い切れませんが、費用をかけてセキュリティ面での悪用防止対策を講じている場合が多いので、悪用の可能性は低いといえます。
3. 無料VPN使用のデメリット
無料VPNの中には、運営体制がしっかりとしていて、セキュリティが高いものもあります。しかしこの場合でも、企業が業務を進める上でネックとなる「落とし穴」があります。
データ送信量に上限がある
多くの無料VPNに共通するのが、データ送信量に10GBや15GBなど上限が設けられている点です。そして、接続できるデバイス数が制限されている場合もあります。企業で利用する場合は、一括契約するとすぐに上限を超えてしまうので、社員ごとに別々に申し込まなければなりません。
しかし、各社員が個別に申し込むと、管理の手間が増えると同時にセキュリティの一括管理が不可能となります。セキュリティを保つためには、社員が使用するデバイス毎に、ログを確認するなどの手間と労力が必要となります。
そのため無料VPNの個別使用は、有料VPNによる一括契約と比較して多くの業務が発生するため、かえって経費がかさんでしまうデメリットがあります。
使用期間が限定されている
多くの有料VPNで無料版サービスを提供しています。運営体制がしっかりしているため、セキュリティ面で優れているのが大きなメリットです。しかし、これらの無料版サービスの多くが「お試し期間」として30日間など限定されています。
「お試し期間」が過ぎる前に、他社の有料VPNの「無料お試し」への切替を繰り返すことで、無料使用を継続する方法も考えられますが、この方法では切替えごとに新しいVPNに慣れるまでの労力がかかるため、業務効率が低下するデメリットがあります。
突然の機能変更の可能性がある
多くの無料VPNの共通リスクとして、予告なしに突然の機能変更が行われる可能性があります。無料VPNは、運営費を広告収入など別の収入源から賄っているため、利用者の利便性よりも自社や広告主などの意向が優先されるためです。
ある日突然、予告なしの機能変更が行われた場合、十分な準備ができずに業務に大きな支障をきたす恐れがあります。また、例え予告が行われたとしても、その対応作業に労力を取られて、本来の業務に支障をきたす可能性もあります。
広告が表示される
無料VPNでは、その運営費用を利用者向けの広告収入で賄っているケースが多くあります
この場合、VPN運営費用の出どころがはっきりしているので、顧客・個人情報を悪用される可能性は低いといえます。
一方で、表示される広告により業務効率が低下するというデメリットがあります。画面を進めるたびに表示される広告を、1つ1つ閉じる作業は数秒程度かもしれませんが、積み重なると大きな時間の損失です。
では、実際にどれくらいの損失になるのでしょうか。例えば、社員数50人規模の企業で考えてみます。1日1人当たり5秒間の広告を閉じる作業が、20回発生した場合、1カ月で約27.8時間もの時間損失となります。
※5秒×20回×50人×20日=10万秒=27.8時間
(1カ月の労働日数を20日とした場合)
しかも、27.8時間の損失以外にも、広告により集中力を乱されることによる業務効率低下も発生します。業務中であっても、興味ある商品の広告が表示されてしまった場合、ついついクリックして見てしまうのが人間の心理です。
こうした、集中力を乱す誘惑は、有料VPNの採用により、可能な限り遠ざけるのが望ましいでしょう。
無料VPNの利用は有料VPNの切り替えを前提に
今回は、無料VPNを企業で利用する場合の落とし穴について、危険度の高い順に3つお伝えしました。無料VPNはセキュリティ面でのリスクや機能の制限、業務効率の低下など、多くの落とし穴があります。
企業での無料VPNの使用は、有料VPNの「お試し無料使用」のみに限定した方が良いのでは無いでしょうか。お試し期間で最適なVPNを見つけたら、有料へ切り替えることをおすすめします。
有料VPNの多くが、データ送信量が多いほど1GB当たりの単価は下がります。つまり企業や子会社などを含めたグループで一括して契約することで、お値打ちに利用できるのです。
ITreviewではビジネス向けVPNにおいて、どのような企業に利用されているか、またどのような評価がなされているかのレビュー(口コミ)を公開しています。またどのVPN製品が人気かひと目で分かる比較表なども公開中です。ぜひご覧いただき、自社に最適なVPN選びにお役立てください。
投稿 無料VPNの意外な落とし穴とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 RPAの無料製品9選|ツールの特徴や選定基準を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本稿では業務効率化の実現のためにRPAは必要なのか、どんな仕様で動くのかといった疑問を持つ方のために、まずはコストをかけずに試せる無料のRPAを紹介していく。
1 無料で利用できるRPAツール一覧
(1)オープンソース製品の利用
まずITツールを無料で導入するための候補としてオープンソースツールを思い浮かべる方も多いのではないだろうか。世界のオープンソースプロジェクトが集うプラットフォームにGitHubに登録されているRPAツール開発プロジェクトは数多く、周辺ツールも合わせると数千に及ぶ。ただし国内企業でオープンソース製品を利用してRPA化に成功した事例は少なく、個人で業務適用した事例がほとんどだ。その点を考慮して導入を検討するのが良いといえる。
Sikulix――GUIコンポーネントを利用してWebアプリ操作を自動化
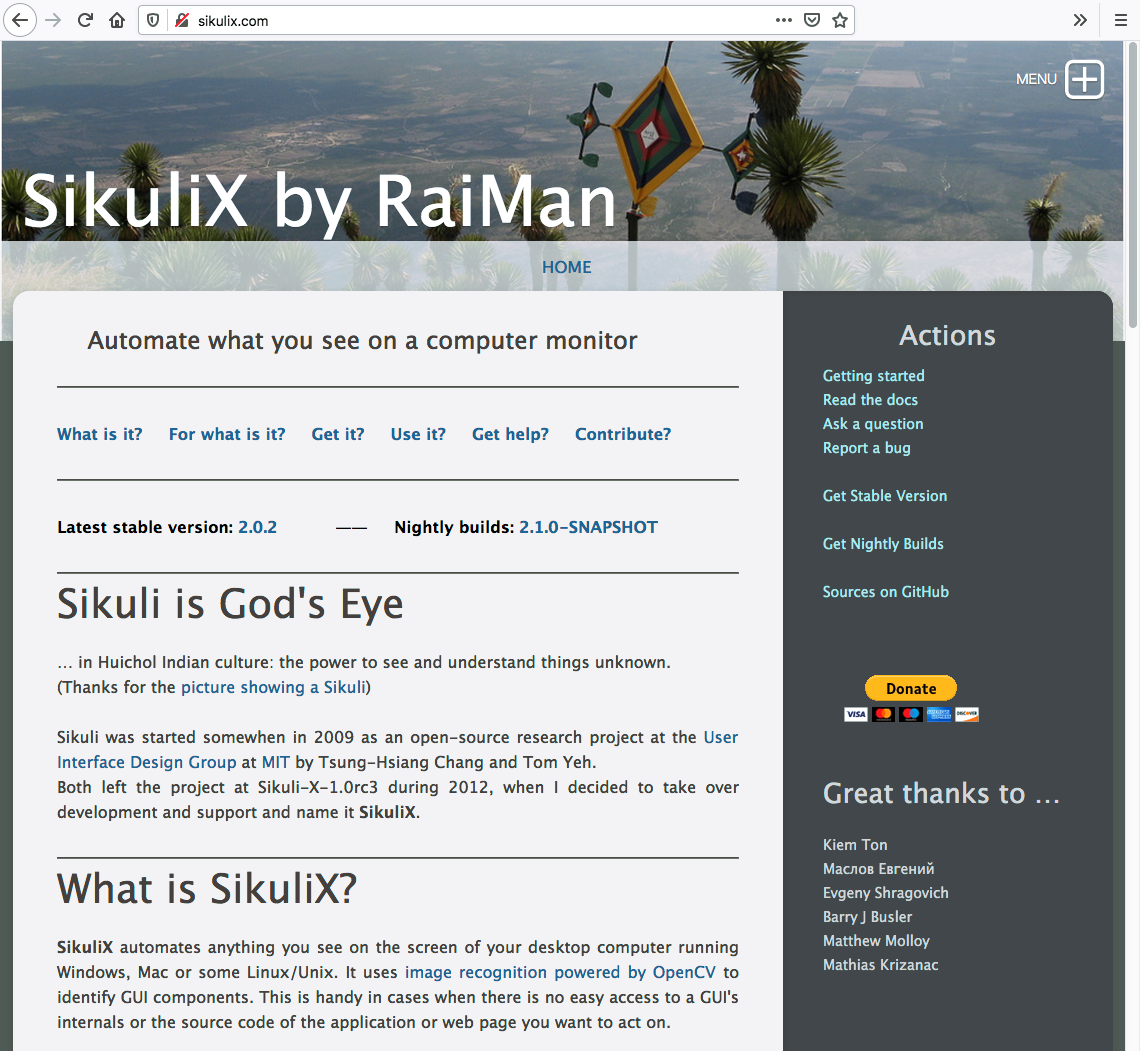
国内での業務適用事例がいくつか語られているツールに「Sikulix」がある。これは操作自動化ツールと呼ばれ、もともとはWebアプリケーション開発のテスト工程で用いられるようなテストシナリオの自動実行ツールであるが、GUIコンポーネントを画像認識して自動化シナリオを作成しやすくしているところが特徴だ。
ユーザー操作を模倣するテストの自動化は、業務自動化とほとんど違いがないケースが多く、こうしたツールは開発エンジニアにとっても利用しやすいため、業務適用もエンジニアであれば難しくないといえる。Sikulixは著作権表示などのルールさえ守ればほぼ無制限に利用できるMITライセンスが適用されるため、無料で好きなだけ使うことができる。
Selenium――ブラウザにアドオンして操作を記録、スクリプト化が可能
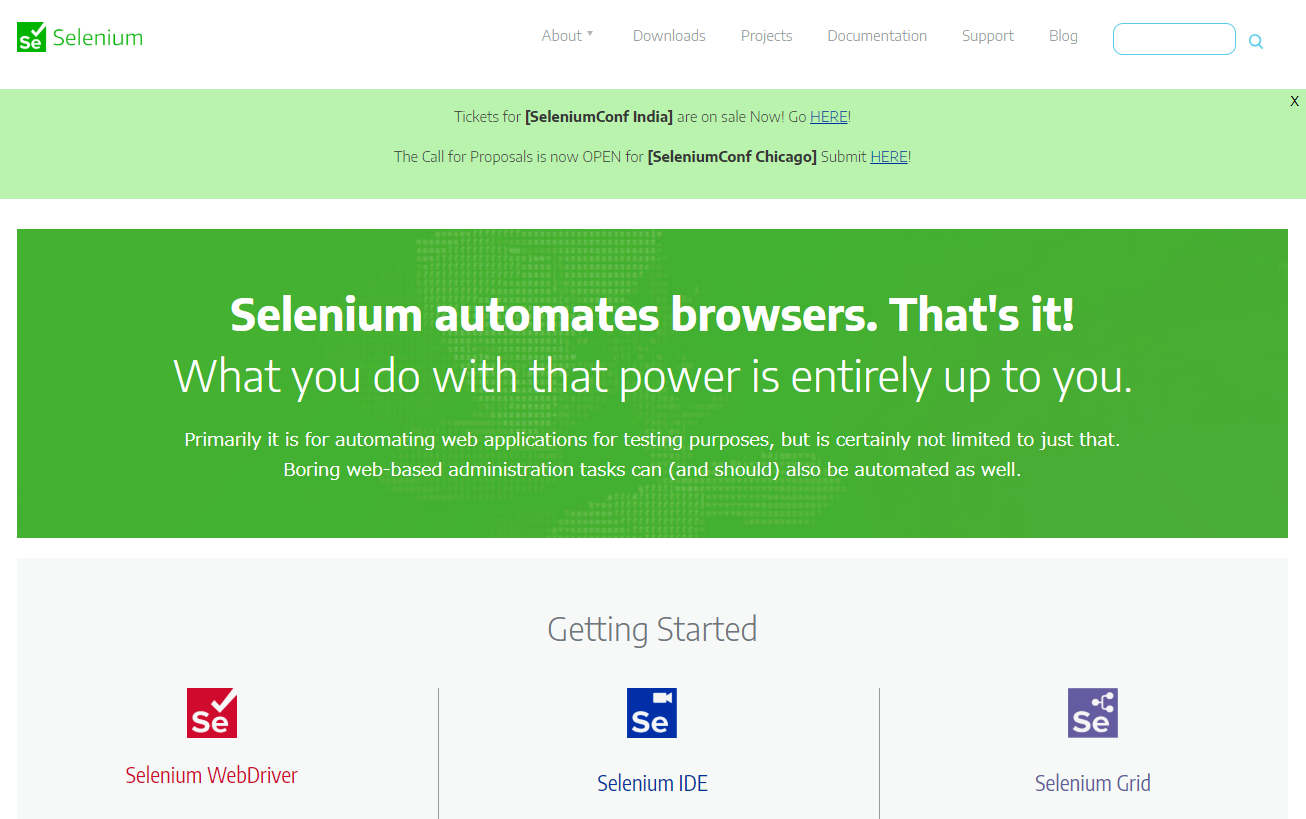
SeleniumもWebアプリケーションのテスト自動化を行うツールだ。Sikulixが画像認識でGUIコンポーネントを識別・制御するのに対し、Seleniumはブラウザ操作からテストスクリプトを作成するオブジェクト方式で処理を記録するところが違う。
Google ChromeとFirefoxのアドオン「Selenium IDE」の機能により、ブラウザ操作履歴をHTMLテストスクリプトとして保存し、必要なら微調整を加えて操作を再現することができる。各種のWebブラウザに対応しており、Webアプリケーション専用のRPAツールとして利用可能だ。また最初からHTMLテストスクリプトを記述してもよく、Java、C#、Ruby、PHP、Perl、Python、JavaScript(Node.js)などの開発言語で記述することもできる。しかし有償のRPAツールと比較して利用の難易度は高く、エンジニアの関与は欠かせないだろう。
(2)無料プランのあるRPAツール一覧
オープンソース以外にも無料で利用できるRPAツールはいくつかある。そのほとんどは入門用であり制限が多いものの、試用して結果がよければ、作成したロボットを含めて本番適用可能な有料モデルに切り替えることも可能だ。
UiPath Community Cloud――最大3台のロボットが利用可能

UiPathはデスクトップタイプのRPAツールとしてグローバルで導入が進んだ代表的なRPAツールだ。有料プランは法人用に「Studio」「Enterprise Cloud」「Enterprise Server」がラインアップされていて、これら3モデルは60日間の無料試用が可能。これとは別に個人向けの無料プラン「Community Cloud」がある。
Community CloudはWindowsのみの対応だが、設計ツールが2ライセンス、最大3台のロボットを運用できる。まずは3台以下のロボットでの運用で様子を見て、ロボットが無制限に作成できるEnterprise CloudかEnterprise Serverに格上げするかどうかを判断するのが一般的な利用法となるだろう。無料プラン内での業務自動化でひとまず十分なら、ロボットを使い続けることも可能だ。
またUiPathはグローバルでユーザーが多く、関連情報はUiPathフォーラムの無償情報から得ることができる。ベンダーサポートは有償モデルでのみ利用できる。
Intelligent Automation Cloud Express――日本語対応でさらに利用しやすく

WorkFusion社が 2019年9月までRPA Expressという名称で提供していたツールが「Intelligent Automation Cloud」と名称変更された。現在同社のRPAツールは「Express」と「Business」「Enterprise」の3モデルに編成されている。全てのモデルで日本語対応が行われて利用しやすくなった(英語、スペイン語にも対応)。このうち無料で利用できるのはIntelligent Automation Cloud Expressだ。
デスクトップ型のRPAツールの基本機能であるアプリケーション操作、マウスやキーボード操作、操作のレコーディングなどはExpressモデルでもカバーできており、組み込みOCR機能なども備えられる。有料モデルではそれに加えて集中管理機能やタスクスケジューリング機能、ワークフロー機能などが追加され、ユーザー数、多数のロボットの運用をしやすくしている。最上位のEnterpriseモデルは分析やガバナンス強化、セキュリティ強化などが追加されているのが大きな違いだ。
基本的なRPA機能がExpressモデルに備わっているため、単一の業務を1台のPCでこなしている場合には、問題なく業務を効率化できることもあるだろう。ただし社内にRPAを普及させたい場合には、複数ロボットを管理し、処理をスケジューリングしながらこなせるBusinessモデル以上がおすすめだ。
Robotic Crowd Agent――Chromeとスプレッドシード、CSVの処理に最適
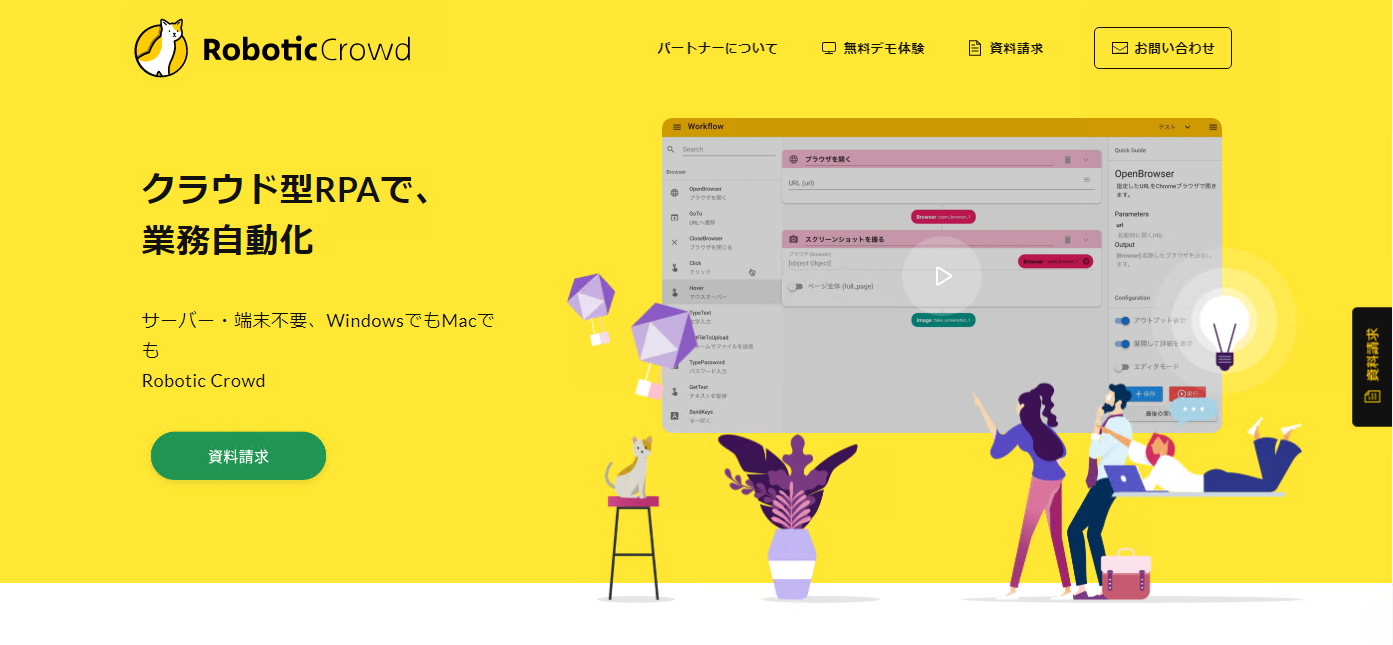
株式会社チュートリアルが、Google Chromeの機能拡張として提供しているのが「Robotic Crowd Agent」だ。もともとは同社のクラウド型RPAツール「Robotic Crowd」と併用して操作レコーディングなどを行う補助ツールという位置付けだが、Agentだけを無償で利用できる。
Agentだけでも、Webブラウザ、CSVファイル、Googleスプレッドシートを使う範囲の業務なら一連のワークフローを設計してロボットを作成できる。例えばブラウザ操作で情報を取得してスプレッドシートに入力したり、CSV形式でファイルに書き出したり、スプレッドシートと連携した繰り返し作業を自動化したりすることができる。
この範囲を超えた処理については有料のSaaS型のツールであるRobotic Crowdを利用することになる。Agentで作成したロボットはそのままRobotic Crowdで使用でき月額10万円(税別)〜の定額でロボット2台を運用できる(その他の料金プランは要問い合わせ)。
(3)無料トライアル版の利用
RPA導入を検討する企業のほとんどが望むのが広範な業務自動化による効率アップであろう。現実的には特定部門からのスタートになるにせよ、RPAツールには相応のスケーラビリティと信頼性・安定性、そして業務部門でもIT部門の支援があればロボット作成も可能な操作性、また統合管理のしやすさなどがいずれ求められるようになる。
オープンソースツールを用いるなどして自社でRPA実現を図れる技術力があればよいが、そうでなければ特にRPA化が効果的な業務に限って上記のような無料モデルを利用するか、ゆくゆくは多様な業務に本格展開することを視野に入れて、ふさわしい要件を備えた製品を試用してみる必要があるだろう。その際、無料トライアルが用意されている製品を複数試用してみると、PoCの一助になるはずだ。
WinActor ――国内トップクラスのシェアを誇るデスクトップ型RPA

NTTアドバンステクノロジーが提供している「WinActor」は国内シェアがトップクラスのRPAツール。Windows対応で、画像認識あるいは座標指定などの技術を駆使してPC操作を自動記録する機能に優れる純国産ツールだ。
デスクトップ型であり、導入が比較的単位間で済むところも特徴である。また導入事例が多く、導入済み企業から経験談が聞ける機会が多いことも、あまり語られないが大事なメリットといえそうだ。無料試用版はフル機能で30日間利用できる。作成したシナリオはライセンス購入後はそのまま利用できる。
Blue Prism ――全社統括管理を実現しやすいサーバー型RPA

イギリス発祥のBlue Prism社が提供する全社統括管理機能に優れたサーバー型RPAツール。最も早期からRPAに取り組んだ同社は近年、日本企業への展開を強力に進めているところだ。
無償評価版は、クラウド環境(Microsoft Azureのアカウントが必要)またはローカルサーバ(Windows 8.1または10(64ビット版)10GBの最小空き容量が必要)にインストールできる。最大30日間、ロボット1台、プロセス数は15までの制限がある。
無料評価版とは別に、学習用無料ライセンスがあるのが特徴だ。こちらは90日間、ロボット1台、プロセス数は5までである。ローカルサーバにインストールして利用する(Windows 8.1または10(64ビット版)10GBの最小空き容量が必要)。
Kofax RPA――エンタープライズ向けのサーバー型ツール

WindowsとLinuxに対応するKofax社提供のサーバ型ツール(旧名はKapow)。操作のレコーディング機能などで簡単にシナリオ作成が可能で、作成したロボットを他のロボットで再利用したり、他のシステムからロボット処理を呼び出したり、ロボットのバージョン管理を含む集中管理、多数のロボットの監視、制御が可能など、大規模展開に有用な特徴を備えている。
BizRobo!やSynchroidが同社のOEMを利用していることも有名だ。またGoogle VisionやIBM Watsonとの連携、コグニティブ技術の非構造化データへの適用などの特徴にも注目したい。
無料トライアルはフル機能で1年間。Windows x64対応、管理サーバ、データベース、ロボット開発環境のセットなどが提供される。
Automation Anywhere--グローバルでの導入実績が豊富
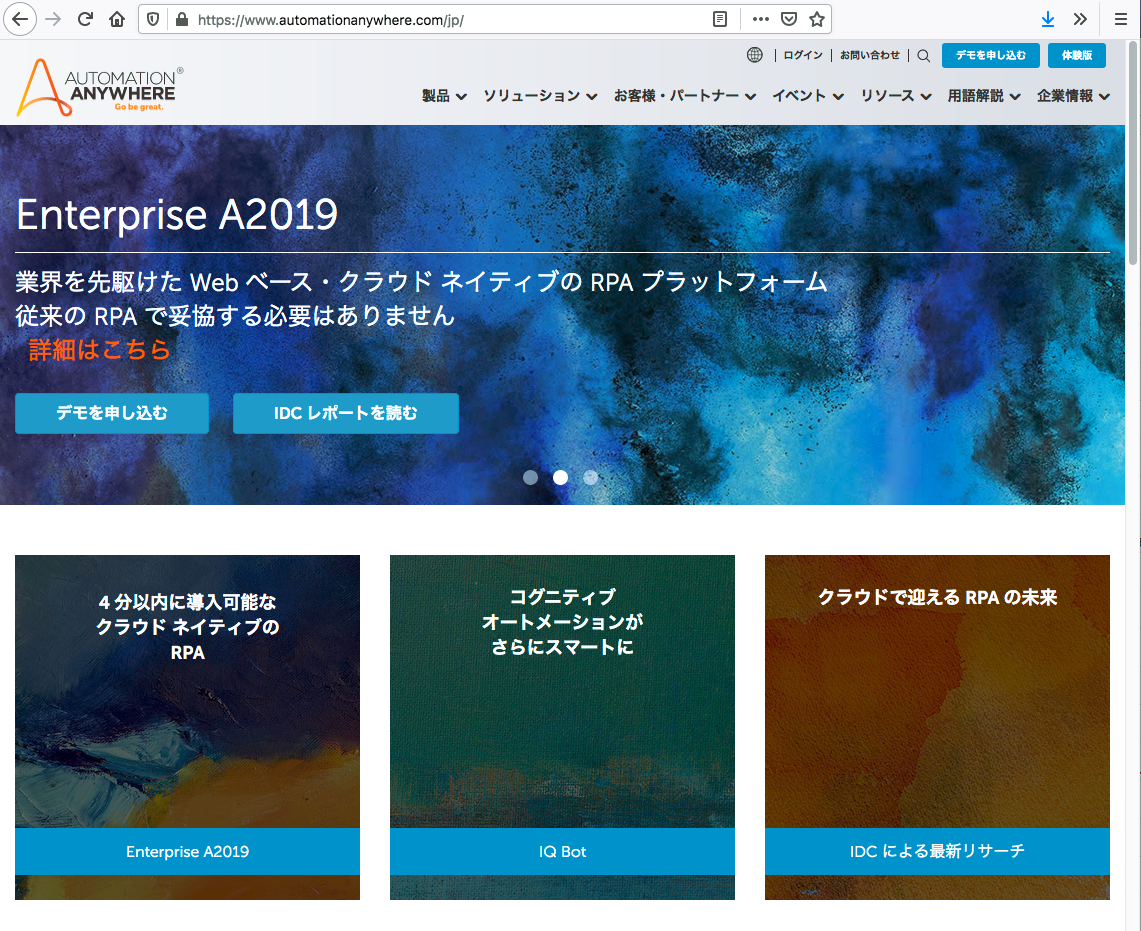
Automation Anywhere社が提供する、グローバルで導入実績豊富なサーバ型RPAツール。世界規模のユーザーコミュニティー、豊富なロボットパーツがダウンロード可能な「RPA Bot Store」やトレーニング環境などを整備しており、大規模展開、統括管理・運用に適した特徴を備えている。
ロボット開発機能、ロボット実行機能、ロボット管理機能に加え、ドキュメント作成支援機能(操作記録に応じたドキュメント自動作成が可能)があるのも特徴の1つ。
無料トライアルは、Automation Anywhere Enterprise RPA プラットフォームのフル機能を30日間利用できる。
2 無料トライアル版、または無料版を利用する場合の注意点
無料トライアル版の利用は、当然ながら有料版を購入することを視野に入れて行うことになる。従って、当面の業務適用で結果を出すことよりも、いずれ自社で本格展開する姿をイメージして、仕様や機能、操作性、性能、スケーラビリティ、運用管理負荷、操作や機能の習得の難易度、要求されるITリテラシーなどを正しく評価し、見積もらなければならない。
とはいえ、RPA利用経験のないまま、また対象となる業務の洗い出しが不十分なままだと、製品の評価はなかなか難しい。できれば無料版をある程度の期間、IT部門などで利用してRPAによる業務自動化の実際を体験し、問題が発生しやすいポイントや、適用するにふさわしい業務の特徴などをある程度明確にした上で、業務部門にヒアリングを行い、業務効率化への希望や現状の課題を把握しておくことが望ましい。
現実的には無料版で事足りることは少なく、RPA化が適切だと判断できれば早期に有料版に移行することを視野に入れて導入プロジェクトを進める方が良いだろう。しかしトライアル期間はだいたい30〜60日であり、またシナリオ設計ができるライセンス数や運用可能なロボット数が少ない場合もある。トライアルでの評価はできるだけ要領よく、ポイントを押さえて実行することが望まれる。
3 オープンソースツールに潜在しているリスク
無料トライアル版は、有料版の機能がそのまま利用できる場合が多く、ユーザー数、作成可能なロボット数、利用期間、サポートの手厚さなどに制限があることだけが違う。基本的にはベンダー側が動作を保証しているので安心感がある。その一方、オープンソース製品には開発者側のサポートがあまり期待できず、日本人の業務スタッフはもちろん、ITエンジニアでも機能・仕様を十分理解して効果的に利用するにはハードルが高い。
オープンソース製品はトラブルが起きた場合や、開発で困った場合に相談できる相手が必ずしも適時に得られるわけではない。情報収集はオープンソースプロジェクトのコミュニティーや公開資料からがメインになり、情報がなければ自己解決するしかない。良くも悪くも自己責任なのだ。この点を踏まえて製品選定をした方が良いと言える。
4 無料か有料か、製品選定の基準は何?
以上をまとめると、オープンソース製品、無料版、無料トライアル版のお勧めの使い方は次のようになる。
・基本的には有料ツールへの移行を視野に入れ、無料版または無料トライアル版を試用する
・単一の業務への適用など、極めて小規模なRPA化で十分なら無料版を長期利用する
・複数業務に適用し、将来の大規模展開を図るなら、スケーラビリティや多数のロボットの統合管理機能が十分な有料ツールの無料トライアルを行う
・社内に開発に精通した人材が豊富で継続的な開発・運用体制がとれる場合はオープンソースツールの利用も検討する
また、RPAツール導入、製品選定にあたっては、事前に次のようなアクションが必要になる。
RPAツール選定前に行うべきこと
・IT部門内だけでなく、業務部門、経営層も含めた業務課題・改善要望のヒアリングを十分行う
・RPA適応候補業務の洗い出し、絞り込みを行う
・RPAツールの基本的な役割、機能について、無料版や無料トライアルを通して理解する
紹介動画の確認で使用感を確認する
なお、RPAの全体像や個別の具体的操作法については、各ベンダーのWebサイトや販売代理店となっているSIerなどのWebサイトに、紹介動画や画面例なども用いた手順解説、あるいは事例解説、Tipsの紹介記事など、さまざまな情報がある。でこうした情報を調べることが、間違いのないRPA導入につながるはずだ。
そしてRPA製品選定の基準としては、主に次のようなポイントで比較することをお勧めする。
RPA選定のポイント
・導入しやすいデスクトップ型製品か、大規模展開の際に頼れるサーバ型製品か
・既存環境との適合(対応OS、ブラウザ、既存業務システムとの連携など)
・操作の自動記録機能の有無や精度、エラーの発生頻度、シナリオ作成の難易度
・汎用的なロボットパーツやサンプルロボットの提供の有無、種類
・多数のロボットを運用する場合の管理機能、セキュリティ、管理者の負担の程度
・導入コスト、ランニングコスト(費用対効果)
こうしたポイントで比較すると、同じツールでも企業により、また適用業務の種類により評価は異なるだろう。自社にフィットするか否かは利用してみなければ分からないことがたくさんある。
まずは情報収集をしっかり行い、要件を洗い出して課題解決にどう役立てられるかを念頭に、各種ツールを試用してみることが重要だ。具体的な操作方法、動作環境、展開方法などについて、大手ベンダーはWebサイトやセミナーなどで解説している。操作についての動画も無料で視聴できる場合があり、トライアル前にある程度様子をつかむことができるので、ぜひ丹念に開発元やベンダーの情報にあたっていただきたい。
投稿 RPAの無料製品9選|ツールの特徴や選定基準を紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 Amazonが運営する「AWS VPN」の特徴や価格は? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そうした盗聴リスクを低減するために有効な手段の1つが、VPNによる通信の暗号化です。VPNサービスの導入により、インターネット経由でのセキュアな通信が可能となります。
本記事では、AWS(Amazon Web Services)で構築したインフラ環境とセキュアな通信を確保するためのVPNサービス「AWS VPN」をご紹介します。
「AWS」とは?

AWSは、Amazonが手掛けるクラウドコンピューティングサービスです。サービス内容は、オンラインストレージやデータベースなどの一般的なものから、開発者向けのツールまで多岐にわたり160種類以上あります。
サーバやルーターなどのハードウェアと、それらを運用するために必要なソフトウェアを同時に借りることで、一元管理できるメリットがあります。
「AWS VPN」の特徴と活用方法

「AWS VPN(AWS Virtual Private Network)」はAWSグローバルネットワークとセキュアな通信を確立するサービスです。「AWS VPN」を利用すると次の2つのVPN接続が可能になります。
1. AWSサイト間VPN接続
AWSサイト間通信を利用することで、IPsec VPN通信を使って暗号化されたVPNトンネルを拠点間で構築可能です。そのため、支店などの拠点ネットワークと Amazon VPC(※注1)への安全な接続が可能になります。
AWSサイト間VPNを利用する上で、拠点からAWSへのVPN接続には、VPN対応ルーターが必要になります。VPN対応ルーターをインターネットに接続し、AWSサイトからルーターの機種別の設定ファイルをダウンロードすることで、AWSクラウドにVPN接続可能です。
※注1)Amazon Virtual Private Cloudの略。AWS内で構築される仮想的なプライベートクラウド環境を提供するサービス。
2.AWS Client VPN接続
AWS Client VPNを利用することで、Windows、Macだけでなく、AndroidやiOSとAmazon VPCをVPN接続することが可能です。モバイルデバイスとAmazon VPCをVPN接続するには、証明書を利用してモバイルデバイスの認証と許可を行います。次に、Amazon VPC上に「AWS Client VPN エンドポイント」に対して、アクセスを承認することで、モバイルデバイスとAmazon VPCとの間でVPN通信を確立できます。
「AWS VPN」の料金
「AWS VPN」の使用料は、月毎の接続時間とデータ送信量によって決まります。料金は、世界の地域によって変わりますが、日本(アジアパシフィック 東京)で接続する場合を見てみます。
※1ドル=109円として算出。
1.AWSサイト間VPN
料金を決める要素は、以下の4種類です。
(1)Accelerated サイト間VPN接続料金
サイト間接続を行った時間に対してかかる料金です。日本では、1接続あたり1時間0.048ドル(5.232円)です。
(2)データ転送(送信)料金
AWS側から送信したデータ量に応じてかかる料金です。最初の1GBは無料で、日本では2GBから10TBまでは1GB当たり0.114ドル(約12.426円)です。通信料の増加に伴い、1GB当たりの単価は下がり、10TBから40TBまでは0.089ドル(約9.701円)、40TBから100TBまでは0.086ドル(約9.374円)です。
(3)AWS Global Accelerator時間あたり料金
「AWS VPN」に接続する拠点に対して、接続時間に対してかかる料金です。接続料金は、1拠点当たり1時間0.025ドル(約2.725円)です。
(4)Acceleratedサイト間VPN DT-Premium料金
送信データ量に対して、(2)の「データ転送(送信)料金」とは別にかかる料金です。AWS側からの送信量と受信量を比較して、多い方の通信にかかります。送信場所と受信場所の地域によって変わりますが、日本国内では1GB当たり0.01ドル(約1.09円)です。
2.リモートアクセスVPN
(1)AWS Client VPNエンドポイントの時間料金
拠点に設置した基地局となる「VPNエンドポイント」がVPN接続した時間に応じて発生する料金です。日本では1時間あたり0.15ドル(約16.35円)です。
(2)Client VPN接続料金
社外のモバイルデバイスが、VPN接続した時間に応じて発生する料金です。日本では、1時間あたり0.05ドル(約5.45円)です。
「AWS VPN」の料金計算例
「AWS VPN」の料金は、複雑なので分かりやすくするため、料金計算の実例で見てみます。
1.AWSサイト間VPN
日本国内のある拠点から別の拠点へ、「AWS VPN」を介して接続を行った場合を考えます。この接続は1日24時間で1カ月(30日間)継続し、1カ月間の通信量は、AWS側からの送信量が500GB、受信量が1,000GBと想定します。この場合の料金は、以下となります
(1)Acceleratedサイト間VPN接続料金
0.048ドル×1(接続)×24(時間)×30(日)=34.56ドル=約3,767円
(2)データ転送(送信)料金
全送信量500GBのうち最初の1GBは無料で、残りの499GBに課金されます。
0.114ドル×499(GB)=56.886ドル=約6,200円
(3)AWS Global Accelerator 時間あたり料金
0.025ドル×2(拠点)×24(時間)×30(日)=36ドル=約3,924円
(4) Acceleratedサイト間VPN DT-Premium料金
AWS側からの送信量が500GB、受信が1,000GBを比較して、多い方の受信量1,000GBに課金されます。
0.01ドル×1000GB=10ドル=約1090円
合計の料金は以下となります。
(1)+(2)+(3)+(4)=137.446ドル=約14,981円(税抜)
2.リモートアクセスVPN
日本国内の拠点に「AWS Client VPNエンドポイント」を作成します。その拠点で使用するモバイルデバイス10個に、それぞれ「AWS Client VPNエンドポイント」を設定します。10個のモバイルデバイスが、同時に社外で1時間VPN接続をした場合の料金は、以下となります。
(1)AWS Client VPNエンドポイントの時間料金
0.15ドル×1(時間)=0.15ドル=約16.35円
(2)Client VPN接続料金
0.05ドル×10(モバイルデバイス数)×1(時間)=0.5ドル=約54.5円
合計の料金は以下となります。
(1)+(2)=0.65ドル=約70円(税抜)
「AWS VPN」を法人で使用する上で注意すべき点とは?
「AWS VPN」は、AWSを利用している方であれば、セキュアな通信を行うために必要なサービスです。大きな初期投資が必要なく手軽に導入できる反面、品質や速度の保証がされていません。そのため、拠点間のVPN接続では通信が切れる可能性や速度が遅くなる可能性などのデメリットがあります。専用回線を構築できるAWS Direct Connectとの併用などを検討する必要があるかもしれません。
「AWS VPN」の料金体系は、基本的に使った分だけ支払う方式なので、場合によっては定額制のサービスより割高になる可能性もあります。しかし、使っていない時間帯には、こまめに通信を切断するなどの工夫で、料金を節約することもできます。
導入を検討される際は1カ月当たりの、データ送信量・受信量を調べて、料金をシミュレーションして見ることをおすすめします。
「AWS VPN」は、拠点間VPN接続での利用以外にも、AWSの他のサービスの連携面でもメリットがあります。AWS VPNにより、AWSの各サービスを、仮想的に社内LANの延長線上で使うことができます。
従って、すでにAWSの他のサービスを利用されている場合は、通信上のリスクを考慮しながら、合わせての導入を検討してみてはいかがでしょうか。
AWSを利用されていない場合には、以下のサイトよりビジネス向けのVPNサービスをご確認ください。
投稿 Amazonが運営する「AWS VPN」の特徴や価格は? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 リモートワーカーに便利なVPNの選び方。WindowsとMacで使えるオススメ有料VPNを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>企業はこうした“働き方の多様化”に対応するべく、リモートワークの実現に向けた環境整備が求められています。外出先からオフィスのネットワーク環境へ安全にアクセスできるVPNは、リモートワークの実現に欠かせないといえるでしょう。本記事では、リモートワークの導入に向けたVPNの選び方や、オススメのVPNをご紹介します。
安全なリモートアクセスにはVPNが必須
リモートアクセスとは、ネットワークを経由して社内に設置されたPC(社内LANに接続したPC)に接続する技術のことをいいます。リモートアクセスを利用することにより、外出先にいても社内PCを利用しているのと同様にファイルサーバ等にアクセスできるようになります。
構築にはインターネット回線とリモートアクセスサービス(RAS)を利用する方法が一般的ですが、不特定多数が利用する通常のインターネット回線では、どうしてもセキュリティ面が懸念されます。こうしたリスクに備えて、VPN構築が有効です。
社内にVPNを構築することにより、インターネット上に仮想的なプライベートネットワークを作ることができ、特定の人のみが利用できる安全な専用回線でアクセスできるようになります。
各拠点にVPN専用機器を設置して拠点間をシームレスにつなぐだけでなく、外出先からVPN経由で社内LANへと安全にリモートアクセスすることも可能です。公衆のインターネット回線よりもセキュリティが向上するため、外部からのデータ盗聴や攻撃のリスクを低減できます。リモートワークを安全に導入するには、VPN構築によるセキュリティ対策が不可欠といえるでしょう。
リモートワークに有効なVPNの選び方
1.インターネットVPNとIP-VPN
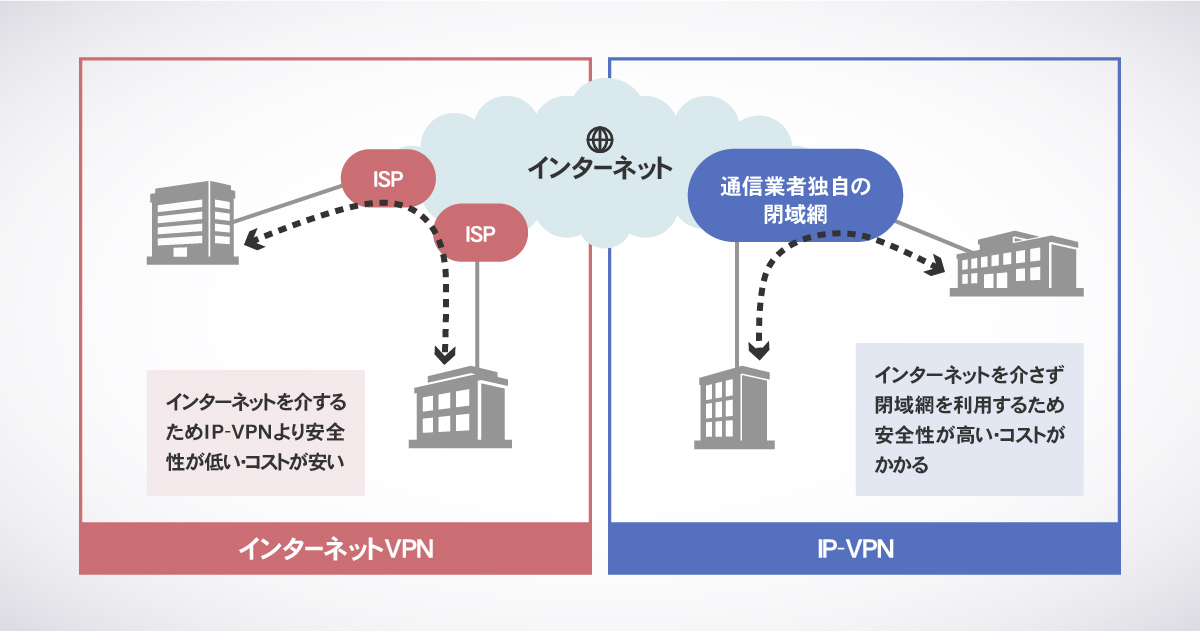
VPNを構築する方法として、インターネット上にVPNを構築する「インターネットVPN」を利用するものと、通信キャリアによって提供される閉域網の「IP-VPN」を利用するものと大きく2種類があります。
インターネットVPNは比較的安価に構築できるという利点がありますが、不特定多数が利用するインターネット回線を用いるため、安全性はIP-VPNと比べて低くなります。
一方IP-VPNは、通信キャリアの閉域網「MPLS網」を利用するため、インターネットVPNよりもセキュアに通信できることが特徴です。維持管理や設備設定などを通信事業者へ依頼できるほか、システムの安定性や帯域についても保証されるため、企業の安定したネットワーク構築において優勢といえるでしょう。
ただし、IP-VPNはインターネットVPNと比べて運用コストが高額になる傾向があります。場所によってはアクセスポイントが存在しない場合もあるため、用途や接続制限に応じて双方を併用することも方法の1つといえます。
2.SSL-VPNとIPsec-VPN
インターネットVPNを使ってリモートアクセスを実現する主な方法として「SSL VPN」と「IPsec VPN」の2種類があります。リモートアクセスに必要なデバイス環境やコストなどが異なるため、それぞれの特徴を理解して導入しましょう。
それぞれの仕組みや特徴は次の通りです。
SSL-VPN
SSL-VPNでは、リモートアクセスデバイスと企業イントラネットを、SSL暗号技術を用いて通信します。あらかじめWebブラウザに搭載されたSSL機能を利用するため、特別な環境設定は不要。使用できるデバイスの範囲が広いことが特徴です。
・デバイスにソフトウェアのインストールが不要(Webブラウザを使用)
・細かなアクセス制御が可能
・導入のコストや手間が抑えられる
一方、決まった拠点間で通信を可能にしたいという場合、コストを管理しやすく高速通信のできるIPsec VPNの方が適しています。
IPsec-VPN
IPsec-VPNでは、IP層で暗号化・認証を行うIPsecを用いて通信します。ただし、リモートアクセスデバイスに専用のソフトウェアをインストールしなければなりません。
・ソフトウェアに対応していないデバイスは使用できない
・細かなアクセス制御はできない
・認証設定などの環境設定が複雑で、導入に手間がかかる
・SSL VPNよりも高速通信
両者の特徴を比較すると、リモートアクセスにおいては「SSL VPN」の方が適しているといえます。デバイスを選ばず複数のユーザーがアクセスできることや、細かなアクセス制御ができるからです。
3.ユーザー数によるコスト追加の有無
インターネットVPN、あるいはセキュリティ強度の高いIP-VPNをプロバイダーと契約する場合、リモートアクセスできる台数が制限されているケースが一般的です。従って、ユーザーのアカウント数が増えるごとに追加コストが発生する場合があります。
料金形態はさまざまですが、インストールするクライアント数によって月額料金が発生するものや、ある一定のユーザー数のアクセス権を初期契約時に買い取るものなどが挙げられます(追加料金が発生しないものもあります)。リモートアクセスの導入状況や今後の予定などを考慮してからプランを選ぶことが重要です。
Windows、Mac対応のおすすめ有料VPN
Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント

Cisco社が提供するVPNサービス。スマートフォンやノートPCなどのさまざまなデバイスから社内LANへリモートアクセスできるとともに、高いセキュリティ環境でのVPN通信が可能です。デバイスにはVPNクライアントソフトウェアのインストールが必要ですが、Windows、Macともに対応しています。VPN未接続のユーザー保護(Cisco Umbrella Roaming)やユーザーIDによる多要素認証(MFA)など、効果的なセキュリティ機能が充実していることが特徴です。リモートアクセスにおいて高い安全性を求める企業に適しています。
Pulse Connect Secure

Pulse Secure社が提供する、クライアント不要のVPNサービス。さまざまなデバイスから社内リソースやクラウドへリモートアクセスできるとともに、ブラウザ上での通信が可能。Webブラウザ方式のみならず、SAMやVPNトンネリングといった幅広いアプリケーションに対応していることが特徴です。
クラウド上のシングルサインオン「SAML2.0」や、リモートアクセスデバイスのキャッシュ自動削除機能など、社外アクセスで安全性を保つ機能を装備しています。大規模な社内ネットワークで安全なリモートアクセスを行いたい企業に適しています。
▼Pulse Connect Secureの製品情報はこちら
SmartVPN

ソフトバンクが提供するサービス。Windows、MacのOSに対応しているほか、さまざまなデバイスから多様な回線で社内ネットワークに接続できます。レイヤー2、レイヤー3にも対応しており、ベストエフォート型やギャランティー型などの帯域環境を複数のプランから選択できることが特徴です。クラウドとのシームレスな連携、モバイルデバイスからの安定した通信を行いたい企業に適しています。
多重認証等のセキュリティ強化が不可欠
従来のオフィスでの業務に対して、リモートワークは外出先からのネットワーク経由となるため、情報の取り扱いやセキュリティ対策においてさらなる強化が求められます。
例えば、社内PCを外部に持ち出す場合、紛失時に備えてシステム管理者によるアカウントロックができる設定をしておくことで、情報漏えいのリスクを防げます。
USBメモリなどの社内データを外部に持ち出す場合には、データの暗号化設定も不可欠です。定期的なパスワード変更やアクセス制限、多重認証などを実施して、セキュリティ強化を図りましょう。
また、社内データや情報の取り扱いについて就業ルール・対処方法などを定めておくことも重要です。リモートワークの実現に向けて、情報セキュリティに関する指針を取りまとめた「セキュリティポリシー」の再検討も視野に入れましょう。
投稿 リモートワーカーに便利なVPNの選び方。WindowsとMacで使えるオススメ有料VPNを紹介 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、MAツールの基礎知識をはじめ、代表的なツールの機能を比較していきます。
MAツールとは
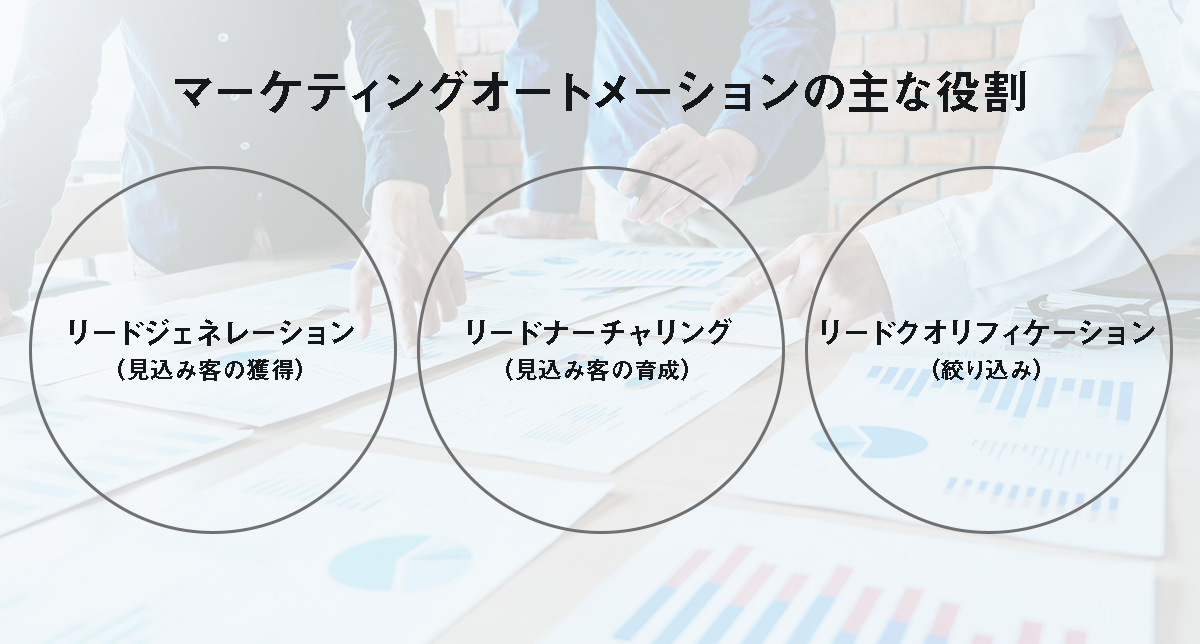
MAツールとは、マーケティングオートメーション(Marketing Automation)の略で、マーケティング全体のプロセスを自動化し、見込み客の獲得・育成に向けた適切なアプローチを可能にするツールのことを指します。
MAツールの主な役割は、下記の3つです。
- リードジェネレーション(見込み客の獲得)
- リードナーチャリング(見込み客の育成)
- リードクオリフィケーション(絞り込み)
| 役割 | 主な機能 |
|---|---|
| リードジェネレーション (見込み客の獲得) |
・リード管理 ・Webページの作成 ・ランディングページの作成 ・お問い合わせページの作成 ・フォームの作成 |
| リードナーチャリング (見込み客の育成) |
・シナリオ設計 ・アクセス分析 ・Webコンテンツ配信 ・メルマガの配信 ・Push通知 |
| リードクオリフィケーション (絞り込み) |
・スコアリング ・ホットリード抽出 |
このように、見込み客の獲得〜育成〜絞り込みに必要な業務を自動で行えるのがMAツールです。
さまざまな情報が行き交う現代において、企業が顧客に対して効果的にアプローチするには、見込み客一人ひとりのニーズに合わせた情報を最適なタイミングで提供し、コミュニケーションを構築する「One to Oneマーケティング 」が重要です。
MAツールでは、見込み客の行動を一元で管理することで、適切なタイミングで適切なターゲットにメールやコンテンツが配信できます。結果的に、製品への関心や購入意欲を高めることができ、企業の収益向上へと貢献します。
また手作業では限界があったメール配信やスコアリングといった膨大な作業を自動化することで、マーケターの作業効率の向上も期待できます。
MAについての更なる詳細はこちら
マーケティングオートメーションが必要とされる背景

2020年現在、企業にマーケティングオートメーションの導入が急速に進んでいます。ベンダーから提供されるMAツールの種類もより豊富に、そして高機能な製品が増えています。
では、企業においてなぜマーケティングオートメーションが求められるようになったのでしょうか。その背景について解説していきます。
顧客の購買プロセスの変化
まず第一にあげられるのが、顧客の製品やサービス購買に至るまでのプロセスが大きく変化したことがあります。
インターネットの普及により、顧客は製品やサービスに関するさまざまな情報を簡単に手に入れることができるようになりました。
そのため顧客は、他社製品やサービスと比較検討をした上で、オンライン上で購買、もしくは購買直前になってはじめて営業担当者と接触するといったケースが増えています。
従来のテレアポや直接訪問といった営業手法は効果を失い、いかにして顧客とオンラインを接点として購入意欲を高めていくかというインバウンド型の手法が重要になってきています。
顧客のオンライン上の行動を分析することで、最適なコミュニケーションを図ることができるMAツールの需要が高まっているのも、当然のことと言えるでしょう。
営業効率の最大化よるコスト削減
MAツールには、スコアリングやホットリードの抽出といった機能が備わっています。これらの機能を活用することで営業効率を高め、今までかかっていた無駄なコストの削減ができます。
従来は獲得した見込み顧客の興味や関心そして購買意欲の可視化ができずに、営業担当者が受注確度の低い見込み客に対して、繰り返しアプローチをするといった非効率な営業がなされることが多くありました。
MAツールを導入することにより、精度の高いナーチャリング(見込み客の育成)が可能になると共に、受注確度の高い見込み客を絞り出すスコアリング・ホットリードの抽出機能で、効率的な営業を展開できます。
労働人口の減少による慢性的な人手不足という課題に直面している日本企業において、限られたリソースを有効に使うMAツールの活用が求められています。
MA導入によるメリット

マーケティングオートメーションの導入によって得られるメリットには、次のものが挙げられます。
- リード獲得作業の効率化
- 精度の高いナーチャリング
- 受注数や受注確度のアップ
リードジェネレーション(見込み客の獲得)の段階では、顧客の情報収集を目的としたWebサイトの作成やフォーム作成、SNSとの連携などが求められます。MAツールを利用することで、これらの作業を効率化できます。
見込み客を獲得した後は、リードナーチャリング(見込み客の育成)によって購買意欲を高める必要があります。MAツールでは、顧客のニーズに合ったメール配信や広告配信、Webサイトでのリアルタイムなコミュニケーションが可能となるため、効率的なプロセスでゴールに導きます。
さらに大きな利点といえるのは、ナーチャリングによって可能性が高まった顧客をスコアリングによって選別できる点です。確度の高い顧客を優先的に営業につなげられるため、成約に至る可能性も高まるでしょう。
MAツールの機能を比較する上でのチェックポイント
導入実績が多い代表的なMAツールをご紹介します。機能の比較で特に注目すべきポイントとしては、下記が挙げられます。
1. 幅広いチャネルに対応しているか
顧客との接点が多様化した現代において、幅広いチャネルで顧客にアプローチする必要があります。
特にBtoC向けのサービスを提供している場合、メールチャネルの他にも、LINEやFacebookといったSNSの活用やスマホアプリ、ブラウザのプッシュ通知など顧客の行動に適したクロスチャネルの活用が考えられます。
そのために、MAツールの機能を比較するときには、幅広いチャネルに対応しているかの確認を怠らないようにしましょう。
2. CRMなどのシステムと連携できるか
マーケティング活動は、自社製品の利用や購入が必ずしもゴールではありません。利用・購入を行ってくれた顧客にリピーターやファンになってもらうために、CRM(顧客関係管理)の視点が必要です。
MAツールは、業務の自動化やリードの獲得、受注確度を上げていくナーチャリングに重きをおいて設計がされています。顧客の購入履歴やコンタクト管理を得意とするCRMツールとは得意領域が異なるので、MAツールとCRMツールの相互の連携を図ることが欠かせません。あわせてCRMツールもチェックしておきましょう。
3. 総合的な機能 or ひとつの機能に特化しているもの
MAツールは、「統合型」と「特化型」に区分できます。
統合型のMAツールは、リードの獲得からナーチャリング、リード管理まで幅広く利用でき、多機能なのが特徴です。一方の特化型のMAツールは、リードの獲得やエンゲージメントの向上など特定の領域に強みを持ちます。
どちらの方が優れているということはありませんが、自社がどの領域に課題を抱えているのかという点に照らし合わせながら、ツール選びを行いましょう。
4. BtoBとBtoCのどちらが向いているか
MAツールは、「BtoB向け」と「BtoC向け」に設計されたものに分かれています。BtoB向けのツールは、展示会やイベントの受付管理など名刺管理ツールなどとの連携が可能なものが多くなっています。
一方の、BtoC向けのツールは、非常に多くの見込み客の一元管理ができ、消費者の興味関心に合わせたOne to Oneマーケティングをサポートしてくれます。自社の扱っている製品やサービス、ビジネスモデルを加味しながら、最適なものを選ぶ必要があります。
また最近では、toCとtoBの双方に対応しているサービスも多く展開されているので、複数のサービスや製品を扱う場合などはそちらも検討すると良いでしょう。
5. サポートの内容
MAツールは効果的に運用すると、売上アップや工数の削減など非常に大きな恩恵を受けることができる反面、運用には高度な知識が必要なケースも多いため、ベンダーの適切なサポートを受ける必要があります。
特に自社に初めてMAツールの導入を行う場合には、手厚いサポートが期待できるツールを選定することが大切です。ツールの中には海外ベンダーが提供するものもあり、日本語でのサポート対応が受けられない場合があります。
各MAツールの機能を比較していく上で、サポート体制に関しても必ず確認をするようにしましょう。
代表的なMAツール
導入実績の多い代表的なMAツールの機能についてみていきましょう。製品の特徴や実績と共に、自社課題にマッチしたツールなのかをしっかりと見極める必要があります。
Marketo Engage(マルケト エンゲージ)

世界の6,000社が が採用しているというMAツール「Marketo Engage(マルケト エンゲージ)」。MAツールに必要な機能が十分に備わっているとともに、顧客とのエンゲージメントの向上に力を入れた一貫性のあるプラットフォームが特徴です。
- 向いている取引形態:BtoBとBtoCに限らない、顧客とのエンゲージメントの実践が目的
- 多様なチャネルに対応:〇
- 統合型 or 特化型:統合型
- 他システムとの連携:〇
- サポート体制:無料と有料のサポートが充実
- 費用:要問合せ
SHANON MARKETING PLATFORM

デジタルとアナログの顧客データを統合管理できるMAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」。国内の導入実績は900社以上、キャンペーン実績は22万件以上を誇ります。
リードジェネレーションやリードナーチャリングに特化した機能が含まれており、継続的な顧客抽出を可能にするスコアリング機能、キャンペーン機能も充実しています。
- 向いている取引形態:BtoBとBtoCの双方に対応
- 多様なチャネルに対応:〇
- 統合型 or 特化型:統合型
- 他システムとの連携:〇
- サポート体制:提案から設定、コンサルティングまでトータルサポートが可能
- 費用:要問合せ
SATORI

国内で900社以上が導入している国産のMAツール「SATORI」。通常のMA機能に加え、匿名の顧客にもアプローチできる「アンノウンマーケティング」機能を搭載しており、Webメディアの集客に強いことが特徴です。シンプル設計で直感的に操作しやすいため、MA運用経験がない担当者でも安心して利用できます。
- 向いている取引形態:BtoBとBtoCの双方に対応
- 多様なチャネルに対応:メールが中心
- 統合型 or 特化型:特化型(リードジェネレーション)
- 他システムとの連携:一部のみ
- サポート体制:オンラインサポートデスクや無料の利活用セミナーを用意
- 費用:148,000円~/月 (別途初期費用が必要)
人気のMAツール11選|マーケティングオートメーションツールの特徴や機能を紹介
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なMAツールを選ぼう!
投稿 MAとは?マーケティングオートメーションの機能・メリット・選び方 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 職場でインターネットVPNを構築する方法|ルーターの選び方は? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>
インターネットVPNの構築が有効なシーン
インターネットVPNには、専用回線のようにセキュアな通信ができ、コストは大幅に抑えられるというメリットがあります。
職場でVPNを構築すれば、以下のようなシーンで活用できます。
・外出先(在宅勤務や営業など)で、社内PCへリモートアクセスしデータを確認したいとき、社内LANへアクセスしたいとき
・本社と支社などの複数の拠点間で、データのやりとりが必要なとき
VPNを活用することで、暗号化による安全な通信ができるだけでなく、拠点間通信や外出先から社内PCやサーバへリモートアクセスが可能となります。モバイルデバイスからも接続できるようになるため、会社と離れた場所から、社内管理のデータやファイルを閲覧・編集するなど、さまざまな業務において活用シーンが広がるでしょう。企業の業務効率化や生産性アップにも有効な手段といえます。

インターネットVPNの構築方法

拠点数が少ない小規模企業では、VPN対応ルーターを利用することでVPN環境を構築できます。ここでは、VPN対応ルーターを用いて自社でVPNを構築する手順を解説します。
VPNルーターを用意する
インターネットVPNを利用するにあたり、各拠点へVPN対応ルーター(VPNゲートウェイ)の設置が必要です。市販のVPNルーターは、価格やセキュリティ性能が異なるほか、有線や無線などさまざまなタイプがあります。中には、ファイアウォールなどのウイルス対策を備えた製品もあります。
自社で利用しているルーターがVPN対応なのか確認し、対応していなければVPN対応のルーターへ交換しましょう。ルーターの選び方については後述します。
本社と各拠点にVPN対応ルーターを設置
VPN対応のルーターを各拠点に設置し、ルーターの接続設定を行うことで拠点間のVPN環境が構築できます。ルーターの設定方法はメーカーによって異なりますが、主に以下の項目を設定します。
・L2TP/IPsecなどのプロトコルの選択
・ユーザー名とパスワードの設定(任意の値)
・接続するPCのIPアドレスの入力
設定が完了した後は、接続元である端末側でVPNの設定を行います。外出先から社内LANへリモートアクセスする際は、接続先のデバイスにVPNクライアントソフトの導入が必要です。
ただし、以下のOS、デバイスでは「L2TP/IPsec」を使ったVPN機能が標準装備されています(PPTPについては一部非対応のOSがあります)。
・Windows 10、RT
・MacOS
・Windows Mobile
・Android
・iOS
標準装備された接続方式を使う場合は、接続先のデバイスへ別途ソフトウェアをインストールする必要はありません。
インターネットVPNサービスを利用する方法も
全国に拠点を持つ企業や、大規模なVPNネットワーク構築が必要な企業では、自社構築が難しいケースがあります。この場合、通信事業者が提供するインターネットVPNサービスの利用がおすすめです。
インターネットVPNサービスを利用すれば、ルーターなどの必要機器がレンタルできるほか、自社で設定やメンテナンス作業をする必要がほぼないため、VPN構築や運用のノウハウがない企業でも導入しやすいという利点があります。
また、万が一故障やシステム障害が発生した場合に、サポートが受けられることも安心です。自社の規模や予算に応じて、適切な構築方法を選択しましょう。

VPN対応ルーターの選び方
レンタルであれば問題ありませんが、自社でルーターを購入する場合にはいくつか注意点があります。メーカーや価格によってセキュリティ機能、対応プロトコルなどが異なるため、購入時には以下を確認しておきましょう。
1.VPNサーバ機能の有無を確認する
VPNパススルー(PPTP・L2TP/IPsecパススルー)対応のルーターを選ぶ必要があります。ただし、社内LANにVPNサーバが構築されていない場合は、ルーターにVPNサーバ機能が備わったものを用意しなければなりません。VPNパススルーに対応しているルーターであっても、サーバ機能が非対応の場合もあるため、購入時にはサーバ機能の有無を確認しましょう。
2.L2TP/IPsec対応ものを選ぶ
市販のVPN対応ルーターは、主にPPTPやL2TP/IPsecのプロトコルに対応しています。ただし、PPTPは暗号化のセキュリティレベルが低く安全性に欠けることから、L2TP/IPsec対応のものが望ましいといえます。使用するデバイスのOSによっては、PPTPが標準対応していないものもあるため注意しましょう。
また、現在最も安全性が高いプロトコルは「OpenVPN」です。L2TP/IPsecよりもセキュリティ強度が高く通信品質が向上していることから、OpenVPN対応のルーターがある場合はそちらを選ぶ方が安全でしょう。
3.セキュリティ機能が付いたものを選ぶ
VPN接続の窓口となるルーターは、セキュリティを高めるために重要な部分となります。通常、VPNルーターはVPNゲートウェイとして社内LANへ直接接続するものが一般的ですが、中にはファイアウォール機能などを備えたものがあります。
安全なネットワーク構築に有効なVPNですが、セキュリティの脆弱性を狙ったサイバー攻撃や情報漏えいのリスクはゼロではありません。より安全性の高い通信を実現できるよう、セキュリティ機能の付いたVPNルーターを選ぶことをおすすめします。

目的に応じて最適なVPNを選ぶことが大切
インターネット環境とVPN対応ルーターがあれば、比較的簡単に、かつ低コストでインターネットVPNを構築できます。選ぶVPNルーターによって機能や価格などが異なるため、企業のセキュリティポリシーや予算に応じて選ぶことが大切です。
ただし、上述したように拠点数が多く自社構築が難しい場合には、かえって高額なコストがかかることもありますし、万が一のトラブルの際、適切に対処できない可能性もあります。
より安全な通信環境を維持するためには、導入時にかかる手間やコストのほかに、長期的な運用ができる管理体制が整っているかどうか考慮しなければなりません。自社構築や管理が難しい場合には、インターネットVPNサービスの利用を視野に入れましょう。

VPNのITreview Grid
ITreviewでは、企業でのVPN導入にどの製品を選んで良いか分からない方に向けて、ユーザーに人気のツールがひと目で分かる四象限の比較Map「ITreview Grid」を公開しています。
ITreview Grid上のツールにはユーザーのレビューも集まっており、どのように評価されているかが分かります。顧客満足度が高いツールをチェックして、自社に最適なツールを選定ください。

投稿 職場でインターネットVPNを構築する方法|ルーターの選び方は? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 遠隔地から社内PCにアクセス可能な「Chromeリモートデスクトップ」、VPN環境との違いは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>しかし、こうしたリモートデスクトップ機能を利用するには、社内のVPN構築が必要です。VPN構築には専用機器の準備や複雑な設定を伴うため、VPN導入に踏み切れないという会社も少なくありません。
そこで視野に入れたいのは、Googleが提供している「Chromeリモートデスクトップ」サービスです。本記事では、Chromeリモートデスクトップの機能や使い方、VPN環境との違いについて解説します。
Googleが提供する「Chromeリモートデスクトップ」とは?
遠隔地から社内PCへのアクセスを可能にする、リモートデスクトップ機能が備わったGoogle Chromeの拡張機能・アプリケーションのこと。「Google Chrome」ブラウザの拡張機能として提供されています。
デバイスに「Chromeリモートデスクトップ」をインストールすることで、2台のPCをインターネット上で結び、外出先からでも社内PCへアクセスして遠隔操作ができるようになります。
最大の特徴は、社内にVPNを構築しなくても良いという点です。インターネット環境があれば無料でリモートデスクトップ機能を利用できるため、VPN機器の準備や複雑な設定は必要ありません。
VPN構築に比べて手間やコストを抑えられるという利点から、小規模オフィスやテレワークなどで、手軽にリモートアクセス環境を導入したい企業に便利といえるでしょう。
Chromeリモートデスクトップの対応OS
Chromeリモートデスクトップは、WindowsをはじめとするさまざまなOSに対応しており、スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスに向けたクライアントアプリも無料で提供されています。(AndroidとiOSについては、Google Play/App Storeからアプリのインストールが必要です。)
対応OS
Windows、Mac、Linux、Chromebook、Android、iOS
Chromeリモートデスクトップを利用する
利用にあたり、まずインターネット環境があること、そしてデバイスに「Google Chrome」がインストールされていることが条件です。その後、各デバイスに拡張機能「Chromeリモートデスクトップ」をインストールしましょう。
スマートフォンなどのモバイルデバイスで利用する場合には、Chromeリモートデスクトップのアプリをインストールしてください。
接続する双方のデバイスでの設定について、主な流れは以下の通りです。
■遠隔操作される側のPC
1.PCからChromeを開き、アドレスに『remotedesktop.google.com/access』を入力
2.「リモートアクセスの設定」をクリックし、画面の手順に沿ってインストール
3.Googleアカウントやパスワードの入力が求められる場合は入力
4.デバイス間を認証するためのPINを設定(任意の数字で構いません)
PINはリモートデスクトップの接続を保護するための認証パスワードです。不正アクセスを防ぐために、推測されないものを設定しましょう。
■遠隔操作する側のPC
1.PCからChromeを開き、アドレスに『remotedesktop.google.com/access』を入力
2.アプリを起動し、リモートアクセスするPCを選択
3.接続先のPCのPINを入力
うまく接続できない場合、ファイアウォールなどのセキュリティ設定によって接続がブロックされている可能性があります。利用可否については、企業のセキュリティポリシーを踏まえた上で検討することが重要です。
VPN環境との違いとは?

「Chromeリモートデスクトップ」機能を用いたリモートアクセスは、手軽に導入できる非常に便利なサービスです。しかしその一方で、外部から自由にアクセスできること、セキュリティ認証が十分でないなどの問題点があることから、不正アクセスや情報漏えいのリスクを把握しておかなければなりません。
その点、VPNは各拠点間を仮想プライベートネットワークで接続しており、通信時にはトンネリングやカプセル化といったデータを保護する技術が用いられています。部外者がデータを盗み見しようとした場合でも、通信内容が見えないよう暗号化されます。
重要なデータを抱える企業にとって、ネットワークの安全性は妥協できないポイントの1つ。実際に、多くの企業ではリモートデスクトップ機能の使用を禁止しているところも多く、テレワークなどのリモートアクセスの構築には、安全性の高いVPNを用いるケースが増えてきています。
VPN機器の導入や設定は必要ですが、社内で安全にリモートアクセスを行いたいケースでは、「Chromeリモートデスクトップ」よりもVPN構築を選ぶ方が安心といえるでしょう。各拠点の重要度や、企業のセキュリティポリシーに合ったサービスを選ぶことが重要です。
投稿 遠隔地から社内PCにアクセス可能な「Chromeリモートデスクトップ」、VPN環境との違いは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 無料Wi-Fiを使うときの注意点。VPNを利用してセキュリティの強化を は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>不特定多数の人が使用できる無料Wi-Fiは、情報の盗み見やウイルス感染などのリスクが伴います。安全ではないと知っているものの「特に対策をしていない」という利用者も多いのではないでしょうか。
本記事では、無料Wi-Fiを使用するときに注意しておきたいことや、すぐにできるセキュリティ対策、VPNを利用したセキュリティ対策について解説します。
【注意点①】暗号化された通信でも安心できない
無料Wi-Fiのなかには、通信が暗号化されたものと、そうでないものが存在します。暗号化されたネットワークは、Wi-Fi接続時に接続のためのパスワード入力が求められます。一方、暗号化されていないネットワークは接続時にパスワードの入力が不要です。パスワードによる認証がないということは、当然ながら悪意あるユーザーに情報が盗み見されるリスクが高いことになります。
しかし、「パスワードのかかった無料Wi-Fiであれば大丈夫」だと安心してしまうことも危険です。調べ物をしたり、動画を見る程度であれば問題ないかもしれませんが、機密性の高い企業情報をやりとりすることはやはり危険です。
なぜなら、無料Wi-Fiに多くに使用されている暗号化は、セキュリティレベルが低い「WEP」「WPA」を使用しているためです。WPAは、WEPよりもセキュリティ強度が向上されていますが、それでも暗号化規格の違いによって安全性は異なります。「必ずしも安全」といえるほど万全なものではありません。
選択するべきWPAの種類と暗号化方式は?
無料Wi-Fiを接続する際には、セキュリティの高いプロトコルを選ぶことが重要です。
WPAの種類と、暗号化規格によるセキュリティの強度は以下の通りです。
1.プロトコル
・WPA:現在の主流となっている
・WPA2:WPAよりもセキュリティが高い
・WPA3:WPA2の弱点を改良した強固なセキュリティだが、対応している製品が少ない
2.暗号化規格
・DES:セキュリティが弱く、データが解読されるリスクが高い
・TKIP:DESより強固だが、AESよりはセキュリティが弱い
・AES:現在主流となっている規格
WPA3は2018年に登場したばかりのプロトコルであるため、現在使用できるケースはほとんどありません。現時点でもっとも安全といえるネットワークは、「WPA2/AES」での接続といえます。暗号化していない、あるいはWEP/DESでの接続は危険性が高いため、安易に接続しないよう注意しましょう。
【注意点②】ログインや個人情報の入力は危険
無料Wi-Fiスポットを使用しているときは、ID/パスワードを使って社内システムにログインしたり、顧客番号などの個人情報の入力は避けるべきです。社内データや、顧客情報をやりとりすることで、その情報が盗み見されたり、パスワード等を盗まれ悪用される可能性があります。
また、情報の盗み見だけでなく、個人情報を使ってさらなる犯罪行為に及ぶ可能性もあります。写真やファイルをコピーしたり、連絡先などを盗んで自宅を特定したりなど、トラブルにつながるリスクがあります。無料Wi-Fiを使用する危険性について、社内で改めて認識しておきましょう。
【注意点③】Wi-Fiが自動接続する設定になっている
スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイス側で、Wi-Fiに自動接続する設定になっている場合は危険です。自動設定は面倒な操作が不要になるというメリットがありますが、暗号化無し・HTTPS非対応などの信頼できないネットワークにも自動接続してしまう可能性があります。
モバイルデバイスにはアクセスポイントを選んで接続するよう設定し、セキュリティ強度が高いネットワークのみを選びましょう。
無料Wi-Fiを安全に使用するための対策とは
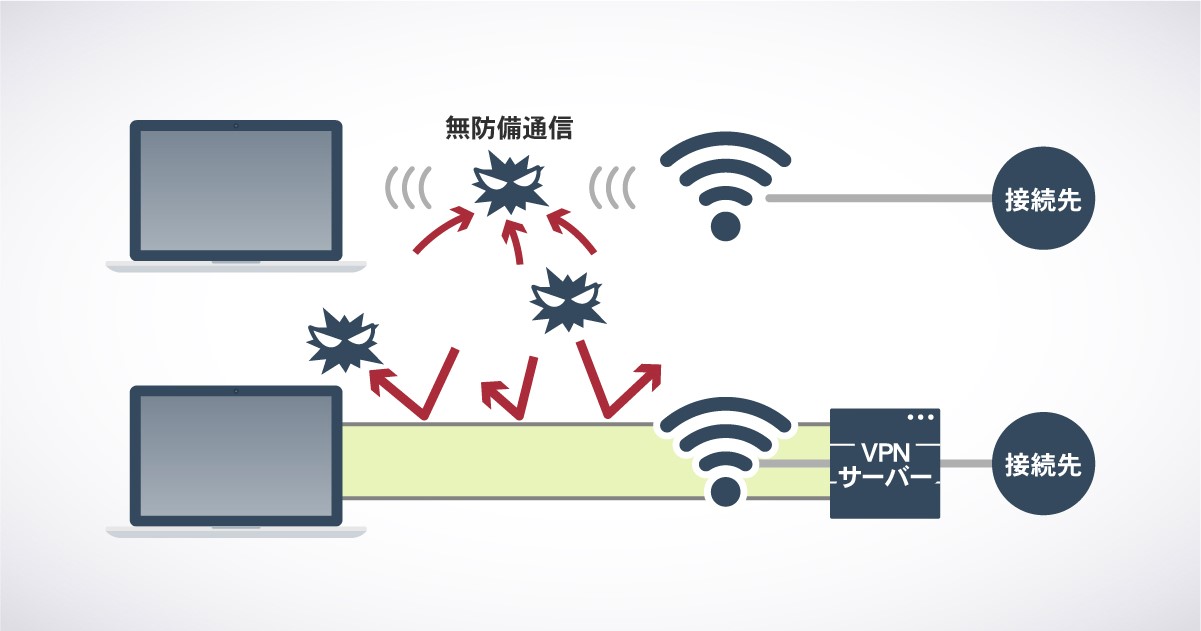
無料Wi-Fiをむやみに接続しないことがトラブルを防ぐ最善策ですが、業務の都合上、外出先でインターネット接続が必要になるケースもあるでしょう。
こうした場合のセキュリティ対策として、VPNの利用を検討しましょう。VPNは、仮想的な専用回線を構築して通信内容を暗号化するため、外部からのデータ盗み見や攻撃に対する防御を強固にできます。出張等で無料Wi-Fiサービスを頻繁に使用する方は、VPNによる適切なセキュリティ管理が不可欠といえるでしょう。
中でもIP-VPNは安全性が高く、通信のレスポンスがインターネットVPNと比べて速くなっています。セキュリティを重視したい、作業効率を落としたくない方は、IP-VPNを選ぶとよいでしょう。
無料Wi-Fiを使用しながらセキュアな通信を可能にするVPN。業務でモバイルデバイスを多用する、現代のビジネスシーンにおいて必要な対策といえます。企業の情報セキュリティ向上に向けて、VPNの導入を検討しましょう。
投稿 無料Wi-Fiを使うときの注意点。VPNを利用してセキュリティの強化を は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 無料のVPNに潜むリスク。安全に使うために知っておきたい3つのこと は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、Free VPNを使用する前に知っておきたい3つのリスクについて解説します。
安全なVPNだけではない
企業活動にインターネットが不可欠となったいま、多くの企業や団体でVPNの普及が進み始めています。暗号化通信によって盗み見や情報漏えいのリスクを防ぐだけでなく、本社と各支店を結ぶ拠点間通信によって、業務効率の向上も期待されています。
同時に、VPNサービスを提供する事業者も増えてきており、企業向けから個人向け、有料版や無料版まで多種多様なVPNが利用できる環境となりました。しかし、Free VPNのなかには適切に運営されていないものもあり、本来のVPNとしての機能を活用できていないケースが見られます。
毎日多くの情報をやりとりする企業では、情報セキュリティ対策が顧客や取引先との信頼関係にも影響します。セキュリティが十分に確保された信頼できるVPNを選ぶことは、経営の観点からも重要なことといえるでしょう。コストを安く抑えられるFree VPNですが、その危険性やセキュリティレベルについて理解しておくことが大切です。
Free VPNを利用する際に知っておくべき3つのこと
公開されているFree VPNのなかには、以下のようなリスクがあります。
1. マルウェアの感染・サイバー攻撃のリスクがある
Free VPNには、セキュリティ面の脆弱性が懸念されます。VPN自体が悪意を持って作られている場合もあれば、セキュリティ上の弱点を狙ってサイバー攻撃を仕掛けてくる危険性もあります。知らないうちにマルウェアに感染しているケースもあるため、社内の重要な情報を抜き取られることや、データを改ざんされるといったトラブルを招きかねません。
また、利用デバイスのデータ悪用や、遠隔操作によって犯罪に巻き込まれる可能性もあります。企業の資産を守るため、犯罪に巻き込まれないためには、こうしたリスクを最小限に抑えられる信頼性の高いVPNを選ぶことが大切です。
2. 暗号化されていない可能性がある
VPN通信では、暗号化技術によって通信内容が傍受されないように作られていることが基本です。しかし、一部のFree VPNでは通信が暗号化されていないケースが報告されており、プライバシー保護や個人情報保護といった権利が脅かされています。
また、暗号化がされているVPNであっても、選択するプロトコルによって暗号化の強度が異なります。現時点でセキュリティレベルの高い「OpenVPN」でないプロトコル(PPTPなど)を使用する場合は、第三者による盗み見や改ざんが起きるリスクが高いといえます。
機密情報を扱う企業にとって、こうしたセキュリティの低いVPNを使用することは非常にリスクの高いことといえるでしょう。
3. ログデータが利用される可能性がある

VPNの安全性を図る手段として、「ノーログポリシー」が挙げられます。VPNログとは、ユーザーがVPN経由で閲覧したサイトや通信履歴といったデータのことです。多くのVPNでは、プライバシーや個人情報保護の観点からこのログを保持しないよう宣言していますが、Free VPNのなかにはログを取得しているサービスも存在します。
IPアドレスや通信データ量などの接続ログに加え、訪問したサイトやファイルまで保存されている場合もあります。こうして保存されたログデータは、第三者に転売されてしまう可能性があるため、プライバシーが守られているとはいえないでしょう。
Free VPNを使用する判断基準とは?
Free VPNが必ずしも良くないと断言はできませんが、有料版と比べ、無料版はセキュリティの脆弱性を狙ったトラブルに巻き込まれるリスクが高いといえます。企業のセキュリティポリシーに反する可能性が高いため、使用の際は慎重に判断しましょう。
特に、プライベートで社用のノートPCを利用する際や、企業データが入ったスマホやタブレットでFree VPNを使う場合は危険です。社内に強固なVPNを構築していても、セキュリティの弱いFree VPNを利用すれば、たちまち危険にさらされます。
企業活動にはできるだけ有料版を使用し、社用のデバイスで無料版に接続しないよう社内へ呼びかけましょう。やむなく使用が必要な際は、プロバイダーのプライバシーポリシーに加え、「最新プロトコルを使用しているか」「VPNプロバイダーの信頼性が高いか」「ログを保持していないか」などを確認しておくことも大切です。
投稿 無料のVPNに潜むリスク。安全に使うために知っておきたい3つのこと は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 安全安心な情報発信の強い味方!大学発の「VPN Gate」とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>そこで、外国で使用する場合の「VPN Gate」のメリットを、従来の商用VPNと比較しながら見ていきたいと思います。
VPN Gateとは?

「VPN Gate」とは、筑波大学が2013年に、学術研究を目的に開始したVPNサービスです。営利目的ではないため、誰でも無料で使用できます。「VPN Gate」は、国外での安全安心な情報閲覧と情報発信を主な目的にしており、以下の通りWindowsをはじめ、主要な4種類のOSに対応しています。
「VPN Gate」が対応する端末と接続方式
・Windows
対応VPNプロトコル
(1)SoftEther VPN(推奨)
SoftEther VPNは、筑波大学が学術目的の研究プロジェクトとして開発した「大学発のプロトコル」です。SoftEther VPNの口コミ・評判は、以下をご覧下さい。
(2)L2TP/IPsec
(3)OpenVPN
(4)MS-SSTP
・macOS X
対応VPNプロトコル
(1)L2TP/IPsec(推奨)
(2)OpenVPN
・iPhone/iPad(iOS)
対応VPNプロトコル
(1)L2TP/IPsec(推奨)
(2)OpenVPN
・Android
対応VPNプロトコル
(1)L2TP/IPsec(推奨)
(2)OpenVPN
外国での安全安心な情報発信に有効なVPN
外国において安全安心な情報発信を行う上で、VPNは大きな役割を果たすと期待されています。
情報統制が行われている国においてよく行われるのが、政府が構築したファイアウォールによるインターネットの情報規制です。そうした国では、政府に都合の悪い情報を規制すると同時に、市民が発信する情報を監視する傾向があります。発信する情報がその国の政府に都合の悪いものだった場合、逮捕・拘束される危険性があります。
政府などの検閲用ファイアウォールでは、情報規制のため不適切な情報を発信した経歴を持つIPアドレスを記録し、そのIPアドレスを「接続禁止IPアドレス」としてリスト化していると考えられます。
この時、通信を通過させる判断基準は、発信元と宛先が「接続禁止IPアドレスと一致しないかどうか」だけの場合が多いようです。つまり、暗号化された「通信の内容」は見ていない場合が多いのです。
そこで、情報統制が行われている国において外国の情報を閲覧する時にVPNを使うことで、政府の検閲用ファイアウォールを回避できます。VPNを使うと、「発信元」と「宛先」を国外のVPNサーバにすることができるからです。
さらに、そうした国の市民が「公正な情報」を得るだけでなく、国外に向けてその国の実情を発信するなど、安全安心な情報発信を行う上で、VPNは有効な手段です。
日本人も無関係ではない外国の情報統制
外国での情報統制は、日本人も決して無関係ではありません。なぜなら、そうした国に赴任した日本人が現地から発信した情報が原因で、逮捕・拘束されるリスクも少なからずあるからです。
事実、日本人が赴任先の外国政府から、身に覚えのないスパイ容疑などで不当に逮捕されるケースも発生しています。あなた自身が、外国へ行くことがなくても、大切なご家族やご友人が外国で不当に逮捕・拘束されるという事態も起こりえます。そこで、そのような国に日本人が仕事などで赴任した場合にも、日本との情報伝達の手段として、VPNは有効です。
VPNは、情報統制が行われている国において、市民はもちろんのこと、その国に赴任した日本人が安全安心に情報発信する手段としても、重要性が高まっています。
商用VPNが抱える課題とは?
このように、自由な情報発信手段としてVPNは有効です。しかし、従来の商用目的のVPNは、ファイアウォールにより通信が不安定になりやすいという課題を抱えています。では、なぜ商用VPNは、通信不安定になりやすいのでしょうか。
従来の商用VPNは、多くの場合において、運営する企業のデータセンターなどに設置されたVPNサーバが情報発信の拠点です。同じデータセンターにVPNサーバがあるとIPアドレスが似通ったものとなり、偏りが生じます。
IPアドレスが似通った番号であることのデメリットは、その国のファイアウォールが原因で発生する通信不良の影響を受けやすい点です。
また、ファイアウォールが特定VPNのIPアドレス群を遮断すべきであると判断した場合も通信できなくなります。
商用VPNの弱点をカバーする「VPN Gate」
筑波大学が提供する学術研究目的の「VPN Gate」は、これらの商用VPNが持つ弱点をカバーし、安全安心な情報発信の有効手段として期待されています。
1. 世界各国約200台のVPNサーバが無料で使用可能→ファイアウォールによる通信不良の影響を受けにくい
VPN Gateは、世界各国にある約200台が提携する中継VPNサーバを選択できるので、IPアドレスに偏りが生じません。そのため、ファイアウォールが原因で通信不良が発生した場合でも、他の連続性がないIPアドレスを持つVPNサーバに接続先を変えることで通信継続が可能です。
さらに、これらの提携VPNサーバは、筑波大学の学術研究に賛同した世界各国の個人・法人により、無償で提供されています。つまり、世界各国200台のVPNサーバを無料で使用できるのです。
2. ミラーサーバによる万全なバックアップ体制
→VPN Gateにアクセスできなくても通信可能
VPN Gateには、中継サーバにアクセスする上で、大きな問題点がありました。各国の中継サーバにアクセスするには、まずVPN Gateのサイトにアクセスして、各サーバのIPアドレスを取得する必要があるのです。もし、その国のファイアウォールが原因で、VPN Gateのサイトにアクセスできない場合は、中継サーバにアクセスもできません。
VPN Gateは、ミラーサーバを設置することでこの問題を解決しています。ミラーサーバは、筑波大学が設置したGateサーバと同じ情報と機能を持っています。中継サーバと同様に、VPN Gateの学術研究に賛同する世界各国の個人・法人によって設置され無償で公開されています。仮に、VPN Gateへのアクセスができなくなった場合でも、各国にある複数のミラーサーバにアクセスすることで、通信継続が可能です。
ミラーサーバの数は変動があるため、Gateにメールアドレスを登録することで、1日3回最新のミラーサーバアドレス一覧が送付されます。
2019年12月8日時点におけるミラーサーバは、日本、米国、英国、スリナム共和国の4カ国において、合計5カ所登録されています。
外国へ赴任する前にVPN Gateをインストールする事をおすすめします
このように、外国でのファイアウォール対策として、安全安心な情報発信の手段として、多くのメリットがある「VPN Gate」。海外にPCを持って一定期間赴任される方は、事前にインストールしてみてはいかがでしょうか?
既に、セキュリティの高い有料VPNを使用されている場合でも、万一の際のサブのVPNとして、インストールしておいて損はありません。インストール後、国内で試してみて使用方法に慣れておけば、海外ですぐに使えて便利です。
以下の「VPN Gate」の公式Webサイトにアクセスして、各端末の種類・接続方法別に、案内に従うことで、VPN Gateを使用できます。
VPN Gate公式Webサイト:https://www.VPNGate.net/ja/
例えば、端末にWindowsを使用し、接続方法としてSoftEther VPNを選んだ場合、必要なソフトをインストールしてVPN接続するまで、わずか10分ほどです。
VPN Gateを使用することで、海外で安全安心な情報発信が可能となるのはもちろんのこと、筑波大学の学術研究に協力することは、日本のVPN技術向上にもつながります。
今後、多くの方がVPN Gateを使うことで、よりセキュリティレベルの高いVPN技術の革新を期待したいですね。
投稿 安全安心な情報発信の強い味方!大学発の「VPN Gate」とは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 オンラインストレージとファイル転送サービスの違いとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>ファイル転送サービスは、無料で使えアカウント登録が必要ないものも多く、すぐに使えるため便利です。しかし、ビジネスで使用するには適さない面もあります。
本記事では、はじめに無料のファイル転送サービスをビジネスで使う上での注意点をご紹介します。そして、無料で登録でき、プランによっては容量無制限で使えるオンラインストレージとファイル転送サービスとの違いを見ていきたいと思います。

無料のファイル転送サービスを利用する際の注意点
無料で利用できるファイル転送サービスは、会員登録などが不要で、誰でも気軽に利用できるのが特徴です。
ただし、ビジネスで無料ファイル転送サービスを利用する上では、いくつか注意点があります。
1.個人情報や機密情報を含むデータの送信に注意する
社内外でファイル共有する場合には、個人情報や機密情報などの絶対に情報漏えいしてはならない情報も含まれます。ファイルによっては、経営幹部や特定の部署のみに閲覧制限したい場合があります。そのためには、ファイルやフォルダ単位での細かな権限設定が必要になります。
例えば、データのダウンロードを許可するのか、編集や削除までOKするのか、といった権限を部署や人によって変える必要があるのです。さらに、組織変更によって、許可する権限も適時変更しないといけません。
無料ファイル転送サービスを使った場合、ファイルを転送した後にアクセス権を変更することはできません。万が一、宛先を間違えて送信してしまうと、取り返しのつかない事態が発生します。従って、無料ファイル転送サービスを使って共有するファイルは、個人情報や機密情報を含まないファイルに限定した方が良いでしょう。
2.セキュリティ対策が十分か注意する
無料ファイル転送サービスでアップロードしたファイルは、閲覧期限は決まっているとはいえ、一定期間データセンターに保管されることになります。ビジネスで利用する場合には、不正アクセスなどの情報漏えいを防ぐため、万全のセキュリティ対策が求められます。
しかし、無料ファイル転送サービスの中のほとんどは、SSL通信に対応しているものの、アップロードしたファイルが暗号化され保管されると明記されているサービスは少なく、データセンターでどのようなセキュリティ対策が講じられているのか不明です。
3.不要な広告をクリックしないように注意する
無料ファイル転送サービスは、サービスページに広告を表示することで、事業運営に必要な資金を確保していると考えられます。サービス運営のために広告が表示されているのは仕方ありません。
問題なのは、広告のリンク先ページがどのようなページか判断がつかないことです。リンク先ページが悪意のあるフィッシング詐欺(※注1)サイトである可能性が無いとは言い切れません。
広告をクリックしないというルールを設けても、利用者がクリックしやすい場所に広告が表示されているため、誤ってクリックすることを防ぐことは難しいのではないでしょうか。
※注1 偽装されたURLをクリックさせることで、ユーザー名やパスワード、クレジットカード情報などの個人情報を取得しようとするオンライン詐欺のこと。
上記の理由から、無料ファイル転送サービスは、ビジネスでの使用にはあまり相応しくないといえます。そこで利用者が増えているのがオンラインストレージサービスです。オンラインストレージサービスにも無料且つ、プランによっては容量無制限で利用できるサービスも数多くあります。
オンラインストレージとファイル転送サービスの違い
一般的にオンラインストレージというと、ファイルサーバのようにデータを保存するサービスと考えている方も多いかもしれません。しかし、多くのオンラインストレージにはファイル共有機能が備わっており、ファイル転送サービスと同じ用途でも利用することも可能です。
では、オンラインストレージとファイル転送サービスは何が違うのでしょうか。無料のファイル転送サービスにはない、オンラインストレージの特徴を、ファイル共有の観点から3つご紹介します。
1.ファイルやフォルダ単位での細かい権限設定ができる
利用するサービスやプランによっても異なりますが、一般的にはオンラインストレージにはファイル共有するフォルダやファイルに対して細かい権限設定を行う機能がついています。
例えば、経営幹部や特定の部署の人のみ閲覧できるように設定することが可能です。そのため、万が一閲覧権限のない人にファイル共有リンクが漏れても、ファイルを閲覧されることはありません。また、閲覧のみの目的であればダウンロードを制限できるサービスもあります。
しかも、オンラインストレージに保存されているデータは暗号化されている場合が多く、万が一外部に流出したとしても情報漏えいするリスクは低いといえます。
一方、ファイル転送サービスの場合には、転送するファイルにパスワードをつけることができますが、パスワードさえわかれば誰でも閲覧することが可能です。
2.アクセスできるデバイスを制限できる
オンラインストレージには、ファイルやフォルダにアクセスするデバイスやアクセス元のI Pアドレスを制限する機能を持ったサービスも多くあります。部署や人単位の設定だけでなく、デバイスやI Pアドレスで制限を加えることによって、セキュリティを強固にすることが可能です。
3.アクセスログを記録できる
オンラインストレージの中には、ファイルへのアクセスログを記録できるものもあります。アクセスログを確認することで、誰がいつアクセスし、ファイルの中身を閲覧したのか確認することが可能です。万が一情報漏えいした場合にでも流出元を特定し、早期に対応を行えます。
一方、ファイル転送サービスを利用した場合には、ファイルアクセスログの記録は不可能です。転送したファイルを誰がいつ見たのか、不正なアクセスはないか判断することはできません。
※上記でご紹介したオンラインストレージの機能は、サービスやプランによって利用できない場合もあります。詳しくは、個々のサービスやプランをご確認ください。
ビジネスでファイル共有するには、法人向けのオンラインストレージをおすすめします
無料ファイル転送サービスは、容量無制限で利用できるものも多く便利です。しかし、詳細なアクセス権の設定ができないことやセキュリティ対策の不安から、ビジネスで本格的に利用するには不向きだと考えられます。最近では、ファイアウォールなどでサービスの利用を制限する企業も少なくありません。
オンラインストレージの中にも、無料で登録でき、プランによっては容量無制限で利用できるものがあります。そして、ビジネスで使うには何よりも情報漏えいを防ぐためのセキュリティが重要です。ビジネスで使うファイル共有ツールには、詳細な権限設定が可能でセキュリティ対策がしっかりしているビジネス向けのオンラインストレージを利用することをおすすめします。
ビジネス向けのオンラインストレージについての口コミ・評判は以下のサイトをご参照ください。
投稿 オンラインストレージとファイル転送サービスの違いとは? は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 バックアップに最適なオンラインストレージサービス3選|増加するサイバー攻撃や自然災害へ備えを万全に! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、バックアップの必要性とバックアップ先としておすすめの法人向けオンラインストレージをご紹介します。
サイバー攻撃や自然災害の増加と高まるバックアップの必要性

サイバー攻撃による被害は年々増加しています。トレンドマイクロ社が発表した「2019年 第1四半期セキュリティラウンドアップ データを暗号化する標的型攻撃」によると、企業を狙った標的型攻撃の中でランサムウェアが使用されたことが複数確認されているようです。
“2017年以降、全体的に減少を続けていたランサムウェア(※注1)の脅威が、2019年に入り再び増加の傾向を示し、2019年四半期( 1月〜3月 )の攻撃総数は約3,750万件と2018年1年間の7割に迫る勢いです。”
引用元:2019 年第1四半期セキュリティラウンドアップ データを暗号化する標的型攻撃
※注1感染すると、PCやサーバのファイルが暗号化され、アクセスできなくなる不正プログラムのこと。アクセス制限を解除するために、ハッカーが身代金(ランサム)を要求する。
1台でもランサムウェアに感染すると、社内ネットワークを経由して、サーバや多くのPCのデータも感染する恐れがあります。場合によっては、全社の業務がストップする可能性すらあります。
ランサムウェアへの感染を防ぐ方法としては、不正サイトの侵入をブロックするためにウィルス対策ソフトを導入することや、使用中のプログラムをアップデートすることが有効です。
しかし、ランサムウェアも進化するため、セキュリティ対策を行えば大丈夫という保証はありません。万が一の事態に備えてファイルのバックアップを行なっておくことが重要です。
サイバー攻撃だけでなく、自然災害の増加によるデータ消失リスクに対する懸念も高まっています。東日本大震災以降は、想定外の自然災害が起きた場合でも事業を継続できるように、経営に欠かせない重要な情報をすぐに復旧するための対策を検討する企業が増えています。
当然のことながら、万が一の場合に備えてバックアップを取っておくことが重要です。しかし、地震などの災害があった場合には、同じ地域にあるサーバにバックアップが保存されていれば、バックアップデータも消失する可能性があります。そのため、自然災害を想定した場合に大切なことは、データの保存地域を分散させることです。
そこで、注目されているのがオンラインストレージを活用したバックアップです。
バックアップに必要なオンラインストレージの機能
バックアップを保管するオンラインストレージを選ぶ際に、重要なのは、「セキュリティ対策」です。オンラインストレージが稼働しているデータセンターもランサムウェアに感染する恐れがあります。従って、ランサムウェアなどのサイバー攻撃に耐える堅牢なセキュリティ対策や万が一の場合に備えたバックアップが求められます。
また、地震などの自然災害を考えると、「データセンターの所在地」も確認しておく必要があります。オンラインストレージによっては、異なる拠点にデータを分散保存しているサービスもあります。事業継続に影響があるようなデータの場合は、データセンターの所在地を分散させ、何重にも冗長化しておく必要があるかもしれません。
次に「ストレージ容量」です。業務で使用する膨大なデータを保存できるだけのストレージ容量が求められます。ストレージ容量が不足して、バックアップできないといった事態は避けなければなりません。容量を気にしなくても済むように十分なストレージを確保することをおすすめします。
そして「価格」です。法人で利用する場合、価格も気になるところです。自然災害やサイバー攻撃に備えたBCP対策とはいえ、価格が高すぎては、継続的に使用できません。
バックアップにおすすめのオンラインストレージ3選
「セキュリティ対策」「データセンター所在地」「ストレージ容量」「価格」を総合的に判断し、データバックアップに使えるおすすめのオンラインストレージを3つご紹介します。
1.AOSBOX Business

最初にご紹介するのは「AOSBOX Business」です。「AOSBOX Business」は、米国の法人向けのオンラインバックアップサービス部門で5年連続No.1を獲得しているサービスです。
「通常ストレージプラン」には100GB、200GB、500GB、1TBのプランが用意されています。復元に時間を要するものの低コストで利用できる「コールドストレージプラン」も提供されており、過去の取引データなど、「使用頻度は低いけれど保存が必要なデータ」のバックアップに最適なサービスとなっています。
セキュリティ対策においては、マシン上、データ転送時、サーバ上と3重に256 ビットAES暗号化を実施しており、クラウドインフラには信頼性の高いAWSを採用するなど、セキュリティに力を入れています。また、データは日本国内の複数拠点、複数デバイスに分散して保存されていることから、災害等においても非常に高い耐久性を実現しています。
・ストレージ容量 100GB(通常ストレージプラン)〜 1TB〜(コールドストレージプラン)
・価格 20,000円/年〜(通常ストレージプラン) 70,000円/年〜コールドストレージプラン)
AOSBOX Businessユーザーのレビュー
“データのバックアップ先として最適
https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/32454
セキュリティがしっかりしていると思います。夜間自動でバックアップが取れている点が楽です。サポートもしっかりしていると思います。”
“万が一の時に安心のサービス
https://www.itreview.jp/products/aosbox-business/reviews/35087
インストール後初期設定のみで、その後は全自動でバックアップが取られる為、非常に簡単。データ復元についても見た目で操作でき、料金が定額である事。”
2.Box Business

次にご紹介するのは「Box Business」です。「Box Business」は容量無制限のため、バックアップに最適です。ファイルのアップロードも5GBとなっており、一般的なビジネス用途であれば、ほとんどのファイルをアップロード可能です。
米国3拠点のデータセンターを自社運用しており、保管データはすべてのデータセンターでコピーされています。通信経路はTLS 1.2で暗号化され、保管時には、256ビットAES暗号化が使用されています。セキュリティについても定評のあるオンラインストレージです。
また、信頼性の高い電源とバックアップシステムを備えた複数のデータセンターを使用しており、99.9%の可用性と冗長性を実現しています。
価格は、1ユーザーあたり月額1,800円です。容量無制限であることを考えると、利用しやすいプランではないでしょうか。
データセンターの立地が米国であることから、ユーザーレビューに「ページ遷移や転送スピードが微妙にワンテンポ遅い」といった声もありますが、やはり大容量は魅力ですね。
・ストレージ容量:無制限(Business以上のプラン)
・価格:1ユーザーあたり1,800円/月(最小3人)〜
Box Businessユーザーのレビュー
“非常に使いやすい素晴らしいサービス!
https://www.itreview.jp/products/box/reviews/33001
ストレージが無制限に使えるところではないでしょうか。ファイルサーバーと異なり容量を気にせずにファイルを突っ込めるので、コラボレーションが推進されていると思います。”
“大容量のストレージサービス
https://www.itreview.jp/products/box/reviews/32354
大容量のストレージサービスです。したがって、大きなデータを保存することができます。そして、バージョンの記録も自動で行ってくれるので、あやまって上書きしてしまってもロールバックが可能です。このあたりの機能は、有料ならではのありがたい機能です。万が一の際にも安心できます。ただし、ページ遷移が、類似サービスに比べて微妙にワンテンポ遅い気がします。また転送スピードについても同様です。もしかしたらすべてUSにデータがあるのかもしれませんが、毎日使うものなので、DCが近距離にあるといいなあと思います。”
3.DirectCloud

DirectCloudのビジネスプランは、ストレージ容量が3TBで月額90,000円。
プレミアムプランは、10TBで月額180,000円と他のサービスと比べると高額です。しかし、ユーザー数は無制限のため、利用人数によっては、一人あたりの利用価格は安く抑えることができます。利用者からは、コストパフォーマンスを評価する声が多く投稿されています。
通信経路は256ビットSSLで暗号化され、ファイル保存時は256ビットAESで暗号化されます。デバイス認証やIPアドレス制限、ログイン履歴の閲覧、2段階認証など、セキュリティ対策は万全といえます。
データは、日本国内の3ヶ所にあるデータセンターに分散保存されており、自然災害などで1箇所が倒壊しても継続して利用できるように冗長化されています。
さらに、サービス品質保証制度(SLA)を明示しており、月間稼働率99.95%未満の場合には、月額利用料金の10%を減額することを約束しています。減額申請期限や適用除外なども細かく定められています。
・ストレージ容量:3TB(ビジネスプラン) 10TB(プレミアムプラン)
・価格: 90,000円/月(ビジネスプラン) 180,000円/月(プレミアムプラン)
DirectCloudユーザーのレビュー
“ニーズにマッチした費用対効果が高いクラウドストレージ
https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/31811
まずは、ユーザ数が無制限。比較的高機能。細かい共有設定には向かないが、社外から保存した情報にアクセスすることができるので、クラウドストレージのエントリーとしては十分な機能を持っていると思う。基盤がAWSというのも信頼ができるポイントだと思われます。
クラウドに抵抗がある企業はAWSのセキュリティの売りを再度確かめるといいかもしれません。”
“満足です!コスト・パフォーマンスが非常に高い
https://www.itreview.jp/products/directcloud-box/reviews/24979
当社にとってユーザー課金ではない!というところが最もニーズにマッチしたポイントです。将来的に全社員が使用することを考えると、ユーザー課金のサービスはコスト的に選択しにくいからです。”
自社に最適なオンラインストレージを使ってバックアップを行い、サイバー攻撃や自然災害への備えを万全にしましょう
自然災害やランサムウェアなどのサイバー攻撃のリスクが高まり、データバックアップの重要性が高まっていることをお伝えしました。さらに、データバックアップツールとしても注目が高まっているオンラインストレージの選び方とおすすめのサービスについてもご紹介しました。
自社のストレージ使用量やコスト、自社のセキュリティ基準を検討し、より良いオンラインストレージを選びたいものですね。今回ご紹介した3つのサービスの他にも、いろいろな法人向けのオンラインストレージがあります。以下のサイトにも、性能比較や利用者の感想などが掲載されていますので、ぜひ、バックアップに最適なオンラインストレージ選びの参考にしてください。
投稿 バックアップに最適なオンラインストレージサービス3選|増加するサイバー攻撃や自然災害へ備えを万全に! は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 オンラインストレージを自作で構築する方法 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>すでに提供されているオンラインストレージサービスは、メンバーとデータ共有をしたい場合に低コストで導入でき非常に便利です。
しかし、既存のオンラインストレージサービスではデータ容量やアクセス権、セキュリティ、コストなどの点で自分たちのビジネスのやり方に適さない、あるいは自社の持つPCやディスクなどのハードウェアをオンラインストレージとして活用したい、といった声もあります。
本記事では、このような場合にオンラインストレージを自作で構築する方法について解説します。
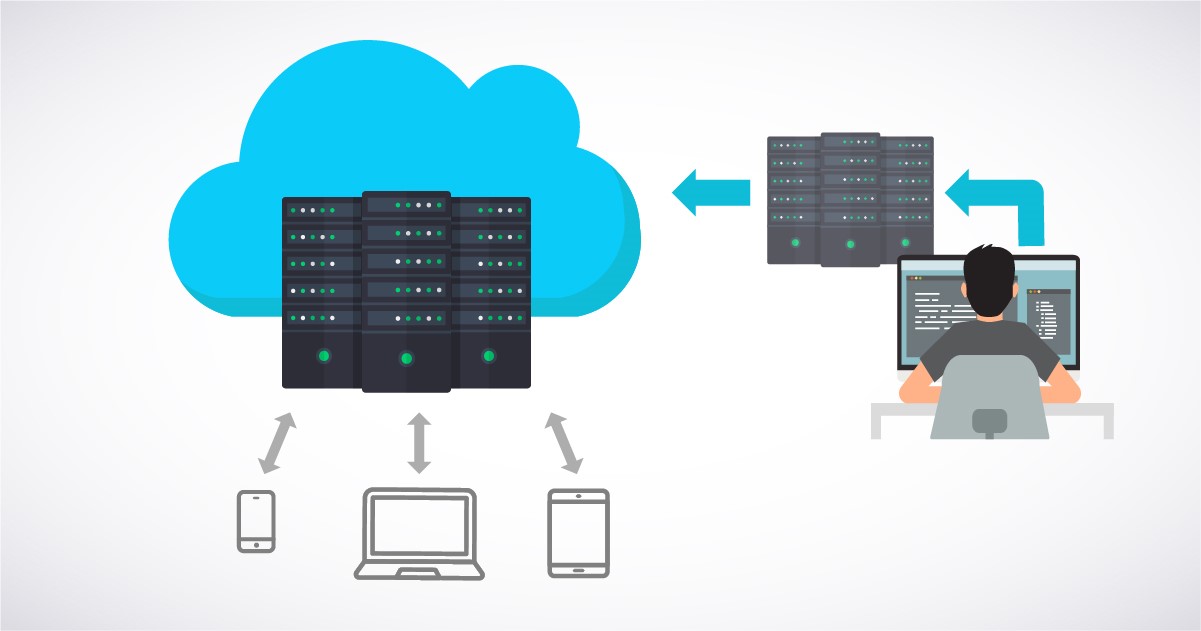
オンラインストレージとファイルサーバの違い
企業などでメンバーとデータを共有する方法として、オンラインストレージの他にファイルサーバを構築する方法もあります。
自作オンラインストレージとファイルサーバの構築では何が異なるのでしょうか?まずは、オンラインストレージとファイルサーバの違いを整理します。
1. オンラインとオフライン(インターネット環境に対する)による違い
ファイルサーバは、企業内の同じ建物内のネットワークであるLAN(Local Area Network)や離れた場所をつなぐためのネットワークであるWAN(Wide Area Network)を使って、データにアクセスします。自社のLANやWANのみを使用する点において、インターネット環境に対してはオフラインであるといえます。
つまり、共有したデータにアクセスする場合は自社のLANもしくはWAN経由となり、インターネット経由ではありません。
一方、オンラインストレージはインターネット上にデータを保存し、それをメンバーで共有するものです。インターネット上にデータを預かってくれる倉庫を借りて、共有するという考え方です。
基本的にはインターネット環境に接続していなければ利用できないという点でインターネット環境に対してオンラインであるといえます。インターネット経由でアクセスが可能となるので、インターネット接続環境さえあれば社内外を問わずどこからでもアクセスが可能です。
2. コスト面での違い
ファイルサーバは初期投資が必要です。先に述べたように、ファイルサーバ用のハードウェア、ソフトウェアおよびLANやWANなどのネットワークを用意する必要があるからです。
ただし、一度構築してしまえばあとはハード、ソフトおよびネットワークの維持にかかる費用のみで運用が可能となります。また、自社のユーザー数やデータ容量、拠点の増加に応じた構成の変更も自由に行えます。
オンラインストレージサービスを利用する場合にはインターネット接続環境さえあれば初期投資等は不要になります。利用が無料のプランもありますが、企業で使用する場合はセキュリティや容量、ユーザー数の面で有料のものを選択することをおすすめします。
オンラインストレージを自作する場合、ファイルサーバで説明したハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの費用に加えてインターネット接続環境構築のための費用が掛かります。
さらに後述のownCloudなどのクラウドサービスを使う場合には、機能によっては月額や年額のライセンス料などが加算され有料になる場合もあります。
表にまとめると以下のようになります。
| 初期費用 | ランニングコスト | 利便性 | 拡張性 | |
| ファイルサーバ構築 | サーバ ソフトウェア ネットワーク機器 |
不要 | インターネット接続環境であればどこからでもデータ共有が可能 | ユーザー数やデータ容量の拡張は自由に行える |
| オンラインストレージ(既存サービス利用) | 不要 | ユーザーやストレージ容量に応じた利用料 | 社内のLANやWANにアクセスできる場所でしかデータ共有ができない | ユーザー数やデータ容量の拡張は、サービス内容変更に伴うコスト増の可能性がある |
| オンランストレージ(自作) | サーバ ソフトウェア ネットワーク機器 |
インターネットへの接続やソフトウェアの利用料 | インターネット接続環境であればどこからでもデータ共有が可能 | ユーザー数やデータ容量の拡張は自由に行える |
自作オンラインストレージに使えるソフトウェア
オンラインストレージを自作するためのソフトウェアとその動作環境について解説します。
1. ownCloud

ownCloudは、オンラインストレージを、企業などの専用サーバに構築し、ファイルを共有するためのソフトウェアです。オープンソースとして開発されていますので、コミュニティー内で開発が進み、セキュリティや利便性が向上しています。
ownCloudには、通常のオンラインストレージの持つファイル共有、バージョン管理やマルチデバイスアプリの提供に加え次の特徴があります。
・LDAP/AD対応:LDAPやActive Directoryなどすでに社内で導入されているアカウント管理システムに連動させることが可能です。
・プラグイン、API拡張機能:機能拡張や他システムとの連携のためのプラグインやAPIが充実しています。
・外部ストレージとの連携:通常のファイルサーバだけでなく、AmazonS3、Dropbox、Google Driveなどの既存ストレージに接続することが可能です。
・日本語対応:他のソフトウェアと比較して、日本語への対応が充実しており、特殊なプラグインを導入していない限りは問題なく日本語が使えます。
2. Nextcloud
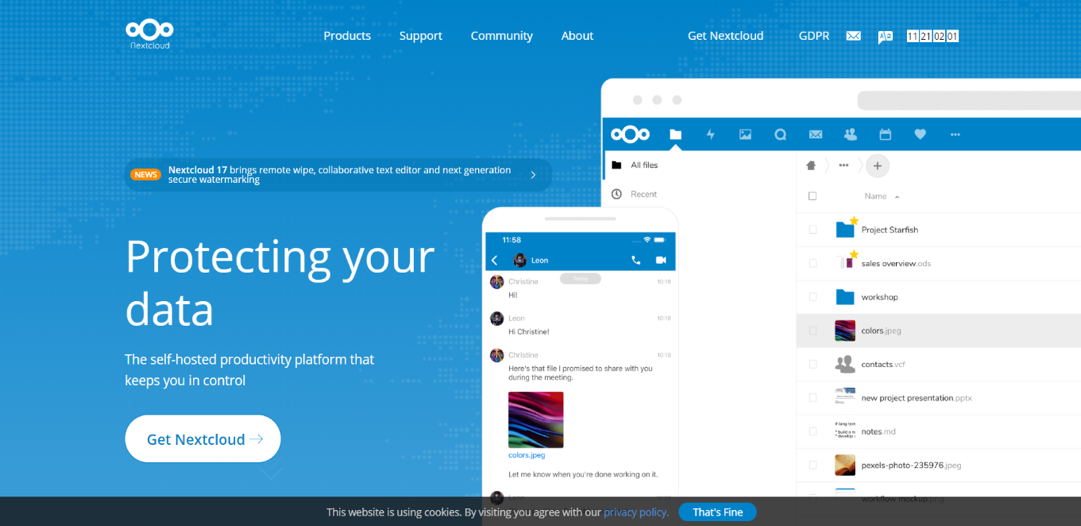
NextcloudはownCloudの創始者がownCloudの全ての機能をオープンソース上で実現させるために2016年にNextcloud社を創立したのが始まりです。
ownCloudのバージョンとともに拡張をしており、ownCloudのエンタープライズ版である機能もオープンソースで利用できます。また、Nextcloudの独自機能も開発されています。
NextcloudはownCloudに加えて次の特徴があります。
・モニター機能:標準のサーバログでは取得できないユーザーの操作に関する記録を取得することができます。
・ファイルのアクセス制御:管理者がファイルにアクセス制限をつけることができます。
ファイルロック機能:複数の人が同時にファイルを編集しても、ファイルが破損しないよう同時保存を防ぐ機能があります。
・ビデオチャット:Nextcloud Talkというチャット機能を持っており、チャットとビデオ通話が可能です。チャット内でファイルの共有や編集をすることも可能です。
3. Pydio
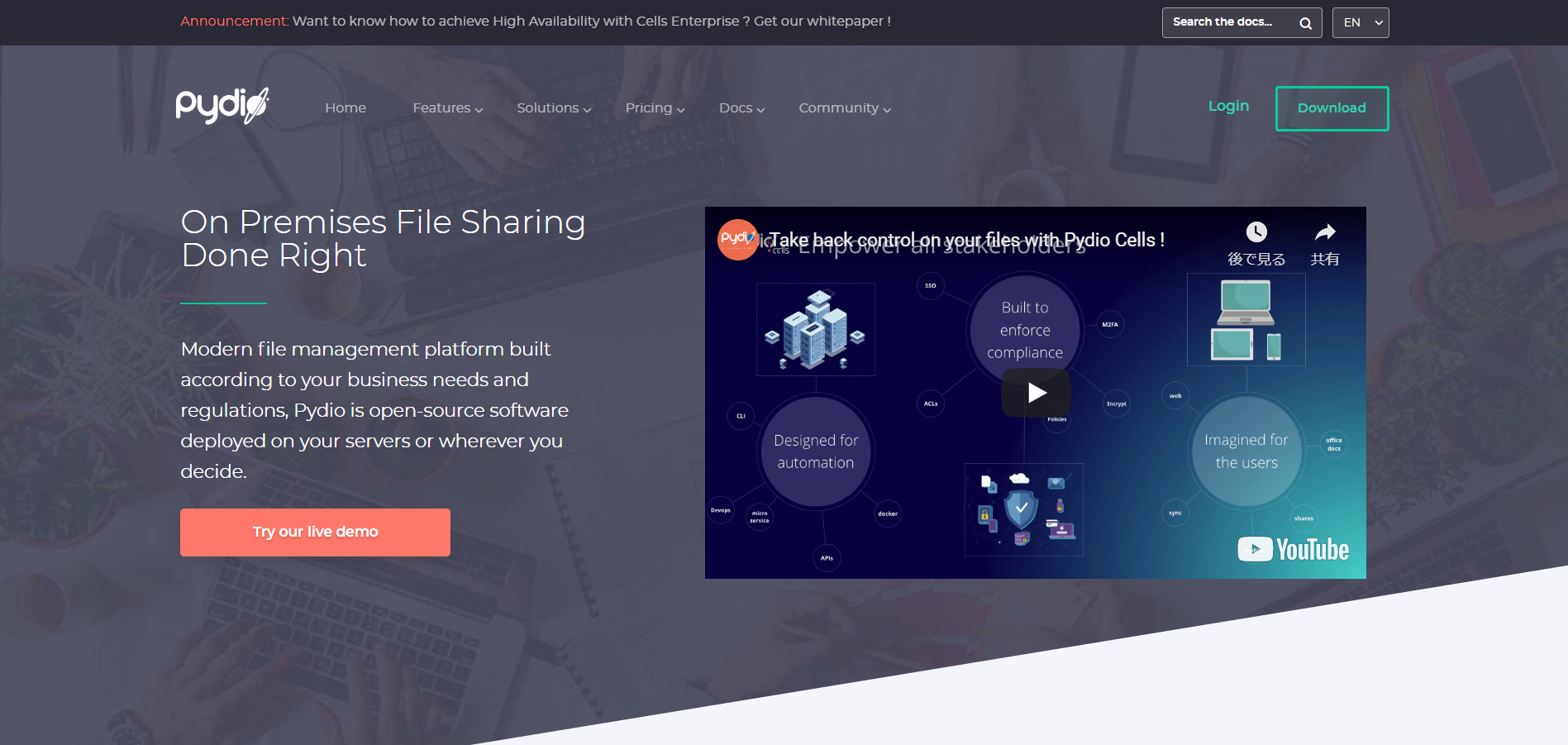
PydioはPHP上で動作するファイル共有のソフトウェアで、AGPLに基づいて公開されているコミュニティー版とEnterpriseライセンスによる商用版があります。コミュニティーで開発が進んでいることやAndroid/iOSのアプリがあること、プラグイン拡張機能を持つことなどはownCloudと同様です。
Pydioの特徴はワークスペースという概念にあります。ワークスペースに対してデータ容量やユーザーのアクセス権が割り振られます。これはownCloudやNextcloudがユーザーごとにデータ領域を割り振り、その一部を共有する方法と異なります。
ワークスペースの考え方により、目的や用途によって領域を自由に変更することが可能です。また、設定項目が多く、導入条件に対応したチューニングが可能です。
オンラインストレージを自作するための動作環境と流れ
オンラインストレージを自作する場合の操作の流れについて、ownCloudを例にとって説明します。
1.オンラインストレージ動作環境の設定
● オンラインストレージが動作するバージョンのPHPをインストール
● Webサーバ(Apache/Nginx)ソフトウェアをインストール
● DB(MySQL(MariaDB)/PostgreSQL)ソフトウェアをインストール
ownCloudを動かすために必要な環境は、それぞれ次の通りになります。
・サーバOS:Linux(RedHat系、Debian系)
・ミドルウェア:
Web:Apache/Nginx
DB:MySQL(MariaDB)/PostgreSQL
・ストレージ:Local storage, GlusterFS/Red Hat Storage, OpenStack Swift他
参考:ownCloud:https://owncloud.jp/requirements
2.オンラインストレージソフトウェアのインストール
・ownCloud本体のダウンロードと解凍
・ 1.でインストールしたWebサーバと関連づけるための設定ファイルの作成
・ ownCloudで使用するデータベースの作成(DB用ユーザー名、パスワードの設定)
3. ブラウザでの操作
・ http://設定中のWebサーバのアドレス/owncloud/をブラウザで開く
・ ユーザー名、パスワードの設定
・ 2.で作成したデータベースを指定し、DB用ユーザー名、パスワードの入力
以上の設定がすべて完了すれば、オンラインストレージを使えるようになります。
オンラインストレージの利用は、ブラウザ経由だけでなく、専用アプリをインストールすることでも可能です。
オンラインストレージの自作での注意事項
これまでオンラインストレージの自作について説明してきましたが、ここでは自作にあたっての注意事項について説明していきます。
ハード、ソフトは自己管理する
自作のオンラインストレージは、ハードウェア、ソフトウェア等を自前で用意することになります。従って、中にあるデータのバックアップや修復だけでなく、OSやミドルウェア等のバックアップ、アップデートにも自分で対応する必要があります。
また、セキュリティ対策や障害対応に対する準備についても自分で行う必要があります。
場合によっては管理者を置かなくてはならない
ユーザー数やデータ容量が多いときや、ストレージを複数に分散させる場合など、管理するものが多くなればそれを管理するための人員や時間も増えてきます。運用のやり方によっては専門の管理者を置き、高度な管理をしなければならない可能性もあります。
設定等がサービス利用よりも難しく、専門知識が必要となる
既存のオンラインストレージサービスに比べ、自社で用意したサーバやストレージ、ソフトウェアのインストールや設定等、使えるようにするための設定が難しくなります。
特にownCloudやNextcloudなどはOSがLinuxであるため、サーバ管理に対する専門知識が必要になります。
また、プラグインやAPIなど拡張機能を使う場合も同様に、高度な専門知識が必要となります。
オンラインストレージの自作は、自社のサーバやストレージなどハードウェアを有効活用したい場合や、既存のオンラインストレージサービスの中に自社に適したものがない場合には有効です。
しかし、初めてオンラインストレージを導入する場合には難易度が高いかもしれません。その理由は前述したように導入や設定、管理に専門的知識が必要であることや管理する項目や手間が既存のサービスより増加するためです。
オンラインストレージをいきなり自作するのではなく、まずは既存のサービスをよく比較して会社のニーズに最も近いサービスを導入し、それでも運用やコストの問題がある、または自社ですでに使用しているハードウェア等を使いたい、という場合には自作を検討することをお勧めします。
ビジネス向けのオンラインストレージの比較については次のリンクも参照してください。
ユーザーによる顧客満足度をベースに、自社に最適なオンラインストレージを選ぼう!
投稿 オンラインストレージを自作で構築する方法 は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 中国でのVPN利用はもう不可能?通信制限を回避できるVPNとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>こうした規制は、出張等で日本から中国へ足を運ぶビジネスパーソンにも支障をきたしかねません。中国でインターネット規制を回避できるVPNはあるのでしょうか?
本記事では、中国で厳しくなっているインターネット規制の現状と、通信制限を回避できるVPNがあるのかどうかについて解説します。
中国政府によるインターネット規制の現状
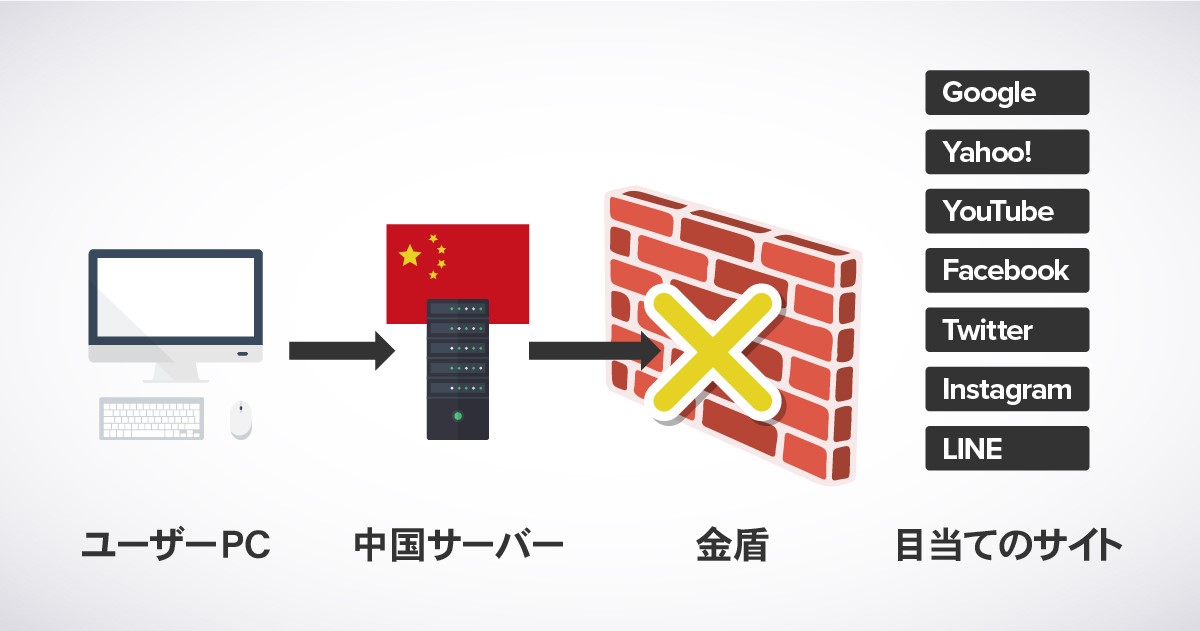
世界の中でもトップレベルのインターネット規制が敷かれている中国。一部Webサイトやサービスを自由に閲覧できないよう「グレート・ファイアウォール(金盾)」という検閲システムが採用されており、日本で一般的に使用しているWebサイトやSNSのほとんどが中国では利用することができません。
現在、このグレート・ファイアウォールの影響により、以下のサービスへの接続が禁止されています(以下は一部です)。
– Google
– Yahoo!
– YouTube
– Facebook
– Instagram
– LINE
この厳しい検閲を回避する手段として、多くの人々に使用されているものがVPNです。しかし、中国政府は2017年からサイバーセキュリティ法を施行し、VPNへのさらなる規制強化を発表しました。
上記のSNSやメッセージルールなどに加えて、VPNサービスまでもが政府から許可を得たものしか利用できなくなり、その結果、これまで接続できていたVPNが政府によってブロックされるケースも珍しくなくなっています。
無料VPNのほとんどが使用できない状況
中国のインターネット規制を回避するための手段として有効なVPNですが、その多くのプロバイダーは政府によって常に監視されています。VPNの規制が強化された2017年1月以降は、特定のIPアドレスへのブロック、無料VPNの接続が制限されるなど、現時点で多くの無料VPNが使用できない状態となっています。
有料VPNまでもが規制されている現状、中国から無料VPNを使って日本のインターネットへ接続することは、現実的に難しいとされています。現在使用できるVPNについてもこれから探知される可能性があり、まさに中国政府とVPNサービスのイタチごっこのような状態といえるでしょう。今後の規制については予測できないため、出張等で中国でのVPN利用が必要な場合には、常に最新の規制情報を確認しておかなければなりません。
中国の通信規制を回避できるVPNはあるのか?
中国で使用できるVPNサービスはかなり少なくなっています。2019年12月時点で、厳しい規制に対応しているVPNには以下が挙げられます。
1. Astrill VPN

中国ユーザーの多くが使用している有料VPNサービスで、中国の検閲を乗り越えられるアクセス機能が備わっていることが特徴です。あらゆるトンネリングプロトコルに対応していますが、より探知されにくい「Stealth VPN」を利用すれば、中国のグレート・ファイアウォールを通過してアクセスできることが検証されています。閲覧したWebサイトにログを残さないため、安全にVPNへ接続可能です。
2. VyprVPN

中国のグレート・ファイアウォールに特化した、OpenVPNベースの独自プロトコル「カメレオンプロトコル」が使用できる有料VPNサービスです。Stealth VPNのようにパケットを隠して規制を通過するとともに、AES-160, 256といった高度な暗号化を選択できることが特徴です。厳しくなったVPN規制後の接続が確認されていますが、定期的にIPブロックが行われるため、今後使用できなくなる可能性もあります。
通信品質、セキュリティ面の考慮が必要
グレート・ファイアウォールでは、VPNで最もセキュリティが強固なプロトコル「OpenVPN」の通信を探知しています。それを回避する目的で全性の低いプロトコルが使用される場合があるため、VPN接続のセキュリティレベルが低下する危険性があります。なんらかの事情でVPNが遮断された場合には、ユーザーのIPアドレスや個人情報が特定されてしまうリスクがあるので、セキュリティに十分配慮しなければなりません。
また、VPNの中には、規制に引っ掛からないよう中国直通のサーバを保有していないものが多くあります。接続にあたり複数のサーバを迂回する必要があるため、動画視聴時や混雑時には速度が遅くなる可能性が高くなります。
このように、中国で使えるVPNには、セキュリティや通信品質における注意点があります。厳しい検閲を通過することが目的であっても、通信をしっかり保護できる高いセキュリティ・暗号化技術を備えたもの、キルスイッチなどの情報漏えいを防ぐ機能が付いているものを選ぶことが重要です。
VPNのITreview Grid
ITreviewでは、企業でのVPN導入にどの製品を選んで良いか分からない方に向けて、ユーザーに人気のツールがひと目で分かる四象限の比較Map「ITreview Grid」を公開しています。
ITreview Grid上のツールにはユーザーのレビューも集まっており、どのように評価されているかが分かります。顧客満足度が高いツールをチェックして、自社に最適なツールを選定ください。
投稿 中国でのVPN利用はもう不可能?通信制限を回避できるVPNとは は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 「PPTP」はもう古い?ルーターがつながらないときはVPNプロトコルの見直しを は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>本記事では、外出先や自宅からVPNへつながらない場合に考えられる原因や、その対処方法について解説します。
VPNにつながらない原因に考えられること
インターネットVPNを自社構築するとき、接続先となる各拠点にVPN対応ルーターを設置する必要があります。ルーターがVPN対応であるにもかかわらずつながらない場合は、以下のことが原因として考えられます。
VPNサーバ機能を備えていない
VPN対応のルーターを選ぶ際「VPNパススルー」「PPTPパススルー」「IPsecパススルー」などのように、VPNパススルーに対応しているルーターを選ぶ必要があります。しかし、VPNパススルーに対応しているルーターであっても「VPNサーバ機能」が備わっていないものは、接続環境によってVPNへつながらない場合があります。
接続するオフィスや拠点にサーバ機能を持つルーターがない場合は、LAN内に別途VPNサーバを構築しなければなりません。または、VPNサーバソフトウェアをPCへインストールすることで、VPNサーバとして利用できるものもあるので、そのどちらかの方法をとる必要があります。
VPN接続時のログイン情報が間違っている
ルーター設定時のログイン情報は、VPNの接続時に入力が必要です。接続が拒否される、つながらないという場合は、接続時のログイン情報が正しく入力されていないかもしれません。
ルーターによって接続設定は異なりますが、主に以下の情報を確認しましょう。
・ルーターに設定したユーザー名/パスワード
・VPNのプロトコル(PPTP、IPSecなど)
・VPNサーバのIPアドレス
・暗号化のための事前共有キー(PSK)
接続時にはデバイス側で「データの暗号化設定」が必要になりますが、ルーターの種類によって接続できる暗号化設定が限られている場合があります。正しい設定に関する情報は、ルーター購入時のマニュアルを確認するのが良いでしょう。
IPアドレスが重複している
VPN接続をしたい社内ネットワークが振り出すIPアドレスと、外出先のデバイス側のIPアドレスが重複している場合、バッティングしてうまくつながらない場合があります。同メーカーのルーターを使用する場合、IPアドレスが既定値として設定されていることがあるため、IPアドレスが重複してしまい接続不良を招くといったケースが起きがちです。
この場合、社内サーバ側のIPアドレスを、接続先のIPアドレスと異なる値に変更しなければなりません。ルーターの設定メニューより、他と重複しないIPアドレスに変更しましょう。
PPTPやIPSecにパケットフィルタが設定されている

外出先からPCやモバイルデバイスを使用してVPNに接続する場合、OSやセキュリティソフトによるパケットフィルターが、PPTP/IPSecに対して設定されている場合があります。フィルターによってプロトコルのパケットが許可されていない状態となれば、VPN接続はできません。
接続先がPCの場合は、ウイルス対策ソフトやWindowsのファイアウォールなどで拒否されていることがあります。スマートフォン等のモバイルデバイスでは、キャリア側でPPTP/IPSecのパケットを制限されている場合もあります。問題を解消するには、フィルターを通過できるプロトコルに変更する必要があります。
新しいプロトコルへ変更すると接続できる可能性がある
上述したように、デバイス側のOSやセキュリティ設定によって、PPTPやIPSecといったプロトコルが使用できない(つながらない)場合があります。
PPTPは、現在使用されているプロトコルの中でもセキュリティの保護レベルが低いため、セキュリティ設定によってブロックされてしまうケースも少なくありません。また、mac OS 10以降の標準機能では対応していないため、利用するデバイスがmac OS 10以降であれば、PPTPでのVPN接続はできません。
IPSecは、PPTPよりもセキュリティ強度が高いプロトコルであるものの、OpenVPNやSSTPと比べると安全性が低くなります。PPTP同様、パケットフィルターかかる可能性が高く、対応している機器が限定されることがあります。
このような場合、VPNサーバのプロトコルをPPTPやIPSecから変更することで接続できるようになる可能性があります。接続時のログイン情報、IPアドレスの設定に間違いがない場合は、VPNプロトコルの見直しを検討しましょう。
幅広く対応&安心して使用できるプロトコルは「OpenVPN」
近年、PPTPやIPSecが持つ、セキュリティ問題や通信品質を改良した新しいプロトコルが登場しています。現在最も広く普及しているのは「OpenVPN」です。強固なセキュリティかつオープンソースであることから、ほとんどのプラットフォームに対応しています。
VPNルーターがOpenVPNに対応している場合は設定変更を行い、対応していない場合には新しいVPN対応ルーターへの交換を検討しましょう。つながらなかったVPNを改善できる可能性があるほか、より安全性の高いネットワーク環境の構築にもつながるため、企業のセキュリティ対策の面においても有効です。
投稿 「PPTP」はもう古い?ルーターがつながらないときはVPNプロトコルの見直しを は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>投稿 IP-VPNとは?企業の導入方法と選定のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>VPNにはさまざまな種類がありますが、なかでも安全性、信頼性が高いVPNといえるのが「IP-VPN」です。本記事では、これからVPN導入を検討している企業に向けて、IP-VPNの仕組みや導入方法、サービス選定のポイントについて解説します。
IP-VPNとは?

IP-VPNとは、通信事業者が提供している閉域IPネットワーク網を介してユーザー拠点を結ぶVPN通信サービスのこと。通信事業者の閉域網を利用することで、管理の行き届いた安心で信頼できるネットワークを構築できます。
VPNには大きく「インターネットVPN」「IP-VPN」という方式があり、一般的なインターネット回線を使用しているものが「インターネットVPN」であるのに対し、「IP-VPN」では閉域IP網を利用しています。それぞれの特徴は次の通りです。
インターネットVPN
・低コストで導入できる
・ 不特定多数が利用するオープン回線のため、IP-VPNと比べて情報漏えいやデータ盗み見のリスクが高い
・ 回線が混み合うと速度低下が起きることがある
IP-VPN
コスト面ではIP-VPNの方が負担は大きくなりますが、セキュリティと通信品質を考えると、IP-VPNが優勢といえるでしょう。
・ 通信事業者の専用ネットワーク(閉域網)を利用するため、セキュリティが高い
・ SLA(サービス品質保証)や帯域保証がある場合が多く、通信が安定している
・ インターネットVPNよりもコストがかかる
IP-VPNを使用するメリット
通信環境の安全性や安定性が求められる企業のネットワークにおいて、インターネットVPNよりもIP-VPNを利用する方が、より多くのメリットを得ることができます。IP-VPNを利用するメリットには、以下が挙げられます。
・ 専用線に近いセキュリティ環境
・大容量データを高速かつ安定した品質で通信
・運用は通信事業者へ依頼できる
・複数拠点をつなぐ大規模なネットワークを、本社で一元管理できる
IP-VPNのデータ通信には転送処理が速いMPLS技術が用いられているので、通信速度が速く、ユーザーごとのネットワークを目的別に分離できます。そのため、大規模ネットワークを持つ会社や大容量データをやりとりする場合でも、安全・安定した品質で通信が可能となります。
コストをかけても社内ネットワークの安全性を向上したい、安定したデータ通信を実現したいという場合、IP-VPNの導入がおすすめです。
IP-VPNを導入する方法
IP-VPNを導入する場合、通信事業者が提供しているVPNサービスの契約が必要です。ただし、VPN機器の準備や設定は通信事業者側で行うため、自社でVPN機器を用意、設定をする必要はありません。
外出先から社内ネットワークへ接続する際は、クライアントとなるPCやスマートフォンなどの端末に、専用のアプリケーションまたはソフトウェアをインストールする必要があります。
選べる回線の種類や帯域、セキュリティオプションなどは通信事業者によって異なるため、導入企業における各拠点の重要度や用途、継続的なコストを踏まえて導入しましょう。
IP-VPNの3つの選定ポイント
利用できるサービスやサポートは、通信事業者によってさまざまです。選定にあたり、以下の3項目を比較してみるとよいでしょう。
1.豊富なアクセス回線が選べる
IP-VPNでは、支社や支店などの各拠点において、必要帯域や重要度に応じたアクセス回線が選べるようになっています。一般的なものとして、高速デジタル専用線やイーサネット専用線、ATM専用線が挙げられますが、中にはADSLやFTTHを利用できる事業者もあります。
また、営業所や店舗などの接続拠点が多い場合には、電話網やモバイルなどの多様なアクセス回線に対応しているものが便利です。マルチデバイスからのリモートアクセス機能が利用可能であることも重要といえるでしょう。
2.セキュリティオプションが充実している
不具合や故障が発生した場合に備えて、「ネットワーク監視」などの保守管理サービスが提供されていることが一般的です。しかし、管理体制は通信事業者によって異なります。
万が一のトラブルに早急に対応するには、24時間365日対応の通信事業者が望ましいでしょう。柔軟に監視時間や検知通知を設定できる事業者もあります。
そして、VPN経由でのセキュリティを向上できる「認証システム」も選定ポイントの1つ。IDやパスワード認証、認証ログのアカウント照会などの機能は、リモートワークのセキュリティ対策としても必須といえるでしょう。その他にも、企業のセキュリテイポリシーに沿ったフィルタリングサービスなどが挙げられます。
3.柔軟なカスタマイズができる
IP-VPNのメリットは、セキュリテイレベルが高く、通信品質が安定していることだけではありません。企業ニーズに合わせた柔軟なアクセス回線、オプションサービスが選べることもIP-VPNの魅力といえます。
例えば、複数アクセス回線を拠点に引き込む「冗長構成」を実施することで、万が一、1つの回線がストップした場合にも別の回線を確保したり、トラフィック混雑時に回線を切り替えて負担を分散したりすることが可能です。
また、高コストになりやすい「帯域保証型」ですが、中には他通信事業者の回線を利用した、低コストなブロードバンド型IP-VPNを提供する事業者もあります。
拠点の重要度に応じて柔軟にカスタマイズすることで、オペレーションの効率化、VPN運用のコスト削減にも効果が期待できるでしょう。通信事業者のサービスやオプション内容を比較しながら、自社に最適なIP-VPNを導入しましょう。
VPNのITreview Grid
ITreviewでは、企業でのVPN導入にどの製品を選んで良いか分からない方に向けて、ユーザーに人気のツールがひと目で分かる四象限の比較Map「ITreview Grid」を公開しています。
ITreview Grid上のツールにはユーザーのレビューも集まっており、どのように評価されているかが分かります。顧客満足度が高いツールをチェックして、自社に最適なツールを選定ください。
投稿 IP-VPNとは?企業の導入方法と選定のポイント は ITreview Labo に最初に表示されました。
]]>